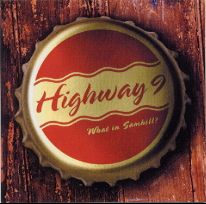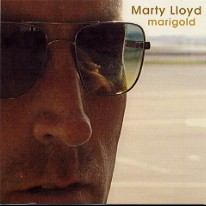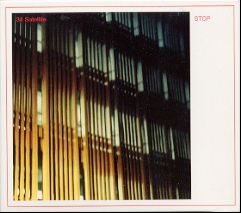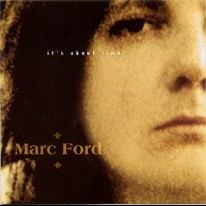 It’s About Time / Marc Ford (2002)
It’s About Time / Marc Ford (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Southern ★★
まずは、ひとこと。
ライオンだか奥様劇場だか知らんけど、あないな地球環境に有害なボケカスアルバムを創ったBlack Crowesはさっさとくたばって、大地の肥やしになれ、スカタン!!!!
ここで、Marc Fordのインタヴューを引用しておこう。少々、神の声筆者の叫びが入るが・・・。
質問:「Marc、君がBlack Crowesを去ってから、Crowes関連では後ろ向きなニュースが多発しているね。・・・・
当たり前●のクラッカーじゃ!タコ!!史上最低のアルバム創ったボケロビンソンは豆腐の角に頭ぶつけて死ね!!!!!!!
「・・・・・。彼らのレコードの売上はアルバム毎にダウンしているし、ライヴのチケットもソールド・アウトになるどころか、どんどんと空席が増えているし。」
当然や!!こないなウンコが売れたら世の中速攻で滅びるワイ!!
「多くの人がそれは君がバンドを抜けたからだ、って思っているようだよ。ファン達は君がCrowesでプレイした時に君が与えた影響が彼らの成功に関連していると言っているけど、何かファンに対してのコメントはあるかい?」
Marc Ford:「そうだね、俺は彼らのレコードセールスやライヴにどんな影響を及ぼしていたかは分からないね。でも、正直な話、彼らのビッグセールスの一部に加わっていたことと、その参加が何年経っても語られることは嬉しいと思っているよ。・・・・・・」
一応、Marc Fordを知らない人のために、彼が在籍した日本でも有名なバンドBlack Crowesをトップページの名前の横に付け足した。とっても、とっっっっても、書きたくなかったのだが、「The Southern Harmony And Musical Companion」(1992)という良質なRoots&Southern Hard RockのアルバムにMarcが参加していたのは評価すべきだろう。
正直なところ、「Amorica」(1994)、「Three Snakes & One Charm」(1996)という箸にも棒にもつかないような最低の駄作にMarcはギタリストとして参加していた故に、MarcがBlackアホCrowesに与えた影響なんぞない方が良いと心から祈っている。
皮肉なのは、ロックンロールバンドとして再評価したくなった、2nd以来の唯一の傑作「By Your Side」(1999)をバンドがリリースした時には、Fordはバンドを解雇されて去っていた後だったということである。彼は正式に1997年半ばでBlack Crowesをクビになっている。まあ、Marc脱退後の奇跡の好盤5thも2001年の核地雷で相対的ポイントは喪失してしまったのだけれど。
Black Crowesからの脱退騒動については、Marc側の意見は以下の3つである。
「6年間もバンドにいたのに、曲を単独はおろか、共作でも書かせてもらえなかったために、疎外感を覚えた。」
「バンドの人気が次第に先細りになり、Robinson兄弟の間にも不協和音が生じ始め、Black Crowes側でも“誰かが悪い”という犠牲者のせいにすることでバンドの存続を図ろうとした。そのスケープゴートがMarcであっただけ。」
「そういったストレスもあったためか麻薬中毒に陥った自分自身の精神と肉体の治療が必要だった。」
結果論であるけれども、最低の駄作にMarcが手を突っ込んでいなかったのは幸いであると思う。流石にあの6thにMarc Fordが参加していたなら、この「It’s About Time」が相当の出来という情報を得ても、食わず嫌いで放置(プレイ)していただろうから。
が、このソロ作を聴くまで、Marc Ford自体をここまで評価していなかったので、1997年に起きた彼の解雇劇も別にどうでもエエニュースだった。つまるところ、Marc Fordというギタリストは、ぶっちゃけた話、筆者には全く評価できないミュージシャンだったのだ。
1990年にメジャーのEpicから発表された「Burning Tree」はキャッチーさの欠片もない、ハードロックの汚さしか見えてこない、癖とアクと毒の強過ぎるアルバムだった。このレヴューを書くにあたり、仕方なく聴き返したが、只でさえ狭い部屋の空間を侵食しているという理由で叩き割りたくなる出来だ。
更に、前述のようにBlack Crowesにて彼が参加した3枚のうち、2枚は筆者的には聴くに堪えない菊座(ヲ下劣)に突っ込みたくなるスカンタコである。
他には、Southern Hard RockのバンドであるGov’t Muleのライヴアルバム「Live with A Little Help From Our Friends」(1999)にギタリストとバックヴォーカルとして参加していることくらいしか、筆者は寡聞にして知らないのだが、ライヴアルバムは積極的に求めない筆者には、評価できない作品だ。聴いてないから。(を)
煎じ詰めると、Marcは主にハードロックの気が多かれ少なかれ、必ずエッセンスとして組み込まれたバンドに所属していることがこれまでの経歴で見て取れる。
先んじて触れてしまったが、Marc Fordのこれまでの足跡を簡単に振り返っておこう。
生まれは1966年。2002年現在で35歳とまだまだ枯れるには早い年齢のミュージシャンである。カリフォルニア州は、LAの衛星都市として発展したロング・ビーチ近郊がMarcの故郷である。
最初に興味を持ったのは、小学生低学年の頃に父親が嘗て嗜んでいたトランペットだったということだ。Marcは吹奏楽器を通して音楽に興味を抱くという、ロックキッズらしからぬ入門をしている。
が、10歳の時、とある日曜日に、祖母に連れられていったフリーマッケットで、Marcは老人が弾くアクースティック・ギターに釘付けとなる。7ドル50セントで売り出されていたその中古ギターは、3番弦がなくなっている程のボロだったそうだが、Marc少年は祖母にねだり倒してそのギターを手に入れた。
そして、Marc Fordはギターを練習するようになり、直ぐに友人達とバンドを組んで演奏を始めるのだ。
高校時代を通じて、全くカヴァー曲をプレイすることなく、オリジナルなレパートリーのみを追求していたと、Marcは語っている。1980年代から盛んになり始めたメタル・ミュージックからニュー・ウェーヴにクラッシックなライヴ向けロックナンバーと、影響を受けた音楽を元に、オリジナル・ナンバーを創作していたとのこと。
Marcは完全に音楽を自分の人生の仕事としたいという欲求にかられ、高校を中退し、ロックミュージックの中心地であるハリウッドで演奏活動をしたいと、両親に申し出る。ただの中退でなく、日本でいう大学検定の資格を取った−つまり高校卒業の学力があるという証明試験をパスした上での中退というから、彼は相当優秀であったか、それ程までに自らを駆り立てる起爆剤が音楽であったのか。まあその両方であると思う。
17歳でハリウッドのクラブシーンで演奏を開始したMarcがつるんだのは、後にLenny Kravitz' BandのギタリストとなるCraig Rossであった。CraigとMarcはデュオ形式でライヴ活動を開始するが、Craigの結成したバンドThe Broken Homesとプレイするうちに、自分が率いるミュージシャンとThe Broken Homesを併せたようなバンドを結成したいと考えるようになる。
結局、1988年にはBuring Treeを結成するのだが、その前身バンドというべき、Head、Cathadral Tearsといったメタル/ハードロックバンドを始めとして、複数のバンドで演奏していたらしい。
そのような折、Marcが出会ったのが、シンガーであり、ベーシストのMark Duttonである。
1990年にEpicからメジャー・プレスされるBuring Treeを、そのMark Dutton(詳しくはCol.Parkerのレヴューに記載してある。)やドラマーのDoni Gray(Izzy Stradlinのバンドにも参加する。)と結成する。
基本的には、当時カリフォルニアのシーンを席巻していたLAメタルのような大仰で華やかな音でなく、よりダークでヘヴィなハードロックが彼のスタイルであったようだ。が、Buring Treeを結成する前は、プログレハード的なバンドやクラッシック・ロックのバンドにも掛け持ちして参加していたとうことから、Burning Tree系列のメタル一辺倒なミュージシャンではなかったようではある。
かなり精力的にライヴ活動を実施していたらしく、20歳前後はLAのインディ・シーンでそれなりにハードロックを中心としたミュージシャンとして地位を築き上げていた。
特に、Burning TreeはLAメタル全盛時の中で異端的なハードロック系の存在であったGuns N RosesやBlack Crowesと共通の、華やかなシンセで装飾されたポップメタルとは対極な方向性が評価されたためか、彼らのツアーのフロントライナーとしても起用され、そのパフォーマンスがメジャー・レーベルからの契約の持ちかけに繋がるのである。ざっかけない言い方をすれば、メジャーが2匹目のGunsやBlack Crowesを狙った尻馬に乗れた、ということなのだろうが。
特に、お互いのデモテープを交換して、大ファンとなったというBlack Crowesのツアーにはカリフォルニア州だけのフロントアクターでなく、全米ツアーにも同行することとなる。更に、1990年に初のメジャーアルバムをリリースした英国のDog’s d’Amourの全英ツアーにも起用され、大西洋を渡るという海外ツアーにまで起用される。
しかし、鳴り物入りで発売された「Burning Tree」は全くセールス的には失敗し、チャートインすらなしという燦々たる結果を残しただけだった。1990年という時代性を考慮するなら、まだメタル/ハードが21世紀現在よりも鬼子扱いされていなかった事実を振り返れば、やはりセールスをメジャー・チャートで記録するには力不足な1枚だったのだ。筆者はこのアルバムは幾度聴いても好きになれない。
活動自体も、シンガー且つベーシストのMuddyが脱退してしまうという具合に、存続自体が危うい状況に陥ってしまうのだ。
結局、Buring Treeに終止符を打ったのは、1992年にBlack CrowesのギタリストであったJeff Caeseの後釜としてMarc FordがBlack Crowesに加入した、という事件のためである。この段階でバンドは消滅。Marcは1997年までBlack Crowesのギタリストとして3枚のアルバムに参加することとなるのは、先に延べた通りだ。
この後は、自らFederaleというバンドを結成してInterscopeと契約するが、レーベルがヘヴィロックのアルバムを作成するように求めたため、契約を破棄して活動は停滞してしまう。が、この「It’s About Time」にはFederaleのメンバーも参加しているので、ソロ名義のバンドアルバムという顔も有しているアルバムだろう。
またGov’t MuleやThe Allman Brothers Bandのライヴ・ツアーにギタリストとして参加する。この時の人脈で、初のソロアルバム「It’s About Time」にはGov’t MuleやAllman Brothers Band関連のミュージシャンが客演をしているのだが。この2つのバンドはBlack Crowes時代にジョイントツアーを行った関係から親交があるそうで、キャリア的にBlack Crowesに在籍したことは無駄にはなっていないのは嬉しい限りだ。
以上の如くあまり活発な活動がなかったMarcだが、(現実としてドラッグの治療を長期間していたらしい。)2002年に入ったばかりの頃、元Black Crowesのギタリスト、Marc Fordがソロ作をセルフリリーするという話を聴いた。正直、ここ数年全く話題のなかった人であり、しかもBlack CrowesのようなSouthern Hard RockやBurning Treeのヘヴィメタル音楽なら些か興醒めなので、全く傾聴に値しないと考えていた。
が、今までのMarc Fordが手を染めた作品とは全く異なるルーツロック、という話が流れてきて、試聴した曲もハードロックのハの字も感じられなかったので、即座に購入したのだ。
で、率直な感想であるが、
物凄い良質なRoots Pop/Rock!
Burning TreeやBlack Crowesのハードさは殆どナシ! グレイト!!
まさに、別人が作ったような作品で、これまでのSouthern Rockのハードさ、メタル音楽を追求していた態度が微塵も感じられない、ポップでアダルトなルーツアルバムである。Black Crowesの奇跡的な唯一の至高作、「Shake Your Money Maker」よりも更にポップで正統派のアメリカンロックである。
女性バックヴォーカルを大胆に導入し、Adult Contemporary色を強く打ち出し、ピアノを中心とした鍵盤も相当積極的に活用している。スライドギターの地味だが玄人ハダシの使い方も見逃せない。
更に、各曲に多彩で豪華なミュージシャンを起用し、とてもCD番号のない自主リリース盤とは思えないゲスト陣を見ることができる。
Izzy Stradlin& The Ju Ju Houndsのアルバムに参加していたJimmy AshhurstやCharlie Quintana。
Allman Brothers BandとGov’t MuleからはMatt Abet、Allen Woody、そしてWarren Haynes。
Ryan AdamsのパートナーでありGlin Jonesの息子のEthan Jones。
元Freewheelersのキーボーディストで殆どの鍵盤を担当するこのアルバムのキーマン、Chris Joyner。
JayhawksのメインライターでヴォーカリストのGary Louris。
音楽活動の草創期からの友人であり、Lenny Kravitz’s Band等に在籍しているCraig Ross。
日本でもブルースシンガーとして著名なBen Harper。
そして、プロデューサーには、Guns N’Roses、Michael Bolton、Crosby Stills & Nash、Chicagoといったヒットアルバムのエンジニアを担当していたJim MitchellがMarcと共同でクレジットされている。他にもテクニックのしっかりとした実力派セッション・ミュージシャンが多数起用されている。
こういったパフォーマーに支えられて演奏されるナンバーは全部で15曲。少々、多過ぎて焦点がぼやけてしまうという欠点はあるにせよ、基本的にはとてもヴァラエティに富んだ曲が詰まっているので、中弛みしたり、長過ぎるアルバムと思える危険性は皆無だ。
どのナンバーもポップロックとしての“掴み”がバッチリで(死語か)、ポップスという普遍的な娯楽音楽の要素と、ルーツ/サザンロックという類の伝統音楽の融合が完璧になされている。
#7『Two Mules And A Rainbow』が15曲の中では一番ポップさが薄いナンバーであり、バーロック的なトーキングヴォーカルを赤土的な汚いサザンロックで塗りたくる曲であるけれども、このナンバーにしてもそれなりにポップである。Burning TreeやBlack Crowesの「The Southern Harmony And Musical Companion」に通じるハードで重たいブルースロック要素を一番振り撒いているナンバーでもある。
ハード感覚なドライヴさと南部ロックのダートさを#7以外に濃く表現しているのは#11『Wake Up And Wake Away』だろう。このナンバーもかなり酔いどれで泥沼をのたうつような地を這うような重力を感じるナンバーである。のたくるピアノとオルガン、そして12弦スライドの音色がLynyrd Skynyrdといった硬いSouthern Rockを想い起こさせる。
その他は、とても良好なキャッチーさが散りばめられたナンバーばかりである。
間違いなくアルバム中の最高傑作である#1『Hell Or Highwater』。ヴィンテージなスライドギターが、懐古趣味丸出しに滑り、これまた数十年前にタイムスリップしたような錯覚さえもたらす、ホーンセクションがゴージャスにアンサンブルを放出する。ピカピカに光る金管楽器の色が見えてくるような、ゴキゲン金色ロックナンバー。
16ビートがガツンガツンと強靭に、然れども軽快に豪快にリズムを刻みグイグイと曲を牽引していく、#2『Long Way Down』は意識せずにコーラスを口ずさんでしまうような吸引力がある。兎に角、ドラムの跳ね回りが極楽気分に楽しいナンバーである。
Marc自身がRon Woodを意識して書いたという#3『Change Of Mind』もクラシカルな雰囲気に、アダルトロックの落ち着きとルーツロックの適度なバラケた雰囲気を内包する、最高のアクースティック/エレクトリックのポップナンバーだ。女性コーラスとピアノを軸としたクラヴィアントとオルガンの鍵盤のハーモニーが旧いけれど新しい、という単語を脳裏に描き出す。
Ben Harperがラップスティールをカントリータッチに演奏する#4『When You Go』にはコーラスでJayhawksのGeryも参加し、中期のJayhawksを思わせるのどかなCountry Rock調子なナンバーで、Marcのルーツ音楽が南部音楽だけでないことを窺わせる。
そういった牧歌的なバラードは後半の#14『Darlin’I’ve Been Dreamin’』でも見ることが出来る。こちらはより現代的なスマートさを感じる。まあ比較程度の問題だが。
#5『Giving』は何処かで聴いたことのあるコーラスが、しかし耳に心地良いバラードである。日本人の好みにもマッチする情緒溢れるバラードである。この曲はLAメタルを経験した世代であるMarcだからこそ、ルーツフィーリングを取り入れつつも極上のバラードに仕上げることが出来るのだろうか、と想像の余地を残してくれる。
Ethan JonesとJu Ju Houndsの構成メンバーで演奏される、ライトなロッキンブルースである#6『Idle Time』は、ハードロックだけを追及していた時代のMarcからは想像出来ないくらいの、複雑な音楽要素を見出せる。女性コーラスがソロパートも歌うというサザン・ゴスペルタッチのヴォーカルアレンジが飽きさせないスケールの大きさを助けている。
#8『Cry,Moan And Wail』はMarc FordとCraig Rossとアクースティックギター2本を左右のスピーカーで分け合う形の真性カントリー・ブルースである。異色なナンバーであるけれども、このドランクンなアクースティック・スウィンギングは最高に臭い。オトコ臭い。
同じスローアクースティックな曲でも続く#9『Shining Again』と#10『Elijah』はナチュラルな故の美麗さとデリケートさを追求した型のバラードである。アコーディオンを絡めて胸を締め付けるような郷愁感を演出している#9と、哀歌という表現がぴったりで、Kirsten Fordという恐らく姉妹になる女性ヴォーカリストとハーモニーのデュエットを聴かせる#10は触れれば砕けそうなデリケートさがひっそりと佇んでいる。
#12『Feels Like Doin’Time』、#13『California』と2連発でロックンロールナンバーが踊りまくるが、どちらもホンキィ・トンク調子の鍵盤が回転する、1950年代R&Bや1960年代のオールディズ・ヒットを再構築したような古典ロックのフックが瑞々しい。ロカビリーやクラッシック・パンクのナンバーを21世紀の録音技術で再生したともいえるか。
ラストのスライドギターが夕暮れ色に黄昏る#15『Just Let It Go』は幕引きに丁度良い、やや投げ遣りなブルーステイストが気怠るく流れる、トラッド感覚の満載ナンバーである。少々締めにはルーズ過ぎるかもしれないが、統一性のない未整理なアレンジと編曲が却ってユニークではある。後半のハードなギターソロと、気合の入らないコーラスの掛け合いが延々と都合9分を超えるのは、やはりやり過ぎかもしれない・・・・。
それにしても、Judas Priestを聴きながら育ち、Jimi Hendrixをバイブルにしているメタル畑のギタリストがここまでルーツでポップなアルバムを創るとは想像をだにしなかった。
が、Marcが最初に影響を受けたのがElton Johnの大作「Goodbye Yellow Brick Road」であり、Peter Framptonの「Frampton Comes Alive」だったというインタヴュー記事を読んで、成る程と思った。Marc Fordのルーツはあくまでポップミュージックであり、ルーツロックだということを漸くにして理解した気分である。無論、この「It’s About Time」にはMarcが後天的に身に付けたメタル/ハードロックの要素は完全に排除されている。
かなりのお薦めなのだが、どうにも注文してもこのCDが中々手元に届かないというトラブルが世界中で発生しているようだ。公式サイトの掲示板にも「1ヶ月以上待てど暮らせど届かないぞ!」的な書き込みが見られる。
著者もアルバムの発売前に事前オーダーしたが、2ヶ月近くも待たされた。催促のメールも何回もして、やっと届いたという感じである。
折角凄い良質なアルバムをリリースしたのに配信方法に問題ありというのは戴けない。このアルバムを現在までのところ、欲しいと思うなら相当の根気と忍耐が必要に思える。
当然、待つ甲斐のある大傑作であるのは確かなのだが。 (2002.6.21.)
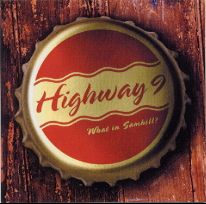 What In Samhill ? / Highway 9 (2002)
What In Samhill ? / Highway 9 (2002)
Roots ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★☆
Adult-Alternative ★★☆
You Can Listen From Here
少々前のことだが、出張先に数日滞在せねばならず、しかも自動車無しでは相当不便な場所であったため、実家からエンジンの腐りかけた愛車を引き出して高速道路を久々に爆走、と相成った。
その時、この「What In Samhill」をCDプレイヤーに放り込んで何度となく往復の高速上で聴いた。
不思議と、部屋で聴くよりも数倍格好良いロックアルバムとして耳に流れ込んできた。
“ドライヴィング・ミュージック”、と感じた。ここ1年少々ハンドルを握ることがなくなったため、その生活の変化が聴く音楽にも影響を与えているなあ、と認識させることともなった。
運転時に流すのに適するのは決してロックンロールやハードロックのアルバムの専売特許ではない。が、やはり部屋で寛ぎながら聴くよりも、アクセルを踏みながら聴く方が相応しいアルバムは多いと思う。
正直、「What In Samhill」を、2001年にこのフルレングスのプロモーションの色合い濃くしてリリースされた5曲入りミニアルバムの「Highway 9」を聴いて期待したよりも、かなり散漫で吸引力に欠けると思い始めていた矢先であった。が、良いと感じると、現金なもので、かなり聴き込めるようになった。
ドライブに適したアルバムでもあるけれど、インドアでもじっくりと傾聴するに値するアルバムと、評価を改めた次第である。
良いアルバムはどのような状況で聴いても良いのだが、良さが分かるまで時間のかかる作品は、染み込んでくる前に投棄される憂き目を見ることが筆者の場合多い。今回は特に、自身の聴き方について一考を迫るものがあったけれども、まあ数回聴いて駄目なものはやはり捨て去るし、「What In Samhill」は勿論最初から“聴ける”アルバムではあったのだから。
聴けるにしても、期待をややスカす段となったのは、このアルバムがメジャー・レーベルのEpic/Sonyからリリースされていることが大きなウエイトを占めていると思う。
アルバムからの1stシングルの#2『Sadly』は、このアルバムの中で、最も世間の流行に迎合したナンバーである、という点に全てが集約されている。
つまるところ、1990年代以降、“妖怪通せんぼ”(何やねん、それ)の如くメジャーシーンに居座り続けているオルタナティヴの影響を如実に感じさせる何かが、『Sadly』の中に、更にアルバムの何処かしらに存在するということだ。
それは、『Sadly』のアクースティック/アンプラグド・ヴァージョンを聴いたことにより、一層くっきりと浮き彫りになってしまった、少なくとも著者の中では。
このプロモーション・クリップを聴いていただければ分かるとは思うが、メロディ的には−これを本邦では哀愁とか美しいと間違った認識で捉えているようだが−どうしてもAlternative的にポップさを押さえつけて抑圧した翳りのあるポップさがないこともない。
が、悪くないポップロックナンバーとしてのメロディラインを持っている曲であることが、アクースティックでアレンジするなら明確に浮き出ている。だのに、現代のメジャーを我が物顔で闊歩しているModern Rock、Alternative Rockのテイストをやはりギターの音出しに感じてしまうのだ。
Highway 9の音楽性はAlt-CountryやAmericanaといったルーツ音楽の要素をメインストリームの潮流と組み合わせたものという評価を海外で見かけるが、筆者の耳ではAlt-CountryやAmericanaと呼ぶにはやはりルーツの度合いが足りなさ過ぎるように思える。
Roots Rockと大別することに何ら異議を挟むつもりはないけれど、例えば同様にメジャーから発売されたBuffalo NickelやGin Blossomsのようにはアメリカン・カントリーの影響を音楽としては前に押し出してはいない。
北米大陸の大地の匂いを鼻腔一杯に感じさせるようなルーツロックではなく、音の重なりの重さやハードさによって安定感のあるフットワークをルーツ的な要素に変換するロックンロールであるだろう。
であるからして、Roots Rockの一翼を担う音楽ではあるけれども、同時にAdult ContemporaryやModern Rock Tracksのチャートで受け入れられそうなサウンドなのだ。
こうなると、既にビックヒットを飛ばしているCounting Crows、Wallflowers、Collective SoulといったAlternativeというノイズ・ラウドに特化した音楽だけに頼らずに、王道的なアメリカンロックを1980年代から継承してきている先輩バンドと同類項に括られる、と考えられるかもしれない。
大まかに区分けしてしまえば、そういったAAAバンド=Adult Alternative American Rockに属するグループであるし、American Trad Rockの21世紀版と見なしても間違いない。
こういった、Alt-CountryやCountry Rockとスッパリ区分できない音楽性を持ったバンドは非常にジャンルを決定することは困難だ。新しいCountryの形をとった音楽としてAmericanaと呼ぶメディアもあるようであるが、筆者的にはもっとルーツテイストが増してくれないと、Americanaと名付けることには抵抗がある。
以上のように、悩んでしまうことが、即ちHighway 9というバンドの限界を示しているのだと考えているのだ。
限界とは、限界点とはどういうことか?
この場合、筆者が言及する「限界」とは
「ビッグ・ネームとしての実績がないアーティストが、メジャーで売るため、またはその目的でメジャー・レーベルと契約するためには、ルーツロックとしての野暮ったさや未整理さを抑え込んで押入れに仕舞わなくてはならない。」
という、メインストリームでルーツ音楽を発表するための音楽的な限界、のことである。
この点については、筆者としては全く否定的ではない。田舎ロックの典型であるCow Punk等がラジオで大歓迎されるミュージックとは全く思わないし、ナショナルワイドで成功するためには、垢抜けない“臭い”音楽要素をスマートなものに研磨していかなくては駄目ということは理解している。
が、別の意味での「限界」については、どうにも我慢ができない腹立たしさがあるのだ。
冒頭にも触れたように、2000年以降のシーンでレーベル側にアルバムを配給して貰うためには、何がしかの流行している音楽のかたち−オルタナティヴ・ロックの色を付けなければならない、ということだ。
無論、1990年代にもHootie And The BlowfishやBuffalo Nickelといった例外はあったが、メジャーで売り出そうとした如何なるバンドも程度の多少はあるにせよ、Alternativeという未成熟な感情を見苦しくぶちまけるために存在するとしか思えない音楽性を入れる、入れざるを得なかったところがある。
このAlternativeの要素をどれだけ消せるかが、筆者としてのメジャーで売り出されたアーティストを評価する着眼点である。
今回書き付けているHighway 9も、どうにかしてAlternativeの匂いを消そうとして努力している足跡が見て取れるし、安易にヘヴィでノイジーな音楽に雪崩れ込まない点は非常に評価できる。
しかし、彼らのAlternative導入のリミット/限界値は、王道ロックを名乗るには心持ち低い気がする。言い換えれるとしたら、Alternativeとの妥協が完全には終了していない未完性さが残ってしまっている、ということだ。本来はあまりオルタナ的な音楽に意欲がないようにも思えるのだが、仕方なくメジャーを指向しているので、いまいち本当に演奏したいルーツロックに踏み切れないような、思い切りの悪さが行間に漂っているようにも思える。
つまり、メジャーで売り出すために、ある程度の妥協をレコード会社としてしまっている、シーンに媚び・流し目を送っているところがまだ微妙に感じられるのだ。この点、完全にルーツロックに固執しているHootie And The BlowfishやBuffalo Nickelの潔さがないのでは、と残念でもある。
とはいえ、殆どのナンバーは非オルタナティヴな良質な曲であり、モダン・ロック的な無機質さもそれ程鼻に突かない程度には緩和されている。ルーツロックナンバーとして素晴らしい曲も多数封入されている。
何より、ガッチリしてタフなロックンロールという点が、筆者の嗜好を直撃してくれるのだ。
絶賛・完全無欠ではないけれども、久々に本格派で正統派のロックバンドがメジャーに名乗りを挙げたと喜ばしい思いである。
毎度のことだが、ベッタリで濃厚なRoots Rockを取り上げるホーム・ページでは絶対に異端審問を受けて、糾弾の対象になるようなロックバンドだろう。草の根的なAlt-CountryやCountry Rockの音楽が至上というリスナーには絶対にお薦めできないバンドでもある。
レーベルも相当このHighway 9に期待を賭けている様である。本格派のロックンロール・バンドとして売り出そうとしている。
2001年に先行ミニアルバム「Highway 9」を売り出す際、プロデューサーにあのPeter Collinsを起用している。
Peter Collinsについては、彼の名前を記憶していなくても、Collinsが手掛けたアルバムなら、普通に売れ線の音楽を追いかけているリスナーでも数枚は手にしたことがあるだろう、という位のヒットメーカーである。
1980年代はRush、Nik Kershaw、Matt Bianco、Billy Squiier、Tracy Ullmanといったプログレッシヴからハードロック、ポップスとジャンルを超越した数々のヒットアルバムを製作し、90年代に入ってからも、Athenaeumのインディデヴュー盤というオルタナティヴからカントリーシンガーのNanci Griffith、ハードロックではAlice CooperにBon JoviそしてQueensryche。
女性ポップシンガーも同様に手掛けていて、LeAnn RimesやJewelというNo.1アルバムをヒットさせたアーティストからIndigo Girlsまで。
ルーツ系のロックでもBrian Setzer OrchestraにShawn Mullinsと大ヒットしたアーティストの作品にプロデューサーとしてクレジットされている、まさに超売れっ子のヒットメイカーである。まあ、ここに列挙したアーティストの作品が全て素晴らしいかというのは置いても、ヒットしたのは事実であるし。
そのPeter Collins がこのHighway 9のプロデューサーなのである。Collinsの手掛けたBon Joviと同郷のニュー・ジャージー出身のバンドであるため、ロックンロールバンドとしての顔を強調する時、Bon Joviや大先輩のBruce Springsteenと比較されることもしばしばだ。
ハードロックやブルースのアルバムは数多く手掛けているが、オルタナティヴは殆ど手を出していないCollinsの意向が反映されたのだろう、メジャー作としては驚くほどにオルタナティヴのカラーが少ない。逆にハードロック的なアレンジの大仰さを感じることの方が多いかもしれない。・・・どっちもいらないのだけれど・・・・率直な話。
そのハードロック的なアレンジがオルタナティヴ的な冷たさを醸し出す原因となっているかもしれない。オルタナティヴの陰鬱さというよりもHR/HM手法の重過ぎるアレンジが、結果としてオルタナティヴ的な暗さを演出してしまっているのかもしれない。
反面、ハードロックにはしたくないバンドの意思のためか、ハードなドライヴ感覚がルーツテイストの構成要素である重厚さを発生させている現象もあるので、一長一短であるだろう。
アルバム収録の12曲のうち3曲はミニアルバムで昨年発表され、#5『Yesterday Came Out All Wrong』もアクースティック・ヴァージョンがミニアルバムで既に披露されている。
残念なのは、ミニアルバムでも出色の出来であったルーツポップナンバーの『Stand Here Waiting(Demo Version)』が正規トラックになってトラッキングされていないことだ。デモ・ヴァージョンとは思えないくらいアクースティックな良作だったのに。
その先行発売された3曲#2『Sadly』、#3『Tug Of War』、#6『Casanova』のうち、#2『Sadly』は冒頭で述べたようにファースト・シングルとなって切られている。
メロディ的にはコマーシャルで良い部分が多いナンバーなのだが、ハードロックやオルタナ・ヘヴィネスを意識したギターのトゥ・マッチなアレンジにより−特に出だしのリフの部分だけを聴くと完全にオルタナ・ナンバーと錯覚しそうである−素晴らしいドライヴ・ロックになることを阻害されてしまっている惜しいナンバーだ。コーラス部分の滑らかなメロディはとても吸着力があるのだが。
#6『Casanova』はミニアルバムから『Stand Here Waiting(Demo Version)』とは逆に入れて欲しくなかったナンバーである。ヘヴィで泥臭いギターをかました東海岸のアーバンテイストと南部の粘っこいテイストが同居するルーツロックなのだが、メロディ的には平凡である。
同様に#12『Quicksand Town』も有終の美を飾るには、かなり力不足なヘヴィさを故意に出そうとしてるロックナンバーである。この曲が最後というのはかなりアルバム全体のイメージを損ないそうだ。悪いナンバーでないのは#6と同じなのだが、取り立てて賞賛すべき点もないオルタナ的なスコアの組み立てが目立つルーツ系のナンバー。
これら以外は、どのナンバーも合格点を与えたいRoots/Adult Alternative Rockである。
筆者としては、こちらをシングルにすべきであると考えているのが、#3『Tug Of War』である。何処かのロック名盤と同じタイトルのナンバーであることも、印象を植え付けるのに一役買うかもしれない。(笑)兎に角、メロウでアクースティックであり、エレクトリックとのブレンドも完璧である。オーケストレーションもバックに流れるAdult Contemporaryのラジオ局で歓迎されそうなミディアム・バラードである。この上品に重ねられたハーモニー・コーラスはEaglesを思い出させる程、良質なのだ。
バラード・タイプのナンバーではやはり、とことんメロディアスでアダルトな#5『Yesterday Came Out All Wrong』が出色だ。先行発表されたアクースティック・ヴァージョンと大きな差異は存在しなく、オーケストラが華麗に流れるブリッジ部分にドラムとエレキギターがフューチャーされ、HRのパワー・バラード的な効果に拍車が掛かったのみだ。ピアノとストリングス、そしてコーラスのハーモニーを中心に曲を仕上げるところは、敏腕プロデューサーのPeter Collinsの力量か。
他のバラードも佳曲が揃っている。
やや、マイナー調子で地味だが、ルーツィーなオルガンが良い仕事をしている#7『Ain’t Nothing But Love』でもハーモニーコーラスが分厚い。こういったナンバーではルーツロックというよりも、1980年代のアリーナ-ロックバンドのシングルカット向きでない渋いバラードに通じる感覚がある。
#11『Heroine』もアクースティックギターのリフからジワジワと盛り上げてくバラードである。歌詞の内容も哀しく、懐古的なもので、しんみりとしてしまう。Peter Schererのソウルフルなヴォーカルが映えるナンバーであり、情感の込め方においては、名曲#5に劣ることがないだろう。
ロックナンバーにおいては、最高に痛快でスピーディな#10『Say You’re Mine』と同じようなポップロックナンバーがもっとあっても良いと思う。ルーツテイストは薄いが、兎に角、ストレートでキャッチーで、どこまでも疾走していくようなハードさを取り払ったBon Joviのようなロックナンバーである。
この#10を挟んで、ミドルテンポのルーツナンバー、#8『Had Enough』、#9『Pain & Suffering』とバラードの#11までが後半の山場であり、#1『Between Your Eyes And Mine』から#2を飛ばして#5に至る、前半の聴き所に匹敵する素晴らしい流れが存在してる。
#8『Had Enough』では適度なローカル色を交えて、ポップにメロディが弾む。コーラスの厚さや泥臭いギターも気持ちの良いレイドバック感を助長してくれる。こういったラフさなら大歓迎だ。ギュウギュウのHRロック的な粗さとは質の違うフックが内在する曲である。
#9『Pain & Suffering』はバラードに近いミディアム・ルーツナンバーだ。バラードと分類しても悪くないけれども、パワフルなギターが叩き出すエモーショナルさはロックンロールの熱さを、バラードの美しさよりも際立たせている。オルガンの使い方も曲に深みと落ち着きを付与するためにベストな使われ方をしていると思う。これまたルーツロックとしてはルーツテイストが濃くない曲だが、じっくりと噛み締めれる味わいのある曲だ。
オープニングナンバーの#1『Between Your Eyes And Mine』もラストナンバーの#12の駄目っぷりとは対照的に素晴らしいルーツロックである。ややゆったりとした余裕のあるリズムに乗る、アーシーなギター。ハスキー気味に歌うPeter Schererのヴォーカルとメンバーのハーモニーの妙。B3ハモンドの縁の下の力持ちというべき埋み火のように暖かい音色。
このルーツナンバーの後に#2の下世話なオルタナギターリフが入る流れが一番嫌悪を覚える箇所である。つまりそれだけ#1が良心的なルーツナンバーなのだ。
#4『Break』も切れ味の良いロック・ポップチューンである。名曲である#3と#5に挟まれて、やや影が薄くなってしまっているのは不遇であるが、シャッフル感が踊るロックテイストは美しい前後の2曲を際立たせる働きをしている。贅沢を言えば、もっとルーツ色が強いナンバーにして欲しかったことくらいか。
と、メジャー発売にしてはかなり本格派でルーツロックと呼んでも差し支えないHighway 9の「What In Samhill」であるが、タイトルは恐らく、アルバム発売直前まで名乗っていたSamhillという名前に向けられたものだろう。
Highway 9の結成母体は1990年まで遡る必要がある。
子供の頃からの友人であった、ソングライターでギタリストのGordon BrownとヴォーカリストのPeter Scherer、そしてベーシスト兼ピアニストのRob Tanicoの3名がアクースティックロックバンドのMr.Realityを1990年に結成したのがプロフェッショナルとしての音楽活動の開始点である。
地元ニュージャージーでかなりの人気バンドとなったこの3ピースは、Capital Recordsが90年代初めに創立したSBKレーベルと契約を交わすことに成功し、「Mr.Reality」というアルバムを1992年にメジャー・リリースする。SBK/CapitalのアーティストにはもっとルーツでポップだけれどもHighway 9と似通った音楽性のあるMichael McDermottや、最低のバンドで全く筆者には受け付けないJesus Jones等が存在した、余談であるが。余談ついでに、SBKは数年後には消滅してしまったことも記しておこう。
「Mr.Reality」は2枚のシングルがカットされたが、全米では殆どヒットすることなく、地元での人気は上昇したが大成功とはならずこれ以上のリリースはない。が、音楽性はそれなりに評価され、Dave Matthews BandやBlues Travelerといったアクースティック感覚を大切にするバンドの、ニュージャージー州でのツアーに同行し、ヘッドライナーを担当もした。
このアルバムは筆者も持っている筈なのだが、内容はあまり覚えていない。今度掘り返してみる予定だ。ちなみにHighway 9の前身バンドとして中古市場で値段が上がっているらしいので、興味のある方は早目に入手した方が無難だろう。
1994年には、バンド曰く「充電期間」のため、Mr.Realityは活動を休止する。そして2年以上の沈黙を置き、1997年にSamhillというバンド名でトリオは音楽シーンに復活する。この時点でもうひとりのギタリストKevin AnsellとドラマーのDave Halpernがバンドに加わり、現在の5名体制が完成する。
このSamhillはニュージャジーを中心とした周辺の州でもかなりの人気を得ることに成功し、翌年98年にはインディレーベルから「Samhill」というセルフタイトル作を早くもフルレングスで発表する。このアルバムはそのモノクロなジャケットだけ米国で見たことはあるのだが、当時買わなかった。かなりレアになっていて現在では全く見つからない。大失敗である。どなたかお持ちなら感想を聞かせて欲しい。
こうしてローカルに人気を獲得しつつ、Samhillはあちこちの大手レコード会社にデモテープとライヴを収録したビデオテープをせっせと送りつ続けた。2000年の終わりには、多くのメジャーがSamhillの獲得合戦を開始する。その中でも一番条件の良かったEpicとバンドは2001年に契約を交わす。
しかし、Epicと契約した段階で、Samhillという名前のバンドが他にも存在すると判明し、バンドはHighway 9と突如改名する。
名前の由来は、彼らの故郷ニュー・ジャージー州北部を走る9号線−Route9から引用したものであり、アメリカの生活に切っても切り離せない道路という存在にまつわる様々な人々の生き様を歌う、バンドとしての態度を表明したものであるらしい。
2002年の5月に、本作「What In Samhill」−“Samhillというバンドが持っているもの”というアルバムはリリースされた。残念ながら、現在までに全く大ヒットを飛ばす兆候は見られない。
また、日本盤のリリースの気配もないようだ。やはり程度の差こそあれ、正統派ロックバンドは世間的に受け入れられないのだろうかと、とても悲しくなってしまう。
メジャーで売ることを目標とするのはとても健全であり、音楽業界という社会では正常な上昇志向であると思う。が、そのために、全てを流行に媚びてしまうのでは考え物だ。
流行に逆らってマイナーに沈むことも、インディの市場だけでも飯の種になる現在では悪いことではないだろう。けれども、このHighway 9のように完全に成功した訳でなくとも、メジャーでブレイクするために、メジャーの潮流と本来のスタイルの融合と緩和を図るバンドは、シーンに活を入れるためにも方向性を失わせないためにも必要だと思っている。
久々にメジャー感覚を有しつつもルーツロックの大器となれる可能性を秘めたバンドがLegends Of Rodeoと時をほぼ同じくして出現したことは喜ばしいことだ。是非、セールス的にも成功を収めて欲しいと祈っている。
話は逸れるが、Highway 9のメジャー昇格に啓発されたのか、The Jeded Sailngersという本格派バンドが最近現れた。このバンドもじきに紹介するつもりだが、Highway 9のような王道的ルーツロック感覚を有したバンドがメジャーに殴り込みをかけることの意義は絶対にある筈だ。
きっとその余波は、第二、第三のhighway 9を挑戦者を生むだろう。21世紀のパイオニアとして腐ったメジャーに新鮮な風を入れて欲しい。 (2002.6.23.)
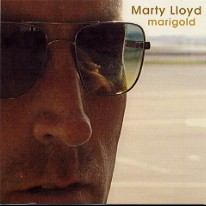 Marigold / Marty Lloyd (2002)
Marigold / Marty Lloyd (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Alt-Country ★★
You Can Listen From Here
知る人ぞ知るバンド(そらそうやね)、Freddy Jones Band(以下、FJB)は5枚目のスタジオ録音アルバムを完成させた直後の2001年に解散した。ほぼ1年位前に(2002年6月現在)、Freddy Jones Bandのレヴューを1本擱筆しているが、その時点で既にこのMarty Lloydは自身のバンド・プロジェクトとして、Marty Lloyd Bandを立ち上げている。
そのレヴューで「まずは、Marty Lloyd Bandの新譜待ちである・・・・。」的な記述をしているのだが、それから約1年を費やして、漸くMarty Lloydのソロ作が届いた。
オフィシャルサイトは、未だMarty Lloyd Band名義で運営がされているのだが、何故か初めてのアルバムのクレジットはMarty Lloyd Bandではなく、Marty Lloyd個人としてのソロ扱いとなっている。如何なる理由で、Marty Lloyd Bandではなく個人名義のリリースとなったのかは、不明である。
まああまり重要なことではないかもしれないが、想像するのは容易い。この「Marigold」には12人ものミュージシャンが演奏者としてリストアップされているが、Marty Lloyd Bandの立ち上げ時にアナウンスされたメンバーとはかなり変わっている。
バンド創設時からライヴ活動を早くも開始していたMarty Lloyd Bandだが、当初のメンバーとレコーディングに関わったミュージシャンに若干の差異がある。
最初はドラマーにLarry Beersという全くの新顔を起用した以外は、FJB時代のバンド仲間である、Jim Bonaccorsiをベースに、Rob Bonaccorsiをギター、そして1997年のFJB最後のスタジオアルバム「Lucid」でキーボードを担当していたChris Cameronを鍵盤、というようにFJBを解散させたものの、他の2名のソングライターを排斥して創設したユニットという色合いが強かった。
が、レコーディング時に残ったのは、FJB関連ではRob Bonaccorsiのみである。新顔のドラマーであるLarry Beersもメンバーとして登録されているが、顔ぶれは全く変わってしまっている。
スタジオ入りする前から、早速ローカルツアーに突入するという具合に臨戦体制をとっていたMarty Lloyd Bandであるが、どうやらバンド内でメンバーの交代劇がかなり大幅に断行されたらしい。
邪推になるとの謗りは免れないだろうが、FJB解散直後にとあるインディ・コンピレーションのアルバムに曲を1曲提供できた程に即応の体制をとっていたMarty Lloyd Bandが、アルバムをリリースするのに1年を費やしてしまったのは、バンド内で何らかの紛糾があったのではないかと考えている。
丁度メンバーが固定しない時期に録音を始めてしまったため、結果としてアルバムの演奏リストに12名の重複する楽器を手にしたミュージシャンが並んだ、と想像するのはあながち間違いでないかもしれない。
この「Marigold」を録音する間は、まさにMarty Lloydとセッション・ミュージシャンという形が基本形であったのだろうか・・・・。
アルバムのインナーは1枚紙のインディ/セルフ盤に典型なペラペラ紙だが、そこにMarty Lloydのコメントが記載されている。以下、ざっと訳してみよう。
「このレコードの曲を書き、吹き込むことは全く楽しかった。僕達はマイペースで録音を行い、音が語るままに僕たちのペースを合わせていった。様々な不自由−電話のコール音、犬の吠え声、自動車の騒音、隣や屋外で騒ぐ連中−を侍らせつつ、僕達はシカゴの我が家でアルバムを作成した。それ以外の活動はテネシー州の、田舎道をどんつきまで進んだ『番犬の耳』という隠れ里のようなスタジオを使った。そこでは創作のための全てが用意されていた。こうして完成した音源を楽しんでもらえると嬉しいね。まだ見ぬ君達へ。」
となっており、レコーディングに時間が掛かったのは、あくまでのんびりと作業を続けたためと延べている。このあたりのコメントを見てみると、或いは、FJBを離れたMarty Lloydというシンガー・ソングライターが『ひとり』で、活動を始めたことを強調するために、敢えてソロ名義にしたのかもしれない、という考えの方がヒネクレておらずまっとうな見解のように感じる。(苦笑)
兎も角、Marty Lloydのソロアルバムは、FJB解散後に初めて起こされた元メンバーのアクティヴな創作活動であり、その出来上がりに期待するところも大きかった。
さて、内容はどうだろう。
やはり、とあるバンドに所属してたアーティストが、ソロ作を発表する場合はどうしても、前身の音楽活動を比較対象として求めてしまいがちである。ソロに転向したアーティストが実質ワンマンとしてバンドを牽引していた場合は、勿論比較することが容易いので反射的に両者を比較してしまう。
しかし、Marty Lloydのように以前の所属グループがワンマン・バンドでなくヴォーカリストもソングライターも複数存在する場合は、いまいち比較が困難である。が、究極的には好みの問題となってしまうので、やはり古巣の所属グループ−この場合はFreddy Jones Band−で、Martyが貢献した要素、受け持っていた役割等、やや切り分ける形になるかもしれないが、やはり新旧の作品を天秤にかけてしまうのは仕方ない。
つまり、Marty Lloydの新作を批評するのに際し、FJBのアルバムを引き合いに出すことが多々あると言いたいだけだったりするのだ。
そのFreddy Jones Bandを基準にして考えるため、幾らかFJBの残した4枚のスタジオ・アルバムについて触れておいた方が無難だろう。「Lucid」のレヴューで言及した内容と重複する箇所もあるだろうが、ご容赦願いたい。
FJBは1992年に自主リリース盤の「Freddy Jones Band」を発表。このアルバムは1994年に契約した中堅レーベルのCapriconeからライヴトラックを増やし、曲目を変更して再発売されている。が、レーベル・デヴュー盤となった1993年の「Waiting For The Night」にもインディ盤の「Freddy Jones Band」からのナンバーがリマスターされ再収録されているため、どちらが1stとなるかという段になると、少々ややこしいかもしれない。
しかし、問題は音楽性であるからして、その点から言及するならこの初期2作は非常に似通った音楽性を有するアルバムである。Alt‐Countryと呼んでも異論を唱えられることがないサウンドが、FJBの2ndアルバムまでの方向性だった。典型的なAlt‐Country Rockというとやや趣を異にするという点はあったにしてもだ。バンドの出身地であるシカゴ・エリアのルーツテイストを如実に感じさせる、Alt‐Country的なトラッド・ロックという言い方のほうがしっくりくるようだ。
これが3枚目の「North Ave.Wake‐Up Call」になると、突如として舵を取る方向が変化する。FJBの3作目ではロッキン・ブルースという表現が一番あてはまる、硬めのロックナンバーと、スローで重めのホワイトブルースが主流をなしていて、これ以前のAlt‐Country風のアレンジはまったく影を潜めてしまった。
そしてラスト・スタジオアルバムとなった1997年の「Lucid」では、ホワイト・ブルース的なロックナンバーに加えて、サザンロックのハードさや西海岸ロックの爽やかさまでもが加わった複合的なロックアルバムに変貌を遂げてしまったのだ。この4枚目もAlt‐Countryとは言い難い作品であると思う。
さて、FJBの4枚と並べてみると、FJBの2枚のリード・ヴォーカリストのひとりであり、またソングライターのひとりでもあったMarty Lloydのソロ作はどのような位置付けを得るだろうか。
大まかに述べれば、FJBの初期の2枚に後期のアルバムのテイストを加味したような作風だと思っている。となると、やはりある種のAlt‐Countryに属するアルバムと考えて良いだろう。初期のFJBと後期の中間にあるという位置付けが一番相応しいサウンドである。
しかし、典型的なAlt‐Country Rockのサウンドが演奏されているかとなると、そうでもない。リスナーによってはこのアルバムをAlt‐Countryとは呼びにくいかもしれないし、Country Rockとはまず呼ぶ人はいないだろうとまで思うのだ。
というのはベタなCountryとAlt‐Countryの要素を「Marigold」の中に見出すことが困難だからである。例を挙げるなら、ロカビリー、ブルーグラス、パンク、カウ・パンク、カントリー・ポップといったCountry系のロックサウンドには典型的に封入されている音楽性が全く希薄なためであるからだ。
要するに軽目で、ダンスミュージックとしての側面を色濃く有するCountryのオーソドックスなジョイフルな音とは違うタイプのルーツ・ミュージックと言うことだ。
こういったカントリー・カントリーしたサウンドでなく、シカゴ周辺のルーツロックやトラッドロック、ブルースロック、そしてあまり引き合いには出したくないのだがJam Rockの要素がAlt‐Countryと溶け合ったような音楽が、Marty Lloydが創り上げたソロ作の基本のスタイルであると考えている。
一言で裁断してしまうと、落ち着きのある渋めで地味なアルバムとなる。Alt‐Countryの端に連なる雰囲気はそこかしこに感じられるが、カントリー・ミュージックよりもさらに低い位置を浮遊しているような感じである。
オーヴァー・16ビートを快活に弾ませ、ウルトラ・ポップなドライヴ感覚で引っ張っていくようなポップロックナンバーは皆無であるし、全体的に抑えの効いたポップ度を保っている曲が殆どである。原色系の鮮やかさよりも、暗色系のクールなポップさとアーシーさを時間をかけて燻蒸したようなトラックがメインの流れを形成している。
こう書いていると、筆者がもっとも気分清涼として聴くことの出来ない、「ポップさが不足した、考え過ぎアルバム」という範疇に組み込まれてしまうアルバムのようにも、書き綴っている筆者自身が思えてきそうだ。
確実なことだが、筆者的にはこの「Marigold」には、絶賛する程のキャッチーなフィーリングはない。となると、同軸上の「ポップ不足の鬱な作」ともなりえる危険性を十分に孕んでいる。
文章化するのはかなり腐心するところであるが、「ポップ不足なアルバム」と「渋くて味わいのある目立たないアルバム」は紙一重に隣接しているのだと、思う。この分水嶺は非常に見極めが難しく、究極的にはリスニング時の気分で評価可能な対象に転がることも、聴くことが鬱陶しくなり放り出す物質となる可能性もまた有しているのだ。
勿論、Marty Lloydが作成したソロ作品は、評価に値する地味・地味アルバムである。手を差し入れても、ガッチリと即応的に掴める質量は多くないが、聴くほどにジワジワと心に残るウェイトを増す形の一枚である。メジャーなコードで目を惹かせるよりも、冷静で一歩引いたポップ度をじっくりと染み込ませるタイプの作品である。
そこには、パワーポップやパンクポップ、エモ・ポップというような単調で終始一遍に同じ音楽を流し続けるような単純さや軽薄さはない。
確かに、地味であることは、往々にして凹凸に乏しいと領域を同じくするし、「Marigold」も一見モノトニアスなルーツナンバーが並んでいるだけのように耳に入ってくる。しかしながら、丁寧に練りこまれた曲の数々は、どれも奥行きがあり不思議と耳に馴染んでしまう。
また、冒険として多彩な音楽要素を詰め込み過ぎた故に、散漫で焦点の定まらないアルバムになってしまったという失敗のベクトルからは完全にフリーになっているアルバムでもある。アーティストの音楽的バックグラウンドに独自性を通さずにただ、模倣するという創作は論外であるが、アーティストの独自性という枷に雑多な音楽性を無理矢理に嵌め込もうとして、結局無味乾燥な作風に陥ってしまうことは、斬新さを標榜するバンドに多い。
色彩で表現するなら、多種の原色系の絵の具を混ぜ合わせると灰色になってしまい、その灰色に生半可な新色を加えても、結局は灰色の量が増えるだけということだ。
Marty Lloydも独自のシカゴ地域の冷静なポップ感覚を軸としつつ、多彩な音楽をそれに融合させているという同様の創造を行っているが、彼の場合は雑多な音楽要素の混合物が鑑賞に堪えれる灰色になっているところが、賞賛に値すると考えている。
多彩をそのまま捻らずに表現するではなく自らの方向性で統一しつつも、単なる単調で変化が少ないサウンドとして完結させずに、心に響く抵抗・手触り・歌のこころ、このようなものを醸し出している。要するにMarty Lloydが才能あるソングライターということなのだが、もう一段ステップアップすれば、よりポップな仕上げが可能になるのでは、とも思う。
まあ、ブルース・ミュージックとグラスルーツを現代的なアレンジを介して纏め上げているところは、やはりユニークなアーティストであるのは疑いの余地はないけれど。
現代的というと、あまり目立たないけれど、ドラム・プログラミングを嫌味にならない程度に活用している箇所が、斬新さへの挑戦かもしれない。控え目な打ち込みだからして、ルーツロックとしての作風を破壊することはない。
このように、瞬間的に押し捲るロックアルバムでないけれど、親しみ易いナンバーは揃えた1枚には11曲が刻まれている。他のライターとの共作もあるが、8曲はMarty単独のペンによるものである。
Marty Lloydは自身のソロ作に付いてこう述べている。
「何かしら新しい要素を歌って、リスナー諸兄を喜ばせたいね。でも同時に彼等がよく馴染んでいる音楽も聴いてもらいたい。」
ライヴでも、FJB時代のナンバーを演奏することにさほど抵抗はないし、ファンが望むことはやりたいとも述べている。が、やはりMarty Lloyd Bandとしての歌がメインになるように持っていきたいとは考えているようだ。
「新しいことに挑戦するのは、気分を一新させるね。で、僕は変革をすることを恐れてはいない。自分のバンドで新しい音楽をやることは僕にとってもリスナーにとっても新しい次元の楽しさをもたらすと信じている。」
これらのコメントを斟酌すると、FJB的な音楽を残しつつも、自らにとっては新しい分野に取り組んだアルバムとなる。新しい音楽性を取り入れると言うのは頻繁に失望と裏切りを感じさせる結果を招く。が、Marty Lloydの場合、FJBで培った土台を元にしての取り組みとなるので、物凄い新しさを彼自身が言及するほどには感じない。
前述のように、FJBの作品全ての中間的な色合いというのが基本のトーンであると思う。ここで各曲に付いて少々触れて、どれだけの変化と新要素があるかも踏まえて見ていくことにする。
アルバム全体を通じて、シングル向き且つ秀逸なナンバーの筆頭は#2『American Dream』だろう。FJBでは、ヴォーカリストとしての力量ではややWayne Healyに劣る気がしたが、この円やかで程好い加減のポップさを持ったミディアムナンバーでのハイトーンに歌う、Martyのヴォイスは非常に和む。FJBの初期のAlt-Countryソングを、後期のRockテイストで割ったようなナンバーであり、これまでのFJBではありそうでなかった、ミディアム・ポップ曲だ。
更にハイライト曲がラスト2曲に連続している。
ペダルスティール、ヴァイオリンを交えて、広大なアメリカの平原をクルージングするような伸びやかさで歌われる#10『Where We Started From』。コーラスのMartyの喜ばしい歌い方には微笑ましいものがある。どちらかというとホワイト・ブルースベースの緊迫感のあったFJBのナンバーと比べると随分リラックスした感想を覚える。このナンバーが最もポップかもしれない。
#11『Dancin Here With You』もパタパタと叩かれるドラムのリズムが気持ち良いミドル・ファーストなロックチューンであり、どことなく暖かさを感じるメロディに打ち込みらしきリズムが加わる。しかし無機的な冷たさは全く匂ってこない、朗らかな開放感を覚えるチューンである。物凄いコマーシャルではないのだが、それもまた肩が凝らないので良いと思う。
他にも一聴しただけでは、燻んだ静かさを纏っているが、じっくり聴くと味が拡がるナンバーが沢山ある。
大胆にドラムマシンをフューチャーしたクールなポップナンバー#3『Come To Me』も面白いし、泥臭いギターが如何にもシカゴ出身のミュージシャンらしく癖のない中庸的なメロディに乗るロックナンバーの#4『We’ll Get By』も心地良い。
アクースティックギターの音色が哀愁を誘うと見せて、軽快なロックのリズムとフュージョンしていく#8『Josephine』も地味だがフックのあるポップロックだ。欧州的な憂いを帯びたメロディを奏でるバリトン・ギターのソロが印象的なナンバーでもある。
ヴィオラを始めとしてストリングスがかなりのナンバーで使われているが、その中でももっともエモーショナルなバラードが#5『Sinkin Like A Stone』である。このナンバーでもドラムプログラミングがリズムを刻むが、美しいピアノの音色とストリングスとの相性は悪くない。何より、感情を込めて歌うMartyのヴォーカルが心に響く。
ここに列挙しなかったナンバーもポップさがやや足りないけれど、底力のある佳曲ばかりである。打ち込みのドラムが多用されているのに、それが全く鬱陶しくないのが一番の賞賛できる点だろう。
FJB時代よりも、よりウエットに、リラックスして、そして自然体で歌っているのが新しい境地のようにも思える。大人の作った大人のためのアルバムという気もする。これもアダルト・ロックの一形態かもしれない。
現在のバンドの編成は、Marty Lloydがアクースティックギターとヴォーカル、唯一FJBからの参加となってしまったRob Bonaccorsiがギター、Michael Rhodesがベース、Larry Beersがドラム、という4ピースとなっている。他にキーボードとペダル・スティール等のサポートメンバーがライヴには同行している模様。
シカゴ周辺を中心に、そう過密なスケジュールではなく、まさにマイペースでクラブサーキットを行っているようだ。
中堅レーベルに属し、全米の大手レコード店ではどこでも並んでいたFJBとはことなり、現在のところ配給はAware Recordsに委託しているとはいえ、リリースのステイタスは完全なインディ・ミュージシャンに格落ちしている。
が、Martyは全く現状を気にしていない。
「Freddy Jones Bandが解散してしまったことに、動揺なんてしていないさ。それよりもこれからの期待にワクワクしているよ。ソロアーティストとして自由に活動できる機会を得たんだから、丁度僕の人生が次の章へ移ったと考えている。」
さて、Freddy Jones Bandのように1枚で10万枚平均の売上を記録できるだろうか。
まずは良いレーベルを見つけることが第一であるとは思うが、このままで歓迎されるならそれが一番かもしれない。
かなり大人しい作品なので、物凄い一般受けはしないと予想しているが、良質なルーツアルバムである。
さり気ないポップさとじっくりと何回も聴くことが好きなリスナーにはかなりのヒットになるだろう。勿論、ルーツロック好きな方には手にとって貰いたいアルバムであるのは言うまでもないが。 (2002.6.25.)
 Please Quiet Recording / Paging Raymond (2001)
Please Quiet Recording / Paging Raymond (2001)
Roots ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Alt-Country ★★★☆
You Can Listen From Here
「Please Quiet Recording」・・・・・・・何とも解釈の余地があるタイトルだ。
細かい文法に斟酌しなければ、「レコーディング中は静かにお願いします。」という訳も成り立つ。
「平静な気分で、落ち着いてレコーディングしませう。」
こういった、まだ駆け出しのミュージシャンがスタジオに入る際の留意事項について述べているとも考えられる。これとは逆に、必要以上にエキサイトし、汗を振り飛ばして熱くレコーディングをするという態度も悪くはないと思うが。
確かにPaging Raymondのサウンドからは、ビリビリとした緊張感のある演奏、といった雰囲気は伝わってこない。反対に余りある技量を、余分な力みを入れずに、さらさらと流れる清流の如く自然体で演奏しているという雰囲気が伝わってくる。
「音を必要以上に大きくしないで静かにレコーディングしませう。」
と、こう意訳することも可能ではないかとも思う。寧ろ、筆者としては「静かなレコーディング」という直訳をし、更に込められているメタファーを酌む必要があると思う。
このタイトルは、現在のアメリカン・メジャーを席巻しているノイズ・ラウド音楽の代名詞たる、Alternative、Heavy Rockといった黒光りする家庭内害虫なみに有害で鬱陶しいサウンドに対する、Paging Raymondの精一杯の皮肉ではないかと思う次第である。
内容は空洞でも、取り敢えずギターの音をノイジーに、スピーカーが割れるくらいにオーヴァーにすることをロックンロールと勘違いしている数多のグループ。まるでエテ公か原始人なみの脳味噌の少なさしか見えてこない。
ただノイジーに、ネガティヴな感情を打ち付けるだけのノイズには、良心もリスナーへの配慮も、何よりも音の組み立てと言う第一義な前提すら感じることが出来ない。
しかしながら、アメリカの10代、20代の年齢層が諸手を挙げて歓迎しているのが、こういったヘヴィでただ喧しい音なのである。自動車に例えると、これでスピードと快感を得たと自己満足している暴走族のようなサウンドだ。
同じ、爆走でもサーキットで闘われる、レーシングの迫力とプロ意識、何よりも技巧と言うギミックを内に宿さないサウンドが、メジャーのチャートにもしっかりと幅を利かせている。
このような趨勢では、どれだけ音の本質を大切にしたメロディックなアメリカンロックを創っても、殆ど広く世間に拡がって行くことは難しい。1990年代以前なら市場的に歓迎されたに違いないクラスのアルバムすら、メジャーの音楽産業は振り向きもしないのである。
こういったメインストリームの大半が良い音楽を忘却し、英国並の芸能化を果たしてしまった時代が長期に及んだために、インディが独自の市場を構築し、インディだけでも何とかビジネスになる時期が訪れている。とはいえ、リスニング人口のピラミッドはインディペンダントでいる限り、その表面積を増やすことは望外の幸運でもなければ、不可能に近い。
良い音楽を創ったのだから、ひとりでも多くの人にCDを購入して貰い、聴いて欲しい。
これはアーティストとしては至極真っ当な欲求である。その良いアメリカン・ポップロックを作成しながらも、ローカル活動をせざるを得ない現状に対して、婉曲的に皮肉ったタイトル 「Please Quiet Recording」。
嘆いても変革できない現状を動かそうとするなら、少しでも良い音楽を創り続けるしかない。進むことを放棄したら後にはペンペン草さえ残らないのだから・・・・とは理解していても、どうしても少しは言っておきたい。
こういった気持ちをPaging Raymondのタイトルに読んでしまうのは穿ち過ぎだろうか。
このレヴューを書くにあたり、Paging Raymondから幾つかの資料を頂いた。その中にこういったバンドの紹介文章が入っていた。
「最近のポップミュージックという文化は、ボーイズ・グループやラップメタルバンドが基本的なポップミュージックの創造やロックンロールのリズムを追い求めるバンドを駆逐してしまっている。より深く、そして流行に追従しないスタイルを追及するこれらのバンドはラジオ局の援護もレーベルの助けも得られず、世には大きく広まっていないAlt-Country、Roots Rock、Americanaを取り入れ、そしてしばしば一時代前のバンドと比較されることが多い。これらの音楽性に、深い歌詞とメインストリームの音楽を追い求める態度を持ち合わせたバンドがPaging Raymondだ。」
さて、筆者の偏見と独断に満ちたアルバムタイトルの曲解に従わずとも、バンドの意味することはお分かりになると想像している。当然ながら、このデヴュー・フルレングスは現在のアメリカ流行音楽とは全く次元の違う、心和むルーツ・ポップロックである。
Acoustic Popであり、Country Rockの側面もあり、そしてやはりAlt‐Country Rockという表現が似つかわしい。 Folk Rockともジャンル分けできないこともないけれど、アクースティックでジェントルな音創りの割には、ロックンロールとしてのフックが極まっているので、よりコンテンポラリーな表現を用いれば、Power Folk Popと呼ぶのが適当かもしれない。
無論、単にアクースティックなだけでなく、不快指数が全くない乾燥帯の夜の大気のようにふんわりと心地よい土臭さがどのナンバーにも感じられる。上でCountryという単語を使ったけれども、あからさまにカントリー・フィーリングを出しているナンバーは筆者的には皆無。
Countryというよりも、American Tradの陽性で明るい部分を、Countryという軽過ぎるフィルターを通さずに、アメリカ中西部の大地を通して組み上げたようなサラサラと手触りの良い草の根サウンドというべきだろう。
こういったカントリーやブルーグラスをコテコテに表現せずに、ポップロックというより普遍的なパイ皮に包んで蒸し焼きしたような中庸的なルーツサウンドが、一番メインストリームたるヒットシングルに近いところにあるのではないだろうか。くどいが、現在は違う種類のゴミがメイン街道を支配しているけれども。
無駄にハードでラウドなギターをフューチャーしていないのに、思いの他ロックンロールを、アップビートの歯切れのよさを感じてしまう。これが実にマジックというか不思議である。エレキギターのドライヴな押し出しが殆どなく、アクースティックなアレンジを中心にアンサンブルを纏め上げている。
通常、こういうフォーキーな方向性を御楯にかざしているバンドは、やはりアクースティックの柔らかさだけが目立つものなのだが、Paging Raymondには高速道路を法廷速度以上で運転している、が疲れる程のオーヴァー・スピードでないクルージングの快感という要素を覚えるのだ。
これは、メロディとビートの組み合わせがとても絶妙で、どのナンバーにもメロディが単なるフォーク・サウンドに終始しない「掴み」が存在する故だろう。イコールReal American Pop/Rockということになるだろう。
ここまでに挙げてきたジャンルや音楽性がが全て網羅可能な音楽性をこのバンドは有している。
つまり、時代が20年前に戻ったなら、間違いなくAdult Contemporary RockやAdult Rockという、または死語になってしまったが本邦で頻繁に使用されたMORという呼び名で通用したサウンドだ。
現在でこそ、Roots Pop/Rock、Americana、Alt-Countryというジャンルに属することになるが、時代がマトモであったなら絶対にTop40入りする筈の王道アメリカン・ナチュラル・ミュージックであると思う。
上にリンクした試聴先の紹介コメントにはこうある。
「好きにならずにいられないメロディのフック、甘いヴォーカルのハーモニー、身体に染み込んでいくような詩に心を和ませられる。(中略)・・・・・・Barenaked Ladiesのポップさの感性を、Counting Crowsの溢れるばかりの感情表現の妙を、Jayhawksのハーモニーの美しさを、そしてRyan Adamsのような驚くべき詩才。これらをよくかき混ぜると、Paging Raymondとなる。」
実際、これだけでPaging Raymondを紹介するに事足りるようにも思える。・・・・まあ、簡潔なのは良いことだが、そうなるとこのHPの意義がなくなってしまうため、レヴューは続くが、ここに列挙されているメジャーなアーティストが受け入れ可能なリスナーならば、絶対にPaging Raymondは引っ掛かりがあること請け合いだ。
寧ろインディペンダントであるため、メジャー発売の制約から自由であるため、更にクラッシック・ポップロックの美味しい面を追及しきれているともいえる。
兎に角、全編12曲のうち、ポップ度合いが足りないのは1曲たりとて、無い。全てがAdult ContemporaryやTop40のラジオ局で歓迎されること請け合いのメガ・キャッチーで激烈ポップなナンバーである。その上、ポップ過ぎるアルバムにしばしば起こりがちな、ポップ過ぎて却って1曲のインパクトがぼやけてしまうとか、軽く聞き流してしまい、後まで残らない、といったネガティヴな効果を付随することもない。
これは、どのトラックにも強烈にリスナーを惹き付けるポップミュージックの麻薬ともいうべきパンチが効いているからであり、編曲が全く自然で耳を疲れさせないからである。
ややロックテイストを増すと、例えとしては適当でないかもしれないが、Nelsonのウルトラ・スーパー・キャッチーな「Because They Can」(1995年)に近い、抜けるようなキリリとした爽快感がある。
ヴォーカルが2枚であり、ハーも-ニーを豊富に噛ましている点でも、Nelsonだけでなく、「Tomorrow The Green Glass」(1995年)のJayhawksをシンクロしてしまう。
ちなみにヴォーカリストは似たようなビア樽体型のAaron AdelspergerとTim Wilsbachさんである。筆者と交流のあるのはTimさんの方、どうでもいいことだけど。(を)
2人のリード担当曲を参考までに紹介しておこう。
#1『23 Miles』、#3『Walking Underwater』、#5『Static』、#6『Pine Street』、#8『Ghosts』、
#10『Queen Of Carolina King』、#12『Parcel』の7曲がAaronのリード。
#2『Alibi』、#4『Colorado』、#7『Let It Out』、#9『She』、#11『Disappear』の5曲がTimの喉で歌われる。
#11『Disappear』のみAaron Adelspergerの作をTim Wilsbachが歌うが、それ以外のナンバーはそれぞれ、TimとAaronが単独で作詞作曲した曲を自分で歌っている。この2人のソングライターがそれぞれ自分の歌を唄うスタイルはバンドの成り立ちに起因するものだが、これらのことは後程紹介することにしよう。
ヴォーカルとしてはAaronがGathering FieldのヴォーカルであるBill Deasyに似た、鼻に懸かったようなキーの高目で甘い声の持ち主がAaronである。
ややラフでソウルフル、ガラガラ声程の行き過ぎではなく、NelsonのMatthew Nelsonを思わせる程好く枯れた柔軟性も秘めたヴォーカルがTimである。
この2枚のヴォーカルがあるからこそ、Paging Raymondの曲はより一層曲ごとにさり気ない変化を持つことが出来、結果として飽きの来ないナンバーとなっているように感じる。
傾向としてはAaronがややレイドバックの匂いが強いナンバーを担当し、ロックビートとタイトなリズムが大目の匙加減の曲はTimが歌う、つまり両者の作成するナンバーの違いが出ているようにも思えるが、どちらのヴォーカリストもお互いの役割を変えても、問題なく嵌まりそうな懐の深いオルタネイトなヴォーカリストである。
裏を返せば、物凄く強烈な個性にはやや欠如するが、親しみのもてる感じの良いヴォーカリストが2枚揃っているということでもあるのだ。このヴォーカル・パフォーマンスはPaging Raymondの一番の武器だろう。
まずはAaronのやや軟体質のヴォーカルが軽やかに弾む、#1『23 Miles』からアルバムは幕を開ける。タンバリンのシャッシャという楽しげな音に、控え目なマンドリンの弦が加わり、更にハンド・クラップ−拍手までが合流し、思わず上半身が踊り出すようなナンバーである。全く癖がないけれども、取っ掛かりの豊富な最高級のポップロックナンバーであり、トラッドのフィーリングも潤沢である。
Paging Raymondはアメリカの中西部であるインディアナ州のバンドだが、1970年代のWest Coast Rockを思い浮かべてしまうような懐かしさもある。
#2『Alibi』はこれまたマンドリンと、アルペジオ的に奏でられるギターの音色がとても綺麗なポップロック・チューンである。Aaronより引き締まったTimのヴォーカルが実に曲にマッチしている。またバックにささやかに流れるオルガンと、サンプリング・ピアノ的に処理されたアクースティック・ピアノの細かい鍵盤運びも見逃せない。2分過ぎからグンと押し出される演出も心憎い。このピアノの音出しはEaglesの名曲『Lyin’Eyes』のエレガントな音響を思わずに入られない美しさがある。また、各パートで微妙に速さを変えるメロディの繋ぎ方も巧みで、一度聴いたら最後まで集中せざるを得ない吸引力のあるナンバーでもある。
#3『Walking Underwater』はTimのハーモニカがとても暖かい音色を大気に溶かし出している、優しいフォークロックというナンバーである。お馴染みとなってきたマンドリンとTimとAaronのハーモニーは言わずもがなである。歌詞もまた哲学的というか、言いたいことが口には出てこない、書きたいことが筆に乗らない、という葛藤を耽美派の詩人のようにロマンティックな世界で表現している。
ハモンドオルガンとドラムの音が中心で歌い上げられるバラードが#4『Colorado』。Timの腰の強いヴォーカルがなかんずく発揮されたナンバーでもある。後半でピアノ、ギターが出現するが、殆どハーモニー・ヴォーカルを無しで歌い上げられる珍しい曲でもある。こういったRootsというよりもAdult Contemporaryな曲はTimが得意のようだ。
対照的にフォークロアで、ハーモニーを多用したレイドバック・アクースティックなバラードが#6『Pine Street』である。こちらはAaronの作品でヴォーカルも彼。静かというよりも閑かというデリケートなしめやかさが余韻を引く。タイプとしては淡白であるが、良いバラードである。
#5『Static』はTimのルーラルなハーモニカの影響だけではないが、かなりAlt-Countryの側面を見せてくれる曲であると思う。12弦ギターのボトルネック的なアレンジも一役買っているのだろう。が、あからさまなヒルベリーそのままというサウンドを聴かせずに、アクースティック・ポップとして仕上げているところが、このバンドがCountryではなくPop/Rockのグループである所以であると思う。
2曲のバラードが続いた後、またもやミディアム・バラードという感じで始まるのが#7『Let It Out』である。筆者が数あるフェイヴァリットの中で最も好みなのもこのナンバーである。形としてはエモーショナルなバラードであるが、ロックンロールとしての力瘤をメロディの進行に漲らせている曲でもある。兎に角、Timの感情を入れ揚げたヴォーカルが何とも感動的なのである。♪「Let It Out」をリフレインするパートはついついTimと一緒に口ずさんでしまう。バラードの3連荘も全く気にならない流れは素晴らしい。
#8『Ghosts』はジャラジャラとしたギターがロックのビートを刻む鋭いドラムと共演を見せる。かなりアーバンで彼らとしてはダークで攻撃的なロックナンバーであるが、この歌をAaronが唄っているのがユニークである。ややルーズで気の抜けたところもある彼のヴォイスで歌われると、それなりにマイルドなロックチューンとなるのが不思議た。
#9『She』もTimのシャウトに導かれて、熱いロックアンサンブルが展開されるロックナンバーである。これまた前半では存在しなかったアグレッシヴなドライヴ・チューンであるが、しっかりとメロディのキャッチーさは押さえているので気持ち良く聴くことができる。内容も歌に併せたようなシンプルなラヴ・ソングである。同じロックナンバーでも#8の内省的な暗い詩とは対照的だ。
ロック2連コンボの後は、かなりトロリとしたルーツ・スローな#10『Queen Of Carolina』が来る。牧歌的というかグラスルーツのユルリとした音楽性を感じるが、同時にポップ・バラードとしてのツボを押さえたメロディ・メイキングが光るアレンジも目立つ。殆どがハーモニー・ヴォーカルで唄われ、かなりのハイトーン且つファルセットなAaronの唄い方まで聴くことができる。
アップビートなチューンとしては最もキャッチーで明るいのが#11『Disappear』である。ロック・マンドリンとしてのパワフルなリフも楽しめる、パーティ・サウンド的なロック曲ともいえる。他のロックチューンとは異なり、アクースティックな楽器の割合を非常に多くした創りが一本抜け出たナンバーとしている。最後に観客の拍手や歓声のSEまで加えてライヴ的な曲であることを強調しているが、確かにアクースティック・セットの会場では軽快なスピードサウンドとして受けそうなナンバーである。3分以内で終了するのが勿体無い。
最後のナンバーはマンドリンとハーモニカをベースに弾き語りのスタイルで奏でられる#12『Parcel』となっているけれども、2分弱というリプライズ・アウトロ的な性格の強い小作品であり、シークレットトラックとなることの方が一般的には多いのではないかと思う。少々最後の2曲が即興的なのが物足りないというか、締めとしては力負けしているように思えるのが、画竜点睛を欠くようでもある。まあ、贅沢な不満でもあるけど。
最後にバンドについて簡単に触れておこう。
活動拠点はレースイヴェントで有名なインディアナ州の州都インディアナポリス。ライヴでは北へと大平原を縦断していけば殆ど真っ直ぐなシカゴとインディアナポリスを行き来するような活動をしている。
「僕たちのルーツは全編に渡り描いたつもりだ。このアルバムはTimと僕とのソングライティングの集大成みたいなものだよ。僕とTimはこのCDの曲をバンドを組む前からそれぞれ独りで書いていたんだ。」
とAaronは振り返る。TimとAaronそしてドラマーのStephen Fieldsはインディアナ大学の学生寮でのルームメイトだったそうで、彼らは独自にバンドに所属し活動していたため、あくまでもサイド・プロジェクトとしてPaging Raymondを作った。
「僕等は高校生の時は、ガレージロックのバンドとして一緒に演奏していたので、一緒に曲を創ったりジャムるのは楽しかった。けれど、結局はそこまでの活動で、バンドとしてライヴをするつもりは全くなかった。」
実際にこのアルバムに収録されている曲で一番古いナンバーを書いた時は1994年のことであり、1998年に正式にライヴバンドとして活動するまでは、スタジオ録音の合間を縫ってたまに曲を書くアイディアを出し合う程度の性格しかない有名無実のバンドだったのだ。
「バンドとして活動するようになったきっかけは、Aaronを僕のスタジオ録音のプロジェクトにゲスト奏者として招いたことだね。その数ヵ月後にAaronが僕に彼とStephenのバンドに加わらないかと打診してきた。ここで第二期のPaging Raymondが動き出したんだ。」
とTim。
「数回のセッションをやった後、このメンバーの持つエナジーを感じた。これはこのメンバーでライヴをやらなければならないと思ったよ。」
Stephenはこう語る。そしてこの3名にプロデューサーのSteve Creechがピアノ、オルガン、ギター等をサポートして2001年1月完成したのが「Please Quite Recording」である。
2000年の夏には準メンバーとしてChris Fosterがライヴのみのベーシストとして加入している。が、レコーディングには参加していない。アルバムではAaronがベースを担当し、Timはマンドリンとハーモニカ、Aaronもマンドリンを抱えている。が、2001年に正式にChrisがメンバーとなり、更に1名を増し、クウィンテットとなる。現在のバンド編成は次の通り。
Aaron Adelsperger (Vocal,Acoustic Guitar) , Tim Wilsbach (Vocal,Acoustic Guitar)
Stephen Fields (Drums) , Chris Foster (Bass) ,Jim Borders (Electric Guitar,Mandolin)
キーボーディストがレギュラーでなくサポートメンバーでツアーをしているらしいのが惜しい。絶対に鍵盤を加えた方がライヴでもしっかりした音の出せるバンドになると思うのだが。
この2枚のヴォーカリストがそれぞれの曲を持ち寄ってアルバムとするスタイルはお隣のオハイオ州のグループであるHensleySturgisと相似点がある。
HensleySturgisがかなりハードでガッチリしたルーツロックであるのとは違い、Paging Raymondはアクースティックでポップなバンドであるが、どちらも最高級のRoots Pop/Rockであることに変わりはない。しかも、今日の潮流からは弾き出されているという状況も共通している。何とかもう少しブレイクして欲しいものである。折角良質な嘗ての主流な音楽を提供してくれているのだから。
メジャーの五月蝿過ぎる雑音にこそ、「静かにレコードを売れ!」・・・・「つーか売らんでエエ!静かにスタジオで引き篭もっとれ!!」と声を大にして言いたい。・・・何時も叫んではいるが。(苦笑)
もう少し良いロックが売れても良い時が来ても良い頃だとは思う。Paging Raymondのような良いバンドが出てくる下地が残っているのだから。 (2002.6.28.)
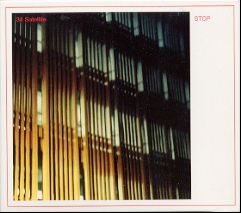 Stop / 34 Satellite (2002)
Stop / 34 Satellite (2002)
Adult-Alternative ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Roots ☆
You Can Listen From Here
「し、司令官!もう限界です!!艦体が持ちません!!離脱の許可を!!」
「凌げ!!何としても離脱は防がねばならない!!脱出は臨界点まで我慢するのだ!!」
だ、駄目です。このままでは皆揃ってお陀仏です!!臨界点突破!!各部被害増大!!もう、もう駄目です!
「イカン!ここで我々が踏み止まらねば、明るい明日は来ない!!各員、持ち場を死守せよ!!」
「む、無茶だ!!・・・・・強制離脱します!このままでは全滅必死だ!!」
「ま、待て!命令違反は厳罰だぞ!」
「構うものか!!強制手動に切り替えヨシ!!」
「止めろ!止めるのだ!!」
「強制離脱開始!!!我々はここで終るわけにはいかないのだ!!全ての責任は本官が取る!!!」
「短慮はよせ!!考え直せ!!!」
「スイッチ・オン!!!」
「止めろ〜〜〜〜!!!」
「脱ルーツサウンドッッ!!!!」
(懐かしの合体ロボットアニメのヒーローが攻撃をする時に叫ぶように言うとなおマルです。)
「ダメダアアアア!!!!!」
<次回!!・・・・・に続きません>
てな音楽性のアルバムです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなんで分かるかああ!!!!
って、ツッコミ入りそうですが、どうにも執筆の気力が十分に惹起しない、悪くないけれど凄いストライクでもないサウンドに変革してしまってるんですよね。
のっけから意味不明な毒を吐きまくってますが、まあ、これにアヤシサとかあやふやさ、評価の定まらない、といったこの「Stop」についての筆者の感慨を読み取ってもらえれば幸いです。(できるか!!!)
まあ、一言でいうと、
殆ど脱ルーツロック。モダン&アダルト・オルタナティヴ式ロックサウンドがグンと増えてしまっている。(長いやん!)
ということになります。
ここで、いまいち微妙なのが、完全にRoots Rockが脱色されて塩素の匂いがプンプンしているかというと、意外にもそうでもないことです。
物凄い、Modern Rock Tracks系のチャートで受けそうなアレンジと音出しになっているし、曲によってはAlternative Rockの下世話な卑俗性が全開なものもあります。
ですので、完全にRootsから足を洗ってしまったというと、少々語弊がありますが、95%以上は脱出してしまっていると思います。
それよりも、何よりも
Alt-Country Rockらしさは完全に消滅しました。秋の青空のように染み一つ残さず消え去ってます。(涙)
これを以って、しょうむないアルバムとは言い切れません、ところがどっこい。
まあ、大好物ともいえないところが、Fine Line(Steve Winwood調に唄うべし)ですけど。
バンドは2枚のEPと3枚のフルレングスをこの「Stop」も含めてこれまでにリリースしていますが、Alt-Countryの色合いが濃かったのは厳密には2枚目の「Rader」(2000年)のみであり、またややルーツ色が相対的に少ない、1st作の「Star」(1998年)もAlt-Countryを感じられるアルバムではありました、2枚目「Rader」程の統一感はありませんが、デヴュー盤であり、バンドとしてもメンバーが固まっていなかったことを考慮すれば良盤でしょう。
が、元来34 Satelliteというバンドそのものが、ペダルスティールやマンドリンを大幅に目立たせ、カントリーをベースにしたCountry Rockをやっていた類のバンドではなく、スマートで洗練された現代的なポップサウンドをルーツとアクースティックなポップロックとミックスすることで足掛りを築いてきたバンドです。
Alt-CountryとModern Pop/Rockの中間を選択していた、かなり境界線の危ういサウンド上のアリア(?)を綱渡りして姿勢を保って来たバンドなので、どちらかに重心を崩して倒れ込む危険性があるかな、と不安を半分くらい抱いていましたが、今回の「Stop」で見事ルーツとは正反対の方向に転向してくれました。
何せ、このタイトルは素晴らしいですね。「Stop」ですから。
まさに#1『Elijah St.Marie』を聴いた瞬間、タイトルを叫びましたからね。
「ちょっと待たんかい!!コラ!!」
(英訳するとStop Itかもね)と。ここまでポジティヴにしろネガティヴにしろ、第一聴の気持ちがタイトルにシンクロするのも稀でしょう。
このセリフをリスナーに言わせるためにこのタイトルを選択したとしか思えないくらいのサウンドの変革がクッキリと居座っています。(ちなみに#5『Stop』の歌詞の内容とは何の相関性もありませんが。)
いきなり、アーバンで硬いギターのリフが来て、その後からはモロにコンテンポラリーな流行を追従したまんまのノイジーなギターが入ります。シンセ類とモダン・ヘヴィ風のギター。このナンバーではルーツカラーは零です。
まさに、旧来のファンで、34 SatelliteのRoots Pop/Rockな側面に魅力を感じていた聴き手に、これ以上聴き続けることを
文字通り“Stop”させかねないオープニングです。イヤハヤ、すぱいすガキイテオルノウ・・・。嫌味。
まあ、救いとしてはGoo Goo Dollsの「Gutterflower」のようにメロディまでオルタナ化していないことが、まず大きな一要素ですね。
これは殆どのナンバーに付いて当て嵌まることです。要するにルーツロックからAAA的Modern Rockに鞍替えしようが、基本のメロディはそれ程スポイルされなかったということです。
が、#1にしても、アナログ・シンセサイザーと、エフェクトを掛けたパーカッションを使っている、少々タルイ流れのナンバーです。ナチュラルさは全く見当たりません。曲自体には物凄い脂ぎったオルタナは感じないところで、かろうじて踏み止まっている感じですね。
この#1を含めて殆どのナンバーがAlternative Rockにズッポリ漬かっていないのはまあ、良かったです。
しかし、完全にAlternative化してしまったナンバーも多いのです。
この「Stop」は今年の発売直後、CMJでかなり話題に取り上げられています。この事実をもってしても、今時のティーンズの好みである、ベタなオルタナ・サウンドやティーン向けラップメタルとは格の違うロックアルバムということは証明出来るのですが、反対に少々スノッブを気取りたい大学生が好むオルタナ的なモダンロック的な要素が多くなったという予想も成り立つのです。
事実、#6『Charleston』の翳りのあるシンセサイザーを多用した歯切れの悪い人工ポップ曲から、#7『There Is Gonna Be A Problem』のモロにAlternativeな下らないノイズ、#8『Caroline』のアンキャッチーでディストーションがてんこ盛りなヘヴィロック、と中盤は最低のナンバーが並んでいます。
更に、#9『Smoke From A Funeral』のイントロとして、ライヴで弾きまくるオルタナ・ギターのリフを入れていることも理解できません。#9自体はモダンロック風ですが、ゆったりとしたバラードの佳曲なのにぶち壊しです。
#10『Rock Stars Plastic Cars』はコマーシャルなコードを織り込んでいるのに、エフェクターを故意に掛けてマシンぽい演出をしたヴォーカルとオルタナギターがかなりメロディの素材を喰い散らかしてます。良いミディアムのパワーロックなんですけど。
とこのアルバムは、#2『Get Out Alive』から#5『Stop』そして締めくくりの#11『Getting High With A Stranger』から#13『Spaceman』が普遍的なポップロックとして鑑賞に耐えるナンバーが並んでいますが、真中が抜けているという、文字通り
空洞化したスカポンタンな部分のあるアルバムです。
しかし、その他のメロディの良いナンバーが全体のレヴェルを、天動説の地球儀を支える象さん・亀さんのように底上げしてくれているために、かなり聴ける作品となっているのです。
特に#2『Get Out Alive』はファースト・ラジオシングルになったのが分かるくらい、ドが付くポップでシャッキリしたドライヴ用のスピード・ロックです。適度に重心が低いのでルーツテイストも感じられます。
ルーツ的な重みのあるが押し付けがましくない気持ちよさがあるのは#4『Longest Day』でしょう。こちらも小気味の良い中速ポップです。何よりもCメロあたりからドラマティックな厚味を演出するストリングスが最高にアダルト・ロック的で素晴らしい。この曲もシングルとしてトップ40に入ってもおかしくないです。
#3『You’re Coming In Clearer』はアーシーな雰囲気とは無縁ですが、スコアのメジャーな組み立てはツボを押さえてますので、聴けるロックナンバーとなってます。ややヘヴィで自然な音出しをしないオルタナ・ギターがウザイですけどね。
タイトル曲#5『Stop』はメロウでアクースティックなアレンジのしっとりしたナンバーで、ここでもストリングスが効果的に使用されています。が、土臭さよりも都会的な流麗さを感じることが多いです。しかもインター・パートでギターソロを強烈に噛ましてアクセントを付けるという演出は正統で宜しいのですが、これがまたオルタナ的な人工ギターなのが残念です。
再び、ルーツロックというか正統派なアメリカン・ポップロックが飛び出すのが、#11『Getting High With A Stranger』と#12『Nineteen』です。両曲共に必要以上なクラフト・ロックなサウンドを使わずに「Rader」ほどナチュラルでもないにしても、Gin BlossomsやAtheneum的なメジャー感のあるナンバーです。
そして、最後がアレンジとしては一番土に近い位置にある#13『Spaceman』です。ギターがこれはかなりAlt-Country風なんですけど、惜しむらくは機械処理したヴォーカルと、マシン・ドラムに近い打楽器の録音アレンジがモダン風なスローナンバーにしてしまっています。
以上、現在はコロラド州をベースに活動する、34 Satelliteというバンドの2002年春に発表されたアルバムに付いて軽く述べてみました。
メロディ的には、Alt-Countryと評された2nd作「Rader」よりも吸着力のある取っ掛かりが増えている曲が多いのですが、問題はルーツとアクースティックの度合いを大幅に削り、モダン・オルタナティヴの面積を増量していること。
勝負曲で観察すると、全体的に平均的だった前作よりもキック力のあるチューンが#2、#4、#11、#12と増えているので返す返すも残念です。
詳しいバイオはいずれ「Rader」を書く時に解説します。
が、2001年になるまでオフィシャルサイトも存在しなく、情報集めに苦心したバンドなので、別の意味で印象が強いです。
有名人の歓迎パレードを期待して待っていたら、裏切られなかったものの、一本向こう側の通りをパレードしていくのを遠目に見ただけで、やや胃もたれする消化不良を感じてしまった、という気持ちが出てくる1枚となりました。。
Power PopやAdult American Alternativeといったジャンルが好きな方ならRoots Rockの愛好家よりも相性は良いと思います。まあ、買って損はないでしょうが、前半と後半だけに見せ場が固まっているので、中盤で相当ダレることは覚悟した方が良いでしょう。 (2002.7.3.)

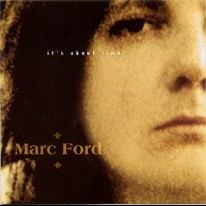 It’s About Time / Marc Ford (2002)
It’s About Time / Marc Ford (2002)