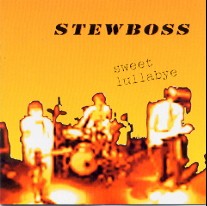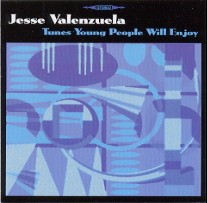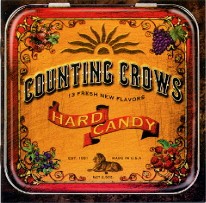 Hard Candy / Counting Crows (2002)
Hard Candy / Counting Crows (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Adult-Contemporary ★★☆
You Can Listen From Here
<Break Down The Rule>
何と言うか、初のフライング。
と書いても、著者の脳内でしか完結していないだろうから、説明をしておこう。(偉そう)
当レヴュー・サイトは発売し立ての新譜を積極的に披露する場所ではない、と考えている。
つまり、完全に筆者のペースで新譜を紹介したり、半年・1年前に購入したアルバムを思い出したようにレヴューすることもあるのだ。基本的に購入して積むことだけは絶対にしないので、それなりに新陳代謝は出来ているが、やはり書きたいものを書くというスタンスなので、帰結としてマイ・ペースにならざるを得ないのだ。
参考までに、英語圏では「マイ・ペース」なる単語は存在しない。完全な和製英語であるので、覚えておくと良いだろう。(更に偉そう。)
つらつらと書いてしまったが、5枚のアルバムで1クールとしている体制で、トップに持っていく作品はその時点で最高の出来と認定している物であることが基本と言いたかったのだ。
但し、数件例外はある。Big Silverのように予想外の当たりがあり、いてもたってもいられなくてレヴューに付け加えた例もあるので。
ここで漸く、つらつらと書き駄弁ってきた結論に入る。
要するに、この「Hard Candy」は、本レヴューで初めて、
未聴なのに、トップにアップしてしまったアルバムなのである!!! ・・・ってフォントを変えるまででもなかったりする・・・・・。
筆者は、「信者」なってしまったらレヴューアとして失格であると思う。
偏見結構、好き嫌い大いに善し、エコ贔屓おこしやす!! とは思っているが、
「このバンドの作品はどんなものでも、有り難や〜有り難や〜♪」
となる状態に陥ることだけはしたくないと、固く誓っている。毒舌を振るい、信者のアイディンティティを破壊するようなことをのたくるなら、絶対に自分は信者になってはいけないと、そう考えているから。これは、自分自身の戒め、とまで御大層な代物ではないけれども、そう心掛けるようにしている。
と述べつつ、Counting Crowsの4作目のスタジオアルバムは、先行シングル#2『American Girl』を聴いただけでトップのレヴューに決定してしまった。
・・・・まあ、舞台裏を明かせば、駄目作だった場合は次回レヴュー予定のStewbossの2nd作、「Sweet Lullabye」に差し替えるつもりだったのは内緒であるが。(をい)
それだけ、Counting Crowsには期待、というかまず大ハズレを堕(だ)すことはない、という勝手な予測をしてしまっていたのだ。
嘗て、メジャーでブレイクして何百万枚も売る成功を収めた後に、その成功を泥と恥で塗り込めて仕舞うような最低の駄作を出したバンドが、ミュージシャンがどのくらい存在したか、もう数えたくもない。
成功した故の自惚れか、次作へのプレッシャーか、はたまた評論家の批評を気にし過ぎたのか、「芸術的」な作品を作らなければならないという大馬鹿な錯覚に陥ったのか。
「新しいこと」をやらなければ評価されない・「進化無し」と批判されることを迷子の幼稚園児のように恐れるがためか、どうにも脳味噌を洗濯機に掛けてみたくなる衝動に駆られる程の迷走した方角へと片道切符で突き進むような駄作を作ってしまい、二度と還ってこなかったバンドについてはもう語りたくもない。(といいつつ、毎回ボロカスに貶すことを止めないが。)
ご存知のように、Counting Crowsはデヴュー前から「無名の大型新人」として、ヴェテラン・ミュージシャンを中心にアルバムリリース前から物凄い評価を得ていたとはいえ、1st作から大ブレイクを記録したバンドである。
1991年の結成から大物アーティストのフロントアクトとして積極的に起用され、デヴューアルバムにも期待を過大というくらいに掛けられたにも拘らず、そのプレッシャーをものともせず「August And Everything After」は850万枚を売り、「Recovering The Satellites」も全米初登場1位のアルバムとなり200万枚を軽く売り上げている。
3作目の「This Desert Life」で初めてチャート的には大成功とは行かなかったが、しかしRIAA公認のゴールドディスクは堅実に獲得している。
セールスとクオリティが全く比例しなくなった現代のチャートだが、Counting Crowsに関してだけは売上とクオリティをまだ信用しても良い気がする。それだけ、万人に訴え掛ける素晴らしさを有したバンドなのだ。
さて、4枚目のオリジナルアルバムとなる「Hard Candy」はどうだろうか・・・・・。
<1990年代におけるカウンティング・クロウズの位置>
以前、「Recovering The Satellites」のレヴューを書いた時、1990年代のアメリカン正統派ロックの屋台骨をこれから支えていくのは絶対にCounting Crowsという趣旨を書いたように記憶している。
今回の4thスタジオアルバムである「Hard Candy」を聴いて、21世紀の初頭に濁りきったアメリカン・ミュージックで最後の防波堤になるのはやはりCounting Crowsしかいないという思いを新たにした。
例え、100歳を超える長寿を私が全うし、次のハレー彗星の接近を思い出にして棺桶入りしたとしても、まず2100年に世紀が一つ増えるまでこの世に生を受けていることは無いだろう。
これからの人生で何年音楽を、ロックミュージックを聴いていけるかは全く不透明だが、Counting Crowsに出会えたことで20世紀後半から21世紀にかけて生きていたことに意義を見出せると考えている。
Billy Joelの名曲『Summer,Highland Falls』でBillyはこう語っている。
♪「They say that these are not the best of times but they are the only times I’ve ever known」
筆者は、1950年代、1960年代、そして1970年代の大半の音楽をリアルタイムで直に耳にしていない世代に属している。尤も、私の世代では大半は1980年代から音楽に入っていくだろうけど。
だから、「1970年代以降ロックンロールは死んだ。」という意見を目にしても、本当の意味では分からないのだと思う。その時代を生で感じていないのだから。
実際に、今がロックを聴くのには良い時代と思ったことは、1990年に突入してから殆ど無い。ポップロックという本来は娯楽性を何処かに内包する筈の大衆芸術が、グランジ・オルタナティヴという、作り手の自慰的な感情の垂れ流しの代弁者に堕落したジャンルが、米国を中心に受け入れられたためである。
しかし、「今が良い時代じゃないと、皆言うけれど、皆だって今現在しか知らないんだ。」というJoelの言葉にあるように、現在進行形で耳にする音楽は、知らない時代からレコードやCDの記憶媒体に刻まれ、時を越えて届けられる音楽よりも圧倒的に存在感がある。
勿論、自分が存在していなかった時空から流され続けているオールド・ミュージックには、永きに渡って愛聴される故の完成度の高さがあり、それは名盤として衰えない輝きを放っている。
とはいえ、オン・ゴーイングで体験してきた歌は、過去からの素晴らしい名盤にはない、追憶や回想を伴った、またこれから伴うという付加価値があるのだ。
だから、1993年に、「August And Everything After」という作品に出会ったことは喜ばしいことなのだ。それ以前にも前座としてのステージをローカルで見たことがあるのだが、本格的にバンドを追いかけることとなる。
「August And Everything After」は、全く当時の売れ筋からは遊離したアルバムであった。オルタナティヴ・ミュージックの影響から完全に逃れていたとはいえないが、それ以上に時代を数十年遡ったようなサイケディリックな緊張に満ち、アメリカンルーツ・ミュージックを現代ロックと絶妙に同居させた1枚だった。
Counting Crowsは以後3年毎に2枚のスタジオアルバムを発表していくが、どのアルバムもオルタナティヴというかAdult Alternative的な要素を含みつつも、メロディの良さがAlternativeという灰汁(アク)に負けずにいて、寧ろ灰汁を取り込んで大きく成長したような作品となっていた。
特に、ハードでスピーディなナンバーを多く内包した1996年の「Recovering Satellites」はそのスケールの大きさ、ヴァラィエティに富んだ多様な音楽性、そして歌詞の深さにより、まさにKing Of 90’s Albumである、私の中では。オルタナティヴ風のラウドでノイジーな演奏も多く聴けるが、それすらもCounting Crowsの紡ぎ出すロックビートを彩る副次的な助剤としかならないくらい、ポップロックの芯が玄武岩の柱の如く屹立している。
このロック金盤と比較すると、1999年の「This Desert Life」は相当大人しくなった作品である。アップテンポのナンバーが少ないのは1作目と共通しているが、「August And Everything After」に張り詰めていた鬼気迫る圧倒感はなく、ややユルめの余裕のあるアメリカカン・トラッド感覚が支配するアルバムだった。
これを成長と感じるか、退行と感じるかで「This Desert Life」の評価は一変してしまうだろうが、相変わらず人間が無意識に触れて欲しくないけれど、何時も頭の中で漠然とした不安や葛藤としてこびりついている事象や感情を大気に晒す働きをもって語りかけるAdam Duritzの詩といい、単にオルタナティヴ的な内省メロディで終わらないポップセンスといい、やはり一級品のアメリカン・ルーツロックアルバムだった。
このように、1990年代を通して、Counting Crowsは一度たりとも、その大成功によって徒に芸術性を追求するあまり、難解で奇怪な音楽に傾倒することも無く、また、そのセールスの好調を維持するため、外聞も恥じも無くオルタナティヴに染まることもなかった。
ここまで安定して大道な、ロック時代の開幕から綿々と受け継がれてきたど真ん中なアメリカンロックを供給しているバンドは、少なくともメジャーにはHootie And The Blowfishを除けば皆無である。
常に、大地にしっかりと足をつけ、自分達の現在を冷静に見つめているバンドであると思う。
1990年代的なモダンサウンド・オルタナサウンドとアメリカンルーツを巧みに融合させて成功したメジャーバンドは、Black Crowes、The Wallflowers、Collective Soul、Matchbox 20、The Jayhawks等結構数が存在するが、これらのバンドは何処かで沈没してしまっている。オルタナティヴやヘヴィロックに足を突っ込んだり、テクノロジーに溺れたり、成功に舞い上がって考え過ぎのアルバムをヒネリ出しただけ、という体たらくで、自ら創作した名盤の栄光に泥を塗っている。
こういった実例を見てきたので、1990年代のメジャー・シーンの良心であり続けた希少なバンド、それが私の考えるCounting Crowsである。
21世紀に突入しての初アルバム「Hard Candy」も、全く王道アメリカンロックバンドの名に恥じない出来となっている。
この先、何枚のアルバムを届けてくれるかは定かではない。リリース間隔もお世辞にも短いとはいえなし、将来的には解散してしまうことだって考えられる。
けれども、この先も確実に期待できるグループであることだけは確かだ。
『枚だけなら、誰でも傑作は作れる。しかし2枚、3枚と創ることは出来ない。』
これは誰の言葉だったろうか。蓋し名言である。Counting Crowsにピッタリな表現だろう。
<カウンティング・クロウズとカリフォルニア>
幸運にも「Recovering The Satellites」の発売時に、私は米国でのたくっていた。
Counting Crowsのホームグランドからは乗用車で8時間ほどの距離にあるL.A.に住んでいたため、直にバンドに触れるということはライヴ以外では敵わなかった。勿論、バーやコーヒーハウスで演奏しているインディバンドのように、ギグの後で一緒に一杯飲れる、などは夢のまた夢だった。
が、ロスであまり変化の無い四季を過ごした一番のサウンドはCounting Crowsだった。
カーラジオから、バーガースタンドのFMラジオから、そして自分のカセットテープの磁気情報から流れてくるシングル曲やアルバムの良曲。
私事ながら、L.A.の風景が、「Recovering The Satellites」と「August And Everything After」の曲を聴く度に浮かび上がってくる。
秋の夜、ハリウッドのクラブでライヴを見た後、フリーウェイを南下し、ダウンタウンの高層ビル街の蹲るようなシルエットとライトを横目にしつつハンドルを握っている時に、カーラジオから流れて来た「Daylight Fading」。
歌詞にあるように、カリフォルニアに忍び寄ってくる冬を感じた。
クリスマスの晩、サンタモニカでパーティをやった後、レドンドビーチをゆっくりと流して帰宅した深夜に聴いた「A Long December」。その時は、まさか転勤を食らうとは思いもせず、歌と込めた意味は反対だけれども、この12月がもっと長く続けば良いのに、と思ったりした。
2月、突然の豪雨の中でフリーウェイに溜まった水に浸かりながら戦々恐々として運転した中で流れていた「Rain King」は、カリフォルニアの雨をまさに思い起こさせる。反対車線でスリップして炎上していた乗用車もこの歌を聴くとくっきりとその惨状が浮かんでくる。
深夜、レポートをアパートで書きながら聴いた「Omaha」。いま、日本を離れてこうしている自分の人生は、10年前には全く予想もできなかったことを改めて感じたりした。
休日、ビーチへとランニングした際に、ヘッドホンステレオで聴いた「Have You Seen Me Lately」。西海岸の気候は夏でも走るのに軽快だったが、更に背中を後押ししてくれるドライヴ・ロック。こういったカラリとしたナンバーは湿った日本で聴くよりももっと爽快感があった。
街中を外れてアリゾナへ向う時、知らない原野の中でフリーウェイを降りて月を眺めた時に、横にあった「Perfect Blue Buildings」。何故、ここまで物悲しい気分にさせるのか。
仕事でかなり嫌なことがあり、憂さ晴らしのドライブで出かけたサン・ディエゴの夕暮れの海岸で食べたチャイニーズ・ファーストフードと「Angels Of The Silences」。嫌なことは紺碧の太平洋へ飛んでいってしまった気がして、少々現実逃避ができた・・・・・。
瑣末な、泡沫のような記憶がどんどん浮かんでくる。「Recovering The Satellites」のレヴューでも似たようなことを書いているかもしれないが、やはり私のリアルタイムで経験した西海岸のバンドはCounting Crowsなのだ。
嘗て、椰子の木と南国風建築のイメージの代表であったEaglesは、既にアメリカの土を踏んだ時は過去のバンドとなってしまい、憧憬のカリフォルニアの象徴である。
だから、遠くに思うカリフォルニアはEaglesであることもあるが、現在はCounting Crowsなのである。
#5『Goodnight L.A.』を聴いて、当地での独りの生活を想い出している。
<で、やっとハード・キャンディについて>
どうやら、Counting Crowsは3年おきにアルバムをリリースするというペースを確立してしまったようである。1993年のデヴューアルバムから綺麗に3年毎に(1998年のライヴアルバム「Across The Wire」は別だが。)スタジオ録音盤を発表してきて、2002年は待望の4作目が届いた。
今回は、ジャケットとタイトルを関連付けして楽しむという遊び心も見せている。見て分かるとは思うが、スチール缶製という些か日本では古典的な意匠を故意に施した高級品や贈答品にしか見られなくなったキャンディの箱をあしらったものとなっている。
更に、「Hard Candy」が13曲入りであることと結び、“13 Fresh New Flavors”=13の新鮮でで新しい味、とコピーを印刷し、製造メーカをもじってEST.1991−1991年設立というバンドの結成年まで提示している。
今までのアルバムのジャケットもかなりアーティスティックな構成が目立つバンドだったが、今回は構図やデザインよりも内容を強調するジャケットになっているように思える。
さて、13の味を持つ“Candy”の出来はどうだろうか。
前評判では、「Hard Candy」がこれまでで一番アメリカン・トラッドの感覚から離れた方向に進んでいるとまことしやかに囁かれていた。
それは予定されていた、またアルバム録音に入ってもオフィシャルにステイトされていたプロデューサーが、元オルタナティヴ・ロックバンドのCamper Van BeethovenのメンバーであったDavid Loweryであったことも原因ではないだろうか。更には私が蛇蠍のように嫌悪して吐き気さえ催す最低のバンドCrackerのメンバーでもあったので、DavidがCounting Crowsをオルタナ色に染め上げないか、かなり本気で心配していたし、絶対にミスマッチのプロデューサーであると断じていたくらいだ。
しかし、意外なことにフタを開けてみると、プロデューサーはSteve Lillywhiteに変わっていたのだ。そしてEthan Jones、Ron Fair、Carl Granvilleといった人達が共同プロデューサーとして何曲かで協力してた。そしてCounting Crowsもプロデュースに名を連ねていた。
Steve Lillywhiteという人は必ずしも一定のジャンルで仕事をする人ではなく、むしろ前衛的や革新的なアーティストと組むことが多い。
Peter Gabriel、U2、Dave Matthews Band、Pogues、XTC、Simple Minds、Talking Heads、Phish、Sinèad O’Connor、Marshall Crenshow、Morrissey等、彼が手掛けたアーティストをメジャーで列挙しても直ぐにこれだけの数が揃う。
中には著者が全く聴けない音楽もあるし、結構テクノロジーを使って斬新さを求める奇抜なアーティストも彼のファミリー・ツリーには多い。David Loweryも心配の種だったが、Steve Lillywhiteもまた安心の出来るプロデューサーではなかったのだ。
しかし、実際に聴いてみると、不安は即吹き飛んだ。
確かにアーシーさ、アメリカントラッドの土臭さは相当数減退をしている。
例えば、プログレッシヴというべきか、ポップではあるが奇怪なマシンノイズやキーボードを加えたアヴァンギャルドな#8『New Frontier』はかなりLillywhiteの影響を感じる曲だ。Counting Crowsとしては珍しく少々首を捻りたくなるナンバーである。悪い曲ではないが、ややアレンジの趣味が宜しくない。歌詞自体はAdam Duritzの内面をマテリアル的に描写した面白い曲なのだけれど。
それは兎も角として、ルーツ/トラッドの匂いがやや薄くなった代わりに、ポップの温度がかなり上昇している。全体を包括して評価すれば、これまでの4作で最もキャッチーなアルバムだろう。
しかも、Alternativeのゲスで糞尿な悪臭が殆ど感じられないメロディと相成っているのだ。
これは若者だけでなく、より幅の広いリスナーの嗜好に歓迎される方向性だ。目立って古臭い音出しもしていないのに、現代ロックに宿唖の如く寄生しているAlternative Rockをここまで濾過して薄めることが出来たとは。
Counting CrowsをAAA=American Adult Alternativeの旗手として取り上げるメディアが多数あるが、このアルバムはもう、AAAではなく、American Adult Contemporaryに成長していると思うのだ。日本でいうAORと同義の音楽ジャンルだ。
アダルトと書くと、ロックを演っていたバンドがバラード中心のポップバンドに趣旨換えしてしまったという印象を持つロックファンも多いと思うが、そういった下世話な言い方でもこの場合は良いと思う。
元来、Counting Crowsは2枚目を除いて、アップ・ビートの曲はアルバムに数曲というパターンを踏襲しているバンドであり、闇雲にロックンロールを叩き付けるだけの単純バンドではない。
この意味においては、「Hard Candy」も1st作の「August And Everything After」からの伝統を受け継いでいるアルバムである。アップテンポのナンバーは殆どなく、ミディアム・テンポ以下の曲が大半を占めているからだ。
ロックンロールナンバーが少なくなり、落ち着いたという印象は3rdの「This Desert Life」で既に感じていたが、最新作の「Hard Candy」の方が遥かに大衆受けする―卑俗な言い方だが―親しみ易さが増している。
これを老成と呼ぶのか、ポップになった堕落と決め付けるかはリスナー次第だ。が筆者の場合はある程度の成長であると思っている。
これまでに、サイケディリック、オルタナティヴ、トラッドといった要素とポップさを同居させつつどこか尖がった雰囲気を緊張感として表現することに成功してきたCounting Crowsが、張り詰めた神経にゆとりを持ちえて、ポップミュージックを素直に追求する下地が固まってきた証左であると感じているからだ。
欲を言えば、老成の方向がアーシーさとルーツテイストに向かい、『Mercury』や『A Long December』のような土臭いトラックが増えて欲しかったのだが、それは将来に期待するとしよう。
バラードとスローナンバーが多いアルバムなのは「This Desert Life」と類似しているが、安定感とロックンロールの質量はこちらの「Hard Candy」の方が比重がある。
特に、ロックンロールなスピードナンバーがほぼ皆無なのに、ロックンロールのパワーと馬力を感じられるというのは、実に稀有なアルバムだ。単にパンキッシュなステロタイプ・パワーポップ音で固めたパンク・ポップのアルバムよりもずっしりとした質感と手応えがあるのだ。
これはバンドのヴォーカルからリズムセクションに至るまでの技量が高いこと、そしてデヴュー時からレコーディングには常に参加し、スライドギター、バンジョー、マンドリン、シタールといったルーツ楽器を一手に引き受けてきた“もうひとりのCounting Crows”であるDavid Immerglückが遂に正式な7人目のメンバーとして加わったことも大きい要因であろう。
直截的な土臭さは後退したものの、Immerglückがメンバーとしてアンサンブルに加わったことで、彼の担当するルーツ楽器が更に堂々と鮮やかな色彩を帯びて、合奏の端々で聴くことが出来る。
このことにより、上品な土の香りがインプロヴィゼイションに付加され、結果としてサウンドを更に地に足の着いた存在に導いているのだ。
また、7人体制にしてしまい、完全にメンバーのみでレコードをライヴステージで再現できるようしてしまうという、バンドの拘りも微笑ましいものがある。Immerglückがツアーに参加しない場合は、David Brysonがマンドリン等をライヴで抱えてきたが、これからはそういった二役を演じる必要がBrysonにはなくなったのだ。
バンドの成り立ちや経歴についてはメジャーなので割愛。このあたりで簡単に各曲について述べ、長過ぎる駄文に終止符を打つこととしよう。
13色・13味のキャンディのうち、鮮やかに味覚を刺激してくれるのは、冒頭の2曲だろう。
これまでの3作でも、オープニングからの2曲は物凄いインパクトのある並びだったが、「Hard Candy」においてもその伝統は生きていたようだ。
#1『Hard Candy』、そして先行シングルとなった#2『American Girl』はハード・キャンディならぬ、ソフトで甘い、しかもテイスト鮮やかなポップロック・チューンである。全体的にスピーディな曲が少ない構成だが、前半2曲は『Daylight Fading』に匹敵するような最高のポップロックである。
クリアで済んだCharles Gillinghamの叩くピアノ音が、クリスタルの玄室に響くような麗朗とした音色を出し、弾むメロディラインを彩っている。ちなみにCharlesはメンバーの中で他のミュージシャンのバックバンドとして唯一来日している人である。バンドのバックボーンを顕示しているかのような西海岸風コーラスにはMatthew Sweetが参加しているのはかなり驚きだった。
そして、これまたCounting Crowsの中でもトップクラスのコマーシャルさを掲げる#2『American Girl』。バックコーラスにはSherly Crowが参加し、曲に華やかな味付けをしている。ルーツ色は殆どないが、モダン・ポップロックとしてトップ40に入る宿命を帯びて作られたような良曲だ。
歌詞は、#1はDuritzお得意のミステリアスでナンセンスな事象に載せた人生を問う感じの詩。#2は一見ラヴ・ソングだが、かなりシニカルな現代の冷めた恋愛感を揶揄しているように感じる。
相変わらず、Adam Duritzの詩は深いのだが、今作はあまり突っ込んだ深い意味合いを求める歌詞や内面世界を不可思議に吐露する感触がやや緩和され、より分かり易い題材を素直に(Adamにしては)書いているようにも思えるのだが、皆さんは如何だろう。
フェンダー・ローズを始めとする鍵盤がじっくりと歌い上げる、Counting Crowsの十八番のスローナンバー#3『Good Time』を挟み、アーシーな地熱が伝わってくるようなミディアム・ロックの#4『If I Could Give All My Love or Richard Manuel Is Dead』が現れるが、このスライドギターを聴くとやはりCounting Crowsにはトラッド風の大地の拡がりを感じさせる曲が必須だと再度思ったりする。
ふと日常を振り返って、歩んできた日々の生活の無意味さを問いたい衝動に駆らせる、Adamの詩作の才能が発揮された#5『Goodnight L.A.』はバラードとしても詩としてもかなりお気に入りなナンバーだ。#3のようなマイナーバラードのデリケートさよりも、こちらのメジャーコードなバラードの方が個人的な好みだから。
#6『Butterfly In Reverse』はストリングスを取り入れた、欧州的なムードを湛えた曲だが、共作詩者があのRyan Adamsであり、しかもヴォーカルとしても参加しているとは。それ程凄い曲ではないと思うが、オーヴァー気味なストリングスに『I’m Not Sleeping』を思い出した。
ストリングスを導入したナンバーなら次の#7『Miami』の方がスケールが大きく、パワフルなビートが気持ち良い曲であると思う。プログラムを使用したようなビートに導かれて始まり、あれっという違和感を数秒覚えるが、そのメロディの吸引力に即引き込まれて、ただ曲を楽しむだけだ。このアルバムでは作曲に最も多く協力しているのがピアニストのCharles Gillinghamだが、新参のDavid Immerglückも#7では作曲者にクレジットされている。曲の内容は『Rain In Baltimore』に通じる、故郷を遠く離れた地での心境を顕したものだろうか。
トランペットの微かな音色が、アーバン・ミュージックやAOR的なクールさと哀愁を醸し出す#9『Carriage』とピアノが美しいバラードの#10『Black And Blue』。#10では女性ヴォーカルがフュ―チャーされ、哀しいメロディを更に深く演出している。
#10でも当て嵌まるのだが、単にスローナンバーの比率なら以前の作品と変わらないこの「Hard Candy」ではピアノを始め、鍵盤の活躍が非常に目立つ。
#11『Why Should You Come When I Call』はルーツィなB3がスウィングしまくり、大らかなコーラスが小さなジャンプを繰り返す、ポップなルーツナンバーだ。微妙にホンキィでシェイキングなメロディラインは、初期のCounting Crowsの鋭角さから年月を重ねて円熟を帯びたサウンド・プロダクションを感じてしまう。この南部と西海岸の結婚で生まれたようなトラッドナンバーこそCounting Crows以外ではメジャー・シーンで表現するバンドはHootieの他は存在しまい。
#12『Up All Night(Frankie Miller Goes To Hallywood』でパーカッシヴな音を叩き出しているのは、Ryan Adamsの相棒であるEthan Jonesである。リズムがとても切れ上がったロックチューンであり、久々のロックンロールを感じれる曲である。力強いロックビートがアリーナロック的なダイナミズムに乗って上昇していく流れは相当に気合が入っている。コーラスもギターもピアノもどれも最大限出来る音を搾り出しているようなギリギリの力場で演奏されているようなナンバーなのだが、どこかにまだ余力が感じられる不思議な曲でもある。
#13『Holiday In Spain』はラストに相応しい、しっとりとしたバラードである。そのスコアの美しさもさることながら、忙しく過ぎ去っていく日常を惰性で過ごす我が身が抓まされるような効果を与えてくれるAdamの詩が、また沁みるのだ。
そして、13味のキャンディはこれで終わりと思いきや、オマケのフレイヴァーがちゃんとサーヴィスされているのが心憎い。思わずニヤリとしてしまうカヴァー曲がシークレットトラックとして収められている。
Joni Mitchellのヒットナンバー、もはやクラッシックとなっている『Big Yellow Taxi』がストリングスを交えた原曲に近いアレンジで、爽やかに登場する。
だから、#13が終わっても暫くはプレイヤーを止めてはいけない。ビートの効いたポップロックが少ないこのキャンディ缶では、この明るくジャンピーなポップチューンは希少価値がある。Davidのマンドリンの音色も実に良い味付けと名ている。オリジナルが良質なナンバーだが、Counting Crowsによってオリジナルから30年以上たってカヴァーされた#14は数ある『Big Yellow Taxi』のカヴァーの中でも一番の出来ではないだろうか。
以上、どんどん長蛇化していくので、この辺で打ち止めにする。
期待が大きいと生半可な出来の新作では、普通採点が辛くなるが、この「Hard Candy」の13色・13味プラス1は全く期待を裏切らなかった。
しかも、これまでのアルバムの中で一番聴き易く、とっつき易い大衆向けな面が掘り出されている。
本国アメリカで、現在の腐敗して変質したチャートで、どのくらいの健闘が出来るか現段階では不明だが、きっと本邦も含めて新しいファンを獲得し、既存のファンには満足を与える傑作を創ってくれた。
まずは、Counting Crowsを賞賛し、3年後に来るだろう5枚目を早くも期待して筆を置くことにする。
四の五の言わないから、ロックファンを自称するなら買っとけ。 (2002.7.18.)
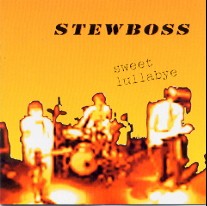 Sweet Lullabye / Stewboss (2002)
Sweet Lullabye / Stewboss (2002)
Roots ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Americana ★★★★☆
You Can Listen From Here
◆#1『Counting To 7 At Your Old Barstool (Time)』
♪「1,2,3,4...1,2,3...Yeah....」
というGregg Sarfatyのカウント・アップからスタートするオープニング・トラック『Counting To 7 At Your Old Barstool (Time)』−些かタイトルが長いが−を聴いた瞬間、
これはイケル!!と確信した。
これ以外にルーツィな表現が出来ないというくらい絶妙なB3の音色が流れる中、Counting CrowsのAdam Duritzから熟成と技巧という柱を取り去って、粗さと勢いを増量させたようなGreggのヴォーカルがスゥインギングしながら曲を揺すり上げる。Country Swingというジャンルよりも、もっともっとゴキゲンで、しかもロックンロールで、ダサい。しかも軽薄さというかCountryの軽さが全く感じられない。
♪「Time,Time,Time......」のリフレイン・コーラスで無意識に身体がリズムを刻まない人はいないだろう。
いきなりライヴ感覚丸出しのナンバーでスタートするとは、かなり驚かされた。1st作の「Wanted A Girl」のオープニングである『Heaven On Mine』は同じくオープニングナンバーながら、フィドルがのったりと流れる典型的なカントリー・ナンバーだったからだ。というよりも、ここまで草原的になるとブルーグラスだろう。
思うに、アルバムのオープニングというのは相当重要なファクターとなっているのだ。アルバム全体の印象を決定付けるという意味合いにて。しかして、アルバムの頭を取るのがグラスソングかロックソングかでは、随分と全体像の持つ印象が変わってしまう。
オープニング効果だけではなく、この2枚目の「Sweet Lullabye」は後述するが相当ロックンロールの割合が増えた作品となっている。が、やはりこの#1が引っ張る効果は大きいといえよう。
◆#2『I Hope You Miss Me』
1999年暮れにオンライン発売された、Stewbossの初のフルアルバム「Wanted A Girl」を手に入れた時は、中々面白いCountry Rock Bandが西海岸に現れたと思った。
アルバムの中には、思わずCountryと銘打ちたくなるような、牧歌的なグラス風のナンバーと、概ねはCountryよりRockというよりもPop/Rockの要素が強いナンバーが混在していたが、最終的にはCountryの匂いがやや強いアルバムであったことは否めない。
まあ、この線引きは非常に微妙で、筆者がRock n Rollと感じるレコードでも、ルーツロックを聴かないリスナーの耳には全部Countryとして届いてしまうことが大半であり、StewbossがCountry系のバンドでないとは、一般論としては言い切れないが。
が、筆者としてはこのバンドは、殊にこの前作から3年ぶりに届けられた「Sweet Lullabye」で更にCountryよりもRockバンドとしての色彩が濃くなったと思っている。
確かに、Countryの影響はサウンドの節々に感じることのできるバンドであるけれども、筆者的にはルーツロックアルバムである。
Alt-Countryというよりもこういった作風は現在の表現を用いてAmericana Rock Albumと呼ぶに相応しいと思うのだ。何回か言及はしてきているが、Americanaという音楽ジャンルは解釈的には全く新しいタイプのCountry Rockというのが米国での一般的な見方のようだ。
が、筆者的にはAlt-Country程ストレートなガレージロックやパンクロックとカントリーの融合を図っておらず、とはいえ商業カントリーに毒されたスカスカな音とは違うルーツサウンドをAmericanaと呼びたい。
まあRoots Rock/Popの一形態、Country的な要素を取り入れた音楽ということだが、こう考えるとAlt-Countryとの境界線がますますはっきりしなくなるようでもある。
ロックンロールのチューンにおいて、パンクやガレージのロックサウンドよりも、より土着的なフィーリングを挟んだロックビートを叩きだす音楽性を便宜上、全く独断でAmericanaとすることにしている。究極はその時の主観にしたがっているだけなので、あまり参考にしなくて良い切り分けである。一応留意していただければ幸いだ。
と前置きが長くなってしまったが、この#2『I Hope You Miss Me』は、アレンジ的は相当カントリーを思わせるところが強力だ。#1とは打って代わって、ノン・キーボード。
牧歌的なハーモニカをコーラスパートやリフへ大幅に取り入れ、トーキング的なリズム・ヴォーカルを楽しげにぶつけて来るという点は、かなりカントリー・ライクな調整を施されたトラックと思える。
しかし、ここまでカントリー的なアプローチをあけすけに見せつつも、それ程カントリー・カントリーしたものを感じないのだ、不思議なことに。(まあ、これも程度の問題だろうが。)
そのゴキゲンな断面のザックリとしたギターとリズムの結婚が、ロック・ビートという副産物を生み出しているのだろう。ライヴ・フィーリングが#1と連続してパンパンに溢れているナンバーである。
◆#3『Sweet Lullabye』
兎に角、切なく甘いバラードである。ハモンドB3オルガンだけでなくローズ・ピアノも独特の覚束ない音色で曲をサポートしている。
このセンチメンタルなバラードではヴォーカリストとしてのGreggの成長が第一に突きつけられる事実だ。パワーは感じるが、単調で不器用なだけのヴォーカリストと思えた1stでの歌唱法とは比較にならないくらい深みのあるヴォーカルを習得するに至っている。
鼻に塊を引っ掛けながら気合を入れて歌うことしか出来なかったのが、甘く、ファルセット気味な声を出せる喉を披露できるようになった。これはバンドとしても表現の可能性が拡がったことを意味している。
タイトル曲で、「甘い子守唄」と素直に訳したいのだが、子守唄=ララバイの正確な綴りは「Lullaby」であり、「Lullabye」ではないのだ。末尾のEが余分であり、グラマティカルな間違いである。
これを単なるバンドの諧謔と取るべきか。好んで口語的な文法の不正確さを歌詞に落とすバンドは古今東西数え切れないくらい存在することだし。
歌の内容に耳を傾ければ、絶望的な状況にいる人物に向けて、「僕が甘い子守唄を囁いてあげる」「一緒に歌おう。」という背中が痒くなるような、Sweetという名にしおう甘い恋歌である、素直に歌詞を追えば。
しかし、些か屈折している筆者は、Lullaby=甘い時期と、Bye=別れの時期をメタファーとしたStewbossの造語ではないかと要らない勘繰りをしている。
甘い時と、苦い別れは表裏一体。そんなことまで捻り出したのだが、バンドのこの歌に対するライナー・ノーツでは
「僕達は人生を支えるために曲を書く。これは形のないセラピーでもあるんだ。僕達はその与えられた効果を返したいだけなんだ。」
となっているので、単に心温める意味でこの詩を書いたという線が濃厚だ・・・・。
◆#4『The Midnight Shift』
デヴューアルバムから、その音楽性をBruce SpringsteenとCounting Crowsの混合。
またはRolling StonesとCounting Crowsを掛け合わせたサウンド、という評価をメディアから得ていたが、Counting Crowsにしてはややカントリーテイストが強いし、サウンドもルーズである。初期のSpringsteenや1970年前後のカントリーに傾倒していたRolling Stones的な音にはかなり近いところがあるとは思う。
繊細さから、大らかなロックンロールまでカヴァーしている点は、Counting Crowsに通じるところがあるとは思う。
その繊細さという一面で、シンガー・ソング・ライター風の味があるナンバーが#4『The Midnight Shift』である。ほのかなハーモニカを、少量であるが効果的に使いつつフォーキーに淡々と紡がれるこのナンバーは、アルバム全体からは目立たないけれども3年間を通してのバンドとしての成長を感じる。アクースティックな中にもアーシーな感覚を盛り込んでいるのが、Stewbossらしい。
内容は、9時から5時という普通の時間帯に働く彼女を持った、夕方6時から早朝3時までの夜勤をしている男のお話。やっと昼勤に変わって彼女と過ごす時間が増えると喜んだのもつかの間、今度は彼女が夜勤になったという喜劇的なストーリーを読んでいる。バンドによれば、あまり使わない実話を歌っているとのことだ。
◆#5『The Moonlight And Me』
カントリー・ロックというかもっとベタなヒルベリー/ロカビリー風なトラッドナンバーが#5である。こういったナンバーがよりソフィスティケイティッドされると、もっとカントリー的な田舎臭さが抜けてさっぱりとしたルーツロックに昇華していくのだろう。が、これはこれでバンドのお気楽さというか、緊張感が抜けているところが表現できるので良いとも感じるのだ。シリアスでないCounting Crowsという表現をもって評されるのは、こういった風味のナンバーを入れているからということもあるだろう。
Stewbossは3ピースである。今作でも1stに続いてインディ・シーンのセッションミュージシャンを多数起用しているが、ライヴではサポートミュージシャンを起用したり3ピースのシンプル編成でパフォーミングしているようだ。
Gregg Sarfaty (Vocal,Guitars,Dobro,Dulcimer,E-Bow) , Jano Janosik (Drums)
Luke Storey (Bass)
となっているが、出来ればキーボーディストを加えた方が、サウンドに厚味が出るのではないかと思う。このアルバムでも#7までの奇数トラックと#10ではB3を、#6でもメロトロンが使われ、良いアクセントをサウンドに加えているのだから。
◆#6『If You Are Mine』
上記した、Stewbossと比較、またはStewbossが比較対象とされるバンドについて、メンバーはこう語っている。
「うん、僕等は全ての事象からある種のアイディアを盗んできているね。それに僕達は様々な音楽を聴いて成長している。僕はニュージャージー出身だからSpringsteenの影響はとても受けやすかった。1枚目のヴォーカルとかは彼の影響もあるね。でも、僕としてはCounting CrowsよりもVan Morrisonからもっと影響を受けていると思うよ。それからツアーを行うようになって、Tom PettyやNeil Youngをより意識するようになった。僕等の音楽はロックンロール少々、カントリー少々、ブルース少々。つまり僕達はアメリカン・ミュージックの全てを取り入れているのさ。」
というコメントを正当化するように、極端な影響をあまり感じない、Roots Rockとしか表現できないナンバーが歌われているが、#6もそういったナンバーだ。
基本のラインをアクースティックなギターのみによって進め、Bメロのあたりからメロトロンやドラムを少しずつ肉付けしていき、ジワジワと湧き上がるバラードに仕上げている。非常に音楽性そのものにおいてオルタナティヴなナンバーである。どのようなタイプのアメリカンロックのアルバムに入っていても違和感の少ない地味なバラードだ。こういったナンバーがアルバムの屋台骨を支えるのだと思う。
◆#7『A Little Goes A Long Way』
#3から続いていた、繊細かつ大人し目の流れをくるりと裏返すのが、ロックナンバーの#7である。かなり骨太のルーツナンバーである。パンキッシュなAlt-Countryというよりも、線のゴツイ太いギターを中心としたロックンロールという曲である。ルーツィでありながらロックであり、カントリーらしくない。まさにストレートなアメリカン・ロックだろう。このナンバーにもB3が縁の下を持ち上げていて、パンチ力をアップさせている。
Stewbossというバンド名の由来は、バンドに投げた質問がまだ還ってこないので正確なことは述べれないのだけれども、直訳すると「シチューのボス」である。
シチューというのはざっかけない言い方をすれば「ごった煮」である。お高く止まった高級料理ではなく、入れれるものは何でも放り込んで強引に味付けして食べれるようにする野趣溢れる料理の代表格だろう。その点は日本の国民食となったカレーにも類似している。
つまり、雑多な音楽性を詰め込んでも、自分達の味付けとスパイスによって美味しく調理できるという、バンドの意思を具体化したネームではないかと想像している。
こう考えると、この#7『A Little Goes A Long Way』はたくさんのアメリカン・トラッドをベースにしたシチューのレシピとしてかなり良い感じにバンドの得意料理を示しているのかもしれない。
◆#8『Up That Wrinkled Street』
デヴュー盤では結構目立っていたフィドルを始めとするルーツ弦楽器がかなり引っ込んだ印象の濃い「Sweet Lullabye」だが、#8でもかなり抑えられたアレンジで使われている。バックで密かに流れているため、殆ど目立たないのだ。
この#8は#4と同様にアクースティックな弾き語り的雰囲気のナンバーである。こういったフォーキーな曲を普通に加えることができるようになったのはバンドとしてのサウンドの拡大を思わせるが、もう少しロックなトラックで纏めても良かったと思うのだ。
が、#8の前後を考えるとメリハリのある曲順であるとは思う。
◆#9『Let’s Go To Texas』
痛快な曲線を描くフィドルと16ビートの豪快なアンサンブルがロック・ビートを走らせるナンバー、#9は、カントリーではないし、ウェスタン・スゥインギングとも異なる、ルーツロックだ。
フィドルのストリングスを外せば、やや古臭いオールド・タイムなロックナンバーになるのだろうが、パーティ・サウンドを主張するように裏返るフィドルの音色によって独特のルーラルな味わいを出している。
歌詞的には、固定観念というか、とある地名に対するベタな通念を偏見を皮肉るようにも聴こえるし、純粋な世間知らずの人物の視点を使い、希望を称えるだけの陽性な詩とも取れる。「さあ、素晴らしいテキサスへと行こう。」という表面上単純そうで、実はかなりシニカルな詩であるようにも感じてしまうのだ。
それにしても、西海岸はカリフォルニアを拠点とするバンドにしては、あまりウエストコースト的な色合いを見せないバンドである。カントリーロック的な曲では西海岸サウンド的なあけすけさも垣間見せるが、こういったロックナンバーはウエスト・コーストロックというよりも、海のないアメリカ中部の州を母体にしたバンドのタフさをより感じてしまう。
◆#10『Meet Me In Your Dream』
「現在のアメリカン・ミュージックの状況についてどう思うかだって?それは2本の腕しかないといえるね。1本はまず、2〜3のレーベルが全てを支配していること。SonyとUniversalレーベル以外が所有している版権なんて殆どメジャーではないだろう。もう1本は、トップ10ヒット、そしてトップ40やトップ200以外ではラジオ局が相手にしてくれないという現状さ。というように2本の腕に操作されたシーンは絶望的だね。
僕等はLAで活動しているけど、状況はもっとヘヴィだね。Deftones、Papa Roach、Kornといった人気バンドは本来のLAミュージックとは違ったものだ。
でもひとつだけ可能性はある。それはインターネットを通じて音楽を探すことさ。インターネットを通じて探すと物凄い素晴らしい音楽がたくさんあることが解り、そういった良いものが如何に注目されていないか理解できると思う。」
このような現状を批判するバンドのコメントを掲載したが、メジャーを支配するそういった音に対するアンチテーゼの如きトラックが#10なのだ。
メロディ的にはブルースを背景にしたヘヴィなうねりがあるけれども、じっくりとその重さを噛み締めることの出来る作りとなっている。土台のしっかりとした家屋の基礎を思わせるナンバーであり、ギターとB3とヴォーカルがこってりとした厚揚げのようなアンサンブルを練り上げても、それが癇に障るようなノイズにはならずに、ガッチリと組み合わさっているのだ。
こういった歳を経ても概観に草臥れが出ない煉瓦作りの建築物のような重さ・ヘヴィさをメロディと融合できる音が本来のメジャーには必要なんだ、と訴えるかのような曲の重さは、その重量が心地良い負荷となってくれる。インテリジェントの欠片も感じないメジャーのヘヴィ・ロックとは月とスッポンである。
◆#11『O’Carry Me』
最後はブルーグラス風のトラッド・ナンバー。少々説得力に欠ける脱力感がある。こういった伝統音楽を叩き台にするべきバンドがStewbossであり、そのままをシチューにするバンドではないと思うのだ。
最後の最後でやや画竜点睛を欠くというところがあるが、全体としてはとても纏まりのあるルーツロックとなっているので満足度は高い。
Miles Of Musicにもこの「Sweet Lullabye」がラインナップされた。「Wanted A Girl」は当初、非常にマイナーなインディのみを扱うDuck Musicというサイトでしか手に入らなかったことと比べると相当の出世と言えるのではないだろうか。(ついでに試聴リンクも借りてしまったが。)
ルックスもそこそこである若いバンドなので、これから人気が出る可能性はある。もっとカントリー的な要素を減らしてソリッドにしなくてはメジャーでは通用しないだろう、という予想をすること自体が哀しいけれど。
Country Rockは苦手、という偏見を持っている人も、Stewbossから入門すれば、随分と世界が開けると思う。
試しに聴いてみては如何だろうか。ロックという要素ではCounting Crowsよりもポイントは高い。同時にカントリーという点でもCounting Crowsとは随分ポイントに開きがあるけれども。 (2002.7.22.)
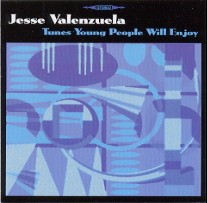 Tunes Your People Will Enjoy
Tunes Your People Will Enjoy
/ Jesse Valenzuela (2002)
Roots ★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Adult-Alternative ★★
You Can Listen From Here
一応Jesse Valenzuelaが10年間在籍していたロックバンドについて簡単に復習しておくことにしよう。
今更説明するまでもないが、Gin Blossomsというアメリカ南西部のアリゾナ州出身のバンドのリズムギタリスト兼バック・ヴォーカリストであったのが、Jesseである。
Gin Blossomsというバンドは日本でもかなりの広範なリスナーに支持をされているバンドである。1997年暮れに解散してしまった後も、熱心なファンが多い。メジャーでは2枚のフルレングスアルバムしかリリースしていないにも拘らず。
Jesse Valenzuelaというアーティストは意外に日陰者というか目立たないメンバーであったように思える。実はGin Blossomsの初代ヴォーカリストに当たり、そしてGin Blossomsの母体とまでは遡らないが同バンドを名乗り活動を開始した1987年時にバンドに在籍していたオリジナルメンバーでもあったのだが。
やはり、メジャーで成功を築いた時点で、グループのリードヴォーカリストという“顔”がRobin Wilsonとして強く定着していたのが理由だと思う。
意外と知られていないが、2代目のヴォーカリストにしてメジャー時代の牽引役であるRobin WilsonはGin Blossomsのパーマネント・メンバーではない。結成から1年近く遅れて、リズムギタリストRichard Taylorの解雇によりメンバーに加わっている。
Robinがリードシンガーの座をJesseから取って代わってしまうのにはあまり長い時間はかからなかったそうだが。
結局、Gin Blossomsの解散時に残っていたオリジナルメンバーは、ベーシストのBill LeenとJesseだけになってしまっていたのである。
2002年、Gin Blossomsは春に全く突然、リユニオン・ツアーを行うことを発表。以前もテンポラリーでチャリティ・ライヴ等のためにステージに立つことは何回かあったのだが、正式にツアーを行うのは1997年以来5年ぶりのこととなる。
2002年に入り、活発に動いていたのはJesse Valenzuelaのみであったので、かなり驚きのニュースであった。
ということで、現在(2002年7月)もGin Blossomsは北米ツアーの真っ最中である。
集客数も上々らしく、10月までスケジュールが延長されている。同時にステージに立つのはSeven Marry Three、Spin Doctors、Spongeという4グループで、Gin Blossoms以外がオルタナティヴやノイズ・ヘヴィ系のオルタナティヴバンドというそのジョイントはかなり違和感があるのだが、メインはGin Blossomsのようで他のバンドのツアーが8月までに対して、早くも10月まで日程が固定されているのはGin Blossomsのみである。
メンバーの仲は上々と伝えられている。新譜に関しては、あくまでも“ツアーのためのリユニオン”ということで、新作を出すことについては全く正式な発表はない。
但し、Robin Wilsonが語ったところによると
「仮にGin Blossomsでアルバムを作るとしたら自主制作にしたい。」
や、今年正式にRoger ClyneのThe Peacemakersを脱退したScott Johnsonの
「過去5年間よりも、皆で作業をする意欲は高まっている。」
というコメントから、ひょっとしたらツアー後にEaglesの「Hell Freezes Over」的なアルバムを作成するかもしれないという期待は持って良いと思う。
未発表曲を満載した「New Miserable Experience」の2枚組みリマスターも2002年秋に発売される予定だし、インディ盤の「Dusted」もリイシューされている。解散から5年を経て、徐々にGin Blossoms関連の動きが活発になってきているのは喜ばしい限りである。
さて、その解散後からの5年間のJesse Valenzuelaの活動をまず追ってみよう。
その活動で関わってきたアーティストや、アルバムを通すと、この初ソロ作「Tunes Young People Will Enjoy」で提示された音楽性が見えてくると考えているから。
Gin Blossoms解散後にまず最初の動きを見せたのが、Jesse Valenzuelaである。Jesseはリードギタリストであった同僚のScott Johnsonを引き連れ、Gin Blossomsとして活動していた頃からのサイド・プロジェクトであったThe Low Wattsを改めてカルテットとして再スタートした。
しかし、Scott Johnsonが同じアリゾナ出身のバンドであったThe RefreshmentsのRoger Clyneが結成したルーツロックバンドのThe Peacemakersと二股で活動を開始。他のメンバーもバンドを抜けてしまい、最終的にはJesse Valenzuelaだけが固定メンバーとして残り、他のミュージシャンを加えたバンドに変遷してゆく。同郷アリゾナ出身のルーツロックバンドであるPistolerosのドラマーであるGary Smithをメンバーに加えつつScott Johnson等も参加という体制に移行して存続を図る。
参考までに、Pistolerosというルーツロックバンドはなかなかのアルバムを2枚作成している。Gin Blossomsよりもルーツ度は高い南部ルーツ系のバンドでJayhawksのGery Lourisもソングライターやプロデューサーとして協力している。日本では殆ど知られていないが(常ながら)、一度手にとってみたら如何だろう。
このようにして紆余曲折を経ながら、1998年にはLow Wattsは嘗てのGin Blossomsの所属レーベルであったA&M Recordsと契約を締結。レコーディングを開始した。
ところが、老舗であったA&Mがハリウッドのエンターテイメント産業から巨大レーベルにのし上ったUniversal Recordsに吸収合併されるという事態が発生。この時点で、A&M主導であったプロジェクトの大半がペンディングとなってしまう。
何とも不幸な事件としか言い様がないけれども、実際問題としてLow Wattsは新しい親レーベルの注目を引くような音楽性ではなかったらしい。レコーディングは凍結。イコール、永遠に延期となってしまう。
結局、メジャーでアルバムを出すことが殆ど絶望となったLow Wattsは自然消滅する。
唯一の残された音源は、1998年にインディ発売のクリスマスアルバム「Christmas To Remember」にJesseのリード・ヴォーカルで収録されたJesseオリジナル作『Christmas Time』だけである。
この歌もプロジェクトが完全に消滅する前に何らかの形で録音を残しておきたい、という意図でアルバムラインナップに加えて貰ったというのが実情らしい。このナンバーのみでLow Wattsの音楽性を想像するのは困難だけれども、そこそこ良質なポップロックバンドを予感させるナンバーだと思う。
1998年、結局リーダーバンドが中途半端に終焉を迎えた故の失意からか、以後数年のJesse Valenzuelaの活動はやや低調となる。
1998年にはThe Rembrandts(というよりもDanny Wildのワンマンバンド)の最悪の駄作である「Spin This!」にソングライターとして参加。第一弾シングル『Long Way Back』をRembrandts名義と共作するも、このナンバーも大したことない脳内にキャッシュされない曲だ。このシングルをしてこのアルバムを、という言葉がぴったりである。
同年の毎度ワンパターンのパワーポップ・シンガーであるTommy Keeneの7作目「Isolation Party」にもバックヴォーカルとして登録されている。
ユニークなのは1999年、New Ageのインストゥルメンタル&ネイティヴ・ミュージックのユニットBurning Skyのアルバムにマンドリンとして参加しているところか。この異色の作品への参加は彼のキャリアに与えた影響は無視できなさそうに思える。
また、カナダはヴァンクーバーのルーツ/オルタナティヴのグループThe OddsのフロントマンであるCraig Northeyがサイドバンドとして1999年に結成したNational Parkというユニットにメンバーとして参加。このバンドはR&B的なロックサウンドを追及した実験プロジェクトだったらしい。が、アルバムはレコーディングを終えたものの、結局時代に合わないとして契約ができずにオクラ入りとなってしまい、現在まで幻の1枚のままだ。
2001年に西海岸のガール・ポップバンドであるAstropuppeesのアルバムに、ソングライター、ギター、ヴォーカルとして全面的に協力。更に弾みがついたのか、女性シンガーであるSusan Sandbergの2枚目のアルバム「Down Comes The Night」にプロデューサー、ソングライター、ギター等で更に深く製作にコミットする。
また、前述したアリゾナのルーツロックバンドであるPistolerosの2ndである「Pistoleros」にも曲を提供するというように、次第に活動が右肩上がりになっていく。
2002年に入ると、ソロでアクースティックな小規模ライヴを続けながら、ソロ作である「Tunes Your People Will Enjoy」の作成に取り掛かる。傍ら、パンクバンドのGhetto Cowgirlのアルバムのプロデュース及び曲を提供。
そうこうしているうちにGin Blossomsのリユニオン・ツアーの噂が流れ始める。その矢先にJesse Valenzuelaの初リーダーアルバムが届けられたという次第である。
こうして、空白の5年間を軽く追ってみると、Jesse Valenzuelaというミュージシャンが決して流行のヘヴィロックやオルタナティヴ一辺倒に活動せず、どちらかというと幅は広いが概して良心的なポップ・ロックのフィールドで活動してきたことが解るのではないだろうか。
元来、数あるGin Blossomsの名曲にかなり手を貸して来たコンポーザーである。
Valenzuela単独の作では『Cajun Song』、『My Car』、『Virginia』、『I Can’t Figure You Out』とヒットシングルは存在しないが、『Follow You Down』、『Till I Here It From You』、『As Long As It Matters』といった代表的なシングルにはJesse Valenzuelaの名前が共同ライターとしてクレジットされている。
ノン・シングルトラックにしてもポップでロックなツボを突いたナンバーばかりである。
このように彼の才能と、メジャーで成功したバンドを離れての5年間の活動がこの「Tune Your People Will Enjoy」に集約されている。
正直、少々手広く間口を広げ過ぎな感じがあり、音楽性が拡散し過ぎて散漫になってしまっている点が残念だ。
特に#9『Andale Pues』はドラム・ループにシンセ・ノイズを多用し過ぎのNew Waveの残りカスのようなミクスチャー的なB級ナンバーで、メロディは悪くないのだがチープに走り過ぎな感は否めない。ここまで冒険するというか型破りをする必要はなかったと思う。
また、相当黒っぽいSouthern RockとR&Bの感覚が同居したナンバーが#7『We Could Still Run』、#8『Bulletproof Jacker』そして#11『Someone Else』。
というように後半に連続して固まっているのが、やや後半のトーンを単調にしているように思える。
どのナンバーも重量のあるマッディな南部風のロックとしてメロディは良いのだが、ドラムループやテクノロジーがやや突出して浮き、折角のタフさを阻害している。
アレンジ的に「現代風」を求めたのかもしれないが、打ち込みのサウンドがかなり品格を貶めている。
こういった関係からか、後半はやや力が落ちているという印象が大だ。
しかし、かなり正統派のアメリカン・ルーツ、そして南部と西部のフィーリングを上手にモダンロックとして料理している快作であることには異論はないだろう。
特に、外部ライターと共作したナンバーには秀逸なものが多い。
#1『Spark』は前述したJesseがプロデュースした女性シンガーのSusan Sandbergとの作。Gin Blossomsのロックナンバーを思わせる、少量にダート感を纏わせたドライヴィング・ポップナンバーである。この軽快なアップテンポ曲を聴けば、まずこのアルバムのこれからの流れに不安を感じることもないだろう。
#2『Lucky Stars』もJesseが全面的に協力したLAのパワーポップグループ、Astropuppeesの女性シンガーであるKelly Ryanが共にペンを執ったナンバーである。
このメロウなハーモニカと優しいメロディを聴いた瞬間、Gin Blossomsの『As Long As It Matters』の甘いラインを連想してしまったリスナーは少なくない筈だ。筆者の嗜好ではこのアルバムのベストトラックと認定したい。
また、初代Gin BlossomsのリードシンガーであったJesseのハスキー・ヴォイスも中々の力量であると思えるトラックでもある。対抗馬が名ヴォーカリストのRobin WilsonであったのがJesseの不運だったとも考えてしまうくらいにValenzuelaの声質は良好だ。
ルーツ/ポップのファンなら知らない人はいないBill LloydまでもJesseと曲を書いている。#5『Looking For You』はハートウォーミングなルーツ・ポップ、アリゾナ風アメリカーナという表現でも過不足ないかもしれない。ややスマートさが目立つナンバーでもあるが、B3の使い方とハーモニー・ヴォーカルの使い方がとても巧みだ。
そして、何よりも驚いたのが、1970〜80年代のファンが泣いて喜ぶ、燻し銀ウエストコーストの孤高(をい)
J.D.Southerが#10『Broken Hearted Kind』を書いているのだ!!
しかもJ.D.らしさが炸裂の何処となく南国海岸を連想させる西海岸の優しさの溢れたバラードである。まさかと思い確認したが、やはりクレジットのSoutherはJ.D.であった。曲風から恐らくは、と思ったが。久々の彼の名前の登場である。1990年代は何処かに篭もってしまったと思うしかないくらいに逼塞していた彼だが、名前を見れただけで嬉しさが込み上げてくる。
更に、懐かしのウエストコースト・カントリーロック風なナンバーとあってはもう言うことはない。
Jesseの単独作もまた注目するべきだろう。(当然だが)
コンクリートの冷たさを思わせるような、ルーツとオルタナティヴの両者が同居したハードでクールな#3『Can’t Go Down』がどうやら最初のラジオシングルのようだ。ロックンロールで一発活を入れるというパイルドライバーなチューンである。
ループドラムでなければ、もっと良かったのがアンビエントなバラードの#4『Damaged Goods』。これまた南部の適当な懐の深さがモダンロックのアレンジの裏に見え隠れする佳曲だ。
そして、ベタベタなブルース・ピアノが炸裂するロッキン・ブルースと思わせて、実はそこそこライトでアッパーリズムのロッカバラードに展開する#6『Company』。ドランクン(酔っ払い)ロックのフラフラとしたいい加減さと芯の強いポップセンスがしのぎを削る、かなりインパクトの強いルーツロック。このアルバムの中では最もルーツロアでパワフルなチューンであると思う。
ここまでJesseがやってくれるとは想像をしなかったが、これは満点を与えたい。曲の出来としては#1や#2には及ばないが、筆者のストライクゾーンど真ん中である。
このようにかなりヴォーカリストとして、そしてソロアーティストとして才覚のある側面を見せてくれるアルバムを発表したのに、リリース後間もなくGin Blossomsのツアーが始まってしまった。
Jesseにとってこれが不運か幸運かの判断は難しいが、ソロアルバムのプロモーションとしてはややビハインドがありそうだ。Gin Blossomsのライヴに足を運ぶ聴衆の目当ては、Jesseのソロではなく、リヴァイヴァル・ソングとしてのGin Blossomsのナンバーだろうし、Jesse Valenzuelaは大多数のファンにはバンドのギタリストとしてしか認識されないだろうからだ。
しかし、これからGin Blossomsとして活動を継続するのか、それともまたメンバーは個々の活動に戻るのかと、どちらにせよ、Jesse Valenzuelaがソロ・シンガーとして十分に独り立ちできる証拠を顕した作品として、とても評価できる1枚だと思う。
最後に、今年中々のアルバムをリリースしたTommy Keeneの9作目「The Merry-Go-Round Broke Down」にJesseがヴォーカルで参加しているが、そのお返しかTommyも本作にギターでクレジットされている。またLow Watts時代の盟友Darryl Icardがベースで全面参加という事実を鑑みると、このソロ作はLow Wattsの停止への回答のような性格を帯びているのかもしれない。 (2002.7.25.)
 The Big Night / David Zollo (2002)
The Big Night / David Zollo (2002)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Southern ★★★★
You Can Listen From Here
ルーツロックやカントリーロック界に限らず、ピアニスト/キーボーディスト専任でリードシンガーというパターンは非常に例が少ない。
レコーディングでギターと兼務で鍵盤をプレイするミュージシャンはそれこそ星の数ほども存在するだろうけれど。
ドラマーでリードシンガーというケースも稀なのだが、鍵盤弾きでリードシンガーというスタイルも負けず劣らず少ないと思う。
試しに、ロック界でピアニスト/キーボーディスト専属のロックシンガーといえば、何人くらいを挙げれるだろうか、少々振り返ってみて欲しい。ヴェテランのビッグ・ネームであるElton JohnやBilly Joelを除くと、恐らく両手の指を折るだけでもかなり苦労するのではないだろうか。
今回、前作の「Uneasy Street」から4年間の沈黙を経て届けられた「The Big Night」の創り手たるDavid Zolloは、その希少なロックシンガーでありピアニストである。
AORやAdult Contemporaryのフィールドではかなりの数がいても不思議ではないが、Roots Rockの歌い手としては、やはりピアニストというのは珍しい。
何を置いても一番好きな楽器はアクースティックピアノであり、バンドのメンバーに専属のキーボーディストがいるだけでバンドの評価を無条件で一段階上げてしまうという鍵盤ヲタクな筆者には、常に追いかけて止まないアーティストのひとりである。
勿論、追いかけるだけの才能と才能を発揮した作品無しでは、トレースすること等する筈もない。
David Zolloはソロ活動とグループでの演奏を通して、嫌味なくらい安定したクオリティのアルバムを発表し続けているアーティストである。だからこそ、4年の空白を置いて本作「The Big Night」がリリースされた時は心から歓迎したものである。
前作をリリースした後も、ツアーを行う傍ら、玄人ハダシのルーツロックやカントリーロックのアルバムにピアニストとして、またオルガニストとして参加はしていたので、特別引き篭もっていたという印象は無い。
唯、ルーツロックバンドであるHigh And Lonesomeで1993年にレコードデヴューしてから約2年毎には何らかのアルバムを世に出していたZolloが、4年間もの空白を持ったことに幾分の疑問と、かなりの不満を覚えているのみである。
しかし、「The Big Night」は4年間を待っただけのことはある、内容の充実したアルバムとなっている。
また、嬉しいことに、殆どのメジャーなオンライン・ショップにも入荷しているので、これまでの2枚のソロとHigh And Lonesomeの3枚の作品のように入手が困難でなくなっていることも大きい。
これでより多くのルーツロック愛好家(人口ピラミッドは物凄く少ないだろうけど)にDavid Zolloを知って貰えるに違いないと確信している。
ここで、彼のこれまでのディスコグラフィーを交えつつ、David Zollloという鍵盤ルーツロッカーについて軽く経歴も触れておくことにする。
David Zolloはアメリカ東海岸のマサーチューセッツ州はボストンで誕生している。が生後直ぐにアイオワ州のアイオワ・シティにと家族が引越しをする。それ以来、Davidはアイオワで暮らしている。
年齢についてはデータがないため正確なことは解らない。が、1960年代後半から1970年代始めの、やや粗い推定となるが、生まれのようである。21世紀に入った時点で30歳を超えているようである。
これは1992年に自分のレーベルを設立してオーナーになっているという事柄から割り出した数字であるので、もしDavid Zolloの年齢をご存知の方がいればご一報を願いたい。彼の音楽性から考えれば40歳を超えていても不思議ではないが、絶対にそこまでの年齢には達していない。
David Zolloの母方の祖父は1930年代から50年代の間、ニューヨークで活動していたそこそこ名の売れたジャズピアニストだったそうである。
また、彼の父親はジャーナリストであり、アイオワ大学で音楽史を教えている講師というお話だ。
こういった音楽に関係の深い家庭で育ったためか、Zolloは4歳からピアノを習い始め、そのままギターやベースに転ぶことなくピアニストの道を歩むことになる。
Zolloの父親はかなりのレコードコレクターであり、Davidは当然のようにそれらのコレクションを聴きつつ成長していく。ブルース、カントリー、クラッシック・ロック、ジャズというルーツ音楽が父親の収集物であったため、Zolloもその類のルーツ音楽に多大に影響を受ける。
そういったアップデートでないサウンドに感化されたためか、中学生の頃には内輪のパーティでRay CharlesやHuey SmithといったピアノR&Bやソウルのカヴァーを弾き語りして家族を楽しませていたという。かなり枯れた趣味を持った少年だったようだ。
1990年の初頭からDavidは地元のアイオワ・シティのクラブやバーでピアノの弾き語りやバーバンドを結成して活動していた。
1992年に演奏をしていたバーで、Zolloは同じくローカルミュージシャンのRuari Fennessyというギタリストと出会い意気投合。一緒にバンドを結成することを企画する。即座にベーシストのDustin Connerが仲間に加わり、既に数枚のアルバムをリリースしていた地元バンドのHead CandyというオルタナティヴバンドからドラマーのJim Vinerが参加、そしてもう1名のギタリストDarren Matthewsを含めて5ピースのバンドHigh And Lonesomeが立ち上がる。
Davidはこのグループでレコードをプレスするため、インディペンダントレーベルTrailer Recordsを設立する。
High And Lonesomeが消滅した後も、David Zolloをオーナーとしてこのマイナー・レーベルは存続し、アイオワ州出自のルーツロッカー、フォークシンガー、カントリーロック畑のアーティストを複数抱える優良レーベルとなっている。
High And LonesomeやZolloの作品に毎回顔を出すBo Ramseyを筆頭にJoe Price、Greg Brown、Brother Trucker、Bejae Fleming、Kelly Pardekooper &
The Devil’s House Band、Eric Straumanis & The Douglas Leaders。
とインディ関連の深いところをを追っかけていないと全く名前も解らないような(笑)フォーク/カントリー/ルーツ関係のアーティストを支援している。これらのバンドの殆どにはZolloがピアノで参加している。文字通り、発掘と援助をしているローカルレーベルなのである。かなりの注目株・・・・なのだが、全く営業努力はしていないようであり、オンラインショップでも9割の商品は品切れとなっている体たらくである。これもオーナーのZolloのいい加減さを反映したものだろうか。(苦笑)
また、ロックンロールと呼べるバンドが少なく、相当濃いルーツ音楽を演奏するアーティストが殆どであるため、良質なのだが、筆者の趣味には少々地面の掘り下げが深過ぎるところのあるレーベルでもあったりする。といいつつ、これらのアルバムは殆ど持っていたりするのだが。(腐)
と、話をDavid Zolloに戻すとしよう。
1992年にルーツロックバンドHigh And Lonesomeを結成したDavid Zolloは翌年1993年にデヴューアルバム「Alackaday」をTrailer Recordsの第壱号作品としてリリースする。プロデューサーにはBo Ramseyの名も共同で見ることができる。
そしてバンドは年間平均200ステージというツアーをアイオワ州と周辺のミズーリやウィスコンシンそして南部や西部の州にも足を伸ばしていく。前座として起用されたのは、Widespread Panic、Freddy Jones Band、Joe Henry、Jayhawks、Uncle Tupeloといった中堅やメジャーの錚々たるバンドのライヴにてである。
かなりライヴバンドとしても評価を受けていたことが容易に推察できるコラボ―レーションである。
そのライヴの模様を収めた7曲入りのミニアルバムがバンドの2枚目の作となった。翌年の1994年に「Livefromgabes」として発表されている。
このイレギュラー的なアルバムは、相当にラフで全く手を加えない小会場の熱気が伝わってくる佳作である。録音状態はお世辞にも良くないのだけれども。
が、本国以上に好評を博したのが欧州である。アメリカでルーツロックのブームが冷え始めて久しいが、独逸を筆頭にして欧州諸国では長期に渡ってルーツロックの人気が安定している。
High And Lonesomeは特に伊太利亜で歓迎され、2回の伊太利亜縦断ツアーを大成功させる。
そういった追い風を受け、1995年にZolloは初のソロ名義のアルバム「The Morning Is A Long Way From Home」をプレス。
これまた欧州にて非常に高い評価を受け、独逸では「Recognize Me」というタイトルを変更して独自に独逸盤がプレスされるまでになる。
余談だが、つい先年までこのZolloのデヴューアルバムは廃盤となっており「The Morning Is A Long Way From Home」のジャケットの入手はとても困難だった。「Recognize Me」なら独逸でまだ生産されているので手に入れることは面倒だが可能という状況だった訳だ。
が、「The Big Night」のリリースに合わせるように、ジャケットをモノクロのZolloの横顔からカラーのややぼやけたものに差し替え再発されたので、現在では容易に手に入ることになった。
そして、1996年にはHigh And Lonesomeの2枚目のスタジオ録音盤「For Sale Or Rent」を発売。この時点でHigh And Lonesomeの売上はトータルで1万枚を超えた。ドが付くインディ・レーベルのアーティストとしては大したものだろう。大半が欧州でのセールスのため、アメリカでメジャーの目に留まることがなかったのは残念だが。
更に残念なことには、High And Lonesomeとして3枚目の(通算4枚目)アルバムを作成中に、突如としてバンドは解散してしまう。理由はバンドのメンバー各人が、自分のやりたいことに進むため、と公表されているが、Zollo以外のメンバーの去就は不明である。
こうして、High And LonesomeのアルバムはそのままDavid Zolloのソロ作として横滑りしていく。元々ソロ作品にはバンドのメンバーは手を貸さずに、Bo Ramsey達と手を組んでいたという経歴があるため、ソロ作への変更もそれなりにスムーズに行われたようだ。
このアルバムが1998年の「Uneasy Street」である。
このアルバムは、
「Rolling Stonesのベスト・ピリオドである「Beggar’s Banquet」から「Exile On Main Street」を現在に復活させた。」と評された1stソロと比較すると、かなりレイドバックして、埃っぽくなったCountryの強い作風が目立っている。
正直、本作「The Big Night」及びデヴュー作 「The Morning Is A Long Way From Home」と並べてみると牧歌的過ぎて1段落ちるアルバムであると思う。無論それでもかなりのルーツアルバムなのだが。
これにはHigh And Lonesomeの分解という事態が影を落としているようにも感じられるのだ。
また、バンド活動が終焉を迎えたからか、この頃からDavid Zolloは他のアーティストのレコーディングやツアー・ミュージシャンとして積極的に活動を開始する。
1998年にはTodd Sniderのツアーに半年間参加。そのままToddの3作目である「Viva Satellite」のラストナンバー『Doublewide Blues』にピアノで参加。この後もToddのステージには鍵盤担当としてかなり長期間同行する。
更にフォークシンガーのDave Mooreのアルバムや、インディ・ポップ/ルーツバンドのDick Prall Bandの地味な作品「Somewhere About Here」にピアノで参加する。
また、自身が経営するTrailer Recordsで発掘したBrother Trucker、Bejae Fleming、Kelly Pardekooper &
The Devil’s House Band、Eric Straumanis & The Douglas Leadersといったグループのデヴュー作にピアノやオルガンで協力。
Bo RamseyやGreg Brownというヴェテランのシンガーでギタリストである大先輩のツアー・サポートとレコーディングにピアノやバックヴォーカルで手を貸す。という具合にHigh And Lonesome時代とは打って変った他のバンドやミュージシャンと関わりを積極的に持つようになる。
こういった活動が、更にDavid Zolloのシンガーとソングライターとしての才気に磨きを掛けたのだろう。ソロ3作目となる「The Big Night」はかなり味わい深い作品となった。
ポップなところは1stと共通項があるが、アップテンポなHigh And Lonesome的なナンバーも幾つかトラッキングされていた「The Morning Is A Long Way From Home」と比べると、更にゆったりとした懐の深いナンバーが殆どとなっているところに使い込まれて黒光りしている工具のような年季を感じてしまう。
High And Lonesome時代では必ず何曲も聴くことが出来たSouthern Rockのストレートなロックテイストは完全に後退してしまっている。
かといって、南部スタイルのロックンロールが死滅したというと全くそうではない。どのナンバーにも1970年代のBoogie RockとSouthern Rockの匂いが、モルトウィスキーの年代物のような芳香が漂っている。
ハードサウンドは論外として、脱穀機のようなパワーで圧倒する泥臭いSouthern Rockではなく、使い勝手の良い鍬や鋤のような馬力のあるグルーヴィーな南部ロックンロールでアルバムを極めている。
あまりにも奇を衒わず、全く創り込みや装飾を度外視した、素のままのローギアでドライブするピアノサウンド、ピアノ・ルーツロックである。
こうもあけすけに、素顔のままのサウンドで顔面を引っ叩かれると、もう何も言えなくなってしまう。ただ、その心地良いクラッシックな根源音楽の綴れ織りを全身で感じて酔うしかないだろう。
David Zolloは、元々それ程手先の器用なピアニストではなく、腕力で音を出していくジャズ・ピアニスト的なプレイヤーであると筆者は捉えている。
Ian McLaganやRoy Bittan、そしてBenmont Tenchといったロック・レジェントの称号を得ているピアニストと比べると、音の出し方や音響の紘げ方がまだまだとは思うが、その分、アップデートな若さが感じられる力の入ったヴィヴィッドなプレイとサウンドを堪能することができる。
このあたりはWallflowersのRami JaffeeやCounting CrowsのCharles Gillingham、Five For FightingのJohn OndrasikそしてBen Folds等の次世代のプレイヤーと共通するプライオリティだろう。
ヴォーカリストとしても、そのルーズさと勢いだけを看板にしていたようなHigh And Lonesomeの頃よりも明らかにギグで使い込んだ喉がその包容力を増している。
そう、アルバムタイトルの「The Big Night」のように。アルバムのバックには夜の移動遊園地らしき電飾を空中撮影した写真が掲載されているが、「素晴らしい夜。」「豪華な夜。」という解釈が、彼のヴォーカルに繋がるように思えるのだ。つまり、全てを覆ってしまい眠りという安らぎを与える、夜。
その夜の宵闇とライトアップされた光と影。夜の持つ包容力と空間の奥行がDavid Zolloのヴォーカルに備わってきたと感じるのだ。・・・・かなり抽象的且つ直感的なインプレッションを書き綴ってしまったが、アルバムのタイトルと成熟したZolloのヴォイスから受ける感慨は以上のような具合である。
まず、David Zolloの成長を測るバロメーターはラストトラックの#10『Driftwood From Kerry』に違いない。
このナンバーはHigh And Lonesomeの1stがオリジナル音源なのだ。ほぼ10年前のヴァージョンと、2002年のセルフカヴァーを聴き比べるとはっきりとZolloの音楽性が変化していることが聴き取れる。
原曲はBo Ramseyがスライドギターをグラスタッチにくねらせる、ルーラルダンサブルな音色。それに重なるように隙間の多い鍵盤とジャム的なアクースティックギターを噛ませた脱力系の歌だった。
が、この2002年録音では、じっくりとしたハモンドに、啜り泣くようなスライドギターを幽玄に合わせた、夜の色がとても似合いそうなバラードとして再編している。
ピアノの響きを局限まで控えて、殆ど音を聴こえるか聴こえないかのレヴェルまで絞っている。また、Zolloのヴォーカルも渋さと甘さが加わって、オリジナル曲のテイクとは比較にならないくらいジンワリとしたルーツナンバーになっている。グラスとジャムロックの原曲から、ルーツロックにまでレヴェルを引き上げることに成功しているのだ。
バラードタイプのナンバーで、Zolloのヴォーカルの熟成と燻製された年輪を感じるのはこれはタイトル曲の#4『The Big Night』や#7『Lonesome Childhood』でも顕著だ。
特に、#7はその切なく物悲しいストーリー性と、感情をストレートに剥き出したZolloのヴォーカル、そしてBo Ramseyのギターソロと際立った点が多いバラードだ。
他の曲も、実に古典的なSouthern Rockのフィーリングが活きている。
ブルージーでファンキーなピアノが転がりまくる#1『While You Undress』でのザクザクとしたリズムと酔っ払いスゥイングは最高にグルーヴィだ。スライドのダイナミックな音色と、腕力に任せて弾いているピアノのズンドコした音の絡まりは、もうブルースロックのポップサイドを追求した曲としては最高の部類に属するだろう。
歌詞もまた、酔いどれなラヴソングというのだろうか。宗教的な観念も窺える。
♪「I was humbled by my vices.Outshattered by my silence.I sat alone and tried to find
my voice.Sometimes the things that bind you.Are the same ones that find you.
Born again and able to rejoice.」
と、コーラスの部分を聴き取ってみたが、彼のやや口を閉ざしたような歌い方では発音がかなりくぐもっていて、ますます酔いどれなシンガーという感が強い。
Bo Ramseyの存在感のあるギターと、この曲ではピアノとハモンドオルガンの鍵盤まで叩くZolloのプレイがガッチリとタッグを組んでいる#2『Eye Of The Needle』はJeff LynneがTom Pettyのアルバムで辣腕を振るったような塩梅の古さと現代のロックのコンテンポラリー性が混じったような不思議なノスタルジーが存在する。
ジャンプ・ブルース的な切れ味のよいピアノと泥臭いスライドを交えたギターが、南部フィーリングを混じえて馬力全開にリズムを叩き付ける#3『Why Don’t You Stop Me Now』でもZolloはハモンドを担当している。
カントリー的な要素がライト・ブギーなメロディラインに見え隠れする#5『Get Away』。このナンバーはBo Ramseyが提供していて、唯一Zolloがペンを握っていないナンバーでもある。同じくヴィンテージライクな軽めのダンス・ブギーを聴かせてくれる#6『You’re Gonna Get What You Wanted』でのZolloの裏声の楽しさ。このあたりのパーティ・ロックの感覚はただ単純に楽しい。
Todd Sniderのロックサイドの音楽性に通じる良質なセンスを内包しているのが、#8『Respect(Ain’t A One Way Street)』だ。このアルバムの中で最もポップで軽快にロックしたクセの少ない素直なトラックである。こういったナンバーが少なくなったからこそ、この煙を浴びた渋色なアルバムが完成したのだろうが、もう少しこのあたりのドリーミーなピアノが鳴る曲があっても良かったと思う。
そして、一番カントリー的な#9『Take Me Away』では、ペダルスティールをフューチャーして南部のディキシィ風のトラッド感覚が聴ける。
♪「My voice it won’t carry.It’s stuck in my throat.It’s the worst night that
I’ve had in years....Take me away from my heartache.away from my grace.
Nothing I want to say...」(聴き取り)
という男の失恋ソングである。密かに悲しむところがオトコだ。(笑)
以上のように、直線的なロックフィーリングよりもブルージーでルーツィでブギーな感覚が増して、ロッカーとしての厚味が増したDavid Zolloの4年ぶりの快作について述べてみた。
こういった地味な没進化的音楽は、あまり世間的な注目を集めないかもしれない。
が、大人として尻の軽いオルタナやパンク・ポップやエモ・ポップではなく、こういった酒を片手に酔いながら噛み締められる音楽を聴いてみるものたまには良い、自分への酔い方でもあると思う。
相当お薦めな1枚だ。 (2002.7.27.)
 Look To The Light / Once Blind (2002)
Look To The Light / Once Blind (2002)
Roots ★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Adult-Contemporary ★★★★
You Can Listen From Here
最初に断っておくが、
かな〜〜〜り好みなサウンドだ。
が、とある事情により今回のレヴューラインナップのトップを飾ることはなかった。理由は後述。
極端にルーツ音楽に傾倒している訳でもなく、かといってオルタナティヴやミクスチャーの鬱陶しさからは100%開放されている。
またジャム・ロックの量産型ザコバンドのように徒にアクースティックさを標榜するだけひけらかしているくせに、メロディがうざいアンキャッチーで退屈なこともない。然れども、しっかりとアクースティックに演奏することろは楽器の生の魅力を最大限に発揮している。
そして、アクースティックな魅力を振り撒きつつも、エレクトリックなサウンドの装甲の厚さをしっかりと感じることのできるサウンド・プロダクションをしている。
この真夏に飲む清涼飲料水のようなスカっとしたドライヴ・フィーリングは、1980年代のアリーナロックや産業ロックのアレンジ過多な側面ではなく、アンサンブルのガッチリとした壮大さを思わせるところが存在する。
やや、誤解を受けるかもしれないが、全盛時のPeter Framptomの西海岸とハードロックとインダストリアル・ロックの混血のような疾走ギターのサウンドを彷彿とさせる要素がある。
言うまでも無いが、ポップさは何処に出ても一級品で通用する完成度の高さがある。
殆どのナンバーをシングルとして切ることが可能だろう。まあ、現代の、迷走して赤色巨星の膨張に飲まれる寸前という体たらくのチャートには馴染まないクオリティの高いリアル・サウンドという意味合いに置いてのことだが。
やや間が空いてしまったが、サウンドの根幹はアクースティックでありつつも、エレクトリックである。この辺りの微妙なバランスを上手に取りつつ、しかもロックンロールとしてのインパクトを全く損なうことない。
デリケートで繊細なところは多分に含むが、ロックンロールのダイナミズムを決して失わない。パーティ・ロックのジャンプとビートよりも一段上品なロック・ポップヴォーカル形式の曲創りになっていると思う。
また、伝統的なロックンロールとポップスの様式美を受け継ぐ形でとても基本に忠実な普通の音楽性をアルバム内で表現しているのだが、1950〜60年代あたりのオールディズ的な懐古型ルーツサウンドや、ロックサウンドの古さを全く感じない。
どちらかというと、1980年代以降の王道的なポップロックとアリーナロックの中間点に位置する、微細に厚さのあるメジャー・ヒットしたアルバムの雰囲気を感じさせるサウンドとなっている。
このように書いていくと、所謂Roots Rockという音楽ジャンルからはかなり遠ざかってしまうような感覚を与えてしまうかもしれない。事実、このOnce Blindというバンドはベッタリのルーツ・サウンドをあまり匂わせないところが多いのである。
Adult Rock、Adult Contemporaryというロック・ヴォーカル的なサウンドをカテゴライズする時に使用する分類方法が最も適当なバンドかもしれない。
少々、混乱を与えてしまう例えかもしれないけれど、Once Blindを初めて聴いた時に連想した音楽は、1970年代後期のFleetwood Mac−丁度セールス的に全盛期に入った「Fleetwood Mac」や「Rumor」の頃−であった。
が、同時に同じFleetwood Macを名乗りながらも(こっちが本家だろうが・・・)音楽的にはブルースを演奏していた頃の初期のFleetwood Macのサウンドの代表である「Bare Tree」や「English Rose」そして「Then Play On」らしさも感じていたからこそ、真っ先にFleetwood Macの単語が脳裏に浮かんだのだと自己分析している。
ここにOnce Blindの音楽性の要が存在すると考えているのだ。
あからさまな土臭いナンバー、もっと言ってしまうとカントリーやカントリー・ロック、そしてオルタナ・カントリーといった性格を帯びたトラックは、完全無欠、100%純正で存在しない。
しかしながら、
フォークロックの繊細さ。
ブルース、というよりもロッキン・ブルースの馬力のある潮流。
ファンク・ロックの連打を与えうるフットワーク。
これらの下地にあるサザン・ロックの重みのあるずっしりとした質感。
こういったCountryとは異なるルーツロックの要素をしっかりと音楽の中に取り入れている。
が、以上の根源音楽はあくまでも下地となっているのである。全体的にはあからさまにBlues Rock、Folk Rock、Southern Rockといったルーツテイストを直球的にぶつけてくることはそれ程ない。
Adult Contemporaryとして、キャッチーであり、ソフィストケイトされ、滑らかなスマートさを湛えている普遍的なポップサウンドで最終的な味付けをされているのだ。
であるからして、田舎臭さ丸出しの野暮天サウンド・耕運機で畦道を暴走。テールからは舞い上がる砂埃、という明らかに田舎ロックというテイストは非常に薄い。
だけれども、産業ロックやプログレッシヴなアレンジでコッテリと南部ルーツのサウンドを包んでしまい、そういった内包物が全く味わえなくなっているというと、決してそうではないのだ。
こういったSouthern Rockの下拵えの風味をしっかりと残しつつ、適度にアーバンでスムーズなアダルト・ロックの甘さとのバランスを保っている。
言わば、Arena Roots/Southern Rockとも解釈すればよいだろうか。
それとも、Adult Rocking Blues Pop。
という得体の知れない造語で組み合わせるのが一番妥当と思えてくる、本来の意味合いにおけるフュージョン・ロックサウンドである。
要するに、直截的なルーツ音楽よりも、ポップロックのサウンドの中にルーツロックの比重が大きい1980年代までのメインストリームなアメリカン・ロックやポップスの21世紀版と考えれば一番ぴったりと填まるのだ。
Bruce Springsteen、John Mellencamp、Bob Seger、Tom Pettyといったアメリカンルーツ寄りの大物アーティストとBilly JoelやEddie Money、Rod Stweart、Bryan Adamsといったヴォーカルのロックシンガーの音楽性を融合させてやや掻き回してラフに仕上げた成果が、Once Blindの音楽と敢えて表現したい。
無論、Once Blindの特有な色合いはこれらのアーティストとは正確には異なるけれども。特に土臭くないのにルーツテイストを感じるという点が。
しかし、サウンドの方向性を表すにはこれが一番の比較対象であるとも考えている。
Arena RootsとかArena Southern Rockという表現を用いると、38 SpecialやAtlanta Rhythm Sectionといった1970年代から80年代に掛けてチャートでも活躍した南部系のバンドやREO Speedwagonのようなポップロックバンドを想像してしまうけれども、ポップさやサウンドの太さという(大仰さともいうかもしれないが)には共通項を見出すことが可能だろう。
まあ、陳腐な表現となってしまうが、多彩な音楽性を取り入れている。そういった場合に起こりやすい焦点の定まらないどっちつかずの混合半端な音楽に陥らす、自身の音楽としてカッチリと土台を固めた独自性を排出しているというところだ。
と、絶賛したいし、ここまでは全く問題が無いのだ。
しかし、お薦めする上で重要な点が2点存在する。1点は、まあ日本では大した問題にならないだろうか。
このOnce Blindというバンドは、聖書を原文で読める方やキリスト教に造詣の深い方なら用意に推察できるとは思うが、クリスチャン・ロックのバンド、宗教バンドである。
バンドの名前とアルバムの題名も、当然宗教観念からの引用である。
「What Would You Have Me Do For You ?」
「The “Blind” Man Said Unto Him,Lord,That I Might Receive My Sight」
「And Jesus Said Unto Him,Go Thy Way;......」
(中略)
「Are You “Look To The Light” ?」
あまりレヴューとは関係ないので中を飛ばしているが、以上のような寓話(と筆者は捉えているが)からアルバムのタイトルとバンドのネーミングをしている。
そう、Once Blindはその拠点である南部諸州の1つであるルイジアナ州の伝統的なSouthern Rockをベースにしているのは確実なのだが、Christian Rockをも基本にしていることが最大の特徴なのである。やや勿体つけた紹介となってしまったが。
ルーツロックに付加、或いは宗教音楽が一番の基礎かもしれないが、ゴスペルとCCM=Christian Contemporary Musicというポップで美しいコーラスとメロディラインが特徴であるジャンルの影響を色濃く顕しているバンドであるのだ。
であるからして、個人的には歌詞に関しては殆ど気に留めずに音楽のラインだけを楽しむ聴き方に終始している。
けれども、これは全く問題ない。最近はかなりCCMにもルーツ系の優良アーティストが数多く現れ、最も注目すべきシーンとなってさえいるのだ、筆者の内部では。殆どがメロディさえ良ければ、で聴いているのだが。
それよりも、問題はフォーマットである。
まず、嫌な予感がしたのが、最初にCDケースを開けてジャケットを眺めた時である。
あからさまにカラー・コピー。・・・・・・まあこれはインディ・シーンを発掘する上ではCasual Day Of The War(謎)であるため、全然気にならないのだ。が、ジャケットを二つ折りにしても
しっかりと正方形になってなひ。四つ切りがあまりにもいい加減・・・・・。嫌〜な予感倍増。
ここで確信したのだが、やはりCD-Rフォーマットだった・・・・・。これまたかなり凹むが致し方ないと諦めるしかない場合が多い。インディであるからだ。
が・・・・・
あまりにも粗悪なコピーのため、ウチの安プレイヤーではノイズで全く聴けず、涙をのんで焼き直し。(涙)やっと聴けた。
正直ここまで粗悪なコピーは今までに2回くらいしかなかった。CD-Rでも殆どプレスCD並みに聴けるものもあるのだけれど。
で、当然、バンドに苦情。ここで無視されたら、如何にこの「Look To The Light」が良いアルバムであるとはいえ、絶対に紹介の場を設けなかっただろう。
筆者は売る以上はプレスCDが当たり前であるし、フォーマットがCD-Rであるならその旨をしっかりと発表すべきであると考えている。が、最近はRメディアの製造があまりにも容易くなったので安易にCD-Rでコピーを増産するミュージシャンが増加し過ぎた。実に困ったものである。であるからしてレヴューのトップにはなるべく持ってこないようにしている。
しかし、即日でリード・ヴォーカルのDoug Admire氏から謝罪が届いた。以下要約する。
「大変申し訳ない。私達はプレスCDを作る予定だから、住所を教えて欲しい。CDが出来上がったら送ります。神のご加護があらんことを。」
という誠意の溢れたお返事を頂き、現在自分の高性能(をい)ドライブで焼いたCD-Rを聴きつつ、正規CDを一日千秋の思いで待ち侘びているという段階だ。
さて、バンドについてはあまりデータが無い。
設立は1998年。以来、4年間教会活動の一環として月に1回程度のライヴを全米の宗教関連のイヴェントやフェスティヴァルで行ってきて、2001年の12月にこの「Look To The Light」を録音。
メンバーは何と男女混合、夫婦や兄弟を含む8人の大部隊である。宗教バンド、特にこういったイヴェントを中心とした活動をしているグループにはゴスペル方式の伝統か、大掛かりな編成が多いようだが、Once Blindもその類に漏れない。
バンドメンバーの中には牧師も数名存在し、メンバーは全員宗教団体と何らかの関わりのある職に就いているということだ。
8人組という全くサポートミュージシャンが必要ない体制のためか、ゲストにはバックヴォーカリストが1名、3曲で手を貸しているだけだ。後は全てバンドが演奏している。
Claude Songy (Guitar) , Kalon Pichon (Keyboards,Vocal) , Mike Perkins (Lead Guitar) ,
John Perkins (Drums) , Danny Milan (Bass) , Gina Necaise (Vocal) ,
Doug Admire (Lead Vocal) . Nikki Admire (Vocal)
というように女性バックヴォーカリストを2名抱えるというゴスペルバンドの特徴が現れている。ソングライティングはリズムギターのClaudeとキーボーディストのKalonが単独或いは共同で全てを書いている。
11曲はどれも非常にCCMらしいコマーシャルで聴き易い。
Dougのソウルフルな牽引力のあるヴォーカルに、女性2名を含むやや控え目のコーラスが実に良いコンビネーションとなっている。
2名のギタリストがアクースティックとエレクトリックなギターアンサンブルを、切れ味の良いザックリとした音出しで巧みに表現している。
Kalonの鍵盤は殆どがピアノ・サンプリングや電子キーボードであり、頻繁にアクースティックピアノやハモンドB3を使用しているようには聴こえない。しかし、どのキーボードサウンドもとても暖かく、流暢、しかも包容力のある厚味が存在してゴージャスに、美しく曲を彩っている。
時にはルーツロック的なナチュラルな鍵盤を聴かせたかと思えば、産業ロックのような浮遊感とカラフルな音色のキーボードを演奏するという具合に、かなり変化自在なプレイを楽しめる。
こういった実力がひしひしと感じられる技巧があり、しかも曲が良質でルーツ的な素養があるとなると、もう最高のポップロックというしか他には選択肢がないだろう。
その最高のポップロックといえば、元気に踊りまくるビートに乗せたソウルフルでストレートなメロディが炸裂する#1『Look To The Light』を筆頭に、#3『Within Me』、#4『Does Heaven Know My Name』、#10『Human Too』というロックチューンがまさに該当する。
歯切れの良いセミ・アクースティックなギターサウンドが切れ込んできて、キーボードやリズムセクションが一緒になりラインをシェイクする、タイトル曲#1。Dougのソウルフルなヴォーカルにはブラック的なソウル・ミュージックの影さえ見えてしまう。
#1はバンドの許可を得てサンプルをHPに30秒のMP3化してあるので、試聴リンクから聴いて貰いたい。万言を費やすよりもこの心地良いサウンドが理解できるだろう。
Eddie Money等が歌っても全く違和感の無い、軽快で存在感の溢れる演奏がパワー満点の#3。かなり早口で歌うヴォーカルワークも圧巻だ。
ピアノを始めとするストリングス・シンセサイザーが控え目に重ねられたパワー・ポップ的なロックナンバーの#4は曲全体を持ち上げる底力というか、REO Speedwagon並みの力強いアンサンブルが甘いメロディと非常に宜しくマッチしている。強弱のあるスコアの変化と爽やかなコーラスもサウンドの重量を手応えのあるレヴェルまで押し上げている。
#10は1980年代のアリーナ・サウンドのドリーミーなキーボードラインを中央に置いた華やかでドリーミーなロックチューンである。これはルーツロックというよりもTOTOのポップロックチューンという趣の方が強烈だ。痛快なギター・ソロはSteve Lukatherのソロプレイを思わせる。
こういった流麗でスマートなロックナンバーとはやや異なり、ブルースを始め、南部ロックの味を強く押し出しているのが、#6『Situations』、#7『Doubting Time』、#11『Time To Chicago』といったところだ。
ブルースの哀愁を、アクースティック・ギターを中心に切なく歌う、ロッカバラードの#6ではヴォーカルが恐らくDougではなくKalonであろう。カントリー・ブルースではなく、ブルースをアクースティックに纏めているところが、Once Blindのサザン・テイストの特異な点だろう。
サザン・ハードロックとファンキーなきな臭さをヘヴィなギターリフに載せたのが#7だ。このアルバムの中では最も硬質なナンバーであり、酸味が強い曲でもある。しかし、コーラスの部分や全体のメロディは暗いというよりも、ハード・ポップであり、どうしてもコマーシャルな良曲となっている。
#10がSouthern Rockとしてもっとも先祖返りしている南部チューンだ。軽めのファンキーなシャウトからスタート。ダート感覚溢れるスライドギター的なギター弦が自在に暴れる。これは生粋の赤土や砂埃のざらつきを感じる南部ファンク調のロックチューンである。
これ以外にも、フォーキーで奥の深いバラードである#2『When I Get To Heaven』や#9『He Holds The Key』でアダルト・ロックの静的な才能を見せている。特に#9でのB3オルガンのしんみりとした音色は感慨が深い。
こういったシンプルなバラードよりも厚目なサザン・フィーリングとシティ・アダルトサウンドの融合が進んだ#5『Never A Believer』や#8『Wasted Time』はBruce SpringsteenやVan Morrisonが歌うとかなり似合いそうなコッテリさとマッタリさが同居したバラードである。#8のオルガン・ピアノ・シンセサイザーと重なった鍵盤の合奏はかなり産業ロック的な面があるが、それでいてルーツ的なゆったり感も存在感を主張しているという、Once Blindならではのナンバーだと思う。
以上、あまりルーツテイストが強くない、ポップロックなアルバムが聴きたいという人なら絶対に気に入る作品を紹介してみた。
最近レヴューしたCounting Crowsの4作目「Hard Candy」よりもポップで親しみ易いだろう。ルーツテイストとアダルト・コンテンポラリーを互いに混在させ、聴かせるポップロックにしているという点でも似通っている。
ジャンプ力とロックチューンのパワーならこちらの「Look To The Light」に軍配が上がるようにも思える。
ただ、ネックはあまりにも酷いCD-Rの焼き方だ。
これがクリアされないと躊躇無しにお薦めという風には断言できない。う〜ん、実に勿体無い。
一日も早いプレスCDの発売を祈ろう。その時は、諸手を挙げてプッシュする予定である。 (2002.7.31.)

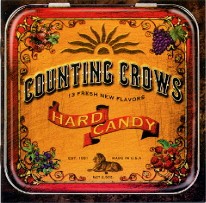 Hard Candy / Counting Crows (2002)
Hard Candy / Counting Crows (2002)