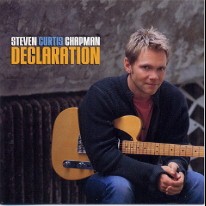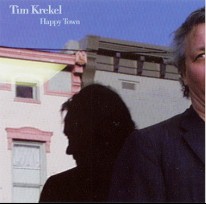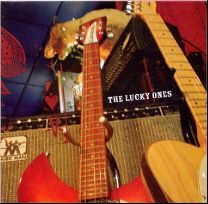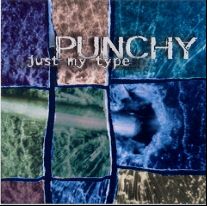 Just My Type / Punchy (2001)
Just My Type / Punchy (2001)
Roots ★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Southern ★
You Can Listen From Here
「それはソングライティングとエネルギーだよ。僕達は曲創りを柱にしている。つまり、全員がロックンロール好きということだね。僕達はフォークロック・ミュージシャンではなく、良い曲を生み出し、それをロックで表現しているロックミュージシャンだ。」
「君にとってバンドと音楽はどういうもの?」という問いに対して、リード・ヴォーカルのFritz Beerはこう答えている。
完全に同意したい。特にこの2枚目のアルバムの完璧なPop/RockとRoots Rockを聴けば、ロックンロール好きには反論の余地はないと考えている。
まず、Punchyの2ndアルバムである「Just My Type」の発売を完全に見逃していた自分にPunchを(寒)喰らわしておこう。結局発売から約1年遅れの入手となってしまった。
入手に際しても少々トラブルがあり、このことも手に入る時期を遅らせたのだが、Punchyのリード・ヴォーカリストであるFritz Beer氏の協力を戴き入手することができた。この場を借りて改めて御礼を申し上げる。
さて、最初にPunchyの音楽に出会ったのは1999年の後半くらいだと記憶しているのだが、mp3.comである。その時、試聴が可能だったのは僅か1曲のみ。1作目の「Punchy」からの#5『Never Question The River』であった。
このナンバーはかなり陰鬱な南部式(拳銃みたいだ)オルタナティヴと聴こえて来るナンバーであり、最もアルバムの中でもアンキャッチーなトラックであった。
ちなみに紹介の切っ掛けを戴いたのはとあるシカゴのルーツバンドのヴォーカリストからである。絶対にお薦め、ということで試聴可能な場所を求めて彷徨っていたら、結果としてmp3.comに行き当たったのだが、正直これでは買う価値ないんとちゃうかな、と考えてしまう程筆者の肌には合わないナンバーだった。
しかもボクシンググローブを嵌めたボクサーがコーナーで待機しているようなジャケットは、イメージ先行で今となっては汗顔の至りだが、「相当オルタナティヴ」という臭いを発散していた。
このボクサーの顔はFritzであるが、ボディは何と若き日のElvis Presleyの写真だそうだ。
グラフィックデザイナーがElvisの身体とFritzの顔を組み合わせたら、見事にマッチしたためジャケットに採用したとFritzは語っている。これにはアッパーカットを喰らった程度に驚かされ、そして笑ったものだ。
が、購入の時点ではそのようなことを知らなかったし、やはりオルタナティヴ系という疑いが捨てられなかった。最終的には購入に踏み切ったのだが、ここではかなり外れる野性のカンが(笑)当たったようだ。まあ駄目元で購入してみよう、どうせ10ドルしないからという動機もあったのだが。
そして、上記の経緯でオーダーしたデヴュー作「Punchy」が届いた。
早速聴いてみると、#5以外の7曲は概ね良好なナンバーが多かった。#1『Spray Job』のように前半で王道サザンロックを予感させて、コーラス部分のヒネリがオルタナティヴ/モダンロックのマイナーさに転調するという肩透かしもあったりしたが、ロックバンドとしてはかなり将来を期待できる1作目であった。
そこかしこでModern RockやPower Popに浮気したりするフレーズやアレンジも見られたが、メロディの良さという点が全てを覆い一纏めにするキャパシティがあったから、注目に値するファースト作となったのだろうが。
テキサスはオースティンで結成され、活動拠点もオースティンというバリバリの南部バンドでありながら、テキサスカントリーやトラッドに肩まで漬からずに、実に均整の取れた中庸的なPop/Rockを表現しようとしている態度に好感を覚えたものだ。(Fritzはセントルイスからの移住組だから、厳密にはネイティヴ・テキサスのバンドではないが。)
正直、このPunchyの1作目では、フィニッシュブローを喰らってマットに轟沈。その圧倒的な力量を持つサウンドのラッシュに遭えなくノックアウト負け、とまでは至らなかった。デヴュー作品らしい粗さ、統一性の無さ、B級さというところがあったからだ。
よって、ジャブを何発か貰ってしまい、何度か危うい局面を迎え、これは気を緩めてはいけないという警戒心を抱かせるくらいのフットワークとパンチ力を有したボクサー、こんな感じに捉えていた。
参考までに、現在はmp3.com上でも試聴可能な曲は増えており、アルバム未収録のシングルナンバー1曲も加えて本来のPunchyらしい曲が2トラック並んでいるので、興味のある方は上のジャケットのリンクからジャンプしてみては如何だろうか。
そのセルフタイトル・フルレングスアルバムから約2年後−筆者は見事にチェック漏れしていたのだが、本当に申し訳ないことだ−Punchyは2作目「Just My Type」を2001年に発表している。しかし、2001年作品とはいえ、筆者が2002年に聴いたアルバムでは年間トップ5入りは確実な大傑作となっている。
1stで足りなかった点を見事に改善して、最高のPop/Rockアルバムを届けてくれた。
今回は完全にKOされて第一ラウンド開始直後にフィニッシュブローの綺麗なワン・ツーを貰って敢え無く轟沈といったところである。
まず、1stでは浮遊感の漂うキーボードサウンドを取り入れたモダン・ポップ風のナンバーが何曲かトラッキングされていたが、今作ではそういったあやふやな柔らかさでリスナーを魅惑するような手法は全く消え去っている。よりソリッドに、鋭角的に、安定感を増し、そしてそれでいて物凄くキャッチーである。
テキサスはオースティンのロックバンドということで、CountryやCow Punk、そしてSouthern Hard風味のダートなサウンドを思い浮かべるリスナーもいるかもしれないが、そういった音楽的素養は実に希薄である。敢えて、トップの分類にSouthern=Southern Rockとしてあるけれど、便宜上の分け方と考えてもらったほうが良いだろう。
勿論テキサス/サザンの土臭さと骨の太さはしっかりと抱えているロックンロールということに疑いを差し挟む余地は全く存在しない。が、それよりも
普遍的な王道Pop/Rock路線の正統派を感じるサウンドである。単なるルーツロックという枠組みでは収まらない=嘗ての大物ロッカーの正当後継者と呼びたい。
ヴォーカル担当のFritzはこう述べている。
「僕は自分でもポップな音楽が好きなんだろうとは思う。けれども甘過ぎるポップは正直苦手だ。僕はエッジの存在するハードなサウンドが好みだけれども同時にキャッチーでないのなら御免だね。僕はメロディとしてフックがある歌には中毒症状を示すくらい甘いよ、だけれどもキャッチーというコマーシャリズムで塗り固められた歌は要らない。(中略)例えばThe Clashの音楽は常に調和の取れたものだと思うけど、エッジがあるし、Tom Pettyはキャッチーな音楽を創り、メインストリーム街道を進んでいるけど、彼の声はダーティだろう。」
筆者としては、Saves The DayやSimple Plan、A New Found Glory、NOFX、そしてBlink 182にWeezer、一部を除いたMatthew Sweetを代表するNot Lame/Mitch Easterサウンドを含めた、Power Popだけ、Emo Popだけ、Punk Popだけというようなオンボロアパートの壁よりも音楽的奥行が薄い音楽性をコマーシャリズムで代弁したバンドがFritz Beerの批判する「キャッチーで固められただけ」の音楽に該当すると考えている。
これらの音楽に共通するのは、一聴する分には非常にポップでソニックでラウドであり、良い気分に浸れる。が、後には何も残らない。ヘドロに埋め立てられた汚染海岸のように水深の浅い音楽ということだ。
反して、Punchyの音楽は、ポップさではA New Found GloryやWeezerの「Green Album」並みを誇りつつ、どっしりとした重みがあり聴き飽きることがない。極端にダウン・トゥ・アースに走っているAlt-Countryサウンドではないけれども、しっかりと耕された畑から立ち上る土いきれのような匂いを感じれるアメリカンルーツの懐の深さが存在する。
パンクポップやエモ・ポップのどぎつい脂ぎった輝きや、ミラーボールのような極彩色の派手さは感じられないけれども、筆者が好んで聴く地味地味なトラッドやルーツポップほど枯れていない。
まさに、上記したように正統派のアメリカン・サザンをベースにしたAmerican Roots Rockである。
“Back To The Basis And Origin From American Music”という呼び方を筆者はしたい。まあ、つまり筆者の一番好む、ルーツでありつつ、極端にトラッド/カントリー化もせず、ハードでダーティな領域まで踏み込まないバランスの良いロックンロールバンドなのだ。
重要なことはポップバンドではなく、ポップでロックなロックバンドという箇所である。これは意外にありそうで中々見つからないから貴重なのだ。
とはいえ、単なる懐古的なBoogieやFaces/Stones風のロックサウンドを聴かせるというとそうではない。1980年代から1990年代にかけての現代的なロック風味もまた表現しえているバンドであるのだ。
海外レヴューサイトでは、Fritzの声質がSoul AsylumのDave Pirnerと似ているという評判からSoul Asylumのフォロワーとして比較されることが多い。またそのロックンロールなサウンドからReplacementsを引き合いに出すレヴュアーも結構いる。
確かにベッタリとルーツに耽溺せずに微妙なアメリカン・ルーツを演奏している点ではSoul Asylumに通じるところがなきにしもあらずだ。当然後期、1990年代以降のSoul Asylumである。
しかし、PunchyのFritz Beerが書く歌はSoul Asylumより遥かにポップで親しみ易いし、その点ではReplacementsやPaul Westerburgはファンには悪いけど(筆者自身好きではある、当然。)、足元にも及ばないライティングの才能がある。
甘過ぎないけれども、リスナーのハートを掴むというフックではSoul AsylumもPaul Westerburgもはっきり言ってFritzには勝てないと断言しよう。後はミュージシャンとしての経験と深みがサウンドの渋さや落ち着きとして、音創りの隙間に降着してくれば、間違いなくこの2つのビッグ・ネームを超えれるだろう。
特に最近ロックンロールを忘れてしまったかのようなソロ名義活動を続けているPaul Westerburgはロックを書くという面で相当のビハインドがある。ヴォーカリストとしては一流とはお世辞にも言えないヘタさが光るPaulよりも、もっと味のあるヴォイスを有するFritz Beerに軍配が高々と上がる。筆者は物凄く似ているとは言い難いが、確かに奇妙な中毒性のあるDave Pirnerの声と似ているところはある。
Punchyのメンバーが影響を受けたアーティストは、The Clash。特に全ての曲にライターとして関わっているリード・ヴォーカルのFritzはClashから最も影響を受けたと語る。
その他、Gram Persons、Tom Petty、Elvis Costello、Bob Dylanといったアメリカン・ロックの大物。そしてThe Replacements、Soul Asylum、Husker DoといったミュージシャンとSoundgradenやAerosmithまでも聴いているという音楽性の間口の広さである。
「誰もが、幅広い音楽性を取り入れて創られた音楽を好んで聴くと思う。当然僕もそういう聴き方から影響を受けているからね。」
とFritzは語る。確かに、非常にオルタネイトなリスナーに歓迎されること請け合いの素直で聴き易いポップセンスが溢れている。かといって、単に聞き流すだけの軽いポップアルバムではないのが最大の魅力だろう。
リピートになるのだが、心に定着する重厚でかつしつこくないコマーシャルなメロディが、絶対にこのPunchyというバンドの音楽を印象的なものにせざるを得ないのだ。アレンジ、コードの重ね方、ヴォーカルとコーラスとどれもパンチ力が100%充填済みなのだ。
見た目が派手そうで、実はパンチ力の無いPower Popとかと比べても、ルーツロック系というジャンルに共通するボディ・ブローの地味さとは異なり、ダイナミックなストレートやアッパー・カットも放てるバンドだ。要するにマスクの差だろうか。エモやパンクは顔がハンサムだが、判定勝ちもできないショーマン・ボクサー。対してPunchyはルックスには難がやや有りとはいえ、実力派のボクサーであり、それ程薀蓄を垂れなくても実力が素人目にもはっきりと浮き出ている、というタイプ。・・・・ちとくどいか、ボクサーの例えは。
デヴュー盤は8曲の収録だったが、今回は11曲とフルアルバムとしては21世紀のスタンダードというところだろう。当然ながらハズレ曲、捨て曲は皆無である。ロック系のラジオなら#5以外の全曲シングルカットが可能なくらい、各ナンバーのヒット性は高い。まあ、現在の死に体のゾンビ化した米国メジャーチャートでは受け入れられないだろうが。
録音メンバーは1作目と同様、バンドの4ピースに2名のキーボーディストがゲストで参加というもので、ベース担当が交代した他はサポートキーボディストの顔ぶれまで同じである。これに前作でも5曲を担当していたプロデューサーのLars Gorannsonがホーンアレンジとバンジョーで参加というのが唯一の相違点だろう。
そして、全てのナンバーが素晴らしい
という一言で終らせても良いのだが、まあ少しだけ各曲について簡単に持ち上げておくことにしよう。
#1『Just My Type』から軽快であり、アップビートであり、ドキャッチーなロックンロールが飛び出してくる。1stアルバムのオープニングも同じようなロックナンバーだったが、コーラス部分でオルタナティヴ風鬱展開を見せていた。
そういった歪みというか斜に構えた姿勢が感じられない。「甘過ぎる曲は嫌い」というFritzの甘さの基準を好意的に疑いたくなる程のナンバーである。しかも単調に進むのではなく、ヴァースとヴァースの間の間奏でスローにビートを抑える小技を使い、巧みにロックの弾みとメロディの親しみ易さを強調している。オルガンとピアノサンプリングの使い方もかなり多彩であり、2名の鍵盤弾きが今回のアルバムでは曲別ではなく競演しているように感じる。
#2『Graces』はタイトルの通り、慈悲深いというか、そこはかとない優しさを思わせるミディアム・ロックチューンである。暖かく表現されたFritzの無理矢理ハイキーを使って所々割れているヴォーカルも、素顔が感じられて親しみが持てる。オルガンとそしてホーンセクションが上手く曲をバックアップし、コーラス部分ではギタリストのErrol Seigelとのコーラスワークが#1以上に決まっている。ブラス好きとしては、でしゃばり過ぎないホーンが少々食い足りない気もするがそれは高望み過ぎるというものである。
#3『Legs Kicked Out』ではテキサス・ルーツパンクという土地柄を示すようなハードエッジなアンサンブルが随所で炸裂するシンプルなロックナンバーが押し出してくる。このナンバーもローファイラップ気味に淡々と進行するチョッパーベースとギターのフレーズもあれば、分厚いギターが泥臭くスライドするパートありとかなりの山あり谷ありな展開を3分間で見せてくれる。ハードなロックとして聴き応えがある。こういうところでポップに纏められたアルバムの甘さを希釈しているのだろう。
#4『On The Way To See You Tonight』ではいきなり打ち込みサウンド的に処理された無機質なドラムからスタートするので、あれっ、と感じるが即座にアーシーなギターが弦を波紋にしていくPunchyらしいSouthern Rockのヘヴィさが聴こえてきて安心する。このモダンなリズムとキャッチーでパワフルなリフの結婚は、Everclearが一番ポップであった「So Much For The Aftergrow」の雰囲気にどこかしら似ている。
#5『Needle Exchange』は最も南部ロックを肌に感じさせる粘っこいグニャグニャしたベントな音出しをしたギターがのたくるヘヴィなタッチのチューンだ。Lynard SkynardやR&Bの酸味を感じるナンバーであり、Punchyのタフさを示す曲でもある。メロトロンやオルガンが調子外れに吹き上がるパートはサイケディリックな面へのアプローチもあるように思えたりする。シングルに向かない乱雑さを持っている唯一のナンバーかもしれない。
#6『By This Time Tomorrow』は#5で思いっきりハメを外した反動か、実に小ぢんまりと纏められたミディアムなポップナンバーである。コーラス部分のフックの即効性は健在だが、クラヴィネットやオルガンをバッキングにしてルーツな下地を大切にしつつ、アーバンなモダンポップロックを表現している。その融合も1st程周りから浮いておらず自然にアルバムの流れに入り込んでいるのが成長の証しだろう。
#7『Standing On Legs Of Lead』はアクースティックで情緒あるオープニングから、やっとバラードの登場かと予想をさせるが、どっこいミディアムなビートの印象的なポップロックナンバーへと転じていく。Dylanを思わせるトーキング・ヴォーカルをメインヴァースで披露しつつ、コーラス部分でのメロディに合わせたヴォーカルのアンサンブルが対照的な故に、不思議とコーラスのモダンビートが印象に残る曲である。
#8『Tears Me Through The Bars』はアップビートに展開する痛快なロックンロール。スペイシーなキーボードがバックで頑張っているためか、削り過ぎた局限のシンプルさというイメージがどれだけソリッドにロックンロールを叩き付けても感じられないバンドなのだが、この曲もそれなりの装甲を有した中戦車のような安定感がある。
#9『Only Words Are Left』も#8のように実にキャッチーなロックチューンである。爽快さと清涼感という吹っ切れた感覚においては#8を凌駕する良好なロックチューンである。こういったスムーズなナンバーになると不器用な凸凹がSoul AsylumのDave Pirnerと似ているFritzのヴォーカルは、少々調子をラインから外してしまっているのだが、そこがまた人間臭い有機的な魅力を発散するのだ。
#10『Try Something New』はかなりハードなロックに突き進むようなオープニングリフを見せるが、やはりスピーディで軽快なロックナンバーへと集束していく。キャッチーな曲しか書けないのか、というこれまた微笑ましい心配をしてしまうのだ。後半の3曲は実に地味であるが、アップビートでメロディにエッジの程好い切れ味があるナンバーが並んでいて旨味のある場所だ。
#11『Take What’s Left On Your Pride』はオルガン、メロトロンサンプリング、そしてホーンといった楽器が暢気にテキサストラッドをジャムる形のスローナンバーである。ここにいたって漸くトラッドを濃厚に感じられる曲が登場するが、決してバラードではない。クラシカルなサザン・フリースタイル曲という感覚が一杯のスゥインギングなナンバーである。結局バラードらしいバラードが無いのだ。
だがしかし、決して単調という感じではない。ルーツロックと現代性を巧みに同居させているが、B級なチープさよりも王道的なPop/Rockの感触の方が上であるし、同系列の曲が並んでいるのは確かだが、曲によって様々なメリハリや変化を演出していてかなりの多彩さが見えるのだ。
さて、恒例により長くなったので最後にバンドの足跡に付いて触れて締めとしよう。
イリノイ州出身で、ミズーリ州のセントルイスで音楽活動を始めたFritz Beer。The Bishopsというロックバンドに所属し2枚のアルバムをリリース。このバンドはUncle TupeloやSmashing Pumpkins、TheConnellsの前座を務めるというそれなりのバンドであったようだ。
同時にローカルでソングライターとして幾つかの賞を獲得する等して地位を固めつつあったシンガーソングライターのFritz Beerがバンドの停滞と活動停止を切っ掛けに、オースティンへと移り住んだのがバンドの始まりである。
「よりソングライティング・オリエンティッドな音楽をやってみたかったし、ロックをプレイしたかったので、ライヴ音楽では世界一と考えていたオースティンを選んだ。」
とFritzは語っている。当時のパートナーは高校時代からの友人であるDan Bullというギタリストだった。このデュオがドラマー募集の広告を貼ったところ、何故かギタリストのErrol Seigelが応募してきた。当然断る意向だったのが、オーディションの前に渡したFritzの創った20曲全てを数週間でマスターし、プレイして見せたためにバンドのメンバーに加えることにしたそうだ。
ドラムレスでスタートした3人は、コーヒーハウスでアクースティックギグを行い始め、自信をつけたため、ドラマーを雇い入れバンド名をPunchyとする。ドラマーは当初は流動的だったらしいが、最終的にはArmando Reyesがセットの前に陣取ることとなった。
しかし、ツアーを始めた当初、Dan Bullが体調を壊し持病であった白血病が悪化。ハードなライヴ生活に耐え切れず、バンドをクビになる。
「そう、僕はDanを追い出した。当時からPunchyは年間150回のライヴを演っていたからね。このまま僕等と活動を続けることは彼にとって非常に危険だと判断したんだ。」
という断腸の決断をした後、ベーシストとしてバンドに加入したのがLee Abramsonというプレイヤー。1999年には年間200回のライヴを行う傍ら「Punchy」をリリース。このアルバムはローカル誌でかなり高い評価を受け、それに目を留めたカリフォルニアのレーベルPinch Hit RecordsがPunchyと契約。このレーベルにはルーツ系のロックバンドはPunchyだけである。後はモダンやパンク、グランジのバンドばかりである。この点からPunchyの音楽性がかなり広い受け入れをされているか判断できよう。
そして、2001年に本作「Just My Type」を発表するが、その前の2000年に1曲入りシングル「Keep Turning Right」をリリースしている。そのシングルを発売後Leeは神経性腰痛を患い、Matthew Hunkeというベース担当と交代している。どうにもベーシストには不運があるバンドなのかもしれない。
このアルバムも好評を博したようで、38 SpecialやCharlie Daniels Bandのテキサスツアーのフロントライナーに抜擢される。徐々に地歩を固めつつあるバンドである。
テキサスで活動するバンドだが、ネイティヴテキサスはドラマーのArmandoのみという異邦人で形成されたロックバンドというやや変り種でもある。Fritzもバンドの音楽を「Midwestern Rock」と呼んでいることからも理解できようが、物凄い南部のロックテイストが振り掛けられたバンドではない。寧ろ米国中西部と南部の中間的なロックサウンドが売りだろうか。
今回のアルバムジャケットはよく見ないと判別が難しいが、金属バットをガラスに突き立てて破壊している写真がモザイク模様にデザインされ、かなりアーティスティックになっている。前回のElvisの身体を使ったボクサーの合成物と比較するとかなり意味深な感じもする。
ボクサーのパンチよりもより一点集中的な金属バットを突き立てる刺激を表現したかったのだろうか?
何れにせよ、破壊力とパンチ力は1st作よりも格段に増していることは事実である。
兎に角、買って聴いてみれば、きっと金属バットで頭を叩かれたような衝撃を受けること間違いなしだ。ロックとポップが好きなリスナーという限定条項が付帯はしているけど。 (2002.10.6.)
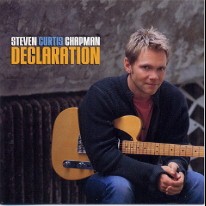 Declaration / Steven Curtis Chapman (2001)
Declaration / Steven Curtis Chapman (2001)
Adult-Contemporary ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Acoustic&Modern ★☆
You Can Listen From Here
Steven Curtis Chapmanは1962年11月に、アメリカ中部のケンタッキー州で生まれている。1987年にChristian/Gospel Musicの、ややトウが経ったアイドル的な扱いを受けてレコードデヴューしてから15年が経過して、2002年現在で遂に40代の大台に乗ることとなる。このレヴューを書いている段階では39歳だが。
Contemporary Christian Music(CCM)、これを訳すと現代の宗教音楽という具合になるだろうが、つまりクラシックや賛美歌ではない宗教ポップ音楽の総称がCCMである。最近はAlternative CCM等の名称も現れ更に細分化の傾向にあるようだが、本質はPop/Rockというところにあるのは間違いない。Alternative逝ってヨシ。
殊に、CCMは日本でいうAOR、米国ではAdult Contemporaryと殆ど同一視されている。またそれは非常に適切な分類であると思う。メインストリームのPop/Rock路線に伝統的なゴスペル音楽を重ね合わせて1970年代頃から発展してきたジャンルがCCMなのであるから。
実際、総合ポップチャートで大ヒットをかっ飛ばしてCCMからAdult Contemporaryに移行したシンガーはどの時代にも存在する。
要するに歌詞を宗教色で纏めたアダルトロックがCCMと考えて全く差し支えないだろう。
今回紹介するSteven Curtis Chapmanという人は日本では全く知名度が皆無に等しいが、米国ではCCMのトップスターである。
「1980年代と1990年代にかけてCCMチャートでは最もレコードを売り、成功したシンガー。」とメディアからは賞賛されている。同系の畑からはAmy GrandやJars Of Clayといったメジャーチャートの常連となったビッグネームも排出されている。
Stevenもメジャーチャートへ何曲かのシングルとアルバムを送り込んでいるが、宗教チャートを離れるまでの大ブレイクを幸か不幸か経験していない。しかしながら、ゴスペルチャートでは殆ど毎アルバムからNo.1ヒットを出し、RIAA公認のゴールでディスクを5枚(50万枚売上公認)、2枚のプラチナディスク(100万枚公認)を獲得。本作「Declaration」も6枚目のゴールドディスクとなっている。
なまじポップ界へと中途半端にシフトしなかった分、堅実な地位をゴスペル・チャートで築き上げたのだろう。
まあ、筆者は最近のチャートアクションはどうでも良かったりするので、チャートの話はこの辺まで。Steven Curtis Chapmanというシンガー・ソングライターが米国宗教チャートではトップアーティストということを認識してもらえればそれで問題ない。
参考までにグラミー賞も1990年代に4回受賞しているが、これこそ腐ったメジャーの最たるものであるので、どうにも評価の基準にはし難い。特にロック系の受賞には納得行くものは近年何一つない。どれも名前と先行イメージで賞を貰った出来レースにしか過ぎないと筆者は思っているので。
だがしかし、Steven Curtis Chapmanのオリジナルアルバムはベスト盤も含めると、この「Declaration」で12枚目となる次第だが、毎回絶対に外れの無い標準以上のポップロックを順調に重ねてきているので、実力相応の評価であるとは見なしている。
そもそも受賞がゴスペル関連で音楽的にはポップロックと同じなのだが、ロック系の受賞ではないので、素直に評価すべきかもしれない・・・・・・。というようなことまで考えてしまうのだ、良質なPop/Rockをパターン化と批判されつつも創り続けるSteven Curtis Chapmanを見るにつけ。
Stevenの父親は音楽好きで、楽器屋を経営する傍らソングライティングをすることが趣味という人だった。Stevenは父の店を幼少時から遊び場にしていた関係で、自然と楽器と音楽に親しむようになる。また、ソングライティングのいろはは、父から手解きを受けたそうだ。
楽器と音楽に囲まれて育ちながらStevenがのめり込んだ楽器はギターとピアノだった。しかし、音楽を趣味としつつもStevenは医者を目指してインディアナ州の医科大へと進み医学予備学生となる。日本では大学入学から6年で医師になる資格を得ることができるが、米国では最低8年の期間を必要とする。飛び級制度があるとはいえ、18歳で医学部に入学しても26歳にならないと医者になることはできないのである。
が、どうしても音楽のことが頭について離れなかったStevenは大学を中退。プロとして音楽に携わるためテキサス州はナッシュヴィルに居を構えることになる。どうもシンガー・ソングライターはテキサスで活動をしたがる傾向にあるようだ。オースティンやナッシュヴィルを目指す若者は多い。
1980年代初めから、Stevenはナッシュヴィルでソングライターとして活動を開始する。当然コーヒーハウスやボールルームでも歌っていたようだが、殆どの開いている時間を費やして曲を書き散らしていたようだ。
Stevenの才能は、まずシンガーとしてよりもライターとして評価され始め、1960年代から活動している宗教グループの重鎮The Imperialsが彼の曲を取り上げたのを皮切りに、1980年代半ばにはSandi PatiというCCMのシンガーやGlen Campbellといったカントリーポップ系のシンガーがStevenの曲をレコーディングする。
これらのアーティストに曲を提供するライティングのセンスがあり、ルックスもハンサム、そしてギターとピアノを巧みに弾きこなし、そしてヴォーカルも光るものを持っているとなれば、1980年代という時代性ではレコード会社が黙っていなかった。
元々、ゴスペル系やカントリー系の歌を書いていたのだが、メジャーのレーベルも相当接触を図ったらしい。が、最終的にSteven Curtisが選んだのは宗教レーベルの中でもアダルト・コンテンポラリー色の強いSparrow Recordsであった。
そしてデヴューアルバム「First Hand」を1987年にリリースする。このアルバムを筆者は未だ聴いたことがないので、どのような位置付けかはっきりと判断しかねる。筆者がSteven Curtis Chapmanを知ったのは、当節流行の長髪ルックのStevenと、ジャケットの大きなアルファベットが如何にも産業ロック系のヴォーカリストを予想させる「Real Life Conversations」からである。
このアルバムはほぼ同時期にデヴューして現在も堅実に活動しているところまでが共通のキーボディスト兼シンガーであるMichael W.Smithの作風にかなり近いアダルト・コンテンポラリーな色合いで統一された作品であり、産業ロックやアリーナロックの大仰で華やかなところも時代性を反映しているといえよう。
この2枚目のアルバムからゴスペルチャートにNo.1を始めて出し、合計4曲のシングルがラジオでヒット。本格的にChristian Rockのスターへの階段を上り始める。
1990年に発表された4枚目のアルバム「For The Sake Of The Call」では5曲のゴスペルチャートのトップシングルを含む7曲ものヒットシングルをカット。グラミー賞のベスト・ゴスペル・ポップアルバムに選ばれる。その時点ではゴスペルチャート的には最も成功を記録したアルバムとなっている。
このアルバムまではオーソドックスなアダルト・ロックとフォーキィなポップソングでアルバムを固めていたChapmanだけれども、1992年の「The Great Adventure」ではアルバムの名前に沿うようにラップ、カントリー、ハードなロックナンバー等に挑戦するようになる。特に、前作から表現し始めたナッシュヴィルのカントリー・カラーを示すようなダートなカントリーナンバーやロックチューンが次第に増えてくる。
7枚目の「Heaven In The Real World」(1994年)でもルーツ/カントリーというかテキサスのアーシーなロックを感じさせる曲とオーケストレーションに導かれたロックバラードが並存するPop/Rockを発表。
そして1996年の「Signs Of Life」は最もグラスルーツやカントリー、そしてサザンロックの辛口なメロディを感じさせるポップ度の低いアルバムを作製するに至る。ルーツになるのは結構だが、少々Chapmanの持ち味である嫌らし過ぎる程のキャッチーさが相当後退したこのアルバムには正直首を捻ってしまったものだ。
しかし、初のベスト盤で新曲入り「Greatest Hits」(1997年)ではStevenらしい甘過ぎる程のオーケストラ・バラードを新曲で聴かせてくれた。それを踏み台にしたように1999年の11枚目のアルバム「Speechless」ではドブロギターやアクースティックギターを大幅にフューチャーしつつも、それを打ち込みドラムを多用したインダストリアルなロックと巧みに融合させ、久々に正統なPop/Rock路線に立ち返った作品にしている。
というよりも時代の適宜に適った呼び方をするならModern Rockの良質なポップアルバムというべきだろう。アクースティックで優しいギターの音色とプログラミングの打楽器と鍵盤を上手に共存させているからだ。
このアルバムも7曲のシングルがゴスペル・チャートでヒット。何曲かはメジャーのトップ100にもチャート・インし、プラチナディスクを獲得。キャリア最大のヒットとなった。当然ゴスペル・ポップのグラミー賞を獲得している。
そして2001年年末には12枚目のオリジナルアルバム「Declaration」を発表。このアルバムもメジャーのポップチャートに顔を出したようである。トレースしていなかったためどの程度の記録を残しているかは定かではないが。シングルも好調にゴスペルチャートでヒットを記録し、発売から1年近くを経た2002年現在でもアルバム、シングルともにゴスペルチャートに居座り続けるロングセラーとなっている。
「今回のアルバムも前作で実行した手法を踏襲しているよ。それはレコーディングにエレクトリックな要素を大幅に取り入れたことだ。プログラミングやサンプリング、そしてドラムループといったものをね。」
とChapmanは12枚目のアルバムを自己分析している。
確かに1990年代に入ってから追求していたテキサスルーツやトレディショナル・カントリーのダートで土臭い南部サウンドは完全に消滅してしまっている。本作も前作「Speechless」と同じくモダンなPop/Rockのアルバムという枠組みに入るだろう。
だが、前作ほどに打ち込みやテクノロジーが主導権を握っているようには感じないのだ。方向性が極端に変じた訳ではないのに何とも不思議な感じがする。この印象の答えはChapmanのコメントから一部なりとも引き出せそうだ。
「でもギターも詰め込んだ。ギターで電子楽器と壁が出切るくらいにね。ギターとギターを重ねた。このアルバムはギターアルバムだと思っているよ。」
確かに、前作よりも物凄くロックにダイビングしたアルバムとまでは激変を示していない。がロックンロールに顔を向けたナンバーはかなりロックのドライヴ感覚が増加し、アダルト・コンテンポラリーなバラード系ソングとの温度差が相当に増しているのに気が付く。
また前作ほどに打ち込みのドラムやキーボードプログラミングが全面に出ずにサポート的な役割を果たしているナンバーがその割合を前作と比して拡大しているのも間違いない。シンプルなギターナンバーに少々電子楽器の力を借りたという感じのナンバーが何曲か目に付くのだ。
結果としてロックチューンとバラードのメリハリが良いアクセントとなったロックの軽快さとサックリした切れ味が強調されたアルバムとなっている。全体の統一感ではやや「Speechless」には劣るかもしれないけれど、多彩さと変化を見せるという点では最大のヒット作を凌ぐプライオリティを有したアルバムになっていると思う。
今回は全部で13曲、60分以上の収録時間というCD時代を象徴するようなオーヴァー・ヴォリュームとなっている。 宗教系の場合、三つ子の魂何とやらで、世界的にも異常なくらい宗教的な信仰心の希薄な日本で精神的土壌を育成してしまった筆者にとっては、「神様、万歳。」、「主よ、お慈悲を。」、「神様に祈ろう。」というワーシップな歌詞がどうにも空絵事にしか感じられない。
この点は長く述べるつもりは無いし、数十カ国の若者と海外のキャンバスで交流して来た経験から言えば、レアなのは日本風の宗教観念だから、まあ文句を垂れるつもりはない。が、やはり偶像崇拝としか思えないし、例えば仏陀や観音菩薩をポップスで称える歌を日本語で聞いたら、さぞかし気色が悪いだろうとしか思えない。
であるから、あまり長いアルバムは苦痛である、正直。純粋に歌詞抜きで聴けば良いのだが、悲しいかな、どうしてもどれだけ耳を鈍感にしても聴き取れてしまうのだ。
この点、Steven Curtis Chapmanは直截的な神への賛歌と、やや婉曲的な曲を半々くらいに歌う人なのでまだ良い方であるかもしれない。が全体としては神を全面に出す歌詞が多いことは確かである。
アーティストのコメントについても、流石にメジャー系の人だけあってインタヴュー情報等は豊富なのだが、どうしても「神様」、「信仰心」、「誠実」とかの概念を踏まえた語らいが多いため、純粋に音楽的な事項だけを拾い上げるのに今回も腐心した。よってコメントは全面的に神様ワッショイの(をい)ものは取り分けた。結果、殆どのコメントが残らなくなってしまったのは必然だろう。
で、話を戻すが、13曲という分量はメロディに限れば聴き飽きることのない良質なナンバーが揃っているので問題ないが、無神論の人でリスニングのアビリティがあるとしんどいかもしれない、と断っておく。
全体的にはストリングスをバックにしたアダルトなバラードと、ギターやシンセサイザーでパワーにポップするロックナンバーの2種類で構成されている。嘗てはここにダート感覚のあるCountryやFolkの要素のあるナンバーが割り込んで来たのだが、今回はそういった音楽は残念ながらない。が、リズムナンバーやラップという色物にも手を出すことを控えているので、その点では堅実な創りに拍手を送りたい。
まず、ロックタイプのナンバーだが、ファーストシングルとなった#1『Live Out Loud』が出色だろう。そこはかとないアクースティックなザクザクと鳴るギターを配してパワフル且つキャッチーに進む。シンセサイザーやサンプリングもシンプルでカッティングが鋭いこのナンバーの補助はすれども邪魔はしていない。分厚いゴスペルコーラスは本来のフィールドであるためこの曲だけでなくどのナンバーでも大活躍するが、元気印という点ではピカイチだろう。
#2『This Day』もロックナンバーと言うほどエッジは尖っていないが、軽快さとアクースティックさではアップビートな明るさを表現しているのでロックチューンに含みたい。ストリングスとアクースティックギターの掛け合わせが実にリズミカルな雰囲気を生み出している。ギターナンバーに上手な装飾を施せば気持ちの良いポップ・ロックが生まれるという好例を示すナンバーでもある。
出だしの3曲の流れがアルバムで最も素晴らしい箇所と考えているのだが、そのロック3連続を締めるのは#3『Jesus Is Life』である。多重録音されたコーラスワークに、抑えの効いたヘヴィなエレキギターが痛快なスライドを絡ませる好チューンである。
ヘヴィなオルタナティヴ風のギターリフから始まり、即Chapmanの甘いヴォーカルのア・カ・ペラに交代し、更にそこからギターとヴォーカルのユニゾンがロックンロールを展開する#6『See The Glory』もフックのあるロックナンバーであり、適度のハードさとそれを全く嫌味にしないポップさのバランスが絶妙である。かなりシンセサイザーを始めとする打ち込みのノイズやブラスシンセといった雑多なサンプリングが配されているけれど、それが心地の良い乱雑さとなりひいてはロックの楽しさを演出している。
#10『Declaration Of Dependence』は#2と同様アクースティックのスティール感覚が気持ち良いリフが曲の感じを代表する爽快なポップチューンである。こういったナンバーでも単なるアンプグラドにはならずに、電気ギターを始めとして多重コーラスや鍵盤類が合流して結果華やかなナンバーになってしまうのがStevenの特徴というかアダルト・コンテンポラリーの王道路線を踏み外さない所以なのだろうと思う。
Modern Rockというよりもアーバンな無機質さが背後に匂っている#11『God Follower』は、オルタナティヴという現代音楽の影響をどうしても感じてしまう。が、結局それなりのポップなロックナンバーに完結してしまうのがStevenらしいソングライティングと言えるだろう。同じマイナー系のメロディを持った#7『Bring It On』はもっとハードロック・産業ロックのスペイシーさと複雑さを内包したナンバーである。
インターミディエイト的なナンバーに#5『God Is God』のようなハーフバラードのようなメロウ・ポップもトラッキングされているが、型としてはバラードに属することになるか、このアルバムの流れでは。
対照的にスローなナンバーになると、ドラマティックでエモーショナルなナンバーが、これこそアダルト・コンテンポラリーという主張を止まないようなナンバーが目白押しである。
#13『Savior』は映画のクライマックスのBGMをサウンドトラックで聴いているかのような、フルオーケストレーションが必要の度を越して主役を張るナンバーである。アクースティックギターの他はストリングスのみという編成はポピュラーのヴォーカル作を思わせる。
#12『Carry You To Jesus』の哀愁漂うキーボードに導かれた静かなバラードは1980年代のプログレ・ハードロックのバンドがシングル用に作成したバラードを思い出させる。非常に日本人のパワー・バラードファンに歓迎されそうな美しくも透明感あるナンバーだ。
#4『No Greater Love』はアクースティックなギターの音色を大切に保持したシンガー・ソングライター的な側面の強いバラードである。ややハスキーとはいえハイトーンなヴォーカルを得意とするChapmanの持ち味が発揮される淡白だが歌唱法を堪能できる曲だ。
このように珠玉の譚詩曲が連なっているが、最大の山は#8から#9に用意されている。
センシティヴなピアノと控え目なストリングスのみにStevenがヴォーカルを載せる#8『When Love Takes You In』は宗教曲というよりもラヴ・ソングの性質が濃い。透明感溢れる儚げな美しさではアルバムで随一を誇る。50代のヴェテラン・ヴォーカリストの風格さえも見せてくれる曲である。ピアノは矢張りSteven Curtis Chapmanが弾き語りをしているが、似合い過ぎだ。
静謐に、シンプルにという狙いで美麗さに特化した#8よりも、重厚でドラマティックな展開を見せるのが#9『Magnificent Obsession』である。Elton JohnやJoe Cockerを重ねるくらいに落ち着いてメインストリームに徹したエモーション・ソングであり、1980年代にStevenがパフォーミングしていた産業ロックにシンクロするナンバーでもある。これまた初期のElton Johnのアルバムのようにオーケストラが大仰以上のスコアで盛り上げる。どちらかというと#13よりもグランド・フィナーレ向きなナンバーだと思うのだが。
以上、とても40歳近いとは思えない童顔のヴォーカリストの最新作について述べてみた。
相変わらず堅実なアダルト・ロックのレールから外れない人である。それ故、退屈であるとか没進化という批判の声も聞こえて来るが、下手にオルタナティヴに手を出されてスクラッチやアーティフィシャルに走ったカチカチのギターで耳を汚されるよりナンボかマシである。
しかし、最近は非常にコマーシャルなModern Rockに変遷しつつあるが、原点とも言うべきカントリーや南部音楽の要素が消えたのが少々残念である。次回はこれらのアメリカンルーツ素材を使い、「Signs Of Life」のようにアンキャッチーに陥らないような作品を密かに期待している。 (2002.10.8.)
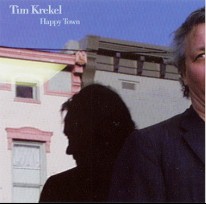 Happy Town / Tim Krekel (2002)
Happy Town / Tim Krekel (2002)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Southern ★★★
You Can Listen From Here
寡作=大物アーティストの証明、という訳の分からない悪しき前例を作り上げたのは一体誰なのだろうと思う。
1980年代半ばくらいから、ビッグ・ネームは3年4年の充電期間は当たり前のような風潮がメジャーシーンに流れ始めた。まだこれなら許せるが、1年程度の短いスパンでドンドンと新作をリリースすることまで否定的な意見さえ出現したのには呆れた。
まあ、特にデヴュー盤がフロック気味に大売れした新人を中心にして、何を勘違いしたのか己を大スターと誤認し、次作まで期間を開け過ぎた連中は、殆どが1990年代初頭から始まった主流音楽の変遷に伴い忘れ去られてしまい、何時の間にか何処へともなく姿を消していった。これは自業自得といえるだろう。同情の余地は無い。ざまあ味噌ラーメンである。
と批判しつつ、何時の間にかメジャーの大物が4年くらいの周期でしか新譜をリリースしないというスタイルに順応し、ああ次はきっと5年後だろうなあ、と新譜を手にした瞬間から妙な悟りを開いている自分自身も殴っておきたい気分になるのだけれども。(笑)
しかし、実績も知名度も充実している御大達とは違い、マイナーやインディペンダントのアーティストが、次をリリースするまでに長期の沈黙に入ると、活動を止めてしまったのではないかとか生計を立てられなくなってアルバムをプレスする資金がないのか、と本気で心配になる。
また、現実問題として以上のような心配が冗談で終わらないことが往々にしてあるため、笑い話にも洒落にもならないのだが。
この度筆を執った対象のTim Krekelというアーティストも、その活動期間の長さから勘案すると相当に寡作なミュージャンの部類に属するだろう。レコード・デヴューは1979年と2002年の現在からは23年前である。しかし、アルバム・デヴューから2002年の最新作「Happy Town」までの20余年にTimが世に出したアルバムは、バンド名義の作品も含めてたった6枚である。
年間で平均すると約4年に1枚のペースでアルバムを作成していることになる。こう考えると、それ程特筆する少数作主義者ではないようにも見える。が、寡作アーティストの代表のようなSteve Winwoodは1977年のソロデヴューから2002年までに7枚のオリジナル作を世に問い、平均間隔で4年以下、Michael McDonaldも1982年から2002年までの20年間で6枚と3年強のペースを保っている。
これを考えるとメジャーのリリースが1枚しかないTim Krekelのレーベル面でのステータスを考慮すれば、やはり少数のアルバムしか発表していないシンガーと枠で括れるだろう。
もっとも、上には上の存在はいるもので、例えば、極端な例になるが、1977年のデヴューから2002年までたった4枚のオリジナルアルバムをリリースしていないBoston(2002年11月に5作目が発売予定ではある。)のアルバムリリース間隔は6年以上。
元RascalsのFelix Cavaliereはソロ活動になると1974年の1stアルバムから2002年までにたった4枚。1980年代には1枚もアルバムを発表していない。寡作で有名なDon Henleyもソロ活動に限れば20年で4枚。この2名は5年以上の平均間隔でしかアルバムを出していないことになる。
しかし、これはあくまでも平均であって、Felixは1970年代には3枚、Donも1980年代には3枚のアルバムというまずまずのペースでアルバム作成をしている。Bostonも最初の2作は1年を開けただけである。だからあくまでも平均のリリース間隔であり、長い沈黙の時代が全体の足を引張っている場合が多い。これも近年の特徴であろう。加齢するに従い、アルバムを出さなく(または出せなくかも)なるというのは。
Timは果たしてどうなのだろうか。以下、アルバムのディスコグラフィーを記してみよう。
#1 「Crazy Me」 / Tim Krekel (1979年)
#2 「Over The Fence」 / Tim Krekel And The Sluggers (1986年)
#3 「Out Of The Corner」 / Tim Krekel (1992年)
#4 「L & N」 / Tim Krekel And The Groovebillys (1998年)
#5 「Underground」 / Tim Krekel And The Groovebillys (1999年)
#6 「Happy Town」 / Tim Krekel (2002年)
以上がTim Krekelがリーダーとして発表した全てのフルレングスアルバムである。発売年を一瞥するだけで判別できるとは思うが、一応触れておこう。1st作品の「Crazy Me」から4作目の「L & N」までの19年間で、彼はたった4枚しかアルバムを創っていない。ほぼ5年平均となる。
それと比較して、4thアルバムの「L & N」以降はそれまでの寡作を埋め立てるかのように順調なリリースを始めているのだ。Tim Krekelは1950年生まれであるから、48歳から突如としてレコーディングがヒートアップしているように見える。
全体的に歳を食うにつれてリリースの間隔が間遠になるヴェテランシンガーが多い中、実に精力旺盛というか絶倫元気オヤヂというか、兎に角中々に底力のあるおやっさんであることは確かなようである。この近年に至っての加速っぷりについては後程考察してみるとしよう。(忘れなければだが。)
少々、過去の作品に対する薀蓄を述べておくと、第1作目の「Crazy Me」は米国ではアナログ盤のみで発売されるに留まり、デジタルメディア化はなされてはいない。このアルバムのみ筆者は聴いたことが無い。欧州ではCD化されたらしいのだが、それも定かではない。現在は非常に入手が困難なアルバムでまだお目にかかったことがない。
「Crazy Me」はCapricorn Recordsというブルースロック系のローカルレーベルからの発売となったが、発売後3ヶ月で、このレーベルが倒産してしまったため、かなりこのアルバムは希少なのである。ちなみに、Freddy Jones Band等が属していた現在シカゴに存在するレーベル、Capricorn Recordsとは全然関係が無いのでお断りしておこう。
そして、デヴュー作から7年後にAnd The Sluggers名義でプレスされた「Over The Fence」がTimの現在まででは最初にして最後のメジャーリリースとなっている。Arista Recordsからリリースされたこのアルバムはルーツロックとして高い評価を得たが全くセールスには結びつかずに終っている。このアルバムも筆者はCDでは所有していないため、是非手に入れたいのだが、全く見当たらない。CDプレスされたことは何処かでアルバムを目撃して覚えているので、何時かちゃんとした形で聴き直したいのだが。
3作目の「Out Of The Corner」は、米国でなく、伊太利亜(イタリア)のレーベルと契約し欧州でリリースされた作品となっている。1992年というグランジ・イヤーを思い返せばTimのような正統派アメリカンロッカーが本国での契約締結に苦戦を強いられていたのは想像に難くない。
これ以降の2枚も既に米国では廃盤であり、入手は難しい。が、独逸や伊太利亜ではまだ欧州盤のストックがあるらしいので、地道に欧州のオンラインショップを探せば見つかるかもしれないが。欲しい人は頑張って見つけよう。(を)
「Over The Fence」を筆者がテープで聴いた時点で30代後半に差し掛かっていたTim Krekelである。当時、色つきサングラスを掛け、長髪にして若造りをしていた(笑)シンガー・ソングライターも2002年の段階では既に52歳である。
1992年、伊太利亜のAppaloosa I.R.D.というレーベルから発売された「Out Of The Corner」以来、バンドとのコンビネーションではなくソロネームでのりリースとなった「Happy Town」だが、基本的な音楽的嗜好はこれまでTimが構築してきた世界から全く逸脱をするものではない。
1990年代終盤に連続でアルバムを吹き込んだThe Groovebillysのメンバーは誰一人として参加していないのが特徴らしい特徴だ。かといってバンドサウンドから遠ざかったということでもない。Tim Krekelが常に追求してきた嫌味になるくらいの普通で基本的なPop/RockとRoots Rockが堅実に刻まれている。
ソロ名義に変更したためか、ややシンガー・ソングライター風の気分を落ち着けるような安心感の流れが強くなっているように感じる。少々スローダウンして年齢相応に落ち着いた雰囲気を身につけた曲が多いようには思う。これもバンド形式からTim Krekelをより中心に据えたためかもしれない。とはいえ、彼のスタイルが激変したということは全くない。元からある音楽的アプローチは呆れるくらい没進化である。
このようにTim Krekelの音楽の変化について言及することはかなり困難である。悪し様に分析するなら、Tim Krekelの音楽がデヴュー当時から殆どその根幹を変えていない没進化系列のものだということである。
が、筆者としてはそれこそ最も難しいことであると考えている。普通のPop/Rockを20年を超えて演奏することは、軽率な時流やファッションに便乗することより遥かにしんどい創作姿勢である。数の限定されたマテリアルからマンネリズムに陥らずに良いものを生み出し、リスナーに支持されていくことは並大抵のシンガーでは貫けない道である。
Tim Krekelが肯定的な意味合いにおいて、自分らしさをしっかりと表現しているので、アルバムとして発表した音源は多くは無いが、全てが良質なロックンロールと総括できるのだと思っている。
Tim Krekelは1950年生まれ。出身はケンタッキー州。
「60年代の『A.M.ラジオロック』に最も影響を受けたね。Byrdsの『霧の8マイル』を聴いたかと思えば、Some And Daveの『僕のベイビーに何か』を聴いていたよ。」
と、60年代のヒット曲を聴きつつ育ったTimだが、自分から楽器を弾くようになったのは50年代の頃であり最初はドラムのレッスンを受けていた。次いでギターに興味を持ったのが10歳を過ぎたあたりらしい。
「ギタリストになれば、ステージの前に立って観客の注目を集めることができる。Rick Nelsonのように。」
という動機でドラムからギターへと楽器を持ちかえたTim少年は、12歳からローカルのフェスティヴァル等で聴衆の前に立ち、演奏を始めている。高校に進学する頃にはオリジナルの曲を書き始め、シンガー・ソングライターの道に歩みを記すことになる。高校を卒業後、Octavesというバンドを結成し、ロードで技術を磨きつつDustyというグループを最終的に創設。DustyはNRBQのケンタッキーツアーに同行する機会を得る。この頃からTimはアマチュア・ローカルバンドとしてではなく、プロフェッショナルとして音楽に携わりたいと考えるようになる。
力量を試すために1970年にはニューヨークまで進出。半年ほど、大都会で活動するが、あまり都会が水に合わなかったようで結局ケンタッキーを基盤に活動することに落ち着く。
「Dustyは日曜の夜にクラブのレギュラー演奏を頼まれるくらいのバンドだった。私のオリジナル曲に3B−Beatles、The Band、そしてByrdsのカヴァーが中心だったね。ある晩、Sam Bushが私たちのライヴを見に来ていて、飛び入り参加でヴァイオリンを弾いてジャムをやったのが思い出だ。」
と次第にミュージシャンの間で評判が高まったDustyは、既知を得てナッシュヴィルでもライヴを行うようになる。そこでTimに注目したポップロック/カントリーシンガーのBilly Swanが彼をバンドのギタリストとして雇い入れる。この時点でDustyは自然消滅し、TimはBilly Swanデヴューアルバムの「I Can’t Help」にギタリストとして参加。その後の全米・全欧ツアーにも同行する。
Billy Swanとのツアー終了後、ナッシュヴィルでソロ活動を開始したTimに目をつけたのがカントリー・ロッカーの大御所Jimmy Buffettのマネージャーだった。TimはJimmyのバンドにギタリストとして雇われ、1978年のJimmyのアルバム「Son Of A Son Of A Sailor」でプレイ。映画「FM」にトラックインされた『Saturday Night Live And In The Movie』でもスライドギターで参加。彼のギターがこの名盤でも聴くことが可能だ。
そして、翌年の1979年に初のソロアルバム「Crazy Me」を後にSteve Earle等のプロデューサーを担当するTony Brownの手により録音。
その後はソングライターやギタリストとして活動することになり、次のThe Sluggersと創り上げる「Over The Fence」まで7年も空けてしまう。が、このアルバムがメジャーでプレスできたのはこの間、Timがソングライターとして様々なアーティストに曲を提供して、それらの歌がヒットしたからだろう。
例えば、1977年に『Don’t It Make My Brown Eyes Blue』が全米第2位を記録するヒットとなった女性カントリーポップシンガーのCrystal Gayleが1984年にTop40カントリーでトップヒットとなった『Turning Away』を提供したり、Jason And The Scorchersが1983年にフルレングスに先駆け発売した「Forever」というミニアルバムに『I Can’t Help Myself』を提供している。
この後6年を置いて、1992年に「Out Of The Corner」をリリースしてから、1998年の「L & N」に至るまでまたも6年の間隔を空けるが、1996年に全米No.1ヒットになった『You Can Feel Bad』をMatraca Bergと共作。
1997年には、これまた女性カントリーポップシンガーのMartina McBrideがトップ10ヒットさせたナンバー『Cry on The Shoulder Of The Road』を提供。
Timは女性カントリータイプのシンガーと相性が良いのか、Kim Richeyの殆どのアルバムで共作者として曲を一緒に書いている。
他にも、Rick Nelsonが密かに取り上げていた彼の1stアルバムに入っていた『Send Me Somebody(To Love)』が死後に発表されたり、BJ Thomas、Aaron Tippin、Delbert McClinton、Sam Bush、Dr.Feelgood、Pat Haneyが彼のナンバーをカヴァーしたり取り上げている。
あのChris Knightの「Chris Knight」でもTimの名前がソングライターとしてクレジットされている。
他にも数多くのシンガーに曲を提供しつつ、1998年からは前述のように自らのアルバム作成に集中し始めた様子で、順調にルーツロックアルバムをリリースしている。
今回のアルバムは今までのソングライターとしての貢献に恩返しをされるような形で、著名なシンガーが共同で曲を書いている。これまでに目立った共作者はTerry Andersonが「L & N」でペンを執っていたくらいだったのだが、「Happy Town」では彼の単独作は約半分の5曲となっているに過ぎない。
残りは前述したように、これまでにKrekelが何曲も提供している女性カントリーシンガーのKim Richeyが#2、#10の2曲を共同制作。以前に当レヴューサイトでも取り上げたTom Hambridgeが#5−彼はバックヴォーカルとしても参加している。更にメジャーヒット曲を何曲かTimとのコンビで生み出している女性カントリーシンガーであるMatraca Bergが#3でも良い曲を書いている。
そして、昨年になかなかのCountry Rockアルバム「Certified Miracle」をリリースして堅実に活動するテキサス在住のルーツロッカー、Duane Jarvisも#8で手を貸している。
今回のアルバムはそこそこの数のゲスト陣が参加してるが、著名なのは#2と#5でバックヴォーカルを歌っているTom Hambridgeとカントリーシーンではかなりの数のアルバムに参加しているRichard Youngがエレキギターを#4で弾いているくらいだろうか。他のミュージシャンはあまり名前を聞かない地元のセッションミュージシャンと推測しているが。
どのナンバーもケンタッキー出身、テキサスで活動という履歴を裏付けるようなグラスルーツとサザンルーツを双璧にしてポップロックで仕上げた味わいのあるルーツサウンドが一杯である。And The Groovebilly時代の2枚のアルバムと比較するとロックンロールの炸裂するナンバーがやや減り、思慮深いTim Krekelの視線を感じることができるようなじっくりとしたナンバーが増えているようだ。が、反面あからさまなCountry風味は減少し、Roots Rock/Country Rockと呼ぶべき中間色の強いナンバーが大半を占めるようになっている。
元来Country Rock畑のシンガーに曲を提供することが多いライターであったけれど、サウンド的にはCountryというよりもRoots Rockという普遍的なポップセンスとロックンロールの素直さが特質の人であったので、これは大した変化ではないかもしれないが。
まずは著名シンガー達と共作したナンバーについて軽くインプレッションを述べてみよう。女性カントリー/ポップのシンガーとして日本でもそれなりの知名度を誇るKim Richeyとの曲が#2『Who You Think You Are』と#10『Come Around』である。#10はケヴィン・コスナー主演の映画「For Love Of The Game」で3年前にKimが披露しているのでアフター・カヴァーである。
#2はグラスルーツの影響が濃い反面、アーバン・カウボーイ的リズムが現代的なCountry Rockタッチのナンバーである。Tim自身が弾くオルガンが中々の聴き所である。
#10はテキサスのサザンルーツが表面に出た、ダークでダーティなトラッドを匂わせるナンバーである。この2曲がアルバムでは親しみ易さでは一番取っ付き難いかもしれない。Kim Richeyとの曲が最もポップ加減においては低空飛行しているというのは、Kimらしいブルージーなカントリーロックの色合いが出ているのだろうか。
Matraca Bergとの何度目かの共同作業の成果、#3『It’s A New Day』はカントリーロック界のヒットメイカー同士が手を組んだにしてはCountryではなく完全なルーツロックに仕上がっている。こちらはMatraceの歌うディレクションではなくTim Krekelに似合う作風を狙ったと思う。かなりのヘヴィなギターが微妙にポップなラインを掴んでビートを叩き付ける。かなり南部のザクっとした粗さを感じさせるナンバーである。
Tom Hambridgeとペンを重ねた#5『Best Thing I Never Had』は実にほんのりとした包容力のある暖かいルーツポップロックとなっている。最近は完全にハードなルーツロックに染まりつつあるTomであるが、Timのポップセンスが巧みに活用されて、ハーフドライ・ハーフウエットな絶妙なナンバーとなっている。
Duane Jarvisとのタイトル曲#8『Happy Town』はアルバムで最もハードドライヴィンなロックナンバーだろう。プリミティヴと言い換えても良いだろう。完璧にスワンピーでダルでラフなサザンロックであり、テキサスを中心に活動するルーツロッカーが手を組んで書き上げたナンバー、さもありなん、というしかない。ややクラシカルなFacesあたりを連想させるギターロックナンバーであり、ロックンロールの質量感が充満している。
そしてC.Woodという人−このCには相当な該当者があるだろうが、筆者が思い当たるライターとは作風が合致しないため特定が不可能だ−と書いた#1『Sunshine Baby』がアルバムで最初、紹介は最後の共同作品となる。
アルバムでは最も軽快でポップで即効性の強い真っ正直なロックチューンであろう。アメリカ中西部の開放感溢れる疾走感と中庸的なメロディが実に印象的なナンバーで、シングルを切るとしたら絶対にこの曲からなのは間違いないと断言できる勝負曲でもある。
残り5曲がTim Krekelの単独曲となっている。これまたどれも良質なルーツナンバーである。
Timのハーモニカとレイドバックした柔らかさが何処までも優しい#4『Loss To Explain』ではTimの決して美声とは言えない朴訥なヴォーカルが小細工無しで胸に語りかけてくるようだ。甘さでいえば#7『Come Back Baby』の高い声域をTimが搾り出している静かな雰囲気の方が上であるとは思うが、やはりアクースティックな訥々とした語り掛けの方がどうしても強く響いてくる。しかし、#7の甘酸っぱいレイドバック・ポップナンバーもしんみりとした地味な味わいがあり、甲乙付け難い。
#6『Sugar From My Baby』はSteve EarleやBruce Springsteenの若い日を思い出させるような馬力を感じるミディアムなロックナンバー。これもまたポップであるが、かなりルーツィである。
#9『Fell Down In Memphis』では更にクラシカルなロックンロールが、1950年代のR&Bロックのような調子で表現されている。Bo DiddleyやChuck Berryを彷彿とさせるベーシックで暴れん坊なロックンロールであるけれども安定感がちゃんと存在して軽薄に転がらないところは流石にヴェテランだ。
オルガンとシャープなドラミング、そして情感の溢れたギターのアンサンブルがじっくりと曲の進行を支えるロッカバラード#11『Just Let Me Be』はリズム自体には余裕綽々なところが振り撒かれているが、それでもロックとしての力を失わずにキャッチーに纏められている好チューン。最後を飾るには抜群のルーツナンバーである。
しかし、近年のスパートの掛け方には驚くばかりである。またぞろ息切れして5年や6年も沈黙せずに、アルバムを届けてくれればこれ幸いなのだが。頑張れ元気な爆走50代オヤヂ。(笑) (2002.10.11.)
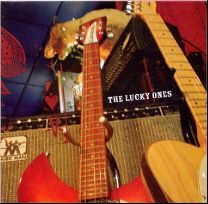 The Lucky Ones / The Lucky Ones (2002)
The Lucky Ones / The Lucky Ones (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Americana ★★★
You Can Listen From Here
ピアノという楽器が好きだ。
ロックンロール・インストゥルメンタルとしてはどうしても必要不可欠な楽器ではないし、ロックにピアノは必要ないと言い切る人間もいる。3ピースというロック編成には普通ピアノは含まれない。
ロックンロールは何処でもパフォーマンスが可能なことが特徴という即応性を第一義にするプレイヤーには携帯性の皆無なピアノという大型道具は邪魔なものに他ならないのかもしれない。
だがしかし、弦楽器・打楽器双方の特質を備えたこのデバイスは楽器の中では最も完成された空間をその内に備えていると考えている。演奏手段としての起承転結を有した小宇宙が筐体の中に詰まっているとも言える。
まあ、理屈はこの際どうでも良い。ピアノ、鍵盤類に関しての偏愛は今に始まったことではないのだから。
まず鍵盤を、特にアクースティックピアノをフルタイムに活用するバンドやシンガーに対する筆者の評価はとかく甘くなる傾向にある。それはポップロックという道に転んだ原因となるアーティストが、Elton John、Steve Winwood、Billy Joelといったキーボーディストであったことが最も大きい。
「ロック少年」なるものがギタリストに憧れ、ギターをキャリングケースに入れて運ぶことで悦に入っているのを横目で眺めながら、手ぶらで歩くことに一抹の寂しさを感じたことはあったが、ギターに必要以上に興味を持つことはそれから20年以上経過しても、無いしこれからも無いだろう。
てなオヤヂ回顧録はこの辺で打ち止め。
今回は2002年にレコードデヴューしたシカゴ出身のバンド、The Lucky Onesについて語ろう。
推測するまでも無いと思うけれども、ピアノトークを少々冒頭にしたのは
ピアノ専科のプレイヤーがThe Lucky Onesのメンバーに入っている!!
からである。(を)それはつまり、このThe Lucky Onesというグループが筆者の嗜好の重要な一角を満たしていることに他ならないのである。しかも鍵盤担当のBrian Andersonは
オルガンやクラヴィネットやシンセサイザーではなく、ほぼ完璧なアクースティックピアノの演奏専門である。
オルガンはゲストプレイヤーが担当している。要するに、このバンドはピアノの鍵盤から打ち出される音階を非常に大切なアンサンブルの構成要素と捉えていると勝手に決め付けているのだ。(をい)と、その判断はあながち間違いでもないように思える。全てのトラックでピアノが補助的な楽器ではなく、ギターと同様にメイン・ラインを彩るインストゥルメントとして活用されているからだ。
また、単純にピアノがたっぷりとフューチャーされているだけで、このバンドを評価している訳でもない。(まあ、そういった傾向もなきにしもあらずだけれども。)
ピアノを中心として組み上げられたルーツロックのアルバムは、David Zoloを始めとしてそうそう多くは無い。まあ皆無という話ほど極端には針が触れないけれども、やはりジャズやR&Bをたっぷりと含んだジャムやクロスオーヴァー系のルーツロック作品に比べるとどうしてもその数は希少となる。
更に、ブルージーやジャジーやビッグバンドという黒人根源音楽系譜のロックナンバーを選択する際、そしてクラッシックなBoogie調やHonky Tonk調のロックンロールにピアノをダイナミックに叩くことで曲をエンファシスするバンドはかなり多いが、普通のPop/Rockに自然にピアノを入れるバンドは非常に少ないと思う。
今回紹介するシカゴ出身のバンド、The Lucky Onesはシカゴ伝統と言って良い中西部の中庸的なメロディにピアノの音色とルーツのフィーリングを巧みに取り入れたバンドである。勿論、ピアノだけでなくギターやリズムセクションも均等な活躍をしているのは言うまでも無い。
これまで何処かに転がっていそうで、その実意外にこういったポップで、しかもAdult Contemporaryに走り過ぎないロックサウンドはあまり創作されていないように思える。事実、筆者も当初はピアノが大幅に入っているというだけで喜んで聴いていたクチであったのだが、次第にThe Lucky Oneの持つ独特な魅力に感性が侵食されて行き、何時しか離せないアルバムとなりつつある。
例えがかなり嗜好の好悪が分かれる物体で恐縮だが、要するに日本人にとっての納豆みたいなものだろうか。普段それ程上等な食物とも見えず、食わず嫌いでいることも多いけれど、一度填まったらそれ無しには過ごせない、という性質を持った。が、The Lucky Onesと納豆の大きな違いは食わず嫌いになるようなクセの強さが肯定的な意味でThe Lucky Onesには存在しないということ。ここを勘案すれば、寧ろ豆腐の位置付けがThe Lucky Onesには似つかわしいのではなかろうか。淡白でありそうなイメージが強いが、本質は実に味が深く、良いものを求めるほどにその世界に入り浸ってしまう魅力を有しているという点で。
と、食物に例えるとキリがないので、この話は打ち切り。The Lucky Onesに話題を修正する。
まずはThe Lucky Onesの音楽性がいかようにして筆者を魅了したか、音楽性を考えつつ述べてみるとしよう。
第一に、メロディである。実にポップで親しみ易い。ルーツロックのバンド、特に南部ルーツにありがちな黒っぽさやファンクさ、そして何よりもダーティな鋭さがない。要するにLynard Skynardという強塩基や強酸性の楽曲をプレイするロックバンドのアクの強さとは無縁なのである。
Southern Rockの楔を打ち込みながら荒野を前進する作業機械の如き重量感はそれ程感じられない。寧ろ、適度なハート・ウォーミングな円熟を帯びた雰囲気に日向の匂いのする大らかな南部テイストを主に漂わせていると思うのだ。
それよりも中西部の根源音楽たるブルーグラスがこのバンドの基盤となっていると感じる。とはいえ、CountryやCountry Rockといったどうにも日本人の感性には合致し難い、スカスカな軽薄さは非常に微量である。というか、殆ど存在しない。
言い方に語弊があるかもしれないが、The Lucky OneのサウンドはRoots Rockであるのは絶対的な真理であるけれども、同時にPower Folk Pop的な側面も有しているのだ。Power Popといっても売れ筋のエモやパンクにベッタリと染まった尻軽な音楽ではない。もっとシンガー・ソングライター風の繊細な感覚を有したポップというべきだろう。
また、Power Popの大勢を占めるメジャーコードでお定まりの16ビートを垂れ流すというような、心の襞に残ることがないパス・バイの聞き流し専用音楽でもない。
アメリカンロックの雄大さ−大地に漂う朝霧のような清涼感と落ち着き、をしっかりと基本にして楽曲を創り、歌っているので安定感は抜群である。物凄くダスティで泥臭いという図太さを大槌で地面に打ち込むような強烈なアーシーさでなく、程好く耕して綺麗に整地された畑の畝から匂い立ってくる土の香りを鼻腔に感じるかの如き、上品なダウン・トゥ・アースの包容力を最も大切にしているサウンドである。
いってみれば、シカゴ周辺諸州のインディバンドに良く見られる、大平原の広大さをサラリと表現する閑な大地の息吹を伝えてくれるグループなのである。
しかし、こういったバンドの多くは、
「悪くないけど、どうにも今ひとつの押しに欠ける為、印象をくっきり残すことが難しそうな音だ。」
という地味であるが故の無個性・どっちつかずで大勢の中に埋没してしまう、という危険性と常に隣り合わせだし、事実即座に忘れ去ってしまったり、良い所はあるにしてもこれでは傾聴するまでの段階には達していない、という評価しかできずにいる存在になり易い。
正直、この「The Lucky Ones」も最初の数回を聴いただけでは、「ああ、ピアノが良いなあ。」という特徴しか突出していないアルバムであったのだ。が、何故か惹かれるものがありポツリポツリと繰り返してCDプレイヤーに乗せる度に、加速度的に好きになってったアルバムである。ジワジワと心の領域を侵食していく地味なルーツバンドは年間を通じてかなり出あうのだが、聴くにつれてこうもさっさと心を奪っていった作品は稀である。大抵は「やられる」アルバムというものは最初のリスニングで心を捕らえて離さないモノが殆どなので。
言わば、クラッチがローギアとトップギアしかないような加速振りである。普通は地味であるがジックリと浸透してくる作品は、シフトアップを確実に行うように填まる様式をなぞるのだが。
これは、やはり地味な音楽構成をしているとはいえ、The Lucky Onesの演奏する曲全てがマンモス級にキャッチーであるからだろう。殊更、キラキラしたスピーティなロックンロールチューンや、パワーバラードに代表される叙情的なスローナンバーは皆無なのだから。
ピアノが上手に取り入れられていたから、幾度も聴こうとする意欲をそそられたということも、無論あるけれど。
どのナンバーも中位のビートを中心に、やや速く、そしてやや遅くという中間テンポの見本のようなナンバーが殆どであるから、即効性を求めるにはコードの連なりとスコアの組み合わせる他にはありえないからだ。
このミドルレンジの速さを基準値のように配したアルバムに、米国中西部のこれも同じく中間的な土臭さとトラッド・ミュージックの感覚が合わさって、実に肌触りの優しいPop/Rockの連なりを創造している。
中庸さ故に、他人に薦めることに万言を費やす必要があったり、言葉では説明がつかずに四苦八苦する良質なバンドが多々あるけれども、The Lucky Onesに関してはそのエクストリームに親しみ易いメロディをセールス・ポイントにすれば良いのでかなり楽である。だけれども、メジャー・チャートで流行している脳味噌が空洞化しつつあるシナプスから排出された極薄の使い捨てコマーシャルさとは一味も二味も異なったフックを持つソングライティングをしているからこそ、ガッチリと印象に残り、駄文を書くエナジーを与えれくれる存在になっていることを忘れずに加えておく。
もう1つのThe Lucky Onesの特色はリード・ヴォーカリストが2名存在することだ。以前レヴューしたPaging Raymondと同様のスタイルである。Rob Brookman、そしてDave Kayという2人のソングライターがそれぞれ単独で曲を書き、自分が完成させた曲でリードを歌っている。
得てして、こういうバンドはそれぞれのソングライターの特徴が反映して、多彩になったり反対に統一が取れなくなったりとユニークな結果を招くことがひとかたならないのだが、しかし、The Lucky Onesの場合は不思議と2枚のヴォーカリストの声質がかなり似通っているだけでなく、お互いに書くナンバーも良質なポップロックからスローなルーツソングまで幅広く、という様子である。
つまりタイプの違うソングライターがチームを組んだのではなく、方向性の近いミュージシャンのデュオがお互いに良い曲を書き綴った結果がThe Lucky Onesというバンドに集束したという体と捉えたほうが適切だ。
ヴォーカルにしても、Rob、Daveの両名が丁寧に使い込まれた作業衣のような擦り切れたハスキーさを有する、素朴で暖かみのある声の持ち主である。ほんのりと身体に纏いつく静かな夜の帳という吸着力が存在するところも共通点である。
声の本質は非常に似ているので気にせず聴いていると、ひょっとすると見分けがつかないかもしれない。が、Rob Brookmanの方が低いバスヴォーカルとしての声質を帯び、Dave Kayのヴォーカルは優しさとハスキー・ヴォイスの擦り切れ加減がやや強い。
兄弟でもこのようにシンクロしたソングライティングとヴォーカルを持っていないかもしれないというくらいに、似たところが多いフロントマンである。この2人を中心としたコーラスは1+1>2の付加価値をもたらす現象の典型というべきマイルドさとまろみを発揮する。これまたこのグループのプライオリティだ。
後、今更付け加えるまでも無いが、アクースティックピアノを中心としたエレクトリックギターとアクースティックギターの綴れ織りの素晴らしさを語らずしてThe Lucky Onesは成り立たないだろう。
さて、Rob Brookman作で彼がリードを執るのは#1、#3、#5、#7、#8、#11の6曲。
対して、Dave Kayは#2、#4、#6、#9、#10、#12と殆ど交互の法則性を帯びて並んでいる。
Robはその声のハスキーさと太さを生かしてソウルフルに、Daveはハスキーさと声の高さを活用してジェントリーにそれぞれの歌を受け持っている。
#1『The Marquee』からThe Lucky Onesの真髄というべきポップで、しっとりとして、且つドライなミディアム・ロックチューンが姿を表わす。Brian AndersonのファジーなピアノにDaveのリードギターがエッジィな色を付ける。
#2『Crawl Into The Night』ではナチュラルなエレキギターに、今度はクリアなピアノが彩りを施し、Daveの包み込むようなヴォイスにコーラスが合流し、極上のミディアム・ロックに纏めている。所々でくど過ぎない泥臭さを掻き鳴らすエレキギターが曲を単調にしない効果を発揮している。
この2曲で「The Lucky Ones」のダウン・トゥ・アースを求めつつも、アメリカンルーツに特化しないポップロックのセンスを知るには十分であるが、#3『The Long Goodbye』のCS&N(And Young)やThe Flying Burrito Brothersのフォーキィなトラッド感を思わせるナンバーもあり、フェンダーローズ・ピアノとオルガンが活躍する珍しくピアノレスの#4『One Woman’s Hand』のサザン・スワンプ風のリラックさが漂うスローナンバーあり、と一本纏まった線を辿りつつ、実はヴァライエティに富んだ音楽性を見せてくれる。
Elton Johnのピアノソロを一瞬重ねてしまった軽いサイケディリックを振りまきつつ、ライトにドライヴするロックチューンの#5『Emily』ではRobの低音域の伸びるヴォーカルがとてもマッチしている。R&Bのバックボーンや英国ロックからの影響をもこの曲には感じる。
続く#6『My World』からもマイナーコードを要所要所で取り入れ、少々ヒネリのあるBeatle Pop的なミドル・バラードを聴かせてくれる。このナンバーではかなりピアノを始めとする楽器が自在にジャム・セッションを行っていて、演奏的には綺麗に纏めている様で、意外にルーズなところもあると実感させてくれる。
フォーキーで美しいバラードの#7『Lonely Hearts’Waltz』ではアクースティックな弦楽器と一緒にピアノが良い仕事をする分、単なるアクースティックギターでしかアレンジをすることができない大勢のバンドよりも更に情感が高まる。こういったシンプルな曲で切々とピアノの鍵盤が叩かれる展開には実に弱い。更にベーシストのJon Williamsrが弾くアコーディオンもトラッドなイナタ臭さをさり気なく煽ってくれる。
このアルバムの中でもフックとロックンロールの力を最も感じられるナンバーの1つが、#8『Ordinary Girl』であり、前曲と並べると大人しいポップチューンであるが、これまた軽快にビートが刻まれる#9『Stella Girl』のウルトラ級のフッキーなトラックも大歓迎のチューンである。#8ではRobがかなりシャウトしてロックビートを盛り上げ、他の楽器も全て元気に追従している。#9ではDaveの甘いセンスが炸裂し、Eaglesを聴いているような錯覚にさえ陥る。
もっと疾走感が際立った痛快なロックチューンもレパートリーに入れることは可能であることを見せ付けてくれる曲が並んでいる、この後半の2連コンボはかなり好きなパートである。
#10『Blue Down In Bucktown』はWilcoの「A.M.」やJayhawksの「Tomorrow The Green Grass」のアーシーでベーシックなアメリカンロックを演じていた頃を思わせるし、PocoやThe Beach Boysの青空コーラスを継承しているとしか思えない爽やかな美しさを持ったルーツバラードである。
#11『Amanda Lee』も筆者が#1や#8に負けず劣らず大好きな即効性の高いアメリカン・ルーツポップロックだ。背後で目立たなく弾かれるピアノといい、浮遊感のあるギターといい、Tom Pettyのヒットナンバーを彷彿とさせるメジャー感覚に溢れている。擦れ切った喉から絞り出させるRobのヴォーカルに共感を覚えずにはいられない。
アルバムの中では最もBluegrass色が豊かなカントリー・ワルツ調子のお気楽ナンバーが最後の#12『‘Til You’re My Baby』である。これまで極力カントリー・カントリーしたナンバーや古典的なA.M.Radio Rockを直接的には表現してこなかったThe Lucky Onesだが、最後の最後で一発楽しくパーティでもやったろかい、的な吹っ切れたノリを感じる。これまた巧みにスカスカにならないポップナンバーとして仕上げているのは凄いとしか言えない。
このThe Lucky Onesというバンドは資料が少ない。シカゴ周辺で音楽活動をしていた2人のミュージシャンが1995年からデュオとして活動を始める。この2名のシンガー・ソングライターである、Dave KayとRob Brookmanが中核となり数年後に、シカゴ在住のミュージシャンを集めて、The Lucky Onesを結成。
バンドの写真等も全く入手できないし、インナーには歌詞が丁寧に織り込まれているのは好感が持てるが、バンドメンバーの肖像は今のところ不明。まあ、顔で良い音楽は創れないので大した問題ではないが。
2001年に誕生した新しいインディ・レーベルであるLost In America Musicと契約。2002年の夏にデヴューアルバムである「The Lucky Ones」を発表している。
メンバーは以下のクゥインテット編成。
Rob Brookman (Vocal,Guitar) , Dave Kay (Vocal,Lead Guitar) , Brian Anderson (Piano) ,
Mike Reed (Drums) , Jon Williams (Bass,Accordion,Vocal)
これにプロデューサーであるDavid Singerがオルガンとヴォーカルをサポートして今作は完成している。
彼らの所属先であるLost In Americaレーベルにはアクースティックポップやルーツポップの優良アーティストが少数とはいえ勢揃いしている。上の試聴リンクからホームページへ飛べるし、The Lucky Onesだけでなく他のアーティストも試聴できるので、是非訪問して欲しい。
しかし、どうにもこの素晴らしいピアノ・ルーツロックバンドのデヴューアルバムの内容を考えると、世間の注目は不当に低空飛行を強いられている様子である。レヴューの数も少ない。これはWeb上での露出情報が少ないためそう感じるのかもしれないが。
Amazon.comでもフルで2曲がダウンロード可能だし、値段もお手頃であるので、是非とも購入して数回聴いて欲しい。そうすれば、確実にこのバンドの良さが分かる筈だ。
意外に有りそうで無い音楽。
独創的ではないが、追従できるバンドはそう多くない才能を随所に打ち込んでいるデヴュー盤だ。Five For Fightingからオルタナティヴさを取っ払って、ルーツのテイストを強める、Moyeからも同じくオルタナティヴを脱色しロックを強化すれば、The Lucky Onesに近いサウンドになるだろうか。
ということは、オルタナティヴさえ消え去れば、このグループはメジャーが争って契約を得ようとする存在クラスのバンドになるに値するのだ。・・・・・・・・・まあ、現状では夢物語だが。
しかし、このアルバムが素晴らしいのは幻想ではない。中庸的なPop/Rock好き、ピアノが入ったロックが好きならなお1段階お薦め度を上げる。まあ、聴いてみよう。万人が聴ける間口の広さがあるから。 (2002.10.13.)
 Resurrection / Mark Hamm Band (2002)
Resurrection / Mark Hamm Band (2002)
Roots ★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★★
Arena ★★★
Sample1 Sample2
『Resurrection』−リザレクション、という単語はRPGなんぞをやっていると結構耳にする単語ではないだろうか。まあTVゲームやファンタジー等に興味が無い人には無縁の単語ではある。
といいつつ、実はこれも邪道というか、神を信じる人にとっては冒涜ともいうべき使い方かもしれない。世界的にブラックホールも真っ青な無宗教国家日本ではあまり関係ないだろうけど。
『Resurrection』はジーザス・クライストの死後の復活を意味する宗教タームである。またハルマゲドン=最後の審判の日の後に人類が復活・復興するという意味合いでも聖書に記載されている。
ということで、タイトルから容易に予想が付くとは思うが念のため。蛇足だが、今節では5本中2本が宗教系の音楽になるというかなり異例の事態になってしまった。音楽の良さだけを考えれば、全くもって妥当なのだが。
まずはCDのインナーに書かれたメッセージを必要な部分だけ要約しておこう。これを一読すれば、Mark Hamm Bandの取り組んでいる姿勢が分かるだろう。
というより、このMark Hamm Bandは宗教バンドに多い、商売っ気があまり感じられないバンドなのだ。この白基調でデザインされたジャケットといい、プレス状態の宜しくないプレスCDだかCD−Rだか判断がつけ難いような粗悪なCDといい。また当然のことながらオフィシャルHPも所有していないので、頼れるのはCCM系のサイトにある断片的な記事とインナーのセルフ・ライナーノーツしかないのであるが。
「CDの作成について回想: CDを作る事はとても大変な作業だけども、同じくらい楽しさがある。私達の主な目的は、私達の演奏をライヴのように、そしてありのまま実直に表現することだった。
ドラム、ベース、ギター、そしてリード・ヴォーカルは同時に一発録音した。私たちはライヴに近い音を出すことを基本として強調するのは主の御心に適っていると考えているし、そうやってCDを創り上げることがより主に近づけることなのだ。私達は完璧なレコードを作成しようと目を点にしたりしなかった。ただ、現実のサウンドにしたかっただけで、それこそがRockなんだよ。だからRockとしては多分完璧なアルバムになっているのさ!さあ、聴いてみてくれ!
何故タイトルが『Resurrection=復活』かというとね、それは以下の通り・・・・・。友達や仲間のミュージシャンが私のことを絶望的なドラッグ中毒とみなしてきたからさ・・・・・そしてそれは事実だったんだ・・・・・。私はドラックにやられてボロボロだった。その時ジーザス・クライストを全く感じていなかった。だから希望なんて何処にも無かった。
でも、私は復活した。このアルバムは私の希望と栄光あるクライストの復活によって、私が蘇生したことを祝福したものなのだ。
・・・・神を信じることにより、どんなことでも可能になるんだ。これこそ絶望に満ちた世界の希望なんだ。」
と、要するにドラック・ジャンキーから信心を再燃焼させることで立ち直ったMark Hammが、その感謝をガソリンにして作成したのがこのアルバムであるようだ。まあ、神の件は適当に流しておいたが。
繰り返しになるけれども、これで宗教バンドでないのなら、それこそ大したものだろう。このロックバンド、Mark Hamm Bandはクリスチャン・ロック系のグループである。広義にはContemporary Christian Music(CCM)と考えることが出来る、かもしれない。かもしれないというのは、広義の意味という点に於いて抵触するところがあると思っているからである。
基本的にCCMとは日米を問わずAdult Contemporaryの枝分かれ的な音楽とみなされることが多く、Pop/Rockで信仰・信心を表現しようとする教会音楽の現代版と荒く解釈しても問題ないだろう。
ここで引っ掛かって来るのが、Mark Hamm Bandの音楽性なのである。試聴できるスペースがないため、何時もの如く30秒サンプルをアップロードしておいたので、まずは読み進む前にクリックして聴いて欲しい。同じ鯖のフォルダ内に置いたサンプルなので接続環境が低くてもそれなりに聴けると考えている。これを聴いて、拙文を読み通してくれた方が、Mark Hamm Bandをどのようなジャンルとして認識するのか興味がある。
今回試聴用に選んだのは#2『Sweet Assurance』、#4『My Everything』という、比較的ポップで取り付き易いナンバーである。実際にはこのようにポップなナンバーだけではないのだが、総じてメロディアスなナンバーの割合は多い方ではあると思う。ハードなサウンドにしてはという条件は付帯するけれども。
メロディの好みや優劣はひとまず置いておき、ギターを中心としたMark Hamm Band(以下、MHB)のサウンドに耳を傾けて欲しい。
1980年代のプログレッシヴ産業ロックを心の何処かに感じさせる音と思わないだろうか。完全に産業ロックとしてレッテルを貼り付けるには、音のゴージャスさというかカラフルさに欠けているとは思うし、プログレッシヴ・ハードロックと切り分けるにはシンプルであり過ぎ、またサウンドの厚みも不足気味だ。
このバンドをハードロックと呼ぶべきか、それともロックと捉えるべきか、と筆者もかなり悩んだ。熟慮、とまで脳味噌のニューロンを使用はしなかったが、やはりハードロックではなく一種のアメリカン・ルーツロックの変化形であると結論を下すに至っている。無論、ハードなサウンドであることは明白だ。ノイジーなハードロック・ギターの手法ゴリゴリというまでには到達していないけれども、通常のルーツロック愛好家がギターから引き出すアーシーな音とはかなり異なっている。
とはいえ、オーヴァードライヴなハードさで突き進むというHR/HMの音とはやはり少々性質を異にしている。それなりにハードロックっぽいサウンドであるのだが、どのような捉え方でも中間的な音出しである。
これでメジャーな要素をもっと加えると、1980年代のBryan AdamsやREO Speedwagon、そしてSurvivorといったインダストリアル・ロックの音楽に近くなるかもしれないが、録音状態の悪さも手を貸しているにせよ、このような嘗てのトップヒットバンドのサウンドと比較すると随分シンプルで手の加えられていない素手で土を掘り返すような感触が存在するサウンドである。
メジャー間隔の不足なため、Southern Arena Rockという単語に代表される南部出身のハードなポップサウンドを泥臭く追い求めている南部系ハードロックの枠からも外れていそうだし。
よって、少々ルーツロックが入ったハードな音楽、つまりハードドライヴなロックンロールに、ルーツのそこはかとない剛直さと良心的なメロディの共通概念を混ぜて加えて練りこんだものがMHBであると考えているのだ。
とても微妙な境界線上にある音楽性ではあると考えているが、やはりアメリカン・トラッドやアメリカン・ルーツの要素が基本にはある歌を演奏しているとは思う。これをRoots Hard Rockと呼ぶのか、それともRoots Rock n Rollとするのかそれとも他のジャンルを創造するのがベストかということについては非常に線引きが難しい。(敢えてやる必要はないという突っ込みは不可。これがロックを語る上での楽しみでもあるのだから。)
こうなるともう単純に嗜好に依存するだけとなるのだが、ハードなロックは大好きだが、メロディをスポイルしてしまう性質のあるハードロックは若輩時に卒業して久しいので、独断と偏見で、ハードなロックと分類することにしている。ハードなサウンドでもメロディの素材の良さを活かせるクリエィションを行ってくれれば問題ないのだが。
であるから、Arena Roots Rockと、筆者個人でジャンルをでっち上げてしまった。ハードロックでもなくベタベタなルーツロックでもないし、それなりにハード・ドライヴィン。よってArena Roots Rockというのが適当だと思うのだが。ハードロックという概念を残してルーツロックと考えるとなると、サザン系かブルースロック系列に落ち着かざるを得ないと思うし。
例えば、ハードロックバンドがブルースロックを手法としてルーツロックの骨の太さを表すようになったバンドとしてはCinderellaや一時期のPoison、後期のGuns N’Rosesといった類があるけれども、Mark Hamm Bandはブルージーなハードロックに特化しているバンドでもないし、Lynard SkynardやDrive By Truckersの最新作「Southern Rock Opera」のようなサザン・ハードロックのダーティさをゴリゴリに演出するといった、ポップメタルなバンドよりも余程ハードに突き抜けているルーツハードタイプの音楽とも趣を異にしている。
もっとも、恐らくこのCDを持っているリスナーは日本には殆ど存在しないと思っているのだが、最初にこの「Ressurection」を聴いた後は単なる柔らか目なハードロックと捉える聴き手はかなり多くに登りそうである。更に、これはハードロックと考えるリスナーもまた少なくはなさそうだが・・・・。
最終的には、聴く人の感性と嗜好によって十人十色なのが音楽の本来の姿、とミモフタもないことで総括してしまうのはやめよう。少なくとも単なるメロディックなハードロックなら筆者がこの場で紹介することは絶対になかったことだけを、念頭に最低置いて貰えれば幸いだ。
と、書きつつ、トラックによってはハードロックかなあ、と思うこともしばしばだったりするのだが。(弱!!)
確かにMark Hammがインナーで述べている通り、このアルバムの録音はかなりチャンネルの少ないトラックで録音されたことは間違いない。とてもCDのデジタル録音時代とは思えないくらい音質が劣悪である。自主制作の宅録アルバムとタメを張る程度までそのレヴェルは低い。
ハード・ドライヴィンなタテノリロックチューンな#14『When I Think Of You』は実際にライヴ会場で録音されているようだ。後程観客のノイズを重ね合わせたとは思えないし、そこまで技巧を凝らす演出はこのアルバムでは選択されていないのだから。
またバンドも実にソリッドな編成で、ベース、ギター、そしてドラムスの3ピース。これにコーラスのみ後からオーヴァー・ダビングされたようだが。
しかし、物凄い臨場感を体感できるアルバムかというと、残念ながらそれには成功しているとは言い難い。というのはライヴ一発撮りをしているのは良いのだが、あまり録音技術が優れないため、ブートレグとして流通すれば、かなり質の良いブートレグとして通用しそうなレヴェルの一歩手前なクラスの迫力しか伝わってこないのだ。
また、演奏にしても曲のアレンジ、構成、組み立てがアリーナ・産業ロックに近いせいか、どうにもラフなライヴのノリを再現しきれておらず、もっと上品なロックアルバムになってしまっているのだ。しかし、録音がショボイので、これまた上手く整理されたサウンドをダイレクトに心を揺さぶるほどには演出効果が生まれない。
というような、録音がそれなりでもそれなりに聴ける筈のインディ盤としてはかなり特殊な位置付けにあるアーティストでありアルバムだと考えられる。ラフさといい加減さも魅力となることが多いルーツロックやトラッドロックの仲間としてはこの点を昇華しきれていない。つまりルーツ度合いがそれ程濃厚ではないという証明をも実践してしまっているところがレコーディングに存在する。何とも皮肉というか必然というか。
けれども、そういったマイナス面があるにせよ、ハードなギターが押し出されているアリーナ系ロック作品としては悪くないアルバムではあると思う。それはやはり全曲ではないが、正統派American RockやAmerican Rootsを直接的に押し付けるのではなく、隠し味的や仄かに感じられるテイストが共存しているからという因子が絡んだ結果の評価であることは言うまでも無いが。
例えば、#1『Right For Me』のオープニングのギターの咆哮は、1983年にNight Rangerの2ndアルバム「Midnight Madness」のレコードに針を落とした時、耳に飛び込んできた『(You Can Still)Rock In America』の冒頭のギターの唸りとシンクロするくらいなハードロックのエッセンスが振り撒かれている。それ以降はNight Ranger程にはハードに暴れまわらないし、カラフルなシンセサイザーのサポートも無いのだが。
このオープニングトラックは、New York DollsやAC/DCに近いシンプルなロックンロールだ。ある意味ルーツ的な側面も見せているともいえるかもしれない。そのプリミティヴなエネルギーを考慮するなら。但し、そこそこキャッチーであるのでAC/DCというよりもZZ Topの方が引き合いには適切かもしれない。
#2『Sweet Assurance』はかなりポップなメロディと、ハードに奔るギターのコントラストが絶妙に溶け合っている、西海岸的な爽やかさをも含んだポップ・ロックのチューンだ。Michael McDermottからルーツ的な要素をさらに引っこ抜くとこのような音になるかもしれない。
Def Leppard程にはJohn Matt Range色の大仰さはないし、Pop Metalのバラードほど情緒を強調するでもないエレクトリックな静を表現したスローナンバー、#3『I’d Rather Be』はアダルトロックとハードロックの中間的なナンバーと言うところだろうか。地味なマイナー調バラードとしては産業ロックバンドのJourneyやForeignerの初期を思い浮かべれば良い。
#4『My Everything』もサンプルに選んだだけあり、ポップでバランスの取れたナンバーである。ハードさがそれ程突出せずにアメリカン・トラッドのキャッチーさとアリーナロックのサウンドの厚さが競合している。まあ、そこでサウンドが華やかにならずに淡々としているところがMHBの音楽なのだが。
#5『I Fall Down』はSammy Hager加入後のVan Halenが嘗て必ずアルバムに1曲は用意していたシングル・チャート向けのポップなアメリカン・ハードチューンに近いナンバーだ。ドラムのハイハットやシンバルのキンキンとした鳴らし方や乾いたギターの音出しはかなりEddie Van Halenのメロディ・メイキングにシンクロしている。が、あそこまでメジャー感覚が出せずに何処か田舎臭い。よってシングルにしてもヒットするか覚束ないところがルーツ的なバンドの色を代表しているのだ。
#6『Never Stop』はMHBの活動拠点、イリノイ州の癖の無い音楽風味を伝えるようなヘヴィなミディアムロック。これで南部よりだったら完全なブルース系ハードになるのだろうが、アーバン的なところとルーラル風の中間で揺れている雰囲気が中西部たる所以。しかし、#7『When You Come』になると、これはハードロックだろう。ヘヴィなロックンロールというよりもポップ・メタルのダークサイドをドライヴさせている。
#8『Lord Of Mine』はアクースティックな手触りのあるスローナンバーであるけれども、これまた素直なルーツロックやフォーキィな音に転ばずに、ヘヴィなエレクトリックサウンドが頭上の曇天という具合に付き纏っている。しかし、このナンバーも何処か幽かに土の匂いが立ち上ってきそうな予感を持たせるのだ。
#9『I’m Getting Closer』は#2や#5に続いてArena Roots Rockというカテゴリーが似合うポップロックの好チューンである。適度なスピード感がやり過ぎない淡々としたポップ加減に交じり合っていくのは、キラキラとした目を奪う派手さよりも、ジワジワと聴き手を引き込む点で秀でている。
#10『All I Need』はこれまでに最もトラッドのダート感覚やブルースの哀愁を感じさせる。アクースティックな肌触りが少々する。こういった哀愁のある暗いメロディは1970年代のプログレッシヴなロックのマイナーナンバーに多いが、これを21世紀のインディで聴けるのはかなり違和感がある。
初めて純粋なアクースティックチューンとして、ルーツ的な要素をそれなりにはっきりと見せるのが#11『Glory Shine』である。曲としては素朴で好感が持てるのだが、Mark Hammの濁声の性質が強い喉であると、こういった繊細なトラックを歌う番にはヴォーカルの力不足を感じる。
次の#12『You Are High』も引き続き、美しいアクースティックなバラードなのだが、この曲でもMark Hammが歌い上げるには少々ミスマッチな美麗さと寂寥感を際立たせてしまっている。2曲続いて良いバラードが並んでいるのだが、これはもう少しコーラス等を加えてヴォーカル側とのバランスを取るべきだったと思う。シンプルに集束したいという意向は賛意を表したいが、あまりにもヴォーカルが曲の輝きに負けてしまっているのは気の毒だ。
#13『Heaven’s Calling』もMHBの特徴たるArena Roots Rockを色濃く反映した気持ち良くドライヴするロックナンバーである。ここでクリアな録音でギターが疾走するとVan HalenやNight Rangerと同じようなハードロックにしか聴こえなくなる危険性もあるので、このくらいのくぐもった低録音質がMHBにはベターかもしれない。ベストとはもっとクリアな手を掛けた音源を聴いてからでないと判断はつきかねるとしても。
前述のようにこのバンドの情報はまるで不足している。というか無いに等しい。たまさかCCMというよりもChristian MetalやChristian Rockのサイトでこのバンドの評判が良かったので聴いてみたら事の他当たりだったというのが発掘の顛末である。
イリノイ州のローカルエリアで活動する宗教系のバンドであり、3人編成。分かるのはこれだけなのだ。
Mark Hamm (Vocal,Guitar) , Kenny Tucker (Drums) , Hugh Reeves (12-Strings Bass,Vocal)
以上がメンバーであり、レコーディングでバック・ヴォーカルがコーラスを申し訳程度に追加しているのみ。
サウンド的に非常にユニークであるし、ドライヴするハードさが土臭さの少ないのは消化不良だけれども、結構快感であったので、この場で紹介してみた。
「私は神が今も人々をより崇高な信仰へと導いているということを信じて止まない。それこそ、神の欲していることだからだ。そしてこれこそが、この地上を天国のような場所に代えることができる唯一無二の道だと思う。」
と言われても、耳から素通りするだけだから、この手のミュージシャンのコメントや記事を読むのは無宗教な筆者にはある意味拷問だ。
「宗教を通じてこそ人生は力を得ることが出来、それがPower Popをドライヴさせるアルバムを創る原動力になるのさ。もし貴方がロック好きなら、そうすれば良い。」
これも一度宗教概念が入ると途端に胡散臭くなる。
とあんまり宗教をコケにすると色々と危ないので、この辺で打ち止め。
歌詞さえ聴かなければ、かなりロックンロールのドライな鎖と錘の重さを振り回して楽しめるアルバムだ。ソリッドでシンプルなハードロックが好きな人なら純粋で濃いルーツロック好きよりも全然お薦め。寧ろ、ルーツロックのカントリー的な部分とトラディショナルな点を抑えなければ満足出来ないリスナーは避けるほうが賢明だろう。
(2002.10.15.)

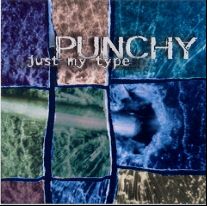 Just My Type / Punchy (2001)
Just My Type / Punchy (2001)