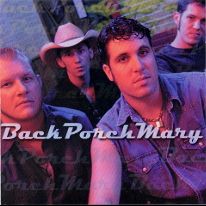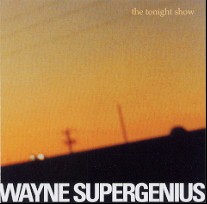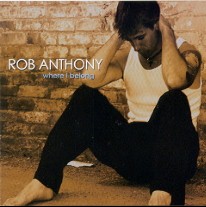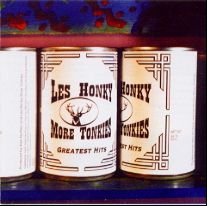Blindside View / The Kickbacks (2002)
Blindside View / The Kickbacks (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Southern ★
You Can Listen From Here
「Blindside View」−視界に入らない側、つまり死角と解釈するべきだろうか。普通、肉眼の視界を通じての死角は「Blind Spot」と表現されることが多い。この場合は寧ろ、ジャケットの写真から察するに運転台からサイドやバックミラーを介してしか視野に入らない死角を見ることを表わす運転用語と解釈する方が正しそうだ。
死角に関しては、俗語で「Dead Six」と云われたりする。これは12時方向で見た場合、6時の方角、つまり真後ろが完全に死角になることから来ているのだが、主に戦闘機乗りの間や軍事関連のタームで使われることが多い。
と覚えていても全く役に立たない、恒例の関係ない話で始まってしまったが、それはさておき、このThe Kickbacksの3枚目−2枚目のフルレングスである「Blindside View」は、タイトルこそ「見えない範囲=死角」とはなっているけれど、
死角なんぞ皆目無し!!
完璧なアメリカンロックのアルバムである。デヴュー時から注目していたバンドであり、その才能には疑いを抱いていなかったとはいえ、正直ここまで凄いロックアルバムが3枚目にして出現するとは予想を大きく裏切られてしまった。無論、喜ばしい裏切りであることは言うまでもない。
また、このアメリカンロック・アメリカンルーツの珠玉と断言したい「Blindside View」は決してAlt-Countryではなく、American Roots Rock n Rollである。これは非常に重要である。
ルーツでありつつ、カントリーさは皆目。つまりCounting Crowsや初期のWallflowers、そして1枚目と3枚目限定だがCollective Soulにも通じる王道まっしぐらなロックンロールなのだ。
カントリーの要素は皆無なのだが、ルーツロックとしての一種の垢抜けなさ、そしてその表裏一体である朴訥さに溢れた誠実さはきっちりと押さえている。また、日本語では非常に訳しにくいのだが、TwangyなPop/Rockであるという音楽性はAlt-Countryに通じるところではあるが。
しかも
The Dirty TruckersのTom Bakerさん大推薦のバンドである。
ま、当然Tomさんに紹介して貰う前からこのボストン出身のバンドは知っていたりする激烈オタクであったのだけれども、筆者は。(Tomさんも半ば呆れていたようだ。)
ということで、The Dirty Truckersが気に入ってるリスナーは
四の五の言わず、買っとけ!!!
試聴リンクに貼ったOHPで全曲フルで試聴可能というリスニングの充実振りなのだ。まあ、ノーマルなロック好きなら(除く、オルタナ好きなリスナー)彼らの音楽に惚れ込むこと請け合いだ。
これまでの2枚のアルバム
#1.「Longitude」(1998年)・・・11曲入りデヴュー盤。
#2.「Blue Man’s Collar」(2000年)・・・5曲入りミニアルバム。フォーマットは但しCD−R。
もかなり高レヴェルのロックンロールアルバムだった。しかし、特に1st作である「Longitude」は、ややAdult Alternative American Rockの翳りというか陰鬱さが微妙に混入されていた感じがある。そういったマイナス面を勘案しても、好盤であり良作であったのは間違いない。
しかし、ミニアルバムの形でリリースされ、そのヴォリュームの少なさに不満を覚えさせた「Blue Man’s Collar」では完全にAlternativeの現代性は消え去り、至極マトモなロックバンドへと成長していく過程がクリアに反映されていたため安堵を覚えたものである。
また、「Blue Man’s Collar」では、ややビターなポップテイストが曲によっては目立ち、少々出来の良いナンバーとそうでもないナンバーの差が目に付いた1stよりもかなりキャッチーさが増量し、その点でもThe Kickbacksはますます目が離せないバンドになっていった。
・・・・・・とヨイショしてしまえばそれまでなのだが、この頃NanaのTomさんからThe Kickbacksを紹介されたが、ロックンロールの醍醐味とそのハードパワーに負けないポップ感覚では、大変申し訳ないがThe Dirty TruckersやNanaにはまだまだ及ばないという感想が付き纏っていた。
所謂、「なかなか良いバンドなんだけど、どうももう一歩強烈にアピールするものが欠けている。」
という、基本に忠実な決して流行の尻馬に乗らない真面目なバンドが得てして陥り易い、“没個性”な印象を帯びてしまうバンドであったのだ。
とはいえ、レヴェルは非常に高い位置にあるバンドであるからして、そんじょそこらの中途半端なオルタナティヴやモダンロックと申し訳ポップな降り掛けで味付けした低俗なメジャーチャートを狙ったバンドの無個性さとは全然質の違う“印象の無さ”を言及しているので、誤解はゆめゆめなされぬように。
音楽性としては、まずもって合格点を遥かに超えた線に、最初からあるロックグループであるから。
1枚目のAdult Alternativeな雰囲気も2枚目からはすっかりと晴れ渡った冬空のように消滅していることだし。
元来、Alt-CountryやCountry Rockと真正面から向き合わずに、Facesや初期Rolling Stones的なルーツでハードドライヴィンなロックンロールを堅実に踏襲する態度を隠さないバンドであったので、基本的な方向性はデヴューの時から、本作「Blindside View」においても変化はない。
では、ここまで筆者を驚かせ、絶賛させているものは何かということだ。
まず、ダメダメなバンドが突如としてロケット発進のように吃驚素敵アルバムを出したのではないことを断っておく。
これまで歯牙にも掛けなかったバンドが、極稀に凄いアルバムを叩き出して、その奇襲効果で脱帽ということは確かに驚きを伴った絶賛に繋がることは多いケースだ。
しかし、The Kickbacksの場合、これまでの2枚が良作以上のアルバムであったので、ある程度の出来は予想していた。2001年から3作目のアナウンスメントがオフィシャルHPでされていたので、たまには巡回して新譜の発売を待っていたものだ。
当初は2002年の春というリリース予定が秋口になってしまったのには少々やきもきさせられたが、結果として待った甲斐は十分にあったので問題にしないけど。
と、話を元に戻すとしよう。
以上のような状況で、仮にKickbacksが2枚目の延長のようなアルバムをリリースしたとしたら、きっと
「ああ、相変わらず良作を出すロックバンドやなあ。」と歓迎して、レヴューも書いただろうが、感動はあまり大きなものにならなかった筈だ。
つまり、『予定調和の範囲内に収まる良作』であったら、喜ばしいことだがそれまで、という程度に落ち着いていた公算が大だ。
ところが、予想を遥かに上回る傑作だったので、ここまで褒めちぎっている。
まあ、これはここまでしつこく触れてきたので、何方でも理解できるだろう。
つまり何が云いたいかというと、分かり難い例えかもしれないが、
「五輪レヴェルで入賞までは行かないとはいえ、世界レヴェルのスポーツ選手がいきなり表彰台に上った」
「何某かの世界選手権という最高峰の舞台にはエントリーできる実力派ではあるが、決して予選を通過して上位に食い込むまでには達していないチームが、いきなり決勝進出して、注目に値する結果を出した。」
という感じである。本当はF1世界選手権のチームに例えたかったのだが、あまりにもマニアックで一般受けしないので上のような例に留めておいた。(汗)
要するに、高いレヴェルにありながら、いまいち伸び悩んでいた風の−あくまでも筆者的主観だけれど−ロックグループが遂に才能を全開に迸らせた傑作ということが言いたいのだが。
で、具体的にはどのようにレヴェルアップし、成長しているかということに言及しておく必要があるだろう。
まずは、マテリアル的な要素からいってみよう。
今作でバンドの総人口が5名のクゥインテット体制になった。これがまずバンドの音の成長と質の向上に大きく寄与していると考えている。
単に人数が増えたということに見えるかもしれないが、あっちこちからゲストを雇ってアルバムを拵えるという方式は、筆者としてはソロアーティストを名乗るミュージシャンが行うべき手法で、いみじくもバンド=楽団を名乗っているならきっちりとステージでレコーディングを再現できる最低の人数は揃えて貰いたいと常々主張している。
The Kickbacksはデヴュー作ではバンドメンバーのクレジットは4人であったものの、インナーのフォトグラフには3人しか写っておらず、レコーディングには参加していたベーシストは結局バンドに根付かなかったようだ。
それ以来、基本として2本のギターとドラムというやや不完全なユニットを維持し、ベースはゲストに弾かせていた。 その他にもオルガンやペダルスティールギターで応援を外部に求めることはあったにせよ、1996年の創設時から基本メンバーはトリオのままだった。
Tad Overbaugh (Vocals,Guitar,Harmonica) , Shawn Byrne (L.Guitar,Vocals)
John Burton (Drums,Percussion)
これに、今作から2名のメンバーが正式に加わっている。Matt Arnoldというベーシストを加え、そして
Steve Scott (B-3,Piano,Trumpet,Trombone,B.Vocals,Percussion)という人が加わっている。
このSteve Scottの加入がクリティカルな刺激をバンドに与えているのは間違いない。
ソングライターとしては寄与していないプレイヤーであるが、マルチプレイヤーとして鍵盤だけでなくホーン各種、そしてバックヴォーカルとしてコーラスにも厚味を付与している。
Steve ScottのハモンドB3を始めとする鍵盤類はThe Kickbacksのサウンドに単なる硬いロックンロールに終始しない円熟味と音響の深さをプラスしている。それだけでなく、彼の加入に後押しされたのだろうか、数曲でゲストも加えたブラスセクションが、華やかにロックンロールナンバーを装飾し、ヴァライェティをアルバムに与えている。
キーボードとホーンが加わったことで、単調になりがちな直球的ロックアルバムが実に彩りのあるレコードに再生されているのだ。無論、多彩な楽器の導入によって装飾し過ぎでゴテゴテした詰まらないアルバムにしてしまうようなヘマはしていない。ソリッドなロックサウンドにビシッとしたアクセントを与えているのだ。
サウンドの面では、2ndミニアルバムから顕著になったキャッチーなメロディを更に親しみ易く、そして痛快なものに仕上げている。
The Kickbacksのメロディだけ−上っ面だけを捕らえれば、Power PopやPunk Popというジャンルに属し、メジャーでも売れているGreen DayやWeezerに匹敵するくらいのコマーシャル性が存在する。
当然、只単に単調なコマーシャリズム・オンリーのヒネリの無い尻軽ポップソングやメジャーコードとノイジーなギターで誤魔化して畳み掛けるだけの十羽一絡げの脇役Emo Popバンドなんぞの浅薄さとは縁遠い、固い手応えのあるロックサウンドをガンガンと打ち付けてくれるバンドである。
The Kickbacksは自らの音楽をこう表現している。
Melodic Tunes ,with A Roots-Rock edge
字として記してしまうと、非常に簡単で単純だが、実際にこの表現通りにレコードを作れるバンドがどれくらい存在するだろうか。このような基本的な事項に従えば従うほど、際立った注目を浴びるアルバムを作るのは困難なのだ。
実のところThe Kickbacksは過去の2枚でもこの沿革には沿っていたが、完璧な実践にはやや遠かったと実直な意見を書いておく。だが、「Blindside View」では間違いなく、メロディックなチューンで、エッジィなルーツロックを彼らなりの手法で完璧に再現して見せている。
今年も数多くの良いロックアルバムに出会ったが、2002年10月の段階では
筆者的年間ベスト1アルバムだ!!
ルーツであり、マンモスキャッチーなメロディ。
然れども、嫌味になったり飽きの来る単調なお馬鹿ロックではなく、ちゃんと地に足の付いた音楽性。
過去の作品に比べると、ハードで押し捲る強引さがややスローダウンしているため、ロックンロールのエナジーという点では特に1stには劣るかもしれないが、その分オルタナ臭さは払拭されていることを考えれば、これはあまりにも厳しい採点だろう。
落ち着きが出たための、ミディアム化、マイルド化が進行している面はあるけれども、ロックンロールを打ち付けるところではしっかりとロックのパワーを発揮してくれているのだから。
さて、デヴュー盤に続いてこの2枚目のフルレングスも11曲。2分台の長さのナンバーは、唯一のカヴァー作品#6『Almost Saturday Night』を含め、2曲のみ。後は3分から4分といった丁度良い長さのチューンが並んでいる。
The Kickbacksには2名のソングライターとリード・ヴォーカリストが在籍している。メインはTad Overbaughであり、デヴュー作から大半の曲はTadの手に拠っている。しかし前作「Blue Man’s Collar」で初めて2曲の単独作を提供したShawn Byrneが本作では3曲、#4、#8、#9を書き、自分の書いた歌ではリードヴォーカルも担当している。
Shawnがこれまでにリードヴォーカルを担当したのは前作のラストトラック『Mr.Moses』だけだったのだが、彼の全面に出る割合が増えているのも特徴だ。
Shawn Byrneのヴォーカルは、Tadの男の汗の匂い満載で酒と煙草の似合いそうな、ハスキーでソウルフルな声と比べると、良くも悪くも癖の無い無難なヴォーカルである。
が、彼の書くナンバーは良い曲が多い。
#4『Be Just Fine』ではゲスト・ミュージシャンのアルトサックスとScottのトランペットが豪快にバックをサポートするビッグなロックチューンが聴ける。このナンバーは実にドライヴ感のあるブラス・ロックで不器用なShawnのヴォイスも曲を盛り下げることにはなっていない。
#8『Hard Time Afternoon』も淡々とした静の展開から、お定まりとはいえ、ジワジワと盛り上げていく極上のルーツ・ポップロックである。メロディは最高に決まっているのだが、こういったナンバーではややShawnのヴォーカルは個性に欠けるところはある。
#9『Behind The Wire』は、恐らくこのアルバムで最もハードでダークな鋭角的なロックンロール。だが、そのダーティでハードエッジな展開に負けることの無い程好いポップの湯加減がしっかりと息づいているナンバーであり、物凄いハードなサウンドを引っ張りまわすギターソロも耳障りではない。寧ろ甘くなり過ぎる全体を引き締める効果を齎しているようにも感じる。
残りの8曲は、Tadがリードを歌っている。カヴァーは1曲、これは初めてのカヴァーのトラッキングでもある。その曲である#6『Almost Saturday Night』については、説明の必要も無いだろう。が、一応書いておくと、John Fogertyの1975年の作品「John Fogerty」からのピックアップ。勿論Johnの代表曲であり、あのThe Georgia Satellitesもカヴァーしているロックンロールナンバーである。
The KickbacksはTadの酒焼けしたようなハスキーで素肌のヴォーカルをソウルフルに乗せながら、コーラスとカラフルなオルガンで色を付けて非常に気持ち良いアレンジに仕上げている。
#1『Spotlight Hits You』は、これまでとは違うKickbacksを予感させるナンバーとも言えるだろう。過去2枚の作品ではオープニングに勝負曲というか、ドの付くキャッチーなロックナンバーを持ってきて畳み掛けるような勢いを感じさせていたバンドが、ゆったりとしたミドルテンポのルーツナンバーを冒頭に置いているのだ。グループとしてのゆとりと成長を掲げているようなナンバーでもある。当然ポップさだけならオープニングに相応しいが、それ以上に、アーシーで、渋い男の鈍色の美学(?)を感じさせるようなナンバーだ。
その渋さを吹き飛ばすようなナンバーが、エッジの掛かったロックリズムに、ホーンセクションがゴージャスに絡む#2『Goin’The Mile』である。爆音のようなスライドギターにトランペットやアルトサックスが、リズム隊が、そしてTadの掠れた声がアンサンブルを織り込んでいく。2002年のブラスナンバーとしてはDiamond Dogsに並ぶ成功例であると考えている。
アクースティックでダスティなナンバー、#3『Banged Up,Black And Blue』や#5『He Was A Fire』ではJohn Mellencampの1980年代の頃のメジャー感覚を再現したような噛み締める大地の息吹、そしてTom Petty And The Heartbreakersの南部感覚を併呑したようなじっくりしたスローミディアム曲が堪能できる。特に#3では女性コーラスが効果的に使用されている。
#5での枯れた雰囲気は、Bruce Springsteenのアクースティック系の作品に繋がる老成を感じてしまう。まだまだ若いバンドなのに、ここまで枯れた音楽が表現できるとは驚きだ。
#7『She’s Gone,I’m Dead』ではジャンピーなオルガンによるダイナミズムに溢れた出だしから、ゴリゴリのロックナンバーを予想したら、意外にもドラムやオルガンが暴れるパートと切々とシンプルにTadが歌い綴る部分に分かれたナンバーで強弱のアクセントがきっちりと付いているロックナンバーとなっている。こういった仕掛けというか構成もThe Kickbacksの成熟を測れるバロメーターだろう。
#10『Guts And Soul』に関してはTom Bakerさんがプッシュする理由が良く分かる、というパワフルでシャープなロックナンバーという印象は最初から最後まで覆ることは無いが。ピアノやドラムの叩き付けるリズムが、何故かDan Fogelbergの1984年のヒットナンバーである『The Language Of Love』を思い出してしまう。
#11『Diamond In The Rough』は、ムーディなトロンボーンがフュージョン的な雰囲気を曲に纏わりつかせる、バーバンドというよりも寧ろベイ・エリアのバンドを連想してしまうようなしっとりとしたナンバーである。これまではバラードがあまり得意という印象を受け難かったバンドだが、本作ではそのイメージが完全に引っ繰り返されてしまった。しかしながら、Scottのホーンの役割を改めて感じるナンバーでもある。
The Kickbacksについては1996年にボストンで結成され、クラブやレストラン、そしてダンスフロア、スクールといった何処でも厭わずに演奏してきたバンドということしか寡聞にして知らない。
現在はクラブサーキットをマサーチューセッツ州を中心に行いながら、新曲を書いているとのことだ。これまでに2年周期でアルバムをリリースしているバンドだが、2枚目がミニアルバムだったことを考えるともう少し回転を早くして欲しいと願っているのだが、4枚目は何時になるのか今から楽しみだ。
これまでにツアーを共にしたバンドとしてはTim Easton、Drive By Truckers、Robbie Fulks、SlobberboneそしてMike Plume Bandといった、筆者が紹介しているバンドが多く含まれている。このことからも筆者の嗜好にピッタリということが推察できると思う。
Tom Bakerさんも相当応援して、「大好きなバンド」と述べているが、今作の「特別な謝意」には初めてTomさんの名前も見られる。さて、次なるボストンからの傑作はThe Dirty Truckersになると嬉しいが。それも今年、2002年のうちに。
「Blindside View」はかなり評価は関係者筋では高い模様で、3枚目にして初めてMiles Of Musicにも入荷した。これまでは契約先のSodapop Recordsでしか買えなかったのだが、複数のオンラインショップでも10ドルくらいで手に入るようになった。是非聴いて欲しい。 (2002.11.2.)
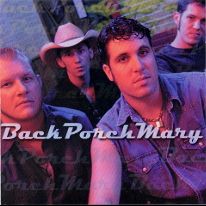 Back Porch Mary / Back Porch Mary (2002)
Back Porch Mary / Back Porch Mary (2002)
Roots ★★★☆
Pop ★★★☆
Hard ★★★
Southern&Punk ★★★
You Can Listen From Here
「Back Porch Maryの歴史は、個人的な悲劇を綴った酷い物語である。それは、幾つもの州を跨いだ、人間関係の崩壊、逮捕劇、裁判所への出頭、そして多くの語ることも出来ない事件を語る奇妙で聞くに堪えない伝説でもあるのだ・・・・・。」
とこのような序文でOHPのバンド紹介は書き始められている。まあ、当然ある種の諧謔と捉えるのが当然だろう。今日に至るまでの苦難の道のりを誇張して語っていることは間違いないと思う。まあ、ロックバンドが破滅的な生活を送るというのは既に古き悪き伝統と化してしまった感が強い現代では、これもオールド・タイム・ロックンロールを標榜した一節とも捉えられるかもしれない。
けれども、Back Porch Maryが1993年に初のギグをカンサス州の学生街であるヘイという街で行った時は、
「75キロのビールが消費され、17台のパトロールカーが出動し、2台の囚人護送車が使用され、地方局のニューススタッフが実況に駆けつけ、そして41人が逮捕された。」
そうだ。Back Porch Maryが単独でライヴを行ったのか、それともフェスティバル形式での大掛かりなイヴェントであったについては言及されてはいないが、恐らく後者の方であっただろう。幾らなんでもデヴューバンドの単独ライヴで破壊活動紛いまで発展した騒ぎになるとは考え難いから。
この記録は全くの実話である。と、バイオグラフィでは謳っている。
当時、Back Porch Maryのメンバーの中心は、現在もバンドに只独り残っている、というよりもBack Porch Maryを現在の形に再編した功労者であるMike KrugとMikeの盟友であるドラマーのJeremie Krehbielであり、彼らはまだ10代の若者だった。
まあ、大学で形作られている街で、アルコールとロックンロールが混入されて、化学反応を起こせば、程度の差こそあれ馬鹿騒ぎや乱痴気騒ぎが起こることは頻繁ではないにしてもそう珍しいことではないだろう。が、それが昂じて逮捕者まで出た暴動に近い騒ぎまで発展するとは。
一体どのくらいアドレナリンを分泌させる熱い、クレイジーなライヴ・パフォーマンスが行われたのだろうか。民族性が我々農耕民族とは異なるとはいえ、かなり常軌を逸脱した一夜であったことくらいは推測できる。
と些かネガティヴな出だしになってしまったが、今回紹介するBack Porch Maryの若かりし頃の逸話を紹介してみた。意図としては、別にBack Porch Maryがデモリションなバンドと言いたい訳では決して無い。
というか、このCDを購入に当たっては、Mike Krug氏に多大なる尽力と親切を戴いた。寧ろ、Back Porch MaryのMike氏は紳士であると思う。が、長じて人物となる人とて、若かりし頃は随分無茶をやるものだなあ、とはしみじみ思うのだが。
この場で強調したいのは、この約10年前の大騒乱の一端に名を連ねたBack Porch Maryの熱い(熱かった)ロックンロール・スピリットが直裁的ではないが、しっかりとこの2002年のセルフタイトル作にも息づいているということだ。
乱痴気騒ぎの導火線の一部を構成したと思われる、ハードでマッシヴなロックンロールは10年を経た2002年のアルバムでも全く衰えていないように思える。もっとも、筆者は当時のサウンドを聴いたことはないので、比較する手段を持ち得ないのだが。
昨今の合衆国のチャートには、メジャーのポップチャートのみならず、Modern Rock TracksやMainstream Rock Tracksといったロックのチャートでさえ、アメリカンロックという看板を掲げることは筆者として絶対に容認できないオルタナ・ヘヴィネスやオルタナティヴロックが蔓延している。
流行として捉えれば、これは仕方ないとも思うのだが、こういった単なるノイジーで、重過ぎる、メロディレスな音楽が「メロディアス」とか「哀愁を帯びている」という謳い文句で日本に輸入されて盲目的に聞かれている現状にはげっそりとしてしまう。
重くて、陰鬱ならロックとして格好良い。それもまた1つの好みであるから、それを喜んで聞いているリスナーを批判するつもりは全く無いのだが、洋楽を親しむ年齢に達した時に、ヘヴィなオルタナ音楽しか最新のロックとして耳にすることができないのなら、それは感性に対して重要な欠如と言うべきで実に気の毒に思うのだ、そういった世代を。
で、不満たらたらと述べたのは、偏にそのようなアフター・オルタナ/グランジロック世代にも是非、このBack Porch Maryをお薦めしたい故である。
Back Porch Maryのサウンドがヘヴィで重いということに掛けては、太鼓判を捺そう。
人によってはハードロックと分類してしまう位のハードなロックナンバーが何曲もトラッキングされていることだし。
但し、ヘヴィでハードなサウンドといっても、インオーガニックなオルタナティヴの耳障りな金属的雑音ではなく、有機的な耕作地を掘り返すような暖かみのある、血の通った重さが存在することをお断りしておこう。
Back Porch Mary(以下、BPM)のサウンドにはオルタナティヴの憂鬱さや怒りといったネガティヴなメタファーは含まれていない。そういった青汁の不味さよりも、アメリカン・ルーツのまるで溶けたチーズの味のようなコッテリした重さがしっかりと根付いているから。
触覚で表現するなら、オルタナティヴ・ヘヴィロックはゴツゴツとした鋭角的な金属の塊を素手で運ぶような痛さと辛さがある。仮に転んだとしたら、その塊が身体に突き刺さって痛みだけでなく血塗れになりそうな不安と不快感が常に付き纏っている。
反して、BPMの場合、畑で収穫したばかりのジャガイモや南瓜をヒイヒイ言いながら、それでも土の匂いを嗅ぎつつ運搬する労働の汗を伴った辛さがある。もし転倒したとしても、大地とお日様の匂いを嗅ぐことができるだろうし、転んだことで身体は汚れても大した苦痛は伴わないに違いない。
とこのようなヘヴィさの質の違いがある。まさに有機と無機のエレメントにおける両極端である。
一応ここで、BPMの音楽性について行間のついでに述べるのではなく、場を定めて語っておくことにする。
まずはBPM自身のコメントを借用すると、こうである。
「Back Porch Maryの音楽を分類することは難しい。唯、確かなことはロックンロールであるということ。メンバーは様々な種類の音楽を聴いて、そしてそれらに影響を受けてきている。またライヴで大きな部分を占める音楽はカントリー音楽である。実際にロックンロールとカントリー・ミュージックに大差は無い。というか全くこの両者には違いは無い。」
このコメントを読むと、Back Porch Maryは一種のCountry Rockのバンドと考えてしまうが、それは正しくもあり、そして正しくもないと筆者は考えている。
そもそも筆者がこのバンドに興味を持ったのはとある海外サイトで“Hard Rock Country,Cosmic American”なバンドであると評価されていたのが切っ掛けである。
で、その当時発売されていたシングルCDに収録された2曲『700 Miles Ago』と『Believe In Nothing』を聴いた瞬間、BPMに惚れ込んでしまった次第である。残念ながら、この2曲は「Back Porch Mary」には収録されていない。
Mike氏曰く、
「既に発表してWeb上でダウンロードできるマテリアルよりも、新しい曲を収録する方を選んだ。」
とのことである。非常にリスナー・フレンドリーだ。現在、この2曲はニューアルバムの発売に伴ったHPのデザイン変更でDL不可になってしまったが、この2曲を聴けば、アメリカンロック好きなら絶対にBPMに飛びつくこと請け合いと言い切れるくらい素晴らしい。
この2曲を聴いた感想は、物凄いキャッチーで、適度にハードさのあるRoots Rockだ、というものであり、ルーツテイストとロックテイストはビンビンに含有されていたが、カントリーっぽさは全然聴き取れなかった。
このシングル曲2曲を知った段階では、やがて完成すると発表されていたフルアルバムは、相当ポップで程好いドライヴ・フィーリングを装着した、まるで直前に紹介したThe KickbacksのようなRoots Pop/Rockになるだろうと漠然と予想していたのだ。
だが、予想は見事に覆されてしまった。キャッチーなルーツロックのピースという基本姿勢からは逸脱するものでは決して無かったけれども。
実際に試聴リンクから全曲の一部を聴けるので、DLして戴ければ明白であると思うが、甘いポップさよりもまさにHard Rock Countryという表現の前半要素であるHard Rock、ハードに疾走するロックンロールが満載のアルバムになっていた。
漠然と予想していた以上にアグレッシヴでプリミティヴ、しかもコマーシャルなメロディをかなり辛口に味付けしたトラックが大半を占めていたのである。
勿論、不足を感じさせないキャッチーさはしっかりと抱えているので、Pop/Rockと表現できないこともないのだ。けれども、やはりPopという語彙は外してRockと分けるべきアルバムであると思う。寧ろHardという修飾をRockの前に載せておくべきだ。
単なるHard Rockのアルバムではないし、全てのナンバーがハードロックトラックという訳でもない、ということは改めて強調しておくけれども。
が、ハードさというのがこのアルバムの特徴であるのは疑いようは無い。その一本突出したハードなドライヴ感覚だけならThe Dirty Truckers以上である。
ヘヴィでワイルドというアスペクトはFacesやMott The HoopleそれにThe Black Crowesにタメを張るだろう。
更に、BPMの音楽性はPunk Rockという面も兼ね備えている。しかもアーシーなSouthern Rockの泥臭さが満点なため、Country PunkつまりCowpunk的な意味でカントリーを感じさせるナンバーも幾つか存在する。
こういった特徴、CowpunkでありRoots Punkでもあるという点ではJason And The Scorchers、Uncle TupeloそしてDrivin’N’Cryin’といったハードなロックンロールやパンキッシュな曲もレパートリーに入れていた南部バンドと近似するサウンドであるとも言える。
だが、最大の着目点は
ガンガンと叩きつけられるスライドギター!ロックスライド好きには堪らないだろう。
この点ではFour Horsemenの「The Four Horsemen」を彷彿させるアルバムである。
もう少し、具体的に突っ込んでみると、Facesの「First Step」の頃の未整理さと野蛮さ、そして「Ooh La La」の時代のルーツィでキャッチーが同居した感じを連想してもらえれば良い。
Uncle Tupeloの場合、「No Depression」をロックサイドにエレクトさせ、甘さを削り取った作風。
Jason And The Scorchersなら「Clear Impetuous Morning」をハードサイドに移行して、カントリーロックとポップさを希釈したと仮定すれば問題ない。
また、Drivin’N’Cryin’なら完全なハードロックのアルバムと化している「Smoke」をポップにしてカントリーロックのあっけらかんとした間を付け加えて“ハードなロックンロール”のアルバムにデチューンしたら、BPMに近い音楽性になるだろうか。
まあ、要するにHard Rock CountryというよりもRoots Hard Rock/Southern Hard Rootsと分類するべき音楽であると思う。全てのナンバーがハードでないところはFacesやJason And The Scorchersと分類を近いものにしている。
ルーツテイストはかなり多いのだが、野暮ったさよりも荒削りさと力技のゴリゴリしたギターリフが爆裂するハードさが際立っているところが特色だ。その点ではAlt-Countryの構成要素であるGarage Rockにも手を染めていると解釈する余地も出てくるかもしれないが、Garageの無秩序で粗雑さの目立つノイジーさという雰囲気は覚えることがないサウンドだ。
荒く、豪快であるけれども、乱雑な五月蝿いだけの喧しさではない。かといってアリーナ系のハードロックバンドのようにハードなギターを武器にしているだけのユニットでもないのだ。こういった鋭く、然れども懐の深い土臭いハードさを兼ね備えているというところではIzzy Stradlinや産業メタル音楽から脱却した「Heartbreak Station」以降のCinderellaにも繋がるか。1970年代のBoogie Rockの代表FacesやRolling Stonesサウンドに影響を受けたことは言及するまでも無いだろう。
シンプルで余計な装飾の無いハードロックで、ハード過ぎない音を欲しているリスナーにはジャストフィット請け合いである。更に、
ハードなロックンロール且つ、メロディがポップである、というのが好きなリスナー。
ハードロックは許容出来るが、ハード一辺倒ではなくポップやルーツソングも同時に楽しみたいというリスナー。
にも推奨出来る。
ルーツ・ハード系の音が好きでパンキッシュなカントリーが好みという趣味なら相性は最高だが。
収録曲の11曲は大別すると、以下のタイプに分かれるだろう。勿論、曲によっては複数の要素が絡まって不可分なものもあるのだが、もっとも際立つ要素でカテゴライズしてみた。また◆弐と◆参は曲感の重さで仕分けたに過ぎないし、◆壱もポップ度合いが高いものを連ねただけだ。
まあ、便宜上の分類と考えてもらえれば良いだろう。
◆壱:キャッチーでソリッドな疾走感がウリのルーツロックナンバー。
#1『Rollin’In Low』、#5『Trash Trush』
◆弐:ダークでヘヴィなハードロックナンバー。
#3『Mitch』、#7『Whiskey』、#8『Days Away』、#11『Your Town』
◆参:サザンロックの泥臭さとアーシーさがあるルーツトラック。
#4『Busted Town』、#6『S.A.P.』、#9『Requicm』、#12『Prison Music』
◆四:パンクなルーツナンバー。
#2『Dig My Grave』、#10『She’s Crying』
「壱」のタイプは筆者の一番歓迎するキャッチーでロックンロールなナンバー。#1は適度なドライヴ・フィーリングとポップなライン、そして重量感のあるギターがMike Krugの野太いヴォーカルに引っ張られて奔る、走る。
#5もスライドギターの爆走を豪快にキャッチーなメロディに載せる骨太なロックナンバーだ。
「弐」、そして「参」の特徴は、前述したが、The Four HorsemenやGeorgia Satellitesのフォロワー的な位置を与えたくなるハードなスライドギターを中心に組み立てられたロックンロールだろう。SouthernとHard Rockの両者を融合した具合の曲が殆どだが、ダーティとかアンキャッチーという減点は少ない。
#3のヘヴィにうねるハードチューンと#4の軟泥でスワンピーなルーツフィーリングに溢れたポップなチューンでもスライドギターが常に咆哮している。
#6は優しく、南部ロックの暖かさが肌で感じられるミディアムなロックナンバーであり、オルガンやフェードの掛かったスライドサウンドが質感タップリにメロディを牽引していく。コーラスの巧みな配置も忘れてはいけないだろう。
New York DollsやAC/DCを感じさせる鋭角的で重い#7と#8はもう少し甘口でも良かったのではと少々不満。同じハードなチューンでも#9くらいのコマーシャル加減があると随分ロックチューンとして引き立つと思うのだが。
ラスト2曲、#11、#12はやはり重いロックナンバーであるが、アップビートである分だけ、#12の方が爆走する元気の良さが感じられるし、コーラスが明るい雰囲気を演出しているので聴き易い。
「四」の場合、#2と#10はかなり極端に曲感を異にしている。#2はこのアルバムでも屈指のハードさとラフさを誇るカウパンクのダークサイドとハードサイドの両面を司るようなヘヴィ・パンクチューン。Mikeのバリトンを更に低くしたシャウトヴォーカルが兎に角ハードヒットするというハード・カウボーイなルーツパンク。
#10もバタバタとしたドラムで組み立てられるオーヴァー16ビートの速さは#2を凌ぐものがあるが、このアルバムで最もカントリー色の強いカラリとしてアッケラカランとした明るさのあるパーティ・ロックチューンでもある。アップライトベースやスネアのインプロヴィゼイションやギターのソロが自由自在に動き回るルーラル・ジャムな曲でもある。
このルーツであり、ハードなロックンロールをテキサスはオースティンで聴かせているバンドについて最後に簡単に経歴をなぞっておくことにしよう。
1992年に合衆国中部のカンサス州で母体が結成されている。現在のバンドメンバーはMike Krugしか残っていないため、便宜上第一期BPMと呼んでおくとするか。
1993年の初ライヴが大騒ぎになったことは冒頭で既に触れている。1993年以降、デモトラックを幾度か録音しつつ、一時期はニューヨークはマンハッタンまで乗り出して演奏活動をしたこともあったそうだが、最終的にはカンサスへ戻り、ローカルエリアの草の根活動を続けている。
そして1997年には、第一期BPMの唯一のフルレングスアルバムにしてデヴュー盤である「Gather」を地元のインディ・レーベルから発売する。このアルバムは残念ながら殆ど売れなかったそうだ。なお、このアルバムのメインのソングライター、そしてリードヴォーカリストもMike Krugではなく当時のバンドのヴォーカリストが書いた曲が大半であったとのことで、現在のBPMとは別物の作品と考えた方が良い。
このアルバムセールスの失敗から回復を図るためか、BPMはテキサスに転居し、活動を開始する。しかし、バンドのメンバーは皆故郷のカンサスを懐かしみ、僅か数ヶ月でバンドは空中分解してしまう。
盟友Jeremieすらツアー用のトレーラーとログハウスを持ち帰ってしまい、Mikeは全く手ぶらでオースティンに残ることになった。しかし、音楽を続けたいという意志を強く持ち続けたMikeはたったひとりでBPMを再建する。ソロとして活動する傍ら、バンドメンバーを集め直し、何十人ものオーディションを繰り返した結果、第二期BPMを見事に結成。
2000年からデモ録音をギグの合間に始め、2001年には前述の2曲入りCDSを発売。これが筆者がBPMを知る切っ掛けになったことは記載した。
そして2002年にはHard Country RockというよりもSouthern Hard Roots Rockという呼び方が似つかわしい、実質上のMike Krug’s Back Porch Maryのデヴュー盤をリリースして現在に至っている。
ソングライティングは歌詞の全てをMikeが、作曲はBPM名義となっている。#5のみ1980年代からプロデューサーやキーボーディストとして主にインスゥルメンタル・ロックの分野で活動しているDavid Keuhnの作だが。
Mike Krug (L.Vocal,Guitar,Slide Guitar) , Shane “Slim” Laurence (Guitar,Vocals)
John Miller (Bass,Uplight Bass,Vocals) , Tim Heart (Drums)
という4人組にオルガンのサポートプレイヤーでこのアルバムは録音されている。
購入に当たって、初の海外からのオーダーということで、サイトを海外からの送金対応に手直しして戴く等、Mike Krug氏には多大な労を戴くことになった。改めて御礼したい。
シンプル・メタル系で、日本盤も発売されたNashville Pussyよりも全然曲としては完成度が高いし、落ち着きもメリハリもあるバンドである。何よりもイロモノで売り出さず、真摯にロックンロールを追求しているところが好感が持てる所以でもある。
送料込みで17.5ドルくらいになるが、特にシンプルなハードサウンド好き、そしてスライドギターのロックンロールが好みな人には絶対に損にならない。
筆者も手持ちのアルバムが少しあるので、試聴して気に入ったら是非メールで連絡して欲しい。
ところで、丁度このレヴューを擱筆した2002年11月5日に、彼らのHPのバイオグラフィーが随分大人しい無難な内容に変わってしまった。第一期のBPMについての記載は一切合切消滅し、かなりソフトな内容のバイオに置き換えられている。これは人気が上昇したために、少々マイルドな文に差し替えたのかな、と想像しているのだが。
何にしても人気が出て欲しいタフなバンドである。 (2002.11.5.)
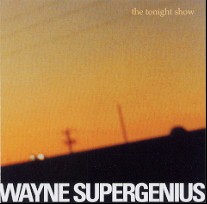 The Tonight Show / Wayne Supergenius (2002)
The Tonight Show / Wayne Supergenius (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Americana ★★★
You Can Listen From Here
Wayne Supergeniusという些か長く、スペリングが妙に面倒くさい名前を持ったバンドは、1999年10月にペンシルヴァニア州で結成されている。
結成の形は解散した2つのバンドが結合して、新しいユニットを創造するというパターンを踏んでいる。こういったバンドの誕生は特別珍しい物語ではない。
グループの知名度の大小に関係なく、解散した複数のバンドの主要メンバーが別のプロジェクトや他のバンドに合流することことは今に始まったことではなく、ある意味バンドが結成された時からこういった展開は起こるべくして起こるとも言えるくらいの日常茶飯事である。
しかし、かなり毛色の違った2つのバンドが結婚して、それが見事に成功したという実例はそうは多くないような気がする。これは商業的な成功、評価の高低に絞った場合の成功と両方を指すだろうが、当サイトの場合は基本的に商業的な成功にはあまり拘泥しない。
そもそも、かなり方向性の違うミュージシャンが集まった場合、一時的にはお互いの持ち味がプラスに作用していい方向に進むことはあっても、長続きした試しは殆どない。
第一、似たような系図に含まれるミュージシャンが、例えばプログレッシヴ・ロックやハードロックのプレイヤー達が、パワーゲームのように分裂と再開と新しいバンドを作っては解散させるという状況はうんざりするくらいに見せられてきた経験があるように、同系統のファミリー・ツリーに含まれるミュージシャンが新しいバンドを協力して興すことのケースが圧倒的に多いし。
勿論、他のバンドメンバーの合流によって、スーパー・プロジェクトが結成されたため、素晴らしい名盤が出来上がったという事例はあるにしても、そもそもどれだけの“スーパー・バンド”が名前だけの存在で終焉したか。数えるのも憂鬱になってしまうくらいに成功例は少ないと思う。
であるから、Wayne Supergeniusのように、母体となった2つのバンドの方向性がかなり違ったものであるのに、それぞれ双方の音楽とは異なった音楽を指向して素晴らしい作品を仕上げたという事実が、何にも増して素晴らしいと考えているのだ。
要するに、Wayne Supergeniusというロックバンドの母体と成ったグループが演奏していたサウンドは、新生バンドのWayne Supergeniusとはかなりジャンルがかけ離れたシロモノであったということだ。少なくともその片方のバンドは現在のサウンドには全く縁遠い存在であったと思っている。
Wayne Supergeniusの母体となったのは、Cole.というバンド、そしてThe Polinsというインディのバンドである。
両方共に筆者は聴いたことはないので、上記したように「現在のサウンドとは全く違う音楽を演奏していた。」と断言するのは早計かもしれない。
しかし、Cole.に対する評価、そしてツアーを共にしたバンドからCole.の音楽性は容易に推察が可能だし、まず大きな逸脱は予想範囲から出ていないと思っている。
Cole.は1990年代半ばに、以下のようなバンドのツアーに同行。フロントアクターとしてステージに立っていたそうである。
Fuel、 Live、Spacehog、更にDel Amitri。
1998年の時点では、Del Amitriはまだマトモなバンドであったので、これだけは例外としておく。(ま、2002年のアルバムは最低だけど。)
他のメジャー・レーベルからアルバムをリリースしているバンドはどれも、ルーツロックやカントリー・ロックの一欠けらも混じっていないオルタナティヴ/グランジ系のバンド、またはブリットポップやモダン・ヘヴィネスとも受け止めることが余裕で可能な、全く筆者の嗜好には受け入れることの出来ないバンドばかりである。
FuelにしてもLiveにしても単に喧しいだけで、必要を感じない近代的なエキセントリックというかテクニックの小手先だけの弄くりがあるだけのどうにも評価がしようにない存在であるからだ。
しかし、自らをAlt.Rock Fav’s=オルタナティヴ・ロックを求めるバンド、と表現するくらいに、Cole.はオルタナティヴ系のバンドであったようだ。そもそもFuelやSpacehogがポップ系のナチュラルなバンドとツアーを行うことはまずあるまい。あまりにも異質な組み合わせであるからだ。
しかしオルタナティヴ・ロックのバンドとしてCole.は地元のインディバンドの人気投票では頭を獲ることもあるくらいの支持は得ていたようである。が、ステージを共にした幾つかのバンドのようにメジャーに昇格することなく、1999年に解散している。
もう1つのバンド、The Polinsの音楽性はCole.程にはWayne Supergeniusと掛け離れたものではないだろう。
こちらのバンドは、所謂Power Popの類に属するグループであったようだ。出身はCole.と同じくペンシルヴァニア州であったようだが、L.A.のポップロックシーンで長く活動。Power Popのバンドが多いカリフォルニアのシーンで揉まれたためかかなり音楽的に成長した様子で、1999年には毎年アメリカで年一回行われるInternational Pop Overthrowにも出演している。
このIPO(=International Pop Overthrow)というイヴェントは、スカンジナヴィアのポップバンドや欧州からのポップバンドも多数参加するという、現在のアメリカでは決してメジャーではないエレクトロニック系に傾いたPower Popバンドが多く参加するのが特徴であり、ニューヨークーで2002年も開催されている。
また、The Polinsは筆者はあまり好きでないレーベルなのだが、Power Popのレーベルとしては著名なNot Lameと販売契約を結ぶまでに至っている。Polinsのアルバム「Starhartflower」はモダン系のパワー・ポップアルバムとしてはなかなか出来は良いので、何処かで見つけたら聴いてみるのも良いかもしれない。
しかし、所謂Alternative Pop的なところもある、電子的な厚いギターが目立つPower Popであるため、これまたルーツ/カントリー系のバンドとは方向性は違っている。
この2つのバンドが1999年にペンシルヴァニア州のハリスバーグという街で解散したのだが、解散後すぐにCole.のシンガーであり歌の書き手であったTony Ryderは次なる活動のためにインディレーベルに在籍していたミュージシャンを集め、アクースティックナンバーのみで11曲入りのデモを完成させる。
このデモ・トラックを録音した行為がTonyに次のバンドを結成させることを促し、Tonyはメンバーを集め始める。
まずはCole.時代のバンドメイトであるMike Passarielloをベースとしてバンドに呼び込む。
次に、The PolinsからTony Melchiorreをドラマーとし、John Fritcheyをギタリストとして迎えている。この2名がThe Polins出身であるかは、現在手元にPolinsのアルバムがないため、不明確であることをお断りしておく。
兎に角、4名が集って、新バンドであるWayne Supergeniusを立ち上げたのが、1999年10月のことである。
しかし、結成当初は、このバンド名ではなく、Blind Faithと冗談で名乗っていたそうだ。
この名前は、Steve WinwoodとEric Clapton、Rick Grech、そしてGinger Bakerが1969年に結成した掛け値無しのスーパー・プロジェクトと同名である。冗談にしてもなかなか名乗れる名前ではないと思うのだが、それを実際に行ってしまうところが度胸が良いというか。
「僕達は、既に使われてしまっているBlind Faithというバンド名を使ったことはさておき、ローカルミュージシャンでいる以上になりたいという大望を表明したつもりなんだけどね、誰もこのジョークを理解してくれなかったようだね。」
とTonyは残念がっているが、やはりバンド名には奇抜なネーミングをしている。
Wayne Supergeniusというバンド名は米国のテレビドラマある「Adventure Of Pete And Pete」という番組で脇役として登場する子役Wayne Pardueという太目の少年の仇名が「Super Genius」であるという設定から引用しているそうである。
これまたユーモア感覚があるというか、いまいち理解に苦しむネーミングの様子だが、Wayne Supergeniusのステイトにその答えが見出せる。
「僕達はこう考えている。名前というのは僕達の音楽について何ら語るものではないし、それが肝要なことさ。多分何かについてユーモアな感覚を有することの方が大事なことだと思う。」
とギタリストのJohn Fritcheyは語る。
つまるところ、名前なんて目立てばどんなものでもオッケーというような開き直りがあるように見受けられる。
「名前って何だろうか?僕達には分からないよ。僕達が最も集中しているのは音楽なんだから。」
とTony Ryderは述べている。
確かに、音楽として最大限の関心を払った結果、この「The Tonight Show」は素晴らしい作品になっている。しっかりと出来ることに最大の努力を投じた結果だろう。余分なプロモーションとかパフォーマンスでメディアに踊らされている猿回しのようなメジャーなヒットメイカーも是非に見習って欲しいものだ。
「このレコードを創るのに3年を費やしてしまった。良いレコードを創りたかったから。」
というTony Ryder氏のコメントを戴いているが、確かに1999年にデモ・トラックが11曲も存在したのに、フルアルバムがロールアウトしたのは2002年9月とほぼ満3年という期間がこの1枚につぎ込まれている。
しかしながら、当然何処ぞの大御所とは異なり、勿体付けて3年もアルバムを作成しなかったのではなく、クラブサーキットの合間にコツコツと良い曲を選りすぐってストックを増やしていたのである。
まずは、本作にもペダルスティールで参加しているSal Saundersを加えて、Wayne Supergenius(以下、WS)は5曲入りのデモを新たに作成する。
この2001年の音源が、Yayhoos関連ではお馴染みのEric Ambelの目に留まり、Ericから賞賛を受ける。Eric Ambelの人脈でVirgin Recordsの担当者、そして雑誌のレヴュアー等にもWSの存在が知られるようになり、直接の契約への援助とはならなかったが、バンドの評判を広げるのには大きな助力となった。また地方ラジオのDJもWSのファンとなったりして、WSはアルバムを作成する前から評判は地道であるが上昇していく。
筆者がこのバンドを知ったのは、当サイトでレヴューもしたCase 150のサイトを通じてである。John FritcheyはCase 150のEPに1曲だけだがエンジニア兼プロデューサーとして協力もしている。
そして、待望のフルレングス「The Tonight Show」の発売の運びと相成ったのが2002年である。
試聴リンクからDL可能な2曲の出来が相当なハイ・レヴェルであったため、新譜が何時出るかと期待していたのだが、不覚にもリリースを半月程見逃してしまった。大変失礼なことをしてしまった・・・・。
3年という期間を集約したかのようにアルバムに収録された曲数は15曲とかなりの多数になっている。正直10曲を大幅に越えるアルバムは良作でも中弛みする傾向があるのだが、WSのアルバムは全くそういった点を懸念する必要さえない。
捨て曲無し、全て1stクラス=極上のRoots Pop/Rockであるからだ。
Wayne Supergeniusは自身の音楽をAlt.Popと表現している。これはオルタナティヴ・ポップという最近頓に増えている、微量のポップ味をオルタナティヴという不味さに付け合せたロックチャートの主流とは全然違う。
Alt.Popが意味する内容は
「Not Quite Pop/Rock ,Not Quite Alt-Country」というものである。
“ポップ・ロックに突出しているのでもなく、ベッタリなオルタナ・カントリーでもない”と解釈すれば良かろう。
つまり、Pop/RockとAlt-Countryの中間にある音楽、と捉えることができる。言わずもがなであるけれど、「二兎を追う者は一兎を得ず」という良い所取りをしようとして結果「虻蜂獲らず」に失落なんぞしていない。両方の旨味を巧みに吸収したサウンドとして完成させている。
これは
Pop/RockとAlt-Countryの美点を均等に要しているサウンド。
と、決して誇大でなく言い切れる説得力がWSの音楽には存在している。
言わば、アメリカンルーツサウンドの1つの形では理想型である。
優しく、ポップで、そして厳しい冬の終わりを感じさせる暖かい春風のような柔らかさがどのナンバーにも流れているのである。それでいてアクースティックな繊細さを目立たせるのみならず、しっかりとロックンロールとしてのビートも過不足なく満たしてくれる。
極端にロックンロールに特化したナンバーは殆ど見られず、甘く爽やかなRoots Popと分類するのが最も適切な音楽性が中心となっているのだが、それ程極端にスローでレイドバックした作風を感じさせない。
また物凄いキャッチーさを全曲に渡って貫いているのだが、単調さを覚えることもない。普通あまりにポップ過ぎる曲が続き過ぎると、Emo/Punk Popのように凹凸の少ない1本棒の流れに集束し易い危険性が多いのだが。
これは偏に、ウルトラキャッチーなメロディを微妙なルーツの度合いで手代え品代え表現しているため、過剰とも言うべきポップさがどのナンバーでも活かされていること。
またアクーステックとエレクトリック楽器のバランスが均質さが保たれていること、更にSouthern Rockのズッシリした質量感はなくともロックビートを大地を噛むスパイクのようにしっかりと打ち付けているからロックンロールのエナジーを体感することができている。
それ故に、甘いアクースティックポップソングが中心になりがちなこの「The Tonight Show」がロック作品としての力強さを持ち得ているのだろう。CountryやHeartland Rockといった適切なメジャー感を含有しているルーツ・フレイヴァーもサウンドの浮き足を抑えるのに貢献し、明るく華やかなアルバムであるのだが、軽薄な印象は全くしない。
中庸的なRoots Rockとでしゃばり過ぎないPower Popの理想的な結婚がWSによって実現されたと思う。
物凄い高望みをするなら、もう少し羽目を外してブンブンなSouthern Rockのスウィング振りを発揮しても良かったと思うし、元気なロックチューンがもっと欲しかったが、それは別のタイプのルーツロックに求めた方が適当であることは理解している。
繰り返すが、この「The Tonight Show」はAcousitc/Roots/Popとしてのアメリカン・ロックとしては間違いなく最高峰を極めてしまっているからだ。
彼らが影響を受けたのは、Eagles、Burt Bacharach、Beatles、Rolling Stones、Gram Parsons、Jackson Browne、George Jones、Willie Nelson、Otis Redding、そしてモータウンソウルといったアメリカンロックや英国ロックの基本的なサウンドである。
これを独自のカントリーとルーツを混ぜて、調理している。しかもポップさでWSと並ぶバンドはこれらの大御所にもいないだろう。カントリーのコアとポップロックのセンスを結合した才能はBig Starや The Replacementsに比肩するという海外レヴューもあるが、この2つのバンドは、WSに比べれば屁こいてプ〜、程の詰まらないバンドだ。(をい)
全然、Wayne Supergeniusの勝ち。当サイトで紹介したPaging RaymondやThe Lucky Onesに共通する素敵なPop/Rock With Roots Relishというところだろう。が、よりスタンスの近いPaging Raymondよりもかなりレヴェルは上のバンドである、Pagingには悪いけれども。
「日曜の昼食に昇るオフクロの手作りミート・ローフのような、心地良い音楽。」という紹介文がまさにピッタリと当て嵌まるバンドでもある。
何時でも身近に置いておきたい。高い値段のする高級料理の豪勢さには劣るが、何時食してもどんな気分で味わっても常に美味しく戴けるサウンド。これがWSの身上だろう。
最後に、15曲について簡単に印象を述べて、長蛇化する駄文を締め括るとしよう。
#1『Lead Me Away』から#15『Without You』まで最高、で終わっても良いのだが、それでは書き手たる側が満足しないので、もう少しだけ書くことにする。
唯一のカヴァーは、何とEurythmicsの1983年のヒットナンバーである#13『Here Comes The Rain Again』。全然違った道を行くNew Wave/Synth Popの曲を取り上げるとは驚きだ。勿論、ペダルスティールを入れ、マシンビートやストリングス・シンセサイザーを外し、気怠いナード感をレイドバックに混ぜたルーツバラードにはアレンジしているが。
このカヴァーにSWの出自を幾許か見て取れるようにも思える。曲のクオリティを比較した場合、このカヴァーが最も程度が低い気がするのだが。(苦笑)
残りのナンバーはTony Ryderを中心としたメンバーとの共作。Tony Ryderが単独で書いているのは5曲。どちらのタイプも良作揃いである。
#1『Lead Me Away』はまさに、Wayne Supergeniusの中庸的なポップロックとルーツ・フィーリングを代表するナンバーだ。心地良いミディアム・テンポのロックがTony Ryderのハートウォーミングで包容力のあるヴォーカルに乗り、クルージングするルーツギターの音色がグルーヴィ。#6『Falling Down』も同じタイプのPop/Rockである。試聴リンクで全編通しで聴ける。こちらではペダルスティールが効果的に使用され、一層埃っぽいダウン・トゥ・アースさが演出されている。この#6が気に入れば、絶対に買いである、このアルバム。
#2『She’s Not That Lonely』は西海岸カントリーロックのようなMike PassarielloとTony Melchirreのバックコーラスが冴える爽やかなナンバーだ。ドラマーとしてバック・ヴォーカルを受け持つのは結構珍しいが、実に良いコーラスの仕事をしているし、ライヴでも再現可能なコーラスというのは貴重だ。
#2のようにペダルスティールを上手く使ってレイドバックなホンワカさを醸し出しているのが#4『Untie My Hands』である。このトラックでは、よりカントリーロックに近いアプローチを執っている。
#3『My Lover』ではコロコロと転がる高いキーを使ったピアノがトイ・ピアノのように響く、R&Bっぽいロックナンバーが聴ける。
#7『You And The Day』はフックのある泥臭いメロディがキャッチーに展開されるが、オルガンやバンジョーといったルーツさを増加される楽器のサポートが嬉しい。続く#8『Leading Into Anywhere』も同系統のスゥイートなポップナンバーである。ここまでポップでしかもアクースティックと土臭さが配分巧みになるには相当の曲の厳選がなされたに違いないと予想させてくれる。
やや、懐の深いダイナミズムとうねりをもった#9『How Do You Know?』ではBoogieなロックがポップにワルツを踊っている。何と言ってもオルガンの包容力が最高にスゥインギングである。
ツイスティで、オールディズやモータウンのジャンプ感をシンセサイザーを使ってダンスさせる#10『All For You』はかなり楽しげでお気楽なナンバー。ドラムの時折バタバタとした演奏やギターのチョッパーが、ヴォーカルのTonyの精一杯な歌とジャムを重ねる。
#12『Made Alive In You』は#5『Feel』や#15『Without You』のアクースティックで静謐な、ジワジワと心に侵入してくる様子のバラードとは異なり、より不透明な茫洋とした荒野に掛かる霞のようなモワっとした雰囲気があるルーツバラードである。西海岸の乾いたフィーリングと南部スワンプの緩さを併せたような感じの佳曲だ。
#5や#15に関してはそのピュアなアクースティックさ、そして広大な合衆国の大地の伝統を引き継ぐトラッド・フィーリングを淡々と歌い込めている。それに耳を傾けるのみだ。
#13『Rise』は、ミディアム・ファーストなWS得意のテンポで進むロックチューンだが、何処となくブルース的な黒っぽさを感じさせる。それ程強烈なものではなく、あくまでアーシーなロックリズムに見え隠れする程度であるが、その粘っこさが、かなりタイトなナンバーとして#13を仕上げている。
まるで、BeatlesやBeachboysのようなコーラスで始まる#14『Goodnight』も誠にWayne Supergeniusのポップなサウンド・クリエイションの才能を明確に示すナンバーである。線が細く見える軽めのアレンジで曲を纏めているが、しっかりと安定感があり、フラフラしない。曲にしっかりとメリハリが付いている。目立たずに鳴るマンドリンがもう心憎い。
どのナンバーでもそうだが、リード・ヴォーカルのTony Ryderのハイトーン・ヴォーカル、2名のリズムセクションのバックアップによるコーラス・パフォーマンスはヴェルヴェットな手触りを音に感じさせてくれる。
またラップスティールやマンドリン、バンジョーからシンセサイザーまで弾きこなすJohn Fritcheyの玄人な仕事振りも忘れてはいけない。
それにしても、このレヴェルにあるバンドが自主リリースというのはどうにも解せない。アクースティック・ポップとか呼ばれて日本で阿呆のように持て囃されているJohn Mayer等と比べて天と地というよりも天上界と煉獄くらいの差があるのだが。
きっとこのWayne Supergeniusが正式にレコード会社のプロモーションを通じて日本で売り出されれば、間違いなくBen Folds Fiveのような独自のヒットを記録すると思うのだ。このままインディで燻っているのは実に勿体無いとしか言い様がない。
これ読んだプロモーターやレコード会社の担当さんがいるなら是非、Wayne Supergeniusを取り上げて欲しい。
これまたThe KickbacksやCounting Crowsとは別のタイプのアメリカン・ロックだが、2002年度私的トップの候補になっているアルバムである。まあ、聴いてみれば分かる。というか聴け!!!!!! (2002.11.10.)
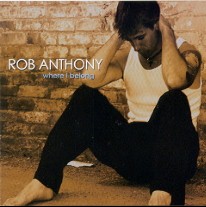 Where I Belong / Rob Anthony (2002)
Where I Belong / Rob Anthony (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Alt-Country ★★★★★
You Can Listen From Here
2001年の年末くらい、非常に底冷えのする日だったろうか、Rob Anthonyのオフィシャル・ホームページが突然消滅してしまったことを認識したのは。
かなりの長期にわたりアクセスが不可能になっていたが、細かい専門知識で恐縮だがついにサイトからPingも帰ってこなくなり、完全にサーバー上からサイトを消してしまったことが伺われた。
それに次いで、Robの情報がネット経由で全く手に入らなくなったのだ。こういった良質なロックヴォーカル・アーティストが突然活動を休止してしまうことは、イコール活動停止・終焉に繋がる場合がかなりの確率で起こりうる。
メジャーでそれなりの名声を得たミュージシャンが、充電期間と称して沈黙の時代に入るのとは訳が違うのだ。
その頃に発表されていたRob Anthonyのアルバムは2000年録音である「Hard To Believe」という9曲入りのフルレングス作のみだったが。
“Millennium Eagles with a touch of Mellencamp”というキャッチ・コピーで高い評価を受けた9曲入りという昨今のヴォリューム過剰の傾向からは相当収録ナンバーが控え目なRobのデヴューアルバム「Hard To Believe」はEaglesとかJohn Mellencampといったロッククラッシックなアーティストを引き合いに出すまでもなく、素晴らしいルーツ/オルタナカントリー・ロックのショウケースだった。
この1stアルバムのレヴューは筆者の不精で2002年にずれ込んでしまったが、Rob Anthonyの経歴も含めて掲載しているので参考にして頂ければ幸いである。
ということで、以前からコンタクトのあった期待のシンガーであったため、即座に問い合わせのメールを出した。彼のような才能もあり、ルックスにも恵まれているシンガーがこのまま消えるかもしれないという不安に押しつぶされてしまいそうだったからだ。
しかし、何の返事も戴けず、「もう駄目か・・・・・」とほぼ観念してしまった。
そして、Rob Anthonyというミュージシャンの存在が1枚のアルバムの中でしか知覚できずに、次第に印象が希薄になり始めた2002年の夏、7月に突如Robからメールが届いた。
これには驚いた。しっかりとアーティストとして健在であった事実も勿論驚愕の原因の1つであったけれども、半年以上前のこちらの一方的な問い合わせに答えてくれたことにである。
どうやら、演奏活動やツアーをほぼストップし、ネット関係からも距離を置いていた模様である。一種の充電期間とレコーディングに2002年の前半を振り分けていた様子が推察できる。
しかし、彼からのメールには「Hard To Believe」が試聴できるページが復活したこと、メーリング・リストの配給再開、2002年の8月か9月には2枚目のアルバムが発表できる予定であり、それに遭わせて新しいホームページも開設する予定、という非常にポジティヴな事項が並べられており、筆者を喜ばせた。
そして、2枚目のアルバム「Where I Belong」は公約をギリギリ守って、2002年の9月27日に米国で自主リリースされた。またもセルフ・プレスというのはどうにも納得がいかないが、まあ仕方ない。再び活発に才能あるシンガーが活動を開始したことを素直に称えることにする。
さて、彼の活動履歴については前アルバムのレヴューに当時出来るだけの範囲で記したので、ここでは簡単にだけ要点を述べて、前作レヴューで書き残した付加分のみ書き出すことにする。
Rob Anthonyはミネソタ州、ミルウォーキーの生まれ。1990年にLAのハードロック・レーベルに所属していたAcrophetというメタルバンドのギタリストとしてキャリアを開始している。
Acrophet解散後、そのヘヴィメタルグループのリードシンガーであった、Dave Baumannとバンドを結成し、Soul Cityというアクースティック・オルタナティヴのデュオとして活動を継続。RobのコメントではDays Of The Newのようにヘヴィでダークなアクースティックロックを暫し追及していたそうだ。
が、1995年くらいから、「自ら慣れ親しんだ音楽を見つめなおす。人が何時かは生まれ故郷へ帰っていくように。」という原点回帰路線に音楽性を変更する。Robは自ら「360度のターンを決めてRoots Rockへ立ち返った。」と述べているくらいに、全くの新境地に踏み込んだわけである。1998年には「Robert Anthony」という本名を題にしたシングルを作成し、ここで初めてカントリーやルーツのサウンドを発表した。
これまで所属していたフイールドである、ハードロック/ヘヴィメタルのバックボーンを1ミリグラムたりとも感じさせないアーシーで爽やかなPop/Rock作を2000年に録音し2001年にネット上で発売している。それが既に紹介した「Hard To Believe」であるのだ。
そして、今回の2枚目のフルアルバムである「Where I Belong」を2002年の大半を沈黙した末に発表し、再びミルウォーキー周辺で活発にライヴ活動を再開しているのが現状となっている。
前作でも10曲に満たない曲数だったが、今回は更に1曲少ない8曲の総トラック数となっている。しかし、2年弱で1桁曲数のヴォリュームのアルバムをコンスタントに出してくれる方が、4年に1枚くらいしかアルバムを発表しないよりも好ましいし、何よりもアーティストがどのような成長や変遷を遂げているのかが現在進行形で見られるので、こういう形で作品をコンスタントに出して貰えるのは歓迎だ。
是非とも、寡作が大物の証拠とか期間を空けて作成したアルバムは完成度が高いように見られると誤解している多くの有象無象は見習って欲しいものでもある。
タイトルは「Where I Belong」。前作に引き続いてRob Anthonyの自分を取り巻く環境に対するメッセージーと感じるのは読み過ぎだろうか。
前作では「Hard To Believe」と2枚ともアルバム収録の曲からタイトルを引用しているのは変わらない。
『Hard To Believe』という曲の歌詞は非常にステロタイプなラヴ・ソングであるのだが、タイトルとしてアルバムに冠した理由は、
「信じがたいかもしれないけど、信じて欲しい。僕がこのようなアメリカンルーツを選択したことを。」
と、Roots Rockに転向したことを強調して伝えるという暗喩があったような気がするのだ。
今回の「Where I Belong」はアルバムのスタートに位置するナンバーである。しかも歌詞の内容はどうもRobの自叙伝的なものが伺える。以下、歌詞の一部を切り取って訳してみる。
♪「僕が愛してきた都会について語ろう。僕の中にある、田舎の故郷を懐かしむ自分がたまに語りかける。
“これで良いのかな”と。オフクロは何時もこう言ったもだ。「生まれ故郷の小さな町こそ、本当の故郷
なんだからね。」と。
でも、僕は今住んでいるこの都会が『僕のいるべき場所』だと思っている。
僕はひとりでやっていけるようになってからこっち駆け足の人生を送ってきた。僕は田舎を17歳で飛び
出し、ひとりで強く生きていくことを学ばなければならなかった。でも親切な人に囲まれ、一度も孤独を
感じたことはなかった。
だから、現在、僕の心はこの都会に属している。
僕は都会に居を構え、この2本の足でしっかりと自活している。こういう生活が僕の可哀想なオフクロに
は出来ない事は分かるさ。オフクロが望んでいた“小さな町で暮らす息子”はいなくなってしまった。
でも、僕は決して忘れないよ、僕が何処から来たのかは。あの田舎のちっぽけな町からね。
でも僕の属すべき場所はこの都会なんだ。」♪
という故郷を離れてしまって、落ち着く場所が出来た−第二の故郷を見出したことへの喜びを歌っているのだが、これは「今追い求めている音楽が、『僕にとっての属する場所』なんだ。つまりルーツやカントリーというロックが僕のやるべきことなんだ。」
という決意を表明したタイトルのような気がする。そして、最初にやっていたことも忘れない、という意志は、Robが2001年にプログレッシヴハードコアバンドのOnebodytoomanyというプロジェクトにギタリストとして参加するというような形で補填していると考えられる。
という筆者の曲解の疑いが濃厚なタイトル「Where I Belong」だが、サウンド的には予想と期待を大きく裏切るものではなく、堅実にデヴュー・フルレングスで示した才能を表わしている。
まさに、「現在、Rob Anthonyが存在する音楽という世界の中での場所」を表わしたアルバムであると思う。
アクースティックで、物凄いキャッチー。そしてアーシーであり、70年代西海岸カントリー・ロックを彷彿とさせる−まさにEaglesの初期から中期を思わせる基本形は不動である。
またベース、ギター、ドラムが基本というシンプルな演奏構成も、プロデューサーも前作と同じ。
が、厳密には幾つかの変化と冒険を目立たない形で行っているようでもある。大元の根っこの音楽性は変わっていないが、1stとはやや毛色の違ったルーツサウンドになっていることも見て取れる。それは何だろうか。
第一に、使用している楽器に若干の付け加えが見られる。前作では全く使われなかったヴァイオリンがかなりのナンバーで使用されている。カントリー・フィドルというベタベタなカントリーのドライさはない。クレジットにもフィドルではなく、アクースティック&エレクトリック・ヴァイオリンとなっているし。
第ニに、Acrophetからの盟友であるヴォーカリストのDave Baumannが前作ではレコーディングには半数ほどの曲に参加していただけだが、今回のアルバムではRob Anthony Bandの一員として正式に全てのトラックでヴォーカルとベースを担当。Soul City時代のコンビに戻っている。
第一の弦楽器の導入によって、アクースティックで爽やかな土臭さが一番の強みであった前作の西海岸サウンドを連想させる要素がやや後退している。ウエスト・コーストロックというよりもポップでアクースティックなオルタナカントリーの要素の方が割合を多くしている。もっとも、西海岸ロックらしい清涼感は未だ健在であるが。
#2『Is There A Page』は1970年のカントリーロックをより現代的なポップアレンジでアクースティックに纏めた感じであり、Andrew Goldの1980年代から90年代のソロワークを近くに感じれるドラムのリズムが心地良い16ビートロックになっている。この#3は前作の雰囲気を最も濃厚に引き継いでいるナンバーだ。
逆にヴァイオリンの音色により、よりセントラル・アメリカ的なグラスルーツさが装填されているのが、タイトルにしてオープニングナンバーの#1『Where I Belong』である。非常にパワフルなリズムパートで引っ張られていくナンバーであるのだが、牧歌的なヴァイオリンによって、良い意味で緊張感が抜けて親しみ易いナンバーとなっている。
#4『We All Need』も少々哀愁を帯びたヴァイオリンの弦が、何処となく甘悲しげなメロディを胸に植え付ける曲を更に滑るような流れにすることに一役買っている。ストリングス抜きでも甘酸っぱいルーツなバラードになっただろうけど、こういった楽器の数が増えたことでもっと曲の多様性が浮き立つことを確かめられる。
第二に、Daveが全面的に演奏に加わったことで、笑顔で爽やか印のコーラスが更に強化されている。また、今回はDaveは曲を書いていないが(前作では1曲ライティングしている。)、彼の全面協力によって、演奏のロックサイドが加速されたのだろうか。嘗てのヘヴィメタルバンドのデュオがコアとなったRob Anthony Bandの曲は、以前よりもロックンロールしているものが多い。Daveの協力がRobの書く曲をよりロックビートに傾いたものにする手助けをしたように思えてならない。
それは「Hard To Believe」でDaveの参加したナンバーが全てアルバムの中ではアップテンポに属するトラックであったことから導き出した推論だが、あながち間違いではないと考えている。
#3『All Do Is Think Of You』は、Rob Anthonyの代表格ともいえる、心地良いアップビートが弾みながら青空に溶けていくような極上西海岸風ポップロックであるが、この速さがもう少し遅くなるとやや大人し過ぎるナンバーになるところで、DaveとRobのロックコンビの握手によってそうなる危険性を回避できたのではないか。
よりロックとしての存在感を増やしているのが、#5『Perfect Day』や#6『Believe In Me』である。
#5『Perfect Day』は俗に言う“Red Dart Sound”的な土に塗れたウェザリング感覚があるナンバーで、こういった骨太さがかなり意外に聞こえてしまう。Rob Anthonyはもっと繊細に爪弾かれるギター弦の爽やかロックの連続と予想していたからだ。が、しっかりとポップさをダーティなアレンジの中にも取り入れているので、浮いている感じはない。
#6『Believe In Me』はペシペシとスネアドラムがリフレインして、ライヴ感溢れるSouthern Rockの気配が濃厚なロックナンバーだ。Dave Baumannのハーモニー・ヴォーカルやバックコーラスの掛け合いもスライドな雰囲気の曲を適度にラフにする相乗効果となっている。
#7『I Should Have Known』もRob Anthonyの1stアルバムのハンサム・フェイスを象徴するような、白い歯が光そうに凜とした涼風が吹きぬけるような、上昇気流ナンバーであるけれど、微妙にメロディのラインが太くなっている箇所が感じられる。#2と比べても全く落ちることのないウエスト・コースト的なルーツロックナンバーなのだが、まるでDon Felder加入後の「On The Border」と「Desperado」の差を感じるような格差が前作の爽やか君ナンバーと比較すると滲み出ている。
ロックに進化していること、これであろう。それは#8『Waiting For You』のパワフルなアンサンブルとかなりエレクトリックなルーツギターの音色でも判別が付くだろう。このナンバーも甘さを控え目にしてロックンロールの重さを加えてみました的なロックチューンである。
タフな男臭さが、キャッチーな進行のナンバーで表現されているところは、よりダートな#5や#6よりもRob Anthonyがロックンロールなルーツ/オルタナカントリーへ歩んでいこうとしていることが浮き彫りになっている。
しかし、もしかしたらこのまま噂も聞けなくなってしまうかと危惧したシンガーが再び期待通りの作品を届けてくれたのは実に貴重だ。ヴォーカリストとしても甘さと強さ、そして渋さを同時に表現できる力量がある。Tom PettyやJohn Mellencamp、Randy Misnerといった歌い手の良い所だけ切り取って集めたような、凄いヴォーカリストであるから、このまま終わって欲しくないと願っていたので更に嬉しい。
「Where I Belong」=「僕が、今ここに居る場所」をしっかりと2本の足で定めたRobが堅実でありながら、着実に進歩しつつある己のやりたいことをさり気なく取り込んでいるこのアルバムは、Robの確かな地歩の固めを感じ取れる要素てんこもりである。
まず、期待ハズレはないので、1stが気に入ったリスナーや懐かしのオールド西海岸が好きなリスナーは、まず聴いてみることだ。1stアルバムは長らく品切れだったが、この度またAmazon.comに並んでいる。こういった点でもRobの活動の順当さが伺えてまた喜んだりしているのだ。 (2002.11.13.)
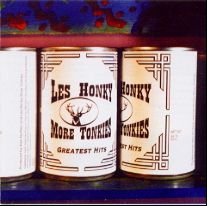 Greatest Hits / Les Honky More Tonkies (2002)
Greatest Hits / Les Honky More Tonkies (2002)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Southern&Country ★★★★
You Can Listen From Here
「Greatest Hits」というタイトルにすること自体で非常に冗談のエッセンスが強烈である。
何故かというと・・・・・・。
一般にメジャーのバンドでない限り、ベストアルバムに「Greatest Hits」と銘を打ち付けることは不文律で禁じ手になっているような空気が音楽界には存在するようである。無論、禁忌ではないけれども。「Greatest Hits」の名前に負けないようなヒット曲のショウケースにならないようなベスト盤には、やはり恥ずかしくて「偉大なヒット集」というネーミングはし辛いのだろう。
しかし、Les Honky More Tonkiesという、「どうすればHonkyを減らして、Tonkiesを増やせば良いんだ?」とマトモに考えると頭を抱えてしまいそうなサウンドスタイルを名前にしたグループ−かなりヒトを喰った名前のバンドは、堂々と「Greatest Hits」とタイトルされたアルバムを作成した。しかも、これまでの活動を総括したアルバムを出したからベスト盤の名前を付けているという常識さえ凌駕している。
というのは、このLes Honky More Tonkiesというグループ、これまでに1枚もアルバムをリリースしていない。この「Greatest Hits」が正真正銘最初の作品になっている。
つまり、第1作目から「偉大なヒット集」と銘打ってアルバムを発表するというトンデモナイ冗談をやっているのだ!
かなり大風呂敷を広げているのか、それともとことんスチャラカな冗談一直線を突き進んでいるのか、少々判断をすることは難しいところであるけれども。それは後述するが、音楽性までを加味した場合のことに限定されるが。名前とかアルバムタイトルに限れば、明らかにイロモノ扱いを意図して実行しているとしか思えない。
まあ、こういう阿保さ加減は筆者としては嫌いではないので、ドンドコとやってくれて構わないけれども。
実際、知名度はお世辞にも高いバンドではないので、これまでにマイナー・シーンで幾枚かのアルバムを発表してきた活動成果の集大成としてのベストアルバムと受け取ってくれるリスナーもいないではないかもしれない。無名故の知名度の低さから、そう解釈される幸運もあるかもしれない。
しかし、無名故にこのアルバムの存在を知るまでに行き着かないリスナーの方が更に大多数を占めるだろうことは想像に難くない。だが、その零細さあってこそ、Les Honky More Tonkiesという冗談のようなバンド名や、1stアルバムから「Greatest Hits」というタイトルを付けたジョークが出来るのだろうけど。
さて、彼らの音楽に付いて語る前に、まずLes Honky More Tonkiesというバンドについて経歴を紹介しておきたい・・・・・のだが、これまた全く資料が揃わないバンドである。試聴リンクから飛べるオフィシャル・ホームページは存在するのだが、マトモなバンドの情報は殆ど皆無であり、他の情報も殆ど似たり寄ったりである。
活動のコアは1998年まで遡る。ギタリスト兼ヴォーカリストのJohnny PyroとドラマーのJoey Lonzoが沢山の友人のシンガーやソングライターを交えてセッションを行ったことから偶発的にスタートしている。つまり、ギターのJonnyとドラムのJoeyにテンポラリーでメンバーが加わると言うセッションバンドであったのだ。
しかし、一時的なグループであった筈のLes Honky More Tonkiesであるが、2人がシンガーのLes Honkyと出会った時から本格的なロックバンドとしての歩みを始めることとなる。
最初のギグでは10名くらいの観客、しかも殆どが関係者だけという寂しい出発であったが、2002年までの4年間に次第にナッシュヴィルを中心としてテキサスとその周辺の州を精力的にツアーを行った結果、かなりの人気をローカルで獲得する。2000年にはベースとピアノを担当するBird Dawgが「この連中はどれだけ酷い奴等と分かっていたけど、バンドに誘われた時にOKしたんだ。」といいながら加入。そして、テネシー出身のギタリストPete Goatroperが5人目のメンバーとして参加、現在の編成となっている。
主にナッシュヴィルのExit/InやHot Houseというその手のファンにはお馴染みのハコでライヴを行うことが多い様子であるけれども、ノースキャロライナ、テキサスといった周辺の州にも出没している模様である。
これまでに、かなりのメジャーバンドやアーティストの前座としても起用されている。それも単にルーツ系のアーティストに留まっていないのが興味深い。
カントリーやカントリーロック系では、Travis Tritt、Hank Williams Jr.、Trent SummerそしてMontgomery Gentry。オルタナカントリーでもV-Roys、Jack Ingram。サザンハードロックのLynard Skynard。
そして文句ナシのアメリカンロックの大将、Counting Crows。とここまではまあそれ程違和感のあるコラボレーションではないが、ラップメタルバンドのIncubus、オルタナティヴ・ポップロックのNo Doubt、そしてプログレッシヴ・ロックのJethro Tullのリユニオンにまで起用されている。
彼らの音楽は、No Doubtは兎も角として、プログレッシヴやラップメタルまでをカヴァーし切れては到底いないのだが、余程座を盛り上げるフロントアクターとしての評判がナッシュヴィルでは高いのかもしれない。
と、メジャーシーンや本邦では問題外として、そこそこ人気のあるマイナー・バンドとして頭角を表わしているのに、このバンドについてはまだ謎が多い。
バンドのソングライターであるが、2曲の外部ライターの作品を除いた8曲が殆どJonny Mark Millerという男のペンに拠って書かれているのだが、この人物が誰かもハッキリしない。完全に芸名であるヴォーカルのLes Honkyが本名で曲を書いているという可能性が1つ。これはハードロックのバンドでたまに見られるのであり得る。
または、ギタリストである中核メンバーのJonny Pyroのライティング・ネームがJonny Mark Millerという線もなきにしもあらずだ。恐らくどちらかであるとは思うが、微量の可能性として外部ライターがバンド外から協力しているということもあるかもしれない。(こういったバンドではまず有り得ないとは思うが。)
次に、Les Honky More Tonkies(以下、LHMTとする)の音楽性について触れておこう。
最初に、彼らの紹介の文にある一説を引用してみることにする。
「以下の音楽を探し続けているファンに最適。Motley Crueのような剛直なロック。そしてMoe Bandyのようなパフォーマンスを超えるバンド。他に表現のし様があるだろうか・・・・。
Black Oak Arkansas以来のワイルドで野蛮な連中である。」
Moe Bandyはホンキィ・トンク/カントリーの大御所。Black Oak Arkansasは1970年代に主に活動していたサザンロックのハードとディープさを売りにするバンド。Motley Crueについては説明する必要はないだろう。
確かに、Black Oak Arkansasの泥臭くて、カチンカチンに固いハードサザンのフィーリング、そしてそれでいてアーシーでポップな面もあるメジャー感覚を継承していると思う。
そしてMoe Bandyのホンキィ・トンクなカントリーな音質も同時にLHMTは有しているので、この2つのバンドを例えに用いているのは的を得ていると思う。が、正直Motley Crueは少々違い過ぎる点が多いのではないだろうか。
野蛮で下品で、ノイジーというハードロックの汚い面を強調した権化のようなMotley Crueは確かに南部ロックやブルースを感じさせることもあるけれども、所詮はハードロックである。
LHMT程にサザンでルーツでカントリーを音楽的には選択していない。恐らく、それだけロックンロールに没頭しているという表明程度に引用しているのだと思っていたのだが、インナーに辞書を捩った解説が付けられている。
以下、国語辞典的に訳してみると
Motleycruegrass (モトリークルーグラス)[名詞]
1:普遍的なロックンロール、カントリー、ブルーグラスをホンキィ且つ暴力的なスタイルにした結果。
2:マイナーなナッシュヴィルのバンド、Les Honky More Tonkies専売特許の音楽スタイルのこと。
としている。かなりMotley Crueの音楽性に拘りがあると見える。が、繰り返すが、そこまでダークでもダーティでもノイジーでもない。ロックであると言う点は幾らか近いところもあるけれど。
“Mix Of Dank Southern Rock And Econoline Country”という説明も見られるけれど、Southern Rockのハードな側面は見せるが、ダークな陰鬱性は皆無に等しい。そもそも、本来Honky-Tonkの意味は安酒場や安キャバレーというもの。そういった場所で叩かれていた酒場ピアノの演奏スタイルを指すようになり、長じて音楽のスタイルとして広まったものだが、低俗性を語源にする単語を更に冗談に変換した名前を冠するバンドが暗いヘヴィサウンドをひたすら演奏していたのでは、どうにも雰囲気が合わないだろうし。
筆者的には、LHMTの音楽性は以下のように捉えている。
Georgia SatellitesのようなタフでキャッチーでハードなSouthern Rockに、Son VoltやJason And The Scorchers的なCountryの要素を加味して更に野暮ったくしたもの。
特別に思い入れがあるから、Georgia Satellitesを比較に挙げているのではない。如何にもGeorgia Satellitesを思わせる姿勢がインナーに記されているからである。一部抜粋してみよう。
「これらのサウンドは丁寧に創られているけど、LHMTのメンバーの持ち物である1インチアナログテープレコーダーで録音してある。プロフェッショナルが使用すべき器具や修正を行えるデバイス等のレコーディングを改善するような存在は一切使われていない。これ本当。本当のこと。凄いだろう。」
とデジタル録音が主流になってきた時代に3枚目のアルバムまでデジタル録音を行わなかったGeorgia Satellitesに類似した箇所を思い出させるのだ。
LHMTは確かに、ソフトとは口が裂けても言えないバーバリックなロックンロールを演奏するバンドである。その垢抜けの無さとバラバラとした乱雑さは、Southern Rockの典型である。確かにBlack Oak Arkansasの再来と評価されるだけのことはある。
が、しっかりとポップなツボは押さえているナンバーが殆どであり、ハードでダークでダートだけで突っ走ることだけしか出来ない一般のサザン・ハードロックのバンドとは違う。
更に、Georgia Satellitesでは窺えないCountry RockやCow Punk、要するにウエスタン/カントリーを明け透けに投げつけるナンバーが何曲か取り入れられており、その点はJason And The Scorchers等のカントリーが強烈なロック/パンクバンドのダサダサな側面を表わしている。
Georgia SatellitesにしてもBlack Oak Arkansasにしても整理されたとか流暢でスムーズという音楽性とは程遠かったがメジャーシーンで活躍することを可能にさせたメインストリームなアメリカン・ルーツテイストとコマーシャルさを有していたが、このLHMTも同様である。
弾けっぷりと言う点ではGeorgia Satellitesには及ばない所はあるし、渋いダークさと言う点ではBlack Oak ArkansasやLynard Skynardに伍するところまでも達していないけれども、サザンルーツとキャッチーなポップセンスとハードなロックンロールの核が上手くブレンドされた好盤である。
ハードなフィーリングはThe Four Horsemenの1作目やThe Black Crowesの2作目「The Southern Harmony And Musical Campanion」にも通じるところがあるだろうか。これらのアルバムよりも、お気楽なカントリーの要素がやや浮き出している作風であるけれども。それこそ、Honky-Tonk『極楽蜻蛉』の面目が立つというものだろうけれど。
あ、Les Honkyだったかな・・・・・・。
まず、アルバムはかなり親しい付き合いをしている同郷のシンガーソングライター、Scotty Melton作の#1『Now That I’m Happy』で幕を開ける。Scottyはフォーキィなトラッドソングを弾き語りスタイルで歌うルーツシンガーなのだが、このナンバーはそこそこワイルドであり、そこそこドライヴ感があり、物凄いポップなサザンスタイルのPop/Rockに仕上がっている。冒頭に外部ライターの歌を持ってきたのも驚きだが、アクースティックシンガーだと分類していたScotty Meltonがこのようなロックナンバーを書いたのにはもっと驚愕した。
#2『Cheatham Co.Line』ではオープニングではゆとりをもってシャガレ声を伸ばしていたLes Honkyが一転してシャウトする軽快なカントリー・パンクタッチのハードロックンロール。Dan Baird主導のThe Yayhoosが好んで取り上げそうな“Country Painted Satellites”という造語を与えたくなるようなナンバーでもある。超絶にアップビートなリズムとガチャガチャの演奏が滅茶苦茶ロックンロール。
#3『Amy』は完全なCountryナンバーである。#2はHard Countryとも表現できそうなロックチューンだったが、こちらはモロにウエスタン/サザンというカウボーイなナンバーである。勿論アップテンポであるのだけれども、ここまで直接なカントリーを聴かされるとは予想しなかった。トラッドや土臭い面を頭の2曲でゴンと投げ下ろしているので、そちらのロックンロール路線で続くと思っていたのだが。
が、次でまたハードな南部ロックに戻る。#4『(You Don’t)Call Me Honey』は酔いどれロックンロールという表現がベストであるだろう。ヤケクソ気味にダルなコーラスに泥臭いギターのアレンジ。ハンドクラップも含めた、ゴツゴツとした曲感。ハードさとアーシーさが粗雑なロックのリズムに非常にマッチしている。然れども、十分にキャッチーであるから聴き易い。
#5『Victim And The Fool』はややゆったりとした大地の広がりが瞼に浮かんでくるようなミディアムなナンバー。かなりトーンダウンして歌うLes Honkyのヴォーカルは少し物足りなさそうでエネルギーのはけ口を求めているようなきらいもあるけど、対してスライドギターとギターの2本のアンサンブルは自在に弾きまくっている。バラード未満、ロック以下というナンバーだが、このスライドする感覚は絶妙だ。
唯一のカヴァーナンバーであるのが、#6『Smoky Mountain Rain』。これはカントリー界のスターで70年代や80年代にはポップヒットも排出しているRonnie Milsapが1981年にカントリー・チャートでNo.1ヒットさせた曲である。寂しげなギターで始まる、カントリーそのまんまという冒頭からダイナミックに進行していくロックンロールな後半部分との温度差が感動的である。LHMTは原曲の雰囲気を壊さずに、よりコンテンポラリーなロッカバラードに仕上げている。
このナンバーではハスキー気味な歌い方をするLes HonkyとJohnnyとBirdのバックコーラス隊との掛け合いが上手く作用している。
曲名通りのリズムとビートで疾走するのが#7『Dirty Hot』。キャッチーであるのだが、エフェクタ-を通してシャウト以上のガラガラ声を演出し、終始パンキッシュに進む。しかし、ここまでヴォーカルに処理を加えなくても十分に豪快なロックの魂が熱く転がっているのだから、しっかりと歌って欲しかった。メロディはかなり良いのである。スピーディだけども重厚な安定感があって。
#8『Mary Please』は再度カントリー的な牧草ソングを狙ったナンバーだ。アルバム後半はこの曲以外は物凄いラフなトラックが攻勢を掛けて来るので、息抜き的なマッタリさが強調されている。このサザンロックとトラッド的なカントリーナンバーの差が大きいところがLHMTの特徴だろう。
思いっきりオールディズ風のBoogie Rockを演奏しているのが#9『Ain’t Gotta Go Home』である。ヴォーカルが取れる人間とゲストヴォーカルがお気楽にザラリとしたコーラスを歌い、ガラスの割れるSEまでもいれたドラム。曲のタイトルをひたすらシャウトとコーラスでバトルさせながら、ハード一辺倒に泥々とマッディに叩き付けられるインプロヴィゼーション。南部ロックのクラシカルでワイルドなR&B風味を凝縮したような暴れん坊ナンバーである。然れども、これまたキャッチーである。そんなところもオール・ディズっぽい。
そして最もハードで、ダークなメロディをウネウネとハードに綴るのが、#10『Black Cadillac』である。スローなリズムだがズンズンと腹に響くようなハードパンチのある前半部から、一転してハード&スピードロックに暴発する後半。4分に満たないくらいのナンバーなのだが、奇妙に長く感じるのはその粘っこさのためだろうか。
Motley Crueに対してそのハードさに憧憬のようなものを持っていることは前述したが、このくらいダーティなロックンロールになると確かにMotleycuregrassと新語を辞書に加えるという遊びをしているのに頷ける。
しかし、8曲目までは比較的真摯で正当なサザンロックのバンドという印象が強いが、最後の2曲の1本抜けた羽目の外し方を聴くと、確かにバンド名や処女作に「Greatest Hits」とタイトルしてしまう茶目っ気があるバンドであることを理解できるように思えるのだ。
録音にはアナログのテープレコーダーを使い、プロデュースやミキシングも極力少ない人数で賄っているいる割には、ジャケットは小技が効いている。というよりも細かいところに拘りがあるようだ。
缶ジュースらしき意匠を施したものに自らのバンド名とタイトルを貼り、裏のジャケットでは普通なら内容成分の表示に当たる箇所に曲目を並べ、含有成分のパーセンテージの欄には演奏時間を宛てるということをしている。
が、一部は故意にか原版となった飲料の表示が残されており、カルシウム33%、ビタミンA3%ビタミンC8%、カリウム15%となっている。ついでにカロリーは1016キロカロリー。相当な濃い飲料または液体調味料らしい。
確かに濃厚なサザンロックとカントリーの土臭さを同時に満たしているアルバムである。ハードさが売りのロックンロールでもここまでキャッチーに彩りを加えてくれると相当に親しみ易い。
パワフルな南部サウンドが好みなら聴いて損はないと思う。
確かに、これで「Greatest Hits」というのは風呂敷を広げ過ぎだとは思うけれど、確かにSouthern Rockの基本形は相当に盛り込まれているので、このアルバムがLHMTの数枚の作品からピックしたベスト盤と事前情報がなければ納得するリスナーもいるだろう。ヒットはしていないけれどもね・・・・。 (2002.11.19.)

 Blindside View / The Kickbacks (2002)
Blindside View / The Kickbacks (2002)