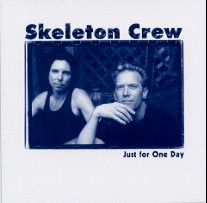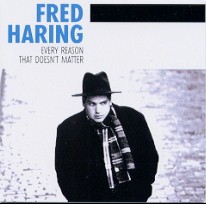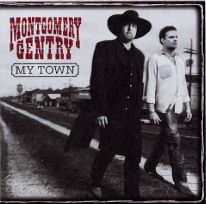Love Note / Big Silver (2002)
Love Note / Big Silver (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Americana ★★ You Can Listen From Here
Special Thanx To All Gentlmen Of Big Silver
まあ、一言で賞賛すれば、
マイナー・シーンのCounting Crows。
セールスの実績だけ足りないHootie And The Blowfish級。これらメジャーバンドに肩を並べる本格派Pop/Rock !!(一言でないやんけ・・・)
傑作、しかも生半可な良作ではなく手放しで褒め称えた名盤を直前作で届けてくれたアーティストの新作というのは、ある意味取り扱い要注意の爆弾である。
傑作以上、所謂名盤を発表したアーティストが、その次に世に出す作品は非常に厳しい条件での受け入れ態勢が取られてしまうことは当たり前である。というか、一度大傑作を作ってしまうと、それがアルバムにせよシングル曲にせよ、ある程度の軛(くびき)になることは有名税みたいなものだろう。
ファンとしては、当然「次もあのようなアルバムを。」と期待するのは当然だからだ。
が、音楽性の傾向は別として、同系等の音楽性で傑作を連続で届けてくれるアーティストというのは非常に少ないというのが大勢ではないかと思う。何故か、名盤が続くことというのは稀にしか起こらない。
名盤のネクステージが「そこそこ」だったり「まあまあ」のレヴェルに留まると、名盤より等水準以上を期待するリスナーの耳には非常に不満足な音として入ってしまう傾向が大だからである。普通なら許容できる良作でも、名盤の直後作と言うのは過大な期待のためにどうしてもハードルが高くなる故に。
よって容易に不満という雷管に衝撃が与えられ、酷評や期待ハズレという爆弾が炸裂し易いのだ。
殊に、日陰者扱いされていたミュージシャンが、傑作を創作しついでにメジャーでセールス的に成功した場合は、期待過多とミュージシャン本人の考え過ぎかヒネリ過ぎかは定かではないが、
「名盤の後に名盤無し」と断言できるくらい酷い作品が届くことが多い。
やはり、この傾向を後押ししているのは、セールスと批評家連中の評価というプレッシャーに負けたり、落ちる人が多いという事実だろう。
勿論、例外的に爆発的な売上を記録しつつも、しっかりと作品のクオリティを維持しているCounting CrowsやHootie And The Blowfishのような稀有な場合もないことはない。が、滅多にないことだからこそ、こういったメジャーバンドが目立つのだ。通常、そうそうメジャーシーンで傑作は続かない。
インディやマイナー・シーンではやや話が異なり、全く名前は売れないのに物凄いアルバムを連発しているアーティストはそこそこ存在することを誰も知らなくても、少なくとも文責は知っている。
今回、2001年のデヴュー盤「Big Silver」に続き、2枚目の「Love Note」を発表したアーカンソー州発のバンド、Big Silverはその筆頭格である。まだ2枚しかアルバムをリリースしていないため、2連続の傑作をリリースと述べるのが正確なのだろうが、この2枚のクオリティでこのバンドの将来性は1世紀以上の期間で筆者が保証する。
思うに、マイナー・リーグではセールスを上げなくてはならないとか、大型音楽雑誌の★印が沢山付かないと格好がつかないという俗事の柵(しがらみ)からかなり距離を置けることも、良作の連続という成果に一役買っていることは確かだ。しかし、バンドの台所事情はなかなか暖まらないため、活動が継続できなくなるケースが現実問題として横たわっているという別の問題もまた存在するのだが・・・・・。
それは兎も角、Big Silverの新譜は、筆者の過大な期待を何ら裏切ることのない出来である。唯でさえ、傑作の後盤には人一倍の希望を抱く性癖のある文責である。これが期待を外そうものなら、さっさとCDを部屋の隅に積み上げて、ミュージシャンに批判のメールをとっとと書くこと、またクソだのアホだのボケ茄子だの見苦しい罵詈雑言を叩き付ける批判家である。
が、このバンドには無条件降伏である。先年にレヴューをした1stアルバムは、枚数合わせに購入したものであり、期待を全くしていなかったため、初めてアルバムを耳にした時はその出来の良さに思わず膝を正した程である。
しかし、Big Silverのサウンドの魔力は一回聴いた後からが本番なのである。物凄く表現が難しく微妙な要素があるために、後から分析にならない分析をするつもりだが、兎に角、聴けば聴くにつれてその良さが増すのである。
一聴して、いまいちと思ったリスナーでも数回プレイヤーでフルに回転させれば、まずその魅力の虜になること請け合いである。
本作「Love Note」も基本的なキャプチャーのされ方は全く同様だったりする。詰まる所、聴けば聴いた回数だけ良くなるというアルバムである。
しかし、微妙なところで1stから進歩を見せていると感じてはいる。これからBig Silverの2ndアルバムの各曲について思うところを述べながら、1stとの差異や共通した点、それらの持つ魅力等に付いて語っていくとしよう。
1stアルバムのオープニングトラック『The Secret』がピアニストShelby Smithのピアノのひと撫でで始まる重量感溢れる骨太なロックチューンだったのに大して、2枚目の始まり#1『Moment』はドラムだけでなくアコーディオンやマンドリンも担当する器用なドラマー、Bart Angelのリズミカルなタッピング・ドラムで始まる軽快なPop/Rock。
いきなりなロックチューンで畳み掛けてきたファースト作よりも落ち着きを感じると共に、良い意味での器用さをバンドが身に付け、新しい音楽性にチャレンジしている意気込みが見えるナンバーだ。カラカラに乾いたドライなルーツナンバーではなく、Shelbyのウエットなオルガンが暖色系のカラーを音符の間に漂わせるようなPower Popを感じさせるナンバーである。何処となくBig Starのナンバーやバンドが最も影響を受けているというElvis Costelloの少しブリティッシュ風味の入った然れどもフワフワとしたポップナンバーを思わせる。
また、半音階ずつ変調させながら軽々と進むファーストヴァースから、Brad Williamの伸び伸びとしたギターワークが冴えるソロパートを通し、最後の部分ではヘヴィなギターがブイブイ言わせる泥臭いスローになる寸前なテンポで終るという演出にも曲創りの多彩さを見せてくれる。
歌としては「Love Note」というタイトルを裏付けるような、愛憎劇を題材にしたものである。お互いに不誠実で、お互いにちゃんと分かり合ったのが「数瞬」だけという関係の別れをサバサバと歌っている。
次いで#2『Love To Hate』に流れていくのだが、これまた1stアルバムとは対を成すような流れ。ラフなロック『The Secret』からゆったりした『Nothing I Can Do』への落ち込みが絶妙だった「Big Silver」とは正反対。
ややホンワカしたオープングナンバーを重厚なラストブリッジで締め括ったその後すぐに、明るいカラフルなキーボードの旋律が印象的なストレート・トゥ・ロックンロールという名称しか与えられない#2がグワっという擬音が入るかのごとく疾走を開始する。
スピーディなロックチューンである上に、歌詞の♪「One Two Three Four....Five Six Seven Eight...」というカウンディングが更に歌詞と曲の語呂を円滑にしている。
これまた、愛について述懐した歌詞である。お互いに憎みあうことが好きだった頃がどんなに酷くケイオティックな生活だったか思い出してみろよ、という若かりし頃の盲目さを語っているような内容だが、これを歌うにはBig Silverはまだ若過ぎるといらぬ心配をしたりもする。
2分少々とアルバムでも最も短いナンバーだが、終了間際のピアノサンプリングの乱れ弾きといい、少し鼻に掛かったようなIsaac Alexanderのヴォーカルといい、聴き所は満点なナンバーである。
この最初の2曲だけを聴くと、やはり
「ああ、これこそBig Silver」のトラックだなあ。」と深く頷いてしまう。それは、物凄いキャッチーな曲を創るのに、どこか英国的なヒネリ具合があるため、即効性が高そうで意外に地味に耳に入ってしまうIsaacを中心としたBig Silver独特の作風である。
あまりポップ過ぎると聴き飽きが早かったり単調なエモやパンクポップのようなポップなことだけしか心に残留しない浅薄な組み立てになってしまうが、Big Silverの場合この点が絶妙というか天然に独特なのだ。
かなりポップなのに、どこかしらビター、ほろ苦さが微量にではあるが要所要所に降り掛けられている。このためにしつこさのないマンモス・キャッチーなメロディラインを創造することに成功しているが、反面地味なナンバーとして最初は聴こえてしまうというマイナス(にならないかもしれない)面を有している。
この点が、上で少し言及した「聴けば聴くほどにハマル」サウンドたる所以なのだ。鯣(スルメ)と捉えてしまうほどには枯れきっていないが、食べ飽きない食堂の定食料理のような安心感が詰まっている。全く構えずに味わえる貴重だが、それを気づかせない曲創り。これがBig Silverの一番の魅力だろう。
即効性がありそうで、なさそうで、ありそうで、なさそうで・・・・・結局は凄くハマルのが結論だが。(笑)
デヴュー作でもレイドバックしたナンバーを幾曲か取り入れていたBig Silverだが、2ndではカントリーへの傾倒を若干強めたようにも見受けられる。1stでもペダルスティールギターでゲスト参加していたBrianの叔父Ken Williamsが今回も唯一のゲストとしてペダルスティールを弾いている。
モロにHootie And The Blowfishのレイドバック・ナンバーを連想してしまう、ブギーな南部風ロッカバラード#3『The Slowdance』ではコロコロ転がるピアノとブンブン唸るKevin Bennetのベースのユニゾンが曲のタイトルのようなダンスを踊っている。それ程スローではないのだが。ペダルスティールが控え目以上にはフューチャーされたナンバーであるが、ライトなホンキィ・トンク調子のためか、カントリー臭さは薄い。
「浪漫珠は覚えちゃいないし、ステージバンドがどのような曲を演ってたかも忘れた。だけれど踊ったスローダンスだけは忘れないさ。」う〜む、格好いい。
続くホルダーナンバーの#4『Love Note』も楽しげに踊るレイドバックナンバーである。曲の雰囲気は実に#3に似ているが、こちらの方がBrian Williamsのギターが泥臭く歌っているだろうか。かなり抵抗力のあるギターサウンドがジャンプし続けるナンバーだが、ペダルスティールが息抜き的な音色をヘンナリと鳴らすので、肩が凝ることは無い。ラストブリッジで曲調がサイケディリックに崩壊していく様はCounting Crowsの「August And Everything After」の作風を全体的にロックで底上げした音を例えるべきかも。
「言葉が上手く伝えられないので、ラヴ・ノート−走り書きした切れ端に思いを書いている。」
赤面しそうなラヴ・ソングだが、曲の印象からはもっと開けっぴろげな恋愛を歌っているように思える。まあ舞い上がっている心境を織り込んだのではないだろうか。
#5『Anything』はBig Silverとしては初めて取り組んだと思われる、完全なブルーグラス調子な真のレイドバックナンバーといえる。Brianの抱えるバンジョーを始め、マンドリン、ペダルスティールと完全にアクースティックに特化した楽器の使い方は1stアルバムでも聴くことができなかったタイプの試みである。
このナンバーは#3から集中的に焦点を当てているゆったりとした土臭いカントリー・フィーリングの頂点である。正直ここまでカントリーにバックすることもないとは思うのだが、時間が緩やかに流れる午睡のトロリとした雰囲気を抱えては放り投げるようなIsaacのヴォーカルを聴く番の曲なのだろう。
ここで、ペダルスティールを加えたCountryへのオマージュ精神はひとまず細る。#6『Lighttime』では泥に拳を埋め込むような粘着性のある音色を踏み出すオルガンを中心に展開する、Big Silverをロックバンドたる所以に仕立てている一面である重量級のロックナンバーである。
決して重過ぎず、しかれどもポップであるのに軽さも感じない。これぞアメリカン・サザン・サウンドとPop/Rockの最良のカップリングと言い切れる。またアメリカンな音を構成しつつ何処となくBlue−Eyed Soulの滑らかさをざらつくギターリフの中に知覚するところは、Steve Winwoodがナッシュヴィルで録音した音源を彷彿とさせてしまったりする。
決してスマートで小手先が器用にならないのに、それが一番の良いところと思えるのが、#7『Boomerang』である。 これまたそこいらの安っぽいポップバンドが創るB級サウンドよりも遥かにコマーシャルで且つアメリカンロックの正道を驀進する鉄の城たる戦艦、というど真ん中なルーツナンバーであるのだ。だがしかし、未整理と言うか各楽器の自己主張が激し過ぎてガチャガチャした聴こえ方が先に立ってしまっているロックチューンでもある。まあ、この元気があるうちは決して枯れたルーツ音楽に走ってしまうようなバンドではないと断言できるが。
1960年代の2分間ロック時代の全盛期を脳裏に描いてしまうくらいの基本ロックでもある。ここであまりスマートにアレンジを決めてしまったらここまでの親しみは持てないかもしれない。
このナンバーでもLoveやNoteの単語が出てくる。内容は失恋を何時までも忘れられない男の心情を歌っているのだが、これまた明るいメロディとはマッチしない歌詞のように思える。このあたりは結構不思議だ。
#8『The Girl Who Loves(The Boy Who Lies)』と#9『Alright To Cry』の2曲はかなりバック・トゥ・ザ・ベーシック/ルーツしていると共に、新境地に挑戦したナンバーでもある。
#8はジャズ、R&Bのアシッドさをメロディに噛ましてみたという感じのあるピアノ・スゥイング曲。戦前のジャズ・スタンダードにモダンポップのアレンジを取り入れたジャズロック。とはいえ、昨今猫も杓子もというジャムロックではない。よりクラシカルなルーツミュージックへのオマージュと筆者は受け取っている。
#9はBig Silverにしては相当陰に踏み込んだ異色作といえる。オルタナティヴというあまり彼らの色合いにはそぐわない音楽の特徴が若干埋め込まれているだろうか。それ以上に、ペダルスティールやチープなパンプ・オルガンを流してみたりと、かなりダークなサザン・ブルース色を感じてしまうのだ。それでもコーラス部分ではそこそこポップ且つロックンロールに纏めてしまうから大したものである。とはいえ、#9には辛目の点数を付けざるを得ない。ここまで鬱なオルタナとブルースの区別が付き難い方向には走って欲しくないからだ。
しかし、締めに向けて、「Love Note」は#10『Movie Stars And Musicans』からロックンロールへと加速を始めていく。#10はBig Silverのソリッドなロックバンドな側面を如実にぶつけているナンバーである。極力甘さを排除し、ギターもオルガンもリズムセクションも一丸となってハードにドライヴする。
こういう真正なビターなロックナンバーもBig Silverらしいし、ポップでなくても聴けるロックナンバーはハードロックだけではないという実証をしてくれるために存在する曲にも思えてしまう。
歌詞はこのアルバムの中でも最も示唆的なメッセージソングの体を成しているだろう。
「テレビに夢中になってしまってから失ったものを想いだしてみろよ。」
「チャンネルから手を離して、降りしきる雨の音に耳を澄ませてみろよ。」
「映画スターもロックスターも、大統領も政治家も、皆その辺を彷徨いながら、曲合わせて手を叩いているだけさ。」 と難解ながら印象的なフレーズの多い曲だ。
#11『8 Baker Drive』はオフィシャル・ホームページで2002年の春先にライヴ・ヴァージョンが公開され、この曲が新しいアルバムに入るかもしれないことと、インディ発売されるJohn FogertyのトリビュートアルバムにBig Silverが参加することをバンドからメールで聞いた。
実際にBig Silverはルーツロックバンドやカントリーロックバンドの若手のみを集めて作成された「Tribute To John Fogerty」で『Wrote A Song For A Everyone』のカヴァーを受け持っている。
#11はライヴ版ではもう少しスローでアクースティックなテイクで録音されているが、アルバムの方は弾むビートも軽やかなアーシーでのんびりしたナンバーとしてアレンジングされている。このナンバーがアルバムでは最も暖かいルーツナンバーであるかもしれない。ウィルツアー・ピアノやハーモニカまで加えたリズミカルな佳曲であり、地味ではあるがBig Silverのさり気ないポップセンスとルーツロックへの真剣な向かい合いを感じずにはいられないのだ。
そして最後の曲#12『Rock And Roll Dreams』でアルバムは更にロックンロールのステップを登っていく。前作のラストナンバー『Everything』もキャッチーでありつつラフでタフな最高の幕弾きナンバーだったが、今回のオーラストラックも全く同様に適度に暴れん坊で物凄いキャッチーなロックンロールな「銀色」を「大いに」楽しめる。
このようなドライヴなスライド感覚とポップなラインを共存させることがサラリと実現できるバンドはそうは多くないだろうと考えている。
なお、暫くの無音区間を置いて、美しいピアノソロが隠しトラックとして数秒演奏される。どうということもないが、そのリリカルなピアノは次回作への幕開け、つまり次回もピアノの美しい音色を阻害しないようなPop/Rockを創るよ、というメッセージを読んでしまうのは考え過ぎだろうか・・・・・。
全体としては、ポップなナンバー、ロックなナンバー、新しいルーツサウンドへの冒険、とかなりメリハリが付いてきた内容になっている。基本路線は前作の延長なことは間違いないが、より各曲でその特徴を突き詰めようとした姿勢が見受けられる。
今回はそういった突き詰めと言うか拘りがプラスに作用してバランスの良い、多彩なルーツロックアルバムを形成してくれているが、あまりPop/Rockの柱から離れて#8や#9のように極端な方向性には走ってもらいたくないと言うのも正直な感想だ。
バンドの情報に関しては「Big Silver」を参考にして貰いたい。特別メンバー等に変更はない。
自主制作であった前作から、小レーベルだがSpinsouth Recordsというレコード会社と契約してのリリースとなったのは肯定的なニュースである。このレヴェルでインディのしかも零細に留まっているのは勿体無さ過ぎる。
最後にバンドからのメッセージを伝えて終わりにしたい。
「僕らのレコードを買ってくれた日本のファンの皆。質問があったらMOTOにどうぞ。(笑)どんな質問でもいいから聞いてくれると僕たちも嬉しいよ。」
ということなので、Big Silverに聞きたいことがある方は掲示板にでも書いて貰えれば幸いだ。
しかし、Big何某という表現は英語の定番とはいえ、まさにこのBig Silverの音楽は金色の派手過ぎさはないけれど、偉大な銀色であると思う。渋いし甘いし、何よりロックンロールである。 (2002.12.10.)
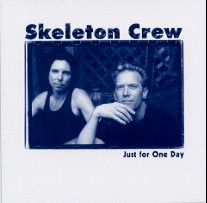 Just For One Day / Skeleton Crew (2002)
Just For One Day / Skeleton Crew (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Southern&Blues ★★★★
Sample #2
Skeleton Crewというバンドは複数存在する。
最近East Side Digitalから復刻された1960から70年代に掛けて活動していたグループのHenry Cowに在籍していたギタリストのFred Frithと数年前に身罷ったTom Colaが1980年代に結成したアメリカンロックバンドが最も有名だろうか。
このSkeleton Crewはかなり熱心なファンも多いと聞く。かなり前衛的なサウンドを演奏していたバンドである。欧州を中心にColaが亡くなった後も根強い人気を保ち続けているようだ。
音楽とは関係がないが、スティーヴン・キングの短編集「Skeleton Crew」も「骸骨乗組員」というまんまな和訳のタイトルを冠され、日本でも発売されている。
このように、Skeleton Crewという単語はそれ程奇抜なものではない。キングの小説が有名なためか、本邦ではホラーやサスペンスのオムニバスや短編集というような意味を表わすのに用いられることが多い。
しかし、原意は「基幹定員」とでも訳せば良いだろう。船乗りの俗語であり、骨となる乗組員=船を航海させるのに最低限必要な人員を指す。これは現在は船乗りだけでなく、多種のプロジェクトの基幹要員を指すことに拡大されている。つまりは中心的な人物という解釈がなされ、様々なドラマや小説にもタイトルとして引用されている。
渦中の人とか、キーパーソン−怪事件や殺人事件の犯人探し等にも用いられている。
音楽の話に戻るが、Skeleton Crewというバンドはそれ以外にも複数存在している模様である。
確かに、「演奏に必要な最低人数」というのはバンドとしての構成条件の必須である。骸骨というおどろおどろしいシンボルもロックンローラーの旗印とするには、ある種の音楽にとってはなくてはならないギミックであったりもするので、この名前をバンドに付けることは、あまり珍しくないのかもしれない。
さて、複数存在するSkeleton Crewという音楽集団の中でも、飛びぬけてマイナーで知名度の低いであろうユニットを今回は紹介したい。このSkeleton Crewは21世紀になるのにオフィシャル・ホームページも運営していないので、発見の困難が予想される。よって購入ルートを示しておこう。以下の場所で購入可能である。少々輸送費が高額であるため、何かと抱き合わせて購入するか、一般のネットショップにもしかしたら(を)入荷するかもしれないので、待つのも賢明かもしれない。
と思ったら、Amazon.comでも扱いを始めていた。こちらの方が総合的にはお買い得になりそうだ。もしかしたら、意外に売れているのかもしれない、その可能性は極低空飛行しているだろうけど。
このSkeleton Crewというバンドは、実にシンプルで飾り気のないジャケットに写し込まれている2名の男達のデュオを中核に成り立っている。Steve Hepler、Layne Wiegertの2名はシンガー且つ、ギタリスト且つソングライターを生業にしている。
12曲のうち、Steveが8曲、Layneが4曲でリード・ヴォーカルを担当しているが、それぞれ自分の書いた歌でリードを執り、それ以外のナンバーではハーモニー・ヴォーカルに廻っているという点は判で推したように共通している。但しLayneが全てを単独で書き上げているのに対して、ヴォーカリストとしての比重がより高いSteveはN.Reneeというライターとコンビを組んで8割の曲を共同で仕上げている。単独で書いているのは2曲だけだが、その2曲が実は最も好きだったりするのだが。
兎にも角にも、2名のシンガー・ソングライターがチームを組んで、協力して書いたナンバーを歌うというスタイルではなく、自分の持ち歌を自分で唄い後はバックアップに回るという手法で成り立っているバンドである。このスタイルはなさそうで結構偏在したりする。
ここまで数回に渡り“バンド”という語彙でSkeleton Crewを説明してきたが、実際にはこのデュオはバンドではなく、2名のシンガーに様々なミュージシャンが手を貸して音楽を構築した形−ロック・プロジェクトと分類すべき存在であるのだ。
前述のように、SteveとLayneがギターとヴォーカルとハーモニー・ヴォーカルを受け持ち、残りは彼らの活動するテキサス州はロックの殿堂であるオースティン周辺のミュージシャンが手を貸すという形式を採っている。
このゲストというか協力する手のミュージシャンには吃驚するほどの大物が顔を揃えている。とても自主レーベルからプレスしたアルバムとは思えないくらいだ。
まず、ピアノにIan McLagan。
今更説明の必要もないが、元Facesのキーボディストであり、このピアニストがセッションマンとしてやバンドのメンバーとして関わったレコードを挙げるだけでこの拙文の分量が倍増すること請け合いだ。元々Ian McLaganはメジャーやマイナーの分け隔てなく、レコーディングに参加する爺さんなので、近年活動の場を完全にオースティンに移しているため、Skeleton Crewのアルバムに参加することは珍しくはないかもしれないが、やはり彼の名前を3曲のクレジットに発見した時は驚いた。ここまでマイナーなアルバムに参加しているとは。
次にサックスにBobby Keys。
Bobby Keysは自分のリーダーバンドも持ってアルバムを作成しているIan McLaganと異なり、更に裏方に徹しているミュージシャンなので馴染みは薄いかもしれない。しかし、ざっと列挙するだけでも、Rolling Stones、George Harrison、Eric Clapton、Lynard Skynard、John Lennon、Humble Pie、Chuck Berry、Joe Cocker、Dr.John、BB King、Delaney & Bonnie、Carly Simon、Ringo Starr.....と1970年代のビッグネームを挙げるだけでも暇がない。
Bobby KeysはFacesやIan McLaganを始めとする元FacesのRonnie LaneやRon Woodのソロ作でもサックスを吹いているので、この「Just For One Day」での協力は恐らくIan McLagan関連での人脈が活用された結果であると推測できる。
また、パーカッションにJames Fenner。
このパーカッショニストは更に上の2名のオヤジ音楽家よりも裏方に足を突っ込んでいる人だろう。
Joe Elyのアルバムの多くや、ロックギタリストであるEric Johnsonのアルバム、1997年に惜しくも他界したTownes Van Zandtといったカントリーやフォークシンガーとメジャーでの活躍は少ないが、南部の出身のインディアーティストのアルバムを中心にジャンルに捕われない活動をしている打楽器使いである。
そしてバンドのリズムセクションとして、オースティンのセッションマンであるリズム・プレイヤーを加えている。
ベースにRobert Ramos、ドラムスにEddie Cantuという玄人好みなヴェテランを起用。この2名ともテキサスのカントリー界を根城にブルースやフォーク、テックス・メックスのインディ・ミュージシャンの作品にしばしば顔を見せ、雇われ仕事人という感じの堅実さが売りである。
オルガンにはNick Connolly。この人もオースティン土着のキーボードプレイヤーで、テキサス・ブルースやブルースロックのマイナー盤でちらほらと目撃できる。相対的にはそれ程有名ではないけれども。
また黒人ゴスペル合唱隊を2曲で起用。いかにも南部のイナタ臭さが体験できそうなピック・アップだろう。
これらのミュージシャンをプロデュースするのがStuart Sullivan。エンジニアやミキサーとしての名前がプロデューサーとしてよりも遥かに名高い職人だ。メジャー作では目立った足跡を残していないが、Ian McLaganがThe Bump Bandを久々に結成して吹き込んだ1999年の「Best Of British」でエンジニアとして登録されている。今回の助力はやはりIan繋がりだと思う。
他にもRobert Earl KeenやMeat Puppetsといったカントリーからパンクロックまで幅の広い作品のエンジニアを1990年代から精力的にこなしている人である。まだかなり若い年代に属するスタジオ・エンジニアだ。
以上、Ian McLagan関連が主とはいえ、相当な実力主義なバックバンドとゲストを加え、Skeleton Crewは処女作の「Just For One Day」を製作している。
アルバムのマテリアルを生んでいる2名のシンガー・ソングライターについては全く経歴不明。何れ問い合わせるつもりだけれども、このような無名のそこそこ若いミュージシャンにIan McLaganが全面的な人脈を活用して協力するということは、彼らの実力がIan McLaganにそれなり以上に評価されているか、またはお気に召しているか。恐らくその両方であると思われる。
確かに、Southern Rockの枠内に位置するアルバムにおいて出来ることが、Ianが参加すると実にピッタリと填まるという付帯事項付きで、存分に詰め込まれている。
色々と手を出し過ぎて、ややアンバランスになってしまっている面もなきにしもあらずだが、それとてアルバムにおける曲のヴァリエーションの豊富さを支えるプラスサイドとして機能してすらいるのだ。
音楽性の基本は、カントリーでもトラッドでもない、サザン・ロックである。特に前半6曲までの構成は完璧であると考えている。ストレートで南部サウンドを集約した様子の馬力のあるロックンロールナンバーと、じっくりと心の面積を覆い尽くすような深みのあるバラードが並んでいる。
特に、ロックナンバーの「動」とスローナンバーの「静」が巧みなコントラストを成していて、お互いの長所を引き出し合う格好になっているところはかなりのものだ。
更にSouthern Rockのメークマークであるサウンドの重みを実現しながら、滅茶苦茶ポップでコマーシャルなのである。南部サウンドの一面たるダークで汚らしい重さを、殊にアルバムの前半戦では完全に排斥しつつ、尻の安定した骨太なロックチューンを並べて大攻勢をかけてくれる。
つい最近紹介したLes Honky More Tonkiesにも通じるホンキィ・トンクな極楽調子・あっけらかんなロックナンバーも飛び出すが、カントリー&ウエスタンのスカスカの明るさとは異なり、まさにホンキィな極楽リズムで曲をリフトしているところは好感が持てる。
また、LHMTみたいにエクストリームなハードルーツやベタベタカントリーに身を投げ出してしまうことなく、あくまでも南部ロックの見本のような一定に押さえたロックンロールに留まっている普通さが実に良いのだ。
そしてこのSkeleton Crewのもう1つの特徴は、ブルースを取り入れているところだろう。バリバリのブルースバンドではないし、ロッキン・ブルースのユニットかと尋ねられると難しいけれど首を傾けてしまうくらいの分量でブルースをロックのビートに加えている程度なのだが、無視できない程のウェイトは存在すると思う。
問題はブルースの加味によって、Pop/Rockとしてのフットワークの素早さが薄れてしまっている箇所があるところである。ブルース色そのものが悪いとは決して言わないが、特に後半のドン詰まりである#10『Leave The Light On』から#12『It’s Not Too Late』までの3曲はかなり肩透かしな終り方にアルバムを陥としている原因になっていると考えられる。
ブルースのスローさがここまでバランス良く綴れ織られて来たロックアルバムとしての回転を完全にスローダウンさせてしまっている。#10はかなりブルースの匂いが漂うスローでネバネバした曲なのだが、ここまでのスロー・タイプのナンバーがブルースの影響を見せつつもポップトラックとしてのバランスの良さを体現していたのに比べると、相当出来が劣ると言わざるを得ない。
#10はLayneの作でヴォーカルも彼がリードなのだが、Steveと比較すると少しインパクトに欠けるWiegertの声もこのブルースナンバーを物足りなくさせているのに負の貢献をしているだろう。
#11『Lovin’Arms』はまるでTrafficが21世紀に甦ったようなR&Bの小粋なビートがうねるナンバーで決して悪くない。が、#10でコテコテのブルースを聴かされると、次がロックチューンというのは歓迎すべきであるのだけれど、ここでまたウネウネと腰をくねらせるブラックをベースとしたナンバーを聴かされると、単調さが際立ってしまう。
#12『It’s Not Too Late』は再びLayneの手によるブルースナンバーである。5名の黒人霊歌チームがゴスペルタッチのコーラスを出番は多くないのだが、効果的に付け加えてくれ、渋い魅力のあるナンバーである。南部の黒人ルーツに感化された白人ロックの典型のようなナンバーである。このそこはかとない哀が漂うナンバーは結構悪くないというか好みのタイプなロッキン・ブルースであるのだけれど、やはり前半、#9辺りまでのPop/Rockを聴いてしまうと尻すぼみという感が拭いきれない。
最初からもっとブルースをたっぷりと加えていれば、ここまで渋くなっても違和感はなかったのだが、これは明らかに構成上のミスだ。「Just For One Day」を初回に半ば過ぎまで聴いた時は、凄いSouthern Rockのアルバムだ、と興奮したものだが、最後のブルースという海溝への急速潜航でかなり萎えてしまった。
ブルースをロックやポップと上手くミックスできているのに、最後の最後でここまで極端に突っ込みに走るのはどうにも勿体無い。最初からロッキン・ブルースやブルースルーツとしての姿勢をここまであからさまに出していなかったのだから、落差が酷い。
とはいえ、十分に評価に値するロックアルバムと思うから、こうやって好き勝手に書く気になっているのだけれど。
しかし、残りの9曲はかなりレヴェルの高いルーツロックのショウケースを形成している。オースティンを拠点にしているのに、全くカントリーの影響を尾首にも出さないという、ルーツロックの電車道をまっしぐらという音楽性には相当の敬意を覚えているくらいである。
#1のタイトルトラック『Just For One Day』から、キャッチーで適度な装甲を纏った極上のルーツポップ・ロックが飛び出してくる。この段階でこのアルバムは少なくとも1曲は傾聴に値するナンバーがあることが分かり、完全な外れではないことが判明する。少々貧乏臭いが、ハズレを購入しなかったことでこのナンバーだけで噛み締めるリスナーは少数ではないだろう。
それだけ、この#1がRoots Pop/Rockとしての出来が宜しいのである。大半の曲に鍵盤が絡んでくる「Just For One Day」の中で、この#1は#7と並んでキーボードレスな曲である。しかし、曲の持つ存在感と厚味は他のどの曲にも引けを取らない。Steveの少しシャガれたソウルフルなヴォーカルと、それに乗っかるLayneのハーモニーという、Skeleton Crewの歌唱スタイルがここで既に確立されている。
バリトン・ギターとエレクトリックギターの安定したリフに、ドラム・ベースのリズムセクションの堅実過ぎてカチカチなところが嫌味なる暗い素晴らしいアンサンブル。ま、完璧な1曲だ。
#2『I Don’t Like You At All』で筆者待望のIan McLagan登場。バリバリのマシンガンピアノを期待通りに叩き付けてくれる。これぞAmerican Rock n Rollというべき、爆走ロックンロールである。こういうナンバーでハーモニータイプのダブル・ヴォーカルが駆使できるデュオ形式は強い。コーラス部分だけでなく、あちこちで強烈なロックビートに負けないコーラスを広げることが出来るからだ。また、Ianが演ってくれると期待していた乱れ弾きするピアノ、やはり登場で最高に嬉しい。
Ianの参加するナンバーは3曲全てがゴキゲンなサザン・ドライヴ・ロックンロールである。アルバムの中でも最も熱くフックを連打してくれる曲が揃い踏みだ。
#2の次に登場するのが、#6『I Want You So Bad』。ロッキン・ロッキン・ロッキン・ファンキー・ブルースというようなハードにキャッチーに揺れ動くスピードロックナンバーである。何と、このナンバーではBobby Keysもテナーサックスで共演。ファンクなサックスをスゥイングさせ、ロックビートを嫌が応にも盛り上げてくれる。Steve Heplerの野太いヴォーカルにクラシカルな♪「I〜〜〜〜〜〜I Want You So Bad」のハーモニーコーラス。何処となくRolling StonesにBobby Keysが頻繁に参加していた1960年代後半から70年代前半頃のアルバムを思い出させるR&Bな黒っぽさも入ったロックチューンだ。
これより更にガチャガチャとしたハードに突っ走るロックナンバーが#9『Can’t Stop Thinkin’』。ドライなピアノとリズムセクションが果てしのない地平のかなたまでアンサンブルを引っ張っていく感じである。寧ろ「Can’t Stop Rockin’」とか「Can’t Stop This Steam Train」というタイトルが似合いそうなロックンロールである。然れどもハードさはそれ程目立たない。ここまで暴れまわっているのに、粗暴なハードさ、野蛮さよりも滑らかさが際立っているところはオールド・ディズのスクールロックやパーティロックの良心的なホンキィさを正確に継承しているからだろうか。
前半のハイライトとなるのは、#1、#2とロックナンバーが続いた後に登場する、とてもインディのアルバムに入っているとは信じられないくらいのメジャー感覚の詰まったバラード、#3『Can We』。
アルバムのスタートからロックでかっ飛ばしてきたテンポを一気にクールダウンさせると共に、じっくりと腰を据えて聴かねばなるまいと決意させる説得力に満ちている。
Bobby Keysのムーディなテナーサックス、Nick Connollyの暖かいオルガン。
女性4名を含む黒人ゴスペル・コーラス隊がじっくりと牽引されてきたファーストヴァースからコーラスラインに移る所で徐に登場するところは鳥肌が立つくらいだ。Steveの引き絞るような情感を篭めて唄うヴォーカルとコーラス隊の掛け合いは是非聴く価値がある。ここにJames FennerのパーカッションとBobbyのサックスが絡んでいくラストブリッジの山場を聴いていると、1980年辺りのヒットラジオ番組を回想してしまったりする。あの頃はこのようなナンバーがラジオに乗っていたのだ。
#3が相当に名曲なため、やや霞んでしまっているのが気の毒なバラードが#4『Julie』である。LayneのヴォーカルはやはりSteveに匹敵する位の説得力には不足が見られるが、やや頼りない優しさがこういったサザン・バラードでは活かされていると思う。
アルバムでは初めてアクースティックギターが聴こえてくるナンバーであり、ギターソロのエモーショナルさでは#3に負けないポップさとメロディアスさを持っているのだ。
#5『Straight』はLayne作の中では唯一アップビートなナンバーである。James Fennerのパーカッションを大胆に配置したレゲエタッチのリズムポップナンバーであり、メキシカンなエスニックさも感じ取れる。オルガンが楽しげに鳴るウエットなアレンジとカッティングを中心にしたギターのドライさが良い対称になっている。全体的に質感のある南部ナンバーが大半を占める中、こういったライトに跳ね回るコマーシャル・チューンは一種の清涼剤になっており、かなりの印象が残る曲だ。
#7『What Is It』はSkeleton Crewのロックな面とブルージーなアスペクトがそれぞれ均等に混合されたようなライト・ファンクな曲調のロッキン・ブルースである。しかし、必要以上に濃いブルース・フィーリーな曲でないため、そのリズミカルなビートは結構心地良い。珍しくSteveがハイ・ファイ気味なトーキングラップで唄うところは黒っぽくもあり、Bob Dylan的なところも同時に存在するように思える。
#8『‘Til The Pain Fades Away』は実に普通な南部チューンとしか言いようのない、ゆったりとしたミドルテンポのポップチューンである。所々でアクースティックギターとスライドギターのリフが綺麗な音色を聴かせてくれる。オルガンのNickも相変わらず出過ぎず、引き過ぎずなスタンスで曲をハートウォーミングにする支えとなっている。調子もついつい身体がリズムを取ってしまうくらいにメロディックでグルーヴィなのだ。Skeleton Crewの良心的なソングライティングを最も端的に集約したナンバーが実はこの地味に終始する#8ではないだろうかと考えてしまう。特に、スライドギターの寂しげな音色がバックで鳴る件は最高である。
こういった和む曲を聴いていれば、「痛みが消えうせるまで」にはそれ程の長時間を必要としないと思う。
Skeleton Crew=最低数基幹乗組員、という名前のインディバンドを紹介したが、是非これからも続けて欲しいプロジェクトである。デヴューアルバムのレコーディングという処女航海は終了してしまったが、オースティン周辺ではバンド形式でライヴをそこそこ行っている模様であり、航海は乗組員をステージミュージシャンに交代して継続している様子であるのは喜ばしい。
次回があるとしたら、今度もまたあちこちから乗組員を集めて、今回以上のスタッフと音楽を届けて欲しいと切に願うものである。 (2002.12.1.)
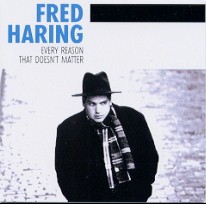 Every Reason That Doesn’t Matter
Every Reason That Doesn’t Matter
/ Fred Harring (2002)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★
Americana ★★★
You Can Listen From Here
最初にこのアルバムを聴いた時は
「う〜〜〜〜ん・・・・・」と思ったのが正直な感想。
そして改めてフロントジャケットのFred Haringの写真とタイトルをしげしげと見返した。
ひょっとしたらFred Haringとは筆者が待っていたアーティストとよく似た同姓同名のミュージシャンかもしれないと思ったりしたのである。しかし、やはり、これは2000年にかなりの良作である「This Grand Parade」を発表したオハイオ州はコロンバスを中心に活動する30代のシンガーである、Fred Haringその人だったのだ。
であるからまたもタイトルと顔写真を凝視。すると、
「Every Reason That Doesn’t Matter」−「どんな批評も全然気にしないよ、兎も角聴いてくれないか。」
以上のようなリスナーへ訴えかけを、Fred Haringの3枚目のアルバムのタイトルが語っているように思えた。
「僕はリスナーの皆にポップさを楽しみ、歌に耳を傾け、そして最後には『ああ、Fred Haringが何を唄っているのか分かったよ』という感じ方をして貰いたい。僕の歌が心の琴線に触れてくれれば至上の喜びだよ。」
これを自らの音楽活動の指標として常々語ってもいる。
だから、どのような色眼鏡も掛けずに、初心に還ってこのアルバムを聴いてみた。少なくともそのつもりで聴こうという努力はした。
しかし、かなり今後に期待を持たせた前作−2枚目に当たるアルバム「This Grand Parade」の呪縛からは完全に自由になることは成しえなかったようである。
良作にはやや足りない、という評価しか与えることの出来なかった、Fredのデヴュー盤「Ghosttowns & Kingdom」(1997年)から、プロデューサーに元Georgia SatellitesのDan Bairdを迎えて作成された2000年発売の2枚目「This Grand Parade」はFred Haringというシンガーの物凄い成長を見せ付けてくれた好作であった。
元来、Fred Haringという男は殊更メロディやルックスでアピールしなくても、彼の持つヴォーカルだけで勝負が可能なほど素晴らしい声を持っているシンガーなのだ。これで曲が良ければその最終形態たるアルバムの内容が悪かろう筈がない。
そういう事実を「This Grand Parade」は謀らずも実証してくれたわけである。つまり良質なナンバーが並んでいたアルバムだったという訳である。この2作目に関しては「簡単に」拙文で紹介している。興味があるなら参考にして貰えれば幸いである。
さて、ぶっちゃけた話、今回は2作目と比較して甲乙を付けるということになってしまいそうだ。
で、ここで最初に書いた
「ひょっとしたらFred Haringとは筆者が待っていたアーティストとよく似た同姓同名のミュージシャンかもしれない」
という事項に戻るのだが、つまり、筆者が期待していた内容とはかなり違ったアルバムだったのだ。付け足しだが、顔写真の感じも前作とは異なって、もっと鋭い男前な写真写りをしていたこともあるが。しかし、裏ジャケットで口のでかい微笑みが健在であることは証明しているけど。
少なくとも、最初に聴いた段に於いては、「う〜ん・・・」と首を捻ってしまう内容だったことは確かだ。
「This Grand Parade」レヴューでも述べているが、かなり筆者はこの3枚目に期待を賭けていた。
この期待というのは早い話が「This Grand Parade」を筆者がどう捉えていたかという評価と同義である。
それを語る上で、2作目と本作「Every Reason That Doesn’t Matter」の相違点に触れつつ、2枚を比較していきたいと考えている。結局はこの分析が3枚目の筆者の評価に行き着く、筈であるから。
まず、プロデューサーであるが、今回は残念なことにDan Bairdはその任を任されていない。今回Dan Bairdはソングライターとして1曲をFredと作成し、バンジョーでアルバムのバックアップを務めるに留まっている。
Bairdの後任にはMike Jacksonというマルチプレイヤーにしてミキシングを主に担当してきた人が充てられている。
このアルバムでもMikeはキーボード、ギター、ベース、バックヴォーカルと手の多さを実証しているが、これまでに目立ったプロデューサーとしての履歴は殆どない。どちらかというとミュージシャンとして、幾つかのインディ・ミュージシャンのアルバムに顔を出している割合が高い。
現在のところ、Haringのコメントが拾えていないので、Mike Jacksonがどのような手法でアルバムをプロデュースしたかはっきりとはしていない。しかし、Dan Bairdとアルバムを創り上げた過程はFredのコメントに残されている。部分的に紹介してみるとしよう。
「Danは僕の浮気性を叩き直して、アルバムの方向性をしっかりと絞る手助けをしてくれた。僕の最初のアルバムでは、どれだけ手当たり次第に音を混ぜていたことかよく分かったよ。
例えば、レコーディングがある日の朝に僕がPoguesの歌をラジオで聴いたら、その日は『ねえ、バンジョーをこの歌に加えたいんだが、良いよね。』というような作業をしていたんだ。
でも、Bairdは違った。僕は最初のレコーディングの日に30曲を用意してスタジオに持って行った。が、Danはその場で半分の15曲をボツにしてしまったよ。これが彼を「切り捨て屋」「焼却屋」と呼ぶことになる最初の事件だった。で、僕は修正した歌を彼に提出して、また切られる。これが1ヶ月以上も続いた。
だけれど、それが酷いこととは思わなくなったね。レコーディングの半分の作業が経過した段階で、プロデューサーを殺したくなったら、そのプロデューサーは凄く良い仕事をしているということだからね。」
「僕は『This Grand Parade』をクラッシックなタイプのアルバムだと考えている。Danはこう言った。
『さて、僕達がこれからレコーディングに入るとするね。さて、そこではレコーディングには2つの選択肢しかないんだな、これが。1つは最初から車輪を作り直すこと、またはクラッシックを創作すること。』
で、僕はクラッシックを選択したんだ。Neil Youngの『Harvest』とRolling Stonesの『Exile On Main Street』を見本にしてクラッシックアルバムを創った。」
というようなレコーディングの経緯をFredは記録に残している。勿論Dan Bairdは、過去のロック古典を焼き直せば簡単だとか、模倣して懐古ロックを作れば、と述べているのではない。Danはreinvent=再発明・作り直しという表現を使っているが、これはロッククラッシックの見習うべき点まで破棄して全て一から作り直すよりも、良い面は大いに取り入れて自分の色に染めれば良いのだ、と言っているのだろう。
ここでロック死滅論を分析するつもりはないので、これ以上の言及はしないが、単なる過去名作の模倣をしただけでは結局その上辺は剥離してしまい、何も後には残らないことになるのは明白であるし、Fredは単なる懐古復刻マニアではないことは、「This Grand Parade」を通して聴いてみれば説明するまでも無い。
ここで問題にしているのは、このようなプロデュースのやり方を目の前で実演して見せた程の経験と牽引力がMike Jacksonというエンジニアには存在したかということである。
結論としては、無難に収める能力には不自由しない、寧ろ適度のフリーハンドを与えた方が良作を作る傾向のあるミュージシャンの手綱を締めるというロールが最も向いている人だと思う。
つまり、未だプロデューサーの力量で作品にかなりの影響が出るFred Haringのようなアーティストには完全なマッチングはしていない人、が答えだ。
第一に2ndアルバムでたっぷりと堪能できた、おおらかさとFredの出身地たるオハイオの平原を連想させるような伸びやかなダウン・トゥ・アースな雰囲気が物凄く濃厚には感じられない。
牧歌的、というとどうにもカントリー・ミュージックに近くなってしまうが、確かにカントリー・タッチの曲は相対的に減少している。
反面、前作のレヴューでも願望として述べているのだが、
ロックンロールなチューンは結構その割合を増している。
少なくとも3曲程度しか速いナンバーのなかった「This Grand Parade」よりはロック色はその濃度を増していることは間違いない。
とはいえ、それによって、この「Every Reason That Doesn’t Matter」がロックンロールの快作となっているというと案外そうでもなかったりするので、説明が難しい。
ロックなナンバーが増え、曲自体も悪い曲は殆ど無い。
然れども、2枚目と比べると、期待が大き過ぎたせいもあるだろうが、あそこまでのインパクトは正直ない。
つまり、
地味なのである!!(結論)
このアルバムには#1『This Grand Parade』や公式ホームページの副題にも選択されている代表曲且つ代表ロックナンバーである#2『Walk In Progress』のようなガツンと一発喰らわしてくれるキラーナンバーが、ない。この事実がデフォルトで地味なシンガーに属するFred Haringの地味な3rdアルバムを、更に地味にしているのだ。
元来、筆者は地味なの歓迎、下手にエモとかパンク・ポップ化して軽薄になったらとんでもない事態なので、地味であることは必須条件であるとは考えている。
であるから、最初のリスニングであまり心の琴線を弾かれなかったのに、珍しくかなりの回数をリピートしてしまったのだ。まあ、これには前作で期待した度合いの大きさに対する失望度が低かったこともあるのだが。念のためだが決して駄作ではない。筆者の好みのど真ん中からは外れるが。
すると、段々と評価が上がってきた。最初は「う〜〜〜〜ん」で、次が「うむむむ・・・・・・」。そして、
悪くないアルバム、というより良作だ・・・・けれどもやはり2ndには数歩及ばないかな・・・・・。
というのが最終的な感想になった。
断っておくと、進歩した面もある。例えば、楽器の使い方だが、Dan Bairdの方針に則ったと思われる非常にシンプルな楽器をメインに構成され、キーボード類の使用は最低限に留められていた前作よりも、積極的に色々なインストゥルメンタルを重ねようとする色気が見られる。
この浮気性は1stでも見られたが、全体的に色々と持とうとして腕から持ち物がキャパシティ・オーヴァーで零れ落ちていた感の強い1stよりも、良くも悪くも堅実にアレンジを纏めることに成功している。これもアーティストとしてのFred Haringの成長を示すものだと思う。
また、ややCountry Rockのスローさが消化不良−Dan Bairdが手掛けたにも拘らずと当初は思ったが、この後のDanの手掛ける作品はかなりロックが沈静化しているものが多かったりしたので今はある程度納得している−であったことに加えて、少し単一色に染まったCountry Rock一辺倒さをヴォーカルの魅力で打ち消しているところが「This Grand Parade」には垣間見れたが、この「Every Reason Doesn’t Matter」ではかなり手を広げようとしている姿勢が窺える。
それだけの手数を持てるように大きくなったというところだろう。
しかし、どうにも不満のある箇所もそれなりに存在する。
筆者はFred Haringの最大の長所を、何度も繰り返すが、最近少なくなった個性的で且つ素晴らしい声質を有した天性のヴォーカリストであるところと見ている。ルーツに限らず、Pop/Rockのオルタネイトな歌い手として活躍できる力量は溢れるくらいにある人なのだ。
しかし、今作では妙に抑えて歌い過ぎたり、トーキング調を混ぜたりと、この磨かなくても金剛石な声を活かし切っていないのである!!
#1『Carousel』のスタートから前作では少なかった軽快なポップナンバーを持ち出し、ヴィオラやピアノといった曲を豊かに彩る楽器を入れて良いメロディが健在なところと、やや遠慮気味だがソウルフルでありつつもしつこくない喉を聴かせてくれる。
し・か・し・・・・・・
この次の#2『Murder By Ballpoint Pen』はアップビートで変調を多用したロックナンバーで、ドライヴするヴァイオリンやヴィオラを始めとして分厚いロックアンサンブルを堪能できる勝負ナンバーな筈なのに、声を故意に低くしてバス・ヴォーカルにしているため、Fredの声が耳に入った途端に瞼に浮かんでくる中部アメリカ平原の雄大な光景が見えてこないのだ。
これは明らかにヴォーカルのプロモートミスである。Fredの声は抑えきった低音で映える類のヴォーカルではないのだ。黒人ソウル系の歌手のように、とことん伸びやかに歌わせた方がその存在感を振り撒ける稀有なヴォーカリストであるのに。
それは70年代フォーク風ポップで大人しい#4『Ain’t Where I Used To Be』でも当て嵌まる。地味でじっくりと暖まる暖房の大気が部屋に広がるように沁みてくるナンバーであるのだが、ここでも必要以上に抑えたFredのヴォーカルが曲を更に目立たなくしてしまっている。アレンジには小さなワルツという感じのピアノを使ったりして小技を効かせているのに台無しだ。
貴重なロックナンバーである#5『I Just Had The Worst Day Of My Life(But I Can’t Stop Laughing)』では大学卒業であるインテリ派(古い)であるFredの詩人たる一面が存分に発揮された歌詞を楽しめるが、やはりどことなく歌い方が曇り空を見上げる気分のように重く、苦しいところがあるようだ。
メロディー的にも前作では見られなかった暗さと鬱に篭もった、ブルース好きなら喜びそうな要素が見られるようになっているのもいまいち不満。
ハードでダートな#9『I Remember When』も重いロックナンバーだが、もう少し魂入れて熱唱してくれないと曲に位負けしてしまう。『A Walk In Progress』で聴けた大らかなヴォーカルは何処へ行ってしまったのだろう。
#6『Under The Milky Way』では豪州出身で現在も活動中のポップバンドであるChurchが放ったトップ40ヒットのカヴァーもする意欲を見せているが、このNew Wave期の流行歌は、Fredとは食い合わせが宜しくない。暗さが目立つナンバーとなってしまっている。
と不満を並べたが、良いナンバーも当然存在する。基本的に地味だが曲は粒が揃っているのだから。
Dan Bairdと再び前作に続いて共作した#3『Angel At My Table』はFredのゲルのように粘りついてたゆたっていくヴォイスを十全に駆使している優しいアクースティク・バラードである。バンジョーを始め(これはDanが弾いている)、ピアノやシンセサイザーやホーンセクションを交えて次第にメジャーコードな盛り上がりを見せる展開は素晴らしい。
やはりDanともう一度コラボレイトすべきだったと残念に思わせる1曲である。
#7『Maybe You’d Come Along』のリリカルなピアノに導かれつつFredが柔らかく唄うバラードも、これまた必殺のクリティカルな魅力がある。この甘く、裏声が1本通っている唄い方こそFredの本領である。しかもシンプルなピアノバラードときては言うことなし。
#8『This Glorious Gamble』も甘く懐かしさを覚えさせる良質なPop/Rockである。オルガンを始めとして、適度に厚目なロックアンサンブルが、心を和ませてくれる。このナンバーもオープニング・ヴァースでFredが思い切り低音なヴォーカルで切り出すので、ああ、これも駄目かと思わせるが、即座に彼本来のハート・ウォーミングな声が聴けるのでこれは嬉しい誤算だ。
一気にレイドバックして埃っぽい音色を聴かせる#10『The Ones Without A World』を聴いていると、キーボードや弦楽器のアレンジは非常に繊細で、これはDanには真似が出来そうもないプライオリティを感じるのだが、如何せん肝心要のヴォーカルのプロデュースが疎かになっているのだ。
#10に関しては、Fredの持ち味を発揮した歌唱法を執らせているのは救いだろう。
最後のフォーク弾き語りナンバー、#11『Patience,Poems,And Wine』でも余分な装飾がこの曲だけ唐突にバッサリと切り捨てられるために、途中で合流する生弦楽器とアクースティックギターというシンプルなバックを静か過ぎると感じさせないFredのヴォーカルが浮き出ている。
このような演出をもっと行わなくてはならないのに、プロデューサーは一体Fredとどのような話し合いをして舵取りをしたのかと詰問したくなる。#11のようなシンプルなナンバーでさえ、Fredのヴォーカルの魅力、否魔力は伝わってくるのである、確かな質感をもってだ。
ということで、聴けば聴くほどには必ずその良さが分かる良作であるのだが、サウンド・プロダクションが成功したとは言いかねる完成度になっている。Fredには良作ではなく傑作を期待していただけに少々残念だ。
プロデューサーを複数起用するなりしてもう少し活性化を図ればもっと違った結果になっただろうか。
後の祭りだが、取り敢えず、プロデューサー逝ってヨシ!!(をい) (2002.12.5.)
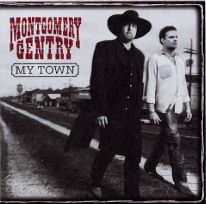 My Town / Montgomery Gentry (2002)
My Town / Montgomery Gentry (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Country&Southern ★★★★★
You Can Listen From Here
#1『My Town(Piano Intro)』〜#2『My Town』を聴いただけで、このアルバムの購入を決めてしまった。
ピアノの切ないイントロからメドレーで続く、産業カントリーロックと呼ばれそうなスケールのでっかい#2『My Town』。確かに節々にドが付くカントリーのアレンジを感じるが、それ以上に楽器を重ねたアレンジには商業カントリーに典型な軽過ぎるところが少ない。寧ろ、サザンロックの豪快さがアリーナ系のコンテンポラリーさと結婚した様子の歌である。
まずは試聴リンクからこの2曲を聴いてみよう。
または、このSony Nashville音楽サイトにある彼らのページでもマラソン形式で彼らのアルバムの何曲かが試聴可能である。曲間にインタヴューを挟んだプロモーション音源なので、リスニングがある程度出来る人なら更に面白いと思う。
最初にお断りしておくと、このMontgomery Gentryと言うバンドは本国アメリカでは完全にCountry/Country Rock扱いされているデュオである。所謂商業トップ40カントリーの典型と考えられていると予想されるし、実際にカントリーのチャートではヒットの常連でもある。
日頃、筆者は商業カントリー、特にナッシュヴィルあたりで量産されている、カウボーイハットを被ってフォークギターを掻き鳴らすようなプロモーションビデオがMTVで垂れ流されている類のカントリー音楽は今でも全然好きにはなれないのである。
しかし、Montgomery Gentryはヒットチャートの常連ながら、あまり軽くスカスカなカントリーを演奏するバンドではなかった。筆者は本当に偶然に中古一括購入の際、彼らの1stアルバム「Tattoos & Scars」を手に入れてからの付き合いになるが、この1作目はかなりダークで重めのサザンカントリーという感じが強い。
女性カントリーシンガーに多く見られるコンテンポラリーな甘さは殆どなく、ブルージーなカントリートラックが多くを占めている作品で、よくこれがヒットしてゴールド→プラチナディスクを獲得できたものだと驚いた記憶がある。それと同時に、オルタナカントリーは継子扱いされ全くメジャーでは売れないが、カントリー・ミュージック自体はかなりの市場性がある米国のマーケットの実情を思い知らされたものであった。
その米国市場のカントリーチャートの上位に食い込みながらも、Montgomery Gentryは肯定的な意味でのメジャー感覚である、軽快なポップさがあまりない曲を中心に歌うデュオであった。
もっとも、近年の傾向としてかなりダークでオルタナティヴ特有の暗くて鬱な雰囲気を歌うカントリー・シンガーがメジャーのチャートでも増加しているのは確かである。これらの音楽をCMA−Country Music Alternativeと呼ぶ。何でもAlternativeを引っ付けるのが最近の流行とはいえ、何処にも家庭内害虫のように蔓延ってくるオルタナティヴは是非ともどっかに逝って貰いたいのだが。大体、こうなるとAlt-Countryとの区別はどうなるんや、とも言いたかったりするのだ。激しく余談・・・・。
という音楽的変遷も踏まえて、Montgomery Gentryを流行に乗っただけのCMAかそれとも硬派なルーツ&カントリーのアーティストか分類するのは困難である。
トラディショナルに敬意を払ったダークなカントリー・ミュージックが、その発表の場がメジャーと言うだけでオルタナティヴに迎合した商業カントリーと断言することも乱暴だし、軽カルでスカスカなポップカントリーがインディバンドというだけで、賞賛に値する売れ筋から外れた音と判断することも宜しくないと思う。
要するに、インディだろうが、メジャーだろうが良い物を持っているバンドは良い、これに尽きるだろう。
Montgomery Gentryに関しては2枚目の「Carrying On」以降はサザン風味の強いカントリーロックと、筆者としては捉えている。メジャーで売れているため、少しばかりやり過ぎなカントリーへの踏み込みもあるけれど、カントリーではなく、カントリー・ロックとして聴ける面積は大きいユニットと認識している。
・・・・まあ、究極的には自分の好みに適っていればメジャーだろうが、インディだろうが、売れていようが売れていまいが構わないと言うことである。とはいえ、筆者のマイナーヲタクの性癖は大売れてしてしまったミュージシャンからは興味を無くしがちという困った奇行さがあるのだが・・・・・。
話をMontgomery Gentryに戻すと、それ程ポップではなく、言い換えればカントリーのアレンジが濃厚な南部伝統音楽という表現がピッタリとくる歌が並んだ「Tattoos And Scars」(1999年)は、Columbia Recordsからメジャーで発売され、前に記したように、1年後にはRIAA公認のゴールドディスク、次いで100万枚のプラチナディスクを獲得している。
明らかに、近年の売れ筋カントリーとは一線を画している重く、濃厚なナッシュヴィル・ルーツを包括したMontgomery Gentryが売れるならもっと売れて然るべきサザンロックや、カントリーロックがあるではないか、という思いは当然存在したにしても、こういった悪い意味でのメジャー感覚−スカスカで単にポップなだけで何も残らない−が希薄なカントリーが売れたのはまだまだ市場も捨てたものではないなという感慨をも抱かせた。
同時にやはりメジャーのプロモーションとバックアップを受ければ知名度とセールスには相当な順風になるということも改めて思い知った次第である。
参考までにだが、彼らのデビュー盤はBillboard Top 200で131位まで上昇。Top Country Albumでは最高10位を記録。しかもTop 100に2曲のシングルを送り込んでいる。
という好調な売れ行きを示していたMontgomery Gentryだが、筆者的にはあまり好みではなかった。基本的に暗いのとかアンキャッチーなマテリアルはどうにも食指が動かない。かといって渋いトラディショナル・ミュージックと仕分けるには少々カントリーのアレンジが強い音楽だったからである。
いわば、評価には値する点は有しているけれども、多かれ少なかれ濃過ぎる音楽がクドいカントリー/カントリーロックであった。
であるからして、2001年に今度はSonyに飲み込まれてしまったColumbiaレーベル名そのままにSonyから発売となった2枚目の「Carrying On」には手を出さないつもりでいたのだが、当サイトでも取り上げているカントリーロックの良心と筆者が見なしているChris Knightがこのデュオに曲を提供していると知り、思わず中古を待って購入してしまった次第である。
評判ではかなりロック且つ一般化しており、カントリーというよりもカントリーロックと呼んだ方が相応しいアルバムになっているということだった。1stよりもポップさとロックのビートが増量しているという評価は間違いなかったことを聴いてから確認できた。
が、それはつまり商業カントリー化してしまったか、単なるカントリーロックになってしまったことと同じではないかという危惧があったが、そこまでコテコテではない独自の良さを持つカントリーロックのアルバムに収まっていたので一安心。まあ普段ルーツを聴かないリスナーやディープなカントリーが好きなマニアにはこれでもベッタリなメジャーカントリーとして聞こえることは想像に難くないけど。
やはり出色はChris Knightの提供したオープニングトラック『She Couldn’t Change Me』だった。軽快なルーツロック/カントリーロックナンバーで、このシングルはデュオにとって初のトップ40ヒットになる。参考までにアルバムの成績はそれぞれ、メジャー/カントリーのチャートで49位/6位を記録。
そして僅か1年少々で3作目「My Town」が2002年の夏に発売される。#2『My Town』は2曲目のトップ40シングルになり、アルバムも23位と初のトップ40入りを果たす。はからずも、メジャー系のカントリーアルバムはオルタナティヴやブラックコンテンポラリーの活性下でも売れると言うことを証明しているようだ。
肝心のアルバムの内容だが、「Carrying On」程硬派なカントリーロック一筋ではないと思っている。非常に微妙な言い回しになってしまうが、メインストリームなContemporary Countryに歩み寄った歩幅が大きい方向性を選択していると考えているのだ。更にSouthern Rockにも色気を出しているようだ。
1stと比較すればポップ化及びコンテンポラリー化しているのは一目瞭然である。更にロックとしてのリズムが強化されているのもよく見える。
これ即ち、メジャーなポップ商業カントリー化−特に女性ヴォーカルに多いコンテンポラリーな詰まらないポップアルバムに終結してしまう線路に乗ってしまったのか、と思いそうだ。
が、そこまで堕落というべきか、レコード会社の思惑に沿ってしまわないところで踏み止まったアルバムであると筆者は見なしている。
確かに、Adult Contemporaryな歌の割合が、#1/#2『My Town』を筆頭に始め増え、2ndで打ち出してきたポップ路線を踏襲はしている。ために、かなり聴き易いナンバーが増え、全体的にポップになった表面積は上昇しているだろう。
しかし、ポップになったからといって、トラディショナルなルーツ回帰路線を軽くいなしてしまわずに、しっかりと抱えているので、骨抜きなカントリーナンバーだけに終始するハメに陥っていない。
後述するが、ポップでアダルトに特化したと同時にブルージーでハードな要素も急激にその割合を増している。それにより、ルーツロック特に南部ロックのルーツと重さを要所には打ち込んでいるため、かなりロックになっている。寧ろメリハリが付いたため、ロックアルバムとしてのフックは前作よりも尖っているようにも感じることが出来る。
が、地味さと言うかトラディショナルへの追求としてはドラスティックなアレンジとアリーナロック的な力過剰のコンポーズが目立つため、評価が分かれそうではある。これを脱カントリーバンドの冒険として評価すべきか、それともやり過ぎと批判するかという点に於いて。
筆者としてはハードなナンバーあり、バラードあり、ロックナンバーあり、カントリーナンバーあり、ブルースロックありとかなりロック化が構成の面からは進んでいるし、メロディの大仰さは語弊がありそうだが産業ロック化したことで力を増していると感じている。
伝統音楽であるSouthern Country Rockからモデレイトされ、より普遍的なCountry Rockから脱却し、ロックバンドへの道を進んでいると判断している。言い換えれば、複雑な輪郭を持ったルーツアルバムへと変化しているということだ。多彩なカントリーやサザンのロックが楽しめるアルバムとなっている。
主色はやはり#1『My Town(Piano Intro)』〜#2『My Town』だろう。ちなみに筆者はこの2曲を2曲で1曲として扱っている。この零れ落ちる雫のようなピアノのイントロなくして#2で曲間なく流れてくるドブロギターの、バンジョーの、そしてマンドリンのアーシーなリフは引き立たない。水晶を叩くように美しいピアノソロから一気にダサダサなカントリー風味の曲に変調するその瞬間が好きだ。
そしてメインヴァースはTwangyなカントリーアレンジに沿ったバンジョーとドブロ、スティールギターにピアノで進んでいくのに、コーラス部分でガツンとピアノやオルガン、エレキギターと女性コーラスを交えたオーヴァー・ウェルミングなパワーバラードに飛び上がるという3段の変化が楽しめる。これは総合ポップチャートでトップ40ヒットになっても不思議ではないだろう。
Gerald Edward Montgomery(バンドではEddie Montgomeryを名乗っている)の野太いカントリーシンガー向きの声がなぞるメインヴァースと、彼よりもロアな性質を持つTroy Lee Gentryが合流するコーラス以降の分厚いヴォーカルのハーモナイズは圧巻である。
♪「Yeah,This is my town.Na,na, na...Hey Where I was born,where I was raised.
Where I keep all my yesterdays.Where I ran off‘cos I got mad,
And it came to
blows with my old man.Where I came back to settle down,It’s where they’ll put
me in the ground.This is my town.Na,na,na......」(筆者聴き取り。)
「俺が生まれ、育ち、俺の過去がある場所。親父とやりあってぶちのめされ、切れて逃げ出した場所。
戻ってきて、根をおろした場所。そして何時か俺が土に還る場所。それが俺の街・・・・。」
まあ、如何にも合衆国らしい「故郷へ帰りたい」的な歌詞のコーラスだが、素直に良い詩だと思う。
#3『Break My Heart Again』はピアノやオルガンをフューチャーしたため少しウエットなカントリーポップナンバーである。このポップさはやはり今作の特徴だろう。こういったストレートなカントリーロックなナンバーが来ると、やはりMontgomery Gentryはカントリー系の土臭い要素を失っていないバンドだと分かる。#2があまりにも強烈なナンバーであるためガス抜きには丁度良いかもしれない。
#4『Scarecrow』はマンドリンとバンジョーがアクースティックで乾いたリフをまず聴かせてくれる。このアルバムのマンドリンは日本でもアルバムが発売されPower Popファンには馴染みの深いDoug Powellが担当しているのには驚きである。彼はもう少しメカニカルなポップアルバムでの活躍が多かったのだが。2002年発売の新譜4th作「The Last Chord」はかなりの評判だが、筆者の嗜好には合わないため、未購入であるが。
このナンバーもトラッド感覚が活かされた軽快なナンバーだが、リードヴァースをTroy Gentryが歌っているためかあまり濃さを感じないスッキリしたアクースティックロックに仕上がっていて筆者の好みである。Eddie Montgomeryの濃く太いヴォーカルはソウルフルだが、やや典型的なカントリーシンガーの枠に填まり過ぎなきらいがあると感じることもあるのだ。
#5『Bad For Good』のホンキィ・トンクなバーロック風のナンバーを聴くと、このバンドの南部テイストとロックへの傾倒を感じずにはいられない。まるでNRBQを思わせるファンキーでダンサブルなピアノ・ロックである。このナンバーにはカントリーバンドらしさは皆無である。
この#5辺りまではかなり明るいMontgomery Gentryで踊れるのだが、#6『Speed』を皮切りにやや落ち着いたSouthern Countryな本来バンドが演奏していたブルージーな感覚が首を擡げてくる。かなり哀しげなスティールギターが印象的な#6に続き、ジャジーなメロディを転がしながら、コーラスでは完全なハードロックに転調する#7『Hell Yeah』と、続けてダークな側面が突出してくる。
#8『Lonesome』でカントリー風のバラードがマッタリと流れ、ハードでブルージーな流れに傾きかけた方向を緩めるけれども、このアーシーなバラードもかなりアンサンブルが分厚い。ピアノ、オルガン、エレクトリックギターがかなりのロックンロールを叩き出しカントリーしたドブロギターからその雰囲気を奪おうと鬩ぎ合う。
#9『Why Do I Feel Like Running』、#10『Free Fall』になると完全なサザンロックである。思いっきりうねるオルガンにローファイラップ気味のヴォーカルワーク。ロッキンブルースに他ならない。#2でスタートするアルバムでこのような粘っこい曲が出現するとは、とこのユニットを知らないリスナーなら驚くかもしれない。
こういった重いロックナンバーになると、やはりEddie Montgomeryのソウルフルなヴォーカルが大車輪で大地を耕し縦横無尽にブルースを披露してくれる。
#11『Lie Before You Leave』はビートが強く曲を牽引するダートなロックナンバーである。このナンバーはTroyがメインヴォーカルのためか、手触りが滑らかである。幾許かワールド・ミュージック的なメロディが耳に残るこれまたやや暗めのメロディを含んだナンバー。
後半で唯一といってもよい暖かさを放出しているのが、美しいロックバラードである#12『For The Money』。このナンバーもアーシーであるけれど、カントリーの色合いが薄いルーツロック・ナンバーである。
アルバムとしては前半にカントリーの分量を増したナンバーを配置して、後半にはロックとブルースで固めた曲を集めた2部構成を狙ったとしか思えない。
#13『Good Clean Fun』に至っては激烈にファンキーなロックナンバー、ファンクロックである。南部サウンドの黒っぽさがメジャーの発売とは思えないくらい振り回されるライヴ感覚一杯のロックナンバーである。正直別バンドにしか思えなくらいハード・ドライヴィンである。このナンバーが最もハメを外しているというか、既存のイメージからの脱出を企画している曲に違いない。
#1や#2でソフィスティケイトされ過ぎと眉を顰めたルーツファンも後半の曲を試聴して貰えれば、随分印象が変化するだろうから、是非とも。
さてさて、このデュオのアルバムを聴いていると、インディで真面目にルーツやカントリーロックを表現しているアーティストと殆ど温度差がないことに気が付く。普通ならナッシュヴィル辺りでマイナーシーンに沈んでいても不思議ではない音楽性である。
しかし、Montgomery Gentryはデヴューからして幸運に恵まれていたのだ。メジャー・レーベルの目に留まりやすい場所で活動をしていたからである。
1963年生まれのEddie Montgomeryは音楽一家に生まれている。ファミリーバンドを営む一座であるHalord Montgomery And The Kentucky River Expressの一家に生を受けたEddieは5歳からステージに立っていた。
また彼の弟のJohn Michael Montgomeryは一足先にミュージシャンとして独り立ちし、1992年からAtlantic Recordsでヒットアルバムを放ち続け、Billboard Top 200の常連アーティストになっていた。弟のソロ活動と並行して結成されたJohn Michael Montgomery And Young Countyに兄のEdwardは遅ればせながらプロとして参加することになった。このバンドに加わっていたのがTroy Lee Gentryである。
Troyは音楽一家に生まれた訳ではないが、10歳になる頃にはローカルのカントリーバンドで歌っていたと言う経歴の持ち主であった。
John Michael Montgomeryのバンドプロジェクトは2年で解散してしまうが、EddieとTroyはその後も意気投合し、デュオヴォーカルのユニットとして活動を開始。トップ10にアルバムを放り込むヒットカントリーシンガーであるJohnの兄と言うことで注目をデヴュー時から集めていたEddieの活動をColumbia Recordsがバックアップ。
そして1999年のいきなりのメジャーデヴューに至る訳である。
無論、Montgomery Gentryにヴォーカリストとしての実力があったから人気が出ているのだろうが、彼らは自分で曲を書くことを殆どしないスタイルを選択している。つまりシンガー・ソングライターという人種ではないのである、厳密には。
他のライターが提供した良作を歌うシンガー専門なデュオなのである。このため、アーティスティックな評価はいまいち低いのであるが、現実として良いアルバムを作成し、売れている。2ndアルバムもゴールドディスクを獲得し、1年で3枚目をリリースすると言う順風満帆な活動が成功を物語っている。
出来ればもっと自作曲を増やして貰いたいのだが。3枚目にしてMontgomery Gentryは遂に自分たちが創造した曲を1つもトラックインしないという手法を選択している。
こういった経過を知るに至り、メジャーに登場することが出来ればもっと評価されるAlt-CountryやRoots Rockのアーティストは数多いだろうことが痛感される。裏返せば、ヒットシーンにはまだ良質なアメリカン・ミュージックが入り込む余地があるということだろう。
但し、その時に掲げる錦の御旗は“Country”でなければ一般受けはしないだろうが。それを良しとしないアーティストがこれまた多そうだから、そう簡単にルーツロッカーのマイナー陣が日の当たる場所に出ることは難しいだろう。
しかし、Montgomery Gentryの「My Town」がトップ40アルバムになるのだから・・・・・・。 (2002.12.13.)
 Sleepless / Peter Wolf (2002)
Sleepless / Peter Wolf (2002)
Roots ★★★☆
Pop ★★★☆
Rock ★★
Blues ★★★★
You Can Listen From Here
5作目のソロにして前作である「Fools Parade」では、4thアルバム「Long Line」のロック/ロッキンブルースなアルバムを期待していたのに、かなりロックンロールが乾いて枯れてしまった如くのブルースが主体のアルバムになっていたこと。
これに相当肩透かしを喰らわされたという印象が強い。
アルバムの完成度は恐らくこれまでのPeter Wolfのソロの中では最も高いアルバムだったろう、1998年発表の「Fools Parade」は。所謂MTVジェネレーション−シングル向けなナンバーを極力減少させて、ナチュラルで自らの原点の1つであるブルースにこれまで以上の歩みよりを見せたソロ作であった。
ヒットしてトップ40入りした2作目までとトップ40ヒットを生んだ3作目、そしてライヴ感覚がはちきれんばかりに詰まっていた4th「Long Line」よりも明らかにギアの入れ方を異にしたアルバムであったと思う。
然れども、やはり「Long Line」のロックンロールなパワーに嘗てのJ.Geils Band時代の熱さを感じていた故、「次もロックアルバムを」という待望を背景に聴いた「Fools Parade」は、ロックというコンテンツに関してはやはり満足度は高いものではなかった。
しかし、この「Sleepless」を聴いてから再び「Fools Parade」をドライブに乗せてみると、とんでもない。「Fools Parade」はかなりのロックアルバムであることが改めて分かるのだ。
つまり、「Sleepless」が更に枯れたブルースの世界に足を突っ込んでいるアルバムである、とこう言いたいのだ。
同じ意味であるが、よりJ.Geils Band時代から続いてきたPeter Wolfのステイタスである“ロック・スター”から遠ざかったスタンスに踏み込んでいる領域が増したということでもあるだろう。
事実、これまで20年間に僅か6枚のソロ−本作を含めてであるが−しかリリースしていないが、J.Geils Band在籍時の仕事を含め、この「Sleepless」が最もロックンロールという単語を直に当て嵌め難い作品となっている。
また、本作は最近Bostonの新アルバムを配給した中堅レーベルであるArtemis Recordsからの発売、つまりソロキャリア初のメジャー以外との契約になっていることからも、売れ線のロックンロールからますます距離を置き始めていることが判断できよう。
余談だが、このArtemis RecordsにはMarah、Graham Nash、Beth Neilsen Chapman、Steve Earle、Lisa Lobeといった日本のレコード屋でも容易にお目にかかれるアーティストが所属を始め、ビルボード誌では「NYCで最も急成長したインディペンダント・レーベル」と評されていたりもする。
ルーツ系に限らない総合系の中堅レーベルでこれからも面白いアーティストが出そうなレコード会社なので、スカも多そうだがそれなりに注目していきたい。閑話休題。
しかし、5作目「Fools Parade」でのロックのスローダウンが緩衝材として作用したのだろう、今作「Sleepless」の枯れ具合に対してはそれ程失望することなくかなり素直に噛み締めて聴くことができたと思う。
Peter Wolfがロックンロールの熱量や圧力だけでなく、そのような直接攻撃に効果のある手法から一歩引いてじっくりと味わう音を創っていることが予備知識として存在したから。心構えというと大仰になるけれど、Peter Wolf=ジャンプするビデオ・クリップに出るオヤヂという図式が先入観から消えたことが、素直にこのアルバムを受け入れられる下地になったのだ。
ちなみに筆者の未だに最も好きなPeter Wolfのアルバム「Long Line」(1996年)のレヴューは以前に筆を執っているので、興味があれば一読して戴ければ幸いだ。
このアルバムは当初、2001年には発売できるだろう、とPeter Wolfのオフィシャルサイトには掲載されていた。しかし、蓋を開ければ結局2002年の後半戦に差し掛かった折にロール・アウトしてきたという遅延を記録している。この遅れについてはまあ、それ程残念であったことはない。
しかし、2001年にはPeter Wolf関連で動きがあったので、アルバムは2001年には届くだろうと予想していたのも確かである。その動きとは、この「Sleepless」で重要な部分を担当しているミュージシャン関連の作品である。以下、簡単に説明しておこう。
2001年末に、キーボーディストでヴォーカリスト、プロデューサーも専門に行うという多才なニューヨークの職人Kenny Whiteが初のソロアルバムを発表している。Kenny WhiteはPeterの前作である「Fools Parade」にプロデューサーも含めピアノやキーボードの担当をしていたかなり年嵩のピアニストである。
Kennyのアルバムに関してはここで殆ど全てを試聴することが可能だから、この名前に興味のある方は是非。
内容としてはピアノ中心のアクースティックなフォークポップという感じの佳作だ。Kenny WhiteはこれまでにShawn Colvinを始め、Marc Cohn、Jonathan Edwards、Cheryl Wheeler、Bill Stainesといったフォークシンガーやコンテンポラリー・ミュージックのシンガーのアルバムにピアニストやエンジニアとして地道に参加してきた人である。
その人脈の成果か、Kenny Whiteの遅すぎるデヴュー作「Uninveted Guets」にはShawn ColvinやMarc Cohnといったメジャーなシンガーを筆頭にかなりの名うてのセッション・ミュージシャンがゲスト出演している。
その中に、今年6枚目のソロ作をリリースしたPeter Wolfがハーモニカで参加していたとクレジットで確認した時は正直驚いた。「Fools Parade」の製作過程で築かれた人間関係がかなり良好なものだったのだろう。元来、Peter Wolfというアーティストは孤高というよりも一匹狼的な雰囲気の強い人で、あまり他のミュージシャンの作品には顔を出さないからである。
本人はかなりくだけた人格の持ち主(くだけ過ぎな不良老年らしいが、実際)であるそうだが、Peterの強烈な個性が仇になり、他のアルバムでは浮いた存在になり易いのだろう。しかし、このようなマイナー・プレスのアルバムでは十二分に彼の持ち味がゲストとしても活かせることを実証している。
そして、今作「Sleepless」でもKenny Whiteは殆ど全トラックでピアノやオルガンを叩いている。また、プロデューサーもKennyとPeterの共同クレジットとして記載されている。
「Fools Parade」ではKennyだけでなく、複数のプロデューサーとPeterがアルバムの作成を行うというスタイルを選択していたが、今回はKenny WhiteとPeterのみの作業となっている。
これを知った時は、Kenny Whiteのデヴュー作品に何処か近いアルバムが出来るかもしれない、と漠然と予想したが、それは遠からず的中したようだ。
PeterもKenny Whiteとの仕事によってかなりの影響を受けたと語っている。PeterもKennyも古典ブルースとR&Bの熱心なファンであり、どうせならその黒人音楽を併せて、ロックンロールよりも主体にした作品に仕上げてみようという開き直りをしたそうである。
前作でもその方向性が顕著に表れていたが、今作では更にアクセルを踏み込んでR&Bとブルースでロックを表現するという手法を煮詰めている。
少なくとも、Peter Wolf=ロックンローラーという嘗て『Centerfold』等のヒット曲で抱いたイメージは随分薄れてしまったことに間違いない。この古典ヒットシングルが古過ぎるというなら『Long Line』や『Up To No Good』のメインストリームに沿ったロックナンバーを思い浮かべて貰っても問題ないだろう。ロックにブルースやR&Bを融合するというレヴェルよりも更に濃厚な世界へと突入した感じである。
この転換は、ある意味J.Geils Bandの初期に回帰したというべきだろう。アルバムを重ねる毎にPop/Rockへの歩み寄りが強くなり、完全なPop/Rockのバンドにブルースロックを混ぜたような作風になった解散前のJ.Geils Bandも初期はもっとしつこく重いホワイトブルースロックなバンドだったのだから。
「Fools Parade」の発表の際、Peter Wolfはアルバムに対する感慨をこう語っている。
「僕が常々最も貴重だと見なしているのは歌い手と歌の間に何ら距離のない、確かな正直さだけがあるという音楽なのさ。『Fools Parade』で、僕はついに長年創りたいと思ってきた作品を完成させることが出来たと感じている。」
であるから、「Fools Parade」の段階で当面のPeterが進んでいく方向はロックンロールよりもブルースやアクースティックに比重を置いたサウンドであるだろう、とその時に感じていたので、Kenny Whiteのアルバムでの協力がそれを確定的な予感にさせたといってよい。
実際に、アルバムを通して眺めてみるとロックナンバーは皆無。
敢えて、ロックンロールを探すとすれば、カントリー・タッチのロッカバラードと表現する方が適当だが、ビートの力強さではロックと呼べる#2『Nothing But The Wheel』とゴスペル・フィーリーが充満しているソウル・バラードのダイナミズムが足踏みしている#4『Never Like This Before』の2曲くらいだ。
J.Geils Bandやソロ活動の前半でメインにしていたハードでブルージーなホワイトブルースのロック・オルタナティヴという方向性は完全に影を潜めてしまっている。
しかし、それでPeter Wolfの魅力が削がれたというと、そうでもない。
やはり、本音は「Long Line」のようなロックでライヴ感覚のあるパワフルなアルバムを求めているのは確かだけれども、「Fools Parade」からのじっくりと自分の原点を見つめ直している様子の年齢に相応な渋い音楽性もそれはそれで魅力がある。
が、やはりメジャーでプロモーションするには幾ら名声を有したビッグ・ヴォーカリストとはいえ、現行の市場性ではかなりレコード会社も難色を示したのだろうか、前述のように初のインディ・レーベルからの発売となっている。(日本ではEpicが配給しているが。)
それはそれで、ヨシ!!
Peter Wolfクラスのミュージシャンはもう十二分な成功を経験しているから、制約の多いメジャー・レーベルで頭を悩ますよりも中堅クラスのインディで作品を納得の行くまで煮詰めて欲しいと思うからだ。
結果としてアメリカのルーツ音楽である、ブルースとR&Bを中心に、カントリー、ソウル、ゴスペル、そしてロックンロールを少々、以上をアクースティック楽器を中心に燻し銀の魅力に染め上げている。
これまで以上にルーツ/トラッドに傾倒したアルバムであるが、やはりPeterらしいメジャーな感覚は何処かに残留していてスマートな都会的音楽センスがトラディショナルへの追及の中にもしっかりと打ち込まれていて、古臭いけれども現代的なアメリカン・ルーツミュージックとして聴ける箇所がしっかり存在しているのだ。
さて、このアルバムには各曲に対するPeter自身のライナー・ノーツ、歌詞、及びレコーディングミュージシャンのクレジットが丁寧に付けられている。このあたりは流石にメジャーを経験してきた人であり、充実なサービスが嬉しい。
日本盤も出ていることだし、Peterについての経歴は全く言及しない。「Long Line」のレヴューでもそれ程は触れていないが、そちらも参照してもらえればバイオ関係については多少の補足にはなるだろう。
とはいえ、やはり、参加ミュージシャンはかなりの顔ぶれが揃っている。
Kenny Whiteは前述のように全てのトラックでピアノ又はオルガン、ウィルツアー・ピアノを担当しているが、マルチプレイヤーとシンガーの才能をここでも発揮し、ギター、バックヴォーカルも務めている。
ギター、ベース、ドラム、そしてバックヴォーカリストには前作の面子がそのままスライドしている。
特筆するのはBob Dylanのツアーバックを頻繁に務めているペダル・スティール弾きのLarry CampbellとDylanのバッキングに限らずTom WaitsやAl Andersonといったヴェテランのアルバムでアップライト・ベースとエレキ・ベースを弾いているTony Garnierがアクースティック・ベースで参加していること。
Rolling StonesのMick JaggerとKeith Richardsがそれぞれ1曲でヴォーカルと楽器で協力。KeithのバンドのベーシストであるCharlie Draytonがドラムを叩き、そして元J.Geils Bandのハーモニカ吹きであるMagic DickがハーモニカをKeith Richardsと同じ曲で披露している。
ホーンセクションとしては、Tower Of Powerのような多くのリーダー作がないために、知名度としては低いがRolling StonesやJ.Geils Bandのライヴにも帯同しているUptown Hornsも顔を見せている。
そして、Steve Earleも1曲でヴォーカルとして如何にもSteveらしいナンバーでデュエットをしている。
メインのソングライターは、前作から引き続き、PeterとWill Jenningsである。この2人がオリジナル曲の8つのうち、6つを書いている。Steve WinwoodやEric Clapton、Barry Manilow....と数え切れないシンガーと作詞、作曲をして名曲をたくさん排出しているJenningsの参加は非常に感激である。21世紀に入ってもライターとして、コンポーザーとして活躍しているのは嬉しい限りだ。
残り2曲はPeterと他のライターの共作となっている。
また#2『Nothing But The Wheel』はJohn Scott Sherrillというカントリーシンガーの新曲を取り上げている。
後の3曲はクラッシックブルースやソウルのカヴァーとなっている。
#1『Growin’Pain』ではマンドリンとペダルスティール、そしてオルガンがダークに、そしてユルく、スワンプを暗くしたようなメロディを淡々と流す。「ここらあたりじゃあ、全てに苦悩が増すばかり」というラスト・フレーズに代表されるように、求道的、というよりも救いようがない苦悶を唄った内容だ。
しかし、今回のアルバムはPeterのキャリアの中で最も痛い歌詞が多く、求めても得られない、救われない、前途が見えないという歌がオリジナルでは大半となっている。一言でいえば、ヘヴィでペシミスティック。
僅かに希望を今後に匂わせるナンバーも存在するが、それすら例外的。内省的な歌詞というよりも自虐的なとことん心の暗黒面を追及して穿り出して、晒すことで問題に直面してみろよ、という意図を汲み取りたい。そう解釈しないとあまりにもこの歌詞は痛過ぎる。
#2『Nothing But The Wheel』は外部ライターの曲だけに、多少はマシな世界が歌われているが、「もうオレにはハンドルを握って車を走らせることしかない・・・・。」と逃避する内容である。メロディ的には優しいロックナンバーであり、Peter Wolfの懐の深いヴォーカルが胸に響くこのアルバムでは即効性が抜群に高いナンバーだ。Mick Jaggerがハーモーニー・ヴォーカルとハーモニカで参加。
Peterがこのナンバーを聴くとJohn Lee Hookerを思い出してしまうと述べている#3『A Lot Of Good Ones Gone』はSteve WinwoodやJoe Cockerが唄ってもピッタリな最高級のソウル・バラード。Uptown Hornsのテナーとアルトのサックスフォンが実にムーディだ。「良い奴等はみな逝ってしまったけど、オレは前に進むさ。」とこのナンバーでは前向きな姿勢が見て取れるが、実に寂しく哀しい歌ではある。
同じようなバラード#7『Five O’Clock Angel』は更に地味だが、トラッド感覚は#3以上に深い。
フォーク・ワルツという感じにゆったりと揺れる#8『Hey Jordan』も佳曲である。
Booker T.Jonesの曲を取り上げ、目一杯ゴスペルスウィングしているのが、#4『Never Like This Before』である。このアルバムには珍しいくらいのデライトフルなナンバー。
ブルージーなアクースティックな#5『Run Silent,Run Deep』ではラインの暗さと共に、歌詞も示唆的な死を唄っているようだ。
J.Geils Bandでも初期に取り上げたOtis Rushのカヴァー#6『Homework』では完全なブルースをコテコテな隙間の多いアレンジで再録している。
が、それ以上に即興的なのが、Keith RichardsやMagic Dickが参加して「大量のウォッカ」と一緒に一発撮りされたライヴ感覚剥き出しの#9『Too Close Together』だろう。ジャジーで、ジャズのア・ド・リヴ性をまったく加工せずに振り回しているだけのバー・ロックである。とてもメジャー・シーンで活動いていたアーティストのアルバムに加わる曲には思えないほどルーズでセッション・デモそのままだが、そこがまた良い。
オリジナルは1960年。シカゴ・ブルースの歌い手Sonny Boy Williams2世が録音している。オリジナルはここまで粗くなかったように記憶している。
Steve Earleの声が聴けるのが#10『Something You Don’t Want To Know』だ。マンドリンやフィドルが目一杯カントリー・フィードバックした、Peterとしては初めてここまでカントリーに踏み込んだ作品だろう。Steveはハーモニー・ヴォーカルだけかと思いきや、短いがソロも歌っている。声の質が異なるオヤヂなヴォーカル2人だが、かなり酔っ払った感じのパフォーマンスには思わずニヤリ。
残り2曲はゴスペルの雰囲気がたっぷりだが、#11『Oh Marianne』ではブルーグラスやテックス・メックスの影響を裏側に感じるような曲が聴ける。スケールの大きなバラードであり、Kenny Whiteのピアノとオルガンは素晴らしい。隠し味として入っているアコーディオンもより南部の雰囲気を伝えている。
#12『Sleepless』は「オレはまだ眠れない。」という神経が衰弱した心情を静かに歌い上げている。シンプルそうなオープニングだが、ホーンセクションやペダル・スティールが加わって、これまたバラードとしてグイと盛り上がっていく。しかし、この歌詞に見られる訴え掛けは相当に切実な求道を見ることが出来る。
1996年の「Long Line」を発売するまで、5年以上ステージにも立たず、ずっと逼塞していたPeterだが、最近はJ.Geils Bandの一度だけのリユニオンステージに立ったり、「Fools Parade」のリリース後は不定期だがライヴを再開したりして、また精力的に活動し始めたようだ。
しかし、LAで活動するプロデューサーにしてソングライターの同姓同名の人と間違われることが多く、データを調べる時にも一苦労する。(苦笑)
ここまで深く、精神の内面の弱さや絶望に触れた歌をPeterが歌ったのは初のことだと思う。完全にロックスターであった『堕ちた天使』を歌っていたWolfは過去の遺物になってしまった感が強い。
「Fools Parade」で求め始めた音楽性が一気に、しかし控え目に全開になったような、オヤヂのアルバムだ。
じっくりと歌を聴きたい夜には非常に良いのではないだろうか。 (2002.12.8.)

 Love Note / Big Silver (2002)
Love Note / Big Silver (2002)