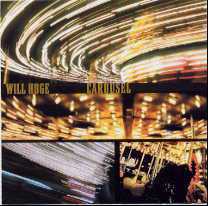 Carousel / Will Hoge (2001)
Carousel / Will Hoge (2001)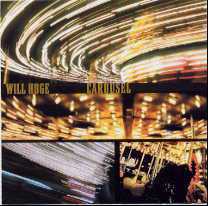 Carousel / Will Hoge (2001)
Carousel / Will Hoge (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Southern&Soul ★★★★☆
Will Hogeの名前はGeorgia Satellites大好きの私のレーダーに昨年から引っかかってはいたのだが、如何せん、ライヴアルバムがいまいち好かんので、あのDan Bairdがツアーとデヴューアルバムに参加しているという1stアルバム『All Night Long Live At The Exit/In』は欲しとはい思いつつ、入手は結構後になってからだった。ダン吉関連は常に速攻で手に入れたがる私にとっては珍しい出来事やなあと我ながら思う。最もライヴ盤で気に入るのはたまにはあるのだが、女性ヴォーカルになると更にヒット率が下がり、オルタナ関連になると「くたばってくれた方がわしの精神安定のために嬉しいアルバム」の方が多いし。ましてやGeorgia Satellitesが好きやぬかしといて、Pearl Jam最高とか言い腐ってるタコは波動砲で原始分解してやりたなる。あのようなクソバンドとサテライツを一緒にして欲しないわい!・・・・あああ、また話がヘヴィネスのこき下ろしのネタになってしまうま。しかしながらそっち系のHPってヒット数が結構あるので更に悔しかったりする。尤もうちのようなページがカキコ過多で管理人が困るという自体は月が落っこちてきてもないのは間違いないが。(笑)さて、1stのライヴアルバムだけど、確かにダン吉が久方ぶりにバリバリにギターを弾きまくっているし、曲もウィルの声もかなり良い感じだった。とはいえ、やはりフェイヴァリットになるのは難しい、自分の場合は。EaglesやElton Johnのように20年以上聴き込んできたバックボーンがないとなかなかベストアルバムにはなってくれない。という訳で、このWill Hogeの場合なまじライヴアルバムがかなり良かっただけに、スタジオ録音アルバムをかなり心待ちにすること大であった。(の割りにはオークションで送料込みで$8で競り落としてたりするんはヒミツやで〜〜。安い方がエエ!!)
心待ちにしていたアルバムの殆どが後悔と悔しさの涙に沈没と相成った2000年度の悪夢がいまだに滅茶苦茶記憶に新しいので、(というか半分トラウマやったね。去年は。)「過度な期待はせえへん、したらアカン」、と自戒ひとしおだったが、このアルバムに関しては、本当に幸いで、そのまんま期待通りだった。2001年の出だしは結構順風満帆であることよ。いずれレヴューしようと意図しているTerry Andersonも期待を裏切らへんかったしね♪。注文かけてる20枚くらいのCDも当たりがぎょうさんあるとエエんやけどね・・・・。揃うのは2ヶ月くらい後やと思うけど。(涙)
さて、まずこの実質の1stアルバム『Carousel』だが、意味は「大宴会」、「馬鹿騒ぎ、大騒ぎ」「酔っ払いの饗宴」言う感じのニュアンス。タイトルソングの#10はこの意味に似つかわしくない、非常に孤独な内面を唄った曲であるが、まあそれはそれで取り敢えず、宴会大好き(壊)!!と訳の分からん毒を吐いても仕方ないんで、真面目に話を戻すが、まさに酒盛りの如く元気で陽気でガンガンとフックの効いたアルバムである、これは。兎に角「イエィ!!ロケンロール」と叫びたくなるアルバムなこと請け合い。この点、単なるヘヴィな音をロケンロールと勘違いしてはるアホリスナーは正座して反省せえ!!(以下自粛)とまれ、14〜15曲入りのアルバムが珍しないこのご時世にたった10曲で、しかも30分少々のアルバムで勝負しているその心意気や良し1本。(いつの生まれや?)全く奇を衒わないストレートなロックアルバムで、ソウルフルなウィルのヴォーカルはかなり説得力がある。ファーストシングルでありハモンドオルガンとドラムの掛け合いのリフが楽しい#3『Ms. Williams』の明るいミディアムロックナンバー他、3曲が(タイトルは若干変更されているが)このアルバムでもリテイクされてるが、残りは新曲。特に#1『She Don’t Care』から#2の『Let Me Be Lonely』のロックでソウルテイスト満載の流れは圧巻。#6や#8でややブルース的なアプローチも見受けられるけれど、基本は#4、7、9のようにキャッチーなロックンロールで、#10のタイトル曲や#5『Heartbreak Avenue』でのバラードでのウィルの粘っこい納豆のようなヴォーカルはめっちゃ印象が深い。
残念なことにDan Bairdはバンドを脱退してしまったが、本音をいうとまたぞろどこぞの新人アーティストを発掘してくれるか、それとも漸くソロが出るのかと考えて、嬉しかったりする。(笑)何でもウィルのギグを見たダン五郎が積極的に彼に声をかけてきて、つるんで活動するようになったとのこと。現在は後任のギタリストのBrian
Layson とWillとの付き合いが長いTres Sasser(Bass)、Kirk Yoquelet(Drums)がバンドのメンバーであるそうな。当初はプロデューサーにあのGin BlossomsやReplacementsのJohn Hamptonを予定していて共同作業をしていたが、彼はエンジニアとしての協力に留まり、インディ系のアーティストを相当数プロデュースしているScott Parkerをプロデューサーとして迎えている。勿論、ダン・ベアードもエンジニアとして敏腕を振るっているのだが、あの顔と敏腕は似合わん思う。(笑)
Will Hogeに付いてあと少々捕捉しておく。カントリーロックのメッカであるナッシュヴィルの出身で、活動拠点も同じとのこと。とはいえ、彼の音楽はカントリー的な臭いは全く無いんが面白い。彼自身もその点について、「ナッシュヴィルにはカントリー系でない良いアーティストだって沢山いるさ。」とコメントしている。楽器を始めたのは18歳と意外に遅く、年齢は正式なプレスが無いが結構おっさんであるような気はする。(笑)で、1991年にSpoonfulいうバンドを組んで活動を始めて、解散後は幾つかのユニットを組んでは解散いう活動を草の根で続ける。そんなこんなのうち、現在のリズムセクションの2名を従えたギグをDan Bairdが見て惚れ込むいう飛躍のきっかけをつかむことに相成る。で、意気投合した彼らはバンドを組み、ウッドストック99に出演。2000年にライヴ・アルバムをリリースして2001年の本作とリリースが続き現在に至る。影響を受けたシンガーは
Van Morrison、 Otis Redding、 Tom Petty、 Chuck Berry、 Bruce Springsteenそして
The Rolling Stonesだそうで、理想のアーティストはオーティス・レディングだそうだ。彼のソウルフルな歌唱法を聴くと成る程とは思うバックグラウンドである。
私の苦手な黒っぽさはないが非常にソウルフルな歌であるし、カントリー系のダサさも皆無。まさに王道アメリカン・ロックである。少々懐かしいがCurtis Stagersという非常に素晴らしい新人(1991年作品)のデヴューを彷彿とさせる。サザン・ロックや上記の大御所が好きな方には是非とも聴いて欲しい。
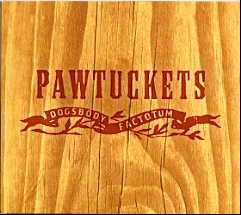 Dogsbody Factotum / Pawtuckets (2000)
Dogsbody Factotum / Pawtuckets (2000)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★
Rock ★★★
Country ★★★★
これまた非常にマイナーなバンド(であると思う。)の紹介をさせて頂く。彼らは海外のレヴューでは結構デヴュー当時のWilcoとかと比較というか引き合いに出されることがそこそこある。ウィルコは日本盤が3枚ともリリースされある程度の知名度を日本でも維持するバンドではあるが、このPawtucketsは全くといって良い程知られていない。レコード・デヴューもWilcoやSon Voltとあまり変わらない1996年である。まあ、パウタケッツにはUncle Tupeloでの事前活動によるカリスマも無いし、メジャーチャートにもランク・インしていないので仕方がないことではある。時にこのアルバム2000年の末にリリースされたので、筆者が入手したのは年を明けてからである。このへんのタイム・ラグは如何ともし難いが致し方なかろう。(涙)然れども、このバンドは決してメジャーでは売れないと思う。少なくとも現在の路線を堅持する限りは絶対にBillboardのナショナル・チャートのTop200に食い込むことも難しいと思う。以前、私的名盤の第一弾のレヴューでGin Blossomsをレヴューしたが、そこで触れた「ジンブロ未満」の典型な特質を備え、なおかつメジャーシーンでも受け入れ難い、商業カントリー音楽とは無縁のダサい土臭さが満載だからである。彼らはテネシー州はノックスヴィルの出身のバンドで1996年に1stアルバムの『Cloud 9 Ranch』を自主制作でリリースしてから今作の『Dogsbody Fuctotum』で3枚目を数える。ほぼ2年に1作のペースであり、インディバンドとしては早くも無く、遅くも無い無難な活動であり、まさに彼らの「普通な」音楽性を反映しているようで、思わず苦笑してしまう。
1998年の2ndアルバムである『Rest Of Our Days』が1stアルバムに比べてかなりポップさが増していたために、今作では良い意味でメインストリーム的な音出しに傾倒するのではないかと、漠然とした予想をしていたのだが、見事に外れてしまった。ポップさはやや後退し、非常にカントリー・ロックとしてのバンドのアティテュードが増している。しかも抜けるような陽気なカントリーメロディではなく、どこか陰りのある落ち着いたサウンドが特徴的である。う〜む、これも「Alternative」的要素なんやろか?ようわからへん。(汗)概して述べれば所謂オルタナ・カントリーであり、典型的なUncle Tupeloのフォロワーというか−語弊がありそうなので、敢えて述べておくがジェイ・ファーラーやジェフ・トゥデイの模倣というバンドではない−ネクスト・ウェーヴ的なバンドであるという印象が強い。がしかし、パンクというかガレージロックのテイストの強いテュペロとは異なり、より一層のカントリーサイドへの傾倒が強い。上記の評価の★をつける時、4番目の項目をCountryにすべきかAlt.Countryにすべきか非常に悩んだが、インフルエンスの強さから鑑みて、敢えてCountryとカテゴライズしたが、無論コテコテのウェスタンや商業カントリーではないことだけは留意して戴きたい。
明るさでいえば、屈託の無いデヴュー作『Cloud 9 Ranch』の方が上であろうし、エレキピアノやアクースティックピアノを多用した2ndアルバムにロックという要素では見劣りする感も拭えない。となると良いとこは何処やねん?と思われる方も多いと思うが、実際「これや」というパンチはないだろう。一番近いテイストや傾向としては初期のThe Jayhawksが最も近いと思う。詰まる所、地味なカントリー・ロック系のバンドである。但し、この手の音楽が好きな管理人のような嗜好のリスナーには非常にたまらない出来なアルバムである、と想像に難くない。どの曲も平均点な出来栄えであり突出したポップセンスは見受けられないが、実にさりげないポップさとルーツテイストが、甘さを抑えたクリームが絶妙に重なり合ったパイの如く深い味わいを醸し出している。先刻も述べたが「ジンブロ未満」という、無意識のうちの身を乗り出すようなポップさには今一歩及ばないが、全く耳に抵抗無く流れ込んでくる音は非常に質が高い。とはいえ、ピアノをフューチャーしたバラードは前作から変わらずメロディアスでそれでいてさりげなく、#10の『End It All Blues』や#12の『Smooth Water』は普通過ぎてそれ故に演奏するバンドが以外に少ない中で、きっちりとこのようなナンバーが入っているのは非常に嬉しい。#1の『She’s Gone』や#2のロックテイストが強いナンバーである『Where You Are』、#10『Old Fashioned Way』等、さりげないポップメロディはオーソドックスなアメリカンロックの良心のように気持ち良いナンバーであるし、#4『August In Arisona』のフィドルを絡めたキャッチーなカントリー風のナンバーはスマッシュヒットくらいはしても不思議ではなかろう。
このバンドは一応中核となるのがソングライティング・コンビのMark McKinney(Vocal,Guitar,Harmonica)と
Andy Grooms(Vocal,Piano,Acustic Guitar)である。William Tell Routineというバンドで活動していたMarkとGrooms
and Kellyというフォーク・デュオで活動していたAndyがお互いのライヴを見て友人となったのがきっかけでバンドを組み、ベーシストのMark
Stuartとペダル・スティール弾きの嘗てのバンド仲間Kevin Cubbinsを加えて発足した。ドラマーは毎アルバムごとに交代し、今作ではついにパーマネントのプレイヤーはいなくなり、3枚全てで準メンバー的なサポートドラマーとしてクレジットされているAnthony Barrasso他がドラマーとしてクレジットされている。興味深いのはハモンドB3プレイヤーとしてソロ作の日本盤もリリースされたRoss Riseがゲストプレイヤーに名を連ねているところか。
万人にお薦めというアルバムではない、特にメジャー・シーンのロックのみというリスナーには地味すぎるアルバムかもしれないが、そのような人はここへはアクセスしないだろうし。(笑)確かに地味であり、攻撃的な色合いは皆無に近いアルバムである。「僕たちはカントリー・ロックを狙ってプレイしている訳ではないが、たまたま皆のベストな表現方法がカントリーという要素で表現されているだけさ。もっとルーズな方向性でやりたいね。」とMark M.。「BeatlesやNeil Youngから影響を受けたよ。やはりシンガー・ソング・ライター系の音楽が原点かな。」とAndy。彼らが良作以上の傑作を出してくれることを期待したいし、可能性を伺わせるコメントであると思う。決して期待外れの方向へ行くことはないだろう。彼らのアルバムは全て良作のカントリー・ロックなので機会があるなら1枚は手に取って欲しい。・・・多分日本では売ってないだろうが。(汗)
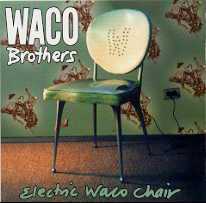 Electric Waco Chair / Waco Brothers (2000)
Electric Waco Chair / Waco Brothers (2000)
Roots ★★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Punk&Country ★★★★
レーベル買いというのを私はしない。以前ある方とお話して、マイナー系のアーティストをお薦めしたら「レーベルは何処ですか?」と尋ねられたけど、知らなかった。というか全く注意してなかったというのが正確な事実である。レーベルというブランドで買うより、自分の直感と(ようけ外れるやんか)感性(世間とずれとるやんけ)を信じたいのである。という建前はアレで、実はレーベル買いしとったら、全部のリリースが欲しゅーなるので予算的に無理なんねんけど格好良いやんけ、わし。(自爆)無論年間200枚近くCDを聴いていると門前の小僧ではないが、それなりにレーベルは覚える。このWaco Brothersがデヴュー当初から所属しているBLOODSHOT RECORDSはパンクとカントリー系のアーティストを多数抱える優良レーベルであるし、2000年にリリースされた5周年記念のコンピレーションである『Down To The Promised Land』にYayhoodsの新曲(?)が入っていたのは非常に嬉しかったりした。というお話は置いておき、今回のレヴューはそのBLOODSHOTを具現化したようなバンドである、Waco Brothersである。このことが言いたいためにレーベルまで持ち出したのだが、あまり効果が上がっていないようである。「文才の無さ身につまされる春の宵」・・・・一句できた。(腐)次第に人格破綻者たる地が出てきているが、その辺は棚に上げてレヴューは続く。
意外(でもなかったりする)とその活動の長さに比して、知名度がまたも絶望的に低いこのバンド、最新作である『Electric Waco Chair』で5枚目を数える。元々はパンク・ロックバンドの老舗The Mekonsのオリジナルメンバーとしていまだバンドに残っているJon Langfordがサイド・プロジェクトとして立ち上げたバンドである。活動拠点は彼の米国での定住先であるシカゴであり、いかにもアメリカ中部の中庸さが特色でもあるバンドといっても差し支えないだろう。無論、カントリーロック系のベーシックな中庸さであることは言うまでもないと思うが。しかし、ラングフォードのおっさん、このプロジェクトを維持しつつ、しっかりMekonsのアルバムもコンスタントにリリースしている。内容的にはJonのヴォーカルは余り好きではないので、最近作はそれ程評価はしていないがやはり驚嘆に値する活動であることを否定はできない。元来はMekonsではあまり表現のできないルーツ・テイストを演りたいがための色合いが濃いサイド・プロジェクトであった要素が強かったように思える。とはいえ、Mekonsも一時期ルーツ音楽に傾倒する時期もあったが、最近はやはりブリティッシュ・パンクに原点回帰しているようなので、やはりジョンはルーツ&カントリーも演りたいのだなあ、と感じる。さてさて、件のワコ・ブラザーズであるが、勿論血縁関係なバンドではない。メンバーは少々変動があり、2000年の時点では、Jon Langford(Guitar&Vocal)、Tracy Dear(Lead Vocal&Mandolin)、Alan Doughty(Bass)、Dean Schlabowske(Guitar&Vocal)、Marc
Durnate(Pedal Steel)そして Lil’Willy Goulding(Drums)であるが、彼は恐らくMekonsにも在籍し結成当初からのドラマーであるSteve Gouldingの変名であると思う。資料が無く未確認であるが。インナーの零細な顔写真だけでは判別が不可能である。1995年に1stをリリースしてから5年で5枚の非常なハイペースでアルバムを、しかも良作を出している。1997年には年末と年始に2枚のアルバムをリリースという70年代前半のメジャー・シーンの如くな離れ業も披露している。彼らの基本は当初に軽く触れたように、カントリーテイストとパンク・ロックである。詰まる所、オルタナ・カントリーと表現すれば良いかもしれないが、やはり彼らの場合は何故かわからないがPunk&Countryと表現した方がしっくりくる。というのはカントリーカントリーしたナンバーとパンクテイストな曲が交互に現れるといった構成が印象的だったからだらろうが、これも実はオルタナ・カントリーの特色でもある。う〜む兎に角、彼らの場合はこれで良いと範疇付けしているので、異論のある方は是非明確なカテゴライズをご教授願いたい。やや話がずれてしまったが(Always Happens)この「ワコの電気椅子」は今までで、間違いなく一番のポップ性が有り、しかもパンクとカントリーの極端な住み分けがなされていた過去の4枚と比べて一番両者の要素が巧みに融合している感が強い。特にファースト・トラックの『It’s Not Enough』はパンクテイストとカントリーの融合というよりは、良作なキャッチーなアメリカン・ロックであるし、続く#2『Make Things Happens』もパンク・ポップというよりやはりルーツテイストなアメリカン・ロックという表し方がしっくりくる佳曲である。まあ、元来彼らはゴリゴリなパンクテイスト満載な暴走系ではなくGreendayのようなポップ・パンクを身上としているのでポップなのはこのアルバムから始まったことではないのだが、実に上手にカントリー寄りの音楽に特有の野暮ったさを隠すというより、ロックテイストに包んで昇華している。#3のフックの効いたマンドリンの音が心地良いミディアム・スローナンバーの『Where The Mighty Fall』にしろ同じく#4にしてもフィドルが絡むナンバーであるが、自然とルーツ・ポップともいうべき洗錬された曲に仕上がっている。とはいえ、脱ルーツして普通のロックバンドに成り下がってしまったかというとそうではない。しっかりと埃っぽいテイストは毎曲間にその存在を主張している。#6や#7のブルースロック的アプローチ然り,#8から#9のカントリー・ロック調の連続は彼らが泥臭さへの憧憬を未だメインとしている姿勢が伺える。#10のキャッチーでエッジの効いたロックナンバーの『Nothing To Say』は筆者のかなりのお気に入りだし、ここからラストへの流れはドラマティックで変化に富
み、最後まで楽しんで聴けるアルバムである。
ちなみに「電気椅子」のタイトルは一貫して死刑反対を唱えている彼らの屈折したメッセージのようである。州ごとで死刑が廃止されていたり、執行方法も異なる連邦国家に住む人々の死刑に対する観念は、日本の死刑へのそれとはかなり多彩で大きく異なっているとは在住経験もあり、法学専攻の筆者も思うところがあるが、その前にWacoの魅力で感電死してしまっているので、米国死刑事情についてはまたの機会に言及しよう。(汗)
 Pocketful Of Sorry / Sorry (1997)
Pocketful Of Sorry / Sorry (1997)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Alternative ★★
Special Thanx Mr. Tim Chan
本来はこのアルバムを名盤に入れたいのだが、さすがにオフィシャルで発売されてないマテリアルを、名盤に入れてひけらかすのも、私の硝子の良心(ヲイ)が咎めるので。彼らを知ったのはこれまたカナダの全然本邦では知られてないバンド、The Skydiggers関連であった。カナダ在住の友人がスカイディガーズのライヴに行った際、ジョイントで出演していたSorryというバンドが非常に私好みやろう、と連絡をしてくれたのがきっかけである。当時北米でとぐろを巻いていた私だが、おいそれとBorder Crossingしてカナダに行くようなヒマは残念ながらなかった。故に、せいぜい「サンプルがあったら聞かせよし。」と「アルバム出したら教えておくんなまし。」くらいの返答しかできなかった。が、時は水洗便所の如く(失礼)流れて1999年、SOUNDASLEEP RECORDSのルーツファン必聴のコンピレーション・アルバムである『Hit The Hay Vol.3』に彼らの曲が収められていることを知った。その少々前にMP3でサンプルが入手できたと連絡が届いたが、アルバムを聴くのを楽しみにしていたので、友人には丁重にお断りして、アルバムの到着を待った。で、収録されていたのがこのアルバムのラスト・トラックである#10『Dear Shauna』であった。フックの効いた非常にポップでロックないかにもカナディアン・ロックなピュアさ全開な好ナンバーで、一気に惚れてしまった。やや古臭い60年代ポップスポップスのような音出しといい、コーラスで入るフィメール・バックヴォーカルといい極上なロックチューンである。で、アルバムのインナーにあったEメールのアドレスへ早速メールした。アルバム内のディスクリプションでは彼らのCDは送料込みで11ドル程で販売可能となっていたので返事を心待ちにしていた。と早速バンドのフロントマンであるTim Chan氏からお返事を戴くことができた。「残念ながら、私たちはオフィシャルにCDは発売してません。」ガーン、ガーン(以下10回以上繰り返して音を出して読むべし)!!が、「CD-Rで良ければ$5送金してくれれば送ってあげるよ。」との非常に嬉しい申し出を受けた。殆ど実費であるが有り難く申し出をお受けした。で、届いたこのアルバムであるが、兎に角非常に軽快でメロディアスなポップロックアルバムである。絶対にオフィシャルで売らない、否売れないのが不思議なくらいである。コーンやリンプやエネミムのようなくたばってしもた方が世界平和のための礎になって、余程世のため人のためのようなカスな音とは、全く比べ物にならないくらい良心的である。バンドのディスコブラフィーについてはオフィシャルでのりリースが無いために全く資料がない。Timさんとは定期的にメールをやり取りしているが「貴方の経歴について教えてください。」とは結婚相談所の調査員でないためそうそう聞くことができない。(汗)前述の『Hit The Hay Vol.3』によるとSorryは1995年にこれまたカナダのローカルバンドである『64 Funnycars』(さすがにここまでマイナーやと知らへんわい)のメンバーだったTim Chan(Vocal&Guitar)とEric Lowe(Drums&Vocal)がベーシストのMarcus PollardとKim Stewart(Guitar&Vocal)を迎えて結成したバンドとの事。活動拠点は西海岸のカナダであり、Timさんはブリティッシュ・コロンビア州在住である。メンバー全員がハーモニー・ヴォーカルをとるところはやはり米国ではないにしろ西海岸ロックの影響が顕著な気がする。ヴォーカルのTimさんと4曲でリードをとりくどくない声が私的にOKな女性ヴォーカルのKimさんの2枚ヴォーカルである。こういった男女混合スタイルはFleetwood Macというより1999年にDan Bairdのサポートで非常に素晴らしいアルバムをリリースしたBlue Mountainの3作目『Tales Of A Traveler』を彷彿とさせるヴォーカルスタイルである。このアルバムもローリー・スティレットのフィメール・ヴォーカルが良い味を出していた。全体としてはやはり女性ヴォーカルが苦手なせいか、Timの唄う曲の方が好みであるのは確かだが。#1の『Here Comes That Monday Feeling』#7『Friend By Habit』そしてKimのヴォーカルの#8『Mr. Sad』は非常にキャッチーなロックナンバーで文句の付けようがない。#4『Minty’s Song』、#5『I’ve Become My Father』の頬がゆるみそうな甘いポップナンバーはこれまた「よっしゃ」とポーズを決めたくなる出来である。#2〜3のロックチューンもTimに唄って欲しかった気がするが、良いナンバーである。#9の2人のデュエットで唄われるしっとりしたバラードの『indie Love Song』は先に賞賛した#10と並んで後半のハイライトである。兎に角、ルーツ・ロックというよりは亜米利加・加奈陀を問わないロック・ヴォーカルアルバムの傑作である。勿論、カントリー的な土臭さはないのだが、やはり広大なカナダの大地を感じさせるナチュラルさが程よく見え隠れしてて、人工的なサウンドの嫌らしさは微塵も無いので、万人に安心してお薦めできる。
ここまで読んで聴きたくなったそこの貴方、Tim Chan氏にメールすることをお薦めする。その際MOTOからの紹介といえば恐らく、多分、きっと、そうだといいが(弱)コピーを送って頂けると思う。もし質問があれば受け付けます。是非、このアルバムを聴いて欲しい。あ、Timにメールして紹介したことを知らせてやらなアカン。・・・・英語でないから読めんやろけどね。(スマソ)
 This Grand Parade / Fred Haring (2000)
This Grand Parade / Fred Haring (2000)
Roots ★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★☆
Contemporary ★★★
この人のアルバムもDan Baird関連というか、ダン五郎がプロデュースをしていると聞いて飛びついたものである。 とはいえ、1stアルバムの『Ghosttown And Kingdom』は1997年にしっかり購入はしていたりした。があまり印象に残ってなかったので、このFred Haringの2ndアルバム『This Grand Parade』の購入を機に棚から引っ張り出して聴いてみた。
だが、やはりインプレとしてはそこそこの良作であるが、対して心のキャッシュ・サーバーにメモリされない凡作であるという感が強かった。とはいえ、デヴューアルバムとしては平均点以上であるので、購入される際には全く躊躇する必要はないだろう。強力推薦とまではいかないが、耳を傾けて損はしないアルバムだ、1stの『廃墟と王国』は。
以前勤めてた会社の新人が「洋楽が聴きたい」というのでルーツ系からインディ・ポップ系のお薦めをCD-Rに落としてやったことがある。
(ハイ、筆者にそれを頼む時点で入門としては終わってるという突っ込みは却下や!!そこ!!)
で彼がのたまわった感想であるが、「ヴォーカルが結構似てません?」であった。その後、日本のゴミ以下のスライムコントロールしてやりたなりそうな似非音楽(絶対アーティストとは呼ばへんで〜)グループを引き合いに出してくれたので、十八番のアンディ・フグ直伝(ヲイ)の踵落としで大地の味を噛み締めさせてやったことはいうまでもないが。(実話)
で、アホ話は置いておき、結局の論点であるが、最近のヴォーカリストの声の傾向が画一化しているという問題というか流行を、音楽知識のない彼が指摘したことに一考の余地があると思ったということである。ハスキーというかシャガレ声系のヴォーカルが確かに目立って多いとは思う。
昔のロック・グループのようにリード・ヴォーカルを2、3人も擁していた頃とは時代が違うといえばそれまでであるが、ヴォーカルも楽器の一部として分業化が進んだことは90年代のオルタナ旋風以降の、良きにしろ、悪いにしろ、大きな流れであるとは思う。
筆者はハイトーン・ヴォイスが大好きであるがルーツミュージックにはハイトーン・ヴォーカルが似合わないというのが鉄則のようで、やはりハスキー系やシャガレ声系がメインストリームであるようだ。で、普段から音楽漬けになっていると気が付かないかもしれないが、やはり何処となく声の本質が似通ったヴォーカルを疑問なく受け入れているような気がする。
無論、悪いこととは思わない。が、そうであるからこそ、このフレッド・ハリングのような艶っぽい、魅力的なヴォイスに出会うと感激が倍増するのだ。彼の声を非才な筆者が表現するのは非常に困難である。ハイトーンでもなく、特筆する程ハスキーでもない。渋いガラガラの声でもない。
兎に角、よく通る声であることは間違いない。Billy JoelやElton Johnの70年代の頃の声や、Bruce Hornsbyのデヴュー当初の声に通じる要素を有した兎にも角にも王道的な魅力満載の声である。非常にしっとりした魅力を持ち、適度に甘く、適度に乾いている。彼のヴォイスはこれ以降のアルバムをその声だけで期待させてくれる吸引力が間違いなく存在する稀有な声質が内包されている。
その素晴らしいヴォーカルがDan Bairdとの唯一の共作曲であるオープニングのタイトル曲で流れてきた時、正直驚いた。ここまで飛躍してレヴェル・アップしたアルバムを聴かせてくれるとは想像してなかったので。
この『This Grand Parade』という曲は非常に示唆的な曲でかなり好みな歌詞である。インナーの裏ジャケットにも一部の歌詞が抜粋されている。
「I’m Glad To Be Here.I’m Glad To Be Alive Part Of This Grand Parade.I Know There’s No Guarantees.I’m Just Glad To Be Here One More Day.」と。
筆者のへっぽこPな対訳をつけて雰囲気をぶち壊すのも何なのでこのまま味わってもらいたい。この曲はゆったりしたうねりをピアノと力強いとギターが彩る傑作曲でさすがベアードという感じである。
しかも間髪を入れずに、Little Feetのビル・ペインばりのオルガン・ペダルのベタ踏みで幕を開ける#2『Work In Progress』は絶対にこのアルバムのハイライト曲である。1stでは見受けられなかったパワフルなロックチューンでこの辺りにもダン三郎の仕事の良さが見え隠れする。小気味の良いロック・ナンバーは他にも#6『There’s Song In My Head』(Dan Bairdのチェロが素敵だ)や#9の『Last Man Standing』にも見れるが、ややロックサイドへの突っ込みがダンがプロデュースした割りには少ない気がして、その点が不満なため、殿堂から外れたのである。
#3のピアノが美しいバラードの『A Prayer For Evan Dando』も素晴らしい。ちなみにこのアルバムからは全然その嗜好は伺えないがフレッドはLemonheadsの大ファンだそうである。歌詞的にはイヴァンへの揶揄が込められているようにも見受けられるが、フレッド曰くそれはないとのこと。
ヴァイオリンノスタルジックな味を醸し出す、#4の『Apathy』に続き#5、#7、#8といったゆったりとしたミディアム・チューンはどれも力強い牽引力がある。フレッドのヴォーカルは勿論のこと、ヴァイオリンやチェロを取り入れながらもカントリー特有の垢抜けない明るさを巧みに抑えたアレンジが、曲のソフィスティケイトに一役買っているのだろう。それでいつつイナタ臭い土の香りはきっちりとスパイスとしてちりばめられている。
要するに極上なアメリカン・ロックアルバムなのだ。#10の暖かく懐かしいメロウな曲『Forgive Me』ではフレッドのヴォーカルが非常に映えている。シークレット・トラックを含めて全12曲でハリングの成長が著しく伺えて、嬉しいのだ が、ここまで敏腕を振るったプロデューサーのダン・ベアードが何故もっとロックなアルバムに仕上げなかったのか正直疑問である。フレッドの声がスロー系の曲に填るのは確かだが、#2のようにロック・チューンでも存分に力量を発揮できるのは間違いない。その点が残念である。
かなりルーツ楽器を活用してミディアム以下の速さのナンバーが多い割りにはバランスの取れたコンテンポラリーなアルバムになっている美点はフレッドとダンの才能がもたらした福音である。良いルーツアルバムだが、カントリーという色合いは非常に適用が難しい位置付けをされている。
最後にFred Haringについて簡単に述べておく。大学卒というミュージシャンで(ドロップアウトしてない。人気が沸騰して学業に差し障らなかったからか?(笑))オハイオ在住で、ソングライティング歴は15年の経験があるそうだ。
影響を受けたミュージシャンはBob Dylan、Uncle Tupelo、Counting Crows、Poguesと多彩で、著者の趣味ともばっちり合致する。
なので単なるオルタナ・カントリー系のアーティストで終わらない予感を持たせてくれる人である。既に今年の秋に3rdをリリースする予定で作業に入っているそうであり、次回作に大いに期待したい。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
