 I’ll Drink To That ! / Terry Anderson (2001)
I’ll Drink To That ! / Terry Anderson (2001)Roots ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Southern ★★★☆
 I’ll Drink To That ! / Terry Anderson (2001)
I’ll Drink To That ! / Terry Anderson (2001)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Southern ★★★☆
しかし、待たされたものである。Terry Andersonが2枚目のアルバムである『What Else Can Go Right』を1stアルバムに次いでリリースしたのが1996年であり、Dan Bairdらの協力を得た快作アルバムである1枚目のリーダー作『You Don’t Like Me』の発表が1995年であったことを鑑みると、かなりの間隔が空いてしまっている。この2枚のアルバムが非常に豪快で、南部テイスト丸出しのロックアルバムであったので、すぐにリリースされるであろう3枚目に非常に期待していたのだが、かなり待たされることになった。この間、テリーの名前は殆ど表面に出て来なかった。元来メジャーではないので、敢えてメジャー・シーンとは記さないが。殊に、1999年以前の音楽活動になると全くと言って良い程情報が途絶えている。著者の知る限りでは1999年にルーツロック・グループのThe Backslidersの2ndアルバムに参加、2000年に(オフィシャル発売は2001年)P.J.O’Connellの初ソロ作である『Dream Life』に参加と近年になって漸く目立つ活動を始めたようである。1998年にコンピレーションアルバムである『Hit The Hay Vol.3』にこのアルバムに収録されている、かなりキャッチーでレイドバック感が嬉しいカントリー風のミディアムナンバー#8『Rock And Roll Girlfriend』が収録されているが、まさかこのアルバムにもトラッキングされるとは思わなかった。
さて、ではいったいこのゴッツいドラマーオヤヂが空白の間何をしていたかというと、本人がインナーに書いている文で明らかになる。ざっと和訳してみよう。間違い・誤訳等は筆者の能力不足であるからして、ご容赦願いたい。
「そうだね、全てはあれから始まったんだと思う・・・・・。ここ数年間、似たような歌を生み出す工場のようになっちまったテネシー州のナッシュヴィルで仕事してたんだ。けれどもカントリー系のラジオのために曲を書くことを強制されることは、ハンバーガチェーンの調理場で肉をひっくり返すのと同じくらい楽しいことに気が付いたのさ。だから俺は自分のロックとブルースの原点に立ち返るべく、ダコタ州はドッジに戻り、鳥撃ちを楽しんだ後、北カリフォルニアを目指して一目散という訳さ。」というコメントから、どうやらカントリー・ロックやオルタナ・カントリーのメッカであるナッシュヴィルでの活動に幻滅したようである。他のアーティストのためにライターとして曲を提供していたような口ぶりだが、どうもはっきりしない。進歩の無いテネシーのルーツ・シーンに嫌気が差しただけかもしれない。「全てのしがらみをとっぱらって、どんなのでも良いので自分が書きたい歌だけを書くことを決心した。どんなのでも自分がやりたいことを。しかし、そんなことを望むべきじゃあなかったんだ。というのも約1年半の間、何にもする気が起きなかった。で、さすがに焦り出したというわけさ。全く意欲が湧かなかったんだ。」というように、一種のスランプに落ち込んでいたのだろう。ドラマーとしてヴォーカリストとしては漸く前述のように活動を再開していたが、曲が書けなかったようである。で、これも紋切り型かもしれないが、ある日、ビールを片手に聴いたDave Edmundsのライヴテープがテリーの「やりたいこと」を思い起こさせてくれたそうである。こういったインスパイアのきっかけは良く耳にするが、アーティストには良くあることなのだろうか?
まあ、そのあたりはどうでも良かったりする。兎に角、Terry Andersonが帰ってきてくれたのだから。ジャケを見ると、トレード・マークのむさ苦しい長髪に口髭、サングラスというスタイルとは決別したようだ。相変わらずズングリ肥満体ではあるが、やや細くなったか?(笑)髭もアゴに申し訳程度に残すだけになって、更に別の意味でアヤシクなっているが、それもどうでも良かったりする。(笑)リリースのレーベルがどちらかというとパワーポップ系のしかもヒネリ系の音が得意なNot Lame Recordsというのもどーでも良いのだ!!(しつこい)兎に角、The Woodsの頃からのファンとしては彼の新作が、しかも全く期待を裏切らない出来であることを素直に喜べば良いのだから。
アルバムの内容はというと、キャッチーでまさにロックンロールなアルバムとしか言いようがない。相変わらず、活動拠点である西海岸を連想させない豪快で泥臭いサウンドが健在である。が、過去2枚のアルバムよりポップさはかなりストレートに前面に出されているし、豪快さも肩肘を張ったハードエッジなナンバーは影を潜め、リラックスしたお気楽な楽しいロックンロールと呼ぶべき感じになっている。勿論、いきなりガツンと魅せてくれる、アメロクの基本の如き#1『$ Of An Education』や#2のブルージーさが独特のスゥイング感を持つ『Daddy Had A Wreck』、軽快なノリがツボの#4『Boyfriend 2』、#3『Killin’ Down In Dillon』や#5のYayhoosを連想させる如き豪快な『Bad Enuff To Crawl』等、前半だけでもロックテイストに全く不足は無い。が、どれも実に正統派なアメリカン・ルーツナンバーであり、無理に豪快さを売りにしようとか、スマートなアレンジに纏めようというような、余分な意図が見えてこない。数年間における煩悶は良い形でこのアルバムに昇華されたようで、慶賀の至りとはこのことであろう。前作まではDan BairdやEric Ambelといったダンが結成したツアーバンドであるYayhoosのメンバーが演奏に参加していたが、今回は自身のバンド中心で彼らには「特別な謝意」で言及されるに留まっている。が、ここでもYayhoosの記述が見られるところを考えると、ヤイフーズは解散宣言はあったものの、パートタイムで活動をしているようでもあり、名前が残っているだけかもしれないが、メンバー間の絆は結構永続的なようで是非、本格的に活動して欲しいものである。おっと、話題がそれてしまった。アルバムの内容に戻るとしよう。#6の『Safety First』以降はややレイドバックしたスローな曲が多く、前半の息もつけないようなGood Rockn’Rollの大攻勢よりトーンダウンする感は否めない。が、ミディアムテンポではあるが、エッジの効いた#7『Nastiest House』と#9『Nya Nya Nya』はやはりサザン・ロック的豪快さが伺えるし、#11の『Mr.Busdriverman』は文句無しのフックの効いたロック・チューンで大満足。と思えば60年代のファンク・ポップのような#10『37 Miles In Reverse』があり、変化に乏しい印象は皆無である。ストリングスと雄大なコーラスが盛り上げる力強いバラードである#13『Stay Away From Your Heroes』ではウエストコースト的な側面も聴くことができて、テリーのバックグラウンドの1側面が伺えるような気もする。また肝心のテリーのヴォーカルは全く変わりなく、ブランクを感じさせることがない。ソウルフルであり、適度に甘く、そして渋い。・・・・・どんなんや??(笑)
バンドのメインは前作からの3人、Mike Krause(Guitar)、Jack Cornell(Bass&B.Vocal)と2ndアルバムではパーカッションがメインであったDave Adamsがピアノやオルガンにクレジットされている。彼らに加えてRoger Gupton(Guitar&B.Vocal)に主役のTerry Anderson(Vocal&Drums&Guitar)となっている。今作のプロデュースは殆ど全曲に渡りガンガンの元気ピアノを聴かせてくれている、Dave AdamsとTerry Andersonの共同プロデュースとなっている。
さて、Terry Andersonをご存知ないという困った方々に一応簡単に経歴を記しておこう。1941年、カリフォルニア生まれのドラマーで、80年代にThe Woods、Fabulous
Knobsというルーツ・ロックグループに参加している。The Woodsの2ndアルバム『It’s Like This』で元Georgia Satellites(涙)のフロントマンであるDan Bairdと仕事をし、ダンが彼の作である名曲『Battleship Chains』を取り上げたのを契機にジョージア・サテライツのアルバムにゲストとして参加し、グループの解散後はダン・ベアードの2枚のソロ・アルバムにバンドメンバーとして参加し、その延長としてYayhoosを結成すると共に、2枚の前述のソロ作をリリースし、約5年のブランクを経て、今作『I’ll Drink To That』をリリースした。・・・ホンマに簡単やね。(汗)
余談であるが、本作は約半年ほどリリースが遅れた。アルバムは2000年リリースとなっているが発売は結局2001年の1月になってからであった。まあ、出たからエエねんけどね。
兎に角。ロックである。アメリカン・ロックである。陽性バッチリ、非常に危険(謎)な傑作である。からして、ルーツファンのみならず、アメリカン・ロック・フリークには必須である。けど、このアルバム日本に来てるんやろか?本邦CD発売のお寒い現実が日米を分け隔てる太平洋以上の壁となって横たわっているように思えてならない。
(2001.4.14)
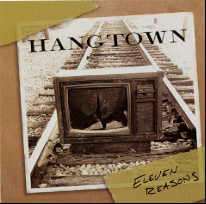 Eleven Reasons / Hangtown (2001)
Eleven Reasons / Hangtown (2001)
Roots ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Alt.Country ★★★★
今後というか、2枚目以降のアルバムを期待させてくれておいて、永遠にセカンド・アルバムが届かなかったバンドは記憶出来ないくらい多い。が、「所謂2枚目のジンクス」殊にデヴューアルバムで大売れした後のアルバムを聴いて、「聴くんやなかった。」と後悔の涙を流したことも快挙に暇がない。どっちがマシかと問われれば、やはりリリースしてくれた方がまだ良いと考える。理由?それは、早々と諦めがつくからである。(笑)何時までも、例え解散がステイトされても、「何時かきっと」的な希望を持ってリユニオンのアルバムを待ち続ける方が幸せなのは間違いないだろうが、ある意味幸せなのは釣りに行く前夜の興奮と同じで、待っている間だけが楽しく幸福なのである。散々待たされた挙句の果てが、積み上げた期待をハンマーで叩かれたの如く破壊し尽くす駄作では目も当てられないし、実際何とその崩壊の多かったことよ。であるからして、傑作アルバムを創ったグループは早々に解散してしまったほうが良いのかもしれない。とこのようなことをのたくりつつも、実際にそのような自ら伝説を創るような真似をするグループがいたら、絶対に許さないとは思うが・・・・。(笑)と、またも不満からの導入になっているが、要するにデヴューアルバムがかなりの良作であったこのバンドHangtownが2年のインターバルで2枚目のアルバムを兎にも角にもリリースしたことを喜んでいるだけである。1999年にリリースされたデヴューアルバム『Here For Now』は王道ルーツロックのアーシーさと、パワーポップのセンスが同居する、かなりの良作であった。ファーストトラックの『Second Chance』はまさにアメリカンロックのアメリカンロックという風情の傑作ロックナンバーで、海外のプレスにもニール・ヤングやスティーヴ・アールを受け継いだバンドという評価を賜っていた。出だしの曲があまりにも出色で後が霞んでしまうというアルバムは多々あるが、まさにこの1枚目のアルバムがそうであり、残りのトラックのレヴェルもかなり良好であったのだが、『セカンド・チャンス』だけのアルバムであるという印象が強いようであった。かくいう筆者も第一印象は全く同様であったので、何らその誤解を批判する権利を有しないが、聴き込むに連れて『Here For Now』が非常に良質なルーツ・ロック&ポップアルバムであること発見したので、この場を借りて訂正しておきたい。さて、1998年に結成され活動を開始したこのハングタウンであるがヴォーカリストであり殆どのソングライティング及びルーツ楽器を担当する、Ted Lukasがフロリダ州のタンパ・ベイ周辺で人気のあったパワーポップバンドであるBarely
Pink(2枚ほどのアルバムをリリースしている。詳細なデータが手元に無いためそれ以上の追跡が不可能である。ご了承を願いたい。)を解散後に立ち上げたバンドである。他のメンバーはBarely
Pink時代の朋友Aaron Akers(Bass)に Mike Anderson(Drums)、 Dave Korman
(Guitar)であり、後ろの2名もタンパ・ベイのインディバンドの出身である。サザン・ロックの豪快さと元パワーポップバンドの出身者で固められた故かのキャッチーなメロディに、ルーツフレイヴァーと、非常に将来が楽しみである1st作を届けてくれた4人組である。ベアリー・ピンクのようにストレートではあるがやや力技と説得力に欠けるなポップなサウンドよりも、アメリカンルーツに敬意を払ったサウンドをLukasはやりたかったそうであり、その意図が見事に1作目から成功していたので、2枚目を待つこと約2年で今作が届けられた時は嬉しかった。1枚のリリースのみで終わって欲しくなかったバンドであったが故のことである。で、冒頭に述べた「2枚目のジンクス」であるが、「デヴューアルバムで良かったアーティストが2枚目で良作を出すことは稀」という稀な方向へ傾いてくれたようだ。「傾いた」のであって「転んで」はいないのがポイントである。確かにとんでもない駄作ではないし、キャッチーなメロディも健在で実に安心して聴ける良質なルーツ・ロックアルバムではある。それには全く異論の余地は無い。LukasのSteve EarleやNeil Youngを連想させるようなヴォーカルも健在であるし、演奏も確実に技量が増しているのが良く分かる。#1の『Number’s Not The Same』から実にポップでアーシーな展開を見せてくれて、この曲以降のレヴェルの高さを容易に予想させてくれる。いかにもアメリカ南部のバンドらしいフックの効いたロック・チューン#2『Twist Of Faith』も大好きなタイプのオーソドックスなアメリカン・ロックナンバーである。音的には1stの旨味をきっちりと継承しているアルバムであることは確実である。#5『Curbside Blues』や#3『Let’s Hide Away』のようにハードでエッジの効いたブルージーなルーツナンバーも悪くない。ちなみにこのアルバムは#1〜#5までをSide1と、#6〜#11までをSide2と銘打ち、アナログ盤を意識した作りにしている。あまり成功しているというか意図がはっきりしないのだが、瑣末なことであろうからこれ以上は触れないで置くが。後半もブルース・ハープが土臭さを倍増してくれる#11『Less Than Nothing』やポップなルーツナンバーである佳曲の#6『Shoestrain Winter』や同様の#8『Can’t Get It Back』といった標準以上の楽曲が揃っていて、特別尻すぼみになったような印象は受けない。むしろこのように王道的なルーツ・ロック&ポップアルバムを仕上げてきたことに賞賛を覚える程である。が、しかし、手放しで完全に賞賛して、今年のベストアルバムには選べないように思えるのだ。期待が大きかったのかもしれないし、『Second Chance』程のキラー・ナンバーがないことが要因なのかもしれない。また、ややサザンロックの魅力である豪快さが抑えられてしまっているところ(これは成長の証ともいえるが)が不満であるのかもしれない。どうも、これという欠点は論うことが不可能なようであるが、一言で言うと「何かも一歩足りない」のである。所謂「ジンブロ未満」な中途半端なポップであるからか?いや、ジンブロまでとは言わないが充分ポップでコマーシャルである。が、微妙な線でもう一つ魅せてくれる要素があれば絶対に傑作になるだろうことが、まず確実なため、非常に歯痒いのである。それは疾走感やドライヴ感が少々増してくれるだけでも、コーラスを口ずさめるくらいのあと少しのキャッチーさが取り入れられているだけでも良かったかもしれない。または演奏に厚みを加えるルーツ楽器や鍵盤系の音がちょっとで良いので絡んでくれれば、とアーティスト側には失礼かもしれないが、デヴューアルバムに加えて発展させた何かの要素が欲しかったと切に思う。とはいえ、良作であることには間違いない。アメリカ中西部のバンドの如き中庸性をきっちりと保持したバンドであるし、音である。
誤解を招かぬように述べておくが、卑近な言い方では「冒険せずに、堅実路線を固持する意気地なし」のような批判をするつもりは毛頭ない。むしろ、少々売れたからといって勘違いし、ひたすらノン・キャッチーな自慰的芸術路線に突っ込んだり、全く異なるジャンルの音楽の要素を付加しようとして魅力を破壊してしまう尻軽バンドの類より、余程地に足がついていて、勇気があると思う。どのようなものでも創作活動に携わる者にとっては「没進化」という批判が最大級の恐怖であろうから。故にHangtownは今後も飛躍が期待できると確かに思える。筆者は同一の方向性を昇華させようと煩悶する限り、きっと何らかの前進があるだろうと信じて疑わないからである。この『Eleven Reasons』では同じ方向性で勝負をかけていくバンドの進化や発展や飛躍を表現することの難しさの5つのReasonくらいは解きほぐしてくれそうである。後の6つは何だろうか?(笑) (2001.4.14)
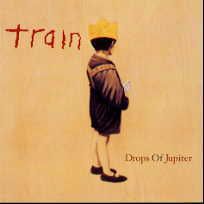 Drops Of Jupiter / Train (2001)
Drops Of Jupiter / Train (2001)
Roots ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★
Modern ★★★★
極、本当に極稀なことであるのだが、大した事のないアルバムしかリリースしていなかったアーティストが、突然変異のアルビノ(白子)のように、突如として素晴らしいアルバムを出してくれることがある。往々にして、こういった場合は入手がかなり遅れることが多い。幾ら年間200枚近く金盤を購入しているアホ物好きでも、ダメと事前に分かっているアルバムに安月給をつぎ込む愚は冒さないくらいの分別はある。と思う。ような気がする・・・・・・やっぱりないか・・・・・多分ない・・・・。何時までたってもハズレ引く強さが健在やしなあ。(涙)それはともかく、やはり前作が駄作やそこまではいかなくとも印象に殆ど残らなかったアーティストのアルバムを買うのには二の足を踏む。最近はネットの発達により、購入した方の御意見や試聴サイトでのトライアルといった手段が取れるため、暗中模索の度合いは減ったが、それすら安心材料には完全にはなりえない。という訳で、最近ではこれまでが気抜け炭酸のようなフニャフニャさが非常に気に入らなかった、Mervelous 3が良さそうだったがかなり購入を躊躇ったのが記憶に新しい。結局大当たりだったからこそ心のキャッシュサーバーにメモリされたのだが。で、今回紹介することになるTrainというグループもその例に当たっていたのである。
1998年、漸く雪が融けて、春らしさが重たい大陸の風の中に感じられるようになった4月、シカゴにて。何となく道化師のようなイラストの陰鬱な昏いジャケットに惹かれて、そしてあの私の90年代ベストグループであるCounting Crowsの鍵盤弾きのCharlie
GillinghamとDavid Brysonが参加していると知って躊躇無しで、衝動的に購入したのが彼らTrainの1枚目のデヴューアルバムであった。(この後に『One And A Half』というミニアルバムをリリースしている。)翌年の1999年にはメジャーチャートのTop100にもランクインし、最終的にミリオンセラーを達成するこのセルフタイトル・アルバムであるが、私にとっては毒にも薬にもならない、単なるラックのヌシと化し埃を被っていく程度のアルバムであった。正直な感想であるが、特に際立ったポップセンスも感じられず、とはいえ、疾走感やハードドライヴなロックテイストも皆無。中途半端なルーツテイストとオルタナサウンドが実に消化不良。苛つくくらい半端に重い。メロディもヒネリとネジリが多用される「これホンマにアメリカのバンドなんかい?大英帝国謹製やろ。」という筆者の苦手なラインしか見えなかった。まあ、何故か売れるというか売れそうな音ではあった。最近のアメリカンロック市場は本来の分かり易さを喪失した迷走する市場になっているので、個人的に断腸の思いがある。はい、脱線修正。が、この「列車」はまさに脱線した迷走(暴走という程にはロックしてへんさかいね。)列車であったのだ。私は切符を買ってしまったが途中下車を決意。実際にタラップに足を掛けていたのである。
兎に角、どこを切っても私的には全く特筆すべき点がないアルバムであった。不味い金太郎飴のようなアルバムだったのでしゃぶり尽くす前に口直しを求めてしまった。実際のところ帰国に際して、荷物を減らすために米国に置いてくるつもりであったCDであったが、何故か荷物の中に紛れて日付変更線を渡ることに成功している。が相変わらず棚の隅で埃の侵食を一手に引き受けているCDの1枚というステータスに変更はない。(笑)『Drops Of Jupiter』の購入に際して改めて聴き直してみたけれども、上記の認識は全く2年以上を経ても色褪せていなかった。シングルになりヒットを記録した代表曲『Meet
Virginia』もやはり「その他大勢の十羽一絡げ」的な歌である。『Free』や『I Am』のシングル曲も同様である。どう考えてもこのバンドがメジャーレーベルと契約し、100万枚を超える売上げを記録したとは信じ難い。が、今の全米チャートが筆者的には信じるに足りない。ヒットチャートに愛想をつかして久しいが売れてもしょうむないクズがもてはやされるのは、やはり精神衛生上宜しくない・・・繰り返しになるので割愛する。どうもいけない。鬱屈が激しいようだ、注意せねば。
と、途中下車を決め込んでいた筆者を躊躇させたのが2000年に偶然聴いた米国の人気TVドラマ(らしい)のサウンド・トラック『Songs From Dawson’s Creek Vol.2』に収録されていたトレインの新曲『Respect』(本作でも#6として収録されている。)であった。実は目当てはEvan And JaronやWheatusそしてトッド・ラングレンの後押しでデヴューしたSplenderであったりしたのだが。(汗)が、全く期待してなかったTrainのこの曲は素晴らしかった。抜けるようなギターをフューチャーしたドキャッチーなロック・チューンで前作のポップさでは味付けとして浮いていた、いかにも西海岸バンドたる爽やかなコーラスも素晴らしかった。セルフタイトルの1枚目のアルバムには影も形もなかった音楽性に、膝を思わず正してしまった。ちなみにこのサウンド・トラックは若手のAdlut Alternative系のアーティストが目白押しな良きサンプラーとして聴けるので結構お薦めである。という経緯でデッキから客室へと戻り、つらつらと待つこと約半年で、ついに2ndアルバムが手元に届いた。結論、すんません、侮ってました。脱帽。まさかここまでキャッチーなアルバムを製作してくれるとは夢にも思わなかった。2001年3月後半から4月にかけて一番のヘヴィ・ローテションとなっている。些か気が早いが、今年の私的ジャンプ・アップ大賞はこのアルバムで決定であろう。(と言いつつ来月には変わっていそうであるが。(笑))まず、1曲目の『She’s On Fire』から非常にポップでキャッチーなナンバーが飛び出す。これで度肝を抜かれた。ここまで明るく分かり易い曲が来るとは思っていなかった。前述の#6『Respect』は良くある「これだけ良い」歌という可能性を捨てきれなかったので。#2のルーツテイストが上品に見え隠れするミディアム・テンポの『I Wish You Would』ではハーモニカやマンドリンが前作では中途半端だったアーシーな魅力を過不足なくぶつけてくれる。そして、メロウで歌詞もロマンティックな#3の「木星の雫」のピアノバラードで敢え無く沈没した。ここまでAlternativeとAlt.CountryとModern Rockの旨味を絶妙に混ぜ合わせられるともう悶絶モノである。#4『It’s About You』ではモダン・ロックのテイストを力強く盛り上がるメロディに上手く乗せている。ミニアルバム『One And A Half』に収録されていた#5の『Hopeless』は1作目の曲に近い暗い陰りのある曲であるが、味付けのピアノとオルガンが重厚さを付加してくれているのでそれ程鼻につかないで済む。#8、#9も同様なやや前作を引き摺った感が強い重苦しいオルタナ・ナンバーが続き、このアルバムで中だるみが感じられる箇所である。もう少し何とかして欲しかった。前半のような明るいテイストに仕上げてくれれば文句なしだったのに。#10『Getaway』と#7『Let It Roll』もやや暗めのナンバーで少々残念ではあるが、さりげないポップセンスは聴き応えがある。最後の11曲目の『Mississippi』のアクースティックなスローナンバーはしっとりとしているがやや地味過ぎか。概して後半の5曲がまだまだ吹っ切れていないというか、息切れというか、サニー・サイド的ウエストコースト・ロックに成り切れない躊躇のようなものを感じてしまうが、十二分に良作以上のアルバムである。アーシーなテイストとオルタナティヴの歩み寄り、トラッド・ロックの魅力が顕著に感じられる、Adult Alternative Rockの好盤と私的に認定する。ぼちぼち日本でも発売されて良いとは思うのだが。プロデュースとキーボードの殆どを担当しているのが、あのBrendan O’Brienである。この人もDan Bairdらと良い仕事をすると思えば、Pearl JamやStone Temple Pilotsといった射殺したいくらい重いだけのいてもーたれヘヴィネス系のプロデュースをしたりと、非常に評価が難しいのだが、今作は良い方向性を打ち出しているので、しゃあないから評価したるわい。(笑)
さて、Trainというバンドについて知らない方が多いと思うので説明しておく。結成は1994年と、発車は結構昔のことである。当時LA在住だったヴォーカル&サックス担当のPat Monahanが元ApostlesというローカルバンドのヴォーカリストRob
Hotchkiss(Guitar&B.Vocal&Harmonica)と組んだユニットが始まりで、サンフランシスコへ拠点を移し、アクースティック・ジャムバンドとして活動を開始し、Jimmy
Stafford (Guitar&Mandolin)、 Charlie Colin (Bass)を加え、 Apostles時代のバンド仲間
Scott Underwood(Drums&Keyboards)を迎えて5人編成なったのが1994年のことだそうだ。それから地道なツアーを続け、98年にセルフタイトルのアルバムリリースが決まった頃は、Matchbox 20、Barenaked Ladies、Counting Crows、Better
Than Ezra といったメジャークラスの前座としてツアーを共にするくらいのステータスを得ていたようである。デヴューアルバムにCounting Crowsのチャーリーとデヴィッドが協力したのもツアーでの既知の繋がりらしい。ジョイントしたアーティストを見れば明白だが、基本的にアメリカンロックの良心的なサウンド(一部その後堕落したマッチ箱のようなバンドもあるが)オリエンテッドなバンドとカテゴリーを同じにしているようである。今作を聴くと充分に納得できるのだが、デヴュー作はやはり中途半端であった。
兎に角、今後は超特急にステップ・アップしそうな予感がするバンドである。鈍行列車に零落れる危惧もなきにしもあらずではあるけど。(笑)是非、乗り遅れることのないように聴いてもらいたいアルバムである。 (2001.4.15)
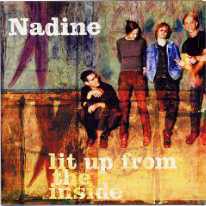 Lit Up From The Inside / Nadine (2000)
Lit Up From The Inside / Nadine (2000)
Roots ★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★☆
Folk ★★★★
実にペースが早い。何が早いというとリリースの間隔である。彼らがデヴュー・アルバムの『Back To My Senses』をオフィシャルにリリースしたのが、1998年の初夏であるから、2000年の時点で最新作である3rdアルバムの『Lit Up From The Inside』まで1年以下の間隔でコンスタント過ぎるペースを保っている。しかも、私的殿堂入りアルバムである2作目『Downtown,Saturday』を含めて駄作は全くない。(というてもたった3枚やけどね。とはいえやはり特記すべき事柄であるとは思う。)少々メジャーで成功して「リリースに間隔を空けるのが大物の証拠」という錯覚に取り付かれて何年も待たせた挙句に、駄作を届けてくれる勘違いバンドより、成層圏と石炭層くらいの志の高低があると考える。無論、Nadineは志が高い方であるのはいうまでもないが。多作が良いとは迂闊には発言できないが、10年待たせてクソのようなアルバムを出したDon Henleyに爪の垢でも煎じて飲ませてやりたい、というよりあのホテカリオヤヂには家の風呂の垢を舐めさせてやりたい。(怒)勿論、頭を足で踏んづけて「ほら、響子さん(誰や?)、ここが汚いわよ。」と小姑の如くいびるのは必須である。(笑)・・・・ああああまたスタンピートしそうなので、ネイディンのポジティヴな批評に戻るとしよう。彼らの活動拠点はアメリカ中部のミズーリ州州都セントルイスである。著者もアメリカ勤務時は何回も仕事で出かけた地方都市である。ここらは標高300メートルを越える土地が皆無で、ひとたびイリノイ州の郊外に出ればひたすら農地と平原が広がっている。果てしない地平線が望める大平原である。このような土地に暮らすと、やはり人間スローダウンするのであろうか、Nadineの織り成すサウンドは優しく、奥行きがあり、そしてまたグレート・プレーンズの風景の如く心に安らぎをもたらしてくれる。寒い冬に大きなストーブに掛けたシチューがじわじわと煮込まれるような、そんな感じの包容力がある音世界を彼らは構築している。脳天を直撃するような即効性の効いたパワーポップ・ナンバーや埃が舞う乾燥帯からの土臭さ満点のサウンドでもなく、どこまでも耳当たりの良いアクースティックな自然さ。それでいて、遠い昔の少年の日に、秋の鈍色な草原に寝転がって嗅いだ草や大地の臭い、そして太陽の臭いという風情のテイストが瑞々しい。非才なる筆者には的を得た表現が困難なくらい非常に微妙なアーシーさが曲間に根付いている。特に2ndアルバムでのルーツに敬意を払ったロックテイストとアーバン風のな優しさと孤独が混じり合ったサウンドは絶妙である。最新作である本作『Lit Up From The Inside』ではこれまでの練り上げてきたサウンド・タペストリーは確かに健在であるが、惜しむらくはアメリカン・ルーツロックの香りがかなり後退してしまっている。アクースティックな面は以前からの彼らの魅力であったが、そちらもブルーグラス的なアーシーさというよりはブリティッシュ・ポップスのような流麗でスマートな印象が強くなっている。60年代の英国フォークロックに通じるテイストが増しているようである。1stアルバムの頃に顕著であったカントリー&ルーツサイドへの追及が薄れているようである。とはいえ、勿論コテコテに泥臭いルーツナンバー大好きの筆者の嗜好を鑑みれば、充分にルーツテイストは健在であることは間違いない。当然のことながら、カントリーやブルーグラス嫌いなリスナーに敬遠される根源のような存在であるクドさは皆無である。やはり大陸風のアクースティック・ポップ風な方向性が強まっているようである。ややロックテイスト自体が薄れているのが個人的に残念であるが、それでも心を落ち着かせてくれる優しいアルバムであるからして、静かな夜に聴くにはもってこいの1枚である。ルーツ好きに絶望視され、海外レヴュアーの間でも「suck」を連発されたWilcoやJayhawksそしてHoneydogsのように極端な脱ルーツロックには全く手を染めてないので安心して戴きたい。ただ、やはりアレンジ、特にドラムやエレキギターの音はやはり土臭さが弱まり、この場合は良い意味でソフィスティケイトされている印象が感じられる。しかし、悪くはないがやや不満ではある。繰り返しになるが。
全体としてはやはりジェントリーなルーツアルバムとなっていて、#1のNadineの得意技であるキャッチーでスローで心温まる『Without A Reply』から幕を開ける。#2『Losing Track』も同じ魅力が満載でヴォーカルのAdam Reichmannの適度に甘い、微量にオブラートで包んだような暖かい声がしっとりとした好ナンバー。#3の『End Of The Night』ではやや都会風のセンスが見えるミディアム・チューンに少々驚くがポップなラインは健在で何ら不安を抱かずに聴ける。続く#4『When I Was A Boy』はスピーディなオルタナ・カントリータッチの曲であるが、英国的なセンスが伺えて、英米要素混在な歌のようである。#9の『Just Couldn’t Lie』も似たようなセンスが光る曲で、1stアルバムの代表曲であった『Back To My Senses』とそっくりなメロディラインを持ち、現在のネイディンが過去の名曲を焼きなおしたような感覚が見えるロック・チューンである。得意のセンシティヴなスローバラードも無論存在し、#5『Streets』、#10『Still Be There』、#12『Four Years Ago』と枚挙に暇がないが、#10は#6や#8のように英国的ポップさとアレンジが顕著でやや違和感がある。この辺りの曲が不満といえば不満である。そして、やはりルーツバンドと再認識させてくれるのが、バンジョーが美しい#7の『Lead The Way』やレイドバック感溢れるオルガンとスライドギターが魅力であるムーディブルース風の#11『Every One-Sided Story』だろう。やはりこういう曲ばかりではうんざりするが、必須で何曲かは絶対にトラッキングして欲しい。
今作から紅一点、女性ベーシストのAnne Tkachがメンバーとして加入し、1stアルバム以来の4ピースに戻っている。元々ゲストを殆ど活用しないバンドであるが、前作のように半数のトラックをWilcoのKen Coomerらに頼らなくともドラミングに専念できるようになったTodd Schnitzerがドラムを叩いている。彼はベースとキーボードも担当し、相変わらず多才である。そして、ギター類を引き受けるSteve Raunerとカナダ人のリードヴォーカルとギターを担当のAdam Reichmannの4人で演奏・作詞作曲をして外部の助けは借りていない。Special ThanksにCentro-Maticのバンド名が見れるのが意外である。このバンドはかなりノイジーな手法でルーツロックを表現する、言ってみれば彼らとはアプローチが対照的なバンドであるからだ。完全に余談になってしまったようだ、失礼。
いずれ、私的名盤のコーナーで『Downtown,Saturday』を紹介する予定なので、バンドのバイオグラフィー関連に就いてはそこで述べたいので、このくらいにしておく。
基本的に、非常に地味なバンドである。ドライヴ感覚溢れるロック・チューンは殆どないし、煌びやかなサウンドとも無縁である。泥臭い豪快さが売りでもない。イリノイやミズーリの大地のように落ち着いてどっしりしたサウンドが彼らの持ち味である。どこまでも広大な農園の風景のように牧歌的で優しく暖かい。しかしながらどこまでいっても地味バンドであるため、まずメジャーでブレイクしそうもないバンドである。日本盤も絶対に出ない。(断言)現在のくだらないUKロック至上主義の日本のマーケットでは売るだけ無駄であろう。全くあのような分かりにくい音が格好良いという感覚は異星人並である。纏めて金星か火星にでも移住して欲しい。そないなリスナーは。(笑)
Nadineの彼らたる所以は、しっとりとした甘いアダムのヴォーカルに乗ったメロディが5月の雨のようにしっとりと心の奥に積もっていくような魅力が身上である。即効性はないけれども、まさに「内側から火を付ける」の如く、じわじわと良さが染み込んでくる音である。聴けば聴くほどに味が良く分かるようになる。勿論、ポップセンスにかけては素晴らしい才能がある。ただ、表現方法が控えめであるためかなりマイナーなサイドに位置しているだけであると思う。このレヴューで幾らかのリスナーにLit Upし購買意欲をFrom Insideから刺激できればこれ以上に幸いなことはないと思う。1stは入手が困難であるがそれ以降の2枚は結構手に入る筈である。質問大歓迎!フォークロック好きな方にもお薦めしたいアルバムである。 (2001.4.15)
 Everyday / Dave Matthews Band (2001)
Everyday / Dave Matthews Band (2001)
Alternative ★★★★
Pop ★★☆
Rock ★★★★
Roots&Jam ★★★
このDave Matthews Bandの輸入盤(2割くらい安い。もっと安うせえ!)を捕獲して帰宅したのは、再就職の目処も立った3月の下旬に差し掛かる頃であったと思う。桜の蕾がぼちぼち春めいてきたくすんだ空に小さな薄桃色の穴を開けるぬるま湯のような日々の頃・・・・・・・。
と、ここまで真面目に書いてきたが、
皆さん、お待たせしました。一部で好評を戴いた「実録シリーズ傑作選」 ・・・・何しか余分な修辞か増えてるねんけど・・・・・・。
満を持しての復活やで〜。ぢつは単なる衝動で行き当たりばったりやんか。・・・・・ゴズッ!!!!「グフッ・・・・・」
ということで要らん突っ込みいれるわしの良心を撲殺してもーたので遠慮なく逝くでえ別名「管理人の恥部の切り売り」という実録シリーズ第2段。
ということで次回に続く・・・・・。来週をお楽しみに〜。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒュ〜〜〜〜〜〜〜〜(南極)
すんません、ちゃんと(か?それほどのもんか?)やりまっさ。
第二回 嗚呼、無情
さて、些か季節に合致したような心地で私は帰宅したねんけど、部屋の前にアメリカからの郵便物が置いてあった。
特に珍しくないことなので、Everydayをプレイヤーに乗せつつ、早速やや厚めの封筒を開けてみた。ふむ、1曲目はかなり重めのロックやね。電気ギターとキーボードの主張が強いやんけ。オルタナ臭いか・・・・・。と思いながら開封。
入っておったのは見知らぬ赤ん坊の写真やった。
「???????????何やこれ????」
で、写真の余白にサインペンでメッセージが。取り敢えず読んでみる。当然やね。
「貴方の子供も2歳になりました。会える日を楽しみにしてます。Y江。マサーチューセッツにて。」
「コーン!!」(アゴが床まで落っこちた音)
「ほんげらげんだらっらっららびっちょほにゅへええええ〜〜〜〜〜!!!!!ポロピロ〜〜〜〜!!!」内心のパニクリを擬音語化。
「待て、ギミアブレイく、俺。落ち着いて考えなアカン。ヒトヨヒミニヒトミゴロ。富士山麓に光子力科学研究所や。」
(錯乱中)
「2歳で今年が2001年やから『ちゅうちゅうたこかいな、ちゅうちゅうたこかいな』で1998年頃のテキサス・ヒットか」
(まだ錯乱中)
「な〜んや。98年やったらわしアメリカにおったやんけ。ああ、驚いた。」
(思考力混線中)
「・・・・・・?」
「な〜んか、間違ってへんか???」
(くどいようだが、パニクリ中)
「あらら・・・・・・」
(以下、こないな混乱が続く。)
「何やとお〜、わしあっちにおったやんけえええええ〜〜!!!!」
以下、内心の擬態語に戻ってこのサークルを好きなだけ繰り返しておくんなまし。
「待て待て、落ち着いて考えてみな。」
<カチカチ、チーン。カチカチカチ・・・・・ジージー> ※俺的こんぴーたーが過去の栄光悪行をスキャンする音。
「LAではあの美人のタイワニーズに振られて・・・・・。」
<カチカチ、チーン。カチカチカチ・・・・・ジージー>
「会社のバイトの中華系2世にも、肘鉄戴いて・・・・・・・。」
<カチカチ、チーン。カチカチカチ・・・・・ジージー>
「シカゴでは全く女ッ気なしのチベットの修行僧な日々を・・・・・。」
<カチカチ、チーン。カチカチカチ・・・・・ジージー>
「ニューヨークでは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・な〜んや全然ダメやんけ。俺。わはっはっははっはっはは」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。喜ぶべきなんかなあ・・・・・・・。」
「うむ、エエンやろね、きっと。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
「そやけど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
「なんしか、心が痛いねんけど、気のせいかいな?(涙)」
(答え:気のせいではありません。)
「で、誰やねん!!こないなえげつないいたずらするんは!!」(とヘルメットとプラカードを持ったオヤヂが出てきいひんか一応、チェックしてから。)
出し人を確認。
「誰や、これ。知らんで。」
ついでに送り先を見ると。
全然住所がちゃうやんけ!!しかも宛名は山MOTO某・・・・・・・・・・・。
ヲイ、郵政省改め(以下自粛)省なめとんのかあああああ〜〜〜〜!!!(何故小文字? 答え:小市民だから)
痛ひ記憶のみ、ほじく出してしもーた、2001年春。痛いのオレだけ。
全く人騒がせだが、ここで写真をうんが〜!!と破ることはボキの(ヲイ)良心が許さない。
ホンマはこのビビリを山MOTO某が味わうかもしれへんので、内心期待している、人間のクズ。
何やこれ〜〜〜〜〜!わしをなめとるんかああああ〜〜〜!!
(暴れん坊●軍と化す)
暴れたいが、ここで怒りモードに突入してまうと、自分の存在を否定して後悔するという(以下痛いので割愛)
ホモ・サピエンスとして完全に終焉を迎えそうやさかい、
ただ
♪ルルル〜〜〜るるる〜〜〜♪(涙)
モードへ切り替えて、最後の一線に踏みとどまる。
今回の結論
壱:日頃の行いに自信の無い人間はいずれ因果応報
弐:人間忘れたいことは都合よく封印できる
参:葉書の宛名は開封前に確認しませう
このお話はフィクションではありません。(涙)
ちゃんとしレヴューを期待された方へ。この時は殆どDave Matthews Bandは聴けませんでした。(あたし前や)
とアホはこっち置いて、真面目なレヴューをという希望があればちゃんと書きます。
・・・・・前にもそないなこと言うた記憶が・・・・・ないわな。(笑顔)※弐参照のこと。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
