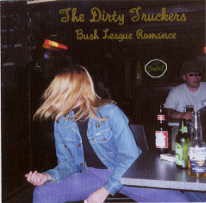 Bush League Romance
Bush League Romance/ The Dirty Truckers (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★★
Southern ★★★☆ You Can Listen From Here
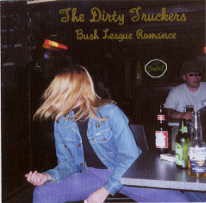 Bush League Romance
Bush League Romance
/ The Dirty Truckers (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★★
Southern ★★★☆ You Can Listen From Here
Special Thanx To Mr.Tom Baker
ラフでラウドで、それでいてハードという単語よりRock n’ Rollという表現がぴったり当てはまる、疾走感と爆裂感に満ち溢れたギターの音。豪快で、ポップでキャッチーなメロディライン。死滅して欲しいオルタナへヴィ茄子のようなアーティフィシャルなアレンジやサウンド処理は微塵も聴こえてこない。
中部アメリカ、ミネアポリス周辺や東海岸に顕著に見られる、腰抜けパワーポップ(自称)のようなフニャフニャした軟弱さは皆無。
メジャーチャートで売れている、商業カントリーの錘の外れた凧のような不必要なわざとらしい明るさよりも、カラリと
晴れ上がったような、吹っ切れて乾燥した切れ味の良い音出し。
何処までもストレートなロックテイストは、ガレージパンクの系譜に連なることを連想させるけれども、ノイジーなだけのタテノリバンドでなく、しっかりと大地に根差したアメリカン・ルーツテイストが、爆走だけの飽き易いサウンドにこのバンドを位置させない。パンクテイストをルーツの包容力で包み込むことにより、両方の旨みだけをロックという生地に乗せ、調理は完璧なロールとしている。
出来上がったのはロールキャベツではなくて(寒)ロックンロールであるけれど。
しかし、ここまでキャッチーなメロディを力強いギターリフに絡めて、しかも直球勝負のロックで表現されてはもう言うことがなくなってしまう。筆者の最大のツボを突いて突きまくってくれる。
ポップさでいけば、ここ数年の私的両巨頭Mount PilotとPat McGee Bandに匹敵している。
もうキラーシングルがないとか、アレンジがラフ過ぎる、とか普通のアメリカンロック過ぎとか、どんな批判を受けようが、このバンド、「The Dirty Truckers」は最高の評価を与える。そうに決定。異論は無し。
もしも上記のMount Pilotがお気に入りのリスナーであれば絶対にヒット間違い無しである。作者の保証を付けてあげよう。
このアルバム欲しい方がいましたら、管理人までメール頂ければ幸いです。このバンドのリーダーであるTom Bakerさんに頼まれているので、それなりの価格で管理人が責任をもって輸入をします。本来このようなことはあまりやらないのだが、この素晴らしいアルバムを聴かされてはやはり広めずにはいられない。(価格は応募された方の数により交渉ですけど。誰もいないかも・・・・。)
しかし、このようなバンドが出てくるとは驚きである。80年代リスナーでGeorgia SatellitesやPontiac Brothers、Drivin’N’Criin’等のサザンロック系の豪快なハードポップ的な音楽性が大好きなリスナーには垂涎モノのアルバムであること請け合いである。
サザンロックと何回か書いているが、あまり南部音楽の趨勢の主流を占めるブルース的な粘っこさが感じられないのが特徴である。むしろ、嘗てのメジャー・シーンのメインストリームであった王道的なアメリカン・ロックのロックな部分が目立つ。つづめて述べれば、不必要に重くなく、パワフルなドライヴ・ロックが中心となっているということだ。
無論、筆者もブルースロックの一側面な重厚さは大好物であるのだが、反面やや暗いメロディラインを持つことや、アンキャッチーなサウンドを提示することがあるという点がややマイナスに思うことが多いのは否定できない。
が、ここまでシンプルなサザンロックの身上の弾むようなパワー・サイドのみを突き詰めてくれると、それだけで十分に重量感のある、腰の据わったサウンドができることを久々に再認識させられた。
西海岸系のサウンドのように大気圏の上の熱圏まで突き抜けていく程までの爽やかさはないのだが、過不足なく明るいポジティヴなメロディに溢れているので、聴いていて自然と身体が弾んでくる。
歌詞的には、ストレートなラヴ・ソングよりもややヒネクレた見方をした歌が多いように思える。まだまだ深いというレヴェルには達していないと思う、正直に。が、ここまでメロディが良いと歌詞は二の次な状態である。最近漸く歌詞にも耳を傾けれるようになってきた。当初はメロディに打ちのめされていたので。(笑)
ヴォーカルについてはギタリストでありB3も披露している、リーダーのTom Bakerが取っている。所謂、現在のルーツ系のインディシーンに目立つ、太くややしゃがれたヴォーカルであり、贔屓目に見ても美声ではないし、ヴォーカルの力量で差別化できるような程度までには至っていない。
しかし、かなりパンチ力のあるヴォーカルで、野太くガンガンと引っ張る演奏に力負けしない元気なヴォーカルであるので、このバンドのサウンド性とは非常に合致していると思う。やや個性に欠けると批判されると反論が不可能であるのは事実であるけれども。が、演奏とバトルの可能な声量と力は間違いなく有しているので、聴いているうちに自然と好きになるヴォイスであると考えている。演歌でいうコブシもしっかりと効いているので、日本では受け入れやすそうであると想像してもいる。(笑)ハイトーンオリエンテッドやオヤヂヴォーカル系が苦手な方でも、クドさは少ない方であるから慣れるのは早そうだ。
さて、一応各曲について簡単にインプレも述べておこう。
簡単に徹すると「捨て曲無し。」「兎に角ロックンロール。」とこれだけなのだ。まあ購入して聴いて貰うか、リンクからサンプルを試聴して戴ければすぐに理解できるとは思うのだが。
しかし、その2つだけでは著者が不完全燃焼なため、もう少し誉めておきたい。(笑)
#1『Settle Down』から既に彼らの魅力が炸裂している。何処までもポップでロックなメロディ。かなり荒っぽいドラミングに、ラフなギターサウンド。地味だけど確実なベース、とかなりパワーだけで押しているように感じる演奏であるけど、かなり技量は高いと感じる。後に記述するクレジットを参照すれば頷けるだろうけど。
もうシングルにすればロック系のチャートでガンガン上昇しそうなナンバーである。ドライヴチューンの典型である。
#2の『Backpack』も同じく、ドキャチーなロックナンバーだが、やや緩急をつけた強弱が曲にアクセントを上手につけていて一本調子なロックナンバーとはしていない。しかし、このパンキッシュな流れはパンクでもなくルーツだけでもない、その中間的な微妙な同類項をきちっと抑えていて、素晴らしい妥協点を見せてくれる。この要素は全トラックにも共通しているが。
#3の『All Wrapped Up』のスローでアクースティックなスタートから次第にルーツロックの豪快さを交えて盛り上がる展開はTomのメロディメイカーとしての非凡さが、地味なナンバーながら際立つ。同系統のスローナンバーに属するのはReplacemantsのカヴァーソングである#10『Sixteen Down』と、#5の『Thanksgiving』のミディアムスローなパワー溢れる歌、そして粘っこいハモンドB3とややブルージーなギターがやや裏声的なTomのヴォーカルと一緒に歌う#7『The Bar』の合計4曲だ。この#7はかなりパワー&サザンバラード的に枯れていてそれでもウエットなメロディが映えるという、背反する魅力が同居するロッカ・バラード的な傑作である。バラードシンガーとしてもTomが歌えることを的確に証明しているナンバーでもある。
#5でのリードギターは門外漢の筆者が感覚だけで感じることであるが、かなり感情が篭っていて、感動的であるという印象が強烈である。この曲も#7に劣らずロックのバラードとして堪能できる曲だ。
#4『Been Around』は結構直情的な恋の歌か。ルーツ・パンクという感じの曲調は初期のUncle Tupeloを髣髴とさせるものがある。まさにベーシックなオルタナ・カントリーとしての魅力も伺えるということであるが、やはり彼らの場合はアメリカンロックにルーツテイストが付加された王道ロックという印象が強い。これでパンクテイストがやや後退したら、本格的なHeartland Rockと呼んで良いかもしれない。
#6『In Quintessence』はこれまたストレートなロックチューンである。やや複雑な進行がサイケディリック的なロックの影響を垣間見れるようで興味深い。やや、シングルにするには粗過ぎるかもしれないが、ルーツロックの剛毅な良さが満ち満ちている。
#8『Hotel Highway View』と#9『The Rise & Fall』は取り敢えず、何処までも突き進む的なノンストップなロックナンバーである。この2連発なロックコンボはかなりタイトで後半にかけても全くトーンダウンしないアルバムの展開の素晴らしさを表していると考えたい。どちらの曲もゴリゴリなキャッチーロックであるけれども、#9のややすっきりしたアレンジやメロディの方がシングルとしては良いような気がする。
そして最後のナンバー『Any Offer』ではかなりハードなドライヴロックが展開される。ここではこのアルバム初の女性ヴォーカルがツインリードの形でフューチャーされている。Emily Groganという女性が単独で、あるいはハーモニーでTomとリードパートを分け合う形式を取っているのだが、フィメールヴォーカルの柔らかさが、ハードロックと呼ぶべき一番へヴィなナンバーを緩和させているように感じる。勿論、爆裂的なパワーと躍動感は損なわれていない。最後までロックに徹したアルバムとなっている。
例えとしてはBryan Adamsの『Reckless』的なキャッチーさがあり、ルーツテイストはGeorgia SatellitesやJason & The Scochersに順ずる、という表現をすればやや方向性が分かって貰えるかもしれない。あくまでも例としての参照であるので誤解されないように願いたい。
さて、この今年で今のところ上半期トップなバンドのバイオグラフィーについても少々述べておこう。情報は全てTom Baker氏から戴いたものであることをお断りしておく。
「The Dirty Truckers」の前身バンドとして1999年にミニアルバムを「Nana」の名前でTomは発表している。こちらもサウンド的にはストレートでキャッチーでタテノリバンバンのロックアルバムであるから、非常にお薦めである。ちなみにタイトルは『Selfish
Propensities』という。結成と活動の場は東海岸の街、ボストンである。
イーストコースト的な落ち着いたサウンドでなく、ゴリゴリのサザンスタイルであるというのは面白い点だろう。
この「Nana」はグループ名を変更した今回の作品と同じDiorama Musicの第1弾である。2番目がこの『Bush League Romance』であるけれど。
レコーディングのクレジットは以下の通りである。
Tom Baker (L.Vocal&Guitars&B3) 、 Roland Smith (Bass) 、 Jim Delios (Drums)
このトリオに加えて各曲で異なるギタリストが参加している。
Davie Minehan(Neighborhoods) 、 Jim Buni(Buttercup) 、 Andy Pastore(Charlie
Chesterman)
と雇われセッションギターはどれも東海岸の良心的なオルタナ・カントリー系バンドからの参加である。
そしてライヴバンドとして初のギグを7月の7日に行ったばかりだそうだ。ジョイント相手はthe
Continental DriftersとCrown Victoria というBill Janovitz(Buffalo Tomの)が立ち上げたニユープロジェクトバンドであるそうな。
メンバーはやや交代して、ベースのRolandはそのままでTom Long がドラムを叩き(元
Dogmatics)、 Tad Overbaugh がギターに収まっている(Kickbacks)
が、Tomが只者でないのは今年年頭に地味ながら味わいのあるオルタナ・カントリーアルバム『Longneck』を発表した 、「Scrimshanders」−筆者も以前レヴューしようとしたが予定を変更している。−にギタリスト兼ヴォーカリストとして参加していることだ。
一度に2つのバンドプロジェクトをこなしているのである。もう精力的の一言に尽きる。
ソングライティングはTomの単独である。彼の聴いてきたバンド、好きな音楽はElvisから始まり、The
Kinks、 Gram ParsonsそしてRolling StonesにElvis Costelloの大御所、更にReplacements、Steve
Earle、Mike Ness、Robbie FulksそしてQueersといったルーツ系やガレージロック系といったところだそうだ。シンプルでアーシーな音楽が多いのは彼の音楽を聴けば良くわかると思う。
それにしても、素晴らしいロックンロールである。産業ロックの対極にあるようなシンプルで泥臭いサウンドが特徴であるが、アメリカンロックの基本なキャッチーでスピーディーな要点はきちっと網羅しているので、後少しアレンジを洗礼させれば、王道中の王道的なアルバムになると思う。
まあ、このラフさと攻撃的な粗さが魅力なのであるが。つらつらと長文になってしまっているが、Rock N’ Rollとしか表現できない。
最後にTom Baker氏の自らの音楽性に対するコメントを紹介して駄文を終わりにしたい。
「Its just your regular Boston R&R band that can do kick ass rockers
and cry in your beer ballads」
まず、兎に角、買って聴け!!! (2001.7.9.)
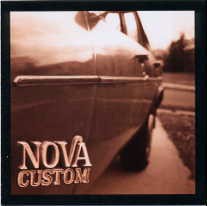 Nova Custom / Worry Stone (2001)
Nova Custom / Worry Stone (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Alt.Country ★★★
You Can Listen From Here
初期の頃のBruce Hornsby & The Rangeがもう少々泥臭くなったら彼らのような音になるだろうか。無論かの名盤である『The Way It Is』ほどピアノが中心ではないし、より垢抜けない音であるのは確実であるので、誤解のないようにして貰いたいけど。
とはいえ、ルーツロックの私的名盤になりそうなのはこの『Nova Custom』も同じなのであるが。
それにしてもこのような素晴らしいアルバムが2000年9月に自主制作されていたとは、全く知らなかった。アルバムの背表紙を見ると、商品番号らしき「ZHS−7720」というシリアル番号が読めるので、どこのレーベルかと考えるのだが、何の事はない。このジャケットに写っている自動車のナンバープレートの番号なのである。裏ジャケやインナーにもこのナンバープレートの写真が幅を利かせているけれども、何らかの愛着があるのかもしれない。
さて、ここまでインディになるとまず日本でも筆者くらいしかこのCDを購入していないように思えてならない。バンドにメールで質問しておいたので(やめんかい!!)いずれ回答は出るとは思うけど・・・・あまり見たくはない。(笑)
このWorry Stoneというバンドについての情報は極端に少ない。バンド名である「Worry Stone」はどのような意味なのだろうか。このアルバムの中でも1・2を争う筆者のお気に入りの#6『Turn Around』で歌われる歌詞の中にその単語を聞くことができる。
♪「Jumped Up Front Door. See The Street You Lived On.It Wasn’t Long Ago But It Seems To」というアナログレコードのトラックのようなノイズとピアノの弾き語りで始まる、この歌のコーラスで「There’s The Place Statue’s Gone And Boy You Know I Wish It Wasn’t So On.Flow Out Your Worry Stone Ya Just Turn Around ,Flow Out Your Worry Stone I’ll Be Coming」というやや難解なフレーズ中にバンド名が歌われている。もっとも完全に筆者の聴き取りであるので、多分相当間違っているが。
察するに「心のしこり」とか「こころに残った愛惜」とでも解釈するべきであろうか。この唄に対するインプレは後に述べるが、かなり個人的に好きなノスタルジックな世界観に溢れていてツボである。
さて、バンドのバイオであった。結成はヴァージニア州のアーリントンという街で、オリジナルと共に、カヴァーソングをプレイしているインディバンドの典型で、主にCounting Crows、Tom Petty、Dave Matthews Band、Barenaked Ladiesといった良心的なアメリカンロック、アメリカン・ルーツバンドをレパートリーにしているそうだ。
そしてオリジナルだけを集めたこの本作を2000年の秋にリリースし、2001年にネット上で販売を開始の運びとなり、筆者のアンテナに引っかかったという次第である。
メンバーは2001年現在で、23歳から27歳までのまだまだ若いというべき年齢層であるだろう。出身は東海岸から西海岸までばらばらのようである。5人組であり、筆者のもっとも大好きなパターンのバンドである。
フロントマンのTim Metz (Vocals&Guitar)は小学生の時から少年合唱団で歌を始めてからずっと唄っているそうだ。合唱団で仲間ハズレにされ、リードパートを取らせてもらえなかったのが未だに心の傷となっているとか。趣味は貝殻集めとそのディスプレイ用のケースを作ること。
リードギターはErich Wildemanで6歳からギターを弾いているそうだ。ティーンエイジでブルースクラブでギターを弾いていたそうな。
ベーシストはChris Miller。クラッシックやジャズ畑を歩んできた人で、トロンボーンもプレイできるとのこと。マイルス・デイヴィスがアイドルであると同時にRandy Bachmanも尊敬しているというユニークなバックグラウンドがある。
Adam Dawson(Drums)は7歳から父親の経営する会社の社員が編成したバンドでドラムを叩き始め、かなりの数のインディバンドを渡り歩き、後述のピアニストであるJayをバンドに引き込んだ人でもある。映画「プラトーン」が大好きで、飲むことと全身治癒のセミナーに行くことが趣味という訳のわからない男。
アレルギーが酷く演奏中は手袋が必要という非常に虚弱なJay Rapoport(Piano&Organ&Vocals)は牛乳を飲んでひきつけを起こし、入院中にドラッグ中毒のリハビリをしていたAdamに出会い、バンドに加入したそうだ。ヴォーカルとしてもリードを取れるそうなのだが、喉が本調子でなく今のところバック・ヴォーカルに専念しているそうだ。何しろ蜂に煙草に牛乳に砂糖に防腐剤と凄い数のアレルギーである。これでこの素晴らしいパワフルなピアノを弾いているので、冗談ではないかと邪推してしまう。
さて、始めに記述したのだが、80年代のメジャー系アーティストに繋がる作風がある。勿論、ルーツィで土臭いところは大前提であるが、カントリー的なアプローチはあまり伺えない。それは作者が聴いての事なので、何とも言えないけども。絶対にカントリーでないと捉えている音を「カントリーやね。」って何度も言われたことか。
とはいえ、南部系のブルージーなテイストもそれ程突出しているわけではない。ガレージロック系譜のパンクテイストに至ってはインタープレーの間に僅少ながら見れるだけである。
要するに基本的なルーツロックなのだと思う。何ら取り立てて新奇なジャンルに挑戦しているわけでもなく、超絶な技巧で難解なスコアを演奏するテクニシャンの集団でもない。まさにキャッチーでアーシーなロックンロールをさりげなく聴かせてくれる、草の根バンドの典型であると思う。
輝くようなアリーナロックのテイストを抜いた、良心的な80年代のポップ・ロックと表現すべきだろうか。それとも70年代の素朴さを残したルーツロックと呼んでも良いような気がする。
実にナチュラルなサウンドであり、アクースティックな曲はそのままに、軽快なポップチューンは軽やかに、と流れるような抵抗のない音楽性が非常に心に落ち着きをもたらしてくれる。全体的に程よいグルーグ感覚が溢れていて、自然と足でリズムを踏み、上半身を揺らしてしまうようなメロディが存在している。
無論、全曲に素晴らしい優しさを付加しているピアノとオルガンが特徴であることは今更言うまでもない。
やはり個人的に一番のヒットであるドラマティックなバラードの#6『Turn Around』は素晴らしい。Timのややハスキーなヴォーカルと、エモーショナルなJayのピアノがマッチして、もう言うことがない。この過去を回想するような、さりげない日常の機微を描いたような詩も、セピアカラーの雨に打たれる下町が見えてくるようで、早くも作者の妄想ヴィジョンが炸裂している。ちなみに、良い曲を聴くと勝手にPVというかドラマ風景を脳内でプロデュースするという悪癖が出るということは、名作バラードの証拠であると考えてもらえれば幸いである。
スローバラードというと#8『All I Ever Did』もかなり地味だが情緒豊かな佳曲である。美しいピアノをメインラインとしてコーラスとのハーモニーで歌われる「Now I’m Empty」という寂寞とした詩。泣くように歌うギターソロも一層バラードとしての良さを際立たせている。70年代西海岸ロックのアクースティック・ポップな香りが漂う曲だ。
反して、ピアノと泥臭いギターで幕を開ける#1『Intellect』はコーラスパートからのラフな展開と導入部のアーシーでホンキィな対比が際立っている。いきなりもっと盛り上がるかと思わせて、ブチっと切る最期もユニークである。
バタバタしたノイジーさで終わる#1に続いて、かなりジェントリーなアクースティックでアーシーなポップナンバーが#2『Fever』、#3『Salt Shaker』と続く。#2はメロディの展開より、時折ガンというように感情を込めて歌うTimのヴォーカルに耳を奪われてしまう。この人のヴォーカルはそれ程美声ではないのだが、エモーショナルという点ではかなりメリハリのあるヴォーカルを楽しませてくれる。
#3はかなり地味なナンバーであるが、ピアノを始め、ベースやギターのアンサンブルが丁寧に織り込まれていて、アルバムトラックという感じであるのだが、飽きさせない曲である。
同様に#4『I’ve Had Enough』もグルーヴィな明るいリズムが特徴ではあるが、ミディアムなどちらかというと地味なポップナンバーだ。軽快なギターがややカントリーっぽいだろうか。しかし、3曲もおとなし目なミディアム・ポップを続けても全てがメロディとして素晴らしいので、単調な気がしないのはかなり凄いことだと思う。
そして、かなりアーシーで粘っこい#5『No Resistance』はブルースロック的なナンバーで中盤にアクセントを付ける意味でも良い構成であると感じる。このような曲が多いとやや苦手な範疇に入るので、この1曲のみで良かったとつくづく思う。
#7『Falling Down』はオープニングと同様かなりロックなチューンである。気持ちの良いグルーヴ・リズムをここでも基本とし、時折ラフに挿入されるピアノソロとややブルース的な手法のギターソロの掛け合いがとても楽しいナンバーである。
と、13曲70分を超えるアルバムが珍しくないこのご時世にたった8曲でこのアルバムは終わる。が、中弛みするようなアルバムより、良作だけで10曲以内に締めてくれると実にコンパクトで聴き易いアルバムになるという好例を提示してくれているようである。最近はこのくらいの収録数だとミニアルバムと解釈されそうだが、8曲という数とアルバムの完成度からしてフルレングスであるのは間違いない。
ちなみに筆者のミニアルバム・ボーダーは7曲である。長年の経験から導いた数値である。(何ぼのもんじゃい)
しかし、このような良心的なロックがメジャーへ登るような市場性がないのは真実悲しい。もっともメジャーアルバムにするにはややアーシー過ぎであるきらいはあるのだが。
が、Tom Pettyの『Wildflowers』や彼らのカヴァーしているCounting Crowsにつうじる魅力は純然としてあるので、この純粋さを保ちつづけて欲しい。
彼らのカヴァー曲も聴いてみたいのだが、現状では無理だろう。
ルーツロックファンには必須の一枚だ。オーソドックスである故の良さが分かる人に楽しんで戴きたいアルバムである。このようなアルバムに出会うと「インディ発掘やってて良かった。」としみじみ幸せを感じてしまうのだ。
(2001.7.10.)
 American Hi−Fi / American Hi−Fi (2001)
American Hi−Fi / American Hi−Fi (2001)
Alternative ★★★★☆
Pop ★★★☆
Rock ★★★★★
Modern ★★★
かなり大上段な名前を付けたものである。「亜米利加の高品質」ときたもんである。これで音楽性が低品質であったら目も当てられない。まあ、Hi−Fiという単語は音楽で使用される場合、他の意味に解釈される。無論AV機器での分野ではなく、音楽性を語る場合の意味合いとしてだが。
筆者が大好きな草の根ロック系はしばしばLo−Fi Soundと表現されるが、これは別にトラッキングが4チャンネルだったり、ミックスダウンが悪いという意味ではなく、「地味・おとなしめ・ゆったりとした」的なニュアンスで解釈が可能であると思う。
反して、Hi−Fi=「派手・アクティヴ・ノイジー」とでも考えれば良いだろう。
実際、その殆どが当てはまるバンドである、この「American Hi−Fi」は。当HPの良作・新作コーナーでは久々に取り上げるオルタナティヴ系どっぷりのアーティストでもあると思う。勿論、このアーティフシャルな処理がてんこ盛りの音楽性の中にポップさとコマーシャルさがしっかりと存在しているけれども。
そうでなければレヴューは絶対にしない。筆者的暗殺リストに挙げて、サヨウナラであるのは確実だ。(笑)
ところで、年々この手の音楽がそれ程心に残らなくなってきている。在米期間の97〜98年をピークにして、人工的な音に対する耐性が年々低下している。昔の耐性が独逸軍五号戦車「パンテル」だとしたら、現在は旧帝国陸軍の主力戦車「九七式中戦車」並みの抗堪性しかなさそうだ。(謎)
特に#8のノイジーな、オルタナでハードロックを演じたようなナンバー『My Old Enemy』は作者的に要らない、必要ない、スキップしてハイ次、的なナンバーである。
人工音と五月蝿く繰り返しているが、プログレッシヴなロックの音はかなり好きである。またハードでも80年代系列に繋がるサウンドを聴かせてくれる音は相変わらず目がない。
一体、何がここまで私的にダメなのであろうと、返す返すも自問自答しても、答えは浮かんでこない。が、明確に言えるのは、やはりこの90年代に特有な硬質な処理のギターであろう。泣くことも、ささやくこともせず、かといって激情に身を委ねるような激しさからも一歩引いている。反面、重い、感情の見えてこない音・・・・・。これを怒りと憂鬱の表現として捉える見方も存在するようだが、やはりそうとは丸まる信じることはできない。
まして、格好良いとかとは絶対に言えない。
と、かなり批判がましいことから書き綴っているけれども、私的な基準でここでは採点が70点以上の良作しか発表しないという、個人的基準には十分届いているアルバムである。
所謂モダンロックという係累の一端を担うジャンルに属している音楽性であると考えている。更にかなりヘヴィな展開をも頻繁に披露してくれて、オルタナティヴロックの臭いがぷんぷんする。
方向性としてはLITの2nd『A Place In The Sun』(1stはゴミ。オレンジカウンティのロック祭りで彼らから直々にCDを買ったが1回聴いてほかしてもーた。)やMarvelous3の3rd『Ready Sex Go』に近い、ハードでポップなモダンロックアルバムだ。が、しかし、ここで引き合いに出した2枚は80年代のハードポップサウンド=産業ロックの一翼を担った音的な大仰な展開が目立つアレンジが見られたが、この『American Hi−Fi』はより贅肉を落とした、現代的なオルタナ・ロックに幾分歩み寄りをしているように感じられる。
その分、ややダークでヘヴィな色合いが濃いように感じてしまう。#3の『A Bigger Room』とかからはNWBHM的な感触さえ伝わってくる。#4『Safer On The Outside』も同様にヘヴィな展開のギターががなるナンバーでオルタナティヴ臭さが鼻につく展開が減点対象だ。
いまいちな曲はまだ挙げれる。#9『Don’t Wait For The Sun』のややアクースティックな暗めなバラードは特別心の琴線に何ら触れてくるところがない、毒にも薬にもならないナンバー。正直退屈であるし、このような曲の組み立てはやはりオルタナである。
また、シンプルなハードロックへの傾倒を伺わせるところも悪くはないが、中途半場に感じてしまうところでもある。#11のハードナンバー『Scar』も悪くないが取り立てて誉める箇所が見つからない。やはりポップさが足りていないのだろうと分析している。
が、アメリカンロックらしいキャッチーな音楽性を見せるとこではしっかりと披露しているので、全体としては結構ポップな印象で聴けてしまうので不思議ではある。
第一弾シングルとしてヒット中の#2『Flavor Of The Weak』はコマーシャルさをしっかりと持ち合わせたロックナンバーでかなりの出来である。シングルになったのも頷ける。♪「He’s too stone Nintendo」というやはり現代的な単語が出て来る、現代的な醒めた恋愛観を歌った内容もシニカルでなかなか良い。
#1『Surround』もかなりハードではあるが、躍動感はあり、やはり80年代初頭のHRを思い出させる。やや屈折したロックへの愛情を歌ったとこは、もう少し素直なとこを見せて欲しかった、とも思うが。サウンドやアレンジ共々に。
#5『I’m Fool』はかなりキャッチーである。続く#6『Hi−Fi Killer』のハード・ポップ的な曲をはさんで、これまた躍動感のあるロックチューン#7『Blue Day』へと雪崩れ込んでいく流れの連続はかなりロックンロールしていて、個人的には好きなところである。#5はシングルになりそうである。が、ラヴ・ソングらしい詩であるが、素直でなく世の中を斜めに見たような感覚で書かれた詩のように思えてならない。
#10『Another Perfect Day』は静かなギターリフからドラマティックな展開に動的に続いていくバラードであり、パワーバラード的な良作であろう。♪「I
still believe it when you say.It's another perfect day」とやや前向きな姿勢も感じれる詩であるが、最期に♪「I
thought that it was real.But I guess it's no big deal 」とやはり枯れたというか、醒めた感性を感じてしまう。
#12『What About Today』も少々ゴリゴリであるが聴きやすいミディアム・ハードチューンで彼らのポップセンスが垣間見れる曲であるが、如何せんラストの#13『Wall Of Sound』がどうということないオルタナナンバーであるので、締めの印象は特別好感触でないのは残念である。
さて、もうすぐ日本盤がリリースされるとのことなので、詳細なバイオグラフィーは不必要だと思うのだが。(手抜きやんか!)まあ、一応簡単な沿革だけは記しておこう。
結成は東海岸、筆者も何回か仕事で出かけた独立の象徴の街、ボストンである。・・・・偉大なロックグループのBostonという単語の意味がより強烈ではあるが、余談だ。(笑)
メンバーは4人の、ボストンにてそれぞれのインディ・バンドで活動していたミュージシャンである。
全ての歌を書いている、Stacy Jones (L.Vocal&Guitar)を筆頭に
Jamie Arentzen (Guitar) 、 Drew Parsons (Bass) 、 Brian Nolan (Drums)
という編成である。プロデューサはBob RockでBryan Adamsの『On A Day Like Today』や『Motley Crue』、そしてAerosmithの『Parmanet Vacation』に『Tal Bachman』に携わってきた人で、HR系やアダルトロック系のアルバムでこれまでは活躍している。成る程、ハードロック的な手法は彼の影響かもしれないが、彼が関わるからにはもっとアリーナロック的な厚めのアレンジを想像していたが、かなりソリッドであったので、予想は当たらなかった。
リーダーのStacy Jonesは元々ドラマーとしてガレージパンク系のバンド「Letter To Cleo」と「Veruca Salt」と活動してきて役10枚のアルバムに関わってきていた人である。リズム隊出身のソングライターというと結構珍しいかもしれない。Bob Rockとの関係もVeruca Saltの女性メンバーであるNina Gordonのソロ作をBobがプロデュースし、そのアルバムにStacyが参加していたという縁からということだ。
このアルバムの曲を書いている時、彼はVeruca Saltの内紛・解散でゴタゴタに巻き込まれ、かなり内心辛かったそうであるので、やや暗めの歌詞はその時の心理状態が影響を与えていると告白している。
しかし、これから21世紀に向けて、このようなアーティフィシャルなロックがやはりメジャーの主流となっていくのだろうか。アーシーなアメリカンロックはもはやシーンを席巻することはないだろうと予想する。
やや憂鬱である。きっとますます筆者のチャート離れは加速していくに違いない。このバンドはそれでも良心的なアメリカンロックに分類できるだろう、現在のチャートの趨勢からでは。
あまり嬉しくない。・・・・最期まで愚痴になってしまったが、悪くはないアルバムであるし、一般のリスナーにはきっと受けそうである。
もはや著者の感性は完全に隔世の感が漂う・・・・・・・。まあ我が道を行くまでだ。 (2001.7.13.)
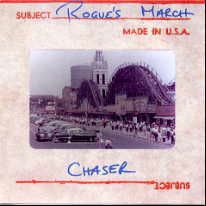 Chaser / Rogue’s March (2000)
Chaser / Rogue’s March (2000)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★★
Southern&Celtic ★★★
You can listen from here
常々考えることのひとつに、「今現在聴いているアルバムより物凄いアルバムが、まだ見ぬ(というより聴かぬか)名盤が、きっと何処かに眠っている。」ということがある。
まさにオタクなマニアなディレッタントな発想である。我ながら度し難いと思うのだが、こればっかりは「わかっちゃいるけどやめられない♪」と踊っても良いくらいの確信犯的思考である。(笑)
で、上記の懸念を証明するように、このアルバム『Chaser』も「聞き逃していた私的名盤」な一枚である。しかもインナーには1998/2000のクレジットがあるところから(曲創りは1998年が殆どのようである)デモテープか自主制作盤が1998年の時点で存在していたようでもある。この辺はバンドとコンタクトを取って確認中なので、情報を修正するかもしれない。・・・・多分めんどい忙しいのでしなさそうであるけど。(汗)
さて、★の欄にCelticとSouthernと範疇付けしてみたものの、正直これで良いのか定義した筆者自体が非常に疑問に思っていることを正直に告白しておく。あくまでもサウンドの構成の方向性という意味合いで4つ目の欄を設けてあるのだが、このRogue’s Marchというバンドは私的にはこの2要素だけでは語れないバンドなのだ。
一纏めとしてAlt.Countryとしてしまっても良いのだろうが、どちらかというと「Alt.」な部分のガレージロックやパンクロックのバックボーンは感じられるのだが、カントリーとなるとアメリカのルーツ系カントリーとはやや味付けが異なっているように思えたので、敢えてこう分類してみた。
海外のレヴューではやはりCeltic系のロックバンドという範疇に見られているようで、このアルバムが買えるサイトもケルト系の通販ショップである。確かに随所に欧州的哀愁というか、大陸的なやや陰りのあるメロディが流れてくるパートがあるのは否めないが、単純にケルトロック・バンドと叩き切ることは作者的には不可である。
ツアーのジョイントの相手が、主にFlogging Mollyというこれまたケルティック系のバンドであり、お互いにベストフレンドと認め合っているところからも、Celticに繋がる色合いがあるのは否定できない。
ちなみに只今触れたFlogging Mollyというバンドはケルティックな毛色はあるが、サイケディリックなフィドルやミクスチャーのようなヘヴィなリズムが鼻について、個人的にはハズレなアーティストであるので敢えてお薦めしないし、これ以上は語らない。(まあ、こんなん持ってる物好きはあまりおらへんと思うのでエエでっしょ。)
隠しトラックの#16の曲は確かにケルト・トレディショナルな曲であるが、これ以外ではあからさまなケルトナンバーは存在しないだろう。#15のヨーロピアン・トレディショナル的なお祭りナンバーの『The Last Picture Show』にはややそういった雰囲気が見えるけれども。
どちらかというと、かなりゴリゴリなバリトンヴォイスの喉の持ち主である、フロントマンのリードヴォーカリストであるJoe
Hurleyに象徴されるようなタフでロッキンなルーツナンバーで示されるパンキッシュな側面が一つ。そして、ケルティックとアメリカンなアクースティックな音楽性が融合したゆったりしたスローナンバーで表現される側面が二つ目。
この動と静が交互に主張を繰り返すようにしてトラッキングされている、つまるところアメリカン的なルーツロックアルバムであるのだ。
アイリッシュ系のロックバンドとして日本でもそこそこ知名度のある(そうか?)PoguesやBlack 47とはやや方向性の異なったバンドであると思う。英語で言うとWhisky Glass Vocalのように例えられる、酔いどれロック的なラフさは共通項ではあると考えているが、これらのバンドよりRogue’s Marchはポップでロックでカントリーでブルースといったアメリカンロックの基本なテイストが取り入れられている。
兎に角、豪快で飾り気のない、ストレートなロックンロールで剛球一直線!という曲を聴かせてくれたと思いきや、マンドリンやアコーディオンが素朴な音を奏でるレイドバックなナンバーが現れるといった、とってもメリハリの効いたアルバムになっている。どちらかというとベタベタな泥臭さとルーツィなダサさがマッシヴな筋肉ロックを押し付ける如くなパワーロックチューンの方が好みであるけど。
楽器としてはマンドリンやアコーディオンは勿論としてUillean PipeやクレジットはされていないがTin Whistle等のケルト・インストゥルメンタルも聴こえてくる。勿論ピアノとオルガンはしっかりと入っている。装飾過多ではないけれども分厚い素朴な演奏がロックンロールの先祖帰りというか原点をそのまま忠実に再現しているようで、実にマッチョである。
何しろオープニングトラックの『On My Way Home』からガツンと一発やられてしまうドラスティックな変調を見せてくれるロックナンバーが炸裂する。やや重苦しいゆったりとしたピアノのソロから始まり、いきなりドンと言う具合に動的に変化する曲なのだ。しかもキャッチーでフックの効いたメロディがOnly Rock’n Rollという単語を連想させてくれる。Joe Hurleyの「Smoke And Beer」という風景が見えてくるようなバリトンヴォイスはかなり暑苦しいのだが、このヘヴィな演奏にはぴったりである。
一転してアクースティックなマンドリンとギター、そしてUillean Pipeのバックで始まる#2『Clear』はややイナタ臭いルーツナンバーである。これもヤケクソのようなJoeのヴォーカルがトレディショナル系の楽器とギターを引っ張るかたちになり、単なるスローナンバーで終わらせない吸引力がある。
交互に動と静が襲撃と先刻書いたが、全くその通り、#3『Gino’s Suitcase』はヘヴィロックのようなリフから展開し、(ここからキャッチーにしかもヘヴィになるとこはさすが)ガレージロックのような強引さで最期まで突っ走るナンバーだ。この緊張感がありながら、投げやり的なルーズさが曲を聴く際に変に構えさせないのが凄いと素直に感じる。
もはや定番になるが、速いナンバーの後にまたもスロー・アクースティック曲。#4『Not At All』はチェロやトランペットもフューチャーされたアダルトロックな手法が試みられているナンバーであり、#3のゴリ押しなロックチューンとの対比によってよりそのリラックスした雰囲気が際立つ効果がある。この辺りの構成はステロタイプでありながらニクイ。技ありな箇所であろう。
パターンはまだ続き、#5『On Your Own』は比較的オーソドックスなロック・ポップチューンであり、軽快さと疾走感が素晴らしいかなりの良曲である。シングルになっても十分ラジオに乗りそうである。ここでもストロング・アルコール・ヴォイスのJoeのヴォーカルが軽快さを泥臭いルーツナンバーとして聴かせることに貢献(または反対に邪魔か)している。
キャッチーでノリの良いギターラインにアコーディオンの日なたのような優しい流れが絡む#6『Dear Old London Town』は欧州的とも新大陸的とも、どちらとも言いかねる、裏返せば両方のフュージョン的なトラッド色とロックのスピード感がしっかりと握手したような佳曲。
#7のスローでダークなバラードをはさみ、#8の『This Town』はこれまたストレートなアメリカンロックであるが、このオーソドックスさが堪らないさりげないポップロックナンバーである。これまたパンチの効いたギターラインとヴォーカルが曲の重心を低くしているのだが、この質量感は浅薄なポップナンバーであは味わえない。
欧州的な、これはケルトと呼べるか少々疑問だが、アコーディオンがもの悲しい、それでいてやや間の抜けたような脱力感を演出するナンバー#9『The Bedsheets Of Lili Marlene』はかなりこれまでの展開では異色だろう。しかし第二次大戦時の世界最大のヒットとなったスタンダードナンバーの「Lili Marlene」を題材に取ったユニークというか郷愁の漂う世界を歌っているのは結構面白い。ちなみにこの曲ではSmithereensのDennis
Dikenがドラムを叩いている。
#10『Pick Up』もスピーディなルーツロックのベーシックといった感の強いさりげないポップロックである。このようなロックチューンが適度な間隔を空けて挿入されているところが、アルバムの構成の妙であるとしみじみ思う。必要以上にドロドロしたクドさを緩和し、ロックなビートを堪能できるので、余計にトラッド的なナンバーが映えるのだろう。
サザンロックというかスワンプ的なスゥイングがアーシーさの中で自己主張している#11『Detour』はオルガンのヒュンヒュンと跳ねる音がルーズさを更に強調させている。これまた楽しい土臭い曲だ。#12『Almost Forgotten』も続いて明るいメロディなルーツテイスト満載のミディアムチューン。リズムの緩さが暖かい。この2曲は大陸的というより、アメリカ南部系の脱力したようなスカスカした感覚が強調されたナンバーである。が、やはり曲の腰は据わっているので、軽薄さよりも陽だまりの歌のような明るさが際立っている。
そしてこの後半はややおとなしい曲が続くが、これまた#13『The Ghost Of Her Husband To Be』は完全にアメリカントラッドなレイドバックソングの典型である。フォーキィな少々古臭い臭いも感じられる。
#14『Behind My Back』はドライヴチューンにルーツテイストを加味させたような曲だ。パンクっぽさが元気なコーラスと相まってリラックスした中にも、ドラマティックな構成を見せてくれるので後半のハイライト曲と呼んでも差し支えないだろう。しかし、タイトな演奏のようで、奥行きがあるように感じるのはやはり余分なことは極力避けた上で、良いポップな曲を創っていこうという姿勢がアレンジにも影響を与えているからであろう。良い曲はシンプルでも深みが感じられるものだ。
かなり好みのマッシヴ系ルーツアルバムなため、インプレが長くなってしまった。故にバンドについて簡単に触れて最期にしたい。
Rogue’s March=「はぐれモノの行進」「山賊の行列」「悪者の征途」というような、かなり斜に構えたバンド名であるが、確かにサウンドはかなりアグレッシヴではある。リーダーでメインのソングライターであり、Whisky Soak(ウィスキー漬け)という名称が似合いそうな声質を有したJoe
Hurley(Vocals)さんは何度かメールでやり取りしているが大変親切な方であるので、バンド名=不良のような爆走パンク小僧とは全く異なることを一応断っておく。
現在のメンバーは、このアルバムを録音したときの6人編成からかなりのメンバー交代を踏まえて7人となっている。
J-F (Guitars) Rich Feridun (Guitar&Mandolin) Chris Nappi (Drums)
Matt Lindsey (Bass) Kenny Margolis (Accordion&Piano) Pat
Robinson (Piano&Organ)
のグループである。がかなり流動的であるため、これからもメンバー交代はありそうである。1stリリース作『Never Fear』から残っているのはギターのJ−FとドラムのChris Nappi(このアルバム録音時と前作はベース担当となっている。クレジット違いか?)のみである。無論、Joe Hurleyは常に中心人物である。Kenny
Margolisは録音時点ではサポートメンバーとしてアコーディオンを一手に引き受けている。
出身と活動拠点はニューヨークである。些か都会的なロックバンドが多いニューヨーク出身とは想像がつきにくいが、NYCのロックフェスティバルでWilco等と出演してかなりの人気を博したそうである。
Joeは大英帝国はロンドン出身のアイリッシュ系のバックボーンを持った人だそうで、彼がケルト系のテイストをバンドに持ち込んでいるのだろう。
が、彼らの演奏する音楽は、アイリッシュ風味の入ったアメリカン・ルーツロックである。これは間違いないことだ。
しかもかなりのパワフルな音を聴かせてくれるバンドである。このような力技系よりもよりカントリーにフィードバックした新人バンドが多い現在、実に筆者的に貴重なバンドである。
現在、夏のツアーのために結構な新曲を書き上げているとのことで、この曲が次の新譜に取り入れられそうな気配である。3枚目のアルバムが実に待ち遠しい。
敢えて類似なバンドを探すとなるとカントリーパンク系の相当にコッテリ濃い濃いなSlobberboneというバンドに近いところもあるような気はするが、このバンドよりヴォーカルは全然上。メロディもキャッチーである。SlobberboneのヴォーカリストBrent Bestはパンク系のガンガン歌う分には申し分のない声なのだが、昨年リリースの3枚目のように普通のロックアルバムにアプローチするとしつこ過ぎる声になってしまう。
その点、Joe Hurleyのヴォーカルはどのような曲でもそのソウルフルで粘っこい声が映える。Slobberboneがあたりなリスナーには是非、このアルバムをお薦めしたい。 (2001.7.15.)
 Big Silver / Big Silver (2001)
Big Silver / Big Silver (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Alt.Country ★★★ You Can Listen From Here
Special Thanx To All Gentlemen Of Big Silver
日本での長寿お茶の間アニメーション「サザエさん」は22世紀になろうとも、おそらく現行の声優さん達が引退されても続いていくだろう。核戦争が勃発しても製作が続行されるかもしれない。(それはない・・・やろなあ。)
ある種の民族に固有のお約束というものが存在するのは間違いないと思う。パターンが分かっていても、「いつかこのネタ見たで、をい。」と思いつつもついついチャンネルを合わせてしまう、日曜18時30分。(笑)
引き合いに出したネタが珍妙だったかもしれないが、今回紹介する『Big Silver』もAmerican Rockという音楽文化の中で、普遍な、しかもお約束な要素が沢山詰まった、ショウケースのようなアルバムである。つまり新奇なサウンドや度肝を抜くような超絶なメロディはないが、どこまでも基本に忠実な「お約束ポップ&ロック」と言い換えられる。
「お約束」であっても全く期待の上を行くからこそ、失笑を買わずに賞賛が可能なのである。
こういうバンドを理想のアメリカン・ロックという。少なくとも私的な嗜好においてそう言う。ボケ茄子な本邦で「ロック」と間違って評価されているようなノイジーな音はアメリカンロックとは言えない。一言、市ね。(又始まった・・。)
Roots Rockのテイストを残しつつも、方向性はキャッチーでポップでスピーディなアメリカンロック。1980年代の王道であったアメリカン・ロックの名盤に何ら遜色のあるところはない。
と、書くと少々大袈裟であるように取られてしまうかもしれない。確かに基本的なHeartland RockとかAlbum Rockとかに分類されるロック名盤に比較すると、やはりインディっぽいというか若さが存在し、ヴェテランオヤヂの創作した、”いぶし銀”的な渋みにはやや欠けるきらいがある。
大まかな雰囲気としては90年代の若手アーティストによる「Power Pop」的なアプローチも感じられる。まあ、このアルバムがデヴュー盤であるので成熟より若さが目立つのは当たり前であろうし、それ故に元気の良さが随所から聴こえてくるので、全くマイナス要因とはないっていまい。
上に「Power Pop」と書いたが、ノイジーなギターでグングン押し捲るタイプの現代的なオルタナ系のポップサウンドではないことをお断りしておこう。あくまでもメロディの良さで勝負するポップ・ロックである。
筆者の大嫌いな人工的な硬いギター処理の雑音は皆無であるし、フワフワとしたメロディだけポップという、これまた、「外側から見たら衣が厚くて美味そう、しかし、あけてビックリ中身スカスカ豚カツやんか、コラ!!」、的な浅薄さとは次元の違う本物のポップさが一番の決め手である。
「Roots Pop Rock」と呼ぶか、単に「American Rock With Alt.Country Gem」と表現すべきだろうか。
このように範疇分けが曖昧なアルバムは、概してどこを見ても平均的な出来であることが多々あり、中途半端な良作近辺に鎮座してしまうケースが一般的である。が、反してというか表裏の関係として、どこをとっても素晴らしい完成度なため、突出したカテゴライズが困難という事例が、名盤にはかなりの確立で当てはまるのも事実だろう。
そしてまさに、この『Big Silver』は超一流のエッセンスが対等にしのぎを削り合っているピースであると思う。
・・・・まあ、現在の本邦の音楽事情で鑑みると、「地味」「普通過ぎ」で括られてほかされてしまうかもしれへんのやけど、リアル・アメリカンロックの愛好家には絶対に「電波」がチャネリングする筈である。(危ないやんか!)
2001年6月は、素晴らしい大推薦なアルバムが相前後して手元に届いたが、その中では一番ルーツテイストがマイルドなアルバムである。
マイルドであるが、土臭さと適度なタフさはれっきとしてメロディのなかに埋め込まれており、これぞアメリカンロックの珠玉の一枚と手放しで賞賛している。このパートで褒めちぎっている「The Dirty Truckers」の豪快なストレートさとはやや方向性を異にする、しかしながらこれまたアメリカンな王道を爆走しているバンドである。
カルテット編成のバンドユニットであり、筆者的絶賛の90%の必須条件となっているPiano&Organが実に軽快にプレイされているのが、これまた特徴である。やはりパーマネント・キーボディストが存在するとサウンドに深みと厚みと調和が生まれて、よりバランスが良くなるのは間違いない。これまたツボのツボ、経絡秘孔突きまくりだ。
このピアノなくても、普通のAlt.Countryバンドより一歩抜きん出るのは困難ではないだろう、彼らの素晴らしい作曲力からすれば。しかし、即効性という点でやはり明白なポップさを打ち出してくれている鍵盤の魅力が、差別化という事項に寄与しているのは闇夜に提灯を燈すより明らかである。
最近漸くmp3.comで試聴サイトが完成したので、是非サンプルを聴いて頂きたい。もっとも、このサンプルは全てアルバムにはトラッキングされていない曲ばかりである。デヴュー時からギグのレパートリーにはなっていた曲ばかりではあるし、このアルバムに#4『Malloy』としてリ・レコーディングされているトラックのデモ・ヴァージョンを聴くことが可能であるからかなり貴重である。このレヴュー読んだ人は全員聴くように。(笑)つーか、聴いて買え!!
但し、アルバムのアレンジよりかなりラフになっていることを留意して戴きたい。アルバムのアレンジはより流麗である。
このレヴューを書くに辺り、バンドに問い合わせたところ、物凄い量の関連記事を戴いた。このスペースでは紹介しきれないくらいである。まずは曲の感想を述べてから、バンドのデータを紹介したいと思う。間違いなく日本で初の紹介だと思う(まあ、今に始まったもんやないけど。)ので極力正確に和訳をしないと・・・・。
さて、燃え上がるオープニングトラック『The Secret』。イントロでまず、ピアノを片手でひと撫でな乱れ弾きで始まるのだが、これであえなくオチた。(笑)パワフルなビートに泥臭いギター。そしてガンガンと叩かれるピアノ。のっけからサザンロック風のロックナンバーから始まる。Georgia Satellitesの『I Dunno』をより泥臭くしたようなチューンで、ラスト近辺でのメンバーのシャウト・パートではついつい一緒に叫んでしまうようなノリである。
続いて2曲目の『Nothing I Can Do』はブンブンと鳴くHammond B3のバックトラックに乗せて、キャッチなーそしてほんのりと暖かみのあるメロディが気持ちよく弾む、ミディアム・チューンの典型な曲だ。さりげないルーツ感覚がとっても口当たりが良いし、クドくなっていない程度に抑えてあるのは、とても新人バンドとは思えない。
#3の『The Silent Type』はヴォーカリストのAlexの優しいヴォイスを堪能できるスロー&アクースティックなナンバーである。メロディラインとしては非常に地味なトラックなのだが、退屈な感じはしない。前面には押し出されてないがペダル・スティールのかすかな弦の音がしんみりとさせてくれる。
そして前述の#4『Malloy』であるが、終始流れるB3とバックで地味に活躍するピアノの下地を元に、とてもキャッチーで疾走感のてんこ盛りな展開が最高な、前半の目玉的なナンバーである。ルーツ・パワー・ポップの秀逸なチューンと呼んで全く大仰ではないと思う。3分と経たずに終わってしまうのがとても残念なナンバーだ。
ややスローなリフで始まり「こら、スローなアルバム・トラックやね。」と思わせておいて、コーラスパートで唐突にコロコロというピアノが叩き込まれて、キャッチーな変調をする#5『All That I Want』はコーラスパートの盛り上がりがピアノのために用意されたような、ピアノロックのためのロックと名付けたい佳曲である。これまた当初の地味な予想に反して、印象に残る曲。
#6『Sorry Boys』はBar Rock的なローファイなそしてブルージーなやや重た目のナンバー。モダンブルースという感が強いし、ややくぐもったヴォーカル処理はR&Bへの傾倒が見え隠れする。この辺りはアーカンソー州出身なバックボーンが伺えて興味深い。続く#7『Taking It Time』も同じくうねるようなリズムと、泥臭くハウリングするギターがブルースロックを演じてくれるが、メロディはかなりポップだし、かなりスピーディなため重過ぎるというマイナス効果は生み出してない。むしろ、ハード・ドライヴィンなロックンロールというべき曲だ。
#8『Young』はアーシーでややファンキーさも取り入れたれたアクースティックでありながら、攻撃的な冒険心が浮かんでくるルーツ・ナンバーである。この曲が強いて言えば一番カントリーに近いようだが、しかれどもピアノを中心に徐々に盛り上がるようで抑えたところが、ロック寄りなバンドであることを証明してくれるように感じる。
そして、またまたガンガンと叩かれるピアノのジャンプするリフから、ギター、ドラム、ベースが合流していき、そのままポップに走り続けるロックチューンの#9『Kaite And Scott』。これで、サザンロック風のルーツロック曲が続いた中盤から、再びパワー・ポップ的にソフィスティケイトされたやや都会的なセンスも見受けられるロックナンバーが復活する。フューチャーされるワイルドなギターは、単なるポップナンバーでは充足されないロックの魅力が一杯だ。これまたシングルにしても良いだろう。
一転してシンガー・ソング・ライター風のアーバン・ポップな優しいナンバー#10『Roy』に繋がっていくが、この曲順は相当練りこまれたような気がする。動から静への変転が巧みである。ところで、アーバンとはいえやはりアーシーで田舎臭いギターが織り込まれているのは、「Big Silver」がやはりルーツ音楽が基本なのだろうと思わせてくれる。
再度、スピーディでコマーシャルな明るい曲に戻るのは、お定まりかもしれないが、曲が宜しいため全く鼻につかないのだ。#11『Ditch This Town』はホンキィなピアノがガンガンとアクセルを踏むように、速度感を上げてくれる軽快なロックナンバーで、この手の曲が必ずある程度の間隔を置いて並んでいるため、トータルではやや地味なアルバムがかなり艶やかに聴こえる効果をもたらしているのだろう。
#12『Everything』はかなり豪快なB3とギターが吼え続けるかなりルーツな、そしてタフなチューンである。これでロックに〆!と思いきや、シークレットトラックとして相当レイドバックしたカントリーっぽいナンバーが入っている。これは、どちらかというとヘヴィなサザン・パワーナンバーで終わってくれた方が良かったように思えるのだ。まあ、贅沢過ぎる不満であるだろうけど。この曲何処かで聴いたことがあると思っていたらどうやらDavid Bowieのカヴァーらしいが、彼についてはあまり深く聴いていないので、よく分からないのだ。(汗)
漸くバンドの紹介を述べられる。折角詳しいデータを戴いたが必要なところをピックして記述することにする。かなり賞賛で埋まっているアーティクルが多いので。(笑)それについては全く同意するが。
このバンド「Big Silver」の母体が始動したたのは、1998年。アメリカの南部のど真ん中のアーカンソー州はSearcy(どう発音するのかよう分からんのでこのまま書く。)で、当時単科大学の学生であったIsaac Alexander (L.Vocal&Guitar)が友人であるBrad William (L.Guitar&Mandolin&Vocals)とバンドを組んだのが始まり。
この2人に現在もベースを担当するKevin BennetとDusty Crawford (Drums)を加えて、彼らはバンドとして活動を開始する。活動拠点は同州のリトル・ロックという街だそうだ。
数回のライヴを行っただけで、彼らは地元紙「アーカンソー・タイムズ」の主催する「the
best original music band of Arkansas」に出演し、一番初めの演奏というあまり印象的には有利でない順番でありながら、見事に優勝する。がこの後ドラマーのDustyがテキサスへと移住し、Bart
Angelという現在のドラマーと交代する。更に鍵盤引きであるShelby Smithを雇い入れ、現在のラインナップが固まる。
Isaac Alexander (L.Vocal&Guitar) 、 Brad William (L.Guitar&Mandolin&Vocals)
Kevin Bennet (Bass) 、 Shelby Smith (Piano&Organ)
Bart Angel (Drum&Acordian&Mandolin)
この5ピースにKevinの叔父のKevin Williamsがペダル・スティールプレイヤーとしてサポートに加わっている。
このコンテストに優勝したため、レコーディングの機会を与えられた彼らだが、最初の録音がかなり意に添わなかったようで、一時、アルバムを作るよりライヴに専念することとなる。
そして、2001年に入り2ヶ月を費やしてこのデヴューアルバム『Big Silver』を自主制作する。とてもセルフ・リリースとは思えないくらい完成度が−前述のように絶賛しているし−高い。現在のアメリカ・メジャーのスタッフの目は節穴であることに決定、兎に角決定。
「僕たちはロックを忘れたことはない。このCDは僕たちが追い求めてきたことをしっかりと掴んでいる。僕たちは皆最高にハッピーさ。」とはドラマーのバートの言。
リーダーでメインソングライターのIsaacが影響を受けてきたのはElvis Presley、Bruce
SpringsteenそしてElvis Costelloといった大物ロッカーであるそうだ。彼のヴォーカルはCostelloに似ていると言われているが、まあ似ていなくもないかな、という程度にしか感じない、著者的には。
「良い歌を作る人から影響を受け、素晴らしいショウを見せる人から良いとこを引き出すようにしてきた。」
「全てが良い曲だと思わないアーティストでも、良い曲は良さを見習うようにしてきた。」
以上は、Alexの言葉。変哲のないコメントだが、実に良心的で誠意に溢れていると思う。
このCDにはIsaac Alexanderの別プロジェクトであるMolten Lavaというバンドの曲もレコーディングされているとのことである。こちらは全く知らないが是非探して聴いてみたい音源である。このセルフタイトル・アルバムのミキシングとプロデュースを担当したDarian Striblingという人がMolten Lavaの作業も担当しているとのことなので、恐らくアルバムが存在するはずだ。
ところで、彼らはまだプロとして音楽活動に専念していないとのことで、非常に驚きである。Alex曰く、
「僕たちはちゃんと現実の仕事がある。Williamは高校の教師でバスケットボール部のコーチも兼任。Smithは医科大学の学生だし、Angelは家業を手伝いながら雇われドラマーとしてかなりのバンドで活動してるしね。Kevinだけはね僕たちも彼が何してるか知らないんだけどね。(笑)」
そして、彼自身も普段はマーケティング・グループのディレクターとして働いているそうだ。
これからがどうなるか、である。是非どこかの良心的なレーベルと契約して欲しいものだ。
最新ニュースとして今年の末に発売予定のJohn Fogertyのトリビューとアルバムに参加が決定したそうである。まずは重畳なことだ。
彼らのサウンドは、オルタナサイドに立った、例えばAmerican Hi−Fi等と比較すれば、全く地味である。が、一回聴いてAlt.Countryの良作と思い、2・3回聴くうちに、素晴らしいアメリカン・ロックの典型であると気が付いた。この普通さは現在、やはりメジャーではアーティフィシャルな音が幅を効かせている状況において、とても貴重である。
筆者、協力推薦、普通で地味なアメリカンロック&ルーツアルバム。誰か一人でも拙文で購入を決意してくれる方がいればと思う。 (2001.7.22.)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
