 Gone / Scott Laurent (2001)
Gone / Scott Laurent (2001)Roots ★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Alt.Country ★
You Can Listen From Here
 Gone / Scott Laurent (2001)
Gone / Scott Laurent (2001)
Roots ★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Alt.Country ★
You Can Listen From Here
ミネアポリスといえば、「ミネソタの中心」・「ミネソタの都市」=「ミネソタの州都」という意味である。ちなみに筆者も嘗て仕事で数回足を運んだことがある。何の変哲もない田舎都市である。
が、この街を一部のロックファンの間で有名にのし上げたのが、1992年にリリースされたThe Jayhawksの名盤「Hallywood Town Hall」である。(邦題:聖林公会堂)この変哲もない小さな建築物がジャケットの写真に使われたことにより、この街があるジャンルのロック音楽のメッカとして認識されるようになったのは大いなる功績であると思う。
ただ、この公会堂の前で写真取るような俗な真似は止めて欲しい。日本の恥じじゃい。というか、まず観光で出向くような街ではないけれども。
さて、恒例の脱線と愚痴を踏まえて、本題に入ろう。このミネアポリスという街は著者的な認識に置いてであるが、中庸ロックの生産地であると考えている。少々(とはいえ日本の感覚では相当だが)南に下ったミズーリ州の州都、セントルイスも、同じく中道的なロックの一大産地であるだろう。が、セントルイス産の音楽は、筆者の聴く範囲ではミネアポリス・ロックよりもルーツテイストが強く、やや陰りのあるサウンドが特徴のような気がする。
対して、ミネアポリス産のロックは、ルーツテイストよりもよりジャンル分けが困難な普遍的なポップさを有している傾向にあると感じる。しかしながら、このことは必ずしも肯定的な意味をなしていない。私的にどうもハズレの多いNot Lame系譜に繋がる軽過ぎな、そしてスノビッシュな捻りを加味し過ぎなロック・ポップがミネアポリスにはここ最近、溢れているように思えてならないからだ。
例えば、同市出身のSemisonicが今作「Chemistory」でUKなロックに傾いた、これ以上UKらしくしたら作者的に暗殺リストに付け加えるギリギリのアルバムをリリースしているし、The Hang Upsに代表されるようにB級のネジレが目立つポップバンドも多い。
更に、最近はヘヴィロックブームがこの都市にも押し寄せ、ラジオ局でオルタナサウンドが懸かり過ぎてかなわん、と当地在住の友人が零していたりする。
また、ミネアポリス・ロックの良心の代表であった筈のThe Jayhawksも2000年の完全なオーヴァープロデュース作品である「Smile」で失望のドン底を見せ付けてくれた。
どうも、あまり状況は良い方向に転がって行きそうもないようだ。が、しかし、その中にあって常にアメリカンルーツロック・ポップの宝石箱−金銀ダイヤモンドがごっちゃりと詰まった下世話な箱でなく、見栄えは地味でも価値は高い宝石が適度に入った箱と想像して戴ければ良いだろう−の如くなアルバムを供給してくれるバンドはまだまだ存在している。
例えば、ロックとポップのバランスのとれたルーツロックを聴かせてくれるThe Cultivators、今年予定の3rdアルバムが楽しみである。それに、ポップロックの良心のような音を届けてくれるLee Rude。このバンドも新作が9月に出る予定で期待が高まる。更に、アクースティックなルーツテイストを大事に仕舞い込んだようなバンドBellwetherは2000年リリースの2ndアルバムで飛躍的に進歩したと思う。また、ややハード寄りなロックを聴かせてくれるBlue Canoeも今後が期待できるメロディアスなバンドである。・・・って誰も知らないバンドばかりやなあ。(汗)
そして、やっと名前が出せる、Scott Laurent。このバンドはまさにミネアポリスの良いところだけを抽出して、ロック&ポップのエキスを極上の量で料理した如くのバンドである。ルーツテイストに言及すると、かなりルーツカラーは希薄なバンドであり、取っ掛かりの良さは中庸性が強く耳触りの良いミネアポリス音楽の中でも、かなり上であった。(一応過去形。後に説明の努力を。)
バンドと繰り返しているが、この3作目以前の名義は「Scott Laurent Band」であった。プレアナウンスではこの3rdアルバムである「Gone」もBand名義で世に出される筈であったのだ。
1996年に1st「Caposville」を、1998年に2nd「Better Off」をリリースしているが、この時のバンドのメンバーがアルバムをリリースして1年以内で、一気に脱退して、Scott Laurent Bandがほぼ解体してしまったのだ。
Scottはこの内部分裂劇について多くを語らない。
「僕たちはクラブでのギグをソールドアウトにできる位のバンドになってきたんだ。けれども色んなことが起きてね・・・・僕たちは皆やる気を失ってしまったんだ。成功しようという気力を。」
Scott Laurentの高校時代からの友人でギタリストであったBrian HalversonがまずHoneydogsのオーディションを受け脱退してしまったことが呼び水になったようだ。しかし、Honeydogsの新譜は最近漸く聴いたが実に詰まらないアルバムであった。Halversonは絶対に選択を誤ったと思う。
内紛と分裂によってモチベーションが殆どなくなったと回顧するScottが、本国よりも人気のあるイタリアへ充電の旅行をし、そこでかなり復活して再びバンドのメンバーを集めだしたのが2000年であった。オーディションを行い集まったバンドメンバーは第一期のバンドと同じく5人編成。
Scott Laurent (L.Vocal,Harmonica,Guitars) 、 Troy Alexander (Drums)
John Kerns (Bass,B.Vocal) 、 Andi Lucia (E.Guitar,Rap Steel)
Tim Oesau (Piano,Rhose,Hammond B3)
以上の筆者の一番好きなカルテットに落ち着いている。リーダのScott以外全てのメンバーが交代して新バンドに近い存在になった故に、Bandの部分を外したのだろうか。とはいえ、音楽的な基本姿勢は前2枚と極端な変化はしていない。実に普通のロック・ポップバンドである。その点がとても貴重であることは言わずもがなであるが。
無論、進歩が見られないとは言ったつもりはない。過去2枚を含めて、一番力強いロックアルバムに仕上がっている。そして、ルーツテイストも相変わらず極端に全面に押し出すことはしていないが、Scottの作品としては一番ロックなビートを取り入れたことにより、少しばかり強調はされている。ここが一番のポイントであろう。
つづめて言えば、ルーツの影響を感じる、アメリカンロック&ポップなバンドである。軽過ぎることもなく、不必要に泥臭くもないし、Honeydogsの新譜のような都会的センスを入れようとしたために変てこな中途半端さが目立ってしまったこともない。
何処までも、基本的なロックサウンドなのである。しかも、このアルバムでは前2作で伺えた繊細さより、男臭いロックビートの躍動感をさらにロアに感じることのできる醍醐味がある。再編成というバンドの存続の危機を乗り越えたが故の、開き直りというと語弊があるが、吹っ切れた意気込みが感じられるアルバムとなっている。ロックな曲はよりロックに。バラードはより美しく。アクースティックな曲はもっとフォーキィにと、緩急の付け具合が一層巧みになっているのだ。
もう十分にメジャーなアルバムとして店頭に並んでいても何ら違和感のない内容となっている。
「メジャーシーンは移ろい易いしね。今が何の流行であるかはっきりわかるかい?だけどその中でちゃんと生き残っている本当に良いバンドは結構あると思うよ。問題はこれらのバンドをオンエアしてくれるラジオ局がなくなってしまったことさ。嘗て良い音楽を流していたラジオを今聴くと眠くなるね。(笑)。」
と、メジャーに対してはあまり肯定的でない、というより現在の下らない歌しか売れないメジャーシーンに対して興味がないような発言をScottは行っている。これは非常に嘆かわしいことだ・・・・・・・・・・・。メジャー志向で上昇を狙うのがシーンの基本であるはずなのに、まともなロックが売れないため、何処かに歪が生成されているようだ。
話が逸れてしまった。軌道修正。念のため付け加えておくと、楽曲の良さとそのキャッチーで心地よいメロディは全く以前から変化していないことが、私的に評価が高い一因でもある。
極端なアーシーさよりもミネアポリスの伝統芸であるポップ&ロックの魅力がもっと強烈なバンドであるので、恐らく聴けるリスナーの底辺はかなり広いと想像できる。
このScott Laurent個人名義となった3枚目のアルバムは、かなりの大人し目のバラードで始まりを告げる。『You Are The One』がそうであるが、過去のアルバムではファーストラックにポップなロックチューンを持ってきて、いきなりリスナーをそのコマーシャルな音楽で説き伏せようとしていたかのような構成とはかなり趣を異にすると感じる。このかなり冷静な観点に立ったラヴ・ソングはストリングシンセとエフェクトの掛かったスネアドラムが印象的である。今作はやや地味でアクースティックかな、と想像させるようなスローナンバだ。
が、#2『Waste Of Time』でその予想はややぐらつきを見せる。今までにないようなシャウト・ヴォーカルを駆使したScottの歌声とルーツィなハモンドが元気一杯に直進する、キャッチーなロック・トラックが既に圧巻だからである。
そして、#3のタイトル曲『Gone』において、この3作目がかなりのロックな方向性を狙ったアルバムであることが分かり出す。#2以上にラフなシャウトでゴリゴリに歌うScottに新バンドのタイトな演奏がリズムをつける、ややサウスサイドなロックを感じさせるこの曲は、今までは聴かせてくれなかった力押しのロックである。とことんがなるScottのヴォーカルは最初は何となく馴染めなかったが、聴き込むうちに直ぐに慣れてしまった。やはりメロディがポップであるという大前提があるからだろう。
更にロックな攻勢は継続し、ややソフトになったがやはりロックなチューン#4『One Chance』でもLaurentはシャウト気味な声を披露してくれる。ここで入るとお決まりだが格好良いだろうというパートでギターソロが入るところといい、ドキャッチーなメロディといい、厚過ぎず薄過ぎないコーラスを含めて、絶対にシングルになったらヒット性が高い名曲である。
これでもか、というくらい弾んだロックナンバーは停止する様相を見せない。Martin Zellarのプロデュースを手掛けたPatrik Tannerが本作のプロデュースをScottと共同で担当している。そのPatrikも含めたバンドのメンバー全員が♪「Nanananana〜」というオールディズ・ライクな合唱を明るく歌う、#5『I’m OK』ではLaurentのハーモニカも随所で唄いルーツな色合いも伺える。しかし、このキャッチーさはこれまたシングル向きである。
#6『Will You Be Mine』で漸くスローダウンして、アクースティックなナンバーが出現する。ラップスティールとアクースティックギターの掛け合いに、コンガのようなパーカッションがカリビアンなリズムを刻むこの曲はやや異色というか、異国情緒が漂う不思議なナンバーだ。
同じような傾向の曲を少々続けるのが、このアルバムの特徴なのか、#7『Building Light』もピアノとオルガンがフューチャーされた夕暮れ色のようなじんわりとした哀愁が感じられるバラードである。やや泥臭目にうねりを織り込むギターソロが、アメリカ中部のルーツロックの有り様を示しているような気がするのは独断だろうか。
オルガンのソロと、ファルセット気味のSE的処理で歌うScottのヴォーカルリフから始まり、やや形骸化した様式だが、ガンと盛り上がりロックの躍動感をまざまざと見せ付けてくれる、ダイナミックなロックナンバーである#8『Memorial Day』。この曲の緊張感溢れるメロディの流れは、如実にScottが今一歩進化を遂げたことが明白な曲である。タイトルから推察可能であると思うが、戦死者の追悼を題材にしているが、バラードとせずにアップテンポな曲にしたことは何かの狙いがあったのだろうか。かなり悲しい歌であるのに、メロディはナショナル・ヒットしても不思議のないポップでロックなものなのだ。
一転して#7の如く、南部ロック的な落ち着きと土臭さが感情を込めて歌われる#9『Being Alone』もLaurentのハスキーなそれでいて高音部もシャウトも対応するヴォーカル・パフォーマンスが光るトラックである。メロディ的にはしっとりとした寂しさが漂うスローチューンである。この淡々と紡がれる内省的であるが、詩的な歌詞はアルバムの中では一番感動を覚えた。孤独に関する哲学的な思考さえ感じ取れる。このくらいの詩が書ける人はそう見つからないようにも思えるのだ。
ハーモニカとアクースティックギターをベースに静かに歌われる#10『Elvis』を挟み、職人芸的な余裕まで感じてしまう#11『Kids』がオリジナルソングのラストナンバーとなっている。この曲は派手さがない、アルバムトラック的なミディアム・チューンであるが、堅実な演奏と上品なアレンジ、そして何よりツボを得た曲の良さで、印象に残るであろうポップナンバーとして自己主張している。捨て曲がないというのは、改めて考えても凄いことだ。
そして、唯一のカヴァー曲#12『The First Cut Is The Deepest』が最後に来たのは予想さえ出来なかった。有名なヴァージョンはRod Stewartであろうか。ロッカバラード調にScottはアレンジをしているが、そこはかとないルーツテイストが織り込まれているところは彼独自の色合いが垣間見えて、ユニークというか好感が持てる。それにしてもカヴァー・ソングを最後に持ってくるというのは結構な自信の表れであろう。他人のイメージでアルバムが終焉するというのはどう考えても、アーティスト側では歓迎し難い締めくくりであるからだ。余程、自らのアレンジに確信があるのだろうし、実際個性が出ているため、成功したカヴァーであると捉えている。
さて、最後にこの日本ではあまりにもマイナーなミネアポリスの素晴らしいミュージシャンについて簡単に説明しておこう。
Scott Laurentはミネアポリス生まれ・育ちの人である。16歳の時、初めてバーのアクースティック・ショウに出演したのがキャリアの始まりで、幾つかのローカルバンドからスカウトされ、1995年にScott Laurent Bandを旧友のBrian Halversonらと結成するまでにかなりのバンドで歌い、ギターを弾く。1996年からBand名義で2枚のアルバムを発表するも、本国では全く無名のまま。が、イタリアとスペインで熱狂的な支持を受け、イタリアのレコードレーベルでも正式にリリースされる程となる。
Husker DuやReplacementsの出身地で活動の場であった都市に生まれ育ったが、実際によく見たバンドはもっとローカルなバンドが多かったのこと。が、音楽が盛んなミネアポリスが故郷なことについては誇りを隠そうとはしない。影響を受けたミュージシャンはJim Croce、Bob Dylan、
Waylon Jennings、The Beach Boys、The BeatlesにThe Whoと様々。80年代に10代のはじめだった頃はBob Segerが愛聴だったそうだ。Bobの持つ南部ロックの豪快さとシティ・ポップに通じるマイルドさをそのまま継承したようなバンドが、彼がリーダーを務めるScott Laurent Bandである。
前述のHusker Du、ReplacementsにJayhawksのそこそこの商業的成功により、本邦でもそれなりにミネアポリスのシーンは注目されるようになってはいる。が、このSLBのような素晴らしいバンドがまだまだ未発掘というのは、信じ難いところがある。
アメリカ中部の中庸的なロックやポップを聴きたい方、そしてあまり泥臭いルーツがいまいちのリスナーに、このバンドは協力推薦である。
オーソドックスという表現は、個性がない、または詰まらないとは全く意義を異にしていると思う。このScott Laurent Bandのようなアメリカンロックの分かり易さを、自らの独創性を取り混ぜつつも聴き易い音創りに昇華した音源こそ、普遍的な良心という意味合いでオーソドックスという敬称を与えたい。 (2001.8.26.)
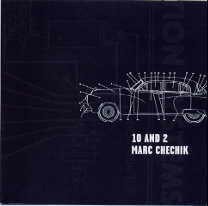 10 And 2 / Marc Chechik (2001)
10 And 2 / Marc Chechik (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Alt.Country ★★★★
ソロアーティストの作品が、嘗てそのアーティストが所属して又は結成していたグループのレヴェルを超えることは果たして、多いのだろうか?それとも少ないのだろうか?
まあ、必ず主観が入るのは必然であるから、「正解」という解答は捻出出来ないかもしれないが、やはり所属先のバンドのアルバム・クオリティがどの程度であったかということは大きくソロ活動の基準線になることは疑う余地はないであろう。
この法則に従うと、やはり偉大なバンドを出自として持つアーティスト程、「過去の栄光」に縛られることになるという道理が成り立ちそうである。実際、ヴェテランバンドを脱退してソロ活動に走ったアーティストで、この部分を引き摺りながら煩悶している人が多いだろう。
うかつに過去の所属バンドの音をなぞらえるだけでは、オマージュでない単なる模倣と捉えられる危険はつき物だし、「バンドを脱退」した意義そのものが問われるだろうから。
これとはやや趣を異にして、グループやプロジェクトに席を置きつつも、サイドプロジェクトとして、インスタントなコラボレーションや別バンドを結成するというパターンが取られることもある。最近はこの「掛け持ち型」が多く見えるのは筆者の幻覚であろうか。
こういった活動に対しての批判を含めた意見は置くとして、こういったサイドプロジェクトはある方向性を持って立ち上げられることが多いため、かなり内容の濃い音楽性になることが多々ある。この点も是非は問わない。幾ら字数を費やしても書ききれそうにないからだ。
しかし、新しい方向性や、やってみたい事を表現するのにはこちらの方法が利発な選択であろう。脱退という大事件を経ずにある程度自分の表現方法を追求できるからだ。小ざかしいという批判をすべきか、多才と賞賛すべきかは個人の判断に委ねるしかないだろう。簡潔に述べれば、筆者はサイドプロジェクト歓迎派である。が、いい加減本題に入らないと、一層拙文を読んで戴ける人口が減りそうなので、この辺でひとまず立ち戻ろう。
さて、このMarc Chechikという名前をご存知の方は相当なルーツロックのフリークであると信じたい。
ミズーリ州の州都、セントルイスには現在、レーベルでCDを買うことをしない筆者が、己の主義に反して非常に注目をしているレーベルが存在する。その名もUndertow。と大上段に発表する程マンモスなレーベルではない。所属アーティストも僅かな数しかいないことだし。
しかし、著者一押しバンドのNadineを筆頭にCentro−MaticsとDolly Varden、そしてこのMarc Chechikがリードヴォーカリストとギタリストにソングライターを務めるWaterlooを擁するこのレーベルのアーティストはかなり良心的でレヴェルの高いルーツ系のロックを届けてくれる。今後の注目レーベルとして見守っていきたい。
ここで触れたWaterlooとは、このMarcとMark Ray(同じくヴォーカリストでありギタリスト。ファーストネームも1字違いという共通点?がある。)が曲創りをして牽引しているバンドであり、1999年頃に結成され、2000年冬に「Going To The Sun」という初アルバムをリリースしている。
このアルバム、ルーツロックを基本にしているのは全く問題ないのだが、そこへオルタナティヴの音楽性とモダンロックのエッセンスを取り混ぜてしまっていて、かなり焦点がピンボケのアルバムになってしまっている。
昨年(2000年)の私的期待アルバムであったのだが、確かに悪くはなかった。十分鑑賞に耐えれうる力量は感じるのだ。が、オルタナティヴ的な平板でアンキャッチーさが、源泉として有するポップセンスとが、水と油の出会いのようなエマルジョン現象を惹起してしまっている。つまり、ルーツ音楽とオルタナ的現代性のフュージョン化に失敗していると敢えて断言しよう。
この2要素が相容れないとまでは言いたくないが、MarcのバンドであるWaterlooが全曲を手放しで賞賛不可能なのは、この点に置いてであることは闇夜の提灯より明白だ。
であるからして、今回のサイドプロジェクトとしてリーダアルバムを作成すると聞いた時も、然程期待はしていなかったのだ。まあ、輸送費のコストダウンのために取り敢えず纏め注文しておこうか、というような動機が主であったことを告白しておく。
がしかし、予想大ハズレ。これほどキャッチーでルーツィなアルバムを製作するとは想像をだにしなかった。というかWaterloo脱退してソロで活動して欲しいとまで夢想を弄ぶ始末である。
前述の如くに、あれこれやろうとして中途半端に終始してしまったWaterlooのサウンドを、より特化して濃度を密にしたアルバムである。特化の向く先は、よりキャッチーに、そしてアーシーに。アンキャッチーなメロディがどうしても不快であったWaterlooでの要素を100%排除することに成功している。
ロックという濃度を上げつつも、全体に流れる中部アメリカ的伝統音楽−ブルーグラスの趣をしっかりと堅持しているところがまさに成功の鍵になっているのだろう。
同レーベルのリーダーバンドNadineの傑作「Downtown Saturday」がお好きなら間違いなくハマレること請け合いのローファイさもまた伺える。が、Nadineよりもロックテイストを訴えかけるストレートなナンバーが多いのが、お気に入りの要因でもある。
まず1曲目の『Broken Radio』から、Marcの弾くピアノが軽快にリズムを刻み、同郷セントルイスの女性フィドルプレイヤーであるMary Alice Woodのバックヴォーカルをフルに取り入れた、極上のルーツ・ポップ&ロックソングがたたみ掛けてくる。適度に枯れていて、そのハスキーさ渋いMarcのヴォーカルが実に良いと初めて感じた。WaterlooではリードヴォーカルをMarkと分かち合っているが、ここまでヴォーカルが良いとは思わなかったものだ。やはり曲が良いものであるとヴォーカルも映えるのだろう。恐らくはMarcがオーヴァーダビングしているアクースティックギターの切なさとエレキギターの土臭さが、妙にマッチしている。
ゲストとして多彩な楽器で参加しているNadineのマルチプレイヤーである、Steve Raunerのドブロギターが、郷愁感というか、逢魔ケ刻の薄闇のような奥行きのある黄昏た色を発進している如くに錯覚するような#2『Miss Your Company』。第一印象としてはとても昏いメロディなのだが、ノスタルジックな哀愁が終始流れている。何時か何処かで見た、自然の風景を想い出して感慨に耽るような気持ちをメロディとして具現化したようなナンバーである。うう、何だか上手に表現が出来ないのが悔しい。一言、セピア色のソフトフォーカスの懸かったバラードだ。
そして、このアルバムの特徴でもある、静と動の切り分けの動の一面を顕したかのような、泥臭いパワーナンバー#3『That’s Right』。サザンロック程の豪快さを、アメリカ北中部の中庸性が見事に抑制したロックナンバーであり、Bob SegerやJohn Mellencampが80年代に残してくれたアメリカンロックの経典にブッキングされても文句が出ないだろうナンバーである。前曲の美しいバラードからの続きであるため、余計にロックンロールとしてのフックが明確に出ているのも変化を楽しむ上で宜しい。
#1に続いてMaryがフィーメール・ヴォイスを聴かせてくれる#4『Reservoir Tower』は6分近い大作である。Steve Raunerが爪弾くドブロと、Tom Townsendというセントルイスのピアニストが弾くピアノからと、静謐なリフで始まるこの曲は、ミディアムテンポに移行し、上品なポップさを軸にアンサンブルが奏でられる。そして後半ではア・ドリヴを多用したインストゥルメンタルのぶつかり合いの場になっていき、2分近い濃厚な掛け合いが堪能できる。ロックのビートではなくてもロックバトルを感じることが出来る編曲となっているが、大仰さを目立たせないところが、このバンドの美点だろう。
赤ん坊の笑い声と鈴の音、これにMarcが弾くピアノを中心としたアクースティックなリズム隊が加わる異色のインストナンバー#5『Sam’s Song』はアルバムの流れに変化をつけてくれるが、とてもユニークで印象に残る。1分程度の小作品に過ぎないのにだ。この赤ちゃんはMarcの実子、Samであるそうだ。
再度スローな曲の後に力強いロックナンバーが来るという流れが踏襲されているのか、#6『Butter Knife』も何ら捻りを入れない素直なロックナンバーである。ここでもアクースティックピアノが気持ち良く踊っている。と、このアルバムには殆どハモンドオルガンが使用されていないのである。ルーツィなレイドバック感覚を醸し出すアイテムとして、実に使い勝手の良いこのB3という楽器をあまり使わないで、このルーツロックなアルバムを製作したのは驚嘆に値することであると思う。しかし、この爽やかなロックンポップナンバーが3分以内の短さというのは残念である。
ややノイジーで粘着力のあるギターリフでスタートする#7『Love On The Swings』はタイトルの如く、リズムセクションとMarcの弾く数本のギターが、ジャムセッションのようにヴィヴィッドな印象を与えてくれる。このようなミディアムナンバーでブルージーな色合いを出そうとしても、何故かローファイな質感が抜けないのは、不思議である。泥臭さよりも、奥行きの深い新月の夜空という風な拡がりが目立ってしまうのだ。しかし、スゥイングするメロディラインは聴き応え満タンであるのは間違いない。
アクースティックでセントルイス・ローファイの基本のような#8『Just Because』はやや地味な、というより相当地味なフォーク調なバラードである。こういった、湿潤さが乾燥したメロディのアレンジと摩訶不思議に同居するところが、このアルバムを何回も聴ける魅力の一つなのだろう。決して、爽快でポップなロックチューンだけが、本作の牽引役でないことが理解できるトラックである。
そして、スローバラードの後はロック。定番化しているが、そこは基本であるから大歓迎である。最もラフというかフリーなスタイルで楽器同士が衝突を繰り返す曲、#9『Empty Bottle(Empty Bed)』ではホンキィ・トンクやジャズのスタイルも取り入れた豪快なロックンロールが聴ける。この動的な部分での弾けかたがとても気分を爽快にさせてくれるのだが、それにしても多彩な曲群である。
ラストはまたもシックなバラード#10『Level Field』がテイクされ、ロックの動とバラードの静が順序良く配置されたアルバムの基本姿勢を貫いている。SteveがここではLap Steelを披露している。また、同時にエレキギターも弾いている。最後の曲にしては少々地味過ぎるきらいがあるのだが、悪い曲ではない。#8と同様にじっくりと噛み締めて聴けるナンバーである。
Nadineとも共通する要素であるが、このバンドのというかMarc Chechikの魅力は埃っぽさを極力抑えながらも、ルーツロックの優しい側面をロックナンバーでもバラードでも表現できるところだろう。
DarkとかLo−Fiという表現よりも、SunsetとかDeserted Placeという寂寞な感慨や黄昏た雰囲気がより当てはまる音楽性が特徴。上品なルーツロックとでも言うべきか、それともウエットなポップセンスにルーツミュージックの安定感を負荷したロックンロール?
優雅であり、しっとりとした音楽性が蒼い闇のように全編に漂っている。その闇を透かして見えてくるのが、さらさらとした手触りで掴めそうな音楽という粒子の拡がりである。
文化的フィードバックは全く異なるのに、何故か幼い頃から大切に保っている心の琴線に触れてくるような甘さと寂しさは、名状し難い。
いずれにせよ、カントリーとは全くかけ離れた、ルーツロックである。ほぼ交互に現れるロックチューンには明るい躍動感があるが、スカスカな商業カントリーサウンドとは一線を画す落ち着いた姿勢が感じ取れるのだ。
Waterlooとは異なった、とまでは行かなくても、余分だった音楽性を取り払い、ポップとルーツに集中することでこれだけの傑作が生まれた。が、メンバーは全員Waterlooとの掛け持ちなのである。
Marc Chechik (Vocal,Piano,Guitars) 、 John Baldus (Drums) 、 Dave Melson (Bass)
のトリオにレーベルリーダのNadineを筆頭にして、セントルイスのインディ・シーンのミュージシャンがかなりの協力を行っている。NadineのヴォーカリストTodd Schnitzerがエンジニアとしてクレジットされているのが興味深い。
Marc Chechikの音楽活動は結構長いらしい。嘗てはニューヨークのハードロック・カフェでDJも勤めていたことがあるそうだ。90年代に入り、幾つかのバンドに参加したり、ソロシンガーとしてセントルイス周辺で活動している。
1998年には地元誌の年間アクースティックベスト10ミュージシャンに選ばれている。2000年初頭には初リーダーアルバムを自主制作しているとのこと。ミニアルバムらしいが、かなりローカル限定な発売であったらしく、探しているのだが未だ見つからないのは残念。今作を聴いて更に欲しくなってしまったのだが。(笑)
このアルバムも筆者協力推薦である。野暮ったい感覚でなく、限りなく正統派アメリカンロックに近似したルーツサウンドが最高に良い。
しかし、もう少しジャケットは見栄えの良いコマーシャルなものにした方が良かったかも。このようなジャケットで飛びつく物好きは作者の他には早々存在しないだろうから。(笑)
(2001.8.28.)
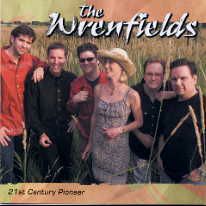 21st Century Pioneer / The Wrenfields (2001)
21st Century Pioneer / The Wrenfields (2001)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Blues&Alt.Country ★★★
You Can Listen From Here
嫌な予感はしていたのである。まあ、分かる方には分かると思うが(そら当然やね。)予感の原因はジャケットの真中に写っている女性である。消えてくれると実に嬉しいが。(ヲイ)この際、フレームの醜美は問題外である。
兎に角、女性ヴォーカルに対してはリピート性を持つこと自体が苦痛な著者(評価はしているのだが。受け付けないのはもう性であるので、致し方ない。)にとってはこのバンドのヴォーカルが、女性だったらどないしょ、という不安が亡霊のように付き纏っていたのだ。
というか、6人もいるのだから彼女はフィドルかチェロのプレイヤーに違いない、そうに決まった!!と勝手に判断−希望的観測ともいうが、を下しての衝動買い。・・・・買う前に情報集めませうね、健全なリスナー諸兄は。(汗)
後で公式HPを発見して、Lead Vocalの欄に女性らしき名前を発見した時は目の前が真っ暗になるくらい落ち込んでしまった。年に数回は試聴できないサイトでこういう失敗をするが。
とはいえ、救いはフィメール・ヴォーカル1枚のバンドでなかったことだ、このWrenfieldsが。ドラムスを担当するJohn Pyroもリードヴォーカルを担当し、紅一点のNoreen Novrickiとヴォーカルパートを分担、時にはデュエットを、またハーモニーの形式も採っている。
こういう男女混合のヴォーカリストなら許容範囲である。よってしっかりと聴き込み、レヴューと相成ったわけであるが、やはり邪魔。決してNoreenが二流のヴォーカリストではないことを記述しておくが、やはり明後日の彼方へと旅立って欲しい。(しつこい)
真面目なお話として、ヴォーカルが単調にならずにアルバムに変化を梃入れ出来る点において、混合ヴォーカルは優れた面を有しているし、このバンドも2枚ヴォーカルを十二分に活用している。
メンバーはジャケットに並んでいるように6人の大所帯である。バンドの人数は多ければ多いほど良いし、レコーディングをライヴで忠実に再現が可能と考えている筆者には、躊躇無く購入を促す編成である。
アメリカ北中部というか北東部になるのか微妙であるが、ミシガン州の大都市であるデトロイトを主体に活動を始めたバンドである。元来はミシガンのポップ・ロックバンドであったMiracleberriesというバンドを母体としている。
実はこのMiracleberriesが1997年にリリースした「Happy Hour」というデヴューアルバムを筆者自身が持っていたことについ最近というか、このWrenfieldsのレヴューを書いている途中で想い出した。ミシガンのライヴ会場で購入したものなのだが、そこそこの印象しかなくてすっかり忘却の彼方へと跳んでいた。まあ、こんなマイナーなCD持ってる物好きは著者以外には存在しないだろうが、音楽性としてはブルースロックとポップを取り混ぜたロックアルバムのようなものである。(?)というか手元に無いし、ここ数年聴いてないので、正直あまり正確には語れないというのが実情である。
今度発掘して聴いて見なければなるまい。ひょっとしたら当たりの可能性もある。日本に持ち帰ったということは聴ける要素があったアルバムであるからだ。
このMiracleberriesのメンバーであった4人
Frank Budd (Bass,Harmonica) 、 Tom Morgan (Guitars,Pedal Steel,Vocals)
Matt O’Bryan (Rhytm Guitars,Vocals) 、 John Pyro (L.Vocal,Drums)
にサポートメンバーであった David Berriman (Piano,Organ,Keyboards)とKiller Flamingosというグループのヴォーカルを担当していた女性シンガー Noreen Novrocki (L.Vocal,Percussion)の2名を加えて2000年に結成されたのが、このThe Wrenfieldsである。
この6人のメンバーの中でそれなりの目立った活動を記録しているのは、リード・ヴォーカル兼ドラマーのJohn PyroとピアニストのDavid Berrimanだろう。
Johnはミシガン−デトロイトのハードロック・シーンで活動を長くしていたドラマーで、ミシガンのバンドAgent Furyというグループに在籍すると共に、日本ではかなり売れたHMバンドであるHalloweenのレコーディングにも参加していた人である。
Davidはセッションキーボディストとしてかなり長いキャリアを持つプレイヤーである。Chuck Berry、The DriftersそしてThe Coasters等の大御所のアルバムにクレジットされている。また最近、自身の美しいピアノソロアルバムである「Happy Hour」をリリースしている。New Ageなこのピアノ・ソロ作品は結構大手のオンライン・ショップで扱っているので、試聴しても良いのではないだろうか。筆者もDavidの関連からこのThe Wrenfieldsに行き着いたクチである。
残りの4名は、些か縁の下な活動のこの2名にも及ばないような草の根活動をしていたミュージシャンである。が、キャリアのあるメンバーが集まっただけはあって、演奏はしっかりしている。新グループらしい粗さは全く見受けられることはない。
プロデュースとミキシングは元JayhawksのヴォーカリストであったMark OlsonのフォークグループであるOriginal Harmony Ridge Creek Dippersの最新作「My Own Jo Ellen」のミキシングを担当していたTyler Brownが担当している。彼の他にはサポートミュージシャンの名前は見当たらない。まあ、これだけの編成になればセッションマンを雇う必要も無いだろう。
さて、メインとなるヴォーカル・パートであるが、繰り返すようにドラマーのJohnと女性のNoreenの2枚体制である。殆どの曲で、JohnとNoreenがハーモニー・ヴォーカルというかダブル・ヴォーカルを聴かせてくれる。が、勿論メインをどちらかが歌うというパターンにハーモニーを重ねるという手法と表現した方がより正確である。
どちらかというと、非常に遺憾ながら(しつこい)Noreenがメインパートを歌う曲の方が多く感じる。というか多い。Johnがヴォーカリストとしては物凄い力量を持っているのだが、ハーモニー形式で歌わせると、Noreenのハイトーン・ヴォイスの方が際立つために、Noreenが主役に感じてしまうのだろうけれど。普段女性モノを聴いていないと、結構女性のヴォイスに耐性が出来なくなるので、耳に新しいのだろう。
全体としては、オルタナ・カントリーバンドと分類しても良いけれども、どちらかというとシカゴ周辺のローカルバンドに顕著なホワイト・ブルース的な言わばロッキン・ブルース的な側面が目立つバンドであると思う。基本をルーツロックのアーシーなところに置きながら、アーバン的な洗練された音創りも何処となく感じされると思えば、田舎臭い埃っぽさも耳に入ってくるサウンドメイキングをしている。
が、根底にあるのは、やはりややウネウネとしたブルージーさであると思う。この芯にポップなメロディとロックの活動さを肉付けして、女性ヴォーカルのまろやかさで包んだサウンドがこのThe Wrenfieldsの音楽性である。
Johnが主導権を取る曲は#1『Wondrous』、#6『Sleeping Bear』、#8『Sweet Mother Alcohol』、#10『Hoochey Coochey』くらいであるが、勿論、Noreenがコーラス・パートに限らずハーモニーを付けているところが特徴だろう。逆もまた然りであるが。
このJohn Pyroというヴォーカリストは声質的にはそれ程際立った点が無いのだが、かなり多彩な歌い方が出来る才能がある。シャウトからハイトーン気味な歌唱法、そして抑えの効いた歌い方まで披露してくれる。
#1はアクースティックなギターのリフから入る、ポップなロックナンバーである。バーバンド的な投げやりな歌い方とリズムにアップライト・ピアノ(グランドではないだろう)の高いトーンが走り回るところが印象的だ。
#6はハーモニカとNoreenのバックコーラスがのったりと流れ、ファズっぽいベースと憂鬱なギターが泣くブルースナンバー。#8はこれまたやや重いメロディラインにパワフルなJohnのヴォーカルがインパクトを与えるバーロック的なロックチューン。地味だが、安心して聴けるナンバーである。
#10はかなりパンチの効いたロッキン・ブルース的な投げやりヤケクソナンバー。(笑)エフェクトをかけて歌うJohnのヴォーカルやバンバンに叩かれるピアノ、泥臭いギターとかなり南部ロックへの傾倒が聴こえる。やはりここで挿入されるNoreenのヴォーカルのためか、黒っぽいソウルナンバーの気配も感じる。
対してNoreenがメインのヴォーカルを担当する曲は#2『21st Century Pioneer』、#5『The Nature Song』、#7『Pretty Nifty』、#9『Sheryl』、#11『Patchouli Train』、#12『Turn』とやはりやや多目である。無論、ソロで歌い切ることはなく、Johnを始めとするバンドの男性陣のヴォーカルがハーモニーやバックコーラスを付ける。
#2はかなりのスロー・ブギを思わせるナンバー。#1を聴いたところで、ひょっとしたら彼女はハーモニーヴォーカル専門かとも期待させたが、見事に突き落としてくれたナンバーでもある。(笑)
#5はキャッチーで、いかにも女性ヴォーカリストが好んで歌いそうなライトなポップナンバー。ハーモニカが殆ど通しで奏でられるところは印象が強い。が、ルーツテイストより、ロックンポップの派手さが際立つ曲である。
#7は相当ハードにドライヴィングするルーツナンバーである。このような重心の重い曲で女性中心のヴォーカルを聴くことが稀なため、かなり新鮮ではある。
#11、12ともに、これまた白人ブルースの影響が濃いナンバーである。がポップなメロディがくど過ぎることw中和しているし、Noreenの柔らかいヴォーカルのため、耳障りは軽目に感じるチューンである。
残りの#3『Rise Above』、#4『Courtin’A Christian Girl』、#13『House Upon The Hill』はほぼ均等にダブル・ヴォーカルスタイルで歌われるスタイルである。
#3は非常にポップでロックのミディアムより速目のビートが即効性満杯なロックチューンで、ヒット性が高そう。このような曲での男女デュオは非常に好みである。
#4はスロー・ブルースの匂いが強烈な、このアルバムのバラードタイプの曲の典型であるが、混合ヴォーカルのためかかなりエモーショナルなバラードとなっており、スローな曲の中では一番印象に残る残る曲である。
全体として、ポップさは申し分ない。が、前評判ではもっとポップでロックな音楽性という情報を得ていたため、ここまでイリノイ州のホワイトブルースの影響が顕著であるのにやや意外さを隠せない。
やはり、結構聴いているのは、ヴォーカルが2枚で男女混合だからだろう。冒頭で貶してはみたものの、このバンドが男性ヴォーカルだけのルーツバンドであったら、多くの音の中に埋もれてしまったかもしれない。
もう少し、多彩なロック寄りの音を出せそうな力量が伺えるので、これからが楽しみなバンドではある。ブルースに大きく傾く可能性も十分にあるのだが。
珍しく、女性ヴォーカルの入ったアルバムを購入したので、レヴューしてみた。年間に数枚聴く分には良いのかも。が、無論このバンドが女性ヴォーカルオンリーであったら、数回聴いたかどうか・・・・・・。
決め手は繰り返すが2枚のヴォーカルのハーモニーとDavidのピアノである。ああ、個人の趣味が丸出し。(笑)
(2001.8.31.)
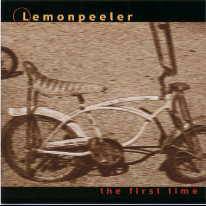 The First Time / Lemonpeeler (2001)
The First Time / Lemonpeeler (2001)
Roots ★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Acustic ★★
You Can Listen From Here
特別に理由がなく、書きたいのに書くことがズルズルと遅れてしまうアルバムが非常に多い。まあ、理由は執筆の速度に購入と聴くことの回転が追いつかないだけの話なのであるが。(汗)
とはいえ、かなりの傑作が未だ書かずに任せている事実や、反対に良作ではあるが、これ書くんやったら他書くべきやったかなあ、という論評も少々ある。
結論としては執筆の回転を上げれば良いだけの話であるが、なかなかそうもいかないのが現状である。
アップデートな紹介ができていないのは反省すべき点であるので、何とかしたいのだが。1人での運営には限界があるのでその辺はご容赦願えれば幸いである。
数行コメントを付けただけのCDカタログ&購入報告サイトにはしたくないので。
さて、最近どうも無駄に前置きが長くなる傾向が強くなってきたように思えてならない。よって早速本題に入るとしようか。
このアルバムも、数ヶ月前から書こう、書こうと考えていたのに、何故か後回しに甘んじてしまっていた多くのアルバムのうちの一枚である。とはいえ、アルバムの印象が薄いとか、書き綴ることが困難という類のアルバムではなくかなり好みな音楽性なのである。
Lemonpeeler=「檸檬の皮むき器」という意味のバンド名である。かなり酸っぱい匂いが立ち込めそうなネーミングであるが、酸っぱいという味覚を惹起するメロディは何処にも見受けられない。
さて、皮を剥いて見るとどうだろか・・・・・・・・・・・。
檸檬にも色々あって、中には甘酸っぱい味わいの檸檬もあるだろう。・・・・が、やはり酸味の感じるこの青臭い表現も彼らには似合わない気がする。人によってはこのようなキャッチーで爽やか系のメロディを「青春の甘酸っぱさ」と赤面したくなるような表現で表すのだろうが、さすがに恥ずかしくて使用を躊躇ってしまう。(笑)
それに、感覚としては、甘酸っぱいというより、「甘い」サウンドと考えているから。甘いといってもこれまた様々な甘味があるだろう。コッテリとした甘さや、甘さを抑えたものまで。
この彼らのデヴューアルバム「The First Time」は酸味を覚えるようなヒネリや変調は皆無に近いが、とはいえ甘さだけで勝負している訳ではない。アクースティックな居心地の良さと、些かの力みも無い素直なメロディ、そして自然体に仕上げているアレンジ。
Gin Blossomsからオルタナティヴの人工的サウンドを排除して、The JayhawksのMark Olson風のアクースティックで優しい作風を重ねたような音。と説明してみたが、あまり巧みな例えになっていない気がする。
パワー・ポップというジャンルは非常に曖昧模糊とした分類方法で、あまり記述したくないのだが、便宜上しっくりと当てはまる単語が見つからない場合、簡便な語彙であるため、仕方なく使ってみると、アクースティック・パワー・ポップな音楽性にルーツ・ポップの土臭さを加味した音。こう表現できるだろう。
とても素直なアレンジとメロディを主体に据えたポップ・ロックバンドである。やはり、個人的にはこのようなポップバンドをパワー・ポップの”1つ”と呼びたい。問題はカントリー的な要素まで伺わせてしまう素朴な側面であるが、パワー・ポップとルーツ系の音楽が一括りになって悪いことがあるだろうか?
ヘヴィロックのノイジーなスコアにポップなヒネリを微量に加えただけで、ハード・ポップと持て囃されているような耳障りな音の蜜月関係も市民権を獲得しているのだから、カントリーとパワー・ポップの締結もあっても不可にはなることはないだろう。
このバンドは今年になって立て続けに傑作・良作なアルバムを届けてくれる一大産地になりつつある、米国東海岸の大都市、ボストンを活動の場としている。
結成の母体は1999年、ソングライターのMichael HayesとギタリストのJim Eddyがデュオを組んだことに端を発する。1995年にミネアポリスからボストンへとやって来たHayesは、ボストンのバークリー音楽大学へ通うが2年程で落ちこぼれてしまったそうである。そのままボストンで、アクースティックなソロ活動を続けるうちに、友人の紹介でJimと出会うことになる。丁度Jimが在籍していたバンドが解散した直後のことであったが、Michaelの書いた歌に惚れ込んだJimは早速ユニットを組むことを提案し、数回のギグを経験した後、本格的にバンドを組むことを彼らは決定する。
Michael Hayes (L.Vocal,Guitar) , Jim Eddy (L.Guitar,Vocals) , Rob Pevitts (Bass)
Booth Hardy (Drums)
の4人組でレコーディングを行い、プロデューサーはPaul Westerburgのエンジニア等を勤めていたDavid Minehanが彼らと共同で当たっている。
Hayesが語るところに拠れば、このバンドが目指すところは
「聴いてくれた人達に、全てが新しく思えた少年少女の時代−初めて自転車に乗り、コケた。初めてキャッチーでポップな音楽を聴いて感動した−を思い出させるような音楽を演奏していきたい。」
だそうである。このコメントを裏付けるように、ジャケットの写真は1960年代後半に流行した子供用の自転車ということ。「The First Time」−初めて自転車に乗った遠い昔の日々を意図して仕上げたアートワークということだ。
「僕はBob Dylanの大フリークなんだ。」と自認するHayesのペンによる曲にはDylanのフォーキィな影響が見えないことも無いが、90年代のハイティーンの頃に地元のバンドで最も印象深かったという、JayhawksとReplacementsのミネソタ州のバンドの方向性を正統に引き継いでいると思う。Jayhawksの4thくらいまでの繊細でくどくないカントリーフレイヴァーとReplacementsのフックの効いたロックテイストを均等に配分したような音楽性が顕著である。が、後者のパンクテイストは殆ど聴こえてこなく、細微できめの細かい暖かいサウンドの側面が突出している。
ポップにノイジーにパンクロックをかっ飛ばすバンドはゴマンと存在するので、この優しさに満ちたロックンロールは特徴があると感じるのだ。
この目指す道は、やはりHayesのコメントからも伺える。
「僕たちは子供の頃、アナログ盤を聴いていた時や、大人になるまで聴いてきた音楽がどのようなものだったかを常に念頭においてるんだ。」
「僕たちは全員、ブリトニー・スピアーズが引っ張る音楽シーンなんかちっとも楽しくないと信じてるし、ヘヴィでラップを仕込んだメタルもどきは絶対に受け入れられないという信念を共有しているのさ。」
実に素晴らしいことを述べてくれる。Michael Hayesは筆者より少々年下であるが、ここまで大口を叩いてくれて誠に嬉しい限りである。更に、彼らの演奏する曲が素晴らしいので、口だけでないところが説得力に満ちている。
事実、このコメントを読んで彼らのアルバムの購入を決めた次第である。
このデヴューアルバムは数回のミニアルバムプレスを経て、リリースされている。地元ボストンでもかなり専門家筋には受けが良いらしく、新聞や雑誌にも好意的に紹介されているようだ。
収録されているのは9曲プラスシークレットトラックというか#1『Automatic』のデモ風のアウトテイク・ヴァージョンが最後に入っている。
この最初の曲がやはりこのアルバムのハイライトであろう。アップビートでポップなドライヴィン・ルーツナンバーである。ややハイトーンでJayhawksのGary Lourisがプレスには繁く比較の対象に持ち出されているが、メランコリックな魅力のあるHayesのヴォーカルとJimのハーモニーがばっちりと決まったナンバーで、ラジオシングル第一弾になったのも当然だ。この1曲で、アルバム全体がかなりナチュラルなパワー・ポップアルバムの印象を受けてしまう程だ。やや内省的なラヴ・ソングと言うべきであろう詩であるが、かなりシニカルな歌詞が面白い。この観点はCounting CrowsのAdamの書く詩にに通じるところがありそうだ。
2曲目になると、ややカントリータッチの軽めのギターがフューチャーされた『The First Time』で、このバンドがルーツ寄りのスタイルを持っていることが分かる。爽やかなコーラスワークといい、ハイトーンなヴォーカルといい、大陸の反対側の西海岸で盛んなロックスタイルを思わせるナンバーである。
#3『Around』も十分にシングルとしてカットできるような完成度の曲だ。アクースティックとエレキのギターの折り合いが巧みについたポップ・ロックである。しかし、歌詞は非常に明るいメロディとは対照的にミステリアスで、どちらかというと死者の追憶のような意味深な詩が耳に入ってくる。多分に想像力が必要な曲だ、理解するには。私的には殺してしまった片思い人への狂気、という類に解釈している。
「Old Bob Dylan Song」という単語も聴かれる#4『Annabell’s Design』と続く#5『The Limit On You』は共におとなしいスローナンバーである。やや黒っぽい影響も伺える#5と切なげなメロディがすすり泣く#4のどちらも良作であるのだが、やや中弛みを感じないでもない。この箇所に#1のような頭が自然に動くようなロックナンバーが欲しいところである。
ミディアムなポップソングの#6『Northbound Plane』はアルバム・トラックとしては申し分ない。しっとりとしたウエット感覚に富んだメロディは噛み締めれば噛み締める程に効いて来るように思える。しかし、歌詞はかなり難解である。宗教観念のような、ラヴ・ソングのようなどちらとも取れるような内容である。
#7『Two Sisters』はアルバム中で、最もハードでロックするナンバーとなっている。少々ポップさが足りなく、即効性がいまいちなのが残念である。が、アルバムの流れにアクセントを付ける意味では良い位置にトラックされているナンバーであるとは思う。
#8『Take Me Back』はメロディ的には平凡である。ここではやはりヴォーカルのHayesのややファルセット気味な鼻にかかったような高い音域が目立つ。この詩は、かなりロマンティックな内容であるように思える。高台から街を見下ろし、日常を振り返りながら昼夜を過ごし、星明りに濡れながら、朝日を待つ。ラヴ・ソングのようでそれよりも深い、という傾向はMichael Hayesが全編で編み上げている詩世界であるが、かなり皮肉な観点が織り込まれているにも拘わらず、綺麗な心風景が浮かんでくるのは不思議である。
#9『Caroline’s Gone』はかなり地味なアクースティックナンバーで、最後を締めるには些か平板な曲に思える。が直ぐに続く#1のデモ的なラフ・ヴァージョンがポップにフェイドアウトを懸けてくれるため、リプリーズ的な効果をもたらしてくれて、アルバムとして起と結がかっちりとはめ込まれて、バランス良く終わっている。
問題は起承転結のうち、「承転」の中間部分がやや一本調子なところか。全体として聴くと、ジェントリーで湿潤なメロディが心を安らげてくれる。のだが、1曲ごとに集中するとまだまだもう一歩、パンチ力に欠けるところが見えてくるのだ。特にレヴューを書く前後は、題材にするアルバムをエンドレスで垂れ流し状態にしながら筆を執るのだが、こうして聴くとやはりポップという点でいまいち開き直れていない。60年代・70年代のラジオ・ソングのオマージュを創りたいという意図はひしひしと伝わってくる。
だからこそ、更なる成長を願いたい。初期のJayhawksのような素朴さが魅力であるので、その点は大事に離さないようにはしてもらいたい。
これからが楽しみなバンドであるので、すぐに解散などせずに活動を継続して欲しいものだ。このアルバムでも、辛口なことを述べているが、かなりの完成度なのだから。
(2001.9.2.)
 Pneumonia / Whiskeytown (2001)
Pneumonia / Whiskeytown (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★☆
Alt.Country ★★★
You Can Listen From Here
Whiskeytownの、個人的にはデヴューアルバム「Faithless Street」(ボーナストラック満載の再発盤ではなく、1996年にリリースされた、ジャケットのバックがこのレヴューの背景色のようなプレスのこと。再発盤はボーナスが多いのは嬉しいが、あまりに収録曲が多く、寄せ集めなばらつきの大きいものになってしまっている。まあお得であると言えば相当お得なアルバムではあるのだが。)以来の傑作となるアルバムは、残念ながらグループが解散してから約2年後、本来のリリース予定からも約2年後に漸く発売の運びとなった。
元来、このアルバムは1999年にはリリース予定となっていた。プロデュースやミキシングを担当したのがR.E.M.との仕事で「5人目のR.E.M.」とも嘗ては称されていたScott Littであった。(T-Bone Burnettからもオファーがあったらしいが。)が、当時、3rdアルバムで漸くメジャーデヴューを果たしたWhiskeytownであったが、所属レーベルのOutpost Records(Geffen傘下)がUniversalとの合併に失敗して倒産・消滅してしまい、このアルバムは最終的なミックスダウンを行う前に宙に浮いてしまったのだ。
が、しかし、例えこの4枚目のアルバムが順当にリリースされたとしてもWhiskeytownとしてのグループの寿命は尽きていただろう。1998年にニューヨークのウッドストック郊外の元教会を利用したスタジオに集まったのは、フロントマンのRyan Adamsに女性フィドル奏者のCaitlin Cary、そして鍵盤からギター、マンドリンにペダルスティールといった多彩な楽器を使いこなすMike Dalyの3人しかバンドには残っていなかったのである。
Genesisではないけれども「そして3人が残った」状態でレコーディングが終了するや否や、レーベルの消滅によるギャラや版権のトラブルが惹起する。当初のアルバムタイトルは「Doing That」であったのだが、1999年半ばまでリリースはされるというステイトメントがあったにも拘わらず、何時の間にか、リリースそのものが先細りで消滅してしまった。
思うに、Ryan Adamsがこのアルバムを何としても発表するという熱意に欠けていたようである。彼ら程のそこそこメジャーでも名前が売れ始めたバンドであったなら、いかようにしてもアルバムをリリースすることは可能であったと想像できる。裏返せば、RyanがWhiskeytownというバンドとしての活動を倦んでいたのだろう。
が、先行プロモ盤としてや若干のアウトテイク盤が市場に流出していたので、ファンの間ではかなりの貴重盤扱いされて、オークションで100ドルを超える値段で取引されるようになったのが、1999年から2000年くらいの間。
「The Forever Valentine Demos」というブートレグとして大半が出回ったようであるが、現在もそこそこの高値で取引されているようである。
肝心のグループとしての活動は、Ryanが明確に解散という言葉を使わずにいたため、開店休業の状態で2000年までズルズルと引っ張られたが、彼の初ソロアルバムである「Heartbreaker」の発表に際して、Ryan Adamsは1999年にバンドから脱退していたこと−つまり彼のバンドであったWhiskeytownは終焉を迎えたと同義になる−をインタヴューで述べたため、もはやこのアルバムが日の目を見ることはないだろうと思ったものだ。
が、しかし新興レーベルであるLosthighway Records(IslandとMercuryの合資会社的レーベル)からまさかの再録音とミックスダウンを経て発売になろうとは。Ryan自体はUniversalと契約しているため、配給はUniversalという実にややこしい契約関係が、いかにもアメリカらしくはある。
2001年の9月末に2ndソロである「Gold」をリリースする運びになっているRyanであるが、このアルバムはソロアルバムのレコーディングへの弾みにするような目的で再録・再構築・再編成された可能性が高い。
実際、ソロ新作のプロデューサーは今作のドラムとベース、そしてマンドリンを担当までしているEthan Johnsである。無論、Losthighwayが版権の問題をクリアにしたからこそ、こうやって発売ができるようになったのは確かであろうけど。元々は2枚組みでリリースの予定であった25曲以上から、14曲とシークレットトラック1曲の計15曲を、大御所のプロデューサーであるGlyn Johnsの(Eagles、The Who、Rolling Stones、Steve Miller Band、Eric Claptonと挙げればきりがないくらい名盤・著名アーティストをプロデュースしている。)息子、Ethanがミックスダウンまで手掛けいている。彼はRyanのソロデヴュー作「Heartbreaker」でもプロデューサーを努めている。かなりの息の合ったコンビネーションのようである。又は、蜜月関係か?(笑)
さて、最早解散してしまったため、Whiskeytownについて詳細に述べる必要もないように思われる。というか筆者的にメジャーレーベルと契約して、あまつさえ日本盤まで(3rdアルバムの「Stranger Almanac」。当時日本にいなかったので長い間全く知らなかった。)リリースされるようなバンドは情報ソースに不足することはないと考えているからである。が、一応簡単に述べると、Whiskeytownはリード・ヴォーカリスト兼メイン・ソングライターのRyan Adamsの個人プロジェクトという色合いの濃いバンドである。
結成は1994年のニューヨーク州にて。元々Ryanはガレージ・パンクロック一筋を追求していたミュージシャンであったのだが、ノイジーなガレージロックを演じることに飽き飽きして、所謂カントリーロックとガレージロックの融合であるオルタナ・カントリーというサウンドを追及するために結成したプロジェクトである。それまで結成していたThe Patty Duke Syndromeというパンクバンドは、Whiskeytown結成後に、即解散させている。
1994年に4曲入りのシングル「Angle」を発表。このアルバムに収録の『Angels Are Messengers From God』と『Tennessee Square』、『Take
Your Guns To Town』そして『Captain Smith』の全てが、1997年にインディリリースされた8曲入りのアルバム「Rural Free Delivery」に再収録されている。このアルバムが当節のカントリーロックの再評価の波に乗り、次いでリリースされたフルレングスの「Faithless Street」がNo Depressionで大きく取り上げられ、注目を集めるようになる。そして、前述の2ndアルバム「Stranger Almanac」をGeffen傘下からメジャーリリースしたのが1997年のことである。その他、「In Your Wildest Dream」というプロモCDシングルと「Bloodshot Singles」という7インチ盤を、いずれもアルバム未収録曲のみで構成しリリースをしている。この2枚は入手は現在は絶望である。
結局は、ソングライティング・クレジットだけに目を通せば、その都度交代を重ねてきたバンドメンバーとの共作曲が圧倒的に多いのだが、やはりバンドの牽引役と原動力はRyan Adamsに位置していたのは疑いようもなく、結成当時から残留しているのはヴォーカルとフィドルのCaitlin Caryのみである。このアルバムの前作である「Stranger Almanac」のリリースの時点でもそれは同様である。
この「Pneumonia」で曲の大半をRyanと書いているMike Dalyは3rdアルバムリリース後にバンドに加わっているために、もはやこのアルバムはWhiskeytownという名前は相応しくないかもしれない。ファン曰く、「RyanなくしてWhiskeytownならず」、であるらしいが。実際、Ryan Adamsというシンガー・ソングライターの個性が一番色濃く露出したアルバムであると思う。Whiskeytownの魅力は、ガレージパンクロックの荒削りな動的音楽性と、アメリカン・カントリーのゆったりした律動に内在する繊細でアクースティックな静的音楽性が、融合というより、交互に顕現するような極端さであったと感じる。
1stアルバムでは特にそのギャップが極端で、ノイジーに突っ走るガレージ・パンクナンバーが聴けたかと思うと、フィドルをバッキングしたトレディショナルな土着ロックが流れてくるという流れであった。
徹底的にカントリーアレンジを突き詰めたインディ時代に別れを告げたような回顧録「Rural Free Delivery」は置くとして、3rdの「Stranger Almanac」ではややこの二元性の音楽が歩み寄りを見せたかのように見えた、というよりカントリー・サイドへ傾いたようであった。
このパンク的な要素を持つシンガーという評価を蹴飛ばしたのが、1stソロ作の「Heartbreaker」であった。「初めて自由にアルバムを創れた」と回顧する彼のソロ作は、陰鬱で暗い、内省的などんよりとした、アルバムとなった。正直ここまでテンションを下げられると、芸術性は高いと評価されそうだが、苦手である。個人的にはあまり好きでない。
が、Ryan Adamsが単なるガレージ卒業からオルタナカントリーに流されたシンガーではないと教えてくれたアルバムであった。
基本的に、特にアルバム前半に置いて、この「Pneumonia」はロー・ファイで、やや鬱の入ったようなスローナンバーで固められている。が、メロディという線を注目すれば、遥かに「Heartbreaker」の上を越している。ポップ・ミュージックの普遍的なフッキングが過不足なく詰まっているため、暗さよりも美しさとリラックスした空気を感じることが出来て、聴き心地は非常に良好だ。
Ryanの言動からは、このアルバムを表舞台に出して嬉しいが、しかしバンド活動自体には全く未練はないことが分かる。
「バンド時代には忘れられない想い出もあるよ。でも、どちらかというと”ロック”であり続けることを期待されたバンドだったね。それにとりすました芸術性を持っていなければならなかった。でも、僕はこれ以上自分を子利口なミュージシャンとして演じつづけたくなかった。僕は僕のやりたいことをやりたいんだ。だからバンド活動という馘から解放されてほっとしているよ。」
「手にとってくれた人達には『Pneumonia』は最新のアルバムだけれども、僕にとってはもう過去の作品なんだ。確かにアルバムを再録してミックスする作業は楽しかったし、聴いていて飽きないけどね、自分でも。」
「それよりこのアルバムは新しいソロアルバムの『Gold』に取り掛かる2週間ほど前に作業を行ったんだ。」
「僕はバンドとして活動するために多くのことを犠牲にしてきた。だからある種の終焉とはいえ、”これが最後にして最高のレコードだ”って言えるのが嬉しいね。これが僕達の最後に吐き出したシロモノなのさ。しかも最高のね。」
という具合である。非常に残念ながら、Whiskeytownは終焉したのである。ここまでのアルバムが3年近く眠っていたのも残念であるし、これ以上バンドとしての音を聴けないのは些か寂しい。まあ、Ryan Adamsの事実上ワンマン・バンドであったため、Ryanが「Heartbreaker」のようなアンプラグド系に走ってくれなければ良しと捉えている。この点については展望は明るいと思う。後に述べるとしよう。
さて、かなりこのアルバム関連の情報が長くなってしまった。次いでアルバムの曲感を述べていきたい。
「雰囲気としては60年代ロックのようなブートレグのような感じを。でも叙事詩的なものよりも現在をコラージュしたようなアルバムに、ロックとしてのエッジを持ったアルバムにしたかった」
とRyanが語るように、アレンジは一見ルーズでクラシカルな耳触りであるけれども、やはり90年代ロックとしてのコンテンポラリーな要素が聴こえてくると思う。ロックのエッジについては、少々疑問というか、感じることはできそうもないが。ライヴ録音というより、古臭い録音機器を使用して作業を行った如くな雰囲気が醸し出されているのは狙い通りであると思う。この内向的とまでは根暗でなく、シックな大らかさは非常にパーソナルなアルバムの感を強くする。が、ソロ前作の内に篭った陰鬱さよりも、滑らかなレイドバック感覚が勝っているのは、アルバムとして成功していると考えたい。
レコーディングはRyanとCaitlinにマルチプレイヤーのMikeというWhiskeytownの最後のトリオにプロデューサーのEthan Johnsがドラム全てと他の楽器も、そしてかなりのゲスト陣の中でも目を引くのは元Replacementsで、現在は再編成されたGuns N’ RosesのベーシストであるTommy Stisonがギターとドブロで、更に元Smasing Pumpkinsのギタリスト、James Ihaが参加しているところである。
Ihaは#5『Don’t Be Sad』をRyan並びにMikeと共作してバック・ヴォーカルにも参加している。この曲はIhaのソロ作を思い出させるようにアクースティックで、ストリングスも取り入れた、やや陰りのある美しいミディアム・スローなバラードである。リフから終始繰り返されるウエットなリフレインとハイトーンなコーラスはこのアルバムを代表してもよい要素を見せてくれる。
通しで聴いても「ロックンロール」というアグレッシヴ・ビートの顕著なナンバーは正直皆無である。ミディアムテンポ近辺と中程度の速さのポップロックなトラックを探してみても、#2、#8、#11、#14の4曲くらいだろう。それも相対的に比較した上であるから、このアルバムの曲が総じてユルイということが推し量れる筈である。
基本的にそれなりにロックして貰えないと、評価が辛くなりがちな筆者であるが、このアルバムはかなりストライクゾーンだ。何故ならば、兎に角、美麗であること。素直でコマーシャルなメロディが実にヴィヴィッドであるからだ。
全体的に暗色系であるけれども、メロディの行間に色が見えてくるくらい視覚的である。古臭いアレンジを施しているけれども、不思議と新しい新鮮な音の重なりがコード進行に平行して飛び出してくるのだ。
やはり#11『Crazy About You』の様に、エレキ・ギターが控えめであるが、陽性のリフを弾き出すようなナンバーはステロタイプという批判を受けたとしても、常に大好きなナンバーであるし、伸び伸びと歌うRyanのややハイトーンとハスキー・ヴォイスの中間のようなヴォーカルも清々しい。
タイプは違えども、フィドルが陽気にドライヴしまくる#14『Bar Lights』も土着音楽系譜の踊り的リズムがあって、耳を傾けてしまうナンバーだ。ややマイナーにヒネリを入れるコーラスワークが脱力感があってユニークだ。
#8『Mirror , Mirror』はホーンアレンジを控えめに施し、ローキーなピアノがホンキィに叩かれるサザン・ソウルっぽいロックナンバーである。このような古典的なロックへの追従は今までのWhiskeytownでは全く聴くことができなかったタイプの曲であり、鮮烈な印象を受ける。
#2『Don’t Wanna Know Why』はアンダーに流れたデモ盤にも収録されていたナンバーであるが、軽快なカントリーロックナンバーで、キャッチーなポップナンバーの見本のような曲だ。マンドリンやフィドルがフューチャーされ、丁寧に重ねられたバック・ヴォーカルとRyanのやや高めの音域を駆使したヴォイスの掛け合いが即効性を倍増させている。#1『The Ballad Of Carol Lynn』のブルースハープをコッテリと織り込んだ極上のルーツバラードから流れるように続くポップ・コンボで、冒頭から後のトラックを期待させる演出を過不足なく表現している。
Ryanのアクースティック・オリエンティッドな静的方向性が聴けるナンバーは枚挙に暇がない。#4『Reason To Lie』、#7『Under Your Breath』、#12『My Hometown』、#13『Easy Hearts』等などである。中でも、ノスタルジックな甘く優しいメロディが、寂しくも懐かしい#13はかなりのお気に入りのナンバーである。Caitlin Caryのバックヴォーカルも良いインパクトとなっている。このような女性コーラスは大好きなのだが。
どことなくカリビアン・ミュージックやレゲエ的リズムが目立つ#9『Paper Moon』も冒険している曲であると思う。ここにマンドセロを中心にしたゴスペルミュージックの素養を加えて独自に消化しているところは、Ryanの多才な面を顕しているように思える。
#3『Jacksonville』もレイドバックした雰囲気が漂うナンバーであるが、全体にのしかかるような気だるさが何ともいえない味わいがある。所々で裏返ってファルセット気味に伸びていくRyanのヴォーカルを聴き込みするには打ってつけのナンバーだろう。前半3曲の流れは、ほぼ完璧である。
そして、最後にシークレット・トラックとして、このアルバムの録音に使用した元教会の聖堂を音響効果に最大限に利用したような音の空間的拡がりを聴かせてくれるナンバーが入っている。50年代のような合唱的なコーラスと壊れかけたようなパンプ・オルガンが印象的な、黒人霊歌を髣髴とさせるナンバーで、これは楽しい。
以上、これまでに必ずといって良いほど入っていた、オルタナカントリーのオルタナ的要素を前作よりも排除して、曲としてはずっとポップさを追求した傑作が、このバンド最後のアルバムである。
まずはちゃんとした形でリリースされたことを喜びたい。また、Ryan Adamsがバンドを辞めたからといって創作意欲が鈍っていないのも嬉しいことである。
もうすぐ発売のソロ2作目「Gold」はソロデヴューアルバムとは異なり、ポップとロックも視野に入れたアルバムのようである。試聴した限り、期待が大きい。
また、Ryanの原点的なガレージロックを目指した彼の別プロジェクトである、The Pink Houseもレコーディングを半分以上完了し、音源が届くのも近いに違いない。筆者的にはやはりロックンロールしたRyanを聴きたいので楽しみである。
これから益々、Ryanはガレージロックとアクースティックなソングライターとしてのニ面性を分けて活動していく気配である。贅沢を言うと、両方を融合して貰いたいのだが、その判断は直に届く彼のソロワークを聴いてからにしたい。
(2001.9.10.)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
