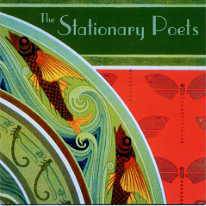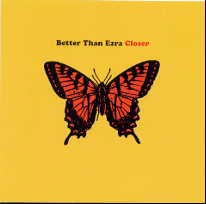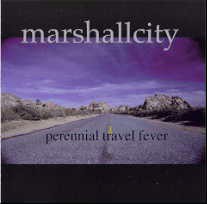 Perennial Travel Fever / Marshallcity (2001)
Perennial Travel Fever / Marshallcity (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Acustic&WestCoast ★★★★★
You Can Listen From Here
何と言うべきだろうか、懐かしさで一杯になってしまった。
この「Perennial Travel Fever」を初めてプレイヤーに放り込んで、流れてくる音を聴いた時は。
大変私的なことであるが、最近どうもLA周辺というか、西海岸から期待を持たせるルーツ系のロックバンドやシンガーが全く現れて来ない。元来、West Coarst Soundという爽やかでアクースティックな音楽は、60年代から70年代に台頭したCountry Rockと殆ど同義で認識されていたと思う。
しかし、時が流れ1990年代になると、純粋な西海岸ロックという音は殆ど耳に入らなくなってしまった。ロートル勢は兎も角として、新人の「こら凄い」という音は殊に2000年以降は殆ど聴くことが少ない。いわんやルーツロックの新人をや、である。
で、このMarshallcityを聴いた時、「こら、絶対に西海岸のバンドやで。」と確信を抱いた。アクースティックで爽やかなメロディと南国系の青空コーラス。どう考えてもカリフォルニアのサンディエゴあたりを拠点とするバンドに聴こえたのである。
このCG合成でもしたかのような紫雲靡く大空に、どこまでもグレイに伸びるフリーウェイというジャケットの持つ開放感も手伝って、ウエスト・コースト・サウンドの典型のような印象も相乗効果を与えてくれた。
が、しかし、実際は違った。このバンドはアメリカ中南部のオクラホマミキサーでその名前だけ有名な(そうか?)オクラホマのバンドであったのは結構ショックであった。あまりサザンロックやテキサス・ミュージックに顕著な垢抜けなさやラフさが−当然存在はするだろうが、オルタナティヴやヘヴィロックと比較すれば−それほど突出していないからである。
冒頭で”懐かしい”と述べたのだが、このアルバムを聴いて即座に連想したのはThe Eagles、Buffalo Springfield、Poco、Rick Danko、Loggins&Messina、America、Crosby,Stills & Nash And Young、Flying Burrito Brothersといったような1960年代から1970年代に主に活躍したカントリーロックや西海岸ロックと呼称されたバンドの数々である。
嘗て、音楽を聴き始めた時に漁りまくり、また音楽マーケットでも純然たる地位を獲得していた、West Coast Rockというジャンルにガッチリと当てはまる音楽性を持った新人バンドに出会ったのは本当に久方ぶりであったので、とても打撃を与えてくれたアルバムであった。
もっとも、聴き込むうちに、単純に西海岸風だけのサウンドを演じるバンドではないということが分かってきたのだが。Country Rockと銘打つよりもAlt.Countryと呼ぶべき音楽性がやはり基本として位置していると思う。Country Rockという表現はいまいち近いけれど遠いという感が強い。
更に懐かしいというのは単にこのようなバンドのサウンドを思い出させるだけでなく、とても甘くノスタルジックな音色を彼らのヴォーカル・ワークとインストゥルメントが爪弾くからだろう。
「僕達のマンドリンが目立ち、ハーモニカがたっぷりの音楽を何と呼ぶかよく分からないね。カントリーの要素というのはこれまでに僕が聴いてきたどんなロックにもあった。その影響が僕達の曲に顕れているんだろうね。つまりだよ、Tom PettyもNeil Youngも彼らのようなミュージシャン誰もがカントリー層をターゲットとしてレコードを作っていないだろう。でも彼らの演ってる音にはカントリーという影響が大きく働いてるのは否定できないだろう。Beatlesの「Rubber Soul」にだってカントリーのテイストがあるんだよ。」
と述べるのはMarshallcityのソングライターであり、ヴォーカリストであるPhilip Zoellnerである。
彼のこのコメントにMarshallcityの位置付けが示されているように思える。
筆者の解釈に拠るまでもないが、要するにカントリー・ロックとかカントリーを狙って曲を演奏しているのではなく、自らの影響を受けたアーティストの音楽性を元に曲を創る過程で、カントリーの要素が出てきたということだろう。つまりボケカスなヘヴィラップロックがどれだけシーンを席巻しようが、綿々と受け継がれるアメリカン・ロックの核を供えたロックンロールをやっているバンドであるということだ。
このように良質なロックバンドを”ルーツ”とわざわざ題を付けて分類しなければならないところに、2001年現在のメジャーシーンがいかに糞尿な音楽の巣窟かわかろうというものである。
筆者としては、このMarshallcityは、やはりウエスト・コースト・ミュージックの爽快さと、暖かさ、それらも含めたAlt.Countryバンドと範疇付けしたい。
ルーツ・ミュージックに不可欠の土臭さは勿論兼ね備えているが、タフやラフという表現が合致するサザンロック系譜のロックよりも、オルタナティヴロックと対極をなす意味でのアクースティックと暖かさがとても際立った、ナチュラルなルーツロックバンドである。
しかし、アクースティック系のバンドはそれこそ星の数ほど存在するが、サッドコアとかスローコアというジャンルに分類される暗くのっぺらぼうな退屈極まりないメロディに走らず、単に繊細なアクースティックオンリーなアルバムにも当てはまることなく、堅実にロックの速さとリズム感を維持しているところが、まさに彼らのリマーカブルなポイントであると思う。
パンクやガレージサウンドに依存することなく、EaglesやBryrdsのようなロックバンドとしての側面をも主張をしている点はとても評価できる。時代が時代なら間違いなくメジャーチャートの上位に居座っていてもおかしくないアルバムである。
さて、このアルバムであるが、バンドが設立したレーベルからのローカルリリースというインディ特有の発売の形をとっていたため、2000年11月頃にプレスされていたが、オクラホマ州以外で発売になったのは2001年に入ってからのこととなっている。故に発売を2001年としているが、この点をご了承願いたい。まあ、セルフ盤にはこのようなインナー表記と実発売の年度のタイムラグはよくあることであるが。話題休閑。
レコーディング時には4名態勢のカルテットであったが、2001年になって1名を加え5人編成となっている。
メンバーは殆ど20代前半で1970年代半ば以降の生まれの青年ばかりである。この若々しさというか蒼さがサウンドの合間に溢れていて、余計に甘さを醸造しているようにも思えるのだ。
メンバーは2001年10月現在で
Philip Zeollner (L.Vocal,Guitars,Piano,Harmonica) , Jay Falkner (Guitars,Mandolin,Vocals)
Jody Parsons (Mandolin,Harmonica,Vocals) , Colby Cook (Bass,Vocals)
Daniel McElroy (Drums,Percussion)
のラインナップ。レコーディング時にはパーマネント・ドラマーが存在せず、Ben Bennetという人がドラムを叩いている。ゲストミュージシャンは#6『Brush Off The Pain』でペダル・スティール、#7『Numbered Days』で女性バックヴォーカル、と2名のミュージシャンが参加しているだけである。
グループはオクラホマの大学生であったPhilipとJodyが1997年、在学中に結成したアクースティック・デュオのYou And Ponyboyというバンドを母体としている。このグループは同名のアルバムを自主リリースしているそうであるが、こちらも是非聴いてみたいものである。入手が可能であれば、の話であるが。
大学を卒業後Philipは中米の小国ベリーズでのヴォランティア活動を経て、故郷のオクラホマの東部にある街、Tulsaに戻り、本格的に音楽活動を開始する。
「帰国した時、もう音楽がやりたくてたまらなかった。これが僕のワイフワークと思ったね。」
とPhilipは回顧する。約2年のブランクを埋めるかのようにPhilipは曲を書き出し、ソロアーティストとしてレコーディングを開始する。が、ギタリストJayを加えた録音を経過するうちに、バンドとして活動したいという意欲が首を擡げ始め、
バンドを結成を決意。
これにギタリストであったJodyとColbyが参加する。
「グループにはもう僕を入れて2人もギター弾けるミュージシャンがいたんだ。ギターばかり増えても仕方ないので、Colbyにはベースを持ってもらい、旧友のJodyにはマンドリンとハーモニカをマスターしてもらったんだ。」
とサウンドの創り方を定めた、彼らは2000年始めにバンドとして活動を開始する。地元Tulsaでのクラブサーキットをしつつ2000年末にリリースされたのが本作「Perennial Travel Fever」である。2001年にはWilcoやBen Harperのオクラホマでのツアーにて前座を務めるまでになっているそうだ。
「僕たちは沢山のものをサウンドに取り入れている。僕たちの様にカントリーミュージックに留まることを良しとしない人達と同じように、現在進行形でやりたいことを掘り下げているのさ。」
というPhilipの発言に彼らのスタンスを読み取れるのではないか、と感じる。
収録曲は全13曲。内#13『Going Home』は40秒程度のアウトテイク的な小節である。ポップで張りの効いたギターとメンバー全員のコーラスが聴ける、彼らの味を極短に濃縮したようなブリッジである。
それ以外は3分以内の曲が大半を占めている。全ての曲がとてもキャッチーである。南部ルーツバンドのお約束なテイクといって良いブルース系やブラックルーツなキャッチーさが少ないナンバーが皆無というのが、非常に特徴があると思う。この事実が彼らを西海岸バンドとして錯覚させた要因である。
#1『Driving Westward』からして”西へ”という副題が似合いそうな「Across From The East To West」な詩である。のっけからマンドリンとハーモニカがとても乾いていて、それでいてハートウォーミングな音色を弾き出し、いきなりMarshallcityのサウンドに引き込まれてしまう。どこまでも青い空”Beneath The Big Roof Of The Blue Sky”という表現がとてもよく似合いそうな、暖かく、織り込まれたコーラスワークが思わず微笑を浮かべさせてしまうような1曲である。ドアを開けた瞬間から、瞬殺されるアルバム=オープニングナンバーが良いアルバムは大抵良作であるのだが、このアルバムもその例に漏れないことを予感させてくれる。しかし、ペダルスティールまで絡めて、マンドリンがカラリとした演奏を奏でているのに、カントリーの軽さが感じられずに限りなく心が温まるのが、彼らのマジックの様にも思えてしまう。
#2『She Took My Heart Away』では元気の良いサクサクしたギターがストレートでキャッチーなメロディを押さえるロックナンバーが炸裂する。#1で聴かせてくれたPhilipの甘いヴォーカルが、このトラックでは一転してシャウトまで聴かせてしまう。前半2曲で既に多彩なサウンドの拡がりを見せつけてくれるのだ。この曲はかなりルーズなロックであり、Marshallcityが単にほのぼの系なアクースティックバンドでないことを冒頭で刷り込みをしているように思えるほど良作である。故意に音程を外したり抑えを効かせたようなコーラスのアレンジも、未整理な故の躍動感ということをより一層強調している。
#3『Ride Into The Sky』はメンバーの中でも好きという評価を与えられているナンバーである。ぽややんとした暖かさが漂うスロー・アクースティックチューンである。殆どギターとハーモニカ、そしてスティックのハーカッシヴ・プレイだけで進行するアレンジに乗せて、分厚く多彩なコーラスをメインに据えた曲である。英国のポップス的な影響、Beatlesのコーラスアレンジが思い浮かぶが、あながち的外れでないとは思う。どちらかというとブリット・ミュージックの素直な一面である、ひたすらコマーシャルなポップさをルーツロックに持ち込んだような曲の様に感じるのだ。
ミディアムロックチューンな#4『Sail』は、殆どア・カ・ペラなPhilipの優しいヴォーカルから導入され、ボトルネックギターやハーモニカがリズムセクションと力み過ぎず、さりとて軽過ぎず・弱過ぎずの中庸さを繁栄していくナンバーである。このようなさりげないミディアムナンバーも非常にクオリティが高く、彼らの才能を痛感せずにはいられない。
#5『I’ll Find A Way Back To You』もミディアムだが#4より繊細でスローリーなアクースティックさがとても柔らかく感じる佳曲である。このような爽やかで繊細な曲を聴くと、やはり70年代のウエストコースト勢を比較に挙げずにはいられなくなる。Americaがプレイしても全く違和感のない調子の曲だと思う。
ペダル・スティールがとてもノスタルジックで落ち着いた雰囲気を演出している#6『Brush Off The Pain』はややおとなし目なテンポで入り、コーラスパートで軽く盛り上がるというポップ・ソングの見本のようなメロディを楽しめる1曲となっている。所々で挿入されるマンドリンのポロポロという音色が何とも言い難い明るさを付加してくれている。それにしてもこのような細微な使われ方をしているペダル・スティールなのだが、この音色を聴くだけでカントリーと決め付けてしまうリスナーが多いどこかの国ではあまり受けない楽器の選択かもしれない。
軽快にパタパタと走り回りる#7『Numbered Days』は女性コーラスも加えて、Beach Boysのようなサーフ風サウンドを堪能できるコーラス・ロックナンバーと呼べばどうかと思う。パーカッションやドラムの必要以上に力をいれずにバタバタと鳴るアレンジがかなり良好だ。しかし、とても南部のロックグループには見えないくらい、メンバー全員で歌うコーラスの折り重なりはハイトーンで甘い。このアップテンポな曲もシングル向きだろう。
#8『Dr.Metheny』はずばりカントリーロックという分類が一番無難な曲であろう。少々軽いアクースティックギターを中心にした弦楽器のアンサンブルが、ビルボードのホット・カントリーチャートのオンエアを聴いているような気分になり、少々スカスカ過ぎるところが不満と言えば不満だ。やはりスティール系のギターが能天気に歌い過ぎるとロックの醍醐味が半減するということだろうか。とはいえ、捨て曲には程遠いカントリー・ナンバーではある。
いきなりのシャウトで始まる#9『Texas』。Marshallcityはケンタッキーやカリフォルニアやアメリカの都市の名前を頻繁に歌に取り入れているが、♪「Rockin All The Way To Texas」というフレーズに彼らの南部音楽への、そのロックな部分への敬意を感じれるような気がしてならない。また歌詞中にBen Harperの名前も飛び出すというロック賛歌の一面も有している曲だ。しかし、どちらかというと黒っぽい音楽への追求をしているBenと、繊細で爽やかな音楽性を持ったMarshallcityに共通点があるのかは甚だ疑問である。
このかなりパンチの効いたロックナンバーは後半のハイライトであろう。彼らのラフ・ライドな側面が#2同様に聴ける曲である。こういった曲を聴くとMarshallcityがAlt.Countryと海外メディアに呼ばれるのもあながち間違いでないだろうという認識を持てる。
#10『Lovin’You』も#8と良く似たややスピーディなカントリー・ロックなチューンである。こういった曲をもっとラフでパワフルに仕上げることが可能であったなら、彼ら自らの主張する「カントリーという呪縛からの脱却」も、より多分に説得力を持つのだろうが、これは今後に期待するだけだ。反対にこのようなカントリー的な匂いの強いトラックが増えるようでは、恐らくここまで評価はできないであろう。基本的にカントリーカントリーしたアルバムは金を払って買う気はないのだから。
#11『Metal Company』はアクースティックなバンドである側面が表に発露している、しっとりとしたナンバーであり、必要以上にペダル・スティールが暴れ回った後半の雰囲気をトーンダウンしてくれる安らぎの1曲という位置付けがもっとも適切だろう。珍しくどの曲でも錯綜しまくるコーラスが殆ど入らず、リードヴォーカルのみで切々と歌い上げられるスローチューンで、実にほっとする。
事実上の最後の曲#12『Make It Last』はPhilipが友人から借りて「ぶっ飛んだ」というSon Voltのような、カントリーフレイヴァーを持ちつつも濃厚で力強い1曲である。スローに漂うファースト・ヴァースからコーラスでグンと変調しバラード調に展開する、一番雄大な曲である。そして、終盤のギターソロでテキサス・カントリータッチのアップテンポに更に変転するという、最後まで予想をつけれないナンバーとなっていて、どこかしら産業ロックの大仰さをシンプルにアーシーに表現したようにも思えてしまうのだ。
それにしても、このジャケットの色合いはとても絶妙である。
正直なところ、試聴をしようとしたが、Quick Timeのインストーラーが筆者のマシンではどうも相性が悪いらしく、聴こうとするとマシンがフリーズを繰り返したため、ジャケ買いすることとなった、結果として。
何とはなしに、爽やか青春カントリー・アルバムになりそうな予感がしていたが、当たらずも遠からず。苦手なカントリーにどっぷりなアルバムでなかったので幸いした。
大好きなMandolinとHarmonicaが縦横無尽に活躍しているところが最高にインプレッシヴであった。が、もう少しボトルネックギターをロックオリエンティッドに置換するアレンジをしないと、カントリーロックに近いカントリーバンドになりかねかい危険性があるように思えて不安である。
つまりもっとロックンロールに傾いてくれれば嬉しさの至上という訳である。このアルバムでもかなりの傑作ではあるので贅沢な要求であるかもしれないが。(苦笑)
嘗ての西海岸ロックのファンなら是非とも聴くべきアルバムである。最近良いWest Coast Soundに出会えないという方に届けられたSongs From Oklahomaと名付けたい。
しかし、納得がいかないのが、Philipがあの世紀のクソアルバムBlack Crowsの”Super Sucker”「Lion」がヘヴィロテであると述べていることだ。このような音楽を書く人があのような金返せアルバムを聴くとは、理解の埒外である。
(2001.10.14.)
 The Tiki Bar Is Open / John Hiatt (2001)
The Tiki Bar Is Open / John Hiatt (2001)
Roots ★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Southern ★★
You Can Listen From Here
『チキチキバンバン』ではないので、自動車が空を飛ぶことはない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『チキチキマシン猛レース』でもないので、ケンケンもブラック大魔王も出てこない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
って誰がこんなネタ分かるんやあ〜〜〜〜〜!!!(でも反応して欲しい、密かに。)
つーかド初牌からハズシしてますな。(涙)
冗談は顔だけにして、「”ティキ”・バー・イズ・オープン」、John HiattオヤヂのVanguard Recordsからの2枚目のアルバムについて語るとしよう。
そもそもTikiという意味は単語的には東太平洋の島嶼群であるポリネシア神話に語源を発している。
一般には民芸品となってしまっている土着信仰の偶像である神像を指すが、本来の意味合いとしては、彼らポリネシアンの世界の始祖となった神様というか最初の人間を言うのである。まあ、アダムとイヴの別ヴァージョンと考えてもらえば良いだろう。これを転じて、宗教的には人類の起源的なメタファーとして雅楽的な用法で用いられるらしい。
こういった実生活ではクソの役にも立たない雑学を述べ出すと、筆者の悪癖である薀蓄が止まらなくなるので、この辺で”単語の雑学”の時間は終わるとしよう。
さて、おやっさんも今年で49歳になるのだが、かなり生え際が後退しているし、頭頂部も相当やばそうである。完全ノン・ドラムで鉄パイプ類をパーカッションの代わりにするという、バリバリなアクースティックアルバムである2000年作品の「Crossing Muddy Water」を聴いた時、外見も枯れてきたけど、音楽も枯れたわなあ、としみじみ思ったものだが、更に外見では枯れ具合が進行している模様である。てっきり50の大台を越えたものばかりと勘違いしていた。ゴメンナサイ。
しかしながら、2001年のグラミー賞で最優秀Contemporary Folk Albumにノミネートされた「Crossing Muddy Water」の路線から今作「The Tiki Bar Is Open」では再びロック路線に返り咲いている。
セールス的には兎も角として−カヴァーされたシングルはバンスカヒットを記録するのに自分のシングルは全く売れない人であるし、未だにトップ40アルバムもないのだ。−各方面で絶賛されたアクースティックな方向性に安易に走らなかったのは、相当なものであると考えている。
1993年にリリースされた「Perfectly Good Guitar」程には切れまくった狂い咲き風なスタンピート・ロックンロールをやっている訳ではないが、1997年のこれはどうにも失敗作にしか思えない「Little Head」と枯れアルバムの「Crossing Muddy Water」とロックンロールとは呼べないアルバムが2枚続いたためか、やはり”おやっさん・まむしドリンクを飲んで復活”(謎)という感の強いロックなアルバムとして耳に飛び込んでくるのだ。
前作の枯れ具合を聴いた時は、真剣に「こら、もうこっちの路線で行くんかなあ。」と十分にいぶし銀的な音を味わいながらも、密かに残念に感じたものであるが、見事に”鬼の霍乱”とでも呼べるようなロックへの回帰を果たしてくれた。
しかも、レコーディング音源としては1988年の傑作アルバム「Slow Turnning」以来のThe Gonersとのコンビ復活であることが、更に嬉しいニュースだ。「Bring The Family」のツアーバンドとして来日も果たしたGonersとまたもタッグを組むとは想像していなかったので、Gonersを伴ってレコーディングに入ったというニュースを入手した時は相当驚いたものである。
「Johnのバンドから解雇された時は(1989年)、JohnのマネージメントからSonnyに連絡が来て、それをSonnyが僕らに伝えるという形だった。ちょっと驚きだったね。だって、もうその頃は『Real Fine Love』と『Through Your
Hands』のデモ・ヴァージョンを僕たちはレコーディングを終えていて、出来もとても良かったんだよ。両曲とも彼の次のアルバム”Stolen Moments”に収録されているけど。でもHiattは一つのユニットに固執しないで、色々なミュージシャンを使うことで有名だったからね。仕方なかったね。」
とベーシストのDave Ransonはジョイントを解消された時のことについて、こう述べている。が、JohnとGonersの間にはあまり遺恨は感じられない。Sonny Landrethの1992年のアルバム「Outward Bound」にはHiattがバックヴォーカルで参加もしている。
Hiattは当時の状況とりユニオンをこう語る。
「僕たちは約1年ツアーをした。それから”Slow Turnning”を録音した。それから、さしあたってやることは全てやったという理由くらいしか考えられないんだけど、特別な理由もなく、僕たちは別の道を歩むことになった。また、一緒に演奏をすることになるまで11年かかったよ。最初は単に楽しむためにツルんで、ちょっとギグをやっただけだったんだけどね。」
「1999年くらいに、20世紀末にまたGonersと組んだら楽しいだろうと考えた。だからGonersの3人とリラックスした非公式のライヴを少しやってみた。自転車に試しに乗るような軽い気分でやったよ。同時に僕たちは全く以前と変わっていないけど、反面全てが変わってしまったことに気が付いたんだ、凄くゴキゲンだってことが。」
と極自然にJohnとGonersは合流を果たしたようだ。お互いに嘗てのライヴパフォーマンスを賞賛していたのは間違いなく、ドラマーのKenneth Blevinsはこう言っている。
「僕が”Slow Turnning”でプレイしていたと知ると皆、このアルバムがとても感動的で出会えたことが人生の至福みたいなことを言うんだ。Rodney Crowellが僕に会うたびに『1988年のJohnとのギグが今まで見た最高のライヴ・パフォーマンスだった』って繰り返すしね。」
こう考えると、やはり戻るべくして戻ったバンド結成というべきだろう。まあ、Johnのことだから、次作はきっとまた新しいパートナーを探しそうではあるが。
新しいことが好きなのか、同じミュージシャンと継続的に活動することが主義に合わないのか、「Slow Turnning」のレコーディングをJohnはGonersに当初は委ねるつもりでなかったこともHiattの奇妙ともいえる性癖の印であるかもしれない。このエピソードも記しておこう。
「Bring The Family」のツアーでのライヴアクトで高い評価を得たJohn Hiattであるが、次作には別のミュージシャンを起用するつもりであったそうだ。Landrethに代わるスライド・ギタリストとして「化けもの」の日本語タイトルを発売して嘗て一部で注目されたDavid Lindleyをレコーディングに加えてアルバムを録音する予定だったのだ。
Lindeyを起用してのデモ・ヴァージョンである『Trudy And Dave』がかなり不満足な仕上がりであったために、急遽予定を変更してLandreth、BlevinsそしてRansonとの収録になったということだ。
さて、実際はJohn Hiatt & The Gonersと呼ぶべきかもしれないこのアルバムは現Counting CrowsのメンバーであるDavid Immergluckを含めて3ピースで録音された前作と比較するとゲストも交えての豪華(程度の問題ではあるが)なミュージシャンが参加している。
John Hiatt (L.Vocal,Guitars,Piano,12 String Guitar,Harmonica,Mandolin)
Sonny Landreth (E&A.Silde Guitar,E.Guitar,12 String Slide Guitar,E-Bow,B.Vocal)
Kenneth Blevins (Drums,Percussion) , David Ranson (E&A.Bass)
にプロデューサーでもあるJoy Joyce(Radney FosterやEvan&Jaronのアルバムにセッションミュージシャンとして参加したり、Tim FinnやEmmylou Harrisのプロデューサを務めている人だ。)が、ギターと鍵盤類や打ち込み系機材を担当している。
また、つい最近の2001年10月に夫のBuddy Millerとデュオ名義でかなり良いアルバムをリリースしたJulie Millerが3曲でバック・ヴォーカルを歌い、David Biancoがタイトル曲でピアノを弾いている。
これらのゲストをJohnは”Hornor Goner”と呼んでいる。(アルバムクレジットではHornoray Goners。)
かなりこじんまりとした編成であった前作のアクースティックアルバムよりは賑やかであろう。
全体を俯瞰してみると前半にロックのオヤヂパワー全開なアップテンポな曲が固まり、後半はスローな曲が目立つという構成になっている。
#1の『Everybody Went Low』から本当に久々に−1995年の「Walk On」以来だろう−Hiattのロック曲が飛び出してきた時は、思わず身を乗り出してしまった。最初から相当吸引力のあるキャッチーでパワフルなアップ・ビートな曲を持ってきたことから、今回はおやっさんロックをやるねんな、と納得させるようなナンバーである。それにしても、こういったアメリカンロックのストライクど真ん中のような曲が売れないのはどうしても納得ができない。このようなメロディが一度聴いたら忘れられないような名曲を数多く創ってきているのに、どうして大ブレイクしないのか未だ持って憤慨と哀しさを覚えてしまうのだ。
「ある日、僕が何となく12弦ギターを手にとって、徐に2コードでジャカジャカと弾き始めてできた曲なんだ。」という彼のコメントにもあるように、適度に暴れてくれるシンプルでキャッチーな曲だ。これがシングルになるのかと思いきや、予想は外れた。
続く#2『Hangin’Round Here』はブルースハープがリフから縦横無尽にスゥイングしまくる、どことなくBlues TravelerのJohn Hopperとシンクロするサザンロック風の軽快なナンバーだ。マンドリンといいアクースティック&エレキ・スライドギターといい、そこはかとなくタイダル・スワンプの湿り気と、乾燥帯の乾いた風が同居したようなレイドバック・ソングの佳曲だと思う。HiattはBob Dylanへの敬意を常に述べているが、この曲も
「Bobに出会ってから、僕はフォークロックの求道者になった。それ以来ロックとフォークの間を行ったり来たりしているけど、この曲は個人的な原点をバンドサウンドで表したものなんだ。」
ということをコメントしている。確かにDylan風のフォーキィな味わいが漂い、それに南部のスワンプ・ロックの楽しさを加味したような感じではある。
このアルバムは特に前半がポップで大好きなのだが、#3の『All The Lilacs In Ohio』もポップロックの最高峰と言える名曲だろう。#1と実に甲乙つけ難い出来である。この曲のタイトルと歌詞のアイディアはHiattのお気に入りの古い映画のシーンで、ラヴ・ストーリーを書けなくて悩む小説家とバーテンダーの会話から取られているということである。Gonersのタイトな演奏が実に疾走感満点だ。またJulie Millerのフィメール・バックコーラスも艶やかな色を曲に加味している。
アルバムからの1stシングルとなったのは#4『My Old Friend』である。これまたキャッチーなポップチューンで#1からこの曲まで息付く暇もないくらいのポップロック大攻勢である。このトラックもハーモニカとマンドリンがフューチャーされ、ややクラシカルなサザン・ポップ風の仕上げをされている。メロディ的には即連想できるのがThe Bandであるというのは些か貧困な連想だろうか。(笑)それにしてもJohnの粘っこいソウルフルなヴォーカルはこのようなナンバーでも、彼独自の味を醸し出している。逆にこの濃厚さが一般受けを妨げているのか、とも邪推したりするが、筆者としてはかなり好みなヴォーカルである。このヴォーカルの張りは「Walk On」のオープニングナンバーである『Cry Love』に匹敵するパンチ力がある。
#5でJohn HiattとThe Gonersの得意技を合体させたような、ブルージーでSonnyのスロースライドギターの冴えがファンには堪らないだろうナンバーでポップ攻勢は一休みとなる。Johnのハイキーを駆使して歌う歌唱法も結構レアな気がする。
初めてのバラード#6『Something Broken』はJohnの踏むHarmoniumが仄かな暖かさと寂しさを醸し出す、セピア色の曲という表現がしっくりくる内省的なナンバーだ。ピアノとアコーディオンのようなアレンジのHarmoniumがとても滑らかな音色を浮き出している。
「この曲は99年にアムステルダムで書いたんだ。僕は一日中麻薬売りの徘徊する地区のホテルでじっとしていた。毎晩窓の下で繰り広げられる風景は僕にかつての麻薬漬けで、狂ったように性欲にはけ口を求めていた日々を想い起こさせた。この記憶が書かせた詩なんだ、アムステルダムにてね・・・・。」
アクースティック・12弦ギターが乾いた音色を爪弾く#7『Rock Of Your Life』もどちらかというとスロー・サザンロック的な色合いの強いナチュラルなメロディが乾いた秋風のように心に染みるナンバーだ。地味ではあるが、とても優しいラインとアレンジの歌である。
乾いた#7とは対照的にウェットなアレンジとじんわりと滲んでくるようなメロディが、同じようにスローな曲でも全く異なった印象を与える#8『I’ll Never Get Over You』はシンセサイザーがトラッキングされた、AOR風のバラードになっている。Hiattとしてはこのようなアプローチは珍しいように思えるのだが、どうだろう。
うねるような黒っぽいリズムとメロディを有したタイトル曲、#9『The Tiki Bar Is Open』はメロディは典型的サザンブルースソングである。筆者の興味はこのタイトルの意味に絞られている。幸い、Johnのコメントがあるので、かいつまんで訳してみよう。
「僕がまだ少年だった頃、”ディトナ・ビーチ”と口の端に乗せる時、それは皆が理想の場所について恍惚と語っていることと同じだったんだ。そう、そこはオズの国のような夢の場所だった。ビーチもホット・ロッド・ファッションも、ポリネシアンビートのリズムも全てがそこに存在していたんだ。一度も”ディトナ・ビーチ”には行けなかったけどね。今は僕はその場所を良く知っている。レースを楽しむのさ、サーキットでね。更に驚くべきことに”ディトナ・ビーチ”はAmericanaミュージックが最低の流行音楽に侵食されていない所なんだ。」
「そう、ある晩、僕はビーチのホテルにレースを終えて戻ってきた。僕は沢山並んだモーテル街をドライブしていた。と、酷くぼろいモーテルが視界に飛び込んできたんだ。『Tiki Bar Is Open』という看板が立っている。即座に”おお、神よ。”って思った。僕は酔ってなかったけど、そこには悲しい瞳が一杯に満ちているのだなと確信した。嘗て夢を見ていた少年の僕の様に。だから僕にとってTiki Barが営業中ということは、理想のディトナ・ビーチが存在しているという記憶の源風景なんだ。」
・・・・・少年の日の夢・・・・・・・・。夢は夢であった方が良いのかもしれない。嘗て、あの山の向こうには、あの大きな煙突の向こうには何があるのか想像するだけだった日々の方が幸せだったのかもしれない。
残り2曲もスローな曲が連続する。しっとりしたバラードの#10『Come Home To You』は#9のコメントを念頭にしてその歌詞を咀嚼すると、その陰りを帯びたメロディの捉え方がとてつもなく愛惜を持ったものとして耳に流れ込んでくるような気がしてならないのだが。普通にメロディに耳を傾ければ、何てことないアルバムトラックのバラードではあるが。
最後の9分近い『Father Star』はループやプログラミング系の打ち込み音が目立つ異色なナンバーである。このサイケディリックな側面も伺わせる長いミステリアスなナンバーは、少々首を捻りたくなる。かなり全体からは浮いているアレンジとメロディであり、これが最後というのは締めには不向きに思えるのである。
最後の最後でちょいと残念という曲である。また、少々後半がスローナンバーばかりであり、前半のロックンロールに弾んでいる流れからトーンダウンしていることは否めない。
可能なら前半の勢いでもっとロック一筋なアルバムにしてくれれば良かったのに、と思う。
が、95年の「Walk On」以来、ロックアルバムとして聴き応えのある一枚になっているのは間違いない。前作の年齢に倣ったようなアクースティック路線も悪くはないが、まだまだ脳の血管が切れそうなロックをぶっ叩くおやっさんでいて欲しいと願う次第である。
それにしても前作から1年でまたもリリースをするとは、精力的である。これで”絶倫オヤヂ”と断言できるくらいのゴリゴリロックをこれからも聴かせてくれれば幸いであると思う。
恐らく日本盤はもうリリースされない気がする。結局「Crossing Muddy Water」も遂に発売がなかった。ボーナストラックを期待して2001年まで待った自分がアホとしか思えない。
これからも、きっとアメリカンロックの邦盤化は減少するのだろう。益々、一般のリスナーがアメリカンロックを聴く機会が減ると思うとやりきれなくはある。
例え、この良盤に満足していても、である。 (2001.10.16.)
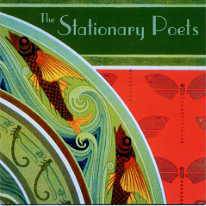 The Stationary Poets / The Stationary Poets (2001)
The Stationary Poets / The Stationary Poets (2001)
Roots ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Acustic&Americana ★★★☆
The Jayhawksの名作「Hallywood Town Hall」と「Tomorrow The Green Glass」を足して、そこに90年代のTom Pettyを掛けて、The Wallflowersを更に掛け合わせ、これらの平均値を算出したようなバンドである。
と、こういった表現はあまり使うと有り難味がなくなってしまうため、意識して使用しないように努めてはいるのだ。が、この「The Stationary Poets」のアルバムを初めて聴いた時はJohn Haydon & The Ten Worldをプレイヤーに入れた瞬間に感じた時と同じく、過去に聴いて現在まで愛して止まないアーティストの名前やレコードのタイトルを無意識に想像してしまった。
と、大風呂敷を広げておいて何なのだが、こういった過去のバンドが即座にして思い浮かぶバンドのアルバムは、筆者にとって結局大名盤になることが少ない。非常に良く出来ているのだが、どうしても私的名盤−こういった”連想”をする場合は世間的にもそこそこ評価の高い作品が大半を占めるけど−と比較してしまい、足りないところが際立ってしまうという、些か捻くれた心理状態が作用することが顕著な故のことである。
このThe Stationary Poetsという2001年にレコードデヴューしたバンドは、ざっかけない批判をすると、確かに満点の出来ではない。
第一にポップならば”どんつき”までポップで分かり易い音ほど大好きという、我ながら分かり易過ぎる嗜好から見ると「もう少し聴き易いコマーシャルさがあったなら最高なんねんけど。」という感想を抱いてしまう。それでも十二分にポップでは勿論ある。
第二にロックアルバムとしてはAmericana Soundのゆるりとした遅さが存在する曲が結構あって、「もう少しはめ外した”80年代チャート狙い”作風なポップ・ロックナンバーがあったらなあ。」とAmericanaと同様というよりも、それ以上に中毒のように溺愛している軽快なロックナンバーの数が不足している。
が、しかし、今年の夏にこのアルバムを入手してからこっち、相当な回数を我が部屋のプレイヤーの上でこのディスクが過ごしていることを考慮すると、実は相当気に入っているのだということが、レヴューを書くために流しっぱなしにしているうちに自覚できるようになったのだ。
とどのつまり、名盤となるデヴューアルバムに次以降の期待を重ねてしまって、過大な満足を求めてしまっているのだ。「次はこうなると嬉しい」という希望を「ここはこうだったら」という個人的願望を100%満たせない点の指摘に転化してしまっている次第である。
故にこのアルバムは既に名作なのである、著者の中では。満点の出来でない=次への飛躍もまだ期待できるバンドという前向きな期待の裏返しである。
と賞賛すると物凄いエポックメイキングなアルバムであるという錯覚を与えるかもしれない。が、、常なることで恐縮であるけど、はっきり言って、とても地味である。Mr.Henryの「40 Watt Fade」のルーツへの追求を少々濃くしたような作風と説明すれば、少なくともこの「ヘンリー氏」を聴いたことのある人なら理解してくれるのではないかと推察している。
ちなみにもう毎度のことになっているのだが、日本からの購入第一号である。登頂した処女峰の何と多いことか。しかし、制覇した山々がジャイアント・クラス(註:標高8000mを超える13座を海外では通例こう呼ぶ)ではなく、名も知られていない峰であるのだから、そう吹聴することでもないのだけれども。
特徴は、何と言ってもギタリスト兼任のRobin Millerが殆ど全曲で弾いているピアノ、オルガン、フェンダー・ローズピアノといったキーボードサウンドをバンドアンサンブルに取り入れていることであろう。が、このアルバムの全トラックに共通することであるのだが、くっきりとした鍵盤の音はバンドの他の楽器に埋もれる形でありながら、自己主張することが顕著である。
あくまで、他の楽器をサポートし、サウンドに奥行きと厚みをもたらすアレンジを主眼において演奏されているのであるが、メインを張っていることは間違いないように感じるのだ。
ともすればギターとリズムセクションだけの音楽というのは無駄がなく、シンプルな風味を創り出すけれども、その味わいが平坦で飽きることが多い薄っぺらさを持つことが良くある。まあ、この瑕疵をいかにして目立たなくさせるのかが、CD作成上で問われる力量ではあるのだが。
無論、ノン・キーボードの編成が悪いということは無いし、絶対的にロックバンドではこちらの編成の方が多い。しかしながら、やはり鍵盤の音をパーマネントとして有しているバンドには音空間の拡がりがより大きいと思う。所謂3ピース編成と比較したら。バラードにせよ、スピーディな曲にせよ、鍵盤を入れるだけで華やいだり、更に引き締まったりすることだってあるのだ。
・・・・・これ以上書いても”鍵盤万歳”の提灯を掲げる以外の何ものでもなくなるので、ここで筆を止めることにするが、少なくともThe Stationary Poets(以下SP)は鍵盤の音をバンドサウンドに取り込むことで成功している良い例であると断言したい。
というのは、彼らの更なる注目点の、Americana的な緩くて泥臭いブルージーさが、鍵盤の明るく健全な音で緩和され、モダンロック的な色合いを帯びる結果となっているからである。モダンというとやや不明瞭かもしれないので、言い換えればメジャー・チャートで大成功したThe Wallflowersの2枚目アルバム「Bringin’Down The Horse」のようにアメリカン・ルーツと垢抜けたコンテンポラリーな要素が同居しているという説明をしておきたい。
SPは東海岸の中央部に位置するヴァージニア州の出身バンドであるが、この州より更に南にあるノース・キャロライナ州から排出されたバンドのHootie & The Blowfishの持つサザンロック的泥臭さと、同州出身のAthenaeumやEdwin McCainが中心にしているモダンロック的なスマートさをも共存させているバンドであるのだ。が、この後者の2バンド程には主流音楽であるオルタナティヴへの追求は聴こえてこない。
もっと垢抜けなく、スワンプロックやAmericanaのリラックスした雰囲気を感じられるバンドである。
まず#1『Greeting Card』で驚いたのは、リード・ヴォーカルがThe WallflowersのJacob Dylanにまんまではないが声質がとても似ていることであった。ハスキーな唄い回しが可能なところは相当類似している。やや深みというか落ち着きという点に関してはJacobに及ばないだろうが、高音域を喉から出すパートではDylanの息子よりも上を行くのではないかと思う。
また、とても文学青年的な暗喩的で繊細な歌詞も(聞き取りであるが)バンド名を反映した如くPoet、詩的である。
「僕のグリーティング・カードはまっさらだ。そこに君の気持ちを書き込んでくれ。」というような意味合いのラヴ・ソングだが、ストレートでいてウィットに富んでいて、更に微妙な心理の描写が青臭いけども、このアクースティックなサウンドには非常に似合っている。
無論、メロディも珠玉である。冒頭のマイルドなハーモニカのキャッチーなラインを聴いた時、思わず姿勢を正してしまったくらいに暖かくポップな曲だ。さり気なく鳴るピアノ、ナチュラルではあるが強いフックを持ったスライドギターと電気ギターの弦パート。所々で流れるハーモニカはJayhawksやBob Dylanをシンクロさせる。コーラス部の♪「Here’s My Greeting Card ,Empty」は思わず口ずさんでしまう程コマーシャルさが満載である。
#2『Crown Of Thorns』は、どこかしら錆びた匂いを運んでくるような潮風のような雰囲気のあるサザン風バラードである。激烈に感動的ではないし、ポップでもないが、やや重たいピアノを中心として淡々としたリフからグイっと力を加えてくリード・ヴォーカルのBill Gaunceの歌と演奏のダブル・フックがともすれば単なる重めのバラードで終わってしまいそうな地味な曲をポップ・ルーツバラードとして盛り上げている。#1の歌詞の後にいきなり宗教曲的色合いが濃厚なトラックが続くとは思わなかったので、その点は少々意表を付かれたが。まあ歌詞の意味を考えれば当初から予想はつけれて当然であるし、むしろ内面の葛藤を宗教寓話に仮託しているような歌でもありそうだ。
#3『All This Love』は軽快なアップテンポナンバーで、初めての速いロックナンバーであるのだが、前2曲がとてもパワフルなフックを持っているがため、すんなりと耳に入ってくる自然体なメロディが心地良い。但し、#1のように即効性を有した艶やかなポップさよりもルーツィな感覚を優先させた如きの抑えの効いた箇所を感じる曲であるため、シングルにするにはやや不足かもしれない。が、それにしてもさりげなくアレンジされたオルガンとスライドギターの乾燥した音色は爽快・痛快である。ややストレートなラヴ・ソングだけれども希望に満ちた内容と明るいメロディの一致がコトリと嵌まっている。
#4『Waiting On A Train』は5分近い、このアルバムで最長の曲となっている。まず、ハスキーさを活用して歌うBillのヴォーカルはドキリとするくらいJacob Dylanに重なる時がある。この曲のみ外部からのミュージシャン−女性コーラス隊を迎えているが、トロリと流れるオルガンやじわじわと胸に迫るように指で弾かれるローズピアノは、ゴスペルの影響が顕著なバラードとしてこの失恋ソングを成り立たせている。アクースティックギターとオルガンでさり気なくスタートするこの曲はもう少しモノトニアスなブルースバラードの体をなぞるかと思ったが、どうしてどうしてコーラス部ではしっかりと盛り上げてゴスペルの荘厳な感覚を聴かせてくれる、変化に富んだ良作に仕上がっている。
#5『Don’t Know』はこれまたオルガンとローズ風にディレイを効かせた鍵盤が印象的なサザン・スローナンバーという感じだろうか。が、曲として全体の雰囲気があまり粘っこくならないのは、彼らのカラーとして貴重かもしれない。どちらかというとBob Dylanがたまにプレイするアーバン感覚を求めたブルースっぽさがありそうに思える。
東海岸のルーツバンドというよりもアーバンポップバンドが好んで演奏しそうなミディアムナンバーが#6『Blacktop Lane』である。かなりナード感覚というか、東海岸バンドが良く披露する取り澄ましたアイロニカルなメロディが聴けるチューンである。スライドギターの音色のようにアレンジされたサンプリングとローズピアノがモダンロックとしても通用しそうな彼らの感覚を顕している。
#7『Wounded』も地味でミディアムチューンなところは前曲に近似していなくも無いが、ルーツィなハーモニカとオルガンに、ローズピアノのアンサンブルとシンプルなリズムのドラミングを聴いていると、よりAmericanaに向けた歌と思えてくる。しかし、BillのブルージーなハーモニカはHuey Lewisを想い出させる瞬間が多々ある。タイトルから想像できるだろうが、あまり明るい歌でなく、これまた作風と歌詞がマッチしている。
続く#8『Shiny Paint』も同じくサザンロック風の泥臭さと粘着力が際立った、あまりキャッチーさがないトラックである。この#6〜8がアルバムでは一番不満なところである。サザンロックというかブルースロックへの敬意を込めるのは良いのだが、前半で聴かせてくれたポップさやアクースティックさが欠如している。とはいえロックの内包する爆走感や軽快なスピーディさとも無縁の曲が3曲と続くのは少々退屈だ。しかし、♪「You’re Not Angel.I’m Not Saint.And Your Hearts Not Made Of Solid Gold It’s Just Shiny Paint.」とかなりシニカルに人間の内面を歌う歌詞は作詞家としてのBill GaunceとRobin Millerのコンビの哲学的というか文学青年的な思考が集約されているようで興味深い。
そんなこともあって、#4ととてもよく似た雰囲気を持ったルーツ・バラードである#9『So Long』を聴いた時はとても気持ちが和んだ。この曲もピアノ、オルガン、フェンダーローズ鍵盤とふんだんにキーボードサウンドが導入されている。特に間奏でのピアノとフェンダーローズの掛け合いはしっとしとした感動を覚えずにはいられない。失恋ソングというか恋を理解できない純真な男性の内面を叫んだような歌であり、情感がこもった熱い、静かな熱さが感じられるバラードである。
後半で唯一ロックンロールしているのが#10『Jurassic Park』である。とてもキャッチーで、シングルとしても切れる曲である。#1のミディアム・アップチューンと双璧のハイライト曲であることは間違いない。湿り気のあるシンセサイザーとオルガンを大胆に全面にフューチャーして疾走感をルーツというよりも華やかなポップロックの1曲としてアレンジしている。こういったところにSPの都会的なセンスも併せ持つ多彩が伺えるのだ。それにしても、またまた#8に続いて社会批判をしているユニークな詩である。ストレートでなく有名な映像作品をメタファーとしてタイトルにしているセンスもまたクレバーである。
最後の些か重苦しい南部ルーツバラードの#11『Can’t Believe』は前曲で浮き立った流れを再びルーツロックの渋さに引き戻さんがためにトラックされたような地味なサザン・バラードである。この終わり2曲の落差が、SPの音楽性の広さを表現しているのだろう。が、最後はもう少し印象に残る曲で締めた方が良いとは思う。少々トリにしては凡作であるように思えてならない。
さて、最後になるが、アメリカ東海岸のヴァージニア州で今年デヴューしたThe Stationary Poetsというバンドに関する情報はあまり手に入らない。インタヴューやレヴュー記事もいまだ収集中であるのが現状だ。
分かっているのは、10代の頃から一緒に活動しているBill Gaunce (Vocal,Guitar,Harmonica)とRobin Miller (Guitar,Keyboards)が創り上げたバンドであるということ。
他のメンバーが
Charlie Corletto (Bass) , Mike Trimble (drums) , Billy kello (Guitar,Slide Guitar)
の同州ノフォーク周辺のミュージシャンであること。このくらいである。
ヴァージニア州はあまりルーツロックの良作・好バンドが輩出されない、とルーツロックファンには言われているらしいが、このような期待の持てる新人がしっかり出てきている。さすがアメリカ。懐が広い。
東海岸のバンドにしてはサザン・ブルースロックへの傾斜がやや急に思える。#10のようにイースト・コーストならでわの垢抜けたセンスをもっと活かせば中盤で必要以上に重くならずにすんだと、繰り返すが残念である。
特に前半で展開したアクースティックでポップな感覚はとても素晴らしいので、是非こちらへと傾倒して欲しいものである。
ところで、このジャケットであるが、デザインとしては飛魚のような魚、蜻蛉か蜻蛉のような昆虫のイラストが描かれていて、デザイン的にはとても芸術性が高いと思う。
が、アンマッチというかサイケディリックともいえそうな原色系ではなく(彼ららしいといえばそうだ)くすんではいるが過多な配色で、やや分かり難いというかチープなジャケットになっているように感じる。
一色をそれぞれ個別に見てみると、とても綺麗なグラデーションがあったり、趣味の上品な色出しをしているのに。
アルバムも同じで、やや纏まりに欠けるというか、足りないものを冒頭に述べたように感じる。
まあ、次を期待したいし、十分可能な新人バンドである。
最初に挙げたアーティストが好きな方なら聴いて損はしないこと請け合いである。このアルバムもレヴューが数ヶ月遅れた。
これ以上書かないと、機会を逸しそうなので情報不十分である。これから入手できたらアップデートしたい。とは常に思っているのだが・・・・・・・。 (2001.10.20.)
 Runnin’ / Gilbertson Morgan Band (2000)
Runnin’ / Gilbertson Morgan Band (2000)
Roots ★★★★★
Pop ★★☆
Rock ★★★★☆
Southern&Blues ★★★★★
You Can Listen From Here
音楽を聴いて「シブイ」をいう表現を使用することは遍く人口に膾炙している、とまでは大仰に述べるつもりはないけれども、音楽を語る基準としてある一定の地位を築いている語句であることに異存を挟むことはないだろう。
が、渋さという概念は、所謂主観であって、各人「渋い」と感じる基準はまちまちであろう。勿論、大同小異にあらかたの人が「シブイ」という感想を有することはあるだろうが、それは本アルバムのレヴューとは関係のない論議になってしまうので、語ることはしない。
まあ、何が言いたいかというと、筆者にとってこの「Runnin’」が「渋い」アルバムという位置付けにあるということなのだが。一言で述べればとても硬派で”燻し銀”な音楽を聴かせてくれるバンドである。
音楽ファンの必須条件として欠かせないのが(そうか?そうなんか!?)巷で言う「ジャケ買い」である。著者的には、このアルバムのジャケット−何のヒネリもなく、数本のギターと共にメンバーが穏やかな表情のスナップを提示してあるだけ−は何ら躊躇無しのジャケ買い基準値クリアである。(笑)
おまけにオヤヂフェチである、これこそシブイ(違)趣味である作者的な嗜好にもがっちりフィットである。
と、これは冗談にしないことであるけど、実際に美形集団ではないが、落ち着いたルックスの伊達な中年軍団という印象はそれほど世間的感覚からズレてはいないと思う。
余談であるが、日本で初の購入者であることに喜んだPhillip Morgan氏が「For My Friend MOTO」と直筆のサインまでして戴いている。至極恐縮であるし、嬉しいことでもある。
相当世間とはかけ離れた購入基準を有する筆者には「名前買い」の悪癖もある。(良い子は真似せんといてね。人間失格電車道やし。)大抵において、”何とかBand”という名前にどうにも奇天烈な魅力を感じてしまうという些か困った性癖があることを告白しておく。何故かは自分でも分からないのだが、名前+Bandというシンプルかつ率直な命名方法に、その音楽性もきっとシンプルで率直なロックンロールを演っている筈だ、という幻想を重ねてしまうのかもしれない。
というか極個人的な趣味において「何とかBandというロックグループは格好良いのだ。」という縦割りをしてしまっているだけなのだが。また、フロントマンの個人名義のアルバムをリリースしているのに、内実はバンドライクなソングライティングやサポートを受けているといった、目立ちたがり屋の鼻持ちならさを嫌悪している感情の裏返しなのかもしれない。
が、名前買いには非常なリスクが伴うので、これまた人様にはお薦めできない。かなりスカを掴む可能性が高いからである。(つーか誰もやらんわなあ。)
兎に角、サンプルも何も聴かずに、この「Runnin’」を買ったことを言いたいだけであったりする。で、しっかりと当たったことが嬉しかったことを、ひけらかす意図もあったりする。
ついでといっては何だが、管理人の購入・評価基準である音楽性に完全に一致していないのに、かなり評価が高いという珍しいアルバムであることもこの場でまず述べておこう。
何が大事というと、”音楽は分かり易くあるべきだ”が大前提、要するにポップでコマーシャルさの無い音楽なんぞはゴミ以下でクソ未満、と公言して憚らない大アホな筆者であるが、この「Runnin’」はドキャッチーであればあるほどベタ誉めするという常なる極私的偏見判定基準から見ると、相当キャッチーさでは下位に位置する。
無論、アンコマーシャルな音楽が至高であるというリスナーや、タコUK難解ロックしか聴かない芸術性を追求したいリスナーの見地からすれば十分にポップであるかもしれない。
が、ここまで約100件のレヴューをつらつら書いてきたうち、キャッチーの度合いでは、間違いなく当レヴューHPで最低の「Raisins In The Sun」の次点順位をキープするくらいのポップさだろう。
それにしても初期のレヴューの短い(=まともな)こと、短いこと。(汗)話題休閑・・・・・・。
とはいえ、ハードロックやヘヴィメタルのストロングリフとヘヴィでノイジーな無機質なサウンドと等閑に付して良い音楽性では絶対にない。速さとヘヴィなリズムでアンメロディアスを売り物にするような似非ロック・スピリット剽窃派という感の強いHR・HMとは音楽の深みが違う。明石の砂浜とチャレンジャー海淵程の差があるだろう。
最初で言及しているようにひたすら渋いというか、一本筋の通ったサウンドを聴かせるバンドである。
つまり、Bar Band風の3コードロックよりも、よりブルースに傾倒したサザンロックの一つの完成形な音楽を演奏するバンドだと思う。
ブルージーなロック、ロッキン・ブルース、ブルースをロックで割ったような音、と言い方は様々ありそうだが、やはりDeep Southern Rockという表現が似合いそうである。またはSouthern Drivin’ Blues Bandという造語を作ってみると非常に音楽性に似合いそうである。
ハードなロック系譜のSouthern RockにもGeorgia Satellitesのようなキャッチーなドライヴ感覚を乗せたバンドもあれば、Lynyrd SkynyrdやMolly Hatchetのようなカントリーロックをベースにしてハードロックのタフネス振りを押し出したバンドもあるし、ひたすらヘヴィメタルに近いようなWatts Leftのようなハードロックバンドも存在し、一概にSouthern Rockと挙げてみても、ハード系でも少々挙げてみただけで、これだけのサウンドが思いつく。
このGilbertson Morgan Band(以下GMBまたはGM Bandとする。)は上記のどれにも当てはまらないようだ。レヴューではGeorge ThorogoodやGrand Funk Railroadを比較対象として出されているが、ブルースベースという点では確かに近似値として扱われるサウンドである。
が、やはりこの2つの大御所程はゴリゴリなロックでない、落ち着いたブルースオリエンティッドな態度が音楽性に顕れているような気がする。また、時折垣間見せるポップセンスが、とても微妙である。ThorogoodやGrand Funkよりは控え目なメロディというかポップのさじ加減は少なめである。
こう書くと、かなりアンメロディアスであるような印象を与えてしまうかもしれないが、確かに耳をそば立てる程のポップナンバーは数曲、それも他の曲との比較においてである。
が、ブルースのうねり具合と、ロックのエッジと、その両者を際立たせるが如く振りかけられた一歩引いたコマーシャルさが、やや枯れた土の匂いを嗅がせるような乾いたサウンドを下地に轢いて絶妙な均衡を保っている。
硬派なロックンロールという、一歩間違うと売れ線ポップ否定派にとられそうな表現ではあるが、実に硬派という表現が似合うのだ。単純にポップからスタンスを遠ざけて、アンキャッチーな自称芸術性溢れるマスターベーションの世界に耽溺しているようなフワフワしたバンドではないのだ、このGB Bandは。
硬派という語彙については、決して浮ついたところのないロックを、渋く地味に聴かせてくれる、といった意に解して貰えれば良いと思う。
そう、やはり渋い。堅実な演奏。よく練りこまれたアレンジ。全く斬新なアプローチはなくても、絶対に聴き飽きの訪れない深み、円熟味がある。こういった要素を渋い、硬派と呼び変えているということだ。
ややネガティヴな表現になってしまうが、頑固一徹、伝統の枠から決してはみ出ない音楽性を確固として暖めているグループとも言える。没進化な音なのだ、と断じてしまうと、あまり肯定的なニュアンスにはならないけど、それを硬派と感じられ、古臭いカビの生えたオマージュもどきの音楽でないと認められれば、彼らの筆者の中での位置付けが理解戴けるものだと考えている。
さて、全体を分厚い霧の如く覆っているブルースのテイスト満載のアルバムである本作の方向性を見せつけるようなナンバー#1『Hit The Ground』で幕を開ける。アルバムのタイトルである「Runnin’」の由来はこの曲のコーラス・パートである♪「You Hit The Ground Runnin’Just As Fast As You Can」から取られているようだ。
ミディアムにたゆたうブルースの流れに、若干ながらポップさをブレンドさせたギターがスライド・ギターが被さり、サザン・ロックの権化のようなナンバーを捻り出していく。Phillip Morganのヴォーカルも、その粘質を帯びた性質が良く曲調に合致して良いハーモニーを奏でているようだ。
続く#2『Love & Learn』は#1よりも更にスローにうねるサザンロックの典型の如きメロディに、ダート感覚のあるギターが伸び伸びと、しかしならがブルージーに絡んでいくようなナンバーである。Phillipのヴォーカルもメンバーとのコーラスワークもハーモニーを重視したやや透明感のある声を強調しており、このナンバーを泥臭いブルースだけにしない効果を発揮しているようだ。ここでも微妙なポップセンスが曲の音符の間で密やかに主張しているような、完全なブルースになっていない、普遍的なロックの要素をも感じられる。
#3『Wheels Of Thunder』はKen Gilbertsonがリードヴォーカルを担当しているようだ。やや何処かを布でくるんだような特徴のあるKenのヴォーカルは、タイプ的にはPhillipよりも空間的な拡がりはないが、ユニークな声質を有しているので、アクセントを付けるにはもってこいだろう。この#3も基本的には前2曲と同系統のミディアムスローなブルースロックである。ここまで全く類似したようなブルース系列の曲を並べておいて、どの曲もちゃんと聴けるようにしているのは大した力量である。
#4『You Should Know』はハイトーンなヴォーカルが印象的だが、これまでに一番ダークでダート感のあるヘヴィなブルースロックである。すすり泣くようなギターがオーヴァーダヴしている後半のギターソロは聴きものだ。またアクースティックなギターの音色が初めて聴けるトラックでもある。
このアルバムで最もポップでアップビートな、一番シングルヒット性のあるロックチューンが#5『Chump』である。やはりスライドギターとリズムギターが豪快にくねらされるサザン・ロックのドライヴ感をオーソドックスに表現した、軽快さとそれに伴うヘヴィなギターサウンドが売りの、彼らの基本は全く変わらないナンバーである。しかし、こういったポップロックも無難に纏めることのできるバンドなのだから、もう少しPop n’ Rockを押し出したロックアルバムにしても良かったのではないだろうかと、思う。この曲のヴォーカルはかなりハイキーな音を使っているが、誰だろうか。
続く#6『Destination』もハードロック風のギターがゴリゴリと唸る、アップテンポなロックチューンだ。前半4曲のレッド・ダート的粘っとしたブルース中心の流れに比べると、このロックなノリは非常に受け入れ易い。リードヴォーカルはかなりのタフなシャウトヴォイスを叩きつける、熱の篭った歌い方をしているが誰がリードだろうか。リズムギター担当のRandyあたりが濃厚だ。ここまで3枚のヴォーカルが入ってくるが、どのヴォーカルも地味ながら個性がそれぞれあって興味深い。しかし、このハスキーで枯れ過ぎたヴォイスは、このハードドライヴな曲には良くフィットする。
#7『Show Me』はレゲエタッチのリズムを取り入れ、それを更に南部トラッドなR&B風味を加えて歌っているやや異色なナンバーだ。ここでも乾いたギターソロとリズムギターの掛け合いは存分に発揮されている。この曲のリードヴォーカルも高い音域を使う人である。誰かがヴォーカル処理をして歌っているようには見えないので、4人ともリードが取れるのか、それとも誰かがかなりの歌い分けができるのかもしれない。
#8『Just A Little』はやや軽快なリフからスタートするが、結構うねりのある重た目のリズムがメインなるロックン・ブルースナンバーである。
#9『Go Yer Gone』も#8傾倒のロッキンブルースナンバーである。ややR&Bやレゲエの影響をビートに感じなくもないが。
スライドギターとアクースティックギターがややダークな雰囲気を出し、押さえ気味のヴォーカルも相乗的にダークなロックナンバーとしての側面を後押ししている、ハードロックナンバー#10『Come On』は相当くぐもった印象から♪「Come On Come On Come On」のシャウトのヘヴィな突出が印象的だ。
#11『Local Hero』で少々ダークでタイトな編成の曲が続いた後半を、ルーズに締めくくってこのアルバムは終了する。殆どをハーモニーヴォーカルで歌われるこのラフでリラックスしたブルージーなロックチューンは、メンバーのヴォーカルワークを統合したような感じもする。同時に感じるのは、実にクラッシックで飾らないギターの音色がどの曲でも存分に枯れて乾いて、ダークでハードな、がしかし隠し味的なポップメロディを演奏していることである。
完全なハードブルースバンドではなく、やはりポップさもあるロックなブルース色強いバンドなのだ。
さて、バンドの経歴について述べる前に、試聴リンクにジャンプした方ならお分かりだろうが、彼らは2001年を迎えるに当たり、バンド名をGilbertson Morgan BanからThe Ditch Ratsと変更している。音楽性が変わった訳でもメンバー交代があったのでもない。単純にこのアルバムが別プロジェクトであったがためのようだ。
バンドの設立者であるPhillip Morganという人は弱冠19歳でGabriel Gladstarというバンドを結成し、アトランティック・レコードと契約を交わしたという天才少年であったそうだ。このバンドはツアーバンドとして5年間活動。その間にテレビ映画の音楽をスタジオ録音して、その音楽がエミー賞にノミネートされたのが最大の功績であった。
このバンドを解散後、新しくThe Hit Bandというロックバンドを立ち上げ、Ron Woodを共同プロデューサーに迎えてアルバムを1枚リリースしているとのこと。また、この頃Phillipはコロンビア配給の映画「Just One Of The Guys」の挿入歌『Burnin』をサウンドトラックに提供している。
これらの活動を経てPhillipが現在の活動地域であるノース・ダコタ州に移り住んだのが1994年。そこで、彼はギタリストのKenny Gilbertsonと出会うことになる。1996年くらいからこの2人は曲を共同で創り、レコーディングを開始する。1997年にはThe Ditch Ratsを名乗り、地元を中心にギグを始める。二人のツインギターワークはそれ以来不変のコンビであるとか。
やがて、バンドにはKenの弟Randy Gilbertsonがリズムギターとして、Randy Shrinkがドラマー、更にベーシストとしてKelly Stoudtを加え5人編成となる。
この「Runnin’」はThe Ditch Ratsの変則プロジェクトであるそうで、名前もGilbertson Morgan Bandとして、ドラマーにJay Billot、ベースは3人のギタリストが持ちまわり録音の形態を取っている。
また新しい音源の録音に入っているそうで、試聴先でも2曲のニューマテリアルが聴ける。
それにしても、あまりキャッチーでないし、ブルースは基本的に受け付けない筆者がここまで繰り返し聴けたディープ系のSouthern Rock Bandは久方ぶりである。
やはりロックであること、ポップセンスが微妙に振りまかれていること、そして徒にブルース一直線でないために聴けているのだろう。しかし、もう少しキャッチーな#5『Chump』の如きトラックが多くても良いのではと繰り返しになるが思うのだ。 (2001.10.25.)
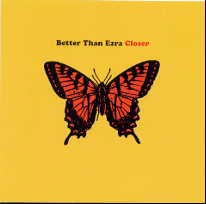 Closer / Better Than Ezra (2001)
Closer / Better Than Ezra (2001)
Alternative ★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Modern ★★★★
『Good』を聴いてBetter Than Ezraの1stアルバム「Delux」を購入した時は
「何や、この1曲だけやんか。後はダメダメっぽいなあ。どこがデラックスじゃ?凸凹ラックス(寒)の間違いとちゃうけ?」と思った。
2枚目のアルバム「Friction Baby」を何故か購入した時は、
「おお、まあ損せんで重畳、重畳。1stで見捨てなくて良かったなあ。まあ何処が凄いいうアルバムでもないし、シングルも大したものあらへんけど、トータルでバランスの良いAdult Alternative Albumとみても良いかな。」と評価を一応したが、あんまりその後聴いてない。
そして、バントとの決別を思わせた3作目である最高の駄作「How Does Your Garden Grow」が1998年に登場した。この鍋敷きにもする価値の無いアルバムを聴いた時の思いは、
「聴く価値も無いオルタナの不味いところを濃縮還元した100%ドリンクのようなアルバム。」なだけ。
くたばってしもても一向にかまへんオルタナアルバム。アメリカンロックでなく、オルタナティヴというクズに堕落。
不自然にヘヴィなアレンジ。エクスペリメンタルと呼べば格好はつくが、要するに人工的な難解なノイズやエフェクトを多用した雑音ロック。
これで完全にBeter Than Ezraとは縁が切れたものとばかり考えていた。
まず、そのグループ名が、頂けない。我が敬愛するアーネスト・ヘミングウェイ文豪の作品から、グループ名を引用しているそうだが、かの文壇の名を関するのであれば、それなりの作品を届けて欲しいものである。
この辺が名前というギミックの使いどころの難しさで、良作を出しているうちは鼻につかないことも、ひとたび評価が下落してしまうと「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」ではないけれども、余計に立腹する原因になるのだ。
まあ、尤も、この4作目を含めて、数々の文学作品を残した、BigPapa・ヘミングウェイに名前負けしていない作品は皆無であるとは思うけれど。
しかし、元来がそこそこの評価しかしていなくて、そこにつけてトドメの一撃を見舞わせてくれたようなグループの新作を買うというのは、我ながら度し難いことではある。
筆者としての購入モットーは、「一度でも良いと思わせたアーティストのアルバムは1回コケても、もう1枚は聴いてから見捨てる。」なので、今回のこの4thアルバム「Closer」を購入に踏み切った訳である。
そしてこの4枚目のアルバム(正確には5枚目)「Closer」を聴いた時、
「おお、今までのアルバムの中では一番マシ。というか初めて聴ける作品となってる。さすがインディ落ちしたことだけのはある。やはりメジャーは”氏ね”!!」
と、最後は関係ないのだか、思った。
しかしながら、手放しで賞賛に値するアルバムではないと思う。理由はなんと言うかスクラッチだ。皿だ。ターンテーブルだ。
トチ狂ったとしか思えないくらいポップな4thアルバムを今夏にリリースした「Suger Ray」もそうなのだが、何故ポップな正統派アプローチに意図を置いたアルバムに近づけようという作品を出しながら皿を回す必要があるのだろう、という疑問である。特に、Suger Rayは正式メンバーとしてバンドにいるスクラッチ・ノイズエフェクト担当の黒人がウキウキエテ吉の如く浮きまくっている。
このBetter Than Ezraを買うことにしたのは、上記の理由もあるのだが、やはりインディ落ちしたという理由も大きいのだ。ある程度、メインストリームの馘(くびき)から逃れた作品を作るには、やはりメジャーでは現在のマーケットでは難しいと思う。
が、折角(?)インディ落ちしたのに、Better Than Ezraは(以下BTE)DJ Swampとかぬかす大タコスクラッチヤーを#2『Extra Ordinary』と#6『Recgnize』に迎えて、ラップやスクラッチをミックスしているのだ。
あまつさえ、1stシングルが#2『Extra Ordinary』ということを当面知らなかったのは幸いだろう。購入前にこのトラックを聴いていたら、
「ああ、折角インディ落ちしたのに、また実験やってるやんけ、ボケ、カス、インケツ!!」
とぶった斬って購入しなかったに違いない。
まあ、大名盤以外のどのアルバムにも、殆ど捨て曲が存在するのは当然なので、ダメ曲と割り切れば良いのだろうが。
しかしながら、BTEはやはりこの良作を聴いてもこれからも100%躊躇無く買うアーティストにはやはりならない。シングルに、やはりミクスチャー系のチープな曲を持ってくることに、あからさまな流行への迎合が見られる。
ここで述べておきたいのが、所謂「売れ線」狙いと「流行への迎合」は似て非なるということだ。
「売れ線」というのは筆者的には現在売れて無い方向性であっても普遍的にポップ・ロックのステーションから常に流れている万人がラジオから流れてくることを期待している音のことである。
「流行への迎合」というのは、無理矢理、コンテンポラリーな趨勢を取り入れた唾棄すべき(売れることを求めるのは全く問題ない。それが当然の姿であるから。)態度である。
やはり、この後者をシングルに持ってきた彼らの姿勢には首が80度くらい傾く。一言でいうなら
「宴会芸で皿でも回して、酔っとれ、ボケ!!」
である。トータル的にみて「Friction Baby」の頃のシンプルなギターバンドという印象よりも、様々な楽器を使用した厚みの出てきたアルバムと賞賛しているのに、皿回し。まあ、回すのは良いだろう。これまたサウンドの多彩さを求めるアプローチの一環であろうし。曲的には悪くは無いが・・・・が、1stシングルに皿かい!!
曲的にはそこそこなので、何故スクラッチを入れるのだろうか。アルバムの流れを破壊していないだけマシだろう。
ということだ、正直なお話。ということで#2と#6に関しては言いたいことを述べた。後は賞賛タイムだ。(多分)
BTEというニュー・オリンズ出身のバンドに関しては3枚の日本盤のライナーにそこそこの経歴が書かれている筈なので、そちらを参照してもらえばよいだろう。結成の1988年からメジャーレコード・デヴューまで7年をかけている下積みの長いバンドであることは、周知の事実であろうから。また3作目の「How Does Your Garden Grow」が当然のことながら内容に比例してセールスが最低を記録し、またまたインディ落ち。
この後、自主制作した「Artifakt」というレア・トラック集をライヴ会場とインターネット販売オンリーで発売。2001年の夏に今作「Closer」をリリースに至る。
ちなみに「Artifakt」は別にレアトラックを聴くほどのバンドではないと考えているので未聴である。
まず、#1『Misunderstood』のメロトロン風(サンプリングだろうが)のリフに、今回のアルバムの、前作で見せた実験とは全く異なる、楽器を多彩にするという姿勢が伺える。やや気だるげに進行するミディアムなテンポも、どちらかというとギターロックバンドの印象が強かったBTEからすると中々にユニークである。しっかりコーラスパートでギターが”がなる”のはやはりBTEらしい。
#3のストリングスシンセも取り入れて、ドラマティックなバラードに仕上げているタイトル曲、『Closer』では、初めてBTEで鑑賞に値するバラードを聴けた気がして、これは素直に脱帽した。実にポップエモーショナルなバラードである。今年の名バラードの中に入りそうだ。少々インタープレイで冗長的であるが、それを補って余る美しいメロディがある。
#4『Rolling』は女性ヴォーカリストのToddy Waltersを迎え、大胆にピアノやストリングスを取り入れ、モータウン・ソウル風の心地良いビートナンバーとして完成させている。BTEをギターバンドとして認識しているリスナーの反発が目に見えるようだが、筆者としては無個性なオルタナ・ギターバンドに終始するよりこのようなポップな冒険は歓迎したいと思う。R&Bや60年代フィリー・ソウルの影響も感じ取れる曲になっている。
#5の『A Lifetime』もストリングスのSEから始まり、アクースティックギターとメロトロン風のアナログシンセのブワブワしたバックトラックがややリズムナンバー味を出しているミディアムナンバーだ。が、コーラス部でダイナミックにハードに盛り上げるところはなかなか緩急を突けていて、変化を楽しめるナンバーとなっている。
#7『Sincerely,Me』はパーカッシヴなスティック・パッキングからミディアムに始まるが、ポップロックの典型と言うべき、いきなりアップテンポにドライヴするロックチューンで、ここまでで漸く現れたBTEらしいというべきロックチューン。この曲がシングルになると思っていたのだが。ギターロックナンバーとして比較的ストレートなアレンジを施されたナンバーだ。
#8『Get You In』はメジャーから良い意味で脱却したとも言えるゆったりしたミディアム・ポップナンバーである。シンセアレンジや数種類の鍵盤も取り入れ、BTE得意のコーラスも上手に機能している。地味だがしっかりと聴ける曲として仕上がっている。
#9『Briefly』は冒頭からハードなギターが唸るので、てっきりオルタナ・ロックナンバーになると思いきや、意外にも淡々とコードが進行し、コーラスでガツンとロックする今作では一番多いパターンとなっている。#5と非常に良く似た展開であるが、ややこちらがシンプルだろうか。
#10『Juarez』の地味で静かなスローナンバーを経由して、ラストの曲#11『I Do』のヘヴィなリフが陰陽の対比をなすような最終2曲の構成は#11の気持ち良いロックナンバーを際立たせるには、十分効果的だ。が、このロックチューンにもミニムーグのようなチョロチョロ鳴るシンセサイザーがフューチャーされている。ここにこのアルバムのアレンジが凝縮されているような厚いロックナンバーである。
ジャケットが何とも趣味の良いのか悪いのか、判別つけ難いこの4th(5作目というべきか)は、3作目の大失敗なアプローチに懲りずに、シンセサイザー、ストリングズ、ホーンセクション、サンプリング、スクラッチというような何でも取り込んでごった煮にしたようなアルバムになっている。
それでいて、それ程散漫な感じになっていないのは、どの曲も基本となるアレンジが似ているからだろうか。
元々それほど重苦しいギターを轟かせるバンドではないが、(3rdは不必要に重いが)かなりライトに仕上がっているようだ。が、アクースティックという訳ではない。鍵盤類が相当フューチャーされているのが一番の特徴だろうし。
とはいえ、ぶ厚過ぎないのはやはり軽目な肩肘を張らせない創りの所以だろう。
ポップなメロディが息づいているからこそ、不必要な軽いアルバムにならなかったのだろう。これで3rdのようなメロディであったなら、軽いだけのエレポップとぶった斬っていたかもしれない。
全体としてキャリア的には一番のポップでコマーシャルな歌が多い良作であることは疑いないのだが、ややインパクトに欠けるアルバムであることも間違いないだろう。どことなく印象が薄いのだ、このアルバムは。
今作は印象の薄さと相まって、ロックアルバムというよりも、ギミックを多用したポップアルバムという位置付けになりそうだ。悪くないとは思う。
これを、このマイルドなアルバムを、旧来のロックバンドを至上とするファンがどう捉えるか、実に興味深いところではある。
取り敢えず、次回作が出るなら購入して聴くべし、と説得力のあるアルバムにはなっていると思う。
(2001.10.27.)

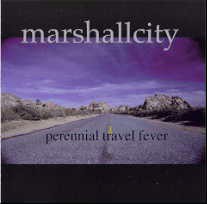 Perennial Travel Fever / Marshallcity (2001)
Perennial Travel Fever / Marshallcity (2001)