 “Stay!” / The Thousand Dollar Playboys (2001)
“Stay!” / The Thousand Dollar Playboys (2001)Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Modern ★★☆
You Can Listen From Here
 “Stay!” / The Thousand Dollar Playboys (2001)
“Stay!” / The Thousand Dollar Playboys (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Modern ★★☆
You Can Listen From Here
音楽の良さが伝わるのに、国境はない!という名言(をい)は著者の言葉であるから、別に剽窃したわけでもないが、やはり使い古された感が強いか。
確かに良いメロディを良いと感じるのは人類全体に共通する感性であるとは思う。しかしながら、極東の島国の歌い手達が世界で全く活躍できないのは英語という壁があるからだろう。歌えないことは致命的。
更に、何を歌っているか曲がりなりにも聴き取れないとリスニングも楽しさ半分になるだろう。
このThe Thousand Dollar Playboysも英語を母国語とするバンドではないが、全く問題なく英語のロックアルバムを創っている。やはり欧州のシーンは英語のポップチャートと母国語のチャートの2極化になっている構造が頷けるものである。と同時に、彼らのような良い音楽を創れるバンドは世界中で評価されるべきであるし、英語の壁がない以上、実現できる可能性は現在の市場性からは困難ではあるが、ちゃんと存在するということだ。
筆者の認識ではこのバンドは非英語圏のモノマネユニットではなく、ボーダーラインを超えたルーツポップロックバンドという集合体でのみ括られるべきバンドなのだ。
待望のセカンドアルバムが届いた。本国スゥエーデンでもまだ通販の始まっていないアルバム(2001年10月現在における)であるが、バンドの方の好意で、配給先レーベルのMassproductionを紹介して戴き、そちらへ送金して発送して頂いた。この場を借りてお礼を申し上げたい。
さて、平素からマイナーというか日本でもとことん知名度が低い音源を紹介しているが、このThe Thousand
Dollar Playboysというスカンジナヴィアのバンドは恐らく日本で誰一人としてご存知ないバンドであると推察している。 非常に残念なことであるけれど、スカンジナヴィアン・ポップは諸外国よりも遥かに優遇されている日本の音楽状況は、俗にいうスゥエディッシュ・ポップというジャンルが既にある一定のジャンルで音楽ファンに浸透し、あまつさえ日本盤も殆どタイムラグを置かずに発売されているという、追い風にあるのに、スカンジナヴィアン・ルーツロックは全く日陰者である。
反して、今年になって日本盤も出されたLast Days In April(99年にはこのバンドを知っていたのは熱心なスカンジナヴィアロックファンだけだったが)に代表されるようなエモコアと呼称されるジャンルのロックも、次第に脚光を浴びている。北欧エモ系となるだろう。
元来、英国や米国の90年代に入ってからのポップという基本を忘れた、鼻持ちならないマスターベーションの煮凝りカスであるような「芸術性」や「やりたいこと」を異様に評価する風潮がのさばり、ポップミュージックの本来有するべき、“何時でもラジオから流れてくるようなキャッチーさ”を恥じるような発言と音楽性を標榜したバンドが細胞分裂のように増殖し、ポップミュージックのコマーシャルさは追い求めることが難しくなっていた。
そういった時代にBeagle、Trampolines、Merrymakers、This Perfect Dayのようなドリーミーなポップを前向きに打ち出したスカンジナヴィアン・ポップの波は強烈に新鮮だった。Beatle Popとも現在では呼ばれて、インディで地位を固めつつあるポップミュージックをシーンに呼び戻したのは、これらのバンドの功績が全てにしてでなくても、幾らかはあったと思う。
が、やはりルーツの持つ安定感というか下半身の安定というものに、これらのバンドは正直欠けるところが感じられるのは否めない。サイケディリックな味付けを持つバンドも多く、それが英国音楽市場の隣人であるヨーロピアンポップスの特徴の一つであるのは理解もできる。
けれども、やはりポップであるならアーシーでルーツなプラスアルファが欲しいと思うのはルーツロックに脳髄まで毒されている筆者の果てることのない願望である。欧州ポップスの中でも、特にポップさでは頭一つくらい抜きん出ているスカンジナヴィアン3国のポップオリエンティッドさにロックさとアーシーさが加わったらどんなに素晴らしいだろうと妄想するのも自然であった。(チガウ)
ロックやパンクという点ではBackyard BabysやHellacoptersといった北欧爆走系のパンクロックバンドが、これまた日本では好意的に紹介されて、北欧はヘヴィメタルだけでないことも認識されてきた。
然れども、やはり爆走パンクは飽きる。底が薄い。ロックンロールではあってもリアル・ロックンロールにはなれないのが、パンクであり、ヘヴィメタルであり、ハードロックであると思う。
そのヘヴィメタルやハードロック、特にオーケストレーションやシンセサイザーをオーヴァードースしてプログレッシヴな浮遊感を持たせた北欧ヘヴィメタルに至っては、現状では独逸と並んで間違いなく唯一の活発な供給源であろうし、その他のジャンルの「北欧モノ」が膾炙してきているとはいえ、やはり北欧メタルがスカンジナヴィアの代表的な顔とみなされているのは否めない事実である。
まあ需要が日本他欧州諸国しかないのはお寒い限りであるけれど。
このようにルーツ関連のロックミュージック以外は、それなりの市場を構築したスカンジナヴィア・シーンであるが、ルーツロックのバンドが台頭してくるのは90年代の半ば過ぎ、後半からである。ロカビリーやカントリーロックバンドで80年代から活動していたインディバンドは相当数あるようだが、如何せん情報が少な過ぎてトレースは不可能に近くなっている。というか英語か独逸語でサイトやネットショップを開いてもらわないと、何が何だか分からないので、言語的にも情報のビハインドがあるのだが。
まだまだこのシーンは、マイナーオタクの筆者にとっても地図に空白が多かった19世紀の暗黒大陸阿弗利加(アフリカ)並みであるのだ。が、それでも良い音楽の発信地というのは自然に伸ばしたアンテナに引っかかるもので、1997年にアメリカのバンドとしか思えないようなサウンドを引っさげてデヴューしたThe Scarecrowsの「Waiting For Wonder」を皮切りにボチボチとカントリーロックやルーツロックのアルバムでかなりストライクゾーンを直撃するバンドが姿を現し始めた。
今や21世紀にはカントリー・ルーツミュージックのレーベルが複数存在するという静かな熾き火のようなムーヴメントが白夜の地に拡がっている訳だが、やはり先にも不満を述べたように瑞典語や諾威語のサイトがまだまだ多く、試聴も出来ないところ(というかどうやってやったら良いか分からん。)が多く、情報入手は困難を極めている。
さて、90年代半ばから興隆した北欧ルーツシーンだが、オルタナティヴバンドからスタートし2枚目のアルバムで相当ルーツロックに傾倒した作品を拵えたLoosegoats(まだまだオルタナ臭いのが困りものだが)、オルタナカントリーの基本バンドのようなElmerに、今年最高級のルーツロックアルバムを届けてくれた、当HPでも紹介しているEnzendoh、ダークなカントリーロックが渋いBen、同じレーベルのAlimony、活動なら10年以上を超える、やや古臭いルーツロックを演じるThe Refreshments(アメリカの同名バンドとは別。スゥエーデンのバンドである。)、サイケディリックやハードロックのカラーが強いRobart Johnson & Punchdrunkersというように、掘れば掘るほど結構期待のできる新人バンドや名前も聴いたことのないバンドが出てきて、筆者個人的に、相当注目しているのである。
サウンド的にも、一握りにルーツミュージックと言っても色々あるように、かなり幅広い音楽が溢れ返っている世界が見えてくる。80年代はどうやらロカビリーやカントリーのバンドが細々と活動していただけのようであるが、90年代半ばからオルタナ・カントリーやルーツロックと呼ぶに相応しい、ロックバンドが台頭してきている。
その中にはざっと名前を挙げてみたかなりレヴェルの高いバンドが多々存在する。どのバンドもアメリカンな音を出すことが特徴で、とても非英語圏のバンドとは思えないことが多い。
ElmerやEnzendohのように、相当オーソドックスな路線を進むバンドが多い中、やや異彩を放っているのが今回レヴューするThe Thousand Dollar Playboysである。
今更再確認するまでもないが、このバンドは北欧三国の真中、ゆりかごから墓場までの福祉の国、スイスほど国家方針が有名ではないが、永世中立国家のスウェーデンのロックバンドである。彼らの音は厳密に言うと純粋なというかコテコテのルーツサウンドでは枠に嵌まりきれないと表現したくなる性格がある。
無論、ルーツロックには間違いない。でなければここでトップに取り上げることはないし。(笑)
一言で言えば、多種多様・多彩、これに尽きる。
と、これでは何が何だか筆者自身でも理解できないので、ひとつ長々と解説、否解明を試みてみたい。
一口に多彩と言っても、どの辺が多彩という問題がある。メロディのヴァリエーションが多いのか、音楽性そのものが多いのか、またあれこれ取り入れようとして欲張り過ぎて、音楽性そのものが明確さを失う結果となったというようなネガティヴな結果もまた多様というマイナスの側面だろう。
勿論、このThe Thousand Dollar Playboys(以下、$1000PB)は、ネガティヴな側面を全く感じさせない多様性を有しているし、その多様さもメロディ、ジャンル、音楽性と全てに渡って発揮されているのが特別な点なのだ。
アーシーなルーツサウンドを竜骨に据えて、モダンロックの現代的なアーバンセンスを、そしてアメリカンなサウンドよりも大陸的な−大英帝国純粋ポップスに近いが−欧州ポップスの懐の深い複雑なコード進行をあちこちに散りばめた音楽性と、そして、あくまでも良心的なロックという範囲に限定してであるが、ジャンルを超越した音楽性という建築材で竣工した豪華客船のような華やかな音楽を展開する。
まあ、アメリカンルーツロックの土臭さを大元にしつつ、独自のセンスで改良を加えたルーツロックと言い換えても良いと思う。1stアルバムでもこういった、スカンジナヴィアン・ポップを大胆にカントリーロックへと融合させたアプローチが見て取れたけれども、この2ndアルバム「Stay!」ではその度合いが随分と増したように感じられる。
筆者の基本として、“脱ルーツサウンド”=“味噌汁で顔洗って出直して来い、ハゲ”であるけれども、$1000PBの
ようにしっかりとルーツロックの持つ、走り込みで鍛え上げた下半身を作ってから上半身で技を凝らしたようなバンドであれば、一もニもなく合格、合格、大合格である。
スカンジナヴィア・ポップサウンドの宿唖であったような、ポップ過ぎて飽きやすいとか、軽さがあり過ぎて聴き飽きるというような瑕疵がないのである。
残念ながら、このように安定感のあるルーツ・アクースティックサウンドを抱えているのに、やや英国的な一筋縄では通過していかないスコアを多用しているのは、勿体無い。スカンジナヴィアのポップロックバンドの嫌味なくらいになるコマーシャルさでメロディを創造しても、全然軽くならずに聴き応えがあっただろうに。正直なところ、BeagleやMerrymakersの夢心地に誘うようなポップさからはワンランクくらい落ちる。が、しかし、そのヒネリが入ったメロディが、ルーツロックのこれまたあれこれな様式を演奏する多彩と実に相性良くマッチして、忘れることの出来ないようなインパクトを与えてくれるのだ。
近い音楽性のバンドを敢えて挙げれば、今月(2001年11月)に新曲3曲を加えたキャリア初のベスト盤をリリースした、大英帝国連邦はカナダのバンドであるBarenaked Ladiesだろうか。
極端にルーツサウンドで砂塗れにならずに、大陸的拡がりとポップサウンドを武器としているところは近似しているだろう。但し、Barenaked Ladiesが真面目さの照れ隠しの様にわざとらしくコミカルな部分を、サウンドとヴィジュアルの両面で強調しているのに比較すると、この$1000PBは遥かに落ち着きがあるというか、真面目さが真面目さとして伝わってくるバンドである。敢えて、ユニークさや一捻りを掲げなくても、その余裕というか遊び心が伝わってくるのである。
遊び心については、当然不真面目な意味ではない。正確には、『様々な音楽に挑戦してみたい』という意気の表明をしつつも、『まあ、そんなに硬くならずに僕等のやり方で改良してみようか』というふてぶてしい程までに大胆なゆとりをかましている、といったところだろう。
兎に角、アメリカンルーツ、スカンジナヴィアン・ポップ、ブリットなポップセンス、アクースティックサウンド、モダンロックというようなあれもこれも取り入れているのに散漫にならずに、素晴らしいアルバムとしてがっちり固まった音世界を提示してくれるのは凄いとしか言いようがない。
このようにあれもこれもでは、どの曲も平均点以下なつまらない薄っぺらなポップロック・アルバムにしかならない危険性が十分すぎるほど付き纏うものであるけど。
このようなルーツ一辺倒でなく、地味ながら物凄いアルバムであるバンドを挙げればMr.Henryの「40 Watt Fade」が更に方向性がどこかで交わるだろう。が、この「Stay!」の方が北欧ポップスの風味を加えている分、相当煌びやかで華やかではあるけれども。しかし、その音楽性の内の深さと不可思議な中毒性は共通だ。
さて、多彩多様だけでは説明が不十分なので、全11曲について感想をのたくってみようか。
いきなりマンドリンのソロから始まる#1『Lonesome Town』のリフで、ああこのアルバムもきっとイケル、と即座に直感したものだ。それにしてもこのトラックでマンドリンを弾いているAnders Bergmanという人は相当のマルチプレイヤーである。6人という大所帯では得てして楽器が専業化するものだが、マンドリン、ボトルネックギター、ペダルスティール、というルーツ楽器に加えてリードギターも担当するしトランペット奏者としてもクレジットされている。このようなマルチプレイヤーの存在する大人数のバンドはBlue Rodeoを筆頭に、殆どが良質な音を聴かせてくれると相場が決まっているのだが、このバンドも例に漏れていない。
リードヴォーカリストのLars Bygdénの鼻の詰まったような独特のソウルフルで甘さもあるヴォーカルも健在であるし、ハモンドB3やピアノの鍵盤類もサウンドにより彩りを与えている。ミディアムなポップロックナンバーであるが、強弱はしっかり付いている。が、物凄いポップな流れに乗る!と思わせておいて、若干大陸的な捻りが随所にマイナーコードとして取り入れられていて、不可思議なポップさを際立たせている。これは1曲目から掴みはバッチリである。
そしてかなり筆者がお気に入りのナンバーが次の#2『Lay You Down』である。3人のホーンセクション−トランペット、トロンボーン、サックス−と3名の女性バックヴォーカリストをゲストに迎えて、ビッグバンドやモータウンソウルにも通じる、豪快でウネリのあるブラスロックナンバーはルーツィでありながら、モダンロックの色合いも感じさせ、更にアメリカ南部のSouthern Rockのパワーも練りこまれている、ブラスルーツロックというジャンルに入るナンバーであると思う。最近食傷気味の米国Jam Rockのように安っぽく、ただラフでスローやサッドさをダラダラと垂れ流している胸糞の悪さは全く感じられない。やはりモータウンに端を発するポップミュージックをRock’n Soulでシャープにしかも複雑に仕上げたチューンだ。
この雰囲気は更にルーズさとスピーディさが増したこのアルバムの1stシングルである#8『Got To Keep Moving』と共通したものである。#2と全く同じサポートメンバーを加えてのダイナミックなロックであるこのナンバーは相違点というとアクースティックギタリストのGotte Ringqvistが#2では演奏に正規メンバーとしては唯一参加していないが、この曲では参加しているということと、女性ヴォーカリストのJenny Gustavssonがリードヴォーカルもシャウト形式でインタープレイと後半で担当していることか。この女性ヴォーカルのソウルフルな参加はとてもインパクトが強く、アダルトロックのファンクチューンのようにも感じられる。またこのストレートなロックを根幹としてスローに変調したり大仰にメロディを盛り上げたりする箇所は初期から中期のChicagoの熱いブラスロックの魂を継承しているようだ。
更に、メンフィスソウル、Al Greenという単語が真っ先に浮かんでくるようなナンバーが#5『As The Desperation Comes』である。またもゲストミュージシャンとして#2や#8と同様の6名のフィーメール・ヴォーカル隊とブラスセクションを加えたマイルドなナンバーである。アメリカ南部のソウルミュージックのユルさと、レイドバック感覚を兼ね備えたこれまたダイナミックさと繊細さが同居したようなホーンロックンロールである。このビッグバンドや60年代カウンターカルチャーバンド風のブラスや女性コーラスを使いつつも古臭さは微塵も感じさせずに、ルーツ音楽の落ち着きだけはしっかりと抑えているところが、何ともはや不気味なくらい腰が据わった新人バンドだ。普通このような曲は若いバンドが演奏すると、若さ故力任せで牽引という動かし方が一般的であるが、そうはなっていない箇所が、このバンドを他のバンドと差別化可能な所以であろう。
兎に角、このホーンロック3曲で、この$1000PBが単なるオルタナカントリーではカテゴライズ不可能なバンドであるとはっきりする。
が、更に彼らの才能に驚くのは#3『A Very Special Christmas』である。バンドの鍵盤担当のTomas Östmanが奏でるピアノを中心に、同時にダビングしているメロトロンのストリングオリエントな美しい音色。そして、Andersのペダルスティールのノスタルジックな音を絡めて、アクースティックにそして静謐なシックさでじんわりと心を侵食されるようなバラードである。Lars Bygdénの抑制の効いたヴォーカル・パフォーマンスも極上だ。
ペダルスティールをカントリー系のヘニョヘニョした音だけで無い用途があると証明しているようなナンバーである。最早、ルーツナンバーというよりもアダルト・アーシーロックナンバーのスタンダードである。
で、またまたヴァリエーションが一体幾つあるのかと驚かせるのがタイトル曲の#4『Stay』である。ここでもAndersが大活躍をしている。彼の掻き鳴らすアーシーでサニーなマンドリンに、同じくオーヴァーダヴされたトランペットがバックでサンプリングの様に鳴っている。更にTomasのマリンバ、ドラマーのJens Höglinのティンパニが加わって、カリビアンミュージックのような南洋の大らかな雰囲気が出たナンバーである。それにマンドリンのアーシーさ、トランペットのソフトソウルといった要素が加わって、ワールドミュージック+ルーツポップという無国籍なトロリとした味わいのあるミディアムチューンとなっている。
#6『Take Me Away』は北欧音楽に共通する−それこそEuropeのTop10ヒット『Kelly』にも通じるような、感動的な哀愁が、オルタナティヴや最近の北欧ヘヴィメタルに安易に使われ過ぎる“哀愁”を、しかも本物に心の琴線を打ち切るような質感をもって、しっとりと流れてくる。ボトルネックギターの夜の音というべきほんのりとした暗さと、ノン・電気ギターのアクースティックさがとても良い働きをしてくれている。しかもアクースティックギター一辺倒のフォーク・シンプルな退屈さは存在せずに、ちゃんとピアノ・ドラム・ベースがアンサンブルを刻み、ロックナンバーとして手応え十分となっている。しかし、このようなバラードでのLars Bygdénの安定感ある声を聴いていると、彼の声質がSon VoltのJey Farrerにそっくりであることが判る。ちなみにヴォーカリストとしては、Jeyよりも彼のほうがどう聴いても上であろうことは疑い様がない。ここまでJey Farrerは歌い分けができていないし。
1stアルバムで聴くことが出来たカントリーフレイヴァー溢れるメロディが最初に飛び込んで来るのが次の#7『Borrowed Money Blues』である。これまたアップビートなバンジョーのリフで始まり、お、牧歌的と思わせておいて、コロコロと転がるホンキィ調のピアノがあちこちでトーンを高低に変えつつ自由にインプロヴィゼイションを楽しんでいるのは微笑ましい。タイトルがBluesになっているが、まさにカントリー風の出だしから、ブギウギライクなポップ・オールドブルースのような50年スタイルを思わせる極楽なビートに展開していく様は、全く脱帽である。
#9『The Mirror』はリードギターも相当な曲で担当しつつリードヴォーカルも取る、これは天才的なミュージシャンではないだろうかと予感させるLars Bygdénのギターが泥臭く自己主張するルーツロックナンバーだ。ここまででは恐らく最も基本的なAlt.Country的なチューンであるけれども、マンドリン、B3、ピアノ、そしてハープのビョンビョンと鳴る間抜けな音、というように多彩な楽器を丁寧に織り込んでいる、単純そうであるけど、聴けば聴くほど奥の深いアップテンポなミディアムルーツの傑作である。ここまで上品にアーシーさを表現できれば、土臭い音がいまいち苦手というリスナーもスカンジナヴィアン・ポップスとして喜んで聴けるだろう。
#10『The Playboy’s Theme』は彼らの文字通りなテーマソングらしいので、どのような曲かとワクワクして聴いたら、何とインストゥルメンタル・ナンバーであった。しかもゲストにアコーディオンを迎え、Lars BygdénのハーモニカやAndersのペダルスティールをフューチャーした、アーシーなライトな曲であることに更に驚く。また、ピアノの音出しをとことんお気楽にハイトーンで処理しているのも特徴的である。物凄く欧州民謡な朴訥さと明るさを匂わせるナンバーである。しかし、インスト曲を持ってくるとは、相当大胆である。
最後の#11は唯一Lars Bygdénのワンマンプレイの曲。アクースティックギター1本でしんみりと歌うフォーキィーな美しいバラードである。最後の締めには丁度良いし、ここでもアクースティックサイトで英国フォークの影響を良質に受け継いでいることが判明し、とても感動的だ。
しかし、1stアルバムの「The $1000 Playboys」もとても新人と思えないくらい多彩なアルバムであったけど、それと全く同じくらいの素晴らしい2作目が届いたのはやはり嬉しい。
さて、このバンドに付いて簡単に解説して終わりたい。結成は1996年末。ソングライターでリードヴォーカリストであり更にリードギタリストも努めるLars Bygdénが以前在籍したロックバンドのGarmarnaというユニットの盟友であったドラマーのJens HöglinとCountry Rockバンドを作ったのが母体だそうだ。
1997年には現メンバーのひとりであるアクースティックギター専任のGotte Ringqvist他、ピアニストやベーシストを加えてレコーディングを始めるが、どの欧州や国内メジャーレーベルも全く彼らの音源に興味を示さなかった。
が、音楽関係の雑誌やジャーナリストには非常に音楽性を褒め称えられ、ツアーでは結構な人気を博し、1999年まで契約は全く話も舞って来なかったが、ツアー中心の活動を続ける。
その間にメンバーも現行の体制にシフトする。
Lars Bygdén (L.Vocal,L.Guitar,Harmonica) ,Tomas Östman (Piano,Organ,Mellotron,B.Vocal)
Gotte Ringqvist (A.Guitar) ,Jens Höglin (Drums,B.Vocal),Roger Norman (Bass,Banjo)
Anders Bergman (Guitars,Mandolin,Pedal Steel,Bottleneck Guitar,Horns)
の6人編成となったバンドはローカルレーベルの特にルーツロック専門ではないMassproductionに売り込みをかけ即座に契約に成功する。このポップスやオルタナバンドにポピュラーといったアーティストを抱えるレーベルに諸手を上げて歓迎されたというのが、彼らの音楽性の普遍性というかルーツロックを基本とはしてもより広範な嗜好に対応できる柔軟性の証拠であると思う。
この1999年末にリリースされた「The $1000 Playboys」はスウェーデン国内でかなりの評価を得ることに成功し、1stシングルの『Preacher』も複数のジャンルのラジオで好調にオン・エアされたそうだ。そして2000年を彼らは国内を中心としたツアーで過ごすことになる。
その後約2年ぶりにリリースされたのが本作である。ジャケットも中国レストランを舞台にしたようなかなり洒落た写真が使用され、アルバムタイトルだけでなく、1曲ごとに中国語で漢字のタイトルもつけられているのが面白い。
何となくでしか意味がつかめないけれど。ちなみに『Stay』は「留下」、#10『The Playboy’s Theme』は「花花公子凋」と対応しているが、合ってるのか、これ?(笑)
とまれ、ルーツとモダンとポップのバランスが上手く鬩ぎ合っている。英国風のポップセンスに傾倒しているのはやや残念だけれども、やはりポップでコマーシャルさは健在。
ルーツファンだけでなく、欧州ポップスフリークにも是非聞いてもらいたい1枚である。購入したい方は管理人まで問い合わせてください。先方に紹介します。
つーか、聴け。(パターンやけどね) (2001.11.24.)
 The Real McGraw / Jim McGraw (2001)
The Real McGraw / Jim McGraw (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Southern&Country ★★★★★
You Can Listen From Here
The Real McGraw−このアルバムで、本当のJim McGrawを知ることが出来ただろうか、と自問してみた。
答えは、どうも中途半端であるけれども、知り得たようでもあり、知るには程遠いというべきでもある。これでは、書いている著者本人にも何のことやら良く分からない。一応説明というか言葉にしてみる努力は試みよう。
このアルバム「The Real McGraw」を聴けば、このJim McGrawという人がかなりの素晴らしいミュージシャンということは間違いがない。が、このスーパー●リオのような(笑)髭オヤヂの詳細について、殆どデータらしいデータがないので、彼について、彼の音楽性について断言することが不可能であるのだ。
このアルバムがデヴューアルバムの新人というなら、それは話が早いのだが、どう見ても新人という年齢ではないし、かなりの長い音楽活動をしているらしい。これも今から述べるが、乏しいデータからの推察の域を出ないものであるのだが。
僅かに公式ホームページやインタヴュー記事から、彼のこれまでの−2001年以前の活動を類推するしかないのが現状である。一応得意の「教えてくれ」メール攻撃は敢行しているのだが、色よい返事はもらえないでいる。まあ、もう一度尋ねては見るが、このままではレヴューが先に進まないので、今回敢えて筆を執った次第である。
が、リピートになるけれども、この「Real McGraw」だけに限定すれば、このJim McGrawという人がかなり筆者のツボを突きそうなミュージシャンであるとは明言できることは、記しておこう。
公式HPのキャッチコピーにはこうある。
『カントリーとロックとアメリカーナのブレンドを届けてくれるアルバムだ。Steve Earle、Bozz Scaggs、Joe Ely、
John Fogerty、Dan Cafferty、Charlie Daniels、Mark Germino、The Hooters、Wallflowers、Tom Pettyそして
John Mellencampというアーティストの音楽性を継承している。』
かなりの大風呂敷である。カントリーロックから王道アメリカンロック、オルタナカントリーにアダルト・コンテンポラリーといった広い範囲のメジャーで著名なアーティストが挙げられている。
正直間違いではないけれども、少々大袈裟ではあると思う。持ち上げ過ぎなところはまあ、宣伝上仕方ないことであるとは思うが。
が、確かに、ここへ列挙されたミュージシャンの音楽が好みならば、このアルバムを購入して後悔することは絶対にないことは間違いないだろう。これらのアーティストを凌駕する化け物のような名盤、とまでは言い切ることは提灯記事を書こうとしても、やはりそこまでは絶賛できるかというと少しばかり躊躇してしまう。
とはいえ、アーシーでポップなアメリカンロックという点では、列挙された才能ある人々やグループに十分に互する素養はある。
しかし、Americana、Rock、Countryの三大要素を標榜しているキャッチ文句を鑑みると、このアルバム「The Real McGraw」だけに限れば、決してカントリー・ミュージックではないけれども、随分カントリー・ロック寄りのアメリカンロックな音楽を彼は詰め込んだ作品になっている。
また、サンプルのみで聴くことが可能なこのアルバム以前の作品(らしい。全く注意書きがない、試聴オンリーなサイトでのリスニングに頼っての判断であることをお断りしておく。)群は相当にカントリーに両足を突っ込んだ音楽性を聴いて取れる。
The WallflowersやJohn Mellencampのようなどちらかというとロックンロール重視でカントリーの匂いが希薄なサウンドに比べると、相当にのんびりとした根アカなカントリーの音楽性が相当量感じることになるアルバムである。
とはいえ、ロックであることは間違いない。決してダスティな軽いだけのカントリーではない。
サザンロックの系譜の南部スワンプの風味も効かせたカントリーロック&アメリカーナと言うのが最も適当でないかと思う。泥臭さというよりも、スワンプ音楽の脱力感漂うリラックスさやライトな口当たりが主なサウンドなのだ。筆者が最も好む、へヴィでマッディなロックンロールとはやや趣を異にするアルバムである。マッシヴな爆走感覚よりも、牧歌的な雰囲気をロックに取り込んだ、カントリーロックである。が、カントリーロックでもロックサイドへ顔を向けている作品である。
さもなくば、聴くことはあってもレヴューには恐らく著者が取り上げることはないだろう。カントリーは相当嫌いだし、カントリーに近いカントリーロックやロカビリーも、はっきり言うと聴いていて嫌悪感すら感じることのほうが多いという、ややこしい嗜好であるからだ。
けれどもこの「The Real McGraw」という12曲入りのアルバムは、キャッチーで分かり易いという大前提を基礎として楔を打ち込みして、更にカントリーに必要以上にのめり込んでいないロックンロールとして分類できる1枚であるからして、大のお気に入りになっているのだ。
しかし、この最新アルバムについてさえ、レコーディングに関わったミュージシャンすらクレジットされていない体たらくであるため、まずはボーナストラックを含む12曲について触れてみたいと思う。
まずは、いきなりドブロギターやバンジョーらしい、幾つものルーツ楽器の土臭く垢抜けないリフからスタートする#1『The Devil’s Eyes』から、カラカラに乾燥したアレンジと、ややウエットなメロディラインが同居して、何ともいえない味わいを演出している。かなりカントリー・ロック風のファースト・ヴァースからコーラス部分に導入するところでフィドルの(サンプリングかもしれない)田園的な音色が聴こえて来る展開もなかなか、カントリー・ヒット曲のようで普通ならお気に召さないところだが、このくらいリズム・セクションとバックのエレキギターに力が入っていると、ポップロックとして聴けるので、問題ない。後ろでワウワウ・ペダルみたいなポニポニ跳ねるギターの音も耳に入ってくる。
こう考えると、どうしてどうして、単純なカントリーロック・ナンバーのように見えるけれども相当創り込んでいるようである。
オープニングのカントリー・ライクな曲から、一気にロックンロールを感じさせるのが#2『Mama Said』の泥臭く、マッチョなギターラインである。初っ端からギターがギュンギュンと鳴って、南部ロックの逞しさを予感させるが、メインパートはややレイドバックした、これまたカントリーロック調のポップロック・ソングになっている。ただ、インタープレイでのギターソロや所々でフィドルとユニゾンするエレキギターは結構派手に掻き鳴らされていて、ロックな印象を与えてくれる。 しかし、冒頭の入りからはまさかフィドルも割り込んでくる埃っぽいナンバーになるとは思いもしなかった。良い意味でお約束をはぐらかしてくれているが、お約束のままタフなルーツロックナンバーを聴きたかった気がして少しばかり残念である。
アダルト・コンテンポラリー的な大人しく、ポップなJimの一面が出ているのが、#3『Remember You』である。ややディレードを掛けたようなアクースティックギターとエレキギターのやや哀愁が感じられる音色をベースにして、低音部を上手に取り入れたピアノ・サンプリングやフィドルに限らないストリングスを同時にフューチャーしたこのナンバーはあまり埃が舞い立つようなカントリー系の調子を狂わせる脱力感を匂わせることがない。むしろ、AOR系のヴェテランシンガーがアルバムに好んでトラッキングしそうなアクースティック・バラードとして仕上げている。が、最後のフェイドアウトに向かう直前からおどろおどろしいサンプリングやギターを引っ張るようなノイズが音を立て始め、アメリカン・ゴシックのような怪奇さも思わせる。この辺は単純なアダルトロックを創りたくないという、Jimの捻くれた精神の発露かもしれない。しかし、ヴォーカリストとしてもMcGrawが秀逸な一面を覚えることの出来るナンバーである。
#4『This Side Up』は南部ロックのようなブルージーなリフでスタートするけれど、即座にルーツポップロックの素直なルーツナンバーに変調していくアップテンポ・チューンである。#2よりもギターの自己主張は少なく、カントリーロックをより髣髴とさせる、Joe Elyのような感覚に溢れているけれど、フィドルやルーツ楽器を極力使わずに、オルガンを非常に抑えて使用したアレンジで、それ程ダサくない、ルーツ&クオーター・カントリーロックの1曲という、ツールロックの良質なナンバーとなっている。メロディさえ良ければ、カントリーロックも普通のアーシーなロックナンバーもアメリカンロックの善きナンバーとなれるような代表例である。
#5『When They Dance』はThe Hootersの1993年の今のところ最後のアルバムである「Out Of Body」のオープニングナンバーであり、代表曲でもある『Twenty-Five Hours A Day』のケルティックなメロディラインを、新大陸風味に焼きなおしたような曲調が所々で聴かれる。恐らくフルート系のトラディショナル管楽器を使用しているが、聴けば聴くほど、Hootersのナンバーに似ていると感じるのは気のせいだろうか。
勿論、ホイッスルのインスト・パート以外はHootersほどロックンロールしていない、牧歌的な雰囲気の漂うトラディショナル・ロック調の明るいナンバーとして構成しているけれども。よって、全体の感じとしてはこの2曲は相当異なった作品として完成しているが、Hootersを引き合いに出される点が、何となく納得行くと考えられる。
やや、これまでのストリームから異質な、ややダークで陰鬱な南部ロックの重さを感じることの出来るナンバーが次の#6『Black Bitha』である。とことん、日の当たるお祭りライクなロックンロールという能天気さが端々に零れ出ていたこれまでの5曲とは全く方向性を異にする曲である。物凄くヘヴィではなく、ハードでもないが、頭上を覆うような暗いオルガンの音色や抑揚の少ないスコアは、南部のRed Dirtと呼ばれるような、ブルースをベースとしながらのハードなロック音楽の影を見ることになる。まあ、変化があって宜しいだろう。あまりカントリー・カントリー的な軽さが続くと飽きが来るのは間違いないので。
ダークで悲しげなナンバーの次は、再び#3に続いて、上質のバラードが聴けることとなる。#7『My Kinda Girl』は、何故かバラードになるとカントリーカラーが薄れるという、McGrawのこのアルバムの特徴を忠実になぞっている。ヴァイオリンの美しい調べとピアノ・サンプリングによる、とてもアダルトな雰囲気を持って始まるこの曲は、しばしばアーシーなボトルネックギターのチョーキングを末尾に加えて、アーシーさを出そうとしている姿勢が伺えるけれども、やはりとても感動的に展開するパワーバラード風の盛り上がりに色を添えるだけの効果をなしているだけである。もっともこのギターの泣きの音色がとても良いアクセントになっていて、曲を更に良い感じにしている。
#8『Two Fingers』は、メロディカの懐古的なリフから始まる、ミディアムな佳曲であり、その使い手の代表者たるHootersのメロディカが頭の隅にちらつく。(まあファンなので仕方がない。)が、どちらかというとVan Morrisonが好んで取り上げそうな大陸的なルーツテイストを感じさせるナンバーである。アコーディオンの音色のようなうねりも聴こえて来る、ゆったりと落ち着いて聴けるナンバーでもある。この後半戦に入ると、冒頭のカントリーロックな印象は次第に薄れていき、ルーツロックなアルバムという感想を次第に抱くようになってくる。
このナンバーもルーツロックといういよりもジャム・ロック的な柔らかいトラッド・テイストの方が目立つポップナンバーとして成立していることであるし。
続く#9『Be Like Them』もアクースティックなミディアム・バラードな曲である。フィドルや鍵盤類が、薄いようで厚めなギターとリズムセクションの間でバランスよくアレンジされている、これまたアダルト・コンテンポラリーなナンバーとなっている。ギターのメロディのフックは非常にポップスの要点を押さえていて、とても快適に聴くことができるのだ。
Bee Geesの奥行きのあるバラードを思い出させるようなナンバーである。しかし、アレンジを微妙に変えつつ、何気に多彩な楽器を持ち込んでいるのは、実に技巧というか曲の肉付けが上手なプロデューサーと組んだものだと感心してしまう。無論、Jim McGrawというシンガーの声がどのジャンルも歌えそうな即応性に富んでいるから可能なアレンジとプロデュースなのだろうけど。
終わり近くになって、漸く#1のようなアクースティックギターとドブロが、ハイトーンで活躍するナンバーが登場する。#10『How Did I Get By』は、しかしながら、カントリーロックというよりも、アクースティックをベースにしたロックンロール、そうコーラスの挿入がとても絶妙であることも効果を付与しているのだろうが、西海岸ロックという感じの爽やかで心をスカッとさせる涼風のような雰囲気を持った曲である。とてもキャッチーで、後半のクリアなギターソロやオルガンのペダルだけを使用した盛り上げ方といい、変化に溢れ、多彩で聴いていて疲れることがない。やや地味ではあるけれども、シングルにしても面白いのではないだろうか。
事実上の最後のトラック#11『Let The Party Never End』は、やや古臭いタッチのカントリー・パンクというかオールド・スクール・ロックという60年代の雰囲気がてんこ盛りのエッジの効いたロックナンバーとなっている。ややラップを掛けるようにシャウトをかまして歌うJimのヴォーカルもとてもスピーディで、まさにダンスフロアのロックンロールであるだろう。オルガンの鍵盤の乱れ撃ちやチューンを引っ掻き回す音が暴れるラストヴァースはまさに、ガキのためのロックンロールという青さまで見えてくる。
このような直球的なロックナンバーをもう少し増やせば、もっとタイトで締まりのあるロックアルバムになったのではないかと思うのだが。兎に角、アルバムの中でもお気に入りのゴキゲンなロックナンバーである。
そして、最後はボーナストラックとして付け加えられた(らしい)ライヴ録音の#12『How Lonley Will You Get』。このアクースティックな弾き語りスタイルは、勿論かなりしんみりとしてて宜しいが、是非歌詞にも耳を傾けて貰いたいナンバーでもある。かなり叙情的な詩を切々と歌い上げるJimの歌唱法はアルバムのスタジオ録音とは全く違った良さが存在する。
元々、#1や#2から、結構スポイスの効いたシニカルな詩を聴かせてくれていたが、この寂しい詩はなかなか心に入り込んでくることを避けれない魅力があるのだ。
と、ざっとこのアルバムをなぞってみたけれども、やはりカントリーロックでは一括りにできないアメリカンロックとしての幅の広さを有したアルバムであることを再認識できる。
ベースとしてはカントリーの色が、その使用楽器やアレンジからも強く感じることが出来るが、多彩な楽器に絶妙なアレンジで、より拡大した音世界を堪能することが可能である。
と、こうやって誉めたは良いのだけれども、再度述べるが、このJim McGrawというシンガーについてはこの最新アルバムにしても全くデータが揃っていないのだ。
以下は、推測も含めてインタヴューやホームページのコメントから筆者が纏め上げた情報である。よって、常よりも更に信頼性の薄いこと請け合いである。(笑)
Jim McGrawという人は、『シンガー・ソングライター』として、幾つかのメディアには紹介されているけれども、このアルバム「The Real McGraw」では1曲も曲も歌詞も筆を執っていない。これが「真の姿」であるなら、些かお粗末な気はするが・・・・。
まあ、今までの経歴が皆目分からないため、何とも判断のしようが現段階では、ない。ただ、このアルバムのクオリティの高い曲群は、Jimとパートナーであると紹介されている、John Boutkamという人が殆ど単独で書き上げているのだ。#5のケルティックな匂いのするナンバーと#6の異色なダークチューンのみBrad Essmanという人との共作となっているが、この人物が実はJim McGrawの変名であるという可能性も残っている。
それ程珍しいことではないし、シンガーが作詞の際に別名を名乗るのは。まあ、そうであって欲しいという願望も多分に含まれているのだが。
筆者は基本的に曲の書けないシンガーを評価する場合、一段下げて捉えてしまうという悪癖があるので。よってやや、Jimがクレジット上は1曲も提供していないというのは、率直には幻滅する要素となっている。まあ、アルバムの出来が良いので、そこまで評価を貶めるものではないけれども。
というか、再三の情報を請うメールを無視されている私怨も入っているので、この辺は読み飛ばして頂いて結構である。(苦笑)
楽器も一応ギターを弾くことくらいしか判明していないし、それすらどのギターがメインなのかも分からない。クレジットは一切なし。インストゥルメンタル・パフォーミングに関する記述も全く見当たらないため、担当楽器についてはこれくらいのことしか言明できないのだ。
さて、ミュージシャンとしての活動は80年代には間違いなく行っていたようである。顔から推測すると結構なオヤヂ顔であるので1970年代からインディ活動していたとしても驚くことはないけれども。
公式HPやインタヴューでもJimは散々にわたって触れているが、非常にレコードレーベルに所属するのが嫌いでたまらないそうである。彼のコメントを引用してみよう。
「私が希望に燃えた若いミュージシャンだった頃、メジャーなレコード会社が契約を幾つか申し出てきた。250ページの契約書を用意してだよ。誰がちゃんと読むというんだい。他のミュージシャン達と同じように、全く読まずに目を通した素振りだけ見せてサインしたよ。ただやりたいことは曲を書いて、弾いて、ネーチャン達を夢中にしてゲットすることしか頭にないんだからね。」
「で、契約して最初に気がつくのは、レコード会社が、僕を型にはめ込んでしまい、僕が本当に考えてる音楽を全くやらせて貰えないということだ。これは不満になるね。でも、最初の支払いがあって、纏まった金を手渡されると、ああこれも良いのかも、って思うようになる。末路はあれさ、どこでも見られるライヴ。ただ、会場に行って、客の前に出て、彼らの夢見るロックスターを演じるだけ。他人の意向に沿うだけでね。」
とJimは兎に角、レコードレーベルに対して不満遣るかたない様子である。きっと過去にトラブルが遭ったのかもしれない。
「まあ、長い話を短く纏めると、私は長い間英国やスウェーデン、オランダ、ドイツという欧州各国に居を構え、音楽活動でかなりの評価と成功を得てきた。でも、自分のステージで演奏する音楽をレコードに吹き込みたい時は、自分がどうしても演りたい音楽を録音したいときは、行き着くところはゴミタメのようなレコードレーベルしかなかった。」
と、Jim McGrawはフロリダ州はタンパ・ベイの出身で、現在の活動拠点も当地であるのだが、以前は欧州で活動していたらしい。何故に欧州へ渡ったかは、契約のゴタゴタに嫌気が指したのか、自分の音楽がシーンに受け入れらなかったか、その辺は全く不明である。兎に角、1980年代末まで、欧州を中心に活動してきたのは確かなようで、この「The Real McGraw」もアメリカ発売前に独逸や北欧で先行発売され、高い人気を博したそうだ。
Jimは更に語る。
「だから、1980年代も終わる頃、終に私は音楽産業というものに見切りをつけて、いつも常夏でビーチが近い地にでも住んで、自分を見つめなおそうと思い立ったんだ。」
実際に90年代の大半を彼は音楽シーンから遠ざかって、たまに気侭に演奏をローカルなクラブでするくらいの音楽家となっていたようである。
「だからLightning Capitol Musicから再び活動しないかというオファーがあった時は、まあ考えたけど、今は最高だね。契約書についてマネージャーと喧喧諤諤する必要もないし、お定まりのインタヴューに答える必要もないし、自分でない仮面を被ってステージに立つ必要もない。「私」でいられる時間が大半なんだ。つまりそれは音楽を演るということ。これが『The Real McGraw』−本当の私なんだ。」
結局はインディシーンでセルフリリースが盛んになってきたり、理解のあるレーベルが増えて(この辺の盛衰は激しいが)きたという、時代が彼の背中を押したのだろう。
1990年代後半はJimにとっては良き時代の到来を意味したと思う。が、本当にレーベルが嫌いだったのか、それとも契約ができない腹いせも含んでいるのかは、彼のコメントからは類推不可能のであるけど。(笑)
彼は他にも非常に辛らつなコメントを結構発しているので、言いたいことをのたくっては自爆している筆者には、かなりのシンクロニシティを感じるところがあったりする。幾つかを紹介して、終わりにしよう。
「私の音楽はロックンロールであって、真性のカントリーではないだろう、って?私にとってのカントリーというのはアメリカに住む人の魂をアクースティックで表現したものだよ。それは人民の人民による人民のための音楽に他ならない。だから私の音楽はShania Twainのとことんレコード会社の手を加えられ、音楽性よりも何枚売れたかだけを考慮して創られた、フォアグラのように太った資本家に捧げられるための金銭ネタよりも、ずっとカントリーだと思う。」
・・・・激しく同意。あんな糞のようなヴォーカルアルバムが何で1990年代最高のセールスになるのは永遠に納得がいかない。あの普通の女歌い手の何処が素晴らしいのが筆者も全くわからん。というより単なるゴミ。
「現在のカントリーミュージック界は問題だらけだね。もしナッシュヴィルあたりで人気のある“格好良い”カントリーロックをやりたくないと君が思い、実践したら、たちまちミュージシャンとしての人気はがた落ち押し、変人扱いされるだろうさ。が、それこそが、現在のムーヴメントであるCountryという名前をAmericanaという真のカントリー音楽に変える潮流なんだ。ナッシュヴィルの連中はとやかくこのAmericanaについて言うけれど、私達は本当の姿にカントリーを戻したいのさ、それがAmericanaなのさ。」
面白いAmericanaの解釈である。彼にとってカントリーとはアメリカ人たる自身が演奏したいロックそのものを指すのだろう。
なかなか、反骨精神のある人でこれからも応援したいのだが、情報くれ!!(笑)
これ以上、紹介することができん。
乏しいながら、これまでにJim McGrawがリリースした“らしい”作品が2つだけ判明している。2000年くらいに独逸オンリーで、今作のボーナスにもトラッキングされた#12が入ったライヴアルバム「“Live” How Lonley」を。更にミニアルバムかフルレングスかも判別できていないが「It’s All In The Hat」というアルバムもリリースしているらしい。
もう一度質問メールしてみるか。すっぽん並にしつこい、我ながら。(苦笑) (2001.12.10.)
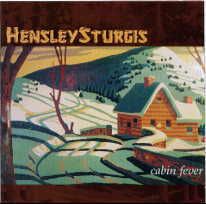 Cabin Fever / HensleySturgis (2001)
Cabin Fever / HensleySturgis (2001)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Alt.Country ★★★★
You Can Listen From Here
何となくであるけれども、この暖かい筆使いを駆使した絵画風のジャケットを見るとTom Petty And The Heartbreakersの傑作アルバム「Into The Great Wide Open」のジャケットを思い出す。この1991年の傑作アルバムもこのジャケットとは風景においてやや違うけれども、硬質な筆使いでないタッチの絵柄がジャケットに使用されている点においては共通項があると思う。
現代的なタッチの絵画であるけれども、モダンアートというような抽象性は全く見えずに、ただ、風景をその輪郭は忠実に、然れども円やかな塗りで仕上げたように思えるこのジャケットは、まさにこのバンド、HensleySturgisの音楽的位置付けを顕しているように思えるのだ。
ルーツロックという、回帰的な音楽表現をその手法としつつも、「今」である同時進行性をきっちりと内包したアップデートな印象を得ることのできる音楽。これは60〜70年代ものの、21世紀に置いては全く新しい音を創造しなくなったバンドやアーティストの「根源」音楽の意味で口端に上る、化石化したルーツ音楽とはそれ自体が含有するヴィヴィッドさ=魚のようだが鮮度と言っても良いだろう、が全くその分量において異なっている。
どれほど、新奇な創造性を取り入れていなくとも、どれほど没進化的な音楽性を根幹にしようとも、こういった現代を生きるアーティストには圧倒的な生の魅力が存在する。
技術的なことはあまり述べたくないけれども、録音技術にしても、楽器のチューニングにしても、クラッシックなルーツロックアルバムとは段違いの感情がライヴで、そのまま演奏面に移し変えられている。
やれ、リマスターだ、何Bitだと、アナログ録音を少しでもデジタルに近づけて高品質を無理矢理叩き出す必要などないのである。こういったテクニカルな面からでも、全く音の持つ質感が異なる。
この絵画ジャケットも同じように斬新な芸術性は見えてこないけども、何処となく安心できるオーソドックスさと、しかしながら埃にまみれていないコンテンポラリーな新しさも感じられるところが、相通じる要素であるだろう。
普遍的な芸術性というのだろうか、斬新な手法に依存しなくても、人々を感動させる芸術・芸能というものは必ず存在するのであるし、いかに「古典的」・「焼き直し」・「模倣」と独創性だけを強調する一派に罵られようとも、手本とした元のマテリアルをそのまま剽窃したものでなければ、それは少なくとも改良した作品という位置付けを与えられるべきである。
また、改良を超えた次元に達することができれば、それは十分に独創性がある個別の作品とみなすべきである。
概論であるが、無から有を創り出すと言うのは非常に困難なことで、はっきりと述べればほんの極少数しか達成できない偉業であると考えている。
音楽論に立ち返るが、ルーツロックのみならず、「模倣」というレッテルを貼るならば、全ては50年代のロック時代に端を発するもので、全てが“真似しい”であると極論できるかもしれない。俗に言うロック無進化論であるが。
が、筆者は始めの一歩はすべからく模倣からスタートするもので、それを元に自身の色で彩っていくものがロックだと考えている。であるから、本当に懐古的なそのアーティストのコピーに終始しているような音は、正直軽蔑する。あくまでも自分なりの手法・意欲を手本となった音楽に加味し、自分なりのカラーに仕上げていると主観的に判断すれば、それは絶対に「焼き直し」でも「発掘品の復元」でもないと思う。
とまれ、ルーツロックというフィールドでは、あくまでも現代を現在進行形で活躍するアーティストこそ光の輝きが異なると言いたいだけなのである、ここまでクドクドと述べたのは。と愚痴をたれたくなるのは、自己弁護的で恐縮であるけども仕方ないことだと考えている。
その所以は、このオハイオ州はコロンバス出身の、デュオ名義を使用するHensleySturgisという良質なルーツポップロックバンドの扱いが、本邦であまりにも冷遇されている憤りからなのだ。
当HPでもリンクしている良心的なインディレコードショップであるコンク・レコードさんで、2000年にこのHensleySturgisを仕入れた時、筆者は他の買い物のついでで恐縮だが海外通販よりも手元に来るのは早いだろうと読んでオーダーをかけた。が、最終的にかのショップで注文があり売れたのはたったの3枚だけであるそうだ。
・・・・・・・・・・・どれだけのルーツロックファンが個人輸入でこの1st作品である「Open Lane」を購入したかは想像の埒外であるけれども、ぶっちゃけた話、殆ど存在しないと思う。
日本においては、WhezeerやSaves The Dayのような明る過ぎるポップアルバムしか全く注目を集めないため、このようなルーツィでポップではあるけれども、華やかさの薄いアルバムが無視されるのは今に始まったことではないため、仕方ないことではある。が、しかしツールロック好きと自称している音楽ファンはいったい現代音楽シーンの何処を見ているのだろう。
2001年現在にもこのような良質なアメリカン・ルーツ音楽を提供してくれるバンドはゴマンと存在するのだ。それを見向きもしないファンが大半を占めるのがルーツロックのフリーク層とすれば、古い音だけを尊重する、非常にコンサヴァティヴなリスナーしか存在しないことになるのではなかろうか。
もう少し、アップデートな音を探求するくらいの熱意があっても良いものだ。リマスターアナログアイテムを探す熱意をほんの少しだけ割くだけで、その世界は果てしなく未来へと拡がるというのに。
と、あまりにも流行らないサイトの管理のストレスをしばきたおして、発散させてしまったが、実際に本音である。
このHensleySturgisくらいのバンドであれば、知名度は皆無にしても入手はそれ程困難を極めない。是非、購入して聴くべきだろう。
まずは、このバンドのツートップの名前を単純に冠したバンドについて、中心メンバーたる2名の経歴を交えて書き綴ってみよう。
バンドの創設のコンセプトである
「二人のソングライターと、二人のシンガーによるバンド。音楽産業の典型の様にリード・ヴォーカリストを中心に据えたバンドにするよりも、2人の創作を平等に反映した体制を組む。」
を具体化するために、オハイオ州の比較的大都市にあたるデイトン(仕事で2回くらい足を運んだことがあるが、地方の大きめの都市という印象で、やはりのどかだった。)出身のBarry Hensleyと、同じくオハイオ州の田舎町であるホーマー出身のJason Sturgisの、それぞれのファミリー・ネームを単純に繋げただけのバンド名を冠したルーツロック・ポップバンドである。
恐らく、2000年発売の1stアルバム「Open Lane」を購入したリスナーはBarry HensleyがBig Back Fortyというバンドの一員に加わって、1997年に発表した「Bested」関連からこのユニットにたどり着いた人が多かったのではないかと推察する。
このBig Back FortyはメジャーレーベルのPolydorが1997年に売り出したオルタナティヴとルーツロックの中間のようなバンドであった。当時音楽メディアにはWilcoの再来とか表現され持て囃されたが、大したセールスも記録せずに翌年1998年には解散している。このバンドにおいてはフロントマンはHensleyではなく、リードヴォーカリストでソングライターでもあるSean Bealであった。Hensleyは2曲でペンを取っているに過ぎない。
良く言えば中庸的、悪く言えば中途半端にルーツロックであったこのアルバムは、悪くはないが物足りないという、クロスオーヴァーを狙ったアルバムの陥り易いトラップにはまり込んだアルバムであったと思う。この手のアルバムは傑作に成ると物凄い名盤に輝く可能性もあるが、特徴がぼやけたアルバムの段階で止まってしまうことが多い。
この「Bested」は比較的良質なバンドであったのだが、惜しむらくは泥臭さを取り入れたは良いが、ポップさが足りないためオルタナティヴの尖がった側面がでしゃばり過ぎてしまった惜しい作品である。
このグループを解散した後、Hensleyは同じバンドのリズムセクションであったPatとSteveのMcGann兄弟を加えて新たなバンドを模索する。そこで意気投合したのが、同じくオハイオのインディ・シーンで活動していたJason Sturgis
であったという次第である。
Barry Hensleyはあの戦前カントリー音楽界の重鎮であったA.P.Carterの遠い親戚に当たるそうで、(A.P.の甥がBarryの祖父であるそうだ。)Barryの両親は自らの祖先のルーツを求めて南部のテネシーからオハイオへと第二次大戦後に移り住んだそうである。
この南部とアパラチア土着の音楽が一家のバックグラウンドに存在していることが、Barry Hensleyの音楽性に多大な影響を与えていると、Barry本人も語っている。
「僕がギターを弾き始めた時、南部音楽やアパラチア系の伝統音楽の要素は僕の聴いていた音楽に密接に関連していた。」
対してJason Sturgisであるが、Hensleyと出合ったのはBig Back Fortyのリズム隊であるMcGann兄弟の紹介であるそうだ。彼はこれまでのキャリアをオハイオのみで過ごしている人で、Big Red SunやTrain Meets Truckというローカルバンドの活動を経て、Big Back Fortyの全米ツアー中にBarryに紹介されたそうだ。このJason Sturgisが在籍していたというローカルバンドの音源についてはマテリアルがメディアの形で発売されているかも不明であるので、何のコメントも付することはできない。
Jasonは音楽の聴き始めは、基本的なものばかりを聴いていたらしいが、10代後半の1980年代にはミュージカルに没頭して当時のメジャーな音楽には殆ど注意を払わなかったらしい。で、90年代に入りミュージカル熱が冷めた後に聴き込んだのがGram Parsons、Robert Johnson、Steve Earle、Richard Thompsonといったアメリカンロックのアーシーな部分をメジャーで表現していた人たちであったそうだ。
この2人のルーツ嗜好が恐らくシンクロするだろうとして仲介の労を取ったMcGann兄弟の思惑は大当たりであったということになる。
1998年末に、Barry HensleyとJason Sturgisはお互いにアイディアを出しつつ曲を創り始める。この2名に加えて解散したBig Back FortyのMcGann兄弟を加えて4名体制で演奏活動を開始する。が、中々良い条件で契約のできるレーベルが見つからず、レコーディングのスケジュールは遅れるに遅れる。
アメリカ本国では遂に良いレーベルにめぐり合えなかった彼らは、独逸のインディ・ポップ&ルーツレーベルの最大大手であるBlue Rose Recordsとの契約に落ち着く。また、瑞典のレーベル、Sound Asleepのコンピレーションにも曲をチョイスされるというように、ルーツポップの主戦場がハードロックのように欧州に移行して来たことをも如実に感じさせるのだ。それはそれとして、
彼らはお互いにアドヴァイスはするけれども、冒頭のコンセプトを尊重し、2名のソングライター体制を保持していることに特徴がある。この2枚目のアルバム「Cabin Fever」のラストトラックである#13『Hazelwoody Haze』で初めてにして唯一の共作曲を発表しているが、基本はあくまでもお互いが単独で書いた曲を1枚のアルバムに入れることで作品を完成させることに主眼を置いている。
リードヴォーカルもそれぞれが創った曲を、創り手が担当するというスタイルがベースのようだ。が、2枚目においてはやや垣根を取り払い始めたようで、2人によるハーモナイズ・ヴォーカルを中心とした曲も少々聴かれるようになってきている。
ややメロディ的にはHensleyがポップさにおいて秀でていて、ロックと泥臭さではSturgisの方がこの側面を強調しているようではあるが、2者の書く歌はどちらも大差なく、ベーシックはポップでルーツでロックである。普通に耳を傾けている分には両者の書く歌の差は、お互いの声質による違いを聴き取れるくらいである。
よって、2人のライターが存在することで、物凄く多彩な曲も聴けるがバラバラな流れになっているというというプラスマイナスの両面を持つようなstyxのアルバムに感じられる、良きにつけ悪しきにつけ凸凹の音楽性は見受けられずに、無難なルーツアルバムとなっている。この無難さが評価されにくいのだろうけど。
担当楽器とバンドの今作でのラインナップは
Barry Hensley (Vocals,Guitars,Pedal Steel,Organ,Accordion,Dulcimer,Autoharp,Fiddle,Percussion)
Jason Sturgis (Vocals,Guitars,Banjo,Percussion)
Trent Arnold (Bass) , Pat McGann (Drums) , Keith Smith (Drusm)
となっており、Barryは相変わらず多様な楽器を受け持っている。「Open Lane」でベースを弾いていたSteve
Mcgannは本作ではクレジットされておらず、Pat McGannもレコーディング後はKeithに席を譲ったようである。
全体としては1作目「Open Lane」よりも相当骨が太くなった。元々HensleySturgisはBig Back Fortyで2曲しか作曲をしていないが、その2曲のポップセンスが際立っていたBarryのポップセンスを泥臭さはそのままに継承したようなサウンドが看板であった。
が、「Open Lane」では悪い意味ではないが、やや全体的に軽いというか欧州ポップス的な下半身の出来ていないランナーのような、座りの悪い便器の感触のような、微妙な物足りなさがあった。
別にギターがラウドに変身したとか、スライドがバリバリと鳴るようなアレンジを施したわけでもない。基本的には殆ど1stアルバムと変化無いのだ。確かにギターの音出しは太くなっている。それだけでは、しかしながらこうも落ち着いたルーツフレイヴァーが際立つようにはならないだろう。
兎に角、ギターが少々重くなったことと、骨太の見返りが宿命の様に若干であるけれどもポップ度が後退しただけなのだ、表現できるのは。無論、泥臭いとはいえ、上品にアーシーなバンドであり、サザンロックのベタベタな泥っぽさは当初から標榜していないバンドである。
骨太くなったとはいえ、ゴリゴリにマッチョにムキムキという意味ではなく、全体的に重厚に、落ち着いてきたということである。これは微妙なメロディの機微やコード進行、アレンジの若干の変更、2作目による余裕のような感じ、と色々な僅かな要素が複合して、音がよりルーツィになったとしか言い様が無い。
カントリーミュージック的なスカスカした筆者の苦手な軽薄さが消えてきたことが一番主要な原因であるとは思うが多分に主観的なものである。そのカントリーの代表楽器の様に捉えられているPedal Steelの名手がこのBarry Hensleyであるのだが、彼のこのバンドにおけるプレイは軽さというか、商業カントリートップ40のPVで流れるようなポロポロウエスタンの如き安っぽさとは無縁である。
が、Barryは2001年にデヴューしたロカビリー・ハードエッジとも言うべきカントリーロックバンドであるWoosley
Bandにも副業的に正式メンバーとしてPedal Steelプレイヤーの位置を得ている。このアルバムでは相当カントリー・カントリーしたプレイを披露しているのが対照的で面白くはある。
そのペダルスティールをBarryはこう語る。
「僕たちは曲を創っている時にどのくらいスティールを入れようかなと意識して考えたことが無いんだ。ただ、僕たちが新しいマテリアルを提示したとき、これはいいんじゃないかと思ったらペダルスティールをアレンジしている。それだけのことだよ。」
というように、カントリーミュージックを作ろうとせずに、このデュオはあくまでもルーツロック・ポップを創作しているのである。よってペダルスティールもロック楽器として活用されている。実際にカントリーフレイヴァーは殆ど感じないところが一番の筆者的なツボである。
とはいえ、ロックンロールというにはやや「Open Lane」よりは逞しくなったが、やはりルーツポップという呼称がより相応しいだろう、押さえの効いた速さになっていると思う。ロックの醍醐味は少々荒さに欠けて物足りないかもしれないが、この太く安定してきた音はルーツポップだけでなく明らかにロックの要素も明確になってきたようで歓迎すべき変化であると思う。
二人の作詞作曲はBarry Hensleyが#2、4、6、7、9、11の合計6曲、Jason Sturgisが#1、3、5、8、10、12のこれまた均等に6曲。で共作が最後のナンバー#13『Hazelwoody Haze』である。何と言う平等公平なデュオであることだろう。(笑)
#13はペダルスティールが埃っぽく取り入れられたカントリータッチの伺える数少ない曲であり、このアルバムのルーツィな重心の低さから言うと少々異色である。ヴォーカルもダブルハーモナイズで歌われるという、共同作業の念の入れようである。
ヴォーカルはSturgisの方がHensleyよりもシャガレたハスキーな声質を持っている。Hensleyはややハイトーンであるけれどもソウルフルさも伺えるという、ヴォーカルであるけれどもやや平凡ではある。
アルバムはSturgisの歌うミディアムでどっしりと落ち着いた#1『Heart Of The Past』で幕開けとなる。Hensleyのノスタルジックな薄霧の漂うようなべダルスティールを印象的にフューチャーしたルーツポップナンバーである。前作の軽快なオープニングトラックとは相当異なる、しっとりとしたパワフルな1曲目である。
#3『Sparks In The Dark』はリズム感のシャッフルが格好良いエッジの効かされたロックチューンであり、泥臭いギターとSturgisのしゃがれヴォーカルが非常にアーシーで良い味を醸し出している好ナンバーである。
#5『I’d Say,I’m Sorry』は何処となく夜色のイメージが漂うポップなスローナンバーであり、こういうチューンでもハスキーなSturgisの声はとてもマッチすることが良くわかる。
#8『Same Old Story』はラフ気味な泥臭いギターサウンドの緩やかなウエーヴに暖かいペダルスティールがハーモニーをつけるミディアムだが、相当パワフルでポップなルーツポップロックナンバーとして相当良い口当たりである。この辺りのオハイオ州のロックバンドに相当共通する、アーシーさとポップさのバランスの良さは特筆すべきだろう。
#12『Abandon』はこれまたスピーディなロックチューンで、バッキングされたオルガンと終始ノイジーなリズムパートで音を捻り出すギターがとても格好よいし、バタバタと鳴るドラムもいい感じであるが、殆どをダブルハーモニーヴォーカルで歌っているヴォーカルパートの分厚さが、最も際立っていると思う。ラスト前にグンと盛り上がる。
Barry Hensleyの曲はほぼ交互に配置され、#2『Which William』からスタートするが、ヘヴィなギターリフを持ってきつつもキャッチーなメロディを聴かせてくれるこのナンバーは前作ではあまり見られなかったラフさが表現されているようである。
オートハープらしきミステリアスなリフからスタートしてヘヴィでやや崩れた楽器がぶつかり合う#4『Ledge』はアルバムでも一番のハードルーツロックな曲だろう。この最初の2曲は明らかにヘヴィさが前作より増加していて、Big Back Fortyを想い起こさせるナンバーである。骨太さが増殖したと思うのはこの2曲のインプレが強いからだろう。
#6『Bottom Land』でHensleyらしい、優しげなルーツポップナンバーが始めて聴けるが、この人はここまでではSturgisよりポップな仕事をしていないように感じる。1枚目ではHensleyの書いた曲の方がキャッチーであったという感想を抱いていたのだが。しかし、この#6はポップでストレートな中庸な曲で、実にHensleyらしい。
アクースティックなバラードである#7『Sherlock』で漸く彼のスローチューンが聴けるが、次の#9ではまたも泥臭くフックの効いた『Driving Back From Dayton』となる。ミディアムスローから、変調しアップテンポで展開していくこのロックナンバーはしつこ過ぎないポップさが実に肌触りが良いというHensleySturgisの代表の如きナンバーである。盛り上がるコーラス部をハーモニーヴォーカルで処理しているところも基本的で良い。歌詞に込められた故郷への望郷の念と敬意はツアーの心境を歌ったものだろうか。
#11『The Hat Song』もルーツな土臭さが程よくミックスされたミディアム・ポップチューンであり、このような曲は地味ではあるけれども捨て曲にならないところに彼らの作品の質の高さを感じてしまうのだ。
全体として、派手さは欠けるけれども、さり気なく聴きやすいポップな世界を上手に展開しているアルバムである。全体としてやはりHensleyの曲がヘヴィにソリッドになってきて、ためにアルバム全体が締まってきたように感じる。
どの曲が飛び抜けているかと質問されると、どの曲も平均的に良い、という作品なために、シングル志向のリスナーには受けが悪いかもしれないが、反対に言えば、どの曲もシングルになれるキャッチーさがあると思う。が、大ヒットするようなコマーシャルさではなく、スマッシュヒットクラスのポップソングが多いのだが。
しかし、こういったアルバムは実に飽きが来ないで末永く聴ける魔法のような魅力がある。
この随分と男らしさを増した2枚目の「Cabin Fever」には1枚目で感じた「もどかしさ」ややや足りないものへの「いらだち」は全く無い。次作への更なる飛躍を十二分に予感させる完成度である。
それにしても1作目から1年半でこれだけのクオリティを有したアルバムを届けてくれるとは、大賞賛に値する。どこかの大物バンドの様に5年くらいに1枚しか勿体ぶって出さないような半化石バンドとは才能が異なるのだろう。
いつからメジャーな大御所は寡作が当たり前の様になってしまったのだろうか。ちっとはHensleySturgisの爪の垢でも煎じて飲んで欲しいものである。 (2001.11.26.)
 Boxfan / Steven Jackson & The Leavers (2001)
Boxfan / Steven Jackson & The Leavers (2001)
Roots ★★★★★
Pop ★★☆
Rock ★★★☆
Blues&Country ★★★★
You Can Listen From Here
“Counting Crowsのリードヴォーカリスト、Adam F.DuritzやTom Waits、そしてBruce Springsteenのヴォーカルを正統に継承する大型ヴォーカリストがフォーキィなカントリーロック・シンガーとして登場。”
このキャッチコピーだけで、1999年のSteven Jackson名義でリリースされた「Gathering Rust」を音も聴かずに購入してしまった。衝動買いである、もはや持病と変わらない。
確かに、この大地の底から湧いて出てくるような粘着力のあるしわがれた声は、Tom WaitsやAdam Duritzの悲しいくらいに悲し過ぎる感情の込められたヴォーカルを髣髴とさせる。ヴォーカルだけをピックアップすれば、このSteven Jacksonのデヴューアルバムは物凄いインパクトがあった。
メディアの表現通りに、Stevenの声がAdam DuritzやTom Waitsそのまんまはではないけれども、確かにこういった太いだけのヴァリトン・ヴォイスだけでなく、他に艶というか渋みというような得体の知れない魅力を持ったヴォーカリストに通じる才能は、明確に感じることができる。
Tom Waitsほどガラガラの酒焼け声ではなく、Bruce Springsteenのように少々力任せのシャウトがクドくなるまでにも至っていない。やはり筆者の1990年代最高のヴォーカリストであるAdam F.Duritzの、古びたハモンドオルガンの如く裏声気味に夜の向こう側から忍び寄ってくるような侘び錆びのある(寂びでもあるかな)声だ。
このSteven Jacksonのヴォーカルを聴くだけでもこのアルバムを手に取る価値は十分にあると考えている。特に引き合いに出されているヴォーカリストが好きな趣味の持ち主なら、100%外れることは無いと思う。
但し、上に貼った試聴サイトへのリンクで飛べる先は1stアルバムの「Gathering Rust」しか聴けないのである。でもって、一度聴いていただけると分かるだろうとは推量しているが、ロックンロールを歌っていたヴォーカリストではなかった、彼の1枚目の作品においては。
フォークロックというよりも、アクースティックなブルースカラーの入ったアルバムであった。全編を通じで殆どが静謐なアクースティックギターに、南部ロックの重たく野暮ったい音色を重ねたアルバムであったのだ。
基本的にロックンロールが大好物というか、それ無しにはいられない筆者にとっては、じっくりと目を閉じて聴けるアルバムというよりは、あまりにもスローでフォーキィが突出したやや退屈なアルバムという印象が第一であった。この2枚目を聴き込むにあたって、もう一度1stアルバムを聴き直してみたけれども、やはりアクースティックなスローブルースというイメージが先行してしまい、悪くは無いがリピート性は少ないアルバムであるという評価は上昇しないで終わってしまっている。
なまじ、声がソウルフルで感情に溢れているが所以で、アクースティックなアルバムであったのに、爽やかさは全く感じることができなく、重苦しさ−ポジティヴに言い換えればブルージーな安定感だろう−が際立ったアルバムであったのだ。
渋いアクースティックで南部系の泥っぽい重さが好物のリスナーにはたまらないAcoustic Alternativeアルバムであったかもしれないが、筆者的には枯れ過ぎていて、しかもロックンロールではないのにべったりとした粘つきのある声が浮き出てしまい、少々方向性を間違えてしまっているとまでは批判しないが、舵を取る舵手さえ優れていればきっとかなりのロックソングも歌える男であるのに、非常に勿体無いと感じたものだ。
その物足りなさを感じたまま、今年2001年9月に今作「Boxfan」がリリースされたと聞くに及んだ時は、正直購入を迷ってしまった。アクースティックなアルバムである1stの如き作品ではきっと大したことがないだろうと、色眼鏡で見ていたからである。
しかし、「ロックンロールの度合いが増した。」との一行であっさり転んでしまった。(笑)
通して全12曲を聴いてみると、ロックンロール系のトラックが確かにかなりの割合で聴けるようになってきているので、殆どアクースティックギターメインで紡がれていたデヴュー作と比べると相当にロックに転じているのが対照として分かる。
が、必要以上にエレキギターが自己主張しまくるナンバーが多いという印象は殆ど無く、基本はアクースティックなサウンドであるように思えてしまう。結構直球的な骨太のロックンロール・チューンが増えているのにだ。
それは、アメリカンカントリーというよりもアメリカン・トレディショナルの陰影を引き摺った感覚が漂っているためであるからだろう。いずれにせよ1stとはうって変わったロック色の強いアルバムである。相対的な意味でもあるけれど、普通のルーツロックアルバムと比較してもハードではないが、ロックンロールの重みはしっかりと伝わってくる。
しかし、ロックとしての重量感の裏側には、ロカビリー、ブルーグラス、フォーク、ブルースといった伝統音楽の影響が色濃く、ロックな曲にしろ、アクースティックな静かなタイプの曲にも共通して流れている。
ただ、アクースティックとはいえ、繊細さよりも感情のたっぷりと満ちた叙情性を感じさせる曲が多く、その原因は彼の太く声量の豊かなヴォーカルパフォーマンスに起因するところが大だろう。
本国のメディアにはAcoustic Americanaと呼ばれているらしい。
元来、Americanaというジャンルは『単純に(というよりも安っぽくか)“カントリー”と分類されることを嫌ったアーティストやルーツ音楽の業界が使い始めたジャンル分けに当てはめらた語彙・分類。』と筆者は解釈している。語学的には、アメリカの風物詩や諸事情・物語とった意味合いに捉えられる。
元来の意味からも、伝統的な伝承を念頭に置いた、現代性のある事象を指し示すものと解釈ができそうで、確かに単なるCountry Musicと大鉈で選り分けられるよりも余程理にかなった分類用語であると思う。
全くモダンロックやアーバンなコンテンポラリーなセンスからは遠い位置にあるアルバムなのに、それほど古臭さを鼻につかせない現代性があるからだろう。
余談であるが、著者はAmericanaをAlt.Country程には現代性がないけれど、Countryの枠に収まらないルーツロックを特徴分けとして使用している。正直、カントリーという音楽ジャンルは相当嫌いなのである。こんなHPを管理していてよく言えた科白であるとは思うのだが。
横道に逸れるのはここまでにして、今回は初めのうちにこのSteven Jacksonというヴォーカリストについて説明をしておこう。
このかなりヴェテランの風格さえ漂わせるアダルトというかオヤヂヴォイスの持ち主は、アメリカ東南部のアラバマ州出身である。歌だけ聴くと40歳と嘘をつかれても信じられるくらいの年季の入った声であるけれども、2001年の末でまだ25歳の若手ヴォーカリスト&シンガー・ソング・ライターである。
1stアルバムをリリースしたのが1999年のであるが、当時彼は22歳であったことになる。相当に枯れた趣味と喉の持ち主であることだけは、実際問題として疑う余地はなさそうだ。
メディアには「彼の音楽はまるで年若いSpringsteenのようで、また書く歌はBossが100歳まで生きた時のようなものだ。」
というような例えで賞賛されている。余分な飾り付けをせずに、カントリー系の音が聴こえるところは初期のBruce Springsteenにシンクロするところがなきにしもあらずとは思う。しかし、“Bossのような音楽”と言われるSteven
Jacksonは自身の音楽キャリアにおいて、全くSpringsteenの影響は受けていないと明確に言い放つ。
「僕は自動車を運転したいな、って考えるようになる年齢になる前から、バーでパンクロックを演奏していた。」
と、彼は自分のロックンロールな表現をパンクミュージックをルーツにすると捉えている。彼の影響を受けたのはもっとクラッシックなカントリー音楽であったようだ。
「僕はトレディショナルに影響されたソングライターから吸収したものが多いんじゃないかな。僕は両親の運転するビュイックの後部座席で、親父やお袋の聴いている楽しいカントリー・ソングを、真剣に気合を入れてディープに歌ったものさ。そういった子供時代を経て、僕はSex PistolsやRamonesといったパンクにハマったんだ。
けれど僕は嘗て乗用車の中で聴いた幾つかの絶対に歌を忘れられない。
その人たちは今でもラジオで聴けるさ。Willie Nelson、Don WilliamsそしてPatsy Clineというシンガーだよ。」
どうやら、Jacksonのルーツはカントリー・ソングであり、それをパンクロックと混ぜ合わせて自分のものにしているらしいことが伺える。が、そうであれば、彼の創る音はJason And The Schorchersのようなカウ・パンキッシュなものになっていそうだけれど、このカントリー・パンクの代表のようなゴリゴリのロックサウンドはとんと聴くことは無い。
彼のキャリアにはまだ付け加える音楽性があるのだ。カレッジ時代のStevenはパワー・ポップバンドやサイケディリックロック、そしてソウル系のバンドと、殆ど節操無しに音楽の垣根を超えてプレイをしたそうである。まあ、柔軟なトライアル精神と好意的に解釈すべきである。何故なら、こういった積み重ねが彼の音楽性になっているのだから。
この4年間で彼は自らのルーツであるトレディショナルな音楽に立ち返ったサウンドこそ、自らが求めるものと原点に返ったような結論を得る。
自分のサウンドをAcoustic Americanaと呼び始めたのはStevenが最初のようである。確かにデヴューアルバムはアクースティックな側面と伝統音楽の側面はしっかりと刻まれた1枚であったと思う。が、パンクやその他のロック音楽に手を染めて模索したロックサウンドを彼が積極的に取り入れるのは今作「Boxfan」まで忍耐強く待つ必要があったようだ。
間違いなく、雑多なロックミュージックを聴いて、彼なりに消化された要素はRoots Rockとして開花しているから。 Steven Jacksonはこう語る。
「歌は物語さ。歌は人々や風土の物語なんだ。僕が唄う歌は、そのうちの幾つかは僕が知っていることであり、また幾つかは僕が本当と思い込んでいるでっちあげた幻想なんだ。それは故郷のことであり、放浪することについて。それは宗教と無宗教について。それはアメリカの音楽。そして僕の歌はブルースやブルーグラスやフォークやロックといったアメリカのカントリー(国土)の音楽に触発されて出来上がっているんだ。」
こういったコメントを聴くにつけ、彼はどこかの田舎で今日もギターを爪弾き、声を張り上げているようなオン・ザ・ロードの埃まみれの風が似合うシンガーといったイメージが浮かんでくるのだ。
スポットライトを浴びて大きなアリーナに立つよりも、場末の紫煙とバーボンの匂いがたち込めるバーの片隅で熱唱するライヴ・パフォーマンスが絶対に似合いそうな、良い意味でのインディ・アーティストの素朴さをまだしっかりと抱えている人のように思えるのだ。Bossのように大スターとなり、何をやっても「Bossだから」というフィルターを通して見られることの無い、純粋な評価で彼の音楽はまだまだ語ることができそうだ。
つまり、まだ等身大な距離にあるミュージシャンということだろうか。それともまだアーティストとして未完成な部分が多い故の“青さ”が上手にかなり稀なヴォーカルとしての力量に彩りを添えているためだろうか。
どちらにせよ、ルーツ・インディという単語の代表のようなヴォーカリストという印象は変わらないが。
さて、前作のソロ名義から& The Leaversとバンドライクな付加のネーミングをされた「Boxfan」であるが、確かにバンドアンサンブルの作品である。まあ、アクースティック1本槍だったデヴュー盤と比較すれば当然であるけれども。
Steven Jacksonはリードヴォーカルとアクースティック&エレクトリック・ギターにハーモニカを担当している。
対してThe Leaversはクレジットの上に注意書きがあるけれど、「常に出て行ったりチェンジしている」の言葉通りに、このレコーディングに関わった全てのミュージシャンの名義となっている。
Chad Barger (Organ,Piano) , Gabe Fonorow (Upright Bass) , Steve Graham (Bass,B.Vocal)
Darcy Harwood (Cello) , Rob Seals (Guitars,Dobro,B.Vocals) , Eddie Walker (Drums)
出たり入ったりと銘打っている割には殆ど固定メンバーに近い編成ではある。一部の楽器を除いてであるが。
このメンツは結構渋い仕事をしているセッションマンが多く、ドラマーのEddie WalkerはMitch Easterを始め、数多くのオルタナティヴからオルタナカントリーやトラッドロックのインディバンドでマルチプレイヤー振りを発揮している人であるし、キーボーディストのChad Bargerはルーツ系のインディバンドCravin’Melonのアルバムに参加。ベーシストのSteve GrahamはBen FoldsがBen Folds Fiveを組む前に結成していたガレージポップユニットのEvan Olsonと付き合いが長いミュージシャンだ。
そしてやはり特筆はプロデューサーも兼務している、Rob Sealsだろう。自分も2000年にポップでアクースティックなアルバム「Revolution Of One」をリリースしてPaul Simonの後継者とかと呼ばれたテネシー出身のミュージシャンである。アクースティックという面からはStevenとハーモナイズする要素が大きいが、ポップだけを取ればRobの方が遥かにコマーシャルである。
今回のアルバムがロックでポップに仕上がったのはRobの仕事も貢献しているようだ。
このような腕の確かなセッションミュージシャンによって作られたサウンドはかなりがっちりとしていて、隙の無い演奏を安心感をもって聴かせてくれる。少なくともインパクトの強いStevenのヴォーカルに演奏が及び腰のような力負けしていることはない。
全12曲で、大半が4分を超える長目の曲が多いのが特徴といえば、特徴なこの「Boxfan」はStevenの振り回すハーモニカのリフから突入するサザンロック風のヘヴィなフィーリングの溢れる#1『Leavers & The Leftbehinds』から始まる。なかなか埃っぽい、グルーヴィなリズムが軽快さと重さの両方を演出するロックナンバーであり、出だしからロックのパワーが全開である。コーラスでファルセットを早くも披露するStevenのヴォーカルはかなり説得力のある存在だ。
#2『Down Sycamore』はオルガンをくど過ぎず、小さ過ぎずにフューチャーしたネバネバとした南部ロックの感性をふんだんに盛り込んだ、軽めのロッキンブルースというようなナンバーだろう。結構ビートを変えながら、時にはアクースティックに時にはノイジーに移るメロディは結構手が込んでいる気がする。反して物凄いシンプルさも感じるので不思議ではある。Counting Crowsならもう少しポップにアーバン風に仕上げそうなロックチューンである。
Tom Waitsが唄っても全く違和感がなさそうなのが、#3『Used To Know』だ。1stを思い出させるアクースティックなサウンドを根幹に据えて、オルガンとパーカッションが程よい厚さのアレンジを施した、やや黄昏たすろナンバーである。しかし、こういったナンバーでの粘っこいStevenのヴォーカルは物凄く濃いけれど実にハマりである。
Steveがエフェクトを通したように、くぐもったアナログラジオから流れてくるようなヴォーカルアレンジで唄う、結構異色なスタイルの曲が#4『If This Was A Western』はまさにウェスタン・カントリータッチの故意に古臭さを創造した曲である。これはStevenの原点であるカントリーシンガーが歌いそうなナンバーである。いまいち好きになれない、カントリーは嫌いな方なので。#6『Moline』もRob Seanが弾くダサいドブロギターを絡めた、これはブルーグラス風のレイドバックソングであるけれども、こちらは牧歌的な味わいとそこはかとない哀愁が漂っていて、悪くないナンバーであるのだが。
タイトル曲のバラード#5『Boxfan』はアーシーなギターが印象的なしっとりした曲調であるが、StevenのヴォーカルとRob Seanが弾く感情の篭ったギターソロが、結構メリハリのあるバラードとしてパワフルな印象も与えてくれる。#3よりも一層エモーショナルなStevenのヴォーカルは、兎に角聴いてもらうのが一番なのだが。やはり彼はバラードもソウルフルなロックチューンも歌いこなせる人だと確認できる。
#7『Changes』はここまでで、最もキャッチーでしかもロックなノリのギターリフから始まるポップロックナンバーである。このアルバムの中ではかなりライトなタッチの曲であり、Robのザクザクと刻む気持ち良いギターとStevenのアクースティックギターのリズムの掛け合いがリズムに乗っていて気持ち良い。地味であるが、サウンドに厚みを与えているChadのオルガンも忘れてはならないだろう。ヒット性という点ではアルバムでも1番のルーツロックナンバーであると思う。
#8『No Quitter』はノンドラム・ノンベースで浮遊感のあるオルガンをバックに、静かにエレキギターとアクースティックギターがすすり泣く、静かなスローナンバーである。地味だけれども悪くは無い。同様にノンドラムでチェロをフューチャーした#10『Carrnival』もややアダルトロックな雰囲気がある。何処までも余韻を残すような尾の引き方をするStevenのヴォーカルはストリングスアレンジにもマッチするのだ。
前曲とは対照的な泥臭いギターとパワフルなStevenのヴォーカルが静と動のコントラストを強調する#9『Say I Have A Lifetime』はこれまたサザンロックのラフな部分が伺えるナンバーとなっている。こういった重いヘヴィなギターが活躍する曲では、ヴォーカルの熱さも加わって更に熱気が増す感じが強い。同じソウルフルな新人ヴォーカリストは2001年に結構聴いてきたが、あまり明るさが無いのに暗くも聴こえないという、摩訶不思議な声をこの男は持っていると思う。
#11『El Dorade』はサンプリング・ノイズを冒頭に1分間ほど流すことから始まる、このアクースティックなアルバムにしては異質な曲である。本編に入ると、テキサスというかラテン系の民族音楽のリズムとメロディがタイトルの如くに調子を刻むナンバーである。ウッドベースのソロも入り、ラテンな影響も随所で耳に入るワールドミュージック風なナンバーといえる。
そして、何時か来るだろうと期待して、やっと届いた美しいピアノをトラッキングしたアクースティックなバラードが最後になって満を持したかのようの登場する。#12『At The Other End』ではStevenのアクースティックギターが、かなり力を加減したStevenのライトな歌唱法と共にじんわりと流れていき、ピアノが遠くでリリカルな音色を響かせている。
そういった流れから徐々に盛り上がり、後半のインストゥルメント・パートでブルースハープとドラムが感動的にピアノとのアンサンブルを僅か30秒ほど聴かせてくれる箇所はお約束ながら、郷愁を感じえずにいられない。
このアルバムの12曲では一番Steven Jacksonの魅力と力量が地味ながら滲み出てくるナンバーであると絶賛している。
しかし、この声、この枯れたメロディを創る男がまだ25歳とは。これからどのような渋く、夕暮れのような寂びた感じの音楽を聴かせてくれるのだろうかと期待するし、ロックンロールサイドとしてガンガンと心を直撃する熱い歌唱も当時に楽しみである。
まだ未完成な部分というか足りないところは存在する作品ではあるけれども、聴き応えは満点である。
ソウルフルなヴォーカリストが大好きな人には諸手を上げてお薦めしたい、大型ヴォーカリストのカントリーやサザンフィーリングに溢れたアルバムである。メディアにSteve Earleと比較されるのも頷けるだろう、一度彼の曲を聴いたらであるけれども。 (2001.11.30.)
 Real Men Cry / Lost Dogs (2001)
Real Men Cry / Lost Dogs (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Alt.Country&Gospel ★★★★
You Can Listen From Here
This Review Dedicated To The Talented Airtist , Mr.Gene Eugene.
このレヴューを殆ど仕上げて、さあアップ前に一息(面倒くさいので校正など殆どやらない。後で気が付いて、ちょくちょく手直しはするが。)というところで、George Harrisonの訃報が飛び込んできた。全くの青天の霹靂という訳ではなかった。もう余命幾ばくもないだろうという話はそこかしこで聞いていたからだ。
しかしながら、いくら事前に彼が亡くなるかもしれないと認識していたとはいえ、やはり喪失感の大きさは避けられない。で、改めて思ったことが、どの程度社会的な地位を築いていたかで、また名声や評価といった賞賛を得ていたかで、一人の人間の死はここまで他人に影響を与えるのだろうか、ということだ。
早く他界してしまえば、殊にアーティストというものは伝説化しやすい。神格化、でも適切な表現だろう。特に絶頂の時期に亡くなったクリエイターというのは、音楽家に限らず評価が高くなる傾向にある。
それは当然で、それ以降世に出したかもしれない駄作も、陥ったかもしれない不振にも、迎えたかもしれない才能の枯渇にも無縁であるからだ。時間が止まってしまった創作活動は、得てして「きっと迎えることができたであろう傑作や才能の輝き」という仮定のフィルターでしか見れなくなる。
その「死」による伝説化・神格化に対しては、筆者的にはどうでも良いと思う。というと語弊があるだろうから言い換えれば、確かに才能があった芸術家はそのように伝説化されることが宿命的な部分もあり、死後の有名税でもあると感じているからだ。だから正直、「ああ、生きていればきっと・・・・・」と思うことは多々ある。
反対に才能を大して感じられないのに「死」によって過大に評価される人物に対しては、「フン、馬脚を現す前に創作活動が終わってしまって良かったんちゃうかね、その本人には。」と些か不誠実な感慨を持つことが多い。
具体的にはどうこう言うつもりはないが、死後「神様」となれるのは、やはり一握りの著名なアーティストだけなのだなあ、という事実を今回の偉大なロック界の先達の、惜しまれる死を目の前にして深く考えてしまった。
というのは、才能があっても世間的な評価を得る前に、また正当な喝采を受ける前に、この世から去っていった人が、どれほど存在したかと考えると、もう完全に暗数の部分であり全く数えることができないからだ。
筆者が知らない世に出なかった才能の持ち主はそれこそ星の数ほど、過去にも現在にも、そして未来にも時空列の垣根を越えて存在するだろうし、逐一そういうことを考え出すと、もう何処までも止まらない「仮定」の話になってしまうので、これ以上はこの点について踏み込んで語ることを止めておく。寡聞な著者の知りえる範囲で、才能を広く認知されずドロップアウトし、シーンから消えていったミュージシャンだけでも相当な数に上るのだから。
しかし、シーンから消えるというのはまだ良いほうなのだろう。死去によって永遠にそのアーティストの仕事を楽しむことが不可能になる訳ではないのだから。
やはり、筆者は死去によって神様に昇格し、崇められるよりも、生きていて創作活動を続けてくれる方が良い。たとえ才能が枯渇して駄作を続けようが、方向性を誤って迷走しようが、である。(まあ、感情的にそうとも言えない憤りを持つことは多々あるけれども。)
少々、George Harrisonの死という衝撃があったため、かなり前置きが長くなってしまったが、今回紹介するLost Dogsにも、全く世間的には事件とならなかったけれども、メンバーの死去という悲劇を経験しているのである。しかも、今作「Real Men Cry」はそのグループのメンバーの一人を失った後にリリースされた最初のアルバムなのである。
このことを勘案して聴くと、特別フィルターをかけて聴いてくれという訳ではないけれども、また歌詞や歌に幾ばくかの深みを感じられるかもしれない。
2000年3月20日、Lost Dogsのリード・シンガー、ソングライター、プロデューサー、エンジニアそしてキーボードプレイヤーのGene Eugeneがカリフォルニアはオレンジ・カウンティ(県や郡と考えて頂けると良いだろう。)の自宅で床に倒れたまま息を引き取っているのが、Geneの友人によって発見された。
38歳になる、この多彩なキーボードプレイヤーは、特にアルコールに溺れていた訳でもなく、麻薬に耽溺していた訳でもなかった。
近しい友人によると、Geneは頓死する数週間前から、体調の不良を訴えていたらしい。また急逝する前日は頭痛を感じていたらしいが、本人にも自覚症状がなかったのだろう、それ程酷い症状ではなかったのかもしれない。が、休日明けの月曜日に、巖全たる事実として、Gene Eugeneは唐突にしてこの世を去ってしまった。
この訃報に対して、Geneの所属していたレコードレーベルには400通を超える弔問のEメールが殺到したそうである。が、このGene Eugeneという鍵盤プレイヤー兼ヴォーカリストの死に注目したのは、日本では恐らく筆者だけであったに違いない。
死者に等級を付けるつもりはないが、George Harrisonの病死と比べると実に寒々しい限りである。
才能に関しては、主観的な問題であるので比較をするつもりもないけれど、ひとこと言いたいのは、Geneはもっと惜しまれ、悲しまれてしかるべき才能の持ち主であった。あるべきである。ギタリスト等に比べると少数派のキーボード・ロック・ミュージシャンであったことを勘案しても、とても貴重な人材であり、真に残念な悲劇であったとしか述べようがない。
こじつけがましいけれども、折りしも他界したGeorgeがスーパー・プロジェクトであるTraveling Wilburysの一員であった経験があるが、Gene Eugeneが所属していたこのバンドLost Dogsもスーパー・グループなのである。
このLost Dogsはクリスチャン・ミュージックという、所謂宗教曲畑のバンドなのである。このクリスチャン・ミュージックというのは無宗教では世界一の日本では非常に馴染みの薄いジャンルであろう。まず、聴き取りの可否の問題が大前提としてあるし、また歌詞の内容にシンパシィを覚えられるかということが、次なる関門として控えているからである。
まあ、宗教音楽というと賛美歌・美麗なコーラス・・・・・少々俗っぽくヒット映画の「Sister Act」(邦題:天使にラヴソングを)というイメージであろうか、一般に宗教音楽というと。まあ、かなり唐竹割りした分類であるけれども、あながち間違いではあるまい。
実際、熱心なロックファンでなければ、クリスチャン・ミュージックに対しては殆ど知識がないだろうし、まあ当然でもあると思う。 また日本で認識されているクリスチャン・ミュージックといえば、“ゴスペル”という答えが返れば非常に上等な部類に入ると思う。そこで簡単にクリスチャン・ロックミュージックの流れを追ってみよう。
前提として、厳粛であると然るべき宗教というものは「ロックンロール」を害悪な世俗の卑しさを代表するものと敵視する風潮は、所謂ロック時代に突入してから、クリスチャンロックというジャンルが定着した現在でも毅然として存在する概念である。
ために1970年代後半までは、一切のポピュラー・ミュージックというものが宗教音楽にはタブーという暗黙の了解があったらしい。宗教曲系のゴスペルラジオ局でも徹底的に商業娯楽音楽−彼らの言うところの−はオン・エアを避けていたそうである。
が、1980年代に入り、時代の波なのだろうか、「要はメッセージを聴かせる事だ」の考えが若いゴスペル・フィールドのミュージシャンの中に台頭してくる。やはり華やかなMTV時代の到来に、依然としてコンサーバティヴな教会音楽を歌うのに我慢できなくなるのは当然だったかもしれない。
で、彼らは宗教曲を、俗に言う聴き易い“売れ線”のメロディに載せて歌い始めるのだ。この変革には未だ賛否両論あるようであるが、少なくともロックで宗教メッセージを伝えるという手法は、市場性を獲得する。それが、ポップでアダルトな曲調の故であったか、リスナーの信心深さに由来するものであったかは、判断は読んで頂いている方々にお任せしよう。
1980年代から台頭した、クリスチャン・ロックの中心となったのは当時、チャートのメインストリームであった産業ロックであり、またリスナー層の幅を考慮したのかAOR系の音楽性が殆どであった。流麗なシンセサイザーやストリングスを取り入れたストレートな産業ロックは、クリスチャン・ロックとしての地位を確固たる物にする。
さらに1980年代の後半には、当節流行のLAメタルというポップなライト感覚のメタルミュージックとも良い相性を示して、クリスチャン・メタル、クリスチャン・ハードロックというジャンルが最も中心となる。これまた悪魔や髑髏、排泄物を標榜し、絶望的なノイズをがなるデスやスラッシュメタルとは異なり、あくまでも「神」「主」をメインにした美しいドラマティックな、現在まで続く北欧ロック系の音が多かった。
同時にこれまたメジャー・チャートの中心となりつつあった女性ヴォーカルにゴスペル関係から転進する組が出始める。ゴスペルシンガーとしては、初の全米No.1ヒットをかっ飛ばしたAmy Grantを始め、アダルトコンテンポラリー音楽でもヴォーカリストの活躍が目立つようになる。
こうなると1990年代には全てのジャンルにクリスチャン・ロックは広まり、グランジやオルタナティヴロックにも進出するようになる。ポップで聴き易いというの代名詞は1990年代のクリスチャン・ロックにはもはや当てはまらなくなっていった。
このように、どの音楽でも宗教音楽が定着すると、当然商業的に比較的「真面目」と考えられる人々の好むとされる(実際は言を置かない。あくまでも既成概念だ。)カントリー・ミュージックにも宗教音楽は進出する。元々、ゴスペルとカントリーはクリスチャン・ロックの独り立ちより以前から良好な相性があったこともあり、敢えてエポックメイキングな出来事ではなかったかもしれない。
が、ルーツロックやオルタナ・カントリーの分野においても、1980年代の後半からぼつぼつとこういった音楽性を持つバンドが排出され始めたのだ。
亡くなったGene Eugeneが率いていたAdam Againを始めとして、現在残されたメンバーのTerry Scott Taylorが組織していたDaniel AmosやSwirling Eddgies。
同じくDerri DaughteryのバンドThe Choir、そしてMike RoeのThe 77’sというような具合にだ。厳密に言うとTerryのDaniel Amos以外はポップなアダルト・オルタナティヴロック的な性格が強くて、物凄くアーシーであったり、カントリーフレイヴァーが充満というバンドではない。アクースティックで美しい曲が多いのは共通しているが、オルタナティヴ色の強烈なモノトニアスな歌やサッド・コアの鼻につく退屈な曲も混じっている。
が、ルーツテイストを感じる音楽性は確かなものであった。これらのバンドのフロントマンであるヴォーカリスト兼ソングライターが終結して、サイドプロジェクトとして立ち上げたのが、このLost Dogsなのである。
改めてメンバーを挙げると
Terry Scott Taylor (Vocals,Guitars) , Derri Daughtery (Vocals,Guitars)
Mike Roe (Vocals,Guitars)
そして本来はGene Eugene (Vocals,Keyboards,Guitars,Bass)の4名となる筈だったが、現在は3名にサポートミュージシャンというスタイルである。創設当初からドラマーとベーシストは在籍していなく、アルバムによってセッションミュージシャンを迎えている。
始まりはコラボーレーションとしてのテンポラリー・バンドとして活動し始めたのが、本人達が意気投合して、本格活動を開始したのである。
演奏を始めたのが1991年の後半からであるから、もう10年以上も自らのグループ活動と平行してこのプロジェクトを続けていることになる。現在までにフル・アルバムで5枚のアルバムを製作している。また1999年には新曲入りのベストアルバムもリリースしているので合計は6枚ということになるか。1992年から2001年までの約10年で6枚のペースはそれほど悪くない適切な間隔であると思う。
もっとも1995年以降は、このバンドプロジェクトであるLost Dogsの方と本業のバンドの垣根が曖昧になってきて、どちらがメインかとは言いかねる活動状況になっている。結構なことだが。
これまでのリリースを網羅してみると
Scenic Routes (1992) , Littel Red Riding Head (1993) , Green Room Serenade Vol.1 (1996)
Gift House (1999) , The Best Of Lost Dogs (1999) , Real Men Cry (2001)
更に、1994年には新曲3曲とライヴトラック1曲の4曲の未発表曲を含めたミニアルバム「Pray Where You Are」をリリースしている。これは8曲入りのヴォリュームであるのでフルレングスと数えて良いかもしれない。
肝心の音楽性については、1stアルバムの「Scenic Routes」はかなりカントリーテイストの入ったアクースティックなオルタナティヴ・ロックというアルバムである。まあ、アクースティック・オルタナティヴと表現しても良いし、アクースティックなカントリーロックのアルバムと評しても良いかもしれない。まあ、アクースティックなクリスチャンバンドとしてスタートしたのである。このアルバムはかなり良いアルバムであるが、現在は廃盤である。
そして翌年の1993年の作品「Littel Red Riding Head」になると大幅にエレクトリック・サウンドを取り入れたロックアルバムに彼らは駒を進める。勿論、アクースティックなベースは保持しての上である。
続く「温室での小夜曲一番」も前作と同じような作風である。
この中期2作(2001年までのタームにおける)はストリングスを駆使したチャーチコーラス風のゴスペル曲もあり、アクースティックなナンバーあり、オルタナティヴ的な重いロックナンバーあり、アーシーなカントリー曲あり、と多彩ではあるがどうも方向性が見えずに全体の印象はぼやけてしまう。各曲を聴くと悪くはないのだが、物凄く良質という訳でもないのだ。
ここでLost Dogsは90年代に主流となりつつあるオルタナティヴ・チャーチ音楽に引き込まれてしまうのではないかと危惧したが、3年の期間を経て−その間、それぞれのバンドで1枚アルバムを作っているメンバーが殆どである−製作された1999年の「Gift House」で所謂オルタナ・カントリーの素晴らしい作品を届けてくれた時は、正直驚いてしまった。かなりカントリーとゴスペルのタッチが強いが、オルタナティヴ的な平板な詰まらないコード進行は姿を潜め、キャッチーでアーシーなカントリーロックな歌が大半を占めるに至り、筆者的評価は鰻登りに上がったものだ。
また同年には初のベストアルバムもリリースし、いよいよこれからと考えていた矢先の2000年春に、Geneの訃報が飛び込んできたのだ。
ぶっちゃけた話、もうLost Dogsは終わったかもしれないと直感した。4人がヴォーカルを取り、4人が曲を書き、4人が共同でプロデュースを行い、Geneがミキシングとレコーディングを自分の家に作ったスタジオであるGreen Roomで担当してきた文字通りの4名で1つのユニットであったからだ。
だから、Lost Dogsが5枚目のスタジオアルバムをリリース予定と知った時は驚いたし、Geneの代わりを誰が務めるのか疑問であったけど、Gene抜きの3人でセッション・ミュージシャンを加えて録音すると分かった時は、余程の事がない限り大丈夫だろうと思った。
というのは筆者好みになった「Gift House」はソングライターがTerry Taylorオンリーになっていたからだ。これまでのアルバムでも5割以上はTerryが曲を書いているが、そのパターンを止め、最もルーツカラーの強いバンドで70年代から曲を書いているTerry一人にライターを絞ってAlt.Countryバンドを目指した路線はきっと受け継がれると考えたからだ。
これで、仮の話だが、Geneが脱退して新しいメンバーを加えていれば、かなり方向性を変える冒険で旧来の音楽性を破棄する行動に出たかもしれないが、Geneに敬意を払って10年近くも活動したメンバー達がGeneのGreen Roomに砂を掛けるようなアルバムを創るはずがないと直感したからである。
結果として直感は当たり、前作よりも更にアーシーでポップに仕上がった作品となった、この「Real Men Cry」は。唯一の危惧であったGeneの喪失が付き纏い、暗い雰囲気の曲の多いサッドコア系の下らないアルバムになるかもしれないという懸念は、全くの杞憂に終わった。
どこまでも暖かく、優しく、美しいロックヴォーカルアルバムになっている。カントリーミュージックへの傾きが一層増したが、ここまでアクースティックにそしてポップに仕上がっていれば、商業カントリーの「焚き火の傍でカウボーイスタイルの兄ちゃんがフォークギターを弾いている」というような安っぽい音とは、壁を拵えて分類すべき音楽性であると思う。ライトであるけれども、尻が軽くないサウンドになっているのだ。
しかもチャーチ音楽のバンドである清々しさと美麗さも聴かせてくれるという、かなりのクオリティを誇るアルバムに仕上がっている。
なお、歌詞は基本的に宗教曲であるので、無心論者な筆者の琴線に触れるものではないため、基本的に言及しないでおく。ご了承を。
まず、オープニングの#1『A Certain Love』から非常にポップで、暖かく、軽快な気持ちの良いポップロックナンバーでノックアウトされてしまう。いかにも西海岸はカリフォルニアのバンドである証明であるかのごとく、爽やかで織り込まれたハイトーンのコーラスワーク。リードヴォーカルのTerry Taylorのやや鼻の詰まったようなジェントリーなヴォーカルも相変わらず健在である。ハスキーでもありやや高目でもあるヴォーカルはPocoのRusty Youngにシンクロする点が多いような気がする。このとことんなアクースティックでアーシーなポップソングは、きっとチャートがまともならヒットするに違いない力量があるのに、と忸怩たる思いがする。
ところが、続く2曲目『The Gates Of Eden』も#1に負けないくらいの滅茶苦茶ヒット性の高い、物凄いウエストコーストしている爽やかポップロックなのである。3人のハートウォーミングなコーラスから突入し、Derriのハイトーンなヴォーカルが、スピーディでかつフックの効いたギターリフとグイグイと進めていくメロディはまさに珠玉の1曲だ。どこまでも綺麗なバックコーラスの厚さと、抜けるようなギターの音は、カリフォルニアの晴れた秋空を、また秋の空の下で風に揺られている秋桜(コスモス)を連想させる。初期のEaglesが演奏していそうな曲である。Gram PersonsやByrdsの風味もしっかりと感じることができる。
タイトル曲である#3『Real Men Cry』はやや抑えたヴォーカルがしみじみと心の襞に浸透していくようなアクースティックバラードである。淡々とした進行の曲であるけれども、彼らの得意なアレンジと曲調が安心させてくれる。控えめなペダルスティールが良いアクセントを付けている。
#4『Three Legend Dog』はこれはスカスカのペダルスティールや、間抜けなパーカッション類がお気楽に開き直る、カントリー・ソングである。目一杯明るく演奏をしているメンバーからはGeneを亡くした悲しみを感じることはできないけれども、ここまで明るいカントリーの曲を持ってきたのは、喪失感を逸らそうとする意図があるような気がしてならないのだ。
#5『When The Judgement Comes』も前曲と似通った雰囲気のカントリー・ロックナンバーである。3人のヴォーカリストが交代でリードを取るところは、ともすれば退屈なステロタイプなカントリー風のロックを変化に富ます働きがあるけれども、ここまでカントリータッチな曲を持ってくるとは、しかも2曲続けてとはかなり意表を突かれてしまう。まあ、コーラスワークとバックのエレキギターのお陰で、それ程嫌いなカントリーにはなっていないのが救いである。
#6『In The Distance』はどこまでも美しく、静かなアクースティックなスローナンバーである。Terryのヴォーカルもここではしんみりとヴェテランの味わいを醸し出してくれる。涼しい夕暮れにラジオから流れてきたらきっと、涙腺を刺激されそうな、華やかさはないけれども、感情の深いところへと落ちてくるような不可思議な重みのある暖炉の炎の色のように暖まるナンバーである。
ゴスペルの浮遊感と、コーラスワークで彼らがクリスチャンバンドだと、初めてのリスナーでも納得しそうな曲が#7『Great Divided』である。エフェクトを掛けたようなぼんやりしたベースにハイトーンのハーモニーヴォーカル、静かなギターとエアブラシというア・カペラに近いアレンジの小作品である。これは#11『Golden Dream』にも共通していて、こちらの方がややアクースティックなミディアムな曲にゴスペルを絡めたような綺麗な曲になっている。
これまでの爽やかさからガラリと曲調を変えて迫ってくるのが#8『The Mark Of Chain』である。これはどちらかというと悲しげな雰囲気の漂うエレジーと表現するべき曲である。とことん抑え目の各楽器のアレンジにDerriのヴォーカルが切々と訴えるメロディはただ、暗く、そして悲しい。ここまでの明るさに陰影を付ける効果のある曲だろう。
というのは次の#9『Dust On The Bible』はバンジョーも聴こえて来る、アップビートな明るいチューンであるからだ。また必要以上に埃っぽさを演出して、ダサくバタバタと展開するアレンジも頭に詰まったストレスを掻き出してくれるような効果があるのか、結構カントリーライクなアレンジなのだが、素直に聴くことができる。
#10でやっとルーツ・ポップロックと呼べるようなチューンが来るので、これは素直に歓迎している。この『Wild Ride』は前半2曲でお披露目をしてくれたように、ややカントリータッチな筆使いを抑えたポップな曲であり、Terryが中盤でシャウト気味に力を込めて歌い切る部分といい、後半のパートで伸びやかな気持ちの良いコーラスがカレイドスコープのように重なるところといい、かなり複雑な流れをキャッチーに纏め上げている、相当に完成度の高い曲であると思う。一聴すると、出来の良い平均点以上なポップチューンにだけ聴こえるかもしれないが、不思議と退屈はしないのである。
#12『No Shadow Of Turning』は、ボトルネック系のギターが使われているが、カントリーの舞い上がる土煙よりも、アーバンなすっきりしたメロディがとろけそうに甘いスローナンバーで、これはアクースティック・バンドとしてのLost Dogsの良質な面を堪能できるナンバーである。3分とたたずに終わってしまうのは勿体無い気がする。このようなアーシーさを抑えたナンバーをもう少し増やしたほうが良かったのではないだろうかと思うのだが。
そしてアルバムには記載がないけれども、公式HPにはタイトルだけアップされている、シークレットトラックの淡白なカントリーバラード調な『Lovely Man』が最後の曲になる。緊張感の微塵も感じさせないリラックスしたこの曲が最後であるのは、少々物足りない気もするが、この押し付けがましくない、宗教バンドでありながら、それ程説教じみていないLost Dogsを集約したようなナンバーとも言えるかもしれない。
以上、13曲。突然の悲劇から1年少々で素晴らしいアルバムを届けてくれたクリスチャンロック界のヴェテラン達に素直に拍手を送りたい。
これからもGeneの死にめげずに活動をしていくようなので、何はともあれ嬉しい限りである。惜しむらくはメンバーでは一番野太いヴォーカルであったGeneが抜けたために、やや全体として軽くなり過ぎるアルバムに聴こえてしまうかもしれないというマイナス点はあるだろう。
が、ゴスペル、カントリー、ポップ、ロックという要素をオルタナカントリーとして表現してくれる数少ないクリスチャンバンドである。これからも活躍を期待したいし、もう少し日本でも知名度が上がっても良いと思うのだ。
なお、冒頭にも記しているが、この駄文を38歳の若さで旅立ってしまったミュージシャン、Gene Eugeneに捧げる。
(2001.12.5.)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
