 Spaghetti Western Complex / AO 55 (2001)
Spaghetti Western Complex / AO 55 (2001) Spaghetti Western Complex / AO 55 (2001)
Spaghetti Western Complex / AO 55 (2001)
Roots ★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★☆
Alt.Country ★★
全く、こういったミュージシャンが突然現れるのでインディ発掘は辞められない、止まらない。カッパえび●ん何ぞ物の数ではない。(謎)
もう万言を費やしても褒め足りないバンドである。間違いなく2001年度の私的ベスト10に入るマスター・ピースとなるだろう。
こういう新しいロックミュージシャンの出現を目の当たりにすると、70年代位までの音楽を「ルーツロック」と呼んで、地を這うようにリマスターやレア盤を探し回ってる人は、本当に貧しいリスニング生活を送っていると、そういった退行的な行動に怒りを覚えるよりも、哀れを催してしまう。
もはや発展性のない音楽を集めるだけのことしかせんのやったら、即座にルーツファンを名乗るの止めれ、すぐ止めれ、アホちゃうけ?さっさと「オールディズ&クラッシック愛好倶楽部」と看板を付け替えて欲しい。(結局怒るのね)
まあ、今回の遠吠えはここまでにしておこう。それだけ、このように素晴らしいロックバンドを見向きもしない自称ルーツロックファンが多いことに、一層憤りを感じさせてしまうような魅力がこの「Spaghetti Western Complex」にはあるのだ。些か逆説的ではあるけれども。
ついでといっては何だけれども、手前味噌は今に始まったことではないので、このバンドを発見した著者の野生のカンも大いに自賛しておこう。「Roots Rock , Acoustic And Alt-Country」というキャッチ文句だけで、さっさと購入を決めてしまった英断はまさに第六感を超越した、セブン・センシズ=第七感であろう。というか試聴もできんのにとっととオーダーするのはアホ以外の何者でもないのだが。(自爆)
と、この辺でAO 55に話を戻すとしよう。このアルバムの何処がそんなに賞賛できるのか、という問いには、
アーシー、キャッチー、スピーディーなロック、アクースティック、ピアノやオルガンやシンセサイザー、ややハイトーンな甘目のヴォーカル、そして多彩な音楽性。
こう、殆ど全ての“良いロックミュージック”としてのエレメンタルを列記しなくてはならないだろう。
良識のあるポップ・ロックファンなら涙を流して有り難がりそうな要素を全て兼ね備えている。
何処をピックアップしても、貶す要素が全く見つからない。筆者が常に求めているポップで基本に忠実なロックバンドとはこのAO 55のようなバンドである。800ccのバイクで砂煙を巻き上げながら爆走していくような、奔馬の如くという表現が似合いそうなロックンロールではないけれども、やはりこういったサウンド、アメリカンロックの美味しい核だけを、余分なものを殺ぎ落とした中から取り出したような至宝のロックサウンドである。
まあ、最上の肉牛の美味しいところを丸ごと焼いて、中から一番美味しいところを取り出したような密度と表現し変えても良いだろう。(食べたら狂牛病という突っ込みは今回は却下する。そういったハズレは結構多いけれども。)
が、取り立てて斬新な、目を見張るような音楽性を有しているわけでもないし、超絶技巧のインプロヴィゼイションを売りにしているわけでもないし、時代に即したヘヴィなアレンジに申し訳程度のポップなコードを付け足ししてポップさを強調して売り出そうとするような安っぽい真似は勿論していない。
内容的には1960〜70年代から綿々と、時には細くなりながらも受け継がれている伝統的アメリカン・サウンドの基本を全く素直に21世紀の録音技術と手法を織り込んで金盤に刻んでいるに他ならない。
味の話に戻せば、決して奇抜な味付けや珍妙なメニューで人目を引くようなコマーシャリズム的なアスペクトには全く顔を振り向けずに、基本の味は守りながら、時代に応じて、塩の塩梅を薄くしたり濃くしたりして大切に核の味を守っている老舗。そこから暖簾分けをしてもらった新興の第2号店という位置付けだろうか。・・・・何だかよく分からないけれども、書いていながら。
やはり、このような嘗てロック史に名を馳せたミュージシャンの影響を何処かに感じさせつつも、現代的なルーツサウンドを模索して、しかもちゃんと自分の形にしているバンドの音というものは非常に聴いていて心が満たされるものである。しかも、そのスピーカーから流れてくる音は、今現在、アメリカ大陸の何処かのコーヒーハウスやボールルームやバーといった街中で、歌い演奏されているという同時代性が存在するということが、やはり感動が異なる要素があると思うのだ。
こういったヴィヴィッドに満ちた活きの良さは、数年に一枚アルバムを出せばまだマシな方、という還暦近いアーティストや、既にレコードの中でしか音を聴くことが不可能なアーティストとは比較にならないくらい輝きに溢れていると信じているし、実際にその通りであろう。
“現在”−2001年の息吹を肌で感じれるミュージシャンとして、このAO 55は、私的に2001年のアメリカン・ルーツシーンを代表する音となっている。きっと何年経っても、2001年に聴いた名盤として筆者の記憶に残るのは間違いのないクオリティの高さを誇っている。
ところで、一般論であるけれども、得てしてポップ過ぎるアルバムは意外に飽きるのが早いという欠点がある。聴き易く耳に優しい手触りだが、少々捻ったアレンジのアクのある曲が多いアルバムの方が、後年印象に残ったり、何時の間にかヘヴィ・ローテーションしているというあの現象である。
が、この「Spaghetti Western Complex」は、筆者をして悶絶・七転八倒させるくらいの激烈キャッチーなコンポーズが充満しているが、軽過ぎて聴き飽きるという事態にはまず陥らないアルバムである。まず、キャッチーという印象ではかなり頭に叩き込まれるような攻撃性のあるパンクやパンクポップのアルバムに多い、『どの曲もポップで馬鹿コマーシャルであるが、何処から聴いても同じようにしか聴こえない』というような単調さがないのだ。
こういった単調で変わり映えのしない曲が多いと、かなり早く聴き飽きてしまう傾向にあるだろう、得てして“金太郎飴”的なアルバムはロング・ランになり難いものだし。
そういった才能の浅薄さを指し示すようなアレンジと曲調の画一さはこのアルバムには全く感じられない。上記したような要素を巧みに組み合わせてヴァリエーションに富んだ作曲で、リスナーを惹きつけてやまないのである。
また、単にノイジーであるとか、ヘヴィだけとか、ライトなポップ性だけ、というようなレンジの狭い音楽性が皆無なため、どの曲を聴いても素直に前後の曲との変化が浮き彫りにされ、何枚かのアルバムを聴いているかのような錯覚にさえ陥りそうだ。まあ、この点は、最初に記した『単調でない』という特色に課なさるものではあるけれど。
そして、オルタナティヴ・ポップバンドや人工系の音をメインにするバンドには付き物の、軽いアレンジで、即効性は確かに認められてるけれども、全く心に残る「沈んでくるもの」がない、といった欠陥が全く存在しないのである。
やはり、これはアメリカならではなドライな感性と、上へ、上へと軽々しく飛び出していきそうな軽いポップの尻軽さを留めている土の匂いがするような根の生えたサウンドを根幹に据えているからだろう。物凄くドロドロで肌に張り付いて取れないような湿地帯の泥の如くなしつこさはないのだが、地平線の向こうからその躍動が伝わってきそうな、赤茶けた色のついた花崗岩のようながっちりした落ち着きがある。
要するに必要以上に重くなく、軽過ぎもない、中間・インターミーディエイトなサウンド性が売りなのである。ともすれば本邦では中途半端とか、特色がないと批判を受けそうな玉虫色な音創りをしていると言われれば、そのバランスよくあらゆるロックの要素を満たすように均衡点で音楽を創造するのがどれほど簡単そうで、困難であるのか理解していない故の無知を表す批判でしかないとカウンターをかませるだけである。
どれほどの数のバンドが所謂「普通」を「普通」と表現できなくて、偏ったような、そうでないような中途半端な作品を世に出してしまったか考えると、この中間性、各要素のブレンドの仕方は天性のセンスを感じざるを得ない。
ベーシックなアメリカンロックを、何の捻りもなくベーシックに演奏し、それが非常にインパクトを持つのにはどれだけの力量と、そして表には顕現しないであろう独創と創作の才能を必要とするか、少し振り返って考慮すれば、このアルバムの品質の高さの程度が分かるだろう。
オーソドックスな音を売ることは、最も難しいことであるだろうが、その難しさをここまで巧みに1枚のアルバムで表現が可能なら、まさに素晴らしい埋もれた(現在は埋もれてしまった訳ではないが。そうなる確率はとても高いだろう、残念なことに。)アルバムとして喧伝できる1枚である。
断っておくけれど、“自称”埋もれたアルバムというのは、本当に埋葬してしまった方が良い大して良くない音なのに専門家の批評だけを鵜呑みにしてレアさを有り難がるような代物が多いのだが、この「Spaghetti Western Complex」は、間違いなく埋もれたとしても、何時か発掘されて陽の目を見るまで、腐敗せずに輝き続けるピースであることは筆者が太鼓判を押そう。
と殆ど賞賛に徹しているが、ここでアルバムの曲の紹介を先にしてしまおう。これまた良くあることだが、このバンドはホームページもメールアドレスも持っていないようなので。更に、発売元のBlue Frog Recordsというところが、HPらしきものは2000年にアップロードしているのだが、何時まで経ってもコンテンツが閲覧できないという、訳の分からないページしか所有していなく、このアルバムに出会うまで、とっくに倒産していたと考えていたようなレーベルであるからして、情報なんぞ引き出しようもないのである。
よって、曲の絶賛だけでこのAO 55というグループの幾らかの良い点だけでも理解して頂ければ、と考えている。
まず、1曲目から、超弩級戦艦の主砲一斉射撃クラスのインパクトを持つ最高のポップロックナンバーが炸裂する。まさに、主砲一斉射撃(サルヴォーという、俗英語では。)の際に甲板に出ていたら爆風で肢体が千切れ飛んだという大和クラスの破壊力がある。と、些か興奮気味なため、ミリタリーオタクな表現方法を使用してしまった。失礼。
兎に角、アクースティックでありながら、秘めたパワーを感じさせるEaglesのギター・ワークを彷彿とさせるエレキギターとアクースティックギターのハーモニー。とても上品な隠し味的に取り入れられたハモンドオルガンの音色。ハイトーンの少し入った伸びやかなヴォーカル・パフォーマンス。そして、一番の決め手の流麗で優しいピアノ。
これら全てが、等間隔に配置され、その力関係が微妙なバランスを保っているという、まさにポップロックソングの基本を全て網羅したような曲である。
「テキサスから離れていると陽光の下にいても、それが悪意の照り付けのように感じる。」というようなあからさまにテキサスへの愛着を唄い込んだ歌であるけれども、このバンドはテキサスのバンドではないところがユニークというか何となく屈折したローカルミュージシャンの気概のようなものを感じられて思わず笑いが出る。無論その笑いには歌を聴いていて自然にその良さに「にやけて」しまうという本能的な顔面筋肉運動も含まれている。
#1は当HPの2001年ベストにも収録したが、この曲が“当たり”ならば迷うことなくこのアルバムは買いである。どの曲もこの#1『Miles Outside Of Texas』クラスのポップロックナンバーと考えて貰って差し支えないからだ。
続く#2『Love On The Outside』はアクースティックであった#1から一転してパワフルでノイジーなギターリフからガツンと始まるロックナンバーである。ヴォーカルもコーラス以外では敢えて低音部を強調したバスヴォーカルの歌唱法が採られている。このギターアレンジは結構な部分で現代的なオルタナティヴの音出しに被さる個所があるけれども、力任せの脳みそがないことを証明するようなキンキンなギター音は全く聴こえて来ないし、LifehouseやMatchbox 20(2枚目のクソな方)的な故意的なノイジーさを演出しようという、むかつきを覚えるようなアレンジではない。あくまでもロックンロールとポップスを土台にした切れ味のある軽快なギターが楽しめる。おまけに、コーラスパートのキャッチーで気持ちの良い速さをB3オルガンが絢爛と演出している部分のギターとオルガンのアンサンブルは、産業ロックのコマーシャルささえ懐かしく思い出させてくれる。JourneyやNight Rangerのソフトなナンバーと置き換えても通用しそうである。
シンセストリングスとピアノをメインにしたアクースティックなリフからスタートする#3『Funny』は、前曲とは対照的にハイトーンなヴォーカルを伸びやかに使用している。そして、次第に盛り上がり、コーラスパートからエッジの効いた泥臭いギターを加え、更に足が地に付いたような安定感のあるハモンドB3を加えて、シフトレバーを急速にチェンジするような分厚いロックンロール演奏が楽しめる豪快なナンバーへと変身するところは、単なるルーツロックバンドではない、アダルトロックの要素まで満たしていると感じてしまう。また、間奏部分でピアノとアクースティックな楽器のみにスケールダウンした後、またもロックアンサンブルをゴツンと叩きつけてくるアレンジなどは、メジャーなバンドにしても全くおかしくない構成の仕方をしている。#1の爽やかさと比較すると、#2・3は泥臭くノイジーなギターが冴えるロックチューンとなっていて、そのロックの速さは格好良いの一言に尽きる。
#4『Empty』はアクースティック・ギターから導かれ、終始アクースティックギター中心に歌い紡がれていくナチュラルなチューンである。このアクースティック・ナンバーは殆ど土の匂いをさせないアーバン・ポップのアクースティックバラード的な側面が強い曲であると思う。ややカントリー系のアーティストならフィドルやペダルスティールを安直に加えようとするだろうレイドバックしそうなユルいスローナンバーであるけれども、ノンドラムス・バラードというプライオリティを安易に活用せず、殆どギターのみで語りかける態度は、もう絶対に只者ではない。またリード・ヴォーカリストのJimmy
Sparksが感情を込めて咽喉の底から絞り上げるようにシャウトする部分の生々しさは、ライヴ感覚をシンクロさせることが可能であると思う。地味ではあるが、かなりインパクトが強い曲である。
#1と同じようなアレンジで、音響が耳の底に尾を引いて行くようなピアノの音の広がりがとても感動的なポップロックチューンが#5『Least Likely』である。陽性ではあるけれども、何処となく陰りのあるメロディといった、相反するメロディの良い部分がブレンドされた不思議なラインがとても印象として強く残るナンバーである。このAO 55の特徴である鍵盤類−この曲では主役はピアノであり、準主役がハモンドオルガンと、折り重なって攻めて来るバックコーラスの隊列だろうが−がとても説得力に満ち溢れた演奏で、複雑な色合いを持つけれども最終的には「綺麗」と表現するしかないミディアムなバラードとなっている。
ハードロックのリフのようなパワーギターにリードされたリフから始まる#6『Trace』はスピーディでパワフルなロックチューンである。#2よりも更にタフでラフな曲であるが、随所でデライトフルに歌われる「Pa,Pa,Pa,Pa,Pa,Pa・・・・」というコーラスがポップさを加味してくれるので、単なるハードッポップなナンバーだけでは終わらないユニークさがあるところが一味違うだろう。まあ、かなりハードエッジの曲でもしっかりとポップなメロディはなぞっているので、聴き苦しい個所はないのだけれども。ムーグ・サンプリングをバックで鳴らしているところなどは演出としては目立つことはないけれども、なかなか音の組み立てが上手であると感じるのだ。
Georgia Satellitesが好んで出しそうなヘヴィで少々泥臭いギターを大胆に中心に据えて、かなりハードなロックンロールを南部の豪快さを見せつけるのが#7『Nothing In The Rain』である。これまた叩きつけるかのように弾かれるB3オルガンがヘヴィなギターと掛け合いをするところは1970年代のクラッシクをベースにしたハードロックの影響も垣間見せるようであるけれども、やはり現代音楽のオルタナティヴ・ロックを経験した世代であるから創り出すことの可能なヘヴィで憂鬱がかったサウンドであるとは思う。が、ヘヴィロックほどには一本調子な頭の悪さを感じることはなくルーツロックあるいはサザンロックナンバーとして聴くことが可能である。これはやはりブカブカと鳴るダサ目のオルガンが随分とオルタナ色を薄める効果を発揮しているからだと思う。それにしても西海岸的なポップロックの#1を聴いた時にはこのようなサザン・ハード的なナンバーが現れるとは想像をだにしなかったものだが。最後の「Nothing In The Rain」のシャウトはヤケクソ気味で荒っぽいところを見せ付けてくれるので、かなり好きである。
2曲連続したハードなロックからガラリと変化して、アクースティックギターの弾き語りから入る#8『Sweet Virginia』は、アーシーというよりも、大地の安定感を有するアダルトコンテンポラリー・ロックという感の強い1曲である。静かで取り立てて華やかなところはない曲なのだが、彼らの故郷であるヴァージニア州への想いを歌った故か、コロコロと高音が伸びていくピアノの音色に導かれたメロディは郷愁と愛惜に溢れている。
「川が流れ、緑の草原や山々の稜線が青い空の境界線になる。」
「誰かが言った。僕はチャンスを逃したって。だから、さあ帰ろう、愛しのヴァージニア、我が故郷へ。涙も止まるさ。僕は全てのしがらみを忘れる。僕は嘘なんて存在しないことまで忘れることができる。」
というような行間から零れ落ちるような瑞々しい感情が伝わってくる歌である。
ピアノのホンキィなリフから始まり、即座に元気一杯なギターとリズムセクションが合流してくる#9『Nothing Happens Here』はもうダイナミックでポップで、思わず踊り出したくなるような躍動感が一杯のロックナンバーである。かなりこってりとした演奏の厚みがあるけれども、全くしつこくなく、それでいてまったり・・・・・・。すんまへん。
と調子に乗ってしまうほどサクサクとしたリズムが快感な、それでいて安定感と重量感がしっかりと根っこに存在する曲なのだ。後半からスゥインギングに出現するブルースハープの音色もこのナンバーの明るさと楽しさに艶やかに色を添えている。ルーツロックであることは間違いないナンバーであるけれども、ビッグバンドやニューオリンズR&Bをポップでロックな口当たりに仕上げ、更にシカゴあたりのジャンプナンバーを意識したジャム的なルーズさを感じる曲である。この豪快で粋ナンバーはかなり筆者のお気に入りだ。
#10『McNelly’s』は1950年代のシンプルなロックンロールや1970年代のパンクロックのテイスト、そして現代のオルタナティヴロックの無機質さといった時代ごとのロックンロールの風味をかき混ぜて、サザンロックの泥臭さで衣を作ってから揚げにしたような、ハードでブルージーな側面ももつクロスオーヴァー・ロックの表現の一端を見せてくれるような曲である。このアルバムではやや異色なトラックであるイメージは拭えないけれども、そのどことなく古臭い匂いと現代的な無感情さが同居し、べったりとしてしまうナンバーは聴いていてなかなかに興味深い。
『マカロニ・ウェスタン』と日本風に言えばこうなるだろうか、タイトル曲。#10『Spaghetti Western Complex』は。というかこのネタは少々古過ぎかも。(笑)極楽能天気なメロディと、お遊び的なカントリー調のアレンジまでされて、かなり全体から見ると浮いた曲ではあるかもしれない。極楽トンボなピアノのコロンコロンと転がす音、考えなしに吹きまくられるハーモニカ、アナログのチューンを施されたようなムーグ系の古臭いシンセサイザー、そして「Ahooooo!!」のメキシカンライクな巻き舌シャウト。兎に角、完全に力を抜いて創った曲であることには間違いないだろう。ピープ・ピープ鳴るシンセサイザーとピアノのビートに乗ってヴォーカルのアンサンブルも陽気に弾けている。
この歌にはグループのインタヴューが存在するので記してみよう。
「一人の異邦人の歌だよ。このラマを引くような歌のリズムは、ある日突然リードヴォーカルのJimmyが歌いだしたのさ。僕たちはその場で座り込み、唄につけるラフな物語をClint Eastwoodの西部劇映画を思い出しながら考えたんだ。けれどもこの歌の真の意味は現在を歌ってるんだ。」
だそうである。あまり歌詞を深読みすると、この雰囲気が壊れそうなので、兎に角楽しむことに筆者はしている。
しかし、歌詞の内容は相当ナンセンスで異邦人という訳よりも異星人という意味で彼らのインタヴューを解釈した方が良さそうではあるな、この詩。
そして#12『I Found Out』は疾走感に溢れた力強い牽引力のあるロックチューン。早弾きされるオルガンとギターがシャウト気味のヴォーカルと合わさって、相当荒い感覚で仕上げているけれども、抜けるようなギターの音色とルーツィなオルガンの鍵盤連打は、やはりルーツロックの有する重みを感じさせる。それにしてもこのロックナンバーもかなりキャッチーであり、曲のポップ度合いは全体では結構ハードでタフな曲もあるのに、相当高いところが特筆すべきだろう。この曲の後に短いシークレットというか#12のアフターブリッジなアップビートな弾き語りの小節が挿入されているが、これまた面白く聴ける流れを醸し出してくれている。
以上12曲、とても多彩だ。兎に角、かなり聴き応えのあるバランスの良いポップロックアルバムである。
さてさて、このAO 55というバンドであるが、アメリカ東海岸はヴァージニア州出身。同州都のリッチモンド周辺で、デュオ名義にて活動するバンドである。
Jimmy Sparks (L.&B.Vocals,Guitars,Drums,Percussion,Harmonica)
Tom Grome (Piano,Organ,Synthesizers,B.Vocals,Percussion)
の2名がAO 55であり、このデュオでカヴァーできない楽器をゲストミュージシャン名義で
J.P.Maheu (L&R Guitars,Bass) , Chris Welborn (Bass−4曲のみ)がサポートしている。また#1のバックヴォーカルでDee Dee Urbanという人が参加、以上のミュージシャンの手によってこのアルバムは創られている。
プロデュースはAO 55の2名とヴァージニアではかなり尊敬を集めているというステイトのギタリストJ.P.Maheuが担当している。この人に付いては全く知識がない、恥ずかしながら。
AO 55の2名はは1995年前後からヴァージニア州のリッチモンドのインディシーンで活動をしていたらしい。
パワーポップバンドのOne Party Ruleというバンドを結成しセルフタイトルのでヴューアルバムと「Pickles for
Porcupines」という2ndアルバムをローカルリリースしているそうだ。
当然聴いたことがないのでどのような音か判断しかねるけれども、是非聴いてみたいのだ。このAO 55を聴くと絶対にポップなアルバムであることは間違いなさそうだが。
このデュオバンドを名乗る前からタッグを組んでいたコンビである。作詞・作曲は常にJimmyとTomが共同で行っているとのことで、二人の立場は完全に同等とのことだ。
AO 55というネーミングは彼らの使用するリハーサルスタジオの部屋番号から取ったという安直さも笑える。
それにしても凄いロックバンドが出現したものである。是非ウェブ上にサイトを開いてメールでコンタクトしたいアーティストなのだが、それが現在不可能なのが非常に残念で堪らない。
最後に彼らの自らの音の紹介と、コメントを紹介して終わりにしよう。
「AO 55はアメリカンルーツロックとオルタナカントリーとアクースティックという裏道を通りつつもポップというフリーウェイを突き進むバンドなのさ。また、眠気に閉じそうになる目や長いバスの旅の友になる安らぎをももたらすバンドなんだ。だから、僕たちの乗る車に車輪が4つ付いている限り、ポップという王道のハイウェイ上には留まらなければならないのさ。」
と、実に基本的なお約束を宣言してくれることが嬉しい。また、歌詞もなかなか機微に富んだ内容が多いが
「僕たちの欠点は、サイコな奴だってことだ。(笑)困ったことに物語りを語るのが好きで堪らないんだ。変な、愉快な、可愛そうな、騙された・大ぼら吹きや、純粋な連中の話をね。」
というコメントからも彼らのソングライターとしての将来が楽しみでもある。
このアルバムで10ドル以下というのは少々価格が合っていない気もするが、兎に角お買い得である。これはルーツという範疇に入りきらない大型のロックバンドであると思う。これからが楽しみであるが、もう少しメジャーになって欲しいものである。 (2001.12.19.)
 Here Goes To Nothing
Here Goes To Nothing
/ The Welterweights (2001)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★☆
Alt.Country&Punk ★★★★★ You Can Listen From Here
Welterweightsを日本語訳すると、一般的には「赤コーナ〜〜〜!世界、ウェルター級チャンピオン〜!グロテスク・鬼瓦〜〜〜!!」(何ちゅーネーミングセンスや)
てな具合で知られる、ボクシングのウェルター級を意味する。例えは些かアホであるけれども。(笑)
ちなみに音楽ネタとは全く関係がないのだが、ウェルター級はミニマム級からヘヴィー級まで17段階ある(2001年現在のルール)のうち、11番目のクラスでウェイトは63.5kgより66.6kgまでという中量級である。
とても陳腐で使いたくない表現なのだが、このWelterweights、意味はウェルター級であるけれども、音楽としての破壊力は筆者的にはスーパー・ヘヴィー級である。・・・・あ〜、やはり手垢に塗れ過ぎた言い回しだ。使ったことにかなり後悔。
しかしながら、現在の流行や趨勢では彼らのサウンドは絶対に世界ランキング入りするどころか、王座決定戦の前座にも選ばれることはないだろう。世間の受け入れ方は間違いなく4回戦ボーイ並みの扱いに違いない、残念ながら。とても世評で2001年新人王の決勝にエントリーできるようなコンテンポラリー性や流行性は存在しない。
まあ、その方が、流行に媚々なクソ馬鹿ヘヴィロックをやったり、凸凹のない退屈なだけなオルタナロックを垂れ流すだけより数百光年分歓迎すべきことではあると思うが。
実際に、筆者的には最高に『大洗い海水浴場』(謎)な音楽性であっても、客観的に評価すると非常にアピールのし辛いサウンドを演奏するバンドではあると、認めざるを得ないところがある。
何と言うべきだろうか、兎に角オルタナ・カントリーの教科書のような音楽を演じるバンドなのである。Alt.Countryと一口に言っても結構な選択の幅がありそうだが、彼らの音楽性はまさにロックなオルタナ・カントリーであることに疑問の余地がない。Alternative Countryの内のAlternativeな部分の基幹である、パンクライクなロックサウンドの調味料が一番強烈に突出しているルーツロックと解釈してもらえれば問題ないだろう。
まあ、パンクのテイストが物凄く強いという程ではない所がまた喧伝が難しいバンドではあるのだが。
というのは、ガレージパンクまでノイジーでがなり立てる音ではないし、ブルーグラスベースやカントリー系の緩くレイドバックしたのんびりさもそれ程感じることもない音だし、Southern Rockタイプの粘つく濃さも希薄な音楽性であるし、現在の解釈で膾炙しているAlternative Rockのような現代的な考えなし大音量出すだけという鬱陶しさは微塵もないし・・・・・・・。
とこう列挙してみると、実に平均的なロックサウンド − こう書くとオルタナのガーベージ・ビン的なロックモドキと誤解されては適わないので、アヴェレージなルーツロック・サウンドとしよう − であることが浮き彫りにされてしまう。
中量級のボクサーが武器とするフットワークとパンチ力のバランスの良いところ、こういった万能性をアピールしているようなロックバンドであることは疑念を差し挟む余地はないのだが、万能を目指して作られるデバイスの殆どが万能ゆえに、特化した状況では使い物にならず、凡作や失敗作の烙印を押されることが多いというのは、技術開発の通説的な真理らしく、このWelterweightsも、中庸的というか、あまりにもベーシックなルーツロックを演じているために、悪い意味での「癖のなさ・アクのなさ」が仇となってしまう可能性があり、実際問題、日本という市場では「平凡過ぎて、退屈だ。」という評価で終わってしまいそうなバンドである。
裏返せば、これこそが、現在のアメリカのメジャーシーンでは姿を消してしまった、希少動物のような本物のアメリカンロック、Real American Rockの一つに挙げられるべき音の証明でもあるのだが。
癖のない素直なアメリカン・ルーツロックな音楽、これこそがこのバンドの最大の売りであり、一番賞賛する語彙に困難を覚える要素でもあるのだ。普通であるが故に素晴らしい、これでレヴューを終わらせてしまえば、5分で書き上げることが可能な音であるのだが、それではこのバンドを紹介する意義が著者的にはないだろう。よって、最大限の貧弱なヴォキャブラリーを使いつつ、Welterweightsについてさらに話をしていくつもりだ。
癖やアクの希薄さを、再三訴えてはみたが、これは別にスカンジナヴィアン・ポップスやアイドル・ポップ音楽のようにひたすら豪華絢爛で売れ線のくっきりした最高なポップさがメインにある、ということではない。
当然のことながら、ルーツロックとしてクドさやアクの強さが目立たないという意味であるため、やはりどことなくOld And Same Rock n Rollのダサさとお約束の風潮を引き摺っている音である、という解釈である。
要するにポップでキャッチーで適度に古臭い、ロックンロールのバンドなのである。但し、メジャーでレコードをプレスできるような整然としたアレンジは探せども発見は困難であるし、ポップチャートでヒットを記録するようなすっきりとした爽やかさは皆無。ルーツテイストを有するバンドが大ヒットを記録するための必要不可欠である都会的なセンスと田舎のアーシーなクラッシックスタイルとのフュージョンは見ることができない、やはり洗練されないロアな点が最大の醍醐味であるインディ・ルーツな田舎臭い音出しを基本としている。
それは飾り気のない音楽と等しいと思う。このジャケットを見て頂ければ、多少なりともバンドのスタンスというか音楽性が推し量れるというものではないだろうか。取り立てて美男・美女もおらず、ダサい普段着ファッションに身を包むだけで、線路の上にだらりんとして並んでいるモノクロームのスナップショット。
ここには一切の虚飾も過剰な虚構の姿も感じることはできない。普段の彼らバンドメンバーの態度を切り抜いて、ジャケットに収めただけのようであると確信が持てるのだ、一度このロック・グループの音を聴いてしまうと。
音楽的には一切の無駄を排したタイトでシンプルなアップテンポなロックンロールを基本とするバンドではありながら、あまりその切れ味のあるロックサウンドの割には、緊張感というか、張り詰めたものを感じることがない。言い換えれば、危うさというか余裕の無さが、実に欠如しており、聴いていて安心というかまったりとくつろげるアルバムなのである。
が、俗に言う『癒し系』サウンドのアクースティックなしっとりとした音楽ではないし、どこまでも美しいナチュラルサウンドを静かに聴かせてくれるという音楽でもない。無論、感動的にメジャーコードとたっぷりとしたアレンジで迫ってくるアダルト・ロックという音楽性でも完全にはない。そのキャッチーさと大人でも実に楽しんで聴ける一般性は、真の意味でのアダルト・オリエンティッドな側面は有しているとは思うが、ここでのアダルト・コンテンポラリーとは少々意味が違うと考えるので、その点は除けておくことにするが。
やはり、安心して聴けるというのは、どこまでも普遍的なアメリカン・ルーツサウンドから全く逸脱するところがないからだと思う。
ポップロックであり、パンクロックの適度な荒さがあり、ルーツロックの泥臭い香りとアクースティックな要素も内包している。引き合いに出されることが海外レヴューでも多いけれども、やはりUncle Tupelo−特に初期の2枚「Still
Feel Gone」までのタテノリなガレージパンクに傾倒したサウンド性やThe Replacementsの後期のアルバム、ガレージパンクからロックバンドとして熟成してきた時期のサウンドに非常に近いところを感じる。
付け加えておくと、ポップさという面ではReplacementsよりも遥かにとっつき易いし、ルーツロックが好きな方にはこのダサさを多分に含んだロックンロール1本道の音楽性のほうがずっとインパクトがあるに違いない。
ヴォーカルという点ではPaul WesterburgやUncle TupeloのJeff TweedyとJay Farrarと比較すると、JayとPaulの中間のようなヴォーカルであり、やや平凡すぎるきらいはあるのだが、十分及第点、悪くない声質である。が、この手のハスキー&シャガレ系は確かに氾濫しているタイプのヴォーカルなので、ここで気に入らないリスナーが出るのは予想されることではある。
ただ、Uncle Tupeloよりもポップ性があるし、ロックとしてのバランス感覚は秀でていると思う。Uncle Tupelo無理矢理な若さに任せての暴走感というか、危ないようなところがないからだ。もっと足の地に着いたサウンドを演じるバンドである。逆にその安定感の良さが、平凡なバンドという印象に拍車を駆けてしまっている点は否定できないけれども。
しかし、南部系のブルースやR&Bといった黒いサウンドに染まらずに、粘着力のまとわりつきが少ないカラリとした乾漆なロックを聴かせてくれるところは、Izzy StradlinやThe Georgia Satellitesの南部ロックのしつこさを抑えてメジャー風なアメリカンロックに仕立てた方向性に僅かに通じる、微妙なソフィスティケイトな味わいも感じざるを得ない。決してメジャーな整然としたサウンドではないのだが、ストレートなロックサウンドはそういったインディのバンド特有の未完成さと、1980年代まではメインストリームであったアメリカン中西部のサウンドをもブレンドした印象を与えれくれるのである。
Alt.Countryという評価をされたり自称するバンドのアルバムを、実際に購入しプレイヤーに乗せてみると、どう考えてもロックっぽいカントリーであったり、グラスソング系列にたまにロック風のアップビートな曲が挿入されているだけというような、あまりRockn’Rollを匂わせないぬるま湯な新人バンドが多く輩出される昨今、このようにロックを柱に立ててルーツサウンドを届けてくれるバンドはとても出会えて嬉しいものである。
特に、このWelterweightsはカントリー系の伝統音楽というパンチ力の強さはアマチュアクラスかせいぜい練習生クラスなランキングにしか位置付けられないだろうが、パンクとロックという順位では相当な上位にランクインするバンドであると思う。ルーツロックのシーンは、ブームのピークは過ぎてしまったが、まだまだ順調に新人バンドを輩出する土壌があるから、このようなアメリカン・ロックな“速さ”を武器にしてくれるグループがこれからも出現してくれることを、このようなバンドに出会うと期待してしまうのだ。
さて、このThe Welterweightsはジャケットで判別できるように男女混合の4人組である。一番素晴らしいことは、鬱陶しい女性リードヴォーカルが皆無なことである。(また始まった・・・・。)
通常、大体男3人に女性1名という編成では、大なり小なり女性がリードヴォーカルの何曲かを担当するのが一般的であるという偏見があるけれども、このバンドはヴォーカルは全て諸手を挙げて歓迎したい男性ヴォーカルオンリーである。件の女性メンバーのElizabeth Scottはベーシストに専念しており、バックヴォーカルもクレジットされているのは、メンバー全員のコーラスが聴ける#10『Little Disasters』と、単独でバックヴォーカルを担当する#11『Already Away』の2曲だけという潔さである。
女性のバックコーラスは大好きなので、もっと積極的にバックヴォーカルに参加しても良いとは思うのだが。まあ、リードを何曲も担当されるよりは全然良いことであるとは思うけれども。
このバンドの母体はアメリカのど真ん中はミズーリ州で、1990年代始めに産声を上げている。ミズーリの非常に小さな街のカークスヴィルというところで大学に通っていた、現Welterweightsのリードヴォーカリスト兼ギタリストのNathaniel WilliamsとギタリストのCorey Heiderが結成したデュオのThe
Petting Zooというユニットがバンドの歴史の始まりである。
このデュオは幾つかのローカルバンドの更なる前座を務める等して、数年間活動をしたが、Nathanielがカークスヴィルの大学で作曲の講師をする一方、細菌学関連の仕事に就いたCoreyがミズーリ州から離れなければならなかったというプラクティカルな事情で消滅してしまった。
が、数年後、やや南に下ったカンサス州の州都カンサス・シティで2人は再開を果たす。ここでこの2人が再開した経緯は何処にも触れられていないが、安定収入のある仕事を捨ててまで、曲を書き、音楽活動をしたいということで2名の意見は一致をみたそうである。
デュオを復活させた2人組みは小さなレコードショップのショウスペースでのライヴを中心に活動を開始する。曲はオリジナルのパンクライクなナンバーを中心にしていたが、大ヴェテランのJohn Prineからギターロックバンドの近年になって漸く日本でもアルバムが発売されだした80年代から活動しているGuided By Voicesまでのカヴァーソングというように幅の広いアメリカンロックを彼ら風にアレンジして歌っていたそうである。
横道に逸れるが、Guided By Voicesの今年2001年春に発売され日本盤もプレスされた「Isolation Drills」はかなりメロディアスなアルバムで、キャリア最高の傑作であるため、是非聴かれることをお薦めする。これまで、これといった当たりなアルバムが少なく、筆者的には多分にただ長く活動しているだけのバンドであったのだが、随分と株価は上昇した。
で、話を戻すと、このデュオにNathanielの高校時代の友人であるドラマーのDave Orvisをある晩のギグに迎えたところ、かなり意気投合してその晩のうちにバンドのドラマーとして契約してしまったそうである。
そして最後のメンバー、紅一点のElizabeth Scottであるが、彼女はカンサス・シティ周辺のガール・ロックバンドの
Nevereadyというグループのベース弾きであったが、音楽的な嗜好がWhiskeytownのようなカントリーロックが好みであったため、他のメンバーとやや目指す方向の違いを感じていたところ、Nathaniel等と音楽の趣味でシンクロを感じ、
バンドのメンバーに納まる。
以上の4名で1年くらいのライヴ活動をした後、2000年に初のレコーディングをカンサス州で敢行する。バンド名義ともう一人のプロデューサー、J.Hallという複数のプロデューサーで完成された4曲入りミニアルバムが「The Dress Rehearsal EP」である。このアルバムは中西部のアメリカのオルタナカントリー系のラジオでそこそこ歓迎され、またベルギーでも発売され、かなりの好評を博したそうである。
そして2001年に入り、バンドはフルアルバムのレコーディングに入る。このレコーディングにプロデューサーとして協力したのが、日本では殆ど知られていない(というか誰も知らない)The MorellsのベーシストであるLou Whitneyである。このLou Whitneyという人はRobbie Fulksのの初期の2枚で、もう一つの彼のグループであるThe Skeletonsと共に演奏の大部分で関わっている人でもある。ちなみに1982年にThe Morellsは「Shake And Push」というアルバムを出しただけで、後は殆ど同じメンバーとの別プロジェクトのSkeletonsとして1990年代を活動していたが、2001年に19年ぶりの「The Morells」をリリースした。このアルバムはPhil Spectorの大ファンであるLouのカラーがモロに出たクラッシックなオールド・ファッションなスゥイング・ロックであるため、興味のある方は購入してみては如何だろう。殆どのネットショップで購入が可能である。
と、また話がズレてしまった。ここで話題にした大御所のインディアーティストであるLou Whitneyのサポートを受けるという幸運と入れ替わりのように、EPの発売後、ドラマーのDaveが東海岸に移り住み、ドラマーの交代があった。このメンバー交代を経て2001年に「The Dress Rehearsal」の収録曲を全てトラッキングした今作「Here Goes Nothihg」が完成したときのラインナップは以下の通り。
Nathaniel Williams (Lead Vocal,Guitars) , Corey Heider (Guitars,B.Vocals)
Elizabeth Scott (Bass,B.Vocals) ,Mark Gardner (Drums,Percussion)
となっている。2000年の7月までDaveが在籍したため、13曲のうち8曲は彼のドラミングである。
先にシンプルで飾らない演奏と記したが、まさにその通りで、#4『Madeline』でペダルスティールがゲスト参加してるだけで、後はギターとベースとドラムだけの3ピースバンドのような楽器しか使用していない。
その基本的な楽器だけの演奏による曲は、サウンドの奥行きという面では確かに単調であるけれども、決して浅薄な表面だけを撫でる擬似ロックではなく、3ピースのように底の浅い演奏でもない。
しっかりとした、安定感のあるロックサウンドを見せ付けてくれるとことが賞賛すべきポイントである。
アルバムのファースト・トラックは全13曲の中では相当カントリー風というか、ゆったりとした軽快な調子の『Nuns & Beatniks』でスタートする。基本的にロックなアップテンポチューンが多いこの「Here Goes Nothing」ではかなりレイドバックした印象が強い。が、大地の底から突き上げてくるようなパンチ力は既にこのナンバーから十全に発揮されていて、Nathanielのシャウトする歌唱法がとても歌自体の存在感を増す働きをしている。のんびりと牧歌的に挿入されるハーモニカも良いアレンジを与えている。当然のことながら大仰でないけれども、聴き心地の良いポップさと中部アメリカのカントリーソングの元祖ブルーグラスのサクサクしたリズム感が何とも言えずグルーヴィである。
軽快なギターリフで導入され、抑えたヴァースで続き、これはロックにジャンプする、飛び上がると思わせておきつつ、お約束どおり「Ha!!」の掛け声と共にガツンとラウドでスピーディなロックンロールへとステップする#2『Little Red Light』はガレージパンクの乗りの良さだけを引っ張ってきて、よりオーソドックスなアメリカンロックのアレンジで再構築したようなロックチューンである。こういったパンキッシュなロックンロールをパンクのように単調に聴こえさせないテクニックは、表層に浮かんではこないけれどもかなりの力量を感じる。
続いて、またもワイルドなロックミュージックが攻勢をかけてくる。デヴューEPにも収録されていた#3『Honeymoon』は2分足らずのパンクロックの代表的な長さを持つチューンであるけれども、パンクらしいパンクというよりも、よりロックのサウンドに近いシンプルなナンバーである。Replacementsや、後期のというよりも最後のスタジオ録音アルバム でのJason & The Scorchersを連想させるロックナンバーでもある。Ramonesのポップセンスを正統に継承している如くなバンドであるけれども、このパンクロックの代表選手のようなバンドよりも、パンクのチープさが希少に感じられるサウンド性を有するところが相当な才能を予感させてくれたりもする。
やや歪んだギターソロから、これまたグングンと力強いラウドなアップビートにキャッチーに羽を広げるかの如くに拡大していくのが#4『Madeline』である。このトラックのみ、外部ミュージシャンがペダル・スティールで参加しているが、普通はグラスソングやカントリー代表楽器の如きペダルスティールギターが、一歩飛び抜けて天窮へとすっ飛んで行くようなロックな暴れ方を、エレキギターと一緒にしているところは、なかなかに面白い。それにしてもCoreyとNathanielのリード・アンド・リズムギターのアンサンブルはとても良いブレンドになっている。ノイジーなリズムラインとやや泣きを入れるかのように歪むリードラインの合わせ技は、ロックンロールの重量感を軽快な音で表現してくれる。
ロッカバラード調の寂しくも、掘り返したばかりの畑の土の匂いに存在するような安らぎを感じるのが、初のスローなチューン#5『Coward』である。こういうナンバーではややリードヴォーカルのアピールが不足しているように感じてしまうが、こういったタイプのヴォーカルを聴き慣れているせいもあるだろうか。もっと感情を込めたソウルフルなバラードならNathanielのヴォーカルも映えるに違いないが。それでも、声が裏返りそうな歌い方は結構耳に残るのだ。
出だしからキャッチーで爆走感覚を予感させてくれる#6『Close Enough』は相当にお気に入りのロックチューンである。エッジの入りまくったメロディと演奏。かなりマッチョなシャウトを搾り出すNathanielのヴォーカル・ワーク。終始単調であるかもしれないがポップでストレートなパンクオリエントなメロディを継続する、まさにAlt.Countryのロックな側面を凝縮したような1曲である。しかし、パンクっぽくはあるけれどもWaco Brothersほどダサさ満点の垢抜けないパンクテイストはそれ程には感じない。更には、Green Dayの初期の頃の考えなしなパンク街道まっしぐらという音ほど単純明快な考えの無さとも何処となく違うのだ。Green DayのアーバンなポップパンクとWaco Brothersのカントリー・パンクな音との中間を演出することを実行に移したかのような、中道的なソリッドなロックナンバーとして成功していると解釈すれば良いだろう。
#7だけが、唯一のカヴァーソングである。しかもChuck Berryの『Whinin’Boy』を持ってきているから正直驚いたものである。比較的な新しいアレンジ−ポップパンクやオルタナティヴ以降のアメリカンロックの影響をそこかしこに散りばめた音であるし−中心のWelterweightsがこのロッククラッシックな大御所のカヴァー・ソングを持ち込んでくるとは、やはり新鮮というよりも虚を突かれた思いである。だけれども、原曲の黒っぽさよりも、パンクロックな元来備わっていたロックのビートを2001年風の現代的な音で顕しているところは、どうしてどうしてオールドロックをわざわざ初のフルレングスに取り入れた価値があるというものである。しかし、やはりChuckのシンプルなロックというのは時代を超えて普遍であると思わせる選曲でもあることだなあ。
#8『Fast Or Famine』はブルーグラスのリズムにエレキギターとロック楽器で肉付けしたような、ミディアム・スローなリズムが素敵なナンバーである。こういったロッカバラードタイプの曲が所々に挿入されているだけで、頭ごなしのパンクアルバムとは随分と重みが違ってくるものだ。しかし、特別アレンジは複雑で無いのに説得力のある質感のある曲になっている。
デヴューEPからの1stラジオシングルにもなった#9『Hardly Used Car』は、相当ツール・ハードなドライヴィング・チューンであり、彼等がロックバンドであるという自負の証明のような気概を、最初にカットした理由として推し量れるように思える。常以上にシャウトするNathanielのヴォーカルも、叩きつけてくるようなヤケクソ気味の演奏も、ソリッドで切れ味の良い野性味溢れるスピード・ナンバーにフィットしている。一見新古品のような自動車という、外見と嘘をメタファーにしたシニカルなメッセージが一見単純な歌詞に込められているように感じて、興味深い。それにしても、これだけタテノリであるのに、それ程品性の無さを覚えないのは不思議である。別に畏まって上品で繊細なサウンドを演じているバンドではないのだが。こういったプライオリティも正統派なロックナンバーを演奏できる故の副産物かもしれない。
#10『Little Disasters』は直前の#9ほどには弾ける直球なパンクロックではないけれども、ルーツィでパワフルなギターワークとビートが冴える好チューンである。かなり泥臭いなかにもキラリと光る清涼感を匂わせるスマートなロックセンスが感じられる。また時にはハードに、時にはスローに、と変調を繰り返す多彩さがあり、この2曲なアグレッシヴなロックナンバーの連続はこのアルバムでもかなりハイライトではないかと思う。
#11『Already Away』は初めて女性ベーシストのElizabethのバックヴォーカルがソロでフューチャーされた、土臭いアクースティックなナンバーである。確かにリードを取るほどの艶のある女性ヴォーカリストではないけれども、バックヴォーカリストとしてはその控え目さと、鼻にかかったStevie Nicksの亜流のような声質は適しているように思えるので、もう少し出番を与えても良いのではないだろうか。
#12『Just Plain Fall』はやや悲しげなメロディを持った、秋というか感謝祭をテーマにした失恋懐古ソングのようである。このアルバムの中では、その抑え気味のポップさと憂鬱さを含んだラインはオルタナティヴの影響を思わせないこともない。オルタナティヴ・ヘヴィのように五月蝿すぎないところはちゃんと一線を引いているとは思うけれど。
#13『Zen Baptist』は、アメリカで訳の分からないブームとなっていたこともある「禅」について歌われている。禅を宗教としてポジティヴに捉えているような歌詞は東洋文化への誤解(笑)が伺えて微笑ましい部類に属すると思う。しかし、歌としては相当に爆走するロックチューンである。#6や#9とタメを張るようにゴリゴリのパワー・ロックであり、#12の暗さを払拭するような働きをしているようだ。とても攻撃的でノイジーなチューンだけれども、ちゃんとポップであるため、嫌にならずに純粋に楽しんでロックの速さを堪能できるのだ。
以上、13曲。飾らない基本的なタフで野趣のあるロックサウンドが詰まっている。が、このアルバムはセルフリリースであるのが、非常に残念である。オフィシャルサイトのカウンターも全然回っていない。
日本でどれだけのリスナーがこのアルバムを購入したかは未知数であるけれど、10本の指に達するなら良いだろうという推測くらいしかできない。
ヴォーカルは確かに差別化出来るほどの名手ではないかもしれないが、このシンプルでベーシックなロックサウンドはとても貴重であると思う。特に、ロックが死滅しつつあるアメリカのメジャー音楽シーンを裏から支えるのはこういった連中なのではないだろうか。
これからも応援していきたいバンドである。 (2001.12.24.)
 Choose Your Fix / Jukebox Junkies (2001)
Choose Your Fix / Jukebox Junkies (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Modern ★★
You Can Listen From Here
ふと、シングルチャートを眺めてみれば、嘗て人々がJukeboxに身を傾けて、麦酒や蒸留酒と一緒に音楽を楽しんだようなアメリカンロックは完全に近い形で消滅している。
もっとも、筆者の世代になると『ジューク・ボックス』という機械はやや馴染みの薄い機械である。(いや、ホンマの話で。)ジューク・ボックスが置いてあるような「アダルト」な場所へ(笑)出入りが自由になった頃にCDの時代が到来し、更にレンタルCDビジネスが大幅に拡大したことで、Jukeboxは廃墟になったボーリングセンターや、潰れたウォーター・ビジネスの建物の改築や取り壊しの現場作業のアルバイトで見た回数のほうが、実際に使われていた所を見たよりも多い記憶がある。
チャートの話に戻るが、常に大勢を占め、ランキングに居座るのはただ、ヘヴィなオルタナロックや、ラップやスクラッチ、シークエンサーを入れたノイジーなギターサウンド。アイドルに女性と黒人モノばかりで、これがまた、しかもロックでない。
まさにJukeboxにセットされていたロックポップは過去を偲ぶ鉄とガラスの箱と共に去っていってしまったようだ。
そのような時代にJukebox Junkiesというような、ともすれば懐古主義のナツメロ・バンドと認識されかねない名前でアルバムを出したグループが2001年秋に出現した。師走に入ると大手のオンラインショップでもこのアルバムの入荷が始まり、比較的容易に入手が可能になったようだ。
相変わらず、筆者は殆どの大手オンラインの品揃えよりも入手が早いのは完全にある意味で終わっているのだけれども。(笑)
と、このバンドについて語る前に、Jukebox Junkiesという名前から連想されるバンド等についてつらつらと益体も無いことを語りたい。ので、興味ない方はさっさと読み飛ばして欲しい。
『Jukebox』という単語を聴くと、筆者にとって思い出すのはForeignerというプログレッシヴ・アメリカンハードロック・グループのヒットシングル『Jukebox Hero』である。まあ、この分類には異論ある方も存在するとは思うが、確かにこのシングルを切った頃のForeignerはプログレ・ハードな音楽であったとは思うのだ。
この重厚なロックシングルがブレイクした当時は、まだまだJukeboxは映像文化の普及によってやや旧式化してきたとはいえ、現役バリバリだっただろうか。
Lou Grammのハイトーンでコブシの効いた声で重苦しいながらも、コマーシャルなこの歌はかなり印象に残っている。
また、全然方向性は異なるが、『Junkies』という単語から即座に連想するのは、カナダは我が愛しの街出身のグループ、Cowboy Junkiesである。このブルースという様に音楽性を固定してしまうには、あまりにも冷たくひんやりと
した肌触りを纏わり憑かせるロックバンドは、地味であるけれども、何故か何時までも耳に残る奥の深いサウンドを提供してくれる。
どちらのロックバンドも方向性は随分と違うが、筆者の私的ロック史上にはかなりのウェイトを占めている存在である。殊に、Foreignerはセールス全盛期をリアルタイムで経験している分、思い入れは強い。
まあ、このバンドについて情報を得ていなかった時に、名前だけで衝動買いしそうになったのは、このようなネーミングに対する入れ込みが全く見当違いではあるけれどあったからである。とはいえ、結局とある情報を入手した途端に、衝動買いしたので、あまり大差は無いだろうけど。(苦笑)
実際にジュークボックスを使用したことは片手に数えるに余るのだが、現実的な生活の面−仕事においても多少この音楽の箱に関わることもあった。
数年前、取引先が、レトロブームか何だか謎なのだが、ジュークボックスやピンボール筐体の製造を始めて、その完成品の輸送手配等について商談を設けた際、筆者はそこで「大体、取引先いうか、買い手は何処なんでしょう?」と質問をしてみた。特にJukeboxという音楽関連の単語を意図したわけでないけど。仕事と趣味はきっちり切り分けるというのが、著者の主義であるので。
で、返答であるけれども、以下の如くであった。
「いや、ブティックとかレストランとかが結構多いんやね、これが。実際に動かさないで、装飾品として使うらしいわ。第一ドーナツ盤(お、おっさんやあ。)とかあまり持ってへんやろしね。実際に音楽CDを売るようなレコード店よりもファッショングッズやアメリカンな服を売っておる店とかからの注文が全然多いなあ。」
というようなていたらく。
まあ、確かに、80年代後半から復活したボーリングセンターなんぞでも、ジュークボックスではなく、PVをコインで流す(これは何て言うねん??)機械しか見れなかったし、アンティークなバーとかのお洒落な場所に高い金捨てて飲みに行くなら、赤提灯やチェーンの飲み屋へ喜んでいくセコビッチな(笑)性質なため、稼動してるジュークボックスは近年殆ど見ていないように思う。98年までの米国駐在でも、本当にコインを入れて動いているジュークボックスを見たのは数回である。安月給であったため、自分でコインを投入したのは本当に数回。しかものんびりと耳を傾けることに耽れるような状況でもなかったことが殆どであった。
近年のレトロブームとかで、日本でも製造が復活したとはいえ、殆ど外見の懐かしさだけを目的に作られた、空洞のような媒体、それが現在日本でのジューク・ボックスだろう。テキサスやミズーリ、ケンタッキー州のドライブインやバーガー・ショップには古ぼけたこの機械が鎮座していたが、あまり頻繁に使用されているようには見えない、人気の無いゲームセンターの筐体のように、妙な暗さを辺りにおどろ線のように垂らしているジュークボックスが多かったように記憶している。
実際のところ、チャンネルが頓に細分化する米国の昨今の事情では、無料で好きなジャンルのラジオを聴いていたほうが、楽しめるだろう、恐らくは。
ある意味、ジュークボックスの斜陽化は、アナログ・メディアの終焉に伴うシングル時代の暗黒化を示唆しているように思えてならない。1990年代のロックバンドのシングルの切り方になったラジオシングルという形態は、ポップ総合チャートでは受け入れられない尖がり過ぎた耳障りな、ロックのギラギラした腹に凭れるだけの栄養しか詰まっていないように思える。
ということで、アメリカンロックの分かりやすさと親しみやすさを兼ね備えた楽曲はどんどんとジューク・ボックスに入れられていた音から、膨張する宇宙論の遠ざかる宇宙の如く、遥か彼方へと吹っ飛んで行っている訳である。
で、そんな時代に現れた、Jukebox Junkiesであるが、
まさにJukeboxに嘗て入っていた如くの音である!
と、断言したいのだが、そう都合良くは嵌ってくれないのが現実の厳しさであろう。(笑)
確かに、基本的なアメリカンロックのアーシーさやポップさは有り余るほどある。が、1970年代や1980年代のポップロックの潮流を彷彿とさせるような、まんまの音かというと、そうでもない。
このJukebox Junkiesの音楽性にふんだんに感じられるのは、1990年型のアフター・グランジ&オルタナティヴの暴風を経験した後に興隆してきた、1990年代のアメリカン・ロックのスパイスである。決して、古臭い音や懐古趣味に走ったブカブカのアナログスピーカーから流れてくるような、レトロ・アクティヴな音楽ではない。
オルタナティヴと現在は解釈されているが、本来の多様性というかどのリスナーにも聴ける汎用性という基本からかけ離れてしまった、ジャンク・ヤードに転がっているようなボケ茄子な現代性は粉微塵も呼吸器に飛び込んでくることはない。
ここで述べている現代性というのは、オルタナティヴの影響を受けつつも、伝統的なアメリカンロックを現代的なアーバンポップやコンテンポラリーな楽器とアレンジで構築し様としているモダン・ロック、良心的なと付け加えたほうが良いだろうモダン・サウンドの素材の良さを表現したい意図を汲んで頂ければと思う。
ここで紹介してきた音の中では、Mr.Henryに近いあまりルーツカラーの濃くないポップロックであろうし、2000年に3枚目の世紀の駄作クソクソアルバムをリリースしやがったThe Wallflowersのこれだけは間違いなく最高傑作である「Bringing Down The Horse」に非常に近い都会的な控えめなルーツセンスを有したアルバムである。
Mr.Henryほど、遭魔ケ時の昏い陽の光や月光の静かな零れ落ちる光線、というような寂寞とした“詫び・寂び”を鼻先に感じ取れるほどには、サラサラとしたびろうとのような柔らかさは無いけれども、その分、一層明るく、ポップである。爽やかな秋口の朝の光が似合いそうなサウンドである。
で、あまり引き合いに出したくないのだが、The Wallflowersの2ndアルバム程には名曲が詰まってはいないとしても、この「Choose Your Fix」はこの1990年代にまともなロックアルバムで成功した数少ないアメリカンロックバンドと比較されるだけの評価を与えても良いと思う。
というか、気の抜けたコーラを電子レンジで温めたような最悪のアルバム「Breach」出した、Wallflowers、今度駄作出したら、アメリカまで天誅を加えにいくで、コラ!!
と怒り狂って、口から怪光線を放ち、眼からビームを発射して帝都を破壊したくなるような殺意さえ覚えるアルバムを含めたWallflowersのこれまでの3枚のアルバムの総合評価と、Jukebox Junkiesの前身バンド、(というか全てフロントマンのMarc Dauerのプロジェクトなのだが)Five Easy Piecesの2枚のフル・レングスアルバムを計上して3枚としてJukebox Junkiesと天秤に懸けてみると・・・・・・・
Jukebox Junkiesの方がトータルバランスでは上やん!!Marcはん、あんさんは偉い!反対に、取り敢えずJacobはドクターキャ●ポでもやって脳味噌メンテしとれ!売れたからって調子に乗るな、スカタン!!
と、好きに吠えてみたが、真面目な話、The Wallflowersの一番良い時の(既に過去形かいな)サウンドに非常に近いところを持ったアルバムである。適度にロックよりなカントリーロックのフレイヴァーを宿し、現代的なやや控えめなロックセンスをも同時に包括している音。王道的なアメリカンロックを1990年代という新世代のフィルターを通して再構築したような古さと先鋭なポップさが同居する傑作性。
1曲の破壊力では、少し前に述べたようにThe Wallflowersは傑作2枚目があるだけに、こちらへ軍配が上がりそうだが、Five Easy Piecesのプロジェクトまで加えると、平均点では相当リードしそうである。ルーツテイストをやや強くしたアメリカンど真ん中なポップロックという以外の何物でもない。
Counting CrowsやCollective Soul程にはオルタナティヴを取り込んでアメリカンロックとして消化しようという気構えはあまり見えてこずに、伝統的なアメリカン・ポップとルーツサウンドを上手に独自の色で染め上げているようなマイペースさを感じるバンドである。オルタナティヴ的な素養は実に薄いが、ややメジャーな音程を微細にマイナーコードに揺らすような、現代ロック的なアプローチは存在しているとは思うけれど。が、大英帝国風のヒネクレ・ネジリン棒なサウンドでは絶対にないことは断言しておく。
さて、まずはこの『ジュークボックスに金つぎ込みまくりなヤツ』というバンドについて触れておくとしよう。Jukebox Junkiesという名前は馴染みが無くても(新バンドなので当たり前か)、Five Easy Piecesは良心的なロックファンならご存知の方も多いと・・・・・・・・・思いたい。(弱ッ!!)というよりも、かなり外れ確率の少ないプロデューサーであるT-Bone Burnettを熱心にフォローしているリスナーが、彼の手がけたメジャー・デヴューのバンドとしてこの名前に出会ったというパターンが多いのではと推測している。
そう、1998年にメジャー・レーベルのMCAからセルフタイトル「Five Easy Pieces」でデヴューしたカリフォルニア州出身のバンドプロジェクトが、このバンドの前身なのだ。
バンドの中心というかソングライターでリードシンガーでギターとヴァイオリンまでも弾き熟す、文字通りの中心人物であるMarc DauerはL.A.中心から1時間もかからないくらい南の衛星都市、ロング・ビーチで生まれている。幼少時はヴァイオリンをレッスンし、ギターに触りだしたのは高校生の時から。
大学は正反対側のニューヨークであり、そこのクラブシーンでMarcはScamというバンドを結成し、初めてバンドの活動を開始する。これが90年代の始めのこと。何となくSteely Danの名盤を思わせる名前のバンドであるように思えるのだが、摩天楼の地、ニューヨークでの活動という意味も含めて、どうでもいいことだが。
しかし、バンドはバンド活動として趣味の一環としか当時、Marcは捉えていなかったらしく、単科大学を卒業後、彼は医科大学に通いだす。
「僕は科学系の勉強が大好きだった。しかも将来のことなんて考えてもいなかったんで、ただ、医療関係の勉強をしようと思い立ち、そうしたのさ。」
まあ、現代ッ子であるのかもしれない。が、才能のある人間というのは何処にでもいるもので、地元に戻りUCLAの研修医にまで進んだ彼は、仕事が忙しくてロクに睡眠も取れずに、音楽すら満足に聴けない生活に嫌気が差し始める。一体、自分は何をしているのだろうか、という疑問に突き当たった彼は空き時間は乏しいながらも全て、引きこもるようにして猛然と曲を書き出したそうだ。
「僕の家族は僕がどうにかしてしまったと考えてたらしい。けれどもその時はこうしなくては僕はいられなかったし、実際に必要なことだったんだ。」
と彼は振り返って言う。で、インターンとしてL.A.郊外の病院に勤める傍ら、作詞の線から知り合ったキーボーディストのJay SchwartzやJayとの共通の友人であったギタリストのJason Sinay等とバンドを結成し、2足の草鞋で音楽活動を再開することになる。この当時はかなり忙しかったらしく、Marcは三交代の合間にギターを持ってステージに立っていたこともあるそうだ。
こういった苦労を些かアイロニカルに表現したのが、このMarcのファースト・プロジェクトFive Easy Piecesの名前の由来となっているそうだ。
「幾つかの方法で僕たちは何でも上手くやれることもあったし、逆に全然ダメで行き詰まったこともあった。こんな経験からヒントを得た名前なのさ。」
とJayは言う。
結局、音楽活動を始めて一年でMarcは医者の道を断念し、ミュージシャンとして専念するようになる。方やお堅い仕事の代表、方や明日をも知れない浮き草のような生活。かなり毛色の変わったアーティストであることには間違いないだろう。ちょっと日本では生まれないタイプの音楽家であるのは確実だ。
そして1996年に、リズムセクションのAl Wolovitch (Bass)とAndy Kamman (Drums)を迎えたバンドは、フルレングス・アルバムの録音に入り、インディレーベルから「Fish Of Death」を翌年にプレスする。
かなり荒削りなところが多いアルバムであり、オルタナティヴ的な臭気が強いアルバムであったけれども、キャッチーなメロディの良さは、かなりのレヴェルにあった良質なロックアルバムである。このアルバムはL.A.を中心にかなりのローカルヒットになり、『South』等のローカルラジオヒットも記録している。
これに、メジャーのMCAが注目し、即契約となる。ここでバンドに紹介されたのが、前述の敏腕プロデューサーT-Bone Burnettであり、更にTom PettyやRolling StonesのエンジニアをしていたDon Smithも数曲でプロデュースを担当、更にミキシングには、数々のメジャーアルバムに参加しているTom Lord-Algeが加わるとう豪華さであった。 デヴュー盤から6曲のリメイクを含んだこのアルバムは、T-Boneの協力でかなりのルーツテイストを含んだアメリカンロックとして1998年に完成し、The WallflowersやCounting Crowsの1枚目に通じるような魅力があった。当時、西海岸では結構レコード店の店頭に横売りされていたものである。ついでにしっかりとライヴも見てきたが、なかなかのしっかりしたライヴでかなり満足度が高かった。
ところが、良いものが売れないアメリカでの常だろうか、セールス的に然程成功を収めるに至らずし、MCAとは契約を早々に破棄されてしまう。このMCAとの契約破棄については、色々と当人のコメントもあるが、かなり金銭的に揉めたようである。今作は初の自主リリース盤であるけれども、
「自分の本当に望むアルバムを創る機会が欲しかったし、もう少し前のアルバムより貯金を増やしたいしね。」
とやや婉曲的な発言をしている。まあ、良いアルバムは是非売れて欲しいから、筆者は金が欲しいという発言は正直で良いと思う。徒に孤高ぶって「儲けはどうでも良い」という輩には「じゃあ、売るな、タコ。」と言いたい。
「僕はこの音をオルタナカントリー・ポップ・ロックと呼びたいね。」
というMarcの発言は些か欲張りであるけれども、まさにその通りの音楽性である。Alt.Countryのアーシーとポップロックのすっきりとしたサウンドの同居、このJukebox Junkiesの音楽性はこれに尽きる。
「僕はずっとThe JayhwaksやWilcoといったオルタナカントリーバンドの熱烈なファンだったけど、同時にBig StarやBeatlesのようなクラッシック・ロックも大好きなんだ。この2つの音の影響を組み合わせて曲を書いたんだ。」
これまた正直なコメントであるが、至極もっともである。これらのバンドが好きなら絶対に聴いておくべき一枚であると断言する。
現在のバンドユニットのメンバーはMarc Dauer (L&B.Vocals,Guitar,etc)を筆頭に
Zak Schaefer (Bass) , Darren Tehrani (Guitar) , Blair Sinta (Drums,Pedal
Steel)
となっているが、このレコーディングにはFive Easy Piecesのメンバー、そして何と再三引き合いに出したThe Wallflowersから鍵盤弾きRami Jaffeeとドブロギターやマンドリンを担当し2000年からWallflowersに加入しているBen Peelerの2名、同じロス・アンゼルスのアクースティック・オルタナ&ルーツバンドのMinibarのメンバーと10人以上のミュージシャンの協力でレコーディングされている。現在のメンバーは誰一人として演奏に参加していない。
このことからも、このバンドはMarcのワンマン的な要素が強いと思う。Marcはあちこちでバンドの和について強調する発言をしてはいるけれども。
さて、かなり無駄話と咆哮(汗)で余分な容量をとってしまったので、簡単に全11曲に対する感想を記すに留めておこう。あまり長蛇化するとさらに読者が減りそうなので。(笑)
全体として、ロックンロールの迸る汗臭さの匂って来るようなスタンピート・ナンバーはない。どれも適度に速く、ミディアム前後のテンポのポップロックソングである。その割に、全体としてはかなりロックンロールに感じるアルバムに仕上がっているのは、これまたWallflowersの「Bringing Down The Horse」にシンクロをしてしまう。
良い王道ロックアルバムというものはそれ程ガンガンとロックンロールの大鉈を振り回さなくても、その説得力で軟弱ポップスや単純パワーポップとは違う重みを持つのだろう。Five Easy Pieces活動時代に、InterscopeがWallflowersの2匹目の泥鰌を狙って売り出したColaより全然重みがある。Colaもそれ程悪いバンドではないのだが、このJukebox Junkiesと比較すると格落ちの感は否めない。
#1『Sentimental Tattoo』からどことなくアーバンなスマートさと、ルーツロックの野暮ったい雰囲気がミックスされたポップロックナンバーが来る。Five Easy Pieces時代よりも明るくなり、纏まりを増加したサウンドに思わずニヤリとしてしまう。この曲にはやはりWilcoやJayhwaksに通じるものを感じてしまう。Wallflowersの名曲『One Headlight』に近いテンポと雰囲気を持つけれども、この1曲目はルーツロックの渋さよりもポップロックのふんわりとした、然れどもザックリした切れ味を感じる。
かなりアーバン・ポップなAOR的なリズムさえ感じる#2『Over And Over』は西海岸というよりもメキシコ寄りのラテンフレイヴァーすら感じる、Fastballの3枚目にかなり見られた、やや斜に構えたポップグルーヴが印象的なナンバーである。ホーンセクションまで入れてしまうところが、ますますFastballの雑食性に近似した個所を思わせるのだ。
良心的な丁寧なパワー・ポップや英国風なBeatle Popのセンスが伺えるのが、#3『A Wish』である。このようなやや軽さの鼻につく安っぽさを、巧みに加味したルーツテイストで上手く浮かび上がらないように楔止めしているところがこのバンドのバランス感覚の良さなのだろう。
シンセ・オルガンでB3のような音出しと、Mini-Moogのようなピロピロし音を演出している、とてもしなやかでおっとりしたルーツバラード#4『Reason To Believe』は、これまたアーバンコンテンポラリーの洒落たセンスと、アメリカンロックの乾いたパワーが両方感じられる、良質なバラードである。
メロトロンやクラヴィアントといったアナログ・シンセサイザーとハモンドB3を多彩に組み合わせた、サザン・ソウルのようなイナタ臭さと明るさを併せ持ったのが#5『Undertow』である。このチープになる一歩手前のキーボードアレンジと、古臭いコーラスワークが不思議な彩りをこのポップロックナンバーに与えている。しかし、どの曲も丁寧でありつつも、1曲ごとに変化に富んでいて飽きることがない。
#6『Wrecking Ball』もMarcの弾くヴァイオリンとメロトロンがアダルト・ロックのフェロモンをぷんぷん匂わせつつも、一緒に演奏されるペダル・スティールやラップスティールが、やや捻りの入ったルーツロックのしっかりした足腰の強さを主張してくれる、ノスタルジックさえ感じてしまうバラードである。
#7『Uptown Train』はもう極上のルーツ・ポップ&ロックナンバー。それだけしか表現できないようにポップでハートウォーミングである。直球的なアプローチのメロディであるのに、これまたシティ感覚というか、どことなくブリット・ポップ的な華やかさとマイナー・コード寄りの手触りがあり、正体不明なクロスオーヴァーな感覚が耳に心地よい。
かなりエッジの鋭角的なロックビートが聴けるのが、ミディアム調子ながら力の入ったポップナンバーである#8『Seven On The Line』である。コーラス部分でのアメリカン・ルーツロックというか、ど真ん中なアメリカンロックの流し方にはもう身体が無意識にリズムを刻んでしまう。
#9『Nothing Gets Me Down』はバンジョー、アコーディオン、ペダルスティールといったルーツ楽器がメインを張る、カントリーポップという印象の強いレイドバックしたナンバーである。相当田舎臭い西海岸風カントリーナンバーであるのだが、ベタなダサさを不思議にそれほど感じさせないのはこのバンドの特徴と言って良いだろう。
パワフルなスライドが活躍する、エモーショナルなバラード#10『One More Song』は間違いなく、このアルバムではトップクラスの出来なナンバーだろう。産業ロックの香りすら思い出してしまう、仄かにもの悲しいメロディラインとアクースティックとエレキギターの巧みなフュージョン。そして、ウィルツァー・ピアノであるだろう鍵盤の地味だけれどもサウンドを厚くする好サポート。ルーツバラードというよりも、HRバンドがアクースティックナンバーをキラーシングルにしていた頃のL.A.のシーンに溢れていたパワー・バラードを懐かしくさせる激烈にメジャーな1曲だ。
そして、やや鬱な雰囲気で、哀愁を込めて淡々と歌いこまれるラストトラック#11『Anything』。Beatlesの名曲『Strawberry Fields Foever』を連想するようなアコーディオン・ライクなアナログ・シンセサイザーの単調なコードのリフレイン。ミステリアスというよりも、何処かの廃墟でうらぶれた爺さんが弾き語っているようなイメージのある、とても斜陽感の存在する曲だ。
以上、11曲。直前に紹介したThe Welterweightsほどのストレートで無虚飾なロックではないけれども、ルーツとモダン・ポップの両要素を最大限妥協させているバンドであり、相当貴重である。このルーツロックのさりげない土台を大切にして、安易なパワー・ポップに走らないで欲しいものだ。
是非、またロスの乾燥した過ごしやすい大気の元で新生バンドのライヴを見たいと夢見る今日この頃である。
ちなみにWallflowersの3枚の合計点数は順に 70点+200点+マイナス200点=70点
Five Easy Pieces&Jukebox Junkiesは 55点+75点+90点=220点である。普通は100点満点であるが、200という極端な点数に込めたのが正直な気持ちである。 (2001.12.26.)
 Straight For The Moon / Little Blue (2001)
Straight For The Moon / Little Blue (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Acoustic&Southern ★★★ You Can Listen From Here
何処までも青く、青く・・・・・・・・・・・・。
Blue−青には色々な想い出がある。自分で体験したことや人づての伝聞にしろ、兎に角、心に残ることが多い色であることは確かである。
モンゴルの大草原に被さるような青・青い空。留学中に当時、モンゴルの国費学生としてトロント大学に来ていた女性は、あの空の色は草原に生まれたものなら絶対に忘れないと、常に口端に昇らせていた。近代化と社会主義の崩壊の只中であった時代の90年初頭。また旧来の遊牧生活と都市にへばりつく欧米型の生活の軋轢。
現在、彼女が激動の90年代をどのように過ごしたかを知る由もない。が、誇らしげにというよりも、残してきた恋人を想うように彼女が語っていた「青い屋根のように広がる空の色」は著者の心の中では既に勝手な心風景画が出来上がっている。死ぬまでには是非、かの国に足を運んで、その青を見てみたいものだ。
昭和20年、日本を焦土と瓦礫に変えようとしていた米国空軍の爆撃に対して、三式戦闘機「飛燕」で本土防空戦を経験した、知り合いの元陸軍空中勤務者(旧帝国陸軍ではパイロットのことをこのように呼称した。)の方が常に遠い目をして語っていた、成層圏の青。偏西風に乗って飛んでくるジュラルミンの剥き出しの怪鳥、B29と実弾で殺し合いをしたこの方は常に言っていた。「あの1万メートルの空の色は、旅客機なんかでは経験のできない、そう海の底に寝転んで揺れる水の青を見ていたように非現実的な青さが深かった。」
この方も故人となって20年近くが経つが、彼の体験は拙い文章ながら大学ノートに筆者の文字で綴られていて、何時かどのような形でも良いから発表したいと思う。
「何時還れないかも分からない死の危険があっても、与圧のないコックピットに身を押し込んで氷点下の世界を飛んでいても、あの空は美しかった。」
筆者は何回かジャンボジェットに乗り、成層圏を飛んだが、彼の見たような空にはお目にかかれないだろう。が、空の深さは小さなジャンボの窓を通しても曲りなりに感じることはできたと信じている。
これほど劇的な青でなくても、筆者の個人的な経験でもBlueという色が浮かんでくる体験は数え切れない。長い宙ぶらりんなモラトリアム生活から脱却して、勤め人になることを決め、住み慣れた土地を離れる直前は憑かれたように朝方の街を徒然なる侭に歩いたものだ。その時に見上げた朝焼けの群青から空色に変わる青は忘れようのない感傷と共に今でもよく覚えている。
また、暑い夏の日、ぶらりと泳ぎに行った渓流の淵。その蒼黒い水の色の、まるで魂を吸い込むように招くような色はついつい飛び込みたくなるような衝動に駆られてしまう。水を見るのが好きという些か枯れた性癖のある筆者には、水の青さというのは抗い難い誘惑が存在する。つい全てを忘れて飛び込んでしまうような。
そのようなとりとめのない思考をかき乱してくれる名前とタイトルとジャケットを、全部ひっくるめて持っているバンドのCDを今回は紹介したいと思う。
Little Blueというバンドを。
Blueという単語は、「憂鬱」や「悲しみ」を顕す色と英語ではされている。また同時に「晴天の霹靂」といった「驚愕」の感情を比喩化するためにも使われることもある。(Blue IceとかOut Of The Blueとかいう口語表現にね。)
が、それらのややネガティヴな感情を暗喩するだけの色ではないのだ、Blueは。
空の蒼、海の青、というような自然界にある生命の謳歌、風景の雄大さや美しさを表すにもBlueは使用される。
このLittle Blueの最新アルバムから感じられる、彼らの創造する「小さな青色」は、どこまでも続く青い海や青空、という爽やかな青さは皆無ではないにしても、少々しか瞼の裏に浮かんでこない。
むしろ、テレビのドキュメンタリーで見るような海の中層、これを想わせる。
光がまだ届く水深の、どこまでも懐が深く、目線を下げれば果てしのない深海底が暗く横たわり、また目線を上げれば陽光に満ちた海面を脳裏に描けるという類の不思議な空間の拡がりとも言うべきか。Deep Blue−紺碧でもあれば、Sky Blue−蒼穹の青にもなり得るような彩り。
自然界に例えれば、このような青さを想像させずにはいられないサウンドである。また自然を感じれないような青さというべきだろうか、例に挙げれば、仕事で疲れた際に、ふと仰いだビルの谷間から見えたくすんだ青空、濁り切った都会の用水路に写る、幻影のような空の青、このような底なしの不安や苛立ちを芽生えさせるような空虚な青さも包括するくらいに腕(かいな)の廣い、青い空間を思わせる音楽が、この「Straight For The Moon」には存在しているのだ。
かなり観念的な思考を文章にしたため、伝わるかどうか心配であるけれども、ジャケットを眺めながら寝転がり、この月と小さな青という言霊が込められたアルバムの音響を耳で拾っていると、まさに思考は千地に乱れていくが、最終的にはその音世界への感動ということで収束していく。
つまり相当心の芯まで染み入ってくるアルバムであるということだ。
しかも、アップロードしたジャケット写真を見て頂ければ、これだけでこのアルバムが欲しくなるリスナーがいるに違いないと断定している。
このジャケットが気に入らないとか、おっしゃりやがるヒトはここで戦略的撤退(何やそれ?)を許可するので、Lifehouseの気色悪いジャケでも抱いて寝れ!!そして悪夢を見てうなされるように。
ということで、誰が何と言おうと、筆者的に2001年のベスト・アートワークはこの「Strainght For The Moon」に決定である。印象派、特に後期の印象派のような春の夜の朧月のような淡い筆使い。写実的ではないけれども、このぼんやりとしたタッチからは、月夜の海の風景が浮かんでくるようではないか。
配色的には非現実的な色をキャンバスに載せているようだが、この紫の夜空やオレンジの月光というような取り合わせは、奇妙な非日常観という描写の裏側に、暖かい日常的風景への素直な感動の波動が伝わってくるようだ。
幾つかの映像的な変換を重ねて、ジャケットの色合いがやや黒色系が浮き出た写真になってしまったが、実際のジャケットに見られる色出しはもっと淡く薄いのである。まあ購入してもらえば一撃で分かるだろうけど。
例え、Little Blueの1stアルバムを結構評価していたという下地が無くても、このジャケット、そしてLittle Blueという繊細そうなバンド名、加えて「Straight For The Moon」というタイトル。以上の三要素は全て筆者の感性のストライク・MaxSpeed 160kmクラスのど真ん中である。始めに綴ったように作者には青色に対する拘りがあることが原因の一つではあるけれども。
よって、このバンドを何も知らなくてもジャケ買いしていたのは疑いなく、100%の確率で起こっていただろう。何につけても、このジャケットは筆者の妄想というか映像的なイメージを掻き立てるものがある。デヴューアルバムのジャケットからは、ここまでこのバンドの名前からの想像が派生しなかったのであることを再確認するに及び、やはりこのジャケットと名前とタイトルが、全て心の琴線にがっちりとフックを引っ掛けたのは間違いない。
実際にLittle Blueの曲を何の試聴もせずに、躊躇も無く購入した。
結果は言わずもがな、大正解である。1stアルバムである「Angels,Horses&Pirates」の良作を更に優越する傑作アルバムである。
定番であるけれども、直前でアルバムタイトルの如く「月に向かってまっしぐら」に吠えているが、Lifehouseのジャケットがスゲエかっちょ良くて、このアルバムのアートワークがピンと来ない人もそれは存在するだろうが、このジャケットよりもLifehouseのジャケットの方が格好良いという感性のリスナーがこのアルバムを聴いてもダメかもしれないということはお断りしておこう。
何の引っ掛かりも無いような人工石やコンクリートのオブジェのように退屈極まりないLifehouseのオルタナサウンドと比較して、このLittle Blueの音楽は実にロックでポップなのはここで紹介する以上は、当たり前であるけれども、プラスアルファとして、叙情的な美しさと、「小さな蒼」というバンド名をそのまま音楽性に冠したようなアクースティックな繊細さ。これらのアダルト・コンテンポラリーロックの気配の濃厚な、アメリカンロックの美麗な側面を具現化したような要素が、サザンロックの泥臭さ−このバンドの別な持ち味、と融合して、最高の化学反応の如くに物凄く深みのある音楽を創り上げているのだ。
そう、このバンドのもう一つの武器はアクースティックな美と他に大きなものがある。それはかなり古典的なSouthern Rockである。
1stアルバムの「Angles,Horses&Pirates」の批評で、辛口のRolling Stone誌に★を4つ半も付けられるという、(但し独逸出版の海外版であるけれども)新人にしては稀有な評価をされたLittle Blueであるが、その当時に売り出されたコピーは
「Acoustic Rock And Blues With A Touch Of Classic Southern Flavor」
であった。この2枚目のアルバムでも、キャッチーでメロディアスなアメリカンロックの曲に挟まるように、ポップなサザンロックナンバーやブルージーなメイド・イン・サウスのナンバーが存在している。
このLittle Blueというロックバンドの魅力というか、構成要素を列挙してみると次のようになるだろう。
■1.アクースティックな透明感溢れるサウンド。
■2.エレクトリック・インストゥルメンタルの直球的でポップなエネルギー。
■3.サザンロックの泥臭さにブルースの影響。
このサザンロックのヘヴィなロッキン・ブルースというか泥臭いロックサウンドが存在するからこそ、Little Blueは「単なるフォーキィーでポップな現代のアクースティックバンド」で終わらずに、説得力のあるロックバンドとして成り立っているのではないかと思うのだ。
このあたりは下手を打つと、非常にこの世に溢れている定番なのだが、「ポップな良曲とアンキャッチーな捨て曲の繰り返し」と呼ばれるようなアルバムや、「故意にポップを抑制して、偽物の芸術性を捏造しようとした自己満足的な」レコードを生み出すことになり兼ねない危険性を孕んでいる。
こういった要素を持つ、特に後者のマスターベーション的なボケタレさが嫌悪して止まないオルタナティヴ・ヘヴィネスなのであるが、これを話し出すと、また罵詈雑言になるので、自主規制。
と、Little Blueの話を続けよう。Bluesライクなトラックが結構混じっていることから、もしかしてこのバンドのネーミングの由来は「ブルースもちょっとばかしプレイするねんで〜。」という意味も含まれているかもしれない。今度本人達に確認してみよう。
また脱線したので、更に再軌道修正。(汗)
Little Blueの場合、かなり酸性なブルース的重さを持ったトラックが、アダルトロックの美しい曲と混在しているのが特徴である。が、捨て曲というレヴェルにまで下がった曲は只の1曲もない。サザンロックのヘヴィな感覚が詰まったナンバーもアンキャッチーと言うほど聴き手を無視したものではないし、この重くてコマーシャルさの少ないサザン・ナンバーが全体を引き締めるのに大きな役割を果たしていると思う。
結構メジャーなアーティストでさえも行う組み立てに、勝負曲の前後に捨て曲やノンコマーシャルなナンバーを配置して、シングル曲を引き立てさせようと言う意図が見え見えのトラック・アレンジメントがある。けれども、このLittle
Blueにはそういった悪い意味で陰陽やギャップを刻もうという企みはない。
元来、古典的な南部ルーツを表現方法の一環にしているバンドであるからだ。もっとも、このようなサウンドを良心的に演奏するバンドは、現在のアメリカでは殆ど脚光を浴びることがないのだが。
些か好意的な解釈になるけれども、1stアルバムでは更に南部ロックの影響が顕著であったのが、今作ではかなり甘いポップロックナンバーが増えたため、メリハリが付いたという効果が増えた故の変化と考えるべきだろう。まあ、とはいえ、Little Blueくらいのレヴェルの高いバンドであるなら、終始貫徹でアクースティックなポップアルバムを作成しても、モノトニアスな流れに染まることなく聴き飽きの到来しない超良作を作成することは完全に間違いないことだろうから、アシッドな辛味のあるサザン・ナンバーを排除した作品を創ってくれてもいいなあ、とは正直思ったりもするのだが。そう、例えば2000年のベスト3アルバムを届けてくれたPat McGee Bandのように。
兎に角、このようにアダルトロック、アクースティックサウンド、エレクトリックなロックテイスト、キャッチーであったりなかったりするサザンロックの要素、と多様な音楽性を包括したこの「Straight For The Moon」は単にRoots Rock
の一言ではカヴァーしきれない、幅の広範なオルタネイトなロックサウンドを提供してくれる、一昔前のメジャーなロックアルバムに匹敵するレコードとなっている。
アメリカンな土臭さはそれ程と言うか殆ど発散させていない。が、Southern Rockへの歩みよりと、アメリカン・ルーツロックへの敬意を払った堅実なサウンドクリエイトが、やはりRoots Rock & Popの魅力も表現してくれるアルバムであることは違いないのだが。上品と言うか、巧みな手法でルーツテイストの突出を抑え、円やかな音楽に仕上げているというような、音の織り込み方を成功させているバンドと賞賛すべきだろう。
例えるなら、やや方向性は違えども、Counting Crows、Wallflowers(3枚目は銀河の果てでワープアウトに失敗して幽霊船となってくれて一向にかまへんので除外)といった有名バンド、そしてインディ音楽ではMr.HenryやFive Easy Piecesのように多彩で聴けば聴くだけ新しい発見があるようなサウンドを想像して貰えれば良いと思う。
アクースティックが目立つとはいえ、サッドやスロー・コアのようなクソ下らない、「Healing」な音楽を張子の虎のように空虚に構築した中身の無さは皆目である。こうやって土台のしっかりとした音楽性の上に重ねられた音が、如何にうわっついたものでなく、きっちりと存在感を示してリスナーの耳に余韻を与えつつ入って来るか、という効能が明確に理解できるバンドであるのだ。
さて、今回の「Straight For The Moon」はメンバー的に前作のカルテット体制から5名にメンバーが増え、しかも3人が新メンバーとなっているが、サウンド的には成長が著しいというポジティヴな面を除いてはそれ程の路線変更はしていない。前作よりも綺麗なAdult Contemporary風の曲が増え、相対数においてゲストミュージシャンが減ったくらいだろうか。
バンドの経歴等は最後に記述するとして、各曲を誉める(もう決めてる)前にバンドのパーマネント・メンバーだけは紹介しておく。共にリードヴォーカルを担当し、結成から残っているメンバーはこの2名。
Steve Postell (L&B.Vocal,Guitars) , Michael Jude (L&B.Vocal,Bass) に新メンバーが3名。
Damian Smith (L&B.Vocal,Guitars) , John Michael (Drums,Percussion,Vocals)
Jed Leiber (Piano,Organ,Keyboards)
以上の5名を中心にかなりのレヴェルの高い演奏が聴けるこのアルバムは、最初の曲から、既に聴き手の心をしっかりと捕らえて離さないナンバーが流れてくる。
その#1『Travelin’ Man』は嘗てSteve Postellがローカルレーベルからリリースしたアルバムのタイトル曲であり、再録版ということだが、是非、このSteveのアーリー・ワークスを聴きたくなるようなナンバーである。アクースティックで何処までも軽やかなギターのリフから、Jedのオルガンが加わり、電気ギターが加わり、ベースとドラムがリズムを付けていく、とメンバー5名だけの演奏で進行していくこの曲。リード・ヴォーカルは当然ライターのSteve。1stアルバムからの3年間の熟成を思わせるように、Steveのヴォーカルはやや渋みを増しているが、ややハイトーンで甘い美点は全く変わっていない。そのリード・ヴォイスに他のリードヴォーカリスト達が西海岸ロック風の爽やかなコーラスをハーモナイズさせ、Steveのギターソロが奔放に走り回る。1曲目からポップなアダルトロックが炸裂している。炸裂と言うほど五月蝿いナンバーではないけれども。(笑)
#2『Willow Lane』ではかなり驚くべき名前がソングライター、そしてヴォーカルとしてもクレジットされている。何と、Hall&OatesのJohn Oatesが曲を共作し、ヴォーカルでも参加しているのだ。しかもHall&Oatesと長年一心同体のように活動している、いぶし銀のミュージシャンT-Bone Walkがマンドリン、ピアノ、ギター、ベースと言った楽器を担当し、マルチミュージシャン振りを見せ付けている。
更に、元Bryan Adams BandのキーボーディストであるTommy Mandelがハモンド・オルガンで参加。これまた驚きである。彼の名前は久方ぶりに発見した気がする。このような実力派でしかも著名なミュージシャンの協力は、Little Blueのメンバーの殆どが着実なバックミュージシャンやセッションマンとして活動を積み重ねてきた成果の現れであると思う。曲は、これまた非常にジェントリーなナチュラルなポップソングである。Steveが担当するバンジョーにTom T-B Walkの爪弾くマンドリンが、土臭さよりもカラリとした明るいラインを紡ぎ上げ、Tommyの指使いが見えてくるようなリリカルなオルガンプッシュが、曲に厚みを付けてくれる。#1と同様かそれ以上に、アクースティックでありながら、程よい味加減のポタージュ・スープのような濃さも併せ持つ極上の舌触りのナンバーである。
今作ではソングライターの中心はSteveと鍵盤及びメインのプロデュースを担当のJed Leiberである。デヴュー作からのSteveの盟友、Michael Judeはメンバー全員の作扱いになっている2曲に関わっているだけであるけれども、彼の独特の浮遊感のあるハイキーなヴォイスが#3『Where You Are』で活躍している。非常に悲しげなメロディと写実的ななピアノプレイが印象深いナンバーであるけれども、ソングライターがこれまた驚きの人物である。80年代にメジャーでかなりのヒットを記録したメタルバンドWingerのフロントマン、Kip WingerがSteveとJedとこの曲を作曲しているのだ。この方向性のアルバムから考えると、かなり異例の起用であるとは思う。が、この産業ロックのマイナーバラードに地脈を通じるような哀愁曲調は、Wingerをアンプラグで聴く様にも思えてくるから不思議である。どちらにしても、欧州的なメロディを持った、Little Blueの音楽性の広さを実感させるナンバーだ。
#4『Color Of Love』では再びJohn Oatesがペンを取り、Steveとのコラボレーションを聴かせてくれる。何でもJohn OatesはSteve Postellと共同で、合間を見つけては頻繁にレコーディングに入っているとのことで、2002年発売予定のHall&OatesのアルバムにはLittle Blueがコミットしてくる可能性もあり、John Oatesと組んでSteve Postellがセカンドソロ作をリリースするかもしれないということで、かなり期待させる要素がある。
が、この曲でリードヴォーカルを撮るのは新加入のギタリスト、Damian Smithである。SteveやMichaelのハイトーン系列の声質とはやや異なった伸びやかなソウルフルな唄い方をするヴォーカリストであり、サザンというよりもファンクロックなこのナンバーには誂え向きのヴォーカリストである。クニャクニャと鳴る、酸味の効いたギターに、ブルージーなオルガンが絡み、更にホーンセクションまで加わり、Tower Of Powerのナンバーを思わせる黒っぽいファンキーなリズムが熱く演奏される。John Oatesも加わったバックヴォーカルの畳み掛けるようなハーモニーはブラック・ジャズ的な雰囲気を出すことに一役買っているだろう。彼らの南部魂を見せ付けられる異色作だ。
次の曲は間違いなくこのアルバムでも注目曲なタイトル曲である、#5『Straight For The Moon』である。これまたJohn Oatesが関わった曲であり、当然の如くバックヴォーカルでも参加している。が、Johnが手を入れた曲の割には、壮大でロックで劇的なバラードである。後半のブリッジで♪「I’ll Be Free Again」と熱く唄うJohn Oatesのソロ・ヴォーカルも聴くことができ、Hall&Oatesファンにも垂涎のナンバーとなるだろう。
歌の内容も自由交易港に生まれたと言う主人公が、海に生きる自由を求めると言う内容の、雄大ですっきりとした感情を歌い上げたものであり、広大な海原と言う自然に囲まれている喜びを「月に向かって進もう」と拳を天空に突き上げるようにして謳歌している心情がひしひしと伝わってくる。リリカルなピアノに乗せて、各楽器がデライトフルに、しかしながらしっかりと抑制の効いた演奏を聴かせてくれる点も素晴らしい。この曲もルーツロック云々を超越した、超一流のロックバラードである。どちらかと言うとベイエリアや東海岸ロックのスマートで艶やかな音の構成をしている曲である。
#6『Fly Away』はあのDavid CrosbyやJames RaymondとロックバンドであるCRPを1998年に結成し、精力的にアルバムをリリースしているJeff Pevarがマンドリンとヴォーカルで参加している。また曲も彼との共同作品だ。CRPのフォークテイストを彷彿とさせるようなアクースティックでクールなナンバーである。ピアノの流麗な音やそのラインに被さるオルガン、そしてさりげないマンドリンの音色がとても落ち着いた音色で混じりあった不思議な感じがするナンバーである。
Jeff Pevarは#11『Going Home』でもギターソロを披露して、もう1曲の参加をしている。このナンバーもヘヴィでアシッドなスウィング感覚を聴かせる、サザンロックというかブルース&ファンキーな曲である。#4よりも更にアンキャッチーで酔いどれオルガンやギターが炸裂するロックであり、アルバムの中で一番ハードなチューンであろう。かなり歪んだギターの爆音が飛び込んでくるので、やや全体から浮き上がってしまう印象は否めないか。捨て曲ではないが、あまり好きなタイプではない。が、このブラックファンクな感性がLittle Blueをふわふらと漂うような軽いバンドに見せない重石であることもまた確かなのだろう。
#7『Take Me Back』は再びリード・ヴォーカルが暫く続いていたSteveからDamianにバトンタッチする曲である。このナンバーと次の曲#8『Hard Day』の2曲はLittle Blue名義の作品となっている。
#4で初めて聴くことになったなったDamianのヴォーカルは曲のタイプもあったせいか、もっとヴァリトン気味のしつこいヴォイスに聴こえたが、このナンバーのような明るい、ポップな曲では朗々とした良く通るヴォイスとして、かなりの存在感を持っていることが判明する。乾漆なピアノサンプリングやアクースティックピアノがクルクルと転がる、ポップスのフックをがっちりと抱えたロックチューンで、ここまでのナンバーでは一番軽快であろう。兎に角、鍵盤が非常に全体を引き立てているアップビートな曲である。インタープレイでのピアノ、B3、シンセサイザーの多彩な鍵盤がブルージーな展開を見せてくれるのも只の終始ポップな作品よりもインパクトが強い。
#8『Hard Day』はもう、もろにニューオリンズR&B風のサザン・スウィング調な曲である。こういった粘っこいメロディを唄うのが定番のようなMichael Judeが案の定リードを担当している。ここまで数曲、ブラックベースと言うか南部ロック風のトラックが挿入されてきたが、この曲はかなりキャッチーである。途中でリード・ヴォーカルをSteveが交代する場面もあり、ガンガンと引っ叩かれるピアノの鍵盤に、ブンブンと唸るハモンドオルガンの息吹といい、かなり古典的なルーツ・ジャンプソングである。こういった曲を入れてくるのは、このアルバムの場合はLittle Blueというバンドの多様性を示すのに一役買っているが、アルバム全体の出来がよくないと、オリジナリティに欠けるという謗りを受けかねないくらい、古臭い風味のナンバーであることもまた確か。敢えて、こういったブルースロックの定番を入れてくるところは彼らの余裕の現れだろうか。
#9『Best Kind』はバンドのオリジナルメンバーのSteveとMichaelのアクースティックセットにゲストのヴァイオリンを入れただけのフォーク的なアクースティック曲。前の#8がバタバタしたタテノリロッキンブルースであったため、落差が激しく、両曲のポイントが明確に際立たされていて良い構成であると思う。なお、このヴァイオリンを弾いているJoel
Derouinという人はElton JohnやPaul McCartneyのツアーでヴァイオリンを弾いているそうだ。
そして#5の壮大なバラードを再び、という感の強いJedのエモーショナルなピアノがリフでソロを展開する、#10『See Me Now』。この曲は下世話な表現で言い換えると、HRバンドのパワーバラードのような分厚いアレンジと北欧メタルの哀愁を思わせる出来になっている。これまたルーツロックと言うには縁遠いナンバーであり、やはりAdult
Comtenporaryのチャートに登場しそうなバラードである。ヴォーカルはSteveとDamianのツインリードで、たっぷりと感情を込めて歌い上げられる。#5と甲乙の付け難い良作であるけれども、#5の爽やかさと言うか廣い歌世界が見えてくるような歌詞でないためか、筆者は#5を上位に据えている。
そしてラストのアナログ的なノイズから始まる、まさにアナログレコードに針を落としたように展開する、これまたニューオリンズ・ジャズと言うか、スタンダードの大定番『Keeper Of My Heart』のカヴァーを何と最後に持ってきているのだ。ムーディ・ブルースと言うに相応しいジャジーで4ビートの、全く斬新な解釈なしでアレンジされたこのクラッシックな曲の♪「Like A Stardust Melody」の著名なフレーズを滑らかにソウルタッチで唄うのは、やはりMichaelである。こういった古さを隠そうとしないようなアレンジな曲では彼の多彩なヴォーカル・ワークの一環が見て取れる。#3のようなハイトーンな唄い方も、この曲のようなスムーズな歌い方もこなせるヴォーカリストがバンド内にいるのは非常に有利なカードとなっている。しかし、まさか、このようなロック時代以前のポピュラー・スタンダードを最後に据えるとは、かなりの冒険と言うか、真剣な遊び心を感じてしまうのだが。
さて、最後になるが、このLittle Blueという日本では恐らくこのHPでしか取り上げないであろう(冗談にならんとこが哀しいが。)バンドについて簡単に述べて結びとしよう。
BeatlesやJimmy HendrixそしてMarvin Gaye、Joni Mitchell、更にSly & The Family StoneやThe Bandといったロッククラッシックをこよなく愛しつつも、Foo FightersにThird Eye Blindといった現代のオルタナティヴ系のバンドも注目していると言うSteve
Postellがバンドを創り上げた人物である。ミュージカルの音楽や映画の音楽の曲を書いたり、ミュージカルMiss Sigonのサウンド・ディレクターとしてツアーに同行したりと、裏方の仕事は長年積んできた人であるようだ。自分でもソロアルバムを出す前にChain O’Foolsというバンドをニューヨークで結成し活動していたり、ニューヨークでライヴハウスを経営したりと、かなり手広く音楽ビジネスに関わってもいるようだ。
自身のソロアルバムを契機として、バンドとしての演奏に熱意を感じたSteveがソングライティングのパートナーであったMichael JudeとLittle Blueを結成し、Elton John BandのドラマーであったSteve Hollyやこのアルバムには曲の提供と言う形で関わっているピアニストのPeter Adamsらと1stアルバム「Angels,Horses&Pirates」を録音し、独逸のインディレーベルから発売したのが1998年であった。
それから3年の間を、インディミュージシャンにはやや長過ぎる間隔を空けて2001年の秋に、これまた本国アメリカで無く独逸の大手レーベルBlue Rose Recordsから本作「Straight For The Moon」をリリース。メンバーの交代については前述してあるように3人が新顔となっている。中でも鍵盤弾きのJed Leiberはプロデュースの中心となり、殆どの曲に共作者としてSteveと名を連ねているという具合に、かなりのウェイトを占める存在になっているようだ。自分でもLAでレコーディングスタジオを経営し、プロデュース業を兼任しているそうな。
新ドラマーのJohn Michaelもセッションミュージシャンとしてかなりのキャリアのある人のようで、現在もBilly Joelのレコーディングに参加している他に、Trevor Rabin、
AmericaそしてMark Farnerというアーティストのツアードラマーやレコーディングアーティストとして活動してきた人。
リードヴォーカルも担当するベーシスト、Damian Smithはシカゴで10年以上バンドを結成したり、ソロ活動をしてきた人であり、現在は自分のソロアルバムを準備しているらしい。
このようにメンバー全員がサイドプロジェクトを持った多忙なミュージシャンの集まりである。
核メンバーのSteveとMichaelはこれまた共同で、A Little Less BlueというLittle Blueの完全アクースティック版ともいうべきアルバムを製作中とのことだ。こちらもとても楽しみな企画である。
しかし、この素敵な名前を持つ、素敵なアメリカンロックを演じるバンドが、アメリカでCDが発売できない状況は如何ともし難い。2枚とも独逸の発売である。ある意味、カントリー・ロックまでルーツに染まっていないポップロックな音創りをするバンドには、受け皿は一層少ないのかもしれない。一般的な音過ぎて、ジャンルに合わせて特化を始めた米国のインディレーベルでの落ち着き場所が無いのかもしれない。
レコーディングはアスペンの自然に囲まれたスタジオとLAのJedが所有するスタジオの両方で行われているらしいが。アメリカでのツアーは殆ど予定されていないらしく、どうも冷遇が過ぎるようである。とても情けないのはアメリカの腐った市場であろう。
兎にも角にも、この暖色系をあしらったジャケットに何らかの共感と美を覚える人なら絶対に当たるサウンドが詰まったかなりの奥行と広さを有したポップロックの名盤である。2枚目にしてこのような傑作を創ってしまいこの先大丈夫だろうかという心配まで覚えてしまうのだ。
まずは、購入して、聴いて、彼らの青に染まって欲しい。が、Little Blueの織り成す音楽は、冷たく蒼い月光のような美しくも冷淡なものでなくて、このジャケットの月の明かりのようにほんのりとした暖かさがある。繊細さと豪快さを1枚で味わえるお得なアルバムである。かなり強力に推薦したい。 (2001.1.13.)
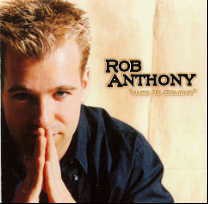 Hard To Believe / Rob Anthony (2001)
Hard To Believe / Rob Anthony (2001)
Roots ★★
Pop ★★★★★
Rock ★★☆
West.Coast&Acoustic ★★★★★
You Can Listen From Here
2001年はMarshallcityという、全然西海岸出身でないのに嘗て西海岸ロックと呼ばれた、The ByrdsやEagles、Buffalo Springfieldを現代に継承するかのようなバンドに出会えたが、今回紹介するRob Anthony(一時はRobert Anthonyと名乗っていたが)も非常にWest Coast Rockのクラッシックな雰囲気を芳醇に抱えているアーティストである。
この当HPで紹介するアーティストやバンドの中ではかなり例外的にハンサムで爽やかそうな(笑)青年は、これまた西海岸出身でないのに、とてもカリフォルニア・サウンドを匂わせる箇所も、Marshallcityと共通項であるところが興味深い。
かなりレイドバックして、全体的にルーズなサウンドプロデュースで独特の味わいを表わしているMarshallcityとはかなりの面で細部は異なるのだけれども、大まかな筆者の印象として、両者とも第一聴で「ウエスト・コースト」という単語が脳裏に即座に浮かんできたことは共通である。
さてさて、この堂々と自分のスナップ・ショットをジャケットにあしらっているRob Anthonyという30代を間近に控えた青年は、アメリカ中部のウィスコンシン州はミルウォーキーの出身である。活動拠点もミルウォーキー周辺を基盤にしているとのこと。
ミュンヘン・サッポロ・ミルウォーキーと“日本のみ”で3大麦酒生産都市に数えられるミルウォーキーにては、大手のビール工場見学ツアーがあり、勿論ツアーの終わりには麦酒が幾らでもロハで飲めると言う嬉しい特典が着いてくるので、是非当地を立ち寄る方がいるなら一杯飲ることをお薦めしておく、ま余談ではあるが。
余談ついでにやはり札幌を世界3大の麦酒都市にするのは、身びいきがすぎるようにも思えてならないのだが、まあどうでも良いか。(笑)これ以上続けると全く関係のない「アルコールよもやま噺し」を始めてしまいそうなのでこのへんでミルウォーキーの地場産業に付いてはなるべく言及しないように努力はする。
しかし、酒精の一大生産地をバックグラウンドに持ちつつも、Rob Anthonyの音楽には「酔っ払い」とか「飲兵衛」とかいうような形容が可能な要素は皆無である。(って、早速引き合いに出してるやん!)アメリカの片田舎にて、バーボンの匂いに満ちた煙草の煙が漂うような薄暗いバーとかで声を張り上げて歌うというような、濃い目の南部ロックなテイストは全く皆無。
俗に言う、ブルース、サザンロックといったようなサウンドの質量で勝負する系列のルーツロックとは全く趣を異にしている。また、Whiskey Soaked Musicと英語で表現されるような木目の粗い、攻撃的なロックンロールの畳み掛ける緊張感とスピード感を堪能するという類のサウンドでもない。
アルコールに例えると、やはりミルウォーキーでも大量に生産され、日本では夏に飲むのが美味いとされている麦酒の口当たりの良さと、喉ごしの快感、そしてきつすぎない癖の良い意味での無さが特徴といった音楽性を、この男は創り上げているように思えるのだ。(ちなみに独逸人には『ビールは夏』というような概念は希薄である。ま、日本より相当長く麦酒を飲んでる国だから当たり前かもしれないが、彼らに言わせれば『ビールは一年を通して飲むもの』だそうだ。歴史の違いよのう。)
誤解されやすいかもしれないけれども、敢えて麦酒を例に取ったので続けると、他のアルコール飲料と比較すると度数の低い麦酒と似通っている、ライトな軽いサウンドであるとも表現できると思う。当然ながら、これは底が浅いとか、全く印象に残らないイージー・リスニング風の音楽を演奏しているというネガティヴな側面を含むものではない。
現在のアメリカの中心となっているような、ラジオ用の垂れ流しにしか使えないようなヒットソングや、リスナーのことよりも自分の欲望のはけ口を一番に表現することで芸術性を気取ろうとするオルタナティヴ系の音楽に見られる自慰行為的な独り善がり故の、退屈さ・感情移入のし辛さは微塵も感じ取ることはない。
ここで筆者が言わんとする「軽さ」というのは、その普遍的なポップセンスと優しさに満ちた音創りからの恩恵とも言うべき間口の広さと、音が耳に流れ込む際の滑らかさ、ということである。
利き酒やコンテストに出されて、自称プロや通が唸る、というような舌触りよりも、誰でも気軽に飲むことができて、しかもどれだけ飲もうと嫌にならない親しみの易い庶民の味、こう表現し直しても良いだろうか。
小難しい芸術性を詰め込もうとして全くポップミュージックの基本を忘れてしまっているヘヴィ・ロックや大英帝国の現在の主流な音楽とは全くその志が違う、誰でも抵抗無く聞き耳を立てれるとっつき易さが存在するのだ。
得てして、こういった良心的なポップロックは日本においては、普通のアルバムで誉める点が少ないという不可解な評価基準により、殆どメディアにも取り上げられることが無い。まあ、今に始まったことではないが、無理してマス・メディアの評価している音を聴いて良い物だと自己欺瞞で通を気取るよりも、麦酒で風呂上りに一杯という飾らない基本を基本で演じているような、斬新さが無くても万能的なポップミュージックのプライオリティを掲げたアルバムを聴くほうが何倍も健全であるとは思うのだが。
またもや愚痴になりそうなので、もう少し具体的なRob Anthonyの音楽性についてスペースを割いてみたい。
まず、筆者に購入を、音を全く聴かずにオーダーを出させた殺し文句が、アメリカの音楽雑誌に紹介された次の一文である。
“Millennium Eagles With A Touch Of Mellencamp”−21世紀のイーグルス。ジョン・メレンキャンプの音を足して2で割ったようなロック−
とでも翻訳すれば良いだろう。まあ、これで買うのを躊躇しては音楽ファンの沽券に拘る問題であろう。(笑)
ところで、実際の彼の曲は、この2つの大物アーティストと比較するのはまだ不利なことは否めないので、本当に類似点があるのかどうか、主観で分析してみよう。
最初に“21世紀のEagles”というコピーに飛びついた筆者であるため、どうしてもEaglesと比較してしまいそうな予感が手元に到着する前からあったため、聴く際にはなるべく先入観なしにプレイヤーに落としてリスニングし、Eaglesと似てないからといって、いきなりマイナス評価をしないように自己に留意を促そうとしていた。
結果的に言えば、この用意は取り越し苦労というか、無駄に終わったのだが。
というのは極論するなら、Eaglesを思い起こさせる云々は別として、この「Hard To Believe」が素晴らしいアルバムであったため、Eaglesに劣るだの似ていないだのというせせこましい考えが、明後日に吹っ飛んでいってしまったからでるが・・・・。
が、やはり海外のメディアに“Millennium Eagles”と評価されるからには、著者としても何らかの考察をしてみたいという欲求を持つのは、文章を書くことに喜びを見出す類の人種の性癖−悪癖であるかもしれないが、だろう。
一口にEaglesと言っても、デヴュー当時の「Eagles」の方向性と、1995年に再結成したメンバーで作成された「Hell Freezes Over」をこの場合は外して、最後のスタジオ録音アルバムと捉える「The Long Run」ではその音楽性が相当異なっているのは、音楽ファンなら言わずもがなであるとは思う。
1970年代のフォーキィーなカントリーロックを基本とした1stアルバムと、Bernie Leadon脱退後のカントリーロックから次第にDon Henleyを中心とした幅広いロックサウンドに変遷していく「Hotel California」以降のサウンドは別バンドとまではいかないにしても相当な変化が伺える。
焦点をRob Anthonyのサウンドに戻して、RobのアルバムがEaglesと比べると(優劣ではない。繰り返すが)どうかというと、確かにEaglesとルーツを同じにするテイストを味わうことは可能だとは言えよう。それは、West Coast RockとAcoustic、Solf Rockという大枠な分類で語られる筈の要素であって、厳格に言うならば、引き合いに出すのはEaglesでなくても可ではあると考えている。無論、宣伝効果を考えれば、この偉大な先達バンドの名前を使えばエポックなことは間違いないので、売り出す戦略としては正しいだろう、些かプラクティカルな見方であるだろうけど。
しかし、Eaglesを持ち出すだけの力量を感じるアーティストであり、それだけ評価されて然るべきアルバムなのは間違いないと思うので、著者もEaglesを基準として考えてみた。
この「Hard To Believe」の全体的な雰囲気は、Eaglesのアルバムで言うと、やはり初期の「Eagles」であろう。そのアクースティックさ、軽快なカントリー・ロック風のポップソング。EaglesがそうであったようにPocoやBuffalo Springfield程にはカントリーに近いロックではないだろう。Robの歌う曲は丁度EaglesとPocoやThe Byrdsの中間のあたりのサウンドを考えてもらうと良いかもしれない。
Eaglesの作品同士で勘案すれば、「Desperado」からカントリー色を相当抜いて、「Eagles」の清涼感ある高い空の青さを、アメリカのインディアン・サマーの下で、大平原に立ち、360度四方を深い青空で覆われているような爽快感がある曲調をプラスしたような感じだろう。
つまり、アクースティックであるけれども、それ程カントリーのカラーが濃くないポップロックと思えば間違いない、Rob Anthonyのこの作品は。EaglesよりもPocoやByrdsのアクースティックさに近いようにも感じる。更にEaglesで言えば、私的に最高傑作である「One Of These Night」のルーツとアダルトなロックの分量が絶妙に配分された頃のサウンドにより近いかもしれない。「On The Border」からDon Felderの泥臭くハードなスライドギターを抜いたようなアルバム、という解釈も当たらずも遠からずかな。
まあ、聴いた回数の違いもあるだろうが、正直Eagles程の評価は(比較するほうがナンセンスかもしれない。)付けられないし、同じくEaglesの「On The Border」以降の多彩さは見ることは不可能である、この「Hard To Believe」には。1970年代当時のアメリカのメジャー・シーンでMORと呼ばれたような、あれこれとアメリカンロックの要素を詰め込んだスケールの大きいアルバムになるには、まだまだクリアすべきハードルは高いだろう。
が、例えば「One Of These Night」からのヒットシングルである『Take It To The Limit』や『Lyin’ Eyes』の甘いポップセンスを継承するようなポップさの閃きは、きっちりとRobは踏襲していると思う。
こうなると、Robの音楽は単にアクースティック系のルーツロックなだけではなく、よりオルタネイトなアダルト・コンテンポラリーロックとしての風格すら感じ始めてしまう。現代ではAAA(=American Adult Alternative)に分類もルーツロックと同時に可能な音楽性であろう。まあ、AAAに関してはかなりAlternativeなものまで最近は含まれるのであまり好きなジャンルではなくなっているのだが、筆者的には。どうでも良いことであるけれど。(汗)
結論というか、長々と述べてしまったが、Adult Contemporary MusicにRoots Rockの味付けをした、または逆という考え方も成り立つナチュラルなポップロックと考えれば問題ないと思う。ルーツの色合いが多いために、アダルトロックの大仰過ぎるきらいのある分厚いアレンジの軛(くびき)に捕らわれず、素直な中西部のアクースティックな特徴を発揮している音楽であるとも思う。
ブルー・グラスの、筆者があまり評価しないトラッドなヌルさは全く表面には出ていないアルバムではあるけれども、グラスソングの自然なアレンジを上手にポップロックとしてアクースティックに表現しているし、それで成功しているアルバムであるとは思う。要するにルーツロックでありながら都会的とまでは行かないが、親しみやすいマイルドな肌触りのある軟らかいロックミュージックであるのだ。
そしてもう一つの比較対象となっているJohn Mellencampの創り出す音楽とRob Anthonyの音楽を比べてみると、これまたなかなかどうして簡単にこれだから近似していると早急な断定が難しい。もっともこれはRobに非があるというより、John Mellencampの音楽性が特にCougarを外したりつけたりして、現在のJohn Mellenchampに改名してからはあまり良いアルバムをリリースしていないので、デヴューアルバムとしてはかなりのクオリティの高さを誇る「Hard To Believe」を持ち上げる材料に使いにくいこと。またMellencamp程にはRobの音楽がハードでもないことが挙げられるだろう。
そういった最近のMellencampの低迷振りを勘定に入れずに、考えてみるとこのオハイオ出身のロッカーが一番輝いていた80年代前半、John Cougar Mellencampのアルバム「American Fool」や「Uh-Huh」の頃の即効性のあるポップさがクロスオーヴァーするのではないかと思う。
また、毀誉褒貶の定まらない見方かもしれないが、John Mellencampの良く言えば癖の無い素直さ、悪く言うとそれなりのレヴェルの音楽は創るのだが、引っ掛かりの少ない個性の欠如、というつづめればやはりアクが少なくオーソドックスな故の美点という箇所が共通項になるのではないだろうか。
もっともMellencampは1990年代は新しい境地を積極的に求めては、お世辞にも成功とは言い難いアルバムを量産しているので、あくまでも1980年代までのMellencampと2001年にレコードを出したAnthonyのシェアするアドヴァンテージという意味である、この場合。
さて、音楽の方向性ということは大概において語ってしまったので、一番目立つというか楽器と考えても注目度合いが高いヴォーカルについて述べてみたい。
正直、このジャケットの写真は相当ハンサムに撮られ過ぎているとは思う。ライヴの写真とか見ると、ここまできりっとした色男ではないので、修正をしたのではないかと邪推すらしてしまうのだ。(笑)が、基本的には結構甘めのマスクの持ち主であることは間違いないため、ヴォーカルも甘いハイトーンな質を有した人ではないかと、漠然と想像する方が多いのではないかと推測する。かくいう筆者も同様に透き通るようなハイトーン・ヴォイスが聴けるのではないかなあ、と予想していたりした。
で、実際のところどうかというと、美声で甘々な、とまではとても行かない声帯の持ち主である。とはいえ、すっきりとしたルックスに反比例するようなヴァリトンの熱いガラガラ声で歌うシンガーでもない。
平凡というと叩き切ることは決してしたくないし、特徴があまり無いというシンガーでは決して無い。というかかなり好きなタイプのヴォーカリストである。サウンド的にはどうしても好きになれない、今年馬鹿売れしたのが未だに疑問なヴォーカルだけはその枯れ具合が評価できる、Lifehouseのヴォーカルに甘さを加え、余韻がより残る声質と説明するのが適切だろうか。
適度に年齢相応の青さの残る微妙な甘さがあり、更にビターなハスキーさも伺えるような、実に表現しにくい、筆者泣かせのヴォイスを持った歌い手である。甘いか辛いかという大別では、やはり甘い系列に入るヴォーカルであるのは確かである。
が、やはり苦味の成分も含んだ皺枯れ声も同居する−俗に言うオヤヂ・ヴォーカルの才能(?)、をも併せ持つかなりの力量のあるヴォーカリストであると捉えている。かなり大型のヴォーカリストになりそうな人であるのだが・・・・。将来性というと現在かなり心配なことがあるのだ。(不安材料は最後に記述する。)
さて、このRob Anthonyはこの自分の最初の名義のアルバムではアクースティックなルーツアメリカンロックを演奏しているのだが、何を隠そう元々はヘヴィメタルバンドからキャリアをスタートさせているのだ。これは筆者も超絶に意表を突かれた。このアルバムを聴いて、RobがHMギタリストとしてキャリアを積んできたと想像できるリスナーは間違いなくゼロに決まっている、そう言い切れる。
1988年にRobのホームタウンであるミルウォーキーでデヴューしたHMバンドでAcrophetという、スラッシュメタル系のグループが存在した。1990年までに2枚のアルバムをHMレーベルの老舗Triple Xから発表している。1990年に2枚目のアルバム「Faded Glory」をリリースしたバンドはリードギタリストの脱退した穴を埋めるためオーディションでギタリストを公募した。ここで当時高校を卒業したばかりのRob Anthonyという10代の男が、課題の40曲もある新曲を2週間でマスターするという才能を見せ付け、オーディションに合格する。
これが彼のプロとしての始まりとなるのだ。Acrophetは北米のツアーをしつつ、3枚目のアルバムを準備していたようだ。当時、LAメタルは失速を始めたが、Guns N’Rosesの人気高騰に見られるように、ハードでアレンジを大仰にしない、後のオルタナティヴの原型の一角を成すハードサウンドは全般的に受けが良かったららしく、Acrophetの人気もその大したこと無いサウンドの割にはかなりのものだったらしい。
が、1993年ツアー中にオリジナルメンバーが諍いを起こし、3枚目のアルバムを録音することなくバンドは分解してしまうのだ。Robの名前は最終的にメンバーとしてアルバムにはクレジットされずに最初のキャリアは終焉する。
しかし、まだ音楽への情熱が全く冷めていなかったRobはバンドのリードシンガー兼ベーシストのDave Baumann
とチームを組んでまたもやハードメタルバンドをスタートさせる。が、このユニットもDaveが一時的に音楽への興味を無くしてしまい一線から後退したため、またもや消滅。
然れども、「皆、ショウビジネスや音楽生活に飽いて家族の下やまっとうな仕事に戻っていったけど、僕は音楽を切り離して生きることはできなかった。」
と当時を回想するRobは自身の音楽キャリアを継続することを決意。彼は故郷のミルウォーキーのスタジオに篭もって、演奏技術やサウンドのプロデュースを独学するようになる。この埋伏の期間にRobは音楽の方向性を「360度ルーツロックにターンした。」と語る。・・・・まあ360度ターンしたら元の木阿弥なのだが(笑)、詰まるところ完全に方向性を変え、ルーツロックに焦点を絞ったことを強調しているのだろう。
「自分が生まれ育ちながら聴いてきた音楽、アメリカン・ルーツを真剣に追求しようと次第に考え、実践したよ。」
の言葉通り、Rob Anthonyは約10年間の大半の伴侶であったメタルサウンドとは似ても似つかないアクースティックで甘いポップな曲を書き始め、1999年の後半あたりからミルウォーキー周辺の小さなクラブで活動を再開する。
このクラッシックギターまで用いるアクースティックさと、1970年代のポップロックを懐かしく回顧出来る音楽性は次第に地元で評判になり、インディ・シーンではかなりの人気者となる。
そして2000年後半に演奏活動をしながら書いた曲を、活動を共にするミュージシャン達と録音する。このマスターテープを自身のレーベルを立ち上げ、ミックスダウンを敢行し2001年春に発売した、それが「Hard To Believe」である。
ウィスコンシンではかなり売れたようで、2001年のローカルなアワードで複数の賞を獲得している。
曲は全部で9曲と、多からず少なからずの数字だろう。RobはElectric・Acoustic Guitarだけでなく、3曲でNylon String Guitar、つまり日本でいうクラッシックギターまで弾いている。
後はプロデューサーを担当しているRamie Espinozaという人が全てのベースギターと一部の電気ギターを担当、そして、ドラマーが一人。基本はこれだけの編成である。楽器はギター、ドラム、ベースだけである。それ以外は全く使用されていない簡素さである。
例外として#8『Yesterday』を共作もしている嘗てのバンドメイトであるDave Baumannが#2『More Than A Friend』と#4『Hard To Believe』、そして#8で友情出演(笑)。元メタルバンドのリードヴォーカルの面目躍如とも言うべき透き通るハイトーンなバック・ヴォーカルを聴かせてくれる。この3曲ではDaveの高く澄み切ったヴォイスがRobのハスキー気味なヴォーカルと合わさり、違った甘さを持つ2つの声が競合して不思議な清涼感を醸し出している。が、Daveのヴォーカルはやはり存在感があり過ぎる傾向があり、全曲に参加したらRobの声を喰ってしまっていた可能性があり(事実、ややRobの声が負けているように感じる。)、この程度の参加が変化を付けるためにも丁度良かったと思う。成功したゲストの導入だろう。
全曲ともに速過ぎず、遅過ぎずのミディアム・ロックの域に収まるナンバーが殆どだ。アンキャッチーな曲は1曲も無く、終始、心を和ませる暖かさと、郷愁に胸が締め付けられるような甘酸っぱいコマーシャル・センスが居座っている。
以下簡単に印象を各曲について記してみよう。
#1『She’ll Come Home To You』のBuffalo Springfieldのようなジェントリーなアクースティック・ポップロックでまず、このアルバムに流れる雰囲気は確定されるだろう。Loggins&Messinaのデュオが紡ぎ出していたほんのりと暖かい自然体な音が現代に甦ったような錯覚さえ感じずにはいられない。
Dave Baumannとのヴォーカルの掛け合いが、こちらはややアップテンポであるけれど、Eaglesの名曲『After The Thrill Is Gone』のGlenn FreyとDon Henleyのデュエットを思い出させる#2『It Wasn’t Too Long Ago』、この曲は西海岸の北太平洋海流が流れる太平洋の海の色のように青い美しさがある。Daveのヴォーカルは微細な哀しさを感じさせる#4『Hard To Believe』でも活躍し、感動的な深みを曲に与えている。
PocoやJackson Browneの持ち味であるカントリーの匂いのする乾いたレイドバック・フィーリングと、繊細なフォーク加減が同居する#3『It Wasn’t Too Long Ago』でまたも和むことこの上ない。
Eaglesの傑作代表曲『The Best Of My Love』級までとはいかないけれども、J.D.SoutherやJack Tempchin
といった西海岸のシンガー・ソング・ライター達が書いて、そして歌っても違和感の無いアクースティック・バラード#5『Sister』のさりげなくエモーショナルなコーラスが、じわじわと心に染みてくるのはどうしても避けられない。
#6『Lucky Old Seven』はややスピーディでRobが90年代のシンガーであることを、漸くにして気づかせるごとくなオルタナ・カントリータッチの明るいロックチューンである。こういう曲ではRobの遠くまで通るに違いないヴォーカルは実に弾んでいて気持ちが良い。続く#7『Just Me And You』もグラスソングの、踊れる楽しさを感じさせる陽性な1曲で、この2曲の連続はとても気に入っている箇所である。
唯一の共作曲な#8『Yesterday』は、どう逆さに振っても元スラッシュメタルの出身コンビがペンを取ったようには聴こえないこと請け合いの、やや大陸的な大らかさを漂わせる、「Yeah〜〜♪」やハーモニーがユルユルと流れていく、田舎の夏をのんびりと過ごすための必須BGMのような曲である。
#9『Fool For Lovin’ You』で、ややロカビリーの入った、カントリー・フレイヴァーを如実に感じさせる曲が登場する。この最後のトラックは雰囲気でなく、メロディ自体が古臭く、まさに60年代のカントリーロックというような調子で、Linda Ronstadtのデヴューの頃を思い出したりもした。
以上、とても心が平穏になるようなアルバムを届けてくれたRob Anthonyである。これからも是非活躍を期待したいのだが、2002年に入り、不可解な事態が進行している。彼のオフィシャル・サイトが突然消滅。そして、2001年まではあちこちのインディ系列の試聴サイトに曲を配給していたのに、殆どのサイトで登録を解消して(または抹消されたか?)いるのだ。どうやらバンドとしてやってきた仲間と解散したらしい、という怪情報もあり本人にメールで確認中である。追加情報が入り次第掲載・訂正する予定である。
それにしても、こういった音楽はフォークロックと一言で片付けられそうな本邦の現状では、「Hard To Believe」を国内で発見するのはまず不可能であるだろう。
是非ともオールドロックファンにだけでなく、新世代のルーツロックファンにも回顧音楽と誤解しないで購入してもらいたいアルバムである。「信じることは難しい」かもしれないが、このアルバムは良いアルバムだ。筆者はその事実を「疑うことが難しい」。 (2001.1.9.)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
