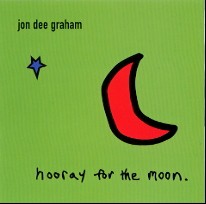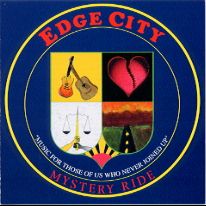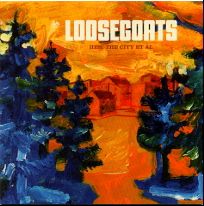 Her,The City Et Al / Loosegoats (2001)
Her,The City Et Al / Loosegoats (2001)
Roots ★★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Alt-Country ★★★★
いや、これは驚きである。何故か?
このフルレングスとしては3枚目の、前作「Plains,Plateaus And Mountains」からおよそ2年振りとなる、この「Her,The City Et Al」で見事に、これまで喉に引っ掛かった魚の小骨のように鬱陶しかった、オルタナティヴなロックを排除して、かなりルーツロックへの傾倒を深めたアルバムを届けてくれたからである。
1995年から翌96年に発売された初期のEP4枚を纏めた1997年発売の「A Mexican Car In A Southern Field」をカウントすれば4枚目となるため、4thアルバムとしても良いだろう。完全なニューマテリアルを詰め込んだアルバムとしては、3作目に当たるのだが。
この場では便宜上、3枚目としておくことをあらかじめお断りしておく。
奇跡的に日本盤までリリースされた2枚目のオリジナル・フルレングスアルバムである「Plains,Plateaus And Mountains」を筆者は現在は消滅したサイトの管理人の方から紹介されて聴いたのだが、Counting Crowsに似たようなルーツィなアメリカンサウンドを見出して、ぶっ飛んだ記憶が強烈である。
が、時間を経るにつれて、
くたばってしもた方がこの世のためで あることに間違いない産業廃棄物バ ンドであるクソ以下のPearl Jamのコ ピーのようなオルタナナンバーまんまの#1『Adversity』や#2『Casillero Del Diabro』が段々聴くのが苦痛になってきていたため、月を経るごとに評価はウナギ下がりやった!!
が、しかし、このアルバムでは2枚目の頭曲に位置していた糞尿以下のナンバーは全く消滅した。ついでにPearl Jamも死滅してくれると有り難いし、オルタナ・ヘヴィロックは絶滅してくれたら悪魔に魂を売っても良いと思う。
兎も角、ここに至り、この3枚目のオリジナルCDを聴くに至り、
評価は赤丸急上昇である!!!
脱オルタナ万歳!!
今更、遠慮しないで批判するが、2ndアルバムがかなりの出来であったため、2000年に早速瑞典から1stフルレングスを取り寄せた。、このアルバムは確かにロックンロールな元気なアルバムであるが、ルーツ3割、オルタナロックが2割、モダンロック3割、ガレージパンク2割くらいのかなり方向性の定まらない内容であった。
確かに、基本はコマーシャルであるのだが、あまりにも安っぽ過ぎるオルタナティックなヘヴィに走りまくったギターの音色が、相当数、アルバムの纏まりと完成度を盛り下げていることは明白であった。
評価できるのは、青さと勢いに任せた熱いロックサウンドが聴けることである。次第にロー・ファイ・ロックに傾斜していくLoosegoatsの足跡がくっきりと刻まれているので、1stから是非通しで聴くことをお薦めしよう。
お、記述を忘れていたが、このLoosegoatsはアメリカンなサウンドを届けてくれるグループなのだが、これまた非英語圏出身のバンドである。既にレヴューしているEnzendohやThe Thousand Dollar Playboysと同じく瑞典(スウェーデン)のロックバンドなのだ。
当HPでのレヴューでは常にスウェーデン出身のバンドが各回のトップレヴュードになっているのが、著者自身不思議であるのだ。それだけ、良質なバンドが北欧で増えているか、それとも米国のルーツ・シーンが衰退しているのかは、未だ判断は下せないけれども、前者の北欧でのルーツロックの興隆は、間違のいない現在進行形の事実であるだろう。
ついでにLoosegoatsの意味は、バンドのロゴマークからも想像できるが、“暴れん坊な山羊”、“野生の山羊”と解釈すれば良いだろうということを付け加えておこう。マスタング−野生馬としなかったところが、非アメリカのバンドであることを強調したかったのかもしれないが。
それにしても、かなり老成したというか、賞賛すべきレヴェルまで達した落ち着き振りが、アルバムを終始一貫して流れている。1stでは力任せのロックンロール、2ndではかなりトーンダウンしたが、前述のようなオルタナ・ヘヴィナンバーやハードにロックするチューンが何曲か見られたが、今作ではハード過ぎるナンバーは完全に姿を消した。
耳障りであったノイジーさが尖がったヘヴィなチューンは1曲もないという潔さである。それだけでなく、ストレートにロックする速いナンバーまで殆どなくなっているという段階までのロー・ファイ・ルーツ化には度肝を抜かれてしまったくらいだ。
殆どがミディアム・テンポ以下の、アクースティックな音色が前作より際立ったナンバーとなっている。厳密には直線的なロックナンバーとなると本国で第一弾シングルとなった#7『Yucca Mountain』とセカンド・シングルとしてEP化された#6『From And The Feeling』くらいである。
ややミディアムナンバーの中でも速目の曲となると#2『Days Of Black(Nights Are Lights)』と#3『Search』そして#8『Straight Arrow』を加えても良いが、あくまでもこの3曲はアルバムの中で相対的にスピーディな曲という意味合いである。1stの殆どがガレージ系のロックナンバーという流れや、2枚目のオルタナナンバー数曲とノイジーなロックナンバー数曲が嵌め込まれた展開とは殆ど別物の抑制の効いたルーツロックを聴かせてくれる。
これはいまいちなのだが、オルタナ的な暗さがあるナンバーとしては#4『Her,The City』がロックナンバーと言えないこともないが。
このロックンロールの力具合の低下を成熟ととるか、それとも堕落と受け取るかで、かなりこの「Her,The City Et Al」の評価は異なるだろう。
オルタナティヴを天賦の要素のように引き摺っていた初期の作品を、現代ロックバンドでルーツテイストもある音楽として認めていたリスナーにとっては、やや力の抜けてしまったアルバムと捉えられてしまうかもしれない。
無論、筆者も1st「For Sale By Owner」でのガンガンとタテノリで攻勢をかけてくるコマーシャルなメロディを基幹としたサウンドは、部分部分に置いて不満があるものの、評価はしているし、ヘヴィロテとなった曲も多々ある。
また、2枚目の「Plains,Plateaus And Mountains」におけるオルタナナンバー−特に頭2曲−以外のノイジーでややグランジの影響もあるけれどもキャッチ−でルーツなロックナンバーを含んだ構成も、嫌な部分が皆無という訳ではないが、高く評価はしている。
しかしながら、この3枚目の音源である「Her,The City Et Al」における、全体での統一の取れた流れは、今までの作品群の中では散漫であれこれと手を伸ばしていたような尻の軽さが殆ど存在しない。よって、じっくりとした旨味のある深さがアルバムとして聴くなら一番の完成度であると思う。
また、1stアルバムからキャッチーな懐かしいオールド・アメリカンロックのメロディを基本にしつつも、何曲かのヘヴィ且つオルタナティヴ風のナンバーで、ポップの路線を逸脱したような曲で、がっくりさせてきたという二面性を有していたバンドであるが、本作では、非常にキャッチーさが均一化されている。
特に1stアルバムの「For Sale By Owner」で際立っていた、極端にコマーシャルなメロディメイキングはやや抑えられ、代わりに2枚目まで必ずトラッキングされていた憂鬱で暗めのアンチ・ポップな曲も殆どなくなっている。結論としてはどの曲も嫌味にならないくらいのバランスの取れたポップス度を持つようになっている次第である。
また土臭さという面では、これまた極端にアーティフィシャルな都会的雰囲気のある硬質なナンバーが減ったのと対照的にアクースティックさとロー・ファイさが前面に出た結果、オルタナのアクの強さが邪魔してやや印象の弱かったダウン・トゥ・アースな色合いがくっきりと浮き出てきて、これまた良い按配のアーシーさを演出している。
が、まだまだオルタナ的な憂色さと硬さが完全には消え去っていないため、オルタナティヴの鬱陶しい憂鬱さが勝る曲も数曲残っている。とはいえ、全体から脱色されたオルタナ・カラーの割合が非常に大きいため、人体に影響のない残留放射能(謎)程度の阻害要素と思えば良いだろう。
「この2001年のアルバムでは、もう一段階ステップアップできたと思う。より暖かく、自然体なサウンドを追求している。ヘヴィさとは対称的なLoosegoatsのライトな側面を強調できたし、アメリカンなテイストをより薄くして、更に僕たちのスタイルを追及した。」
というソングライターであり、リードヴォーカリストでもあるChristian Kjellvanderのインタヴュー記事から推察するには、アメリカンな要素を減らしたというのは、2001年現在での主流であるLifehouse等のオルタナティヴで重いだけの申し訳程度ポップなサウンドから脱却して、バンド創設時に掲げていた
「ハイ・ファイなサウンドを目を点にして演奏しているバンドこそ、ローファイな音を何時かは演奏したくてたまらないという気持ちを抱いてるんだ。」
という1996年のデヴュー時のChristianの意向に回帰したようなアルバムである。
Christianは1980年代から90年代前半にかけて、9年の間もグランジロックの発祥の地である、核爆弾を落として壊滅させとけば良かったシアトルに住んでいた経験があり、Pearl Jamのかなりのファンであったらしいが、スカンジナヴィア半島に帰ってかなりの年月を過ごすうちに、その悪影響を洗い流すことに成功したようだ。
1stや2ndアルバムのリリース時にアメリカのメディアからインタヴューを受ける時に、必ず「Pearl Jamのファンでしたね。」と聴かれていたようだが、今作ではまったく、この最低のへヴィバンドから影響を受けた痕跡は見受けられない。誠にもって重畳である。
また、本作の原点となるような別バンド・プロジェクトをChristianは2000年に立ち上げている。この音楽性が、本業であるLoosegoatsのルーツ化を後押ししたのは間違いないだろう。
Christianが弟のGustafと組んでLoosegoatsのパーマネントメンバーも殆ど参加したプロジェクトであるSong Of Soilというグループが2000年末にリリースしたアルバム「The Painted Trees Of Ghostwood」はかなりレイドバックしたルーツロックが聴ける、これまでのLoosegoatsよりも地に足のついた1枚だった。また、弟のGustafも自らのバンドを率いてヴォーカリストとして活動しているため、兄弟のツイン・ヴォーカルが聴けるというプライオリティがあり、やや入手が難しいアルバムだけれども、是非ファンなら聴くべきだろう。
このサイドプロジェクトたる「The Painted Trees Of Ghostwood」よりはロックに比重を置いているが、求める方向性は同様であるのが、2001年のLoosegoatsとしての作品である「Her,The City Et Al」だろう。この別名称であるが、同一人物を中心として作成された2枚のアルバムは、スカンジナヴィアン・ルーツシーンに、漸く本格的なルーツバンドとして誇れるようになった作品であると思う。
これまでの作風ではルーツであるが並行してアメリカン・オルタナティヴのヘヴィさもある音楽、と評されるべきであったからだ。
これで本HPで取り上げた北欧ルーツバンドの本格的な仲間入りをしたと極個人的に祝福したい。
さて、収録曲は全部で11曲である。多からず、少なからずだろうか。10曲を超えるとどうも展開が冗長になるアルバムが多いのだが、このくらい出来が良い作品なら十分に耐性のできる演奏時間ではある。11曲で50分というのはかなり長い曲が多いことになるのだろうけど。
まずは、彼らのアルバムのオープニングナンバーとしては初めてのスローでアクースティックなトラックである#1『Traveller』が、このアルバムの方向性を雄弁に物語っている。1stアルバムのファーストトラックである『Disdialogic』の人工的にキンキン五月蝿いガレージロックのチープさも、2ndアルバムのモロにPearl Jamの追っかけナンバーである『Adversity』の重いだけでドン暗いナンバーによる始まりの気持ち悪さもここには存在しない。
ヴォーカリストのChristian Kjellvanderも得意技のファルセットをあまり捏ね回さずに、しっとりした歌い方を心掛けているようである。最初からかなり落ち着いてナチュラルな土臭いポップナンバーが来るので、過去のアルバムで伺えた頭ごなしの強烈なインパクトは欠如しているが、この緩やかで自然体を活用したスローポップなナンバーの余韻は深く心を打つ。バンドの活動の航跡をなぞるように、しかし淡々と歌い込められるナンバーには、もう勢いで未熟さを誤魔化していたようなオーヴァー・パワードな安易さは感じられない。
そして、軽やかなバンジョーの掻き鳴らす音色が聴こえるリフから始まる#2『Days Of Black(Nights Are Lights)』はビブラホーンも取り入れられたとてもライトでポップなナンバーである。ここで、あの独特な裏声が歌の冒頭から聴くことができ、やはりLoosegoatsのヴォーカルは健在であることが確認できる。このような軽快であるけれども、冷静なアレンジを施したミディアム・アップな曲は今までの彼らの作品には見られなかった形であり、この欧州的なパワー・ポップの要素まで見受けられる複雑なサウンドの重なりがゆっくりと耳に馴染んでくるところが、即効性よりも良い曲を創ろうとする彼らの方向性が解るというものだ。マンドリンの音色もそれ程クリアではないが、曲の重量を支えて、更にルーツなドライ感覚を助けているように思える。
#3『Search』は#2より更にレイドバックした土臭さを直接的に表現した中庸なテンポのポップナンバーである。暖かい音色を紡ぐハーモニカの活躍と、ハーモニーによるコーラスの重なりの妙がとても懐かしさを覚えさせるナンバーである。スチール的なスパーンと響くスネアドラムの音が格好良い演出となっている。非常に丁寧に創りこまれたルーツ・ポップチューンであるだろう。マンドリンの弦も聴こえてくるようだ。こういった#2や#3のような地味ではあるが、郷愁をそそるような優しい曲が、アルバム全体のクオリティを高めているのは明らかである。
タイトルの一部となっている#4『Her,The City』は、やや鬱の入った哀しげなメロディと、ヘヴィにうねるギターのサウンドがオルタナティヴ的なマイナー音程を出している。粘着質に叩かれるピアノもあまり綺麗なユニゾンを成しておらず、あまり好みの曲ではない。が、このような悲哀の漂うメロディは、北欧ヘヴィメタルに通じる叙情性をも根源としているかもしれないので、完全にオルタナ的な昏さを持った曲ではないかもしれない。美麗さはあまり感じることができないけれども。
まあ、前2枚の濃いオルタナティヴの無機質さを引き合いに出せば、随分とメロディを中心としたナンバーにはなっているだろうが。
続く#5『Nez Percé』はこれまたローファイで哀しげなスローバラードである。#4との違いは遅い曲であることと、殆どのメインヴォーカルがファルセットで歌われていることだろうか。このナンバーもオルタナ的なスローナンバーの臭いがして、味わいを噛み締めるよりもやや退屈で頭の芯を重くするような憂鬱さが勝るようなナンバーである。この2曲の部分がアルバムとしては一番出来が悪い流れだろう。
#6『From And The Feeling』はライヴ盤がEPとしてリリースされたが、シングル向きのロックチューンである。明るい中にも、北欧の地に訪れる冬将軍のような、微妙な翳りを漂わせているナンバーである。また極北の地に拡がるラップランドのような茫洋とした奥行をも思わせる比重の高さが、キャッチーなメロディの行間に存在しているので、軽く聞き流さずに、しっかりと心に残るナンバーでもあるだろう。トランペットやフリューゲルホーンもゲストミュージシャンにより演奏に加わっていて、ややクラシカルなルーツナンバーを思い起こさせる側面もある。
次が、先行ラジオシングルとしてカットされた、一番ストレートでパンチの効いたロックチューン#7『Yucca Mountain』であり、#6のEPに挿入される際には完全な取り直しヴァージョンが収録されているそうである。これまでのLoosegoatsのロックナンバーと異なるのは、中盤でスローな間を置くというように、これまでのロック一点張りの余裕のなさから脱皮しているところだろう。
スライドギターといい、ややハードにアレンジされたギターといい丁度良いロックの醍醐味が感じられて、一番ロックラジオ向きなルーツロックである。
#8『Straight Arrow』もミディアムテンポよりやや速目のコマーシャルな曲であり、アクースティックな側面とロックな魅力が同時に堪能可能なナンバーである。このトラックではヴォーカルの感情の込め方がかなり強烈であり、裏声がキャッチーなメロディラインに善く映えている。
重厚なピアノのエコーがかかるような演出からスタートする#9『Marrow』は、アクースティック&ルーツにエモーショナルな叙情を加味したバラードと名付けたい。取り立てて大仰なアレンジはされていない。ギターが泣きを見せる訳でもなし、ピアノの音が流麗な美しさを醸し出す訳でもなし。しかし、切々と歌い上げられる想いがジンジンと伝わってくるように説得力のある曲であり。数曲スピーディなナンバーが続いた後だけに、その存在感は大きくクローズアップされている。
演出というか曲順の組み立てが成功している好例であるといえよう。
ハーモナイズされたヴォーカルの織り成す仕事とスライドギターやラップスティールのナチュラルな音色によって、暖色系の色使いで仕上げられたアルバムのジャケットが浮かんでくる#10『1912』は、鍵盤レスなアクースティックなバラードである。前曲よりも明るくメジャーなコードで展開し、そこはかとなくエレクトリックとの融合も巧みにこなしている佳曲であり、心に届く感動は#9よりも分量が大きそうだ。
それにしてもCounting CrowsのAdam Duritzをファルセットに歌わせたようなChristianのヴォーカルは絶品であると感じる。特にこのようなバラードにおいて。
最後のナンバー、#11『Family』は後半に集中される構成となっているスローナンバーである。これまた静かに始まり、アナログ・シンセサイザーのような浮遊感のあるハーモフォンを中心にじっくりと盛り上がっていくナンバーである。やや地味に徹しているきらいもあるのだが、ラストトラックとしてそのルーツさと落ち着きで、この老成した雰囲気の支配するアルバムの締めとしては過不足のない印象を植え付けてくれる曲となっている。
さて、最後にLoosegoatsについて簡単に説明を加えておこう。
結成は1994年に3ピースでスタートしたが、即座にギタリストを加えて4人体制に。1995年に6曲入りのEP「Small Lesbian Baseballplayers」をリリース。ちなみにスウェーデンでは野球は存在すら知らない人が殆どということであるが、このタイトルからしてアメリカの文化を意識していたということだろうか。
このEP以降ベーシストが交代しているが、リードギタリストを除けば、それ以来リズムセクションとヴォーカルの3人は不動のメンバーである。1996年には3枚のEPをCDにてリリースする。「Mule Habit」、「Country Crock」そして「Slotmachines And Busted Dreams」。この3枚にデヴューミニCDを加えた音源は1997年に20曲入りのアーリー・ワークス集として編集、再リリースされている。前述の「A Mexican Car In A Southern Field」である。
1996年末に1stフルアルバム「For Sale By Owner」を自身とスウェーデンのエンジニアと共同でプロデュースし発表する。
このバンドが日本で注目されるのは1999年の2枚目のアルバム「Plains,Plateaus And Mountains」である。プロデューサーにJayhawksの「Sound Of Lies」、Wilcoの「A.M.」、Son Voltの「Trace」を手掛けたBrian Paulsonを迎えたからであろう。そのためか、日本盤までリリースされるが、残念ながら全然売れなかったらしい。
Paulsonが作成した割にはヘヴィロック的な要素が強過ぎたと思うし、そのオルタナ的な重さが瑕疵になってしまったアルバムでもあろうけど。
そしてアナザー・プロジェクトのSongs Of Soilでレイドバックしたサウンドへの方向性を固めて、今作を2001年にリリースしたが、日本盤はやはり出なかった。筆者も年の瀬近くまで本作のリリースを知らなかった。明らかなチェック漏れであった。
まあ、またオルタナ臭い、中途半端なルーツアルバムになるだろうと高を括っていたため、追跡がおざなりになっていたこともあるけれども。
しかし、アメリカンな現代サウンドとしての宿唖であるオルタナヘヴィネスをかなり排除して、今作は完全にルーツ作品と呼んでも誇大表現にならないものとなったのは、とても喜ばしい。まだ、残留しているオルタナの怨念というか残り粕がしみついている曲もあるけれども、この方向性を堅持するならば、いずれ完全に霧散するだろう。
油絵の暖かい絵画をジャケットにあしらって来た意図が、サウンドのハートウォーミングさが格段に増したため、シンクロしていて、とても感じの良いアルバムとなっている。
これからもドンドン残ったオルタナの色を消していって欲しい。もう殆ど残っていないけれども。
贅沢を言えば、もう少しアップテンポであり、しかもヘヴィなオルタナのキツさのないナンバーが増えてくれるとロックバンドとしてより楽しめるとは思う。が、これで及第点を遥かに超えるK点越えのジャンプを見せてくれたので、満足度は高い。
北欧産の野生山羊も猪突猛進だけでなく、ゆとりを持った歩みを始めたようである。 (2002.2.28)
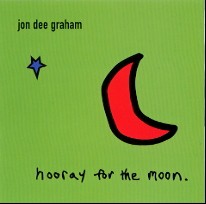 Hooray For The Moon / Jon Dee Graham (2002)
Hooray For The Moon / Jon Dee Graham (2002)
Roots ★★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Americana ★★★★★
「お月様、万歳。」
直訳すると、タイトルの「Hooray For The Moon」はこのようになるか。
また、「月下でのどんちゃん騒ぎ」とも解釈が可能だろう。こうなるとTom Pettyの1989年のソロ名義の名盤、「Full Moon Fever」を思い返さずにはいられない。というのも、タイトルの意味が近似した内容になりそうだからである。もっとも、Tom Pettyのソロアルバムの場合は月が満月であるが、このJon Dee Grahamの3作目の場合は、ジャケットの絵からはクレセント−三日月のようであるけれども。
月をタイトルに冠したアルバムはかなりの数に登るだろうが、意味的にかなり似通ったTom PettyのアルバムとこのJon Dee Grahamの3枚目は、その位置付けにも類似点があるように思えるのだ。(あくまでも月下の乱痴気騒ぎとHoorayを解釈すればの話であるが。)
まず、この「Hooray For The Moon」がJon Deeが嘗てパンクロックを演奏していたことを思い出させるようにロック色が強い作品であり、前作と比較して方向の転換を図り、しかも成功していると愚考しているのだが、Tom Pettyの「満月は馬鹿騒ぎ」も、これまでどうにも2級のロッカーという印象を1980年代を通して払拭できなかったTomがJeff Lyneという鬼才の協力を得て、メロディメイキングに新しい方向性を見出した作品であると考えており、それが成功しているという点に共通項を見出せると思うのだ。
つまり、この月をタイトルに掲げた2つのロックアルバムは、既存の築き上げた方向性を破壊することなく、舵を転舵し、回頭に成功しているという功績があることが同様であるのだ。
とはいえ、Tom Petty程、冒険というか新しい境地に踏み込んでいるわけではなく、Jon Deeの場合は、既存のサウンドを底上げしたものと捉えた方が良いだろう。
勿論、Tom Pettyのアルバム以外にも、Moonが題された名盤は数多いだろうが、取り敢えず、思いつくまま、そして意味合いが似ていると解釈したため、引き合いに出してみた、「Full Moon Fever」を。
しかし、このおっさん、ギタリストとしてのキャリアはかなり長いミュージシャンであるのだが、この顔で
まだ42歳(2002年3月現在)というのは、人類の老け顔の概念に対する挑戦としか思えん。(を)
つーか、60歳でも通用する爺いっぷり(謎)がアクセントである!
(顔写真はアルバムには勿論、あちこちの関連サイトで見れるので、一度見れば驚愕すること請け合いだ。)
ということで、年齢について触れた機会に、まずこのJon Dee Grahamの経歴を説明しておこう。
実物も老けていたが、写真では更にじじむさく見える、このJon Dee Grahamは1959年にメキシコと合衆国の国境線であるリオグランデ河に程近い街で生まれている。南北戦争の戦跡の地であるEagle Passの近郊の田舎町の様で、人口は320人くらいとのことである。
メキシコに近い州のカリフォルニアやテキサスに多いように、彼もメキシカンの血を引くヒスパニック系のアメリカ人である。
12歳で、カントリー・ロックバンドに加入してベースを弾き始めるまで、彼がラジオから聴いていたのは、カントリーとメキシカン・トレディショナルとポップスが殆どであったそうだ。ここにトップ40ヒットと70年代のプレ・パンク的な音楽も加わっていたそうであるが、主に聴いたのはやはりメキシカン・ミュージックとカントリーロックのようである。
バンドを始めてから、即座にベースからギターの方が性に合っていると感じて持ち変え、現在までギターをメインに弾くミュージシャンである。ソロ名義のアルバムを1997年にリリースするまでは、ギタリストとしてキャリアの大半を送っている。
18歳のになると、テキサス大学に通うため、オースティンに引っ越すが、ここで、まずパンクロック系のアングラバンドであるWhippetsというバンドに加入。このバンドでプレイしている時に、The Skunksのオーディションを受けるように薦められる。
1970年代後半に盛り上がったパンク・ブームに便乗するかのようにして登場していた、パンクロックバンドであるThe Skunksは創設時のメインメンバーのギタリストであるEddie Muñozが、Peter Case等を中心に結成されたパンク&ニューウェーヴバンドのPlimsoulsに引っ張られて脱退してしまったため、ギタリストを探していたのだ。
1979年にベーシスト兼ヴォーカリストであるJesse Sublettに認められ、The Skunksに加入したJon Deeは大学を中退し、演奏とローカルツアーを生活の糧とするようになる。
John CaleやThe Ramonesといったメジャーのパンクバンドの前座としてロードに出た時、弱冠19歳であったJohn Deeは初めて体験する大都会ニューヨークのラッシュアワーにびびりまくり、「田舎へ帰りたい〜。」と泣きべそをかいたという、今の爺いフェイスからは想像もつかないような可愛らしいおのぼりさんなところがあったそうだ。(笑) 1981年に、John Deeは残りのメンバーに言わせると、「前触れもなく突然バンドから脱退して、テキサスに戻ってしまった.」らしい。Johnはテキサスで、女性ブルースシンガーであるLou Ann Bartonのツアーギタリストとして1年くらい活動したそうだが、1982年の彼女のアルバムには、演奏メンバーとしてクレジットされていないところを見ると、ツアーでのサポートメンバーだけだったようである。
そして、この後空白をやや置いて、Alejandro EscovedoとベーシストのDenny Degorioが中心になって結成したルーツロックとメインストリームのハードロックが交錯したようなバンド、True Believersにリードギタリストとして参加する。ルーツとパンクのロックテイストを持った音楽性は、同時期にブレイクしたThe Georgia Satellitesよりも更に泥臭く喧しいロックサウンドであったと思う。
南部を中心にかなりの数のツアーをこなし、地道に人気を得てきたTrue BelieversはJim Dicknsonのピアノとプロデュースという両方のサポートを受け、メジャーと契約に成功する。
当時はこういった音楽にメジャーも寛容であったであり、1986年にEMIからセルフタイトルのアナログ盤を1枚リリースする。
そして翌年2枚目のアルバムを吹き込んだ段階で、1枚目のセールス不振、バンドメンバーの方向性の食い違い等により、バンドは解散する。この2枚目のマテリアルも解散後に少数リリースされたようだが、現在は全く出回っていない。というか2枚ともにCDとしてはリリースされていないのだ。
が、後の1994年にRykodiskというレーベルが2枚を1枚に纏めた総集編である「Hard Road」をプレスしている。このアルバムも現在は廃盤になってしまっているが、Alejandro Escovedoのファンとハードでパンキッシュなルーツ系のアメリカンロックが好きな人にはかなりの適性があると思うので、見かけたら是非入手しておくべきだろう。
バンドが解散した翌年の1988年、Jon DeeはL.A.に移住する。ここで、Jon Dee Grahamはセッション・ギタリストとして、かなりのアーティストのアルバムに参加している。
メジャー活動を中心に挙げてみると、元パンクロックバンドXの女性リードシンガーであるExene Cervenkaのソロ3作目の「Running Scared」(1990年)にギタリストとして参加。
こちらも元XのシンガーであるJohn Doeのソロデヴュー盤である「Meet John Doe」にギタリストとして参加し、ツアーにも同行する。
ちなみに2000年に6年ぶりに発売された、John DoeのバンドJohn Doe Thingの名義での3rdアルバム「Freedom Is...」は暗鬱なオルタナヘヴィなナンバーがめっちゃ増えた、クソのような作品であった。2枚目までのルーツテイストが殆ど聴こえなくなるという堕落ぶりであり、こんなんとツアーやったりバンド組んだのはJonの汚点であると思う。あまつさえ、名前まで似ているので更に腹がたつ。(関係ない)
1992年に、これより2年前に解散したパンクロック系のバンドであるCrime & The City SolusionのリードシンガーであったSimon Bonneyの、かなりルーツロックに傾倒したデヴューアルバム「Forever」にて、ドブロやボトルネックギターをプレイしてサポート。
同年に、カントリー・ブルースシンガーとしてRCAと契約したTerry Garlandの2枚目のアルバム「The Edge Of Valley」にベースやギターで参加する。
元Green On Redのギタリスト、Dan Stuartが1995年に発表したソロアルバム「Can O Worms」でギターとラップスティールでヘルプ。
と、このようにTrue Believers解散後は、西海岸に居を構え、ギタリストとしてメジャー・インディ、そしてジャンルも広く取って活動し、アルバムにはクレジットされなくても、沢山のミュージシャンのツアーに同行したりする。
また、1995年にはテキサスはオースティン出身で、現在は主に欧州での人気が高いため、独逸を中心に活動しているカントリーブルースを主に歌う酔いどれルーツロッカーである、Calvin Russellの6枚目のアルバムとなる、「Dream Of The Dog」のプロデュースとギターを担当する。
この2001年末に久々のスタジオアルバム「Rebel Radio」をフィラデルフィアで録音した、2002年には54歳になるオヤヂのテイストはJon Deeよりも更にディープなテキサスカントリーブルースが多分に含まれた枯れ枯れゴリゴリのサウンドであるが、渋いロックンロールサウンドという方向性では共通点も見出せるように思える。
このCalvin Russellの欧州ツアーにもギタリストとして同行し、1996年まで欧州を廻ることになる。
そして、1996年に欧州から帰国すると、Jon Dee Grahamは再びオースティンに拠点を移し、Kelly Willisのツアーにバックバンドの一員として参加、同年テキサスだけで発売された4曲入りEP「Fading Fast」の製作にも協力している。このアルバムはミニアルバムながら、ファンの間では非常に評価が高いが、著者は女性ヴォーカルはどうでも良いので、全く聴いていないことをお断りしておく。
このKelly Willisとのツアーの間に、更に曲を書き溜めていき、1997年についに自身の名前でプロミュージシャンとしてデヴューした1979年から18年を経過して、初のソロアルバムを発表する。
このテキサスのインディレーベルであるFreedom Recordからプレスされた「Escape From Monster Island」は、これまでのキャリアの大半を占めたパンクロックとカントリーロックを天秤にかけると、ややカントリーテイストというかカントリーブルースの味が強い、しかれどもロックの太さも兼ね備えたルーツロックアルバムとして、ファンの間では高い評価を得る。
Counting CrowsやAlejandro Escovedo、そしてRichard Bucknerのエンジニアを歴任してきたAndy Taubをプロデューサーに迎え、Mike Hardwick、George Reiff、Rafael Gayolというかなり通好みのプロフェッショナルをバンドとして揃えたところはかなりの渋さであった。
が、2年後の2ndアルバム「Summerland」ではやや枯れたブルースロックの幅が大きくなったようで、長年培った筈のパンキッシュなロックンロールの力が足りないように感じで、悪くはないが、相当不満の残る内容であった。こういったアルバムを出すと、こういった地味なシンガーはどんどんと枯れたカントリー系のブルースに走る蛍光が強いというのは定型化しているし、実際にロックから半歩でも外れてしまうと、ロックンロールに回帰しなくなる地味シンガーは多いからである。
しかし、2001年の晩夏に録音され、2002年の1月に一般発売されたこの3rdアルバム「Hooray For The Moon」では1stを遥かにしのぐタフなルーツロックナンバーが増え、更にポップな度合いは2枚目の意図してマイナーコードを多用したような捻くれたメロディがなくなったため、格段に上昇している。
ミュージシャンには、何とあのJim Keltnerがドラムで参加している。そうJohn HiattやRy Cooder、Nick Loweと組んでThe Villegeでドラムを叩いたり、(このアルバムはあまり好きでないのだが。)Bob DylanやPaul Westerburgに今は亡きGeorge Harrisonと、参加したセッションやレコーディングを取り上げれば、枚挙の暇がない名ドラマーがメインでスティックを握っている。
これはドラマーのRafael GayolがFlatlandersのツアーに参加したための臨時の応援であったらしく、現在はRafaelがバンドのドラマーに復帰しているそうだ。
また、ベースにはハードロックバンドのHearからポップロックバンドのFireballまでという幅色い音楽暦を誇るtMark Andesが、ギタリストは1stから続けてMike HardwickがJon Deeと共に友誼を通じている。
他のゲストとしてはHeartbreakersの何処にでも出現する(笑)ギタリスト、Mike Campbellが#4で、パンプ・オルガンで参加。またCrakerのベーシストであるDavey Faragnerが#2、3にてバックヴォーカルで参加。
更にテックスメックス、ラテン系のシンガーであるLittle Joeが#5でバックヴォーカルを聴かせてくれる、とかなり有名なバンドの裏方が集まっている。
前述したように、前作のスローに走りかけたディレクションから、見事にロックンロールに軌道修正しているところが、とてもエポックである。この方向性に向かうこと自体、大いなる針路変更という気がする。
正直、このままどんどんと枯れて、マニア好みのスロールーツロックを演じるおっさんになってしまうと危惧していたからである。この点がTom Pettyの90年代に入ってからの見事な成長振りを、やや目指した方角は違えども、思い出してしまうのだ。
爆走パンク&ハードロックオヤヂの切れっぷりが見られるほどの、ゴリゴリ直球ロックンロールではないけれども、ソロデヴューまでの18年間の大半をパンクバンドとパンク系のシンガーのバンドで過ごした経歴を、現在の自分の年齢や立場、力量という要素をしっかりと把握した上で、昇華しているようなロックアルバムとなっている。
少々、まだまだ羽目を外して頭を縦にブンブンと振り回すようなロックを演っても良い年齢である割には(顔は絶望的に老けているが)、まだリミッターが効いてしまい、ホームストレートで300km出せないフォーミュラーカーのようなところがあるけれども、これはこれで地に足が着いてる重量感のあるロックアルバムとして非常に良いアルバムとなっている。
曲は全部で11曲と、まあ、21世紀の趨勢からすれば少な目の部類に入りそうだが、10曲以下のほうが聴き疲れも中弛みもないので、まあ許容範囲な分量だろう。プロデューサーはTom Petty & The HeartbreakersやDave Stewartのエンジニアを務めていたDon Smith。
全体としては、キャッチーなナンバーが前作より大幅に増え、骨太なロック曲も割合を増している。また、静と動のメリハリが1stより大きく分けられ、コントラストに富んだアルバムとなっているのが特徴だろう。
より、アルバムとして聴き易くなってきたというか、聴き応えが出てきたとも言えよう。
#6『Volver』のように、目一杯メキシカン・トレディショナルなサボテンと岩石砂漠でポンチョを着たバンジョー弾きのオヤヂが歌いそうなラテン・フレイヴァーに溢れた曲も有り、Jon Deeの民族的なルーツの一旦が見えてくるようで面白い。歌の意味はさっぱり解らないけれども。(笑)
基本的にキャッチーさがこれまでのアルバムでは一番底上げされていて、実にとっつき易いサウンド・プロダクションが全体を貫いている。#1『One Moment』からして、実にポップな仕上がりである。堅実で隙のない演奏でありながら、Jon Deeのヴァリトン&オヤヂヴォイスが、全体をラフでルーズに聴かせる働きをしていると思う。テンポとしてはミドル級の速さなのだが、程よくパワフルなギターの音のためか、実際よりもアップビートに聴こえる。
#2『The Restraining Order Song』は続いて、これまたかなりポップな味付けをされたミディアムなナンバーであるが、枯れつつもハードに歌いまくるJon Deeのヴォーカルに引っ張られるようにして、ロックンロールに聴けるナンバーであるだろう。様式としてはかなりディープな南部ロックであるのだが、Davey Faragnerのバックヴォーカルの重なりと、泥臭くもキャッチーなギターソロが、しつこさを抑えて、良質なポップロックな1曲としてこのトラックを完成させている。
#3『I Go Too』はアクースティックで静かな南部ナンバーの味わいを十分に出している曲。スワンピーな粗さと、どっしりとした骨太さが同居しているナンバーである。Michael Hardwickの担当するペダル・スティールがスゥインギングに鳴っているが、全くカントリー臭さがないナンバーである。
続いて、#4『Something Moves』もJon Deeのいぶし銀的な自然体の音楽を十全に感じ取れるナンバーとなっている。ドブロギターが控え目にフューチャーされ、棺桶に入るまで黄昏た雰囲気を引き摺っていくような、男の背に漂う哀愁のような情緒が匂ってくる曲である。この深い、深い質感はとてもメジャーで黄色い声援を受けているような若僧中心のオルタナバンドには出しようがないだろう。夜の深い底を覗いたような深遠さを感じる1曲だ。Mike Campbellが弾くという異色のキャストであるパンプオルガンの鄙びた音も寂れてて良い。
かなりハードでダークなメロディ展開を見せるのが、#5『Way Down In The Hole』である。このハードさとサザンロックの粘っこさが満載のナンバーは、そのべたつきが嫌味にならないところが、ロックンロールとして成功していると思う。ややアメリカン・ゴシック風に大仰な展開を見せるハードナンバーである#7『Waiting For A Sign』ではエコーというか音響を積極的に取り入れた面を披露しているのも、やや意外であったが、ロックナンバーとしては面白いアプローチであるのではないか。
直球勝負なマッディで重いロックナンバーである#8『Laredo』のノイジーでパンキッシュなアレンジは、Jon Deeがパンク畑出身であることを知ることが、初めてのリスナーでも可能なチューンであるだろう。しかし、生来のヴァリトンヴォイスに加えて、ここまでシャウトしてしまうと、更に男臭さよりもオヤヂの体臭がプンプンと匂ってくるようだ。ややオルタナヘヴィのような力任せな点があるけれども、アーティフィシャルにギラギラしていない音創りなため、全くハナに突くことはない。
#9『The Huisache Tree』のレイドバックしたドブロやペダルスティール・ギターが活躍するナンバーを挟み、Jimのスネアドラムの音がとてもリズミカルな#10『Home』が始まる。このナンバーも諸手を挙げて降参するようなポップさは感じられないけれども、ツボはきっちりと押さえたコマーシャル加減はしっかりと健在である。ラフでタフなヴォーカルと、奔放なハードギターワークがとても気持ち良い。
5分30秒を越える、このアルバムで一番長い曲であり、インプロヴィゼイションもたっぷりと堪能が可能だ。やはり出色はJim Keltnerの堅実なドラミングであろう。何回か強弱をくりかえして、うねっていく曲の流れに耳を傾けると、このナンバーが一番レコーディングで楽しめて演奏できたのでは、と想像してしまう。
最後の#11『Tamale House #1』の乾いた、しかし心の暖まるメロディを聴きつつアルバムが回転を止めると、その余韻がどこまでも尾を引いて行くようである。サクサクとしたギターの爽快さと、ゆったりとしたリズムがJon Deeの枯れたヴォーカルと非常にマッチして、どこまでも想像が広がっていきそうな奥行のあるナンバーである。
それにしても、このシンプルだが、とても印象に残るジャケットは良い。1stの芸術写真のようなジャケットもユニークで不可思議さが合ったし、「Summerland」の油絵と水彩画の中間のような絵画的なジャケットも見応えがあった。がしかし、この単純であるけれども、何故か心に残ってしまう、デフォルメされた落書きのような絵が今までのアルバムでは一番の出来であると思う。
画中に存在する、正体不明の暖かさ。そして、真っ赤な月に青い星、緑色の空といった、非現実的な配色も全く違和感を感じずに受け止めれてしまう。
このジャケットを選ぶセンスはかなりのものだと思う。素直に賞賛したい。
しかし、現実の月を夜空に仰ぎながら、独り静かに「お月様に乾杯」してもハマるアルバムでもあるし、多人数でのんびりとマイペースで飲みながら、楽しく「今宵の月に乾杯」しても、状況にぴったり来るアルバムでもあるだろう。
太陽でなく、月に万歳するところに、Jon Dee Grahamの生き様が見えてくるような、男の人生を匂い取れる作品であると思う。
Jon Deeの3作目の傑作さに、乾杯といこうではないか。 (2002.3.5.)
 Frazzle The Giant / Frazzle The Giant (2001)
Frazzle The Giant / Frazzle The Giant (2001)
Roots ★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Alternative&Modern ★★
You Can Listen From Here
しかし、この全然売る気のなさそうなジャケットは実に良い。コマーシャリズムとは対極にあるような意味不明の怪しさがある合成映像の如きアートワークである。
実際に、この「Frazzle The Giant」は未だマーケットには正式に流れていないアルバムなのであるからして、「売る気」がなさそうというのもあながち間違いではないかもしれない。(んな訳あるかい!)
とあるインディサイトで試聴して、非常に良さそうであったため、バンドのリーダーであるRussell Chudnofsky氏とコンタクトを取り、送金と引き換えにCDを送ってもらった次第である。が、ジャケットもアップロードされていない程度のマイナーさであったため、配達小包からこのジャケットが出てきた時は、正直「?!なんやこれ?」と感じてしまったのである。まあ、これにはRussell氏とずっと連絡を取り合ってきたので、Frazzle The Giantという名前を半ば失念していたためもあるけれども。
しかし、この足元にある知的生命体が発生しそうな岩石惑星(地球かなあ。)を足蹴にして踏み潰しそうな巨人のオヤヂのヒゲが素敵なジャケットから、サンプルで聴いたポップでアクースティックな音楽性を連想するのは即応としては困難であったことは告白しておこう。
ちなみにRussell Chudnofskyさんは、この太鼓腹巨人とは全く関係ないすっきりとした容姿のミュージシャンです。ま、筆者の30年後の姿がこんなんかも。(笑)
バンド名のFrazzle The Giantを訳せば、「ボロボロになった巨人」とか「ズタボロに疲れきった巨人」という感じであろうか。まあ、このジャケットを飾っているアメリカのうらぶれた場末のバーでバーボンをかっくらって、くだまいているようなおっさんが、当の巨人かは判断をし兼ねるところであるけれども。(間違いないだろうけれど。)
それにしても、外見は相当草臥れてはいるが、心労でボロカスになっているような印象は正直受けない巨人であると思う。別に惑星を支えている訳でもなし(笑)、飛来する流星や異星人の宇宙艦隊と戦って擦り切れたようにも見えない。
単に人生に疲れた、という意味でのFrazzleかもしれない。ちなみにちゃんと腕時計も嵌めているし、肥満度を見る限りは栄養状態も過剰なまでに良さそうであるから、きっと顔の陰鬱さに顕現しているように、内面がボロボロになっているのだろう。
しかし、突然咆哮してやや遠方に浮かんでる衛星(月だろうが)にウエスタン・ラリアートを喰らわしそうな、危ない雰囲気をもった巨人である。絶対に近寄りたくないし、仮に友達に持つと、間合いを保つのに苦労しそうなおっさんであろうからして(謎)遠慮したい。
現実問題として、このジャケット見て、即購入に走るような高尚な趣味の方が存在するなら、それはそれで素晴らしいと思うけれども。
まあ、ジャケットと音楽性はリンクしている必要は全くなく、反して幾らジャケットの絵柄や写真の趣味が宜しかろうと、肝心の内容と音楽性がダメダメでは本末転倒である。その点、この「Frazzle The Giant」の初のフルレングス・アルバムは、何とも名状し難いが「良い」と断言できる部類の音楽が詰まったアルバムである。
であるからして、購入を躊躇する必要は全く感じられない。この怪しいジャケット−まるでアンダーグラウンドのプログレッシヴ・ロックやインスト・ハードロックの絵柄だけれども−にも何処となく・・・良さ・・・・というよりもアナーキズムが漂っているか、やっぱり。(笑)
しかし、強引にFrazzleという単語とCosmos-「宇宙」という情景を結びつけると、かなり意味深に曲解できなくもないこともない。これはもういい加減くどくなってきたので、後述しよう。
ま、素直にジャケットを見れば、これで奇抜でユニークではある。このバンドのユニークさと捉えどころが難しいサウンドとある意味共通点を、こじつけがましいが感じてしまったりもするのだ。
現実問題として、賞賛すれば多彩、論えばバラバラ、というように両方に評価ができうる音楽性がアルバム全体を貫いている。確かに、筆者自身、このアルバムのカテゴライズは非常に頭を悩ませた。“これ”といった明確な確定要素がないためである。
Roots Rock 、 Acoustic Rock 、 Adult Rock 、 Adult Alternative 、 Alternative Rock 、 Modern Rock、そしてCountry RockにPunk Rockという21世紀の現在も廃れていないアメリカンロックの構成エレメントの全てが当てはまりそうなのである。曲によって、方向性がかなり違うものも存在するのだが、これらの素材がごった煮状態になって同一曲に存在していることすらある。無論であるが、筆者が憎悪して止まないAlt-Rockのテイストはそれ程のものではないけれども。
が、これだけなら、アメリカンロックと大まかに分類してしまえば良い、と指摘されたらそれは正しいのだが、これらだけでないのである、このアルバムから感じる音楽性が。
このRussell Chudnofskyという、非常に好青年な外見を有する(言うまでもなく、とても親切な人である。)ライターの書き綴る曲には、1970年代後半から1980年代初頭にかけて大流行に流行ったNew Wave的なアプローチが感じられるのだ。それも安っぽさをあまり伴わないものが。
これをブリティッシュ・ポップや大英帝国本土産のロック・ヴォーカルのテイストと置き換えても良いだろう。
要するに、ストレートでズバズバと投げ込んでくるようなアメリカンロックの速球勝負さに、変化球の曲がりや落差が加味されたものと考えれば良いだろう。
また、Modern Rockというジャンルの、コンテンポラリーな感覚がサウンドに存在するが、どちらかというと最早古典的な存在になりつつあるNew Waveの先進性に近い、微妙に浮遊感のある音創りをしているしているように見受けられるのだ。
TheCarsやDuran Duranのサウンドプロダクション、そしてそこにNick LoweやElvis Costelloの持つような独特の英国的なポップセンスの息吹を肌に感じる。このヴェテランが有するこれまたグレートブリテン的なややナードなルーツロックのエッセンスが存在することは言うまでもないだろう。
また、The Smithのような捩れた作風も見えないこともない。
基本として在る、アメリカンロックの中芯の外側に、これだけの雑多な音楽的要素がコロニーを形成して繁殖していると想像して欲しい。実にイメージが困難な音楽性のように思えては来ないだろうか。
とはいえ、更なる源はポップでキャッチーという要素である。あれこれと手を出した挙句に、奇々怪々な高温で炙られたガラス細工のように不定形なメロディと、行く先の見えないサウンドを「作った」と錯覚し、スノビッシュになっている音楽屋が、英国を中心としたブリット・ミュージックや、米国でのクロスオーヴァーと錯覚しているミクスチャー・ロックである。
勘違いの、思い込み芸術家気取りと呼称しても、軽蔑には当たるまい。そこまでの音楽創っていないのだからして。
が、このバンドの生産する音世界は、そのような袋小路にはまり込んだものではない。まして、出口のない迷宮や迷路に自らを置いて、その場で恍惚としているような“独り善がり”の馬鹿さ加減とは正反対の意図を持っていると想像している。
そう、良いメロディで、良く吟味されたサウンドを、気取らずに届けるという。それに付け加え、ある程度の矜持というか、冒険的な新しさを、気張らずに取り入れているという、間口の広さも見せている。
得てして、新しさを追い求めるが故に、ポップミュージックという、娯楽音楽の大前提を失念し、自慰的な満足行為に走りがちなバンドが、ModernとかArt Rockとカテゴライズされるバンドには多いが、このFrazzle The Giantはそこまで斬新さにのめり込んではいない。
しっかりと、自らの足元を見て、アメリカンロックのルーツを念頭に置きつつも、その枠の中で独自性を追求しようとする努力が伺えるし、実際に何回か触れたように、名状し難い音楽性の複合的な融合を成功させているバンドであると感じている。
決して不満がない訳ではない。筆者の物凄く好きな路線の上を走っているバンドであるが、ともすれば脱線はしないとしても、ダイヤの遅れや乱れがある。そして何よりも、走るスピードはあるかもしれないけれども、急勾配に差し掛かったり、悪天候化での運行に不安を感じる馬力の不足を感じてしまうことがある。
と、置き換えた仮託論では更に意味が不鮮明になるだろうから、ばっさりと切ってしまうが、ここでガツンと行け!というポイントで、やや脱力気味のフニャリとしたサウンドプロデュースが目立つのだ。元気だけのタテノリ一点集中が満点であるとは思わないが、締める箇所を締めてないと残念に思うところがしばしば見受けられるように思える。
まあ、このブリット的というか大陸的な腐れ具合は、このバンドの音出しの特徴でもあり、評価できる点でもあり、言ってみれば諸刄の剣であるのだけれども。こういった点はBarenaked Ladiesと共通する要素がありそうだ。このカナディアン・ポップロックバンドも、敢えて遊び心を出すのが特色であり、真っ正直なポップソングよりもどこか捻りを加えて月面宙返りを敢行するような捻くれ振りを見せてくれる。
音楽的には一番近いのが、Barenaked Ladiesかもしれない。このバンドほど緻密な作りをしていないし、ルーツロックへのアプローチは分量として多いけれども。
Barenaked Ladiesの現代ロック風メロディに、Todd Rundgrenのユニークなポップセンスと切り口を足して他の上に挙げたようなアーティストをかき混ぜてみた音楽。こう表現すると結局はやはり多彩なアメリカンロックの一形態と表現するしかないのかもしれない。
振り出しに戻ってしまった感じがある。(苦笑)
さて、このFrazzle The Giantというバンドについては、殆どデータが存在しない。Russellさんとのメールのやり取りから得たコメントやお話と、紹介しているインディサイトの掲載情報が全てである。
活動拠点は、筆者が好みの音楽がガンガンと輩出されていて、正直テキサスとかの形骸化して動脈硬化を起こしているようなヌルイ、もうぬるま湯なカントリーロックの新人しか出てこないような南部地方より、余程個人的に注目している州である、マサーチューセッツ。
その中心都市、ボストンの近郊のバーリントンという街で、Skypaint Musicという自主レーベルを興して音楽活動をしている。ボストンエリアのローカルなルーツロックバンドやアクースティックバンド、そしてロックバンドとしばしばジョイントライヴやクラブ・サーキットを行っているそうである。
Russell氏はルーツ系の交流のあるバンドとして、Amelia WhiteやJess Kleinを紹介してくれている。厳密にはルーツというよりもアクースティック系のバンドであると思うが。
バンドのメンバーは4ピースの体裁を取っている。
Russell Chudnofsky (L.Vocal,Guitars,Wurlitzer Piano,Hammond Organ,Bass)
Lesley Smith (Vocals,Bass) , Dave Hayes (Bass) , Dan Koetke (Drums)
このバンドクレジットとなっているが、3曲でヘルプドラマーがドラムを客演している。
何と言っても特徴はソングライターであり、ヴォーカリストであるRussell Chudnofskyのマルチプレイヤーとしての手腕であるだろうが、それ以上に、女性シンガー(ベースは#2で弾いているだけだ。)であるLesley Smithの存在がある。
殆どの曲でRussellのヴォーカルにハーモニーをつけ、殆どソロで歌うことはないが、ツインハーモニーは頻繁に聴くことができるし、バックヴォーカルとしても喉を振るっている。特段美声でもないが、ややハスキーであり、悪い声質の持ち主ではない。それの故に、もしリードヴォーカルを執ることになると、力量不足が浮き彫りになるに違いない女性シンガーであるけれども、決して単独で目立とうとせずに、Russellのやや調子の外れたような頼りないヴォーカルのサポートに徹することで、とても歌唱のレヴェルを底上げしている。
また、プロデューサーはアクースティックなポップロックの熱心なファンならかなり名前が浸透している、Scud Mountain BoysのJoe Perniceが2000年に発売した「Chappaquiddick Skyline」というアルバムのミキシングを担当していたMark Alan MillerがRussellと共同プロデュースを行っている。エンジニア関連は、全てMarkが受け持っているのは言わずもがなだろう。
この人は他にもインディポップ系のアルバムを多数手掛けている。メジャーな仕事ではDinosaur Jr.の2001年に発売されたベスト盤「Ear-Bleeding Country:The Best Of Dinosaur Jr.」のエンジニアとしてクレジットされていることくらいだろうが。
どちらかというと、ノイズ系のポップやハードコア系のロックアルバムを手掛けることが多い中堅レーベルを中心にプロデューサーとミキシングの仕事をしている人であり、このMarkの関わったオリジナルアルバムで良かったのはまず存在しなかったのだが、今回の「Frazzle The Giant」が初の評価できるアルバムとなったのは、筆者自身意外であったりする。
やはりノイジーでオルタナ系の重いナンバーが殆どないからだろう。
リリース時機は2000年まで遡るが、5曲入りEP『Turnstile Night』でアルバムデヴューをしている。このミニアルバムは残念ながらRussell氏の手元にも残っていないそうである。かなりプレス数が少なかったようだ。初めてのフルレングスCDプレスがこのセルフタイトルである「Frazzle The Giant」である。
しかし、サンプルを聴くにつけて、こちらの入手が殆ど不可能な5曲は非常にアクースティックであり、ツインハーモナイズな歌唱形式が殆どのようで、こちらの一貫した作りの方が好ましいように思える。
色々手を出して、膨らみ過ぎて破裂していないこのセルフタイトル・アルバムはそれだけで、変化に富んで面白いのだが、オルタナティヴを指向したナンバーが見られるのが唯一の瑕疵であると思うからだ。
その代表が、唯一必要以上にヘヴィであり、ノイズロック、ミクスヘヴィネスと分類できそうな曲。10曲収録のこのアルバムの最後に位置する『My Dog Died』である。ディストーションの効かせ過ぎなギターが唸り、Russellのヴォーカルもシャウト、というかエフェクトを掛けたデスメタル・チックなくぐもった音響をがなり立てている。
こういった曲が3曲以上あったなら、絶対にレヴューの対象にはならなかったに違いないが、1曲ということで何とか我慢のできる範囲に収まっている。しかし、トリのナンバーがこういったアルバムの流れからすると、まさに「余分」であること字の如しのエクストラ・トラックのような曲であるのが、とても惜しい。もっと良い曲を絶対に書ける人なのに敢えて、このようなガチガチに不恰好な完成度の低い曲を持ってきたのは、何らかの意味があると思いたい。
それが何かは筆者には想像の埒外であるのだが。単にプロデューサーのMarkの趣味の反映かもしれない。それは余計なことだろう、若しこの仮定が合っているとすればだが。
残りのナンバーには現代ロック的な肥料が全面にわたって撒かれているが、オルタナティヴ的な暗鬱さは殆ど感じることはない。
#1『Never Goes The Time』から適度にキャッチーであるが、何処となく1980年代初頭のNew Wave的なあれもこれもと詰め込んだようなアレンジと、大英帝国的な複雑なポップセンスを、ルーツであり、またモダンでもある曲の骨組みの中に感じることができる。
やや、ドロンとしたルーズさのあるRussellのヴォーカルに、女性特有の高さのあるLesleyのヴォーカルが重なり、ルーツロックの基本のようなハモンドオルガンが、複雑に変化するラインを巧く補助している。さり気なく、ポーンと鳴っているウィルツァー・ピアノも良い。英国と米国が結婚したような折衷的なルーツナンバーである。
#2『My Movie』はCarsのRick Ocasekのように頼りないヴォーカルワークから、グイと力が入っていく歌い方が特徴だ。どことなく田舎臭さもあるのだが、都会的な整理された音の連なりを感じさせる。テンポはゆったりとしているけれども、結構ハードなギターが効いたナンバーである。この曲ではLesleyが一部でツインリード・ヴォーカルを担当していて、男女のデュオで中間的なロックを叩きつけるように歌う様はFleetwood Macのセールス全盛期のポップ時代を思い出してしまったりする。
いかにも、Aメロが終わったら、ガツンとキャッチーにスピーディに上昇するだろう、と予想をさせるような、ポップでおとなしめのリフから、お約束にロックする#3『Move』は、がっちりとしたタフなギターが余すところなく、「Rock And Roll」と主張するようなファーストクラスのパワーナンバーである。こういったラジオに乗りそうなシングル向けのナンバーでは、やはり東海岸の泥臭くないダウン・アースさを持ったバンドだなあ、と思ったりする。
あまり好きな表現でないけれども、Power Popと言っても良いだろうし、メインストリームなModern Rockの傑作と言い換えても問題ないだろう。
#4『Mediaval Dream』は、基本はルーツィなミディアムスローナンバーであるだろうけども、Russellの低く押さえたヴォーカルと泣きの音色がギンギンに響いてくる弦を聴いていると、これまた不可思議なモダン・ロックのナンバーであるようにも思えてくる。「La〜,La,La,La」とヴォコーダーを使ったような弱いコーラスが、この曲を素直な泣きのナンバーにせずに、間抜けな演出を効果しているのが、何とも言えない、良くもあり、悪くもありか。英国の影響を匂わせるサウンド・プロダクションである。
厚めの男女ツインハーモニーがたっぷりとコーラスに取り入れられた#5『Save Me』から、数曲が、どうにもこのアルバムの無方向性を強調しているように思える。
まず、#5はアメリカンというよりも大陸的なのっぺりと流れる哀愁を感じさせつつ、しかもアメリカ北部の中部から東海岸にかけてのビッグバンド的なリズムが含まれているようなのだ。ホーン・セクションこそ取り入れられていないが
管弦楽器が入って、ジャジーに踊りたくなるようなナンバーである。
続く#6『Miss Her Whisper』も欧州的な暗さと拡がりを感じさせる哀歌的なアクースティックな曲だ。かなり上空を覆う暗雲のようにドーンと圧し掛かってくるような翳りのあるナンバーであり、英国のアクースティック・ポップバンドが好んで取り上げそうな曲調のトラックだ。
そして、#7『Laugh Her Away』もまた、ジャム的と言うべきか、ジャズのスゥインギングな振りのある、これまたブラスセクションがいないのが違和感を覚えるようなナンバーである。どちらかというとラテンアメリカのリズムを連想してしまったりする。
そして、3曲続いたアウト・オブ・アメリカンな曲から一転して、#8『You’re Going Nowhere And Nobody Cares』は8人のゲストをコーラスに招いて、ポップで元気にロックする、かなり派手なナンバーとなる。冒頭から殆どヒネリを加えずに、ストレートにロックに没入していく正統派なナンバーである。常に男女2名のヴォーカリストが掛け合いをするように、軽快に歌を進行させて生き、コーラスパートでゲスト陣との合唱に入り、スカっとするギターソロがそこを割って流れるというように、この曲はアメリカン・ロックである。もっとこういう感じの曲で固めてくれても良いのに、ちょっと残念に思う。
そして、この曲でアルバムを終わらせれば有終の美を飾れたに違いない、カントリー的な身近な土の匂いを嗅ぎ取れるようなアクースティックな、バラードタイプの#9『Disappear』も、アメリカン・ルーツを根本として保持しつつも、現代ロックのスマートさや英国的な複雑さが見えてくる、感動的な複合ルーツナンバーである。とても味わいのある1曲であり、ルーツロックもRussellに影響を与えた音楽だろうことが想像できてくる。
現在、Russell氏は詳細なバイオを準備中とのことなので、完成次第、こちらのレヴューに加筆を加えるつもりである。珍しく、ルーツから色々と浮気気味なバンドのレヴューをしたが、多彩でもメロディがしっかりしている下半身の強さがあれば、どのようなジャンルでも良い作品に仕上がることを立証してくれているバンドだろう。
巨人級な大名盤とまでにはまだ至ってはいないが、将来性を考えると、もっと方向性を定めれば、ジャイアントになれる資質は十分なグループである。
このCDが欲しい方はRussell Chudnofsky(恐らく東欧系移民の末裔だろう、この苗字は。)氏に15ドルを送金すべし。連絡先は筆者に遠慮なくたずねて欲しい。 (2002.3.7.)
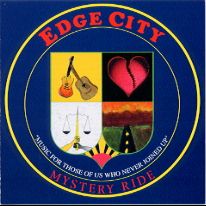 Mystery Ride / Edge City (2000)
Mystery Ride / Edge City (2000)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★
Southern&Country ★★★★
You Can Listen From Here
ジャケットを見ただけで内容を確認せずに、衝動で購入してしまうことを何と言うだろう。
答え:単なるアホやん!!
ま、という冗談はどっかに置いておこう。俗に言う、ジャケット買い−ジャケ買い(ジャケ害とも諧謔的に言う地方もあるとかないとか。)で幾度失敗したか、筆者は数えるのを既に放棄しており、全く見当もつかない。
・・・・・実は数えるのが怖かったりするのだが・・・・・。
まあ、オヤヂが写ってるジャケットで躊躇なしに購入する奇特な、もとい、特殊な趣味人がどれだけ作者の他に存在しているかは不明であるが。
が、このジャケットは少なくとも「趣味が悪い」という烙印を、購入したことにより捺されることはないだろう。
某自動車メーカーのエンブレムのような基本形をデザインとし、その4分割されたスペースにそれぞれ戯画的に描かれたイラストをあしらっている。
左上から時計回りに眺めてみると、まず、エレキギターとアクースティックギターが、このユニットが構築する音楽を代弁するように描かれている。
そして、破れたハート、ブロークン・ハート。しかも一度破れた所を縫ったが、また破れたことを仄めかすように、縫い目の跡が破れた箇所に付いている。これは歌詞の内容を暗示するものだろうか、失恋、傷心?
夕焼けの空のように橙色に染まった空の底にうずくまっている山塊に伸びていく道路。草原を割るようにしてどこまでも続いていくようなフリーウェイ。こういった写真のジャケットは年間を通して必ず何処かで見られる程の典型的なジャケットであるが、このようにぼかして覚束なく見せている油絵的な手法で見せられると何やら新鮮なものがある。
この絵は、このバンドの音楽がカントリー・サイド(都会的でないこと)を主張しているのだろうか。
最後に剣を持つ、黒と黄色い肌の腕。そして剣には天秤が。古来、天秤は「公正な裁判」「中立の判定者」といった意味で、西洋社会で象徴化されているものである。しかし、剣と言う武器の象徴に、公正・バランスの象徴たる天秤測をあしらうというのは、どうにも解釈に困る構図である。
剣の刀身という、触らば己が身が傷つくという危うい存在に乗っている、バランス。その剣を2本の色の違う手で支えるという構図。どうも、現代社会が内包している危険性について、または危ういところで踏みとどまっている何か、それは経済危機かもしれないし、環境汚染、戦争、食糧難、熱帯雨林の現象、というギリギリのEdgeにある危機のようにも考えられる。このバンド、Edge Cityという単語を加味すれば。
さて、このアルバムは実を言うと、相当長く埃が積もっていたアルバムであった。購入年次は2000年の後半であると朧げに記憶しているが、定かではない。2001年の秋に実家で掘り出して聴いて「あれま」と思い、現在に至るまで携行しているという次第である。
何故、ここまで購入からレヴューのピッキングまで時間が空いてしまったかというと、#1『Will Not Let You Down』が女性ヴォーカルであったからだ。この1曲を聴いただけで、メロディ自体は相当好みであったのだが、萎えてしまった。何せ、女性ヴォーカルである。どうにも好きになれない(極少の例外はあるけれども。)のは生理的な問題であるからして、こればかりは仕方ない
所謂“女性モノ”は最初の数回はかなり聴けるのだが、全然心に響かなく全く継続して聴く気がしないのだ。どうにもヴォーカルという「楽器」に頼り過ぎのきらいが、女性ヴォーカリストにはあるように思えてならず、メロディがコマーシャルであるとなおさら、その頼り過ぎなところがハナに衝き、浅薄・軽薄に感じてしまうのだ。
よって、即抱いた感想は「しもた!女性モノ買うてまったかあ!(涙)」であり、その1曲聴いただけで放り投げてしまったのである。
が、ある時、試聴サイトでこのEdge Cityの曲を何気に聴いてみたら、男性ヴォーカルのナンバーが流れてきて吃驚仰天したのだ。他の曲を更に聴いてみると、著者の大好きな男女混合ヴォーカルの曲があった。
この段階で、あっさりと第一印象を彼方に投げ捨て、再発掘を決定した。男性ヴォーカルも女性ヴォーカルも聴けるアルバムは全然問題ないからである。
これはゆめゆめ捨て置けないアルバムのようだ、と“あたり”を付けたのだ。
結果的に、やはり最初の1曲で、ゲ、となって聴くのを止めずに1回は通しで聴いておけば良かったと、深く反省する次第である。聴く量が半端でないため、気に入りそうもないのはさっさと隅に遣ってしまうのは我ながら余り良くないとは自覚しているが、大したことのない作品を「これは良いんやあ!」と自己欺瞞をして、聴き過ぎたあげくに「耳慣れてしまい、良いアルバムになったような錯覚」を覚えることは、極個人的に最低の聴き方であると思うので、この態度を代えるつもりはない。
と、聴き方について文句を垂れ流し始めるとキリがなくなってしまうので、今回は聴き方に問題があったと一応猛省することにして、次へと話題を進めよう。
問題の1曲目、『Will Not Let You Down』はこのEdge Cityの2枚のヴォーカルのうち、女性リードシンガーであるSherry Brokusのヴォーカルで始まり、コーラスでもう一人のヴォーカリストのJim Pattonがハーモニーをなぞるけれども、殆どがSherryのパートである。曲としてはこのアルバムの中でも1・2を争うポップさであろう。
Sherryのとても暖かく、鼻に掛かったような不透明さがあるにも関わらず、声がピンと通る声質は、これが13曲全て歌われたら、絶対にほかしてしまうところであるが、この男性ヴォーカルと共同で歌われていく分には、曲ごとにアクセントを付けることができるので非常に宜しい。
軽薄でないけれども、軽めのギターソロから気分良く始まるアップテンポのナンバーである。内容も「君を失望させたりしない。助けてあげる、だから逃げずに頑張れ。」というような、エンカレッジ・ソングであり、希望を見出す意思に繋がる明るさがあるナンバーである。
女性に歌わせるのにうってつけであった#1のライトなポップナンバーの次には、バンドのソングライターであり、中心人物であるJim Pattonがローファイ・ラップ気味、彼の音楽活動の始まりと模範になったBob Dylanのヴォーカルを何処かしら思わせる舌の廻し方が独特な#2『No Reason』が続く。
「私はDylanの曲をギターで弾くことで音楽を身に付けていった。」というJimのDylanへの傾倒が推し量れるように曲も何処かしら1960年代のサイケディリックやフォークっぽさが匂ってくる。マイナーなラインを曲の始めからクネクネと泳がせるフィドルはソロパートもユニゾンパートも何処かサザン・アシッドな捻くれた感じがする。かなりハードに弾かれるギターと合わさって、ドライヴ感覚を助長している。
#3『Million Miles Away』もJimがメイン・リードを担当する。前曲のようにコテコテなラップをこの曲でも廻しているが、やはりDylanの歌い方から影響を受けたことが丸分かりな歌唱法である。コーラス部分ではちゃんとメロディに乗せて歌ってはいるけれども、ローファイ・トーク調子のヴォーカルは変わらない。特別印象に残る強烈なヴォーカルというと、こういったミディアムナンバー以上の曲では、あまり力量を発揮しないタイプのようで、メロディとユニゾンするよりも独特の舌を廻すように歌う方が似合うヴォーカリストであるように「この時点」では思える。
この曲はヴォーカルよりもドブロギターやアクースティックギターが全面に押し出されてきて、それが、一定のリズムで合流してくるエレキサウンドと塩梅良くブレンドされている点が注目点だろう。また、優しげで抑えられたポップさが心地良いことも挙げられる。勿論、JimとSherryのハーモニーがどの曲でもオールドタイム・ポップスを思わせるように温かみのあるコーラスを聴かせてくれるのは、このバンドの一番の点であるけれども。
#4『I Turn To You』。JimとSherryの娘−この2人は夫婦のようである。別姓である理由は何処にも言及されていないが−であるMeaghan Pattonの親子3人のハーモニー・コーラスがとても微笑ましいナンバーである。アコーディオンがマンドリンが、暖かい春風のようなどっしりとした湿り気を持って覆い被さってくるような、ゆとりを演出する傍ら、Sherryを中心に殆どのパートが夫婦デュオか親子コーラスで歌われる。
歌詞も、安らぎを見出そうとする現代人の心情を切実に、しかしポジティヴに歌ったようで、とても心を癒されるナンバーである。
♪「In This World Full Of Trouble,Pain And Sorrow.In This World Full Of Hate And Misery.
When I Can’t See No Light Before Me.I Turn To You In My Hour Of Need...」
<この世は困難と痛みと悲しみに満ち、そして憎悪と悲劇が支配している。僕の目の前が真っ暗になって
しまう時、僕は君に目を向ける。必要とするだけずっと・・・・。>
スローバラードの次は一転して、ザクザクとドラムリズムが刻まれるロックチューンの#5『Outsider』が飛び出す。これまたJimのかなり吹っ切れたような勢いのあるヴォーカルにブルーグラス風のフィドルが絡まって、リズム隊とメインラインを引っ張っていく。バックには控え目にオルガンの音も聴こえる。そして、コーラスでの男女ヴォーカルの掛け合いが♪「I’m Outsider」の部分で繰り返され、ギターがガンガンとソロを取る。フィドルが非常にグラスソングな弾かれ方をしているのに、カントリーやグラスライクな印象は全く無く、どちらかというとガレージロックをレイドバックしたような曲に仕上がっているのが面白い。
♪「Just Turned 33,You’re Desperate Man.You’re Juggler.」
<33歳になってしまった。君は絶望の真っ只中にいる一人の男、そう君は曲芸師のよう。>
という一節がとても筆者の現在に近いものがあって、シンクロニシティを思わず感じてしまったのが、#6『Juggler』である。The Bandのようなサザン・アクースティックさが溢れているナンバーであり、その日向臭いアレンジと、乾いた楽器の音色、そしてスローなメロディといい、このアルバムで歌詞を含めても一番のお気に入りである。
このナンバーも#4のようにマンドリンとアコーディオンが、しっとりとしたハートウォーミングな雰囲気を盛り上げている。Jimの語りかけるようなDylan調子のヴォーカルとSherryとのハーモニー部分も、とてもメロディに合っている。
「君は曲芸師(ジャグラー)。ずっと演じつづけなければならない。全てを騙さなくてはならない。だって君は曲芸師なんだから。」
というような、永遠に落ち着ける場所を求めて足掻き続ける人生を歌っているが、これは人類の虚栄心や偽善に対して投げかけた疑問のように聞こえてくるのだ。
♪「And You’re Still Standing Tall By The Light Of That October Moon.
You Still Want To Dance When The Band Plays That Rock’N’Roll Tune.
You’re Juggling The Things That You Know With What’s Left Of Your Dream.
And The Man You’ve Become With The Person You Thought You Might Be.」
このラスト・ヴァースを聴くと、何とも言えない透明感のある純粋な寂しさと悲しみが身体の奥からせり上がって来るように思える。何とも哀しく、美しい詩である。敢えて解釈はしない。曲を是非聴いて、自分で感じて欲しい。
#7『Finest Hour』は引き続いて美しいバラード。アクースティックにアレンジを纏めているし、ストリングスシンセのようにミキシングされたフィドルが鳴いているナンバーであるけれども、それ程ルーツ、アーシーさが感じられない。どちらかというと、Adult Rockのアルバムに入っているバラードのようなあっさり目のバラードだ。が、Sherryのリードで歌われるこの歌の美しさは前曲に引けを取らないだろう。深みという点では負けているが、それは#6が大名曲なためであるから致し方ない。
#8『It’s Over Now,Baby Blue』は言わずと知れたBob Dylanの1964年の作。Jim PattonのDylanへの敬意が明確な形を取って込められている選曲だろう。この曲については特段コメントは必要ない。かなりバタバタのドラムとリフからブンブンとくぐもるベース、そしてハードなギターでロックンロールとして捧げられている。フォーキィやカントリーの感覚よりも現代のガレージロック的な匂いがする。
#9『Prisoner Of The Blues』は筆者がデフォルトで評価を高くするマンドリンがバックで鳴るギターよりも主役を張るミディアムなポップナンバー。この曲ではJimがメロディに合わせて流れるように歌っているという、このアルバムでは結構珍しい形となっている。ギターソロのパートでは、産業ロックのギターソロのようにパワフルな音色が被さる中で、淡々とコードを進行するマンドリンの音色はHootersのロックナンバーを思わせ、著者がとてもお気に入りのナンバーとなっている。ロックンロールでのマンドリンは土着ソングでは楽しめないインパクトがあると思う。
ドブロギターの音色がとても暖かい、#10『Alicenna St』は#7のようなアクースティックなバラードであるけれども、こちらの曲ではレイドバックした感覚がきっちりと演出されており、Jimとのハーモニー・ヴォーカルもとても曲のゆったりと流れる大河のような雄大さに色を添えている。
しかし、このナンバーも朝から晩まで働いて疲れた夫を見る主婦の視点から歌われた曲であり、「働けど働けど我が暮らし楽にならず。じっと手を見る。」という古典に見られるような世界観がたゆたっている。何処となく人生の虚しさを匂わせるが、悲観的でない内容である。が、その「貧しさから脱却したい夢」を持つこと自体が、哀愁を更に募らせるような気がしてならない。詩人としてのJim Pattonの世界観が伺えるナンバーである。
#11『Baby I Remember You』はリードヴォーカルを男性のJimに置き換えたような#10といったタイプのスローバラードである。ドブロギターとスライドギターが#10よりも尾を引くように泣きを見せるナンバーである。歌の内容は、ある日嘗ての恋人と過ごした場面を思い出す、思い出す、想い出す、というようなとてもシンプルな歌詞が続いていくだけである。それ故に、想いの深さが感じられる。また過ぎ去った日々を良いものとして懐古するようなニュアンスも見受けられる。
誰もが何時か何処かで想い出す、青い春のような昔の記憶、というようなロマンティックなルックバック・ソングだろう。
そしてクレジットの最後の#12『By The Water』は8分以上に及ぶ、キャッチーであるが、壮大な変化で流れていくナンバーである。その後の雄大な展開を匂わせる叙情的なピアノと抑えたギターでスタートし、中盤でアップテンポに転じ、気持ち良く流れていくメロディは、大物アーティストがたまに演じる「長い曲」に匹敵する変化が堪能できる。
Jimは時にはラップやトーキング調子の早口で歌詞を追い、時には曲に乗せて歌い、Sherryのハーモニーとバックヴォーカルも実に調子が乗っている。しかも展開される歌詞の内容も長い物語となっていて、これは聴き応えがあるナンバーである。長い曲で長いストーリーというパターンは意外に少なく、大半はインストゥルメンタルのバトルが占める割合が多いというパターンの中で、これは凄い。
そして全くクレジットされていないシークレットトラック#13は、以前にEPで発表している『Nick』だろう。アルバムタイトルの「Mistery Ride」というフレーズが聴けるのもこのナンバーだ。かなりアクースティックでカントリー調の曲でありJimの歌唱法もメロディに完全にシンクロして歌っているという、これまた珍しいナンバーだ。
そして#14にはこれまた以前に発表された『After The Dance』のファーストフレーズだけがアクースティックアレンジでアウトテイク的に短く挿入されている。このナンバーはショウの終わりとその終わりからの始まりをを暗示するような曲なので、そういったこれからを示唆して最後に入れられたのかもしれない。
以上、14曲。米国東海岸のメリーランドはボルティモアを拠点に1970年代から活動を続けてきたソングライター、Jim Pattonが1994年にテキサスのオースティンに移住し、南部を活動の場としてからも妻(元かもしれない)のSherry Brokusとヴォーカルを分け合うように活動している、Edge Cityのアルバムの内容について触れてみた。
このアルバムに収録されている曲は、一番新しく書かれたものでも1996年。#12に至っては1975年に原曲が考え出され、1985年に現在の形に仕上がったようだ。
この「Mistery Ride」は現在と違うラインナップで1995年ごろに「Outsiders」というタイトルでリリースされたアルバムを再録、一部変更したもののようだ。またその後すぐに4曲入りのEP「Ray Of Light」をリリース。こちらは『Niki』のようなフォーキィでカントリー風の曲を集めたエクストラ・ワークの発表を意図していたらしい。
また1997年に「Schaffer's Safety In Numbers,Vol.1」というオースティンのシンガーソングライターのコンピレーションアルバムに2曲『After The Dance』、『You Are Everything To Me』を録音している。
このアルバムでのメンバーを集めて、レコーディングに没入したのが1999年。幾つかの資料では1999年に初めて結成と書かれているが、実際はボルティモア在住時からEdge Cityとして活動しているのは間違いないようだ。詳しい方がおれば是非情報を戴きたい。
このアルバムではJim Pattonがリズムギターとヴォーカル、Sherry Brokusがヴォーカルというデュオを中心にして、Joe ElyやJohn MellencampバンドのギタリストであったDavid Grissomをリードギターに。
ソロアルバムも数枚発表している女性マンドリン・フィドル奏者のDarcie Deaville。彼女はオースティン在住のミュージシャンのアルバムで多数客演しており、Jimmy LaFaveやKelly Willisが有名どころか。
更にハワイ日系3世のGlenn Fukunagaをベースに。彼はJoe ElyやAlejandro Escovedoのバックバンドで演奏歴がある。Bob Dylanの『Series of Dreams』のベースも彼と紹介されている。
更に、アコーディオンとキーボードにTish HinojosaやBruce RobisonのバンドでプレイしていたChip Dolan、ドラムスにPaul Peacyという人達を迎えている。ドラマーのPaul Peacyはこのアルバム以前の録音のプロデュースも担当している。
そしてプロデューサー兼、ドブロギターとアクースティックギターにLlyod Maines。彼の名前は1990年代初頭のオルタナ・カントリーブームから著名バンドを追いかけていたリスナーには懐かしいかもしれない。ドブロギターやペダルスティールの奏者として、Uncle Tupeloの「Anodyne」、Wilcoの「A.M.」、Wagonの「No Kinder Room」に参加している。またCharlie Robinsonの「Bandera」のプロデューサー、Richard Bucknerの殆どのアルバムにボトルネックギター系のプレイヤーとして参加、プロデュースも受け持つという幅広い活動歴を誇っている。
これらのミュージシャンによって録音された「Mystery Ride」はJephason AirplaneミーツEverly Brothersとメディアに表現されたようにテキサスと故郷の東海岸ではかなりの評価を得ている。
現在はテキサスとメリーランドを中心にツアーを順調にこなしているようだが、ユニークなのはテキサスと東海岸でバックバンドを交代しつつツアーをしていることだ。
核はヴォーカルの2名だけで、後はツアーごと、地域ごとにメンバーを集めての演奏というテンポラリー形式のバンドとして演奏を続けているところが面白い。レコーディング時の面子で、バンドに参加しつづけているのはマンドリンプレイヤーのDarcie Deavilleのみである。彼女もオースティン近隣での活動にしか参加せずに、普段はソロアーティストやバックミュージシャンとして生計を立てているそうだが。
フィドルやドブロ、マンドリンをかなり使用しているが、あからさまなカントリー臭さがなく、レイドバックとアクースティック感覚の強いロックバンドとして印象を植え付けているところが、このバンドがロックバンドとして評価できる所以である。
また歌詞がとても暗喩的であり、メッセージ性の強い人間の弱さや必要悪に対する感慨を顕したような、深い詩がとても素晴らしい。
「私が描く人々は、争い、無気力になり、そして何もする気が起きなくなり、絶望する、このようなプロセスを踏んでいるんだ。でも彼らはその問題について考えを巡らせ、何とかしようともがいているんだ。」
というJim Pattonのコメントにあるように、かなり痛い詩も多いが、必ず希望を持てるような、Jimの暖かい視線も練りこまれているため、単純に鬱になるような詩は存在しない。
基本的に明るいメロディとその前向きに生きようという込められた願いが、このアルバム陽性の属性を付加しているようだ。
「私は言葉に魅了され、そして物語性にも魅力を感じている。20年前から音楽として良く響く詩を書いてきたし、これから20年後も同じように歌とマッチする詩を書いていきたい。」
というJimの新しいマテリアルに期待したい。このアルバムでは1996年以降の作品はないのだから。
しかし、Edge Cityというのは、都会と田舎的な音楽の間に立っているという音楽性を示したいのか、それとも都会と田舎の人間模様をその中間に立ってみていると比喩したものか、そんなことを考えてしまう、彼の曲を聴いているうちに、無意識にであるが。
勿論、後者であると思う。 (2002.3.9.)
 Late Last Night / Shame (2001)
Late Last Night / Shame (2001)
Roots ★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Alternative ★★
You Can Listen From Here
Shameという、いかにも現代のオルタナティヴ・ロックバンドが好んで付けそうな名前の(そうけ?)バンドがリリースするCDとしては、この「Late Last Night」で4枚目となる。
しかし、メジャー・チャートを見て、日本の売れ筋という洋楽CDの売上上位を眺めると、まさに
「こんなん買ってて、恥ずかしいやんか!!。」とか、
「こんなんメジャーで出すなんて、只の恥知らずとちゃうやろか?。」
って叫びたくなるような詰まらない作品の何と多いことやら。(ああ、またいらん敵を求めて増やすような発言が出てくるなあ・・・・。)
その点、このShameは、日本語訳としては「恥じる」とか「恥ずかしい」という直訳を当てはめることのできるバンド名を持っているけれども、筆者的に言えば、
知らなかったら、ロックファンとして“恥じ”やん!!
・・・と迄は言えないところがまだ弱いねんけど・・・(笑)
手放しで賞賛しても何ら“恥ずかしくない”アーティストであるのは太鼓判やで〜。
の程度までは咆哮可能なレヴェルにあるポップ・ロックバンドであると、確信している。
デヴュー・アルバムである「Seeking Shelter」は当初、カセットテープのみの発売であったが、2ndミニアルバムの「Shade Of Grey」の発表後にCDとしてリマスターされて再発売の運びになっている。よって、彼らの作品は全てデジタル音源として入手可能である。
この1stアルバムのタイトルは、Bob Segerの大名曲『Against The Wind』の歌詞を思い起こさせ、未だ聴いてはいないのだが、興味はそそられる。いずれは手に入れたいアルバムである。
ペンシルヴァニア州のリーディングという街の近郊を活動拠点とする、このShameという東海岸のロックバンドの音楽を知ったのは、その2枚目の「Shade Of Grey」からである。
ジャケットがとても綺麗であったため、米国のインディストアで購入したのだが、内容はぶっちゃけた話、印象に然程残るものではなかった。ジャケットも同時期に発売されたバッファローのバンド53 Daysの2ndアルバム「Hot Water Music」の写真を色違いで模写したような「水滴落ちて波紋が拡がる」というデザインであったので、眼を引いた故の購入であったのだが。
余談になるが、2枚の素晴らしいアルバムと、最後の1枚、紙ジャケのレアトラック集−大変残念ながらこの5ドルという低価格のミニアルバムは2枚のオリジナルアルバムの出来と比較すると、駄作の誹りを免れない酷い代物であった。値段的には妥当だが。(苦笑)−を最後に53 Daysは終に解散となってしまった。
しかし、解散直前の内紛後のメンバー交代したそのままで、新しく名前を変えて活動をするとのことで、まずは一安心というところだろう。但し、ソングライターの1人であった、Tom Robinson氏を欠いて、以前のようにルーツでしかも正統派ロックな音楽路線を踏襲してくれるかについては、やや不安が残る。
参考までに、新バンド名はThe C.J.Moore Bandというリーダーの名を冠したものとなっている。
と、53 Daysの今後を話す場ではなかった。Shameに話題を戻すとしよう。
と言いつつ、また別のバンドを引き合いに出してしまい恐縮だが、この4枚目を聴くにあたり、前作の3枚目「Pop 20」と今作「Late Last Night」を何度も聴き直してみた。
そして、第一に連想したことが、昨年2001年に全米で一番の売上を記録したロック(と言われているようだ。)バンド、Lifehouseの存在だった。がしかし、このShameがLifehouse、引いてはその複写元のMatchbox20の完全無欠な金返せアルバム「Mad Season」の亜流とかと述べるつもりは更々ない。
Shameの演奏する音楽は、オルタナティヴの如く独善的に重く、暗鬱に拡がるような曇天を視覚的に感じるような音楽では、決して無い。が、何処かしら「あ、Lifehouseに似てるやん。」と思わせる要素が存在したのは間違いない。まあ、聴き込むにつれて、その印象は次第に希薄になり、終いには消えうせてしまったけれども。
で、今段、レヴューを執筆するにあたり、その理由を改めて考えてみた。そして、思ったことは、オルタナティヴとルーツ系のロックという基本形の違いこそあれ、“抑えたポップさ”が存在すると言うことである。
が、Lifehouseでの、どうにも我慢の出来ない中途半端なポップさと、気が滅入りそうになる遅いんだか速いんだかどうにも判断が尽きかねる曲のテンポのように、ネガティヴな「抑制」をこの「Late Last Night」では感じることは、間違っても無い。最初に聴いた時の印象でも否定的な「似ていて良くないやん。」という感情は涌いて来なかったし。
けれども、どうやら「抑え」ということに対する幾ばくかの不満が突出する形で、この比較すべき対象として挙げた両者の印象を結びつけたようである。
Shameの「Late Last Night」や「Pop 20」に感じるのは、あくまでも「抑制の程よく効いた」ほろ苦いポップさであり、もっとストレートに攻めても良いのにという、ある意味自己の趣味を求め過ぎな故の不満こそあれ、中途半端というマイナス評価だけで大両断すべき作品では決してないということである。
全く方向性の見えない、無思慮に売れ筋の潮流に乗っているだけのオルタナティヴのように、恣意的にポップなメロディ・メイキングを避けているような、気持ちの悪さは、このバンドには感じ取ることはできない。言い換えれば、それは「抑え込まれた故の鬱屈」であり、そういった感情をメロディに篭めること自体、娯楽音楽と言うジャンルの一端であるロックミュージックに反している以外の何物でもないと思うのだが。
まあ、オルタナ系を貶し出すと、また永遠に罵詈雑言の垂れ流しになるため、この辺で一応打ち止めにしておいた方が賢明のようだ。(遅い。)
と記述しているが、散々酷評しているオルタナティヴ・ロックの愛好家にも受け入れられる下地を有したバンドがShameであることも、これまた否定できないと考えているのだ。その点については、以下のバンドの提供するサウンドの全体像を述べていく段で説明を試みてみたいと予定をしているが。
まあ、全体の感じとしては、とても地味である。兎に角、地味である。何処を切っても地味と言う樹液が滲み出てくるくらいに地味である。が、地味だからとはいえ、ポップさを言い訳程度に付加しただけのサッド・コアやスロー・コア音楽と同様にアンチポップを追求したような嫌悪感は感じない。
が、前作までに必ず何曲かはトラッキングされていた、アップテンポの少しオルタナティヴやパワー・ポップを匂わせるようなロックチューンは殆ど姿を消してしまっている。殆どがミディアムな曲となり、美しいバラードと中庸な速さの曲だけの構成に変じてしまっている。1stアルバムのみ未聴であるため、全体を通じてというにはやや語弊があるけれども、これまでには拘りの様に何曲かは必ず創作していた16ビートのシンプルなロックンロールという世界構築からは、やや距離を置き始めたなあ、と思わずにはいられない最新作になっている。
更に、元来の傾向としてルーツロックではあるのだが、カントリーとかブルーグラスといったアメリカン・フォーク系の音は綺麗さっぱり存在しないバンドであり、サザン、スワンプとも全然違う音である。
近いというと、The Wallflowersを更に地味にしたようなもの、或いは英国出身のアメリカン・ルーツサウンドを模倣に徹してみたが、いまいち完全なアメリカン・ルーツの音を出し切れていないMiniberに近いだろうか。
悪し様に表現すれば、「中途半端」だろう。熱心なカントリーロックやサザン・ロック、スワンプロックの愛好家からの見地では、Roots Rockの分類に入らないとなるかもしれない。
ゴンゴンなオルタナティヴではないのは間違いないけれども、Modern Rockと表現すれば多少は適切だろう。ルーツロックを下地にしつつ、1990年代以降のメジャーなロックの流れを取り入れているバンドである。
こう表現すると、ロックの暗黒ディケイドであった1990年代ですら、希にメジャーでも出現していた王道的なアメリカンロックサウンドを思い浮かべることになりそうだ。であるが、そこまで際立った要素がどうにも今一歩欠けているのだ。好意的な表現をすれば、冷静に大人びたポップを演奏しているとなるだろうけれども。
実際に、アクースティックなところもあり、エレクトリックな「出っ張り」も存在するし、Wheezer程ポップ仕立てにはなっていないけれども、下世話にならないくらいに程よく心地良いキャッチーさはある。また、ルーツィーなダウン・トゥ・アースな安定性を芯としているし、それでいて現代的というか、埃まみれ・泥まみれなダサダサなサウンドは聴こえて来ず、都会的なクールさと淡白さも同居しているのだ。
こうなると、仮に好みのツボを外れたら、「何だかわからない、オルタナティヴっぽいアメリカンロック。」「特徴無い。」と裁断されても仕方の無いサウンドであるかもしれない。
仮定の話として、後少し、コマーシャルにしてメジャーなタテノリロックンロールな曲を増やして、全体を元気印な若者アルバムに仕上げていれば、Power Popの良作と本邦の市場でも認知されそうな程度の雰囲気が支配しているとは感じる。
が、惜しむらくは、そこまで衆目の注意を引くようなコマーシャルの権化のようなサウンドを持っていない。オルタナティヴで「ポップ」という表現を通常当てはめられている多くのバンドよりは、比較にならないくらいコマーシャルなのだが。
苦みばしった、ヒネリ系の音ではないし、とはいえ「渋い」と万人に同意を得れるというと、やや弱い。
「渋い系統に属する」音楽であろうか・・・・・・・。どうも曖昧であるけれども。
どのジャンルにも算術的公式でいう、集合の円が重なっているような音楽は、真の意味でのAlternative=万能性を持つ可能性もあるが、対称的に、どれも中途半端にしか良さが顕現していない、「多色を混ぜ合わせると灰色になる」を実践するような没個性な代物になってしまう危険性もある。
このShameの最新アルバムは、ギリギリのところで危うい一線に留まっている曲が集まったアルバムのように思えるのだ。アップビートな曲が全く無いけれども、ルーツロックをベースに置いているため、ロックンロールとしての重量感は、フワフワと尻も軽く浮き上がってしまうことを押し留めるだけの分量は確保しているし、耳に心地良いポップさが感じられるナンバーもちゃんと揃っている。
若手のバンドの割には、燦々と輝く太陽の下で聴くよりも、晩冬午後遅くの傾いた陽射しの下や宵の口に気持ちを開放して一日の疲れを癒しながら聴くという状況が似合う、落ち着き過ぎた音を創造しているが所以であろう、どうも巧く枯れた雰囲気を出し過ぎのため、更に地味に聴こえることに拍車が掛かっているのだろうが。
今作では収録曲は僅かに8曲と言う、1980年代のアナログ盤並みの曲数と収録時間である。合計約32分というトータルの演奏時間は、集中して耳を傾けるには適当な長さだろう。曲数・収録時間が膨張し、しかも内容が長さについて行けずに冗長的なアルバムが多くなるという、昨今の傾向に真正面から立ち向かうような纏め方は、このアルバムに限って考えると成功しているようである。
これ以上、長いと、さすがにこの地味さでは食傷気味になる危険性が多いだろうから。
また、8曲のうち3曲、#4『Left Untold』、#5『Porch Light』そして#7『Rain』が1999年発表の前作「Pop 20」に収録されていたナンバーの再録音である。純粋な新曲は約半分の5曲しかないのである。
前作を発表後、バンドはソングライティングの技術を向上するために、1年以上全くクラブサーキットを行わずに演奏活動を休止していたそうだが、その間に前作への不満が顕現し、録り直しという形を取ったのだろうか。
とまれ、8曲入りの「Late Last Night」は2001年の12月にインディ・レーベルから4枚目のアルバムとして、新作としてリリースされた。
#1『Roadside』から力強いギターのパンチとハモンドB3がルーツロックの匂いをプンプン振りまく、上品なルーツナンバーが登場する。リード・ヴォーカルのPeter Errichの程よく枯れたハスキーなヴォーカルが、曲の鄙びたような雰囲気を更に盛り上げている。物凄くポップでではないのだが、アーバンロックに通じる秘められた情熱のような感慨が行間から沸きあがって来るようなミディアムなナンバーである。後半でのヴォーカルのシャウトとオルガンの乱れ弾きは聴き場所である。
#2『One Note Serenade』は#6『Before We Say Goodbye』と並んで、このアルバムの中では速いロックチューンに分類されるだろう。#6は軽快さでは#2よりも上を行くだろうが、現代ロックの物足りないコマーシャルさが曲全体を支配しているためか、今一歩入り込めない。ライトなポップナンバーとしてはややアンキャッチーに終始しているし、ハードで縦割り勝負のアップチューンとしてはインパクトが足りないので、これはやや消化不良である。
が、#2のシンプルなコードを繰り返すギターリフにオルガンが追いつき、リズム・セクションが合流し、適度なビヨンド・ミディアムなロックを演じてくれるのは結構楽しく聴ける。かなりパワフルであるのだが、ここでもオルタナティヴ的な色合いが幅を利かせていて、コマーシャルに徹しきれないのか。或いはルーツロックよりもオルタナティヴにまだしがみつく傾向が抜けないのか、悪くないのだが、一本抜けきれていない感じは否めない。
ルーツ・ハードナンバーとして評価可能であるとは思う。ルーツと現代ロックの融合失敗作と捉えるよりは。
#3『Ghosts In The Tavern』はアクースティックで、ビターなスローナンバーである。ヴォーカルのPeterの声がとても伸びやかに拡がっているナンバーである。とても20歳前半のメンバーで演奏しているとは思えないくらい、落ち着いたナンバーであるのだが、やや暗過ぎるか。サッドコア系のファンには歓迎されそうだが。
#4『Left Untold』も似た様相を呈している、アクースティック且つオルタナティヴの影響を感じるナンバーである。この2曲に共通しているのは、抑え過ぎてポップさが後退し過ぎている点だろう。良いところは、情緒というか透明感のある悲しみが普通にさり気なく流れていることだろう。
そしてスライドギターが、やや泣きながらオルガンとハーモニーを奏でる、#5『Porch Light』。前作「Pop 20」のオープニングナンバーであったこの曲は、旧アレンジと聴き比べるとバンドの成長が如実に伺えるトラックでもある。
オルガンの音がより低い空域を飛ぶように、じっくりとしたアレンジになり、前ヴァージョンでは殆ど聴こえなかったスライドギターを大胆に前面に出している。また、ヴォーカリストとしてPeterの喉が非常に成熟したことが明確に感じ取れる。まだ青臭さの残っていた3rdアルバムでの歌唱と比べて、格段に男の色気のような艶が出ている。また、コーラスの重ね方も巧みになり、実に黄昏た寂しさの漂う名曲に生まれ変わっている。
また、再録音の最後1曲『Rain』を含むラスト2曲は、#5と並んで、最大の聴き所であるのは間違いない。
#7『Rain』は、元々はアクースティックギター1本に、オルガンがバックを担当する静かなナンバーであったが、この新録音ヴァージョンでは、リリカルな響きのピアノを大胆にフューチャーし、ハモンドB3をかなり引っ込めている。また、電気ギターの雄大な演奏まで加わって、後半ではかなりの美しくもドラマティックな盛り上がりを見せてくれる。
内面に溢れる感情を吐き出すように歌うPeterのリード・パートにパワー満載のコーラスが合わさり、バラードとして王道の出来となっている。
#8『Raslyn Square』もバラードとしてとても美麗な曲であり、ルーツとかオルタナティヴを超越した、ヴォーカル・ロックとして素直に感動できるクオリティが内在しているナンバーである。ギター兼務のMichael Noeckerが弾くピアノだけがインストゥルメンタルであり、切々と練り上げられるメロディには脱帽だ。殆どPeterのソロ・ヴォーカルだけであるが、ラスト近くでMichaelも参加して綺麗なヴォーカルのフュージョン・プレイを聴かせてくれる。
こういった#5、#7、#8のような名曲が全てバラード型なため、全体の印象はかなりスローなアルバムと錯覚してしまうのだ。実際にスローなナンバーが多いのは確かであるけれども。
以上、バラードで物凄く進歩したバンド、Shameの最新作の各曲について触れてみた。
折々について、触れてきたが、これまでにミニアルバム1枚、10曲が最大という潔い長さのフルアルバムを3枚リリースしている。
メンバーはこれまでに中核のソングライター2名を除くと、流動的に変化している。現在のラインナップは
Peter Errich (L.Vocal,Guitars) , Brian Rutolo (Drums,Percussion) ,Keith Knowles (Bass,Vocal)
Michael Noecker (Guitars,B3,Piano,L&B.Vocal)
の4名。今作ではMichaelの鍵盤が前作よりも控え目であるが、より要点を突いて演奏されているため、ルーツテイストの向上に一番寄与しているだろう。
結成母体は高校の友人であったPeterとBrianが共同で曲を作り始めたこと。彼らは1978年生まれであるというので、まだ23〜4歳である。1990年代半ばの高校在学中からShameと名乗ったバンドを結成し、街の小さななクラブで演奏を始めていたようだ。
1996年に高校を卒業後、即ツアーを開始。周辺の3州と、海を渡って英国まで足を伸ばしてツアーをしたそうだ。
1997年から毎年のように新譜を発売して、1999年の「Pop 20」を発売する頃にはWanderlustのような日本でも一部では知られているそこそこのバンドとジョイントでライヴを行えるくらいのステータスは獲得していたようだ。
その後、2001年半ばまで、充電と学習を兼ねたモラトリアムに突入し、この「Late Last Night」で復活したという次第である。
メンバーが影響を受けたミュージシャンはBob DylanからCounting Crows、Dog’s Eye View、Tonic、REMそしてWallflowers、Radioheadとメジャーに限って挙げてみてもかなりバラバラである。
こういった現代のバンドとアメリカン・ルーツへの嗜好を纏めたのがこのサウンドなのは非常に理解できる気がするのだ。まだまだ、完成に至っていないところは、やはりMinibarに似ていると思う。
また、何度か英国をツアーして歓迎されているところが、アメリカのバンドながら、英国のバンドが模倣したような控え目なルーツテイストを感じれる根拠なのだろう。根っからのアメリカンなサウンドだけを演奏するタイプのバンドではないからだ。
冒頭からの繰り返しになるけれども、知っていて恥になることは全くないし、むしろこういったバンドは万人に聴ける間口の広さがあるだろうから、機会があれば聴いて欲しい。
良い曲も入ったアルバムを製作しているので、これからのバンドであるだろう、間違いなく。注目は続けていきたいところだ。
是非ルーツ寄りな音楽の進路を歩んで欲しい。今作でかなり音楽的に成長したバンドである。
(2001.3.12.)

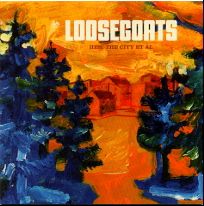 Her,The City Et Al / Loosegoats (2001)
Her,The City Et Al / Loosegoats (2001)