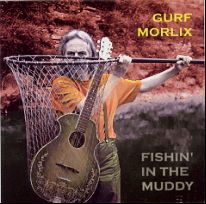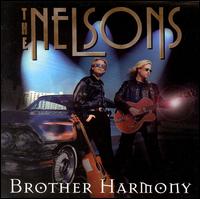 Brother Harmony / The Nelsons (2000)
Brother Harmony / The Nelsons (2000)
Roots ★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Country ★★★★
You Can Listen From Here
まず、何を差し置いても賞賛したいことなのだが、
某著名音楽雑誌である「燃焼!」(をい)に間違っても掲載されることのないようなアルバムを、Nelson兄弟が創ったことに拍手を送りたい!!!
またぞろウィルスメールを喰らうような危険なことを書いているが、いい加減ここいらで、HR至上主義でありしかも掲載レヴューで点数が高いアルバムは殆どハズレという伝説を持つこの雑誌が、殆ど唯一の「ロック」の読み物と言う現状から進歩した方が良いんでは?と考えていることに偽りは無い。
筆者的にはハードロックはあくまでもハードロックであり、永遠にリアル・“ロックンロール”にはならない。常にベストにはならないジャンルの音楽である。
従って、日本に於てのみ、依然世界で唯一つともいえるHRが命脈を保っている市場性に色んな意味で涙を禁じえない。
という本邦の状況を鑑みて、本作ではThe Nelsonsという名義になっているけれども、実際はNelsonというバンド名(またはデュオ名)の方が最後のハードロックの楽園である日本では遥かに通りが良いだろう。
そう、グランジ・ヘヴィロックの侵略目前たる1990年に、4枚の全米トップ40シングルをブレイクさせたNelsonが、The Nelsonsと改名して発表したアルバムを今回は取り上げることにする。
一般流通から、チェック漏れのために約1年遅れで入手した「Brother Harmony」だけれども、まず、「After The Rain」(1990年)、「Silence Is Broken」(1997年)、「Imaginator」(1996年発売。実際のレコーディングは1993年。)こそNelsonというリスナーは、絶対に手を出さないほうが賢明である。
そういった音を期待しているなら、このレヴュー読まれても時間の無駄なので、とっとと戦術的転進(撤退・退却のこと。どこかのインペリアル・アーミーは「負ける」「下がる」ことが概念的に許されてなかったので、こういう表現で欺瞞したのだ。どーでもエエねんけど。)を強力にお薦めする。
1stで輝きを放っていたBon Joviの系譜に連なるような、しかも同年にデヴューしたFirehouseを凌駕する艶やかで、ゴージャスなサウンド−これなら産業ロックと呼んでも差し支えないだろう−は完全に姿を消している。
ましてや、市場性に合わないということで、発売前にお蔵入りとなった「Imaginator」を覆っていた、一般的な水準ではそれ程でもないけれど彼らにしてはダークでヘヴィな感じなと爪の垢程も存在しない。
更に、無理矢理ヘヴィ・ハード路線を追求したナンバーが、彼等の持ち味の爽やかなポップロック・チューンと水と油のような違和感を発信していた「Silence Is Broken」における統一性の無さ等は、議論を待つまでもなく、当然なしである。
と、ここまで少々述べただけだが、要するに
筆者の如く「Because They Can」こそ、Nelsonの最高傑作じゃああ!!!
と思わないNelsonのファンには、絶対にお薦めできん!!
・・・・まあ、どっちかと言えば、筆者の方が異端かもね。Nelsonファンとしては。
即ち、「Because They Can」(1995年)での純粋な産業ロックというよりも、Arina West Coast Rockという方向性が好きであり、「Life」(1999年)のAdult Contemporary路線が駄目でなかった人にはマストという、正反対のNelsonを許容可能な層へのマスター・ピースである。
が、「Because They Can」がアリーナサウンド+西海岸ロックンロールであり、「Life」がかなりポップでアクースティックなAdult Rockであるとするなら、このオフィシャル・リリース順では「Life」の前とされている、が実際のリリースは2000年になるため、バックナンバーとしては6作目のスタジオレコーディングとなる「Brother Harmony」は、Country Rockであり、1970年代のWest Coast Musicの21世紀での再現ともいえる音楽性を有するアルバムとなっている。
1990年以降のシーンに興味がない人でも、Rick Nelsonの双子の息子が彼らと言えば、それなりに親近感が沸くというリスナーには諸手を挙げて推薦できる内容だ。
という訳で、ルーツロックが全てカントリーに聴こえるようなメタル・ハード系のリスナーはきっと鼻を鳴らして子馬鹿にするような作品であることも、想像に難くない。
お断りしておけば、筆者は「After The Rain」は非常に良いアルバムだと考えているし、カントリー/ポップスの大スターであった父親Rickの足跡を安易に辿らずに、当節流行であったアリーナロックのサウンドでシーンに勝負を掛けたその姿勢は、とても評価に値するとも考えている。
が、アクースティックな側面も魅力であったNo.1シングル『Love And Affection』や、爽快感の突き抜けていたトップ5ヒットの『After The Rain』といったナンバーでの最大の武器は、ハード・ロックとしてのギター・リフではなく、やはり爽やかなメロディに在ったと思う。
また、『Only Time Will Tell』や『More Than Ever』といったヒットナンバーにしても、メロディアス・ハードの代表と表現できるように、メロディが際立っていたわけである。
メジャーデヴューのために、時流に敢えて迎合し、1980年代のシーンを席巻したポップメタル・産業ロックのスタイルを取り入れたことは決して悪いとは思わない。しかし、彼等本来の音楽性がハード/メタルに在ったかというと、矢張り疑問に思うことが「Because They Can」を聴く前からあった。何処となく、かなり無理矢理にHair Metalと表現されたハードサウンドを導入しているようなナンバーが既に1stでも見えていた。
敢えてハードロックの方向性を追及しなくても、Nelson兄弟の持つポップセンスで十分に“Hard Rock”としてではなく、“American Rock”として売り込んでいけるだけの実力があるのではないのか、という疑問は実質の2枚目作である「Because They Can」で図らずも見れることとなったが。
レコード会社に駄目出しをされた本当のセカンド・アルバムである「Imaginator」では、かなりハードでダークな趣に走りかけるが、それでもそのボツ企画から数えて2年後に、アクースティックであり青空ロックという表現がぴったりと似合うアルバムをリリースしたのは、単にレコード会社の方針に従っただけでなく、Nelson兄弟の音楽性に凡百のハードサウンドにしがみつくことのないバックボーンがあったからに他ならないと思っている。さもなくば、いくらハードロックなアルバムに駄目を出されても、1stのような作品を持ってくれば良かったのだし。
その「Because They Can」のハード・メタル離れした音楽性にファンから非難の集中砲火を浴びたためか、当時のインタヴューでも「HRをもう一度やりたい。」的な発言をしつつリリースされた「Silence Is Broken」はあまりにもハード寄りなチューンと、ハードロックを演ると意気込んではみたものの、結局ポップで歯切れの良い普通のロックチューンも取り入れていた故に、その両者の隔絶が激しく、どうもバランスの悪い凡作なHRになってしまっていて、この時点で少々彼等には失望してしまった。
結局米国では1999年まで発売されなかった「Silence Is Broken」では、“1stセールスの夢よもう一度”の意図で作成されたとしか思えないアルバムだった。が、それなりの完成度にしてしまうのが流石ではある。
が、これまたHRカラーを抜いてきたけれども、まだまだ“産業ハードロックやった方が良いのかなあ・・・・”的な迷いが見えた「Life」では、「Because They Can」に近いキャッチ−でアダルトなロックへの再度の歩み寄りを見せ、やや手応えは薄かったもののこれからを期待させるアルバムにはなっていた。
その「Life」で、父Rickの「Life」をカヴァーし、2000年にはRick Nelsonのカヴァーをライヴ録音した「Like Father,Like Sons」を発表する等、次第にNelson兄弟がCheap TrickやQueenと同時に聴いて育ったと言うCountryやCountry Rockへの傾倒を表に出し始めていた。
参考までに、「Life」は日本のみ先行発売されている。アメリカでの発売は2001年であり、ジャケットもハンサムな双子のショットである日本盤とは大きく意匠を変え、恐らくは幼少時代のNelsonsを絵画的にしかもかなり暗鬱に描いた、お世辞にもコマーシャルとはいえないジャケットとなっている。
そういった経過を踏まえて、2000年末に一般流通に乗ったのが、この発売順では7枚目となる「Brother Harmony」である。公式には1998年発売となっているが、何処でもプレスされた形跡がない。
米国のWebサイトなどでは「Life」と同じく日本のみで大先行された、という記載も見られるがそれは完全に誤りであり、このアルバムの日本盤は未だリリースされていない。(と思う。)というか、こういうCountry Rockなアルバムが日本盤化される筈がないことを米国人は理解していないのだろう。嘆かわしいやら、笑えるというか・・・・。ハードロックバンドなら何でも日本だけの発売、という認識自体は全然事実なので、こういった誤謬も仕方ないかもしれないけれども。(苦笑)
実際にレコーディングの日付等はインナーにも記載されていないが、1998年にある程度はレコーディングを終えていたことになっている。しかし、この「Brother Harmony」は結局正式には発売されていなかったようだ。
このカントリーロックのアルバムをリリースする前に先駆け、このアルバムのデモトラックとコンプリートしたナンバーを含んだ特別限定盤である「Masters & Demos」を少数プレスしている。そして、1998年末にこの「Brother Harmony」を極少数プレ・リリースしたことになっているが、これが何処で発売されたかは全く不明である。
察するに、やはり「Because They Can」と同一の方向性を有するアルバムとはいえ、まだ産業ロックサウンドの存在していた同作よりも、もっとポップス寄りの「Brother Harmony」を唐突に発売するのは流石に、商業戦略上躊躇ったのだろう。GunnarとMatthewの兄弟だけでなく、レーベルも。
よって、まだアメリカン・ハードロックな手触りの残留する「Life」を先に発売したのだろう。その後、「Like Father,Like Sons」でRicky Nelsonのトリビュート形式のライヴがある程度の受け入れをされたため、2000年末に本作の発売に踏み切ったのだと想像している。
本邦では「Life」以降のアルバムは全くCDとして国内盤化されていないが、米国としては2000年から2001年にかけて今までプレスされていなかった彼らのアルバムが次々に発売ラッシュとなった。これも日米の市場性の違いを示すようで興味深い事象である。
それにしても、敢えてこの「Brother Harmony」のリリースを2000年末まで引き延ばす必要はなかったと思う。ハードロックのフリークには駄目の烙印を押されそうだが、良質なアメリカンロックや1970年代の西海岸サウンドやカントリー・ロックのクラッシックが大好きなリスナーには最高の一枚だと考えているからだ。
例えるなら、Eaglesの初期2作「The Eagles」、「Desperado」。The Byrdsの「Sweetheart Of The Rodeo」や「Ballad Of Easy Rider」、そしてPocoやBuffalo Springfieldあたりの爽やかでカラリとした音楽性が、フォーキィでカントリー・ライクなサウンドを求めるなら問題なく大推奨である。
商業カントリーとは全く違い、やはりNelsonらしく、Country Rockとカテゴライズするなら、その両要素の基本となっているのはRockである。アクースティックであり、いかにも西海岸風のコーラスワークは、やはり1960〜1970年代の西海岸のロックサウンドを彷彿とさせるものがある。
ギュンギュンと咆哮するエレキギターに代わり、フィドルやスティール・ギターそしてマンドリンとアクースティックギターを全面に押し出しているが、根底に流れているのはキャッチーなアメリカンサウンドであり、ポップなアメリカンロックの魂であると思う。
タイトルの「Brother Harmony」が実に当てはまる、「Harmony Rock」のアルバムと呼ぶのが最も相応しいと思える、優しく明るいハーモニーを中心としたアルバムだ。
ソングライター陣は、GunnarとMatthewのNelson双子が拘っているのが12曲中9曲。その内、Nelsonだけでの作は兄弟名義の#7『Goin’Goin’Goin’』とGunnar単独作の#9『What About Me』の2トラックのみで、残りは外部ライターとの共同作業となっている。
その共作陣も、この「Brother Harmony」の方向性を示す好材料となっていると感じる。というのは、12曲中でほぼ過半数の5曲でSteven McClintockとVictoria Shawnが手を貸しているからである。
この2名の男女アーティストは、Contemporary Folk、Adult Contemporary Countryというジャンル付けをされて、1990年代のEaglesとかLinda Ronstadtという紹介をメディアにされている、シンガー・ソング・ライターである。
特に、アーティストとしては、Victoriaは2枚のメジャーヒットアルバムを持っている。あのDesmond Childが積極的に演奏とソングライティングに手を貸して、女性版Garth Brooksとまで言われている。(嫌な例えだが。)
当然、筆者は女性アーティストはどうでも良いので、彼女のアルバムは聞き流しただけだが、メロディ的には懐かしのウエスト・コースト・ポップという印象だった。
また、こちらは筆者も大好きなSteven McClintock。このNelsonsのアルバムと非常に方向性の近い、アクースティックで甘々なCountry Rock/Adult Contemporaryの自己作品を2枚リリースしている。
その「Mind The Gap」と「Roadwise」というウルトラ・コマーシャルでHRファンには軟弱ポップロックと一蹴されそうなアルバムは、相当な筆者のストライクゾーンである。Nelsonの「Because They Can」からアリーナ色を抜いて、ルーツ&カントリーのフレイヴァーを強くしたという本作「Brother Harmony」と同様の音楽性を持った好作だ。
が、Steven McClintockは自身のインディ発売のリーダーアルバムよりもソングライターとしての名前で成功を収めている。15歳でデヴューしたカントリー・シンガーのTiffanyの『All This Time』を始めとして、彼女に多くのナンバーを提供している。またポピュラー・シンガーの大御所Andy Williamsにも曲を提供する等、ライターとしてはミリオンセラーのアルバムに多数名を密かに登場させている。
また、1999年から2000年の間に、「Brother Harmony」のプロモーションも兼ねたThe Nelsonsとの共同ツアーにもジョイントしていて、かなり親密な関係にあると思われる。ちなみに、このツアーでのメインアクトはAir SupplyやAmericaというかなり懐かしいヒットメーカーだったようだ。
他のライターとしては、Dan PennやGuy Clarkのアルバムでギターを弾いているGary Nicholsonの名前が見えたりして、やはりCountryとRoots Rock畑の人が一緒にペンを執っていることが多いようである。
バックミュージシャンは20人近くが起用され、殆どの曲で演奏メンバーが異なるようだ。詳しいクレジットは記されていないが。ギタリストのラインナップに、トラッドグラスシンガーのRichard Bennetの名前が見えることからも判断できるが、HR系のギタリストは皆無。全員がフォーク、カントリーロック、カントリー系のギター・プレイヤーである。
また、スティールギターにはTom Brumley、ドブロプレイヤーとしての方が著名なScott Sandres、そして2000年にかなり素晴らしいルーツポップアルバムを発表し、先日更に素晴らしい2枚目の「Stop」をリリースした34 Satelliteというバンドでもスティールを弾いていたMike Dalyというヴェテランがクレジットされている。
また、殆どのナンバーで聴くことのできるフィドル・プレイを担うのは、Lex Browningというこれまたルーツとカントリー系のセッション・マンが参加。完全にHR/HMとの糸は切れてしまっているように見受けられる。
#1『Try My Love』から、Nelson兄弟のハイトーンでソウルフルなヴォーカルが、爽やかにハーモナイズを刻みながらも、過去のHRのアルバムのような余分なシャウトはせずに、丁寧に唄われる。同時にスティールギターやフィドル、そしてイントロだけで小さな音量で転がされるピアノ、という風に西海岸ロックの良心のような作品がどんどんと続いていく。
フィドル・ダンスナンバーという感の#2『One Of The Things About You』は完全なカントリーロックであるけれども、ポップでアップビートなため、カントリー音楽の野暮ったさよりも、弾んだ明るさが上回っている。これはThe Nelsonsの天賦のセンスだろう。
Victoria,McClintock&Nelsonsのライティング・チームが作成したナンバーはどれも素晴らしいが#4『She Loves Me』も#2と似たタイプのナンバーだ。フィドルを前編に躍らせたアレンジはカントリーロックな雰囲気を演出しているが、爽やかなハーモニーと、流麗なメロディは、西海岸ロックと呼ぶ方が適切に感じてしまう。無論、カントリーロック調な曲=西海岸ロックという図式は当てはまるのだが。やはり、単なるカントリーではない。
彼らの十八番であるバラード・タイプの曲もバランスよく散らばっているけれども、全体の感覚から比較すると、カントリー&ルーツロックのテイストはあまり感じさせないナンバーが多い。
名曲『Love Me Today』を思わせる、アクースティックでセンチメンタルなバラード#3『Just Once More』ではルーツ的な要素が薄い。不必要なHRパワーを削ぎ落としたアレンジによって、更にNelsonのロアなヴォーカルとそれに込められた感情が伝わってくるようだ。これは#12『You Call That Mountain』も全く同じであり、産業ロックの色合いがやや希薄なだけで、その素顔はNelsonのバラードである。『Only Time Will Tell』に通じる情感がたっぷりと篭められている。
ア・カ・ペラのメランコリックなコーラスから始まり、ペダル・スティールギターとピアノが綺麗なラインを紡いでいく#6『With This Kiss』やよりアクースティックな#9『What About Me?』にしても、ルーツテイストを匂わせるのはスティールとフィドルの音色だけであり、アレンジ的には普通のアメリカンロックのバラードだ。こういったナンバーでは、やはりNelsonのヴォーカルにも気合が入っていて、嘗ての産業ロックアルバムでの歌唱法を再現しているようだ。
『Walk Away』のようなコーラスリフから始まる#5『From The Word Go』だが、このナンバーでの主役はエレキサウンドではなく、鍵盤とアクースティック系のルーツ弦楽器である。曲のテンポも『Walk Away』よりもゆったりとしたポップナンバーとなっている。
電気ギターが気持ち良くフューチャーされた#7『Goin’Goin’Goin’』、#8『What’s In A Name』と折り返しからの後半2曲は、フィドルやスティールが活躍はするけれども、本質はポップロックナンバーである。このあたりにハードドライヴなギターを載せると、デヴューアルバムのようなサウンドが出来上がるのだろうが、こちらの優しく、ナチュラルなアレンジで演奏されるNelsonのサウンドは清涼感が満ち溢れているため、とても耳触りが宜しい。
晴れた秋の無窮を見上げているような視覚を感じるようなくっきり・すっきりしたメロディは、聴くだけで微笑んでしまう。ギターがバランスよく鳴らされる#7もドラムのカッティングがスッパリと切れている#8も、このアルバムでは一番アップビートに乗っている箇所であり、最大の見せ場でもあるだろう。
#10『She’s Way Too Cute For Me』は1960年代にタイムスリップしたかのような、ホンキィ・トンクなライト・ブギー調子のロックンロールである。父のRickの世代が歌っていたオールディズをこのアルバムに持ち込んでいるのはやや違和感がなきにしもあらずだが、元気一杯なローリング・ソングとしてRockのアクセントを付けてくれるナンバーでもあり、純粋に楽しめる。
続く#11『Forever isn’t Long Enough For Me』はムーディ・ブルースとも呼ぶべき、これまたクラシカルなソウル・バラードである。アーシーなルーツナンバーではなく、ポップ音楽のルーツを再評価したような演奏が聴ける。
この後半2曲の古典的な音楽は、Nelsonsの音楽的なルーツ・バックグラウンドを示唆しているように思えるこういったナンバーはHRアルバムではトラッキングできないため、この作品で漸く発表の場を得たと考えるのが妥当に思える。
それにしても、これ程「兄弟の合奏」が際立ったアルバムは初めてだろう。Nelsonのポップな面を突き詰めたのが「Because They Can」であるなら、更にアーシーで、父親譲りのカントリー・センスをそれに付加したのが本作の「Brother Harmony」であると思う。
正直、もう少しロックンロールな痛快ギターが欲しいとは思うけれども、平凡なメロディック・ハードな音を創られるよりも、ずっと親しみやすい等身大の素直さが存在するこのアルバムはとても素晴らしいと思う。
最近のNelson(The Nelsons)は、どうやら脱ハード・メタルサウンドに移行しているようだが、著者個人としては最高に歓迎すべき事柄である。次もアクースティック&アーシーな路線を期待できるからだ。
日本では絶対に受けが悪くなる方向性であるのは間違いないだろうが、このポップさと爽やかさ、柔らかさは現在のロックシーンにおいてはかなり貴重であると思う。70年代ロックファンなら是非聴かなくてはいけない1枚だ。
(2002.4.18.)
 Gutterflower / The Goo Goo Dolls (2002)
Gutterflower / The Goo Goo Dolls (2002)
Alternative ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Modern ★★★
Reviewed By Kyotaさん
1995年に『Name』がチャ−トを駆け上り始めたときは、「ああ、アメリカでは流行がどう変わろうとも、バラ−ドはやはり強いんだなあ」と妙に感心すると同時に、「えっ、あのGoo
Goo Dollsが・・・。」、という驚きを感じずにはいられなかった。
私が彼らのことを知ったのは、それよりさらに遡ること2年前、映画のサウンドトラック・アルバム「Son
In Low」に収録されていたキャッチ−な名曲「Fallin' Down」であったが、その後アルバム(「Superstar
Car Wash」(1993年)を聴いてみて、その親しみやすい楽曲群に惹かれつつも、やや一本調子なジョンとロビ−のヴォ−カルに、シンプルかつガッツィ−なギタ−・リフをフィ−チュアした「勢い&ノリ重視」のアルバムは、メジャ−・シ−ンで展開するにはやや普遍性が欠けているように感じたからである。(正直いって他のアルバムを買って聴こうとまでは思わなかった)
しかしその大ヒット曲「Name」を収録したアルバム、「A Boy Named Goo」は、こちらの「いいバンドだけど、大ヒットを出すのは難しいだろうなぁ」という失礼な予想を打ち砕く、バラエティに富んだ非常に充実した内容を持っており、彼らの潜在能力に驚く他なかった。このアルバムはほとんど完璧といってよい、売れて当然の素晴らしい作品だと今でも思う。
以前からCheap Trick等の先輩バンドと比較されることの多いGoo Goo Dollsであるが、はっきりいって彼らはCheap Trickほど器用なバンドではない。特にヴォ−カルの力量の差は大きい。ジョンやロビ−はロビン・ザンダ−のようにどんな曲でも器用に歌いこなせるといったタイプのシンガ−ではないのだ。(特にロビ−は力で押す、曲を選ぶタイプのシンガ−だ。)
しかし、ポイントは彼らが器用さに多少欠けていても、その分豊富なアイディアと柔軟性、そして何より自分達に何が出来るのかを良く理解しているということである。
もう一度「A Boy Named Goo」と前作「Dizzy Up The Girl」を聴き返してみよう。もちろん、最も大事なのは「良い曲」を書くと言うことにつきるのだが、作曲面、アレンジ面、歌い方の面等で様々なことにチャレンジしつつも、決して自分達のカラ−に合わないこと、能力の限度を越えたことはしていない。
アルバム全体がバラエティに富みつつも、「A Boy Named Goo」以前のアルバムにあった、最初から最後まで一気に聴かせる「勢い」も失わない普遍的アメリカン・ロックとして完成されている。
ごく自然体でステップ・アップしているのだ。
まあ、ここら辺のサジ加減は難しいところで、この「新境地」も繰り返していれば(人によっては)ただの「保守」ととらえられかねない−新作「Gutterflower」にも特に新しい要素は見られない−のだが、私は彼らの方向性は全く正しいと思う。
折角手に入れた、自分の体にぴったり合った服を今更捨てることなんてないよ。Cheap
Trickのように、信念を
持って自分達のスタイルを貫き続けて欲しいです。
新作「Gutterflower」.....個々の楽曲のインパクトでは「A Boy Named Goo」、「Dizzy
Up The Girl」に劣るかもしれませんが、アルバム全体としての出来は上々。
サウンドも非常にシャ−プかつクリアで、飽きずに長く聴き続けられるアルバムという気がします。
(2002.4.10.寄稿/4.12.掲載)
まあ、何ちゅうか(本●華・・・古ッ!)
1990年代以降のメジャー・シーンというか売れる作品というものの限界を感じさせてくれた1枚です。
肯定的・否定的の両義に於てですけど。
さてさて、ここまでメジャーなバンドならバイオ関連の説明は日本盤買って見て貰えれば問題ないでしょう。(を)
ですんで、感想オンリーで綴ることにしましょう。
正直、初期のアルバム3枚(極初期リリースの「First Release」は内容的に「Goo Goo Dolls」と同じな故に計算に入れていません。)は、鑑賞に耐えない雑音程度のアルバムであり、1993年の「Superstar Car Wash」くらいから、マトモに聴けるようになったバンドが、ここまで1990年代のメインストリームたる、Modern RockとAlternative Rockの良心的なサイドの代表格になるとは予想をだにしなかったのが、偽りのない感想です。
1990年代後半から、完全にオルタナ離れをしてしまっている筆者が、2002年現在で「Goo Goo Dolls」のようなアルバムを初めて聴くこととなっていたら、即座にスーパーダメダメパンチでマットに沈めているような音楽を演奏していたGoo Goo Dolls。
正直、「Superstar Car Wash」は単調なメトロノームをぶん回している如くの、悪くないけれども聴いてると疲れるアルバムとか、次作の「A Boy Named Goo」の、折角直線的なポップさをオルタナティヴ的な重さと翳りで閉塞させている作品は
「良いヒトなのよね・・・・。でもそれだけなの・・・・。」(=結構どうでも“良い”ヒトちゅうこったね・・・。) という評価しか与えれません。
と、チープな別れ話の、これまた手垢に塗れて価値が鐚銭程にもないセリフが実に良く似合う3ピースであったのですね、個人的には。(うう、色々このセリフは痛いがな・・・・。)
が、1998年にかなり脱オルタナした「Dizzy Up The Girl」をリリース。先行シングルである『Iris』は当時在住の米国で耳がタコに成るほど聴いた、聴かされました。この当時はラジオオンリーのシングルが総合チャートでのランクインが認められなかったので、ヒットのピーク時を逃したためかトップ100シングルとしてはNo.1にはなっていないと記憶しています。
しかし、続く『Slide』がエアプレイ・オンリーのシングルとしては初の全米No.1ヒットになり、続くシングル『Dizzy』、『Black Balloon』、『Broadway』は全てトップ100シングルになったように朧気に覚えているのですが。
ま、チャートアクションについては記憶する気が更々ないので、このあたりを訂正してくれる方募集。(を)
兎に角、オルタナでなければ基本はオッケーという筆者の歪んだ嗜好にばっちりと“近づいた”この6thアルバムでThe Goo Goo Dollsはおさおさ捨て置けないバンドとなり、個人的に相当期待を課せるバンドに昇格したのです。
で、変則的なベストアルバムを2001年に挟んで、今作「Gutterflower」が2002年に発売された次第であります。
明るく、ライトになった前作と比べると、方向性は(「Superstar Car Wash」+「A Boy Named Goo」)×成熟、という数式になるでしょう。
少々オルタナがまたぞろ臭く匂ってきて、鼻を摘みたくなることもありますなあ。
それは#7『It’s Over』、#9『What Do You Need?』そして#12『Truth Is Whisper』といった、程度のこそあれども、鬱陶しいオルタナの不味さがスパイスされた曲であり
全く必要ないナンバーやけど、こういった曲を入れないとメジャーでは見向きもされんやろから、仕方ないでんなあ・・・。#5『What A Scene』もあんまり要らない。
やはり、メジャーシーンで若手が音楽で成功するにはオルタナティヴというのは必要不可欠な要素であることを再認識したりしました。筆者としてはこの不要な香辛料をどのくらいモデレイトできるかが、最早Adult AlternativeとModern Rockの限界攻勢点といえますね。旧帝国陸軍のように補給線が延びきってますけど。(謎)
と、批判しつつも、アルバム全体としての完成度は先に「成熟」という単語を使用したのと同義で、これまででは一番の纏まりを見せていることに同意することにはやぶさかではありません。
しかし、前作で総合チャートの上位を賑わした程度に達している、リマーカブルなシングル向けのナンバーが少ないため、全体としてはやや地味な感じに落ち着いているのは否定できないでしょう。
が、前作の全米15位まで上がり、Billboardのトップ200から消えるまでに200万枚のセールス★が付いていた実績は伊達でなく、第一弾シングル#3『Here Is Gone』は2002年4月第三週のチャートで先週の22位から、2つポジションを上げて20位まで上昇中。う〜ん、トップ10入りは厳しそうですね。ま、チャートを信じるようなヒトはここのレヴュー見ないからどーでも良いっしょ。(を)
流石というべきは、この#3だけでなく、今回も数曲のメジャーヒットは間違いなく生み出しそうなアルバムだということですね。。
売れ筋モダンロック・トラックのお手本のような#1『Big Machine』、メロディアスな#2『Think About Me』、Green Day名曲−でも異色ナンバー(笑)の『Good Riddance』を連想させるアクースティックな#8『Sympathy』というように良い曲は存在してます。特に、頭3曲はかなりのハイ・レヴェル。
その曲の良さもさることながら、ハスキーで色気と艶気のあるJohn Rzeznikの声がこのバンドの最大の差別化を生み出せる要因ですね、そこらのモダンロック・バンドとGoo Goo Dollsを比較した場合。
然れども、このアルバムからカットしたナンバーはトップ10ヒットがやや辛いかな、という感想が最新作の「Gutterflower」と「Dizzy Up The Girl」の違いとなって顕在化しているとは思うのですが。
で、#4『You Never Know』以下、合計4曲でリードヴォーカルを担当している、ベーシストのRobbyですが、彼が作詞・作曲したトラックはどれも、オルタナティヴの味付けが薄口で、“最近”のGreen DayやWhezeerが傾向としているポップ・パンク調のキャッチーで明るいナンバーなのですが、
おまい、相変わらずヘタレなヴォーカルやなあ。
というのが偽らざる感想です。というか、
初期のアルバムではRobbyがメインのリード・ヴォーカリストであったという事実は悪夢以外の何物でもありまへん、とまで言ってしまいませう。(をい)
彼はベーシストに専念して欲しいものです。Robby Takacのコンポーズした曲をJohn Rzeznikが歌えば、名曲『Broadway』クラスのヒットシングルが望めると思うのですが・・・・残念。
Johnが書く曲は、Robbyの作よりもヒネリと厚味があって概ね上を行ってますが、オルタナティヴの呪縛も感じるので、曲を書くことはこれからも2名で続けては欲しいです。
後、3ピースという体勢もどうも気に入らないですね。3人で可能なことには限界があり、今作もシンセ・プログラムや数人のゲストミュージシャンがレコーディングに手を貸してますが、ガレージ・パンク時代の音からここまで脱却したなら鍵盤弾きや、アディッショナル・ギタリストを雇い、バンドとしての音をかっちりと構築した方が好ましいと、余計なお世話ですが、毎回思うことであります。
いずれにせよ、メジャー市場に於て、売れる音楽の枠内という制約の中で正統な現代ロックを演奏するバンドとしては、トップクラスのモダン系ユニットであることは間違いないでしょう。
確実にアルバムをリリースするごとにステップアップしている事実を証明する好盤では、あります。
・・・でも恐らくリピートせんやろなあ・・・・。深みが足りない・・・・・。(ボソッ)
まあ、買って損はしないとは思うのですが、手放しでハナマル付けれないですね、こういう方向性の音楽は。
ですが、筆者の偏った耳と異なり、メジャーに氾濫している音楽が苦にならない健全な(=一般的な)感性の持ち主にならお薦め度は激高です。
それにしても、相変わらず、ルーツ系でないと暴走しないで、適度な文章量のレヴューになりますね。(苦笑)
(2002.4.12)
 Mono / Grandpaboy (2002)
Mono / Grandpaboy (2002)
Roots ★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Punk&Alternative ★★
You Can Listen From Here
大概に於て、覆面バンドとかプロジェクトというのは、ライトリスナーには兎も角として、熱心な音楽ファンには覆面で隠す意味のないバレバレなことが多い。で、ライトリスナーというのはそういった覆面バンドの面の顔バンドすら聴かないことが殆どだろうから、根本的に覆面バンドの意味というものは、それ程には無いように感じる。身もフタもない話だが。(苦笑)
少々古いけれども、Traveling Wilburysなんぞは如何にWilbury Brothersの変名を詐称しようが、ジャケットの顔ぶれを見ただけで、誰かは即座に分かったのものである。
レーベルとの契約等があって本名が使えないということは往々にして起きることだが、ぶっちゃけた話、売れてしまうとそういった問題が等閑に付されることが殆どなのも確かである。
それは件のTraveling Wilburysにしても、Golden Smogにしてもセカンド・プレスから本名でのクレジットに変わった事実を踏まえれば、理解が容易だろう。
究極的に、アーティストが既存のイメージをぶち壊すような方向性の音楽に手を染めたい時に、変名や覆面を使うことは是非は兎も角理解できる。
例にするなら、文豪と後年称される文筆家が、官能小説や女性向浪漫珠(ろまんす)読み物を別名で書いて糊口を拭ったという話はそれこそあちこちに転がっているが、そういった本来の己が定めた正道から悪戯心で道草した、それよりも切実に飯を食うために止むを得ず仮名を使用するというなら、その態度が正しいかはどうあれ、動機は推し量れる。
が、このGrandpa Boyというアーティスト名義でプレスされたCDは、本人も最初は名前を伏せようとしていたようだが、それ程積極的に隠す努力は全くしていない。(それは後述するが。)また、どんなにこの修正を加えた顔写真でWesterberg本人を隠そうとしても、元の顔の面影というか、特徴が見事にデフォルメというか戯画化されて残っているので、見る人が見れば
をを、Paul Westerbergやんか!
って、分かってしまう。しかし、1997年に、このGrandpa Boys名義でミニアルバムをインディレーベルからリリースしているので、今更ではあるけれども。
で、詰まるところGrandpaboyというのは、公には最早覆面でもなんでもないPaul Westerbergのサイド・プロジェクトである。
これまでに7インチシングルを1枚、ミニアルバムを1枚発表しているが、最後のリリースからほぼ5年ぶりの、しかもフルレングスが2002年に限定発売された。公称1万枚限定、というのがこの「Mono」の謳い文句である。
で、限定盤の先行リリース大いに結構なのだが、来る4月23日には、本名(というかPaul Westerberg名義)で通算4枚目のアルバム「Stereo」を発売予定となっている。これもまたヨシ、が、
「Stereo」は何と2枚組みで発売されることが決定。2枚目にはこの「Mono」が入り、「Stereo/Mono」として発売される。ここで、以前に触れた「本人が名前を匿名にする意図が希薄」という事柄が、はっきりと示されている。それは兎も角として・・・・・・。
つまり、その2枚組みを買えば、この先行限定盤の「Mono」はまさにコレクターズ・アイテムとしての価値しかないことになる。言いたくないが、イコール=金の無駄、となる。コレクター以外には。
しかも、しかも「Stereo」は基本的に2枚組みという大判振る舞いのようである。
まさに、コレクターとは違い、あっちこっちの音楽を手広く(浮気性ともいふ)聴く、著者にとっては涙である。
何で最初から2枚組みで出さんのじゃあああああ!!!(血涙)
と叫びつつも、結局「Stereo」も買うのだが・・・・・・。(弱ッ)
というように、慣例の文句も済んだことであり、脱線はここまで。何故Paul Westerburgが別名でアルバムをリリースしたかについて考察を続けるとしよう。
「これはロックン・ロールのレコードだ、完全無欠の、ではないけれどね。特に明確な意図を持ってではなく、ちゃっちゃと即興で演奏したものを録音した。
どんな音楽?、何を言いたいのか?、誰がどのように参加してプレイしている?、なんてことは関係ない。感じていることをそのままに顕しただけさ。僕の血管に流れているものをね。」
というのがGrandpa Boyの名前でPaulがインナーで書き綴っているコメントである。
また、これまでのPaul Westerbergのアルバムでは、必ず彼の素顔が何処かにインプリントされていたのに、この「Mono」に限っては、かなり趣味悪く手を加えられている。
付け加えて、TheReplacements解散後のPaulのソロ作品が、積極的にバンド時代の音から遠ざかろうとする方向性に突っ走っていること。
ここで述べる程の情報でもないが、ガレージロック、オルタナ・パンクの元祖とも言うべき、The Replacementsは次第に初期の音から遠ざかり、晩期はそこそこガレージとかオルタナティヴのノイジーさから脱出しつつある段階を迎えた折に解散。その後、Paul Westerbergがソロ作で展開した音楽は、ややThe Replacementsに近かったといえるのは、1stソロ「14 Songs」のみ。
それ以降はどんどんと大人しい、ガレージロックとは対極的なアルバムになっていった。
こういった、断片的な要素を考慮に入れた上、何故に変名を使う必要があったのかと分析したらどうだろう。
まず、どう考えても、Replacements時代に演奏していたWesterbergの音楽から、アルバムを重ねる毎に、彼は遠ざかろうとしているのは明確だ。
前作、1998年の「Suicaine Gratifaction」に至っては、速いナンバーが皆無のピアノやキーボードを主体としたヴォーカルアルバムと成っていて、Replacementsの時代を至上とするファンからは酷評されたものだ。「Paulはロック・スピリットを失ってしまった。」とか怨嗟の声が聞かれたものだ。
が、作者個人としては、変にReplacements時代を引っ張るような歪んだギターと、捻り過ぎのメロディに固執した形勢が顕著な1st「14 Songs」なんぞよりも美しく、メロディアスなアルバムという位置にあった。確かにロックナンバーが無いのは寂しかったが、これはこれで良いと考えている。
それは置いておき、このGrandpa Boyで展開されるのは、久々にロックンロールな音楽である。本人(クレジット上はGrandpa Boy)のコメントにもある通り。
しかし、ロックンロールとはいえ、Replacements時代の退屈で苛立たしい、オルタナティヴやグランジ・パンクの重さや礼儀の無さを感じるナンバーは非常に希薄だ。皆無ではないが。
この、「Mono」で提示されたロックンロール、しかもポップで、アメリカンな成熟さ−土の香りがそこはかとなくするという意味合い−を兼ね備えた、オーソドックスでクラッシックだけれども正統な伝統的ロックンロール。
これまで、どうしても媚を売っていたようなモダン・オルタナへの卑屈な歩み寄りはそれ程感じられない。
思うに、次第にロックンロールから離れていく自らの方向性を肯定しつつも、Westerbergには何処かでロックンロールをやりたいとは常に感じているのではないだろうか。
だが、多くのファンがあまりにもReplacements的な、“彼らの”ロックサウンドを求めることに、彼は辟易しているように見える。
3rdアルバムをリリース後のインタヴューで、Paulはこう答えている。
「多くのファンが、まだ貴方の中にはReplacementsの音楽を創りたいという思いがあり、何時でも創造できると期待しているのに、貴方はしなかったですね。」という問いに対して
「彼らが求めるReplacementsのレコードね・・・・。それは、僕たちがまた再結成を発表してスタジオ入りし、何も録音されていないアルバムに“The Replacements”と銘打って発売すればいいね。で、彼らに金を払って貰うとしよう。きっとファンは怒って僕らを貶すだろうね。でも、そういったことがまさに『Replacementsよ、もう一度。』という人達が欲しているものさ。」
という発言をしている。一方、
「仮に、別のアルバムを今録音することになったとしたら、それは「Suicaine Gratifaction」と同じくらい良い物にしたいね。つまりもっとアップテンポなアルバムも心から創りたいと思えば、創るということさ。または、わざわざもう一枚創ることなんてしないかどっちかだね。(それだけ3rdに満足していたということ:筆者註)」
とロックンロール作品を創造する気力が失せたのではないことも表明している。
こういったWesterbergの考えから想像するに、「ロックなアルバム」=「The Replacementsの再現」という見方をされるのに、また「Replacements、カム・バ〜ック!!」という期待にPaulがウンザリしているのではなかろうか。
Rock寄りのアルバムを作成したら、Replacementsの復活か、という意見に代表されるように、すべからくReplacementsと比較されるのが嫌で、敢えてGrandpa Boyという変名を使い、ロック・アルバムを作成したのでは、と思ったりする。無論、完全なる憶測で、ソロ4作目以降に必ずやされる、Paul Westerbergのインタヴューを心待ちにしているのだけれども。
以上に触れたように、Paul WesterbergがGrandpa Boyという覆面名でリリースした3枚目のレコードは、筆者にとっては久々のロックアルバムである。
まだ、Paulがメジャー・レーベルと契約を保っていた1997年に7インチのアナログ盤「I Want My Money Back」をインディ・レーベルのMonolyth Recordから発売。次いで、5曲入りのシングル盤「Grandpaboy」を同年にリリース。
矢張り、メジャーでは受けそうも無い、オルタナ度合いが低いアルバムなため、インディでのプレスとなったのだろうが、Monolythでは、即座にPaulの別バンドという売り方をしたので、匿名もへったくれもなかったりした。(笑)
そして、3rdソロを挟んで、2002年に初めてのフルアルバムの発表をこれまたインディのVagrant Recordsからレーベルを変更して行ったのが本作「Mono」である。
The Replacementsの熱心なファンには、このアルバムがロックと捉えられるかは少々疑問ではある。必要以上にノイジーでもガレージでもない、かなり普通のロックアルバムであるから。
しかし、Westerbergの持った、独特のヒネクレ具合というか一筋縄では気がすまないメロディ・メイキングのセンスがあちこちに散りばめられて、彼の作品では常に目立つコード進行−「ここでこう変調させるか!?」とか「もっと素直に直線的なメロディでも良いのに」という変化球的な肩透かしも見られるのは、相変わらずWesterbergらしい。
とはいえ、Replacementsで披露していた、力任せというよりも無理矢理に貫くという表現が相応しい、浅薄で軽薄その割に耳を覆いたくなる五月蝿さは殆ど払底されている。
表面を引っ掻くだけだったガレージサウンドから、より心の入ったナチュラルな音を尊重した音楽性−ソロリリースを重ねる度に顕著になっていった要素−が程好くブレンドされて、良心的なアメリカンルーツ系のポップ・パンク、またはパワーポップ、そしてモダンロック的なスマートささえ見せるアルバムになっている。
「14 Songs」の頃のサウンドから、ガレージとオルタナティヴ的な無機質さを取っ払い、適度の泥臭いナチュラル・ギターの音を増加させたアルバム、という表現がより簡潔に「Mono」を代弁できるかもしれない。
演奏はベース、ギター、ドラムスの3楽器に、パーカッションとバックヴォーカル担当が加わった、至ってシンプルな編成である。とはいえ、演奏自体が薄っぺらとか簡素過ぎるという段になると、決してそうでもないのだ。
確かにシンプルで飾り気のないインストゥルメンタル・パフォーマンスが終始続いているけれども、それなりに厚味のあるアンサンブルを聴かせてくれる。むしろ、曲としてのパターンが、ノンバラード且つポップでツールィな曲が連続しいるため、パンクのアルバムによく見られる傾向が浮上している。つまり、やや単調な流れになっているという聴いていて一本調子な故に凹凸が感じられないリスナーも出るという危険性を示唆したい。
だが筆者的にはキャッチーで元気なルーツロック・ルーツ・パンクが聴けるので、取り立てて退屈を覚えることは無い。更に特筆する点は、これまでのWesterberg作品に宿痾と言うべき程に付きものであった、良い曲とダメな曲の落差が激しいという欠点がないアルバムということである。
このことは「単調」というマイナス点と同類に括られる可能性があるが、裏を返せば「どの曲も平均点以上」とレヴェル的にかなり高いアルバムにもなりえるということだ。無論、著者にとっては、全体的にシングルにしても良いナンバーが並んだ“当たり”のピースである。
それよりも、ヴォーカル−リード・ヴォーカルについてが問題だろう。やや安っぽさが、いつものPaulのアルバムよりも際立っているのは否めない。元来、とても名ヴォーカリストとはいえないし、唄い方もお世辞にも上手でないPaul Westerbergであるが、このアルバムではそれに輪をかけてヴォーカルが弱い。
ヴォーカル至上主義の聴き方をすると、場合によっては致命的になるくらいインパクトは弱い。この頼りないヴォーカルがWesterbergの味であるのも確かだが、ソロ作ではアルバムを出すごとに徐々に成長を見せていた喉が、このアルバムでは恣意的にチープにしているようで、メロディが常に無く分かり易いため救われているのは、間違いないと思う。基本的にPaulのヴォーカルが好きな筆者の色眼鏡を極力排した見方である。
ソロ・ワークの2作目「Eventually」や3枚目である「Suicaine Gratifaction」で、奇妙な味わいのあるヴォーカルが熟成をしている過程を覚えている耳には、やや残念である。『Love Untold』で聴くことの出来た珍妙なコブシの振り回しも、『Best Thing That Never Happened』でホンワカできた繊細な唄い方、というような印象に残るヴォーカルは少ない。
その、Paul(Grandpaであるけど、ここでは。)のヴォーカルが比較的暖かく、上手に唄われているのが、オープニングの#1『High Time』である。バンドの構成はシンプルであるが、数本のギターがオーヴァーダヴされていて、意外に質感がある。また、ギターの音の尾やコーラスのラストの音階を必要もないのに捻じ曲げているのがPaulらしい。
それにしても、キャッチーなルーツナンバーである。
#2『Anything But That』は、このアルバムタイトルの「Mono」の読んでの通りに全てのトラックがモノラルで録音されているが、その代表のようなナンバーである。#1よりも更にねちっこいギターが唸り声を上げている。メロディはかなりPaulの本格派からのアウトサイダーな面が表面化していて、相当に捩れがある。極めつけはエレキ・ヴァイオリンのような奇怪なギターソロである。
対して、脱力したコーラスと気怠るいPaulのヴォーカルが、筆者の苦手なBクラス的なポップソングとして見せている#『Let’s Not Belong Together』にしても、#4『Silent Film Star』のやる気の感じられないヘニャっとした展開も、メロディとしてはかなり直線的な素直さが出ている。
しかし、何処となくチープで倦怠感のあるPaulの持ち味のために、分かり易いナンバーである筈がややミステリアスな雰囲気を持ったポップナンバーとなっているのが可笑しい。
このアルバムで一番The Replacementsを連想させるのが、#5『Knock It Right Out』だろう。演奏時間も2分半以下というところも、ガレージ・パンクな曲としての特徴を主張している。ディストーションを不必要に捏ね回すところや不器用にシャウトしているPaulのヴォーカルも、正直曲のフックを感じさせないので、このナンバーは中盤で流れを乱すことで全体の展開の活性化に寄与している意外には何ら見るものは無い。
やや、アクースティックで、ソロキャリアを進めて行く過程でPaulが求めてきた音楽性を伺えるのが、#6『2 Days ‘Til Tomorrow』である。これまた複雑というよりも未整理なギターがあっちこちで掻き鳴らされる、ガチャガチャした雰囲気があるけれども、Replacementsの頃には存在しなかった優しさを感じるポップナンバーだ。
#7『Eyes Link Sparks』はややオルタナティヴライクなノイジーなギターリフに調子ハズレのヴォーカルとコーラスが即興的に合わせているという風なガレージロックの残滓を救い上げて音符の隙間にばら撒いているようなスカスカとしたロックナンバー。ややチープ過ぎるか。
それよりも、メロディ的には落ち着いてきっちりとフックのある#8『Footsteps』の方が同じくオルタナティヴ的な硬さがあるにせよ、曲としては前曲#7よりも上だろうか。これまたメロディをあちらこちらへとうねらせるし、ダークなギターソロも噛み付かせているWesterbergの投げ遣りなタレントをよく示している。
シャープなドラムのシャッフルに、気持ちの良いメロディが被さっていく#9『Kickin’The Stall』は#1のように珍しく素直でスルスルと進んでいくパワー・ポップ的なロックチューンだ。が、これまたPaulの音階を故意に外しているようなヤケクソヴォーカルのために、崩れた雰囲気が纏わり憑いている。まあ、このナード感覚と苦味が彼のカラーであるから、良いのだけれど。
#10『Between Love & Like』もどこか、エフェクトを掛けてくぐもらせたようなヴォーカルが、そこはかとない脱力感を主張し、ドライヴなロックンロールを表現するメロディとドロリと溶け合って、ゴロゴロとした自然岩を触るような感覚を創造しているナンバーだ。ポップでロックな好トラックなのだが、Paulの手にかかるとどうもスンナリと型に嵌らないのである。そこが個性的なのは確かだ。
最後の#11『AAA』は歌詞から判断すると「Anything,Anyone,Anymore」の略称なようである。小気味の良いフックの効いたロックチューンであるが、曲の最後の方でコードがいきなり崩壊を起こし、また唐突にメジャーなコードに戻るというのが、このアルバム全体に共通な未整理とライヴ感覚を代表していると感じる。
以上のように、どのナンバーも古典的なモノラル録音であり、アレンジ、曲調といった要素はかなりレトロな雰囲気を持っている。また、複雑なコードは殆ど使われていないが、突然のマイナー・キーや前衛的な音楽作品に見られるようなヒネクレ具合を有しているのも、ユニークだ。
このネジクレ故に、本来なら相当に単純で明るいロックアルバムになるはずが、どうにもビターで複雑な展開が正体不明な心への印象を焼き付けている、怪作である。同時に、快作でもあるのだが。
基本となる核のメロディは、これまでのPaul Westerbergが手掛けた音楽の中では一番コマーシャルで親しみやすいと思う。綺麗さではソロ3作目の「Suicaine Gratifaction」に劣り、締り具合では2枚目のソロである「Eventually」に一歩譲ることになるだろうけど。
しかし、Facesや初期のRolling Stonesを彷彿とさせる木目の粗いルーツ・ロックをPaul Westerbergが創ったという事実が微笑ましいのだ。しかも、かなり面白いアルバムになっているし。
数回聴いただけでは、やや印象の薄い1枚であるかもしれないが、聴く度にこの妙に苦くて甘い音世界に引き込まれてしまう。タイトなようでルーズ、直線ポップでありそうでブリット的な歪みがある、とちょっと一言では表現しきれないアルバムだ。
もっとポップでヴォーカルに締りを射れたらとんでもないロック名盤になるポテンシャルがあると思うので、少々歯痒くはあるけれども、十分に楽しめるアルバムである。
Paul Westerbergの生来有する毒というかアク(殊にヴォーカル)に慣れているなら問題なくお薦め。
本当ならPaulのリスナーよりもルーツロック好きな人に推薦したいアルバムだ。ヴォーカルの好き嫌いがかなり出そうではあるけれども。いくら「Mono」でモノラルとはいえ、ヴォーカルの捨て鉢とも誤解されそうな歌唱法は良く言えばスワンピー、悪し様になら弱い声、となるような危惧を抱いている。
しかし、対のように発売されるPaul Westerbergのソロ4作目「Stereo」が気になる。こちらはステレオ録音ということであるが、方向性としては「Mono」とどう比較できるのだろう。噂では既に色々と耳にしているのだが、実際に聴くまでは筆者のイメージだけを頼りに予想を述べることは止めておく。
4月23日が楽しみになったアルバムだ。次作を失望させる出来でなかったことだけは、贔屓目を抜きにして保証することに躊躇いはない。 (2002.4.14.)
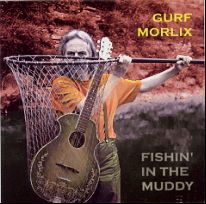 Fishin’In The Muddy / Gurf Morlix (2002)
Fishin’In The Muddy / Gurf Morlix (2002)
Roots ★★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★☆
Americana&Swamp ★★★★
You Can Listen From Here
まず、このタイトルとジャケットのセンスが凄い。
完全無欠のオヤヂ臭さが丸出しである。まさにオヤヂの中のオヤヂという感じである。が、同じオヤヂでもJohn Dee GrahamやJohn Hiatt等と比較すると、かなり地を這うような地味な、然れども渋いオヤヂの味わいを感じるアーティストだ。
しかも、タイトルが「Fishin’In The Muddy」である。「泥中の魚を釣る」、これからしてもう南部のスワンプの印象を強烈に与えるタイトルである。で、メータクラスの魚もキャッチできそうな、ランディングネットに掬い上げられている獲物が、アクースティックギターであるというのが、もう堪らない。鯔や鯉といった泥臭い川魚をツマミにして一杯やってるような草臥れた男の哀愁を何処となく感じてしまったりする。
それにしても、アメリカ南部に点在する湖沼で釣りを楽しんでいるおっさんの汗の匂いが嗅げそうなジャケットである。日本の沼地でのルアーフィッシングを想像しても問題ないだろう。
まるで、大気がゲル状になってしまったかのようなクソ暑い夏の夕方に、蓮や蒲といった水生植物の隙間からトップウォーターをキャスティングして、雷魚(学名:カムルチー。あの外見やけど食用。中国では結構食べるらしい。筆者も食べたが味はいまいち。)やブラックバス(ご存知、水生の悪食。白身で結構美味い。)を狙った少年の日の、草いきれや泥の匂いが伝わってくるようである。
と、少年の日々の青臭い思い出に浸れるようなアルバムではない。あくまでも湿地での釣りという雰囲気を文章にしてみただけである。やはり、究極的にオヤヂの体臭がムンムンとしてくるアルバムだ。
しかれども、暑苦しさよりも、格好の良い枯れたオヤヂの態度を連想させるサウンドが、このGurf Morlixのアルバムに零れんばかりに詰まっているのだ。
まず、長い音楽キャリアをすべからく裏方で支えてきたGurf Morlix(ガーフ・モリックスと発音を確認。これやったら、ガーフ・モーリーと発音できんことも無いので。)の経歴や発言を掲載していこう。
自然にこのオヤヂがどのような態度で音楽と付き合ってきたか理解してもらえるだろうから。
「私は自分がスターになりたいと思ったことも無いし、スター性があるとは思ってもいない。シーンの表舞台から一歩引いた場所で仕事をする。それが私のスタイルだ。」
「誰でも知っているような存在にはあんまりなりたいとは思わないね。少しばかり、無名でいる状況の方が好きだね。つまり、たくさんの無名な仕事をしてきたし、これからもしたいんだ。」
「Beatlesがヒットした時代、皆がくびったけになった。Beatlesをカヴァーすることが大流行したけれど、Beatlesの歌を自分でどのように演奏しようが自由だったよね。自分のやりたいようにやる、私はこうやって活動してきた。」
というようなGurfの言葉に、彼の経歴が集約されているだろう。そう、2000年に初のリーダー・アルバムである「Toad Of Titicaca」をシカゴのインディ・レーベルであるCatamountから発売するまで、Gurf Morlixはずっとシーンの日陰で活動してきたのだ。
Gurf Morlixの生年月日は実は明確に発表されていない。まあ、メジャーでは間違っても発売されることの無いような、商業カントリーや売れ筋カントリー・ロックとはかけ離れた音楽を演奏するミュージシャンなので、オフィシャルな資料がとても少ない。よって、かなりの割合をインタヴュー記事に頼っているのをお断りしておく。
Morlixが音楽に興味を持ったのは、生まれ故郷のニュー・ヨーク州は国境の街、バッファローである。少々車を走らせればすぐにナイアガラの滝から隣国に越境できる土地である。
彼は、そのバッファローで四半世紀近く(1948年から71年まで)、物凄い高視聴率を誇ったエド・サリヴァン・ショウを見た。
「Elvisのショウを見たのは、5歳か6歳の頃だったように記憶している。その番組を見た時、私はミュージシャンになりたいと考えている自分を発見したんだ。そして、10歳くらいから正式にベースのレッスンを受け始めたんだ。ギターは薦められなかったからね。」
ElvisがThe Ed Sullivan Showに出演して、空前の85%近い視聴率を得たのが1957年のことだから、恐らくGurfは1950年くらいの生まれと推定できる。
1960年半ばに、Gurfはバンドを結成して活動を開始する。その頃にはMorlixはギターを手に取っていた。学校のパーティ会場で演奏するバンドからキャリアを始めている。そして活動開始からすぐに、彼はギャラを得てステージに立てるくらいの、いっぱしのミュージシャンとなる。
「中学三年の時にバンドを組んで歌を唄い始めたのを覚えている。ダンスのための音楽をプレイしていた。兎に角楽しかったね。その感覚をロックンロールって言うんじゃないかな。」
「高校生時代はレギュラーでイージーライダーの集まるバーで出演し、定収を得ていた。月曜の午前2時までプレイして、翌朝学校に通ったものさ。その金額はライヴを行って貰えるギャラと同じだったね。
うん?両親はどう思っていたかって?最初はそのような道に入ったって絶対に成功しない、って説得されたよ。でも彼らはバーまで私を自動車で連れて行ってくれたし、2時に仕事が終ると迎えに来てくれた。結局、それが私の人生の仕事と納得してくれたのさ。内心は穏やかではなかっただろうけど。もし、自分の息子が生涯を賭けてやりたい道を見つけたら、そこへ進ませてやらなくちゃいけないね。」
高校で学歴を打ち切った彼は、同州のハンバークという街で活動していくが、やがて、カントリー・ミュージックに興味を示すようになる。最初はBob DylanやThe Bandの歌からカントリー音楽に惹かれ始め、スティールギターを常に抱えるようになる。そして、彼はHank Williamsの音楽に出会う。
「もう完全にHankの歌に完全に参った。それからカントリーにドップリとハマってしまったよ。私はDylanを、Williamsを、Rolling StonesをPink Floydを、そしてMuddy Watersをカヴァーしたかった。けれど、廻りを眺めると、ニューヨーク州には、バッファローにはそういう音楽を演奏するミュージシャンは殆ど存在していなかった。」
故に、Gurfはカントリー音楽の生産地であるオースティンに移住する。1975年のことである。アドヴァイスを求めた時に、ボストンかオースティンが良いだろう、という推薦をされたが、暖かい土地が好きだったGurfは迷うことなくテキサスを選択したそうだ。
オースティンで彼はGram PersonsやJohn Prineのカヴァーバンドを結成して演奏活動を開始する。が、オースティンの当時の市場性では演奏活動をフルタイムで続けるには、活動の場が少な過ぎて(または、無名のバンドには提供されるステージが少なかったのだろうか?)Gurfはオースティンと近隣のヒューストンを数週間のサイクルで往復して演奏活動を続ける。
この間、多くのミュージシャンとセッションをしたり、バンドを組んだりしたが、どれもアルバムをプレスする程の成功には至っていない。が、この数年はGurfにとって彼の現在のルーツを固める上で重要であり、楽しんだ時期でもあったようだ。
70年代の終わりに、Gurfはジャズ・ブルース系のシンガー・ソングライターであったBlaze Foleyに師事し、ソングライティングを学習するようになる。奇しくも後にコンビを組むLucinda WilliamsもFoleyと親交があった。
更に運命的に、両者ともに1980年はじめにLAに活動の拠点を移すことになる。Gurfはオースティンとヒューストンの両方で活動するには、両方の都市でバンドのミュージシャンを探さなくてはならずに、ベースプレイヤーが見つからす苦心した末、音楽都市として巨大なポテンシャルを抱えるロスを新しい活動の場に選択したためと述べている。
折りしも、1980年代のLAではルーツパンク/カウパンクのムーヴメントがカントリーシーンで盛んになりつつあり、Gurfはセッションを通じてDwight Yoakamや彼のバンドのギタリストでありプロデューサーでもあったPete Andersonと活動するようになる。Pete AndersonはLucindaのアルバムでギターを弾いているが、まだ両者は交わらない。知人の知り合いという関係が数年続くのだ。
PeteのプロデュースによるLAのカントリーミュージシャンのコンピレーションである「A Town South Of Bakersfield Vol.2」にギターとして参加。このアルバムは1992年にVol.1とのカップリングで再発売されている。
このコンピレーションにもLucindaは『Dark Side Of Life』という曲を提供しているが、Gurfがギターを演奏しているのは90年代後半にデヴューするカントリー・シンガーのJeffrey Steeleの曲なのである。Lucindaとのタッグは1985年まで待たなくてはならない。
Morlixは旧知であった(1966年以来の知人であるとのこと。)Peter Caseと活動を共にし、彼のバンドであったPlimsoulsにライヴミュージシャンとして1983年にバンドに加入。同年の解散までバンドに在籍。後にPeter Caseの1stアルバム「Peter Case」(1986年)にもヴォーカルでバックアップをしている。
「Lucindaのバンドでドラムを叩いていた、私の友人でもあるMichael Bannisterがお互いを紹介してくれた。ひと目で何か来るものがあったね。即座にバンドを組んでハリウッドで演奏を開始した。8ドルのチケットのね。それから突然、Rough Tradeレーベルから僕たちにレコード製作のオファーがあった。
Lucindaが『誰がプロデュースする?』と尋ねたんで、即『私がやる。』って答えた。即決だったね。」
こうして1988年に、前作から8年ぶりにリリースされた「Lucinda Williams」は物凄い高い評価を各メディアから受けることとなる。このあたりから、Gurf Morlixの名前がギタリスト、そしてプロデューサーとしてアルバムにクレジットされ始める。
1992年にはグラミー賞にノミネートされたLucindaの4作目「Sweet Old World」がリリースされるが、これまたGurfはプロデューサーとバックヴォーカル、そして各種のギターで参加。
全てをディスコグラファイすることは、スペースも時間もないので、代表的なアルバムだけ列挙してみよう。特に1998年以降の活動は相当精力的である。あまり書けないけれども。
1992年 Michael Pennの「Free-For-All」でペダルスティール、バックヴォーカル。
1994年 Robert Earle Keenの「Gringo Honeymoon」にてギター各種と、バックヴォーカル。
Robert Earle Keenの以降のアルバム3作全てにプロデューサーとして、ギタリストとして参加。
1995年 Buddy Millerの「Your Love And Other Lies」にギターとベース、バックヴォーカル。
同アルバムに『A Girl Like You』を提供。Buddyの1997年作「Poison Love」にも参加。
1996年 Teddy Morganの「Louisiana Rain」にギター各種、ミキシングを担当。
1997年 Slaid Cleavesの「No Angel Knows」にプロデューサー、ミキサー。2000年の「Broke Down」
でも全面的にバックアップ。2001年の「Holiday Sampler」も同じ。
1998年 Beaver Nelsonの「Last Hurrah」でヴォーカル。
1999年 Tom Fruendの「Sympatico」でギター。
1999年 Jullie Millerの「Broken Things」でエンジニア。
1999年 Jimmy LaFaveの「Trail」でギター。
1999年 Ian McLagan And The Bump Bandの「Best Of British」でギター、ヴォーカル、ミキシング。
2000年 Jim Whitfordの「Poison In The Well」でプロデューサーとギターその他。
2001年 Ray Wylie Hubbardの「Eternal And Lowdown」でプロデューサー、エンジニア、殆どの楽器。
2001年 Tom Russellの「Borderland」でプロデューサー、エンジニア、マルチインストゥルメント。
一応、知名度の高そうなアーティストに絞ってみても、これだけある。2000年には前述した通り、初のソロ作「Toad Of Titicaca」をリリースし、2001年には自身をフロントマンとしたサザン・ゴスペルバンドのプロジェクトである、Imperial Golden Crown Harmonizersを結成し、セルフタイトルを発表。
そして、2002年のソロ2作目である「Fishin’In The Muddy」と続くのである。
このようにフロントマンとして活動するようになったのは大いにBuddy MillerにインスパイアされたからとGurfは語っている。
「Buddy Millerがソロ作を出したことに相当影響されたよ。彼も私のようにずっと脇役に徹してきたミュージシャンだけれども、幸運にもソロ作は成功し、歓迎された。私はそれを目の当たりにして、同じような音楽人生を送ってきた自分にもソロアーティストとしてやっていけるんじゃないかな、って思うようになったんだ。」
更にLucindaとの蜜月関係の解消も転機になっているだろう。彼女は1992年に「Sweet Old World」を発表してから、結局1998年の「Car Wheels On A Gravel Road」まで6年の期間を置いてしまっているが、1996年の時点でMorlixは同アルバムに収録する数曲をレコーディングし終えていた。(実際にギターとしてクレジットされている。)
が、1998年に発売された時にはGurf Morlixの名前はプロデューサーとしてもメインプレイヤーでもなく、一ゲストミュージシャンとしてインナーに書かれていたに過ぎない。
Gurfはその解消について多くを語らない。
「結婚した男女に良くあるようなことさ。私は彼女のしたいようにやらせたけれども、全く上手くいかなかった。」
と彼は語る。どうやら、レコーディングが8〜9割方終った時点でLucindaが自分のヴォーカルが気に入らずに何回も最初からやり直したのが、嫌になったらしい。「Sweet Old World」でも2回以上最初からのリテイクがあったそうだが、それ以上の完璧をLucindaがヴォーカルに求めたようだ。
Lucindaとのコンビを解消した後、暫くGurfはツアーにも出ずにプロデューサー及びレコーディング・ミュージシャンとして活動する。1999年に英国へと渡り、Ian McLaganのツアーとレコーディングに参加したのが久々のロードであったということだ。
こういった地道な活動から、初めてソロ作を発表。ここ3年は毎年自分のリーダー作を提供してくれている。
「私は長い間、曲を書き続けていた。が、自分のアルバムを作る段階になって、私と活動していたミュージシャン達−例えばLucinda Williamsの書いた曲と比べられる傾向にあるようだ。これは辛いよ。」
と、Gurfは苦笑混じりに語っているが、確かに彼の創る歌に華やかでヒット性のあるナンバーは殆ど無い。1stソロではスワンピーで重厚なナンバーが多く、実に熟年の渋さが滲み出るアルバムであったけれども、ロックというテンポの良さや、親しみ易さという点においてはかなりリスナーを選ぶ作風であったのも確かである。
しかし、ソロ2作目になり、良い意味で軽くなり、耳触りの良いナンバーが増えている。軽いという表現が不適切というなら、明るくなったと言い換えしても可である。
参加ミュージシャンの詳細なクレジットはインナーには存在しないが、「特別な謝意」としてかなりのGurfが関わってきたミュージシャンの名前が見えるので、幾人かは参加があるかもしれない。しかし、基本としては1stソロと同じ編成であり、Gurf Morlixが全てのベースとギター、Ian McLaganがハモンドオルガン、Rick Richardsがドラムというタイトな編成は変わらないようである。
Gurfの声は、相変わらず決して美声とも巧みの技が冴える、というような賞賛を得るような性質ではないが、とても老たけた等身大の親しみを感じる暖かさがある。Son VoltのJay Farrerが加齢を重ねればこのような声になるだろうか。またはSloberboneのBrent Bestからクドさと臭さを抜けば、Gurfのヴォーカルに近くなりそうである。
Morlixの弾き出す様々な弦からの音色も、常と変わらず得体の知れない魅力がある。重過ぎず、かといって軽過ぎず。泥臭くあるけれども、しつこ過ぎず。締りがあるようで、どこか間の抜けたルーズさが内在している。この音世界はまさにMorlixの構築したスワンプとルーツのある種の頂点だろう。
全12曲は、かなりモノトニアスであったデヴュー作「Toad Of Titicaca」と比較すると、多種多様で色々な楽しみに溢れている。
軽快にロックする#5『Center Of Universe』や優しいポップチューンの#9『How To Be』、サックリとしたシャッフル感が特徴の#10『Driftin’Apart』ではGurfが10年近く西海岸で活動してきた影響を覚えずにはいられない。前作では聴けなかった、爽やかさと明るさが見えている。
ブワブワのハモンドオルガンと泥臭いギターに支えられつつ、アップビートにロックする#2『I Ain’t Goin’That Way』やヘヴィにグルーヴするリズムに、エフェクターをかけたヴォーカルがうねる#4『Fishin’In The Muddy』等のメロディを重視した野暮ったいロックナンバーは南部ロックの教科書のようでもある。
ブギーロックのルーズさがダンスする#6『Big Eye』やそこはかとない哀愁を帯びたなロッキンブルースの#7『I’m Hungry And I’m Cold』、ダートでパンキッシュな荒さがダブダブな#8『Your Picture』の三連続に加え、#11『There Goes The Bone』の投げ遣りにも近い酔っ払いロックンロールの転がりという、未整理なルーラルさはバーボンを片手に沼地で釣りをしながら聴きたくなる。
そして、やはりGurfのスワンピーでアクースティックな背景が全開の、ダークなサザンナンバーの#1『Torn In Two』や、やる気のない気だるい塊が漂う#3『My Lesson』での下半身の安定がなければ、Gurf Morlixのレコードは始まらないだろう。特に#3の酔いどれぶりは聴いていて上半身がスウィングしてくる。
最後を飾るのは、東洋の祭り太鼓のようなトラッドのリズムと、大地の底から湧きあがってくるようなサザン・ブルースの重力を感じるような#12『Let The Rhythm Rule』である。こういったナンバーはとても現在のメジャーではトラッキングできないだろう。何処までも尾を引いてくるように粘着力のあるナンバーである。
「これまでにリリースしたソロ作で、私の名前が劇的に広まることは無いと考えていたし、実際にその通りだね。少しくらい名前が知られているので十分だよ。Lucindaが周りが彼女をスタートして扱い、彼女がそう振舞おうとして苦心しているのを見てきたからね。自分の演奏をして、ファンがそれを楽しんでくれる。それがベストさ。」
というGurfのスタイルはこれからも変わらないだろう。かなりコマーシャルになったこの2作目でも、Gurf Morlixの商業流行から距離を置くという、自己流の拘りは健在である。
が、そういった固執が独り善がりの聴くに堪えない作品となっていないのが、やはり凄い。Buddy Millerと並んで、筆者の中ではマイペース・オヤヂの筆頭に浮上してきているアーティストである。 (2002.4.21.)
 Ephemera / Case 150 (2001)
Ephemera / Case 150 (2001)
Roots ★★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Alt-Country ★★★★★
You Can Listen From Here
2002年4月に至り、漸くこのデヴューEPである「Ephemera」が西海岸の大手オンラインショップであるMiles of Musicに並んだ。これでより多くの人が(程度の問題ではあるが)このCase 150というバンドに親しんでもらえるのではないかと思う。
早速、バンドのリーダーであるThom Bissy氏にメールで「おめでとう」、と連絡しておいた。が、実は内心は結構複雑であったりする。今回のラインナップにおけるエンドプライスは6ドル50セント。直買いの時よりも相当なディスカウントをされている。まあ、送料が加わればそれなりに両方の金額が近づくことにはなるのだが、やはり釈然としなかったりするのだ。ま、早いものが損をするというのはある程度のリスクではあるから致し方ないけれども。(苦笑)
しかし、損をしたという気持ちは全くない。Wilcoのヘタレ新作を買うなら断然こちらをお薦めだ。
さて、当レヴューサイトではこれまで150本以上の作品について擱筆しているが(2002年4月現在)、これまでにEPはおろかミニアルバムについても取り上げたことはない。殊に、特別の意図があってミニアルバム以下の分量を遠ざけていた訳ではないのだが。結果的に常にフルレングスのアルバムについて筆を執ってきたことになる。
筆者的な基準では7曲あればフルレングス扱いしている。実際にアナログ盤の頃は7曲とか8曲のアルバムがとても多かった。プログレッシヴ・ロックになると5曲とか6曲。Yesの大作である、邦題「海洋地形学の物語」なんぞは2枚組で4曲という現在の市場性では考えられんようなインプロヴィゼィションの権化だったりする。
と、そういった例外は除いて、やはり6曲/20分台の作品をフルアルバムとするにはまだ抵抗があるので、今作品の「Ephemera」はまさに6曲入りのミニアルバムとなる、このHPのスタンダードでは。
それにしても、6曲で終ってしまうのは実に惜しい作品だ。ために、今回紹介の場を設けたのだが、偶然に業界では大手の通販ショップへの入荷と並んだのは、喜ばしい偶然である。
今回のディストリビューションに際して、恐らくパッケージングは変更されていないと想像している。
私の手元へ届いたときには、安物のスリムケースに入ったCDと一枚のインナー。バックインレイはなかった。しかも、CDであるけれど、Playstation Oneのソフトのように演奏面が真っ黒なディスクである。
一瞬ゲームCDかと勘違いし、Playsation 2に入れてしまった。(実話)が、流れてきたのはとてもポップに弾むラインを持ったルーツロックであったので、即演奏用ドライブに入れ直した次第であった。これまでにCD‐RがプレスCDの代わりに入っていたということは、インディの作品購買においてはあまり珍しくなかった。
が、まさかPlaystationモドキの真っ黒なCDに、ラベル製作ソフトで拵えたのが丸分かりのCDラベルを貼って届いたことは今回が初めてである。(笑)どうやら、CD‐Rと思いきや、著者のポンコツCDプレイヤーでしっかりと演奏してくれるため、PSソフトのプレス方式で作製された音楽CD‐ROMのようにも思えるのだが・・・・・。ま、それはどうでも良いだろう。
価格からして、それ程問題のあるコンポーネントではないと思う。EPと思えば、スリムケースにバックカード無しも大して気にはならないだろうし。
Case 150というバンドの母体が結成されたのは1997年まで遡る。フロントマンであり、リードヴォーカリストでもあるThom Bisseyはアメリカ南部のアリゾナ州はトゥーソンという砂漠の真中の街で音楽活動を続けていた。(確か、アメリカ横断某クイズに出てきたような気がする。話題休閑。)
彼のコメントに拠れば、Thomはかなり雑多な音楽を多くのローカルバンドで演奏してきたようで、“スマートなパンクロック”に、“ジャズの邪道”、“そしてカントリーミュージックだけどどこか違う”、というようなジャンルを経験しているそうだ。詰まるところ、特定の音に傾かない、中道的なアメリカンロックの基盤というような音をプレイしてきたというように解釈できると考えている。
生まれ故郷のアリゾナで、Bissyは80年代の終わりくらいまでThe Bandicootsというルーツロックバンドを結成し活動をしていた。が、1990年初めに、Thom Bissyはバンドの活動拠点をペンシルヴァにア州へと移す。
理由は「もっと上手いチーズサンドウィッチを捜すため。」と冗談めかされているが、実際のところはオリジナル・ソングを歌える場所を探しての大移動であったようだ。が、状況は変わらなかったようだ。
「僕は当時のクラブシーンの趨勢に馴染めなかった。たくさんのカヴァー・ソングに混じって少しだけオリジナルを歌うんだぜ。クラブに出演して、カヴァーソングを演奏したら、満座から馬鹿にされるのは西海岸だけだったね。」
結局、Thomは地道な意に添わないカヴァーバンドをローカル・シーンで細々と続けていたらしい。このBandicootsというグループに関してはデータが全く存在しないので、どのような音楽をやっていたかははっきりとは判明しないのが残念である。興味はあるのだが。
そのThomがCase 150を結成したのが、1997年。この頃になると、インディ・シーンでもオリジナルを演奏することが商売となる、という市場が出来上がっていた。
Case 150という名前の由来はThomが所有している納屋に格納してあるトラクターに付いている150個のパーツが入ったケースから採った、ということだ。農場と納屋−如何にもこのルーラルなバンドらしい。
結成から、メンバーは全く安定せずに、相当数のミュージシャンが短期間加わってはまた離れていくという形を繰り返していたようである。が、転機は1999年に訪れる。
1999年にThomが友人のEd Yashinsky(同名のウクライナ人の友人がいるので恐らく露西亜系)とWilcoのコンサートに行ったことが切っ掛けとなった。
丁度、Case 150のベーシストが脱退し、ベース弾きを探していたThomがEdに誰かベースを弾ける人を知っているかと尋ねたのだ。Edは1987年までベースを弾いていたが、それ以来弾いていないので、自分では駄目ということを口走った。が、Thomが過去にベースをプレイしていたなら、すぐに弾き方なんて思い出すだろう、と彼をベーシストとしてバンドに誘ったのである。Edはギターをずっと引き続けていた半アマチュア音楽家だったようである。
それ以来、Case 150はThomとEdを中心として動き始める。このデュオと頻繁に交代するメンバーという形での活動に移っていくのだ。
そして、2001年の夏、二人は元BadleesというバンドのギタリストであるBret Alexanderというミュージシャンが所有・経営するスタジオに入る。このスタジオはペンシルヴァニア中部のローカルアーティストにとってはかなりのステータスシンボルである場所のようだ。人気ローカルバンドが幾組みもレコーディングを行っている。
Bret Alexanderと彼のバンドメイトであったドラマーのRon Simasekの協力を得て、二人は#1から#5までを録音する。このレコーディングがEdには初の本格的なスタジオ入りであったそうである。
「僕等は20分くらいの長さのアルバムを創るつもりでいた。」
というEd Yashinskyのコメントにもあるように、最初からフルレングスにするつもりはなかったようである。
5曲をその場で仕上げ、最後の#6だけをPaul Smithという人と別のスタジオでレコーディングし、この「Ephemera」が完成したのである。
「Ephemera」を完成した後、2001年の冬にはバンドして4ピースの形となり、現在に至る。
Thom Bissy (L.&B.Vocal,Guitar,Bass) , Ed Yashinsky (Vocals,Bass,Guitar)
Ken Geist (Guitars,Vocals) , Tuck Lentz (Drums)
という編成となる。リード・ヴォーカルはインナー記載の情報でははっきりとしてないが、殆どがThomのリードヴォーカルである。唯一#5『Wrecked Up』のみEdがリードヴォーカルを担当している。これはThom氏に確認済みの情報なので間違いない。
「Case 150のサウンドはアパラチア山脈の大自然の中で休暇を楽しんでいたR.E.M.が家に帰る途中で迷子になってしまったような音楽さ。」
というのがEd Yashinskyの自己評価である。あまりにも文学的で難解な表現であるけれども、R.E.M.のような新世代のアメリカンロックをカントリーサイドのトラディショナル風味で染めた音楽、とでも言うべきだろうか。
「A.M.」の頃のWilcoや、Son Voltのカントリー・ロックに傾倒したアレンジを持っているのは疑いようのない美点である。が、単なるカントリーロックよりはずっとRock n Rollだ。ポップミュージックとしてのツボはきっちりと押さえている点は、「Tomorrow The Green Glass」の頃のThe Jayhawksのアレンジを更に垢抜けなくした雰囲気に近いようにも思える。
この飾り気のないジャケットにも彼らの音楽性が集約されていると思える。焚き火を囲んで寛いでお茶をしている人々の醸し出す、伸びやかでリラックスしたルーラルな空気。こういったゆとりが全編に漂っている。
Case 150がルーツとしているものは何か、という問いに対してリーダーのThom Bissyはこう表現している。Case 150の由来となったスタジオを有する納屋も掛けての答えであるだろうが、
「そりゃあ、ビールが入った冷蔵庫がある場所。それが僕達の原点だね。」
と述べている。つまり生粋のBar Rock Bandと解釈して良いと考えられる。10年以上、オリジナルソングをクラブシーンで披露して活動してきたThom Bissyの心情がここに代弁されているようだ。
全く余分な装飾をせずに、素の侭を盤面に落としたような等身大の熱意が伝わってくる。が、暑苦し過ぎず、脱力し過ぎずという適度な力加減を心得ているかのような、長年のキャリアを感じてしまう。
とても、このミニアルバムが処女作であるとは思えないくらいのふてぶてしさを発散しているが、反面、どこかまだ青さが抜けきっていないような頼りない覚束なさも同時に存在し、その不器用さがとても親しみを覚えてしまうのだ。
EPなため、たった6曲でトータル演奏時間は25分くらいという短さであるけれども、捨てナンバーは全く含まれていないし、緊張をせずにスルスルと耳を傾けれる滑らかさが全体の流れとして通っている。
まずは、バンドのスピードサイドを代表するかのような、ざっくりと切れ込むロックチューン、#1『She Got Home』からアルバムはスタートする。やや裏声と線の細さを感じさせる、喉から胃の腑を吐き出すかのように歌うThomのヴォーカルは、美声でも魂消る絶叫でもないが、非常に独創的だ。ひとりで歩かせると倒れそうな不安定さがあるのだけれども、その点にこそ一度聴いたら忘れられないインパクトがある。
東海岸のクラブシーンのルーツサウンドに共通であるけれども、ダサダサな野暮天ギターを掻き回してもそれ程のドロドロした感覚が浮かんでこずに、適度なドライヴ・フィーリングを顕しているのが、ポップロックとしての中庸さを保持している。
#2『Kaite』は、#1のタテノリなタフナンバーから、ひょいと息をつけるアーシーなポップナンバーである。垂直方向から水平方向へのロックビートの移行と述べれば良いだろうか。ファルセット気味の歌う節の尾がヒュ〜ンと伸びていくThomの暢気なヴォーカルとハーモニー・コーラスの掛け合いが楽しい。
16ビートのドラムに、西海岸風のコーラスが被さるのが実に歯切れがよい#3『Cascade Of Blonde』である。これまた弾むようなメロディラインが特徴的なウルトラ・ポップなハーモニー・ナンバーである。6曲の中で唯一3分を切るナンバーであるけれども、その短さはパンクロックの手法を匂わせてもいる。
Thomのヴォーカルが一番活きているのが、トラッドなイナタ臭さが夏の午睡のように気怠るく流れていくスローバラードの『Ten Years』だろう。メロディアス・ハードロックのような情緒のあるギターソロをいきなりアレンジしているのはトラッドからアリーナ、というような変転が見えてとてもユニークである。
クルクルと振り回せるくらいに重量がある鞄のような重量感のあるギターがカッティングで痛快感を演出しているナンバー#5『Wrecked Up』はEd Yashinskyがリード・ヴォーカルを、Thomがハーモニー・ヴォーカルに回っている。
Edのヴォーカルは繊細で女性的なThomとは対照的に野太く、ドロンとしてるのだが、不思議にファルセット気味の喉の震えがThomと似通っている。かなりルーズなバタバタとした構成とアレンジで繋がっていくナンバーであるけれども、ポップであり奇妙な優しさが存在する。
最後のナンバーは、オルガンサンプリングされたキーボードとルーツィな弦がアンサンブルを奏でつつ、緩やかに流れていく#6『My Side Of Town』である。アクースティックな色合いが一番くっきりと際立ったナンバーだろう。何処かでガツンとギアが入るかと思いきや、淡々とメロディがたゆたっていくのがこのバンドのカントリー・サイドな側面なのだろうと思う。弾き語りに近い曲なのだが、結構厚さがあるので、どっしりとした安定感がある。
以上、6曲という短いスパンに収められたナンバーを紹介した。こういった良心的なアメリカンルーツを普通に演奏できるバンドがまだちゃんと出現してくれるのはとても喜ばしい。
が、Case 150は中々ライヴの予定を組めずに腐心しているようだ。現在はフィラデルフィアの近郊を中心に活動しているようなのだが。
「現在は観客がいないんだ。つまりシーンも活性化していない。つまり、何故良いレストランが無いんだろうって不満を言う状況と同じなんだ。実際は良いレストランはあるけれども、人々が利用しないで錆びれるというのが現状ということさ。人々は気持ちの良い音楽を聴こうとし、不快にさせる音は遠ざけるのが心理的な働きのはずなんだけど、実はやはり周りで氾濫している曲を聴いてしまうんだ。」
とBissyは現在のメジャー音楽について述べている。実際に、とても腹立たしいことである。良い音楽が常に日陰者になってしまっているのだから。が、彼らは決してめげていない。常に自分たちのペースで活動してく意思を持っているのだ。
「シーンで認められる地位を築くのと同じくらいに凄いのが『もし、俺達のシーンが存在しなければ、俺達が作ってやる!』って宣言することだけど、そんな暇もエネルギーも僕にはない。それよりもファンが僕達を賞賛して受け入れてくれる場所を一つでも多く訪問してプレイしたいね。」
とEdは述べている。あくまでも草の根活動を続けていくのだろう。
そういった適宜な時代でないというビハインドを抱えつつも、バンドは確実に前進しているようだ。
「今年の夏くらいにはフルレングスをリリースしたいね。スケジュールが決まったら教えてあげるよ。」と彼はメールで語ってくれた。
また、ソングライティングをEdにもっと担当させ、リードヴォーカルをもより多くEdに執って貰いたいという意向を示している。更に、ギタリストのKenやドラマーのTuckにもハーモニー・ヴォーカルからもっと積極的に参加してもらい、レコーディングを進めて行くとのこと。
バンドとしての地歩を固めつつ、新しいマテリアルをレコーディングに向けて整理しているようだ。
今年中に是非フルレングスが聴きたいものだ。こういったバンドがもう少し脚光を浴びればシーンも面白くなると想像するのは現状では夢想の域を出ないのか・・・・・。 (2002.4.24.)

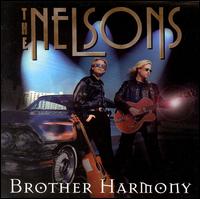 Brother Harmony / The Nelsons (2000)
Brother Harmony / The Nelsons (2000)