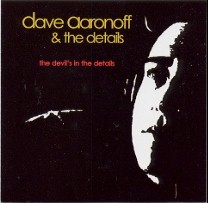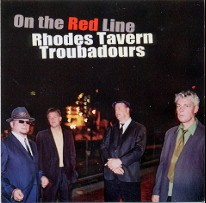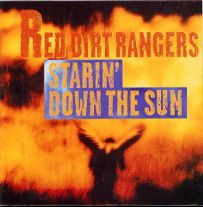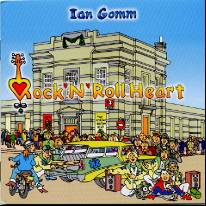Palace Of Gold / Blue Rodeo (2002)
Palace Of Gold / Blue Rodeo (2002)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Alt-Country ★★☆
You Can Listen From Here
日本で洋楽を追いかけていては仕方ないかもしれないが、米国で普通にシーンを見ていてもBlue Rodeoというバンドの音楽業界における位置は意外に見えてこないのだ。
ここでいう位置というのはBlue Rodeoの本国であるカナダでの一般的評価のことを指す。つまり、人気、ステータスという単語と置き換えが可能なものだ。
北緯49度付近を北上して米国からカナダに入り、カーラジオをカナダのポップチャンネルにチューニングすれば、Blue Rodeoの曲はアルバム発売当時ならば間違いなく頻繁にオン・エアされている。これはカントリーや総合ポップチャート、ロックチャートに跨ったエア・プレイである。
つまり、米国では控え目に表現してもマイナー以上の扱いにはなっていないBlue Rodeoも、本国カナダではカナディアンのTop200アルバムのチャート上位20位以上には常にリリースするアルバムを送り込んでいる、国民的にはそれなりの人気を誇るロックバンドなのである。
100万枚というミリオンセラーには、総人口3000万人という国内マーケットの規模からすると相当に辛いのだが、10万枚、20万枚という数字は、アルバムを発売すれば数ヶ月も掛からずに達成している。総人口が1億2千万人である日本で、世界でのCD売上が2位の市場であっても早々は国内盤のミリオン・ブレイクが出ない事実を鑑みれば、その人口数から比して10万単位でアルバムを売るバンドなら激烈にメジャーと言って良いだろう。
何と言っても、Blue Rodeoは1987年に「Outskirts」でレコード・デビューした当時から、巨大メジャーレーベルであるWarnerと契約をしているメジャーバンドなのだから。・・・・とはいってもWarnerのインターナショナルカンパニーであるWea Canadaなのであるが。
結局は、国内では大メジャーでも所詮は国際的−音楽の場合は否応無しに合衆国と大英帝国という2大巨頭が国際的、相対的に見れば合衆国が国際市場の顔になるが−にはドメスティックな辺境国家の人気バンドに近い扱いなのだ。
1995年にBlue RodeoがDiscovery RecordsからそれまでWeaからプレスされ米国では廃盤扱いになっていた5枚のバックナンバーを再発売して以降は、徐々に合衆国でもBlue Rodeoという名前はインディを中心に浸透していってはいる。1992年には米国のレコード屋では全く見かけることの出来なかったBlue RodeoのCDも、1996年にはそれなりの品揃えをしているのを実際に目撃して驚いた記憶がある。
が、人気や評判は確実に上向きであるのだが、米国でのアルバムセールスは全く振るわないのはデビュー当時から残念なことに不変である。
しかし、まだ米国事情はマシと言ってもよい。太平洋を渡った極東の島国では、1990年代後半までBlue Rodeoというバンドのアルバムは殆ど輸入すらされていなかった。1994年に日本の大手外資系のレコードショップで軒並みBlue Rodeoという名前さえ理解されなかったのには相当なショックを受けた。洋行(笑)帰りとして。
また、筆者的にはBlue Rodeo最大の凡作(駄作とまで酷くないところがこのバンドの凄さ)である2000年のアルバムにして前作の「The Days In Between」がどうやら日本盤でリリースされる寸前まで漕ぎ着けたのだが、ご破算になってしまった(情報提供:コンクレコード様)という具合に、現在に至るまで輸入盤を扱う大型店舗以外では見かけることも出来ないという状態が続いている。
少なくとも、大手外資系の軒先には並ぶようになったのは進歩であるとは思うのだが。
とここまでクドクド述べたのは、Blue Rodeoというバンドは決してインディペンダントのバンドでもマイナーな零細バンドでもないのである、彼らの出身国では。そして出身国から殊更離れて米国を中心に活動をするカナディアンに言わせると「裏切り者」(笑)でもないのだ。
ここに最近のBlue Rodeoに対して筆者が声を大にして言いたいことがあるのだ。それは、
メジャーチャート(加奈陀限定)常連が、シングルカットを考えないようなアルバムを創るのはどうかと・・・・・・。
ということだ。この「Palace Of Gold」にはそれなりにシングルになるナンバーは揃ってはいるが・・・・・。
Blue Rodeoの音楽性に関しては、レコードデビュー当時からかなり様々な評価があるが、かなり昔からこのバンドの熱心なファンであった筆者からすれば、
絶対にPop/RockとRock n' Rollが基本のバンドなのだ。
Alt-CountryとかCountry RockとかAmericanaとか、Folk Rockとか。特に最近はカントリー系のロックバンドと言う設定が目立つようになっているけど、ルーツのテイストをオーソドックスなPop/Rockと美味く融合させた王道北米ロック=カナディアンロック≒アメリカンロックのバンドだと考えている。
たまたま、ルーツロックというエッセンスをバックボーンとして強烈に有し、オルタナティヴとかヘヴィロックとかいう没個性の流行音楽に安易に傾倒しない見定めの確実さが際立ったバンドなだけである。
1970年代から80年代にかけて全米のポップチャートに必ず顔を見せていたロックシンガーがしばしばカントリーの影響をストレートに表現したナンバーをアルバムに入れてくることが普通であったのと大して変わらないアプローチと見なせば問題ないだろう。
この観点からはHeartland Rockという分類法も適用は可能である。
ちなみにこれまでのBlue Rodeoのアルバムを筆者なりに分析すると以下のようになる。
◎傑作 ●良作 ▲普通 ×問題あり を基準にすると
▲「Outskirts」(1987年)
まさに普通のPop/Rock。未完成さは否めないがメジャーバンドの処女作としては満足出来るレヴェル。
●「Diamond Mine」(1989年)
大幅にアーシーさとアクースティックさを増したアルバム。色々やってみるという意図が明確に現れている。
◎「Casino」(1990年)
前作とは全く逆にルーツロックの要素を極力減らしたPop/Rock。このバンドの中では一番キャッチーな作品。
初期の集大成的金字塔。
◎「Lost Together」(1992年)
最もロックンロールであり、ルーツロックを明らかに本格的方向性として打ち出した傑作。
●「Five Days In July」(1993年)
前作のルーツロック路線から一層カントリーやフォーク路線に傾倒した牧歌的1枚。
▲「Nowhere To Here」(1995年)
サイケディリックで暗鬱なオルタナティヴ風味を持った異色作。がシングルナンバーはしっかりと抑えている。
明暗のハッキリしたアルバム。
◎「Tremolo」(1997年)
アクースティックでありつつ土臭さを程好く抑えたPop/Rockの名盤。ルーツとメジャー感覚のバランスが絶妙
に均衡している。
×「The Days In Between」(2000年)
地味というか、メジャーバンドとは思えないくらい焦点がボケた駄作。Blue Rodeoの作品でないのならば、そ
れなりに評価は可能。悪い意味でマイナー指向に走り過ぎ。
●「Palace Of Gold」(2002年)
前作でもう駄目かと思ったが、キャッチーな路線に戻ってきた。「Five Days In July」と並んでカントリーロッ
クの匂いが最も強いアルバム。しかし・・・・・
これを俯瞰して戴くと、筆者の近年におけるBlue Rodeoへの不安が少なからず分かって貰えると想像する。
まず、2000年の「The Days In Between」の評価が筆者は圧倒的に低い。それまでは「Nowhere To Here」が駄目の東前頭筆頭だったものだが。
シングルとしてカットできる曲が一聴しただけでは全く存在しなかったのには驚いた。更に地味というよりもダーク路線のAlt-Countryに正対し過ぎているのは、カナダのマーケットで正統派のロックンロールを売ることのできる数少ないバンドの仕事とは到底思えなかった。
繰り返すが、Blue Rodeoはメジャーサウンドのカナダ的良心に当たるバンドだと思っているからであり、その考えはそれ程的外れではないとも考えている。
が、2000年の駄目作より1997年の「Tremolo」を発表後に相次いでリリースされた2枚リードヴォーカルのJim CuddyとGreg Keelorのソロ作にこの問題は端を発するかもしれない。Jimは完全なカントリーロック作を提供し、GregはGregで全くルーツを感じさせないAlternativeのアルバムを作成したあたりから、Blue Rodeoはメジャーに依存することを厭い出したのかもしれない。
アーティストが陥り易い「売れ筋」と批判されるメジャー路線からの脱却がBlue Rodeoにも影を投げかけつつあるかなとかなり嫌な気分になったものだ。
しかも、1992年の「Lost Together」にペダルスティール奏者として準メンバー扱いで参加して以来、バンドのルーツでアーシーな音の部分を牽引してきたKim Deschampsが2000年に脱退したというニュースもあり、このままBlue Rodeoは迷走するかもしれないという危惧さえ抱くようになっていた。
しかし、この最新作「Palace Of Gold」はかなり明るめのPop/Rockという懐かしのBlue Rodeoが戻ってきたかのような作品となっていて、当初は相当の安堵感を覚えたものだ。
ところが、少し初期の興奮を収めて聴き返してみると、やはり気になる点がある。良いアルバムであるという感想は不変であるのだが、かなり微妙な箇所が目に付くのだ。
第一に、非常にCountry Rockという表現が似合う音を創造しているところが非常にはっきりと見て取れる。古くは「Diamond Mine」からフォークやカントリーという隣国の草の根音楽への傾倒を示していたBlue Rodeoであり、「Lost Together」からは明確にルーツロックの路線を走り始めてはいた。
が、「Five Days In July」以来のカントリー寄りなアレンジが目立つアルバムを持ってくるとは、かなり意外という思いを禁じえない。また、フォーキーで内省的な面も伺えた「Five Days In July」とは根本的に異なっている側面が存在していると思う。
特にアナログ盤ならA面に当たる前半でカントリーアレンジが飽和するくらいに突出しているのだ。しかも、妙にアンダーグラウンド的なインディバンドっぽさが存在する。その点がしっとりとして落ち着いたアクースティックさが素敵な「Tremolo」や牧歌的な余裕が溢れている「Five Days In July」との違いだ。
それが悪いこととは思わないが、Blue Rodeoのキャリアを考えるとどうにも首を傾げる趣は前半から中盤に掛けてかなりの頻度で現れている。
タイトル曲の#1『Palace Of Gold』での目一杯ダスティさと独特の脱力感を醸し出すペダルスティールに、妙にチープなオルガン。曲としてはキャッチーでツボを得たメロディメイキングをしているのだが、このナンバーがポップチャートで受けるとはいまいち思えない。
#2『Holding On』ではJimのハイトーンでありつつもハスキーであるウォーム・ヴォイスが全開であるけれど、これまたかなりレイドバックしたカントリーロックの要素が強いトラックだ。シングルになれそうだが、それには今ひとつキリリとした芯が欠けているように感じる。
#4『Bulletproof』はアルバムからのファーストシングルとして本国でヒットしただけはあって、ストリングスを絡めた、Jim Cuddyの浪漫ティックな面がはち切れんばかりに詰め込まれた静かなバラード。ウィルツアー・ピアノを多用している点に、しかしどうにも地味と言うかメジャー路線を外れたがっている、マイナーカントリーなロックバンドへの憧憬を匂いとして嗅いでしまう。
同系統のバラード#7『Love Never Lies』はチェロやヴァイオリンがストリングスセクションではなく、ソロの弦楽器のユニゾンを聴かせる目的でアレンジされたメランコリックなJim得意のバラードだが、少々弦楽器がカントリー的なイナタ臭さを出し過ぎており、Blue Rodeoとしてはストライクど真ん中まで好きになれない。もっとストリングスとポップソングとの折り合いのつけ方が上手なバンドだと思うのだが。
#3『Homeward Bound Angel』もマンドリンを始めホーンや女性ゴスペルコーラス隊といった音要素をヴェテラン集団らしく上手く活用しているのだが、これまたスムーズさが少し足りない気がする。カントリーがあからさま過ぎなきらいのある曲なのだ。が、この曲では他の問題を耳にしてしまうのだ。
これが第二の危惧。
それは、リードヴォーカリストとして、ラフでソウルフルというBlue Rodeoのロックサイドを支えてきたGreg Keelorの声の衰えがかなり激しいことがこのアルバムで明確に理解できるに至っているということ。
前作「The Days In Between」でいまいちアルバムにBlue Rodeoらしい「華」がないと不満が募った一因は、Gregの声がかなり力不足になってきているからだと改めて気が付いた。
元来、美声でもなく器用な歌い回しも出来ないヴォーカリストであるGregの良さは、直球勝負のパワフルな声とコブシの振り回しだったのだが、その2つが落ち着いたと言い難いくらいに落ち込んでしまっている。
が、#8『Stage Door』は非常に儚い切なさがメロディに乗った極上のバラードなのだが、こういうタイプのナンバーではかなり頼りなくなってしまったGregの声が妙に悲哀と切なさを加速してくれるので、予想以上にハマリなヴォーカルになっていたりもする。まあ、仄かに暖かいホーンの音とピアノのリリカルな音色が絶妙のハーモニーを奏でるこの曲は元からクオリティが高いということもあるけど。
元来Gregはバラードよりもミディアム以上のナンバーでその手腕を振るっていたヴォーカリストであったのに、オルガンが極彩色にラインを染めていくバラードの#12『Glad To Be Alive』でも意外にフンワリとした包容力を醸し出してくれるのだ。
ラストナンバーの#14『Tell Me Baby』でもその不器用さ故の朴訥さが、美しいメロディと妙にミスマッチでユニークな仕上がりとなっている。このナンバーもペダルスティールがカントリーっぽさを放出しているが、このルーツさとポップな流れとの同居がBlue Rodeoの最も素晴らしいところだったので、前半の3曲、4曲にはどうしてこれが出来なかったのかと疑問を投げたい気分である。
災い転じて、ではないがGregがバラード向きになってしまうと、Jimとのバランスの取れたコンビネーションが崩壊する危険性がある。JimもGregも「片方だけしか歌えない」シンガーではないが、やはりバラード系はJim、ロック系はGregというパターンが多かったBlue Rodeoのこれまでを振り返ると、グループとしての根幹に一抹以上の不安を感じずにはいられない。
第三に前半のカントリー路線と比べて、かなりモダンロックの影響を感じる、最近のヴォキャブラリーならAmericanaと呼べるタイプのトラックが中盤以降多くなっており、ややアルバム全体の釣り合いを見下ろすと、不安定さが見えることだ。
#5『Comet』はセミ・サイケディリックというか「Nowhere To Here」で見られた暗く、捻くれたマイナーソング。ちょっと似合わない。
#9『Cause For Sympathy』はかなり複雑な展開と多彩な楽器を使ったポップなナンバーなのだが、少しごちゃごちゃと乱雑に流れてしまっている感じが強い。メロディもコマーシャルであるのだが微妙に暗いマイナーさをなぞるところがあるのが少し気になる。アルトサックスやフルート等の使い方は面白いのだが。
#10『What A Surprise』は前半のカントリー・フィール溢れる展開に相反するようなBeatlesの影響を感じる浮遊感のあるポップナンバーであり、面白い曲なのだが、これまたシングルには向かない。何処かしらCarpentersのようなオールドポップスをなぞるかと思えば、崩れた進行を見せると、かなり複雑なナンバーだと思う。
とここまでは些かネガティヴにしか賞賛してないが、久方ぶりの再開を喜べるという感のナンバーも含まれているのだ。
#6『Walk Like You Don’t Mind』はこのアルバムでやっと登場したBlue Rodeoのロックンロールなアスペクトを抽出したかのようなラフでブギーな熱い曲。前作はおろか、傑作の「Tremolo」でも極力抑えられていたロックンロールへのハメ外し。こういった奔馬の如く、名前のようにRodeoする彼らをアルバムで聴くのは実に暫く振りなのだ。
#11『Clearer View』もスピーディなホーンとJimの裏返るジャンプ・ヴォーカルが楽しくロックを弾ませてくれる良作であると思う。このようなメジャーで王道的なロックナンバーこそ「Lost Together」の頃を懐かしく、そして現在でもBlue Rodeoはロックの担い手であると再確認させてくれる。
そして、バラードとしては「Tremolo」の雰囲気を持ち込んで、更にゴージャスな肉付けを−実際にホーンでしてあるのだが−した#13『Find A Way To Say Goodbye』がシングル曲の#4よりもダイナミックで筆者は好きだ。
・・・まあ、全体的にJim Cuddy好きであるので、評価の高いナンバーはJimに多いのは生来の傾向なので、Blue Rodeoの2枚ヴォーカルを均等に愛しているリスナーは割り引いて読んで貰えれば幸いだ。
また、長年−日本で全くアルバムが手に入れられない時代からのファンを継続しているため、少々の良作では満足できない故、かなり辛口になってしまっているが、こちらも割引券を大量に発行して欲しい。
バンドの経歴等については、何れ書くBlue Rodeoのバックナンバーで言及する予定だ。今回はそのスペースが尽きてしまったので。1997年の傑作から、ライヴ盤「Just Like A Vacation」に駄作(をい)、そして2001年の「Greatest Hits」と暫くオリジナル盤が出ていなかったので、この良作は嬉しいことは間違いないのだ。
と、さり気なく「The Days In Between」は無かったことにしている。(苦笑) (2003.1.21.)
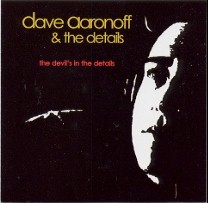 The Devil’s In The Details
The Devil’s In The Details
/ Dave Aaronoff & The Details (2002)
Roots ★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Americana ★★ You Can Listen From Here
無名のGin Blossomsという称号を与えたい。いきなりで何だけど。
今年になって驚くべき飛躍をしたアーティストが少なからず記憶に残っている。
例えば、最高のルーツロックアルバムを5人編成のゴージャスなアンサンブルで叩き出したThe Kickbacks。これまでのどうにもポップさが足りなかった方向性から一転して素晴らしいルーツロックアルバムを届けてくれたMartin Zellar。アルバム前半で一気に筆者を骨抜きにしてくれたJohn Cate・・・・・。
と挙げれば相当数が浮かんでくる。
そのひとりに是非とも付け加えたい“Jump Up”な赤丸急上昇中のアーティストが、今回紹介の場を設けたDave Aaronoffである。
この「The Devil’s In The Details」は2000年末に発売されたDave Aaronoff & The Details名義のデビューアルバム「Your First Time In The Details」に続く2作目であるけれど、最も特筆すべき変化はアメリカンルーツな方向性をサウンドが帯び始めた点にある。
元来、Dave Aaronoffというミュージシャンはルーツミュージックと言うフィールドとは全く縁のない音楽経歴を持っている。実際にソロとして(バンドのThe Detailsを従えているけど。)のキャリアの第一歩となった「Your First Time In The Details」はかなりポップ、というよりもPower PopとAdult Alternativeがメインディッシュであった。
このアルバムでElvis Costelloに匹敵する才能の持ち主と呼ばれたことから判断できる人もいるだろうが、ブリティッシュ・ポップのキャッチーな面と、英国版解釈編ルーツロックと言うべきパブ・ロックの薄いルーツフィールは感じ取れたとはいえ、根源的な基本音楽は、Pop/Rockであり現代的なモダン/オルタナティヴの影響をより多分に感じる作品と言う感想を抱いていた。
しかしながら、The Detailsを従えての2年振りの2枚目では、最近ブロードに適用され始めているモダンビートに加えてカントリー的な土臭さを感じさせる、Americanaという一種のルーツロックの存在を掌に掴み取れる方向性に、一歩以上踏み出している。
デビュー作にしても、薄いパプロック風とはいえルーツを感じ取れないことも無かったのだが、今回は胸を張ってアメリカン・ルーツに一翼を連ねるアルバムを提供したと言えるのが嬉しい。
ここで留意しておきたいのは、Dave Aaronoffの2枚目は、1作目よりもアメリカンロックとしてのルーツさを持ち始めたとはいえ、ベッタリのルーツロックアルバムではないと言う点であるだろう。
後程これまでのバイオグラフィーに付いては言及する予定だが、全くルーツやカントリーのサウンドを演奏する機会には、少なくともプロのバンドに加入しレコーディングに関わるようになって以降からは経験していない男なのだ。繰り返しになってしまい恐縮だけど。
1970年代から80年代にかけてのPop/Rockの素直なメロディラインをベースにして行った先が、何時の時代にも誰かが演奏している、アメリカンサウンドの良心というべき、適度に大地の豊穣さを感じさせつつも分かり易いメロディに満ちたサウンドを完成させるに至ったと筆者は分析している。
であるから、カントリー的なアサイドは正直0%の含有量となっている。カントリーからロックに変遷して、最終的にルーツロックというカテゴリーに達したという手順を経ている音楽性ではないからだ。
Dave Aaronoffのバックボーンにカントリーが存在するかと言う事柄については、Daveの数少ないインタヴュー等からは判別が不可能である。が、影響はやはり多かれ少なかれ受けていることとは予想される。影響が即音楽性に反映しない場合もあるし、1作目と比較して相当ルーツロックに傾いてきているので、これから将来Daveの音楽がどう転ぶかは全く分からないことだし。
少なくとも、「The Devils’ In The Details」に於いてはルーツが大好物なリスナーを定量分満足させることが可能な柔らかくも懐かしいアーシーさが感じ取ることは出来るようになってきている。良い傾向だと思う。
しかも物凄いポップなソングメイキングのセンスがあり、現代的な要素も兼ね備えている。これが冒頭で、
「無名のGin Blossoms」と強調した所以である。
さて、「The Devils’ In The Details」であるけれど、これまでのDave Aaronoffのキャリアを反映するナンバーは少なくなっている。
Dave Aaronoffは1993年にボストンで結成されたスカコア/パンク/オルタナティヴという1990年代のロックメインストリームの典型である音楽を演奏していたグループ、The Shodsが1995年に「Here Come The Shods」をインディ・リリースした直後にセカンド・ギタリストとバックヴォーカリストとして参加している。
このShodsに近いバンドとしてはOff Springや初期のEverclear、Smash Mouthが挙げられるだろう。アダルト・ロック化した最近のAAAよりもよりノイジーで五月蝿いパンクノイズを追及していたバンドである。
The Shodsにギタリストとして在籍する傍ら、1985年からスカとパンクを演奏しつづけるボストンのヴェテラングループであるThe Mighty Mighty Bosstonesのツアーやアルバムに、こちらはキーボディストとしてサポート参加。
という経歴をソロ活動−自身がリーダーとなってバンドを結成する−以前に行ってきている。
双方のグループに於いて裏方のメンバーであり、ルーツのルの字も追求しておらず、しかも追求している音楽がメロディアスなサウンドにそれ程拘泥していないという点まで似通っている。
このパンク/スカ的な背景を匂わせるナンバーはそのエレメント純粋のみで構築されているナンバーとなると、皆無になってしまうだろう。2作目でかなりオルタナティヴとモダン・パンクのみに偏った以前に在籍していたバンドの活動をフォローする様式の曲は姿を消してしまったので。
よって、パンキッシュでAdult Alternativeと更にルーツ的な音楽性を併せ持つナンバーが現在に至るDave Aaronoffの活動を反映したものと捉えた場合を考えることにする。
特にパンクロックを感じるのは
#6『Don’t』
#9『Get Some Kicks』
#10『Get Yourself Together』
の3曲だろう。何れもロックンロールと太鼓判を捺せるトラックである。勿論、他にもロックナンバーは存在するのだが、他のナンバーはパンクロックという基準で考えるとより普遍的なPop/Rockという仕分けが相応しい曲が多いのでこの3曲とはポップさでは同等に近いがこの3曲とは別にして語った方が良い。
#6『Don’t』は非常にクラシカルなR&Bオールディズを感じさせると共に、このカントリーさが無色な作中で唯一カントリーロック的な雰囲気を纏い付かせている曲である。カントリーと言うよりもクラシカルなロカビリーと呼ぶほうが適切だと思う。2分少々という如何にもパンクナンバーというレングスであり、泥臭いギターがアップテンポなダンス・ワルツを能天気に、同時にパンキッシュなガチャガチャした調子で踏みしだく。
こういったアメリカンな根源音楽に対する胸襟を開いたナンバーは、デビューアルバムではあまり見られなかったので、ここにもDaveのアメリカンロックへの歩み寄りが見て取れる。
#9『Get Some Kicks』は、所謂1990年代型のパンクロックナンバーに分類出来るだろう。非常にキャッチーでありつつ、固めのギターサウンドを奔走させるスピーディさで強引にリズムを巻き込んでいく歌である。しかし、ただガチガチのオルタナ系パンクになっていないところが、筆者がDaveを成長株として認めた理由なのだ。
何と、このアルバムには大御所のオルガニスト・キーボーディストのAl Kooperがハモンドオルガンとウィルツァーピアノで全面的に参加しているのだ。これがDave Aaronoffの2枚目を購入した主な動機だったりもするのだが、それは置いておこう。
Al Kooperといえば、長年Bob Dylanのアルバムで鍵盤を弾いているし、Rolling Stones、Neil Diamond、Lynard Skynard、Tom PettyにJRick Nelsonという大物から、Honeydogsのような最近のバンドに至るまで30年以上に渡りピアノやオルガンを担当し、自らも10枚以上のメジャー作を発表している玄人オルガニストである。
そのAl Kooperが#9のパンクナンバーでも縦横無尽にハモンドのペダルを踏みまくり、鍵盤を押し付けている。このオルガンと人工的になり過ぎないギターが、このパンキッシュなチューンに尻の座った感覚を与えている。
#9は確かにモダンパンクの風味はあるのだが、同時にルーツィなエッジの主張もある曲となっているのだ。
#10『Get Yourself Together』は完全にタテノリでシェイキングなリズムが走り続けるパンキッシュさが目立つロックチューンであるけれども、初っ端から極彩色の音色を放出するAlのオルガンと、コロコロとローリングするJay Buckleyの間歇的に飛び込むピアノが全体をキャッチーなPop/Rockとして耳に届かせる役割をしている。無論、Daveが書いた曲のラインがキャッチーであるからアンサンブルが活きて来るのだが。
曲調の速遅を忙しく変更してあっという間に終ってしまう2分足らずのナンバーであるのは非常に食い足りない。もっとキーボードのソロを加えた豪快な変調ロックンロールの大作に昇華できうる曲なのに。
次に、デビュー当時から比較対象となっているElvis Costelloを代表とするブリティッシュ・イノベーションからの影響は、今作でもしっかりと息衝いている。
筆者的にはCostelloやNick Lowe的なパブ・ロックな英国的センスを感じるし、The JamやBig Country的なパンクだけでないサイケディリックでプログレッシヴなNew Waveの何処か捩れてガスが抜けたエキセントリックさも内包していると思う。
これらのアメリカンロックというよりも英国・大陸的な匂いを発散させているナンバーは
#3『Down The Drain』
#8『Trixie’s Playground』
#11『Between The Stones』
といったところ。
まず、チェロやヴァイオリン、そしてソフトなトランペットまでフューチャーされた#3『Down The Drain』だが、この曲は殆どノン・ロックインストゥルメントである。ベースやドラムは完全に脇役である。ギターにしても後半で刺身のツマ程度に出番があるだけ。
いわば、前衛的なストリングスナンバーというべきか。ルーツというか大陸的な哀愁を持つメロディが淡々とストリングスのアクースティックな弦によって紡がれる様は、この曲の前後がバリバリの正統派ルーツロックでありポップであるがために一層異色さを醸し出している。こういう点は完全に英国音楽への愛着を感じさせる。特に後半でソロを受け持つジンワリと滲んだようなムーディ・トランペットはナイト・ミュージックという名称が似合い過ぎる音色を溶け出している。
#8『Trixie’s Playground』は玩具のピアノやトライアングル等のパーカッションだけをキラキラと鳴らす1分未満のインストゥルメンタル曲だが、こういう小技は良い意味で小細工が苦手なアメリカンルーツ系のアーティストには出来そうもない演出だ。とてもユニークである。
#11『Between The Stones』はAlの弾くウィルツァーとR&B風なリズムピアノがマイナー調子のワルツを奏でる英国的ポップス。特にコーラスの入れ方やエコーを掛けたヴォーカル処理はモロにJohn Lennon風のBeatlesを連想させてくれる。
こういったブリティッシュ・イノベーションの影響とアメリカンロック、ルーツサウンドが一層融合を進め、Nick LoweやJohn Hiattの初期に見られるパブロックに少々ルーツを濃くした要素が、今作でのDave Aaronoffのルーツへの向かい合いと思うのだが、
#7『World Of Her Own』
#12『Thank You』
の2曲が英国と米国の中間的なルーツロック風で、Daveのアップデートな変化の一面を伝えていると考えている。
#7『World Of Her Own』は何となく1st作の頃のCounting Crowsを思わせるサイケディリックなうねりと、The Band風のザックリしたメロディの深さがストリングスを含めた牧歌的な風味に複雑に溶けている。
かなり土の匂いのする曲なのだが、それ程にアーシーさが目立たないのは、Counting Crowsに似ている点が見出せそうだ。このナンバーでもパーカッションが効果的に刻まれている。物悲しい弦楽器やピアノの音と、バタバタしたドラムやパーカッションのコントラストが対照的。
#12『Thank You』はアクースティックなアレンジを最初から大っぴらに表明しているDaveにしては珍しいナンバーである。しかし、徐々にピアノやエレキ楽器が肉付けされていって、程好いロックの躍動感を加えたバラードに育っていく。この甘くて、酸っぱい西海岸アクースティックサウンドを思わせるナンバーは、このアルバム中最も正統派な展開をするバラードである。こちらは英国の影響は#7とは異なりかなり少ない。
というよりも殆どブリティッシュ・インフルエンスを感じさせない気持ちの良いルーツ加減を含んだナンバーとなっている。
そして、グループで裏方メンバーをやっていた頃には見出すことの出来なかったポップな曲創りの才能が遺憾なく発揮されているのが、残りのナンバーだ。
有り余る程のキャッチーな性質はデビューアルバムでも提示されていたが、今回はそのポップな柱を装飾していたオルタナティヴやモダンパンクという不純物が全部とはいえないが、過剰にならない程度に抜けているため、非常にアメリカンなPop/Rockとしてのストライクど真ん中を突っ走る曲が多くなった。
#1『Alisa O’Neal』
#2『All The Gary Details』
#4『Clever Girl』
#5『Left For Dead』
と前半に全力を投入している趣が無きにしも非ずだが、こういった一歩間違うと単なるPower Popにしかならないナンバーだけが終始一貫するアルバムになるよりも、「The Devils’In The Details」の多彩さを活かすために、このウルトラキャッチーな曲だけが支配するアルバムにならなくて良かったかもしれない。
・・・・といいつつもう少し後半にこのグループに属する曲は欲しかったとは思うけど・・・・。
まず、#1『Alisa O’Neal』。ひとこと、2分足らずで終焉するのは勿体無い最高のPop/Rockであり、American Rockであり、Roots Rock。
兎に角、快感しかないナチュラルにエッジの効いたギター。Al Kooperの前のめりにダッシュするオルガン。元気なコーラス。全体をふんわりと包むルーツ・フィーリング。
完璧な2分間ロックトラックだ。
#2『All The Gary Details』は#1程にはマンモスキャッチーで即効性のあるスピード・オブ・サウンドは押し寄せてこないが、ドリーミーにラインを装飾するハモンドB3、青空に溶け出すような美しいピアノ、1970年代のシーンを彷彿とさせるコーストロック風のコーラスワーク。
全般をルーツィとシティさの色合い両方に染め上げるハモンドの音色は特にそのポップなコードランニングと共に脳裏に焼き付けば二度と離れない吸引力がある。
Power PopプラスRoots Pop時々Classic Rockという公式が当て嵌まるナンバーであると思う。この出だし2曲で完全に圧倒されてしまうリスナーは多いに違いない。
#4『Clever Girl』も悶え苦しむくらいに甘いラインが心を捕らえて離さないPop/Rockの王道ナンバー。Al KooperとThe Shodsの鍵盤弾きであるJay Buckleyのダブルキーボードがこのアルバム最大の魅力であることはこういった軽快でコマーシャルなチューンを聴けば百人中全員が理解できるだろう。
ギタリストである以前に、鍵盤弾きであるDave Aaronoffがどれくらいキーボードの使い方に長けているか、はっきりと分かると言うものだ。
しかも、上品に土の香りが漂うギターの音色が加わり、やや青臭いDave Aaronoffのヴォーカルが加われば、これは無敵である。
そして、ややAlternativeの風味を残しているけれど、それ以上にザックリしたルーツの感触を有しているハードなロックナンバーである#5『Left For Dead』を聴くと、どうして最近のメジャーで受けている若手ロックバンドはこのようなアメリカンロックの伝統を消化して継承している曲が表現できないのか不思議に思ったりするのである。
こういった主力級の(?)ナンバーはGin Blossoms以上の即効性があるのは間違いない。ヴォーカルさえもう少し独創的ならGin Blossomsを凌駕していると思うのだが。
1995年からの5年間をバンドのいちギタリストとして、それ以上の期間をサポート鍵盤弾きとして過ごしてきたソングライターの才能がようようにして開花し始めたようだ。
Daveは語る。
「確かに僕はShodsというバンドで重要な役割を担っていたと思うよ。でもそれ以上その受け持ちを続ける気にはなれなくなっていた。僕はソングライターになりたかったんだ。でもバンドにはKevin Stevensonというライターがいたからね。彼は素晴らしいソングライターだったから、僕が自分で作った歌は殆どバンドで取り上げられなかった。」
1999年にDave AaronoffはThe Shodsを脱退する。しかし、彼の脱退後、The Shodsは翌年にアルバムを1枚放った後に解散する。解散後に再度メンバーを集めて再スタートしたが、結局活動は続かなかった。そのメンバーのひとりはThe DetailsのピアニストJay Buckleyであるのも面白い。
「僕が脱退後にShodsが解散した理由。う〜ん、正確には何とも言えないよ。僕が原因であるとは思えないけど、ミュージシャンは時たま、ライヴに出て人前で演奏したくなくなることがある。これが続くとどうにも隠せない問題が出てくるものさ。」
解散劇に巻き込まれなかったDave Aaronoffは自分はそのようなことはなく、兎に角バンド活動をしたいという意向を隠さない。
「時々、僕は理想とするバンドのようになりたいと言う本能的欲求と闘っている。僕はCostelloとThe Jamに溺れて追いかけをやりたい。けれども、誰かの歌の影響をあからさまに似せるだけでは駄目だから、そういった曲を書いたら即座に捨てるようにしているし、かなり捨ててきた。(笑)影響を受けるのは良い事だけれど、それに圧倒されてはいけないね。」
というオリジナリティをあくまでも大切にし、且つ良い先達の音楽を視野に入れている限り、Dave Aaronoffはもっと大きくなる才能の持ち主だと思っている。是非今後にも期待したい。
機会があれば、デビュー作と今作だけでなく、The Shodsや、2001年にDaveがベースと鍵盤とヴォーカルで参加したオルタナティヴ/パンクバンドであるKickoversの「Osaka」やThe Mighty Mighty Bosstonesのアルバムも聴いてみてはどうだろう。あくまでも、Daveが正常進化をしていることを知るためなので、方向性的には面白くないから余分な出費になるだけだが。(苦笑) (2003.1.25.)
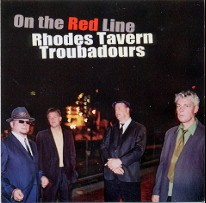 On The Red Line
On The Red Line
/ Rhodes Tavern Troubadours (2002)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Bar band ★★★★ You Can Listen From Here
The Rhodes Tavern Troubadoursという非常に長く、早口で繰り返すと舌を噛みそうな名前のバンドのデビューアルバムが2002年の秋に手元に届いた。
CDの表面にはRhodes Tavern Troubadoursと表記されているのだが、インナーや上に貼った試聴リンクからジャンプ出来るオフィシャル・ホームページではThe Rhodes Tavern Troubadoursと定冠詞が頭にくっ付いている。
本レヴューではCDの表や背表紙に従って、Theを抜いた形で記すことにするので、ご了承願いたい。・・・・とはいえ、恐らく誰も気にはしないと思うけれど。
このRhodes Tavern Troubadoursという、日常的にはあまり馴染みの無い単語の羅列をバンド名にしたグループの名前の由来から今回は語ることにしたい。
固有名詞であるRhodesは兎も角として、TavernとTroubadourに関しては少々厚目の英和辞典を引いてみれば意味は即座に把握できる。
Tavernは酒場とか宿屋という、やや古風な趣を表わす時や裏街道的なうらぶれた風景を表現する時に使われる単語。
Troubadourは中世欧州の叙情詩人のことを指す。まあ、吟遊詩人と考えれば現代的なイメージに近いと思う。
で、実際のRhodes Tavernとは、1799年に立てられたバンドの拠点であるワシントンD.C.最古のキャバレーの名前から引用されている。1801年には酒場兼宿屋に変わり、その後ワシントンD.C.初の公会堂となる。南北戦争の戦火からも生き残り、後に株式証券取引場や新聞記者クラブの建物として使用される。
しかし、1984年には老朽化により解体され取り壊される。
以上のように、歴史はそれなり以上にあったのに保存されるでもなく消滅したワシントン府の庶民的な伝説を背負ってきた建築物に敬意を払い、また貴重な建築物を取り壊してしまった政治組織への抵抗と皮肉を込めて、バンドはその名前を、Rhodes Tavern Troubadoursとしていることのこと。
日本語に訳せば、「ローデス酒場の吟遊詩人たち」となるが、Rhodes Tavern Troubadours(以下、RTTs)の音楽性を鑑みると、叙情詩人達というよりも寧ろ「ローデス酒場で屯している放浪者」と解釈した方がピッタリくるのだが。
この命名から推し量れるように、RTTsはワシントンD.C.を根城にして活動する一団である。
ジャケットの写真を眺めれば、即理解できるだろうけど、バンドとしてのアルバム発表はこの「On TheRed Line」が初めてになるとはいえ、20代〜30代の若いプレイヤー達で構成されたグループではない。
ジャケットの向かって右端のダンディなロマンスグレイなJack O’Dellは確か1940年代後半の生まれだったと思うし、ベーシスト兼ヴォーカルのMark Nooneは1970年代から中堅クラスのバンドのヴォーカリストとして広範な活動をしているヴェテランである。
他の2名もワシントンエリアでは1980年代から演奏をしているミュージシャンである。
つまり、このRTTsというバンドはこれまでに20年以上のキャリアがある熟年ミュージシャンが集まって形成されたローカルだが一種のスーパーグループなのである。とはいえ、日本での知名度は絶望的に低いのだが。本国でもそれなりのステータスがあるのはメンバーのうち2名だろう。
Dave Chappell (Guitars,Vocals) , Jake Flack (Guitars,Vocals) , Mark Noone (Bass,Vocals)
Jack O’Dell (Drums,Vocals)
以上の4ピースがRTTsのメンバーである。
この中で最も著名なのはJack O’Dellだろう。1960年代に発足したカントリーロック/ロックンロールのバンドであるCommander Cody & His Lost Planet Airmenに在籍し、1986年からはワシントンD.C.にてToo Much Funを結成し現在も精力的に活動を続けるBill Kirchen。
このBill Kirchen & Too Much FunのドラマーがJack O’Dellである。殆どのアルバムが中堅インディレーベルから発売されているため日本での知名度は低いが、本国ではゴールドディスクもカントリーチャート中心に獲得しているバンドである。
JackはBill Kirchenの殆どのアルバムに参加し、ドラムだけでなくリードヴォーカルまで歌ったこともある。この繋がりから、Bill Kirchenが#12『DC’s The Telecaster Town』でセカンドギターとして参加もしていたりする。
更に、2001年にワシントン周辺のルーツ、カントリーロックのミュージシャンを集めてバンドを結成したプロジェクトであるThe TwangbangersのアルバムにもドラムとヴォーカルでBillと一緒に参加していたりする。
Jack O’Dellは曲は殆ど書いていないが、実質バンドの最長老であり、リーダー格であるようだ。
次に名前が売れているのはベースのMark Noone。1976年にワシントンD.C.にて結成されたパンク/ガレージロックのバンドであるSlickee Boysが1977年にレコードデビューする時、前任のヴォーカリストが脱退したため代わりにメンバーにリードヴォーカリストとして加入し、1989年の解散アルバムまでバンドのフロントマンを務めていた。
このSlickee Boysは今は無きルーツロック系のレーベルであるTwin/Toneに在籍していたので、1980年代に南部ロックやパンクルーツを追いかけていたファンにはもしかしたら知っている人が存在するかもしれない。
また、1997年にはRuthie Logsdonが結成したカントリー/カントリーロックバンドであるRuthie & Wranglersにベーシスト兼バックヴォーカリスト、そしてプロデューサーとしてもバンドに加わり3枚のアルバムに関わっている。このカントリーバンドは、ワシントンではアルバムを出す毎にアワードを受けるくらい人気のあるバンドであるそうな。
残りの2名のうち、Jack Flackは筆者は知っているが、一般のリスナーは殆ど聞いた事すらない名前だろう。
1980年代後半にテキサス州はオースティンを中心に活動していたルーツハードなロックバンド、The Neptunesのギタリストでありメインのソングライターだったのが、Jack Flackである。Joe Elyの1988年のアルバムにも姿を見せている。
このThe Neptunesが唯一発売したアルバム「Nocturnal Habit」はかなり面白いルーツなPop/Rockでハードドライヴィンなサザンロックが詰まったアルバムなので何処かで発見したら迷わず確保することをお薦めしておく。
また、ルーツとオルタナティヴ音楽の微妙な境界線を行くバンドを扱っていたFreedom Recordsから1997年にデビューしたニューオリンズのThousand Dollors Carというバンドにもギタリスト兼ソングライター兼ヴォーカリストとしてクレジットされていて、これまでのキャリアの多くを南部エリアで活動していたミュージシャンである。
そして最後にDave Chappellだが、ハワイアンとカントリーミュージックを混合したユニークなバンドであるHula Monstersに参加していた他にもワシントンD.C.のローカルバンドを幾つも渡り歩いていたギタリストである。ちなみにHula MonstersにはMark Nooneもウクレレでゲスト参加していたりもする。
このような70年代から80年代にかけて、そこそこメジャーまたはマイナーシーン中心に活動してきた4人のソングライターとミュージシャンが集まって結成されたバンドがRhodes Tavern Troubadoursである。
レコードデビューは2001年の秋。
主に首都ワシントン周辺で活動している米国東海岸北部のバンドを中心としてリリースされたルーツロックとカントリーロックのコンピレーションアルバム「Americana Motel」に、RTTsは#17として『Then You Can Tell Me Goodbye』を提供。
他にはLast Train HomeやLittle Pinkといったワシントンのバンドが参加している面白いコンピレーション作だ。
『Then You Can Tell Me Goodbye』がかなりあっけらかんとしたポップなルーツナンバーであったので、それ以来RTTsに注目してきたが、2002年に入ってOHPに2曲の試聴サンプルがアップロードされ、更に購入意欲が湧き、発売後即座に入手したのが、この「On The Red Line」である。
このアルバムで面白いのは、発売元のレーベルが専業のレコードレーベルではないこと。Route11というレーベルを名乗っているが、実はこの会社、ポテトチップスの販売で成長した会社であり、現在もポテトチップスを東海岸を中心に23州で販売している。
つまり、専門音楽レーベルではなく、所謂企業の多角化によって生まれた部門から発売されたアルバムなのだ。
そのRoute11のホームページでは
“The Rhodes Tavern Troubadours are Washington,D.C’'s premiere roots-rockin’,foot-stompin’,power-popping musical combo”
という端的だが的を得た紹介をされている。
しかし、笑えるのはこの点ではなく、RTTsがアルバム最後のナンバーで#14『Route 11 Chips』というナンバーを入れてスポンサーを宣伝していることだ。
ベタベタのオールド・カントリー曲であり、1分もしないで終ってしまう、要するに「ルート11のポテトチップスは最高。食べようぜ〜。」というCM曲だ。
笑ってはいけないかもしれないが、色々とビジネスには事情があるものだ、と思ってやはり苦笑してしまう。しかもこの#14だけはRoute11のHPで聴けたりするのだ。ローカル放送ではCMソングになっている可能性もありそう。
その変化球的な#14を除けば、残り13曲は至って正統派のバーバンド・ロックンロール。
非常にラフで、隙間の多いとネガティヴではない意味でのルーズさが心地良い。
つまりはルーズと同居した滑らかなスムーズさが存在するグルーヴィな音を出しているバンドなのだ。
隙間が多いけれど、かなりスルリとした軽快さがあるというのは、南部に多く見られる力技のサザンロックとは少々異なるし、スワンプロックのように音が緊張感に支配されていないユルさが特徴の音とも違う。
メロディとしてはフックが鋭角的であり、然れども硬質的な鋭さではなく、触れて暖かい有機的なサウンドが聴けるのだ。更に、ルーツサウンドとはいえ、どれか一極に特化するのではなく、シチューの王様、ごった煮的に多彩なバックグラウンドが音出しに反映されているのも見て取れる。
Alt-Country、Blues、R&B、Roots Rock、Country Rock、と兎に角アメリカン・ルーツの係累に属する要素が雑多に詰め込まれている。
大分類では敢えてAlt-Countryとしているが、それ程強烈にCountry RockやAlt-Countryがリードを得ているということもない。あくまでも便宜上の措置と考えて頂くと良い。
これは、4人のライターがこれまでのキャリアで培ってきた音楽性がそれぞれ出過ぎた自己主張をせずに、適度に仲良く同居しているために、ルーツロックとして中道的な音楽が完成したのだと思う。
初めて、このフルレングスアルバムを聴いた時、即座に連想したのはNRBQである。
しかも、最近の老成したゆとりサウンドを売りにしたNRBQではなく、1970年代中盤から1980年代初頭の頃の最もバンドとして脂の乗っていた時代のNRBQをだ。
所謂バーバンドのポジティヴな意味合いのいい加減さと、熱いロックンロール精神が同居しておりながら、丸みを帯びたサウンドが大勢を支配しているタイプ。
ライヴ感覚全開というところまでのソリッドさを敢えて見せつけずに、スタジオ録音盤の技術が活用できるところはしっかりと活用しているライヴとスタジオ演奏の双方を満足させるパフォーマンス。
決してミュージシャンとしての履歴は浅くないのに、なまじ大御所とならなかった位置に定着し続けていた故に、スレ過ぎてもいないし、ロックンロールの大切なパワーを失っていない、非常に純粋なバーロックのバンド。
これがRhodes Tavern Troubadoursであると考えている。
仮定の話だが、NRBQが1990年代にデビューしていたとしたら、RTTsと同じようなアルバムを作成したのではないかと思わせるくらいのポップでルーツなローカル色豊かなグループである。
RTTsの特徴としては、全員がソングライターであること。またメンバー全員がソングライティングをほぼ単独で行っていること。Jack O’Dellだけはクレジットされている2曲でJakeとDaveそれぞれと共作しているが、残りは全てシングル・ライティングだ。
内訳はJakeが7曲、Markが4曲、Daveが1曲、Jackの共同作が2曲。とJake Flackが書く割合が共作を含めずとも5割という構成だ。
Jackはルーツ系ベッタリというよりはハードロック色の強いThe NeptunesやオルタナティヴっぽいThousand Dollors Carに属してきたが、ここではハードやヘヴィのサウンドに走ることなく、バランスのとれた多様なPop/Rockを書いている。もっとも、他のライターも同じくして、自分のキャリアだけを反映したような狭いレンジで収まる単一色のライティングはしていない。
結果、全体としてヴァライエティに富んだルーツロックアルバムとなっている。
★ポップでルーツフィーリングが一杯の曲★
#1『Red Line Train』はRTTsのポップでグルーヴィな側面を端的に3分間で焼き付けた感じの良質なポップソングとなっている。Mark Nooneの飾らないヴォーカルが如何にもバーで演奏されそうなメロディに乗って行く。またリードヴォーカルの経験豊富な残りのメンバーが追従するコーラスはSister Hazelのような若い世代のバンドに負けない張りがある。
#5『My New Hero』はとても単調なコードをパンチィなリズムで繰り返すPop/Rockであり、しかもフレーズもコーラスもインターパートまで全く同じパターンをリフレインする。そしてギターのソロがかなり羽目を外して弾かれる。後半はファーストヴァースにコーラス隊がプラスされるという、全体を通してみるとそれ程際立った曲ではないのだが、キャッチーさとしては一流のポップナンバーだ。
#6『Cut Out Romeo』はアルバムの中で最もフンワリした土臭さがあるナンバーであり、同時にポップでロックでもある相当に完成度の高いナンバーである。あまり目立たない曲なのだが、ミディアムテンポから微妙にスピードアップするコーラスの部分やロックのエッジが効いたギターリフのザクザクした感触、メリハリのある展開等、このアルバムではオープニング2曲と並んでシングル候補に挙がる曲だと思う。筆者のお気に入りでもある。
★バーバンド・ロックンロールが聴ける曲★
#2『Eye To Eye』ではハードで豪快なリズムが刻まれるストレートでポップなロックナンバーが先制攻撃を加えてくれる。ブンブンと唸るベースやギュンギュンと吠えるギターが軽快なメロディをややアンバランスに彩るが、このロックンロールの速さが、NRBQが次第に失っている精神であると感じている。
やはり、バーバンドはロックンロールをやって貰いたいし、ノリの良いパーティロックは本来酒と煙草の支配する空間では必須だった筈だし。
#4『Earl Weaver』はロックンロールとしてスピーディという訳ではないのだが、非常にジャンピーでホンキィなロックの楽しさが自由に表現されている。また、「E.A.R.L.ARIES!!」の大合唱が最高に印象的だ。
#8『Lord Sakes』は恐らくJack O’Dellがリードヴォーカルを担当しているだろう。終始シャウトで貫かれるサザン・ヘヴィロックの重さが圧し掛かってくるようなハードチューン。しかし、不快感というよりも予想外の馬力に圧倒されるという感想を抱くナンバーだ。全体にリラックスしただけではなく、このような締まったタイトなノイズナンバーも創作可能なバンドなのだ。
★R&Bやロカビリーのリズムがクラシカルな曲★
#7『Home Wrecker』は非常に明るいロッキン・ブルース。R&Bのアーバンテンポとブルースの泥臭さが交互に出現するようなラフで自由なナンバーだ。
#10『Gal For Me』は完全にChuck BerryやBo Daddyが嘗てロカビリーやR&Bロックとしてヒットさせたオールドタイムズ・ロックンロールを思わせるR&Bロックソング。50年前の時代のラジオを聞くような錯覚に陥るくらいな曲。
#11『Not Enough Of You』はR&Bベースのロックンロールではなく、更にコテコテのR&Bナンバー。粘着するグニャグニャしたリズムがR&B特有の硬いアレンジで暴れる。中盤から更にバラバラした展開になるのは、やはりRTTsがロックバンドの証拠だろう。
#12『DC’s Telecaster Town』もオールディズを21世紀に転送した如く古臭いR&Bのダンサブルなリズムが印象的なナンバー。しかも酒場バンドのア・ド・リブを一発録音したようなダブルベースやエアブラシの音はジャズの影響も濃密に表明している。
★レイドバックソングのノンビリを聴く曲★
#3『Games』はとても和める、アクースティックなユルイ手触りが気持ち良いナンバー。こういう殆ど弦楽器だけで進むシンプルなスローナンバーは印象が薄くなりがちだけど、RTTsのチアフルなリズムメイキングによって、かなりじっくりと聴けるアレンジになっている。
#9『.com Guy』はカントリーの色合いが希薄だがレイドバック感覚が全面に漂うナンバー。カントリーロックというよりも、レイドバックロックという表現の方が当て嵌まりそうな曲だ。ソロパートでギターが泣いてくれるが、この手のバラードは少ないので、侘しげなギターが聴けるのはこのアルバムでは#9だけ。その意味では貴重である。
また、#13『Eastwood』は唯一のインストゥルメンタルナンバー。完全なブルースである。しかもノン・ヴォーカルであり、お気楽極楽ナンバーが多いRTTsにあってはかなり悲哀の漂う、酒場ソングのもう1つの定番とはいえ、パーティサウンドにはならない方の曲。
これを敢えてインストナンバーにしてきたところが、演出として巧みだと思う。基本が元気ノリノリなRTTsのヴォーカル・ワークでは、こういったナンバーは少々浮いてしまいそうだから。ヴォーカルレスにすれば、与えるインパクトはそれなりに大きいし、新鮮な気分で聴けるだろうし。
以上、キラーシングルで勝負するよりも、全体の雰囲気と暖かいアレンジとラフなロックサウンドを混在させることで聴き飽きるということをさせない、ヴェテラン4人組のアルバムを紹介した。
完全にキーボードレスであり、ゲストもギターが2名で2曲というシンプルなバンド演奏オリエンテッドさも、このバンドではプラスに働いているようだ。
しかし、出来ればホンキィトンクなピアノやタテノリを加速するようなオルガンを入れると、更にバンドの音が引き立つと思うのだ。次回は是非、ゲストでも良いので鍵盤弾きを加えた酒場音楽に浸らせて貰いたい。 (2003.2.1.)
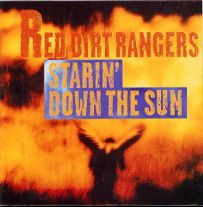 Starin’ Down The Sun / Red Dirt Rangers (2002)
Starin’ Down The Sun / Red Dirt Rangers (2002)
Roots ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Alt-Country&Bluegrass ★★★★★
You Can Listen From Here
誰もが小学生の頃、音楽の時間に歌ったと思われる、『赤い河の谷間』。
♪「サボテンの花咲いてる〜。砂と岩の西部〜」♪(当時は独立13州より西は全部西部だったことが偲ばれる。)
原題を『Red River Valley』というアメリカ民謡である。この歌は中々好きだったりする。全般に筆者は民謡は大好きだし、童謡も同様。(寒)
まあ、全く知らないという人はいないくらい日本でもポピュラーな民謡だ。
しかし、原詩は日本の歌詞とは全く全然、徹底的に違うのだが。オリジナルを初めて聞いた時は、思わず笑ってしまいそうになったが、そのセンチメンタルな歌詞にはジーンと来てしまい、非常に複雑な感情で聞き耳を立てたことがついこの間のようである。
学校ではあまり歌われる機会の無い、歌詞の3番くらいになると少々シンクロする箇所もあるけれど、原曲はラヴ・ソングであるから。
そういう余談はこのくらいにしておく。
詩中に登場するRed Riverというのは、テキサスとオクラホマ州の州境に跨るランドマークでもあり、大河ミシシッピ川の支流ともなっている。通称、The Redと呼ばれる河だ。
と、いきなり懐かしい「みんなのうた」ワールド的お話から入ったのには、実は大した理由はなかったりする。
語源自体は定かでないが、オクラホマ、アーカンソー、テネシーといったアメリカ中南部のステップ性気候に属し、草原と岩石砂漠が混在する地域で発展したトラッドロック/カントリーロックをベースにしたロックミュージックをRed Dirt Musicと呼ぶことがある。海外のレヴューにも時たま発見できる地域色が強い音楽ジャンルだ。
河の名前がRed Riverとなるくらいだから、赤茶けた地形が拡がる土地であることは想像可能だし、実際に写真や映像で米国内陸部の乾燥帯のランドスケープは何処からでも閲覧することはできる。
そういう土地柄を土壌に培われたミュージックだから、Red Dirtという修飾語を伴った音楽という呼び名が付いたのだろうと事単純に推察しているが、詳細は不明である。間違いがあれば指摘して戴きたい。
が、The Red River等という地名が付くのだから、風景は何となく想像はできる。カリフォルニアやアリゾナ州の人口希薄地面積の大半を占めている岩石砂漠とそう風景的に大差はないと思っているのだが。
そんな名前のRed Dirt Musicが存在するロックミュージックの生産地であるオクラホマ州で活動するバンドが、今回筆をとったRed Dirt Rangersである。
Rangerという単語には、軍隊のレンジャー部隊というタームから推し量れるように、特殊部隊隊員という意味から、米国英語の騎兵隊、森林警備隊というドメスティックな範囲までを指す。
更に、Red Dirtという如何にも土や泥の感触が生で掴める語感を入れたバンドとなるともうルーツロックやカントリーロック以外のミュージシャンには早々は使われないバンド名だと思う。
実際に、名前の響きから来る印象を裏切らず、Red Dirt Rangersは一般にいうカントリーやルーツミュージックに属する集団である。
だが、筆者の貧困で特定のカラーに染まったイメージではRangerという単語は、レンジャー部隊やある種のロールプレイングゲームの定番ジョブであるレンジャー(野外活動専門家)の、アグレッシヴでファイティングライクというフィルターが掛かってしまっているので、どうしてもレンジャーというと攻撃的なサウンドを有するロックバンドと考えてしまうのだ。
この場合は、ダートでマッディなサザンロックバンドというイメージでRangerという語彙の入ったバンドをついつい見てしまうということである。また、HRバンドであるNight Rangerのハードでポップなアリーナサウンドの分厚さもこの曲がったインプレッションに一役買っていると自己分析。
・・・・我ながらRanger=ハードドライヴなロックバンドというイメージが浮かんでしまうのは如何ともし難いとはいえ、情けないことである。閑話休題。
しかし、お世辞にもRed Dirt Rangersは豪快でハードでガンガンとワイルドさを叩き付けて来る類のロックンロールな音を創作するバンドではない。
Red Dirtという土と埃と乾いた空気が眼を瞑ると瞼に浮かんできそうなサウンドを届けてくれるバンドであるのは間違いないが、ロックンロールを馬力と腕力で引き倒してしばき倒して、どつき廻すというタイプのグループとは全然毛色が異なっている。
まあ、筆者の持つRangerのイメージがあまりにも低俗なのが原因なのだろうが、Red Dirt Rangersの音楽性を列挙するなら、
●和み系のCountry Rock。
●キャッチーで明るいAlt-Country。
●草の根的なローカル臭漂うRoots Pop/Rock。
●ブルーグラスやオクラホマ・フォークの香りが振り掛けられたTrad Rock。
●牧歌的でゴスペルサウンドの影響が顕著なSouthern Country。
という感じである。よって、Red Dirt Rangersの音楽性を踏まえると、この場合のRangerとは、単語根源の意味である、放浪者や探索者(無目的な)、という解釈をするのが適当だろう。
乾燥地帯を放浪する一団−まさに、ツアーであちこちを巡るロックバンドには似合いの名前である。
基本的には、Rock n Rollという爆走一直線を槍のように扱くサウンドではなく、Country、Bluegrass、Gospel、Traditionalといったより田舎臭く、ポピュラー音楽産業に染まっていない地方サウンドが音の芯を走っていると考えるのが適切だ。
しかし、良い意味でRed Dirt Rangersはブルーグラスやトラッドミュージックな野暮ったさに凝集することなく、次第にポップミュージックとの融合を果たすことに成功しつつあるように見える。
ロックやポップというよりもローカルなテイストが大きな顔をする音楽は、その手の嗜好のリスナーには堪らない渋さがあるということは理解できるが、どうにもPop/Rockが副次的な要素となっているジャンルの音は筆者の守備範囲を逸脱してしまい、食指が殆ど伸びない。
であるから、Red Dirt Rangersが漸くにしてAlt-CountryやRoots Rockのグループと堂々と述べれるようになったこの「Starin’ Down The Sun」をこれまでで最も高く評価したい。
上の様に書くと、どうにもこれまでのRed Dirt RangersはAlt-CountryやRoots Rockのバンドとは異なる存在であったように聞こえるかもしれない。これは半分正解、半分近く正解というところに落ち着く。
このオクラホマネイティヴなメンバーだけでなく、周辺の州からや遠方から流れ着いてきたミュージシャンも含めて構成されている放浪者=Rangerの集団は、これまでに今作を含めて5枚のアルバムを世に出している。
結成は1990年前後であり、最初はバンドの核になる数人が集まってカントリーやオクラホマ・グラスを演奏するローカルバンドだったようだ。
そのうち、現在廃盤となっている1993年発表の「Red Dirt」は完全にオクラホマ・フォークであるブルーグラスとお隣のテキサス州の田舎サウンドである、テキサス・スゥインギングを基本にしたそのまんまカントリーアルバムである。
また翌年に、チャイルド・レコード形式を取った「Blue Shoe」というアルバムをリリースしている―ここからオフィシャルサイトで購入可能だ―のだが、これまた、
『良い子のかんとりい、ABCだよ〜ん』(何やそら?)
というお子様向けのカントリー作品である。まあCountry Musicが米国における童謡・民謡の末に連なる性格を帯びた音楽の1つである以上、チャイルド・チャートにはカントリー系のアーティストが殆どという実情を把握していなくても、カントリー=子供のための音楽という図式は理解できる筈。
これまた、一部の紳士淑女からは堕落の音楽と見なされているロックミュージックからは一線を引いた、上層教育向けの作品。一応、アルバムには「大人から子供まで楽しめるさ」という副題は付いているのだけれど。
この辺でバンドについても触れておこう。
こうやってブルーグラス/カントリー草の根バンドとして、1990年前後にデビューした頃から変わらないメンバーが、最近までバンドの中核をなしていた4名のミュージシャンである。本来は現在も、と書きたいところなのだが、ベーシストにして最もカントリー的な間の抜けたヴォーカリストだったBob Wilesがこの「Starin’Down The Sun」を発表後にバンドから脱退している。
もっとも、初期からこっち、一番カントリー的なグラスソングを歌っていたのがBobなので彼の脱退は筆者にとっては残念というか、不謹慎だが歓迎したい。
という個人的感想は後回しにして、バンドの核は4名。
Brad Piccolo (Vocals,Guitar) , Ben Han (Lead Guitar,Vocals)
John Cooper (Vocals,Mandolin,Percussion) , Bob Wiles (Vocals,Bass)
という3名のリードヴォーカリストにドラムやオルガン、ピアノ、バンジョー、フィドル、ホーンといったゲストプレイヤーが加わって毎回のレコーディングをこなしている。
最新作ではJim KarsteinというドラマーとRocky Friscoというピアニストが準メンバー扱いとしてクレジットされているが、Jimはこの後バンドに正式なドラマーとして加わっている。
同時に新ベーシストのJamie Kelleyとフィドル及びペダルスティール担当のRandy Crouchが加わり、2003年現在は6名編成の大所帯となっている。
この放浪者たち、は核の弦楽器持ちを中心にアルバム毎でメンバーを必要に応じて加えていく形を取っていたので、これまでメンバーは流動的だったが、最近はしっかりとした正式メンバーを募り始めたようだ。これは良い傾向であるとは思うが、ピアノかオルガン弾きも何故加えないのかと問い詰めたいが。
現在の状況はかくの如しとして、Red Dirt Rangersは1996年からレコーディングバンドとして始動を本格的に開始するようになる。
1996年には又も自主リリースながら「Oklahoma Territory」を。3年後の1999年に「Rangers Command」を3年置いて発売する。「Oklahoma Territory」は完全なカントリーアルバムで、そこに少々ロックの色が付いている程度のオクラホマ・フォークだった。
しかし、1999年の「Rangers Command」からCountry Rockとしてのキャッチーでスムーズなロックのノリを身に付けるようになり、かなり期待を持てるバンドになってきたことを印象付けてくれた。
そして、その期待を3年の間引っ張ってくれたのが、本作「Starin’Down The Sun」ということになる。
予想を裏切らず、相当にポップミュージックとロックンロールという娯楽音楽への歩み寄りが顕著に出ている作品であるので実に嬉しかったが、それと同時にしっかりと南部エリアのフォークソングやトラッドミュージックの匂いも同時に濃厚に満たしているところに拍手を贈りたいのである。
ただ、単純にポップ化する(それはそれで筆者としては問題ないけれども、ルーツサウンドである限り)道を辿ったのではなく、テックス・メックス、オクラホマ・トラッド、カントリー、レゲエ、ケイジャン、スワンプという周辺のエリアの音楽をそれぞれクドクならない程度にロックビートに取り込んでいる。
無論、上記したようにロックンロールアルバムであるが、未だ心棒は土着カントリーであり、フォークロアな雰囲気の漂う地方色豊かな根源音楽であるが、このレヴェルに達すればロックサウンドとして普通に歓迎される程度には成長していると思う。
曲の大半でクレジットされているのが、リズムギタリストにしてヴォーカリストのBrad Piccoloである。これにJim Cooper等が続いている。また、同じオクラホマ出身で現在はオースティンで活躍しているフォーク系ルーツシンガーのJimmy LaFaveの盟友であるライターのBob Childersがデビュー時からのスタンスを継承し、ソングライターとして4分の1の曲に手を貸している。
最新作の特徴として、あからさまなブルーグラスやカントリー&カントリーというトラックが減っているということだ。裏返せばAlt Country、Pop/Rock化が進行したということだけれど。勿論、ルーツロックやカントリーロックを普段聴き慣れないリスナーからすれば、殆どがカントリーとして耳に入ってくるかもしれないことはお断りしておくが。
ベタベタなカントリーとしてはメンバー全員共同作の#9『Come On Down』だろう。ペダルスティールが、フィドルが、バンジョーが、パンプオルガンが、ウエスタン・スゥインギングなカントリーを踊らせる。
また、最後のナンバーで、レコーディングに入る前のバンドのトーキングが冒頭に聞こえて来て、まず一発撮り間違い無しのフィールド・レコーディング風−まさにオクラホマネイティヴ音楽であるフォーキィな#13『Each Step You Take』がそうだろう。ポロポロとかんとリーの権化のステップを爪弾くペダルスティールに、マンドリン。南部の祭りでブルーグラスバンドが即興で歌いそうな曲だ。こういうタイプはBob Wilesが実にハマリ役である。
また、スワンピーでカントリーな#3『What’s The Chance』もAlt-Countryとも解釈できるので微妙だが、これも相当カントリー風味がタップリなナンバーである。これまた年経た年輪が見えてきそうな粘っこい親父声のBobがリードを担当しているようだ。
ベタなカントリーとは非ロック的という側面では似ているとはいえ、その性質は違うが、ロックやポップでの味付けというモデレーションがあまりされなかった、Red Dirtな土地柄に吹く風を運んでくるようなトラッドなナンバーも面白い色をアルバムに加えている。
テックス・メックスのスパニッシュな雰囲気が見えるナンバーが中盤に続いている。#6『Time Ain’t Nothing』と#7『Angelia』である。#6がメンバー全員の合唱で軽快に歌われ、オルガンの柔らかい音色とポップなラインに助けられて、包容力のある和みナンバーとなっているのに対し、スパニッシュ風の哀愁を湛えた#7はモロにメキシコへクロッシング・ボーダーしている曲である。
哀愁という点では#7に通じる暗さと粘っこさのあるのが、#10『Starin’Down The Sun』だろう。エスニックなピアノソロをエキセントリックに響かせるリフから始まり、Red Dirtというダートで熱砂の陽炎をヴィジュアルに見せてくれそうなジンワリとした重さを引き摺るナンバーだ。
ブルースロックとしての説得力にとても溢れている南部ロックナンバーである。まさにRed Dirtの静の面を向いている曲だと思う。
こういったトラッドが自己主張を強くするナンバーの手を取って踊り始めることで全体の雰囲気を明るくしようとしているのが、残りのAlt-CountryやCountry Rock調子のトラックである。
糸を引くハモンドB3がフワフワのダンシングチューンを刻む、#5『Good Mornig Maryanne』はレゲエタッチのルーツポップ。単なるレゲエソングにならずに、バンジョーのソロや泥臭いギターが音に纏わりついて埃っぽくなるところがRed Dirt Rangersの所以だろう。
オープニングから優しいハーモニー・ヴォーカルとルーツ楽器のアンサンブルが、ノスタルジックな感覚を惹起させる#1『We Don’t Have To Say Goodbye』は1970年代の西海岸カントリーロックをそのままに21世紀に再現したようなソフトさを持っている。Bradの飾らない素のままのヴォーカルも好感が持てる。
フィドルやピアノ、マンドリン、オルガンと様々なインストゥルメンタルが耳に優しい。単純なレイドバック・ソングという括りで片が付けられない南部ポップの名曲だ。コーラスには1960年台のヴォーカルグループの肌触りもあるようだ。
と思えば、Alt-CountryともRoots Rockとも取れる、ロックンロールしてくれるナンバーもある。
#2『Kite Fliers』ではサイケディリックに暴走するフィドルが馬力を抑えてロックするギターを喰ってしまいそうなロックナンバーであるが、その軽快なテンポと重く飛行するギターのアンバランスが、赤土を掘り返して進むキャタピラの如きパワーを放っている。
#4『Leave This World A Better Place』はよりブワブワしたワウワウなロックナンバーだ。グニャグニャと音を出していくエレキギターとパンプオルガンのスワンピ―な掛け合いが快感となる。John Cooperの不器用なヴォーカルが演奏に隠れてしまっているのは残念だが、その分女性コーラスが活用されているので相殺としておこう。
#12『Elvis Loved His Mama』は、一言で斬ればホンキィ・トンキィ・ソング。そしてロカビリーも入っている。50年前にタイムスリップしたナンバー。まさにElvisがステージでロックを演奏しカルチャーショックを蔓延させてた頃のオールド・フロア・ダンスナンバー。
また、サニーでポップなナンバーが見れるようになったのもRed Dirt Rangersの特徴だろう。
感じとしては#1に近いが、レス・カントリーでありレイドバックはしているという、表層だけのソフスティケイトではないバンドの変革を感じる、#8『Don’t Forget About Love』。コロコロと歌い転がるピアノに、オールディズバンドのコーラスが追従する南部の日向ポップ加減全開のナンバー。こういうルーツポップがサラリと出来るようになると次の段階でどう化けるか更に期待ができるというものだ。
そして全米トップ40ヒットを幾つか記録しているオクラホマ出身のポップシンガーで産業ロックも経験しているDwight Twilleyがヴォーカルとして参加している、#11『Dwight Twilley’s Garage Sale』。タイトルもそのまんまだったりするのはジョークが利いている。
Dwight得意のポップナンバーに敬意を払ったようなドリーミーなポップナンバーとなっており、Dwightが実はキーボードでも参加しているのではないかと思いを巡らせるほどに厚目の鍵盤がオクラホマ風カントリーを感じさせるメロディに乗っかっている。
このナンバーも豪華なゲスト参加も含めて、リマーカブルなハイライトソングだろう。
しかし、ここまで多彩にロックアルバムとして、同時にオクラホマルーツを過不足無く再現してくれるとは予想をしていなかったので驚いている。これから更にロック化、ポップ化しそうな勢いを覚えるアルバムの出来だけれども、これだけ自分達の足元を見て音楽を創造していれば、安易な流行やチープなトラッシュ・ミュージックは作らない。そう断言できる完成度だ。
しかし、Red Dirt Rangersのアルバム配分から考えると、次は2006年になってしまうのか。それだけが気がかりであるのだ。
Rangers―放浪者としてクラブサーキットに明け暮れるのは構わないから、アルバムはもう少し早く届くことを祈りたい。 (2003.1.27.)
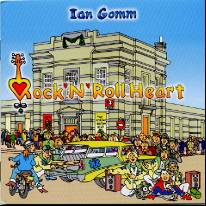 Rock‘N’Roll Heart / Ian Gomm (2002)
Rock‘N’Roll Heart / Ian Gomm (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Pub Rock ★★★
You Can Listen From Here
まずは、Ian Gommについてその経歴を述べておこう。
日本では知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、というレヴェルにあるアーティストだろう。(考えてみれば当たり前やがな。)
チャートマニアなら、1979年に突如全米のチャートでヒットを記録した『Hold On』の歌い手として、またそのカット元になったアルバムが「Gomm With The Wind」という映画のパロディ風であったことで、Ian Gommの名前を記憶しているかもしれない。
しかし、同年にはプログレッシヴ/ハードロックという産業ロックバンドに属する音楽を演っていたカナダのロックバンド、Triumphが2曲しかない全米トップ40ヒットのうち1曲『Hold On』をこれまたヒットさせているので紛らわしい。
ジャンルとしてはStyxやRushと比較されていたTriumphとは全く違うタイプのシンガーとはいえ、Ian Gommの『Hold On』もキャッチーなロックンロールナンバーでヒット性が高いという点では似た所があるのは興味深い。
つまりマトモなヒットシングルがヒットする時代であったと・・・・(以下愚痴なので割愛。)
ちなみにIan Gommは典型的な一発チャート・ヒッターであり、この全米18位まで上昇したシングル以外は全くヒットソングはない。参考までに、Triumphは確か40位くらいのスマッシュヒットよりやや上程度の最高位だったような。
余談はこのくらいにして、Ian Gommについて。
日本では昨年2002年に、ベスト盤である「Twenty Four Hour Service」が邦盤としてリリースされたようだが、筆者は1997年に米国で最初のベスト盤である「Come On」を購入しているので見送っている。新曲とか入っているのか全く知らないので、情報ある人は教えて欲しい。と思ったらこの邦盤は1979年の全米ツアーのライヴ盤だったということ。(情報提供:Ice Nineさん。Thankx)
また、1997年には日本のレーベルであるMSI配給で、「Crazy For You」が発売され、世界中へ輸出されたが、現在海外では物凄いプレミア価格で販売されている。こちらは当然当時は手が出なかった。日本での販売価格も安くはないが、その2倍半以下のところは米国でもなきに等しいという具合だったので。
これらを踏まえると、Ian Gommというアーティストはそれ程マイナー中のマイナーという扱いは、少なくとも日本ではされていないと思うのだが、やはり知っている人口分布は熱心な英国系音楽のファンに集約されることは間違いないと思っている。
よって、最初にバイオグラフィーを記述することにする。本音の部分では、Gommくらいの大御所になると派手な活動はしていなくても経歴を収集することはそれ程難しくないので助かる部分は大いにあったりするのだ。(笑)
Ian Gommは1947年イングランドはオフィシャルの記載を引用すればチスゥイック生まれ。他にも幾つか出身地についての記載が見られるので、正確なところは不明。丁度このレヴューを書いている前後にIanのOHPがアクセス不能になってしまっているため、そちらのバイオグラフィーがオンタイムで参照できないのが残念。
しかし、どうやらOHPは閉鎖されてしまったようだ。ドメインは生きているのに、ページがレンタルサーバーのマスターに繋がってしまうので。どうなったか少々心配。余談であるけれど、やはり少々不安だ。
確実なのはIanがロンドン育ちであるということ。ロンドンっ子のIan Gomm少年が10代の青春時代(笑)を共にした音楽はThe Ventures、The Everly Brothers、そしてThe Beatlesだった。
しかし、Ianは音楽キャリアをミュージシャンとしてではなく、製作側からスタートさせている。
1965年に英国EMIのメカニカルエンジニアとして職を得たIanは5年間、EMIに技術職として在籍する。.その間、Ianは2足の草鞋を履く形で、仕事をこなしつつ自ら楽器を演奏することに本格的に取り組み始め、幾つかのインディバンドを渡り歩く。
Ianの結成したバンドは次第にロンドンのクラブシーンで注目を集め、The Who、Pink Floyd、The Move、Rolling Stonesといった当時はまだ若手のバンドだったツアーのフロントライナーとして起用され始める。
そのようにミュージシャンとしての知名度が上がり始めた1970年に、IanはEMIを退社。
話によると、金曜日にEMIを脱退し即日英メロディ・メーカー誌の広告で発見したバンドにコンタクトを取り、翌週の月曜日にはその広告のバンドBrinsley Schwarzに加入していたという。
Brinsley Schwarzのマネージメントがバンドのメンバーを募集するために広告に入れた条件は以下の通り。
「リード・リズムギターが弾けて、ヴォーカルを担当できる力量があり、ソングライティングがこなせ、他の楽器もプレイすることができる人。カントリーのフレイヴァーのある音楽に興味があるか、実際に行っていた方。」
という演奏能力だけ見ても、「超人か、コヤツ。」と思うくらいのハードルが高い基準の上にある。まあ、職探しの人間が会社に出す履歴書と同じで、能力の一部は水増しして売り込めるが、楽器の演奏に関してはオーディションを受ければ即、糊塗は剥がれ落ちるので、振り分けは買い手側にはし易いだろうけど。
この条件を問題なくクリアしたIan Gommは速攻でBrinsley Schwarzに加入。1970年のバンドとしては2枚目のリリースとなる「Despite It All」のレコーディングには間に合わなかったが、ヴォーカリスト兼ソングライターであるNick LoweとギタリストのBrinsley Schwarzが主導するこのバンドのツアーにはすぐさま同行することになる。
本格的にライターやヴォーカリストとしてバンドに関わっていくのは4枚目の「Nervous On The Road」からであるけど、3枚目の「Silver Pistol」からクレジットされている。
Brinsley SchwarzはDave EdmundsやPaul McCartney And Wingsの全英ツアーの前座として起用されるという具合に欧州と英国ではかなりの人気を獲得する。
米国のカントリーロック程にはカントリーしないルーツロック、所謂英国風ルーツロックのパブロックとパンクロックを基本にしたこのバンドは、Ianの加入後も毎年のようにアルバムを発表しつづけ、1975年の解散までに合計4枚のスタジオ録音盤を残す。
1974年の「New Favorites Of Brinsley Schwarz」でレコードの作製は終ってしまったが、バンドは1975年初頭まで活動していた。バンドの解散の原因は一説には最後のレコードのセールスが相当外れてしまったから、不協和音が始まったためと言われているが、定かではない。
バンドの解散後、著名なのはやはりNick Loweのソロキャリアでの成功だろう。米国でも1980年代はしっかりとしたセールスを記録し、1990年代にも確実に堅実な作品を供給し続けてくれる英国ロックシンガーである。
片や、件のIan Gommであるが、Brinsley Schwarzの解散後、家族とともにウェールズへと移住。当地にレコーディングスタジオを建設する。
ここで自分のソロアルバム用のマテリアルをデモテープに収録しつつ、EMI時代に培ったエンジニア技術をベースにして、プロデューサーとレコーディングエンジニアを同時に仕事にするようになる。
この時期にはPeter Hammillの「Over」(1977年)のエンジニアを務めたり、英国パンクバンドの重鎮と後になるThe Stranglersのレコーディングをサポートしたりしている。
元同僚のNick Loweがロンドン周辺で活力的にライヴを行いメジャーなアーティストへとのし上がっていくことと比較すれば、かなり地道な活動を行っているといえよう。
そして、こうしてスタジオワークをこなしながら溜めた音源を発表する機会は、1978年に英国のインディレーベルから初のソロアルバム「Summer Holiday」をリリースすることで訪れる。
このアルバムは、今で言うPower Popの要素を大量に含んだ作風になっていて、Brinsley Schwarz時代のカントリーロックな味わいは全く含まれていない。英国的なポップセンスのうち、ヒネリやマイナー調子よりもキャッチーさを優先してはいるが、やはり英国人的感覚が見られるパンキッシュでポップな曲が並んでいる。
これをパンクから派生した英国音楽としてNew Waveと呼んでも問題ないと思う。しかも、Power Popの都会的なスマートさだけでなく、英国的ルーツ音楽への解釈たるPub Rockの在り様はしっかりと含有された作品になっていると思う。
このデビュー盤を米国で発売する際に2曲加えて改題したものが、冒頭で少し触れた「Gomm With The Wind」であり、ここから唯一のチャートインしたシングル『Hold On』が生まれたことは既出だ。
このシングルヒットのおかげで、Ian Gommは当時頭角を表わし始めたDire Straitsの「Sultans Of Swing」発売全米ツアーに同行する機会を得て、初めて米国でライヴを行う。
が、次第に観客の反応が良くなってきたため、途中からソロライヴツアーに変更になったとのことだ。
この頃、カントリーシンガーのGlen CampbellもIanの曲である『Hooked On Love』を取り上げるという様子で、セールス的には1980年前後がIanの全盛期だった。
しかし、The Stranglers、The Buzzcocks、Human Leagueといった英国のミュージシャンをゲストに迎えて作成された3枚目(米国で)の「What A Blow」(1980年)は更に脱パブサウンドしたPower Popの良作だったが、セールス的には全く振るわなかった。
次いで、1982年に「Village Voice」は欧州ではそれなりに評価を得たものの、本国英国でも売上を記録することができないまま、ついに1986年にはオランダだけのリリースとなった初めてのセルフプロデュースアルバムである「What Makes A Man A ?」を発表。
このアルバムは欧州の他の国で「Images」のタイトルで同年に発売されている。一般に出回っているのは「Images」のイシューということだ。
そして、1986年から1997年に日本のレーベルから「Crazy For You」を発売するまでの10年間、Ian Gommは長い沈黙に突入する。
この10年をIanは気ままに曲を書き、新しいレコーディングスタジオを好きなように建設することに費やしたということだが、何とも悠々自適な生活だ。更にエンジニアやプロデューサーの仕事も行っていたらしいが、記録に残っているような仕事は手元には見当たらないので何ともいえない。
そして、また前作から5年を置き、発表されたのがこの「Rock‘N’Roll Heart」である。最初は英国と欧州のみの発売だったが、2002年末になってやっと米国の店頭にも並べられるようになったそうな。参考までだが、前作を契約した日本のレーベルだったことで、2001年に日本では大フライング発売されているとのこと。(情報提供:Ice Nineさん。)
しかも、自身のセルフレーベルGommsongsを興しての発売という、Gommにとっては初の発売方法となっている。時代がインディリリースには決して向かい風ではないにしても追い風でもないのだから、てっきり何処かの英国レーベルとでも契約していると予想していたらアッサリと覆された。
この最新作は、実は2000年の夏からレコーディングが始まっている。
ナッシュヴィル周辺のセッションプレイヤーであるベーシストのJeff‘Stick’Davisや、Nanci Griffith’s BandのドラマーであるPat McInerney等を自分の英国スタジオに招いて、まずレコーディングが開始された。そして後にIanが米国まで飛んでナッシュヴィルのスタジオで残りの部分をRussell Smith等と仕上げたとのことだ。
2001年には完全にレコーディングが終了したが、アルバムの契約先の問題でリリースが延び、結局2002年の春先まで発売は行われなかった。
ちなみに筆者がこのアルバムを購入した先はスウェーデンである。一番安かったので。(笑)
アルバムの内容は、前作で見せてくれた英国風ルーツサウンドが更に増加した、非常に良心的なPub Rock/英国風ルーツポップアルバムになっている。
1980年代までIanのアイデンティティの如くだった、New Waveを感じさせるPunk RockやPower Popの要素は前作でもかなり薄れてしまっていたが、今作では更に薄い。
沈黙の10年がIan GommをNick Loweの最近の作風に通じるようなシンガーに変質させたことは疑いようがないこととは思うが、しかしNick Loweの枯れ始めた近年の作品よりもかなり完成度は上だと正直考えている。
「Rock‘n’Roll Heart」という、如何にも「ロックしてるぞ、オラヲラ」な印象を受けるタイトルとは全く異なり、ロックのスピードで牽引するアップビートなナンバーは皆無。
しかし、Nick Loweのように繊細さや枯れた感覚を目一杯出して渋さを狙う路線ではなく、何と言うか純粋−ピュアなポップソング、アクースティックでルーツィで、程好くスマートな英国調理法が施されたナンバーが揃い踏みなアルバムなのだ。
全てのナンバーが、渋さではなく、親しみ易い英国ポップ感覚と、包容力のある米国ルーツサウンドの巧みなブレンドによって成り立っている。やはり、このキャッチーなメロディメイキングは、やや難解で英国的なベント感覚を掘り下げ過ぎるきらいにあるNick Loweよりも巨大に評価したいところである。
まあ、産業ロックやロックンロールにかなり染まっていた1980年代のNick Loweが枯れた中途半端パブサウンドに傾いているのとは違い、1980年代をPower Popで打ち止めしたIan Gommの方が、まだアメリカンロック的な追求が済んでいないため、このようなアメリカンルーツを押さえ気味に着床させたアルバムを創ってきたのかもしれない。Nick Loweは成功を収めた1980年から90年代に掛けてのキャリアでどうにも大切なポップソングの基本を失ってしまっているように思えてならない。特に最近のどうにも中途半端なアルバムを聴いていると。
現在は筆者的ランキングに於いて、完全にIan Gomm>Nick Loweになっている。もっとも、Nick Lowe自体、筆者にとってはそこそこのアルバムしか出さない、常に買うのが後回しになってしまう人という意見が加味されていることはお断りしておく。
アルバムは全12曲だが、40分以内の演奏時間という、コンパクトな曲が纏まった1枚となっている。
どのナンバーもギターの弦を必要以上に唸らせてロックンロールを暴走させるという手段は取らずに、丁寧に楽器のありのままの音量を重ねて音を一つにしたという感が強い。
楽器自体もベース、ドラム、ギターにキーボード類やルーツ系の弦楽器が曲によって適材適所の使用をされているプロダクションになっており、過剰な楽器でロックサウンドを厚くする試みは行われていないので、人によってはあっさりでシンプル過ぎると感じるかもしれない。
が、実にナチュラルに耳を傾けれる気持ちの良さと、リラックスしまくった楽しさを全編で感じることが可能。
この肩肘を張らない楽しさ、これこそがIanの表現したい「ロックンロールのこころ」−Rock‘N’Heartだと思う。
そういった緊張感から解き離れた伸びやかで緩やかなリズムがレイドバックしている#1『Gone Fishin’』からアルバムは幕を開ける。
スローなブギを歌うようなベースリフから始まるこの曲は、ゲストヴォーカルにRussell Smithを迎え、牧歌的な雰囲気が何時までも余韻を残すように流れていく。バックで鳴っているシンセサイザーの音に微量なNew Waveの残滓を感じてしまうのは考え過ぎだろうか。
#2『Rock‘N’Roll Heart』はこのアルバムの中では元気の良い部類に入るロックナンバーと言える。アクースティックなギターと、かなり頑張ってヴォリュームで筐体が割れそうなくらいにはち切れているアコーディオンの音色が良いアクセントとなっている。レゲエと欧州トラッドのアッケラカンとした陽気さを含んだナンバーだ。
#3『Little Last Now』で何を差し置いても強烈な印象を与えてくれるのが、オルガンやムーグキーのサンプリングを押し付けてくるキーボードと女性コーラス、そしてアメリカンカントリーを直接連想させないくらいに歌っているペダル・スティールだろう。このようなシングルにしてもスマッシュヒットしかしないだろうけど、丁寧に組み立てられそのオーヴァー・ドースを感じさせないポップナンバーというのはかなり好きである。
次の#4『The Devil I Know』も控え目にアメリカンルーツを感じさせる地味曲。#3程には取り立てて挙げる点はないナンバーだが、良曲としかいえない。
#5『Don’t Cry』はヴォーカルにNanci Griffithが参加しているところがやはり特筆すべきだろう。歌的には静かなバラードタイプのシンプルトラックだが、Nanciのハイトーンな歌声が透き通って抜けて行くのは、デュエット好きの筆者でも少し出過ぎに思ったりする。
同じバラードタイプのレイドバックソングなら、美しいピアノを絡めた#6『You’re Broken Every Heart』のメロディとアレンジの方がピッタリと嗜好に合致する。堅実で重量感のあるギターとフワフワしたペダルスティールの掛け合いが宜しい。
2分少々で終ってしまうのが勿体無い、元気な南国風サウンドを聴かせてくれるのが#7『Ten Commandments』。マンドリンとアコーディオンの音色は英国というよりもテキサスルーツ音楽の匂いが濃いと思う。
パブサウンドらしい、R&B風味の効いた#8『Hold On To A Dream Tonight』の脱力感は#1にも通じるところがあり、Ian Gommのバックボーンが多彩なことが伺えそう。#10『Everybody Wants To Get It』にも同様のリズムが配されているように思える。こちらはレゲエをより感じるだろうか。
#9『All The Other Girls』ではソウル・バラード風の少し黒っぽいポップバラードが美しく、再び女性コーラスを伴って展開される。この感覚は英国的というよりもゴスペルタッチのアメリカンな肌触りを感じるのだ。
レイドバックしたバラードが再び#11『You Treat Me Like A King』でゆったりと流れ、最後に現れるのが最もラフなトラックである#12『Strange Feeling』だ。
特別オーヴァー16ビートでもなく、ハードに尖ったロックチューンでもないのだが、これまで暖色系統に染まってきた流れの中では暴れるスライドギターやラップスティールがかなりラジカルにジャムり、ロックンロールの荒削りな醍醐味が楽しめる唯一のナンバーでもあるだろう。
こういうルーツのエッジが楽しめるナンバーがもう少しあっても良かったと思っている。マッタリ進行のため、非常に心安らかに聴けるアルバムなのだが、今ひとつ凹凸に欠如した面がないこともないので。
が、全体として相当ルーツサウンドをアメリカンなテイストを使用せずにタップリと挿入している上質のパブロック作品になっている。
長過ぎるブランクや沈黙の10年があったとは俄かに信じ難い出来だ。
是非、オリジナルで行けば、7作目となる筈の(除く、ベスト等)アルバムは、1年でも短い間隔で届けて貰いたいものである。 (2003.2.4.)

 Palace Of Gold / Blue Rodeo (2002)
Palace Of Gold / Blue Rodeo (2002)