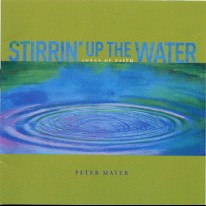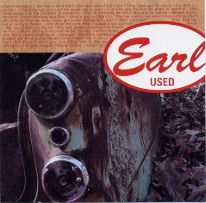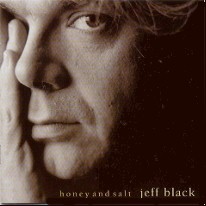 Honey And Salt / Jeff Black (2003)
Honey And Salt / Jeff Black (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Acoustic&Adult-contemporary ★★★☆
「君自身の在り方を見極める、少なくとも君の人生を左右する何かを特定しなければならない時というのが来るだろう。それは苦労の末に見つかるポジティヴな感情かもしれないし、おためごかしの裏にある負の感情かもしれない。
また、時間、お金、愛情、幸福という概念かもしれない。僕にとっては、音楽こそが永遠に探求すべき真実を埋蔵しているものだった。そして、僕は今も探求の途上にある。
僕はアメリカ合衆国に生まれ、農地を失い、世界大戦に勝利し、都市へと住処を移した・・・こういう時代を経験した世代に育てられた。僕は彼等の物語を聞いて育ち、そして現在も物語を探している。
僕の祖父は僕の叔父と同じようにギターを弾いていた。彼らのことは全く知らなかったけど、僕は彼等のことを良く理解できる。僕の祖母はピアノを弾いた。僕は子供の頃祖母を見ただけだけどね。
僕の父親は少年の頃ギターとバンジョーを弾いていた。そして母に出会った。その物語は甘い恋歌。
そう、ここに僕も上手く表現できないのだけれど、代々受け継がれてきた「こころ」があるのさ。抱えきれないほどの想い、人生に影響を及ぼす歌、夢といったものに支えられてね。そして、僕は今も探求者だ。」 Jeff Black。
この前、都内某中古CD店で、Jeff Blackの1stアルバムである「Birmingham Road」が500円でワゴンに入っているのを目撃して少し鬱になった。
が、よくよく思い返してみると、筆者はこのアルバムを1998年夏の発売から半年以内で、3ドル99の「Best Buy」シール付きでNYCにて購入したことを思い出してしまった。更に鬱。
が、約600円で手に入れたJeff Blackのデビューアルバムは、コストパフォーマンス=対費用効果という側面に於いては絶大に効率的だった。詰まる所、非常に価格を考えるとお釣りが出過ぎるくらいに素晴らしいアルバムだったという訳だ。
という消費者レヴェルでの損得勘定はひとまず置いておくとして、発売後数ヶ月でワゴンセール品となり、「Nice Price」や「Best Buy」のラベルを表面に貼られるアルバムというのは、セールスに大失敗したメジャー作品の辿る典型的な末路なのである。
巨大レーベルからそれなりのプロモーションをされて売り出すからには、1000枚や2000枚のプレスで済まされることはないため、初期段階でそれなりの枚数が捌けないと、量販店に初期ロットの在庫が大量に余り、結果として不良在庫になってしまう。
ために、こういったCDは発売半年程度を目処に大量にワゴン品として捨て値で放出されるのだ。
参考までに、2003年現在でも海外中古ショップの大多数で簡単に入手が可能で、平均価格でも1ドル台を未だキープしているという惨状である。こういったそれなりの規模のネットショップでは、新故品やカット盤の受け皿というロールを果たしてもいるのだが、そのくらい売れなかった余剰在庫が卸されたのだろう。
・・・・書いていて、次第に涙が出そうになってきたので、このくらいで中古流通に関しての記述を停止しておく。
しかし、Jeffの「Birmingham Road」はかなり素晴らしいフォーキィでアダルトなシンガー・ソングライター作なので、この値段でなくても買い。1ドル前後なら何を差し置いても手に入れておくべし、とだけはフォローしておこう。
クリエイティヴな作品の市場価格というのは、音楽CDに限らず、適正価格が保たれている訳では必ずしもないことの証明が、ここでもなされている。
って、やっぱりフォローになってなかったりするのだが・・・・。(涙)
そう、Jeff Blackの「Birmingham Road」もこの類に漏れず、残念ながらメジャー・レーベルからのリリースでデビューを飾るという好機を得たにも関わらず、商業的に失敗してしまったミュージシャンなのだ。
1998年に、Arista Recordsから期待のシンガー・ソングライターとして売り出されたJeff Blackは、全米の大手量販レコード店の試聴機にそのアルバムが積極的に取り入れられたにも関わらず、商業的には全く成果を残せず、契約はご破算となってしまう。
モノクロームで地味に過ぎるジャケットのインパクトが強くないという点を差し引いても、全く話題にならなかったというのは、やはり良質なフォーク系のシンガーへの需要が下降曲線を描いていた1990年代末の時代性を反映していると思う。
確かに、非常に丁寧で繊細で、冒頭に翻訳したJeff Blackの「歌の探求者」の如き詩人な側面を色濃く反映した「Birmingham Road」はシングルカットが可能なナンバーが詰まったコマーシャルさからは一歩引いた地点にあった作品かもしれない。
しかし、殆どのナンバーは十二分にポップであったし、メジャーでは殆ど見れなくなった「歌」を聴かせるシンガーでもあった。何よりも、ルーツやカントリーという土臭い雰囲気を殆ど持たずに、良質なアクースティックさをメロディに載せているという点が王道的と感じだものだ。
少し方向性としてはズレてしまうかもしれないが、Billy JoelやJackson Browneを連想させる側面が、このシンガーには存在した。都会的Pop/Rockのシンガーという、繊細さと流麗さの両者を兼ね備えた才能が。
ルーツロッカーというよりも、寧ろロックヴォーカルやアダルトフォークロックの歌い手という位置付けがシックリとくるようなシンガーは1990年代のメジャー・シーンでは殆ど絶滅しかかっていたタイプであったので、商業的な動向も含めて注目はしていたのだが、さっさとワゴン逝きになってしまったのは悲しかった。
同時期にWhiskeytownも全く近似した道を歩み、見事ワゴンセールの常連となっていたのは記憶に鮮明に焼き付いている。ま、もっともRyan Adamsは態度とか発言がとても許せる範囲を超えたことを最近やってしまっているので、さっさと氏んで欲しいところがあるからして、Jeffとの比較はするまでも無いが。
正直、試聴機で聴いた瞬間、連想したのはBilly Joelではなく、Marc Cohnだったのだが。アダルトでシンガー・ソングライターの細かいエモーションを紡ぎ出す歌が、Marcをダブらせた。とはいえ、Marc Cohn程にはキーボードやテクノロジーに依存してはいなかったし、AORの影響よりルーツミュージックのバックグラウンドを強く感じさせたけれど。
だから、期待したいけど、多分売れない、という些か失礼な予測をして購入に待ったを掛けた。この点は同時期に試聴機に入っていたThe Connellsの「Still Life」と同じ判断を下している。・・・・これまたクオリティの割には全然売れなかったアルバムであるが・・・・。まあ、両方とも安く手に入ったので筆者の判断を自画自賛したいけど、この流行には忸怩たる思いがあることは間違いない。
そして、Jeff Blackの名前が1999年から全く聞こえなくなった。案の定、インディ落ちしてしまったのだ。この間、Jeffは南部、主に出身地のミズーリやテキサス、テネシー州といった場所で地道にライヴを行っていたらしい。活動の拠点として彼が選択したのはテキサス州はオースティン。言わずとしれたカントリーロックやルーツロックシンガーの聖地である。
元来、セールスは全くの空振りに終ったとはいえ、評論家筋や批評としてはかなりの高得点を得ていたデビューアルバムを抱えていたので、インディで活動するにはそれ程困ることは無かった様子である。というよりも、かなり過密なスケジュールでアクースティックセットのギグを行っていたし、現在も継続中である。
また、アクースティックのイヴェントでRadny FosterやTom Freundといったメジャー・レーベルやシーンで活動経験のあるルーツロック系シンガーとコラボレーションやジョイントツアーも敢行していたそうだ。
以上のようにメジャーでの躓きにめげずに、地道なライヴ活動を行いつつあったJeffの新しい情報が飛び込んできたのは、2002年の後半であった。
まず、メジャーデビュー前から、このアルバム「Honey And Salt」までに書き溜めた未発表曲を集めて、これを固定メンバーで録音し直したアウトテイク集(厳密には違うが)である「B Sides And Confessions,Volume One」を自身のOHPに限り先行発売を開始する。
このアルバムは米国でも2003年3月より、インディレーベルであるDualtone Recordsから発売される予定であるので、Amazon.com等でも先行予約を開始している。
筆者は当然既に購入済みであるが、かなりパーソナルでアクースティックな内容である。が、曲の粒はそれなりに揃っていて、B面集と名付けずに、新作扱いしてもファンなら納得できる内容であると思う。
この「B Sides And Confessions,Volume One」とほぼ並行して作業を進め、2003年の1月に欧州は独逸のレーベルであるBlue Rose Recordsから発売になったのが、オリジナル2作目である「Honey And Salt」である。
「B Sides And Confessions,Volume One」とは全くミュージシャンが複合しないのが面白い。記事に拠れば、「B Side〜」が後から作成されたとしている記述もあるが、まず「Honey And Salt」の方が新しいと考えるべきだ。
現在、この「Honey And Salt」は欧州のみでしか入手不可能な状態だが、2003年春までには米国でのリリースも予定されているとのこと。恐らくメジャーでのリリースは確率としてゼロに近いだろうけど。そもそもメジャーがプレスするなら、欧州のインディレーベルから先行発売することは殆ど無いだろうし。
インディ落ちして、更に都落ちして本国以外の発売となった本作であるけれど、内容的には遥かに1stアルバムを超えていると考えている。
演奏、歌唱法、アレンジ、曲創りという全ての要素でレヴェルアップしていることが顕著である。
演奏という面では、元々マルチプレイヤーとしての評判が高かった、Jeff Blackであるけれど、今回もその例に漏れず、アクースティックとエレキギターを筆頭にピアノ、キーボード、アコーディオン、ハーモニカという具合にかなりの楽器を使いこなしている。
これに加えて、参加ミュージシャンの顔ぶれが相当豪華だ。
まず、Todd SniderやTommy Womack、そしてJosh RoseやBilly Joe Shaverでのプレイで名高いWill Kimbroughがギターで全面的にサポート。Willも1990年代に2枚のソロ作をリリースしている。2作目は2002年の後半に発売されたが、未だ未聴であるので、聴かなくてはならないなあ。
また、ドラマーにはSteve EarlのバンドであるThe DukesのドラマーであるCraig Weightが選ばれて、全ての打楽器を叩いている。
そしてベースには、Tommy WomackやDuane Jarvis、そしてKevin Gordonといったテキサス周辺のAlt-Countryやルーツロッカーのアルバムで好演を見せているDavid Jacquesが顔を見せている。
後、ピアノとオルガンでJody Nardoneというプレイヤーがクレジットされているが、こちらの名前は寡聞にして知らない。女性のようだが。
こういったオースティンやナッシュヴィルで活動するセッション・ミュージシャンをバックバンドとして、Jeff Blackが送り出したアルバムは、基本的には1st作の延長拡大版と考えてよいだろう。
相変わらず、アクースティックで繊細な部分はしっかりとホールドしているし、シンガー・ソングライター的な内省的な雰囲気も割合としては減少しているが、損なわれた訳でもない。
しかし、こういった前作で目立ったプラスに加算できるポイントを超えて、この「Honey And Salt」は素晴らしいアルバムとなっている。まず、
ロックンロールとしてのパワーとアンサンブルが1作目より格段に上昇している。
全体的にフォーキーで優しいアダルトロックという側面が強かった「Birmingham Road」よりもかなりロックンロールするところが増えている。
更にルーツロックとしての濃度が増量している。
Adult Contemporaryな骨子は1stアルバムの作風を受け継いでいるのだが、デリケートで美しいナンバーよりも土を掘り返した時に漂ってくる大地の芳香が感じ取れるというザックリとした音の構成が多くなっている。これはロックンロールとしての底上げが一役買っていることは間違いないとはいえ、全体的に南部のサザン感覚を加えた音楽性を反映し出したことが要因となっているからだろう。
この結果、アクースティック/アーバン・フォークに終始していたデビュー盤よりも変化に富んで強弱の山と谷のある多彩な展開が楽しめる好盤になっている。
アルバムのスタートになるのは、かなりルーツ・フィーリングを押し立てつつも、アダルトロックの良さを同時に備えた#1『One Last Day To Live』だ。1作目のオープニング曲である『A Long Way To Go』はAdult Rockとしてクリティカルにヒットする名曲だったが、今作の#1ナンバーは、ロックンロールというスピーディなリズムを美しいメロディにシンクロさせた更なる名曲になりそうなポテンシャルがある。
まるでキーボードのようなディレイドが掛かったギターが印象的なリフから始まるこのナンバーは、オルガンを筆頭にキーボードのサウンドも上手にアレンジされている。それでいて、アーシーなエレキギターも働きどころをわきまえており、しっかりとロックリズムをサポートしてくれる。
Will Kimbroughらしいサザンなギターと、Jeff Blackのアクースティックギターのユニゾンがまず聴ける。
#2『Honey And Salt』はロックナンバーとしての主張が強かったオープニングと比較すると、アダルト・ロックのヴォーカルであるJeff Blackのカラーを強調したナンバーだ。
ウィルツァー・ピアノのエコーが掛かった音色に語りかけるようなJeffのトーキングヴォーカルが被さり、それもコーラスでは流暢な歌い方をたっぷりの情感を込めての歌い方に変わる。こういったナンバーでは、やはりMarc CohnやBilly Joelのヴォーカルとしての性格が浮き出ている。
それにしても、Jeff Blackは優秀なマルチプレイヤーであるためか、鍵盤の使い方が巧みだ。このトラックでもウエットなキーボードを複数駆使して、それでいてルーツィなドライさも描写しているのだから恐れ入る。
ロックンロールという要素を含めるが、それ以上にサザン・アクセンツを濃厚に匂わせる曲が取り入れられたのも本作の特徴だ。
低音の効いたピアノリフからスタートする#3『All In Good Time』は、かなりSouthern Rockへの没入を思わせるブルージーなロックナンバー。ドラムのスネア、ハイハット、シンバルの音がとても気持ち良く鳴っているが、その前に落ち着きのあるオルガンのラインとピアノの低空飛行する音階を忘れてはならない。このナンバーはキーボードで引っ張られる南部の重さが漂うナンバーだから。
それ程激烈ポップということはないのだが、不思議に耳に残るアッサリ目のポップラインが重心の低いメロディと合わさって馬力を倍増させているようだ。
また、モロにサザンロックという面と、路上のロックヴォーカルともいうべき都会的なセンスが同居しているのが、#7『You Belong To Me』だ。このナンバーもオルガンとピアノが酸味の効いた黒っぽいロックナンバーを演出しているところは#3に近いが、それと同時にやはりアダルトロックの流麗な面も残っているところが、Jeff Blackたる所以であると見ている。単純なSouthern Rockも勿論素敵だが、こういったスマートな空気を加えてくれると、しつこくなり過ぎることがないので嬉しい。
ロックンローラーとしての変質を明確に打ち出してきているのが、#1とは比べられないくらいにカッ飛んでいるロックチューンの#4『Rain』、そして#8『Shout From The Secret』だ。#4は恐らくはWill Kimbroughによるバリバリのスライドギターが暴れ、Jeffの野太い歌唱が聴ける、ただロックンロールというしかないナンバー。この図太さはどちらかというと優等生的な顔を大切にしていたメジャー作では押さえつけられていたJeffの意向ではないかと想像したりする。
#8はラフでヘヴィなノリで押し切っていた#4と比較すると、クリアなピアノをオルガンの他にも加えたポップなロックチューンであり、かなり好みのナンバーである。この曲でもJeffはかなり荒っぽい歌い方を見せてくれる。
また、後半のオルガンとシンセサイザーのソロはかなり筆者のツボである。こういったルーツィな鍵盤ソロは意外に出会うことが難しいので。
シンガー・ソングライターとして、シンプルで美しいナンバーを歌う、詩人的なJeff Blackも勿論健在。
殆どピアノの弾き語りのみで綴られる#5『Rain』での叙情的な世界は、Jeffの静かなるエモーションを代表するナンバーだと思う。
また、完全にアクースティックでシンプルな演奏をバックにして、まるでShawn Mullinsのようなローファイラップ/トーキングで囁くように語る#6『The Leaving』は、ピアノとアクースティックギター、そしてリズムセクションの美しい演奏を聴くだけにするべきかもしれない。ヴォーカル曲としては少々異色だ。
同様に、もとい、それ以上にシンプル且つアクースティックなギター弾き語りのフォークナンバーである#9『Persephone』ではしっかりとJeffの“ヴォーカル”が歌われる。しっとりとした優しいアレンジとメロディはまさにJeff Blackがデビュー当時から持っているイメージの権化のようだ。が、そこが良いのだ。
最後のトラック#10『Home』もまたかなりアクースティックで静謐なナンバーだ。ややダートでダークな南部風フォークナンバーであるとはいえ、流れとしては#9と似ている。確かに木目の細かいJeffの感性が見えてくるナンバーだけれども、直前の曲がアクースティック弾き語りだったので、ここでは違ったインパクトが欲しかった気はする。
このアルバムでの流れ的に不満なところはドンジリの2曲だ。
それにしても、「Birmingham Road」でもJey Bennett、Ken CoomerそしてJohn Stirrattといった、インディ活動時代にWilcoのJeff Todayに才能を評価された関係で、豪華−というよりもWilcoのメンバーがフル参加−なゲストが顔を揃えていたが、インディ作となった「Honey And Salt」にもWill Kimbroughを筆頭に、インディ界の玄人ミュージシャンが集まったのには驚いた。
やはり、かなり音楽仲間でも評価の高いシンガーなのだろう。前作から考えてみれば5年も経過してしまった2作目(「B Side〜」も加えると3枚目)だが、長いブランクを吹き飛ばしてくれるような良作である。
今後も南部を中心にライヴ生活を続けるらしいが、またメジャーでアルバムが出せるくらいの評判を獲得して欲しいものである。
何はともあれ、Jeff Black、久方ぶりのカムバック、おめでとう。 (2003.2.18.)
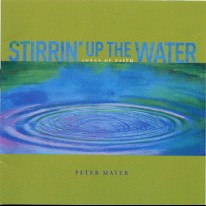 Stirrin’ Up The Water / Peter Mayer (2002)
Stirrin’ Up The Water / Peter Mayer (2002)
Acoustic ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★
Adult-contemporary ★★★★☆
You Can Listen From Here
Peter Mayerというアーティストを、1980年代後半頃、シャカリキになって洋楽、特に日本でのAORに当たる、Adult Contemporary Rockを追いかけていた人なら記憶している、こともあるだろう。
要するにマニアやヲタクと呼ばれる類の音楽ファンなら覚えている程度の活躍はしているし、その類の人種に歓迎されると推察もしている。実際に、当時はかなりその種の音楽にハマっていた筆者のレーダーにはしっかりと引っ掛かった人であるし。(参考にはならんわ。)
もっとも、Peter Mayerではなく、PMというバンド名の方が日本に限らず、AORファンには通りが良好に違いない。
更にいえば、PMというロックバンドよりも、印象が強いのはこのPeter Mayerが結成したバンドPMがヒットシングルとしてチャートに送り込んだ『Piece Of Paradise』(Adult Contemporaryチャートで8位まで上昇。日本でも洋楽系のラジオで少しオン・エアされた。)の方ということは十分にあり得るが。
特に、21世紀になっても、AOR(アダルト・オリエンティッド・ロック)という見事に間違いの和製英語のジャンルが確実な売れ筋として市場を形成している日本においては、PMのサウンドはメジャーリリースされたのにも拘わらず、発売当時に日本盤がリリースされなかったのは結構珍しいことのように今では思える。
また、所謂「懐かしのAOR云々シリーズ」等で復刻されても良さそうな音楽性のあるアルバムなのに、未だ日本で復刻されたという話も聞かない。これまた少しばかり意外の感を拭えない。
とはいえ、筆者は日本盤のリリースには絶望的に疎いのだから間違っている可能性は非常に高いので話半分にして貰えれば幸いだ。
ここまで書けば想像することすら陳腐であるだろうが、一応述べておくと、PMのリーダーであったPeter Mayerは、Adult Contemporary / AORな音楽性を引っさげて、1980年代にデビューしたミュージシャンなのである。
現在、Peter Mayerは、活動名義はソロシンガーの形を取っているが、実質はメンバーの過半数はPM時代からのバンド仲間であり、PMがPeter Mayerというフルネーム記述に変化しただけと考えるのが適当だろう。
まずは、このアルバムについて述べてみたい。Peter Mayerの経歴については折に触れて、織り交ぜていくことにしよう。
ここにジャケットの写真をアップロードしてあるが、「Stirrin’ Up The Water」というアルバムタイトルの、UPとTHEの下に、小さく白抜きの文字が見れると思う。それ以上はかなり解像度が低いので肉眼で読むのは辛いだろう。 ここには「SONGS OF FAITH」という副題が付けられている。
このイディオムでピンとくる人もいると思うが、このアルバムは、宗教アルバムであるContemporary Christian Music=CCMに属する。
と、「SONGS OF FAITH」だけではジャンルの特定が出来なかった人もいるかもしれない。
しかし、#1のタイトル曲である『Stirrin’ Up The Water』を聴けば、まず間違いなくこのアルバムがCCMとまでは行かずとも、宗教色の強いアルバムであることは察することが可能だ。
何せ、この美しく、アクースティックでアダルトなポップトラックである#1で、♪「Ahallelujah,Ahallelujah,Ahallelujah〜」♪、とPeterがその甘いヴォイスで連発しているからだ。
Ahallelujarは、HallelujarやAlleluia、Alleluiahともスペリングされるが、日本語で言えば「ハレルヤ」である。ヘブライ語からそのまま英語に継承された単語で、「主を称えよ。」「神の栄光を褒め称えよ。」という意味を持つ。
かなり多くのCCM系ソングや黒人霊歌にもお定まりのフレーズとして登場するので、お馴染みの人は多いと思う。
筆者の場合、勝手に分類しているが「神様の歌」になると、完全に歌詞を聞き流してしまうので、このアルバムもその類に漏れない。このことをお断りしておく。
しかし、Peter Mayerは1985年にLeft LaneというAOR/ジャズロックのバンドでデビューを果たした時からCCM系の詩を書いていたのではない。
宗教アルバムの体裁をMayerが打ち出し始めたのは、2000年に発表されたクリスマスアルバムである「Stars And Promises」からだ。このアルバムもクリスマス・ソング自体がチャーチミュージックと切っても切れない関係であるため、宗教色を帯びるに至ったという側面を持っている。
であるから、オリジナルのCCM作品としては、本作の「Stirrin’ Up The Water」が初めてというべきかもしれない。
以下のようなコメントがアルバムのインナーに寄せられている。
「8年前から、僕は僕はとある特定の場面を描写した歌を書くようになり、歌い始めた。それは教会、宗教、結婚、献身ということについて内面と外面から見たものを歌ったものだった。
時々、ファンの皆がこれらのマテリアルをレコードにして欲しいと頼んできたり、どのアルバムでそれらの曲を聴けるかと質問をされてきた。
数年掛かって、十分な数の歌を書き溜め、僕と兄のJimはこれらのマテリアルをCDに収録しようと思うようになったのさ。始めはギターとヴォーカルだけの可能な限りシンプルなスタイルで録音をしようとしたのだけれど、3ヶ月以上に渡るJimのレコーディングやエンジニアリング、ミキシングに演奏という多岐に渡ってのヘルプがなかったら、とってもひとりではこのアルバムが完成しないことが分かったよ。Jimは物凄い時間をこのレコーディングに割いてくれた。とても感謝している」
というように、これまでライヴ等で少しずつ歌ってきた宗教関連の歌を集めて、折からのCCMへの傾倒を踏まえた上で、Peter Mayerはこのアルバムを世に出したらしい。
また、2002年には、もう1枚の宗教アルバムである、「Stars And Promises Alive」という2000年のクリスマスアルバムにほぼ忠実な曲順でライヴ演奏をしたショウをアルバムに収録して発表している。2年で3枚というハイペースのアルバム発売だ。
しかし、歌詞云々というよりも、#1ではそのスゥイートなメロディとシンプルなアクースティックサウンド、そしてハートウォーミングなPeter Mayerの声が織り成す歌世界の流麗さに心を奪われるだけである。
ここまで綺麗に曲を提示されると、♪「Ahallelujah」のフレーズもその気持ち良いライムを楽しめるようになり、つい一緒に口ずさんでしまう、「ハレルヤ」と。・・・・筆者は無宗教なのだが、ただ韻と発音を楽しむというのも洋楽の楽しみであることは否定しない。(笑)
そのくらいにコーラスの部分を含めて、ソングライティングが激烈にキャッチーなのである。
Adult Contemporary Rockのアクースティックな極限を突き詰めたようなポップソングが最初から最後まで敷き詰められているのだから。
しかも単にFolk Rockというのではなく、しっかりコンテンポラリーなポップスのアンサンブルを大切にしている。
Adult Contemporary Folkという名前で定義するのも悪くは無いのだが、フォーキィな素朴さよりも、New Age Music−自然回帰サウンドやアクースティックの美しさが際立っているため、やはりフォークよりもアダルトなPop/Rockという呼び方がしっくりとくると考えている。
#2『Ever Walk With Me Lord』は更に繊細なゾーンまで踏み込んだこれまた甘いバラード・ポップ。ストリングスやバンジョーという補助、そして如何にもゴスペル・ミュージックの代表という具合のハイトーンなコーラスのリフレインがヴァイオリンの音色と緊張感をホンノリ含んでデュエットする。
これ以降のナンバーは全て、#1や#2に習った何処までも優しく、美しいナンバーとなっている。
#3『Blueprints』はストリングスのラインが、何処かしら聖歌でトラディショナルでもある『Joy』(邦題はしばしば、「主よ、人の望みよ、喜びよ。」と付けられる。)のメロディを思わせる。このトラッド・ソングからPeter Mayerがラインを借用したかは不明だが。
#4『Loose In The World』はフォーク系の歌というよりも、まさにAORやAdult Rockという表現が相応しい、ややアップテンポなナンバーだ。
打ち込みっぽいが、絶対にハンド・パーカッションであろう打楽器がリズミカルにアクースティックギターの弦とワルツを踊ってくれる。このあたりのセンスは、全盛期のTotoとかに通じるリズム感ではないかと思ったりもする。
少し低音域を使って歌う、#5『“A” Is For Angel』は、直訳でもすれば、「AはAngelのA」というところだろうか。全然関係ないが、某SF小説の有名な邦題「ウは宇宙のウ」なんてものを思い出して重ねてみたりした。
少し大人し過ぎるナンバーで非常に地味。常にハイトーンのクリアなヴォイスが淀みなく流れていくこのアルバムの一連のストリームにアクセントを与えるという意味では意義のあるナンバーかもしれないが。
#6『Light My Way』も非常にシンプルなアクースティックギターで殆どが語られる曲。このアルバムではPeterの兄であり、共同ソングライターでもあるJimが殆どウッドベースを弾いているということだが、それが明らかに分かるトラックでもある。
#7『We Are Changed』の辺りまで来ると、次第に瞼が下がってくることが多い。所謂アルファ波ミュージックのヒーリング効果がどの曲にも満載になっているからだ。
この#7もナチュラルなギターと所々で挿入される美しいコーラスの繰り返しが静かな波のようにヒタヒタと心を洗ってくれるようだ。
#8『Mighty This Love』になると♪「Ohh〜」というア・カ・ペラな激甘コーラスから始まり、しっとりとしたギターパートが暫くして歌本編と一緒に登場という形をとった、宗教バラードのキャッチーさを全く外さずに取り入れているナンバーである。ここまでゴスペルっぽくなると少し食傷気味になるという面は存在する。
#9『Only You』のように、素朴なアクースティックバラードの形でジワジワと盛り上げてくれた方が、聴き易いというところはある。あまりにコーラス隊の大仰さが全面に出過ぎというのもToo Muchだから。
ところで、全く同姓同名のシンガーである、「違う」Peter Mayerという人がミネソタ州で活動している。また奇遇なことにこっちのMayerはフォーク一筋なシンガーであるのだが、少しアンサンブルを付けてシンプルなアクースティックに留まらないContemporary Folkなところが、Adult Popにどっぷりな本レヴューのPeter Mayerとかなり被るのだ。
しかし、相対的にはミネソタのPeter Mayerの方が土着フォーク指向が強いとは思う。
ちなみに、アナザーなPeter Mayerはこちら。この人のアルバムもアクースティックという点では光るものがある。より森や山や木々を感じさせるシンガーであるけれども。
#10『Pass It On』、そして#11『Yes I Will』は、キャリアの最初からフォークシンガーであるミネソタのPeterにより近いといえる、ほぼアクースティックギターの弾き語りナンバーとなっている。#10の方が、透明感のある秋空を見上げた時に感じるような奥行があって好きであるけど。
オーボエかフルートだと思うが、木管楽器の使い方も、#10では非常に上手だ。
やや、美し過ぎて途中で聞き流すきらいのある作品であるし、パターンとして綺麗過ぎなため変化に乏しいという瑕疵は存在するけれど、この美しさと優しさ、ハートウォーミングな手触りは非常に貴重だと思う。
Peter Mayerの最近作を配給しているのは、宗教レーベルではなく、アクースティック系音楽専科のLittle Flock Musicであるけれど、このアレンジとジェントルなメロディならWindamHill Recordsでも十分に歓迎されてリリースされそうなくらい自然回帰さが溢れている。
ところが、Peter Mayerの経歴を振り返ってみると、CCMは兎も角として、最初からアクースティック路線をひた走っていた人ではないので、この近年の方向転換は意外である。異様とは思わないけど。基本にしているのはポップでアダルト受けする音楽であることは変わらないからである。
しかし、特にPMを名乗っていた時代と比べるとかなりの変化が見られることは確かである。
Peter Mayerは1966年に、インドで生まれるという珍しい出生地を持つアーティストである。両親が当時インドに在住だったためで、彼が生まれて直ぐに家族は母国である米国に戻り、ミズーリ州のセントルイスで居を構える。Peterはセントルイスで育つ。
1970年代からPeterは自分でアマチュアバンドを結成して音楽活動を開始するが、当時カヴァーしたり聴いていたのは、Chicago、Styx、Super Trampといった産業ロック、アダルトロックのメジャーバンドだった。
「その頃のポップミュージックのラジオの定番といえば、こういったものだったからね。」ということだ。
が、高校生の頃になると、Peterは次第にジャズに傾倒するようになる。Keith Jarretを始めとして、特にのめり込んだのがPat Mathenyだったということ。
高校を卒業するまでにはかなりのジャズギター技術を独学で身に付けてしまったPeterはWebster大学でジャズギターの講師としての職を得る。
この仕事の傍ら、Peterは5歳年上の兄であるJim MayerとドラマーのRoger Guth、そしてキーボードにRay Kennedyを迎え、Peterはジャズ/フュージョンロックバンドのLeft Laneを結成。
1985年にスウェーデンのレーベルからアルバム「In Common」を発売する。このアルバムのプロデューサーはこれ以降も交流を続けていくセッション・キーボーディストのJay Oliverだった。JayはGlenn FreyやJimmy Buffettを始めとするメジャーアーティストのアルバムでそこそこ顔を見せている。ちなみにこの「In Common」はLPオンリーの発売だったが、21世紀でも瑞典での購入が可能だ。
このアルバム自体は米国のマーケットでは殆ど注目を集めなかった。ここでPeterはジャズ/フュージョン路線からPop/Rockへ戻ることを決意。JimとRogerというソングライターがバンドにいたので、3名で協力して曲を書きつつ、デモテープをあちこちのレーベルへとせっせと送り続ける。
その甲斐あって、幾つかのレーベルから契約のオファーが来る。最も条件の良かったのがWarner Borthersだったので、1998年にPeterはWarnerと契約。バンド名をLeft LaneからPMに変更し、セルフタイトルのアルバム「PM」を発売する。
プロデューサーは、何とElliot Scheinerが務めている。Elliotはエンジニアやミキサーとしてのキャリアがプロデューサよりも著名かもしれないが、確かに大物のプロデューサーだ。George BensonやAerosmith、REM、Glenn Freyのエンジニアから、Donald Fagan、John FogertyそしてEaglesのカムバック作「Hell Freezes Over」といった幅広いプロデューサーを歴任している人である。
この「PM」からシングルヒットが生まれ、馬鹿売れとまではいかないがそれなりの枚数を売ったにも関わらず、Warnerは翌年契約を破棄。PMはインディへとレーベルを移す。
また、Elliot ScheinerがJimmy Buffettのプロデューサーを担当した際に、ElliotはPMのメンバーをJimmy Buffettのバックバンドに推薦する。PMをオーディションしたJimmyは即座に彼のバンドであるCoral Reefer BandにPMの3名を招くことを決定したそうだ。この関係は2003年現在も順調に継続し、Peter Mayerとバンドメイトは未だJimmy Buffettのバンドメンバーとして扱われている。
Jimmy Buffettのバックバンドとして活動しつつ、PMはそれから2枚のアルバムを発表。この間にギタリストのVince Varvelがメンバーに加わっている。
「Street Dream」(1991年)は再びジャズロックっぽいカラーを加えたロックアルバム。
「Red Wine And Lemonade」(1993年)は「PM」系のアダルト産業ロック作。
ここで、PMから名義をPeter Mayerに切り替え、「Green Eyed Radio」を1996年に発売。この作品あたりから少しアクースティックさが増すが、まだまだアダルトなPop/Rockの典型であるヴォーカルロックアルバムという性格が強く感じられる。
Peter Mayerがアクースティックなロックに移行するのは、1999年の「Romeo’s Garage」からである。同年にスタジオライヴアルバムの「Spare Tire
Orchestra」がリリースされるが、この2枚ではかなりアクースティックギターが目立つようになる。
しかし、この後のCCMに向かい始めた音楽性と比べると、アクースティックではあるが、まだロックンロールとしての味わいが残っていた趣はある。本当に、ここまで静謐で美しいアルバムを世に問い始めたのはここ2年ばかりのことなのだ。
AORやフュージョンロックからキャリアをスタートさせ、アダルトな産業ロック風のヴォーカル作でメジャーデビュー。
そして、大御所のJimmy Buffettのバックバンドを行いつつも産業ロックを追及する。そしてアクースティックに変遷しつつ、迎えたのは宗教音楽と、ロックとは呼べないくらいに美しくなったストリングスとナチュラルギターのゴスペルソング。
非常に面白い変化を経験して、現在も元気に活動しているアーティストである。この次はまたCCMではなくて、最近少なくなった柔らかいキーボードを多用した産業ロックアルバムにでも戻ってくれても面白いと思う。
しかし、ここまでキーボードから離れるとは「PM」を聴いていた時点では想像すらできなかった。
Peter Mayerの場合、安易にアンプラグドのブームに流され、上っ面だけの原点回帰を標榜したアクースティックサウンドへ迎合した訳ではないから、特にこれからについての不安は抱いていない。
非常に透き通ったハイトーン・ヴォイスの持ち主で、ロックヴォーカルとしても最近少なくなったタイプのシンガーでもあるから、頑張って良作を出し続けて欲しいものだ。
もうひとりのやや顔がおっさん臭いPeter Mayerも、こちらのPeterが好きなら一聴の価値有りと、両方を賞賛しておくことにしよう。 (2002.2.20.)
 Love Ain’t A Cliché
Love Ain’t A Cliché
/ Dan Israel And The Cultivators (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Americana ★★★
You Can Listen From Here
「実のところ、僕がCultivatorsというバンドの名前を思いついたのではないんだよ。バンドのベースプレイヤーであるJeremy Smithが練習している時にポロリと漏らした名前なんだ。そして、それはバッチリ僕等のバンドに合っているように思えた。
僕はこれまでに幾つものバンド名を考えて付けてみたけれど、それは全部どうしようもないくらいアホなものだった・・・・うん、恥になるんでこれ以上は語りたくないなあ。だから、僕には上手い具合の名前を考えつける星回りがないと自分でも考えているよ。
バンドに名前を付けるという行為は本当に難しいよ。全部がとっても馬鹿らしい響きになってしまうように感じる。そして、ある時は凄い格好良い名前と見えていたのが、次の日にはくだらない名前のように思えてしまったりする。
また、折角良い名前を見つけても既にどっかのバンドに使われてしまっていたりする。これは最近の問題だね。
でも、The Cultivatorsという名前は僕はとっても好きだよ。この単語には含蓄や暗示する要素がたくさんある。プラス、君がインターネットのサーチエンジンで検索するととても愉快な結果になることを知っているからね。(笑)『日曜園芸者のページ』に行き着けば、僕の言いたいことは分かると思う。
ところで、僕達はデビューアルバムではDan Israel And The Cultivatorsと名乗っていたけど、今はただのThe Cultivatorsだよね。これはヒネクレモノのDan Israelがノイローゼでバンドを抜けた・・・ってことじゃないからね。
単にThe Cultivatorsという名前の方が相応しいと思ったからなんだ。」
とDanはThe Cultivators名義でリリースされた前作−Danの実際の作品としては2作前となるが−「Mama’s Kitchen」をリリースした後のインタヴューで述べている。
しかし、The Cultivatorsという名前は結局1枚限りのものとなってしまっている、現行では。
Dan IsraelがThe Cultivatorsとして発表する3枚目のフルレングス「Love Ain’t A Clichè」では、再び1作目のスタイルであるDan Israel And The Cultivatorsが使用されている。
この名前の復活に付いてはまた後述することにして、このアルバムの発売によって確実になった名前と音楽性の相関性について先に述べておくことにしよう。
Dan Israelは完全に音楽性の棲み分けを確立してしまったように思える。
The Cultivatorsの名前が入る場合はロックンロールのアルバムを。
Dan Israelのソロ名義でアルバムを発表する場合は、ロックアンサンブルを全く含まない完全にアクースティックな内省的かつフォーキィな作品に。
という使い分けをしているのだ。
これまでにDan Israelが中心になって世に出したアルバムは全部で5枚。
1.Before We Met / Dan Israel And The Cultivators (1997年)
2.Mama’s Kitchen / The Cultivators (1999年)
3.Dan Who ? / Dan Israel (2000年)
4.Cedar Lake / Dan Israel (2002年)
5.Love Ain’t A Clichè / Dan Israel And The Cultivators (2002年)
となっている。このうち、3枚目、4枚目は完全なアクースティック・アルバム。特に3rdの「Dan Who ?」は内省的な沈鬱さが詰まった暗いアルバムで、これだけはどうにも筆者の性に合わない。ギターとDan Israelのヴォーカルだけという完全な弾きと語り“のみ”のアルバムであり、ここまでシンプルにされてしまうと、ちょっと引いてしまうのだ。正直、Danは好きなタイプの飾らないヴォーカリストだけれど、お世辞にも美声の持ち主とか、パワーのある名ヴォーカリストとはかなり違った次元で語るべき、「普段着」のヴォーカルを持つ人だと思うので。
同じくソロとして出された、4枚目の「Cedar Lake」は2002年にオフィシャルサイトでDan Israelから直に買うか、ライヴ会場で買うしかなかった、前作に続いてのDanのワンマン・パフォーミング・アルバムである。
2002年の冬に5作目、前半に「Cedar Lake」を発表という、年に2作のリリースをDanは実行しているのがまず手放しで褒め称えたい。
そういった内容抜きの面だけでなく、アルバムの中身もアクースティック中心とはいえ、Danはピアノやハーモニカをプレイし、ヴォーカルも重ね撮りしてアクースティックで繊細ではあるけれども、カントリーやルーツロックを感じさせるキャパシティのあるアクースティックなアルバムとして仕上げている。よって、筆者も良いアルバムだと考えている。
が、残念なことにこのアルバムは現在入手不可能。プレスが終了してしまっている。
対して、The Cultivatorsが名義に封入された3枚のアルバムは程度の差こそあれ、バックバンドであるThe Cultivatorsを加えたロック演奏が聴ける、ロックンロールなDanの側面を見せるアルバムなのだ。
1stは非常にCountry Rockの要素が強く、2ndは中西部・中部米国エリアの中庸ロックンロールを代表するようなミディアム・ルーツのテイストが濃厚な名盤。というようなデファインは後程することにして、ここで判断できるだろうけれど、The Cultivatorsがサプライ側の名前に入ると、そのアルバムはロック作となるのだ。
つまりはBruce Springsteenの「Nebraska」や「Tunnel Of Love」。またはNeil Youngの「Harvest Moon」や「Silver And Gold」に当たるのが、Dan Israel=シングル・パフォーマーとして発売する場合のスタンスということ。
「Dan Who ?」の時点で、名盤だった「Mama’s Kitchen」の続編を期待して裏切られたため、Dan Israelとして作成するアルバムにはかなり懐疑的な眼で見つめていたが、「Cedar Lake」の良質なマウンテン・フォークという感じの音を聴けたことで、アクースティック・ダンである作風にも偏見無く接することが出来るようになった。
然れども、1999年からこっち、すっかりソロアーティストとして、フォークギターを抱えて密やかに歌うスタイルが定着した出した感の強い活動が3年くらい続いてしまっていた。
ロックバンド、殊にミネアポリスの中道ロックの良心であったと筆者が勝手に決め付けていたにせよ、優秀なロックユニットのリーダーとして期待を掛けていたDanがロック離れをしてしまったのではないかと危惧し始めた頃が、「Cedar Lake」が届いた2002年のことだった。
しかも、The CultivatorsのメンバーとDanは一緒に行動することを止めたという情報まで伝えらていた。
そういった流れの中で、まさかこれほど早くCultivatorsの新作が届くとは思わなかった。
まず、Dan Israel And The Cultivatorsというバンドを名乗る前、ミネアポリスのアンダーグラウンド・バンドとしてクラブ演奏していた時代以来のメンバーである、ドラマーのAndy Rauh、ベースのJeremy Smith、ギターのTom SampsonというCultivatorsのメンバーは誰ひとりとして、「Love Ain’t Clichè」でのThe Cultivatorsには含まれていない。
これには2年以上に及ぶ、Danが少しバンド活動を停止して、ソロアクースティックな演奏に専念するという急激な方向転換に、メンバーが追随しきれなかったためかもしれない。
「面白いことに、僕が創った最もシンプルな音楽が一層注目を集めているね。これまでに僕は3枚のアルバムを出してきたけど、一番赤裸々なアプローチをしたアルバムが最も売れている。
僕は30歳になって、借金があり、面白味のある日々の仕事をこなしているけど、もしかしらた止めた方が良いかもしれないって思う。けれども、僕は音楽を創り上げることが大好きだし、少しずつだけど進歩していることは自分でも自覚できているんだ。」
以上の「Dan Who?」を発表した直後のインタヴューを眺めてみると、1980年代後半から、そのキャリアの殆どをロックバンドの一員として、リーダーとして過ごしてきたDanがスローダウンを意図していたことは理解できる。しかし、実際問題として「Mama’s Kitchen」を発表した直ぐ翌年に、ギターのみのスローアルバムに転向するという舵取りはかなり意外であった。
以下のコメントは1999年次のものであるけれど、Cultivatorsというバンド内でのメンバーとの関係には、ポジティヴな意見を表明している。
「Cultivatorsは僕の独裁者的なリーダーシップで運営されている、ってことは全く無いよ。でも、完全無欠な民主主義バンドってこともでも無い、とは思っている。
僕が以前にテキサスで運営していたバンドのPotter’s Fieldにいた時、僕はかなりのフラストレーションを感じていた。というのも、このバンドのコンセプトは、『メンバーは平等な立場でバンドを運営する。』
だったんだけど、実際にバンドが動き始めると主要な責任は殆ど僕の肩にかかってきたんだ。
Cultivatorsと一緒に活動している際も、僕が完全にフラストレーションから自由になっているとは言わない。けれども、僕達はより良い関係をベースにバンドを始めている。多分、もっと正直にお互いの主張をするってことかな、それは。
つまり、僕だけではなく、バンドとして雑用を、ブッキングや交渉を行うようにしているということなんだ。けれども、僕がバンドのメンバーを代表して様々な雑務をしなくてはならないことは既に了解しているからね。
だから、このバンドから抜けるつもりは無いよ、凄いバンドだからね。
でも将来的には他のミュージシャンと演奏したくなったりするだろうし、他のメンバーがバンドに加わることもあるだろう。それから、僕は多分ソロアクースティックなアルバムをひとりで創りたいと思っている。このあたりが考えつく限界だね、Cultivators以外の活動としては。」
しかし、「多分」「将来的に」やりたかったソロ/アクースティックなスタイルに、この後即座に鞍替えしてしまっているのだ。だから、アクースティックなヴォーカリストとして地歩を固めていくような流れが、2000年あたりからのDanの意図のように思えていたからである。
しかし、現実に2002年10月にDan Israelは新生のThe Cultivatorsを率いて、新作「Love Ain’t A Clichè」を届けてくれた。
ここで、バンドとしての前作に当たる「Mama’s Kitchen」がThe Cultivatorsであったのに、デビュー時のDan Israel“と”The Cultivatorsというクレジットに回帰しているのは、やはりThe Cultivatorsを名乗る前から一緒にバンドとして活動してきたベース、ドラム、ギターという面々がバンドを離れたため、あくまでも新しいThe CultivatorsとDan Israelが発足したということを強調したいがためではないかと思うのだ。
要するに、仕切り直し、ロックユニットととしての活動再開という意味で、原点−活動開始時代−に遡ることを込めてのAnd The 〜形式を選択したと思っている。
さて、この通算5枚目のDan Israelのリーダーアルバム(これ以前にも複数のバンドに所属しているが)であるけれども、ひとことで述べると、
これまでの必殺パターンであった、オープニングトラックがベストナンバー、または傑作!という線を見事に外している。
インディバンドに限らず、1曲目に最もシングル向きのナンバーや自信作を配する形のアルバムは数多い。これはやはりアルバムのスタートというのはリスニングの形態上、CD時代に変化したとはいえ、一番聴く回数は多いし、アルバムのイメージを植え付けるのに貢献し易いという事実があるからだろう。
Dan Israelもこの“頭に傑作”のパターンを繰り返してきた人で、「Before We Met」の『Almost Started To Believe You』、そしてThe Cultivatorsの大傑作と呼ぶしかない「Mama’s Kitchen」の『All Alone』と、どちらのアルバムの1発目もアルバム中で恐らく一番キャッチーで親しみ易いナンバーをぶつけてきていた。
ところが、この「Love Ain’t A Cliché」のオープニングトラックである#1『Some Times』はアルバムの中で最も重苦しく、ポップの度合いすら最低な粘っこい南部タイプのロックチューンである。Dan IsraelはJayhawksやBellwetherといった極端にサザンやスワンプロックのルーズさや酸味とは異なるタイプの、米国中西部を代表するニュートラルなPop/Rockのスタンダートといえるミネアポリス出身である。またこれまでにルーツさは十二分に兼ね備えておりながらも、サザンロックを身近に感じさせるようなナンバーはあまりなかった。
しかし、低空飛行するオルガンの音色といい、流石にポップではあるけれども、アシッドでダートな風味満載のミディアムナンバーである#1はルーツィであるけれども、かなり粘着力のあるナンバー。流石にアンキャッチーということはないけれども、アルバムの他の曲と比較すると目立ったメロディラインは持っていない。
この#1の印象が強いこともあるけれど、このアルバムは一言でいえば、
地味。これに尽きる。
とはいえ、元来良質なポップセンスと適度なロックテイスト、そしてAlt-CountryやCountry Rock、Americanaのフレイヴァーが程好くブレンドされたサウンドをDan Israelは創造するのだけれど、派手さとは無縁な作風だったので、改めて地味と喧伝する必要は無いとも思う。
だが、根本で地味なバンドなのだから、更にくすんだカラーの重たいナンバーを頭に持ってくると、アルバム全体がかなり沈んだトーンを纏って見えてしまうのだ。事実、#1にはアルバムをかなりローファイなロックアルバムと錯覚させる効果がある。
このためか、筆者も実を述べるとこのアルバムは2002年の秋にトップレヴューで紹介する予定だったのだが、ここまで延びて、しかもトップに配しなかった経緯がある。
また、本作を地味に見せているのには、この「Love Ain’t Cliché」がこれまでのDan Israelの全てのアルバムの中で一番ロックカラーが強いからということも関係していると思っている。
#2『Don’t Feel Like Laughing』や#3『Friend In This Town』はとてもコマーシャルなラインを持ったロックチューンであるけれども、これまでのThe Cultivatorsが持っていたリラックスしたAlt-Country的なロックナンバーよりもかなりラフでハードとまでは言わないが、ロックンロールを掌に掴める如き馬力を感じることができる。
#1から#3までの、既存のDan Israelよりもかなりヘヴィなロック攻勢が強いインパクトを持ったため、地味プラス重たいロックアルバムという印象が先走ってしまい、このアルバムはいまいちかなという第一印象が強くなってしまったのだ。
このため、最初は評価が「Mama’s Kitchen」より低かった。やはり『All Alone』のハート・グラスピーな最上クラスのナンバーが冒頭になかったためだろう。
しかし、アルバムを聴き込むにつれて、全体の流れとしてはこれまでのどのアルバム−アクースティックソロ作も含めて、最高の完成度を誇っていると理解できるようになった。これが極最近のことだ。
「Love Ain’t Cliché」を少し侮ってしまったことに対して、Dan Israel氏にこの場を借りて謝罪しておく。
実際に、良く耳を傾けると、『All Alone』クラスのナンバーは結構トラッキングされていると思う。
#7『Feet In The Water』は滑らかに延びるオルガンに、これぞMinneapolis Pop/Rock(筆者が勝手に作ったジャンル)の真髄としか言いようのない軽快で胸弾むロックアンサンブルが乗っかる最高のポップチューンだと思う。
こういったナンバーはJayhawksには出来なかった少々泥臭いセンスとロックンロールサイドに力を入れた方向性が活かされている。
極端にCountry RockやAlt-Countryに傾倒しない点ではボストン周辺の東海岸のRoot Rockに通じるところがあるとも思う。
#8『Overloaded』のギターが気持ち良く歌うアップテンポのアーシーさとロックのスマートさがバランス良く共存しているトラックや、#5『Killing Time』の前半はアクースティックな牧歌さを演出しておき、メインヴァースに入るとトラクターで荒地を掘り起こすが如きガツンと芯の入ったナンバーがそういったカントリー・ミュージックを使わずにルーツという要素を出そうとしている音楽を連想させる。
また、#8ではCheap TrickのTom Petersonがベースとしてゲスト参加しているのには驚きだ。これはSwag関連からの繋がりかもしれないが。
が、やはり東海岸のロックバンドよりはタイトというか固めのロックなスクウェアさが中西部の大地の広大さを代弁するかのように少なめではある。これは優しさとか大地の豊穣さが、都会的な東海岸ベースのルーツサウンドよりも豊富であるミネアポリス・サウンドの特徴であると考えている。
また、Alt-Countryのトラッドな感覚を普通にPop/Rockに混入させることのできる才能がDan Israelには備わっているのだ。
#4『Jump Through The Rings』はアクースティックな柔らかさを基本にしつつ、ソロ作とは異なり、オルガンを始めとするリズムセクションやエレキギターもアンサンブルの補助に加えたフォークロックを背景に思わせるナンバーである。
#12『The Knot』もCountry Rockのフレイヴァーを漂わせつつも、良質なメロディとクリアなリズムセクションの導入により、野暮ったさよりもテンポの軽快さでルーツポップを堪能できるアレンジに仕上げており、単なるAlt-Countryという次元で語れない良作だ。
#9『Dark Corner』はホンキィなピアノを加えつつ、カントリーの味わいがこのアルバムで最も直接的に出されたローカルな雰囲気の漂うナンバーである。スライドな音色のギターがお気楽な音色をヒネクリ廻すが、しかしこのナンバーもそのままCountryとはならないところが、Dan Israelのセンスだ。複雑でユニークなルーツポップとしての印象が単なるCountry Rockのナンバーという単純な決め付けを凌駕している。まあ、そこまでしゃっちょこばった曲ではないのでお気楽に楽しんで聴けばいいと思うが。
更に本作ではこれまでにはなかった新境地への挑戦、裏返せば多彩な音楽性への追求がなされている。
#6『Hey Kid』や#10『Sandbag』のドラミングは明らかにR&Bを意識しているし、アクースティックなギター弦を中心に据えつつもオルガンをウネウネとバッキングさせるようにルーツ・フィーリングとR&Bミュージックの融合を意図したところが見えている。
しかし、この2曲ともに、R&Bを感じさせるが、しっかりと南部風のライトなルーツ感覚をコアにしたナンバーとして仕上がっているので、他の流れから浮いてしまっているような失敗は感じない。寧ろアルバムに凹凸を付ける曲として成功している。
トランペットを加えて、レゲエのリズムやメキシカンな雰囲気を醸し出した#11『Never-Ending Circles』も結局はルーツィな安定感のあるポップナンバーとして無難過ぎるくらいに集束している。
この普通過ぎるように見えてしまう纏めとアレンジと曲創りの巧みさが、地味な作風となってしまうのかもしれないが、地味であるけれども、没個性に非ず、そして曲ごとのインパクトも薄くないというところがDan Israelの凄い点であると信じている。
「ラヴ・ソングを書くことは僕は得意ではないんだ。」というDanのコメントを証明するように、このアルバムのナンバーは殆どがメッセージ性の強い非ラヴ・ソングばかりであり、9月11日の悲劇を暗喩的に歌った#2のようなソーシャルソングも見受けられる。かなり深い詩が多いので是非とも傾聴して貰いたい。
その中で、最後のナンバー、#13『Wasn’t Last On Me』はラヴ・ソングらしき曲だ。ストリングス・シンセとキーボードを細かく使いつつ、アクースティックなバラードに仕上げている。曲のタイプとしてはオーソドックスだけれども、ラストのナンバーとしては余韻が残るしっとりとしたメロディとアレンジがお定まりであるけれども的確だ。
以上、よくよく聴き込むと、Dan Israelのアルバムとしては最高傑作にランクアップした「Love Ain’t Cliché」を語ってみた。Dan Israelの経歴については、これ以外のアルバムをレヴューする時に述べたいと考えている。
それにしても、「Love Ain’t Cliché」=「愛は陳腐なものじゃない」というタイトルの割にはラヴ・ソングが少なかったりするのは面白い。
また、ジャケットがキャンディのようなデザインになっていて、各トラックには味やカラー、素材の副題が付けられているところはCounting Crowsの「Hard Candy」と何処か似ている気もする。偶然であるだろうけど、どちらも名盤というのも少し笑ってしまうくらいの共通点だった。
2002年に2枚の良作を発表してしてくれたのは嬉しいが、今後のブランクがこのための反動で大きく開いてしまわないか、それだけが心配の種である。少し贅沢なタネだろうか。 (2003.2.27.)
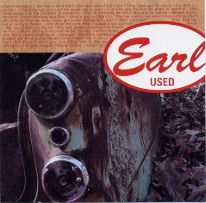 Used / Earl (2002)
Used / Earl (2002)
Roots ★★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Alt-Country Rock ★★★★☆
You Can Listen From Here
「Used」という短いがそれ故にタイトルの示唆する事柄への解釈が広範になりそうなアルバムのジャケットを見れば、このCDの創り手のサウンドが聴こえてきそうに思えないだろうか。
一見だけでは何の写真をジャケットに使用しているのかは掴み辛いかもしれないが、廃車になったのだろう撃ち捨てられ、錆びが拡がった自動車が横倒しになった構図をジャケットに取り入れるバンドが、芸術的で緻密なサウンド構築をすることはあまりないだろう。
実際にその通りで、簡潔に叩き割ると、
小細工ナシ!!
という誉め言葉・・・・誉めてるかな?・・・・がとても似つかわしいバンドが、2002年の春先にフルレングスアルバムを自主リリースしている。このアルバムもレヴューしようとして常に後回しになってしまっていたのだ・・・。
Earlという単語は、紅茶のアール・グレイにも見られるように、その基礎は英国英語である。一般名詞の場合は、貴族階級の「伯爵」を意味する。当然Steve Earlのように人名でも固有名詞として使われる。
しかし、今回漸くレヴューをする運びになったEarlは、「伯爵」という卑俗なイメージでは「お上品」とか「金持ち」、「上流階級」といった−書いていて自分の貧困な連想に頭痛がしてきた・・・・−温雅に繋がる名前とは全く似ても似つかない音楽を演奏している。
ちなみにEarlという名前が付いた経緯については、フロントマンのJimmy Kennedyはこう述べている。
「僕達が名前を前のバンド名であるBenderから変えようと喧喧諤諤やってた時、あるヤツがこう言ったのさ。『Earlってのはどうだい』って。僕等は言ったね、『冗談じゃない、そんなの絶対にイヤだね。』と。
するとソイツは4メートル近い横断幕を引っ張り出してきたんだ。それにはCDのジャケットのロゴにもなっているEarlのシンボルが描かれていた。この広告はガソリンスタンドの案内用に配布されたものだったんだけど、横断幕と一緒にたくさんのステッカーも付けられていた。で、当然ステッカーはタダだったんだ。
『こりゃ、バンドの宣伝にタダでステッカーを使えるね、名前をEarlにすれば。』ってことで名前が決まったんだな。」
という即物的な事情があるのだけれど、音楽的には即物的というか商業的な色合いからは程遠い。
このEarlというバンドは、とても純粋で純粋で純粋なAlternative Country Rock=Alt-Country Rockを、さあどうだ、と云わんばかりに眼前に付き付けてくれるロックバンドである。
1990年代の後半からこちら、Alt-Countryというジャンルは完全に独立したミュージックとして定着するようになったが、21世紀を向かえた現在は、ナッシュヴィル周辺のカントリー・チャート向けCountry Rockに対するアンチ・テーゼという解釈で分類されるようにもなっている。
また、Alt-CountryとAlt-Country Rockという更に進んだ定義付けも行われるようになり、その正確な解釈は困難になりつつある。
これにAmericanaという比較的新しい音楽ジャンルまで加わり、Country RockやRoots Rockを含めて、様々な解釈の余地が生まれそうな様相を呈しているのが現状だ。
始祖、という意味合いではAlt-Country Rockの源流はGram Personsとする見方が強いが、やはりこのAlt-Countryという単語を広く膾炙せしめたのは、「No Depression」というアルバムタイトルが21世紀現在もAlt-CountryやCountryの全米で最も老舗で権威のある専門雑誌名として冠される作品を世に出した、Uncle Tupeloだろう。
1980年代にアンダーグラウンドで盛んにプレイされ確立された、Cow PunkというCountryとPunk Musicの両方を追求したカテゴリーから、よりGarage PunkとCountryの配合率が均等な融合音楽へと昇華させたのは紛れも無くUncle Tupeloだった。
また、Uncle Tupeloが評価されるに従い、Alt-Countryという単語が一般化し始め、数年後にはひとかどの地位を築くに至ったのである。
もっとも、「No Depression」と「Still Feel Gone」では確かにAlternative Country Rockのモールドと定めるのが当然の如くなガレージ・サウンドとカントリーのブレンドの具合が宜しかったが、R.E.M.のPeter Buckがプロデュースした3枚目の作品「March 16−20,1992」では全体の3分の1近くトラディショナル・カントリーな曲を取り入れた、パンクロックと伝統カントリーの両極端な方向性へ鞍替えしたのを契機に、それ以降はAltよりも単なるアングラなカントリーバンドの残りカスを燃やすようなバンドにかなりの部分が変質してしまったように思え、3作目以降のUncle Tupeloは筆者としてはそれ程高評価にはなっていない。特に何故か一般で持て囃される3枚目は虫が好かないのだけれども・・・・。
しかし、Uncle Tupeloの「March 16−20,1992」の音楽を聴けば理解できるだろうが、こういった単純な温故知新もAlt-Countryという見方をされていることから推し量れるように、Alt-Countryは当初の定義から拡大解釈をされ続け、最近はAltやRockの部分よりもCountryの体積がウェイトの大半を占める音楽ですらAlt-Countryと評される傾向が強い。
というよりも、独自にアンダーグラウンドなカントリーを演奏していると、それだけでAlt-Countryのレッテルを周りが貼ってくれる模様ですらある。
よって、海外の音楽レヴューに「格好良いオルカンのバンド」と書かれていたという理由でそのCDを購入すると、ドが付くカントリーに申し訳程度のロック“モドキ”がプラスされたアルバムだった=筆者的には地雷を踏んだ、ということが殊に1990年代後半は高確率で起こり、被爆の度合いが高かったものだ。
かなりジャンルと定義論に話題の秤が傾いてしまったので、このあたりでEarlの話題に戻すとしよう。が、Earlを語るには1990年代後半からのAlt-CountryやAlternative Country Rockの風潮を対比として記しておきたいので、今暫く話を引っ張ることにする。
この場で述べたいことは、単にAlt-Countryといっても、本来のガレージやパンクサウンドから掛け離れてしまった存在が近年多くなっているという現状があり、それを、カントリーは場外ホームランとして地球外にかっ飛ばしたくなるくらいに嫌いで、反面土臭いロックサウンドが最高に好きという非常にアンビギュアスなラインを跨いだ嗜好を持った筆者は、実に苦々しく思っている。これなのである。
下品に叫べば、
「おめ〜ら、Alt-Countryって自称するんやったら、ロックせえ、ロックを。カントリーに毛の生えたトラッドサウンドでお茶濁してど〜すんじゃ、ボケ!!」
てな感じ。だから、ルーツ回帰をただのカントリー・ミュージックの追求としている新人バンドや新世代のミュージシャンにはイロイロと失望させられてきている。
そうやって痛い目に遭いながら、矢張り心のどこかで「本当の意味でAlt-Countryを再現してくれるバンドは出ないものだろうか。」という期待は悲しきファンの性でしっかりと持っていたりするのだ。
そこで、Earlである。
AmericanaとかRoots Pop/Rockという比較的カントリーのウエスタンさやライト過ぎるあからさまさがモデレイトされたジャンルが最も好きなピンポイントに当たるが、それとはまた別に、
ロックでありつつ、Alt-Countryなサウンド。
こういったラフな草の根ロックンロールもやはり欲しい。
この願望を具現化してくれたのが、Earlなのである。
彼等の音楽を言い換えた表現に以下のようなものがある。
Hi−Octane Roots Rock、と。
云い得て、絶妙である。確かにAlt-Country Rockの基本とは直前に著したけれど、それイコール基本的なRoots Rockであるとほぼ同義であると考えているからだ。
ここで、Earlのメンバーが自らを語っている文章を紹介してみる。
「僕達は、出来る限り要らないものを殺ぎ落としてシンプルな音を創ろうとしている。陳腐な言い方だけれども、オールド・アメリカン・ロックンロールがそれそのものだね。
余分なものは何一つ加えてないし、特別な仕掛けもサウンドには無い。僕達は労働者クラブや酒場のバンドに過ぎない。世界を変えなくっちゃとか何かを動かしたいなんて思ってもいない。単に楽しいからロックンロールをしているだけ。」 Jimmy Kennedy。
非常に正確にEarlの方向性を自覚しているし、実践もまた行われていると思う。
Earlはミズーリ州はセントルイスを基盤に活動するバンドで、1998年に結成されている。当初はBenderという名前で活動していたが、バンド立ち上げ後間も無くEarlに改名して現在に至っている。
地道に活動を続け、2001年末にはセントルイス周辺のインディのロック系アーティストを集めたコンピレーションアルバムである「Pajamas Party」に#2『Ellie』及び#9『Sympathy』の2曲が収録され、レコーディングのデビューとなる。
活動はミズーリ州に留まらず、隣接するイリノイ州のシカゴやカンサス州のカンサス・シティでライヴを開ける程度にサポートを受けている様子。
この「Used」を発表後には、Lynyrd SkynyrdとTed Nugentのライヴの前座にもピックアップされるようになってきている。Vigilantes Of LoveやChuck Berryの前座も過去に務めた経歴があるということ。
4ピースのバンドであるが、ライターでリードヴォーカル、そしてハーモニカを演奏もするリーダーのJimmy Kennedyの言にあるように、鍵盤やルーツ楽器のサイドワークを殆ど許さないシンプルな演奏を行っている。つまり、リードとリズムギター、ベースとドラム。これのみでほぼ12曲のフルレングスを作成しているのだ。時折、B3ハモンドが聴こえる気はするので完璧にキーボードレスではないと思うのだが。
先に説明しているように、Country Rockではなく、ハードでエネルギッシュなAlt-Countryのプリミティヴな根っ子を振り回すようなアーシーで野暮ったいロックンロールが身上のバンドだ。
ガレージパンクのワイルドな面と、カントリー音楽の田舎臭さは溢れ返ってしまうくらいに満載のルーツサウンドだけれど、この両者のバランスは実に良好。
Uncle Tupeloがパンクとカントリーのフュージョン化を推し進めた開拓者であるのは間違いないけれども、Tupelo程にはガチャガチャしていないし、遮二無二若さに任せて突っ込み、不器用なところを誤魔化そうともしていないのだ。
本人たちはソリッドに先端を尖らせ切ったサウンドを実行しているつもりだし、事実そうなっているだろうけど、荒削りな演奏の裏に円熟味がしっかりと感じられる。
その証拠にガレージ風の直球ロックンロールと、カントリー起源の土臭いザワリとした音とメロディの融合はUncle Tupeloとは比較にならないくらいに巧みで、ポップ。基本は非常にポップだ。
ガレージの神様的扱いをされているThe Replacementsはガレージの喧しさだけが特に初期のアルバムでは鼻につくけれど、Earlのサウンドは全く五月蝿いとは感じない。それよりも重量級のキックをサンドバッグに叩き付けるような痛快なロックビートが腹にズシンと響いて気持ち良い。
この点では初期のSoul AsylumやR.E.M.というガレージパンクとルーツの両者を取り入れようとしていたメジャーグループよりも遥かに上を行っている。
パイオニアではないため、インディシーンに甘んじているけれども、同時代に、仮にUncle Tupeloと同じ1980年代に活動を開始していたら、間違いなく始祖たるグループを食っていたことは筆者が保証する。
というか、
2003年3月にはUncle Tupeloの廃盤群がリマスターとボーナストラック付きで再発されるけれど、終ったバンドのCD買いなおすくらいなら、Earl買え!!!(手に入れてなかったらこっちも買うべし)
と声を大にして言いたい。
繰り返すが、Alt-Countryとしてでなく、Roots RockやAmericana RockとしてTupeloよりも全然程度の高いロックサウンドを聴ける。レイドバックした古典カントリーやTupelo関連に思い入れが無いなら、それよりも何よりもロックンロールが好きなら
Earl > Uncle Tupelo > Replacements > Early Soul Asylum
というランキングになる。田舎臭い何の変哲もない馬力本願なロックンロールならEarlの独壇場だ。
サウンドに奥行か余韻という深さやヒネリを期待してはいけない。こういったバンドは単に楽しく聴くことが一番なのだから。
フルレングスに先行して発表された2曲のうち、#9『Sympathy』のようにハーモニカを甘酸っぱく絡めてレイドバックなフィーリングを演出するタイプのナンバーは、他に#3『The Game』がある。
不器用にガラガラな声を精一杯に使い尽くして歌うJimmyのヴォーカルはとても流暢とはいえないし、説得力を伴って胸に迫るという感動もないけれど、#3や#9の素朴なメロディは心の奥にある昔懐かしい記憶を少し震わせるような誠意を感じる。
バラードに徹した#3と、ややダイナミックな展開を見せる#9では、やはり先陣を切って発表された#9の方がインパクトは強いと思う。ブルージーなハープが大活躍するという箇所は共通項であるが。
スローな流れを聴ける曲は他にも少しある。#6『The Lie』は少しエキセントリックなマイナーコードが突発的に姿を見せるロッカバラードである。アクースティックと時折押し寄せるエレクトリックなギターの攻守交替が聴きどころ。
アルバムの後半はロックですっ飛ばしていたアナログ盤ならA面を冷却する効果を狙ったかのようにタップリとしたスローなロックチューンが多いが、#9から#11までのヘヴィでありつつ土臭いルーツ感覚を阻害しないポップさのある曲が並んでいて、後半の山場でもある。
ザラザラに擦り切れたようなヴォーカルに感情を素のままにぶつけて来るギターの熱演が被さる#10『Pusher’s Blues』はタイトルはブルースでも実際はハードなルーツロックバラードになる。後期の産業ロックから足を洗ったCinderellaがレパートリーに加えると光りそうなトラックでもある。
#10と同じように斜陽や夕暮れの風景のコマが似合いそうなノスタルジック風味のバラード、#11『No.26(Somehow,Someday)』は前のナンバーよりもアクースティックな弦を強調したアレンジを見せる。また、クレジットには明記されていないが、B3オルガンらしきバッキングが低音量で演奏にも加わっているのは珍しいかもしれない。
対して、アルバムの動であるナンバー、つまりロックナンバーが残りの大半を占めるが、こちらこそEarlの真骨頂と呼べると思う。
Uncle Tupeloがソングライティングとスムーズさを身に付けていたら当時でもこんな曲を録音させたと思わせる、Alt-Countryなロックナンバーのスタンダードである#1『Long,Long Time』。固目のガレージ剛球なラインを薄めてルーツロックに引き寄せようとするハーモニカの音がブンブンと唸るロックギターと不思議な融合をしている。
Dirty Truckersがもっと田舎のバンドであったらこんなロックナンバーが増えたかもしれないと連想させる#5『Abigail』もひたすら周囲を顧みずに突き進むドライヴィング・チューン。ロデオを見ているようなロックンロールだ。
また、ガレージロックが強く表に出た#7『Highway Song』や#8『New Reality』のように暗いハードパンクが際立ってしまったタイプのロックナンバーも存在するが、ここでもハーモニカがルーツロックの領域に暴走しがちなガレージサウンドを留める役割を果たしている。
#12『Walter Midway』に至っては明らかに一発スタジオ撮りしている。歓声が重ねられていないので、スタジオ録音の合間にジャム的なライヴとしてのサウンドチェックをした折にスピンアウトしたトラックかもしれない。
このナンバーもスピーディで快感がある。
先行発表された#2『Ellie』もポップでルーツィなEarlの特性を具体化しているナンバー。良質なキャッチーさがAlt-Country的なアレンジで上手に活用されている。少し出来過ぎなポップチューンな気はする。Earlの勝負シングルの1曲というのも頷ける。
同様にミディアムなテンポでありつつ、ロックンロールの底力を感じさせる#4『Big Shot』と#2がEarlの将来性を最も暗示できているナンバーではないだろうか。直球のみのルーツバンドでは終らないだろう可能性を見せてくれる曲であるからだ。
2002年は某ゲーハー&デーブーなオヤヂのEarlのアルバムにはかなり失望した。(丸分かりだ。)しかし、只のEarlはロックとオルタナ・カントリーの原点を掘り出して再構築・改善したと賞賛できる好盤を届けてくれた。
Earlもまだまだ捨てたものではないかもしれないので、Sの頭文字なEarlはもう少しやることやってくれ。頼むから。
(2003.3.1.)
 Roadsigns For Astronauts / The Fountains (2002)
Roadsigns For Astronauts / The Fountains (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Modern ★☆
You Can Listen From Here
ジョージア州はアセンズを拠点に活動する、「インディバンドの中のインディバンド」と地元で評価されているThe Fountainsもこの「Roadsigns For Astronauts」で5枚目のフルレングスを迎えた。
これまでは1994年のデヴューアルバム「Welcome」(筆者が唯一未聴な作品。完全に廃盤。)から一貫して自らが設立したレーベルのF.I.S.T.
Recordsを通して発売を行っていたが、5作目でフォークロックやモダンロック、アダルトオルタナティヴと雑食系の色合いのあるレーベルであるI Town Recordsへと移籍。ローカルオムニバス盤に曲を取り上げられた以外では、初のローカルとはいえ、他レーベルからのリリースとなった。
めでたくも自主制作・自主リリースの環から脱出したのだが、このアルバムを発表して暫くしたら突然OHPが消滅してしまった。The Fountainsが活動を休止したのか、それとも単にホームページを閉鎖してしまったのかどちらかは現在も不明。
ただ、この5thアルバムを発売した後、暫くはアクセス可能だったし、もう半年近くURLが見つからないので、かなり不安を感じている。検索を掛けても、Fountainsという単語でのヒットは膨大な数に登るので事実上、The Fountainsの足跡をネットで追うのは厳しい。
ライヴのスケジュールページ等でも全くゲストとしてThe Fountainsの名前が出てこなくなってしまっているので、最悪The Fountainsというバンドは結成10数年を経て解散の憂き目を得た確率が高そうだ。
それにしても、Fountainsでヒットさせるとアホのように出てくるFountains Of Wayneは鬱陶しいの極限を超えてしまっている。只でさえ好きでないフニャフニャ擬似ポップタイプのバンドなのに、筆者の検索を阻害するとは万死に値するので何とかして貰いたい。つーか、消えれ。
Fountainの単語を名前に充てているバンドは結構存在するが、やはり本邦で著名なのはFountains Of Wayneであることは遺憾ながら確実だ。
しかし、あのようなB級ポップバンドの食い足りない中途半端ポップとは異なり、こちらのThe Fountainsはこれまではカントリーロック、フォークロック、オルタナティヴ、パンクロックという様々な音楽をミックスさせつつ、アーシーなルーツロックを創作してきた全然正統派な集団だ。
ここは声を大にして、The Fountainsこそ「本家の泉」であって、Fountains Of Wayneは単にレコード会社のリリースを盲追しているリスナーに支えられた柱も土台もスカスカの「砂上の楼閣」な音楽だ、と叫びたい。(ヲイオイ)
・・・・が、正直この「Roadsigns For Astronauts」は、純正のルーツロックアルバムとは云えない箇所が増えた1枚となってきている。
これまた誠に残念だが、Fountains Of Wayneのモダンなポップを思わせる要素が実はかなり拡がってしまっているのである。とはいえ、このアルバムが駄目ということでは決してないのだが・・・・・。
元々、これまの3枚(1stアルバムは未聴なため、判断は下しかねる。)で土臭いアメリカンロックというベースは共通しているが、かなり毛色の異なった作風を毎回ごとに打ち出してきているバンドではある。
前回のアルバムの方向性と新作がそっくりということは嘗て無かったように思っている。
これ故に、「Roadsigns For Astronauts」も新しい方向性を模索するグループというこれまで踏襲してきたアドヴェンチャーに沿っていると考えるべきなのだろう。
が、しかし、ここまでモダンでスマートなアレンジを施してきたのはやはり結構意外だった。New Waveというかなり広範な要素を指すジャンルのうち、パンクロックについては、特に2ndと3rd作でそれぞれ形を異にして追求されているのだが、今回はキーボードとシンセを活用したアーバンなポップセンスがかなり浮上している。
個人的には、これまでの3枚で一番良かったのは、4thの「Diamond Wheel」(2000年)だった。フェンダー・ローズピアノやシンセサイザーを初めて意欲的に演奏に参加させたアルバムだったが、とはいえ脱ルーツしているとかモダンなポップアルバムになったという訳ではなく、これまでの作品と同じようにドブロギターやマンドリン、ペダルスティールにバンジョーといったルーツ弦楽器をしっかりとフューチャーしたフュージョンルーツロックに仕上げていたからだ。
アクースティックでダウン・トゥ・アースなカントリー・ロックの手法を微妙に残した、然れどもコテコテのルーツサウンドに没入しない均整の取れたサウンド。これが「Diamond Wheel」の雑感だった。
完全に同系統ではないけれど、Edwin McCainのようなAdult AlternativeとTrad Rockが共存したアルバムと考えればそれが一番近いと思う。
それ以前の「Stamp」(1995年/廃盤)は、まるで1980年代のカウパンク・サウンドにガレージやオルタナティヴのヘヴィさが顔を出すようなパンクとオルタナとカントリーがバラバラと並んだものだった。
3rdの再発時にはジャケットが変更されている「Ideal Amusement」はオルタナティヴの色合いはかなり凹んだものの、依然ペダルスティールを使ったダスティな音にヘヴィなパンク風のハードサウンドが混在したAlt-CountryとAlternative Rockが交互に出現するようなロックアルバムだった。
この3枚目までのオルタナティヴが入ったルーツアルバムという、微妙に筆者の好みの境界線上に位置する作風よりも、「Diamond Wheel」は遥かにポップでアクースティックなアレンジがくっきりと浮き出ている良作だった。
これまでにルーツロックのベストなポイントを発見するために、長い間暗中模索であったThe Fountainsが到達した最高峰とは云わないが、最長不倒距離と思わせたのが、2000年発表の前作だったのだ。
この「Roadsigns For Astronauts」に至るまでに、The Fountainsが単なるカントリーロックやベタベタのサザンロックを選択するようなローカルバンドではなく、もっと普遍的なルーツロックを追い求めるグループということは理解できていたので、今作もすんなりと賞賛できるアルバムにはならないかもしれないという、漠然とした予感は確かに存在したのだ。
幸いにしてWilcoやHoneydogsの如く、無様に脱ルーツロックして捻くれ曲がりパワーポップサウンドを創るという醜態を晒すことなく、デビュー時から錘石としていたルーツサウンドをしっかりと掴んだサウンド構築はしてくれているので一安心だ。
けれども、前述のようにモダンポップ、野暮ったさが薄れたアレンジが相当押し出されている。
別の表現をすれば、UKサウンド風のPub Rockが幅を利かせた感じのルーツロック作品となっているのだ。
この変化は時代と共にアーシーな感覚を投棄するように減らしているCollective Soulの最近作とデビュー時のサウンドの差までには極端ではない。
繰り返すけれども、しっかりと土臭い手触りを持つ音楽性は土台に据えているからだ。こういう方向ではWallflowersの「Bringing Down The Horse」に共通する点があるかもしれないが、この名盤ほどにはメジャーなPop/Rockとルーツサウンドの折り合いは付け切ってはいないことは確か。
正直、「Diamond Wheel」で固まってきた確たる舵取りに安住せずに、また未完成なロックサウンドを探す冒険を開始したような印象を受ける。そのくらいにあちこちへと手を伸ばしてトライを行っているアルバムであると見なしているのだが。
筆頭のナンバー、#1『Colors』からして、かなりこれまでのThe Fountainsと比べると変り種の曲になっていることから、「Roadsigns For Astronauts」でのやりたいことが推し量れるというものだ。
#1でのパーカーッシヴなドラムとパーカッションのリズムは、かなり泥臭い要素とは離れた空気を曲に持ち込む。アフリカンというかカリビアン的なエスニックリズムと1960年代英国ポップバンドやBeachboysが好んで実践しそうなコーラス主体のアレンジ。
アクースティックでTwangyなギターはあくまでも控え目に鳴らされ、ア・カ・ペラなソングの雰囲気もあるこのナンバーは文字通りアルバムの『Color』を普通のルーツロックや南部ロックで落ち着かせないカラーリングを施しているようにも感じる。
#2『Follow The Down』は、ジョージア州というバックボーンを濃く反映した、ヘヴィなルーツギターが低く浮遊するミディアムだが馬力のあるロックナンバー。しかし、あまりねちっこいサザン・ロック特有の重さを感じないところが、このバンドの味だ。Collective Soul程にはオルタナティヴサウンドを活用していないけれども、このギターのロックビートには都会的な無機質さをそこはかとなく感じる。
#2を聴いていると、やはりThe Fountainsが1990年代の影響を受け、1990年式の音を創ってきたバンドだと解することが出来ると思うが、同様に馬力のあるギターが噛まされた#3『Sold The Car』になると、ハーモニカが加えられるし、#2よりもハードにスライドするギターが一層ルーツ的な要素のメートルを上げている。
しかし、ここでも素直にサザンなルーツロック曲として収まることをしないで、北欧や英国のポップバンドが頻繁にアレンジする高いバックコーラスをエンドレス・パターンで、「Chu,Chu,Chu・・・」と些か気合が抜けたように繰り返させることで、これまた田舎ロックとせずに、モダンな衣で包んでいたりする。
ここまでは、しかしオルタナティヴよりもルーツロックとしての大地に繋がれたサウンドが強かったけれど、#4『Hat On A King』になると、前半は少しアーシーなAlternative Rockで、少しシティ風のタイトさを演出し、曲の後ろ半分に差し掛かってからは、頭で見せていたモダン・サウンド的な浮遊感をかなぐり捨て、完全なヘヴィロックに持ち上げていたりする。こういったナンバーではカントリーやアメリカーナの要素を匂わせることはない。
#4を聴くと、このバンドがかなりオルタナを意識したルーツアルバムになるような予想をするかもしれないが、これまた次の曲で全然違うことをやってのける。
#5『I Can Be The Man』はアコーディオンを隠し味にして、R&B風味に調理した、南部トラッドにアーバンポップの黒人音楽が融合したような不思議なナンバー。これも言ってみれば、ヒネクレ系のトラッドポップに分類されるようにも思える。
直前で、ヘヴィなギターを捻り出していたバンドが出すような音ではないような意外性がある。
すると、今度は冒頭の#1に戻ったようなフワフワしたアンダーグラウンド・ポップソングが顔を見せるのだ。
#6『Winter』は英国New Waveの旗手であった(まだ現在進行形?)XTCやDoug Powellが好んで取り上げそうなローズ・ピアノの音とマイナーコードをメジャーラインに複雑に絡ませて押し出しているソフトなナンバー。
ここでは、南部のバンドということを忘れそうになるくらいダウン・トゥ・ザ・グラウンドな乾燥したアレンジは皆無。ウェットというよりもアンビエントというべきだろう。
同様に#7『In Here Out There』もムーグシンセサンプリングをチョロチョロと鳴らして、スローなワルツを奏でるアンビエントタイプの曲だ。
けれども、密かに聴こえるマンドリンの音色とか、口笛、そしてゆったりとしたトラッド風のメロディ創りが、このアーバンなポップソングに、不思議なアーシーサを追加し、何とも名状し難い仕上がりにしている。#6では全く匂わせなかったトラッドな土臭さが入っているナンバーだ。まあ、ルーツ系という分類ができそうな曲であるのだけれど、こういったナンバーばかりだとやはり嫌だが。
中盤で変にフニャ〜とした曲が続いてしまったが、#8『Never Say Goodbye』と#9『Good Sam』そして、#13『Get On』の3曲はハードエッジなロックチューン。
#8『Never Say Goodbye』はスピーディでそこそこなキャッチーなメロディをもった爽快なロックナンバー。かなりオルタナティヴ的なギターアレンジも見受けられるけれど、必要以上にノイジーにしない匙加減はやはりこのバンドは単なるオルタナティヴに終始しない意図があると伺えよう。
対して、かなりオールディズ風の古典的な、言ってしまえばThe Beatlesの影響があからさまに出ているビートから始まる#9『Good Sam』は、コーラスの入れ方、ギターのカッティング、ドラムのリズムといい、英国ロックの古き善き時代を懐かしむような作風。これに現代的なオルタナ・ロックの硬さが微妙に溶かし込まれている。
#13『Get On』がこのアルバムの中では一番気楽にロックンロールとして聴けるシンプルなナンバーだろう。現在売れ筋でもあるPunk Popのメジャーバンドが演奏しても全く違和感のないキャッチーでストロングエッジの痛烈なロックチューン。
ここまで元気にギターを暴れさせると、少々ヴォーカルの弱さ、特にロックチューンでは歌い負けてしまう傾向があることが判別できてしまう。とはいえ、ヴォーカルとしてはGaryとJeffreyの兄弟ツインヴォーカルは決して悪くない。
寧ろ、#10『Please Don’t Ask Me Your Name』や#11『Coda Made For Radio』といったピアノをフューチャーしたスローバラードに於いては、鼻に少し掛かった声は威力を発揮する。
この恣意的に並べられたと思われる、2曲のピアノを入れたバラードは似ているようで結構対照的。
#10『Please Don’t Ask Me Your Name』はかなりデリケートなルーツバラードである。アレンジもピアノを中心にして、リズムセクションやギターを極力抑えてはいるが、アンサンブルの妙には気を配ったアレンジを施している。南部ジョージア州のバンドというよりも、より一般的なロックバラードとして染み入る曲だ。
#11『Coda Made For Radio』は、少し調子ハズレのサイケディリックさはあるにせよ、#10以上に静謐に始まるアクースティックなバラードと思いきや、1分を経過すると、ノイジーに螺旋を描くギターがガツガツと蹴り上げる産業ロック全盛の頃を思い出させるようなパワーナンバーにもりあがっていく。が、ここでもやはりオルタナティヴの無軌道さを感じてしまうのは、The Fountainsが現代のバンドという証拠だろうか。
この2曲の後に来たために、霞んでしまっているのが、#12『The Fall』。モダン・フォークというジャンルに入るのだろうか、フォーキィさとモダンビートが同時に表現されているメロウなナンバーだが、如何せん線が細いか。
繊細さでは似通った最後のトラック#14『Who Hang The Moon』はツイン・ヴォーカルの効果もあるだろうが、最もカントリーを感じさせる曲になっている。「Diamond Wheel」ではこのタイプのアーシーでフォーキィなナンバーがかなり見られたが、このアルバムでは、モダンアレンジのフォークナンバーにほぼ入れ替えられてしまっていたので、この素焼きの器のようなナンバーを聴くと不思議に安心できるのだ。
The Fountainsは1990年代の初めに、ジョージア州のアセンズで結成されている。
中核となっているのは双子のミュージシャンであるGaryとJeffreyのAndrews兄弟。この双子デュオにドラマーのJeremy Allenが加わり、ベーシストのJonny Hambyが加わって、1992年くらいからThe Fountainsを名乗る。
Andrews一家は音楽家系で、双子の祖父と大叔父はFountain Boysというバンドを結成して1940年代から50年代まで地元の人気楽団として活躍していたそうである。
途中、ベーシストだけ2回ほどの交代があったものの、他の3名は2002年の5枚目のフルレングスまで全くの不動を誇っていた・・・・・。
のだけれども、最近の動向が掴めないのは最初に記述した通りである。
南部ロックの発信地の1つであるジョージア州のバンドであるが、極端にルーツロックに拘泥することなく、これまでに1990年代型メジャー感覚を取り入れたロックアルバムを作成してきている、少し風向きが変わっていれば、Sister HazelやHootie And The Blowfishのようにナショナルレヴェルでブレイクできた可能性があるバンドだ。
もう少し作風が絞れていないため、インディに甘んじていることは否めないとは思うけど。
それにしても「Diamond Wheel」で完成形を創ったと筆者も感じ、一番評価されていた音楽性をかなりに渡り殺ぎ落としたのには驚いた。
ソングライターであるAndrews双子の創作の「泉」は枯れるところを知らないらしい。
しかもこの「泉」はかなりの濁りが混じってしまっても、飲料水に適する良質な水質を持っているようだ。これまでにあれこれと混ぜつつも、確実に基本のアメリカンロックの尻尾を抑えているからだ。
だからこそ、例えThe Fountainsというバンド形態を採用したGaryとJeffreyの音楽的探求が終っても、このライターチームにはこれからも元気に活動して欲しいと願って止まない。
The Fountainsはこれまでに4枚のアルバムを5000枚以上ライヴ会場とローカルレコード店で売ってきている。完全にインディのロックバンドとしては悪い数字ではない。
この「Roadsigns For Astronauts」は恐らく1000枚は優に売り切ったと予想している。それ以上のポテンシャルはあると思っているからだ。
次回が、6枚目があるのなら、今度は是非とももう少し焦点を絞ったアルバムにして貰いたいが、まずはバンドの存続を祈ることにしておく。 (2003.3.4.)

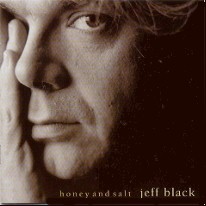 Honey And Salt / Jeff Black (2003)
Honey And Salt / Jeff Black (2003)