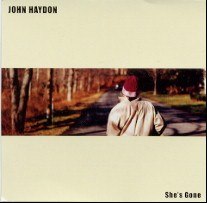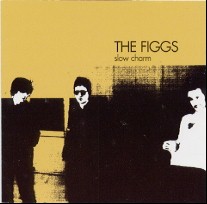Chasing Daylight / Sister Hazel (2003)
Chasing Daylight / Sister Hazel (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Southern ★★★ You Can Listen From Here
「Chasing Daylight」−「日の当たる場所を追い求めて」、とでも訳せば良いかな。
Sister Hazelの3年ぶり、4作目のタイトルは何とも示唆的な名前になったと思える。
1993年にフロリダ州のゲインズビルで結成されたSister Hazelは、常に「日の当たる場所」=「メジャーレーベルでの成功」を目指して活動していたと考えられる。少なくとも、地方の一人気バンドで小ぢんまりと終息してしまうような目標を掲げて演奏活動をしていたのではないことは明白だ。
リードヴォーカルにしてメインのソングライターであるKen Blockがバンドのメンバーを募集した1992年からこちら、Sister Hazelは決して流行に迎合することはないにしても、自らの出来る事を行うことで成功への道を模索し続けていた。これは以下のバンドリーダーであるKenの発言からも見て取れる。
「いつも何時も尋ねられるんだ、『最良の音楽シーンがあるエリアは何処だと思う?』って。
で僕たちはこう答えてきた。『何処の地域であれ君が成功したとしても、音楽シーンというものはバンドの成功によっては起こらない。音楽シーンの潮流というものは、自分の道を進んでいる人々によって創造されるのさ。』そして、僕たちが常にこれ以上のことを行いたいと目標にしている、こういった行為によって形成されていくんだ。」
自分で流行を作ってしまおうという発言に取れないことも無いけれど、寧ろ「意志あるところに道がある」という意味を含んでいる発言として考えるべきだ。良い音楽を創り、それをより多くの人々に聴いて貰うことで、自らが流行の一部を形成していくのだ、こういったポジティヴ且つアグレッシヴな姿勢を常に保持しているバンドだと考えている。
常に日陰者に甘んじることが無いように努力してきて、4年後の1997年にその結果をしっかりと現実に打ち出してもいることだし。
つまり、1997年には前年にセルフリリースした「Somewhere More Familiar」が、晴れてメジャーのUniversalからメジャー盤としての再発売をなされるに至るまでの成功は、決して漫然とマイナーバンドに甘んじていた状況で偶然に舞い込んだものではなかったのだ。運が全くなかったというとそんなことはないだろうけど。
また、このアルバムからカットされ、全米第11位まで上昇し、アクースティック・ヴァージョンやライヴヴァージョンというオルタナティヴまで頻繁にラジオでオン・エアされたシングル『All For You』が生まれ、アルバムはRIAA公認のプラティナ・ディスクを獲得。
一躍メジャーの人気バンドに収まる。更に、デビューアルバムの「Sister Hazel」までもUniversalからリイシューされて、メジャー発売されるようになった。一発当てただけでは、中々売れなかった時代の廃盤やインディ盤は再発してくれないのが米国のマーケット事情なのだが、こうも簡単に再発されたということは、1997年当時にSister Hazelの人気が如何に高かったかを物語ってもいる。
更に、3年の間を置いて最初からメジャー発売された「Fortress」も全米60位前後まで上昇というそれなりのヒットを記録し、シングル『Change Your Mind』も全米50位程度のスマッシュヒットを記録。
大ブレイクとまでは行かないが、それなりの安定したセールスを見込めるバンドという地位を得、筆者の評価云々は別として、このまま日の当たる場所を歩んでいくように思われた。
ところが、大コケした訳でもないのに、Sister Hazelの新作は1996年のオリジナル盤「Somewhere More Familiar」以来のセルフ・リリースと相成った。
ステータス的、市場での地位からすると、日の当たるスターダムから、日陰に落ち、再度「日の当たる場所」を追いかける立場に戻ってしまったと云えよう。
このUniversalとの手切れについては、ベーシストのJeff Beresがこう述べている。
「Universalから脱退することは正直不安だったよ。当初は、メンバー全員が望んでいたのはメジャー・レーベルと契約を結ぶことだったからね。でも今では最良の選択はメジャーから離れることだったと確信している。彼女と別れる時のように別離に対する心配は付き纏っていたけどね。
僕等はUniversalで仕事をしたことで多くを学び、吸収できたし、喧嘩別れしたのじゃないから関係は良好なままさ。
でも、時には分かれることがベストって状況もある。それが例えとても辛い選択だったとしてもね。
僕等は自分達のペースでリリースとプロモーションが可能だと信じれる量の音楽を拵えていこうと思い立ったから、最終的に自主リリースになった。」
実際には契約を渋られたかもしれないし、提示されたギャラが満足なものではなかったのかもしれない。現実問題として3作目の「Fortress」は2ndアルバムよりも相当セールスは劣っていたからだ。
が、バンドはこのインディ落ちという事態をネガティヴに捉えてはいない様子だ。寧ろ、フロリダ州やジョージア州で地道にライヴ活動を行いつつ、人気を徐々に上げていた頃の初心に立ち返り、再び「日の当たる場所」を目指そうという気構えが伝わってくる。そういう肯定的な意志が篭められたサウンドがこの「Chasing Daylight」で聴ける。
また、この一度スターダムを経験した後の、「日の当たる場所を追いかけて」という姿勢は、冷静さを加えたものであり、我武者羅にメジャーでの成功を追い求めるのではなく、バンド自らの正道に立ち返り、自分達が「日の当たる場所」と信じるフィールドで活動していこうというマイペースなゆとりすら感じられる。
これを老成といえば、枯れた感じになってしまうが、やはり成長の一環として捉えれることは確実だ。
実際に「Chasing Daylight」というタイトルは#2『Come Around』のアイディアから思いついたもので、そもそもの#2がKen Blockの友人がペルシャ湾岸から始まり、環大西洋海岸を旅した経験からインスパイアされて書いたものだということだ。
「Chasing Daylight」というタイトルのコンセプトに付いては、Ken Blockが以下のように語っている。
「人生というのは暗闇を抜けて、また暗闇に入るという連続かもしれない。でも暗闇に潜んで、闇を見つめているよりも日の光を追いかけた方がずっと良い。Chasing Daylightだね。希望のあるシチュエーションを追い求めること。
僕達の音楽は、僕達が希望を追い求めることを助けてくれるし、他の人達の助けになればとも思っている。僕達にとってSister Hazelの音楽はセラピーみたいなものだけど、他の人達にとっても僕達の経験してきたことは何らかのシンクロがあると思う。
だから、歌詞を書く際、僕達は膨大な労力と時間を要してわざと曖昧な部分を(勿論僕達はその曖昧なところはしっかりと理解しなくてはならない。)描き、多くの人が自分個人のシチュエーションに擬えることが出来る余地を残すように務めているんだ。
違う時代の様々な人々に対して色々な意味をもたらすことのできる何かを追いかける、そういった“日の光を追い求める”ことを僕達はやっていきたい。
叙情的な音楽や内省的な曲もやりたいけど、プライマリーでオーガニックなリズムを創っていきたい。深く考えることなく楽しめる音楽を。
時にはドアを閉めて、座り込んで考えることを為す音楽も良いね。けれども、運転している時にヴォリュームを上げて窓を開け放してアクセルを踏み、スピード違反の原因になるような音楽を僕達は供給出来ると信じている。」
と、人生前向きに行こうよ、というメッセージをリスナーだけでなく演奏する自分達にも訴え掛けているような示唆に富んだタイトルを冠した4作目「Chasing Daylight」であるが、実際に「Fortress」でかなり増量したオルタナティヴ的な重さや暗さを、台風一過の青空のように吹っ切ってしまった如くの出来になっている。
敢えて、こう断言してしまおう。
Sister Hazelが初めて放った大傑作且つ本格的サザンロックのアルバムが、これだ。と。
筆者にとっても想い出の深い、1996年のアルバム「...Somewhere More Familiar」は確かに素晴らしいカントリー風のPop/Rock作品だった。やはり出色は#3『All For You』から曲間を空けずに続く#4『Look To The Children』の2曲の流れだ。
また、セールスは大ヒットとは云えないまでもそれなりだったが、サウンドにかなりの翳りと失速振りを晒してしまった前作に当たる2000年の「Fortress」にしても、#1『Change Your Mind』から#3『Thank You』までの流れは完璧だったと思う。
特にスライド・アクースティックなインスト曲、#2『Back Porch』を間に挟んだ頭3曲は、アルバム全体の感触がSister Hazelの最高峰である「Chasing Daylight」を聴いた後でも、局部的な編曲としては最大の傑作、と譲れない評価として筆者の中で固定されている。
しかし、ロックアルバム、ロック作品として、ここまで完成度の高いアルバムは過去には見ることができないという考えは変わらない。
まだまだ不恰好さの抜けきれていない1作目「Sister Hazel」。1997年にリミックス、リマスターを施され全米50位前後まで上昇、ミリオンセラーを記録した出世作の「Somewhere More Familiar」もシングルとして良好な曲は非常に多いが、まだまだ完成度としては完璧とは言い難い凸凹が見て取れるアルバムだったと思う。筆者の個人的な好き嫌いは別として、Pop/RockだけでなくR&Bやブルース、レゲエにオルタナティヴとあれこれと手を出しているところが安定感に欠けているきらいはある。
そして、ヘッドの部分−3曲目までは完璧な本格ロック作だった「Fortress」。後半に移ろうに従って、加速度的にオルタナティヴ臭くなってしまい、典型的な竜頭蛇尾の作品に堕ちてしまったのは、現在思い出してもとても不満だし、残念極まりない。
その3rdアルバム「Fortress」で為し得なかった、オルタナティヴではない本格的なアメリカンロックを追求した一種の完成形態を、3年遅れてSister Hazelは実現してくれた。
2ndアルバムの繊細さと3rdアルバムの太過ぎたロックンロールをバランス良く融合させた、王道ロックの1枚。
とも云える。また、筆者のこの感慨はあながち的外れではない。それは、このアルバムを作成する際、バンドが根幹に置いていたコンセプトを紹介すれば判ると思う。
「今回はレコーディングに入るとき、『どのような曲を完成させるか』というような内輪のルールすら定めなかった。
多くの先人達がサザンロックにレゲエ、強烈なアクースティックサウンド、無駄を極限まで殺ぎ落としたサウンドや反対にたくさんの楽器を組み合わせたフル装備、という具合に様々なサウンドを持ち込んできた。
そこで僕達は、シンガー・ソングライターの柔らかさとハイ・オクタン価なロックバンドの直接性のギャップを埋める架け橋を目指した。
ノらせるダイナミックさを中心に据えているけれども、曲をその基本のみで運ぶことは絶対にしていない。
僕達は様々なアイディアを取り入れることが好きなだけでなく、それを演奏することが出来るバンドだからね。」
とSouthern Rockをベースにして、アクースティックとロックンロールの中道を目指したサウンドを創造するように心掛けたと読み取れる発言を、Ken Blockは残しているが、まさにその通り。
どのナンバーもしっかりと骨太の南部ロックの魂が篭められている。それでいて、アクースティックな生の音楽を手触りの感触として楽しめる有機的なサウンドをロックンロールのノイズに負けない程度に残している。というよりも、節々で顕現するアクースティックな弦楽器の音色が実に印象深いアレンジに纏めているナンバーが多い。
また3rd「Fortress」で陥った間隙−ロックンロールのダイナミズムを求めることが、メジャーのメインタイドであるオルタナティヴを呼び込んでしまった、というミステイクを見事に回避している。
これをAdult Alternativeと分類していいかはかなり微妙な線だが、このロックンロールリズムを損なわないキャッチーさが十全に活用されたメロディを鑑みると、AlternativeよりもPop/Rock、Rock n Rollという表現が最も相応なところだと思う。
デビュー以来不変の5ピースバンドであることは相変わらずだ。いい加減キーボードレスから脱却して欲しいとは思っているのだが、ここまで素晴らしいギターアンサンブルを見せ付けられると、筆者にしては珍しく、「4人以上のバンドで鍵盤無しは逝ってヨシ」の原則に当て嵌めずに賞賛できるバンドである。
2曲でハモンドオルガン、数曲でパーカッションがゲスト参加しているが、後はメンバーの演奏オンリーである。
だが、忘れていけないのはストリングス・セクションがかなり積極的に活用されていることだろう。
#1『Your Mistake』から、大仰になり過ぎず且つ曲に大らかな空気を吹き込んでいる弦楽器部隊が非常に的確なサポートを行っている。
このオープニングトラックがアルバム全ての雛型と云っても過言ではないだろう。
Ken Blockの掻き鳴らすアクースティックギターの爽やかな音色。
Ryan Newellが担当するスライドギターの、時にはハードに爆走し、時には枯れた哀愁を紡ぎ出す玄人仕事。
Jeff BeresのベースとAndrew Copelandのリズムギターにバックヴォーカルの確実な仕事。
骨太サウンドの根幹を支える、Mark Trajanowskiのパワフルなドラミング。
新人バンドの頃から、年齢に不相応な落ち着きと渋さで異彩を放っていたバンドだが、この「Chasing Daylight」で漸く年齢がサウンドの渋さに釣り合う程になった様子で、まさに脂の乗った演奏が聴ける。
そして、爽快でポップなメロディ。
このアルバムには『All For You』や『Change Your Mind』、『We’ll Find It』、『Thank You』のような強烈な牽引力とヒット性を有するナンバーは少ない、というか殆ど無い。
どのナンバーも#1程度にはコマーシャルでロックで優しいが、悪い言い方をすれば平均的なスマッシュヒットを望めるレヴェルの曲が並んだアルバムだ。
しかし、得てして無個性になりがちな「それなりな」メロディが一杯のアルバムなのに、各曲のクオリティがサザンロック基本のアメリカンロックとして非常に高い位置にあるため、全体のレヴェルは物凄く高くなっている。
別の言い方をすれば、どの曲もシングル未満な平均的アルバムとは対極の、どの曲もシングルカット可能な平均的アルバムと云える。キラーシングルに欠ける為、強烈なインパクトは不足がちになるが、聴けば聴くほどにその完成度が理解として深まるタイプの、長く愛聴可能なマスター・ピースだ。
よってどの曲も良質なロックトラックなのである。
オルガンが曲の太さを増している、#2『Come Around』はアクースティックとエレクトリックな対比がピリリと利いたファイン・ナンバー。
#3『One Love』はSister Hazelがデビュー時から言い続けている、「良いハーモニー」をしっかりと継続しているのが分かるコーラスワークが活かされたロックチューン。コーラスパートでの過激に責めてくるロックビートは圧巻だ。
#4『Best I’ll Ever Be』はストリングスとアクースティックギターが静かにバラードを歌い上げつつ、ジワジワと盛り上がる弱火で沸騰させた薬湯のような味わいのバラード。
最近は鳴かず飛ばずだが、1980年代後半に才能を全開に発揮していたソングライターのRichard MarxがKen Blockと作詞作曲を行った#5『Life Got In The Way』。Richardらしいポップでミディアム・アップなビートが光るロックナンバー。Heartland Rockの風格があり、今作がサウンド的にはメジャークラスであることを再度痛感できるトラックでもあったりする。
#6『Everybody』はかなりダウン・トゥ・アースなアレンジがリズミカルに踊るかなりキャッチーなロックナンバー。故郷フロリダ州のバックボーンを感じるカリビアンなリズムもそこはかとなく感じられる。
元気のよさでは#6に引けを取らない#7『Swan Drive』もグニャグニャと廻るスライドギターがリフで聴こえた時はハードなナンバーになると思いきや、コマーシャルでラフなロックナンバーに展開していったので驚いた。同時に安易にダークでダートな南部サウンドに落ち着かせないSister Hazelのメロディメイキングに拍手を送りたくなった。
中期U2を彷彿とさせる重心の低いミディアムロックチューンの#8『Killing Me Too』までは全くポップなレンジを逸脱する曲は存在しない。が、#9『Sward And Shield』で初めて、「Fortress」に多く収録されていた暗めのメロディが姿を表わす。のたうつストリングスとハードなギターを使った如何にもサザンロックなトラックだが、アルバムの箸休め的には悪くないナンバーだ。こればっかりだと嫌気が刺すだろうけど。
#10『Hopeless』は必ずといって良いくらい1曲はリードヴォーカルを担当するAndrew Copelandが、今回もリードを担当している。がバックコーラスのKen Blockのおっさん臭い声に完全に食われてしまっているのが涙を誘う。この曲はAndrewのヴォーカルよりも曲創りに元HeartbreakersのStan Lynchがクレジットされていることだろう。曲も1980年代のTom Pettyのカヴァーと説明されると納得してしまうような重めのサザン・ナンバーだ。
このアルバムでは#9〜#10が少し重過ぎる流れになっていて、ここのポイントが少し減点対象になっている。
#11『Effortlessly』は骨太のロックナンバーだが、陰鬱さからフリーなため、痛快な曲として楽しめる。曲自体のテンポが歯切れ良いのに加えて、楽器同士のバトルが熱く展開されるため、ついつい身体でリズムを取ってしまう。
#12『Can’t Relieve』はスライドな南部チューン。これまた後半の特徴だが、結構ヘヴィで暗めのアレンジとメロディが詰め込まれている。しかし、オルタナティヴとは全く違う次元のダークさであり泥臭さであり捻り方をされている。
つまりは典型的なサザン・ロックナンバーとなるのだが、これを考えると殆どの曲が南部を感じさせるのに、キャッチーなPop/Rockとして成り立っているのだ。ここがこのアルバムが王道ロックとして賞賛すべき第一の点だと思っている。
それにしても、メジャーから離れた第一弾が素晴らしいアルバムになるとは正直予想外だった。前作の3曲目までを何処かで再現してくれたら、という筆者の願望が実現された形なので、とても満足度は高い。
思えば、「Somewhere More Familiar」という良作でメジャーに出現し、「Chasing Daylight」という傑作でインディへと遷移していくという活動をSister Hazelはしていることになる。
恐らくは3年後になるだろうが、(これまでのリリース間隔を考えると)5作目がこのアルバムレヴェルになれば、またぞろメジャーレーベルが黙っていないと勝手に思いを巡らせている。
メジャー全てが悪いとは思わない。寧ろこの素晴らしい非オルタナティヴアルバムを引っ提げて、メジャーに残って頑張って欲しかったなあと、複雑な気持ちでいたりするのだ。
「Fortress」を聴いた時は、「次はインディに落ちても仕方ないな。」と手前勝手にぶった切っていた自分を殴りたくなった。(苦笑) (2003.3.14.)
 Hootie & The Blowfish
Hootie & The Blowfish
/ Hootie & The Blowfish (2003)
Roots ★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Southern ★★ You Can Listen From Here
Hootie & The Blowfishが初めてリリースした、カセットテープのみの作品は「Hootie & The Blowfish」というタイトルだった。形としてはデモ/プロモーション版ということで、主眼はレコードレーベルに配布されるために録音したものだが、ライヴ会場や地元のレコードショップでも販売されていたので厳密にはプロモーション・オンリーで仕上げられたカセットテープではない。
その“初代”4曲入り「Hootie & The Blowfish」が録音されたのが1991年。
そして、オフィシャルにはカウントされることが少ない、その幻のデビュー盤から12年後の2003年にHootie & The Blowfishは再度セルフタイトルを冠したアルバムを世に出した。
思えば、Atlantic Recordsからの3枚目である「Musical Chairs」から数えると5年ぶりの新作となる。そこまで久方ぶりに感じないのは、2000年に未発表曲及びカヴァーソング集である「Scattered,Smothered And Covered」を番外編として発売しているからだろう。このイレギュラーなイシューを間に挟むと3年ぶりのアルバムリリースになるのだ。
ちなみに、「Scattered,Smothered And Covered」をオリジナル・ワークに加えれば「Hootie & The Blowfish」は5枚目のアルバムとなる。個人的には2000年発売のレアトラック集はデモトラックや不完全な音源は全く含んでいないため、オリジナル作に準じると思っている。
けれど、まあB面集と考えると正規のラインナップに加えるのはどうかということもあるので、便宜上「Hootie & The Blowfish」は4枚目のアルバムということにしておく。
で、タイトルの話に戻るが、デビューからかなり経過したミュージシャン、殊にセールス的なピークを過ぎてしまった所謂下降線気味な人が、自分やグループの名前を冠したセルフタイトル盤を発売することは結構ある。
1stアルバムを出す時にセルフタイトルを使用することが、グループの名前を認識してもらうのに最も手っ取り早い手段であるので、そちらで使われることが一番頻繁だとは思う。
が、デビュー時にセルフタイトルを“温存”したミュージシャンは、勝負作としてセルフタイトルを付けたアルバムを出すことがままある。
結構、「活動が長いアーティストのセルフタイトル」=「勝負作、起死回生を狙ったアルバム」という認識が存在するようで、日本盤ライナー・ノーツでも「シンプルなタイトルで、原点に戻って〜」云々な記述を目にしたことはかなりの頻度で見受けられる。
ミュージシャンのインタヴューでも、セルフタイトルに賭ける意気込みというコメントはそこそこ見かけるので、あながち的外れでもないだろう。
然れども、前述のように頂点を極めている、またはセールス的に順風満帆な時代の最中にいるミュージシャンが、敢えてセルフタイトルのレコードを出すことは余り見かけないように思える。大抵デビュー時に使い切ってしまっているか、または、絶頂期を過ぎた後のアルバムに使われることが多い。例は敢えて挙げないけど。
更にプラクティカルな話になるけれど、ヴェテラングループやシンガーが、そうやって放ったセルフタイトルには、正直しょうむない駄作の方が絶対的に大数を占めていることのほうが比率として高い。
人気や販売の落ち込み、チャートの成績が振るわないことにストレスや焦りを感じているのか、ミュージシャンの言う「新境地」に挑んだアルバムが多く、しかもその挑戦に失敗して散々たる結果だけを残した汚点となる場合が、悲しいかな殆どだとも思う。
別のパターンでは、セルフタイトルではない1作目が予想外に売れたため、2作目でセルフタイトル盤を持ってくる新人というのもあるが、これまた1作目の予期せぬ高評価に考え過ぎたのか、愚にもつかない駄作を発表−所謂“2枚目のジンクス”に丸ごと当て嵌まる場合が頻繁に起こっていることも確か。
大変ネガティヴな見方を書いてしまったのだが、Hootie & The Blowfishの新作がセルフタイトルであることを知った時には、これらを踏まえてかなり嫌な予感がしたのだ。
3rdメジャーアルバムの「Musical Chairs」はチャートポジションこそ最高位全米4位を記録したが、最終的に総合ポップチャートには1曲のヒットシングルも送り込めず、かなり早足でTop200から退場してしまった。
全世界で1800万枚を売ったといわれる、「Cracked Rear View」や初登場で全米No.1を記録し数百万枚を売っている2作目の「Fairweather Johnson」からはトップ10ヒットを含む数曲のトップ40シングルが出ていることを考えると、明らかにセールス記録としては下降線を辿っている。
そうはいっても、非オルタナティヴなロックアルバムがチャートのトップ10入りするというのはCounting Crowsと並んでHootie & The Blowfish以外にはほぼ不可能だろうから、如何にバンドが広範な人気で支えられているかは理解できるが。
そして、レアトラック/B面集である「Scattered,Smothered And Covered」に至ってはトップ40アルバムにさえならなかった。
こういった事実を踏まえると、これまで数多く目撃してきた実例からして、ひっとしたら
「Hootieよ、お前もか!」
的な路線変更をしてしまうのかという不安が心の片隅に湧き上がってしまうのも仕方なかった。
また、2002年に中堅レーベルから発売された、リードヴォーカリストであるDarius Ruckerが放ったソロアルバム「Back To Then」が既存のHootie & The Blowfish(以下Hootie)とは全く異質な音楽ジャンルであるR&Bやソウル・ミュージックを歌った非ルーツロックンロール作品だったことも、不安に拍車を掛けたこともある。
もしかしたら、バリバリのヘヴィロックアルバムか、黒人フレイヴァー盛り沢山のブラックコンテンポラリーなアルバムになるのか、はたまた打ち込み多用のモダンロックを持ち込むのか、とネガティヴな想像がかなり脳内で生成されていたのだ。
さて、肝心のメジャー4作目は如何と相成っただろうか・・・・・・・。
結論から述べると、上記の心配は完全に取り越し苦労だった。一部を除いてだが。
#2『Little Brother』ではバンドとしては恐らく初めてドラムループを取り入れ、完璧なR&B黒人的ポップスなリズムをご開帳している。
また、#10『Little Darlin’』ではヒッピーなSEを出だしに挿入させ、キーボードや打楽器をパーカッシヴに練り込み、ソウル・ポップ的性格の強いリズムナンバーを見せる。
#12『Go And Tell Him(Soup Song)』では50年代のR&Bロックサウンドのポップさを見せたり、コンピューターノイズまで取り込んでいるが、全体の流れはファンクのアフリカンリズムを感じさせる。70年代ファンクロック特有のダイナミックでプログレッシヴなサウンドにも共通項を見出せる複雑な展開を見せるナンバー。
というように、これまでのHootieとしては絶対に出さなかったカラーを数曲で打ち出している。
しかし、基本としては極めてオーソドックスなアメリカン・トラッド・ロック、ルーツロックのアルバムという線は決して外していない。
寧ろバランスとしては、メジャー作としては少々ディープに傾き過ぎた南部とブラックサウンドの濃さ混入のため、クドくなり気味な2作目の「Fairweather Johnson」。
そして、カントリーな田舎臭さを特に後半で出し過ぎた3作目「Musical Chairs」よりもスッキリとしたメインストリームサウンドとして安定しているとさえ思う。
言わば、メジャーなPop/Rockアルバムとしては、かなり纏まりのある無難な出来映えということだ。
が、バランスの良さというか、平均的起用さ・優等生的なポップアルバムが即座に傑作となると同義でもないことは厳然たる事実である。
こういったオーソドックス過ぎる作品は、癖なく耳心地の良い好盤になるか、または、得てして印象度の低い平均点しか貰えない凡作に落ち着いてしまう。以上の両義性を常に内包している。
で、実際の「Hootie & The Blowfish」であるが、喩えるならこんな感じである。
五輪で金メダルが確実視されていたアスリートが、3位銅メダル獲得で終ってしまった場合に、「まあそこそこ頑張ったかな。」と微妙に賞賛と失望が同居した視線で評価できるアルバム。である。
言い換えると、
とある競技で優勝を期待された、「オラが村」の代表が、入賞で終ってしまった。
ガッカリではないけど、もう少し上を狙えたのではないんだべか、意外に延びなかったっぺ。
てな感慨を抱くアルバムだ。・・・・・・・分かり難いかな・・・・・・・。
Hootie & The Blowfishといえば、数少ない1970年代から続く正統派なアメリカンロックの歴史をメジャー・シーンで継承している数少ないバンドである。
実際に1990年代10年間で「ロックアルバム」としては最高のセールスを記録し、ロック時代の名盤として燦然と輝くビッグ・ショットな「Cracked Rear View」という足跡を残している。
ので、嫌が応にも、嘗ての大傑作をビヨンドしてくれという期待を持って新作を聴いてしまうのは仕方ない。デフォルトの期待が大きければ、普通の良作ではどうしても評価が辛くなる、という次第である。
身も蓋もない言い方だが、Hootieクラスのバンドならそれこそインディ・シーンには、売れない、だけでゴロゴロしていると思うし、現実にHootieのアルバムくらい売れて然るべきクオリティを持ったグループやシンガーもそれなりの数が水面下で活動はしているのだ。
とはいえ、実力だけでは数百万枚を売り捌けるビッグネームにはなることは現実不可能だし、幸運や時代性の後押しがあったにせよ、全世界に
「90年代のアメリカンロックはオルタナティヴやヘヴィロックだけでなく、このような普通のアーシーなPop/Rockもあるのだぞ。」
と知らしめた、また知らしめるキャパシティを有した作品を堂々と発表したという功績と実績がHootieにはあるのだ。
筆者としては、表舞台に上がる能力とサウンドを持ちながら、全く世間一般からは冷淡に扱われている良心的なアメリカン・ルーツロックを草の根活動で細々と行っている多数のアーティスト。彼らが世間に機会さえあれば広く受け入れられるということを実践で示している旗頭の一頭。これがHootie & The Blowfishなのだ。
だからこそ、生半可な良作や、そこそこの平均的なアルバムでは満足できないし、バンドサウンドとしてもよりメジャー感覚と古き善きアメリカのサウンドが同居した一昔前なら大メジャーな普通のPop/Rockを彼らに求めてしまうのだ。
大人しさ、滑らかさというメジャー・フィーリングでは確かに1st「Cracked Rear View」に立ち返った点はある。
しかし、1曲ごとに含まれるパワーは1stよりもトーンダウンしている。
云ってみれば、綺麗に無難にサウンドをプロデュースさせ過ぎな感覚が真ん中にあると思う。
これまで、メジャーと契約してからずっと起用していたプロデューサーのDon Gehmanを外し、全く新顔であるDon Wasを迎えたことが、それ程プラスにはなっていない。
筆者としてはDon Gehmanは「Fairweather Johnson」で濃い南部ブルースサウンドを取り入れ過ぎたり、「Musical Chairs」でも折角最初の3曲では胸のすくようなヒット性の高いルーツロックンロールを配置したのに、それから後は妙に商業カントリーっぽいブルーグラス的なレイドバックに拘りを見せたりと、行き過ぎな面がハナに突いたので、彼を外してくれたことについてはやぶさかではない。
これからバンドとしてより良いものを創造するには新しい舵取りとアドヴァイザーが必要だろうから。
しかし、Don Wasはどうかと・・・・・・。このプロデューサーが良い仕事をしたのは、Felix Cavalierの「Dreams In Motion」だけしかないと筆者は見なしており、正直3流プロデューサーの偏見から解き放たれないのだ。Felixにしても元来才能のあるシンガーであるからDon Wasがいなくても良い作品は作成しただろうし。
アーティストにフリーハンドを与えて才能を引き出すことには長けている人らしいが、Hootieのように相当な割合で完成してしまっているアーティストと組むとプラスアルファの相乗効果があまり見込めないだろう。
案の定、Hootieの持っているアメリカンルーツへの追求心のみに頼って、これだけの普通以上のアルバムは完成したが、これといってエポックメイキングな点は、過去3枚(または4枚)のメジャーアルバムと比較すると見つけることは困難と云わざるを得ない。
無難な基本的アメリカンルーツな1枚だが、これといってこれまでのアルバムと比して優れた点はなさそう・・・・。
仮に、新人のバンドがメジャー、インディに関係なくこのレヴェルと等価のアルバムをリリースしたなら、間違いなく筆者は絶賛するに違いない。
しかし、Hootieである。2000万枚以上のレコード売上を実績として持ち、アリーナクラスの会場を全米ではフルハウスに出来るバンドなのだ。
外したところはないが、既存の枠を打ち破れてない、更に上に到達したとはどうしても云えない程度のアルバム。
些か口は悪いがこう評価するだけだ。
手堅く骨組みを型どって、少しR&Bなビートを振り掛けて、新しいこともやったよ〜、とアピールしてみました。
こんな感慨を抱くだけ。
断っておくが、悪いアルバムではない。十分に及第点だし、聴き易さでは2作目、3作目の濃い作風が薄められたためか、1作目に匹敵するライトさが良いと評価するリスナーが多いかもしれない。
が、1曲1曲のインプレッションはやや薄め。これがこのアルバムの出来を「それなり」と感じさせてしまう要因かもしれないのだが。というよりも、
隠しトラックである#13『Alright』が一番Hootieらしいナンバーであるのもどうかと思うが・・・・・。
マンドリンをクリアに響かせた、スピーディで激烈ポップで土臭いところも抑えた、「これぞHootie」というナンバーの筆頭が、#12の終了後2分程度の空白を開けてトラッキングされている#13なのだが、シークレットトラックやボーナストラックが一番良いと感じるのは大概あまり本編が光り輝いていないアルバムの特徴でもあるのだ・・・・・。
それにしても、名曲『Only Wanna Be With You』をダブらせるこのナンバーは個人的にヒットしまくり。この曲を聴けただけでも購入した価値はあると筆者は思っている。
ファーストシングルになった#3『Innocence』はアクースティックギターのリフから、バリバリのメジャーコード進行でストリングスシンセサイザーを交えて盛り上がるというパワー・バラードの典型で、ヒット性は高い方。1stメジャーを出した当初のチャートアクションを期待すればトップ40シングルも容易いだろうが、最近のチャート事情からは総合ポップチャートでの大ヒットは難しい。
「Cracked Rear View」から常にサブメンバーであり、第5のHootiesとも呼ばれるJohn Nauが今作でもオルガン・ピアノと鍵盤類を一手に引き受けているが、Johnのピアノ、オルガン、サンプリングがバランス良くHootieの力強い演奏と絡む#1『Deeper Side』の軽快なミディアムロックの方が第一弾シングルには適当であったと思うのだが。
#4『Space』も#1同様に実にポップで歯切れの良いチューンであり、あまり多くないロックナンバーでもある。もう少しこういったロックンロールの粗さを掌で掴めるようなナンバーが多ければアルバムももっとインプレッシヴだったかもしれない。
#5『I’ll Come Around』そして#8『Show Me Your Heart』も#1や#4と同じく、効果的にオルガンが使用されている。両方ともサザンロック風味のバラードで『So Strange』を少しモデレイトした感じのバラードだ。こうやってポップ化することはアクを抜くことに近似していて歓迎すべきなのだがいまいちインパクトに欠ける。パワフルと濃厚さを同時に抜いてしまったというところか。濃厚な箇所だけ抜ければ良かったのだが。
同様に#6『Tears Fall Down』のアクースティック一辺倒なバラードも弱いし、最もレイドバックして女性ヴォーカルをブリッジとして参加させているバラード#9『When She’s Gone』も悪くないが、鮮烈さではそれなり。
唯一のカヴァーソング、というかオリジナル作では初のカヴァートラックの封入だと思うが、Continental Driftersの1999年のアルバム「Vermilion」からのピックアップである#7『The Rain Song』にはこの曲のライターであり、オリジナルを歌っている女性ヴォーカルVicki PetersonとSusan Cowsillがバックコーラスでゲスト参加している。
『Goodbye』に通じるところが存在する#11『Woody』は実に素直なバラード。ピアノ、シンセサイザー、ギターがしっとりとした雰囲気を漂わせているが、エモーショナルな説得力では『Goodbye』には及ばないかもしれない。
概して、真摯で真面目な態度は物凄く伝わってくる丁寧なアメリカンロックアルバムだ。
が、Hootie & The Blowfishとしては実に普通のレヴェルで納まってしまっている作品であると思う。
セルフタイトルをメジャーデヴューして9年目に持って来たのだから、もう少し、「Hootie & The Blowfish」を強く記憶領域に焼き付ける輝きの欲しいアルバムになっていることを期待したのだが。
あまり誉めてはいないけれども、標準水準から見ると凡作ではないし、絶対に悪くはない。昨今の破滅的なメジャー・シーンでは良心的音楽の上位に位置する。
聴いても損はしない。過度の期待が色眼鏡になっていなければ、だ。
最後に、日本盤は2ヶ月以上遅れて、2003年5月の発売になるそうである。
「Cracked Rear View」は5曲のボーナストラックに釣られて米国盤と日本盤の両方を買ったが、「Hootie & The Blowfish」はボーナスが5曲付いていても筆者は2度買いはしない。
これをもって本アルバムの最終評価としたい。 (2003.3.16.)
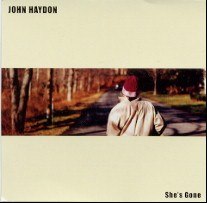 She’s Gone / John Haydon (2003)
She’s Gone / John Haydon (2003)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★☆
Alt-Country ★★★★★ You Can Listen From Here
John HaydonのOHPにはこのような紹介が、入り口でされています。
「Buddy HollyとHank Williamsを足して、その精神をRhett Millerの新しい世代の音楽解釈を調味料として入れて細かく混ぜたような音楽・・・」
そして、ホームページのバイオグラフィの頭には、こんな一文が寄せられています。
「Tom PettyとLucinda Williams、そしてJeff Tweedyの精神を引き継ぐJohn Haydonは、オルタナ・カントリー音楽そのものの最高峰です。」
ここには一点のみ激しく同意し兼ねる人物が含まれていますね。
云わずと知れた、Wilcoをエレポップなバンドに導いている存在です。今更多くは語りますまい。
が、こう考えたのは私だけではない様子です。
上にリンクした試聴可能なmp3.comでも、OHPと全く同じ紹介文が当初は掲載されていました。TomとLucindaそしてJeff Tweedyの名前が比較対象として挙げられていたのですが、何時の間にかそれがJay Farrarに摩り替わっていました。さもありなんです。
厳密には最近の、というかSon Voltを開店休業にして以降のJayも、Uncle TupeloやSon Voltでコンサーヴァティヴに追求していたAlt-Countryの権化なサウンドから次第に遠ざかりつつはあるとは思います。
しかし、Wilcoを正体不明のエレクトリックバンドに変質させたJeff程には異次元な変化を起こそうとはしていない点では、なんぼかマシな比較対象でしょう、Jayは。
素晴らしいAlt-Countryの良心と云うことに筆者が何の躊躇いも無い、このJohn Haydonを語る場合には。
まあ、mp3.comでも、流石にあの「米国東海岸北部系人種の宿泊所云々」というWilcoの地球資源の無駄使いに他ならない最低でWasteなアルバムを拵えたJeffと、John Haydonを同列で扱うことには抵抗があったのだと思います。
ここでJay FarrarをJeff Tweedyの代わりにしてしまっているという安直さには、幾分の興醒めがあるのですけれどもね。そうはいっても、一時期のJayやJeffが求めていた、アメリカントラディショナルなカントリー・ミュージックとロックンロールの融合という路線を、John Haydonがなぞっていることは確かです。
ですので、「最近の」という接頭語さえ切り離せるなら、John HaydonはJeffやJayが嘗て書いていたサウンドと並べて語られるには十二分に値するアーティストだと思っています。
というか、
Wilcoに“「A.M.」よもう一度。”を期待する精神的なエナジーを持っているなら、素直にJohn Haydonのアルバムを聴く方が絶対に生産的でしょう。
更に言ってしまえば、確かに「A.M.」はAlt-CountryとPop/Rockの融合の可能性を膾炙させたエポックではあったけれども、既に過去のクラッシックになってしまっていると思うのです。最早、「A.M.」の路線をWilcoが振り返ることはないでしょうから。
それに、
John Haydonの書く歌は、正直Jeff Tweedyを数万光年上回るものになってしまっているのです。
つまり、John Haydon>>>∞>>>Wilco(Latest)という図式が完成しているのです。
こんなこと書くと、根強いWilcoの信者に刺されそうですが、同一ジャンルとして比べることが不可能に近い最近のWilcoだけでなく、Alt-Country期にWilcoが放ったマスターピースである「A.M.」ですら、これまでJohn Haydonが陣頭指揮をと執って作成してきた2枚のフルレングスアルバムと1枚のEPと比較しても、何らプライオリティは見出せません。
結論は、「A.M.」聴くなら「She’s Gone」を聴いておくべきです、これですな。
単に本邦に限らず、知名度の差のみでWilcoは、John Haydonに先んじているに過ぎません。当然、John Haydonがエレポップやモダンメカニックなサウンドに手を出すとは思えませんので、この物指しは、Wilcoがルーツロックやオルタナカントリーと呼ぶことの出来た時代の作品と、John Haydonを比較したという限定的なものですけれど。
さて、何時までもWilco関連を叩いていてもスペースと容量の無駄なので、ここでJohn Haydonへと話題を戻すとしましょう。
John Haydonの経歴については、John HaydonがAnd Ten World名義でリリースした1stアルバム「Resolve」のレヴューでそれなりに解説しているので、そちらを参考にして貰えば幸いです。
これまで2001年の4曲入りEPも含めて、John Haydon And Ten Worldsというバンドを従えたネーミングで活動を行ってきたJohn Haydonですが、この2002年末に発売され、商業流通に乗ったのが2003年となってしまった2枚目のフルレングス作では、単にJohn Haydonという単独ミュージシャンとしてアルバムを発表していることがこれまでとの大きな違いです。
しかし、実際はAnd Ten Worldsの頃と内容に大差はない模様ですね。メンバーに若干の変動はありますが。
前作からベーシストがSeth Petersonという人に代わっている、このくらいが大きな変化です。また、レコーディング時にはPeter Weiseというミュージシャンがメインメンバーとして登録され、メロトロンやアクースティックギター、シンセサイザーサンプリング等を担当していますが、現在のJohn Haydonのバンドには加わっていません。
「Resolve」でもレコーディング時には正式メンバーだった女性バックヴォーカルがレコード発売後にはバンドには登録されていないことがありましたが、それと同じような状況でしょうか。
また、ドラマーのSteve Chaggairsと別のバンドを組んでいるオルガニストのKen Clarkもこれまでのアルバムに引き続いてハモンドオルガンでヘルプしています。
他にもJohnがベーシストとして在籍していたバンドのリーダーMatt Griffinもバックヴォーカルで参加ているのを筆頭に、これまでのアルバムから比較するとかなり多くのミュージシャンが演奏にクレジットされているのが特徴。とはいえ、6人程度なのですが。
12曲(隠しトラック1曲を除く)を書いているのは、ほぼJohnです。2曲のみ他のライターで、そのうちの1曲はベーシストのSethが提供しています。
ですので、これまでと演奏するメンバーが若干変化しただけで、John Haydonの音楽の骨子は殆ど以前と同じスタイルで作成されていると見ています。
サウンド的にも「Resolve」で打ち出したAlt-CountryのAlt-Countryたる、Alt-Countryの所以、という馬鹿が付くほど真っ正直なAlt-Country/Country Rockな路線からは逸脱をしていません。
が、それはJohn Haydonに成長が見られないという否定的な見方と同意ではありません。2001年のEP「This Time」で、1作目を凌ぐポップなメロディラインを打ち出してきたJohn Haydon And Ten Worldsですが、その好ましい変遷−1作目よりも親しみ易いポップさへとシフトしつつある−を継承しています、この「She’s Gone」では。
デビュー作での拙文で、「もう少しアップテンポなロックンロールナンバーがあっても良かった」な旨を書き綴っていますが、その点に関しては残念ながら、牧歌的なカントリー・フレイヴァー漂う音世界が今回もメインとなっています。
解説すると、Son Volt的な荒削りなロックテイストやカントリーパンクを武器にしているのではなく、カントリーにかなり近いPop/Rockにレイドバックな柔らかさを加えた、Alt-Country RockではなくAlt-Countryなバンド、ということになるでしょうか。
ここに東海岸北部諸州のマサーチューセッツ州のボストン周辺をベースに活動するバンドに頻繁に見られる、南部ロックの癖の強い音を、ルーツロックという希釈を通して、よりクセを抜いたサウンドにした、という音楽性を見て取ることも可能です。
米国中部の代表格であるミネアポリスのAlt-Countryやルーツロックもこのモールドに当て嵌まることが多数あるけれど、ボストン周辺の音楽は南部カラーがミネアポリス周辺のバンドよりも薄いという感想を抱いています。
そして、John Haydonに関しては、南部系の濃さよりも、不変的なカントリーサウンドを大きく取り入れたポップなロックサウンドということが彼の音楽性の解説としては適切ですね。
よって中庸性は東海岸のルーツロックシーンに頻繁に見ることの可能な線をトレースしつつ、それにフォークロック風の柔らかさとカントリー風の野暮ったさが強めに加わったアルバムというのが、今回もJohn Haydonが作成した音楽の印象となっています。
パワーポップに通じるエッジの刺さったギターサウンドにルーツロックの力強さが組み込まれたのが、ボストン・ルーツロックの傾向でしょうが、パワー・ポップのタテノリよりもナチュラルなトラディショナル音楽とアクースティックサウンドを際立たせた音がJohn Haydonです。
実際は、John Haydonはコネティカット州生まれであり、ニューイングランド州を中心に長く活動をしています。現在はボストンの衛星都市の1つ、ケンブリッジという街が彼のホームグラウンドですが。
しかし、ここまで基本に忠実で素直な音を出すと、単なるカントリーとして、特にルーツ系に馴染みのないリスナーには聴こえてしまう可能性は高いでしょう。HaydonのアレンジはCountryとFolkの純粋割合が高い方向性を有しているためです。
更に馬力でロックを押し通すタイプの音は出さないため、余計にカントリーらしさが突出した特徴になって耳に入る傾向も高いと予想されます。
ですが、矢張りJohn Haydonの音楽はポップでありロックであると筆者は思っています。アレンジとしてはカントリー臭さがかなり直截的に表現されていますが、Pop/Rockの大前提として必要不可欠なキャッチーさと親しみ易いメロディが備わっているからです。
初期のWilco−「A.M.」とか−やSon Voltにも同様に単なるカントリーという解釈が一部ではなされているので、John Haydonはやはりこれらの1990年代のオルタナ・カントリーのムーヴメントを立ち上げた先達の最もマイルドな分部を継承しているとも考えていいかもしれません。
さて、この「She’s Gone」は12曲プラス#1『This Time』のデモ・ヴァージョンがシークレットトラックとして最後尾に収録されています。
また、12曲のうち、#1『This Time』、#5『You Got Me Lost』そして#8『Where You Used To Be Tears』の3曲は2001年の先行発売の性格が強いEP「This Time」に収録された音源であり、聴き比べたところでは新録された様子はなく、そのままのテイクが採用されている感じです。
特に、#1と#5は軽快でアップテンポなリズムが目立つ、アルバムではロックンロールの色合いを強く放出するナンバーの代表格ですので、先行シングルに収められたのも納得というところです。
他に、#1のような軽快なロックビートを感じるのは、速さの差こそあれ、#3『Blue Sue』、#6『Could Have Said Goodbye』、#10『If You Could Be』、そして#12『Half As Much』でしょうか。
しかし、アップテンポな曲とはいえ、電気ギターのパワーによって突っ走るタイプの曲は皆無。アルバム内の他のスローテンポに属するナンバーと肩を並べた場合、速いという定規で見た場合ですね。
そして、ロックタイプのどのナンバーもカントリー・フレイヴァーやレイドバックしたルーツフィーリングがふんだんに盛り込まれているところが特徴です。
オープニング曲であり、本アルバムを代表すると思われます、勝負ナンバーの#1『This Time』でもバリトンギターがしっかりと畑を耕すようなオーガニックサウンドを低く鳴らしつつ、Ken ClarkのルーツィなB3ハモンドが非常にルーツナンバーをルーツナンバーとして厚味を付ける働きを巧みにしてくれてます。
#3『Blue Sue』はそれ程アップビートではないのですが、「A.M.」やTom Pettyのナンバーといっても違和感のない心地良いテンポが貫かれる、特にドラムリズムが気持ちの良いナンバーです。優しいJohn Haydonのヴォーカルはこれは間違いなくJeff Tweedyのヘタウマヴォーカルよりも上のレヴェルにあると思われます。
この曲ではまたもKen Clarkのハモンドが、ラップスティールやマンドギターといったルーツ弦楽器と同じく、暖かみのあるAmericanaの権化とも云うべきサウンドの屋台骨を支えています。
Stationary PoetやYearlingsを思わせる、ルーツロックナンバーの#5『You Got Me Lost』は#12『Half As Much』と並んで、John Haydonの創ったナンバーでは一番ラフでガチャガチャしたロックの奔放さを感じる曲です。
この2曲共に懐かしさを一杯含んだコーラスワークが使われているのが大きな共通点ですが、ハーモニカを使ってカントリーフィールドなポップセンスを活用した#5の方が、ペダルスティールやラップスティールを多用してグラスルーツの根明かさでトラッドをロックに引き込んだ#12よりもPop/Rockとしては好みです。
#6『Could Have Said Goodbye』は少しダークなナンバーです。ペダルスティールやマンドギターといったカントリー楽器を使っていますけど、最も硬い感じのメロディですね。優しく柔らかいナンバーの多いJohn Haydonの作風としては珍しいロックチューンですか。
#10『If You Could Be』は#5をスローダウンさせたようなポップナンバーですか。ハーモニカがさり気なくアレンジングされているところは似ていますし、バリトンギターの音でアーシーさを演出している点もまた然りです。少し音階を外したようなJohn Haydonのヴォーカルが何故か印象的ですね。ラップスティールの時折インテイクされるソロの音も印象に残りますし、パワーのあるギターソロを聴くと、#10にJohn Haydonのロックとレイドバックの双方が織り込まれているのが良く見えてくるでしょう。
少し、異色なのが、マンドリンソロをメインラインとしてジャムられる#11『Jimmy』ですね。ローファイラップ、まるでBob Dylanを匂わせるJohn Haydonのヴォーカルに隙間の多いアクースティックアレンジが乗っかるのは面白い試みです。
そして、ミディアムテンポ以下のレイドバックしたアクースティック感覚が活きているナンバーは相変わらず処女作から噛み締める味わいがたっぷりです。
#2『I’m Missing You』ではペダルスティールやオルガンとアクースティックギターのリフが実にしっくりと決まっていますし、エレキギターも情感溢れるソロを聴かせてくれます。
#4『Nothing Now』ではメロトロンのソロやストリングシンセといった電子鍵盤を大胆に投入して、スケールの大きいバラードに挑戦してきています。#2のようなアクースティックとレイドバックに頼らずによりロックンロールとしての性格の強いアレンジへとドアを開く姿勢には好感が持てます。WilcoやJayhawksのように鍵盤に全ての有機成分を吸い取られずにしっかりとオーガニックな雰囲気を維持していますから。
#7『Living Wrong』、#8『Where You Used To Be Tears』、#9『Broken Too』と3曲のバラードが続く後半の一連の流れではパンプオルガンやメロトロン、ハモンドB3がとても好ましいサポートをしています。#9では鍵盤よりもペダルスティールが主役ですし、#8のマンドリンのポロポロと零れるソロもインパクトは強いですけど、こうした鍵盤の深みのある音が単なるアクースティック一辺倒なカントリーロックバンドにJohn Haydonを貶めていないと思うのです。
しかし、1stフルレングスに続いて、実にレヴェルの高いAlt-Countryを届けてくれました。この2枚で既にJohn Haydonのアルバムは筆者にとって安心して買える安全牌になっています。
が、前回のレヴューでも述べましたが、もう少しロックンロールな強さを見せて欲しいという欲求は完全に満たされてません。キャッチーで親しみ易くなったという点では完全にTom PettyやWilcoのレヴェルに追いついていますから、後は「ソロ活動に入るまでは、ここまでカントリー・フィールドに填まった音楽をやってなかったけどね。」というJohn Haydon氏自身のコメントにもある、よりメインストリームなアメリカンロックへと少し戻ってくれても良いかな、と期待したりしてます。
Alt-Country PopからAlt-Country Rockへとシフトして貰いたいのですが、その辺に転がっている荒っぽいだけのカウパンクの末席に連なるAlternative Countryにはなって欲しくも無い。少し複雑ではあります。
なお、このアルバムは2002年7月に亡くなったJohn Haydonの母に捧げられています。この場を借りて、筆者も冥福を祈りたいと思います。 (2003.3.30.)
 Are You Feeling Anything Yet ? / Buzzie (2002)
Are You Feeling Anything Yet ? / Buzzie (2002)
Roots ★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Southern ★★★ You Can Listen From Here
大変惜しい。
ジュエルケースを開けてビックリ。演奏面は青い。レーベル面にはこのジャケットの顔の部分だけがプリントされている。
詰まる所、CDーRだったのでした。
いきなり仮定の話になってしまうが、この「Are You Feeling Anything Yet
?」が
もしもプレスCDだったなら、間違いなく筆者の年間トップ10ベストにランクさせていたクオリティのあるアルバムだ。
(註:この文責は、CDーRメディアは極力書かないことにしているし、絶対にトップレヴューにもしない。送料だけと5ドル以下の実売価格でない限り、かなりの減点対象と考えているため。)
つーか、
こんな悪趣味な顔イラスト(ヲイ)をプリントする資金があるなら、何故無地で良いからプレスCDにしなかったのかと、文句を小一時間言っておきたい。
で、本題だ。(ヲイ)
2002年後半になって、Blue Cartoonというバンドが前作「Downtown Shangri-La」から実に3年ぶりに新作を出している。
「Gin Blossomsよりもルーツなバンドで、SmithereensやBill Lloydのポップさを持ったバンド。」
とメディアに評されたBlue Cartoonだけれども、筆者はそれ程好みのバンドでは無かった。1stはまずオルタナティヴ過ぎて不合格。2nd作の「Downtown Shangri-La」も数曲は光るものがあったけど、今ひとつPower PopとRoots RockそしてAlternative Popとの境界線がハッキリしない微妙な出来が最終的な評価となっていた。
言わば、悪い意味でアングラなインディ・ポップに突っ込み過ぎなきらいがあったのだ。
そういったいまいち消化不良な過去作のネガティヴなイメージを払底することが可能なくらいにメロディが親しみやすくなったという触れ込みで発売されたBlue Cartoonの3作目「The Wonder Of It All」だが、確かにソングライティングの面に関しては格段にコマーシャルに変化を遂げたと断言可能だ。
アレンジ的には、シンセサイザーとサンプリングノイズを取り入れた曲が相当数増えてしまい、前作と比べた場合、ルーツィな雰囲気が、その影を薄くしてしまったという面と入れ替わりであるけれども。
しかし、曲が宜しくなっても、Blue Cartoonには大きな落とし穴が口を空けていた。
それは、ヴォーカルがかなり弱くなってしまったということである。何と、「Downtown Shangri-La」を放った後直ぐに、バンドのリードヴォーカルであったJohn Mcelhenneyがバンドを脱退してしまったのだ。
Blue CartoonはJohn Mcelhenneyの後任として、キーボーディスト兼任のヴォーカリストである、David Lorenをメインの歌い手に雇い入れ3rdアルバムを録音したという訳だ。
このキーボードが演奏楽器であるリードヴォーカルの加入がBlue Cartoonのドリーミーなキーボードポップ化を推進したことは想像に難くない。それはそれで元来Adult AlternativeとPower Popの性質を包括するBlue Cartoonには似合ったアレンジメントとも取れるからだ。
だが、線の細過ぎる女性的なDavid Lorenのリードヴォーカルはハーモニーやオーヴァーヴォーカルの重ね着、そしてエコー等のエフェクトの力を借りてすら、やはり頼りない。
嗚呼、惜しむらくはJohn Mcelhenneyの存在であることよ。彼の人は何処へ・・・・・・
と、白々しく書くまでも無く、このBuzzieをプロジェクトとしてJohn Mcelhenneyは音楽活動を現在も継続している。
ここで、Blue Cartoonに言及した理由をお解り頂けるだろう。
問題は、Buzzieの知名度の低さは仕方ないとして、John McelhenneyはおろかBlue Cartoon自体がマイナーに過ぎるので、Blue Cartoonの名前を持ち出しても理解が得られるのはパワー・ポップファンの熱心な層にだけ限られるかもしれないということだが、今更述べても詮方ないことでもあるか。
ということで、John Mcelhenneyというシンガー兼、ソングライター、そして時々ギタリストという元Blue Cartoonのメインヴォーカリストが自分独自の音楽を模索するために、自身曰く「平和的」にBlue Cartoonを脱退して結成したプロジェクトがBuzzieになるのだ。
バンド脱退の経緯がどうであったか詳細は寡聞にして知らないが、ソングライターがJohnも含めて3名も在中し、しかもほぼ均等な割合(3割ずつ)という曲を書く平等な役割分担がなされているBlue Cartoonにあっては、自分の曲を好きなだけ書きそして歌いたいと欲するミュージシャンにとっては物足りないところがあったことは想像に難くない。
また、他の2名のライターが共同で曲を書くことがあっても、常にJohnは単独でライティングしていたことと、彼の曲の割合が2枚とはいえ常に一番少なかったことも、自分の道を進みたいという欲求を持っていたというMcelhenneyにとってはフラストレーションの蓄積することだったのかもしれない。
いずれにせよ、1999年にグループとして2作目のアルバムを発表した後、John Mcelhenneyはバンドから独立し、Blue Cartoonのホームタウンであるテキサス州はオースティンにてソロ活動を開始する。
古巣と同じ街で活動することを現在も行っているのだから、脱退劇は劇という接尾が付くことも無く、安泰に行われたのは真実のようでもある。
まずは、簡単にBlue Cartoon脱退後の足跡を辿ってみることにしよう。
古巣のBlue Cartoonから離れた翌年、John Mcelhenneyは自主リリースにて早くもソロアルバムを発表する。
タイトルは「Diablo Del Soul」で、これまた青い円盤であるのが残念。
スタイルとしては殆どがJohnのソロ・アクースティックなワンマンプレイのトラックが大半を占める、かなりパーソナルな1枚だ。当然アクースティックだけではなく、ドラムやバックヴォーカリストが参加している曲も中にはあるのだけれども、2作目=本作「Are You Feeling Anything Yet
?」のデモ的性格を帯びたアンプラグド/アクースティック・ヴァージョンな曲が殆ど。
本アルバムにも収録されている
#1『She’s Gone』
#8『The Same Thing』
#12『My Life World Of Love』
と3曲のアクースティックが副題として付けられたテイク。アクースティックと銘打たれていないけれども、
#2『I Want To Know You』
#3『I’m Inside You』(ファーストテイクのタイトルは『Inside You』)
#6『A Place To Go』
#10『Beautiful Beautiful』
の4曲のアンプラグド・アレンジな曲と、合計7曲が本アルバムにもテイキングとなっている。
これを鑑みると、「Diablo Del Soul」は本格的なソロ活動の前にデモ集として仮録音していた音源を1枚に落とし込んでみたテイク集と考えるべきだろう。
更に、これもBlue Cartoonと関係してくるのだが、「Downtown Shangri-La」でJohn Mcelhenneyが創り、歌っていた曲が#1『She’s Gone』と#3『I’m Inside You』であり、このアルバム収録ヴァージョンが3テイク目となる。
確かにこの2曲は「Downtown Shangri-La」でも出色の出来で、アルバムを代表するトラックだ。『Inside You』はオープニングナンバーにもなっている。
敢えて、Blue Cartoon時代にロックヴァージョンを演奏している曲を2曲もソロ作に持ち込んだのは、バンド時代のアレンジに不満があったのか、それとも余程お気に入りで何回録音しても足りないくらいなのか、それともネタが足りないのか、と下らない邪推を巡らしてしまったりする。当然、ネタ云々の不足に関しては冗談の域を出ない。「Diablo Del Soul」に入っていたのに、こちらの選に漏れたというか、トラッキングされなかったナンバーは6曲もあるのだ。
このあたりに、矢張りJohn Mcelhenneyの模索する方向性のヒントが存在するように思えるのだが、それは後述することにして、Johnの活動をさらっておこう。
2000年にソロアルバムで活動を開始したJohn Mcelhenneyは、その後もオースティン周辺でライヴ活動を継続しつつBuzzieのメンバーを集める。2002年に入ると、パワーポップ系のロックの祭典であるInternational Pop Overthrowに参加。
これで耳目を集めたのか、「Diablo Del Soul」がmp3.comのフォーマットCDで再発される。これに伍するように最新のアルバム、2枚目のソロ作である「Are You Feeling Anything Yet
?」を発表。
レコーディングにはオースティンのギタリストとしてかなり玄人ミュージシャンの注目を集めている、Scrappy Jud Newcombをゲストに迎え、殆どのメインギターをScrappyが担当する。これだけでオースティン界隈のルーツロックを追いかけているファンには垂涎モノだろう。
が、それに加えて、1970年代からマイペースで活動を続けるPower Popバンド20/20のフロントマンの片割れであるRon Flyntがプロデュースと各種楽器で参加している。
RonはBlue Cartoonのデビューアルバム「Blue Cartoon」のプロデュースも担当し、「Downtown Shangri-La」では、レコーディングクレジットには掲載されていないが特別な感謝を捧げられており、John Mcelhenneyとの関係はかなり長くて親密な模様だから、今作のプロデュースを依頼されたのだろう。
他にもBuzzieのメンバーとしてリズムセクションやギターにオースティンのセッションミュージシャン等が採用されているが、Jud NewcombとRon Flyntという大物の前には霞んでしまう。
このようにヴェテラン且つ腕利き−片やパワーポップの職人プロデューサーにしてマルチプレイヤー、もう片方はルーツギターやブルースギターからロックギターまで玄人を唸らせるプレイを展開できるオースティンでもトップのクラスに属するギタリスト、というサポートを得たJohnが作成したアルバム「Are You Feeling Anything Yet ?」。
デモ盤の資質が強かった初ソロアルバムと比較すると完全なロックアルバムにステップアップしている。
第一に挙げておきたいのは、John Mcelhennyのヴォーカルの成長だ。
Blue Cartoon時代のやや青臭い甘さは確実に残しつつ、微妙にハスキーさが増し、所謂男の色気が出てきたヴォーカルを聴くことができる。
線の細さというか、美形で若い美男子系の「色気」があるハイ・キーなヴォーカルは、Blue Cartoonのトラックでリスニング可能な頼りなさを同梱させたところからステップアップしている。
Blue Cartoonはソングライターとしてだけでなく、看板ヴォーカリストが脱退してしまったことを嘆くべきだろう。
また、再三のリテイクと相成った#1『She’s Gone』や#3『I’m Inside You』を聴くと、Power Popよりの演奏とアレンジが為されていたBlue Cartoon時代のファーストテイクとの差が顕著に見えてくる。
この2曲に、John Mcelhenneyが目指した方向性がしっかりと転写されていると考えている。
豪華な現代的ギターを数本取り入れていたBlue Cartoon版『She’s Gone』と比較して、ギタリストのScrappy Jud Newcombの技量に寄るところはあるだろうが、実に深みと落ち着きのあるアレンジがなされている。少しばかり、初回テイクよりもスローなテンポになり、ポップで甘くなった箇所が目立つが、それ以上にルーツィでサザン・フィーリングを嫌味にならない程度に身に着けいていることが感じられる。
ギターの歯切れのよさとクリアな彩りではオリジナルの方が一般ロックファンに受けそうではあるが、このオースティンという土地柄をサウンドの節々に感じさせるルーツ・サウンドへの適度な傾きを見るにつけ、John Mcelhenneyの成熟を感じずにはいられない。
Blue Cartoonヴァージョンよりも、ソリッドで無駄を削いだ、それでいて地熱を掌にジンワリと感じる土の手触りを思わせるハートウォーミングなルーツポップに纏まっている。
Blue Cartoonがルーツの感覚のあるパワーポップであるなら、John Mcelhenneyはパワーポップのコマーシャルさをスコアに取り入れたサザン風ルーツロックとなるだろうか。それもライトで南部の音楽としてはかなりスマートで野暮ったさが少ないPop/Rockを主眼に置いたサザン・ロックと表現するのが良いと思う。
#3『I’m Inside You』も、ゴージャスでドリーミーなPower Pop味明るめ風味だったオリジナル版と比較すると、シンプルでアーシーなギターをメインに据えている。Blue Cartoon版のキラキラしたスゥイート・ポップ版も捨て難いが、この数本のギターが適度に抑えられたアンサンブルを確実に演奏するソロテイクの方が、オトナのロックと思え、好ましく感じる。
ファースト・ソロアルバムに収められていた、#2『I Want To Know You』を始めとする5曲も、弾き語りに近かったデモ・ヴァージョンからロックアンサンブルを施され、実に耳心地の滑らかなPop/Rockとして再生されている。
Jud Newcombの目立たないスライドギターがオケージョナリーに飛び込む#2は極上のルーツポップだ。パンプオルガンがメインの楽器として活躍しているが、それ以上に成熟した果実の甘さを覚えさせるJohnのヴォーカルが実に映える曲でもある。
#6『A Place To Go』でもB3ハモンドが効果的に使用され、ミディアム・ファストな即効性の高いメロディを着色している。「Diablo Del Soul」ではもっとクリアなアクースティックギターが頭を張るナンバーだったが、ギターを始めとするリズムセクションの追加により、目立たなくともアルバムの全体のクオリティを底上げする役割をしている。当然、シングルになって然るべきなキャッチーさは備わっているが。
やや南部ロックらしいビター・スゥイートなマイナー風味のある#8『The Same Thing』は英国ポップにも影響を受けただろうPower Popのバンドに在籍したという背景を感じさせる。キーボードやサンプリングSEが南部の酸味と同時に盛り込まれているモダンロックの浮遊感を強調している。
ルーツでありながら、モダンロックやアンダーグラウンド・ポップの名残を感じさせるのもJohn Mcelhenneyの特色だと思うが、この#8はその好例だろう。
そのスマートさの裏返しでもあるモダンテイストは#10『Beautiful Beautiful』にも少し浮き出ている。ハモンドオルガンをあまりルーツロック的に使用せず、ギターも土臭い音色を抑え、ルーツに近いポップナンバーを演奏したという、Blue Cartoonの作風に近い曲となっている。がこれもまた親しみ易いメロディのため、耳障りが良好だ。
#12『My Life World Of Love』はアクースティック一辺倒だったファーストテイクから大きく変化したナンバー。かなりヘヴィでダウン・トゥ・アースとサザンハードの中間にあたるギターが暴れるロックンロールチューンだ。重いとはいえ、オルタナティヴではなく、サザンロックの感覚が強いのがJohnのアレンジのポイントだ。Ron Flyntは元々パワーポップ系の人だが、良くぞこういったダートなアレンジを大切にしてくれたと、感心することしきりだ。
残りの5曲は、このアルバムで初お目見えする純粋な意味での新曲。
#4『You’ve Got That Way』もモダンロックやパワーポップを随所に感じさせるナンバー。キーボードのスペイシーな音と、英国風のマイナーコーラスが特徴のナンバーで、これまた純然たる南部サウンドとモダンサウンドの融合を匂わせている。少しサイケディリックの入ったエレクトリックなポップアレンジが特徴的。
ブルージーなラインと、鍵盤のバッキングが不可思議に同居しているのが、#5『99 Days』のスローナンバー。こうしたサザン・サウンドを濃く反映する作風は、Blue Cartoonn時代には見られなかったものだ。
テンポでは#5の同系列に属するスローな#7『Angela』は#5よりもロー・ファイで、じっくりとした懐の深さを漂わせている曲だ。ここでもブワブワと鳴らされるシンセサイザーのポップサウンドが印象的に耳に入ってくる。
それにしても、ここまで低空飛行すると、流石にBlue Cartoon時代よりも地面の芳香を直接感じることが可能なサウンドが主眼にあると否応なしに気が付くことになる。
#9『Not Alone』は南部サウンドの太いラインとオルタナティヴの重さの丁度中間に位置する如きヘヴィなトラック。しかし、南部サウンドの重みを感じこそすれ、オルタナティヴやパンクロックのラウドなだけや陰鬱なだけの薄っぺらい要素は表出していない。
同じようなハードで重めのギターが、波動を広げているナンバーが#11『I Know』では何処かにTears For Fearsを連想させる厚目な構築をされたナンバー。この曲も#9と同様に重みのあるハードなギターが低く飛ぶ。バックコーラスに明確に女性と分かる声を配しているのはこのナンバーのみ。途中からサザン・ソウルやゴスペルの黒っぽい感覚も現れる、これまたオースティン界隈のサウンドと標榜している曲だが、New Waveの影響も受けていることを思わせるところがある。
しかし、この(Southern Rock+Power Pop)×Roots Rock÷1/4Modern Rock(?)のようなバランスの良いサザン・ポップロックがCD-Rでのみの発売というのが勿体無い。図らずもこれが現在の米国市場の現状なのだ。
ルーツ一筋−濃い音楽とレイドバックを捧げるのだ!!というサザンロックも悪くないが、やはりこのように万人受けする要素のあるPop/Rockなアメリカンロックを南部サウンドの生産地であるオースティン発で発見できると嬉しいものがある。ルーツサウンドが一部のマニア向けに特化する傾向を緩和してくれる良心という見方を筆者はしてしまうからだ。
試聴リンクから聴ける曲は少しアルバムの中では下に属するレヴェルなものが多いので、是非購入してから堪能してもらいたい1枚だ。・・・・青い円盤が嫌でなければ、だが・・・・。
しかし、Scrappy Jud Newcombがこのような一般的なロックアルバムにフルタイムプレイヤーとして顔を出していたことは驚きだった。彼は全体的にももっとルーツ度の深い作品ばかりに参加しているという印象が付き纏っていたからだが。Judのギターを聴くだけでこのアルバムの価値はあるとは思うのだ。 (2002.4.2.)
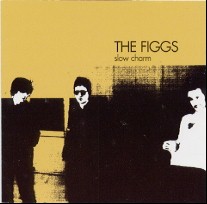 Slow Charm / The Figgs (2002)
Slow Charm / The Figgs (2002)
Roots ★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★☆
Adult-Alternative ★★★ You Can Listen From Here
◆The Figgsについて
The Figgsの発足は1987年と10年以上昔に遡る。創設メンバーはギタリストにしてシンガーのMike GentとベーシストのにしてヴォーカリストであるPete Donnelly、そしてドラマーであるGuy Lynosがバンドを組みThe Figgsと名乗ったことから始まっている。結成の地はニューヨーク州はサラトガ・スプリングという小さな街ということ。
1989年迄、このトリオ編成でFiggsは活動する。しかし、Guyが兵役のために陸軍へと入隊したため、バンドはPete Hayesを変わりのメンバーに向かえて、1992年までFiggsは3ピースバンドを維持する。
1992年にGuyが兵役の義務を終了し除隊して戻ってくると、Guyはギタリストとしてバンドに再度加わることになった。ここからがThe Figgsとしての本格的な活動が始まる。
既に初のフルレングスアルバム「Ginger」を1992年に自主制作の上発売していたが、(カセットテープのみ)4名体勢になったバンドはこれまで以上にニューヨーク市やその周辺の街で精力的にライヴ活動を行うようになる。
そして、Guyがレコーディングに初めて参加した2枚目のフル・レコードである。しかし、この2枚目の作品もまたカセットテープのみ。殆ど手書きレヴェルのジャケットになっているのは1枚目に同じ。
お手製ジャケットのカセットテープをライヴ会場で地道に売るという活動が、しかし効を奏し1994年にはインディレーベルから初のCDデビューを果たすことになる。オフィシャルにはこのCDが最初の作品だと解釈しているサイトも存在するくらいだ。確かに、始めの2枚は同人的なレヴェルのアルバムだったかもしれない。
が、現在構築中のThe Figgsの公式サイトにはこのカセットテープ2本もディスコグラフィーに加えられているので、バンド側としてはしっかり作品群のバックナンバーに加えたい意向を表している。
このCD「Lo-Fi At Society High」はポップパンクなアルバムであり、1990年代半ばに始まったポップパンク、オルタナティブ・パンクのブームの潮流に乗るように発売されたとPete Donnellyは述べている。
「僕らのレーベルはFiggsを1994年の数ヶ月で延び始めたポップ・パンクのムーヴメントに乗せて売り出そうとしていたね。僕らのシングル『Favorite Shirt』はオルタナティヴトップ40のチャートに入り、ラジオ局で頻繁にオン・エアされた。そしてラジオ局によるピック・アップは特にリリースした年は助けになったね。
何故なら、ポップ・パンクと言う音楽がまだ出来たてだったからだね。Green Dayは丁度「Dookie」を売り出したばかりだった。それにレーベルが全面的にバックアップしてくれたからかな、成功したのは。」
特筆すべきは、Hootie And The Blowfishのプロデューサーとしてこの後直ぐ脚光を浴びることになる、Don Gehmanがアルバムのプロデュースを行っていることだ。
同じ1994年に作成したHootieの「Cracked Rear View」は90年代のロックアルバムとして最高のセールスを記録していることは非常に対照的でもある。
とはいえ、「Dookie」の全米No.1ヒットで社会現象まで生み出したGreen Day程にはスターダムに持ち上げられた所迄は行き着かなかったのだが。それでも、The Figgsはメジャー・レーベルの注目を浴びる存在までは成長し、メジャーのCapitalと契約を交わすに至る。この直前にEPである「Hi-Fi Drop Out」をインディへの餞別という形で発表し、1996年には「Banda Macho」を晴れてメジャーからリリース。
Figgsのメンバーは全員が揃ってルックスが中々宜しい、と言うインディのバンドがメジャーへ昇格する上で必須ではないけど、有利に働く要素を持っているので、これもまた後押しをした要素であるとは思う。
「Banda Macho」の発表と同時に全米ツアーを敢行する。しかし、Capitalから十分なサポートを受けれなかったとバンドは不満を言い立てている。まあ、プロモーションを殆ど受けれなくてもメジャーでブレイクするミュージシャンは幾つかは毎年のように出現するので、これだけが理由ではないと思うが。
実際、「Banda Macho」はポップパンクのロックアルバムとしては悪くないけど、やはりAlternative Pop & Punkと呼ぶべき音楽性だった。同年に発表されたCounting Crowsの「Recovering The Satellites」、Wallflowersの「Bringing Down The Horse」、Matchbox 20の「Someone Or Yourself Like You」、Gin Blossomsの「Congratulations...I’m Sorry」といったメジャーなアメリカンロック傑作と比較すると、そのレヴェルの差は歴然として提示されるだろう。
そして、1997年にFiggsは契約を失い再びインディ落ちする。
「契約を破棄されたことは少しは堪えたよ。けれども、何時までもそのことで落ち込んではいないよ。メジャーレーベルに在籍している時ですら、『これだ!』と興奮することは無かったしね、僕等は常に冷静を保っているのさ。」
とはベースのMike Gentの言。
マイナー落ちしたFiggsは、アメリカ北東部をツアーして廻り、地道に活動していく道を選んだ。しかし、一気に収入が減り、借金が残っただけのメジャー移籍は長く尾を引き、1998年の次作である「Couldn’t Get High」は再び自主リリースとなる。
更に、この間の混乱によりギタリストのGuyがバンドを脱退して自分の生活を追い求めることになってしまう。
このため、バンドは再び3ピースに戻ることになるのだ。
セルフ→インディレーベル→メジャーレーベルというステップアップを確実に果たしてきたのに、ここでまた振り出しに戻ってしまった次第だ。
この鬱屈が歌曲にも滲み出てしまったのだろうか、この3枚目のCDはかなりオルタナティヴ・ヘヴィネスの傾向とGun’s n Rosesタイプの直球的ハードロックが最も強いアルバムだ。この「Couldn’t Get High」をリリースした段階でGuyは既にFiggsを脱退していたのだが、レコーディングには殆ど参加して曲も書いているので、クレジットはされてメンバー扱いされてはいる。
それでもFiggsは活動を継続した。幾人かの雇われギタリストをツアーメンバーに加え、バーやクラブでのギグを熱心に繰り返しつつ、アルバムを発表する場所を探し続ける。
この熱心な活動が効を奏し、2000年にはボストンのインディレーベルであるHeadboxと契約を締結。このレーベルは筆者のベストバンドの1つであるThe Kickbacksもディストリビュートしているロック色の強いバンドを扱うのが特徴となっており、Superdrugもこのレーベルが販売元となっていたりもする。
この新レーベルから、7曲入りEP「For EP Fans Only」を発表。この頃から、Power Popと呼べるくらいのポップな音楽を提供するようになってくる。この頃から、筆者もこのバンドに注目を始める。「Banda Macho」の頃から存在は知っていたが、どうにもオルタナ臭くて好きにはなれなかったのだ。
更に同年の後半に、ファンの間でも最も人気の高いアルバム「Sucking In Stereo」、そしてアナログ盤オンリーの発売であるアウトテイク集「Rejects」を発売。(このアルバムはアナログ盤専門の別レーベルから。)年間を通じて3枚のリリースという物凄いペースでの活動を開始する。
またその勢いは衰えを見せず、2001年には再び6曲入りのEP「Badger」。このEPは「Sucking In Stereo」で見せたハードポップ、パンクポップな流れを確実に継承している。
そして2002年には本作「Slow Charm」と、何と3年間にLPをEPを含めて6枚のアルバムをリリースという、ハイペースでの作成を実行している。
2003年現在もアメリカ東海岸でライヴを精力的に行っている。
◆本作「Slow Charm」について
2001年前半から2002年3月に掛けてレコーディングがなされている。約1年未満を費やしてじっくりとレコーディングを行っている様子だ。
メインのプロデューサーはTim O’Heir。ボストンを中心にして活動するエンジニア兼プロデューサーだ。主にインディのオルタナティヴ・ポップやガレージロック、パンクロック等を中心に手掛け、Figgsの前作EP「Badger」も彼のプロデュースによる。
有名どころではBuffalo Tomのエンジニア、Dinosaur Jr.のエンジニアというところくらいだろう。それから筆者もそれなりに注目しているエモ系のポップバンド、All-American Rejectsもデビューから一貫してTimがプロデュースを行っている。2002年にDreamworks Recordから発売された「All-American Rejects」はAdam SchmittやTommy Keeneの若手時代を思わせるくらいの、パワーポップとしては出来の良いアルバムとなっている。
少々横道に逸れてしまったが、「Slow Charm」はTimとThe Figgsの共同プロデュースが全14曲中の9曲。残りの大部分はギタリストでシンガーでもあるPete Donnellyが単独で実行。PeteはFiggsの一員なので、実質1曲を除くとTimとFiggs関連の手による采配でアルバムは録音されている。
ゲストはバックヴォーカルに若干名とアクースティックギターやシンセサイザーで2名程度が参加している位。殆ど3名のメンバーが楽器をこなしている。
このアルバムはアナログ風に組み立てられており、それぞれ7曲ずつSIDE ONE、SIDE TWOというメニューが付随し、並んでいる。要するにアナログ盤のA面とB面を意識しているのだが、それぞれの1曲目、イントロに当たる部分に、インストゥルメンタルというかSEが置かれてレコードを引っ繰り返す演出として使われている。
#1は『Intro #1』で、パレードのマーチを遠くから聞いているような街角録音のSE。
#8は『Intro #2』で、レコード針が盤面に落とされたノイズを10秒少し流すという、文字通りアナログ盤のシミュレーションとして挿入されている。
ので、実質アルバムは12曲と考えた方が良い。
肝心のアルバム内容だけれども、「Badger」や「Sucking In Stereo」で顕著だったノイジーなギターを加えたハード・ポップ/パワーポップという路線よりもトーンダウンした感じだ。
トーンダウンと言うよりも落ち着いて、90年代的オルタナティヴ風のポップ色が弱くなったと考えるべきかもしれない。ラウドにかっ飛ばしてパンクを転がすという一直線さにブレーキが掛かったというべきか。
ポップさは「For EP Fans Only」からの流れを断ち切るものではなく、相変わらずPower Pop/Underground Popの基本であるコマーシャルさをそれなり以上に維持している。
だが、やはり特筆すべきは1990年代型オルタナティヴのアレンジよりも、Figgsが原点としている英国ニュー・ウエーヴやパブ・ロックサウンドの影響が増加して、古典的なNew Wave Pop/Rockな雰囲気が出てきている。しかし、Figgsにはそれ程強烈な英国性を感じることは無く、英国ロックのフォロワーと言う範疇にガッチリと填まっているようにも見えない。
「バンドのルーツはChuck Berry、Rolling Stones、KinksそしてそれよりもElvis Costello The JamにGraham Parkerといったパブロッカー達が70年代後半から染まったニュー・ウェーヴなんだ。
僕達はFiggsの最近のサウンドを原点回帰してルーツなロックンロールでありポップと表現している。僕達はクラッシックなロックに大きな影響を受けている。60年代や70年代、それ以前の音楽にね。
特に全体的にブリティッシュサウンドに拠る所は大だ。それは良いことだけど、それだけではFiggsの可能性は縮んでしまう。僕達音楽性には、人々が認識している以上にアメリカンなサウンドが組み込まれている。僕達のサウンドはアメリカン・ミュージックを下地にしているんだよ、多くの英国バンドが入門として見習った音楽がね。」
というMike Donnellyのコメントにあるように、英国のニュー・ウェーヴを叩き台として持ちつつ、アメリカンな古典ハード・ポップ的な割合が多くを占める音を構築している。
爆走的ラウドサウンドや勢いだけパンクロックが主流であったこれまでよりも、70年代のハードなロックンロールバンドをオマージュとした現代バンドにシフトしつつある過渡期のレコードが本作「Slow Charm」となるのかも。
◆各曲解説
#2『Back To Being』
アルバムで唯一アクースティックピアノが使用されている曲。やや重苦しいが、アメリカンルーツを感じさせる。緩急が付いて曲に単調なものが多かったFiggsから、一歩違ったFiggsへと進む姿勢が見れる。
#3『Sit And Shake』
ソリッドでヘヴィなオルタナティヴと古典ロックが融合した感じのナンバー。しかし、過度のノイジーさが突出していないので、それなりに聴き易い。
#4『There Are Never Two Alike』/#14『Are You Still Mine ?』
少しスペイシーなギターアレンジをしたモダン・ポップ風のナンバー。少しこれまでのアルバムよりもポップとしての濃度を下げた代わりに、アクースティックなギター弦を持ち込んでサックリ感を出している。#12は更にシンセサイザーをグニャグニャと使い、英国風のナードなラインを出している。モダンポップと言うよりもアートロック崩れな風味だ。
#5『Soon』
Mikeが弾くキーボードとマイナー調メロディが、ニューウェーヴの70年代ブームを懐かしくさせる。
#6『Public Transportation』/#12『Protcol』
ウィルツァーピアノを使用したR&B風のスローポップ。#12の方がブラックミュージックへの寄り掛かりが強い。ブルージーなギターソロも聴ける。
#7『Static』/#9『Metal Detector』
両方とも、70年代ニューウェーヴ風のバラバラとしたパンクロック。#7ではウィルツァー・ピアノのチープな音色が懐古的だ。
#10『Lose The Pain』
かなりストレートなパンクポップ。21世紀のGreen Day等に似た分かりやすさを持っているが、音のアレンジとしては古典ロックの落ち着きがある。同時に地味であるけど。
#11『The Trench』
かなりアメリカン・ルーツを含んだ、懐の深みを匂わせるPop/Rock。パンキッシュでオルタナティヴの要素も微量含有しているが、このバンドがアメリカ出身と理解できる1曲。
#13『Slow Charm』
タイトル曲は、マイナー調のパンクロック。かなりアンダーグラウンドなラフさと怪しさがある。初期のパンク・ムーヴメントに近いイメージが湧いてくる曲だ。
◆Figgsのコメント紹介
「僕達の歌の多くはポップソングだ。決して“インディ・ロック”ソングではないし、メッセージを隠して伝えようともしていない。僕は分かり易いメッセージをこめて強く心に届く曲を書くことにしている。僕達のバンドでは皆が曲を書くようにしている。独りのシンガー、独りのライターを中心にして廻っているバンドが殆どだけど、そういうバンドは長続きしないものだよ。」 Pete Donnelly
「僕の父親は30歳を超えた時、レコードを買うのを止めてしまった。僕は30歳を超えてしまったけど、まだレコードを創るのを止めるつもりは全く無い。」
まだまだ、発展途上のバンドだと思う。タイトルの通り、聴くたびに少しずつ好きになれるアルバムだ。まだ「魅了」されたとまでは言い難いけど、直に「Fast Charm」してくれるアルバムを出してくれることが期待できるバンドだ。
(2003.4.10.)

 Chasing Daylight / Sister Hazel (2003)
Chasing Daylight / Sister Hazel (2003)