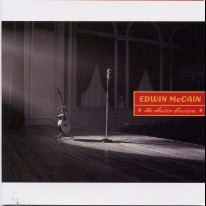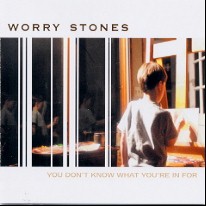 You Don’t Know What You’re In For
You Don’t Know What You’re In For
/ Worry Stones (2003)
Roots ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★☆
Americana ★★★★ You Can Listen From Here
Special Thanks To Toshiさん
◆名曲『Turn Around』が新録音で還って来た
前作であり、デビューアルバムでもあった「Nova Custom」に収録されていた#6『Salt Shaker』。
そして、前作の最大のハイライト曲だった#9『Turn Around』が全く新しく録音し直されている。
これだけでも、前作「Nova Custom」でWorry Stonesが気に入ったリスナーには朗報になる筈だ。
特に『Turn Around』は2001年に筆者が聴いた曲の中では、そのメロディ、その歌詞共にトップに居座るくらいの極個人的なヒットだった。
その『Turn Around』が来るべき2作目のアルバムに入るらしい事を知った時は、「オリジナルに多少のリミックスを加えたトラックか、オリジナルか、それとももしかしたらフルに新規録音し直したテイクか。」、と頭を悩ませたものだ。
そしてアルバムの曲目が正式に発表された後、Worry Stonesに既出の2曲がどのようなテイクかを尋ねてしまったのだ。気になって夜も寝れなくなっていたので。(嘘)
で、リード・ヴォーカルのTim Metz氏からの回答は、「『Turn Around』はリレコーディングのヴァージョンだし、『Salt Shaker』も右に同じさ。」。
ということだったので、狂喜乱舞して新作を待つこと暫し。しかも、この質問に対応して、OHP(試聴リンクに貼り付けてある。)の曲目に、それぞれ『Salt Shaker(2003)』、『Turn Around(2003)』とヴァージョン違いを明記する旨の付加をしてくれた。極東のマイノリティの意見を反映してくれるという、如何にも等身大な姿勢には多分な親しみを覚えずにはいられない。
そして、アルバムが届いた。
真っ先に聴いたのは、矢張り#9『Turn Around』。ベスト盤でもなければ、普段は頭から順番に聴いていくのだが、まずはWorry Stonesがどの程度の変化を遂げたかを知る計算尺としては、以前の歌の新録ヴァージョンが最も適当かと考えたからだ。
・・・・実際はただ単にこの名曲が一刻も早く聴きたかっただけなのだけれども。
まず、クラッシック・ピアノを思わせる美麗なアクースティックピアノソロのリフが流れてくる。ブルース的なインプロヴィゼーションを交えながら40秒ほど続くこのピアノソロからして、ファースト・テイクの『Turn Around』とは大きく異なっている。
1stヴァージョンではアナログ盤または遠くで掛かっているラジオから流れるようなフェードの掛かった演出がされたア・カ・ペラ・ヴォーカルから曲に雪崩れ込む手法を取られていたのだ。
今回は歌い出しの部分にもピアノの伴奏が付いている。しかし、その後から曲の印象はガラリと変わるのだ、この2ndアレンジトラックでは。
オリジナル版ではピアノとギターが等分に配されてピアノで導かれるルーツ&ロッカバラード風の編曲がなされていたが、この『Turn Around(2003)』では、バリバリのスライドギターが主役を張る。アクースティック・ピアノはあくまでも躍動するギター・パートを側面から支える楽器となって一歩引いた形に収まっている。
更に、全体的に幾分かアップビートに引き上げられ、叙情的な一面を見せてくれた初回版とは異なり、マッシヴなロックンロールナンバーとして変貌を遂げているのだ。
しかも、歌そのものがスマートになって、ロックンロールとして走るための空力と馬力を新たに加えた位に切れ味が増しているのだ。
少し覚束なさが存在し、その素朴さが持ち味だった所謂『Turn Around(2000)』とはメロディと歌詞を同じにしながらも、本質的な曲自体の魅力が変質してしまっているのだ。無論、この変質はネガティヴな変化を示すものではなく、諸手を挙げて抱擁したくなる類のメタモルフォーゼだ。
デビュー時ならでわの不恰好さが、実は朴訥さと土臭さを梃入れしていたオリジナル・テイクの良さは今でも素晴らしいと考えている。だが、ハートウォーミングな柔らかさを備えていた3年前のトラックよりも、感情の装填の仕方、曲のメリハリの付け方、そして何よりもPop/Rockとして磨き上げられたリズムの持つ説得力。
全てに於いて、成長が見られ、ファースト・ヴァージョンの良さを補ってなお上回る、新生『Turn Around』へとまさに進化を遂げているのだ。
ここで#9『Turn Around(2003)』について賞賛した項目は、他の全ての曲に対しても有効。つまり、#9で見受けられる要素は全てのトラックにも共通していると考えられる。
そして、このWorry Stonesの成長は、1作目から持ち越した「良い素材」の曲が故に助長されたものではないことも理解できるだろう、アルバムを一度でも通して聴けば。
◆ZHS-7720からZHS-7721へ
2000年にWorry Stonesの処女作として自主リリースされた「Nova Custom」は、CDの収録限界の上限が増すにつれて収録曲が二桁を超えるのが当たり前となった、昨今の趨勢を暗に批判するようなヴォリュームだった。
僅か8曲−この表現に我ながら高容量のメディアに慣れ親しんでしまったことを痛感−という1980年代のアナログ時代なら普通にフルレングスの曲数だっただろうトラック数で処女作をリリースというところに、Worry Stonesの精選主義を感じてしまったことがある。
取り敢えず曲数詰めて、入れるだけ入れてアルバムを出そうという短絡的な指向ではなく、納得の行くマテリアルを選んでアルバムに並べていったら8曲になってしまった、という印象を受けた。
その一桁曲数、CDの容量が遂に800MB(90分収録)可能になる時代に迎合することを善しとせずに、己が信じる道を行くぞという気概を含んだアルバムには古臭いセダンの写真が使われていた。
その古い自動車のナンバープレート番号が「ZHS−7720」であり、それがCDの製品番号として使われていることも前作のレヴューで言及している。
そして今作「You Don’t Know What You’re In For」の製品番号が“ZHS−7721”となった。
残念なことに、何処かのレーベルと満足の行く契約を結び得なかった模様で、Worry Stonesの自主リリースであるシンボルとも言えるZHSの記号は変化することが無く、ZHS−7721と下一桁の番号が進んだだけのカタログナンバーとなっている。
しかし、ZHS−7720の「Nova Custom」が売れ行き不調のために再度セルフプレスとなったのではないと思う。
2000年の末に発売され、2001年から本格的に商流に乗った「Nova Custom」は発売から2年程度で、ライヴ会場とインターネット通販を含めて4000枚以上を売り上げている。
全くの自主制作アルバムで1万枚以上を売れば大成功。メジャーが接近し繰る可能性が大、とまでのレヴェルにはまだ達していないが、プロモーション活動に大手のバックアップやマネージメントすら満足に受けれない完全インディペンダントのバンドにしてはかなりの好調な数字である。
1stアルバムからラジオシングルとしてプロモーションコピーが配布された『I’ve Had Enough』はヴァージニア州にありつつも米国の首都として単独の州扱いをされているワシントンD.C.を中心にしたカントリーやルーツロック系のラジオで頻繁にオン・エアされ、セールスを補助した。
2002年に入ってからは、ヴァージニア、メリーランド、ウエスト・ヴァージニア、テネシー、そしてデラウエア州といったホームグラウンド周辺の諸州で精力的にクラブサーキットを繰り返していた模様。
また、2003年には遂にNYCのLion’s Denまで足を伸ばしてライヴを行えるまでに知名度が上がっている。
このライヴにはToshiさんが足を運んで、実際に体験されたそうなので、同氏の素晴らしいレポートを抜粋させて戴くことにしよう。
「Lion’s Denは所謂ライヴハウスでRodeo BarやLakeside Lounge等のライヴスペースのあるバーではないので(バー自体は中にあるんですが)、基本的に客は音楽と聴きくために入場料を払って来ているはずなんでどのくらい入っているか興味があったんですが、ざっと見たところ40人ぐらいで思わずあのHighway
9のライヴを思い出してしまいましたね。
自分もすこし遅めに着いたんですがまだ機材もステージに持ち込まれていなかったんで、これはもうしばらくかかるかなとと思い一度外に出て現金を下ろしに行ったりしてたんですが、戻ってみるとなんともう既に始まっているじゃないですか!
そして終わってみ分かったんですが『Turn Around』は(多分)その時もうすでに演ってたんですよ。正直一生の不覚ですね。(苦笑)客はやはり地元からバスツアーで来たのがかなりを占めていたようです。
ショーの方はほぼすべて新譜の曲でトータル45分ぐらいの短いものでしたが『Turn
Around』が聴けなかったことを差し引いても予想以上に良かったです。
まず思ったのはライヴバンドとしての力量がかなりあるな、と。『Friday
Night Fight』や『I Can’t Believe』などドライヴ感もあって兎に角ライヴ向けの曲でした。
とはいってもジャムバンドのようにリフだけで飛ばすのではなくメロディーもしっかりしているあたりが非常にポイントが高いです。ただ前列でノってる人たちが(地元から来ているコアーなファン?)数名というのは非常に寂しい光景でしたが・・・。
そしてTimのボーカルもパワフルでアルバムの感じとほぼ変わることが無かったのもよかったです。その他特に印象に残ったのはCounting
Crows風のキャッチーな『Some Things』と電子鍵盤のソロが良かった『Salt Shaker』ですかね。
ところでTimが曲の合間に話していたんですが、NYに来る途中でHolland Tunnelでつっかえて遅れたらしくて、それで到着後急いでショーを始めたということだったようです。まあ前座の一番手で遅れたらその分プレイの時間が短くなるのは仕方が無いんですが、店から「あと一曲」とアナウンスが流れてアンコールもできないというのは非常に寂しいもんです。
ショーが終わっって機材を片付け終えたTimがステージの前で知り合いと話してたんで「CD買いたいんだけど」と
尋ねたところ「OK、今持って来るから」といって楽屋から取ってきてくれました。」
と、ラウドや派手なステージパフォーマンスで誤魔化とお茶濁しを行っている、ヒットチャート常連の偽者バンドがメジャーシーンで幅を利かせているのとは対照的に、実力のあるライヴ・パフォーマンスをアルバムに遜色なく実行できるロックバンドなのだ。
2002年秋口から、Worry Stonesが新作の準備に入り、そのタイトルがBeatlesの「Abbey Road」にちなんだものになるだろうという情報がファンの間で流れていた。
しかし、結局タイトルは「You Don’t Know What You’re In For」になったのだ。
同時に、リードヴォーカリストにしてギタリストであるTim Metzは同郷のバンドであるVirgina Coalitionの3枚目のアルバム「Rock N’ Roll Party」に参加している。このVirgina Coalitionはこれまたドインディなバンドであるが、3枚ともハズレの無いアルバムなので、興味のある人は購入を薦める。
そのVirgina CoalitionやLucky Townといった地元の良質なルーツロックバンドのプロデュースを行っているTed Comerfordをプロデューサーに迎え、Worry Stonesは2002年から2003年に掛けて2ndアルバムを録音。2003年4月に発売を開始し、それと同時にこれまで以上に広範なライヴ活動を開始している。Toshiさんにレポート戴いたNYCのライヴがその活発さを示す好例となるだろう。
なお、メンバーは5名体制という点では1作目と同様なのだが、ベーシストがJeff Nesmithという新顔に代わっているのが唯一の変更点である。キーボードを加えてガッチリとした編成を組んでいるのはCounting CrowsやFive Easy Peicesそして全盛期のWallflowersを想い起こさせる。
◆It’s Just Rock n’ Roll / Real American Rock Icon
一言でいえば、↑である。
1st作「Nova Custom」は正統派のRoots Rockであり、同時にAlt-CountryやCountry Rockの優しい不器用さが感じられるアルバムだった。
無駄なことを一切せず、ピアノとギターを中心とした朴訥なPop/Rock。良心的なAmericana。これが全てだった。
良質なアメリカンルーツロックアルバムにしてヴォーカルロックだったが、多くを望むなら、もう少しロックンロールして貰えないかな、という点が足りなく感じられたものだ。
だがしかし、2作目にして図らずもWorry Stonesは筆者の高望みを満たして溢れさせてくれるような最高級のロックンロールアルバムを届けてくれた。
1970年代から1980年代にかけて、常にメジャーシーンで高い評価を得ていたBob SegerやJohn Mellencamp、そしてBruce SpringsteenのHeartland Rockとカテゴライズされる、一昔前の王道ロックンロールをまっしぐらに突き詰めた激烈正統派アメリカン・ルーツロックである。
元々、メジャーなどっしりとした感覚は兼ね備えているバンドであり、少々アーシーでAlt-Countryっぽいところが良い意味でインディ臭かったのだが、そういった純朴過ぎる田舎テイストは相当減少している。
が、土臭さが無くなったということは決してなく、丁度良いレヴェルのダウン・トゥ・アースさがタイトなロックアンサンブルに装填されているのだ。
Worry Stonesはオリジナルがライヴステージで揃わなかった頃からCounting Crowsのカヴァーを長期に渡って取り上げているが、この「You Don’t Know What You’re In For」はCounting Crowsに擬えて語る資質のある作品であると思っている。
Counting Crowsで最もロックンロール色の強いアルバムは2枚目の「Recovering The Satellites」だが、この全米初登場No.1アルバムは同時にオルタナティヴ的な現代性と相当妥協したアスペクトが存在する。
そしてCounting Crowsのサイケでエキセントリックな鋭角さを緩和し、最も親しみ易いサウンドを実現したのが4作目の「Hard Candy」だろう。
Worry Stonesの2ndアルバムは、丁度「Recovering The Satellites」からロックンロールの大鉈を吸い上げ、アレンジと優しさでは「Hard Candy」に流れる大気を吸収した、所謂良い所取りの傑作であると思う。
ロックンロールのタフさと、それが耳障りにならない「うたごごろ」のある大地の恵みとも表現できる芳醇さをサウンドに有しているのだ。
他のバンドで表現すると、今年2003年に素晴らしいロック作をインディ発売したSister Hazelの「Chasing Daylight」からロックンロールの酒精を取り入れ、それを「...Somewhere More Familiar」のアクースティックで大らかな雰囲気でオブラートしたようなアルバムと言い換えても適切だと思えるのだ。
◆全てがロックンロール+全てが名曲=脱帽
#9『Turn Around』に関しては冒頭で述べたので、これ以上は言及しないが、名曲はやはり名曲。これだけは言っておきたい。
また、同様に処女作からのスライド組みである#6『Salt Shaker』も地味なアルバムトラックであったファースト・テイクと比較すると、格段の進歩を見せてくれる。
アクースティックで実直なルーツポップだった最初のヴァージョンよりもリズムをアップして、ピアノ、オルガン、ローズピアノと各種鍵盤が活躍し、それ以上にギターが存分に仕事場を与えられたミディアムなロックチューンとして甦っている。TimとギタリストであるErich Wildemanのハーモニーは演奏が分厚くなっても不変にして良質だけれども。
同様にポップさが光るのが、フェンダーローズのディレイが掛かったリフから、美しいミディアムロックに飛び上がる#3『Some Things』。キャッチーでジャンピーなロックンロールを十全に表現しているナンバーだ。ギターのソロは1980年代のヒットシングルを聴いている錯覚さえ感じてしまう。
唯一のバラードともいえる#5『I Might』でのハモンドオルガンとピアノを中心としたエモーショナルな組み立ては、見事と表現する以外に方法はないし、エレキギターとスライドギターのアンサンブルは産業ロックまで俗化することのないロックンロールバラードとしての情感をたっぷりと見せてくれる。
ローズピアノが軽快に転がる#7『She’s Not Enough Done』。1stアルバムに多く見られたさり気ない暖かみを最も内包している曲だ。このロックの速度がやや緩いナンバーではTim Metzのヴォーカルとしての才能を観察することが可能だ。
Hootie And The BlowfishのDarius程には濃くなく、Sister HazelのKen Blockよりも緊張感を抜いて聴くことが出来るタイプのソウルフルな喉がTimの魅力だ。
また、バラードではないが、スローでヘヴィな#4『Dreams』も、ロックバンドとしての手応えを感じさせてくれる。この2作目がロックアルバムとして発動機を換装した如くなパワーバンドに変身したことを最もダートでマッディに言い換えているのだ。ポップな曲が粒揃いの中ではシングルに向かない唯一のナンバーだけれども、Worry Stonesが細かいポップバンドに纏まらないでいることが見て取れる。
これ以外の#1『Friday Night Fights』、#2『I Can’t Believe』、#8『#8』(そのまんま)、#10『Land Lover』というトラックは大同小異が存在するとはいえ、ゴキゲンなロックンロールナンバーだ。しかもどのナンバーもアメリカンルーツとポップソングのバランスを巧みに保った時代がマトモなら大ヒットを次々とかっ飛ばしても不思議ではないものばかりである。
オープニングからロックンロールの醍醐味を叩き出すスライドギターとルーツサウンドの暖かさを紡ぎ出すアクースティックギターのアンサンブルに圧倒され続ける、#1『Friday Night Fights』。前作よりも馬力5割増というところのTimの真剣な骨太ヴォーカルもインプレッシヴだ。
1960年代のオールド・スクール・ロックという風味のあるスピーディなナンバー、#2『I Can’t Believe』。早口のヴォーカルにバタバタしたリズムで非常に忙し気であるのに、レゲエタッチの能天気さが何処かに住み着いていて、聴くだけで楽しくなってしまうファイン・チューンでもある。この曲でのオルガンの暴れっぷりは必聴だろう。
スマートなPop/Rockという点ではピカ一の#8『#8』。澄んだ音色のピアノが高音でギターやリズム隊の分厚い演奏にアクセントを加えるところは、秋の空の高さという具合の清涼さを覚えるし、それ以上に頑張るオルガンにロックンロール・キーボードの真髄を感じて取れる。
ピアニストのRay Rapoportは勢いと印象度ならWallflowersのRami Jeffよりも勝っていると筆者は思う。ここまでメジャーな鍵盤を弾ける人はメジャーでもそうはいないと思う。ルーツロックのキーボード弾きではなく、Pop/Rockの鍵盤としては若手の一番株かもしれない。
そして、最もワイルドで元気の良いロックナンバーであるのが、#10『Land Lover』。オープニングトラックの#1もロックンロールの馬力が溢れていたが、この#10のダイナミックなメロディのうねりは#1以上に強烈なロックスピリットを伝えてくれる。
スピーディさでは#1や#2に劣るとしても、ロックンロールのエッジの鬩ぎ合いという野趣溢れる流れからすると、このラストナンバーが最も自由奔放だ。
◆で、結論は
まあ、買わないと損する。これだけ。
某所でマイナーばかり漁っているのは廃人であり、人としての道を踏み外していると見なしている集団が存在する様子だ。が、このWorry Stonesに出会えない、テキサスのそれなりにマニア受けするカントリーやルーツシーンを漁るだけの生活するくらいなら音楽聴くの止める、と断言したい。
アメリカンロック、ルーツやカントリーに限らず、Rock n’ Rollがポップミュージックが好きならば、このバンドを知らないでいるのは大きな罪であるといえよう。
この2作目は処女作よりももっと成功を収めるだろうし、この自主制作には不似合いな高いレヴェルなら、メジャーが何れ目をつけそうな予感がある。
気の早い話しだが、次に来る3枚目はメジャーや中堅レーベルから配給されることになると予言しておくぞ。(大丈夫か?) (2003.4.15.)
 Bridges Left To Burn / Paging Raymond (2003)
Bridges Left To Burn / Paging Raymond (2003)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Americana ★★★★ You Can Download Full Ver. #1 , #4 , #11
◆レイモンド氏はバンドに不在
「僕達にはレイモンドという名前の知り合いもいないよ。
ある時、Timが夢を見た。その夢の中でTimは空港にいて、アナウンスか何かでPaging Raymondという声を耳にしたんだ。僕達はその響きがバンドの名前としてとっても格好良いと思ったんで名前に使うことにした。」
と、メンバーにページングさんもレイモンドさんもいない、インディアナポリスのバンドが2年近くのブランクを経て2作目のアルバムを発表した。
◆高音質で試聴が可能
上の試聴リンクは、Paging Raymondの二柱ともいえる、ツイン・リードヴォーカリストの片方であるTim Wilsbach氏の好意によって公開されているものだ。
新譜のプロモーション用にサーバー上にアップロードしてくれた3曲をそれぞれ曲順に対応させナンバーを振ってある。アルバム収録の音質レートと同等のトラックがフル・ヴァージョンでダウンロード可能である。
日本のマーケットでは「音質は変わらない」と闇雲に主張するレコード会社が、CCCD(コピーコントロールCD)の乱造に踏み切り、蔓延り出しているという情けない体たらくなのを鑑みると、豪く違うサーヴィス精神をお持ちであると思う。
また、ブロードバンド専用の回線も特に#1『Fall Away』のみ提供して戴いているので、こちらもリンクを貼っておく。
現在、Paging Raymondの公式サイトはサーバーを移転して全面改装中であるため、このようなテンポラリーな処置で試聴希望者に対応してくれているのだ。
Paging Raymondの公式サイトはこちら。まだ、コンテンツは殆ど稼動していない。が、本CDである「Bridges Left To Burn」を購入できるリンクもなされているので、マメに足を運んでみるのも良いと思う。
直にmp3.com等で多くの曲が試聴可能になると思われるので、それまでの暫定処置と考えるべきだろう。
まずは、3曲のサンプルをフルで聴いて貰いたい。そうすれば、この「Bridges Left To Burn」が素晴らしい2ndアルバムであることは、言葉を拙文で重ねることも無いだろうとは思う。
だが、さあ迷わず購入しよう、とは手放しで薦めれない事情が存在したりするのだ・・・・・。
◆残念ながら、CD−Rメディアでのファースト・プレスに・・・・
最初にお断りしておくが、このアルバムを「聴く」ことを他人に薦めるかと言う点では、筆者は躊躇なく太鼓判を捺してお薦めする。殊に、1Stアルバムの「Please Quiet Recording」がツボに填まったリスナーなら是非聴いておくべきだと考えている。
更に、Pop/Rock、Alt-Country Rock、Roots Rock、Folk Rockとカテゴリーは何でも構わないのだが、良質なアメリカン・サウンドが嗜好に合うというリスナーにも一度は聴いて貰いたい良作であるのも間違いない。
が、フォーマットの関連でPaging Raymondの2枚目フルレングスである「Bridges Left To Burn」を、全てのリスナーには強力にプッシュはし兼ねるのだ。
そう、上に書いた通り、今作はCD-Rメディアでの発売となってしまっているのだ。
また、インナーもコート紙(艶のある耐水性の紙の事ね。)となっているのだが、内側の歌詞とクレジット面は如何にもカラーコピーとインクジェットプリンターで家内制手工業しました、という跡がハッキリ見える程度の印刷となってしまっている。
これについて、愛惜の意を筆者はバンドに伝えてみた。1stアルバムが、プレスCDであり、しかもしっかりとした印刷のインレイ・カードを使っていたことを考えると、言い難いことだが退歩の一種だと思うからだ。
以下、Tim氏から戴いた回答を翻訳しておく。
「また、CDを聴いて貰えて嬉しいよ。2枚目を買ってくれた人達有難う。僕達は正直資金繰りに困っていて、残念ながら2枚目のプレスを暫定的且つ短期間と考えてCD−Rから始めたんだ。
プレスする資金が集まり次第、プレスCDに切り替える予定だよ。それからインナーの印刷もあまり綺麗に仕上がっていないのもご指摘通り。こちらもあるべき姿にしたいと思っている。資金が揃い次第ね。」
・・・・という事情である。昨年の12月からレコーディングに集中するため、一切のライヴ活動を行っていないそうなので、クラブサーキットで得る収益が全く無かった模様。
マイナー・ミュージシャンになると、ツアーを行っても客が数えるほどしか入らなくて十分なギャラが手に入らず、ツアー用のワゴンやバンの中で毎日寝るハメになる。と、このようなことは日常茶飯事だそうであるが、それでもPaging Raymondの場合、数ヶ月の間一切ギグに出ずにアルバム創りに集中という姿勢は賞賛されて然るべきだ。
スタジオに篭もっている限り、外部活動によって得れる収入源は、過去作の売上しかないのだから。
よって、プレスCDに拘る人、チープなジャケットが気に入らない人はPaging Raymondが資金を揃えてプレスCDの発売に切り替えるのを待つ方が選択肢としてはベターだろう。
しかし、このCD−Rで生産したアルバムが売れなかったら、恐らくプレスCDはやって来ない気がする。(Paging Raymondの皆さん、御免なさい。)このディレンマは強烈だ。プレスCDが欲しいけど、それを実現するにはCD-Rベースの暫定盤ともいうべき初期プレスを購入してバンドを盛り立てなくてはならないからだ。
だがら、ファンならお布施も兼ねて購入すべし。(涙)
真面目な話、聴く価値は絶対に存在するアルバムなので、来たるべきプレス正規盤は保存用ということにでもして置こうではないか、と思うのだ。(涙)
◆やはり、強みはTim WilsbachとAaron Adelspergerのツイン・リードヴォーカル
Paging Raymondの特徴は、タイプがそれ程似てはいないけれども、とはいえ物凄い型違いではない2名のリード・ヴォーカリストが歌を唄えることにあると思う。
前作のレヴューでも述べたが、Gathering FieldのBill Deasyの声を連想させるAaronの鼻で唄うヴォーカル。
そして、NelsonのGatthew Nelsonのような少しシャガれた、Timのソウルフルなヴォーカル。
この2枚のヴォーカルが、時にはソロパートを、またはハーモニーのツイン・ヴォーカルを、そしてデュエットをもこなして、各曲を様々に着色しているのだ。
また、この2名はそれぞれ自分が作詞作曲した曲をPaging Raymondに持ち込んで1枚のアルバムに纏めるというスタイルを前作で採用していたが、この2作目ではどうなっているだろう。
まずは、シンガー兼ライターとしてバンドの創作部分を支えている2名のソングライターの書いたナンバーと、担当リード・ヴォーカルについて、Timさんからお伺いしたので書き出しておこう。
トラックの前に付けた記号がそれぞれ以下に対応している。
★・・・Tim Wilsbach作詞作曲で歌もTim。
■・・・Aaron Adelsperger作詞作曲で歌もAaron。
●・・・Aaron Adelsperger作詞作曲で歌はTimとAaronのツインリード。
▼・・・Aaron Adelsperger作詞作曲で歌はTim
★#1『Fall Away』(作:Tim Wilsbach / 歌:Tim Wilsbach)
●#2『Wrote It Down』(作:Aaron Adelsperger / 歌:Tim Wilsbach & Aaron Adelsperger)
★#3『Numb』
●#4『Wake Up Caroline』
★#5『Crazy』
■#6『Madaline』(作:Aaron Adelsperger / 歌:Aaron Adelsperger)
▼#7『Exiled』(作:Aaron Adelsperger / 歌:Tim Wilsbach)
■#8『Wither』
■#9『Anchor』
▼#10『I Know』
▼#11『NHS』
そして隠しトラックとして、Johnny Cashのカヴァー・ソングである#12『Folsom Prison Blues』をAaron Adelspergerが唄っている。
全体を眺めてみると、曲を書いている比率ではAaron8曲に対して、Timは3曲となっている。処女作ではTimが4曲を提供し、Aaronが8曲だったので、割合としてはほぼ均等に引き継がれている。
がリードヴォーカルに関しては、デビューアルバムでAaronが7曲、Timが5曲を唄っていたのに対して、少し変化が起こっている。
「Bridges Left To Burn」ではTimが6曲を歌い、Aaronが3曲。(隠しトラックまで含めれば4曲だが。)2人のハーモニー・ヴォーカルが2曲ということで、ここまで含めるとTimの出番が半分以上となっている。
どちらのヴォーカリストも甲乙を付けがたい魅力を持つ歌い手であるけれど、格好良さで見れば筆者的にTim Wilsbachのヴォイスの方に一票を与えたい。よって、Tim Wilsbachのパワフルな喉を聴ける割合が増した分だけ、このアルバムでは得をした気分になっている。
ソングライティングについて言及すれば、Tim WilsbachとAaron Adelsperger双方とも実にポップでアップビートな歌を書く才能に恵まれている。どちらのライターもポップ感覚という点に付いては全く人後に落ちるところは無い。
ただ、微妙な差異としては、Tim Wilsbachの曲は渋いレイドバック感覚を上手く曲に盛り込むという点で秀でており、加えてロックンロールの鋭さを強調した曲を書くという印象がある。
比べてAaron Adelspergerの場合、キャッチーさではTimよりも親しみ易い曲を書き、ソリッドで深みのあるTimのルーツセンスとは対照的にアッケラカンとしたAlt-CountryやCountry Rockの陽気さを曲に混ぜ合わせるのが巧みという創り手であると思っている。
Country Rockの元祖的な扱いをされているJohnny CashをAaronが取り上げているところに、AaronとTimの嗜好の微弱な差を見ることが出来る気がする。
TimはRoots Rockが得意。そしてAaronはPopやAlt-Countryに根差している部分が多い。
それぞれに、近似しているが全く同じフィールドには立っていないソングライターが曲を持ち寄り、異なったタイプのヴォーカルを展開する。こういった多様性と肯定的な意味での複雑さが、Paging Raymondを単なる地方のAlt-Countryバンドやアクースティックバンドに終始させない要因であると思うのだ。
◆「Please Quite Recording」と比べると
「今度のアルバムは、一点に集中したものになっているね。最初のレコードはランダムに色々な歌を詰めたという感じになる。ソフトなアクースティックなトーンを中心に組み立てた1stよりもエレキギターを入れて、アンペアが上がっているだろう?」
とは、ドラマーであるStephen Fieldsのコメント。
1作目としては今後が心配になるくらい完成度の高かった「Please Quite Recording」。
概して、良作の後に続くアルバムは前作を超えることをリスナーに期待される傾向が強いため、辛く祭典をつけられがちになってしまうものだ。その点、「Bridges Left To Burn」はどうだろうか。
最初に述べてしまえば、1作目に負けず劣らず素晴らしい出来となっている。しかも、1st作の良い所はしっかりと継続して持ち込みつつ、食い足りなかった面を伸ばしているという、2作目の理想形に当たるアルバムなのだ。
まず、全体的にレイド・バックの傾向が増している。反面、カントリー、カントリーロック的な軽過ぎる音楽性はぐっと少なくなっている。
ここに本作「Bridges Left To Burn」の大きな特徴がある。
より一層ルーツ・フィーリングの手応えを覚えることができるようになっているのに、カントリーロック的な部分が減少している。このことは、Paging RaymondがAlt-CountryバンドからRoots Rockバンドへとシフトしつつあることを示しているように思えてならない。
つまりは、カントリーアレンジに依存する割合の少ないPop/Rockなバンドへと変遷を遂げつつある過渡期に、Paging Raymondが差し掛かったと見て良い。
同時に、Paging Raymondの大きな魅力を占めていた、フォーキィでアクースティックな面が、エレキギターを含めた豪快なロックサウンドの増加のため、バンドの特徴として占有する面積が相対的に減少していることも挙げておく。
繊細で優しい雰囲気が焼失したということではない、念のため。ロックバンドとしての底力が全体的に水準を上げているのだ。コマーシャルでジェントリーなメロディが最も心地良かった処女作よりも、ロックンロールバンドとしてロックリズムを楽しめるバンドに変革しつつあるということ。
ここで、Rock n Rollなバンドへと『成長しつつ』とか『過渡期にある』と繰り返しているが、まさに完全にロック専科の集団に移行し切っていない状態にあるのだ。丁度アクースティックなルーツポップから、ロックビートを中心としたバンドの中間に位置する音楽性が、2枚目現在のPaging Raymondの作風と思うからの故にそう表現している。
が、もしかしたら、過渡期とか中間期ではなく、アクースティックとロックンロールの狭間でレイド・バックミュージックを表現することがPaging Raymondの定点になるのかもしれない。
どちらにせよ、このポップでフッキーなメロディとTimとAaronのヴォーカルがある限り、Paging Raymondはどのようなフィールドへと移行しようが、信頼の置けるバンドということに変わりなはいが。この2作目の出来を確認したことで、1作目で抱いた信用が更に確実なレヴェルへと登った。
◆ロックなナンバーが増えた。でもやっぱりルーツでアーシーなバンドだ
「最近のバンドでは、Wilco、Train、Barenaked Ladies、そしてやはりCounting Crowsにインスパイアされて影響を受けていると思う。」
「僕達は高校生の頃、LAヘヴィメタルと80年代グラムロックの大ファンだった。僕たちの部屋にはBon JoviやIron Maidenのポスターがベタベタ貼られていたものさ。だから、僕たちのルーツはそういったハードなロックなんだよ。ライヴで演奏をする際、その影響を隠すことは今でもないね。ステージを見て、聞いて貰えば、分かってくれると思うけど、僕達は1stCDの作風をライヴでそのまま演奏するバンドではないよ。
アルバムに入れてないマテリアルを使えば、4日間で毎日4時間のライヴが出来る。が、大半は音楽的ルーツからヘヴィメタバンドが得意にしていたバラードなんだよ。そういった会場の雰囲気をしんみりさせてしまう曲はあまり演奏したくない・・・・。」
この2つのコメントを読むと、2枚目でPaging Raymondがロックバンドとしての“地”を出し始めたのが理解出来る。更に、Alt-Countryではなく、もっとメジャーなロックンロールを目指していることも見て取れる。
「Bridges Left To Burn」収録のトラックで、カントリー的な要素の強いナンバーは、#6『Madaline』、#9『Anchor』という2曲くらいだろうか。しかも2曲ともにアップビートでカントリーらしいダサダサな明るさが目立つとはいえ、やはりロックナンバーに属するタイプだ。
確かにバンジョーやマンドリン、そしてアコーディオンまで揃えた#6は、Aaronのカントリーシンガー向けでもあるヴォーカルとマッチしていてモロにカントリーロック風味だが、#9はCountry Punk Rockと呼ぶ方が合っているタイプのバタバタした忙しなさがカントリーに通じる所があるというくらい。#12の『Folsom Prison Blues』は、Johnny Cashのカヴァーという出自が出自だけに、カントリーロックしているのは仕方が無いところだろう。
全体的にカントリーなナンバーは激減している。
それ以上に、Alt-Countryと呼ぶべきよりもRoots Rockと分類するべきナンバーが殆どとなっている感じだ。
ブルージーなハーモニカとギターで綴られるヘヴィでスローなナンバー、#8『Wither』は完全にSouthern Rockなルーツベースのブルースだし、マンドリンやオルガンの音色が印象的な#2『Wrote It Down』にしても、Alt-Country Rockではなく、Hootersの『Brother,You Don’t Walk Away』をスローダウンしてレイドバックさせたポップナンバーという位置付けが正しそう。
#2『Wrote It Down』はTimとAaronのハーモニー・ヴォーカルが実にマッタリとした曲調に合った粒揃いのアルバム前半の一角を占めるナンバーでもある。
同様に2人のヴォーカリストがメインヴァースをハーモナイズさせる#4『Wake Up Caroline』では更に強力で馬力のあるエレキギターが積極的にアンサンブルを引っ張る、ルーツロックのミディアム曲の定番だ。#2ではAaronのヴォーカルが前に出る感じだったが、こちらではTimの張りのある声が目立っている。
元来ロック指向の強いTim Wilsbachが作ったナンバーは、何れもテンポの速い遅いに差異はあるけれども、ロックナンバーだ。
レイド・バックサウンドに力を入れているPaging Raymondを強烈に印象付ける役目を背負ったようにも思えるオープニングトラックの#1『Fall Away』。乾いたピアノやマンドリン、バンジョーがジンワリと満ちてくるようなユルいリズムを確実に運んでくる。Timのソウルフルなヴォーカルが心に染み、マンドリンのソロが侘び寂びすら感じさせる。
オルガンとギターがタイトなロックビートを叩きつける#3『Numb』は1stアルバムでは見ることの出来なかったストレートなロックナンバー。Counting CrowsのロックナンバーやWallflowersの『One Headlight』を思わせるルーツィなローファイ・ハイオクタンなロック曲。
そして、Paging Raymondのポップセンスとルーツ感覚が目一杯発揮された#5『Crazy』はアルバムでも屈指の出来なルーツ・ポップロックだろう。#1とこの曲だけがアクースティックピアノを伴っているが、同時にフューチャーされているオルガン共々、零れるような美しい鍵盤のソロが最高にフッキーだ。
パーマネント・キーボーディストの不在な5ピースでこのように心に残る美しいピアノソロが聴けるとは予想外だった。
Aaronのポップな曲創りが活かされたナンバーが後半にはPop/Rockチューンとして勢揃いしている。しかも歌を担当するのはAlt-Countryナンバーよりもロックトラックを唄うことに長けた声質を有するTim。
お互いの長所を合体させた最高の仕事をしている。
#7『Exiled』、#10『I Know』共に、スピーディさでは#3に劣らないが、キャッチーさでは遥かに上を行く軽快さが身上のロックナンバーだ。両方のナンバー共にドラムソロが気持ち良いリズムを叩き出す。
エレキギターが大活躍する#7と比べると、ややアクースティックな爽やか音色が含まれる#10、という具合にタイプが多少違うアレンジを施して飽きさせない流れにしている。特別に意図したものではないかもしれないが。
そして、ヘヴィなギターが唸るリフからスタートする#11『NHS』は、伸びやかでダイナミックな1980年代の産業ロックに通じる豪快且つ華やかさのあるロックンロールトラック。この曲はルーツロックというよりも、バンドのメンバーが高校生時代に追いかけていたアリーナサウンド風だ。エフェクトやエコーを多用したコーラスやヴォーカルは、アクースティックバンドという既存のPaging Raymondとはかなり違うが、ロックの疾走感はガッチリと感じられる。
Counting Crowsのテーゼとも云える『A Murder Of One』を彷彿とさせる大作だ。
◆2枚目も傑作。だから頑張れ!!
ということで、2枚連続して、しかも違った魅力を柱にしてアルバムを作成することを行った才気溢れるバンドについて2回目のレヴューをしてみた。
是非ともプレスCDが出せる資金を稼ぎ出す以上に売れて欲しいアルバムだ。
「多くの人が、僕らのバンドをAlt-Countryって見なしている。個人的にはそれで全然構わないと思う。が、完全に正しい認識かどうかは疑問だよ。僕達は自分自身をアクースティックを基本にしたロックンロールバンドと考えている。」
このコメントは2枚目のロックアルバムを聴けば、頷ける筈だ。Paging RaymondはRoots Rock Bandと呼べる集団に成長・・・・・元々1作目からレヴェルは高かったので、熟成したと言っておくことにしよう。 (2003.4.22.)
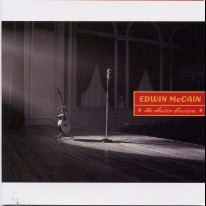 The Austin Sessions / Edwin McCain (2003)
The Austin Sessions / Edwin McCain (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★☆
Acoustic ★★★★☆ You Can Listen From Here
◆Edwin McCain、メジャーとの契約破棄される
1995年にEdwin McCain Band名義でAtlantic Recordsと契約。「Honor Among Thieves」を世に放って以来、順調に4作目までのメジャー・アルバムを発表し続けたこのバンドも時代の趨勢には逆らえなかった模様だ。
「メロディアスな作品が、ラウドなノイズロックよりも評価され始めている。」
このようなお題目はオルタナティヴ/グランジサウンドが蔓延し始めた1990年代から、日本のプロフェッショナルなライナーノーツ書きやレヴュアーに、まるで免罪符の如き乱発手形として発行されてきた。
しかし、時代が20年以上前の情勢に立ち戻ることは無く、メジャーシーンから良質なアメリカンサウンド−ルーツやトラッドの基本を踏まえた−は姿を消しつつある。どっちを向いても、メロディアスな本格的ロックサウンドはポピュラーシーンにてその存在を感知不能になってきているのだ。
メジャーバンドの中ではかなり良心的なアメリカン・トラッドロックの担い手だったEdwin McCainも前作「Far From Over」が総合チャートのトップ100入りを逃すという苦戦が祟ったためか、この「The Austin Sessions」を発表する以前にAtlanticとの契約を失った。
不思議なもので、メジャーからインディに落ちた直後のアルバムは物凄い良作か、またはメジャー落ちの原因となった駄作に輪を掛けた糞味噌に貶されて然るべきシロモノに成り下がるか、と極端な出来になることが多い。
メジャーで成功を期待されるというプレッシャーから開放されたためか、精神的な制約から解き放たれた創造欲がプラスの方向を向くか或いはマイナスの進行方向を目指すのか、という差異によって完成度が大きく端から端へと振れるのだろうと筆者は考えている。
これは契約ロスト直前のアルバムだけでなく、それまでメジャーに在籍した期間のスパンを展望して、アルバムの出来がどのような曲線を描いていたかを観察すればある程度の予測は出来そうな気がするのだが、実際はクリエイトな産物の常として傾向ははっきりと掴めないことが殆ど。
つまり、アルバムを出す毎に評価点数が下りカーヴを描いていたアーティストが、インディに落ちると同時に曲線が急上昇する傑作を出す場合もあるし、逆にインディに落ちるまでセールスの結果が伴わないけれど力量は登り曲線として書き出せていたアーティストが、メジャーからドロップするや否や平均点を下げまくる駄作を出してしまうことも起きているということだ。
このあたりの境界線となるのは畢竟、所謂都落ちとなってしまった事実に対して落っこちた本人達がどう考えているかに左右されると考えられる。
ぶっちゃけた話し、インディ落ちを好都合な方向性の変化の理由とか心機一転の契機と捉え、ポジティヴに次の創作に取り組みが出来た側。そしてグレードが落ちたことに腐ってしまい迷走や堕落を始めた感性の持ち主になるか。
これらの違いが如実に反映した結果が、メジャー陥落直後の作品が両極端な出来となる傾向を生み出しているのだと思う。
そして、当然のことながら、Edwin McCain作「The Austin Sessions」はインディ落ちが、少なくとも作品クオリティにはプラスに働いた事例に属するアルバムである。しかも、これまでの5枚のメジャー盤と1枚のインディペンダント作を併せた場合でも、最も素晴らしい作品となっている。
Edwin McCainの内心を読めない以上、彼らの発言やインタヴューから思いを廻らせるしかないけれども、メジャーからの都落ちに対して落ち込んだり、自暴自棄になっている印象は受けない。無論、言葉面だけでは真実は判別しないのだが、この「The Austin Sessions」自体のクオリティがEdwin McCain個人の内面を明確に物語っている。
現状に投げ遣りなミュージシャンが、傑作アルバムを創り上げることは皆無とは言わないけれども、多くは無いとは思っている。不幸な状況にあるミュージシャンがそれをバネや起爆剤として活用し、鬼気溢れる傑作や問題作を提示することはまま起こりうるが、それはまた別の議論になるから、この場では語らない。
◆インディ落ちと「The Austin Sessions」への道
「僕はAtlanticで作った歌をとても誇りに思っている。丁度、契約が舞い込んだ時と同じで、関係が終る時だったんだと思う、今回は。」
「メジャーレーベルとの契約下で注目しなくてはならないことは、自分が何をしているのか本当に理解してくれている人々に向けてプレイするため、広告活動やキャンペーンを行う必要があること。
ファン−僕はこの言い方が大嫌いなんで、音楽を通じての仲間と呼んでいる。彼らには、2通りのタイプが在って、まず自分の歌が真実どのようなものであるかをメディアやキャンペーンに惑わされずに十分理解してくれる人々。これは上で述べてるね。
そして、もう一方が、自分の音楽を記憶や気持ちの一点にも引っ掛けない、歌を理解しようとしない人たち。
本当はこういう人たちのために歌を捧げなくてはいけないと思う。」
些か定型化しているが、Edwin McCainはメジャーに在籍して良い経験を積んだことと、メジャーの管理下でのプロモーションでは特定の支持層にしか自分をPRできなかったと述べている。即ち、現在は演奏の自由を得たと言っているのだろう。
新しい移籍先はATC Records。2002年には本CDに先立って映像作品である「Mile Maker Acoustic Highway」を発売しているレーベルだ。Edwin McCainとゲスト達を含めたアクースティックセッションのDVDである。既にこの時点で「The Austin Sessions」の基本構想は固まっていたようだ。
「しょうもないことが減ったね。とてもほっとしているよ。例えば、テレビ出演時に黒のズボンを穿くのに15人のスタッフの同意が必要だったことを考えるとね。こういう手順は僕には煩雑過ぎた。今はATCの配慮で音楽的にもフリーハンドを得ることが出来たよ。」
そして、その自由な状況でEdwin McCainが作成したのが、アクースティック・ユニットを中心とした、所謂アンプラグド・スタイルに酷似したアルバム、本作「The Austin Sessions」という訳だ。
McCainはこのアルバムについて以下のように述べている。
「僕たちは、ず〜っと、アクースティックなアルバムを作らないかと沢山の人に尋ねられてきたよ。アクースティックなアルバムを求めている人たちは、僕が常に言明している『ソングライティングが最も中心になるべきだ』という主張を好きでいてくれた。その人たちがオール・アクースティックアルバムを欲しがっているので、僕等は実行に移った。
真底ルーズであり、そしてオーヴァー・プロデュースから縁遠いアルバムさ。僕はヴォーカルの取り直しは一切やらなかった。歌ったままをレコードに吹き込んだ、そのままね。」
厳密にはSessionsとタイトルが付いているが、ライヴ作品ではない。が一発録音が多数なされ、オーヴァー・ダビングや処理も最低限に抑えられたアルバムである。
適度にエンジニアリングされたスタジオライヴ/スタジオセッションと考えるのが妥当だろう。
◆「The Austin Sessions」は新譜か?
Edwin McCain Bandでの長年のパートナーである、Larry Chaney(ギター)、Craig Shields(サックス)と組み、アクースティックなフォーマット、即ち音の本質そのものが音楽を語れるスタイルで表現したアルバム。幾つかの新しい歌と、お気に入りの古いナンバー、そしてカヴァー・ソングをセレクトした。
以上が、「The Austin Sessions」の骨子とMcCainは説明している。
まず、くどい位にEdwinが主張していた、
「Edwin McCainとは個人のミュージシャンではなく、バンドなんだ。」
という発言からは少し異なったものになった気がする。
元来、メジャー1作目の「Honor Among Thieves」(1995年)からアルバム上の表記はEdwin McCainとなっていたが、ライヴ情報等ではEdwin McCain Bandというバンドユニットを主張する名前を使用していた経歴がある。実際にアルバムクレジット以外では、バンドという実体を強調するため、Edwin McCain Bandを使っていたらしい。
メジャーのプロモーション活動に於いて、何々Bandと名前の後に続くグループ名はあまり好まれず、変名やリーダーの名前だけを冠するように求められることが多いらしい。確かにインディ・シーンでは数限りない“誰彼バンド”というネーミングはメジャー・シーンではあまり見られない。
それは兎も角として、これまでの経緯からして、Edwin McCainとはソングライター且つリードシンガーのEdwin McCainを中心とした5ピースのバンドなのだが、名前としてはEdwin McCainを名乗っていた次第。
が、今回のアルバムは5ピースというスタイルからも逸脱している。ベースのScott BannevichとドラムスのDave Harrison、そしてギタリストとして新しく6人目のEdwin McCain Bandメイトとなった(ソロアルバムも彼らの公式サイトで販売され始めた)Pete Rileyも、参加しているのは2曲だけ。
この「The Austin Sessions」はEdwin McCain Bandとしてではなく、Edwin McCainがバンドメンバーと協力して作成したイレギュラーなアルバムという位置付けが似合いそうだ。
しかし、公式にはEdwin McCainの6作目として数えられていることを挙げておこう。
また、冒頭に記したように、このアルバムは新曲、リメイク曲、そして他のライターが提供した曲及びカヴァー・ソングからなる。所謂アクースティックベストという性格も付随しているのだ。
とはいえ、これまで放った2枚のトップ40ヒットを含めた数曲のヒットシングルはアクースティック・リアレンジとして登場していないので、ベスト盤と見なすのは苦しいかも。
Edwinが気に入ったナンバーをアクースティックで再録した、パーソナル・ベスト+アルファと考える方が妥当だろう。
内訳は以下の通り。
●新曲・・・5曲のうち、4曲はEdwinと他のライターとの共作。
#1『Let It Slide』
#3『I Want It All』(フルバンド演奏。ファーストシングル。)
#4『Little Girl』
#10『Wino’s Lullaby』
#12『Beautiful Day』(フルバンド演奏)
●リメイク曲・・・・カッコ内の数字は収録元のアルバム。
#2『Go Be Young』(Messenger)
#5『Sorry To A Friend』(Honor Among Thieves)
#8『Ghosts Of Jackson Square』(Messenger)
●カヴァー曲又は外部ライターの提供曲
#6『Popcorn Box』
#7『No Choice』
#9『Island Song』
#11『Romeo And Juliet』
カヴァー曲で著名なのが、Dire StraitsのMark Knopflerが創り、そして歌ってヒットさせた『Romeo And Juliet』(邦題:ロミオとジュリエット・・・そのまんま。)だ。後の曲はオースティン周辺のシンガーやソングライターということ。
また、これまで殆どの曲を単独で書き上げていたEdwin McCainが外部ライターの曲を積極的に取り上げたり、共同制作したナンバーを新曲の殆どに充てていることも、新しい試みだと思う。3曲のリメイク曲は全てMcCainの単独作品という事実を見れば、かなり既存のスタイルから変革を求める姿勢が見えてくる。
ということで、リメイク曲は全体の4分の1の3曲で、純然たるカヴァーは#11だけなので、ほぼ新譜と考えて何ら差し支えないだろう。見方を変えるなら、9曲の新マテリアルに3曲のアクースティック・リヴァージョンが付け足されたアルバムとすれば良いのでは。
◆2曲のフルバンド・パフォーマンスも良いけど、アーシーなアンプラグド新曲が輝く
3曲のリ・レコーディング曲に関しては、オリジナルからドラムス、エレクトリックギターを始めとしてオーケストレーションやキーボードを排除しつつ、楽曲的には元ヴァージョンを忠実になぞったものだ。
元来、どの曲にもEdwinの弾くアクースティックギターが含まれていたので、大幅な改変を感じることは無い。
しかし、非常にメロディアスな曲がドラムレスのフル・アクースティックで堪能できるので、新曲として考えても楽しめると思う。
外部ライターのピックアップ曲が3曲含まれているが、特段Edwinの曲と並べても浮き上がったり違和感を覚えることもない。
英国フォークの繊細なメロディを滲ませている#6『Popcorn Box』には、Craigのテナーサックスが良く似合い、フュージョン・ポップやAORといった1980年前後の良質なアダルト・ポップをフォーキィに焼き直しした如くな感想を覚える。
マンドリンのリフが美しく、恐らくはフルートだろうが、バックで密かに鳴っているリコーダーの音色が更に曲調をセンチメンタルに演出する#7『No Choice』も優しさが溢れるルーツ・ポップとなっている。フルートのソロとマンドリンのソロが掛け合うパートがとても微笑ましい。
懐かしの西海岸ポップ、と叫びたくなるメロウな#9『Island Song』が提供された3曲の中では最もソフトで蕩けそうなメロディを持っている。爽やかなアクースティックギターの涼しい弦。これを彩るテナーサックスとエレキギターのバックアップは、Andrew GoldやAlbert Hammond、J.D.Southerという懐かしの西海岸ポップを聴いていた頃にタイムスリップした感覚を与えてくれる。
そして、Dire Straitsの曲の中でも一際ポップで美しいバラードの#11『Romeo And Juliet』のカヴァー。Mark Knopflerのガラガラでトーキングラップ気味なヴォーカルで切々と歌われるオリジナルも得体の知れない味わいがある。が、Edwin McCainのヴォーカルで、アクとドギツサと華やかさをBryan Adamsの声から抜いたような深みのあるハスキー・ヴォイスをして表現しているこちらのヴァージョンも、静かでしかし熱い感情が満ちている。
そして新曲になるのだが、#3『I Want It All』と#12『Beautiful Day』のみ、Edwin McCain Bandが総出演しているエレクトリック・フルバンドなパフォーマンスが聴ける。
特に#3『I Want It All』はCraigが弾くフェンダーローズや、ゲストミュージシャンのピアノまで取り入れられた良質なポップロックソングであり、ハイトーンなコーラスが散りばめられた極上のヴォーカルが聴き所でもある。Craigのサックスはここでも最高に光っている。
こういった単なるジャズやアクースティックの上っ面を掬うだけでJam Bandを名乗る有象無象とは異なるメロディ・メイキングの才能がEdwin McCainをメジャーバンドに為さしめた要因だと思う。
#12『Beautiful Day』は少しJam Rockさが見えてくる、Edwinお得意のスタイルなポップチューン。フュージョンロックというかジャズロックの影響を匂わせつつ、トラッドサウンドと絶妙に同居させているところは流石だ。
が、今まで以上にルーズで土臭いアクースティックなナンバーがこのアルバムのメインだろう。
マンドリンのスライドが実に心地良い、#1『Let It Slide』はHootersやBruce Hornsbyがヒットさせたトラッドなポップシングルを更にアクースティックに特化したような良質なRoots Pop/Rock。アクースティックさでは元々十分なアレンジを施してきたEdwin McCainだが、ここまでテキサス的なルーツフィーリングを見せたことは初めてだ。前作「Far From Over」もアーシーな下地が過不足無く存在していたが、それを遥かに上回る暖かいトラッド・フィーリングが活きている。
#4『Little Girl』も#1や#3と並んで、筆者の大のお気に入り。ドラムレスな編成で演奏するというスタイルを補うために、ハンドクラップ−手拍子がパーカッション代わりにアレンジングされているが、これが実に素朴な曲調に似合っているのだ。また、このパートはEdwinのヴォーカルを重ねているのだが、ハーモニー・コーラスが元気に踊っている。
ジャンピング・フォークという名前を付けたくなるアクースティックロックだ。
#10『Wino’s Lullaby』のみ、唯一のEdwin McCainが独りで書いた曲。スライドギターの鳴きの音とアクースティックギターのしっとりとした音色のユニゾンが聴けるバラード。この曲もこれまでのEdwin McCainに近い感じがする。が、アーシーなテキサス風サウンドがやはり特徴ではある。
どうやら、共作や外部ライターと接した方が、Edwinは土臭いアメリカンルーツ寄りな歌が書けるのかも知れない。
◆「The Austin Sessions」は買いか?
アルバムジャケットの、ぽつんと立てられたマイク。そしてその横に立て掛けられたアクースティックギター。
これでアルバムの方向性を想像できると思うが、これまでのEdwin McCainのアクースティックでメロディアスな側面が好きなら迷わず買い。
ジャム的なジャジーでアクースティック・オルタナティヴというもう1つのEdwin McCainの特徴に重きを置くリスナーには正直お薦めはしない。
今までのアルバムで最もルーツでアクースティック、且つメロディックだ。ロックバンドとしてのパワーは、アルバムの性格上非常に希薄であるけれど、それを補って余るモノが存在する。
静かな熾き火の如きエモーショナルでアーネストな感性が、この閑静なアルバムに満ちているのだ。
インディ落ちがどうやらプラスな転機となったようであり、喜ばしい限りだ。次は恐らくロックアルバムを持ってくるような予感がするが、これまたアーシーなルーツ感覚を継承してくれれば最高だ。是非期待したい。
(2003.4.20.)
 I Began To Fall / Dan Gediman (2002)
I Began To Fall / Dan Gediman (2002)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★
Americana ★★★☆ You Can Listen From Here
◆珍しい副業(?)のマルチプレイヤー
このDan Gedimanの2作目「I Began To Fall」を聴くにつけ、Dan Gedimanというシンガー・ソングライターが演奏する楽器の多様さに目を奪われてしまう。
ギターを始めとして、ベース、エレクトリックピアノ、オルガン、シンセサイザー、アクースティックピアノ、マンドリン、という具合にドラムスを除く殆どの楽器に手を入れている。
これに加えて、当然ながらリードヴォーカルとバックヴォーカル、曲の作詞作曲を行うという、最近はあまりお目に懸かれなくなったマルチプレイヤーとシンガーソングライターという多面体もかくや、という活躍をしている。
更に、このDan Gedimanという人はミュージシャンだけを生業にしていない。
最も好きで一番の仕事と思っているのはミュージシャン、とDan本人も述べているが、レギュラーで幾つもの仕事を抱えているラジオ局のプロデューサーでもあり、パーソナリティでもあったりする。
15年以上も、ナショナル・ワイドのラジオ番組のプロデュースをしたり、放送を書いたり、実際に出演しているので、こちらではかなり有名らしい。
「子供虐待を止めるためには。」、「多重人格の崩壊。」といったプログラムで幾つもの放送関連の賞を受けている人でもあるらしい。
著名なミュージシャンにDJを担当させるというのは日本のFMでも珍しくないが、実際にプロデュースから放送作家までこなしている人がシンガーとしても活躍しているという事例はあまり多くなさそうな気がする。
一風変わったシンガーであることは確かだろう。
◆一概にAlt-Countryとは言い難いけど・・・・
正直、Dan Gedimanの音楽ジャンルを決めるのは難しい。
普段ルーツロックを殆ど聴かないリスナーであれば、単なるカントリーやカントリーロックとして分類されそうなくらいにレイドバックしているのは確かだ。
例えば、Jack Ingramをカントリー・シンガーと見なしている人であれば、十中八九Dan Gedimanはカントリー系のシンガーと認識されるだろう。しかし、当然筆者とすれば、Dan Gedimanがカントリーのみのシンガーとは思っていない。
とはいえ、Alt-Countryのパンキッシュでトワンギィなロックンロール的要素が突出していないため、Alt-Country系のロッカーと断じることも難しい。Alt-Countryとしての尖がりというべきか、爆走っぷりがこのシンガーの特徴としては浮き出ていないのである。
どちらかというと、John Hiatt的なカントリー風のロックナンバーも有り、シンガー・ソングライター的ナンバーも有り、そしてルーツロック的な総括的な曲を持ち味にしている歌い手と捉えておきたい。
しかしながら、良い意味でメジャー的なアレンジメントを曲に持ち込んでいるJohn Hiatt程にはソフィスティケイテッドされてはいない。Dan Gedimanは肯定的な意味で、マイナー・アーティストならでわの素直で実直な感情の込め方を、ソングライティングに感じさせる。
要するに、イナタ臭くなったJohn HiattやJohn Mellencampというイメージを思い描いて貰えば非常に適切なゾーンにぶち当たるというところだ。
John Hiattまでカントリー臭いシンガーとして敬遠するようなリスナーには最早お薦めは不可能だが・・・・。
しかし、ドブロギターを目一杯使い込んだ、ドが付くカントリーなナンバーも何曲かあるし、全体的にミディアム以下のナンバーが大半を占めている所とかを挙げてみると、かなりカントリー寄りなシンガー・ソングライターということは明らかだ。
このジャンルをAmericanaと便利な単語で括るか、それともAlt-Countryとした方が良いのか。この点で結構迷ったが、「歌い手」=シンガーである面を無意識のうちにアピール出来、している人だと思うので、ルーツなシンガーという意味でAmericanaと便宜上分類しておいた。
やはり、Alt-Countryのバンドに特有なスカスカなカントリーの明るい面を見せたり、遮二無二パンクのアクセレーターで前進するという、所謂バンドサウンドには欠ける人だ。
じっくりと歌を聴かせる、落ち着いて歌を唄うということに重きを置いているシンガーだと思うので。無論、だからとって、ロックンロールとは掛け離れた場所でトラッド音楽をのへ〜〜んと歌う人ではないのだ。これは今更断るまでもないとは思うが、念のため。
◆第1作目の「I’m Trying」から5年振りに2枚目を発表
Dan Gediman & The Mind Reelというクレジットで発表された「I’m Trying」の録音が1996年。発売が1997年である。本作「I’m Trying」まで5年間の空白が存在し、またAnd The Mind ReelというDan Gedimanが従えていたバンドの名前が消えている。
実際のレコーディングに関しては、元々Danがかなりの楽器を使いこなしているので、今作も演奏のスタイルが劇的に変化したということは無い。但し、The Mind Reelのメンバーだけでなく、曲によってかなり異なるミュージシャンと共演している。
才能のあるマルチプレイヤーなため、バンド形式に拘ることはなかったと、前作の時点で感じていたため、この曲によって多くのサポーターを迎え入れるというスタイルの方がDanには相応しいと思う。
又、5年の空白の期間にしても、ラジオの仕事は続けていたので、全く逼塞していたということでもない。Danは自分が一番好きな仕事はミュージシャンと述べているが、実際にラジオの固定番組を受け持っているためかなりの日数を拘束されることは間違いなく、これが5年もの間隔を2作目まで空けてしまったことの1つの原因であるだろう。要因であるかは不明なところだが。
Danのデビューアルバムは、「ブルーグラスの味わいのあるインドア的ロックンロール」とか単に「フォーク・ポップ」という表現で、メディアにはかなり好意的に迎えられた様子だ。
確かに、フォーキーでかなりカントリーっぽいところがあるシンガーの作品だった。
この1枚目と比べると、新作はかなりロックンロールとPop/Rockを感じさせる。
正直、筆者がこのアルバムを聴いて真っ先に思い浮かべたアーティストは、「Walk On」の頃のJohn Hiattであり、元Del LordsのScott McClatchyだった。後、少しばかりJoe Elyとか、Neil Youngとかも。
カントリーというよりも、レイドバックと呼ぶ方が適切な、より土臭いレイドバック感覚が鮮明に打ち出されている故、全般的に渋みが増している。同時にポップな曲創りは健在以上の親しみ易さを誇っているため、トラッドの燻し銀な鈍色さだけで勝負するという一元的な作風でもない。
ルーツ・カントリーミュージックの渋さと落ち着きを保ちつつも、キャッチーなポップソングを書けるライターなのだ。
そして、決してアップビート主体でガンガンと攻勢を掛けて来るのではないけれども、ロックンロールの深みと表に全てを出さずに力を感じさせるという、1枚壁を隔てて機械の馬力を知覚するという感じ。少々表現し難いのだが、エンジンの発熱を、フィルター越しに手触りで感じるという類の、一歩引いた所からロックンロールのパワーを表現可能にしているという所がある。
直接的にロックの馬力を投げかけずに、じっくりとした曲にロックンロールの重みや深みを込めて、それをリスナーに伝えることが出来る。言わば老獪なセンスを感じさせるアルバムだ。
普通、こういったロッカーとして老境に差し掛かった人に感じることの出来る特徴を、まだ年齢としては決して年寄りに当たらないシンガーに感じることができるというのは珍しい。
正直、筆者は「ヴェテランの渋み」を売りにした方向のアルバムはかなり虫が好かないことが多い。年齢相応の深みや重みを、そのミュージシャンが積み重ねてきた人生経験を基にして曲に出すことに付いては全く嫌悪感は無い。
が、「狙い過ぎ」な如何にも「重鎮らしく、熟練らしく、大人向けの芸術的作品を作りましたよ。」とターゲットを絞っているような、俗に言う大御所のアルバムは聴く気が阿保らしくてしない。
ポップやロックの基本を蔑ろにして、自分のキャリアをひけらかした如くの表層的な渋さや燻しを狙ったアルバムは、ロックと言うのも烏滸がましい。
そのような偽善的な“ヴェテラン味”とは無縁な、実に素朴で基本に忠実なルーツポップ・ロックをDan Gedimanは提供してくれている。ここに疲れとか気怠るさを感じる余地は無い。
良心的なレイドバックサウンドを創ること。この種のとても純粋な意図に沿って、この「I Began To Fall」は作成されていると思うのだ。ロックンロール重みや暖かな味わい、ゆったりとした大人の感性。こういったものが実質的に付随するのは、故意に狙ったものでない限り、実に好ましい。
◆タイトル曲は、月琴を思わせる月影なバラード
アルバムのタイトル曲『I Began To Fall』は全12曲のうち、3曲目にトラッキングされている。
まず、この#3のリフには驚かされる。マンドリンをDanが弾いているのだが、この透明感溢れるマンドリンの音色は、月琴を思わせる。実に透き通った美しさがある。
全体的にルーツ楽器として使用されるマンドリンは田舎臭いアーシーな音色を出すことで採用されるものが多い。実際に、マンドリンは美しいというよりも懐かしい、暖かいという印象を抱かせる音を発する役割として用いられることが普通だろう。
しかし、Dan Gedimanは、この#3に限り、クラッシックやニュー・エイジで使用されるオーケストラマンドリンの如く、徹底的に清水な音色を弾き出すデヴァイスとして手に取っている。
このアルバムではそれなりの曲でDanがマンドリンを掻き鳴らしているが、このようなロック楽器としての用途から掛け離れた弾き方をしているのはこのナンバーのみだ。
また、マンドリンを補助するように、エレクトリックピアノ、オーケストラ、ベース等が静かにバックアップをしている。然れども主役は常にメイン・ラインを辿るマンドリンと、Danのヴォーカルだ。
ラジオのパーソナリティとしてキャリアが長いのが頷ける、くっきりした発音と力のある声質。少し粘着質な男臭さが魅力なDan Gedimanのヴォーカル。しかし、ここまで浪漫ティックなバラードをアルバムに採用するとは予想の外であった。マンドリンを使っている・いないを別としてこれはルーツバラードというよりも、吟遊詩人の弾き語りを思わせるアダルト・コンテンポラリーソングだと思う。
◆やっぱりロックナンバーは良い!!
タイトル曲は美麗さを追求したもので、それはそれで良し。
でも、やはりDan Gedimanの本領はロックナンバーだと思う。
まずは、Hooters顔負けのマンドリン・ロックである#1『Forget-Me-Not』。Danのマンドリンとギターにリズムセクションと女性ヴォーカルが加わっただけのシンプルな編成だ。
このナンバーが筆者が最もこのアルバムで好きな曲なのだが、メロディ的にもっとロックンロールだったり重厚なルーツナンバーだったりする曲は他にも存在する。つまり筆者の好みのストライクゾーンを突いてくるトラックは他にも偏在しているということだ。
それらを差し置いて、このまさに『忘れないで』というタイトルに、「絶対に忘れない。」と答えたくなるくらいインパクトを貰ったのは、マンドリンの使い方だ。
スライドするギターと適度に厚い楽器のインプロヴィゼーションに、効果的に絡んでくるマンドリン。このマンドリンがポップなメロディと相まって、思わず気分が踊り出すような明るいルーツナンバーに#1を持ち上げている。
他の曲に於いてマンドリンは、カントリー・フィーリングを補填される使い方をされており、この#1のようにロックマンドリンとして弾かれているのは無いからかもしれない。
アーシーでたっぷりしたギターが地響きを立てて進撃するような分厚いミディアムナンバーの#2『Terreplane Motel』。アルバム中で最もハードドライヴなナンバーだと思う。Danはケンタッキー州のルイヴィルを拠点に活動をしているが、まさにアメリカど真ん中の広大な大地の質感を叩き付けるようなリッチな曲。Danの担当するオルガンがSouthern Rock的な骨太さを出しているが、この極端に土臭くならないアレンジは1980年代のアリーナサウンドの影響も見て取れるように感じる。
アクースティックとエレキギターが気持ちの良い快感を紡ぎ出す#4『This Is The Place』でも、オルガンはクリティカルな音を出しつづけてくれる。ウエストコースト風のギターリフにピロピロと重なるオルガンのエコーがアンサンブルの装甲をギター一辺倒で纏めずに、厚目にならしめている。
また、♪「A−Ha,Ha」と頭からリフレインされるテナー・ヴォーカルが単調ゆえに耳に憑いて離れなかったりする。
最後のナンバー、#12『Don’t Let Me Go』もルーツィながら、分厚いラウドさが満ちているアリーナロック的な側面のあるロックチューン。アリーナロックという言い方が不適切だとしたら、Adult Alternative
+ Roots Rockだろう。
ディストーションの効いたギターとシンセサイザー、そしてハーモニーを付ける女性コーラスと、シンプルながらスペイシーで浮遊感の存在するサウンドを淡々と続ける。異質とまでは行かないが、Danの複雑な音楽性を最後の最後で振り返らせる曲。
◆Boogie Rockもあるぜよ
ライト・ホンキィ・トンク風の#5『Do You Think About Me ?』はStones/Faces風のピアノロック。サックスのゲストまで加わり、クラシカルなBoogie-Woogie Rockをたっぷりと演奏してくれる。
何と、この曲でスライドギターを弾いているのは、レーベルメイトにしてヴェテラン・プロデューサーでもあるTim Krekelというから驚き。Timのギターを聴くだけでも、この曲は注目に値するだろうが、やはりトンキィなピアノを終始弾きこなす、Dan Gedimanの手数の多さには賞賛を与えずには要られない。
#7『Just Don’t Know』もブギーなルーツロックだ。#5よりも更にルーズでラフな酔いどれロックナンバー。このナンバーではDanがピアノを担当していないのだが、ジャジーなピアノソロを自身のギターソロに絡めて、思いっきりスゥイングしているところはセンスを感じる。
また、Danのヴォーカルも何時に無く調子を外したような酔っ払いヴォーカルとなっている。このあたりの切り替えと歌い分けは決して美声とはいえないが、耳に良く響くDanのヴォーカルのオルタナティヴを代表している。
これらのロックンロールとは趣を変え、スローでじっくりとブギーするのが#10『So Hard』。Danはドラム以外の全ての楽器を一手に引き受け、ハモンドB3サンプリングを始めとする幾つかの鍵盤からギター、ベースまでと、マルチプレイヤーの本領を発揮している。またオーヴァーダビングしたコーラスも全て自分というところまで徹底している。
が、これで打ち込みドラムでも使われた日には萎え萎えになりそうだが、そのあたりはちゃんと心得ているようで、絶対にプログラミングを持ち込まないところにDanの拘りと良心を感じるのだ。
◆ドブロギターとマンドリンでカントリー
ここまでの曲では、Dan Gedimanがカントリー系のシンガーという面は見えてこないと思う。
しかし、#6『Terrible,Horrible Thing』を始めとしたドブロギターとマンドリンを主役に選んだ曲では、ベタベタなカントリーナンバーが聴けるのだ。
女性ヴォーカリストとのほぼデュエット形式で歌われる、#6ではもう完全無欠なブルーグラスソング。Danのヴォーカルがカントリーに転がりまくっているテナーヴォイスでないのが救いというしかないくらいお約束なグラスソングだ。
#8『Some Day』ではブルージーなメロディに沿っているが、これまたドブロが鳴き声をあげ、マンドリンがクネクネと弾かれるカントリー曲。カントリーロックではなく、完全なケンタッキー・カントリーだ。
#11『Best Of Dads』のみ、少々他のドブロナンバーとは趣を異にする。
#11はギター1本とドブロギターだけで綴られるスライドなアクースティックナンバー。しかし、フォークサウンドの柔らかさは全く存在しない。ブルージーというよりもひたすら泥臭いドブロが泣く、シンプルな曲だ。弾き語りブルース、カントリー風のブルースという言い方でも良いかもしれない。
こういった弾き語りナンバーに、こういう辛目のナンバーを持ってくるところが、これまたDan Gedimanのディープなルーツ嗜好を思わせる。ポップ寄りな人であるのだが、このような曲でドン深いルーツ感覚を出すところが、一枚岩でないDanの音楽なのだろうが。
◆ケンタッキー州の面白いシンガーに注目
まだ2枚しかアルバムが無い。普段はラジオ関係の仕事が中心で、ライヴも月に平均3〜6回しか行っていない。
このような変り種のシンガー・ソングライターのDan Gediman。
かなりケンタッキールーツのブルーグラスの影響を感じるかと思うと、出身地のボストン風の都会的なロックセンスも見せるという、かなり面白い感性を持った人だと思う。
シンガーとしても、パワフルな喉を持っているので、熱唱は似合わないが、説得力のある誠実さを歌に刻み込むには打って付けだ。
音楽活動が最も好き、というコメントに沿うように、もう少しミュージシャンとして活動をして貰いたいと願っている。
そうすれば、3枚目はもっと早くに届けられると思うので。 (2003.4.26.)
 Rainy Day Music / The Jayhawks (2003)
Rainy Day Music / The Jayhawks (2003)
Roots ★★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Alt-Country ★★ You Can Listen From Here
◆急病を経験したGary Louris
本作「Rainy Day Music」は2002年の夏には基本レコーディングは終っていた。2002年中にはマスタリングやミキシングも終了し、本アルバムの作風に合わせたと考えられる、The Jayhawksのアクースティックツアーも同年11月から始まっていた。
が、2003年1月、突如としてGaryのマネージメントサイドからLourisが急性の心嚢炎で危険な状態に陥り、救急車で病院に運び込まれたことが伝えられた。
幸いにして大事には至らず、Gary Lourisは間も無く退院して、翌月の2月にはCrosby,Still&Nashのオープニングアクターとしてステージに立っている。
しかし、健康上の障害を起こしたというニュースを聞いた時、Garyを心配したのは勿論だが、Jayhawksというバンドが既に中堅以上の活動歴を持っていることを改めて思わずにはいられなかった。
ミネアポリスでMark OlsonやMark Perlman等とThe Jayhawksを結成したのが1985年−18年前である。アルバムデビューが1986年の「Jayhawks」だから、17年で7枚のアルバムとそこそこのペースで活動しているバンドということが見て取れる。
しかし、今回の新作「Rainy Day Music」は実質、7年ぶり。「Tomorrow The Green Grass」以来の、Jayhawks本来のアルバムになったと思うのだ。
◆Tomorrow The Green Grass 以降
Jayhawksのインタヴューを扱った新聞記事の前書きに以下のようなことが書いてあった。
「ヴェテランバンドは自らのトレードマークとされるサウンドから実験的なサウンドへと移行することに対して、リスクと恩恵の両方が存在することを知っている。熱心なバンド信者や信奉者は、この打ち上げに追従することが出来るし、そのバンドの冒険心に対して拍手喝采するだろう。
ただ普通にCDを買っていたファンは、きっと『駄目だこりゃ』と切り捨てることになる。そして、新しいファンが離れていったリスナーに取って代わることになる。彼らはバンドの過去のサウンドについては興味がなく、単に新しい試みによって生まれたグルーヴに耳を慣らして行く。」
この記事は、まさにJayhawksのルーツ&カントリーロックの集大成と言うべき「Tomorrow The Green Grass」を発表以降、バンドが「Sound Of Lies」、「Smile」という既存のJayhawksの方向性を破壊する如き非ルーツアルバムを送り出したことに言及している。
しかし、どれだけのファンが「Sound Of Lies」、そして打ち込み音やシンセサイザーを多用した完全エレクトロニック・ポップアルバムという事実を突き付けた「Smile」に拍手喝采しただろうか。
筆者としては、上記の記事で述べられている新しい世代のファン−「Sound Of Lies」以降からJayhawksを追いかけ始めた−を除いては、決して無条件で脱ルーツの傾向を受け入れていたのではないと考えている。無論、熱狂的な信者は別としてであるが。
何時までも既存のトレードマークサウンドに張り付くことを良しとしないミュージシャンは数多いが、そのトレードマークが大好きだったリスナーは、ある程度の裏切りを喰らっても、「しかし、今度こそは・・・・。」という儚い希望を抱きつつ、バンドのアルバムを買い求める。そのうちに、現在進行形の最早実験的サウンドとは呼べない方向転換に慣れ切ってしまうことだってあるだろうけど。
かく言う筆者も、Jayhawks=カントリー・ロック、ルーツポップ。以上の公式で見ている世代である。Jayhawksの筆おろし(笑)が、完全カントリーバンド時代だった「Blue Earth」(1989年)なのだから、これはある程度仕方が無い。
だから、陰鬱で内省的な「Sound Of Lies」はどうしてもJayhawksの作品と呼ぶには抵抗があったし、打ち込みダンスナンバーなんぞを加えてきた「Smile」に至っては、論外だった。正直、ELOの劣化版としか思えないくらいの酷い裏切りだったのだ。
「Smile」を聴いても、決して微笑むことは出来なかったのである。
Jayhawksファンの間でも、この辺りの評価も見事に割れていて、「Sound Of Lies」や「Smile」からJayhawksに入門したレヴュアーは、「Smile」に対して肯定的なレヴューを捧げているが、昔からのファンは相当批判的な意見を投下している人が海外筋では多いのだ。「Big Mistake」等という表現は頻繁に見られる。
当然、ジェイホなら何でもオッケイ、という信者は数には入れていない。
ということで、次に駄目だったらファン辞めようかと思い始めた頃、「次はルーツアルバムになる」というニュースを耳にした。
2002年夏から7週間近くを掛けて始まったレコーディングの経過では、ライヴ録音中心のアクースティックなサウンドを活かしたアルバムになるというリアルタイムな情報も飛び込み、期待半分以上になっていった。然れども、拭いきれない不安は存在していた。「Sound Of Lies」=「偽りのサウンド」というタイトルが示す通り、1997年からこちらJayhawksには偽られ続けていたからである。
果たして、この情報が嘘でなかったことを、Jayhawksは7枚目のアルバム「Rainy Day Music」で示してくれた。
そう、これは1995年発売の「Tomorrow The Green Grass」以来のルーツアルバムとなったのである。
◆然れども、Mark Olsonは戻らず・・・・
今回の久方ぶりのルーツロック、カントリールック回帰について、バンドリーダーであるGary Lourisは以下のようにコメントしている。
「新しいアルバムはBob Ezrinのキーボードやシンセサイザーを多用したSmileへの反作用みたいなものさ。
私達は、大仰で、装飾的で、楽しく、そしてキラキラしたポップレコードを作った。だから、私達は自分達自身にこう言い聞かせた。『さあ、180度向きを変えて、幾つかのエリアを再び訪れることにしよう。それは多分、もっとアクースティックベースな下地で、けれども出来る限りライヴ録音するということ。そして、これまでに私達が上手くやってきた要素を取り戻すこと。』とね。
私達はそのアクースティック且つライヴ性の高い音楽というテリトリーに過去7年の間落ち着いていた経験があるけれど、今やその場所は再び新しいテリトリーとなっているんだ。」
このコメントを読み、優等生的信者サイトなら、きっとこう書くに違いない。
“「Sound Of Lies」と「Smile」という回り道があったからこそ、「Rainy Day Music」の原点回帰があるのだ。」、と。
しかし、筆者は木っ端ミジンコにもそんなことは考えない。一言で断ずれば、
要らん回り道で6年も無駄にせんと、キリキリルーツアルバム作ってれば良かったんじゃないか!!
つーか、作れるなら何故今までやらんのじゃい? となる。
実際問題として、「実験的作品」、「新境地に挑んだ作品」が全くの詰まらないアルバムになってしまっているので、今更「原点回帰で新境地を再度得た。」とかノタマワレテモ、はっきり云って興醒め。
素直に、「スイマセン。エレクトロポップとか脱ルーツ作品では売れなかったです。元に戻します、ゴメンナシャイ。」
と謝罪して貰った方がなんぼかマシである。
といいつつ、紆余曲折を経た結果、久方ぶりのルーツ系アルバムを発表することになった結果自体は、好ましいことと捉えているけれど。
しかし、「Tomorrow The Green Grass」以降、急速にJayhawksからカントリー色やアクースティック色が霧散してしまったのは、当然Jayhawksのルーツ部分を担当していたMark Olsonが1995年に脱退してしまったからと考えていた次第であった。
現実に、Olsonが古巣を離れた後に結成したMark Olson And The Original Harmony Ridge Creekdippers(現在はMark Olson And The Creekdippersを名乗っている。)は元バンド以上にフォーキィでカントリー・ミュージックに踏み込んだプロジェクトだった。
それと相対するようにGary Louris率いるThe Jayhawksがルーツサウンドから遠ざかっていったので、ジェイホのカントリー・パート=Mark Olsonの役割、という公式が填め込まれても不思議は無い。
ところが、7枚目のフルレングスとなった「Rainy Day Music」は「Tomorrow The Green Grass」どころか、更にカントリーバンド丸出し度が強かった「Hollywood Town Hall」や「Blue Earth」の頃のアレンジに近い作品になっているのだ。
そして、ルーツ楽器とレイドバックなサウンドに流れるハーモニーやヴォーカルワークの中に、Mark Olsonのハイトーンでジェントリィなヴォーカルを見つけることは出来ない。
そう、今回のアクースティックでルーツなアルバム−Mark OlsonのCreekdippersが手を貸したと説明されても何ら疑問を抱かない如き−にはMark Olsonのクレジットは存在しない。
Mark Olson抜きで、ルーツアルバムを完成させた。この意味では確かに、Jayhawksは再度既に開拓したテリトリーに踏み込みつつも、その地域を新しく感じているという発言は、あながち間違いではないかもしれない。
◆メロディ的にはこれまでで最もポップか?
今回、正式にJayhawksのメンバーとしてクレジットされているのは僅かに3名のみ。デビューから一貫して4名以上のバンド編成を維持し続けたJayhawksも、3ピースになってしまった訳だ。しかし、元Long RydersのギタリストであるStephen McCarthyが準メンバー扱いでレコーディングに加わっている。Stephenはヴォーカル、ペダルスティール、ラップスティール、そしてバンジョーといったルーツ系のギター系楽器で8曲に参加している。2003年のツアーにも5月から参加し、正式メンバーとして迎えられる可能性が高いということだ。
また、コアメンバーは3人としても、数は少ないが豪華なゲストが参加し、サウンド的な薄さは全く感じることは無い。
そして、ことコマーシャルさに関しては、非常に近いアレンジで構成されている「Hollywood Town Hall」とは比較にならない程ポップである。「Tomorrow The Green Grass」そしてメロディだけに限ればかなりキャッチーだった「Smile」を凌駕する位に親しみ易い曲が揃っている。
Mark Olsonが脱退した後、その苦悩を反映したかのように陰鬱で内省的なサウンドに変じた「Sound Of Lies」の面影は全く見られない。更に、単なるカントリーロックであり、ソングライティング的には特筆するべき点の無い「Jayhawks」(幻の激烈プレミア盤)や「Blue Earth」とは異なり、“カントリーロックだけ”が取り得のアルバムでもない。
真実、ルーツアルバムでありながら、ポップアルバムであるのは本作と「Tomorrow The Green Grass」だけであると思っている。「Hollywood Town Hall」はカントリーロックやルーツアルバムとしては非常に評価したいが、如何せんロックやポップ作品としては難があると筆者は考えているからだ。
◆「Rainy Day Music」についてGaryが語っていること
「飾り気のないルーツ的アルバムを作ろうという計画は最初からは無かったね。アクースティックツアーが始まるから、そのツアーに対応したアクースティックなアルバムを作る必要があるだろう、ってプランは既にあったけど。だから、今回のアルバムは偶然の産物といって良いと思う。アクースティックツアーを行うから、それに合わせたアルバムを作っただけ。私達はレコードを発売しないけど、しばしばツアーに出る。バンドを続けることは何も、1千万枚レコードを売る必要はないからね。レコードを出さない3ピースのバンドにはツアーに出ることがいちばん簡単なモチベーション維持の方法なのさ。」
「“Smile”の時とはかなり曲を書く過程は異なっている。事実、私達は歌をアクースティックギターだけで演奏して、後からヴォーカルを加えようというアイディアから出発した。それが本当に歌が良いモノかどうか分かる方法なんだ。私達が学んだことの1つに、このようなことがある。スタジオの機材を弄くることはとても面白い。けれど、コンピューターや機材に没頭すると、曲作りの過程を失うことになる。ひいては本当の歌を見失ってしまうんだ。
このレコードで私達が集中したことは、歌は素晴らしいもので、歌というのはアクースティックギターや生オーケストラで伴奏されてこそ素晴らしいものになる、ということ。」
「Rick Rubinはかなりの部分でレコード製作に関わってくれている。私の知る限り、彼が手を入れているプロジェクトでは殆どの時間をアーティストと過ごし、常に舵取りをして最善の曲を書けるように気を配っている。Rickはエンジニアと調整が付くまで、決して彼の手を離さない。彼は人心を掌握し、最大限の努力をさせる手腕を持っているし、全てのことに対して注目している。レッド・ホット・チリペッパーズと組んで実行した以上のことをJayhawksと一緒に行ったという訳。
私は幾つかのデモトラックをRickに送ってから、ロスへ飛んだ。私はこう思っていた。『今日は最初の日だから、Rickとの打ち合わせは1時間くらいかな。』と。
が、午前3時までRickと顔を付き合わせることになった、合計8時間だ。私達はギター片手にソファーに根を生やし、デモを演奏しまくった。Rickは随時『ちょっと待った。そこは良くなっている。』『それは凄い。』『もっと良く出来ないか?』と意見を述べ、私達がベターなラインを掴んだと確認するまで決して流さなかった。
でも、私が彼のアドヴァイスに最終的に同意しなくても、Rickは『それで良いよ。』と言うだけで押し付けは絶対にしなかった。大抵彼の提案は的を得ていたけど。
Rickはアルバムジャケットやタイトルにも関わっている。」
「レコードの仕上げ作業を3回行ったけど、エンジニアにEthan Johnsを雇うまでレコードは完成しなかった。私が興味を持っていた人物であるEthanが丁度手すきと知り、Rickと会わせた。RickはEthanが気に入った。Rickはその日その日で良いと思うことを実践するタイプで、その方向はコロコロと変わる。反対にEthan Johnsはとても頑固なタイプのプロデューサーだ。RickとEthanに挟まれて、バンドは全てをやり直すハメになったよ。
この2人とレコードを作れたことは大きな福音だった。簡単ではなかったけどね。
Ethanとデモやラフなミックスを仕上げて、Rickの最終的な賛成を得るというプロセスはまるで宿題を認めて貰うような気分で、ドキドキしたものさ。でもこういった2人のプロデューサーのやり取りの中で、彼らはお互いの中間を選ぶという道を得たからね。このレコードにはRickとEthanから得たものが込められている。当然私達バンドも寄与しているけど。」
◆このレコードは長過ぎる・・・・
筆者としては、この「Rainy Day Music」は十分に良作であると思う。だがしかし、14曲というヴォリュームで通し聴きすると、かなり冗長だという印象を拭いきれない。このことはフォーキィーでロックンロールのタテノリに乏しいアルバムには宿縁の如き要素かもしれないが。
ところが、Gary Louris自身が、このアルバムは長過ぎると述べているのだ。
#1『Stumbling Through The Dark』は#14にもリプライズとして殆ど同じ長さのアクースティック・デモ的なトラックが収録されている。バンジョーとアクースティックギターがカントリー的な弦を紡ぎ、ハーモニウムやピアノまでルーツィに使用された、本作の方向性を代表するトラックである。
「私達は最初にデモトラックとして#1を録音した。するとTimが、『この曲はこのままで行くべきだ。』と主張した。実際にアクースティックで演奏したらピッタリだった。私はこのレコードは長過ぎると思っている。しかし、それは曲が良くないからではないよ。
レコードに適切な曲数は12曲前後だと思っているんだけど、近頃は1年に2枚レコードを出すことなんて誰もやらない。3年毎くらいが平均かな。だから、私達の次のレコードは2010年までには出るだろう・・・・。
うん、私は#1のバンドヴァージョンと、アクースティックヴァージョンのどちらが良いか判断付かなかったので、両方を加えたんだ。レコードの間隔が開くなら、曲を少しでも多くした方がファンのためだろうから。」
1曲ずつを取り上げると、実に良いナンバーが多いと思う。
驚くべきことに、元Eaglesにして1990年代の殆どをレコード会社の製作サイドの仕事に廻り、活動をしていなかった“元”EaglesのBernie Leadonがバンジョーで参加している曲がある。
#2『Tailspin』は「Rainy Day Music」の中でもロックナンバーとしてのヒット性の高いギター・ポップ風の曲だ。ペダルスティールやバンジョーが加わっているが、ロックでポップ。これぞJayhawksの真髄だろう。バックヴォーカルにはMatthew SweetやあのStephen Stillsの息子で、シンガーとしてメジャーアルバムもリリースしているChris Stillsが参加している。
美しいピアノのリズムが印象的なミディアム・ポップナンバーの#4『Save It For A Rainy Day』。メロディメイキングの妙を見せ付けられるナンバーである。甘くて繊細なJayhawksの魅力全開な曲だ。筆者としても#2と並んで、最も印象が強いナンバーだ。タイトルにも関わっている曲なのでそのインパクトは強い。
WallflowersのJacob Dylanがヴォーカルで参加した#8『Come To The River』もロッキン・カントリーと言うか、アーバン風のカントリーロックというべきか、兎に角、ラップスティールの捻くれた音が面白いロックチューン。
#9『Angelyne』も軽快でポップナンバーとしては#2とタメを張るチューンだろう。アコーディオンのソロがユニークな感覚を伝えてくれる。
◆しかし、どうにも物足りない
繊細でフォーキィだった時代をフラッシュバックさせるような、#3『All The Right Reasons』、#12『Tampa To Tulsa』。そしてレイドバックしたカントリーロックバラードの#13『Will I See You In Heaven』はMark Perlmanの作。
Mark Olsonに代わるようにハーモニーヴォーカリストしてGaryをバックアップする、ドラマーのTim O’Reaganが2曲でリードヴォーカルを担当している。
#7『Don’t Let The World Get In Your Way』と#11『You Look So Young』がそれだ。
ヴォーカリストとしてはGaryと全く異なっていた声質のMarkに続くタイプではない。どちらかというとGary Lourisに似たヴォイスの持ち主だと思うが。
どちらの曲もストリングスシンセサイザーのシャンバリンが活躍する、バラードタイプだ。Timは後半に盛り上がる曲に縁があるようだ。リードを執っている#7や#11がそのタイプのバラードである。Timは#7と#12を書いている。ソングライターとして単独でバンドに寄与したのは今回が初めて。
と、バラードというか大人しい曲が多いためか、どうにも全体像としてはくっきりとした良さがいまいちだ。強烈に伝わる、これぞJayhawksという要素が不足しているのだろうか。
ややロックナンバー寄りのトラックとしては、微量な哀愁を含んだミディアムロックの#5『Eyes Of Sarahjane』やブルージで粘っこい#6『One Man’s Problem』があるし、また、ザクザクしたサザンカントリータッチの#10『Madman』等は、かなりのルーツサウンドへの回帰を感じるトラックであり、ペダルスティールの使い方に最近忘れ去っていたルーツ感覚を見出せて嬉しかったりするのだ。
確かに、大御所に属する経験を積んでいるJayhawksに寄せる期待がやや大き過ぎるという点もあるだろう。全体的に辛目の評価を下しているという自覚は、筆者にもある。
が、このアルバムには嘗て『Blue』や『Settle Down Like Rain』を聴いた時の、Mark OlsonとGary Lourisのハーモニー・ヴォーカルに覚えた魂の震えが、無い。
ぶっちゃけた話、なまじルーツサウンドに回帰したため、却ってMark Olsonの不在が浮き出てしまっているように感じているのだ。
やはり、カントリーでルーツなJayhawksにはMarkのヴォーカルだろう。Matthew Sweetを始め、ゲストヴォーカルやTimのヴォーカルでは埋められない思い入れがオヤヂファンの筆者にはあるのだ。
とはいえ、ここ2作のガッカリアルバムと比べると天と地の差がある名盤には違いないのだが・・・・。
折角原点回帰を行うという仕事を始めたのだから、ここいらでMark Olsonを呼び戻して貰いたいなあ、とこの「Rainy Day Music」を聴くたびに思うのだ。
しかし、このアルバムは雨の日よりも晴れた日に聴いた方が相応しいと思う。多少ウエットな感覚がドライなアーシーサウンドに見え隠れするという湿度は、晴れた大気の下で聴きたいものだ。 (2003.5.1.)
P.S. ど〜でもイイが、ボケ茄子ディスク付き限定版で、ユーザーの購入意欲を煽るのヤメレ!!
Ryan Adamsの時も同じ事やってる、Lost Highway逝ってヨシ!!! (間違えて通常版注文したヒガミ)

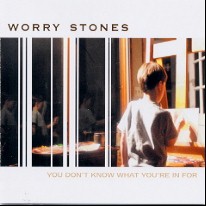 You Don’t Know What You’re In For
You Don’t Know What You’re In For