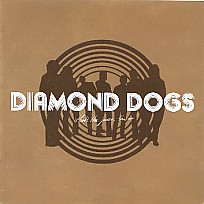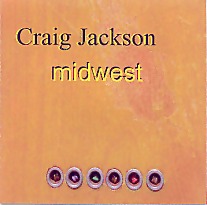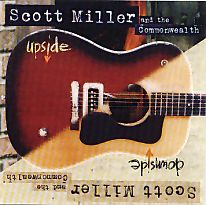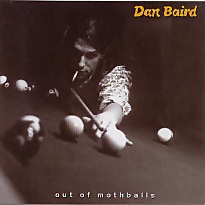 Out Of Mathballs / Dan Baird (2003)
Out Of Mathballs / Dan Baird (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Southern Rock ★ You Can Listen From Here
◆何と、ベアードはんの直筆サイン入り!!
ブックレットの内側にサインペンでDan Bairdの直筆サインが入っている。Danと一緒にレコーディングに加わった、元Georgia SatellitesのドラマーであるMauro Magellan等もサインを並べている。
熱心なSatellitesファンなら(どれだけ存在しているかは知らないが)これだけでも意義がありそうなアルバムだ。
当然、Danのサインだけがこのアルバムの価値ではない。寧ろ、充実の内容を見るなら、サインはかなり副次的な順位までその価値が下降するとまで言い切ってしまおう。
◆単なる未発表曲アルバムを超えた出来
一応、未発表曲集という形を採っているアルバムだが、内実は単なる未発表曲のコラージュではない。
収録曲は全て、1990年から1993年の間のセッションで日の目を見なかったトラックだ。
その11曲のうち、2曲はDanをフロントマンにしたGeorgia Satellites最後のアルバム「In The Land Of Sulvation And Sin」の第2期サテライツメンバーと録音した音源である。
そして残りが2枚のソロアルバムの選に漏れたトラックとなっている。
第2期という表現に付いて、違和感を覚える方も見えると思う。
実際として、Georgia Satellitesがメジャーで活躍したのは1986年の初フルレングス「Georgia Satellites」から1989年の3作目「In The Land Of Sulvation And Sin」である。
通常、80年代ロックファンにとっての“ジョージア・サテライツ”はこのメンバーで構成されたユニットを指すだろう。厳密には1985年の英国のみで発売されたデビューミニアルバムである「Keep The Faith」があり、Rick RichardsとDan Baird以外のメンバーが異なっているため、こちらを第1期と考えれば、ヒットバンドとして短い期間活躍したSatellitesが第2期という解釈も可能だ。
◆古くて新しいSatellitesが登場
以上のように、筆者も「Keep The Faith」も含め、1980年代のGerogia SatellitesをDan’s Satellites(第1期)、1996年にRick RichardsとRick Priceが興したバンドをRick’s Satellites(第2期)として、“これまで”は考えていた。
よって、このアイディアを選択するなら、「In The Land Of Sulvation And Sin」のメンバーは第1期となる筈だ。
が、2003年になってこの第1期を改めなくてはならない事態が勃発した。
元来、Georgia Satellitesの母体を結成したのは、Rick RichardsとYayhoosのベーシストでもあるKeith ChristopherにドラマーのDavid
Michaelsonだった。これにDanがヴォーカル兼ギタリストとして加わって、1982年にKeith & The Satellitesとして活動を始めたのがそもそものスタートだ。
Keithが脱退し、ドラマーとベーシストのマイナーチェンジを繰り返した結果、Georgia Satellitesとして1984年に英国発売されたミニアルバム「Keep The Faith」が“ジョージア”・サテライツとしてのレコードデビューとなった次第は少し熱心なファンなら既知だろう。
が、このKeith & The Satellitesが2003年にOriginal Satellitesとしてリユニオンのコンサート2回だけアトランタにて行っているのだ。
オマケに、1981年と1982年にKeith & The Satellitesとして録音していた11曲のオリジナルなSatellitesの音源も世界で初めてデジタル音源化されて発売が始まった。
タイトルは「UH-OH , It's Keith & The Satellites」。
このアルバムは手元に届き次第レヴューする予定なので、そちらにて触れようと思う。よって今回の脱線はここまでにしておこう。
◆アルバムの大半がTerry Andersonとの共同曲
とかなり話が逸れてしまったが、要するにKeith & The Satellites名義のアルバムが発売された現在、第1期サテライツをKeith’s Satellites。次にDan’s、そして現在もライヴをまばらに行っているRick’s Satellitesまで3期に分けるべきだと考えるに至った次第だ。
その第2期メンバー、卑近な表現を用いれば黄金時代の面子で録音された音源が、#1と#7。
これらはSatellites解散−というかDan Bairdが自らをGeorgia Satellitesから解雇する直前の活動成果と見る方が適切だろう。
その他は全て、Danのソロ作「Love Songs For The Hearing Impaired」と「Buffalo Nickel」のセッションからのスピンアウトである。
その9曲のうち、1曲がカヴァー。1曲がDan Bairdの単独作。残りの7曲がYayhoosやThe Woodsでのバンドメイトで長年の友人であるTerry Andersonとの共同作となっている。
筆者は、Yayhoosのレヴューでも触れているが、ソングライターの力量としては寧ろBairdよりもAndersonを高く評価しているので、この黄金コンビによる全くの新曲が聴けるのはとても喜ばしいのだ。
以下、その内容を述べる前に、ブックレットに記載されたDanの各曲に対するコメントを訳してみよう。
筆者がグダグダと拙文を書くよりも、明らかに曲の背景が分かる・・・と思う。
◆Danのコメント
以下、●が各曲に寄せたDanのライナー・ノーツ。■が筆者のインプレッションとしている。
マスタリングを終えて、収録する曲を5回目に繰り返している最中に、それぞれについて何か書かなきゃ駄目だな、って思い立った。
●#1『Rock The Place』
このナンバーは1990年頃に「Salvation And Sin」をGeorgia Satellitesで録音した後、John Stamos主演の映画「Born To Ride」用に録音した。
俺は映画のプロデューサーにこう言ったさ。「決してベストな歌じゃないけどさ、でも映画よりは良い線行ってるよね。」
ってね。
でも、誰も俺にサウンドトラックの仕事を持ち込んでこなかった。とても不思議だったよ。何で声が掛からないんだよ、という具合に首を捻った。
だけど、この曲を再び日の当たる場所に出した時、俺はなんつーボケナス野郎だったんだ、って思い返して赤面モノになった。俺は元々紐付きやあらかじめ枠のある仕事には向いてないんだけど、この歌は俺の出来る範囲ではベストだったと思うよ。
俺とRickがそれぞれソロパートを交互に弾いている。俺はソロにカウベルを加えようってなアホなアイディアを出したけど、Rickは凄い演奏をやってくれ、馬鹿の考え休むに似たり・・・って証明してくれちゃったね。
このソロはBrendan O'Brienが俺の音楽人生に再度関わる切っ掛けにもなっている。Brendanはミキシングの作業をこのトラックで担当したからね。
■#1
「Can You Gimme Your Name Ya!」
のエフェクトを掛けたヴォイスからいきなりトップギアに叩き込まれる、これぞSatellitesというロックンロール。
{In The Land Of 〜」に収録されていても全く違和感の無いトラックでもある。
Rick Richardsのスライドギターがバリバリとオープニングリフから快走するのを聴くに付け、往年のGeorgia Satellitesの雄姿を思い出さずにはいられない。
ガラガラと転がるピアノが演奏に加わっているが、これが「〜Salvation And Sin」からの延長にあるとすれば、ピアノは同アルバムに参加していたIan McLagan爺さんと考えるのが妥当だが、ブックレットの「謝意」に目を通すと彼の名前はないので、恐らくミキシングを担当したBrendan O’Brienがピアノをぶっ叩いているのだろう。
Satellitesのレアトラックと見なすのが一番適切だと思うが、それにしてもかなりの弾けたロックチューンだ。Satellitesのどれかのアルバムに収録されていればきっと人気の出たワイルド・チューンに違いない。
当然、筆者も即気に入った。
アルバムに収録するにはややラフでハードドライヴィング過ぎるかもしれないが、Danらしいポップで力任せな、これぞロックンロールという曲だ。
●#2『Picture On The Wall』
一番最初に俺とTerryが書いた曲で、同じくケンタッキーの我が家で最初に録音された曲でもあるんだ。
この曲の他にも#4『Any Little Thing』、#6『Little Stories』、#8『Lock And Key』それから#10『Shake It Wild』、といった具合に俺が設立に関わったDef American RecordsのためにTerryと一緒に書いた歌は沢山あったよ。
その内の何曲かは「Dixie B」収録の『The One I Am And Knocked Up』のようにレコードに吹き込まれている。
そして、俺は今ならその時の1・2曲をアウトテイク集に入れれると思い立った。
かなり昔の曲と聴けば分かると思うし、でも同じ頃に録音した曲でも全部違った歌だとも分かるだろう。そしてこれらの曲にある違いを聴いてもらえれば、何らかの新鮮なモノが楽しめるんじゃないかとも考えているね。
付け加えると、プロデュースをしてくれたBrendanを、才能あるヤツと何度も何度も繰り返すのは止めておくよ。いい加減飽きてきたんでね。(笑)
事実を教えようか。
俺達は『Picture On The Wall』をアルバムに加えようとしていたんだ、スタジオで作業していた時は。でも、その後何故かそう思うことが無くなってしまったんだ。だから、この歌はこれまで日の目を見なかったんだ。
俺とTerryは4トラックのカセットテープでこの曲をレコーディングして、(ここから録音機材の固有名詞等や略語が続くため、一部略:訳者註)ドラムを被せた。俺が全部の楽器−ドラム、ベース、2本のギターをマッピングして、Datに再びミキシングした。それから2トラックのレコーダーに移し変えてヴォーカルを加えた。
これが今君が聴いている音源になっているんだ。
ヒジョ〜〜〜〜〜に申し訳ないけど、ヴォーカルの音程がずれているよね。でもレコードに収録していないマテリアルでは俺はこの曲が最もお気に入りなんだな。
この曲を録音していた時はとっても楽しかったね。間違った事はしなかったけど、少しハメを外し過ぎたかもしれないなあ。苦手な部分でもあったかな、こういう作業は。
やりたい事をやった結果に出来上がった曲だよ。このセッションが後のYayhoosの雛形になったようにも思うね。これらの曲を録り終えた数ヵ月後にEric Ambelが彼のレコードでの作業を幾つか行うためやって来た。数ヵ月後に彼のアルバム「Frozen Head State Park」が完成した。
これらの数曲を聴いて貰った君達が、録音当時の俺達が感じていたクリエイティヴな雰囲気を共有して貰えれば嬉しいねえ、それから俺がこのデモを好きな理由は、俺のセンチメンタリズムの脊髄反射で出来た曲ではない、って事だね。
Terryがドラムを叩き、ハーモニー・ヴォーカルを唄っているけど、残りは全部俺が演奏したと記憶しているよ。(例外は書いているけどね。)
俺達がどれだけ馬鹿やって悪乗りしたか、ちょっと表現しきれないし、デキタ!!って手応えを感じる歌を生み出す時に覚えるポジティヴな喜びも言葉では表しにくいね。でも本当にレコーディングに関わった連中の誰一人として、こういった行動を取ることに疑問のある奴はいなかったね。
勿論、俺達が作った曲の中には、Def American用に書き下ろした以外のマテリアルもあるさ。でもね、大まかだけど、それらの曲は完全に屁コキ虫なレヴェルなんだ。自由にやり過ぎで手綱を締めないと、結局はトバッチリを食うんだよ。あ〜イタタ。
まあTerryのスネアドラムでも聴いてくれよ、そんなのは気にしなくて良いからね。
俺は詰まんない音源も含めて、この当時に創って録音したナンバーは今でも好きだよ。
■#2
Terry AndersonのルーツセンスとポップセンスがDanの才能と融合した好例だと思う。スピード感とストレートなロックンロールの大鉈の合力では#1に劣るけれど、ルーツィでキャッチー。まさにDan BairdやTerry Andersonの独壇場な正統派アメリカーナ・ロックだ。
RockとPop、Rootsの兼ね合いがきっちりと均衡しており、このナンバーがアルバムの選に漏れたのは確かに不思議で堪らない。
筆者としてはアルバムで1・2を争うお気に入りのトラック。TerryのスネアドラムはDanのコメントではないが、非常に気持ち良い叩かれ方をしていると思う。
この曲の解説が一番長いが、他の#4以下の同時期に録音された音源の解説も兼ねているからだろう。
●#3『Memphis』
皆がこの曲を気に入っていたんだけど、適当なコーラスが付けられなかった。という理由でオクラ入りになってしまったんだ。今、日の当たる場所に引っ張り出してみると、この曲は俺の駄目ダメアルバム「Buffalo Nickel」に入れるべきだったと思うね。
カセットテープ以外でこの音源のマスターを見つけられなかったので、幾つかの雑音やオフレコなヴォイスがカット出来なかった。これらの要らない音は俺とTerry,そしてMauro、Brendan、Keithが発生源なんだ。
俺は子猫ちゃんのように可愛らしい女性バックヴォーカルとドロドロなBrendanのギターを愛して止まないね。
『Memphis』、#5『Shine A Light』そして#11『Don't Open The Door』の3曲は全部「Buffalo Nickel」からのアウトテイクだよ。他にも幾つかアウトテイクナンバーがあったんだけど、俺は#3以外の2曲のみ残した。後はヘタレなシロモノばっかりだったんだ。
理由は自分でもはっきりとしないんだけど、このナンバーの感じがこの新アルバムにバッチリだったんだ。
Brendanはこの3曲でビシッと光を放つギターを弾いている。Terryには#11と『Memphis』でBrendanと一緒にバックヴォーカルをやって貰った。
キーボード全般、姦しいタンバリン、それ以外のパーカッシヴな音を出す器具は全部Brendanがプレイしている。
俺の2枚のソロの大きな違いってのは、俺がナッシュヴィルに戻った事と、2枚のアルバムの空白の期間にBrendanが有名になった事だね。俺は「Buffalo Nickel」のレコーディング中にずっとBrendanが大物になった事をネタにしてアイツをからかってやったもんさ。だけど、Brendanも俺をオモチャにしていたからね、どっちもどっちだ。
■#3
1stソロアルバムに比べると、南部のルーツ色が増したのは良いが、全体的に重く、ポップさが後退してしまい筆者的にはいまいちな「Buffalo Nickel」だが、この#3は如何にもその南部カラーの濃いアルバム向きなレイドバックした泥臭いスライドギターナンバー。
が、Danのヨーデル気味のヴォーカルや投げ遣り風味のヴォーカル、そして今回リミックスされたバックヴォーカルと、実にダウン・トゥ・アースなスローロックとして良い出来となっている。かなり後半のブリッジ部分ではハードな泥ドロロックになっていくのがDanらしい。こういうナンバーばかり続くと退屈するが、1曲としては非常にハイ・レヴェルだと思う。この曲は「Bufallo Nickel」に加えたほうが良かったと思う。
●#4『Any Little Thing』
おお、神様、クリスマスプレゼントにボクを素晴らしいスライドギター弾きにしてください、お願いします。
そう願ったら、俺はTerryと俺の比較ではベターなスライドギタリストになることが出来たよ。でもそんなに大きな差は無いんだけどね。
くだらない感傷だけれども、この曲がDan Baird/Terry Anderson作の中では一番好きなんだ。俺達のNRBQやBad Fingerに対するアンチテーゼと斬り込みがこのナンバーなんだ。俺はこう思うよ、グルーヴィな何かを創作する時はもっと謙虚にオマージュとして創った方が良かったなあ、と。
■#4
実にポップでスライドな巧で好チューンだ。
アクースティックなギター弦の旨みを活かしつつ、うねるスライドギターのレイドバックな音色でサザンロックの本質を浮き立たせている。こういった中テンポのスライドナンバーをここまでRock/Popとして完成させているのに、日陰に眠っていたのは本当に勿体無い。
確かにスライドギター弾きとしてのDanは激烈な名手とは云えないかもしれない。Rick RichardsやMarc Fordの方が実際良い仕事をするだろう。が、このメロディメイキングと不器用な歌唱はDan以外に真似の出来なオリジナリティに満ちている。
●#5『Shine A Light』
すんごいロック。あからさまだけど、FreeやBad Companyへのオマージュだね。Buffalo Nickel用のデモカセットから#3と同様にピックアップした。何でこの曲がレコードに入らなかったのか全然覚えてないなあ。
■#5
大袈裟な言い方に聞こえるかもしれないが、この曲が入っていれば「Buffalo Nickel」(以下、BN)はもっと良いアルバムになっていた筈だ。というか断言する。
これまたスライディッシュなタップリ特濃南部ロックンロールの代名詞。BNの代表曲で看板ソングでもある『Younger Face』よりも遥かにロックでルーツでダイナミック。しかもしっかりとハードな流れをポップで締めている。この点がBNでは食い足りなかったのだが、こういったストレイト・フォワードなロックチューンがあってこそのDan Bairdだと改めて感じ入ってしまったサザン・チューン。
これまた大のお気に入り。
●#6『Little Stories』
Everly Brothersになりたい・・・愛を込めて。
トレモロとマラカスを聴いてくれ。Terryがセカンド・ヴァースを歌っている。
■#6
いきなりオールディズ風のR&Bポップ。Terryとのハーモニー・ヴォーカル。ノスタルジックでアクースティックなアレンジは派手さは無いが、ジワジワと浸透してくるパワーがある。
マラカスやシェイカーを本当にコメント通り使用しているが、スライドギターに結構合うので驚きだ。
箸休め的な曲として和む。
●#7『Trouble Comin’』
イカれたカウベルとビンビンにおっ立つロックが代名詞だったGeorgia Satellites時代のナンバー。#1と同じ映画のサウンドトラックより。
優雅とは程遠い歌詞。
クソッタレなスライドギターとバックヴォーカルまでロックンロールしてる。
何てこったい、どうしてRickは何時も歌う時はこうもクールに決めれるのかね?俺が歌うより全然いいじゃないか。多分彼がヴォーカリストに向いているんだろうけど。
■#7
初期のハードロックバンドとしての顔を見せていたSatellitesに立ち返ったようなハードでダークなロックトラック。ヴォーカルがRick Richardsという段階でアウトテイクらしいかな。
ルーツナンバーというよりも完全なハードロック。後のIzzy Stradlinのアルバムで活躍する前夜のRick Richardsを見れた気がする。
しかし、Rickの歌をDanが取り上げたのは意外だ。勿論ハーモニー・ヴォーカルとしてDanも相当な部分をダブル・ヴォーカルとして参加はしているが。
Satellitesファンには嬉しい1曲だと思う。
●#8『Love And Key』
Terry AndersonとDan Bairdのタッグ再び。Rolling Stonesを聴いたことは一度も無いんだぜ、本当だよ、誓っても良いね。
■#8
DanはStonesのパクリと取られるかもしれない危惧からか予防線を張っているが、別にこのナンバーがストーンズ・ロックだとは思わない。Stones程に黒人的な部分はないし、何よりも米国南部をバックボーンとした大らかさのあるロックチューンだからだ。
が、英国ハードパブロックやFaces、Stonesがその昔プレイしていたダイナミックでスゥインギングな懐の広いロックナンバーに連なるロックトラックなのは確かだ。
こういったキャッチーでアーシーな曲をやらせるとDanの本領が完全に発揮させる好例だ。やはりDanはロックンローラーである以前にルーツロッカーであることを事実によって証明している。これまた大好きな曲だが、このダイナミズムにグランドピアノが欠けているのが惜しい。
●#9『Seventh Son』
Wille Dixon氏作。アルバム「Love Songs〜」から。
俺達はStan Lynch(筆者註:The Heartbreakersのドラマー。説明の必要も無いか。)に曲創りに手を貸してくれないかと頼んだんだ。けれどStanはB面用のカヴァーソングを持ち込んできたよ。最初、StanはJohnny Riversの『Bad Side Of Town』をピックした。俺達は多数決を取って、Johnnyの曲をカヴァーすることに決めた。だけれど、その後Stanがこのナンバーをスペアとして録音しておこうと言い出したんだ。
俺はこのトラックのドラムはStanが叩いていると記憶している、間違いないね。・・・がひょっとしたら記憶違いかも。(汗)
俺はその頃、Johnny Riversが大のお気に入りだった。Johnnyは等身大な人間として凄い格好良いからね。それにJohnnyはあのJames Burtonをバンドのメンバーにもしていたからね、凄いよ。
俺はこの曲がB面としてもリリースされて無いと思っているけど、既に何処かでこの曲が入った音源を買ってしまっている人がいたらゴメンネ。
この曲は楽しさに満ちているだろう。楽しんで欲しいよ。
■#9
シカゴブルースの大御所、Willie Dixonの「I'm A Blues」(1970年)からのカヴァー。リズムボックスが導入される前のポコポコブラコン以前の純粋なブラックロックを実にゴキゲンにカヴァーして、サザンロック仕立てに手直ししている。
こういったデライトフルで純粋なナンバーなら黒人系のロックも良いのだが。無論転がるピアノをバックに、クラシカルなナンバーを歌いまくるDanのカヴァーはハマリ役。
このクオリティならB面にする必要も無いくらいだ。
●#10『Shake It Wild』
俺はTerryを非難しているよ、狡い事をしたってね。
“俺は逃げるため、車をドライヴしている”。・・そうさ、俺もCCRの『Run
Through The Jungle』からアイディアを頂戴している。子狡いねえ。でもそれが実にピッタリと俺のアイディアに合ったんだ。
Terryのアイディアはベースラインに活かされているよ。
■#10
かなりナスティでダートなサザンブルースナンバー。ちょっとメジャーのレコードには入れ難い曲だろう。そのためにアウトテイク化した可能性が高い。
正直ここまでブルースする必要はDanにはない気がする。彼らしい南部ルーツナンバーだが、筆者が唯一いまいち気に入らない曲。
●#11『Don't Open That Door』
BNのカセットからの曲。俺はSteve Cropperばりの素のままで踊れるギターラインを書きたかったので、この曲を創ったんだ。某ベーシストの夢想が、しんどい作業をアホらしい事件にしてしまったんだけどね。
俺とBrendanは“Ya-he-he-ya-he-he”てな具合にギターを弾いて、Robert Deleoを馬鹿にして遊んでいた。それからBrendanとNick Didiaがこのフレーズのループを作った。Nickはレコーディングスタジオの持ち主で、俺達がメチャメチャなテイクを録音した後、それをミックスダウンしてヘッドホンで聴かせてくれた。
言うまでも無く、最初のテイクは酷いもので、1時間と聴き続けられなかった。皆プラグを抜いてしまったよ。
Nickは更にとある著名バンドのライヴ・テイクをミックスしてループ化している。(5ドル送ってくれればそのバンドの名前を教えてやるぞ)。彼はそのループを使って良い曲をミックスしたそうな。
■#11
単調でノイジーなギターがリフレインするハードなブルースロック風ナンバー。これまたアウトテイク本来の姿に近いラフなナンバーだ。
このヘヴィでシンプルなロックンロールの在り方は確かにDan Bairdの一面だと思う。
ロッキン・ブルースとして面白い曲に発展したかもしれない、より練り込めば。
◆活発に活動する2003年のDan Baird
詳細は、もうすぐ手元に届くだろう、Keith & The Satellitesの音源で触れるつもりだが、2003年のDanはプロデューサーとして筆者が知るだけで3作を担当し、かなり精力的に活動している。
更に、Keith Chriotopherを迎えて、Original Satellitesとしてのリユニオンステージも前述のように行っている。
そして、お流れになったが、Georgia Satellitesの復活ツアーも非公式ながら企画されるまでになった。
その代わり、現在はDan & The Friendsとして欧州や全米をソロツアー中だ。
平行して、Rick PriceとRick Richardsが率いるSatellitesもライヴの回数を増やしている。俄かに最近Danの周辺が賑やかになっている。
これだけの高いレヴェルにあるアウトトラックを出せるなら、本当の新譜もソロかまたはYayhoosを問わずに欲しい所なのだが、それよりも何とかして流れてしまったGeorgia Satellitesの再結成に踏み込んでもらえないだろうか。
これを未だに切望しつつ、まだ届かない音源を待っている。 (2003.8.30.)
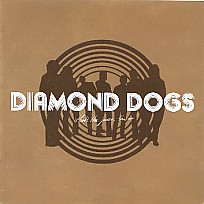 That's The Juice I'm On / Diamond Dogs (2003)
That's The Juice I'm On / Diamond Dogs (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★☆
Boogie ★★★★ You Can Listen From Here
◆相変わらずの回転の速さ
Diamond DogsがデビューEPの「Among The Non Believer」を発売したのが、2000年。
で、現在2003年までにミニアルバム(EP)と本作「That’s The Juice I’m On」までを加えると、足掛け4年以内に5枚のアルバムをリリースしている勘定になる。
全体的な傾向として、寡作化・少数作化が加速化している1990年以降のメジャーのロックアルバム発売に対する完全なアンチテーゼとして評価したくなるようなペースを保っている。
あたかも、1970年代前半−年に2枚のリリースが珍しくもなく行われていた時代を取り戻そうかという行動意欲だ。
2002年に「Too Much Is Always Better Than Not Enough」というフルレングスアルバムを出したばかりだが、ひょっとしたらすぐに次が来るかもしれないという予想は漠然としていた。
が、本当に1年毎で新作が届くと、やはり嬉しいものがある。
しかも、これだけ過剰ともいえる作品を世に出しているのに駄作や失敗作が皆無という所がこのバンドの凄さだ。
◆安定? それともマンネリ?
しかし、直線的なロックンロール一筋な作風を貫いているため、パンクロックやハードコアといったDiamond Dogsと同地域で活発な他ジャンルの北欧サウンドが陥り易い、パターン化したサウンドに、完全に非該当というと厳密にはそうでもない。
実際に、1stアルバムから通して聴くと、Diamond Dogsのサウンドの構築と構成、プロデュースの成長が理解できるのだが、さらっと聞き流すだけではワン・パターンの不器用なロックバンドとしてしか評価されないかもしれない。
が、開き直った言い方だが、変な色気を出して折角築き上げた良さをぶち壊しにしてしまうミュージシャンが多い中、このように頑固な位に自らのシンプルで荒削りなロックンロールのスタイルを変えない姿勢は、チャレンジという免罪符を拡大解釈して全く失望の対象でしかない駄作を出し続ける某バンドやミュージシャンよりも余程賞賛に値すると思う。
◆厳密には完全新作ではない
と、凄いペースと誉めておいて何なのだが、通算5枚目(これ以前にも7インチやシングルを幾枚か本国瑞典で発売をしている。バンドのディスコグラフィー等については、前作を拙文でレヴューした際に可能な限り詳細に記述したので、興味のある方は参考にして貰えば幸いだ。)のフルアルバムは新曲を揃えた完全なオリジナル盤ではないのだ。
とはいえ、只のベスト盤とかレアトラック集とも一味違う。
まずは、ブックレットに記載されたリード・ヴォーカリストにしてメインのソングライターであるSuloのコメントを紹介する事にしよう。ここにこの5枚目のアルバムのコンセプトが全て説明されている。
◆Suloの解説
親愛なる、リスナー諸君
それは1996年の冬だった・・・僕らは新しいDiamond Dogsのアルバムになるだろう録音を行っていた。けれども諸々の事情で、結局シングルのリリースで終わってしまったんだ。(このコンピレーションアルバムでそのシングルのB面を聴けるよ。)<筆者註:#10『Hurt You Twice As Much』の事。>
これがDiamonod Dogs第1期の始まりだったんだ。
バンドは一旦分解して、後からそれが正しい選択だと実際に分かったよ。だって、そうでなかったら新しくバンドを再編して、新しい確実なプロジェクトとしてDiamond Dogsを始める機会は訪れなかったからね。再生という事が重要という訳さ。
兎にも角にも、数年が過ぎ、他のバンドの仲間を違うバンドの殻をぶち壊して見つける事が出来たんだからね。(僕はちょっとヤバイので元のバンドの名前は言わないでおく。)
その間、良かろうと悪かろうと、僕はずっと曲を書き続けていた。結局それが僕の習慣であり、無しでは生きていけないのさ。で、僕の場合はまさに「Too Much Is Always Better Than Not Enough」が座右の銘になるんだ。それは分かってくれるよね?<筆者註:4枚目にして2枚目のフルレングスアルバムのタイトルが「Too Much 〜」>
僕たちの内々のお約束なんだけど、アルバムを出す間に、必ずEPをリリースするようにしてるんだ。で、このコンピレーションではこれまでに出した2枚のEPの大半の曲を収録した。そのうち2曲はAlernative Mixの別ヴァージョンで、6曲はこれまでに発表しなかったトラックだよ。
別の見方をすれば、古いマテリアルに幾つか楽しんで貰えるように新しい音源を加えたレコード、と言えるかな。
1999年にFeedback Boogie RecordsのルーサーがDiamond Dogsの古いカセットテープを掘り起こして、その曲にシビレてしまった。彼は僕に即日電話を掛けて来て、新しいEPを創る気力と素材があるか意気込んで尋ねてきたんだ。
彼は何回も打診をしてきて、数回のやり取りの後、僕は折れた。
レコード会社はスタジオや機材の手配をしてくれたけど、僕たちはまだドラマーを決め兼ねていた。でもデットラインは刻々と近づくし、頭を抱えていたんだ。
と、Boba<筆者註:HellacoptersのBoba Fett。Diamond Dogsには別名で参加。>がDDにバッチリはまり役のドラマーを紹介してくれた。それがJaspersで、リハーサルはまるで夢が現実になったくらい完璧だった。
Jaspersを加えた時が、本当の新生Diamond Dogsの始まりになったんだ。
◆ということで、新曲+未発表曲+2枚のEPからの再収録を集めたアルバム
Suloのコメントはまだ続くが、後半部分は本作のレコーディングに言及しているため、曲の解説で随時紹介することにする。
このSuloの寄稿にあるように、Diamond Dogsのメンバーの表現では“伝統”としていた、「アルバムの間にはEPを挟む」というパターンを崩すように14曲入りというサイズで今作「That’s The Juice I’m On」は発売されている。
しかし、未発表音源が6曲、残り8曲のうち4曲ずつが、均等に2枚のEPから再度収録となっている、マテリアルだけを見ればミニアルバムのヴォリュームとも解釈可能だ。
また、その内2曲−2002年の「Shortplayer」で録音済みだった#2『Just Ain't Right』と#7『Throw It All Away』は別ヴァージョンとなっている。
この2曲は、筆者の解釈では新録音として撮りなおしたナンバーだが、それは後述。
現在、2枚のEPはリテイラーの在庫にある以外は廃盤になってしまっているので、Diamond Dogsに最近目覚めたファンには福音となるかもしれない。
全部の音源を網羅(初期のEP以外)している筆者には素直に新曲としてEPでもミニアルバムでもどちらでもいいが、少数曲でリリースして貰えても問題なかったのだが。
◆6曲の未発表曲のうち5曲は新曲と呼べる
#1『From Now On』(2003年)
#4『I'll Drink To Ya』(2003年)
#6『Get The Money Off』(2001年)
#8『Travelin’ Rose』(2003年)
#10『Hurt You Twice As Much』(1996年)
#13『You Captured My Smile』
以上が、“Previously Unreleased”となっている曲だ。
1曲のみかなり古い時代のナンバーで、前述の#10。最初のDiamond Dogs(以下DD)のセッションで生まれたシングルのB面曲だったそうだ。
かなり荒削りで北欧パンクロックの影響が濃いナンバーだが、ちゃんとピアノを取り入れ、単なる縦押しパンクに終わらないルーツロックの香り漂うチューンにしている所は流石。
が、やはり他の近年のナンバーと比べると完成度、そしてバンドの風格が滲み出ている『ゆとり』が欠如しているのが明白だ。
#1はかなりクラシカルなパーティロックンロールで、前作から積極的に活用を始めたホーンセクションをタップリとかましたナンバー。
このブギーでスゥインギングなロックチューンは、何とBTOやGuess WhoのRandy Buchmanがヘルシンキにレコーディングに訪れた際、Suloを始めとするDDのメンバーと交流し、セッションを行っている間に生まれたナンバーという。
1970年代の懐かしい懐の深いロックナンバーが蘇ったような風のトラックで、我武者羅にロックしていた初期と比較してかなりの余裕を感じる。
同様に#4も崩れたスライドギターを筆頭に、ややサイケディリックに、そしてルーズに酔っ払う太いロックナンバー。
これまたホーンセクションを加え、タテノリロックや北欧ハードコアとは全く次元の違う本格的なロックトラックとして完成させている。エレキピアノが実に良いアクセントになっている。
エレキピアノサンプリングは#6でもスタートからメインリフを奏で、このバンドが如何に鍵盤の音を大切にしているか良く理解できるナンバーでもある。
この#6もパンクの滅茶苦茶なノリを上手くルーツの土台に乗せており、単なるヤケクソロックで流さない質感が存在する。ややファンクを意識している点ではRolling Stonesの初期から中期のハード・パブサウンドに通じる所もあるか。
ライヴ感覚丸出しのロアなギターが吼える、#8もハードドライヴなナンバーだが、スピードだけに頼って引っ張らない奥行きを感じるハードポップなナンバーだ。
DDの大きな特徴はハードなサウンドに負けないキャッチーさがあることだが、初期のフルレングスではハードに特化した曲がちらほら見られたのに対して、明らかにポップミュージックのツボを心得つつあるのが、こういったハードでワイルドでも聴き易いロックチューンで証明されている。
そして一番新しい8人目のメンバーであるギタリストのDarrel BathがピアニストのHenlik及びSuloと拵えたブルージーなバラードが#13となる。
アクースティックピアノとタンバリン等のパーカッションというギタリストが4人も在籍するDDには珍しいくらいギターが控え目のナンバーだが、切なく美しいメロディが印象的だ。産業HRバンドのバラードをより削り落としてシンプルにしたらこのようなポップでブルースを感じさせるバラードになるだろう。
◆1st作「Among The Non Believers」から4曲
#3『Weekend Monster』
#9『Lunatic Eye-Rolling Delivery』
#11『Position Right Here』
#14『Slim Busty Blonde』
全5曲入りのEPから1曲目の『Bite Off』を除いたナンバーが再度収められている。シングル化された1曲目を敢えて外したのは、やはりシングルとダブるリスナーへの配慮だろうか。
このうち2分足らずのハードロックなインストゥルメンタルナンバーの#14だが、オリジナル収録時は『Slim Busty Blonde (Part
2)』とタイトルが付いていたが、今回のヴァージョンは全くそれと同じだ。ひょっとしたらPart
1が聴けるかもしれないと期待していたので残念だ。
残り3曲のうち、やはり代表格は#3だろう。突っ走るピアノとオーヴァー16ビートの激烈ジャンピーなロックンロールであり、筆者がこれでDDに転んでしまった記憶にとどまっているナンバーでもある。
ハードさと生のままの60〜70年代英国系ロックンロールの匂い、そしてコマーシャルで即効性の高いメロディと全ての要素を満たしている傑作だ。1stを買えなかったリスナーはこの曲を入手するためにも、本アルバムを買う価値があると思う。
#9は直前にも言及したように、やや北欧メタルやパンクロックの色合いが濃く出たナンバーで、暴力的なまでにハードでダークなロックナンバー。こういったタイプのハードコアもDDには悪くないけれども、この手の音を出すパンク野郎はスカンジナヴィア半島に掃いて捨てる位存在するので、こちらに特化しなかった“現在のDiamond Dogs”と比較してほっとしてもいる。
#11はロックバンドとしてバランスが取れた側面が出ているDDのナンバーだ。荒っぽくワイルドな性格が目立っているバンドだが、アレンジの深さとサウンドの重厚さがポップセンスと巧みに融合している事を忘れさせない曲である。
時折見せるルーツミュージックへの敬意が生の演奏を押し立てたギターの弦に現れている。
◆3rd作「Shortplayer」から2曲のリミックス
#2『Just Ain't Right
#5『Passion Through My Heart』
#7『Throw It All Away』
#12『Pills』
インナーに「Shortplayer」は“新しいシングルではなくてアルバムとアルバムの間に楽しんでもらう繋ぎ=ショート・プレイヤーなんだ”と書かれていた3枚目の作品且つ2枚目のEPからも4曲がチョイスされている。
外されたのはStonesの『Connection』でもう1曲のカヴァーである#12は無事にトラック・インの運びになっている。
このうち#2『Just Ain't Right』と#7『Throw It All Away』はSuloのコメントに書いたが、“Alternative Mix”と名前が付けられている。
実際オリジナルとの差はメロディ的には皆無だ。曲の演奏時間も全く同じ。
変わった点はオリジナルでテナーサックスがフューチャーされていた#2のソロパートでサックスがオミットされた事。大きな楽器の違いはその程度だ。
では何が違うか、何がオルタナティヴか、と耳に集中してみると・・・・
録音が綺麗になって、各楽器がクリアに聴こえる、これくらいだ。細かいシャウトや歌いまわしが少し違っているが大した問題ではない。
オリジナルマテリアルでは、アナログ時代のくぐもった録音を再現する狙いがあった為か、アナログ音源を擬したようなクオリティを故意に低くした音で録音されていたこの2曲が、現代のデジタル録音を忠実にトラッキングしたと考えて差し支えない良質な音で再度ミックスダウンされている。ギターも数本が錯綜してごちゃごちゃしていたファーストテイクよりもスリムでソリッドに纏められている。
要するにデジタルで再録音した感じだ。
当然ブギーでルーツィなダイナミズムのある#2も、パーティサウンドの権化のようなロックチューンの#7も非常に良い出来で、Diamond Dogsの持ち味と特性が初期の頃から出ていた好ましいナンバーの例にもなるだろう。
そして緩急が付けれるバンドなんだぞ、と主張するようにアクースティックさを活かしたナンバーの#5も、単なる北欧爆走バンドではないDDの何面もある顔を見れる佳作ナンバーだ。Henlikのオルガンが実に膨らみを曲に付随させている。
#12については最早説明の必要もないだろう。New York Dollsのヴァージョンが最も有名で、パンクバンドやルーツロックでロック寄りなバンドがしばしばカヴァーするパンクロックの名曲だ。
◆儲けモノなお買い得作
EPが手に入らないとお嘆きのリスナーは即買うべきだ。収録された未発表=新曲のレヴェルはかなり前作を超越していると思える。
ロックバンドという定型を崩さないため、マンネリ化として見られてしまいそうだが、速さだけ、ハードエッジだけを追い求めていた方向性が強かった初期の時代と比べると、かなり手数が増え、米国と英国ルーツをより広範に解釈し、咀嚼出来ている。
これをバンドの成長と呼ばずして何と呼ぶか。
新マテリアルの6曲でもアルバムを買う価値は十分に見出せる。特に2001年以降の新発表ナンバーのクオリティは驚くほど高い。
このアルバムもDiamond Dogsのパターンである、フルアルバムの間に於ける繋ぎ、的なニュアンスを筆者はSuloのコメントから読んでいる。手前勝手な解釈である可能性は高いけれど。
となると、2004年にはDDの新作が届く確立が非常に農耕になってきている。これだけハイペースを保ち、それだけの人気を欧州を中心に増やして獲得しているバンドなのだから等分は失速したり解散したりしないと思う。
次のアルバムにその速いリリースも含めて期待したい。 (2003.9.4.)
 My Private Nation / Train (2003)
My Private Nation / Train (2003)
Roots ☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Adult Alternative ★★ You Can Listen From Here
◆売れ過ぎた前作、「Drop Of Jupiter」
正直、全米トップ10に前作の「Drop Of Jupiter」が食い込むとは予想していなかった。
無論、アルバムがロック系のバンドとしては(除く完全なオルタナ/へヴィイロックのバンド)近来稀な大ヒットを記録したのは、アルバムの中でも他の曲より頭3つ程抜きん出ていたタイトル曲『Drop Of Jupiter』のシングルヒットに依存する所は大だ。
しかし、アルバム前半は曲がりなりにも良質なアメリカン・トラッドロックのアルバムとして、それなり以上に見れる出来映えとなっていた「Drop Of Jupiter」も、後半に入るなり−キャッチーなやや浮き気味のロックチューン『Respect』を境にして−エアポケットに落っこちたジャンボジェット機の如く降下線を描き、単なるジャム系のオルタナティヴアルバムに終息してしまっていた。
極論を述べれば、「どのミュージシャンも1曲は名曲を作れる」という名言ではないが、まさに当時は“それだ”と直感的に思った『Drop Of Jupiter』に引っ張られて全体的な評価が底上げされた凡作程度のアルバムでしかない。
実際に、Trainのフルレングス2枚目を今現在聴きたいかと自問した場合、『Drop Of Jupiter』他数曲を選曲して順番に聴けばそれでオッケー、位の評価と感慨しか抱けない。
以前、「Drop Of Jupiter」を拙文でレヴューしたが、当時「Trainという電車から降りる=聴くのを止める、つもりでいたが、このアルバムでもう少し列車に付き合ってあげるか、という気分になった。」
という趣旨の感想を書いている。
まさに、その程度だ。デフォルト購入をするかどうか迷っていたバンドのアルバムがたまたまそれなりの出来だったので、驚き、勢いで評価が浮ついただけ。
率直に言えば、レヴューを書くほどのアルバムではなかった。
然れども、次は買ってもいいかな、と購入意欲を一歩前進させる程度。
少なくともデビューアルバムよりは進歩していたのは間違いない。
・・・・一応褒めているかな・・・・・?
◆で、大ヒットの後の新アルバム
という事で、最新作の「My Private Nation」は前作ほど躊躇う事無く購入の運びと相成った。まあ、平均点程度のアルバムだった前作がこのくらいの効果をもたらしたので、それなりに大したものという事か。。
過度の期待はしていなかったし、そこまで期待を乗せるバンドでもないというのが事前の認識だった。
当然購入前に一通りサンプルを試聴してみたら、少なくとも順当な成長は感じ取る事が出来ていたので、2作目を買った時程には不安感は持っていなかったが。
で、実際に何度も聴いてみて、結構驚いている。
普通大ヒットをかっ飛ばすと、その次は駄目になる事が、殊にメジャーのロックバンドでは多い。Wallflowersの糞以下の産廃アルバム「Bleach」とかMatchbox Twentyの地球環境に無駄以外の何者でもない「Mad Season」とか挙げればキリが無い。
が、デビューアルバムでシングルではトップ40ヒットを記録し、ミリオンセラーを記録するという順風満帆な出だしを記しているTrainは、2作目で大きく外す事をせず成長をある程度見せ、更に実際のクオリティを遠く外れて成功となってしまった2枚目の後もレヴェルアップをしっかりと見せ付けてくれている。
要するに、出来としては何故売れたか未だに理解不能の1作目は言うに及ばず、前半だけならそれなり以上の(メジャーにしてはだ。)アルバムだった「Drop Of Jupiter」を遥かに超えた良作を発表しているのだ。
正直、甘く見過ぎていたかもしれない。
が、やはりメジャーで活動する以上、必要最低限はオルタナティヴや90年代型のモダンサウンドに擦り寄る必要が未だ必須なバンドであるという、バンドの底の浅さをも同時に露呈もしている。
つまり、まだまだオルタナティヴを完全に排斥して本当のアメリカン・ルーツ/アメリカン・トラッドなサウンドだけで構成されたアルバムを作成できるに至っていないバンドなのだ。
売れるためには仕方ない妥協だとは思うが、良かった頃のWallflowersやCollective Soulは自らの独自性で勝負していた事だし。
とはいえ、メジャーでこれだけオルタナティヴのエッセンスを薄めたアルバムを作成出来た事には素直な賞賛を送っておこう。
Trainと同様にアメリカントラッドなサウンドと現代性を同居させたサウンドを創作していた、Edwin McCainは大したヒットに長期間恵まれず、2003年にインディ落ちして、実に味わいのあるアクースティックアルバムを作成している現実を鑑みると、かなり明暗が分かれていると思う。
他のモダンとトラッドを組み合わせたAdult Alternative系のバンドからは頭ひとつ以上抜けたロックバンドに成長したといっても差し支えなかろう。
◆5人から4人へ、でもあんまり関係ないかも
このアルバムを録音途中に、Patrick Monahanと共にバンドの創成期からのコアメンバーだったRob Hotchkissがバンドから脱退した模様だ。公式HPでもメンバーのリストから外れている。
本作は2002年から録音作業を行っていたが、録音途中まではバンドに在籍していた様子で、4曲にはクレジットされている。
また、Trainというバンドは殆どのナンバーがメンバー全員の共同成果として提供されることがほぼ十割という、共同ソングライティングの傾向が近年のオルタナティヴ系バンドでは珍しいスタイルを行っているユニットだが、Robも収録11曲のうち、後半の#6から#11まではソングライターチームの一員としてクレジットに名前を並べている。
これらの事から、彼の脱退は結構唐突に思い立ったものかもしれないと推測できる。
オフィシャルのステイトでは、家族との生活を大切にしたい旨を表明している。まあ、売れ始めたバンドには付き物のメンバー脱退と革変の時期に丁度当たっているのだろう。
望外ともいえる成功を収めたバンドから幾人かが抜けるのは特に珍しくも無いだろう。
また、筆者としてはいまいちRob Hotchkissのバンドにおける役割が不明瞭だったため、あまり重要なファクターではないように思っている。
バンド結成時のコアメンバーという事だが、正直、ジャムバンドとローファイなオルタナティヴの特徴しかない初期のTrainは、ど〜〜〜〜〜〜でもイイバンドなので、寧ろ今後のTrainの方向性にはポジティヴに作用する可能性すらあるのでは、と些か失礼な予想までしていたりするのだ。
残念な点は、唯一Robが兼務でピアノを中心とした鍵盤弾きでもあったので、バンドからキーボーディストが抜ける事によるアレンジや楽器選択への影響が起こり得る程度か。
が、これまたメインの鍵盤類はドラムマシンも含めてドラマーのScott Underwoodが舵取りをしているようなので、杞憂の部類に属するとも考えているが。
元来、5人もメンバーを揃えて置きながら鍵盤担当がバンドに存在しないという事実がそもそも異常(ヲイ)なのだから、これを機会にキーボーディストを正規メンバーとしてグループに加えて貰いたいくらいだ。
ここまではゲストやプロデューサー系のミュージシャンに協力を仰いでピアノを筆頭とした鍵盤サウンドを補強していたが、特に「My Praivate Nation」のようなアルバムをこれからの基本にしていくなら鍵盤の音は必須だ。(後述する)
現段階ではRobの脱退によってマイナスに働いている要素は無いと見ている。レコーディング・ミュージシャンや楽器のチョイスは前作の形を踏襲している様子だから。
これはプロデューサーが前作に引き続き同一人物という面も大きく作用した結果だろうが。
◆1980年代のアリーナサウンドを思わせる音はそれなり。しかし中盤がダレ気味なのが・・・
今回のアルバムで最も既存のTrainと異なっているのは、ジャムバンド的なアクースティックへの一方的な依存が見られない事だ。完全には無くなっていないが。
これまでのフルレングス2枚は量の大小を問わずジャムバンド的な隙間が多く、マイナーでアンキャッチーな音。所謂Acoustic Alternative
/ Jam Bandと表現されるサウンドが特徴だった。
「Drop Of Jupiter」の前半ではアクースティックなアレンジにアーシーなアメリカンルーツの匙加減が加味されていたので、オルタナ的メロディにかなり改善が見られたものの、結局後半で失速していた。
ジャムの分量が減少するのと平行してサウンドが全体的に厚くなり、まるで1980年代のラジオフレンドリーな産業ロックやアリーナサウンド、そしてアルバムオリエンティッドなPop/Rockに近い要素を見ることが出来るようになった。
とはいえ、1990年代以降のサウンドの影響も混ざっているため、産業ロックにモダンやオルタナティヴを加えて割って加工したような微妙なカラーもまた存在する事も確かだ。
しかし、ファーストシングルとなりトップ40ヒットを記録した#1『Calling All Angels』からオルタナティヴのメロディに負けないコッテリしたロックアンサンブルが見られる。メロトロン・サンプリングやピアノを演奏に絡め、シンセサイザーのノイズやエコーを多用したややオーヴァー・ドースなアレンジは1980年代のシンガーやロックバンドに近い空気をやはり覚えさせる。
曲調はマイナーから入り、やや地味なミディアムなナンバー#6『Get To Me』も80年代のヒットラジオチャンネルから流れてきても違和感の無いUKポップ風のナンバーだ。キーボードをパーカッシヴに使うところがアルバム・ロックっぽい。
#7『Counting Airplanes』も同様にベントで暗いメロディと打ち込みサウンドが目立つナンバーだが、コーラス部分ではメジャーな転調をする、典型的なクラッシックポップのアプローチを見せる。オルタナティヴ的な憂鬱な雰囲気が支配的なのは現代メジャー界のバンドである以上は仕方ないかもしれないが、いまいち吹っ切れが足りない。
#8『Following Rita』も鍵盤を上手く使用したスロー・ミディアムなナンバーだ。サウンドは厚めに鎧っているし、アコーディオンをアレンジしてトラッドな色を出そうと努力しているが、やはりコアの部分にジャムバンドのロックとしてアクセルを踏めない箇所が残っている気がする。
このアルバムがいまいちなのは、中盤#5あたりから#9『Your Every Color』まで似たような、「サウンドアレンジ80年代
/ メロディはジャムオルタナ」と表現したくなる中途半端なスロー系のスカっとしないヌタっとしたナンバーが続く事、これに尽きる。
この部分がもう少し何とかなっていればメジャーでヒットするのに疑問の無いアルバムになったと思うのだが。
◆続投、プロデューサーのBrendan O'Braienは吉と出た
前作に続き、プロデューサーにBrendan O’Braienを迎えたTrain。
取り敢えず、この継投は大きくプラスに作用したのは間違いない。Brendanはとても良いプロデュースをしたと思う。
また、Brendanはミュージシャンとしても更に深くアルバムレコーディングに関与している。
ピアノ、オルガンを始めとするキーボード類全般、そしてパーカッションやギターでも演奏に加わり、Robの抜けた穴を埋めて補うものがある。バックヴォーカルでも参加し、ミキシングも手掛けている。
更に加えて、Pat Monahanと共同で3曲の曲を提供までしているのだ。
O'Braien / Monahanとなっているのが以下の3曲。
#2『All American Girl』
#4『Save The Day』
#5『My Private Nation』
何れも曲としてはロック系に属するというのが、Brendanが手を貸した所以かもしれない。
基本的にサウンドの肉厚はあるのだが、テンポとしてはミドル近辺のゆったりしたナンバーが多いこのアルバムではロックンロールとしてのマッチョぶりを際立たせている。
特にオルタナ風味のギターに、ライトファンクなリズムが乗っかる#2はアルバムの中でも最もパワフルなロックナンバーになる。
かなりモダンロックとオルタナティヴ、そしてアメリカンルーツの各要素が複雑に混じり合い、判然としないロックチューンのため、やや安っぽく見えてしまうが、オルガンやピアノの乱れ弾きも飛び出し、ダイナミックな80年代式アリーナサウンドの顔を見せるナンバーでもある。
このあたりが、80年代から活躍するBrendanの嗜好が出ている地点だと思う。
#4はこれまた軽めのファンクさが織り込まれたロックチューン。かなりくぐもったドブロギターのような音色をバッキングさせておいて、突然リズムを変える手法のためか、それ程ロック的な性格は強くないのにロックナンバーとして聴こえるのだ。
しかし、Pat Monahanのヴォーカルはこういったバタバタしたナンバーになると役不足に感じてならない。特に欠点がある訳ではないのだが、チープで底が浅く感じてしまう。
#5は西海岸ポップスの流れを含んだ、ややダークなビート・チューンだ。これまた産業ロックのエッセンスが厚めのサウンドに盛り込まれており、ラウドでノイジーさが中心なメジャーのロックな音とは少しばかり方向が違っている。とはいえ、やはりオルタナティヴの無機質で冷たい味気なさもまた同居しているのだが。
Brendan O'Braienという男を、筆者は天と地、至高とどん底の両方のアルバムを作るプロデューサーと見なしている。
Dan BairdやBlack Crowes(初期限定)と組んで質の高いアメリカンルーツロックのアルバムを作成したと思えば、Pearl JamやStone Temple Pilotといったへヴィロックの権化の塊なバンドのアルバムを補助し、更に卑属で商業主義音楽が間違った退化を遂げたPapa Roarch、Limp Bizkitといったラップメタルや聴くに堪えない雑音レヴェルのバンドまでプロデューする。
かと思うと、DylanやNeil Youngにプロデューサーとして起用される才能の持ち主でもある。
要するに器用貧乏が嵩じて、安定した一本の仕事では終わらない人と好意的に解釈していいのだろうが、それにしてもラップメタルや打ち込みヘヴィロックまでアメリカンルーツロックと等列に作成出来るのは凄いのか、それとも単に売れ筋の音が得意なのか・・・・。
であるからして、Brendanを無条件でデフォルト買いプロデューサーとはしていないし、実際にハズレが多くもある。(その分当たりは出ればでかいが。)ミュージシャンとエンジニア以外ではあまり評価してもいない。
実際、本アルバムでPatと創った3曲は、どれもそこそこのレヴェルで安定してしまっているし。
が、今回はかなり良い出来をマネージメントしていると考えている。
Trainサイドとしても2作続けて同じプロデューサーを起用する事自体、プラスとマイナスの両面があると思うが、前作を超えようとする試みを、同じプロデューサーと組んで行ったことは評価対象になるし、事実前作はかなり超えたアルバムに仕立てた点は賞賛に値する。(相対的な評価なので、前作のレヴェルは考慮しないでおく。)
なまじ前作が大売し、それなりの完成度と売り上げを求められてしまうメジャーレーベルでの活動のため、安全牌としてBrendan O’Braienを再度選んだという側面も無きにしも非ずだとも邪推可能だが。しかし、手堅く小ぢんまりとした無難な作品を狙うのではなく、かなりサウンドに手を加えて、レヴェルが上がっているので、今回はBrendanの手掛けたアルバムとしては当たりの部類に入ると思う。
◆バラードは安定した良作揃い
個人的に当たりかゴミクズのオール・オア・ナッシングの傾向が強いBrendan作製のアルバムで当たりを引いたのは確かに喜ばしい。
が、それ以上に筆者として喜ばしいのは、Elton Johnの初期から中期の名作でオーケストラアレンジメントを担当して、彼の黄金時代を支えたスタッフの一人であるPaul Backmasterが#9『Your Every Color』と#10『Lincoln Avenue』で指揮棒を振っている事だ。
『Drop Of Jupiter』のアレンジメントで自身としては初のグラミー賞を2002年に受賞したのはかなり驚きでもあったが、これはロックの名バラードが如何にラジオでブレイクしなくなったかというお寒い現状のバロメータでもあるのだ。
それはそれとして、バラードは今回もレヴェルは高い。
Monahanの裏声もバラードの甘さにはとても相性が良い。
#10『Lincoln Avenue』でのPatのヴォーカルが裏返る箇所は、ヴォーカルワークとしては過去最高の感情が篭っていると思う。そしてPaulのストリングスアレンジメントは曲を十分に活かしている。
ノイジーさとシンプルだけで攻めるのが主流となっているメジャーのロックバラードに対する反論を感じてしまう懐かしのバラードらしいバラードだ。
が、バラードの中のバラードといえば#3『When I Look To The Sky』も#10と甲乙付け難い。ピアノを堅実にフューチャーしたアリーナロックのバラードを思い出させるサクッとした切れ味のあるトラックだ。シングル用に用意された、と直感的に思ってしまう所が80年代しているような。(苦笑) ・・・勿論誉めているのだ。
#11『I’m About To Come Alive』は打ち込みドラムのシークエンスから始まるため、期待していなかったがどうしてアクースティックだがトラッドでアーシーで優しい。
ジャムロックの腑抜けた腰の弱さがないアクースティックなバラードだ。脱ジャムサウンドに関しては厚目のロックナンバーが目に付きやすいが、寧ろ最後のこのトラックにTrainの変化と変革が最もくっきりと表現されていると考えられるのではないだろうか。
◆脱線せずに堅実なダイヤで運行できそう
という事で、今回も途中下車せずに最後までこの「列車」に付き合えた。
不満は結構あるが、それを相殺して並以上のアルバムになるとは思う。
とはいえ、やはりメジャーでの活動を意識してレコード会社の意向が多く入り過ぎているとは思う。
本格派としてアメリカントラッド系のバンドを志すなら、駅のひとつやふたつを予告無くスルーするような暴走振りを見せてくれても良いのでは。
本作もトップ10入りして順調にヒットはしている。が、多くの海外レヴュアーがTrainをCounting Crowsの後釜や後継者扱いしているのは、持ち上げ過ぎた。率直に言って、このメジャーへ媚コビがある限り、Counting Crowsの足元にも及ばないし、KickbacksやWorry Stonesといったインディバンドより格段に劣っている。
録音機材とスタッフでは勝負にはならないが、サウンドクオリティでは比較にならないくらい風下だ。
もう少し自分のサウンドをやって貰いたい。まあ、その結果ジャムとオルタナに戻るなら、それは評価して見捨てるだけだが。
『Drop Of Jupiter』が「売るため」だけに妥協して作った名バラードではないことを証明するような脱オルタナ・メジャーのサウンドで走る「列車」を次回は希望する。 (2003.9.11.)
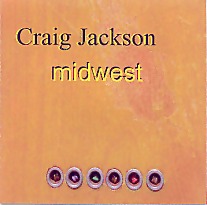 Midwest / Craig Jackson (2003)
Midwest / Craig Jackson (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Adult Contemporary ★★☆ You Can Listen From Here
◆この「Midwest」を聴いて思うこと
Tom Pettyの「Into The Great Wide Open」や「Full Moon Fever」といったTraveling Wilberysの活動にインスパイアされ、これまでのB級感覚から脱却し始めていた頃を思い出す。
風格としてはどっしりしたロックアルバムとなった「Echo」に近い安定感がある。
Bob Segerのヒットチャートと親和性が存在し、尚且つロックンローラーとしての立場もしっかりとレコードで表現出来る才能も見出せる気がする。
思わず、「Stranger In Town」、「Against The Wind」、「Like A Rock」、「The Distance」といったオヤヂの名盤を引っ張り出して聴き返したい衝動に駆られた。
リマスター盤が欲しいぞ、コンニャロメ!!
また、John Hiattが初期のいまひとつ方向性の見えないこれまたB級のロックから抜け出て、ルーツロックとポップミュージックの美味しい箇所を捉え始めた「Bring The Family」を初めて聴いた時の事も懐かしく記憶から浮上してきた。(とはいえ、このアルバムはそれ程評価している訳ではないけれど。『Have A Little Faith In Me』はロックの名曲。)
更に、「大西洋を渡る」前後までのRod Stewartのルーツとポップミュージックを程よくブレンドした名作群を無意識に連想したりしてもう一度聴き直してしまったりもした。
が、方向性としては「Atrantic Crossing」や「Night On The Town」の頃が最もCraig Jacksonと似通った音楽性を持っていると思う。
つまり、極端にルーツミュージックを意識せず、どちらかというとより一般的にモデレイトされたPop/Rockに傾き始めたRodの動きに近い要素があるのだ、Craig Jacksonの音楽には。
誤解を生むかもしれないが、Billy JoelやElton John、更にJames TaylorやJackson Browneといった著名なシンガーソングライターをも知らず知らずに比較対象としてしまうメロディの親しみ易さが存在する。
当然、Jackson Browneを除くと、ルーツ色という点においてはCraig Jacksonと比べること自体ナンセンスかもしれないことは前提としておこう。
特に、Craig自身がプレイするのではないが、メインの楽器として多用されているピアノの巧みなアレンジを耳にすると、ピアノ・ロック、しかも最近では全くお目にかかれないPop/Rockとしての円やかさを楽しむ事が可能だ。
ここまで全くオルタナティヴの影響を感じられないPop/Rockに出会う−しかも重要な所はルーツ・ミュージックのエレメントがそれなり以上に組み込まれている点−のはとても嬉しい。
Worry StonesやKickbacksをリーダーとして、カントリーではない正統派のPop/Rockは探せば結構見つかるものだけれど、やはり貴重なものは貴重である事には変わりは無いのだ。
但し、メジャーアーティストとなるには至ってないけれど、前座としてはかなりの大物に起用された実績があり、実力はかなり認められているように思える。このあたりは後に書く事にするが、正当に実力が評価されていないDirty TruckersやKickbacksを思えば、Craigはまだ恵まれた状況にあるように思える。
とはいえ、レコードは自主レーベルから今作も含めて3枚連続とはなっているのが現状ではあるのだが・・・・。
Counting Crowsもオルタナティヴを感じられる現代性というか90年代の香りが初期の頃には多かったが、次第に独自のアメリカン・ルーツを押し出して、完全なステイタスを確立しているが、このCraig Jacksonにも同じ感触を覚える。
2枚目までのWallflowersや、売れ出してからのShawn Mullins、Sister Hazelといったオルタナティヴのどうしようもない重石から開放されて自らの音楽を創造している、近年のヒットメイカーやメジャーなアーティスト達に比較して何ら人後に落ちる事の無いクオリティを持つアルバムなのである。
◆タイトルは「中西部」だけれど、西海岸の人
Craig Jacksonのアルバムは今回で3作目となる。タイトルは「Midwest」で米国中西部を指す。(当然米国でMidwestといえば、中部エリアの平原諸州を意味する。要するに自分の国の中西部だから、米国中西部となる訳だ。また地勢的にもど真ん中の中部地区も一般には「中西部」として区分される傾向にある。)
タイトルからしてHeartland RockやAlt-Countryの良作の宝庫を示唆する物であり、最近筆者が最も注目しているボストンを始めとする東海岸中緯度から高緯度に掛けての地域と同じく、中西部は良い物に出会う確率が高い。
実際にCraigのサウンドはAC(Adult Contemporary)とダウン・トゥ・アースな感覚が程よくブレンドされたHeartland Rockのサウンドの親類以上のものだ。
Jimmy RayserやMicheal McDermottといった米国平原諸州で地道に活動している、カントリーとは無縁だけれど、アダルトで懐の深い包容力を有したシンガーのアルバムに通じる要素も存在する。
と、ここまで書くと、Craig Jacksonもミネアポリスやシカゴ、コロンバス界隈で活動する中西部のシンガーという感じが書いている自分でもしてくるのだ。が、Craigは現在L.A.の衛星都市というべきロング・ビーチに居を構え、モロに西海岸で活動しているアーティストだ。
そもそものキャリアのスタートはカリフォルニア州の北部にあたるサンフランシスコのベイエリア周辺だったそうで、生粋のウエストエリアの人だ。
西海岸といえば、EaglesやPocoに代表されるカントリーロックの名所でもあるが、Craigにも西海岸ポップやロックの特質がやはり見て取れる。
しかし、西海岸カントリーとは異なるタイプの音楽で、俗に言うL.A.ポップスの影響がより顕著に出ている音楽性ではないかと思う。
目立つ程ではないけれど、プログラミング系のパーカッシヴなリズムを使ったりして、ベッタリ重いルーツ音楽には入り込んではいない。
海岸付近で特有の、清涼感のあるサーフロック的な側面が時たま耳に入ってくる事があるのだ。
がこれが前面に押し出ているのではなく、あくまでもACとルーツ的な南部サウンドの隙間に存在する要素であるため、却ってCraig Jacksonの音が聴き易くなっていると思う。
ルーツロックサイドよりもポップロックサイドを補助する働きで彼なりの西海岸的背景が活かされているのだろう。
しかし、これまでも今作のような、ルーツとアダルトロックの狭間に位置するような、アメリカン・ポップロックを発表し続けてきた訳ではない。
◆Tom Pettyを引き合いに出される事が多かったが、それは・・・
前作にあたる、「Last House On The Left」でTom PettyやJackson Browneと比較されて、次世代の彼ら大御所とまで評価されているレヴューが海外ではそれなり以上に見受けられる。
例えば、こんな記述。
“The Best Tom Petty Album By Someone Other Than Tom Petty.”
賛辞としては最大級のものだと思う。
確かに2枚目のアルバムでは非常に南部サウンドへの傾倒が顕われている。
中にはラジオフレンドリーなポップで即効性の高い曲もあったが、どちらかというと渋めで暗め、そしてメロディよりも深みを重んじる曲が多い。試聴リンクで2作目のサンプルもダウンロード可能なので、聴き比べてみることをお薦めしておこう。
見るからにサザンサウンドをベースにしたアダルトなロックが主体で、サンプルを聴いていると、1980年代前半までのTom Pettyのアルバムを連想する人はかなりの数になると予想している。
少し枯れたヴォーカルも何となくだけれど、Pettyに似ている箇所がある。(というか、ヴォーカルだけならTom Pettyよりも流暢で説得力があるだろう。クセが一杯のTomのヘタウマヴォーカルのほうが印象度は高いかもしれないけれども。)
AC系のラジオ局を通して、結構頻繁にオン・エアされたという『Blind By Love』を聴くと万言を費やすよりもはっきりするだろうが、モロにサザンでマッディな粘着性のあるオルガンが映えたTom PettyがB級ミュージシャン(筆者独断と偏見)だった頃をそのままCraigが歌った感じである。
◆メロディがぐっとポップに、聴き易くなり、これぞ本領発揮
という具合に、2作目までのCraigは西海岸で南部サウンドをベッタリと歌うのが基本のルーツロッカーだったのだ。これならインディでも納得の出来だと思う。(?)
ちなみに処女作の「Make It Right」は未聴だ。
足掛け5年前にリリースされた前作の「The Last House On The Left」を筆者は米国で入手しているが、完全に忘れてしまう程度の我が嗜好度とのシンクロ率だった。
ベタなサザン系ルーツアルバムとしては悪くない出来だが、このくらいの歌い手なら需要と供給の兼ね合いは別として、マイナーシーンには数多く存在する。
だからして、「Midwest」というタイトルに、灯火目掛けて飛んでくる蛾のように惹かれて試聴に辿り着いた時、Craig Jacksonというミュージシャンは完全に記憶から飛んでいた。大変失礼な事をしてしまったようだ。
が、第一弾シングルとなり、Top40やAC系のステーションで歓迎されているという#4『Just A Memory』を聴いた瞬間に、別の意味で吹っ飛んでしまった。
まさに、筆者がそれまで唯のたま〜にポップなシングルを出す歌い手と見なしていたTom Pettyが「Full Moon Fever」で驚かせ、「Into The Gread Wide Open」で吹っ飛ばしてくれた時の驚愕まで再現してくれた。
これまでは暗く、重めでマイナーな南部の玄人好みなサウンドを中心に組み立てていた人が、このようにACに擦り寄ったサウンドに針路変更し掛けている事に対して、サザンサウンドの濃い口の部分が好物なリスナーは抵抗を覚えるかもしれない。
が、キャッチーでなくして何の大衆娯楽サウンドか!!
という筆者の手前持論と嗜好からすれば大歓迎だ。
しかし、冒頭で述べているように、完全にPop/Rockで固めた−日本で言えばAORに当たるだろう−アルバムになってしまった訳ではない。
ちゃんとルーツィな部分は、非常にオイシイ所を中心に残してあるのだ。
◆ルーツ中心の曲と、アダルトロックに比重を置いたナンバーの棲み分け、そして融合
全体として、サザンサウンドを濃く残したナンバーにしろ、より一般的に耳に入るようになったポップやロックのトラックにしても、全体的にポップさが底上げされている。
そして重要な点は、どのナンバーにしても必要最低限はアーシーで安定感のあるアメリカン・トラッドの感性が活きている事だ。
ために、この曲はルーツ、この曲はAOR的なナンバーと区分するのはあまり良い分け方でないかもしれない。
が、その中でもルーツ指向・南部指向が強いナンバーは存在するし、よりポップチャート向けに(本人がどう考えているかはまだ回答を戴いてない。)精選されたPop/Rockなルーツロックもある。
よって、ルーツの度合いがどのくらいか、牽いてはポップミュージックにどの程度Craigが傾いたかである程度曲のタイプを切り分け出来そうだ。
大別すると、そうなるが、その中でもCraigはかなりの引き出しとトランプの多さ(切り札)を今回は披露してくれているので、やや単調な南部アルバムに終始していた前作とは及ぶべくも無いバライェティに富んだアルバムになっているのだ。
この1枚で散漫にならず、且つ良質なルーツ系のポップロックが楽しめるというのは名盤の条件である。
「Midwest」はその条件を完全に満たしている。
時期が良ければ、筆者としてもトップにジャケットを飾るレヴューに選んでいたと思う。
総括すると、ルーツとポップロック、この2つが微妙に混じり合い、強弱を分けて曲ごとに棲み分けを行っている。然れども、基本はルーツサウンドとベーシックなヴォーカルロックの融合と見るべきだ。
近年絶えてしまったかのような、ヴォーカル系のロックはインディシーンでもジャンルのクロスオーヴァーが進む割には見つける事が結構稀であり、こういったサウンドに出会えると−しかもあまり期待していなかった人による−とても喜ばしいのだ。
◆ルーツ中心の曲と、アダルトロックに比重を置いたナンバーの棲み分け、そして融合
全体として、サザンサウンドを濃く残したナンバーにしろ、より一般的に耳に入るようになったポップやロックのトラックにしても、全体的にポップさが底上げされている。
そして重要な点は、どのナンバーにしても必要最低限はアーシーで安定感のあるアメリカン・トラッドの感性が活きている事だ。
ために、この曲はルーツ、この曲はAOR的なナンバーと区分するのはあまり良い分け方でないかもしれない。
が、その中でもルーツ指向・南部指向が強いナンバーは存在するし、よりポップチャート向けに(本人がどう考えているかはまだ回答を戴いてない。)精選されたPop/Rockなルーツロックもある。
よって、ルーツの度合いがどのくらいか、牽いてはポップミュージックにどの程度Craigが傾いたかである程度曲のタイプを切り分け出来そうだ。
大別すると、そうなるが、その中でもCraigはかなりの引き出しとトランプの多さ(切り札)を今回は披露してくれているので、やや単調な南部アルバムに終始していた前作とは及ぶべくも無いバライェティに富んだアルバムになっているのだ。
こういった、1枚で色々と手数を見せながらも散漫にならず、且つ良質なルーツ系のポップロックが楽しめるというのは名盤の条件である。
「Midwest」はその条件を完全に満たしている。
時期が良ければ、筆者としてもトップにジャケットを飾るレヴューに選んでいたと思う。
総括すると、ルーツとポップロック、この2つが微妙に混じり合い、強弱を分けて曲ごとに棲み分けを行っている。然れども、基本はルーツサウンドとベーシックなヴォーカルロックの融合と見るべきだ。
近年絶えてしまったかのような、ヴォーカル系のロックはインディシーンでもジャンルのクロスオーヴァーが進む割には見つける事が結構稀であり、こういったサウンドに出会えると−しかもあまり期待していなかった人による−とても喜ばしいのだ。
◆ピアノ>オルガン なアレンジが目立つ / アップテンポな曲が特にキャッチーになった
まず、#1『Down』から軽やかな録音が為されたピアノの音が印象的だ。ドラムはやや人工的なビートだが、やや皺枯れたCraigの声とは対照的に、クリアな音を転がすアクースティック鍵盤が曲全体を上手く纏めている。
このピアノを弾いているのは、プロデューサーも兼ねているJoe Simonという人だ。恐らくBarry Manilow等のアルバムに手を貸している人とは同姓同名の別人だと思うが、実に良い仕事をしている。
それに、ハーモニーヴォーカル専属として、とても耳に残る女性ヴォーカルを受け持っている、Lori Lynnerという人が最初から素晴らしいダブル・ハーモニーを聴かせてくれる。
クレジットには“Vocal & Soul”と銘打たれているが、まさに“心からの歌”が心に残る。
やはり、女性はリードなんぞ歌わずに、男性のヘルプしているのがベストだと、完全な独断と偏見で思っている筆者の主張を具現化したヴォーカル・ヘルプだ。
このミディアム&アダルトなロックの教本のようなオープニングから、ピアノがメインを張っている事が予想されたが、実際この3枚目ではピアノが良い仕事をしている。
前作にてサザンロックの枯れた感じを後押ししていたオルガンも、無論使用されているが、今回のアルバムはポップになった事にも関係するだろうが、ピアノが目立つ。これは良い事だ。
#1でややスマートなミディアムナンバーを出してきたかと思うと、John Hiattの「Slow Turning」を思わせるスライドギターがのっけから炸裂する#2『Ten Feet』が続き、ルーツィでレイドバックした基本をCraigが保持している事を確認できる。ここでもピアノとLoriのバックヴォーカルがポップフィールドに曲を繋ぎ止める働きをしている。
まるで、デビュー当時のBruce Hornsbyのようなコマーシャル且つ田舎臭いルーツロックとポップロックの中間に位置する極上のソングである。
これもスライドギターを目一杯南部風に鳴らしながらも、軽快なアップビートなロックソングに仕上げており、#1と同様にシングルに切りたいトラックだ。
ファーストシングルは#4『Just A Memory』だが、感じとしては#1と#2の真ん中のような中テンポの、これまた80年代ならメジャーチャートが放って置かない親しみ易いナンバーだ。
スライドギターも時折自己主張をするアーシーさを持ちながら、少しコーストサウンド特有の憂いが見える、西海岸的なポップ感覚が裏に見えてくるナンバーだ。
やや、サーフ的な爽やかな明るさと、ソウルリズム的な弾みの快感がインプレッシヴな#8『The Words』はデビューしていきなりブレイクした頃のRichard Marxを懐かしく振り返らせてくれる。
「Richard Marx」程乾いたフィーリングではないが、オルガンやループを上手く活用して、西海岸アダルトポップのユニークさをしっかりと刻んでいる曲だ。
しかも、転調と変調を僅かずつ繰り返し、ギターソロ、オルガンソロ、女性ヴォーカルとの掛け合い等を次々と登場されてくれる。
本作の、濃いルーツオンリーな既存作からもう一歩進もうとしている姿勢が反映したナンバーで、興味深い。
◆スロー系の曲に残る南部サウンドへの拘り
#3『Won't Let Go』のややダートな暗さと淡々としたテンポは、かなり地味目である。特に#1、#2そして#4、#5とシングルにどう転んでもなるしかなさそうな良作が並んだ中では見劣りするが、箸休め的なスローナンバーとしては良い位置にあるだろう。
このナンバーは特段ルーツィではなく、アーバン・ヴォーカル的な感じだ。後期のChicagoがアレンジを抑えて演奏をすればこんな曲がアルバムに入りそうな気もする。
モロにルーツ的な偏りを感じるのが、Tom Pettyが好んで取り上げそうな#6『Arrive』だ。ミディアムなテンポを軸に、少し憂いを帯びた南部特有のマイナー調子が切々と語られる。
前作でよく見られたパターンの曲だが、こういったタイプの曲がたまに出るなら、じっくりと聴くに向いている事を改めて思ったりした。続き過ぎると暗くなり過ぎるし、バック・トゥ・ルーツに走りが加速してしまうのであまり宜しくないが。
ピアノやオルガン、スライドギターを使いつつ、かなりスマートなポップソングに移行するかなと思わせつつ、かなり捩れた南部テイストを見せる#7『Another Voice』。
これまたCraigがこれまで得意にしていたサザン・ロックの典型だ。
このアルバムはかなり積極的にループドラミングが使われているけれども、人工ビートを重ねつつもしっかりとアーシーな色合いを出している所は賞賛に値する。
ピアノとオルガンが短いがバトルを行う間奏の一部分はかなり好きだ。部分的にだけれど。
◆勝負バラード#5『Time』とアクースティック・ミュージシャンとしての主張な#11
Craigは自らバンドを編成し、演奏活動を行っているが、何故か鍵盤担当がバンドに存在しない。ギタリストが複数在籍し、これだけアルバムに鍵盤を活用しているのに。
この点は納得が如何しても出来ないのだが・・・・。
それは置いておくとして、Craigはバンド活動と平行してアクースティックギター1本で歌い上げるソロ活動もやっているのだ。試聴リンクでアクースティックなライヴ音源やデモ音源が聴ける。
そのアクースティックでフォーキィな興味を提示しているのが、#5と#11の『Time』である。
#5はストリングスやループドラム、ピアノ等をフューチャーし、AC音楽の権化のような名バラードに仕上げている。
このアルバムでは最もバラードらしいバラードだろう。まさにバラードの王道だ。
が、ボーナストラック的な性格が強い#11『Time(Acousitc)』では、そのままにギター1本で歌い込むヴァージョンが聴ける。
こちらは一層Craigの渋いヴォーカルに集中が可能だと同時に、打ち込みドラムが無い分メロディの素直さと良質さが際立っており、どちらのヴァージョンも甲乙付け難い。
この2つのアレンジのナンバーに、Craigが生の音を大切にするシンガーという拘りが見えてくる。
とはいえ、やはりロックアンサンブルのアルバムがCraigには似つかわしいだろう。
フォーキィ一筋なアルバムは味わいがあるが、それでアルバムを1本綴ってしまうとどうも退屈してしまうからだ。
しかし、Craigがアクースティックな基本を忘れない限り、このアルバムのようなオルタナティヴに全く諂わない良質なルーツロックを重ねてくれるに違いないと思う。
◆未聴の1stが欲しくなったアルバム
という事で、本人にコンタクトしないと入手が出来ない1作目「Make It Right」に俄然興味が沸いて来た。
是非とも手に入れたいのでコンタクト中である。
90年代のTom Pettyが好きでヴォーカルロックに目が無い人はこのアルバムを。
80年代のPettyが好きなら前作を。
こうったチョイスでまずCraig Jacksonに触れてみる事をお薦めしよう。
「Midwest」というタイトルの名に恥じない中庸的な平原州風のロックが、西海岸ポップを絡めて昇華したサウンドが楽しめるだろう。
まずは試聴してみて、そして買うが吉だ。 (2003.9.28.)
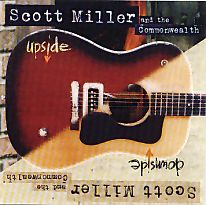 Upside Downside
Upside Downside
/ Scott Miller & The Commonwealth (2003)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★
Alt-Country ★★☆ You Can Listen From Here
◆微妙な意味で鋭角的だったソロデビュー作を振り返る
2001年に前作「Thus Always To Tyrants」を聴き、レヴューを書いた。確かこのScott Millerのソロ処女作に対して、以下趣旨のような事を綴った。
オルタナティヴとカントリーの両面性が出ているロックアルバムで、特にオルタナティヴ的なアレンジが目立つ。
オルタナティヴかルーツかどちらかといえば、ルーツロックとして最終的に落ち着いているけれど、ポップに特化したアルバムと問われると首を捻る事になる。
かなりハードコアな部分もあり、音楽的な分類はAlternative Countryではなく、Alternative & Countryとしたい。
しかし、格好良いか悪いかを考えるとかなり格好は宜しいロックアルバムになっており、解散した元バンドであるV-Roysのオルタナやモダン性を強調しつつ、そこにカントリー・ミュージックのテイストを加えたユニークだけれども、かなりアクの強い尖ったアルバム。
その癖が特徴でもあり、不満でもあった一長一短な作品。
そんな評価を自らしている。そのアルバムから約2年が過ぎ、同じ名義であるScott Miller And The CommonwealthでMillerの2枚目リーダー作が登場した。
The Commonwealthというバックバンドの名前だけではなく、ジャケットのデザインからも、Millerのインテリゲンチャな趣味が湧出していた「Thus Always To Tyrants」の特異な雰囲気とは異なり、近作の「Upside Downside」はギターを2本あしらったデザインをジャケットの写真として使っている。
見るからに音楽のアルバムとなっている点で、無難で平凡な先行イメージを勝手に脳内で形成してしまっていた。聴く以前に。
さて、実際はどのようなアルバムだっただろうか。
◆ジャケットとタイトルに見られる二面性
細々と解説する必要もないだろうが、まずはジャケットに注目して貰いたい。
アクースティックギターとエレキギターが正方形をそれぞれ三角形で割ったような合成写真として貼り付けられ、一見ツートーン・カラーのギターに見える・・・・・見えないかな・・・・。
そして矢印でエレクトリックギターに「Upside」、アクースティックギターには「Downside」と指示されている。
で、アルバムの題目が「Upside Downside」となる。
明らかに、アナログ盤を意識したA面とB面で方向性を縦割りした構成となっている。
近年、こういった擬似的にLPのスタイルを採用しているアルバムを目にするようになってきた。メジャーどころでは、Counting Crowsが最新盤にてSide-A、Side-Bという形でアルバムを分けている。
しかし、明確にアクースティックサイドとロックサイドをタイトルにまで付随する試みは、ありそうでなかなか無いものである。
2枚組みでライヴ盤等には、ロックとアンプラグドをそれぞれ割り振る手法が多く選択されるけれども。
そもそも、こういった試みはアルバムを単調にさせてしまうマイナス面が存在する。
ロックアンサンブルとアクースティックなナンバーが混在してこそ、面白いサウンドが楽しめる場合が一般的だし、同一的なナンバーが並んでしまうと、どうにも退屈を−特にそのフォーマットが凡作な場合は致命的とも云える−覚えてしまう事はしばしば。
基本的に筆者がアクースティック一辺倒なアルバムをあまりレヴューしないのはそこに原因があったりする。
和みなナチュラル弦は良い物だが、そればっかりでは物足りないからだ。
で、実際にしっかりとロックとアクースティックに分かれているか、この「Upside Downside」を聴いてみると、
確かに6曲ずつほぼ縦割りにされ、「Downside」はアクースティックアレンジで纏まり、「Upside」はエレキギター中心に構成はされている。
しかし、「Upside」には#3『The Way』のようにアクースティック系のバラードもあり、どちらかというと、アクースティックとエレクトリックを含めたロック・ジャム風の狙いで「Upside」は形作られている感じである。
それが悪いとは思わないし、失敗しているとも思わない。
が、全体としてみた場合、この試みは成功しているだろうか。この点は纏めに書くとしよう。
◆「Upside」は回顧主義か?
オルタナティヴの残滓−V-Roysで中途半端に抑えていたモダンサウンドへの鬱屈−を晴らしたようなナンバーが時折、ガンガンと流れを揺さぶっていた「Thus Always To Tyrants」でのオルタナサウンドは完全に払底され、殆ど見られなくなっている。
その分、よりアーシーでポップ、そしてかなり古典的な南部サウンドやBoogieスタイル、オールディズといった根源音楽へのアプローチを増やしている。
特に、1950年代や60年代のR&Bロックやロック・アラウンド・クロック時代を連想させるような古臭さと懐かしさを同居されたナンバーが「Upside」には多い。
その傾向を顕著に物語っているのが、曲の演奏時間である。
「Upside」6曲のうち、実質アップテンポではない#3『The Way』以外は全て3分以内の長さしかない。
2分台のヒット曲しかラジオ局に求められなかった、ロック時代初期から60年代をそのまま持ち込んだような擬似A面となっている。
古典ロックのシンプルさを代弁するように、今回は演奏ミュージシャンの数もシンプルになっている。
インナーに「A-Side」という題と共に、6曲が後半と分割して書き出されている。それと一緒に各曲に対するScottの短いコメント及び演奏メンバーのクレジットが曲ごとに掲載されているが、核となる演奏メンバーはほぼ完全に固定。
Scott Miller (Guitars , Harmonica , Vocal)
Shawn McWilliams (Drums , Percussion)
Eric Fritsch (B3 , Keyboards , Slide Guitar , Percussion , Vocals)
Park Chisolm (Bass,Vocals)
唯一、#6『Chill , Relax , Now』にて全員のハンドクラップとヴォーカルにRichard McLaurinという人が参加し、#3『The Way』でハーモニーヴォーカルを担当するPatty Griffinがイレギュラーな応援となっている。
前回の「Thus Always To Tyrants」では、合計14名ものミュージシャンがThe Commonwealthとして登録されており、Scott Millerを補助したミュージシャンの総称を「大英帝国連邦」と呼んでいた感が強かったが、今回はかなりこじんまりした編成に変化している。
当然、ツアーやギクには固定のバンドメンバーが存在する訳で、今回のアルバムはそのコアなメンバーを中心に録音されている。
Another Sideとスリーブには記載されている「Downside」ではまた顔ぶれが若干異なるけれど、この4ピースは全編を通して共通である。
キーボード及びスライドギターを演奏するEricが前作から引き続きのバンド入りとなっているが、他の2名は記憶を探ると今回が初参加か?
現在手元にアルバムが無い為、このメンバーの構成に関してはやや記述が曖昧になってしまっている。
◆ロックサイドである「Upside」
さて、それでは各ナンバーに寄せられたScottの短いコメントと共に、「Upside」について書いてみるとしよう。
あまり意味のない覚書程度であり、直感で書かれている文章なため、意味を成さない事が多々ある。しかし曲の雰囲気を掴む手助けにはなるかな。
●#1『It Didn't Take Too Long』
「この曲はモノラルでミックスされている。でも僕の叔父さんが曲中でショットガンを装填している音がステレオで聞こえるね。」
モロにロック時代元祖を思わせる、シンプルなロックナンバー。『Roll Over Beethoven』なノリを連想すれば極めて妥当な感触が得られるだろう。Chuck BerryやBully HollyといったR&Bロックのヒットシーカーの足跡をそのままプリントしたような曲だ。
パーティロックな楽しさが存在するが、「Thus Always To Tyrants」で代表的なアップビートナンバーだった『Yes I Want』等と比較すると、かなり即興的で刹那的だ。
要するにシンプルで分かりやすい。ネガティヴな表現をすれば、粗過ぎていい加減な投げやりさすら見える。
もっとも、かなり哲学的な鬱屈と懊悩をサウンドに託していたと感じられる前作とは打って変わって、アッケラカンとした明るさと思い切りの良さが伝わってくるので、素直に楽しむのが吉だろう。
●#2『Raised By The Graves』
「随分昔の事だけど、祖父と街を練り歩いた記憶がある。(彼は徒党を組むのが嫌いな民主党支持者だった。)祖父は道路の脇を指差してこう言った。『ここは嘗て儂がニクソン大統領の辞任を聞き、嘆きながらへたり込んだ場所だ』ってね。」
#1より更にファン・ロックで縦にノリノリのカッティングが鋭いロックナンバー。これまた#1と同様に古臭いイメージが満載になっている。
終始B3とギターが小気味良いシェイキングを繰り返し、リズム感覚としては抜群なノリがある。単調なコードをひたすら繰り返す事がロックの醍醐味のひとつである事を教えてくれるようなナンバーだ。
3分に満たないナンバーだが、ヴォーカル部分よりもロックにジャムっている時間の方が長いように思える、ライヴにシンクロした曲でもある。
Scottのライナーノーツで話題にしている事はこのナンバーとは無関係ではない。♪「I was
raised by the graves」=「オレは墓の傍で人生を送ってきた。」というある男の人生を駆け足で歌う形式を擬態しつつ、実際はややシニカルな合衆国の政治批判を交えた、メッセージソングの類。
●#3『The Way』
「僕がずっと見失っているもの。」
「Upside」唯一のバラード。というかアクースティックな曲がこれ。そしてこのA面で唯一3分を超えている長さでもあったりする。
Scottのハーモニカ、かなりノスタルジックなハモンドB3、そして時折聴こえる女性のバックヴォーカル、とバラードの要素を過不足無く満たしているオーソドックスなトラック。
このアルバムからの第一弾シングルとしてカットされ、前作の曲や未発表ナンバー、そしてNeil Youngのカヴァーまで含めたミニアルバムとして、所属先のSugar Hill Recordsから新たに「The Way」として発売されている。
良い曲だからシングルにしても問題ないとは思うが、このロックサイドに並んだロックナンバーと同じ流れに落ち着いていると、如何せん地味な感は拭えない。
それにも増して、何故に「Upside」にスローナンバーを入れたのかが疑問でもある。
●#4『Pull Your Road』
「僕が通学のため故郷を離れた最初の年、家に戻って来て最初に創った歌は、英文科を選択した1回生の若造みたいな出来だった。その歌ではSamuel Beckttに触れていたと記憶しているよ。それから自分の部屋を出たら、親父に捉まり、僕が農場の仕事を継ぐべきだったというお説教を聞かされてしまいそうになった。だから僕はさっさと部屋に回れ右してこの曲を書いた。」
ハードなドライヴィングにブラックミュージックのファンキーさとスティッキィさを付け加えた、俗に云う“ストーンズ・ナンバー”の一種と見てよい。R&Bロックの小粋な面ではなく、よりプライマリーな荒っぽさを主張させている曲。近年は打ち込みブラックコンテンポラリーとラップによって絶滅しているナンバーだが、そもそもこういった曲はブルーアイドな白人のバンドが得意としているので、復刻があるとすればMillerのような白人ルーツロッカーに頼るしかないとは思っている。
これまたオールディズとまでは云わないが、かなり古臭いシンプルなロックンロールを思わせるナンバーだ。当然3分間以内に収まるコンパクトなトラックでもある。
●#5『Second Chance』
(不適切な表現が多いので割愛)
A面である「Upside」の5曲のロックトラックスの中で、唯一Millerの現代的なポップセンスが活用されたナンバーだ。
とはいえ、現代的な面が突出し過ぎてオルタナティヴの湿地に片足を突っ込んでしまっていた前作のそっち系曲とは異なり、実にバランス良のよい2分間ポップスとなっている点を取り上げておきたい。
寧ろ、Matthew Stweetの短い全盛期、Adam Schimittや偉大なるワンパターン・パワーポッパーなTommy Keeneの極上なポップフィーリング等と所属を同じくにする曲だと思う。
他の曲ほどには暑苦しくロックを転がしてはいないが、反して受け取りやすさは一番な柔らかさのあるPop/Rockだと思うのだ。
●#6『Chill,Relax,Now』
「Booker T. JonesとNeil Youngの誕生日は同じ日。その日に丁度この曲を録音した。何となくツイているように思っているね。」
R&Bライクなオルガンが印象的で且つ即興的なナンバー。しかも殆どがインプロヴィゼーションのバトルに近い。いってみれば、インストゥルメンタル曲に少しヴォーカルが入る形の曲である。インストバンドが楽器のひとつとしてサンプリングヴォイスを活用する事は多々あるが、この曲もそれに近い。
何せ、ヴォーカルは「Chill」「Relax」「Now」のみだから。
この黒っぽさは、「Upside」に共通する事項だが、Millerが念頭に置いているのはRolling Stonesを始めとする60年代のR&Bロックなのは間違いない。
が、この曲に関して言えば、Greatful Deadのライヴのノリをそのまま持ち込んだ感が強い。
◆全体のクオリティは高いけど、ややインパクトに欠ける「Downside」
インナースリーヴでは“Another Side”を冠されている「Downside」。
アルバムジャケットが示唆するように、全体がアクースティックに傾斜したアレンジの曲が集中している。
また、マンドリン等を表に出してカントリー・ロックへの相変わらずな歩み寄りを見せているパートでもあったりする。
こちらをアナログのB面として考え、A-Sideと比較した場合、その芸術性というか音に顕われる渋みと深みは明らかに「Downside」の方に軍配が上がるだろう。
まあ、アクースティックを押し出した繊細な感覚が、意識してチープで剛力で締め上げた前半のロックサイドよりも深みが出るのは当然の帰結といえばそれまでだ。また、Millerが「Upside」と「Downside」のコントラストを強化する為、敢えてロックサイドを単純且つ単調にしていると筆者は見ているので、こちらのナチュラルサウンドを引き立たせる事には成功していると思う。
が、ロック好きな筆者にとっては、後半でいきなりペースダウンしてテンションが落ちてしまったというマイナスな感覚が先行してしまう。
シンガーソングライターとしての内省的な顔。
カントリーやブルーグラスを聴いて成長してきたScott Millerのバックボーン。
こういった要素は解り易過ぎる程に表現されている。
デジタルメディア全盛の時代に、逆行するかのような擬似アナログ構成を採った冒険は評価すべきだ。だが、プレイヤーから一度取り外して裏返し、ターンテーブルに乗せ換えるという作業の必要が無い為、どうしても前半と後半のテンションの違いが際立つ。
最近の主流はアルバムによってエレクトリックなロックサウンドに纏めたり、アクースティックなアルバムにするという、アルバム毎でのアレンジ変更だ。
単調とまで言い切らないが、やや構成上ミスったのではないかとは考えている。
やはり「Upside」の#3『The Way』のように緩急織り交ぜたアルバム構築の方が適切だったと思う。意識して「Up」「Down」を分割すると、それぞれ両端に特化し過ぎて似たような曲が並んでしまう。または並んで見えてしまう危険性があると思っているが、このアルバムはまさにそのネガティヴな部分を幾らか内包しており、それで随分損をしていると思うのだ。
しかし、繰り返しとなるが1曲それぞれを聴くとかなりの出来なのだ。
●#7『Amtrak Crescent』
「僕は家でダラダラしていると、しきりに旅に出たくなる。で、旅を始めてしまうと、今度は家に帰りたくなるんだな。」
前作にもThe Commonwealthとして参加していたTim O'Brienがマンドリンを奏でる。サイドが変わってから、いきなりにブルーグラスなトラディショナルさを持ち込むナンバー。転換点に置く曲としては適切だ。
といってもベタベタではない。それなりにカントリー風味がある程度だ。
曲調はポップで明るい。けれど、歌詞自体は相当に重い。
人生に失敗した連中だけが使用するAmtrak(=大陸横断鉄道もその一部である、米国を走る長距離列車の事。)のクレセント(=三日月)号について唄っている。
こういったうらぶれた雰囲気をカラリと唄えるのがカントリーやブルーグラスの特権だ。
曲調としてはテンポは速い。アレンジがアクースティック中心な為、こちらのサイドに収録されたのだろう。
●#8『Angels Dwell』
「僕にはこの歌を歌う“歌姫(エンジェル)”として、Patty Griffin以外に素晴らしい人材を思い浮かべる事ができないなあ。」
実にしっとりとして、浪漫を感じる極上のローファイ・バラード。
後半の「Downside」のコアを形成する名曲だろう。フェンダー・ローズピアノのやや曇りが掛かったような音色が独特の寂寞感を演出している。
Patty Griffinのヴォーカルとのコラボレーションもアンバランスなようで良く似合っている。
●#9『Ciderville Saturday Night』
「Tim O’Brienを#7『Amtrak Crescent』のレコーディングのために顔を見せた時、僕はこの曲を彼と吹き込む事に決めた。僕はこの曲の大体を吹聴していたけど、彼は一度もこの曲を聴いた事がなかったので、かなりレコーディングにはビハインドがあった筈だったんだけど。でも5分と経たずに、彼は完璧に演奏してしまった。僕のケツに火がついてしまったよ。未だにその時のショックが残ってるね。」
ScottのアクースティックギターとTimのマンドリンのデュオスタイルの、モロにグラス的なナンバー。それ以外にはコメントが付けられない。途中で転調し、カントリーなワルツになる流れなぞ完全に田舎ナンバーだ。
●#10『I’ve Got A Plan』
「この曲は本当に何処にも行く宛てがない。でも僕がこの曲を書いた時も何処にも行く場所が無かったけど。」
ラップスティールを加え、かなりエレクトリックな雰囲気になっているナンバーで、相当土臭いスロートラックに必須な安定感がある。こういったスライドな曲をもう少し増やしてアルバム後半を骨太にしても良かったと思う。
●#11『Red Ball Express』
「第二次世界大戦を戦い抜いた世代はかなりの犠牲を強いられている。生命そのものが犠牲になってしまった人もいれば、若さを失ってしまった人もいる。」
前作では南北戦争や独立戦争をテーマにしていたScottだが、この歌は欧州戦線に出征した兵士の心情と状況を歌っている。アコーディオンとギターのみのかなり欧州的な悲哀が感じられるメロディで仕上げている。曲そのものは印象的ではないが、歌詞とその場面にシンクロするようなラインがMillerのインテリゲンチャを示しているように思える。
●#12『For Jack Tymon』
「どんな世代でも、以前の流行や決まりを頭から叩き出さないと駄目だよね。進歩できないし。でもゴメン、僕は古いファッションとごちゃまぜにしてる。」
まさに「Downside」を象徴するような弾き語りソロナンバー。とことんアクースティックでフォーキィ。
タイトルに沿ったラストであるとは思うけど、少し淡白過ぎるきらいがある。やはりアクースティックサイドにする意図に縛られ過ぎてしまっているかもしれない。
◆概ね、良好で聴き易いアルバムだけれども・・・
アルバムとしては、より手堅くオーソドックスな出来になっており、オルタナ性が混入していた前作よりも潔い方向に向かっているとは思う。
ただ、アクというかクセが減ったため、与えるインパクトは減少するかもしれないが。
カントリーやカントリーロックの堅いアルバムをリリースするイメージしかないSugar Hillのアーティストの中ではかなり異色な存在になっていると思う。
前作のかなり現代的なロックを取り入れたアルバムの次も、手堅い系の同レーベルからアルバムが出るとは予想はしていなかった。
それだけ前作が評価されたという事なのだろう。
問題はやや個性が分散してしまったこの3枚目のソロ(スタジオ盤としては2枚目)をどう評価するかに掛かっているだろう。
筆者としては「Upside」だけでそれなりに元は取れているし、シンガーソングライターやグラスの担い手としてより、ロックンロール・ガイとしてのScottを望んでいるので、次もオルタナに走る事無く、ロックアルバムを目指して欲しいと考えている。 (2003.10.10)

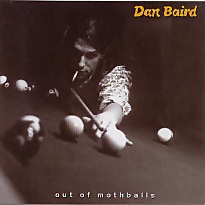 Out Of Mathballs / Dan Baird (2003)
Out Of Mathballs / Dan Baird (2003)