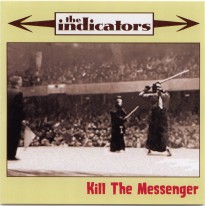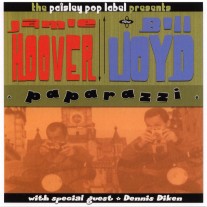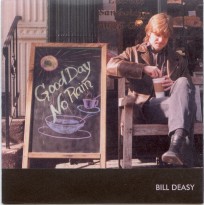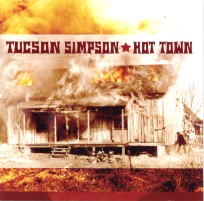60 Cycle Hum / Steel Rodeo (2003)
60 Cycle Hum / Steel Rodeo (2003)
Roots ★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Southern&Boogie ★★☆ Official Site
◆粗末な外装、しかし中身は
実にシンプルな装飾である。
本邦で古典ロックのリイシュー版に使われる事も多い紙ジャケットとは異なる、本当の紙でCDを挟んだだけのケースである。通常、メジャーや中堅ミュージシャンがプロモーションとして配布する無料シングルCD等に使用されることが多い、LP式の収録をされる紙ケースである。
しかも、CDのレーベル面にバンドのメンバーが並べて書かれているという省エネ方式。(笑)
以前の作品に付随していたインナーもブックレットも無しだ。
筆者註 : Steel Rodeo名義1作目となる「The King's Highway」には歌詞カード付のブックレットが(要するに普通のCDと同じ)有り、CDで買い逃した前作「Treats」にもブックレットが付いていた様子。こちらは現在確認中。2003年に再プレスされたCD-Rではなく、プレスCDでの「Treats」がトレーディングで手に入りそうなので、情報を得次第、更新する予定。
以前、Gathering FieldのリーダーBill Deasyがソロ作を放った時、フロントジャケットにまで歌詞を記すと言う、省スペースな技を披露しているが、今回のSteel Rodeoの外装は最もシンプルなものになっている。悪く言えば、実に安っぽい外身だ。
しかし、10曲で38分弱と言うアナログ時代並みのヴォリュームでプレスされた「60 Cycle Hum」の内容自体は実に濃厚でタップリと味わえるコクが詰まっている。
これ程、中身と外装のギャップのある作品も珍しいだろう。
残念ながら、1994年に発売されている、バンドのリーダーにしてソングライターであるEddie Sevilleのソロ名義作品の「Steel Rodeo」のみ筆者も未聴だ。が、それ以外のスタジオ作2枚と比較すると、最新作「60 Cycle Hum」はレヴェルが一段上にある最高傑作だと考えている。
とはいえ、「Treats」も「The King’s Highway」も実に良質なロックンロールアルバムであり、凡百なメジャーのMTVトラッシュやモダンソニック何ぞは比べ物にならない良作であるのだ。
特にサウンドの重ね方とメロディで大きな進歩を見せている「Treats」とメロディ的には互角なのだが、全体として聴くと更にロックンロールの純度が上がっていると感じれる。
良作を超えた傑作。
ワンセンテンスで表現すれば、「60 Cycle Hum」はそんなアルバムである。
この内容に触れれば、チープな外装なぞ誰もきに留めなくなる事請け合いだ。
◆Ryan Adamsの「Rock N Roll」が児戯で紛い物にしか見えなくなる、本当のロックアルバム
2003年、日本のメディアがこぞって持ち上げているRyan Adamsの「Rock N Roll」。
最初に断っておくが、筆者はこれをロックンロールなどとタイトルしたRyanは豆腐の角に頭ぶつけて(以下略)と声を大にして言いたい。
まあ、北欧爆走パンクと英国ブリットポップのノイズサウンドを改悪した音がロックンロールと捉えれるなら、それはその時点でそのリスナーのロックンロールになるだろう。
このアルバムを購入したリスナーを貶めるつもりは毛頭ないが、こういったアルバムしか選択出来ない世界の狭さには同情を禁じえない。
だがしかし、筆者はこのアルバムに「Rock N Roll」というあざといタイトルを付けたRyanは、インドの山奥でダイ○・ダッ▲に修行を受けて、空に掛けた夢でも追ってくる事を強烈にお薦めしたい。
これ以外のタイトルならば、特に突っ込む事はせず、単なる駄作と認定するのみに留めていただろうけど。
嘗て、ロジスティクス−兵站という概念を無視して、自国の100倍の国力を持つ大国に喧嘩を売った帝国が存在していた。その陸軍ではこのようなざれ歌が流行していた。
「輜重部隊(=補給部隊)が兵隊なら、蝶も蜻蛉も兵のうち。」
「輜重部隊が兵隊なら、電信柱に花が咲く。」
そんな戯言で総力戦に突入した結果、70%の戦死者が餓死と衰弱死という燦々たる敗戦に終わっている。
と話題が宇宙的にズレてしまったが、極個人的に、正対した皮肉を込めて筆者は言いたい。
「Ryanの『Rock N Roll』がロックならば、蝶も蜻蛉もロックンロール。」
「Ryanの『Rock N Roll』がロックならば、電信柱に金が成る。」
要するに、普通にアメリカンロックが聴けるならという前提に於いて、一度「60 Cycle Hum」を聴いてしまえば、Ryan Adamsのロックンロール?
( ゚д゚)ハァ?( ゚д゚)ハァ?( ゚д゚)ハァ?( ゚д゚)ハァ?( ゚д゚)ハァ?( ゚д゚)ハァ?( ゚д゚)ハァ?
となる事請け合いだ。
これぞ、Real Rock n' Rollというべき。安易な英国パンクや北欧パンクの取り込みに走った作品とは、深みも重みもメロディも精神も全てに於いて別次元にあるアルバムと断言する。
このアルバムを聴いて、Ryanのアルバムを最初、「まあまあ、ロックだな。」と肯定した我の感性の貧相さを思い知らされた。
その意味でも、「60 Cycle Hum」の本物さには感激と感謝を捧げたい。
◆It’s Open All NIght Aka The Georgia Satellites For 21st Century
前作「Treats」のB面(当初、カセットテープしか所持していなかったので)の高潮のように存在感を持って押し寄せるロック・アタックに圧倒されたが、その流れを凌駕するロック魂が本作で燃えている。
特に、#3『I Believe Get Home』のメリハリの効いたダイナミックな展開は、まさに21世紀のThe Georgia Satellitesとしか呼び名を与えられない。
しかも、カントリーにやや傾いた「In The Sulvation And Tin」やハードロックを取り入れざるを得なかった「Georgia Satellites」ではなく、最もロックンロールのバランスが取れた2作目「Open All Night」に近い王道ロックの風格まで本作は持ち合わせている。
『21世紀の「Open All Night」@ジョージア・サテライツ』を具現している筆頭格となるのが、#3『I Better Get Home』。
“ジョージア州衛星”の名曲である『Keep Your Hands To Myself』を彷彿とさせる野暮ったいヴォーカルとスライド弦のプレリュードが泥亀のようにのたくる。かなりやる気が欠如したようなダスティでトラディショナルなスロー展開でジワジワと間を引っ張る。
さあ、来るぞ、来るぞ、と期待を持たせて、裏切る事無く一気にアクセル全開となるロックンロールの大津波。そこからの展開はまさにサテライツ版『Don't Pass Me By』そのもの。
バタバタとしかし、引き締まって鳴るドラム。ブンブンと唸るベースライン。スライドとエレキギターのバトル。
決してEddie Sevilleの奔放なヴォーカルを邪魔する事無く、しかしコーラスに明るいアクセントをつける、Sallyul Sianniの女性コーラス。
メロディ的にかなり整ってきて素晴らしいアメリカン・ルーツロックアルバムとなっている「Treats」でのメロディの良質さをそのまま継承し、更に馬力を加えたナンバーには圧巻。
しかし、その直前の2曲、特に#2『Carol Ann』のロック大攻勢も負けず劣らず大迫力。
最初に、アルバムの前半の山場を形成しているのは#1『Shot Of Love』から#3『I Believe Get Home』に間違いない。
この「60 Cycle Hum」は10曲のうち8曲が一切手を加えず、ライヴレコーディングの一発録りとなっている。
オーヴァーダブもリミックスも加えていないとステイトされているが、その迫力が最もグングンと伝わってくるナンバーが、#2『Carol Ann』である。
軽いタイミング合わせを兼ねた掛け声が入り、サウンドチェックの為のシャキシャキしたドラミングで加速を終わらせ、ガツンと息もつかせないストレートロックに突入。
特に、オープニングソロから活躍するバタバタと暴れるスネアドラムが滅茶苦茶格好良い。
現在のメジャーで幅を利かせている金属質で耳の痛くなるラウドなギター(というよりも瘰独活と呼びたい。病にかかった独活)とは異なった、ズッシリと存在感のあるスライディッシュなギターアンサンブル。
ソロパートでの崩れたスライドソロは鳥肌モノだ。
この痛快な速度とポップな流れは、Terry Anderson作、演奏お披露目The Georgia Satellitesの名曲『Battle Ship Chain』を連想させずにはいられない。
ここでも、Sallyulのバックヴォーカルがとても適切なサポートをしている。目立たないオルガンも演奏に膨らみを与えるのに寄与している。
ドラムといえば、George HarrisonのNo.1ヒット『Got My Mind Set On You』を思わせるような乾湿なドラムリフで始まる#5『Long Way Out』のリフが最高に気持良い。
ドライヴしまくるラフでフックのあるギターの音色もグルーヴィだが、それ以上にサウンドの骨子を支えるドラムラインが快感を覚える位にパンチ力がある。
メロディとしても軽快でありつつもハードでアーシーな、ルーツロックとしての要件は全て満たした佳曲である。サテライツの『Sheila』に通じる所のあるゴキゲンな縦割りロックナンバーだ。
そして、ロック・タイダル・ウェイヴの幕開けとなる、オープニングの#1『Shot Of Love』。
このトラックで驚いたのは、リードヴォーカルであるEddie Sevilleの声の成長である。「Treats」でも何となくDan Bairdに声が似てきたなあ、と感じたが、まだまだ良くも悪くも青臭さの残るヴォーカルだったし、微笑ましい不器用さも目立っていた。
しかし、7年を経て発売された「60 Cycle Hum」では完全に“出来上がった”ヴォーカリストに成長していた。
その声の持つ張りといい、得体の知れない伸びといい、粘つくようでいて、それでいて切れの良好なシャウトは、もうモロにDan Bairdだ。
曲としては、ストリップ・ダウンしたロックンロールとしか云い様がない。Rod Stewartの初期やFaces、そして1980年代以前のあまり黒くないRolling Stonesのナンバーをやや地面に近づけて再現したような感じ。
アクセル全開にせず、来るべきオーヴァー・テイクポイントを待ってアクセルとクラッチに足を乗せている。このような爆発寸前で押さえている熱気が伝わってくるようなロックチューンだ。
◆よりサザンに、よりアーシーに、そしてルーツに忠実に
前半3曲の圧倒的なパワーに幻惑されがちだけれど、本作ではこれまでにないくらいミディアムからスローテンポに近い曲の割合が増えているのだ。
元来、カントリー・ミュージックへの愛着を感じずにはいられないバンドだったが、Eddie Sevilleが大本はハードロック畑のミュージシャンと交流が多く、仕事もそちらの裏方が多かった事から、直接的なカントリーへの向き合いはあまり見えていなかったバンドだった。名前がSteel Rodeoと、カントリー的なネーミングをされているにも拘わらずだ。
しかし、#10のタイトル曲『60 Cycle Hum』は完全に南部カントリーの影響が表出しているナンバーだ。
流石にペダルスティールを振り回す事まで突き進まないが、スライドギターをクネらせて、カントリーロックの雰囲気に全体を染めている。
控え目ながら高音域を駆使したピアノも挿入され、レイドバックしたアレンジに華を添えている。
ドが付くカントリーではないし、牧歌的なソフトナンバーという見方の方が適切かもしれないが、他のナンバーよりも存在を主張しているShallyulの女性コーラスはカントリー・ポップの特性を付与するのに一役買っている。
更に、#6『Ghost Train』も非常にサザン・カントリーの空気が支配するスローナンバーである。
タイトルナンバー程には、グラスルーツ化していないとはいえ、哀愁を込めたスライドギターのソロには濃厚なカントリーサイドの主張が感じられる。
冒頭のギターリフはモロにカントリーロック風だ。
全体的にライヴレコーディングスタイルの影響からか、ピアノの活躍が目立たなくなっているのが本作の個人的に残念な所だが、このトラディショナル風味のスローロックでもピアノの音は控え目。間歇的に美しさという要素を際立たせる為に挿入されている使われ方だと思う。
それにしても、こういったジックリと聴かせるタイプのレイドバックソングを豊かに歌えるようになっているEddieの声量と技量には頭が下がる。
ここに挙げた2曲を始め、全体的にルーツサウンドへの回帰路線が強くなり、「The King's Highway」でのパワーロックや「Treats」のより中庸的なルーツロックンロールから濃いベクトルへと以降しつつあるにも拘わらず、より一層ロックンロールを鮮烈に感じる事が出来るのは、Eddie Sevilleのヴォーカルが、その説得力を増しているからだろう。
◆カントリーというよりもAmericanaやHeartland Rock
カントリーの背景を感じるが、それよりもAmericanaというかSouthernスタイル−HeartlandやAORルーツソングとして絶妙のバランスを誇るのが、後半の山場を形成している#8『All This Time』と#9『Unshaken Faith』だ。
非常にハートウォーミングなハモンドオルガンを主格にしてマッタリと流れる、#8『All This Time』。ダウン・トゥ・アースなアレンジは基本に据えつつも、リッチなサウンドプロダクションで肉付けした極上のアダルト・ロック。
明記されてはいないが、スタジオライヴ形式の一発録音をされなかった2曲は、恐らくこの2連続トラックだと想像している。他のシンプルにストリップダウンしたナンバーと比較すると、「Treats」で確立した丁寧に練り上げたアレンジを覚えてしまうからだ。
ゴスペルタッチが反映されているナンバーでもあり、Shallyulのコーラスも目立つ位置まで押し上げられている。新しいポップセンスと古典的な南部サウンドが融合した、まさにAmericana Rockと分類される曲だ。
この#8は、時代が20年くらい前ならば、まずチャート入りしてスマッシュヒットしてもおかしくない良質なメロウ・ロック。どちらかというとロックンロール一直線だったSteel RodeoとEddie Sevilleだが、ここに成長が伺える。
しかし、#8以上に正統派のアメリカン・ロック、もはやArena Roots Rockと呼びたくなる最高のロッカバラードが#9『Unshaken Faith』である。
繊細なアクースティック弦のリフから、Dan BairdそのものなEddieのヴィヴィッド・ヴォイスが合流し、爽やかなロックンロールリズムに舞い上がっていく流れは、Top40ナンバーの風格がある。
12弦ギターの済んだ音色と、ハモンドB3の暖かい音が、パワフルな演奏に優しさと暖か味を加えてくれる。
もうBob SegerやBruce Springsteenのヒットナンバーと並べても遜色の無いアメリカン・ポップロックの優等生的な名曲だ。正直、ここまでお約束のアダルト・サウンドをSteel Rodeoが持ってくるとは思いもしなかった。
間違いなくバンドの名曲の1つとして取り上げるべきナンバーである。
独自の多様性を持ち始めたのは、「Treats」でも感じていたが、より深い個別カテゴリーに踏み込みつつも、中庸感覚をキープしている点は只者ではない。
◆色々と手を伸ばし始めたかな
引き出しの数が増えたのは、#4『And Day Now』で顕著に提示されている。
ジャズスタイルのピアノから、粘っこくジャンプ・ブルースする#4は、ハードドライヴなロックから個々のルーツ要素に特化した曲をレパートリーに入れ始めた事が分かる。
ブルージーなピアノと、ブギウギなシェイキングは、リズムボックスが持ち込まれる以前のブラック・ロックそのもので、ラスト近辺では南部ブラックを濃縮したようなブルースハープまで登場する。
R&Bクラッシックを思わせる、ちょっと風変わりなナンバーだ。
#7『Two Hearts Collide』もブルースを感じさせるハードドライヴなナンバーで、Steel Rodeoのアイデンティティたるロックバンドとしては欠かせないタイプだ。
しかし、そのリズムにはドラムループっぽいトリミングにモダンロックの要素がチラリと見えたり、東海岸バンドに流れる都会的な硬質のセンスが見られ、ブルージーで粘っこい音が支配しているのにも拘わらず、モダンロック風味が同居しているように思える。
筆者としてはあからさまに黒人ブルースに足を突っ込まれるよりは、こうやってロックの肌触りを残している方が好ましいが、ブルースロックに現代的なオルタナティヴ・ミュージックのセンスを加えてきたのは少々驚いている。
まあ、間違ってもRyan Adamsのようにはならないバンドだとは思うので、特段心配はしていない。
この#7にしてもワイルドでタフなだけでなく、ある程度整流出来る技量のあるロックバンドである事が見えるし、ロックナンバーとしてもこの力強さは好ましい限りだ。しかも、それなり以上にポップに仕上げている事だし。
◆7年振りの新譜となった「60 Cycle Hum」
残念ながら、Eddie Seville名義の「The Steel Rodeo」のみ所持していないので、この初フルレングスアルバムに付いては語れないが、Eddieがアルバムを発表する1993年以前から、Eddieはソングライターとして活動を続けている。
1980年代後半から既にソングライターとしてレコーディングスタッフの裏方として、ハードロック系のバンドに連なる人たちと親交を結んでいる。
この事実から想像可能なように、元来ハードロック系のミュージシャンであり、Peter Frampton BandのキーボーディストだったFrank Carilloと組んでレコーディングを地道に行っていたらしい。1990年にはアナログEPの「Long Way Home/Savannahs Song」を自主レーベルから発売している。
また、Blue Oyster Cult、Playput、Danger DangerといったHR/HMバンドのプロデューサーで知られるPaul Orofino、同じくBlue Oyster CultのギタリストDanny Miranda、Bad CompanyのドラマーであるSimon Kirke
、KISSのギタリストだったBruce Kulick。という完全なHR/HMのスタッフとして働いてきている。
が、ハードロックとルーツロックは遠いようで近い音楽でもあり、Eddieのハードでソリッドなロックンロールをベースにした基礎が、ルーツロックの極上品として発展した事は、それ程不思議には思えない。
ちなみに、彼のソロ活動時代に作られ、未発表となっているナンバーの幾つかがここでストリーミング可能だ。
「The Steel Rodeo」も扱いとしてはソロではなくバンドらしいので、Steel Rodeoとしての活動は1990年代前半に始まっている。
そして、1995年に「The King's Highway」。同95年にブートレグ扱いの「Live At The Bitter End」を。翌年の1996年に3作目のスタジオ盤「Treats」を、とここまでは非常にハイペースでアルバムを出してきたのだが、この後プッツリと新譜が出なくなる。
その間、何をしていたのかは正確には不明だが、筆者は1999年にニュージャージー州でSteel Rodeoのギグを観ている。この時に#2『Carol Ann』や3『I Better Get Home』を確かに聴いてノリノリになった事も覚えているので、本作のマテリアルは全て新しい曲でもないことは個人的に保証する。
この時に「Treats」のカセットテープと「The King's Highway」のCDを購入。「Live @ The Bitter End」をライヴ盤だからと買わなかった事を現在は少し後悔している。
どうやら、少々ペースを落として、コネティカット、ニュージャージー、ニューヨーク州といった東北部諸州にてライヴ活動はそれなりに行っていた様子だ。
Eddie自ら、
「オレ達は常にロードの電車道に乗っかっているロック野郎さ。ショウが開けるなら何処だって停車してやろうじゃないか。たとえ、それがクソッタレなテキサコのガソリンスタンドだっていいぜ。オレ達にとっちゃあ、歌こそ全て。イメージやトレンドを気にし始めたら、もうそれは単なるファッションショーだからね。」
とロード至上なコメントを記している。まあ、この手のバーバンドがライヴ命であるのは一回でもコンサートを観れば明らかだけども。
メンバーはソングライターにしてリードヴォーカルのEddie Sevilleを中心にした5ピース。ブルースハープとギターも担当している。
一度バンドから抜けて「Treats」ではクレジットされていなかったドラマーのKevin Marronが復活。
パーカッション兼というよりもバックヴォーカル専任の感が強い紅一点のSallyul Sianniは活動当初から残っている唯一のメンバー。
今回はエグセクティヴ・プロデューサーともなったベーシストのJunior Cainが単にJuniorと変名して前作から継続参加している。
リードギタリストは毎回変わるが、今回はBilly Kotsaftisという人がメンバーになっている。
しかし、正直な所、まさか7年ぶりに新録音のアルバムが出るとは思わなかった。
このアルバムと同時にロットアップとなっていた「Treats」もCD-Rで再プレスされ発売され始め、再びSteel Rodeoとしての活動が再燃した感じが見て取れる。
こうなるとまた以前のような兆速サイクルでアルバムを出すような活動が始まるのではないかと、密かに期待を始めてしまっている。
野生の馬に乗るロデオ・ドライヴァーではなく、鋼鉄のロデオ乗りが、21世紀になっていよいよ内燃機関に再び火を入れたと希望せずにはいられないくらい、格好の良いリアル・アメリカン・ルーツロックである。
The Georgia Satellitesが好きならば、このアルバムはマストだ。
また、Rod Stewart初期やFaces等にも思い入れのある方は、「Treats」もこの際だから一緒に買う事をお薦めしておこう。2枚共に損は絶対にしない出来だ。
筆者的2003年のベスト5には確実に喰い込むマスター・ピースである。 (2004.2.7.)
P.S.現在、「The Steel Rodeo」のみデータが手元に無い(ライヴ会場でも売ってなかった)のが非常に悔しい。
どなたか情報のある方は是非筆者までご連絡を。お礼は致します。
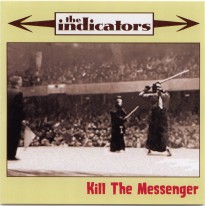 Kill The Messenger / The Indicators (2003)
Kill The Messenger / The Indicators (2003)
Roots ★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★☆
Southern&Garage ★★☆ Official Site
◆ルーツロックバンドがガレージサウンドやパンクに転ぶ事はあれど
逆に、パンクバンドやガレージバンドが、ルーツロックに転向する事は殆ど無い。
ガレージロックのバンド−例えばThe Replacementsの後期型のような存在−で、幾許かルーツロックに色気を出していたり、若干アーシーなバンドが本格的なルーツサウンドを創造する事もそうは多くない。
普通は、アメリカン・ルーツも感じられるオルタナティヴやパンクロックという程度に落ち着く事になるのだ。
この場合、そういったフュージョンサウンドを謳うバンドへの評価は、どれだけルーツ度合いがオルタナティヴのアクを覆えるかに依存する。(無論、筆者基準に於いてだ。)
大概に於いては、原型がガレージロックであり、ノイジーなパンクバンドであったユニットでは、どう足掻いても「ルーツ」っぽいオルタナティヴになるのが関の山だ。これはこれで、それなりにユニークな音を創造する場合もあるが、大抵は筆者の好みには完全に合致しない。
ところが、完全にハードエッジなカレッジスタイルで登場したバンドが、いきなりルーツ系のバンドに衣替えしたという稀なケースが2003年に出現した。
これが、The Indicatorsの2作目となる「Kill The Messenger」である。
俄かには信じられないくらい、ルーツロックバンドとして太鼓判を捺せるサウンドを創り上げてきたのには正直驚きを隠せないでいる。
それくらい1stアルバムとは異なった種類の音楽性を打ち出してきたのである。
◆完全同調ではないが、変遷はSoul Asylumに似ているかも
『Runaway Train』の大ヒットにて、一躍カレッジチャートのいちバンドからナショナルワイドなロックバンドに駆け上ったSoul Asylum。(でも絶対にこのヒット曲はライヴでは演奏しない。どんだけアンコールしても無駄。)
これまでの所、随分間が開いてしまっているが最新作である「Candy From A Stranger」と、インディ時代の5枚のアルバム、そして一部の曲を除いた「Grave Dancers Union」の頃までの音楽性を比較してみよう。唯ひたすらにノイジーなカレッジガレージだった初期作風と、「Let Your Dim Light Shine」以降のポップでアメリカン・ルーツを意識したメロディ中心の音楽との格差に驚くだろう。
殊に「Candy From A Stranger」でのポップ加減は、もう初期のバンドとは別物と考えた方が良いくらいだ。
都合5年以上も新作を発表していない為、完全なガレージパンクで幕を開けたSoul Asylumが完全なルーツバンドに昇華したかは結論を下すに至らない。
だがしかし、初期は雑音と変わらないくらい耳障りな音を捏ねくり廻していたSoul Asylumが、『Runaway Train』という、あわやトップヒットにならないのに、年間No.1シングルになり掛けたルーツロックのマイルストーンを拵えたのは、かなりの変質があったと見て良い。
その1曲で元に戻るのではなく、以降の2枚のオリジナル盤もガレージサウンドに戻る事が無かった事実も評価対象とすべきだ。
他の例としては、1980年代末から90年代初頭のR.E.M.も、カレッジ・オルタナティヴからある種の変異を遂げたバンドとして書き出しておく。
周知の事実だが、R.E.M.がそれまでのカレッジチャート専用−とはいえ、時代がカレッジロックやオルタナティヴを認識し始めた境目に当たったので、メジャーでも受け入れられていたが−のオルタナノイズ+ちょっとAlt-Countryっぽさがなくも無いという音楽から、レイドバックしたアメリカン・サウンドに振れたのが、彼ら自身の云う非ロック2連作である。
「Out Of Time」と「Automatic For The People」のアクースティック音を強調したアルバムでは、それまで申し訳程度にも欠けていたメロディアスでアーシーなサウンドが活用されていた。
バンジョーやマンドリン、足踏みオルガンといった、オルタナティヴ・ヘヴィネスには全く親和性の無いインストゥルメンタルを多用したこの2枚は、物凄いセールスを記録し、一時代を築いた。(もっとも、成功の理由として、結局R.E.M.がオルタナティヴやカレッジロックバンドの枠を抜けられなかったコンテンポラリーさが一番の要因だろう。皮肉な話しではあるけれども。)
一般的に変遷を知り易いメジャーバンド2つを挙げてみたが、インディやマイナー・シーンには、こうやって脱オルタナティヴやガレージするのではなく、最初からルーツサウンドとオルタナティヴ・ロックの両方を指向しているグループが多数存在する。
どちらかというと、名前の意義とは全く裏腹に、どのようなアメリカン・ルーツサウンドにも親和性も混和性も欠如するというオルタナティヴではなく、よりポップでメロディを重視したパンクサウンド。そして、ロックンロールの発電装置としては良質であるガレージサウンドを基礎としてルーツサウンドと融合する場合の方が多く感じるし、ある程度以上の成功を収める可能性も高い。
が、The Indicatorsはそういったインターミディエィトな路線をハナから指向していたとは考え難い。前述のように、処女作は完全にガレージパンクでありカレッジハードなロックサウンドだったからだ。(後述するが、これはこれで意外ではあったけど。)
メロディとしてはパンクの正統性を継承したのか、それなり以上に親しみ易かった。が、それとてメジャーで売れる為の道を選択しているGreen DayやA New Found GrolyといったEmo PopやPunk Popなポップだけならポップは突出しているという音世界よりも、カレッジチャート向きなノイジーでクランチーなプロダクションが目立っていた次第だ。
ややタイプは異なるが、NOFXやBlink182、初期のWeezer。Guided By Voiceの初期作風のポップさも感じられるかな、という所であった。
更に近いのが、パンクロックバンドのSuperdrugという感じだろう。
こういったバンドが、あのAlt-Countryの第一人者的な地位を占める雑誌のNo Depressionに紹介されるようになったのが、本作「Kill The Messenger」を発売したからに他ならないのだ。
◆しかし、ルーツロックの下地は十分に存在してた
The Indicatorsのリーダー且つソングライターであるMichael Goldmanには長期に渡るAlt-Countryバンドでの活動経験がある。
それは、The Estradasというバンドへの参加である。テネシー州のノックスヴィルという街で1994年に、The Estradasは結成されている。中心となったのは1980年代からカントリーロックやアクースティックバンドを率いてノックスヴィルで活動していたBob McCluskey。Michaelはリードギターとバックヴォーカルを担当していたので、Michaelの嗜好がバンドのサウンドに即反映していたとは一概には言えない。
また、Michaelはお隣の州であるジョージア州都アトランタを拠点に活動しており、The Estradasに専念していたのでもなかったりする。実際に、Estradasは開店休業状態となり、Michaelは自分のリーダーバンドであるThe Indicatorsを1998年に立ち上げているのだ。
しかし、2000年にBobとMichaelは再びコンビを組んで、リズムセクションを雇い入れた後、The Estradasの名前で「Last Summer’s Folding Chair」というルーツポップやAlt-Countryと直に向き合ったサウンドを詰めたアルバムを発表している。
その翌年にガレージロックとハードパンクサウンドに狙いを絞ったIndicatorsのデビュー作「Beauty Is A Whore」をリリース。
Michael自身が舵取りをするプロジェクトでは、てっきりカレッジ向けハードオルタナティヴが主体。つまりMichael Goldmanの本来の嗜好はガレージパンクと思わざるを得ない材料を提供。
EstradasのソングライターもリードシンガーもBobだった事を考えると、The Indicatorsの顔役としてのミュージシャンとなったMichaelにルーツサウンドを求める事は少々疑問に感じたものだ。古巣のバンドから独立したバンドでは2番手だったミュージシャンが、旧母体の方向とは全然違った音を作成する事例は多いし。
しかし、このEstradasを超越したパワールーツロックの出来栄えを鑑みると、果たしてMichaelの本質はガレージサウンドなのかルーツロックにあるのか非常に迷う所である。
筆者が愚考するに、Bob McCluskeyというルーツ系のミュージシャンとチームを結成するくらいの人物だから、Michael Goldmanにはルーツロックやオールドタイムロックンロールへの愛着は並々ならぬものがあるだろう。しかし、ひとたび自分がリーダーとなってバンドを率いる節になって、Bob主導のEstradasの二番煎じを避ける為、敢えてガレージパンクを際立たせたラウドロックのアルバムを拵えたように感じる。
そして、そういった気負いが冷却した2年後に至り、漸く本当の趣味でアルバムメイキングが出来た。そのアウトプットが「Kill The Messenger」なのだろう。
でなければ、あれだけのカレッジハードから良質なルーツロック系のアルバムがワンクッションも置かずに生み出される事は簡単ではないだろうから。
原点回帰と呼んでしまうと途端に陳腐化してしまうが、まさにMichael Goldmanは「Kill The Messenger」にて原点に立ち返ったのだ。
しかし、他の良質なルーツ系ミュージシャンがそうであるように、Michaelのバックボーンは単なるカントリーやルーツサウンドに留まらない。その辺りに1作目でのパンク追求の姿勢に対する理由が見出せそうだ。
◆60年代サイケディリックバンド、Spritのカヴァーが表すガレージ風モダンロック
アルバム収録曲の14トラックのうち、唯一のカヴァーソングが#8『I Got A Line On You』である。オリジナルは1960年代後半に西海岸で活躍したロックバンド、Spritが1969年に放った「Family That Plays Together」からカットされたヒットシングル。
ハードで粘っこい、サイケディリック時代独特のロックナンバーだ。これをオリジナルよりもバラバラした粗さで叩きまくっている。そのアレンジがパンキッシュというと筆者的にはポジティヴで、ヘヴィロック的な粗雑さと言うとネガティヴになってしまうが、丁度その中間といった具合。
「Beauty Is A Whore」で猛威を振るったガレージサウンドの名残が伺えるトラックだ。
他のオリジナルソングの何れよりもガレージ風味を包括したナンバーがカヴァーソングと言うのは、本格的にルーツバンドへとシフトを始めた証と受け取りたい。
その他、処女作の雰囲気を残すトラックが幾つかある。
といってもガレージロック一辺倒という感じとも少々違う。
モダンロックとパンクロックの中間的な#7『Walkaround』。Superdrugとかに通じるパンク感覚と硬めなオルタナティヴ的ヴォーカルがガチガチしているけれど、メロディ的には素直だ。ダークな感じはしない。
勢いのあったWeezerの1stを思わせる、オルタナティヴ・ポップな#10『Satellite』。ソニックサウンド的な現代性を覗かせ、The Indicatorsがルーツロックに完全に填まり込んでない状態を表している。
他のルーツやアメリカンカントリーをベースとした曲と比較すると、変化を付ける為のアクセント作といった感が強いと思っている。
多彩を求める姿勢という点では、#12『Your Way』がユニークだ。
チープなシンセサイザーを張り巡らした、モダンーポップ的なアップビートを主流にしつつ、ギターソロでは結構クラシカルな重厚さを表現している。
パワーポップとルーツギターがコロコロと立場を変えて出現する2分少々のナンバー。ガレージロックというよりも、モダン・ルーツという枠に入れた方が適切なトラックかもしれない。
これらは全て、Michael Goldmanの手によるナンバーであり、新規加入したKen Mortonの曲は、良く言うともう少し統一感がある。
◆カンフル剤となった新ライター&ヴォーカリスト、Ken Morton
知る人ぞ知る、パワーポップのローカルバンドWonderlust。
数枚のアルバムをリリースして、2001年頃に解散してしまっている。そのメンバーだったギタリストでヴォーカリストのKen Mortonが「Beauty Is A Whore」をリリース直後、The Indicatorsに加わっている。
「Wonderlustが解散した後直ぐ、MichaelにIndicatorsでプレイしないかと誘われた。僕は正直気が進まなかった。だって自分には合わないバンドだと思ったからね。でも実はベストな場所だった。バッチリだね。」
「僕が加わった時、バンドのメンバーはヴォーカルとギターをもっと演奏に加えたい意向だった。僕は、もし参加するならリードギターとソングライティングも行いたいと申し出た。Michaelは全てを同意してくれた。それ以来、僕たちはお互いのベストな産物をバンドに持ち込むようにしている。」
ワントップから2頭リードになる事を嫌うフロントマンが多い中、MichaelがKenの立場を同格として扱っているのは、彼の度量の大きさだと思う。中途参加のメンバーが中心となる事でギクシャクしてしまう事も珍しくないのに、実に上手な2シンガー体制を築き上げたのはひとえにMichaelの人間性によるものだろう。
さて、そのKen Mortonだが、オリジナル13曲のうち、5曲を書いて、歌っている。
#2『Eye Spy』、#4『China Blue』、#9『I’m Gone』、#11『Ordinary Blues』、#14『Open Road』 の5トラック。
かなり作風の幅が広いMichaelのナンバーに比べると、Kenのナンバーはオーソドックスで安定感がある。
基本的にスライディッシュでライトブギーなロックナンバーである。スライドギターが活躍する余地が多いタイプの曲が多いのも特徴だろう。
Michaelのストレートなガレージ風ロックやPower Popなトラックと比較すると、よりブルースロックに近い率直さが目立つ、#2『Eye Spy』。しかし、オルガンが加わり、掠れたギター弦の音も手伝い、必要以上にハードになっていない。
ポップ度合いからすると、Michaelの華やかなセンスには一歩譲る感が否めないが、その分、南部フィーリングの剛直さが表出する部分がある。
モダンロックの軽薄な部分ではなく、スマートなセンスをサザンブギーに持ち込んでいる、パワーロックだ。
スタートのギターリフがアルバムでは最も分厚い#4『China Blue』。こちらはガレージサウンド的なパートが残留していた#2とは異なり、よりルーツロックなトラックになっている。
スピードハードになると思わせ置いて、適度にアクースティックな感覚を持ち込み、8ビートで流す落ち着き。
MichaelとKenのヴォーカルハーモニー。オルガンの挿入。そして、埃っぽいスライドギターのソロ。
実にジョージアのバンドらしいアメリカンロックだ。
#9『I’m Gone』では、更にレイドバックしたラフでダスティな感触がポップなメロディに合わせてのたくっている。潰れたように唸るスライド弦が実にブルージー。リズムはロッキンブルースだが、曲全体としてはオーソドックスなルーツロックとなっているポップセンスは素晴らしい。
レイドバックな雰囲気に優しさとクラシカルなR&Bロックのリズムが伺えるのが、#11『Ordinary Blues』。コーラス部分でのピアノの被せ方と指使いの細かいギターソロが、単調なリズムにアクセントを与え、退屈な曲にはしていない。
そして、殆どの曲が2分後半から3分台前半の長さというアルバムの中で、唯一5分を超える大作の#14『Open Road』が最後に登場。のっけからスライドギターが唸る、これまたサザン・フィーリング一杯のミッド・テンポロック。
新規加入のベーシストMichael Arnettと、メジャーのインディヴィデュアル・チャートでヒットを記録した事もある中堅バンドMagnapopのドラマーだったDave McNairが支えるリズムセクションも骨太なナンバーを良く支えている。
特にオルガンを含めた後半のインポロヴィゼイションはこの曲の聴き所だ。Alt-CountryとSouthern Rockの中間点を押さえるようなルーツナンバーで、長い割に冗長な部分を覚えない。アルバムの締めとしては相応しいナンバーでもあるだろう。
◆レイドバックルーツとガレージサウンド、何でもござれのMichael Goldman
自分のスタイルに拘り、キープしているKenとは対照的に、Michaelはヴァラィエティに富んだ曲を提供している。
前述の、#7『Walkaround』のカレッジハードナンバーから#10『Satellite』、#12『Your Way』のようなモダンPower Popで馬力を見せるかと思うと、このアルバムを代表するようなRoots Pop/Rockの良心というべき#1『I Guess By Now』でファースト・インパクトを与えてくれる。
適度に土臭いギターと、目一杯キャッチーなラインに支えられ、ロックが弾む#1は、The Indicatorsがルーツバンドとして新たに出航した船出を飾る曲だ。
Kickbacksの非カントリー、然れどもルーツでポップなタイプにまさに当て嵌まるナンバーだ。やや覚束ないKenの時折裏返るヴォーカルとは異なり、飾り気の無い安定したヴォイスで元気に唄ってくれる。
この甘さと馬力とアーシーさが全て揃った#1はアルバムのベストトラックになると思う。
マンドリンやハワイアン・ウクレレの本国仕様であるスティールギターの音がスライドギターに重なる#3『Easier To Find』も#1に負けず劣らずベストなナンバーである。
オルガンをかなり前面に出し、よりルーツさを強調しているが、Kenの作とは少々毛色が異なりあまり南部の匂いを感じさせない普遍性がある。スマートと言うと御幣があるが、野暮ったさよりも本来のアメリカン・サウンドが持つ特質でルーツィなトワンギィさを出せているのが凄い。
ホンキィなマシンガンピアノが明るく進む、#5『Arsentic Bells』も、取り立てて地方色を思わせない、Roots Rock + Power Popという極上のタテノリナンバーだ。単なる浅い暴走ポップにならないのは、やはりダウン・トゥ・アースなギターや雰囲気が曲に装填されているからだろう。コーラスの青さには、ウェストコーストの影響すら感じる。
直接的なアプローチはパンクルーツからやってくるものかもしれないが、パンクの粗さよりも、寧ろ50〜60年代のパーティ・ロックの歯切れの良さを連想してしまう。
#5とは一転して、埃っぽいブギー調子が冴える、#6『Flesh Hits The Bone』。こちらはやや英国的なマイナーセンスを感じるが、ギターの音色やオルガンの入れ方は、やはりアメリカン・サウンドの特質も見える。女性コーラスを加えるといった芸風の増加も見逃せない。
#8のSpritのカヴァーでも伺えるが、サイケディリックや60年代のロックンロールが持っていた英国プログレッシヴサウンドへの憧憬もあるかもしれない。
と思うと、マンドリンを決して大量にではないが効果的に使って暖かさを出しつつ、ルーツポップとR&Bクラッシックロックのノリを同時に満たしている#13『Say Goodnight』もある。
特に目立つ曲ではないが、後半でのアクセントを付けたヴォーカル・パフォーマンスや、ファンキーなスゥインギングにはMichaelの才能を感じる。
欲を言えば、MichaelもKenも、もう少しスローナンバーに力を入れても良いのになあ、とは思う。
特にMichaelはアップビートな曲を書かせると、つい口ずさみたくなるポップなラインを創造できるのだから、彼の手腕を思うとバラードやトラディショナルを活かしたスロートラックも聴いてみたくなってしまうのだ。
◆大和魂の理解者?
余談になるが、Michaelはかなり日本の武道に興味があると筆者の質問に答えている。
このアルバムのジャケットは、紛れも無い剣道−ジャパニーズ・フェンシングである。
柔道や空手、合気道とは異なり、米国ではそれ程広まっていない剣道をジャケットに持ってくるのは間違いなくMichaelの趣味の発露だ。
しかも、Michaelは柔道2段、合気道も有段者という、かなり本格的な体育会系なシンガーだ。(笑)
確かに、写真では恰幅のよさが目立ち、無差別級に出場できるような逞しさが見えたりする。
武道有段者というからには、小手先の日本文化模倣ではなく、ある程度の東洋文化に理解があると想像している。
しかし、筆者よりも柔道の段が上なのには恐れ入った。(苦笑)
◆時流に逆行するかのようなバック・トゥ・ルーツ
元来、Alt-Countryと呼ばれるサウンドが、パンクやガレージサウンドと無縁はおろか、非常に密接な関係にあったといえる。完全なAlt-Countryの元祖ではないにしても、ブーム及びAlternative Country Rockの単語を生み出す要因を担ったバンド、Uncle Tupeloはそもそもカントリーにパンクやガレージサウンドを混ぜ込んだ音で名を広めたのだから。
しかし、荒っぽいパンクサウンドが特徴だったTupeloも、後半になるとトラディショナルカントリーへの偏重が目立つようになるといった具合に、Alt-Countryが市民権を得るに従い、カントリーがより強いサウンドを求めるバンドが多くなり、それらをAlt-Country Rockと分類するようになっていく。
オルカンの裾野が拡がったといえば聞こえは良いが、要するにこれまでカントリーやカントリー・ロックと呼ばれていた存在までAlt-Countryのカテゴリーに含まれるようになったのだ。
こうなると、パンクやガレージ味の強いAlt-Countryバンドは異端に近い存在として捉えられがちになっていく趨勢があるとみえる。
カントリーでもなく、さりとて完全なオルタナティヴ・ガレージでもない中間色を好む音楽人口が少ない為と、天秤の針が少々傾くだけでどちらかの音楽性に容易に傾いてしまう不安定さがその理由と睨んでいる。
それでも、ルーツサウンドとオルタナティヴ系の音楽を融合させようと、デフォルトで中間サウンドを選択するバンドは存在する。その殆どがクセとアクの強いオルタナティヴにルーツサウンドの良さを上塗りされてしまい、中途半端なオルタナティヴもどきの音に終始してしまっているが。
対して、ガレージやパンクサウンドは、オルタナティヴ程融通が利かない事は無い為、ルーツロックとの親和性はそれなりに高いのは前述の通り。それもオルタナティヴの濃度がある程度薄いという前提があっての事柄であるけれど。
The Indicatorsのサウンド性は、正直、かなりオルタナティヴ・パンク色が強かった。
パンクポップというリスナーフレンドリーさより、ノイジーハードの傾向が重かったとみている。
故に、ルーツロックバンドとして変身を遂げた事に加えて、良質なルーツロックバンドとして成功を果たしているという点に於いて、非常に稀な例だと思うのだ。
元々、折衷的なルーツサウンドを主眼に於いているバンドではなく、処女作が異例と考えれば、当然の結果かもしれないけれど。
しかし、WlicoやRyan Adamsのように、流行を追い求めて脱ルーツする連中が多い中、正反対の方向に進み、それを良質なポップ・ロックとして成し遂げた事は、WilcoやRyan等の醜悪で1グラム=鐚銭という酷い“新境地サウンド”とは比較にならないくらい素晴らしい。
特に酷いサウンドに「Rock n Roll」と銘打っていい気になっているRyanはMichaelの爪の垢でも煎じて飲んで貰いたいと思う。
今後も、日本の武道と武の意(こころ)を理解しているに違いないMichaelの、誠実な活動を切に望む。
(2004.1.31.)
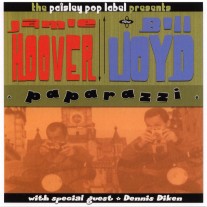 Paparazzi / Jamie Hoover & Bill Lloyd (2004)
Paparazzi / Jamie Hoover & Bill Lloyd (2004)
Roots ★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Acoustic ★★☆ Official Site of Hoover / Lloyd
◆ポップス精神は不変
今回、初めて公式にタッグを組んだJamie HooverとBill Lloyd。
筆者も知らなかったのだが、今回Bill Lloydがインナーに寄せたセルフライナーにてJamieとBillの出会いは意外なグループが絡んでいる事が判明した。
「Jamieと顔見せ的な出会いをしたのは、1980年代半ばのSpongetonesのライヴだった。ナッシュヴィルでの。だけど彼と本当に親しくなったのは僕がDan BairdとThe Woodの幾つかのデモ音源をプロデュースした時だった。僕とJamieはどうやったら音階が活きて良いスコアになるのかと頭を捻って多くの時間を過ごしたものだよ。」
ルーツロッカーとしてよりもパワーポッパーの印象が強い両者だが、ルーツバンドのThe Woodが仲立ちになったというのは興味深い事実である。
目に見える両者の交流はそれ以降となる。
実際、LloydはHooverのバンドSpongetonesの5作目「Textural Drone Thing」(1995年)にて、3曲をJamieと共同で書き、提供している。(『Better Lucko Next Time』、『Just Another Dream』、『Whenever You’re Abound』)
更にJamieのサイドワークであるVan Deleckie'sのファーストにも『A Photograph』をJamieとコンビで書いて提供している。
が、直接ではないにしろ、この両名が競演をしている舞台も2つ存在する。この2つ、というか2枚のレコードは、HooverとLloydがポップスというジャンルに対してどのような関わりと地位を有しているのかを図らずも実証しているように思えてならないのだ。
まず1枚目が、ポップとテクノロジーの先駆者にて、愛すべき実験オタクでもあるTodd Rundgrenのトリビュート・アルバム。その名もストレートに「Tribute To Todd Rundgren」(1993年)。
“For The Love Of Todd”−トッドに愛を込めて、の副題で発売されたこのインディ・トリビュートで、Jamieは1974年作の『Izzat Love?』をカヴァー。
Bill Lloydも1973年発表の『I Don’t Want To Tie You Down』を同じアルバムでカヴァー。
共に、ポップの鬼才である−エキセントリックで前衛的な個性を音楽に反映するので、必ずしも一般受けはしていないし、大成功を収めた事もないが−Todd Rundgrenのモニュメントに参加する資格を、その活動によって認識されているポップシンガーという事の一証拠となるだろう。
Don Dixonや、Terry AndersonのThe Woodsという面子のカヴァーが集められている。
更に時代は下った2001年。今度は、1970年代にTop40を量産した『世界最小のロックオーケストラ』、E.L.O.の顔役であるJeff Lynneのトリビュートアルバムが企画された。
こちらが、Not Lame Recordsのマネージメントで実現した「Lynne Me Your Ears : A Tribute To The Music Of Jeff Lynne」。
E.L.O.の曲だけでなく、ソロ作やあのTraveling Wilburysからもピックされた曲も含む。
ここでもBillとJamieが顔を合わせている。
Jamieが唯一チョイスされたWilburysのトップ40ヒット『Handle With Care』をカヴァー。今は亡きRoy Orbinsonを偲ばせてくれる。
BillはE.L.O.のアルバムでアウトテイクとなり未発表曲となってしまった『When The Time Stood Still』という少々マイナーな曲を担当。
他にはSwag、Doug Powell、Shazam、CMMグループのPFR、そして大御所としてTodd Rundgren、という具合にかなり豪華でマニアックな面子が顔を揃えている。
ポップの職人として、Jeff Lynneの地位は不動のものがあるが、そのトリビュートにJamieとBillがまたもや招かれているのだ。
この偶然には、彼ら両者の積み重ねた活動と評判という必然が深く関わっている。つまり、偶然ではなく、なるべくして顔を同じアルバムに見せる事になったといえる。
以上のように綿々と受け継がれていく良質なアメリカン・ポップスの担い手として、JamieとBillはそのの継承と維持に貢献し、オルタナティヴやミクスチャーに塗りつぶされたシーンの只中で、ポップス至上の精神を貫き通している男達であるのだ。
決して若手と呼ばれる歳ではなくなってしまったが、まだまだ大御所の活動をリアルタイムでクロスオーヴァーしていた世代の代表格でもあるだろう。
こういうミュージシャンが、良き音楽を守り、伝えていくのだと思う。
まずはこの2名について、簡単に経歴を見てみるとしよう。
◆Jamie Hoover
1956年2月生まれ。2004年の時点で48歳。
本邦での知名度は、相方のBill Lloydよりも圧倒的に低いだろう。
セルフパフォーミングではなく、他のミュージシャンに提供した歌等の数ではBill Lloydに軍配が上がると思うが、バックミュージシャンとして他のシンガーやバンドに協力している活動ではBill Lloydと同等以上であると考えて間違いはないのだが。
Jamieの活動は、彼のリーダーバンドであるThe Spongetonesを1980年に結成した時から始まる。ミュージックビジネスの世界では20年選手なのだ。
当節の流行であったシンセサイザーやキーボードを加えたニューウェーヴ・ポップパンクのバンドとしてシーンに登場。
AORよりもアクティヴでハードドライヴなサウンドを中心とした音を、当時はAORと呼んだものだが、1980年代後半からPower Popという単語で語られるようになってくる。
Spongetonesはまさに1980年代のパワー・ポップバンドの代表格だろう。
チャート的には全く注目を浴びたことは無いので、80年代型パワー・ポップの始祖はMarshall Crenshowと捉えられる事が多いのが、個人的には非常に無念だ。中規模のヒットアルバムを幾つか記録したCrenshowがパワーポップの祖と祭り上げられるのは仕方ないかもしれないのだが。
しかし、The Beatlesから続く、ポップソング。殊に英国ポップの香りを伝えるアメリカン・ロックとしては、何処か影のあるMarshallよりも陽性なベースを持つSpongetonesが相応しいと考えている。
元祖的なバンドであるBig StarやCheap Trickが持っていたキャッチーでダイナミックな、それでいて豪華なアリーナサウンドの継承者として、Crenshowは小さく纏まり過ぎというかコセコセとした感じがあり過ぎると見なしているし。
しかも、Spongetonesは1982年のファースト作発売から、これまでの所最新作である「Odd Fellows」まで実に息の長い活動を継続している。
更に、「Odd Fellows」は日本盤に限り、メジャーの大本であるSony Japanと契約。活動20年目にして海外盤とはいえ、メジャー発売を獲得している。
1980年代前後のニューウェーヴ・ポップのムーヴメントに乗って登場したバンドの大半が、10年以内で終焉を向かえ、20世紀末のパワーポップ再評価の時流に合わせて再結成を乱発した。
以上のような流れではなく、随所に長い休養を挟みつつも2〜5年間隔で地道なリリースを続けていた所にSpongetonesの凄さがある。
これもその息の長さが招いた成功だといえよう。日本での根強いパワーポップ人気を受けて、そこそこ売れたらしい。筆者としては、Spongetonesレベルに於いてはあまり良質なアルバムとは思っていないのだが・・・・。
この実績にレーベルが気を好くした模様で、更にスーパーベスト盤的な25曲入りのアルバム「Beat! The Spongetones」を2002年にソニーから日本盤のみ発売。これはNot Lameを介して本国に逆輸入されている。
現在、バンド活動は開店休業状態だが、ソニー・ジャパンが新作のオファーを持ちかけているとの事。「今度は5年も懸けないで新譜を出す」とバンドはステイトしているが、さて、どうなるか。
Jamieの単独活動としては、1990年に初のソロ作「Coupons, Questions, And Comments」を発表。時代性からも殆ど話題を集めなかった。しかし、ポップロックのファンの間ではかなり好評を得たアルバムであり、長い間廃盤となっていた故、再発売が待たれていた。その念願が適い、2004年2月に発売予定であるJamie Hooverの2枚目のソロ作の発売発表に連動して2003年にリイシューされた。(が残念ながらCD-Rなので、プレス盤の欲しい人は中古マーケットを漁ろう。)
Jamie関連としては筆者個人の嗜好に頼るなら、Spongetonesよりも全然好みである、別プロジェクトのバンド、The Van Deleckie’sを第一にお薦めしたい。 JamieとBryan Shumateによるデュオ・ユニットであり、Spongetones最大の空白となった「Textural Drone Thing」(1995年)から「Odd Fellows」(2000年)の間を埋めるようにして立ち上げられたJamieのアナザー・ワークである。
「Letters From The Desk Of Court S. Van Delecki’s」(1996年)
「Ebum Shoobum Shoobum」(1999年)
の2枚を作成。
今作「Paparazzi」の1曲目である#1『Show & Tell The World』がVan Deleckie’sのデビュー盤1stトラックである『Moonlight』をモロに連想させるウルトラ・ポップで胸躍るキャッチー・トラックなのは、デュオ形式繋がりなのだろうか、と意味も無く考えてしまったりする。
それくらいThe Van Deleckie'sは親しみ易く、レイドバック感覚も含んだルーツ・パワー・ポップなユニットである。
相方がShumateとは比較にならない知名度を持つBill Lloydに代わっているが、基本サウンドはJamieの活動履歴という物差しを用いれば、SpongetonesではなくVan Deleckie’sが類似となる。
固有バンド活動以外では、Bill Lloydに比肩するポップの職人ぶりを遺憾なく発揮している。
最もメジャー所では、やはりHootie & The Blowfishへのヘルプだろう。
2000年のレアトラック集「Scatter,Smothered And Covered」にて、未発表曲でオルガンや12弦ギターを担当している事が判明。
近年のHootieのツアーには頻繁に同行。『Only Wanna Be With You』のマンドリンや『Good Bye』のキーボード、『She Crawls Away』のオルガンといったバンドメンバー以外の楽器をマルチにこなすサポーターとして活躍しているらしい。
YayhoosのTerry Andersonのソロ1作目「You Don't Like Me」のミキシングを担当。
ポップシンガーとして本邦の隠れ(?)ファンも多いDon DixonやMarshallの弟であるRobert Crenshowのアルバムにマルチプレイヤーとして様々な楽器で参加。
豪州のルーツポップバンドであるOrange Humble Band。Mitch Easterが参加している事もあったのか、日本盤まで発売されたが、彼らの2作目にベースやギター、ダルシマーを引っさげて協力。
他にもポップ系のシンガー達を始め、ハードパンクバンドAntiseenに鍵盤を中心に参加したりと、意外な程に活躍している。
◆Bill Lloyd
1995年12月生まれ。2004年の時点で49歳。
言わずと知れた、1980年代後半を象徴するようなのカントリーデュオ、Foster & Lloydの片割れ。
1990年にRadeny Fosterと袂を分った後、Radneyがデュオを継承したカントリーやカントリーロックのみに走ったのとは対照的に、パワーポップやロックンロールを含め、カントリーサウンドにも力を注ぐというマルチな方向を進む。
とはいえ、1987年に「Foster & Lloyd」をリリースする傍ら、パワーポップ作品である「Feeling The Elephant」を同年に発表しているので、ベッタリなカントリー系のミュージシャンでない事はシーンに登場して即表明はしていた訳ではある。
そもそも、このソロ1作目は1980年代からデモ音源としてプライヴェート的な録音をしていた音源を纏めたデモ・コレクションの性格が強いのだ。つまり、カントリー・デュオとしてメジャーで登場する以前からBillにはポップライターとしての顔が存在していたという事になる。
Radney Fosterとのコンビで活動する傍ら、レコードデビュー以前から行っていたソングライターとしての活動も継続。
1990年にこのデュオは解散。Fosterは即座にソロアルバムの作成に取り掛かったが、BillはPocoのリユニオン盤「Legacy」に1曲を提供した縁からか、「Legacy」ユニットが終焉した後、Rusty Youngが結成したカントリー・ロックバンドのThe Sky Kingsにメンバーとして参入。
殆どの曲をRustyや他のライターと共同で書いている。ちなみに、Billは2002年のPoco新作「Running Horse」にもギタリストとしてゲスト出演。Rusty Youngとの良好な関係を保っている事を見せてもくれていたりする。Poco関連では、Paul Cottonのソロ作「Firebird」にも客演していたりもする。
しかし、The Sky KingsはEP1枚を放ったきり、契約の関係からフルアルバムをリリースせずに解散となる。(後年、ライノから音源を集めた編集盤が発売される。)
ここで漸くBill Lloydとしてのソロ活動を開始。1994年には2作目のソロ「Set To Pop」をリリース。メジャーで脚光を浴びる事は無かったが、パワーポップのシンガー・ソングライターとして高い評価を獲得する。
続いて翌年、4曲入りEP「Confidence Is High Plus 4」を発表と順調なソロキャリアを歩き始めたかなと思えた。しかし、これ以降はJamieのSpongetonesと同じように実にスローペースで活動。
1999年のソロ4作目「Standing On The Shoulders Of Giants」までソングライター又はバックミュージシャンとして地道にキャリアを重ねて行く事となる。
ソングライターとして最もエポックな事件は、90年代の数少ない正統派メジャーバンドのひとつHootie & The BlowfishがLloyd & Fosterのナンバーを取り上げた事だろうか。
Hootieのメジャー2作目にして全米トップアルバムでもある「Fairweather Johnson」からのファーストシングル『The Old Man And Me』のB面に彼らの曲『Before The Heartach Rolls In』が収録された。この曲は、後年彼らのレアトラック集「Scattered,Smoothed And Covered」で改めて発表されてもいる。
その他、Beth Neilsen Champman、Michael Hall、G.B. Leightonの2作目「Come Alive」ではLeightonと『Man In The Moon』を書いていたりもする。
Billの一面として興味深いのは、ソロアルバムは全て所謂パワーポップというジャンルに属するサウンドで構成されているのに、ソングライターやバックミュージシャン、プロデューサーとしてはカントリーやルーツ系の人達に協力する事が多い点だ。
勿論、英国オルタナパンクバンドであるPlaceboでのエンジニアリングといった例外はあるが。
著名どころでは、ソングライターのみならず、プロデューサーやミュージシャンとして、Steve Earleのアルバムの幾つかのアルバムに登場。
その他、Beth Neilsen Chapman、Marshall Crenshaw、Robbie Fulks、Al Kooper、Tommy Womack、Kim Richey、Swag、Ricky Van Sheltonと挙げれば幾つものカントリーからパワーポップのミュージシャン達のアルバムで演奏している。
筆者の一押しバンドであるThe Thompson Brothers Bandの2作目「Blame It On The Dog」ではプロデューサーを始め、ミュージシャンやライターとして全面的なサポートも行っている。
パワーポップが米国よりも歓迎される日本では、Bill Lloydの名前はかなりマニアックな部類に属するのは仕方ないとしても、Jamie Hooverよりも格では上に感じる。
Adam Schmitt、Tommy Keene、Matthew Sweetといった1990年代パワーポッパーの元祖的な存在として一定以上の評価を確実にされている男であるだろう。
しかし、パワーポップの歌い手としてのイメージが強い人だが、ベタなカントリーを中心に、ルーツ系のミュージシャンとの仕事が多く、そもそものキャリアがカントリー・シンガーとして始まっているのが面白い。
◆その両者が手を組んだ
そのキャリア、目立たないがマイナーポップス界の重責というべきに相応しい両名が初めて正式にチームを組んでアルバムを作成したのが、2004年1月に発売された「Paparazzi」である。
特にバンドやデュオ名を冠せず、単にJamie Hoover & Bill Lloydとコンビを記しているのは、自身の名前に対する自信の表明にも思えてくる。
実際、JamieにしてもBillにしても、マルチミュージシャンであり、経験を積んだプロデューサーでもあり、レコーディングエンジニアでもあるからして、このアルバムのつくりは全ての面に於いて実に手堅い。その自信を裏付ける活動履歴は十分に備わっているのは上記の通りだ。
案の定、制作の全てをBillとJamieで実施。Jamieは必要ならばドラムを叩く事もあるのだが、今回はこれまたパワーポップのヴェテラン(1990年代は腐ってしまったが)である、SmithereensのドラマーDennis Dikenを迎えている。
が他のミュージシャンは以外には全く登場しない。
全てJamieとBillが楽器を重ね撮りの形式でアルバムを拵えている。
クレジットに留まらず、ユニットの補足としてWith Special Guetstという一章をアルバムのフロントジャケットに書き加えているのが印象的だ。
への感謝を伝える以上に、他の楽器は全部自分たちの演奏だ、と強調していると見える。
◆ポップであるけど、意外に土臭い
先に、BillとJamieのユニットはVan Deleckie’sに似ている点があると書いているが、レイドバック度ではVDを上回る感じがある。
このアルバムはパワーポップというよりも、ルーツポップのアルバムと解釈する方が妥当である。
両者の活動拠点であるナッシュヴィル色が濃い、如何にもナッシュヴィル・サウンド−商業カントリーソングという意味ではなく、土臭いサザンテイストを持っていると言う意味−が詰め込まれている。
また、パワーポップの主流であるキーボードとラウドなギターを活用しまくったモダン・ニューウェーヴな側面を持つパワーサウンドとはこれまた異質の、アクースティックでストリップダウンを可能な限り実行した音が特徴でもある。
これは、シカゴ周辺の中西部パワーポップではなく、ナッシュヴィル・パワーポップと呼ぶのも良いかもしれない。
全体として華やかなパワーポップソングである#1『Show & Tell』にて意外に泥臭いギターソロが挿入されたり、マンドリンやバンジョーが隠し味に使用されている事が、このアルバムのトラックが目指している方向性を物語っている。
#1と同様に、煌びやかなポップラインを持った#2『Better Left Alone』もクラヴィネットが使われていたりと、キーボードアレンジにも気を配っているが、随所にハーモニカーがのどかな音色を吹き入れている。華やかなJamieとBillのコーラスやシャッキとしたシンバルに幻惑されがちだが、かなりレイドバック感覚が盛り込まれているのが解る。
意外に骨太なナンバーも多く、Billの朴訥なヴォーカルでリードされる#3『Screen Time』はザクザクとしたギターの重みが冴える南部を感じさせるロックナンバーとなっている。ピアノやシンセサイザーはバックアップとして活躍するに留まり、グニャグニャとうねるギターの音色を引きたてつつ極度に泥臭くならないように曲を支えている。
更にハードで何処と無く英国サイケディリックの不可思議さも漂う#5『The Bucks Stops Us』も#3のようにルーツっぽさやアクースティックさが目立つナンバーではなく、産業AORの感触に近いロックチューンだが、厚めのサウンドが一風変わっていて面白い。
そして筆者の最高に好きなナンバーの#8『Still Not Over You』。そして#11『It Could Have Been Me』。
どちらも実に素直で純粋なポップロックで、こういうタイプのナンバーなら大歓迎だ。
#8は小粋にスライドするギターの唸りからスタートする、ジャンプナンバー。シャイニーなシンセサイザーとぶっ太いギターのシンコペーションが最高のコントラストになっている。ここにBeach Boys風のオールドタイムなコーラスが跳ねるとなれば、もう言う事無し。
#11は#1と同様にポップミュージックの明るさとロックンロールの熱さを上手にブレンドし、ノスタルジックな暖かさの漂うロックチューンに仕上げている。極度な装飾をせずに、素材の良さを活かしたシンプルパワーポップの代表と言うべきナンバー。BillとJamieのダブル・ヴォーカルも滑るようなメロディと適度にギターが重なったふくよかな演奏にピッタリと合っている。
◆B級感が少ないのが宜しい
筆者がPower Popというジャンルの中でどうにも好きになれないヘナチョコ英国モドキサウンドというかB級メロディがあまり見られないのがこのアルバムの最も評価したいポイントだ。
Marshall Crenshawをどうしても筆者が好きになれないのは、このブリティッシュ的なヒネクレマイナーメロディが多いからだ。どうも世間の大半を占めるポップと言う感覚が、筆者と違うのか、筆者がズレているのか(多分こちらだが)、パワーポップに広く見られる、なんちゃってBeatlesの英国調メロディが駄目なのである。
正直、BillにしてもJamieにしてもこういうタイプの曲をアメリカンなストレートさを持つナンバーと混在させるアルバムを作ってきている。その辺りがどうしてもパワーポップに踏み込めない原因となっている。
B級メロディというか、ちょっとナードなマイナーエッセンスがメジャーな進行に加えられるJamieとBillらしい#7『Reality Not Alone』も、華やかなメジャーコードとは少々離れたスノビッシュなシティ・ポップのヒネさを感じない事もないが、ルーツ的な安定感がそれらのマイナスを補っている。
寧ろ、スローナンバーでややB級メロディの弱っちい点が目立つ。
#6『I Can't Take It Back』、#9『All She Wanted』、#12『Firefiles』といったバラードやスロータイプのルーツポップナンバーが、いまいち印象に残らない。メジャーなアップビートトラックの出来は出色なのに、こういったバラード系統の曲に得意のウルトラポップさを活用したハイライト・ソングが無い。
これが「Paparazzi」のウィークポイントとなる事は余談を挟まない事実だと考えている。
バラードの中にも、アクースティックの繊細さを前面に押し出し、Jamieがひっそりと歌い上げるた#4『As You Were』のような暖かく優しいタイプはこのデュオのアクースティックなアプローチの発露として出色だ。
また、#10『Walking Out』のように素直なメロディで、美しくメジャーに仕上げたバラードも、ポップスのハートウォーミングな一面を十全に利用し武器としている。何より、次第に盛り上がるコーラスワークに腰が強いギターサウンドが曲をバックアップしているし。
もう少し、アメリカンパワーポップなスローナンバーが欲しかったのが正直な意見。
◆久々のソロ作への弾みとなるか
2004年3月にはBill Lloydの5年振りとなるソロ作「Back To Even」が発売予定となっている。
対するJamie Hooverはソロ2作目−1stはデモ音源中心だったので、本来の意味では今度がファースト作とも言えなくも無いが−「Jamie Hoo-Ever」が2004年2月には発売されていた筈なのだが、未だにリリースの公式アナウンスメントもされていないし販売も行われていない所を見ると、延期の模様だ。ジャケットは出来上がっているのに。
ソロ作で言うと、14年振りとなる。
両人の本当に久方振りのソロ作への期待は、このコンビで作成された「Paparazzi」を聴く事でとても高まっている。
どうしてどうして、「私達の仕事をちょっと『追い掛け回して、スクープしてやったぞ。』でも本番のソロ作にはもっと期待してくれよ。」というメッセージがこの「Paparazzi」というタイトルに見えてくるのだが、如何なものだろう。
それにしても単色処理しているとはいえ、本当にパパラッチのポーズを決めている中年2名のジャケットには笑いを誘われる。このユーモアのセンスがゆとりとなって本来の持ち味を殺さない、流行に惑わされない形でソロ作に反映される事を祈るとしよう。 (2004.2.28.)
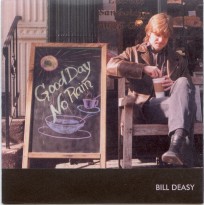 Good Day No Rain / Bill Deasy (2003)
Good Day No Rain / Bill Deasy (2003)
Roots ★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Adult Contemporary ★★☆ Official Site
◆Good Things Lead To Good Things
Bill Deasyが彼初のソロアルバム「Spring Lies Waiting」を発表したのが2000年。
歌詞がアルバムのジャケットに書かれているという省エネ仕様が非常に印象的だった。資金が無いという穿った見方は身も蓋もないので止めた方が宜しいだろう。(苦笑)
その内容は普通のアクースティックアルバムだったので、取り立てて記憶に残る要素はなかったと云ってよい。日本でもメジャーなシンガーであるNeimee Colemanとの混合デュエットがかろうじて耳に引っかかる程度だ。
その後、てっきり「Reliance」(1999年)を最後にして活動を終了したと考えていた彼のリーダーバンドであるGathering Fieldで4枚目のアルバム「So Close To Home」を録音。(Gathering Fieldについては、拙文にてその履歴を記しているので、宜しければ参考にして貰いたい。)
しかし、Billのソロも2枚のバンドレコードも大した注目を浴びる事はなかった。
Gathering Field(以下GF)の2作目「Lost In America」が発売後2週間で3000枚を売り、その成果がメジャー昇格を生んだ時代と比較すると、実にマイナーな活動期となってしまっている感は否めない。
それ以降、約2年間。Bill Deasy関連のアルバム情報はめっきり入ってこなくなってしまっていた。しかしその間、実は彼の歌が全米を通して流れていたのである。
2001年秋に、大手TV局のABCのモーニング・ニュース&トークショウ番組である「Good Morning America」が、新しいテーマソングを選ぶキャンペーンを開始した。
GMAのエグゼクティヴ・プロデューサーは150曲にも及ぶデモを聞き、幾つかの候補を絞っていたが、Bill Deasyと、Kim RicheyやThe Four Topsといった女性ヴォーカリストに曲を提供しているライターのLarry Gottliebが共作した『Good Things Are Happening』。このデモテープを耳にして、これだと思ったそうだ。
それまでは以前テーマ曲として採用していたビッグネームであるShania TwainやStingクラスの採用も頭にあったそうだが、Billの歌を聴けば聴くほどに惚れ込んでしまったという事だ。
元来このナンバーはBill達が自分のレコード用ではなく、他のシンガー用として書き下ろしたマテリアルなのだが、番組のスタッフはBillのヴァージョンをいたくお気に入りになり、彼の歌を新テーマソングに採用したのだ。
結果として、1分のショートヴァージョンに纏められた『Good Things Are Happening』が毎日ブラウン管から流れるのみならず、Billが実際に演奏するビデオまで番組のゲスト出演の一環として撮影され、フルコーラスのヴァージョンも正式に録音されるに至っている。
残念ながら本作「Good Day No Rain」に収録されていないのだが、ここでインストゥルメンタル・ヴァージョンとヴォーカルのエディット版が聴ける。
歌詞も掲載されているが、歌のメッセージ共々、朝の番組に相応しい前向きで気持ちの良いポップロックという事が分る。
「Lost In America」をAtlantic Recordsから再発売し、全く注目されずに契約を切られてしまった事件と比較するとかなりの幸運が舞い込んだと考えられる。
まさに、Good Things Are Happeningだ。
この人気プログラムの主題歌に選ばれたシンガーという事実が、Billの新作「Good Day No Rain」を容易に手に入る後押しをしている。
現在、彼のソロ2作目はAmazon.com、B&N.comといった大手ショップを筆頭にして色々なオンラインストアで簡単に発見が可能だ。
ファーストソロ作が極短い期間にMOMのみで売られていた頃を考えると格段の待遇改善だ。一度はメジャーになったGathering Fieldでさえ、大手のネットショップでは在庫切れという状況にある中、大した評価をされているひとつの証拠になるだろう。
◆Five For Fightingの影響を語る
2004年、Five For Fighting(以下FFF)が3作目のメジャーアルバム「Battle For Eveything」をリリース。初のトップ40アルバムに押し上げている。
しかし、今回の成功の基は2000年に発売され、翌年にトップ20ヒットシングル『Superman(It's Not Easy)』を記録したアルバム「American Tonight」だ。
アルバム自体は、結局トップ40に届かなかったが、シングルとしてカットされた『Easy Tonight』を含むFFFの曲が頻繁にオン・エアされ知名度が大きく拡がったのは事実だ。
Bill Deasyも「American Tonight」以前のFFFを知らなかったひとりだが、FFFの曲を聴いた事が今回の「Good Day No Rain」の取っ掛かりになった事を自ら語っている。
「2002年の11月、僕はナッシュヴィルへ車を走らせながらFive For Fightingのレコードを聴いていた。僕はFFFのサウンドをとても好きになり、その場で広報担当に連絡を入れた。彼女がFFFのレコードをプロデュースしたGregg Wattenburgと面識があるかどうか尋ねる為にね。
そして全ては、彼女がGreggと短い面談を持って、僕と会う手配をした事から始まったんだ。
その後僕が書いてきた歌で、彼が気に入っている幾つかを弾いて見せた。そして僕達は何曲かを一緒に録ろうと決めたんだ。
そうして始めた作業が、最終的には「Good Day No Rain」というニューレコードのリリースに繋がった。最初はGreggとの仕事が何処へ向かうのか自分でもはっきりとしていなかったんだけどね。」
以上のように、「Good Day No Rain」はFive For Fightingの最新作を含めた2枚のアルバムを手がけている(新作は一部参加)Gregg WattenburgとBill Deasyの共同でプロデュースされている。
Gregg Wattenburgは1990年代後半から頭角を現してきた新しい世代のプロデューサだ。これまでの作品は基本的にAlternativeだ。が、ヘヴィネスやハードコア系ではなく、Adult Alternative系に属する比較的にポップなバンドとの仕事が殆どなのも彼の色だろう。
Eve6の「It’s All In Your Head」、Dishwallaのカムバック作「Opaline」、かなりキャッチーでハードなバンド、Poundの一枚だけ放った「Same Old Life」、オルタナ系のヴォーカリストとしてはそこそこ注目できる新人Bob Guineyのデビュー作「3 Side」。そしてダークでアンビエントなオルタナバンドStageの「Stage」他。
Five For Fightingは「Battle For Everything」でほぼ脱オルタナティヴしているが、「American Town」ではオルタナ臭い曲が目立つし、ここで挙げた他のバンドもどうにもオルタナティヴという泥の膜が纏わり付いたバンドばかり。良い曲もあるけど、完全には筆者の好みに合致しないというアルバムばかり並んでいる。
正直、そのGregg WattenburgがBill Deasyの新譜の舵取りを行うとアナウンスされた時、こう思った。
嗚呼、またGathering Fieldのオルタナ版になるのかなあ、と。
GFというバンドが、アクースティックなシンガーソングライター風味を備えると同時にどうしても拭い切れないオルタナティヴの軛を持っていたからだ。
ピアノを上手に活用した4作目「So Close To Home」でもルーツテイストに絡むオルタナ芳香臭がどうしても気になっていた。これは「American Town」までのFFFと同じである。
しかし、単にアクースティックの程度を増すだけではJohn Mayerのような腐れモダン・フォーク崩れに堕落してしまうので、このあたりの分量配分は実に難しい。
さて、Bill Deasyの新作はどう仕上がったのだろうかとなるが、FFF的な影響は確かにが現れている。そして、その部分はしっかりと個性を放っている。
それはアクースティックピアノの積極的な導入である。FFFのJohnのレヴェルまでピアノをメイン楽器に置いてはいないが、「So Close To Home」よりもピアノの活躍が目立つ。
鍵盤類の使い方に進化と進歩が見られるという現象は、Greggの影響を思う。
◆ソロ1作目とバンドサウンドとの違いは?
まず、Billが初のソロアルバム「Spring Lies Waiting」について自ら語っている事柄を見てみる。
「僕がソロアルバム用に書いたナンバー全ては、Gathering Fieldというバンドの歌としては完全にフィットしないものだね。そして、僕はそういった曲を表に出したいと感じたからソロアルバムを作成したんだ。」
「“Spring Lies Waiting”は意図的にローキーを馴染ませ、そして自分がプロのソングライターだという考えにより近づいた作風を心掛けた。」
となっている。これには筆者もほぼ同意する。というのも、1stソロは完全なアクースティック且つローファイなアルバムで、アクースティックな音が中心のバンドであるGFよりも更にシンガーとしての個人を追及した意図が見て取れるからだ。
対して、3年後のお目見えとなったソロ2枚目「Good Day No Rain」はどうだろう。
1stソロと本ソロアルバムを繋ぐ形になるGFの4th「So Close To Home」の音についても着目して考えてみたい。
アルバムを購入する前、筆者としては漠然と、バンドサウンドを維持しつつも、よりアクースティック色が強くなった「So Close To Home」の発展系を予想していた。つまり、1stソロの弾き語り的アルバムにオルタナティヴと少々のロックテイストを加えた、フルアクースティックとGFスタイルの中間的な作品である。
しかし、良い意味で筆者の勝手な予想は裏切られてしまった。
第一に、シンガーソングライター的なアクースティックの部分は相当存在をアピールしているが、1stソロのようなフォーキーな路線よりもロックアンサンブル中心の組み立てとなっている。
フォークではなく、アクースティックなロックな作風を求めたアルバムなのだ。
これは、単なる作風の上っ面だけを挙げると、Gathering Field時代、特にファーストからサード・アルバムまでのアプローチと重なる部分が無きにしも非ずだ。
しかし、GFとこの「Good Day No Rain」には大きな違いが存在する。それこそが、本作を持ってこれまでの10年間で6枚のアルバムを作成してきたBill Deasyの最高傑作、と筆者に言わしめる理由でもある。
それが第二の予想を覆された部分である。
フォーキーな1stソロは別として、これまでのGFのサウンドには必ずといって良い程、オルタナティヴ音楽の影がチラついていた。
Gregg Wattenburgが手掛けてきているミュージシャン群と比較すれば大した量ではないのだが、矢張りオルタナティヴの陰性と鬱性を含んだ音がどのアルバムでも聴ける。まあ、これはCounting Crowsにしてもそうだが、メジャーでアルバムが出せるようなバンドの殆どは多かれ少なかれ1990年代型のオルタナティヴをベースにしているものだから、宿業みたいなものでもあるが。
ところが、「Good Day No Rain」ではオルタナティヴの要素を殆ど感じる事がないのだ。
モダンミュージックやアクースティック・オルタナティヴ的な側面が皆無とまでは行かないが、これこそまさにシンガーソングライターの会心の一撃というべき、ヴォーカルロック作品だ。
脱オルタナティヴと表現するまでオルタナティヴに染まっていた人ではないが、やはりオルタナ離れした事は明白だ。この点だけでオルタナ死滅を心から願う筆者にとっては、強烈に高評価したくなってしまう。
実際、オルタナティヴのマイナス因子を計算に加えなくても、非常に良質なアクースティックサウンドを活かしたPop/Rockであるのだ。
ノン・オルタナティヴの良い例として幾つかピックしてみよう。
R&B風のリズムを持ち心持ち泥臭い#2『Blue Sky Grey』は、これまでのGFの流れで行くなら、きっとオルタナティヴ的な音楽性を覚えるナンバーになっただろう。が、この曲をR&B風味ルーツ味モダン風味という感じに、様々な要素をミックスをした多様な楽器を楽しめるトラックに仕上げている。アクースティックギターやピアノのみならず、アナログシンセサイザー・サンプリングやストリングスも加味。ユニークな曲だが、決してオルタナティヴではない。
マイナー調子のぎたーソロが、すわダークオルタナが来たかと思わせる#7『I’ll Be There』も途中からメジャーに転調を開始。オルガンやピアノでラインに彩りを加え、最終的にはかなりの盛り上がりを見せるエモーショナルなバラードにまで持ち上げている。
こういう例を見ると、これこそロックヴォーカルのアルバムという感慨を持たずにはいられない。
◆スローナンバー中心のライターから変貌
ソロフォークアルバムは言うには及ばず、GFというバンドは全体的にミディアム以下からスローテンポの曲を得意としているグループ。こういったイメージが強い。特に最新作である「So Close To Home」では、バラードのみが非常に良質という感慨を抱かせる傾向が強い。
しかし、アップテンポで前向きな『Good Things Are Happening』である程度速い歌への手掛かりを得たのだろうか。
1stソロ作にて、これまでバンド形式では書けなかった曲を吐き出したが故に、他のシンガーに曲を提供する事に興味が沸いた、というBillのソングライティング提供者としての活動が影響を与えた事もあるかもしれない。
何れにせよ、本作ではBillにしては珍しいくらいのアップビート曲が強いインパクトを放っている。
それは、GFでも聴けなかった位のエレキギターが軽々と舞う、ドライヴィング・ロックの#4『Prosoner』だ。このアルバムからシングルを切るとすれば筆頭になるだろう。
Bill Deasyがここまでエレキギターを痛快に使った曲はこれが初めてだと思う。フックのあるリフとパワフルなアンサンブルは、Power Popという呼び名こそ相応しい。
Tommy KenneやTitanic Love AffairがBillに乗り移った感じがしなくも無い。そのくらいアップビートなのだ。
#4程には突っ走らないが、アクースティックな手触りを大切にしながら、ミディアムファーストな気持ちの良い速度で流れていく#6『Somewhere In Me』。アクースティックなリフからオルガンと乾いたドラムリズムが曲のシフトアップをしていく、これまたヒット性がありそうなポップなナンバーだ。シャッフルの効いたギター弦のリズムにオルガンの温かみが加わる点が宜しい。
更に、#9『It's All Right There』。土臭さが少ないメロディメーカーであるBillの作風を代表するようなロックナンバーだ。
ノイジーに然れどもローファイに唸るエレキギターはU2のモダン性をモロに連想させる。シンプルなコード進行とパワフルなリズムセクションのバトルとオルガンのブワブワした波は、中期にヒット曲を生み出していたU2にとても近い。Bonoが歌っても違和感の無いUK的無謬さを感じる曲だ。
モダンロックという点では、アンビエントなピアノのシンコペーションと、ループのようなパーカッションリズムで淡々と続く#3『In My Head』だろう。
ジャムバンド的、アンビエントさと近代的さを備えたナンバーであり、John MayerのようなDave Matthews Bandのコピー屋が得意とするタイプの曲。これでリリカルなピアノが組み入れられてなかったら、後半でのヴォルテージの上昇がなければ好きになれなかったナンバーだ。
しかし、同系列なアンビエントナンバーの#1『I Want To Know』になると、全然良好な曲になっている。
これはジャムロックへの単純な追従ではなく、Bill Deasy自身のセンスが#1にはしっかりと吹き込まれているからだと思う。
アクースティックギターのみならず、FFFを念頭に置いた美しいピアノソロとキーボードアンサンブルを巧みに封入している。しかも、曲の持つパワフルさがオルガンとピアノが生み出すラインに引かれて浮き出ているのだ。
デリケートだが、アクースティック楽器の様式美を覚える、しめやかなロックチューン。これが#1のカタチだろう。アルバムの中でも屈指の優しさを誇るナンバーだ。
◆バラードはやはり上手
特に、6分を遠く越す#5『I’ll Rescue You』と#10『The Gift Of Seeing Through』はアクースティックとかオルタナティヴを超越した、AORとしてのメジャー感覚を備えた名曲である。
しずしずと進むアクースティック弦に乗っていく静かなBillのヴォーカル。この閑かな展開から、オルガン、リードエレキギターのサポートを得て、まるで産業ロックのバラードのように切なく、感動的に訴えてくる組み立て。ありきたりとはいえ、やはりアクースティック感覚とエレクトリック・アンサンブルのメリハリが付いたバラードは大好物。素晴らしい。
#5と同様にBillの弾き語りで幕を開ける#10『The Gift Of Seeing Through』。典型的な泣きのメロディなトラックだが、明るさがあった#5と比べると更に物悲しい郷愁に満ちたラインが印象的である。大仰にリフトアップしてくる#5程熱しないで、オルガンとピアノが抑え気味に視覚的にも美しい世界が見えてくるようなアンサンブルを彩る。
8分近い大作だが、最大の聴き場所は4分前半から、グンと盛り上がってくるコーラス部分。スライドギターがノスタルジックなソロを奏で、その音がエレキギターの弦に溶け込んでいきながら、更に
女性ヴォーカリストのLiz BerlinがBillの暖かいヴォーカルに華を添える。
そして再度スライド弦の泣きという具合に、ラストに向けての怒涛の感情の入れ方。まさにアルバムの締めくくりに相応しい。
この2曲と比較するとやや霞んでしまう#8『Who Are We』だが、これまたミディアムなバラードとしてかなりの良トラックなのである。ストリングスの使い方は完全にACロックな大人の味付けだし、叙情的なピアノリフも、Billのハスキー気味なヴォーカルに被さるコーラスも中々だ。
こういった厚目のミディアムバラードはあまり持ち歌にしないシンガーと考えていたが、どうしてどうしてしっかり出来るではないか。
◆残念、『Good Things Are Happening』フルコーラス版が入ってない
これまでにない明るさと豪華なロックアンサンブルが、まさに「Good Day No Rain」というタイトルを顕している。
「気分は快晴、心に曇りなし」というタイトルは、メジャーレーベルとの契約以外で知名度を得る成功を掴んだBill Deasyの心境にシンクロしているとしか思えない。
惜しむらくは、やはりまだまだ内省的な面が見え、オルタナ的暗さではないが、独特の鬱フィーリングをスコアの組み上げの行間に感じる点だ。
希望に満ちた『Good Things Are Happening』のような陽性のナンバーがもう少し欲しかった。同じく#4のようなストレートなロックチューンをもう少し増やして、シンガーソングライターよりもろっくんろーラーとしての顔を前に出しても良かったとも思う。
しかし、返す返すも残念なのが絶対に入れてくれると信じていた『Good Things Are Happening』のフルヴァージョンがトラッキングされなかった事だ。
単に、個人的に聴きたいという理由のみならず、この明るく楽しいナンバーがラインナップに入れば、もっと楽しいアルバムに性質が引っ張られたかもしれないからだ。
Billはシンガーとライターとしての自分に傾倒して曲を作る性格だと彼のコメントから伺えるが、『Good Things Are Happening』に代表されるように、他人向けに書いた、より力みの抜けた曲を自分で歌ってみるのも面白いかもしれない。
何にせよ、次回作がGathering Fieldになるのかソロ3作目になるのかまだ見えて来ない段階とはいえ、まさに『Good Things Are Happening』な状態を経験して追い風な状態なのだ。更に“Good Things Lead To More Good Things”というポジティヴな気持ちを曲にも反映して頑張って欲しいと思う。
かなり彼を見直したアルバムだった。 (2004.3.15.執筆 / 2004.3.31.加筆訂正・掲載)
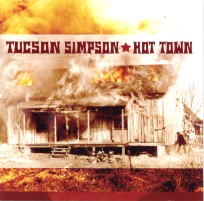 Hot Town / Tucson Simpson (2002)
Hot Town / Tucson Simpson (2002)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Southern ★★ Official Site
◆This review is dedicated to Mr. Sam Plumlee was a great guitarist
このアルバムを録音中に、Tucson SimpsonのリードギタリストであるSam Plumleeが急逝している。
アルバムの曲作りには積極的に参加し、10曲中3曲を他のメンバー全員と。そしてアルバムの最後を飾る#10『Down Into You』はSamの単独作である。
#10の副題が“The Sammy Song”。このアルバムにおける残りの曲は、リードシンガーであるGraham Perryが全てに於いてタッチしている事を鑑みても、30代の若さで夭逝してしまったメンバーの一人に対する想いを込めて、Samの作品を収録したのは想像に難くない。
しかし、こういった事情から、皮肉にもSamは#10のギターを弾く事は叶わなかった。
バンドはJeff Millerというギタリストの手を借り、Samが最終的なレコーディングに参加が不可能となった#3『Beat This Dead Horse Down』、#8『Can't Help You』、そして#10を吹き込んでいる。更にTerry Fergusonというプレイヤーに#2『Bottle Of Pain』のギターを任せている。
彼ら公式サイトの情報では、#5『The Moment Ain't There』を録音直後に亡くなったと記されている。このパワフルなロックチューンでの気持ちの良いギターワークが永遠に聴けなくなってしまったのは誠に残念と云うしかない。およそ半分のマテリアルをレコーディングしている最中の出来事だった。
そういった事情を踏まえた上で、是非#10の「サミーの歌」を聴いて貰いたい。
アルバムの最後を閉じるのに似つかわしい、壮大なスケールを感じるナンバーだ。スライド弦の泣きもしっかりと加わった、ガッチリとした枠組みのロッカバラードとして存在感を主張している。が、全体に何処と無く漂う寂しさはそういった現実の事情が幾許かは影響を与えているのかもしれない。
カントリー臭さを全く感じさせないボトルネックギターの音色が、とても黄昏て聴こえる。
バンドサウンドの根源の1つとして、カントリーロックがある事は明確に読み取れるのだが、これがカントリーにならないし、カントリーな雰囲気もあからさまに見えない。こういったTucson Simpsonのバンドカラーを臨時に加えられた歌でも見られる。
それにしても、バンドには他にもギタリストが在籍しているのに、メンバーが欠けた穴を残りのメンバーの代演で埋めようとせずに、新しいギタリストを雇い入れてしっかりと録音しているという事実。
一歩間違うと、冷酷とも取れる姿勢だが、しっかりとSamの歌をオーラスに加えている事。これが亡くなったメンバーへの敬意と尊敬の現れであるのは間違い無し。
そして、安易にオーヴァーダビングに流れず、バンドとしてのアンサンブルを尊重する創作姿勢。この音楽へ対する真摯な向き合いが、何よりもSamに対する誠意の表れだと見做して構わないと思う。
この拙文を、今は亡き素晴らしいギタリスト、Sam Plumlee氏に捧げる。
◆着実な1stEPからの進歩
予感はあった。Tucson SimpsonのデビューEP「Drawn & Ready」を聴いた時。
というよりも、確実な予想だったというのが正しいと思う。
このバンドは凄い才能があると。
『Everything』のストレート・フォワードなロックンロールと南部サウンドの率直さが重なったアンサンブルに。
『So Cold,So Lonely』の泥臭く飾らないサザンロックの不器用さに。
『Marionne』のキャッチーでスピーディ、それでありながらルーツ的な土臭さのあるロックリズムに。
『Afraid To Die』のアクースティックとエレクトリックが融合したスケールの大きなサウンドに。
たった4曲とはいえ、Tucson Simpsonが内包する魅力と才能を十分にアピールしていた。
しかしながら、4曲というヴォリュームだからこそ、悪い表現になってしまうがアラが見えない場合もある。フルレングスで自身の音楽を表現しようとする段になると、その才能の底の浅さを露呈してしまうバンドはこれまでに結構見てきているのだ。
EPやミニアルバムを聴いた時は、「お、これは期待できそうだ。」と思わせてくれるのだが、実際にフルアルバムを出してみれば…
駄曲が大半を占める=たまたまEPでは良い面が集中的に発露しただけ。
多数の曲を収録しなくてはならないのでアレコレと手を出してみたが結局散漫なアルバムに終わってしまった=ひとつの作風だけでフルアルバムと言う間を持たすことが出来ない。とはいえ多種多様な内容を表現できる程にも多芸ではない。
という具合で失望を覚えたバンドに幾つ出会ったのかを数えるのさえ億劫になってしまう次第である。
しかし、時にはEPやミニアルバムを聴いただけで、絶対にハズレは無いと断定できる素晴らしい新人バンドに巡り合う事だってある。
そのひとつが、今回紹介の場を設けたTucson Simpsonである。
事実、2001年に発売されたEP「Drawn & Ready」に続いてリリースされた「Hot Town」にて、筆者の期待を裏切らない良質なロックアルバムを届けてくれた。
しかも、デビュー作で感じていた彼らの音楽性の良さはそのまま継続して表現してくれたばかりではなく、更なる可能性と才覚をしっかりと見せてくれている。
更に、これからを予感させてくれるバンドに共通して見られる、前作よりもレヴェルアップを果たしているのだ。
まさに上り調子のロックバンドといえよう。
これから、Tucson Simpsonというバンドの魅力に付いて語ってみたいと思う。
◆CMJチャートで歓迎される普遍性と、マニア向けの濃さの同居
CMJ(College Music Journal)チャートを、少しインディーズ音楽に興味があるならご存知の方が多いだろう。
全体的に若年層向けのメジャーまでは行かない音楽を扱うメディアのチャートであるのは周知の事と思う。
一時期は筆者もかなりチェックを入れていたが、オルタナがどうしても感性に合わないし無理して聴くのは人生の浪費と気が付いてからは殆ど見るのを止めてしまった。これにはここ数年のジャム・ロックやアクースティックの名前を借りたAcousitc Alternativeという似非音楽の氾濫に嫌気が差してしまった事も原因の一翼となっているのだが。
と、それは良いとして、CMJはそれこそオルタナティヴからメタルサウンド、ヒップホップまで含んだ総合的なポップロックを取り扱う事を身上としている。懐かしい所ではR.E.M.等がCMJチャートから火が付いてメジャーに駆け上がっていったバンドという例があったりする。
しかし、コンセプトがBillboard誌のチャートで扱うメジャー以外の紹介と言いつつも、結局は20〜30代のリスナーの流行に敏感という性質を持つため、様々なインディ音楽だけを分け隔てなく取り上げるという姿勢は、最終的に現在流行している音楽に歩み寄る傾向になる。
つまり、CMJチャートではカントリーロックやAlt-Country、そしてそもそもルーツロックが脚光を浴びる事は殆ど起きないのである。
精々、ややルーツ的な性質を有するAdult Alternativeがピックアップされれば御の字という趨勢である。
しかし、Tucson Simpsonは、全くオルタナティヴの影響が見られない正真正銘の、非オルタナティヴなアメリカンロックを演ずるバンドであるのに、CMJにて注目をデビュー時から集めている。
この事実だけを見ても、稀有なバンドであることが窺い知れよう。
流石に4曲入りEPがCMJチャートにランキングされる事は無かったが、翌年メンバーの喪失というアクシデントを乗り越えて発表された「Hot Town」は登場週にCMJチャートの14位を記録。
カントリーやルーツ系の音楽が、CMJで全くピックアップされない訳ではないのは、直前にも書いた。しかし、ここまでオルタナティヴやジャムサウンドに染まらず−メジャーやファッションとしてそう簡単に排除出来る要素ではない−不器用なまでのアメリカン・ルーツを表現するバンドがインディ専科とはいえ「現代」のサウンドを扱うCMJで評価されるのは稀有な事件だ。
やはり、オルタナティヴとかモダンロックとかクラッシックロックとか、そういった細かい事項を超えて存在する、良いPop/Rockというものはどの時代にも存在し、そういう貴重な音がTucson Simpsonには備わっているからこそのCMJでの高評価なのだと思う。
彼らのジャンルや世代を超えた、所謂普遍性を代表する曲が、「Drawn & Ready」における『Marionne』だった。Power Popと呼びたい素直なメロディと、頭ごなしのラウドサウンドではない本物のロックリズムによるポップチューン。これがEPで最も希求力のあるナンバーだ。
その流れを正確に受け継いでいる代表格が、それぞれタイプは異なるが、#1『Coldmater』であり、#3『Beat This Head Horse Down』、そして#5『The Momey Ain’t There』といったポップでパワフルなロックチューンである。
そして、自らをデルタ・ブルースのバンドと表現するTucson Simpsonの、もう一つの特徴である、濃いサザンロックや南部ルーツサウンドを余すところ無く表現しているのが、ブルージーでサザンアクセンツのある#2『Bottle Of Pain』、#8『Can't Help You』を筆頭とするナンバー群だ。
◆懐かしく、古臭いけど新しい
無論、明確に現代的なポップセンスと、クラシカルでインディ丸出しの南部の根っ子サウンドは上記した様に、全てのトラックではっきりと区別する事は難しい。
何故なら、現代的なセンスとルーツミュージックへのマニアックな傾倒は、殆どのトラックに両者とも存在するからだ。
曲によって王道的なメジャーポップセンスが強かったり、より根源的なローカル色が面積の割合を増す、という具合に殆どの曲が両者を内包。それらがTucson Simpsonの馬力満載なロックサウンドを形成してるのだ。
こうなると、特に一般受けしそうなキャッチーなナンバーに共通しているのが、1970年代のメジャーチャートのヒット曲を連想したくなる、古いけど、何処と無く懐かしく、そして21世紀のロックユニットとしての活き活きとした新しさである。新しさで語弊があるのなら、若さ故の余りあるパワーと言い換えても良い。
決して、モダンロックとかオルタナティヴやジャムサウンドという「現代性」ではなく、それらの音楽を聴いて育ちつつも、自らの骨子をしっかりと据え付けた曲創りと演奏の舵取りを、現在進行形で行っている新しさである。決してディケイド以前の懐メロの復刻ではない。
彼ら自身によるバイオグラフィーには、
“An eclectic mix of Delta Blues , Commercial Pop and Southern Rock”
−デルタブルースとコマーシャルなポップミュージック、そしてサザンロックの全てを混ぜてエレキサウンドで表現した音楽−
とある。
確かに、これらの要素は全て彼らのサウンドに混入している。しかし、これらだけでなく、アクースティックサウンドやカントリーロック、更にHeartland Rockの優しさまでもがしっかりと消化された上で、詰め込まれているのだ。
決して斬新さは無いのだが、単なる70’s回顧バンドでは終わらない、Tucson Simpsonの独自性というものがしっかりと表現されている。
それはディープなルーツサウンドへの傾倒をかなりの割合で行いながら、悪い意味でインディーズに落ち込まずに、適度なコマーシャル性と一般的な柔らかさのある音作りだと思っている。
特に、バンドが自ら挙げているデルタブルースに良くある、コテコテのブルースロックの濃さとマイナー感覚が殆ど見られないのだ。
これこそが、1970年代にはしっかりとメジャーでも評価されていたアメリカン・サウンドだ。
その代表格が、やはり#1『Coldmater』だろう。
南部のバンドたる所以をきっちりと表明した骨太なサウンド。しっかりとつぎ込まれた土臭い感触。適度にエレクトリックでありつつもアクースティックな部分を残したアンサンブル。
気持ち良く刻まれるドラムス。
黒人ヴォーカルといっても通用しそうな、リードシンガーのGraham Perryのソウルフル・ヴォイス。
その熱い歌唱に重なる、CSN&Yを思わせるコーラス。
そして、メロディがキャッチーとなれば言うこと無しだ。このナンバーに限って云う事ではないが、Tucson Simpsonにはそれ程強烈なデルタブルースの色合いは無い。
愛すべきローカルバンドの親しみ易さは、ご近所の州出身のナショナルバンドであるHootie & The Blowfishを連想させずにはいられない。
特にGrahamの声はHootieのDarius Ruckerに比肩する熱さと伸びの良さがあると思う。
Hootieの名オープニング曲である『Hannah Jane』クラスのルーツロックナンバーだ。
同様にして、HootieやSister Hazelがプレイしていても一向に違和感の無い#3『Beat This Dead Horse Down』も実にヒット性の高いポップロックである。
アクースティックギターのリフにオルガンが重なり、ユニゾンしていく頭出しは希求性抜群。
サザンロックの腰の強さに加えて、デルタブルースの特色のひとつであるお気楽さがメロディ全体を躍り上がらせている。スローコードとファストコードを巧みに入れ替え、曲に強弱を付ける手法は斬新ではないが、明るい前向きなメロディには似合っている。
この2曲よりもタフでハードなロックチューンの#5『The Money Ain't There』は、かなり南部ルーツの激しさとブルージーなピアノやギターのラインが目立つ。しかし、キャッチーなラインにより、クドさや濃密なローカル色は緩和され、FacesやStones的なクラシカルR&Bロックの顔も感じられる。良好なロックチューンであり、インディバンドならではであるが、一般性も兼ね備えている。
◆カントリーやブルース的な南部の核
こういったポップ度が高いナンバーには、CMJで人気を得る理由となるコマーシャル性が目立つが、それらポップ性をある程度以上持ちつつも、南部ロックの泥臭さを表現している、図太いナンバーも魅力的だ。
タフでブルージーなギターが唸りをあげる#2『Bottle Of Pain』や#2よりも更にダートな南部のカルシウムたっぷりといったゴツさが際立った#8『Can’t Help You』
この飾り気の無い素のままのロックナンバーでのギタリストが、実はSamではないというが、実に勿体無い。
客演ギタリストの2名は、とても良いディストーションが適度に効いたサザンスタイルのギターを弾き飛ばしているのだけれども。
#2でのグニャグニャとのたうつギターのアンサンブルは、意外にポップに纏められたラインをガッチリとサポートしているし、リズムの歯切れが良い#8でのロッキンブルースとサザンアクセントの混じった野暮ったさは、これまた予想外に耳触りが宜しい。
どちらも、ベッタリしたサザンロックなのだが、素直なメロディラインが(物凄いポップではないけど)一般受けする程度にまで純度が降下している為、アルバムの流れを妨げず、他のポップなロックチューンと違和感無く並んでいる。
また、このアルバムで唯一他のライターがクレジットされている#6『Owen’s Mill』。これはソングライターのGrahamが、同郷出身のカントリーシンガーであるMartin Crutchfieldのセルフタイトルソロ作に6曲を提供した分からのフィードバックである。
Red Dirt Musicというべき、南部カントリーやカウパンクのスピーディさとダートさがあるナンバーで、かなり濃厚な南部センスを感じる。しかし同時にオルタナティヴやメジャーなロックサウンドのリズムも取り入れているように思えるのだ。
単なるハードカントリーなナンバーではない。但し、他の曲と比較するとアルバムにトラッキングされるのには微妙な違和感がある。やはり他のライターの感覚が入っているせいかもしれない。
#6のタイトさとは対照的に、#9『Divided』は極楽な南部カントリーの明るさを前面に出した、古典的なパーティサウンドの側面も持ち合わせたホンキィ・トンキィなトラックだ。
単なる50〜60年代サウンドの焼き直しにならないのは、サザンフィーリングたっぷりのギターが加えられているからだろう。それにしても、こういったスピードに頼らずに元気印を醸し出す曲を持ってくるのは上手な構成だ。全体に重くなり勝ちなサザンロックやブルースの性格が強いアルバムの清涼剤的なナンバーでもあるだろう。
◆熱唱、#4『Cry Like A Baby』とセンチメンタルなバラード#7『Afraid Of The Dark』
Tucson Simpsonのスケールの大きさと普遍性をポップなロックナンバー達以上に伝えるのが、この2曲のバラードだ。
いかにもサザンロックバンドという事を誇るように、ジックリしたテンポとリズムでパワフルに歌いあげられる#4『Cry Like A Baby』。その悲しげなメロディは、Hootieの大ヒット曲『Let Her Cry』をダブらせるくらいの懐の深さがある。
スライド、アクースティックの弦、そして目立たないがアンサンブルをカッチリと支えているオルガンの音色。
時に透明感を伴い、伸びやかにそして熱く歌うGrahamのリードに重なるKevin Kilgore、Bill FrazierそしてSamのバックコーラス。特にラストブリッジ部分での掛け合いは、さり気なく魂が篭っている。
南部の大地を表現するようなおおらかさでは#4に及ばないが、ボトルネック弦の泣きや、切ないハーモニカ、そして覚束ないキーボードの微妙な音色等を骨肉にした#7『Afraid Of The Dark』も心に染み入るバラードである。
特にインタープレイのギターソロ以降からエンドまでの盛り上がりは、#4よりも壮大でエモーショナルに聴こえる。
ラストのしめやかな引きは情感が溢れている。
どちらも素晴らしいバラードであり、ルーツロックとか南部ロックという地域性を越えて、Heartland Rockの王道感覚を兼ね備えている風がある。
極端にルーツ的な土着に拘らない、素直で暖かいメロディメイキングが齎した福音だろう。
この2曲のバラードは、#1や#3に劣らず、Tucson Simpsonのポップ性を代表する良質なトラックだ。
◆メンフィスのクラブバンドに留まらず
1999年に、Graham Perryを中心に結成された、Tucson Simpson。メンバーの全員がソングライターとしての経験があるという、才能に恵まれたバンドである。
デビューEPのリリース時からCMJやロック系のラジオ局に注目を浴びていた事もあってか、2002年に発売された「Hot Town」は、テネシー州はメンフィスのクラブバンドとしては破格の評価を得ている。
2003年からはAmazon.comを始めとした複数のウェブ・ストアでも取り扱いを受けるようになり、入手はそれ程困難ではないという、インディバンドとしては追い風の状況にある。
デビューEPや、彼らの『Bottle Of Pain』トラッキングされたインディバンドのコンピレーションアルバム「Buzzlighter #4」も彼らのオフィシャルサイトで入手が可能なのは言うまでも無い。
「Hot Town」を録音中にメンバーの一人が急逝するというアクシデントに襲われたが、見事にフルアルバムをロールアウトさせているその熱意も凄いと思う。
現在は、定期的にメンフィスやアラバマ州にてライヴ活動を行っているようだが、これから先、方向性さえ誤らなければだが、第二のHootieやEdwin McCain、そしてSister Hazelのようにメジャーに昇格できるポテンシャルを十分に有するユニットだと思う。
次のフルレングスが勝負だと思うので、是非頑張って欲しいものだ。
その前に、この「Hot Town」を購入して、彼らの評判の底上げに貢献する事を忘れずに行って欲しいものだ。この拙文を読まれた方全てに。
最後に今一度。この駄文を、Sam Plumleeに捧げる。
(2004.3.9.執筆 / 4.10.加筆訂正及び掲載)

 60 Cycle Hum / Steel Rodeo (2003)
60 Cycle Hum / Steel Rodeo (2003)