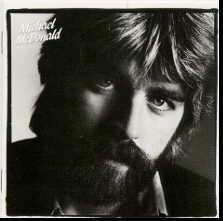 That’s What It Takes / Michael McDonald (1982)
That’s What It Takes / Michael McDonald (1982)
A.O.R. ★★★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★☆
Contemporary ★★★★☆
このジャケットを見て、某音楽番組を思い出す80年代洋楽ファンはかなり多いのではないだろうか。あの司会者の後ろに数週に渡ってこのジャケットが展示されていたのが印象深い。さて、Doobie Brothersをロックバンドから変革した張本人としてロックファンからかなり評判が悪いこともあるし、反対にアーバン・ロックやフュージョン・ロックそしてAOR好きには評判が良いこともあるMichael McDonaldが前述の「麻薬兄弟」を81年に解散した後に出されたソロ・第一弾がこのアルバムである。正直、これ以降の彼のソロ作品は非常に駄作が多い。特に3rdアルバムの『Take It To The Heart』は目一杯打ち込みを活用して非常にリズムが気持ち悪いアルバムであるし、最新作の『Blue Obsesion』では、元々R&Bに傾倒がある人ではあるが、くどいくらいに安っぽい黒人R&B風のアルバムをリリースしてくれて、踏みつけて割りたくなった。最悪の駄作である。ロックの要素が微塵も聴こえない。思わず彼の名前を私的にマイケル・馬鹿ドナルドに変更した上、フェイヴァリット・アーティストから外させて戴いた。30年近く駄作のなかったSteve Winwoodも今のところの最新アルバム『Junction Seven』でもろにR&Bアルバムを作成し、遂に駄作を進呈してくれたように、私はブラックミュージック・シーンに溢れている打ち込みやループやシークエンサーを使った音がオルタナ・ヘヴィネス以上に大嫌いである。それらの音を纏めてブースターをくっつけて太陽に放り込んでやりたい、全く。という感じで、このアルバム以降は駄作率が5割という高打率を誇り、残りのアルバムも良作の域を出ない創作活動しかしていない人であるが、このアルバムは間違いなく名盤である。2ndの『No Looking Back』と4thの『Blink Of Eye』は良作であるが、個人的贔屓が入り過ぎているようなので殿堂入りはしていない。もっとも、このレヴュー自体が独断と偏見のみによって構成されているのだが(笑)、さすがにこの人のアルバムはどんなに駄作でも自分にとっては名作、という評価はしていないつもりである。兎にも角にも、この邦題「思慕(ワン・ウェイ・ハート)」(何で??)は80年代の特に前半において大流行したAORの金字塔的作品であるのは間違いないだろう。セールス的にも全米第6位を記録し、軽くプラチナディスクに認定され300万枚以上は★がついていたように記憶する。ヒットシングルは全米第4位まで上昇した『I Keep Forgetin’(Every Time You’re Near』(妹のMaureen McDonaldのヴォーカルがフューチャーされている)だが、このR&B風のいかにもアーバン・ソウル風のナンバーより良い曲は沢山あるので、もう1曲の中ヒット#4『I Gotta Try』(Kenny Logginsとの共作でケニーも歌っている)が確か50位前後と、たった2曲というのは正直意外である。当時も最低あと1枚はシングル・カットしてくると想像していたのだが・・・まあAORの面目躍如というところだろうか。ところで、本邦ではAORをAdult Oriented Rockと間違った解釈がなされて久しい。ライナーで卑しくもそれで飯を食べている人まで平気で間違えを犯しているのは噴飯ものである。AOR本来の使われ方はAlbum Oriented Rockが正しい。つまりアルバム全体のクオリティで聴かせようとする方向性のこと。日本でのAORと同意義なのはAdult Contemporaryであり、このHPでのContemporaryはそれを表している。話題休閑。
今、各曲のクレジットを見ると、当時の西海岸シーンのセッション・ミュージシャンや腕利きスタジオミュージシャンが揃い踏みといった感が強く、非常に懐かしい。Edgar Winter(Sax)、Greg Phillinganes(Piano)、Steve Lukather(Guitar)、Steve Gadd(Drums)、Dean Parks(Guitar)、Willie Weeks(Bass)、Jeff Porcaro(Drums)、Tom Scott(Lyricon)、Ted Templeman(Per)と主な名前を挙げるだけで、AOR系やAdult ContemporaryにR&B界のプロフェショナルが見られ、通な方はニヤリとしそうだし、半分以上は少しでも80年代のAORを齧った経験があれば知っている名前が見つかると思う。無論、マイケルはピアノ他、シンセやフェンダー・ローズを弾いている。後年、打ち込み系の音だけになりがちな彼であるが、ここではシンセサウンドを活用しながらきっちりアクースティックな音出しの醍醐味も味あわせてくれる。ヴォーカルに至ってはこれ程特徴のある声も少ないだろう。聴けば一撃で認識できる、甘く、そして胸の奥にギュンとせつなさが湧いてくるような優しいヴォイスは誰にも真似が出来ないだろう。その声に乗せて始まる、まさにアダルト・ソフトロックの最高傑作である#1『Playin’ By The Rules』は筆者の永遠のフェイヴァリットナンバー。甘いエドガー・ウィンターのサックスと後半でグンと盛り上げてくれるストリングス!!最高。#3『Love Lies』のDoobie時代を思い起こさせるような粋なリズムとタイトさは格好が良過ぎる。#9の『Losin’ End』はご存知だとは思うがDoobie Brothersで披露したナンバーのリテイク。こちらはメロウなスローナンバーでレゲエ調の明るい元曲とは全く違った魅力がある。メロウさでいえばハイトーンな歌を聴かせてくれる#5『I Can Let Go』がベストだろうけど。#7のタイトル曲と#8『No Such Luck』はミディアムなロックナンバーでこれはシングルにして欲しかった。そしてシンセのリフが鳥肌モノのラスト#10の
『Believe In It』は後半でのジャジーでポップな展開がユニークである。#6の『That’s Why』は勿論大好きでドラマティックなミディアム・バラード。まさに捨て曲なし。80年代のAORを代表する名盤である。マイケル・マクドナルドの稀有なヴォーカルを充分に活かしたロック・アルバムである。これ以降の彼はロック&ポップより黒いサイドへの影響が強くて、ロックなアーティストとは言い難いかもしれない。ドゥービー時代の交代直後に見せた、ロックとアーバン系の融合は解散間際には随分色あせてしまっていたが、このアルバムで『Takin’ It To The Street』の頃のロックな姿勢を復活させている。まあ、あくまで程度の問題であってハードロック・ファンにはきっと受けが悪いかもしれないが、このアルバムの良さがわからへんのはジャリな証拠やから、10年経ったら是非聴いてみよし。良さがきっと分かる。
このアルバムを初めて聴いてからもはや19年が過ぎた。が未だにメディアをアナログからCDへと変えて、しっかりと愛聴晩として私のコレクションに鎮座している。きっと死ぬまで聴き続けるアルバムであると思う。それにしても、90年代からのリスナーの世代諸君にはこの名盤がリリースした当時、現世に存在してなかった方も多いと思うと、無駄に歳を重ねてきたような気がしてならない、春の宵である。 (2001.4.6)
 Into The Fire / Bryan Adams (1987)
Into The Fire / Bryan Adams (1987)
Industrial ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★★
またも80年代アルバムの登場である。80’sの逆襲・・・・というと実にチープな本邦の、カントリーミュージックへの冒涜以外の何物でもない、大馬鹿企画アルバムと重なるので・・・・・ああ、また危険な発言をしている。(汗)
という訳で!!!ロック・オヤヂの回顧録的レヴューが続く。メジャーなアーティストをレヴューしないと誰も突っ込んでくれないという危機感からでは断じてない。当時の年齢と現在を比較してひたすら若さを懐かしがるのは30歳を越えてしまった故の理由無き僻みであろうか。うう、卑近な存在が自覚され更に自己嫌悪。(自爆)
さてさてさて、やはりBryan Adamsでどのアルバムが好きなのか?という問いには、前作のポップで元気の良く、若さに任せて突っ走るロックアルバムである『Reckless』が一番という意見と、もろにデフ・レパード風のサウンドでハード且つキャッチーに引っ張る大ヒットシングル『(Everything I Do)I Do It For You』を擁した『Waking Up The Neighbors』へのどちらかの支持が主流なようである。その大ヒットアルバム2枚に挟まれるような形でリリースされた、この『Into The Fire』がベストという方には殆ど出会っていない。(涙)確かに『無謀』でのポップ&ロックの楽しさも『安眠妨害』での派手さや煌びやかさには全く無縁の重く、そして暗い曲が多い。歌詞も明らかなラヴ・ソングというのは1曲も無い。明らかに社会問題や内面の葛藤に焦点を当てた一昔前でいう「社会派アルバム」的な歌が殆どである。尤もブライアンがあからさまにメッセージ・ソングを狙って書き上げたというより、彼自身のメジャーシーンでの大成功の後に様々に思うところがあっての葛藤や苦悩が浮き上がってきたように感じるのは私だけだろうか?そう、ソング・ライティングといえば、非常に重要な問題がある。とはいえ、このアルバムでは全く顕在化していないので、このアルバム以降のブライアン・アダムスについてのことである。シンガーとてデヴューする以前から、ソング・ライティングコンビとして様々なアーティストにも曲を提供してきた(38 SpecialやRod Stewartのヒット曲等多数)長年の盟友Jim Vallanceとこれ以降のアルバムで袂を分かってしまうのだ。現在のブライアンは決して才能溢れるアーティストとは言い難い、というより既にピークを過ぎたか才能が枯渇したかに見える、ざっかけない言い方だが。この次のアルバムはジョン・マット・ラングの手腕により力技でアルバムを創り上げることができたが−もちろん映画「ロビン・フッド」の主題歌の相乗効果も忘れてはならない。勢いに乗るというファクターの絡みではあるが−『18 Til I Die』から向こう、年齢の成熟をもアルバムに表現できなくなり、嘗てのヒットソングを歌うことでツアーをするという凋落が著しいアーティストに成り下がってしまった。全てとは言えないがこの才能溢れるライターとのコンビ解消が彼の最悪のターニング・ポイントになってしまったように思えてならない。おっと、貶してばかりではレヴューに(しかも名盤の)はならない。こちらのアルバムの話に戻そう。まず、確かに前後のアルバムに比較すると地味でハード(『近所迷惑』の力みが入り過ぎた感じとは違い、自然な感じの重さである。)で、重い。が、アレンジは非常に素晴らしい。特に『Reckless』では活かされていなかったピアノやオルガンの音が乾いたアレンジで効果的な味付けをしている。ギターにしてもドラム・ベースのリズムセクションも勢いだけで演奏していた前作に比べて、きっちりとしたバンドとして纏まりのある聴き飽きのこない、深い演奏を展開している。メンバーはまさに全盛期のラインナップのBryan Adams Bandで、Keith(G)、Tommy(Key)−このアルバムでは準メンバーだが−、Dave(B)、Mickey(Dr)に前述のJimがピアノで参加し、他はキーボードにサポートプレイヤーが3人程参加している。録音場所はブライアンの自宅を使用したとの事で、じっくりとプライヴェートに練り上げられたであろうサウンドが詰まったアルバムである。Top10ヒットを量産した前作と異なり、ヒットは#1のかなり重苦しいヘヴィなロックの『Heat Of The Night』が全米第6位になっている他は#9の『Hearts On Fire』が同28位を記録したのみ、とセールス的にはアルバムと共に大して振るわなかった。が、ヒット云々以前にアルバムとしての出来と言い、非常に示唆的で問題提起を多く含有している歌詞といい、成熟した男臭さがムンムンに漂っていてボクシングのボディブローのようにじわじわと聴けば聴くほどに味がある。92年にカナダのハイウェイをナイアガラの滝へとドライブした。丁度薄暮がただよう時間帯で、その時ラジオから流れてきた#10のバラード『Home Again』を聴いた時、グッときて滅茶苦茶寂しくなった。故郷を離れた望郷の歌詞が異国で暮らす自分にオーヴァーラップして。#5の『Native Son』や#8の『Rememberance Day』(英連邦の英霊追悼の記念日。やはりカナダ人である、彼は。亜米利加では名称が違うしね。)もメロディは地味だが味わい深いバラードで、歌詞も素晴らしい。ラヴ・ソングとは無縁の硬派な詩の世界という感じだろう。#2の『Into The Fire』や#4の『Another Day』や特にお気に入りの#6『Only The Strong Survive』といったヘヴィなロック・チューンはポップな即効性はないが、とても印象に残るアレンジと演奏であり、胃の奥にずっしりと記憶されている。
ブライアンのイメージとして強い「明るさ」とか「元気の良さ」は殆ど皆無といってよい。かろうじて#9がやや明るいか。だが、こういったメッセージ色の強いアルバムに普遍の要素である力みや肩の力が入りすぎといった印象は希薄で、むしろ自然にペンが走り、曲が出来上がり、自然に身体が動いて演奏をしているように思えてならない。
このように素晴らしいアルバムを出して大人のシンガーに大きく一歩を踏み出したブライアン・アダムスであったが、なまじ90年代初めに大ヒットに恵まれたために道を踏み外してしまったのではないかと考えている。『Reckless』の大ブレイクの後には、このようなしっかりとした浮ついてないアルバムを作れたのだから、その辺が非常に不可思議である。
Bryan Adamsがまたこのようなアルバムを出すか、はたまたデヴューの頃の甘いロックに帰ってくる日があるだろうか?彼も40の声を聴いているはずだ。これから3ピースになったバンドは何処へ向かうのだろう。 (2001.4.7)
 Crowman / The Scarecrows (2000)
Crowman / The Scarecrows (2000)
Roots ★★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Southern&Country ★★★★☆
完全無欠なサザン・ロックの豪快さとアメリカン・ルーツの埃っぽさが同居する、これぞまさにアメリカン・ルーツ&オルタナ・カントリーの王道!と諸手を挙げて賞賛したい・・・・・・・のであるが実は彼らはアメリカのバンドではなかったりするのである。あまつさえ、大英帝国連邦に所属する英語圏の国家出身でもない。話題が逸れることをお断りして恒例の(そうか?)愚痴を展開するが、United Kingdomをイギリスと呼ぶのだけはやめれ!!そのような国家は存在しない。もはや本邦は鎖国をして紅毛人ののことを阿蘭陀語の発音から「えげれす」と呼称する時代ではないのだ。せめてUKと言って欲しい。大体大英帝国の住民にとってはイングランドもスコットランドもウェールズも別物なんやし。一緒くたにしてイングランドとか言うと、プライドが高い(だけやけど。・・・ヲイ)彼らは絶対遠まわしに「英国的」に文句を言うだろう。これが好かん。と、今回は意外に早く終わったので、彼らの出身国に話を戻そう。日本では北欧ポップスというジャンルが独自に市場を形成しているが、(米国では殆ど顧みられないけどね。北欧メタルもEurope以来メジャーではさっぱりやし。)そのスカンジナヴィアン諸国の最北の国、ノルウェーのバンドなのである。これは少々信じ難い。一度聴いて戴ければ明確に私の驚きがお分かり戴けると思うのだが、どう考えてもアメリカ南部のクラブでライヴを演っていそうな音以外の何物でもない。99年辺りから北欧ルーツも素晴らしいバンドを排出し始める。LoosegoatsやBenといった良質なバンドが台頭を始めている。とはいえ、ややオルタナ臭さが珠に傷のLoosegoatsや少々ポップさが不足のBenよりこの『案山子ズ』の方が筆者のストライクゾーンど真ん中である。ここまでに『Waiting For A Wonder』(1995)、『Scarecrows』(1997)、そして今作の『烏男』(ショッ●ーの改造人間みたいやね。)とコンスタントにアルバムをリリースしている。が、一番の問題は彼らが非英語圏のバンドであるということである。1stなどは歌は英語であるが、インナーのクレジットとかはノルウェー語(多分)であるし、2ndも前に倣え。VocalはVokalと書かれ、DrumsはTrommerであるし。それはそれで良いのだが、問題は情報収集である。彼らについて書かれた記事の多くが英語で無いので、正直、読めない。(涙)オフィシャルサイトが昨年開設したが、あまり充実したバイオグラフィーが置いてない。歌の歌詞を置いてくれるのは非常に嬉しいが、それならしっかりインナーに記載して欲しいというのが率直な希望である。言い訳になるが、ために彼らの経歴やパーソナルについては全くといって知識がない。現在、バンドへ送るメールを書いて、このレヴューの記載と同時に送るつもりである。「あんさん達の経歴教えておくれやす。」と。という理由故にバンドについては殆ど現段階では言及できない。まあ、個人の情報力などたかが知れているので、ご容赦願いたい。
まず、前2作について簡単に触れておくが、はっきり言って野暮ったいカントリー・ロックである。勿論、筆者は野暮ったい土臭さは大好きである。が、この2作は良作であったが私的名盤とまでには到達しないアルバムであった。ちなみに入手順は2nd→1st→3rdである。偶然LAで手に入れたのがこのバンドとの出会いであった。当時はバンドのメンバーの名前が米国風でなく、てっきり阿蘭陀か丁抹(デンマークね)のバンドと思っていた。独逸語は当時勉強していたので少々読めた。今は錆び付いて公園の隅で雨に濡れているが。(謎)そうそう、前2作の評価であった。シングル的にはすばらしいルーツ・ロックソングもトラッキングされているのだが、やはり豪快さやロックのダイナミズムにやや欠けており、手放しで賞賛するには少々首を捻るという出来であった。しかしながらレヴューを書くにあたり、1stから聴いていくと、ヴォーカル、メロディ、演奏共に順調に成長していっている過程が顕著で、バンドとして正常進化を遂げているようで喜ばしいものがある。一時は6人編成であったこともあるがメンバーがアルバム毎に交代しているので、1stから残っているオリジナル・メンバーはBjØrn OrØnvik(L.Vocal&Guitar)、Dagfinn Leinum(Guitar&Mandolin)、Erik Svendsgård(Bass)にMagne Morken(Drums)の4人である。現在はそこにバンジョーやヴァイリン奏者のSvein Grostadを加えた5ピース編成になっており、サポートメンバーも加えて7人くらいでツアーをしているとのことである。是非彼らのライヴを体験してみたいものである。サウンド的にはピアノやオルガンのフューチャーがかなり減少していて鍵盤至上主義の筆者にはそこが瑕疵ではあるが、それは瑣末な問題であろう。アメリカ南部の豪快で疾走感溢れるサザン・ロック系のサウンドに大きく歩み寄っている。つまりロックテイストが大幅に上昇したということである。まだまだメインストリーム(何時のかは押して知るべし。Georgia SatellitesやHootei & The Blowfishに初期のBlack Crowsのような音と考えてくれれば満点。)系のメロディほどすっきりした埃っぽさ(?)の段階までは至らずに、カントリー・テイストがしっかりと自己主張をしているが、そこがまた魅力である。魅力といえば、かなり荒削りでパワフルに変質した開き直ったような演奏と、アルバムを重ねるたびに腹の底から湧きあがってくるようなパワー一杯のBjØrnのヴォーカルがガンガンと南部のスピーディなロック中毒の私の琴線を揺さぶってくれる。#1のおどろおどろしいアメリカン・ゴシック調のヴァイオリンのブリッジである『Crowman』から曲間の切れ目無しでストレートなロック『Read Between The Lies』、前向きな夢追いな歌の『Rainbow’s End』、極上のロカビリー風バラードの『Sleeping In The Shadow』までのメドレー的な流れでつかみはばっちグリグリ(シーラカンス級絶滅語)である。これを嫌いになるサザン・ロックファンは皆無だろう。以降の曲もカントリー的陽気さとリズムを基本としながらも、実にパワフルでロックしている。あと少しスマートになれば2000年にダニー・コチマーのサポートでメジャーシーンへ踊り出たアトランタの新人Buffalo Nickelのような感じになるだろうが、このダサさと荒削りさは彼らの大事な武器になると思うので、是非とも失わないでもらいたい。個人的にお気に入りは#5『For All The Wrong Reason』や#8『Ghostville』そして#11『The Way It Stinks』のフックの効いたミディアムなロック・チューンであるし、#13の『Empty Cradle』の寂莫たる歌詞であるアクースティックなレイド・バックナンバーも捨て難い。#14の『Red Eye Mission』はゴリゴリの力押しサザン・ナンバーの権化のようで、どう考えても彼らがノルウェーのバンドとは思えない。しかし、スカンジナヴィアン・ポップの煌びやかでモダンなイメージの強い北欧からこのような良質にアメリカン・ルーツに敬意を払ったバンドが出て来たのは驚きである。まさに「欧州事情は奇々怪々也」(といっても総辞職はせえへんけど・・・・・。ああ、歴史オタクなネタやなあ。社会科が好きなヒトやったら分かってくれはるわね?)といったとこだろうか。オフィシャル・サイトによると、既に4枚目のアルバムを彼らは視野に入れているようで、アルバムに収録するに余る曲が完成しているそうである。意外に早く彼らの新作が聴けそうな予感に期待ひとしおである。2000年に過去の2枚もリイシューされたらしいので、メジャーな通販サイトで比較的入手がし易くなったようである。この機会に聴いてみては如何だろうか。 (2001.4.7.)
 Dizzy Up The Girl / The Goo Goo Dolls (1998)
Dizzy Up The Girl / The Goo Goo Dolls (1998)
Alternative ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Contemporary ★★★
ポップになったらダメ、という意見を私は心から軽蔑する。とここまで筆を進めて(って未だ何も書いてへんど)あまりにレヴューが画一化してきた気がするので、今回は異色の「実録シリーズ」(って連続モノにするんかい、おまい!?)をレヴューに代えたい。以前に某掲示板で披露したことがあるが、あちらはβ版ということで、こちらが正規ヴァージョンである。・・・・何ぼのもんじゃい?
あれは2000年の3月末日のことであった。当時筆者が在籍した会社は社会の底辺たる運送屋であり、引越のピークであるその日は朝から単身パックの荷物を積んで、下ろして運び込んで、廃材を持ち帰り、更に積み込んで配達という、海岸に砂の城を作るような作業を朝から夕方まで続けていた。で、16時過ぎ。さすがに厭世観の虜になった筆者はMr.ドー■ツで摂れなかった昼食を摂取するという英断を下し、作業ズボンに迷彩バンダナという『いなせ』な(阿呆)格好で店内に突入を敢行。バッタもの飲茶セットをオーダーし更にドーナツを注文という離れ業をこなし独り席についた。この恐怖はそこから始まったのだった・・・・。(ナレーションは水曜スペ●ャルの田中氏の声で。)
店内には有線放送やろか、ロックが流れている。まずはGin Blossomsの『Follow You Down』や。うむ、掴みはオケやね。そやけど、これホンマに飲茶かいな。わてかて香港や中国へ行った訳やあらへんけど北米の中華街で食べまくったヤムチャとは別モノやなあ。と、次はCounting Crowsの『Angel Of The Silences』が流れてくる。おお、エエ趣味やんか、選曲のセンスはバッチバッチ。
と隣の姦しい集団がこの曲について話しているようや。どーも、日本語を使い慣れてへんようで異星人の言葉のようでわかりにくい。格好も何故か金髪や茶髪の毛髪に、地獄の針の山でも楽々歩けそうな底の厚いブーツを履いている。ドブ浚いにでも行くんやろか?オマケに化粧が、そのまんま大気圏突入してもザクのように燃え尽きる心配が無いくらい、コーティングが完璧。・・・・低レヴェルで大気圏突入が可能なんはガン★ムくらいと思うてたねんけど、侮り難し。最初は海外の方々や思うてたけど、どーやら日本人のようである。(註:以下の会話はとてもしらふではタイプでけんので、筆者がそれなりに現代語訳している。)
●女性其の壱
「ねえ、この曲、結構格好良いね。」
●女性其の弐
「うんうん、何てヒトの曲かなあ?」
●女性其の参
「知らないよ〜。●●×(筆者知らず。恐らく日本の原始細胞クラスの真似バンドと推察。)かな〜?」
「あああ、教えてやりたいわあ。どないしょ??」
ここで熟考。自分→顔が怖い+シチーボーイ(?)とはかけ離れた服装+無精髭面=結論
推察:このようなオヤヂが「この曲はねえ」と声をかけて来た場合。客観視して
(1)怪しげな宗教の勧誘と勘違いされる
(2)年甲斐も無くナンパが目的と勘違いされる
(3)公序良俗に反するので表現を控えるが犯罪行為に直結する予備行動と思われる
(4)単なる危ないヤツ(えっ)と判断されそそくさと席を立たれる
・・・・・・・・・。・・・・・・・・・・。何故こうもネガティヴなポシビリティしか思い浮かばんのやあ〜〜〜!!
あああ、どないしょ、どないしょ〜〜、と内面で煩悶を続けるうちに曲はGoo Goo Dollsの初のTop20ヒットであり、出世作の『Name』に変わる。
●女性其の壱
「あ、これ知ってる。確かシティ・オブ・エンジェルスの歌だ。」(答え:違います。)
●女性其の弐
「あれ、ニコラス・ケイジとメグ・ライアンだったよね〜。」(それはエエから間違いに気づけ。)
●女性其の壱
「あれ?違ったかな・・・・。もう少し@♀∞(意味不明−恐らくドラマティックというニュアンスやろ)な曲だった
気がする。」
(そうそう、ちゃうねんで。)
●女性其の参
「どーでもいいよ〜。それよりこれ誰だっけ?レンタルしたい。」(どーでも良くないし、第一買え!)
●女性其の弐
「う〜ん、何だっけ?」
(あああ、おぢさんは知っておるねんで!!教えたい〜〜〜!!)
●女性其の弐
「確か、何とかドールズだったじゃん?」(うむ、後一歩。)
●女性其の壱
「そうだった、そう。確か可愛い名前〜〜。」
心の中でガッツポーズを取るわし。(よっしゃ!!ニアピン賞。世界丸ごとハウ●ッチ(古))
●女性其の弐
「う〜んとね・・・・・」
(うむうむ。)
●女性其の弐
「そう、ブーブードールズ!!」
(ちゅどーん!!!)内心の破壊音
●女性其の参
「そうそう、可愛いよね〜。」
ガツン!!!テーブルに沈没。痛ひ・・・・・。
そうか?ホンマか?お前ら鶏もどきの懐かしのアニメキャラファンか!?
所詮その程度なんやね〜〜〜〜(爆涙)
ということで、The Goo Goo Dollsのことは諸兄の印象に深く残ったと推察する。
以上でレヴュー終わり!!!
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
い、石を投げるなああ〜〜!!!
真面目にレヴューして欲しいという声があればちゃんと追加します・・・・・。フォローになってへんわい!!
 Bad English / Bad English (1989)
Bad English / Bad English (1989)
Industrial ★★★★★
Pop ★★★☆
Hard ★★★★
Progressive ★★★
しかし、John Waiteというヴォーカリストはハード・ロックでもアダルト・コンテンポラリーなロックでもフレキサブルに歌いこなす人である。Babysやこのバンド、Bad English以外にもソロ活動として7枚程アルバムを残しているが、ソロアルバムでのスタイルはヴォーカル・ロックであるのが大半で、このような産業ロック系の所謂プログレ・ハード・ポップ的な感じのアルバムは皆無に近い。むしろ、いかにもLAメタルスタイルの長髪ルックスが最初にビデオ・クリップを見た時は異様に映った。どちらかというと短髪でハンサムな人というイメージが強かったから。その長髪でないソロ活動で顕著なアルバムは、やはり1984年の『No Brakes』だろう。そこから全米No.1ヒットになったミディアム・バラードの『Missing You』をユニークなプロモーション・ビデオと共に記憶しているMTV世代は結構多いのではと想像する。が、焦点は本作であるインダストリアル・ハードロックの『Bad English』であるから、彼のソロ作についてはこれ以上の言及は避けておく。聴いたことが無くて興味のある方は、このようなハードさを求めて聴くと肩透かしを食らうこと請け合いであろう。
さて、Journeyのファンには今更バンドのバイオグラフィーを述べるまでも無いだろう。Babysより日本ではJourneyの方が遥かにファンが多いと想像するので、敢えて、Journeyを先に持ってきたが、無論Babysファンにとってもなじみの深いバンドであるだろう。ハードロック界では頻繁に起こるが、まあ2つのヴェテラン・グループが解散後合体したバンドである。この辺は説明の必要はないと思う。JourneyからNeal Schon(Guitar)とJonathan Cain(Keyboard)−尤も彼は以前Babysにも在籍していたのであるが−が、BabysからJohnとRicky Phillips(Bass)が、ドラムには元Wild DogsのDeen Castronovoが集まった。Deenは昨年リリースの出さなければ良かったアルバム『Arraival』にJourneyのドラマーとして参加している。このくらいでバンドの紹介は充分であると考える。Journey関連の日本盤を買えば更にこの辺のファミリーのツリーが説明されていると思うので。
Journeyからの仲良しコンビ以外にとってはこのアルバムが最大にセールス的に成功したアルバムであろう。全米No.1ヒットとなった必殺パワー・バラードの#5『When I See You Smile』を始め、(後はあやふやである)同第5位の#8『Price Of Love』(ビデオ・クリップがDon Henley『Boys Of Summer』の二番煎じやったなあ)にTop20ヒットになったバラードの#3『Possession』(筆者は#8よりこちらの方がヒットすると想像していたので、意外に伸びなかったので不思議であった。アクースティックなリフが好きなのだが。)そして60位前後のスマッシュ・ヒットでとどまったハード・ロックチューンの#2『Heaven Is A 4 Letter Word』と#4『Forget Me Not』と、合計5曲がTop100に食い込んでいる。また、全米でヒットこそしなかったが欧州や日本ではシングルになった#1『Best Of What I Got』も忘れてはいけないだろう。この曲はシルベスタ・スタローンとカート・ラッセル競演のB級アクション・コメディ映画の「Tango And Cash」(邦題:デッド・フォール)の主題歌である。この映画、非常にチープだがエンターテイメントとしては素直に楽しめるので、結構好きだったりする。スタローンのセリフで「Ranbo Is Pussy」には爆笑した。兎に角、このいかにも産業ロック・ハードチューンで始まるこのアルバムには初っ端からパンチがある。ジョン・ウェイトも久しく聴かせなかった力強い唄い方を披露してくれている。演奏に関しては名うての技巧派揃いなので、何ら賞賛を与える必要も無いだろう。上記したヒット・ナンバーの他にも当時のシーンでならきっとヒットしたであろう曲が更に数曲ある。#11の激烈な盛り上がりを見せるキャッチーな『The Restless One』や#13の美しいアクースティックなポップチューンの『Don’t Walk Away』もそうだし、#10の『Lay Down』他殆どのハード・チューンが#2や#4がヒットしたならきっとヒットした曲ばかりであろう。しかしながら、この後の2nd『Backlash』で大きくセールス的にこのプロジェクトバンドは躓く。1991年という時代は確かにハードロックやメタルが売れなくなり、グランジ旋風が起き始めたチョーク・ポイントであるが、それ以上に内容が酷かったと思う。実際殆ど聴いていないので深い印象はないが、UKハード的な重いサウンドを主体のアルバムだったように記憶している。好意的に解釈すれば、売れ筋のアリーナ・ロックの路線を放棄して、アーティスティックな道に走ったと捉えられるかもしれないが、個人的には1stが予想外に売れてしまったので、変に硬派を気取ったとしか考えられない。実際、グループ内でも色々と方向性の食い違いがあったようで、間も無くツアーも殆ど敢行せずBad Englishは解散する。メインのソングライターである、ニール・ショーンとジョン・ウェイト、そしてジョナサン・ケインとの歩調がずれ出したかららしい。ソフト路線を強調した2人に対してもっとハードさを追求したかったニールが三行半を叩きつけたようである。実際に翌年の92年にニールはHardlineというグループを組む。が、メロディアスという点ではBad Englishの2枚目より上であると思うのだが・・・・・。
兎に角、この1枚目のリリースの時点では後年の不協和音はなく、がっちりと纏まったバンドとしての作品を届けてくれている。時代性か、かなり装飾過多のメロディアス・ハードであるので、シンプルなロックを好む人には受け入れられないかもしれない。実際、現在私がこのアルバムを聴いて買うかというと、正直疑問である。(汗)とはいえ、この分厚い音世界はやはり80年代の産業ロックアルバムの締めくくり的な1枚として、自分では名盤に位置している。
近年、数多の新人が特に欧州から輩出されているが、あまり素晴らしいバンドには出会わない。メロディアスを哀愁漂うマイナーな音と勘違いして解釈しているバンドばかりの気がする。(あるいは筆者の感覚がずれているのかも。こちらの方が正解のような・・・・・。)そんな不満をクラッシックなロックアルバムで解消するのにこの1枚はうってつけである。些か後ろ向きではあるが。(汗)
分かりやすさとキャッチーなメロディはナチュラル・人工的サウンドと対極的でも、究極的にはアメリカンロックのエッセンスであるのだから、その要素を嫌いにならない限り、このようなこってりハードロックも細々と新作を探して年月を重ねていきそうである。 (2001.4.7)

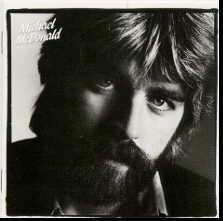 That’s What It Takes / Michael McDonald (1982)
That’s What It Takes / Michael McDonald (1982) Into The Fire / Bryan Adams (1987)
Into The Fire / Bryan Adams (1987)
 Dizzy Up The Girl / The Goo Goo Dolls (1998)
Dizzy Up The Girl / The Goo Goo Dolls (1998) Bad English / Bad English (1989)
Bad English / Bad English (1989)