 Back In The High Life / Steve Winwood (1986)
Back In The High Life / Steve Winwood (1986)Adult Contemporary ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Blue−Eyed Soul ★☆
 Back In The High Life / Steve Winwood (1986)
Back In The High Life / Steve Winwood (1986)
Adult Contemporary ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Blue−Eyed Soul ★☆
恐らく、80年代では一番聴いたアルバムであると思う。レコードからテープにダビングし、CDで再発された瞬間に買い替え,猿のように聴いた。彼はThe Spencer Davis Group、Blind FaithやPower Houseでのエリック・クラプトンとの活動から(無論、まだ筆者は生まれていないのでリアルタイムではないが)Traffic、Third Worldに至るまで全て素晴らしい創作活動をしている。勿論、沢山のロック史に残る名盤を残しているのはいうまでもない。さすがにツトム山下のGoの音源だけは持っていないが。(汗)しかしながら、やはりリアルタイムで聴き始めたためか、ソロ活動のアルバムの方がやはり心に残るし、大好きである。基本的に打ち込みダメな筆者が何故か、Steve Winwoodの初期の打ち込みオンリーなアルバムがとてつもなく大好きなのは自身にも分からないが、やはりこの素晴らしく艶のあるヴォーカルであろうか。それに絶妙のメロディ−キャッチーでいてそれで複雑なコード進行と奥行きのある。まさに天才であると断言する。というかそれ以上の表現方法が見つからない。英連邦で偉大なヴォーカリストを挙げろ、と言われればまず、彼WinwoodとElton JohnそしてVan Morrisonを真っ先に持ってくる。・・・・・独断過ぎるかも。(笑)まあ、独断ではあるが実際スティーヴの声はやはり素晴らしいと思う。良く通り、適度に澄んでいて、それでいて清流の淵に見られるような紺青の色合いのような深みがある。アップテンポからミディアム、スロー・ナンバーまで過不足無く歌い分けるその幅広さ。特にヴァースの末尾でグンと伸ばして歌う歌唱力の凄さは、気持ち良いを通り越して鳥肌モノである。黒人系のヴォーカルのようにパワーで押しまくるソウルフルな強引さは無いのに、非常に吸引力を包括した力強さがある。ハイトーン系のヴォーカリストに顕著な美しさと流麗さで勝負という、一枚だけの看板ではなく流麗さの中にも様々な魅力が内在し単なるハイトーンというより、やはり透明度は高いが遠くから見ると濃緑色や紺碧に見える山上湖のようなずっしりとした重量感が兼ね備わっている。かなり抽象的で恐縮だが、彼の成層圏まで届きそうな伸びやかなヴォーカルは、非常に表現が困難である。実際に聴いて頂くしかあるまい。付け加えておくと最近のロックシーンで顕著な、やや私的に食傷気味なハスキーヴォイスとは全く異なった次元のヴォーカルである。まさに二つとない特徴の声質であると思う。このような素晴らしいヴォーカリストがそろそろ出てきて欲しいものである。また、英国英語発音が顕著なのも特色であると思う。これは特別に魅力という訳ではない、余談の部類であるが。さて、あまり語彙が豊富でないため、くどくどと彼のヴォイスを誉めても繰り返しになりそうなので、兎に角、アルバムの内容について触れていこうと思う。ここのレヴューを読まれる方なら、彼については一通りの知識をお持ちであると考えるので、スティーヴの過去の栄光については触れるまでもないと思う。一応、ソロ活動に限って簡単にリリース歴を追ってみると、『Steve
Winwood』(1977年リリース/全米第22位)からソロ活動をスタートさせて、『Arc Of A Diver』(1980年/7位)、『Talking Back To The Night』(1982年/47位)、そして本作が1986年リリースで最高位が全米3位である。グラミー賞を2部門獲得しロングセラーとなったのはまだ記憶している方も多いと想像する。そして1988年に再びグラミーアルバムとなった名作『Roll With It』(全米第1位)をリリースする。この頃がセールス的にはキャリア最高であった。1990年には『Refugees Of The Heart』(全米第23位)をリリースしたが、やや売れ行きが落ちる。シングルヒットも1曲だけに留まっているし。但し内容は素晴らしいアルバムであるとは思うが。この間にベストアルバム的な『Chronicles』を1987年に(ヒットソングだけでない選曲が激シブ)リリースし、過去の小ヒットに留まった曲を含め、3曲をリミックスしてリテイクし2曲のTop100ヒットを生んでいる。そして全てのキャリアを網羅する63曲入りのアンソロジーボックスの『The Finer Things』(日本未発売)を1995年に出している。1994年にはTrafficのほぼ20年ぶりになる新作『Far From Home』も発表しているが、これはかつでのTrafficの名盤と比較すると良作の範疇でしかないだろう。そして只今最新作となる『Janction 7』を1997年に出したのだが、これは彼のキャリアを汚染する程の単なるチープなR&B駄作アルバムであるので、耳が穢れること請け合いなため、絶対に聴かない方が良い。何故こんな駄作を作ったか97年にLAのアリーナでライヴを見た時、襲撃を敢行して尋ねようと思っていたのだが、彼に握手されて短い会話をしただけで舞い上がってしまい、覚えているのはあのハンサムだった伊達男が皺だらけになり、白髪が非常に目立っていたことだけであった。年月は平等に凡人にも天才にも降り積もることを痛感したカリフォルニア駐在の想い出である。但し、声は全く変わらずに伸びやかであった。話題休閑。
さて、Steve Winwoodのアルバムでどれが一番好きか、と考えると非常に選択に困る。ソロ活動にだけ限定しても、良質なブルー・アイド・ソウルの魅力満載の1st作も捨て難いし、ワンマンレコーディングでマルチプレイヤー振りを発揮している2・3作目の無機質なクールさも大好きであるが、やはりこの『Back In The High Life』と『Roll With It』の2枚−これまでスタジオに篭って練り上げてきた精密なステンドグラスのようなサウンドから決別して、緻密ながらバンド・アンサンブルを取り入れた、文字通り「ハイな暮らしに戻った」かのような元気な音創りをやはり選ぶ。何と言っても、ラジオで初めて聴いた1stシングルである『Higher Love』を聴いてぶっ飛んだ時の印象は15年を経た今でも鮮烈である。先に述べたが、前2作でどちらかというとビートを効かせたロックというより、シンセサイザーを多重に織り込んだドラムマシンの冷静なリズムが彼の当時のイメージであったからだ。当時、Hall & Oates Bandから正式にBryan Adams BandのメンバーとなったドラマーのMickey Curryのシンバルをジャム・セッション的にテストトラックで叩いてもらったら、Steveが大変気に入りそのままトラックインしたという、小粋なスティックの連打で幕を開けるこの曲は、確かに格好良かったが、まさか全米No.1シングルになり、グラミーを獲得するとは全く思わなかった。チャカ・カーンのソウルフルなバック・ヴォーカルと多彩なホーン・セクションの後半の掛け合いが素晴らしいこの曲は、現在の筆者の嗜好では聴かないようなナンバーであるかもしれないが、やはりスティーヴの声はインプレッシヴである。吹っ切れたような明るさが目立つ歌い方である。そして、次の#2『Take It As It Comes』もパワフルなホーンが映えるロック・チューンで、フェイドアウト前の最終パートではSteveが弾きまくるギターソロが滅茶苦茶グルーヴィである。何故、この曲をシングルにしなかったか不思議なくらい大好きなナンバーである。全て素晴らしい曲が詰まった本作でもベスト3に入る出来であると思う。次の#3『Freedom Overspill』は基本的にはあまり好み出ないファンクっぽいナンバーであるが、EaglesのJoe Walshがぶっ叩くドカンと破裂するような重たいスライド・ギターとこれまた力強い管弦パートが不思議な吸引力を持っている。3枚目のシングルとしてカットされ、Top20ヒットになっている。シニカルな歌詞も非常にツボだ。そして、名曲中の名曲である『Back In The High Life Again』。これはもはや語るべき言葉がない。彼にしてはマンドリンを絡めた、イナタ臭いナンバーで、ピアノとストリングスが織り成す、お日様の臭いのような優しさが、心を暖かくしてくれる魔法のような効果を十全に発揮してくれている。バグパイプのようなスコットランド風のシンセソロがやはり彼のルーツはブリティッシュにあると納得させてくれるナンバーである。私的生涯Top10バラードである。ライヴでも最後の「Oh ,I’ll Be Back」は常に観客全員で大合唱であった。そしてこれまたヒットシングル(全米第7位)の変調を多用したキャッチーなポップナンバーの#5『The Finer Things』。Steveの弾く、ムーグシンセソロが鍵盤オタクとしては卒倒モノである。非常にキーボードがオーヴァダブされたナンバーであるが、こってりして食傷気味にならないナンバーに仕上げているのはまさに技有りだ。Winwoodがお気に入りの曲#6『Wake Me Upon Judgement Day』はアナログではなくシンセホーンを使用したR&Bというかライト・ファンクな小気味の良いナンバーである。歌詞が非常に意味深であると思う。これまた歌詞を必死に覚えた。というより、このアルバムの歌は空でも歌える程に聴き込んでいるので、この曲に限ったことではないが。(笑)当時の売れっ子セッションギタリスト/プロデューサーであったNile Rodgersのカッティング・ギターがまさに職人芸である。そして、#3でも参加しているJoe Walshとの共作である#7『Split Decision』はこれまた私的に大好きなナンバー。ジョー・ウォルシュの泥臭いギターとスティーヴ・ウィンウッドのオルガンの掛け合いがとても格好良い。特にジョーのソロパートでのギター弾きまくりは圧巻である。聴くたびに鳥肌が立つくらい見事な演奏が楽しめる。そしてわずか8曲しか入っていないこのアルバムの最後のナンバーは過去の名曲『Dust』や『There’s A River』を彷彿とさせるようなしっとりした『My Loves Leavin’』である。スティーヴの伸びやかなヴォーカルが堪能できる。彼のソロ作はどれも最後のトラックが名曲である。しかし、1986年には8曲くらいが平均であったのに2〜3年で10曲入りは当たり前に、現在は70分を越える15曲入りのアルバムが全く珍しくなくなっている。確かに沢山の曲が1枚のアルバムで聴けるのは歓迎したいが、中弛みのする冗長的なアルバムが何と増えたことか。名盤というアルバムは概して曲数が少なめであることが多いような印象がある。やはり10曲くらいできっちり纏めて、散漫なアルバムや本来入れなくても良いという感のトラックを外した、凝縮した「名盤」を聴きたいと思うこの頃である。これまた横道な話題であるが、このアルバムに関してはもう少し曲が欲しかった。まあ、そう思わせるところが名盤たる所以であるとは考えられるが。
分かる方には最初からお見通しであるとは思うが、このホーム・ページの各パートのタイトルは全てSteve Winwoodの曲から取っている。タイトルのAgainst A Windは無論異なるけど。(笑)当初はメイン・タイトルも『Back In The High Life Again』にしようとも考慮したのだが、一応英国ロックに分類されそうなアルバムであるため、断腸の想いで変更した。このことから、いかに著者がWinwoodフリークか想像が可能であろう。(笑)もうこのアルバム無しでは私的80年代の音楽生活は語れない、否Steve Winwood抜きではである。それにしても最近全く表に出てこない彼、元々寡作な人であるのであまり心配はしていないが、ぼちぼち腰を上げて欲しいものである。
まあ、このアルバムを貶すような輩は管理人的密着系プロレス技のフルコースを用意してあるし、聴いていないのであれば直ぐに購入して100回は聴かねばこれに反則技のオンパレードが加わること請け合いである。兎に角、聴け。イッツ・オブリゲーションね。(何故) (2001.5.7)
 A Place To Call Home / Joey Tempest (1995)
A Place To Call Home / Joey Tempest (1995)
Adult Contemporary ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Roots&Acustic ★★★★
これまでに幾人かの方にこのアルバムの音源を紹介して、かなり好評を戴いたが、彼が元北欧メタルグループのリード・ヴォーカリストと教えてあげると一様に驚かれたようである。ましてやあの、80年代に日本でも馬鹿売れしたグループ『Europe』のヴォーカリストと知ると更にショックなようであった。というより気が付かない方が大半であったようだ。そう、あの『The Final Countdown』や『Carrie』のTop10シングルや『Cherokee』に『Rock The Night』のヒットシングルを引っさげて、アルバムFinal Countdownが全米でも大ブレイクしたバンドEuropeのヴォーカリストが彼、Joey Tempestなのである。当節流行りの産業ロックの権化のような分厚いサウンドに乗せて、長髪を振り乱してハイトーンなキーを目一杯使ってシャウトしていたヴォーカリストで、ヒット当時は体育祭のBGMなどにも使われた、『The Final Countdown』のプロモ・ビデオを覚えている80’sファンは多いのではないだろうか。あのJourneyを大ブレイクさせた仕掛け人のプロデューサーコンビのKevin ElsonとRon Nevisonをして、スティーヴ・ペリー以来の天才ハードロックバラードシンガーと言わしめた歌い手である。1991年にEuropeとしての現在最後のスタジオ録音アルバム『Prisoners In Paradise』をリリースしてから約4年のブランク(Prisoners In Paradiseのツアーを1993年まで敢行していたので、活動としては2年半のブランクになるか)を経て届けられたアルバムが本作『A Place To Call Home』なのだが、まず最初に、Europe的な音を期待して聴くとカルチャー・ショックを受けること間違いなしと警告しておこう。(笑)というか別のヴォーカリストと考えて聴いて戴いた方が精神衛生上宜しいとも考える。想像するに、Joey Tempestの名前で即座にEuropeを連想できるような音楽好事家がこのアルバムを買う動機は、多かれ少なかれEurope的なサウンドを求めてのことであるのではないかと思う。期待するEurope的な部分が、初期のドラマティックで大仰な北欧メタルの典型のようなナンバー『Seven Doors Hotel』であるか、または『Final Countdown』のアメリカナイズされたハードロックなのかは別の議論が存在すると推察するけど、このアルバムの音楽性とは全く関係ないので、それは遠くへ置いておこう。ともかく、ハードロックやヘヴィメタルとは全く縁のない音のアルバムをJoeyは製作した。実のところ、筆者も産業ロック的なEuropeを一面として期待を込めて購入した1人である。その期待というか予想を見事に外してくれたのがこのアルバムである。非常にポップで、しかもアクースティック・ギターを大幅にフューチャーしたアダルトな雰囲気の漂うロックアルバムになっている。第一に特筆するべきは彼の歌い方とヴォーカルである。Europe時代は高音部をガンガンに使い尽くして、コブシをブンブン振り回した歌唱法を見せていた彼であるが、このアルバムでは殆どシャウトヴォーカルをせずに、リラックスして歌っている。またハイトーンを縦横無尽に駆使したヴォーカルは全く別人のように変貌し、伸びやかに自然体な音域を丁寧に歌っている。先にこのアルバムの購入要素を一面として記したが、もう一面はJoey Tempestのヴォーカルが大好物のハイトーン・ヴォイスであった故に、当初は別人のように感じてしまったが、各パートのフレーズの尻でグンという牽引力を見せる歌い廻しは、やはりジョーイの歌であることを見せてくれるし、どちらかというとこのナチュラルなスタイルのヴォーカルの方が飽きが来なくて良いようにも感じてしまう、何回も聴いているうちに。完全に余談になるのだが、このアルバム実に頻繁に中古屋で見かけるのだが、Europe的な音を期待してスカされたハードロック好事家達が手放した故ではないかと邪推してしまう。(笑)このような良質なポップ・ロックアルバムが中古市場でのリピート性が高いのが嘆かわしいので。・・・・・・失礼。しかし、そう思うのも仕方ないくらいのEuropeとは全く色合いの異なるサウンドが詰まったアルバムなのである。Europeがこってりステーキ定食なら、こちらの『A Place To Call Home』はオフクロの味−日替わり定食であろうか。兎に角、聴き飽きが来ないアルバムになっている。Europeのスターダムでの活動に疲れて「僕達には自分達の居場所が欲しい=A Place To Call Home」と考えた末、グループを解散させたジョーイ・テンペストが悠悠自適の生活を送りながら振り返ったのは「本当に好きな音を探す」ことだったようで−この辺りの経緯は日本盤のライナーノーツに詳しいので参照して戴けると幸いである−Jackson Brown、Tom Petty、Bob DylanやBilly Joelといったアーティストの音源を聴き始めて、更にVan MorrisonやThe Waterboysといった英国サウンドにもインスパイアされて完成したのがこのアルバムという次第である。「シンガー・ソング・ライターが自分の場所」と考えて作成したというだけあって、ソングオリエンテッドの傾向が非常に強い。ヘヴィなドライヴ・ロックで牽引しようという意図は微塵も感じられない。まず、#1の『We Come Alive』からして欧州ポップスというかスカンジナヴィアン・ポップの(彼スゥエーデン人だしね)コマーシャルさを代表したようなポップ・ロックチューンである。コーラスで絡んでくるゴスペルのような女性ヴォーカルといい、この段階でEuropeとは全く方向性が異なることが音速で分かる。冒頭のカウントはスゥエーデン語なのだろう、きっと。#2の美しいピアノのリフから始まる、ミディアムナンバー『Under The Influence』でアダルト・ロックへの傾倒は確固たるものと理解ができる。女性ヴォーカルとストリングスの導入でドラマティックな盛り上がりを見せるが、あくまでもポップソングとしてのそれであり、メタル的な激烈さはなく、ただひたすら優しい。#3のタイトルソングは前述したアメリカン・ロックとポップスのヴェテラン達の影響が顕著な素晴らしいロックチューンで、さりげないアーシーさとアクースティックさが魅力である。歌詞もEuropeの成功からスローダウンして自分を振り返るまでを書き綴ったような哲学的な歌である。このアルバムのベストトラックの1つである。まさにJoeyの『A Place To Call Home』な気持ちを代弁したような曲だ。#4『Preasure And Pain』はアメリカ南部音楽の影響が垣間見れるブルージーな味のあるナンバー。そして#5のストリングスをフューチャーしたバラード『Elsewhere』や英国ポップス風の明るい#6『Lord Of The Manor』では嘗ての歌唱法の残り香が漂う感の強いハイトーンヴォイスが堪能できる。このくらいまで聴かないと彼が同姓の別人と疑いたくなるくらい、前半の曲は以前とヴォーカルスタイルが異なる。そしてこれまたアメリカンロックの醍醐味を凝縮したようなドライヴ感覚溢れる傑作#7『Don’t Go Changing Me』は文句なし。、スピーディでフックの利いた、どちらかというと欧州的なポップスの哀愁味もそこはかとなく感じられる2曲、変調が多用されたキャッチーな#8『Harder To Leave A Friend Than A Lover』と疾走感のある#9『Right To Respect』を経て、これまた非常にポップでジェントリーでスピーディな名曲(歌詞も非常に心温まるメッセージソングである。まさに名曲。)#10『Always A Friend Of Mine』、ハモンドオルガンの流れやストリングスの入れ方はBilly Joelのようなポップセンスを思い起こさせる。#3と並んで、このアルバムのベストトラックであると思う。更に力強いVan Morrisonあたりが使いそうなゴスペルのような女性ヴォーカルとシンセで始まるミディアムバラード#11『How Come You’re Not Dead Yet?』が続き、ポップ性の攻撃は休むことなく続く。そして#13の日本盤ボーナスのタイトルトラックのアクースティック・ライヴヴァージョンも佳曲であるが、実質ラストナンバーの#12『For My Country』のストリングスとアクースティックギターのみで綴られるバラードは、これまた故郷をペィトリオット的に歌い上げた曲であるが、真に込められているものは、やはり「自分の場所」への憧憬ではないかと想像している。20歳になる前からオン・ザ・ロードの生活を続けたJoey Tempestが求めたのが自分らしさであり、自分の安らげる空間であったのだろう。このアルバムで彼は初めてシンガーとして歌を創り、そして歌えたと感じられてならない。HR/HMファンには物足りない甘いアルバムであるかもしれないが、ポップ&ロックとしては極上の1枚である。意外に広まっていないアルバムであるので−日本盤もリリースされたのに−是非良質なヴォーカル・ロックが好みなリスナーには聴いて欲しい1枚である。Joeyはこのアルバムで「自分の場所」を見つけたらしい。4年後の1999年に欧州ルーツとトラッド色を取り入れた2ndソロ『Azalea Place』をリリースする。彼はそのままソロ活動を続けて欲しいと願う人である。私自身の「A Place To Call Home」は未だ見つからないのだが・・・・。
(2001.5.11)
 Lucid / Freddy Jones Band (1997)
Lucid / Freddy Jones Band (1997)
Roots ★★★☆
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Blues ★★★
大変残念なニュースが届いた。今回紹介するFreddy Jones Bandが、録音中という6thアルバムのレコーディングを終えると時をほぼ同じくして、解散したとのことである。
しかも、その6枚目のアルバムはリリースされることなくオクラ入りになるらしい。デヴュー当時からの1ファンとして忸怩たる思いである。本当に残念である。
さて、このFreddy Jones Band、本国アメリカではそれなりに名前の通ったバンドであると思うが、日本では全くといって構わない位地名度が低い。海外メディアではDave Matthews BandやAllman Brothers Bandを引き合いに出されて紹介されるバンドであり、ライヴアルバムと再発インディ・デヴューアルバムを加えると、50万枚以上のセールスをトータルで記録している。
1枚あたり10万枚という数字はそれ程悪くないとは思うが、彼らの素晴らしい音楽性を考えると少々物足りない気がするのが正直な感想であるが。少なくともFreddy Jones Band(以下FJB)はDave Matthews Bandのようなジャズへの傾倒は少ないし、Allman Brothers Bandより現代的ロックのテイストが強いと思う。勿論、基本はややホワイトブルースのカラーが入ったルーツロックであるし、比較に挙げられる2つのバンドとの共通の、アメリカン・トラッドに敬意を払った魅力はしっかりと有しているのは間違いないが。
結成は1992年のシカゴである。まず、この全米第三の都市の周辺のクラブ・サーキットをこなしつつセルフリリース・アルバム『Freddy Jones Band』を自主制作する。(このアルバムは1995年に所属先となったCaplicorn Recordsから再発売され、日の目を見ている。ライヴトラックがボーナスとして収録されている。)
バンドメンバーは結成時から解散まで基本的に変化していない。
Marty Lloyd(L.Vocal&Guitars)、Wayne Healy(L.Vocal&Guitars)、Simon Horrocks(Drums&Mandolin&Guitars)と兄弟であるJim Bonaccorsi(Bass)、Rob Bonaccorsi(Vocals&L.Guitar&Slide&Mandolin)、そして中心人物のFreddy Jonesと書きたいのだが、実はFreddy Jonesなる人物はメンバーに入っていないし、ゲストとして参加している訳でもない。
バンド編成時に考えられた架空のメンバーの名前がFreddy Jonesなのである。
つまり先に挙げた5名のクゥインテット編成なバンドなのである。
「突出したリーダーシップを取る人間が勝手にバンドを引っ張らないように、皆で活動をしたいバンドにしたかったからフディ・ジョーンズという想像上の人物をバンド名にしたのさ。」というようなコメントをMarty Lloydさんから伺ったが、確かに突出した才能のリーダーが牽引していくバンドではなかったように思える。
ソングライティングは単独で曲を創るのが2枚ヴォーカルのMartyとWayne、そしてドラムのSimonの3人であるが、残りの2人も積極的に曲作りに参加しているので、全体の割合はほぼ均等である。リードヴォーカルもWayneとMartyがこれまた殆ど半々に歌い分けている。(Robも1曲くらいは歌うが。)
お互いに才能を尊重し合い、良いアルバムを作り続けてきたのだが、何処かで歯車が狂うと意外と強烈なリーダーシップを取る人物のいないバンドは脆いものかもしれないと、今更ながらに思う。
さて、バンドの解散後のお話は後にするとして、ディスコグラフィーに戻ろう。1994年にFJBは実質的なデヴューアルバムである『Waiting For The Night』を発表する。この2ndアルバムからMartyの歌うルーツポップナンバーの『In A Daytime』がシカゴを中心としたAC系やアダルト・ロック系のラジオでかなりのヒットとなり、彼らの知名度を広げることになる。また、『The Puppet』や『One World』も頻繁にオンエアされ、アルバムも好セールスを記録する。
1995年にはオン・ザ・ロードの生活を綴ったかなりスローなブルース的色合いを増した『North Avenue Wake Up Call』をリリース。
余談だがこのタイトルのモデルとなったNorth Avenueは、シカゴ在住時筆者がけっこうドライブをした通りである。東洋人は殆ど住まない地域をぶち抜くストリートで治安の良い地域から悪い地域まで、長く続いており、シカゴの素顔が伺える通りである。
そして1997年にリリースされたのが本作、最後のスタジオ録音アルバムとなってしまった『Lucid』である。
これ以降に5枚目のアルバムであるベスト盤的ライヴアルバム『Mile High Night』を発表している。
前作である『North Avenue Wake Up Call』がロックチューンの殆どない、かなり渋いアルバムであったため、どのようなアルバムになるか少々不安が在ったのだが、どうしてどうして、2ndのポップセンスを持ち込み、更に磨き上げたキャッチーさと、かなりダイナミックな粘っこいロックチューンが顕在化し、素晴らしいルーツロックアルバムとなっている。
かなり爽やかな西海岸的なアプローチも伺えて、ブルージーな南部のロックのようなナンバーが並ぶ間に明るいナンバーが挿入される形になり、多彩なサウンドを楽しめる傑作となっている。勿論、基本はトラッド色の見えるルーツロックであるが。
1stラジオシングルとしてオンエアされた#1『Wonder』は珍しくハーモニーではなく、WayneとMartyがお互いのパートを歌い分ける形式のツイン・リードとなっている。シカゴ周辺のホワイト・ブルース的やや軽快ながら、うねるようなロックチューンである。このアルバムから大胆に取り入れられ始めた鍵盤類を一手に引き受けるChris Cameronのピアノとオルガンのブルージーな演奏も良い味を出している。
そして、アルバムの中でも1、2を争うキャッチーで爽やかなロックチューンである#2『Waiting On The Stone』がMartyの珍しくややハイトーンな音域を使った伸びやかなヴォーカルに乗って流れてくる。このアプローチは過去の彼らには見られなかったが、実に気持ちの良いチューンであり、ウエストコースト・ロックの好きな方には必聴である。
2枚目のラジオシングルとなった#3『Better Tomorrow』もオルガンとピアノがフューチャーされた、ややブルース的な色合いが垣間見れるナンバーであるが、佳曲である。Martyが本来のハスキーなシャガレ声を活かして歌っている。
続く#4のこれは非常に優しいミディアムなロックの『If I Could』はWayneのよく通るやや高い声がとても填る、これまた素晴らしい西海岸の香りのするトラック。後半でのギターソロとオルガンの掛け合いで盛り上がるパートは感動的である。
一転して#5『Blue Moon』ではキャッチーなラインを保ちながら泥臭い、ノイジーなギターが炸裂する彼らがライヴで得意とするブルース&トラッドナンバーが豪快に展開する。ここでもピアノが積極的に転がっているのが過去との違いであろう。サウンドに厚みが出来て、重厚な味わいのあるドライヴナンバーに仕上がっている。#6の『Mystic Buzz』も同様なシカゴ・ブルースロック的なメロディが顕著なナンバーであるが、Wayneの伸びやかなヴォーカルが清涼感を感じさせてくれる。このナンバーもオルガンの主張がかなり激しい。
#7の『She Said』はアクースティックなギターリフから展開していく地味なバラードタイプの曲であるが、これまた抜けるような透明感が見られ、次に2曲続くやや重めなブルースロックなナンバーの緩衝材のような感じがする。ちなみに#9のかなり黒っぽいホーンを導入したファンクナンバー『Come On Back』のヴォーカルは粘っこいRobの喉の独壇場である。彼のヴォーカルはChicagoの夭逝したテリー・キャスのような粘着度があり、あまりリードを取るとしつこくなるが1曲ならばインパクトを与える上で丁度良いと思う。
これまたB3がうねり、カッティング・ギタープレイとパーカッションのリズムがユニークな、ブルージーロック#10『C Minor Contribution』を経て、著者お薦めのナンバー#11『California』が来る。これは絶対に西海岸のバンドとしか思えないくらいの爽やかなコーラスとメロディが爆裂している。マンドリンのサニー・サイド的な明るいメロディも全く素晴らしい。Pocoや初期のEaglesが演奏しても全く違和感のないナンバーである。
そして、一転してハードなギターのリフが豪快にロックする、#12『Burning By』−最もハードなナンバーでサザンロック系のブルースというべきであろう曲でこのアルバムは幕を閉じる。
やはり根底にはシカゴエリアでポピュラーなホワイト・ブルースへの傾倒が感じられるが、オルタナ的ノイジーなゴミロックに走っていないので、ちゃんとロックとして聴けるし鑑賞に堪えられる。
Black Crowesのオルタナに媚びた最悪の重いだけの最新アルバムとは天と地の差があるだろう。
しっかりと方向性を持って、同じような音楽を続けるということは、「没進化」「守りに入っている」といった批評を受けやすい。が、常に「挑戦」という玉虫色の言霊を利用して、あちこちのジャンルに噛み付いて、酷評されたり、セールス的に失敗しても、「チャレンジした結果」という逃げ道を確保しているようにしか考えられないアーティストの姿勢よりどれだけ勇気がいるであろうか。
余程の才能がない限り、クロスオーヴァーしたジャンルへの浮気はロクな結果にはならない。「成功したアルバムの2番煎じはやりたくない」実に立派である。それ以外の方向性で成功すればの話であるが。
話がかなり逸れてしまったようである。あまりにも前述のBlack Crowsのアルバムが酷すぎてヒートアップしているようだが、好きなバンドが期待しない方向へ行ってしまうのが腹立たしいのは我儘であろうか。
ファンとしてはやはり意に添わないアルバムは酷評すべきであると信じているし、実践している。敵は増えるが。
しかしながら、解散である。バンドはMarty Lloydが中心となりBonaccorsi兄弟を加え、そして本作でキーボードを担当した準メンバーのChris CameronにドラマーのLarry
Beerという人が合流して、新たにMarty Lloyd Bandとして活動を開始している。新曲をDLして試聴したが、感覚的にはFJBとさほど変わらないような気がする。
Martyが「次のステップに進みたい」と考えて、バンドを脱退したのだから是非とも、更に上のレヴェルに達した作品を届けて貰いたいものである。残りの2名のソングライターの足取りは資料がなく不明である。
どのような形にしろ、良い曲を書いてきたバンドが分裂してしまったのは残念であるが、才能が拡散し、良質なバンドが増えると考えれば嬉しくならないこともない。
兎に角、当面はMarty Lloyd Bandの新譜待ちである。 (2001.5.14.)
 Chris Knight / Chris Knight (1998)
Chris Knight / Chris Knight (1998)
Roots ★★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Alt.Country ★★★★
待望の2ndアルバムが2001年の8月21日に発売される、しかもプロデューサーはDan Bairdということである。(未確認なので分かり次第ステイトします。YASさん、おおきに。)
兎に角、嬉しさの余り、急遽レヴューと相成った。まずは、この今年40歳を越える、「遅れて来た新人」について述べておこう。Chris Knightはアメリカ中部はケンタッキー州のスラウターズという人口わずか200人の街で生を受け、現在に至るまでその田舎町で暮らしている。楽器に触れたのは僅か3歳の時、「クリスマスプレゼントは何が欲しいの」と聴かれ「僕はオモチャのトラックや外に止まっているトラクターには興味がないんだ。」と答えてオモチャのギターを貰った時だそうである。
田舎町で兄弟に囲まれて育ちながら、彼の音楽環境は恵まれているとは言い難かった。聴いていた音楽はラジオから流れてくるJohnny Cashと叔母のブルースレコードコレクションだけだった。彼自身もバンドを結成するといった環境からは縁遠い生活を送る。
が、15歳になりハイ・スクールに進学した彼に出会いが訪れる。一番上の石炭採掘坑で働いていた兄がギターを購入したのだ。夜勤のシフトに入っていた兄は深夜から朝6時まで働き、酔っ払ってくだを巻いては、また深夜に仕事へ通い、クリスの手元にはコード表とギターが残された。彼はギターを手にとり友として、コードを毎夜なぞり始め、Jone Prineの曲を50曲くらいマスターしてしまったそうだ。
このように本格的に音楽に親しみ始めたChrisは友人や家族の前で演奏を披露する程度の音楽を楽しむ傍ら、西ケンタッキー大学に通い、農業学を専攻。しっかり単位を修めて卒業し、1989年から1994年までの6年間、彼は採掘後の土壌再生改良会社で勤め人となる。
「ケンタッキーの地表採掘法は広範な法律でありすぎて、書類仕事から石炭盗掘の罰則までカヴァーしなくてはならなかった。」と回顧するKnight氏は仕事に忙殺されながらも、歌を書き続けていた。
本格的なインスパイアを受けたのはラジオで流れていたSteve Earleの歌を聴いた時だそうである。「自分には歌に込めるメッセジーがある。一日の終わりに全身が綿のように疲労して、手の爪という爪が真っ黒に汚れひび割れている男たちの心の悲哀を、それを表現したい。」と思い立った彼は1992年にナッシュビルまで足を伸ばし、これまでインドアで曲を創ってきただけの私的な活動からライヴステージに立つトライを始める。
オーディションにパスした彼はブルーバード・カフェのショウで歌うようになる。その彼に目をつけたのがナッシュビル周辺でブルーグラスやカントリー系のアーティストをプロデュースしていた−本作も彼のプロデュースである−Frank
Liddellであった。
ChrisとFrankは意気投合し、ナッシュビル界隈でつるむようになる。が、ここで簡単にレコードデヴューとはならないのである。Chrisがプロとして音楽ビジネスに参入する気が全くなかったからだ。「僕は自分の仕事に立ち返ったし、仕事から幾つの未来が開けるなんて全く気にもしてなかった。音楽の世界へ飛び込もうと本気になったことはなかった。フランクは良き友人で在り続けたし、彼と歌うことは続けたけどね。それだけさ。」
傍ら、FrankはChrisにレコードを出すように説得を続けて、「レコードを出すこと」に同意させる。そしてBluewater
Musicにアプローチをしたが芳しい返事は返って来なかった。そこへMCA傘下のDecca
Records がオファーを持ち掛けた時、Frankはこの稀な才能を世に出したいということを第一義に考え、契約を締結し、漸くChris Knightのセルフタイトルが世に出ることとなったのである。
「リビングのソファに座って曲を書くことが最高。小説家のようにね。」
「曲を創るのに数年かかった。12曲を作るのはとても楽しかったが、楽しむことより曲を書く方に没頭したよ。」
「曲を創るとき、感性を刺激してくるのは人々の歴史−積み重ねてきた生活さ。特に恵まれた環境にない人達のね。特に多くを経験し、しがらみを断ち切ってきたタフな人達。例え過酷な状況に置かれても、何とか生き抜いている人々のお話さ。」
「僕にとって音楽とはリズムの付いた短い詩というより物語と人々なのさ。」
非常に真摯で真面目な、しかも内省的な文学青年を思わせるキャラクターではないだろうか。実際にライヴも、鬼気迫るとまではいかないが、実に落ち着いた、じわじわと終わった後で余韻が残るような演奏と歌がとても印象深いものがあったことを記憶している。
彼が歌う歌詞は、全て彼の語るように「人々の生活と内面を」題材としている。非常にさりげない心の機微や変化せずにたゆたう日常、そしてハードな生活に苦しむ孤独。詩人というより私小説家という趣がある。
さて、アルバムについて少々触れておきたい。プロデューサーは前述のFrank LiddellとGreg Droman(エンジニアとしてナッシュビルのカントリー系のインディアルバムで仕事をしている。)の共同プロデュース。
基本となるバンドのメンバーはChris Knight(Vocal&Guitars)にSteve Earleのアルバムにも参加しているRichard
Bennett(A.Guitars)、Kenny Greenburg(E.Guitar)と David Grissom(A.Guitar)−共にJoe
ElyやJohn Mellencampと仕事をしている−にドラマーのChad Cromwell(Neil Young、
Mark Knopfler、Jackson Brownの演奏をこなす)、更にベーシストにGlenn Wolf、オルガンにTony Harrelといった地味ではあるが、職人的なヴェテランが顔を揃えている。特筆すべきは、あのBuddy Millerが半分ほどのトラックでThanksとクレジットされていることである。資料がないので明確には言いかねるが、アレンジ等に何らかの寄与をしたのではなかろうか。推測の域を出ないが。
「本来はもっとアクースティックな感じにすべきだったのかもね。でも、僕は歌が歌としてあるために力強さを出来うる限り込めた。」
というクリスのコメントからも推し量れるが、基本をカントリー・ロックに置いた、実にレイドバック感覚溢れるアルバムであるが、アクースティックの流れるような美しさより、がっちりと大地に根を下ろしたような力強い、乾燥帯を突っ走るボロトラックのような乾いた駆動力が凛として存在する。
どちらかというとオルタナ・カントリーというよりはカントリー・ロックの分類に傾いたアルバムであるようには感じるが、決してカントリーにどっぷりという印象は受けない。やはり、ロックが底辺に存在するSteve Earleのようなルーツ・アルバムであると考えた方がしっくりくるだろう。
しかし、このセルフタイトル・アルバムはトラッド感覚満杯な、アコーディオンやグリーク・マンドリンのボゾキがパワフルなビートにうねるナンバー、#1『It Ain’t Easy Being Me』からスタートする。思わず、上半身をスゥイングさせてしまう程の気持ち良いグルーヴ感覚が堪らない。自分の行き場を失いかけた、行き場所を求道する男の歌だろうか。「自分自身で在り続けることは簡単じゃあない。」のっけから名曲で始まるアルバムはやはり印象が良くなりがちである。
が、続く曲が大したことなければがっくりくるのだが、次も素晴らしいルーツロック・チューンが続く。#2『Frame』はこのアルバムでも最もポップでスピーディなナンバーであろう。「Frame=冤罪」で人生を棒に振った田舎の男の物語が、ヤケクソ気味な回顧を代弁するように軽快に歌われる。
#3の『Bring The Harvest Home』は軽快なカントリータッチの明るい曲である。ロスで夢破れた男が歌う望郷の歌であるようだが、実はカリフォルニア周辺の砂漠化問題を暗喩していると思うのは考えすぎだろうか。
そして、ゆったりとしたアクースティックなバラードの#4『Something Changed』。時の移ろいと共に変化するもの、しない物、人生に、故郷に、人々・・・・・・。深い歌である。
ややうねるような南部ロック的アプローチを感じさせる#5『House And 90 Acres』を挟み、これまたレイドバック感がゆったりとしたリズムに誘ってくれる#6『Summer Of 75』が心地良い。歌詞は、もう赤面モノの甘い青春と失恋と初恋の歌であるからして、解説するまでもないだろう。兎に角、メロディも歌詞も甘酸っぱい。(笑)が、きっと誰もがこの歌には
ある種のシンクロニシティを覚えるのではないかと邪推するが。(爆)
次の#7『Run From Your Memory』も軽快なカントリー・ロックのリズムに乗せて、メランコリックな青春が炸裂する歌である。以上。
地味なロック・チューン#8を経て、最もハードエッジな展開を見せる#9『The Hammer Going Down』は、ラヴ・ソング。ストレートなラヴ・ソングである。この曲Chrisのはロックンロールな面が見れるかなりノイジーなトラックである。
#10の『The Band Is Playing Too Show』も力強いリズムが織り成すミディアム・ナンバーで、昔の恋を「いつまでも変わらない曲を演奏するミュージシャン」のライヴで懐古するような、これまたオトナ向けの曲である。
残りの2曲『The River’s Own』のパワフルな盛り上がりといい、しっとりとしたアクースティック・ギターのみで歌い上げられる『William』の困難に満ちた人生を送ってきたウィリアムに捧げるバラードも、兎に角味わい深い。特に前者の父から子へと受け継がれる「河」に仮託した土地への愛着と血の繋がりを歌った内容は、ドラマを見るような物語性がある。
かなりカントリー寄りの地味なアルバムであるが、是非、歌詞カードを追いながら、オトナに聴いて欲しいアルバムである。1曲毎に込められた歌の「ストーリー」を噛みしめれるのは、ヘヴィさをロックのステータスと勘違いしているようなリスナーには決して与えられない特権であると思う。
この飾り気のないメロディと真実溢れる歌を分かって頂ける方が1人でも増えるなら、駄文を苦心して書いた甲斐があるというものである。
冒頭にも述べているが、是非とも2001年8月の新譜は期待したい。 (2001.5.16.)
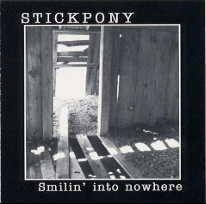 Smilin’ Into Nowhere / Stickpony (2000)
Smilin’ Into Nowhere / Stickpony (2000)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Punk ★★ Special Thanx:Mr. Brid Jones
ポップでロックでアーシーで、パンクの味付けもある。飛びぬけたキラー・シングルは探すのに苦心するかもしれないが、全ての曲が良作である。
と著者の弱点全てを満たしてくれるバンドにまた出会うことができた。残念ながら日本の音楽市場では決して受けることの無い音楽性=非常に良質なアメリカン・ロックである。完全にセルフ・リリースであるため、情報がなかなか入手できなかったので、思い切ってバンドのリーダーでソングライターであり、リード・ヴォーカリストでもあるBrid Jonesさんにメールで問い合わせをしたところ、大変親切なお返事を戴いて恐縮している。
今年2001年5月に新作アルバム(ライヴ録音と新曲入りのアルバム)をリリースしたので送ってくれるとオファーを戴いた。取り敢えずこのレヴューを見てもらうまでは安易に好意に甘える訳にもいかないので、お返事は保留している。
・・・・が、英語でレヴュー書いてへんので、どのみち彼には読めないんやから、困ったものである。(汗)
兎に角、少しでも多くのリスナーにこのアルバムを知って欲しくて筆を取った。誤解を受けないように前置きしておくが、Jones氏に情報を貰えなくても筆者はこのアルバムのレヴューを何らかの形で書いただろうし、親切を受けたからといってレヴューを持ち上げるほど善人ではない。(書いてて痛くなってきた・・・。)
まあ、兎にも角にも、レヴューを書かせるだけの魅力は絶対に内包するアルバムであることは確かである、と言いたいのであるが、回りくどかったか。
まず、全体的な印象から述べるが、ルーツでロックである。ブルーグラスやカントリー、アメリカーナというとやや範囲が広くなるが、要するにロックの魅力より、よりルーツ系に傾倒した新人バンドが多く見られる中に、ストレートなロックを基本としてアーシーな味付けをふんだんに施した彼らの音は、音楽的には表現に困るくらいにオーソドックスであるが、非常に特徴がある。
ルーツ音楽であるが、ロックの魅力が勝っているバンドという点で、筆者的なポイントは高いのである。あまりスローテンポ過ぎるルーツミュージックやレイドバックソングは好物であるが、一味足りないという嗜好の著者には、このロックとパンクの疾走感がしっかりと根付いているサウンドが素晴らしく嬉しいものである。
とはいえ、パワーパンクでガンガン爆走するという極端さは全く無く、あくまでもオーソドックスなカントリーっぽい要素を随所に見せるところが、これまたただのパンクバンドではないことを表している。
この辺の、いわゆる釣り合いがとても良く取れているバンドなのである。「地味」「独創性がない」と叩き切られそうな危険性がこの手の中庸バンドには常に付きまとうが、やはりキャッチーでアーシーという要素は私的に何物にも代え難く、地味&オーソドックス万歳と叫びたい。
繰り返すが、非常に基本なアメリカン・ロックの要素を均等に表現することに成功しているバンドである。煌びやかなパワー・ポップでもなく、渋いカントリー路線でもない、まさにロックとカントリーの融合がパンクという触媒を得て、顕現したような感じがする。ギターは適度にノイジーで、適度に埃っぽく、ベースやドラムのリズムセクションは地味ながら好サポートを怠らず、そしてやや甘めのBrid Jonesのこれまた中庸的な魅力のヴォーカルが紡ぎ出す、キャッチーのちアーシーで所によりカントリーでパンキッシュな音の世界。これというシングルは選出が難しいが、どの曲も非常にルーツに傾倒した良質なロックミュージックである。
敢えてお薦めを選ぶなら、やはり疾走感溢れるパンキッシュなオープニングのロックナンバー、#1『Small Town Hero』を選ぶだろうか。パンチの効いた、いかにもインディ・ロックという典型なチューンである。非常に分かり易くオーソドックスである。そこが素晴らしい。出だしから素晴らしいロックナンバーである。
#2『Last Letter Home』はややレイドバック感覚が前面に出された、しかしながら埃っぽさよりもロックとしての側面が強いミディアムなナンバーで、リズムを取るアクースティックギターが奇妙な土臭さを淡々と表現するナンバー。
続いてややルーツ・「ロック」寄りの感じがする#3『Stall Out』は疾走感が名乗りを挙げるほど速いナンバーでないが、ポップなメロディラインと爽やかなコーラスがパワフルな快感を与えてくれる佳曲。
彼らの魅力の一つである、アーシーなリズムがこれまた目立つ、#4『Climbing』はカントリーとまでは言い切れない、中庸的なロックナンバーで、ギターソロがバーバンド的なダサさを捻り出すところがダスティでユニークである。無論、とてもコマーシャルなチューンである。この曲のみカヴァー・ソングで1984年にCurt Kirkwoodというシンガーが歌っているそうだ。
結構ノイジーなギターが、カントリータッチのラインに絡んでくる、スロー・ミディアムナンバーである#5『Hurt Any Less』は所謂オルタナ・カントリーの典型とも言うべきだろうか。アクースティックギターのようなドブロギターのようにも、そしてバンジョーにも聴こえるマンドリンが耳に残る。
続く#6『Fellow Traveler』と#7『Nothing』はややヘヴィなリフが、彼らの出身地テキサス州に顕著なブルースの影響を垣間見せるように、うねりを泥臭く演出するナンバーであるが、良い意味でくどくない。この軽めなテイストが印象をやや弱くしている一因であるのは否めないが、やはり聴き易いのは筆者的に歓迎である。#10の『Worry』はよりヘヴィというか、ブルース的なうねりが顕著な曲で、テキサスのルーツシーンを想像できるような気もする。
ポップであり、流れるような堅めの音出しをしているマンドリンがカントリー的な色合いを強くする軽快なチューンの#8『Leviticus』は彼らを代表するようなトラックである。キャッチーなメロディがやはりダサさを美味く調理するのに役立っているだろう。やや乾いた感じのするパンクの傾倒も伺える曲である。
パンキッシュというと、#9の『88』はよりストレートにパンクテイストを味わえる。言うまでもないが、キャッチーでスピーディなルーツナンバーである。ややくぐもった歌い方を見せるところは、オルタナティヴの要素も垣間見れる。
最後の#11『Armageddon Song』はキャッチーであるが南部テイストの泥臭い重さが絶妙に挿入されたトラックである。この辺のロックチューンをさらりと演奏できるのは、とても貴重なバンドだと認識を新たにさせてくれる。
全体的に即効性にはやや欠けることは、賞賛しつつも自覚できる。良い意味でやはり地味である。
さて、グループのこれまでの活動を紹介しておこう。結成は1997年10月、テキサス州のカントリー・ロックのメッカ、オースティンにて。1998年3月から地元を中心にライヴ活動を開始する。ツアーはアメリカ中西部に2回しかしていないとのことで、やはりテキサスを中心にローカルでライヴを繰り返しているようだ。このアルバムのレコーディングで在籍していた
2名のメンバーGreg Wilson (Lead Guitar)はAlex Crumpに交代し、紅一点のメンバーStacey
Sperling (Drums)がNathan Fontenotにチェンジして、オリジナルメンバーの2名、Brit
Jones(L.Vocal&Guitar)と Steve MacDonnel(Bass&Vocals)と合わせて現在はカルテットで活動しているそうだ。
影響を受けた音楽はかなり幅広く、ロックからカントリー、パンクまで雑多である。Jonesが挙げているのは、Uncle Tupeloに Gram Parsonsや Waylon Jenningsといったカントリー系シンガーソング・ライターから、更にThe Replacements、The Hickoids、The Dead Kennedysに及び、「聞き齧っただけだよ」という Rolling Stonesや Small Facesに Derek and the Dominoesといった大御所まで。
彼らの音楽はこれらのアメリカンロック(英国産もあるけど)の良き部分を叩き台にして、自分達なりのオルタナ・カントリーの次世代としての方向性をスパイスにしたような感じであろうか。ストレートなロックとパンク的なある種の乱雑さにルーツの垢抜けなさが加わり、やはり出来上がったのはルーツ・ロックであった、というところだろう。
ベーシックな南部ルーツでしかもロックな音を求めるリスナーは聴いておいた方が良いと思う。
新譜がとても楽しみである。ところで、このレヴューを誰かStickponyに訳してくれるだろうか。多分無理だろう。(汗)
(2001.5.23.)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
