 �@�@�@Recovering�@The�@Satellites�@/�@Counting�@Crows�@�i1996�j
�@�@�@Recovering�@The�@Satellites�@/�@Counting�@Crows�@�i1996�j�@�@�@�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@�@Alternative�@����
 �@�@�@Recovering�@The�@Satellites�@/�@Counting�@Crows�@�i1996�j
�@�@�@Recovering�@The�@Satellites�@/�@Counting�@Crows�@�i1996�j
�@�@�@�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@�@Alternative�@����
�@�@Counting�@Crows�ɏo���Ȃ�������Ƃ��ɉ��y�Ƃ��������W���[�V�[���ɐ�]�����̂͂����Ƒ��������ɈႢ�Ȃ����낤�B�E�E�E�E�����Ƃ��A���̐摗��ɂȂ��������Ȃ̂�������Ȃ����B�i��j
�@�@1997�N�A���R�ɂ��ނ�̃A���o��������ɒ��Ăł������Ƃ������āA���C�������\���邱�Ƃ��ł����B
�@�@��HP���̃��C���E���|�[�g�ł���B�����ł��ނ�̃��C���̕��͋C���`����Ē�����K�����B
�@�@�Ȃ��A���̃��|�[�g��horiai����̃t�@���T�C�gSULLIVAN�@STREET�ɈȑO����ӂŌf�ڂ��Ē��������|�[�g�����M�C���������̂ł���B�@
�i1997�DOct�D�@Brockbustergrenhelen�@Pavilion�@At�@San�@Bernardino�@County�@In�@California�C
�@With�@Gigolo�@Aunts�@And�@The�@Wallflowers�j
�@�@���C�݂͓V���ł���B���C���Ă݂Ă��݂��݂Ɨ����ł����B�ƍߓs�s�A�ƃe���r�̔ԑg�̓��W�ɘ_����Los�@Angeles�ł��邪�A��Ȃ��Ƃ���ɂ͍s���Ȃ���Ηǂ��̂ł���B�i�n���́~���������I�I�j���Ȃ��Ƃ����̋��Z���Ă���Torrence�͎��Ɏ������X�����A���12�����炢�ɃW���M���O���Ă����Ȃ������B
�@�@�e�Ɋp�A�����͈����A�C��͗ǂ��B�̂�т肵�Ă���B�����ĉ����A���炩�̒��ڃA�[�e�B�X�g�̃��C�����w�ǖ����������ōs���Ă���I�I�E�E�E�E����������̘b�ł��邪�B
�@�@��͂�A������Ballroom��Disco�ACoffee�@House������Bar�̏����̃M�O�֑����^�Ԃ��Ƃ����������B�A���[�i�N���X�̃��C���͖w�Ǎs���ĂȂ������B�Ƃ�������D���ȃo���h�͑�̂ɂ����ăA���[�i�[�N���X�̃o���h�łȂ��Ƃ������Ƃ������ł��������炾���B
�@�@���A�������A�J�E���e�B���O�E�N���E�Y������A��Ђ̃X�p�j�b�V���n�p�[�g�^�C�}�[���炱�̘b�������A�u���I�I�I�v�Ƒ吺�������Ă��܂����B�₩�ɂ͐M�����Ȃ������B�c�A�[�̃X�P�W���[��������Ȃ��ƑS������Ȃ��Ȃ�o���h�������̂ɁA�܂����ނ�̃��C���������Ƃ́B
�@�@�����`�P�b�g�E�}�X�^�[�Ń`�P�b�g�w���B���R�d���͗��R�����ău�b�`�ł���B�i�j
�@�@���A�c�O�Ȃ���A�A���[�i�͊����B�A���[�i�̏������̐Ȃ���ɓ������͍̂K�^�������B���������ɔ���������Ȃ̂����A���Ԃׂ�������`�B�`�N�V���`�`�I
�@�@�Ƃ��낪�A�`�P�b�g�ɂ�San�@Bernardino�Ƃ������{�̘A���͑�����ł������̔��]���������ȁi�~���^���[�E�}�j�A��Ȃ��j�n�����B�ꏊ���ɕ�������Ȃ��LA���S����250�L���قǐ��ɂ��邻�����B
�@�@�J����7��������B�d���̒莞��6���B�Ԕ���Ă��Ԃ͂����邩��A���Ƃ�5���߂��ɂ͌���������ē����悤�ƁA��ח��Ƃ��̂悤�ɒ��ޑ��z�ɐ������B�������ACalifornia�̓������͋��B���w���z�����Ȃ����߁A�����ɐ������˂��h�����Ă���B���āAEagles��Glenn�@Frey�����N����A�����̂悤�ɋu�ɓo���Ēn�����ɒ��ޗ[�������Ă����Ƃ����G�s�\�[�h�ɃV���N��������̂������Ă��܂����肵���B
�@�@���āA����悭5���ɑގЂ������u�Ƃ�Â�v�����ߍ��B�l�N�^�C�A�X�[�c�p�̂܂܁A�Зp�Ԃ̃J���[���Łi�A���Ԃ�������G�ɂȂ邪���ꂪ�����ł��B�j�t���[�E�F�C��405��������10�����Ɍ������B
�@�@�������A�Â����Ă����I�ILA�_�E���^�E���̑�a�B���킶��Ƃ������ꂸ�A�d���Ȃ��̂ŗ[�H�Ɏd����Ă������n���o�[�K�ƃ`���`�[�Y�t���C��H�ׂC���C���B
�@�@�X��10�����͍x�O�̃x�b�h�^�E���ɋA���p�Ԃő�a�BLA���S����ꎞ�ԑ����Ă��̂�̂�^�]�B�A�����������������A���C���ɒx�ꂽ���Ȃ��̂ʼn䖝�B
�@�@Ontario�Ƃ����J�E���e�B���������肩��A������͍r���Ƃ�����������ڗ��悤�ɂȂ�B���߂ă��X�������ɐ������悤�ȓs�s�Ƃ������Ƃ���������B�����ACalifornia�̍r��ɑ��z�����݁A�邪���킶��ƈł̗̈���L���Ă��镗�i�͊���̍����ɂ���������Y�傳������̂����A���̎��͂Ђ�����ł��Ă����̂ŁA�w�NJ��z���Ȃ��B����U��Ԃ�ƁA���ɑf���炵�����R�̂P�R�}�ł������̂����B
�@�@���Ƃ����ǂ蒅���Ɗ���8�����ɂȂ��Ă����B���́ALA���烉�X���F�K�X�ɔ����Ă����������u�̊Ԃɂ�����O�X�e�[�W�B���͂͌��n������r��ƍ����i������j�B�l�Ƃ͑S���Ƃ����Ă悢�قǂȂ��B�������ꏊ�ł���B��x���ł��Ȃ�A��H���Ă����̂ŁA�S�͂œ��ꂷ��B���A�A�����J�l�͂����炩�Ȃ̂��A���C�Ȃ̂��A�N���}�����Ƃ��Ă��Ȃ��B�Ƃ������ז��ł���B�̂��̂��������Ƃނ����ŁA�z���}�B�ŁA�l�g��~�������O�i���Ɂu����v�ƁA�X�e�[�W�Ŋ������オ��B
�@�@�Ɓu���AJacob���o�Ă����I�B�v�ƒN����������ۂ�W�c�}���\���ɕω��B�ɒ[�Ȗ����ł���Ɨ�ÂɎv�����}���\���ɎQ�����Ă��鎩�����E�E�E�E�B
�@�@�K���AThe�@Wallflowers�̌����͂��Ȃ�x��āA21������n�܂����̂ŁA�[���Ɋ��\�ł����B���͈͂��|�I�ɔ��l�������B���F�l��⍕�l���ӊO�ɏ��Ȃ��BWallflowers�̃T�|�[�g��Counting�@Crows�L�[�{�[�f�B�X�g��Charles�@Gillingham���T�|�[�g�o�����đ劅�т𗁂тĂ����B
�@�@�����āAJacob�@Dylan���u�����A����̎���ɏo�Ԃ�����ˁB�v�Ƒޏꂵ����A��30�����������Ȃ����Ƃ��̏�Ȃ��B�ڂ���Ɍ�����Ɛ���ɔ�s�@�炵�����_���A�_�ł����ړ����Ă����B���ƂȂ��wDaylight�@Fading�x�̈�߁�uIt�fs�@Getting�@Cold�@In�@Carifolnia�v��������Ō�������ł���ƁA�Ɩ�����Ăɗ�����B
�@�@�^���ÂȃX�e�[�W�̏ォ��劽���Ɍ㉟�������悤�Ɂ�uGonna�@Get�@Back�@To�@Basics�v�ƃA���o���ƃc�A�[�̃^�C�g���ȁwRecovering�@The�@Satellites�x���������Ă���B�u�ԁA�ϋq�͑������B�߂��߂������F������������B���������ł���̂킩��Ȃ����т������A�͂����ς����������B�ƁA�W���P�b�g�̃V���[�e�B���O�X�^�[�̂悤�Ȑ��̊G���o�b�N�ɕ�����ł���B�����ł܂��劽���B���x��uWildest�@�C�@Wildest�@�CWildest�@People�v�̐���オ��ɓ������Ƃ���ŃX�e�[�W�����邭�Ȃ�B
�@�@���ɂ͑S���Â����Z�b�g�͂Ȃ��A�����W���P�b�g�̐��Ƃ����������̃}�[�N���o�b�N�Ɍ����Ă��邾���B���ɔނ�炵�����o�ł���B
�@�@�܂�������̗��B���H�[�J����Adam�̓J�V�~�A�n�̃{�^���_�E���̃V���c�ƃ`�m�p���Ƃ������ł����B��������ȑ̌^�Ƀ��Q�G�~���[�W�V�����̂悤�ȃw�A�X�^�C���i���Ƃ����̂��͒m��Ȃ����ǁj�ŁA�������ɂ��i�D�ǂ��Ƃ͂����Ȃ����A�}�C�N���E��ɋ�������Ԃ�Ȃ���X�e�[�W�����E�Ɉړ�����B
�@�@�����ɃO�����h�E�s�A�m�����邪�ACharles�͂��̍��ׂɂ����Ă���n�����hB3��e���B�����v�W�����ɁA�u���b�N�W�[���Y�A�ٌ�m�̂悤�Ȑ_�o�������Ȋ�Ɨǂ��}�b�`���ĉs�����͋C������B���������@���Ƃ̗��B
�@�@Ben��10���̐��C�݂̂��Ȃ蔧������C�̉��ł��s�V���c�ꖇ�ŁA�s�A�m�̉E�ׂɒ������h�����Z�b�g��@���B
�@�@�x�[�X��Mat��Charles�̏����O�ŁA�Â��ɒ�����U��u���u���ƃx�[�X��~���炷�B
�@�@���䍶���ɂ�Dan���A�E���ɂ�David�����ꂼ��G���A�R�ƃG���L�M�^�[�S���Ēe���Ă���BDan�͂��̃c�A�[�����������M�^���X�g�����A�c�C���M�^�[�̃n�[���j�[�͑f���炵���B
�@�@�Ђ�Ƃ�����T�|�[�g�Ƃ��ĉ�����Ă��邩�A�Ɗ��҂����y�_���E�X�e�B�[����}���h�����S����David�@Immergluck�i���F���݂͐��������o�[���肵�Ă���j�͌���ꂸ�A6�l�̃����o�[�݂̂̉��t���B
�@�@�A���o���̃^�C�g���Ȃ��I���ƁA�܂�����劽���B���A�ϋq�̐⋩���܂��~�܂ʂ����ɁA�Ԕ������ꂸ�ɃV���o���̉����V���b�V���ƒe�݁A�h���C���B�ȃM�^�[�̃��t������B�A�_�����҂��҂���ђ��˂āA�wAngles�@Of�@The�@Silences�x���X�^�[�g�B�A���o������̃t�@�[�X�g�E�V���O���ł���B
�@�@�O���̃A���[�i�ł͊��ɊJ�n5���Ń^�e�m����ԁB�F�_���X���n�߂���A�W�����v���n�߂�B��������������ƃ^�e�m���J�n�B���X�g�̃M�^�[�\�����A���o���Ɛ�����킸David���v���C���A�������������H�̖��ɕ����オ��B���̃M�^�[�E�\������D���Ȃ̂ł����������m�ł���B
�u�X�Q�G��A�Ȃ��A��������I�I�v�Ɨׂ�̔N�z�̂�������ƃn�C�^�b�`�B�uGattya�I�I�v�Ƃ�����ŁB��������Ԃł���B��ɔ������ꂽ���C���E�A���o���ł͂��̐��ȉ��������Ȃ��B����C���̕����f���炵���B
�@�@�����ŁA�Q��Adam���u�����́A�݂�ȁB�v�ƈ��A�B�E�I�[�ƒn��̂�ȕԎ����Ԃ�B
�@�@�u���̃T���E���F���i�f�B�[�m�E�J�E���e�B�Ń��C�����J���̂͏��߂Ă����ǁA�����͂���California���B�i�������[�I�j����̓~�l�\�^��Minneapolis����c�A�[���n�߂����ǁA�l��͖w�nj̋��ɋA���Ă����B�嗤�����f���ĂˁA�����A���Ă����I�I�i���A��[�I�j�����A���̉̂�California�ɂ��Ă��̂��Ă���I�i��������[�I�����[�I�j�v�E�E�E�E�Ƃ�����ŊJ�n10���قǂŊ��Ɋϋq�ƈ�̂ɂȂ��Đ���オ���Ă����B
�@�@�\���ǂ���A�wDaylight�@Fading�x���n�܂�A�A�_�������t�ŃW�����v����B���\�d�����ȑ̌^�Ȃ̂ŁA�W�����v���Ⴂ���i���j�B
�@�@�����ďƖ����_�[�N�ȐF�����ɂȂ�A�wChildren�@In�@Bloom�x�̃T�C�P�f�B���b�N�ȃw���B�i���o�[�����t�����B
�@�@�����Ă���ƃo���[�h�wGoodnight�@Elsabeth�x�iCharles���O�����h�E�s�A�m��e���B�ނ�����i�D�G�G�B�j��Adam�̃��H�[�J�������\�B
�@�@�u���̕ӂŁA�ꖇ�ڂ����������[�B�v�ƁA�����Ȃ�_�����M�^�[��e�����A�A�����W�������A�N�[�X�e�B�b�N�ɕς���Ă���
�u�V�������E���E���E���E���v������܂ŊF�wMr�DJones�x�ƋC���t���Ȃ��B���̕ӂʼn����Ă��邪�AAdam�̓M�O�ł͂��Ȃ�̃A�����W���{���ĉ̂��Ƃ������ƁB�ŐV�Łi���̎��_�ł͂��̃A���o�����B�j����̃i���o�[�����Ȃ�Ǝ��ɃA�����W���āA�U��ĉ̂��B�C���X�g�̉��t���̂̓X�^�W�I�^���ɒ����Ȃ̂ŁA���C���ŃX�^�W�I�^���̍Č������߂�t�@���ɂ͂Ȃ��߂Ȃ���������Ȃ��B���ʏ��c�A�[�̏ꍇ�͋ɗ̓A���o���ɋ߂��̂��̂��P��Ȃ̂����A����܂��N���Ĕj��ł���B�wMr�DJones�x�ł��A�̂��Ƃ������A��肩����悤�Ȓ��q�ł���B
�@�@�����A����1st�̖��ȃo���[�h�w�r���������������@Street�x�ł́A���Ȃ�X�^�W�I�E���@�[�W�����ɒ����ɉ̂��BDavid���}���h������t�ł邪�A��͂薼�Ȃł���B�ׂ̂��������
�u�����Ȃ�v���Č�������u�z���}��ȁ[�v�ƋȂ��I���Ɠ����ɁA�܂����n�C�^�b�`�Ŋ�ԁB
�@�@�����āADan���o���o���ƒe���M�^�[�ɏ���āwHave�@You�@Seen�@Me�@Lately�x���n�܂�B���C���f������ȂŁA�O�����h�E�s�A�m��]����Charles���V�u���BMatt����Ԓn���ɒW�X�ƃx�[�X��e���B
�@�@����ł��c�C�X�g���u�M���悤�킩���t���[�ȃ_���X���n�܂�A�����^�R�x����I�B�����ŁA�O���I���B
�@�@���R�A�uCome�@On�I�i�͂�A�o�ė����j�v�̗��B5���قǂŃh���}�[��Ben��擪�ɍēo�ꂷ��Ɗ�������̔��肪�B����ŏI���ł͂��������s�LjȑO�̖�肾�B
�@�@�����āA�����Ȃ�Charles���X�e�[�W�E���ŃA�R�[�f�B�I�������˂点��B�wOmaha�x�Ƃ����ɉ���B�㔼���1st����̃i���o�[�������ȉ߂���wPerfect�@Blue�@Buliding�x�A�}���h���������ރA�b�v�e���|�ȁwRain�@King�x�ŃY���ƃC���p�N�g�����āA�wHanna�@Begins�x�ł�����Ƌq��X�点��悤�ɂƌq���鉉�t�̘A���͂������������B
�@�@�}���h�����ƃA�R�[�f�B�I�����t���[�`���[�����wMercury�x�iAdam���s�A�m��e�����������B�j�܂ŁA�Z�J���h�����1�Ȃ݂̂ł���B����͏��X�ӊO�ł������B�w�ǂ�������Ɗ��҂��Ă����̂����B
�@�@1st�̃��X�g�g���b�N�wA�@Murder�@Of�@One�x�Ńg���̃i���o�[�ƂȂ�B��ɑ呛���ɂȂ�Ɠ���ł����̎��́�uCounting�@Crows�v�ł͈Ă̒�A�������ő升���B���̂̊Ԃ��J���āA�����A�ꏏ�ɂƃ}�C�N���ϋq�ȑ��Ɍ�����Adam�̒��ڂ��C�����܂����B��uShame�@Shame�@Shame�v�̂�����ł�Adam�ƃV���N������悤�ɑ�ϏO���W�����v���邽�ߒn�������������Ă��܂��B���̃i���o�[���̂��������Ȃ�u���v�I�ɂȂ��Ă���B
�@�@���R�A�����o�[������������A���R�[���̑升���B��Ȗڂ��wRaining�@In�@Bltimore�x�Ƃ͋����B���̂悤�ȈÂ߂̃X���[�i���o�[���Z�b�g�ɋ�����Ƃ́B�������ȁwA�@Long�@December�x�Ƃ����o���[�h2�A���ɂ́A�����C����������ϏO�����𗎂������Ď����X���Ă���B�������Adam���s�A�m��e����肵�ACharles�̓A�R�[�f�B�I����S���B���̕ӂ̃��[�c�e�C�X�g���ނ���D���ȑ��݂ɂ��Ă��鏊�Ȃ��B
�@�@���ʁA�A���R�[���̍ŏ��͐���グ�邽�߃��b�N�i���o�[�������Ă�����̂����A�X���[�i���o�[�ŏ�������ނ�̎��͂ɒE�X�ł���B������2�x�ڂ̃A���R�[���ɂ���1�ȁA�A�N�[�X�e�B�b�N�i���o�[�́wWalkaways�x���̂��Ȃ���A�t�����g���C�i�[�A�X�^�b�t�A�o���h�̃����o�[���Љ�āA�����̖�2���Ԃ͏I�������B���Ԃ�12�����߂��B��������LA�܂�2���Ԉȏ�B�������d���Ȃ̂Ō��\�����Ǝv���Ȃ���A�ƘH�ɒ������B�����A����ȕƒn�ɗ��邱�Ƃ͂Ȃ��낤�Ǝv���Ă������A�N�������ăG�A���X�~�X�����ɍĖK���鎖�ɂȂ�E�E�E�E�E�B
�@�@����ȍ~�ALA���ӂ�3����ނ�̃��C����ǂ������邱�ƂɂȂ����A�H�̓����ʂ������̑����ł́A�ꐶ�Y����Ȃ��o���ƂȂ����B�@�@�i2001�D9�D7�D�j
�@�@�Ȃ��A���̌����ł���ٕ����f�ڂ��đՂ���horiai����ɂ��̏����Ċ��ӂ̈ӂ����߂ĕ\���v���܂��B
�@�@�����A���̓������[��I�C�������Ł`�B
�@�@��uIt�fs�@Getting�@Cold�@In�@Carifolnia�CI�@Guess�@I�fll�@Be�@Leaving�@Soon�v
�@�@�@�@�@/�@�����J���t�H���j�A���~�̋C�z���Y���悤�ɂȂ��Ă����B���낻�낱���𗷔����������悤���B
�@�@����#3�̃A�����J�����b�N�E�|�b�v�̋������̂悤�ȉ́A�wDaylight�@Fading�x�����сA�v���o���̂�LA�̒��S�X�̃r���Q�����Ȃ���A�t���[�E�F�C�𑖂����A�ӏH�͖��Los�@Angeles�B
�@�@�n���E�b�h�̎R�̎�Ń��C����1�T�Ԃ�5������ẮA�A�12��������Ă������̍��B
�@�@�J���t�H���j�A������38������Ă���A���ɂ�����Ɨ�C���~��Ă���悤�ȁA�H�̃J���t�H���j�A�ւ̈ڂ낢�������A�����玀�̋G�߁|�Ă͐����̒a���E搉́A�H�͐����̉����E�Ō�̋P���E�����ē~�ւƎ������鎀�B
�@�@�u�����v���Ƃ́A����āA�ǂ����̊y���ւƌ�����������]�Ȃ̂��낤���B
�@�@���ɂƂ��Ă̓J���t�H���j�A�����y���ł������̂ɁB
�@�@��̃t���[�E�F�C405���B10���Ƃ̕���B�p�T�f�B�i�ւƑ����A�S�Ăł��L���ɌÂ��t���[�E�F�C�̂ƂĂ��댯�ȐV�����Əo���B
�@�@�ߏ��̎���n���o�[�K�[�V���b�v�A�`���`�[�Y�E�t���C���R�̗l�ɐ����ăo�N�o�N�ƐH�ׂ����ƁB
�@�@20��Ō�̈�ڍ�������āA�����ɋʍӂ������ƁB
�@�@�����ԈႦ�ē쒆�S���ACompton�̂悤�Ɍ���Ɋ댯�Ȓn����ԂŜf�r�������ƁB
�@�@�H�̖��B���{�̋�Ƃ͈Ⴂ�A�Q�ɂǂ��܂ł�����B�n�������Ȑ����ŁB
�@�@�ނ���r���X�B�钆�̃t���[�E�F�C�B
�@�@���W�I�����Counting�@Crows�́wLong�@December�x�AThe�@Wallflowers�́wOne�@Head�@Light�x�ACollective�@Soul�́wListen�x�E�E�E�E�E�����̎��ԁB
�@�@�r�[�`�Ŕ����ŃW���M���O���āA�C�ɓ������琅���₽�߂������ƁB
�@�@����Counting�@Crows�����тɁA�Ԉ���ďA�E��20��̔����ׂɘQ��Ă��܂����A�_����Ƃł̗B��̎��n�������A�����J���݂��v���o���B
�@�@���̂��A�����ɂ͎��s�������Ƃ⌙�ȑz���o�̓t���b�V���o�b�N���Ă��Ȃ��B
�@�@�ꂵ���v���o�E�h���L���́A�S�āA���̃A���o���̃W���P�b�g�̂悤�ȗ����̔@���A��u�ɁA�����Č��̗l�ɗ���Ă����B
�@�@��uDaylight�@Fading�@Come�@And�@Waste�@Another�@Year�v
�@�@�@�@/�@���̌����Ă���H�A�~�ɂ����Ď���Ɏ�܂��Ă����G�߂̈ڂ낢�̒��ŁA�܂�1�N���ׂɉ߂����̂��낤�B
�@�@���̉̎��ɁA�@���Ɏ��������\�N�����Ȃ��l���ʂɉ߂����Ă������A�Ɋ����Ȃ���͖����B�������A�n�����ɒ��ސ^���Ԃłǂł����[�����A�A��鎞�A�l���ʂɔ�₷���Ƃ����A�ō����ґ�����Ȃ��B
�@�@����ȕ��Ɏv�����Ƃ�����B����̓J���t�H���j�A�̊�������C�ƁA�u���[�O���[���̊C�����̂悤�Ȋ��S����������̂�������Ȃ��B���������������{�̓���ł͂��̂悤�ȍl���͑������ׂ����̂Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�@��uA�@Long�@December�@And�@There�fs�@Another�@Reason�@To�@Believe�CMaybe�@This�@Year�@Will�@Be�@Better
�@�@�@�@�@Than�@The�@Last�v
�@�@�@�@/�@�@12���͒��������ė~�����B����͂ˁA���N�͂����ƍ�N��肢���N�������ƐM���������R��T�����Ԃ��K�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����炳�B
�@�@#12�wLong�@December�x�����тɁuBest�@Yet�@To�@Come�v�Ƃ����t���[�Y���v���o���B
�@�@�����ǂ��Ȃ�A�������d�����ɂȂ�A�����Ɖ����̓������͐����E�E�E�E�E�E�E�E�����l���āA�ǂꂾ���A���ʂȎ��Ԃ��߂����ė������낤�A�Ƃ��̉̂����тɎv���B���́A�̐��́A�u���N���������Ɩ��������Ȃ��B�v�ƔN���̎G���łӂ�1�N��U��Ԃ�A����̖������������o����u�ԁB
�@�@�����ƒN����Long/�肤�@�@�@Long/�����@�@12��
�@�@�����āA����uMy�@Finest�@Hour�v�͖����摗��B�����āA��������V���Ď��ɋ߂Â��E�E�E�E�E�E�E�E�B
�@�@��uThe�@Smell�@Of�@Hospitals�@In�@Winter�CAnd�@The�@Feeling�@That�@It�fs�@All�@A�@Lot�@Of�@Oysters�@But�@No
�@�@�@�@�@Pearls�v
�@�@�@�@/�@�~�̕a�@�B�k�������B��R�̉��y�����邯�ǁA���g�̐^�삪�S�������Ă��Ȃ��悤�ȋ���������B
�@�@��uIt�fs�@Been�@So�@Long�@Since�@I�fve�@Seen�@The�@Ocean�CI�@Guess�@I�@Should�v
�@�@�@�@/�����ԊC�����Ă��Ȃ��A�C���������E�E�E�E�E�E�E�B
�@�@�̎��I�ɂ͕ʂ̃��@�[�X�ɑ����邱��2�̃t���[�Y���ƁA�ڋ߂ő����ۂ��C���[�W�����A�h�a��̏������a�@�̑�����C��T���Ď����������֓����Ă���h�Ƃ������f���������ԁB���R�A�a�@�͐ԗ�������Œӂ����܂��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�j
�@�@�����́A�����N�����������������������������Y�ꂽ���A�������ɒN���̌������ɘA��čs���ꂽ�B�C�̂��̑傫�Ȕ��������ŁA����������C�����������B�o���Ă���̂͐H�ׂ����Ă�������`���R���[�g�Ƃ��̍ӂ���g�������B�ӂƁA�������̏�i������ׂɓ��ɕ�����ł���A���̃A���o�����ƁB
�@�@��uGonna�@Get�@Back�@To�@Basics�CGuess�@I�fll�@Start�@It�@Up�@Again�v
�@�@�@�@�@/�@��{�ɖ߂�B�܂��ŏ������蒼�������̂��B
�@�@�^�C�g����#10�wRecovering�@The�@Satellites�x�̃t�@�[�X�g�E�t���[�Y�����ɂ���ƁA���ƂȂ��A�����ł��l���U��o���ɖ߂���悤�ȋC�����Ă���̂ŁA�ƂĂ��s�v�c���B���x�����ʂɂ��Ă��鎞�Ԃ��A�ŏ������蒼����B
�@�@�ȑO�߂Ă����ꕔ����Ƃ��A��i�Ɲ��߂đސE�������A���̖��邢��]�𝪂������Ă����悤�ȃ����f�B�Ɓh�q�������߂��h�Ƃ�����߂����̎��ɐ����S��I�ɋ~��ꂽ�C������B
�@�@�h�q���h�Ƃ͏����ɉ����������݂̂悤�ł���A���̉̂̒��ł́B���A���͗��z�A�������A���z�ƌĂ�ł��ǂ��̂�������Ȃ��B�����A�܂��ɐl�H�q���̗l�ɑ�C���O�̎�̓͂��Ȃ��Ƃ�����A���݂͒m���Ă��Ă������ĕ��ʂɂ͌����Ȃ����́B����ȑ��݂����߂��B�����̂������Ă���悤�ȋC������B
�@�@����Ō����Ȃ���Ζ]�������g���A�撣��Ή��Ƃł��Ȃ�B����ȃ��b�Z�[�W�B
�@�@��uI�@Wanna�@Be�@Scattered�@From�@Here�@In�@This�@Catapult�v
�@�@�@�@/�@��������J�^�p���g�ɏ悹�Ėl���ˏo���ė~�����B�����������ցB�S�Ă�Y��邭�炢�����G�ŁB
�@�@��uAll�@Of�@A�@Sudden�@She�@Disappers�v�ƕ������ɂ��̎��ŃX�^�[�g����#1�wCatapult�x�B���́A�����Ǝ��Ȃ�ɂ߂��邾���ɂ߂��悤�Ƃ���悤�ȁA�����\���O�B���̃J�^�p���g�i�K���_������ɂ́u�s���܁`���B�v��ˁB�j�Ƃ����M�~�b�N�ŁA������\������Adam�̃Z���X�ɂ͂�������������B
�@�@�������A�����A���g�ŃJ�^�p���g�őł��o���ꂽ�Ƃ�����B20�g���߂��W�F�b�g�͍ڋ@��ł��o������̃J�^�p���g�ɏ悹���ꂽ�Ƃ�����B�܂��ɁAScattered�@/�@�o���o���E���X�ɂȂ��Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��B
�@�@��юU������E�����E���E�E�E�E�E�E�E�E���ŁB
�@�@���̉̂͌��𗬂��C���[�W������B�����A�����ɂ̓J�^�p���g�őł��o�����E�C�������̂ɁA���̎��Ȕj����������Ŗϑz����j�B
�@�@����l�́A���B�̒N���������Ă���ɈႢ�Ȃ��A���Ȕj��Փ��B���E�Փ��Ƃ܂ł͌���Ȃ����A�l�ԂɎ��E���q��������Ă��邱�Ƃ͈�`�q�����ʼn𖾂���Ă���B
�@�@�u���Ȃ�������i�C�t�v�A�ƍ쒆�ł��̂���悤�ɁA�S�Ă̐l�Ԃ̐��_�����͗��������̂�������Ȃ��B
�@�@���̂悤�ɁA1�Ȃ��ꂼ��ɁA�����閲�z�E�ϑz�E����ȃC���[�W�����̐S�̒��Ɋ�Ƃ��đ��݂���B
�@�@����14�Ȃ��ׂď����o���Ǝ~�܂�Ȃ��̂ŁA��芸����4�Ȃ����ɂ��Ă����B
�@�@�����܂ŏ����Ďv�������A����̓������[�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�@�@�̂ɐ��K�Ń������[��200�{�ڂɍ��𐘂��ď��������Ǝv���B
�@�@�\�Ȃ�A��ÂɁB�@�@�i2001�D10�D28�D�j�@�@�@�@
 �@�@�@Long�@331/3�@Play�@/�@Buffalo�@Nickel�@�i2000�j
�@�@�@Long�@331/3�@Play�@/�@Buffalo�@Nickel�@�i2000�j
�@�@�@�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@�@Rock�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@Southern�@������
�@�@�܂��͎c�O�Ȃ��m�点�Ń������[���n�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��A���Ȃ�߂����B
�@�@�I�t�B�V�����Ȕ��\�͂��ɂȂ��������i�M�҂̒m�����j�ABuffalo�@Nickel�Ƃ����o���h�͉��U�����A�Ƃ��������ł��Ă��܂����E�E�E�E�E�B���m�ɂ͉��U���̖��̂�Gary�@Stier�@���@Buffalo�@Nickel�ł��������A�������̑厖���Ɣ�ׂ���ׂȂ��Ƃł���B
�@�@2001�N��6�������肩��A�o���h�̊Ԃŕs���a�����������悤�ɂȂ��Ă����B���̃o���hBuffalo�@Nickel�͂��̓����A���W���[�E���R�[�h�f�����[����͂����N���炢�ŁAGary�@Stier�@���@Buffalo�@Nickel�Ɩ��O��ς��Ă����̂����A���̐߂̓C���f�B�o���h�ɂ悭������o���h���[�_�[�̖��O�����܂Ɋ�������߂����肷�錻�ۂ��ȂƁA���������Ă����̂����A����Gary�������̖��O��Buffalo�@Nickel����O�����i�K�ŁA�ő������̕���͊m���ł������̂�������Ȃ��B�i���A���W���[���[�x�����������Ȃ��B�j
�@�@�܂��A�V���K�[�ł���A�o���h������l�̃\���O���C�^�[�ł���Gary�@Stier������3�l���Ԃ��������̂悤�ɁA�\�����������C���ɂĊJ�n�����̂��A6���̖��B
�@�@�܂��A�ȑO���烁�[���ł��������đՂ��Ă���Buffalo�@Nickel�̃x�[�V�X�g�ł���o�b�N���H�[�J���X�g��Richard�@Turner����u�V�����o���h���Z���Brit��M�^���X�g��Charlie�ƌ�������B�v�ƘA����Ղ����̂����x���̍��ł������B
�@�@���N��3�����炢�܂ł̓��C���E�t�F�X�e�B���@���ɏo��������A�o�g�n�̃A�g�����^�𒆐S�ɐ��͓I�ȃ��C���c�A�[���s���Ă����̂��A�t������Ɠ������炢�ɁA�ˑR�T1�炢�̃y�[�X�Ƀe���V�����_�E�����Ă��܂��Ă����̂ŁA���X�S�z�ł������̂����B
�@�@�����čX��Richard������V�����o���h�̖��O��Mason�@Dixon�ƂȂ邱�Ƃ��`����ꂽ�B���̒i�K�ŁA���҂�Buffalo�@Nickel�Ƃ��Ă̊����͍���ǂ��Ȃ�Ƃ����₢�ɑ��ẮA�ނ͈Ӑ}�I�ɖ������闧�����т��Ă����̂ŁA�ǂ����I���ł���Ɗm�M������n�߂��̂��A7���B
�@�@�Ƃ���ŁA����Mason�@Dixon�Ƃ����o���h��1980�N��Ƀe�L�T�X�𒆐S�ɂ��Ċ������Ă������J�r���[�E�J���g���[���b�N�o���h�Ɠ������O�ł���B�̂ɁA���O�̏d�����������o���h���V�������O��T���Ă���A�Ƌ�����ꂽ�肵�āA���S��Buffalo�@Nickel�̘b���Richard�����畷�����͕s�\�ɂȂ����B�̐S��Gary�@Stier�Ƃ͖ʎ��Ƃ������������Ȃ����߂ɔނ̃R�����g�⊴�z�𖢂������Ă��Ȃ��͎̂c�O�����B
�@�@�����ă��W���[�ւ̃W�����v�E�A�b�v�ƂȂ������������Ƃ��Ȃ���Black�@Crows�̃t�����g���C�i�[�ł�����������̕t�������ł���Ƃ����AChris�@Robinson�̖����ŁA�ނ̃o���h�̖��O���ꕔ�����Blackberry�@Smoke�Ƃ��Ĕ��������Ƃ����A�������[�����O���X�g�o�R�œ͂����̂�9���̏��߁B���̒i�K�ŁuFormer�@Buffalo�@Nickel�v�Ƃ����������g��ꂽ���Ƃ�����I�ł������E�E�E�E�E�E�E�E�B
�@�@���Ȃ݂ɂ���Blackberry�@Smoke�Ƃ����o���h�́ABuffalo�@Nickel�̃��Y�����ł���Richard��Brit��Turner�Z��ƁA�M�^���X�g��Charlie�@Gray�����[�h���H�[�J���ɐ����āA�X��Fred�@McNeal�Ƃ����M�^���X�g��������4�l�g�ŁABuffalo�@Nickel������w�D�L���E�S�������E�n�[�h�ȃT�U�����b�N���������邱�Ƃ��ł��A�l�I�ɂ͊y���݂ȃo���h�ł͂���B
�@�@����A���̃A���o���̋Ȃ�1�Ȃ������đS�č쎌��Ȃ��Ă���Gary�̓����ɂ��ẮA�S���ƌ����ėǂ��قǏ����Ȃ��B�ނ̓\���V���K�[�Ƃ��Ċ������n�߂�̂��i�����ɂ͍ĊJ�ƌ����Ȃ����Ȃ��B��q�j����Ƃ��܂��o���h����������̂��낤���B���ɋC�ɂȂ�Ƃ���ł���B�����t�H�[�N�n�V���K�[�ł���Michelle�@Malone�̃A���o���ɎQ��������A�ޏ��ƃW���C���g�Ń��C�����s�����Ƃ������݂̂ł���B
�@�@�ȏ�A2001�N9���܂ł̏������Ă݂��B
�@�@#1�wThis�@Ain�ft�@Nowhere�x�����u�ԁA���������Ƃ́A�h�����AHootie�@���@The�@Blowfish���܂��������h�Ƃ��������ł������B�W���[�W�A�B�ݏZ�̗F�l������̐������[�J���o���h��Universal����f�����[����A�ƕ����Ă������A�܂��������܂ŃA�����J���E���[�c���J���g���[�������ɂ����T�U�����b�N�ȉ��̃o���h�ł���Ƃ͎v��Ȃ��������炾�B
�@�@�W���[�W�A�B�s�A�g�����^�Ŋ�������T�U�����b�N�E�O���[�v��Lonesome�@Jones�Ƃ����o���h�����āA���Ȃ�L�]���ł���Ƃ����b���ݕĒ��ɕ����Ă������A���̉��U�����o���h�̃l�N�X�e�[�W������Buffalo�@Nickel�ł��邱�Ƃ͑S���m��Ȃ������B
�@�@����ȑO�ɂ��̃T�E���h�ł���B���R�[�h�����O�Ƀr���{�[�h�̋L������
�@�@�u�l������Wallflowers��Matchbox�@20�Ɠ����t�B�[���h�Łi�}�b�`���͂��̌�N�\�ȊO�̉��҂ł��Ȃ��I���^�i�ɛZ�т������I�ň��̃A���o�����o�����̂ŁA���ғI�ɏ��O�������̂����B�j���y���������Ă���B�v
�@�@�u���s�ɘf�킳�ꂸ�ɁA��D����Eagles��Neal�@Young�̂悤�ȉ������t�������B�v
�@�@�Ƃ����悤�ȃC���^�����[��ǂ�ŁA���҂͂��Ă����̂����A�����܂�1990�N��̃��W���[�V�[�������E�������f���炵�����[�c�A�����J�����b�N�����Ă����Ƃ͑z�������ɂ��Ȃ������B
�@�@�������A���W���[���[�x����Universal�ł���B�����W���[�W�A�B�̃A�Z���Y�o�g�ł���Sister�@Hazel�Ƃ��_�Ă��郌�[�x���Ȃ̂ŁA�܂��N���蓾�钿���i�H�j�̂悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B���A������2nd�A���o�������[�J���ő�u���C�N�ƂȂ��ă��W���[�A���o���Ƃ��čă~�b�N�X���ꂽ�uSomewhere�@More�@Familier....�v�Ń��W���[�ւƔ����オ����Sister�@Hazel�������P�b�g�E���[���`�I�ȋ삯�����ł���B
�@�@���X�q�ׂĂ��邪�A�A�g�����^�o�g��Gary�@Stier����������Lonesome�@Jones���uSmells�@Like�@Bacon�v�Ƃ���7�C���`EP�����ĉ��U�����̂�1997�N���炵���B���ɂ�����ŋɏ����̃V���O�������[�J�������[�X���Ă���炵�����������Ɏ������Ȃ��B
�@�@���̃o���h�����U���Charlie�Ƒ�w����̗F�l�ł���Turner�Z����}���āABuffalo�@Nickel����������̂����AGary�@Stier�̖��O�Ŋ������Ă������Ƃ��Z���Ԃ������������B�̂ɍ���̉��U���̌�̃\�������͏��ł͂Ȃ���������Ȃ��Ƃ����̂��A�捏�G�ꂽ���ׂȓ��e�ł���B
�@�@���Ȃ݂ɂ��́uLong�@331/3�@Play�v��2001�N�̉ĂɃ^�C�g�����uBuffalo�@Nickel�v�ƕύX���čă����[�X����Ă���B���m�ɂ͏q�ׂ��Ă��Ȃ����A�o���h�̉��U�ɂ��o���h���̗����W��̑[�u�Ƃ����\�ł���B�����A����͉����������B�i���j
�@�@���āA�{���Hootie�@���@The�@Blowfish�̑�u���C�N���v���o�����Ă����悤�ȃA���o���ł���B�Ȃ̂����A�����悤�ɃT�U�����b�N�Ƃ������J���g���[�v�f�������Ղ�܂A��{�I�ȃA�����J�����b�N�������Ȃ�����O�҂ƑS���قȂ�̂́h�S�R����Ȃ������h�i�܁j���Ƃł���B
�@�@�����Ȃ���A3�������X�x��ē��{�Ղ������[�X����Ă���B������̉���͖ܘ_�ǂ�ł��Ȃ��B�{�[�i�X�g���b�N��2�Ȃ��t���ΐ�ɍw�������ł��낤���B�i�j�����Ƃ�����ɂ̓v���̃��C�^�[�̕����ڂ����o���h�̓��e��������Ă�����Ƒz������̂ŁA���m�ȏ���m�肽���Ƃ������͂�����̍w�������E�߂���B���A�����lj����A�M�҂̎��W�������Ɍ�蓙����A�`�����Ē�����ƍK�����B
�@�@���A������͋������Ƃ��Ȃ��A�{�M�ł��S������Ȃ����������ł���B���ɔ��ꂽ��ُ�ł��낤���B�i��j
�@�@���炭�AUniversal�ɂ̓c�A�[�ɂ���Ă��킶��ƕ]����L���A���݂ł�2000�����߂����Ă���Hootie��1st�A���o���̖��������x�A�̑_�����������̂��낤�B
�@�@�ܘ_�AKenny�@Wine�@Shephard��Fastball�AThe�@Black�@Crowes�B�����đ僔�F�e������Willie�@Nelson��Steve�@Earle�A�X�ɂ̓I���^�i�n��Cracker�ɃJ���g���[�F�̋���BR-549�A�ȏ�̃t�����g���C�i�[�Ƃ��đS�Ă����A���R�ɂ��啨�v���f���[�T�[��Danny�@Kortchmar�̖ڂɂƂ܂�A��������ɍ��ꍞ�܂�A����悠���Ƃ����ԂɃ��W���[�f�����[�̉^�тɂȂ����̂́A�ނ�̉��y�����͂̂�����̂ł��������Ƃ͋^���悤�͖����B
�@�@���W���[�Ńf�����[���ď��ƓI�ɑS���������Ȃ������̂̓o���h�ɂƂ��Ă����[�x���ɂƂ��Ă��t���X�g���[�V�����ɂȂ������Ƃ͑z�����Ղ��B���������A�C���f�B�ŃT�[�L�b�g�����Ă��烁�W���[�ւƏオ������ƃO���[�v�Ƃ��đ����ł������ƍl����͖̂��z���낤���B
�@�@�ǂ݂̂��A��C�ڂ̓D�ӂ͖��̖̉��ɂ��Ȃ�������ł��邵�A��͂�ǂ��A�����J�����b�N�͊�Ղł��N���Ȃ����胁�W���[�ł͔���Ȃ��Ƃ������Ƃ𗧏��āA�o���h�͏I�������B
�@�@�������ܑ̖����B�o���h�̊j�ł���Gary�ɂ͂߂����ɂ��̕��������т��ė~�������̂ł���B���[�c���y��@����ɂ���70�N���80�N��̃��C���X�g���[���Ƃ��Ēn�ʂ��l�����Ă����A�{���̃A�����J���E�T�U�����b�N�����B
�@�@�A���o���͑S12�Ȃō\������Ă���B
�@�@�Q�X�g�w�͒��ꗬ�̃��F�e��������ł���BHeartbreakers��Mike�@Campbell��Benmont�@Tench�̃R���r�͂��̎�̃��[�c�n�̎��̃��W���[�A���o���ɂ͖w�NJ���o���Ă���B�ނ��M����Jayhawks��Gary�@Louris��Kenny Aronoff (John�@Mellencamp's�@band)�AMichael�@Ward�iThe�@Wallflowers�j�Ƃ������B�X�����Ԃꂪ�T�|�[�g���Ă���Ƃ���͂������Ƀ��W���[�A���o���̖ʖڂƂ����Ƃ��납�B�ܘ_�}���`�v���C���[�ł���v���f���[�T�[��Danny�@Kortchmar�����t�ɎQ�����Ă���B�N���W�b�g���ڍׂłȂ����߁A�N���ǂ̋ȂŃT�|�[�g�����Ă��邩�z������̂��ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�@�A���o���̍\����#9�wWhat�@You�@Don�ft�@Need�x����#12�wLet�@It�@All�@Come�@Down�x�܂ł��y���ȃJ���g���[�t���C���@�[����A�b�v�e���|�ȋȂ��S���Ȃ��A�X���[�ȃT�U�����b�N�̃��b�J�o���[�h��A�����ۂ����b�L���u���[�X�i���o�[
�Ōł߂��Ă���̂����P���ȗ���ƂȂ��Ă���_�ȊO�͖w�ǖ����̏o���ł���B�����܂ł��Ȃ����A���XR&B��S�X�y������킹��d�ڂȃr�[�g�i���o�[#11�wOne�@Man�fs�@Ceiling�x����ԃA���L���b�`�[�ł��D�݂łȂ��ȊO�́A��̌㔼3�Ȃ̊���̓��ꍞ��Ƃ����A�p���t���ȃo���[�h�̊����Ƃ�������͑S�������B
�@�@1st�V���O���ƂȂ���#4�wGood�@Day�x��I�[�v�j���O��#1�wThis�@Ain�ft�@Nowhere�x��Gin�@Blossoms�̖��ȁwFollow�@You�@Down�x���霂Ƃ�����悤�Ȏ������Ă���́A�A�����J���E���[�c���b�N���|�b�v�̌��_�̂悤�ȑ喼�Ȃł���B����2�Ȃɂ�The�@Byrds�ɘA�Ȃ�J���g���[���b�N�̂��ƁABruce�@Springsteen��Bob�@Seger�ɒ[����A�����J���������b�N�̐��_�������Ă���B�u�q���̍��AMac��Lindsey�@Buckingham���V���E�g����̂����̂��A���܂łōō��̉��y�̎v���o����B�v��Gary�͈�ԍD���ȃ��H�[�J���X�g��Fleetwood�@Mac�S�����̃��[�h�V���K�[���s�b�N���Ă��邪�A�m���ɃR�}�[�V�����̌����̂悤�ȃ����f�B�͊�Ƃ��đ��݂��Ă���B
�@�@����#1�̂��肰�Ȃ��I���K���ƃA�b�v���C�g�s�A�m�̃o�b�L���O�́A����ȏ�O�ʂɏo��ƁA�M�^�[�T�E���h���ڗ����Ă��܂����E����Ń����f�B��a���ł��āA���̍ۂǂ������_���m�ł���B
�@�@���ɂ��t�ȃM�^�[��u�₩�ɃA�����W����#4�ł́A�암�I�ȓD�L�������A���C�ݓI�Ȑ�������90�N��̃T�E���h�ɏ����Ă���Ǝv���B
�@�@#2�wFool�@Enough�x��Georgia�@Satellites���Ԃ������Ȃ�悤�ȃn�[�h�ȔS���͂̂���A����ł��ă|�b�v�ȃt�b�N�̌������암���b�N�����W���[�ȃ��[���ɏ悹����A���̂悤�ȓ˂�����������邾�낤�Ƃ����c�{�ɂ͂܂����悤�ȃ��b�N�i���o�[�ł���B�I�n�u�₩��#1�Ƃ̃R���g���X�g���f���炵���B
�@�@#3�wMiss�@America�x��#5�wComeing�@Up�@Roses�x�͂��ꂼ��Hootie�̃g�b�v10�q�b�g�ł���wLet�@Her�@Cry�x��wHold�@My�@Hand�x��A�z������悤�ȃ��b�J�o���[�h�ł���B���D�̂��郁���f�B�ɓD�L���M�^�[�̃T�E���h�����ނƂ���́A���̂����D���I���^�i�I�J�T�Ɗ��Ⴂ���Ă���ǂ����̍��̃��f�B�A�ɁA�u���ꂱ���������R���b�N�ȃo���[�h��v�Ƌ��т����Ȃ邭�炢�A�ǎ��ł���B
�@�@���ʂɃ��[�c�I�ȐF�������������A�s��I�Ȑ������ꂽ�|�b�v���b�N�ȃ`���[���Ƃ��čۗ�����#6�wStayed�x�͂���܂��V���O���ɂ��Ă��S���ߕs���̂Ȃ��A�f�G�ȃ����f�B���������i���o�[���B�����ɂȂ�Ȃ����炢�̃��[�c�e�C�X�g�̐D�荬�����́A��͂胁�W���[���[�x���ɂ͂��̂��炢�̂������肵���A�����W���K�v�Ȃ̂��ƍĊm�F�����Ă����B���̕������̃��W���[�ȃA�����W�Ȃ�劽�}�Ȃ̂����B
�@�@�\�E���E�|�b�v�I�ȃT�j�[�T�C�h�ȉ��y�����C�����̗ǂ�#8�wEvil�@Wind�x�̓n�X�L�[��Gary�̃��H�[�J���ƃo�b�N���H�[�J���̘V��Lennon�t�@�~���[�̐D�萬���R�[���X��60�N��̃|�b�v�X���������ނ悤�Ȗ��킢��������B���H�[�J���̏d�˕��ł͍ۗ������|�b�v�i���o�[�ł���Ǝv���B
�@�@Jayhawks��Gary�@Louris���M�^�[��e���Ȃ炱�̃A�N�[�X�e�B�b�N�i���o�[�łȂ����ƁA����ɑz�����Ă���̂�#7�wRagged�@Out�@Heart�x�B���X�ɐ���オ�郁���f�B���C���ƁA����܂����d�ȃR�[���X���[�N�ɁA�s�A�m�̏���I�Ȑ������A�n���ȓW�J�Ȃ���A�����O���̗������Ȃ��o���[�h�Ƃ��Ďd�グ�����Ă���B
�@�@#9�wWhat�@You�@Don�ft�@Need�x������܂������̓������o���[�h�ł���B���X�o���[�h�̔䗦�������A���o���ł���Ǝv���̂����A�ǂ̃o���[�h���f���炵���̂ŁA����ŗǂ��Ǝv���Ă��܂��Ƃ��낪���ɂ���Ă���؋��ł��낤�B
�@�@�o���[�h�̍ō���ł���͓̂암�I�ȏd�S�̒Ⴓ�ƁA�u���[�X���b�N�I�ȏd�������Y�V���ƐS�ɑł�����ł����#12�wLet�@It�@All�@Come�@Down�x�ł���Ǝv���B�����I�ȓW�J�ƃ����f�B�ɂ����Ă͑��̃o���[�h�Ɉ�����邩������Ȃ����A�G���[�V���i���ȉ̂ւ̋C�����̍��ߕ��ƁA��≩���������Ƃ肵�����o�ƃT�U�����b�N�̃p���[�̗Z���͐▭�̌��ʂ����āA�A���o���̃g������������ƒ��߂Ă����B
�@�@�̂ċȂ͖ܘ_�Ȃ��B�����Č�����#11�����ދ����B�����փ|�b�v���b�N�ȃA�b�v�e���|�ȃ`���[������э��߂Ί����ȗ���ɂȂ�Ǝv���̂ɁA�Ə���Ɏc�O�����Ă���B
�@�@�܊p���{�Ղ��܂��o�܂���Ă���̂ŁA�w�����Ă��Ȃ����b�N�D���ȃ��X�i�[�͒����ɍw�����������ǂ��B�w���B���b�N�ƃS�e�S�e�ɑ��������~�N�X�`���[���y���҈Ђ�U�����20���I���ɁA���̂悤�ȃX�g���[�g�ȃ��[�c���b�N�A���o�����������ꂽ���Ƃ͋����ׂ����Ƃł���B�J��Ԃ����B
�@�@���U�͎c�O�ł��邪�A����Buffalo�@Nickel��Gary�@Stier�̃����}���o���h�ł��������Ƃ��ӂ݂�A�ނ̍˔\�̓\���ɂ���A�V�����o���h�ɂ��悱�ꂩ����\���ɒ�����Ǝv�����ABlackberry�@Smoke�̂��f�B�[�v�ȃT�U�����b�N�����\�ł���ƑO�����ɍl���Ă��������Ǝv���B�@�@�i2001�D9�D18�D�j
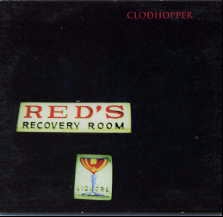 �@�@�@Red�fs�@Recovery�@Room�@/�@Clodhopper�@�i1998�j
�@�@�@Red�fs�@Recovery�@Room�@/�@Clodhopper�@�i1998�j
�@�@�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@Alt�DCountry��Traditional�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here
�@�@�g���f�B�V���i���E�\���O�n�̃��[�c�A���o���Ƃ����͔̂��ɑ��l�ɑE�ߓ�Ƃ��낪����B�Ⴆ�A���N2001�N��Blue�@Mountain���uRoots�v�Ƃ����薼�܂�܂̃g���f�B�V���i���E�\���O���J���@�[�����A���o���������[�X���Ă��邪�A���̃A���o���𖢂��w���������Ă��Ȃ��B�O��uTales�@Of�@A�@Traveler�v�ɂ�Dan�@Baird�̋��͂ɂ�肩�Ȃ�|�b�v�ŃL���b�`�[�ȃ��[�c�o���h�Ƃ��ĐV������Blue�@Mountain���x�b�^���̃��[�c�A���o�����a�������邱�Ƃɒ�R�����邩�炾�B�M�҂̕]���̒Ⴂ�A���o���͂ǂ̂��炢���Ԃ̕]���������낤�ƁA���E�߂͐�ɂ��Ȃ��̂��Ɍl�I��`�ł��邩�炵�ă_�������ȃA���o���͎��グ�Ȃ��A�����Ȃ��̂��B
�@�@���̂悤�Ƀ��[�c�D���ł����Ă��A�g���f�B�V���i���E�\���O�|�܂�͓��{���ɕ\������Ζ��w�ł��邪�|���D���Ƃ͌���Ȃ��̂ł��邵�A�����N�Z�̂���g���f�B�V���i���E�A���o���������B
�@�@�g���f�B�V���i���ƈ���Ɍ����Ă��A�X�^���_�[�h�n�̃��H�[�J������A�y���n�̃J���g���[�J���[�������c�����g���f�B�V�������y������B
�@�@�������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�ŋ߉J��̃^�P�m�R��Ԃɗї����Ă���Jam�@Rock�Ɠ��`�ɑ������Ă���Trad�@Rock�ł��낤�B���̈Ӗ��ł̃g���b�h�͂����܂ł��`���I�ȉ̗w�̏Ă������ł͂Ȃ��A�������y�̃��t���Ɩ��������A�y�ю��R�������b�N�Ƃ������f�B�A�ŕ\���������̂ł���BDave�@Matthers�@Band�����g���b�h���b�N�ƕ��ނ��Ă��邪�A�ނ炪���̍��Ȗ��w���̂��o���h�ł͂Ȃ����Ƃ́A���m�̂Ƃ���ł��낤���B
�@�@�ƁA�����Ȃ�E�����Ă��܂��Ă���̂����A���́uRed�fs�@Recovery�@Room�v�Ƃ����A���o���͂����܂ŐG��Ă����A�g���f�B�V���i���\���O�Ōł߂��A���o���ł͌����ɂ͂Ȃ��B
�@�@���X�A���W���[�߂����ł��邪�AHooters��3rd�A���o���uZIG�@ZAG�v��2nd�V���O���ƂȂ����w500�@Miles�x���g���f�B�V���i���\���O�̐V���߂ł������悤�ɁA����Clodhopper���I���W�i���̉̂̏��X�Ƀg���f�B�V���i���̂�ނ�Ȃ�ɉ��߂��A������A�A���o����n���Ă���B
�@�@���A�S�̂Ƃ��ăI���^�i�E�J���g���[�ւ̉��y���̋����ƁA�`�����y�ւ̒Nj�������قNj�ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ��낪���ɋ����[���A�X�ɂ��̃A���o�����h���[�c���b�N�h�ȃA���o���Ƃ��Đ��������Ă���̂��B
�@�@�Â߂Č����A�I���^�i�J���g���[�n�̃��b�N�����Ȃ�g���b�h�X���Ă���A�Ƃ������Ƃƃg���f�B�V���i���E�\���O�̃A�����W�������������b�N�Ƃ��Ē�������߂��Ȃ���Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B�����o����錋�_�Ƃ������S�̑��́A�Ƃ��Ƃ�g���b�h�ɗ����܂œ˂����A�_�T���C�����Ȃ��A�������y�̓�������������悤�ȃA���o���ł���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�@���A�Ƃ�����A�������y�n�̃|�b�v�X��b�N�A���{�Œ����ȑ吼�m��n������u���e�����̐��Ɉʒu����A�C�������h�̃P���e�B�b�N�E�~���[�W�b�N���Ɏ��ƁA���܂�ɂ��������y�Ƃ��ẴA�N�������ă��b�N��|�b�v�̃R���e���|�����[�ŃR�}�[�V�����ȗv�f�������Ă��܂��Ƃ����댯���i���ʁA������Ƃ������Ȃ����Ȃ��B�f�B�[�v�E�g���b�h�m��h�ɂ���ł��邯��ǂ��B�j�Ɋׂ肪���ȗ��Ƃ����ɛƂ܂邱�Ƃ̂Ȃ��A���o���ł���A�ƍl���Ă���B
�@�@���Ȃ��Ƃ��A�g���f�B�V���i���̃X���[�ɉ߂���r�[�g�̑ދ����������邱�Ƃ����͂Ȃ��B���̓_�ł����܂ł��u���b�N�v���D���Ȓ��҂̚n�D���ߕs�������������Ă���Ă���B
�@�@���āA���́uRed�fs�@Recovery�@Room�v�̃W���P�b�g�Ƃ������A���o���S�̂߂Ă݂悤�B���Ɋȕ։߂���n���Ȃ̂ł���B�f�W�p�b�N�d�l�̂悤�ȕ��ʂ̃v���X�e�B�b�N�P�[�X�ɓ����Ă͂��Ȃ��A���o���ł��邪�A������f�W�p�b�N�ƌĂԂɂ͂��Ȃ�ꕾ������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@�@�f�W�p�b�N�̗l�ɁA�������J����CD�����o���`�ł͂Ȃ��B�����A�ꖇ�̕\�W���P���J����CD�������邾���B���̃P�[�X���܂������ACD�V���O���̎��W���P�Ղ����y���y����������Ȃ��B�i�j�Ƃ�����CD-R�̃X�����P�[�X���ȃ`�[�v�Ȋ�ł���B�e�Ɋp�A�ɔ��ȃA���o���ł���B
�@�@�܂��A�C���i�[���S�����C�Ȃ��A���R�[�f�B���O�ɎQ���������C���̃A�[�e�B�X�g4���ƃT�|�[�g�~���[�W�V�����̖��O�A������1997�N�ɃJ���t�H���j�A�ƃ����^�i�B�Ń��R�[�f�B���O���s��ꂽ���Ƃ��K�v�Œ���ɁA���Ƀv���N�e�B�J���ɏ�����Ă��邾���ł���B�ܘ_�v���f���[�T�[��~�L�V���O�͂��납�A�e�����o�[�S���y��̃p�[�g�Ȃǂ͋L�q�̂��낤�����Ȃ��B
�@�@�X�ɁA���̃C���X�^���g�J�����łǂ����̏ꖖ�̔ɉ؊X�̃l�I�����B�e���A���̂܂܃W���P�b�g�ɂ����悤�ȑS����̍���łȂ��W���P�b�g�ʐ^�B�i����͂���łƂĂ����������Ė{��̍앗�ɂ��q�b�g���Ă��邪�B��q�j
�@�@�ǂ������C�����ł̔̔����������r�߂Ă������Ă�����A�����ɓ\���������R�[�i�[�ւ̃����N�ŃW�����v���\�ł���AAmazon�@Com�D�ɕi��Łi���j�u���Ă������B�����͉\�����A���ׂ������Ƃ͂���2�N�Ԃň�x�������̂͋C�̂������낤���H
�@�@�Ƃ����̂́A�ǂ���炱��Clodhopper�̏������Ă���Our�@Planet�@Records���|�Y�����͗l�Ȃ̂��B���ɂ�Marc�@Olsen��Citizens�fUtilities�Ƃ��������\�����I�Ɋy���݂�Adult�@Alternative�n�̃A�[�e�B�X�g����������V���g���B�̃��R�[�h���[�x���ł������̂����A2000�N���炢����I�t�B�V�����T�C�g�����ł��A�V�����A�[�e�B�X�g�̃����[�X�����������Ȃ��Ȃ��ė����̂ŁA���ł͊m���ł���B
�@�@�����̊Ԃɂ������Ă��܂��O�ɁAClodhopper�̃y�[�W�͐���ڂ�ʂ��������ŁA�����Ēu�����̂ō������[���L���ɍۂ��Ĕ��ɏ����W�ɕ��S���邱�ƂɂȂ����B�C�O�ł���͂胍�[�J���o���h���������Ėw�ǂ܂Ƃ��ȏ�����ł��Ȃ��B�ȑO�ɏW�߂Ă������̋L���̒f�ЂƁA�ɏ����̋L�q���炵�����̃O���[�v���M���m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�@�@�c�O�Ȃ��Ƃ�1999�N�ȍ~�̊����Ȋ������͑S�������A�F���A�ł���B���U�܂��͋����A���R���ŁA������~�A�Ƃǂ���̂��Ă��l�K�e�B���ȗ\�z����������ł��Ȃ��B
�@�@�������Ȃ���A���̃o���h�̃��[�_�[�ł���Danny�@Pearson���O�g�̃o���h�����U������A����Clodhopper�̃A���o���𐢂ɏo���܂Ŗ�5�N�������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�܂��܂������ߊς������̂ł͂Ȃ���������Ȃ��A�Ƃ�����]�I�ϑ������Ă������B
�@�@1983�N�̌�������1994�N�̉��U�܂ŁA7���̃A���o���������[�X�����T���t�����V�X�R�o�g�̃o���h�AAmerican�@Music�@Club�B�i�ȉ�AMC�j���̃_�[�N�şT�ȃT�E���h�������I�Ȃ��[�c�̃e�C�X�g���������O���[�v���ADanny�@Peason�̏�����ł������B���I�ɂ͂��Ȃ茙���ȃo���h�ł���B�I���^�i�I�Â��ƃ��m�g�j�A�X����80�N�ォ��o���Ă����o���h�����炾�B
�@�@���̃|�X�g�E�I���^�i�e�B���ƌĂԂׂ��A�Â��J�T�ȃT�E���h��ɂ��Ă����o���h�ŁADanny�̓x�[�X�ƃo�b�N���H�[�J����S�����Ă����B���܂�ڗ����Ȃ����݂ł���AAMC����̓��[�h���H�[�J�������o�b�N���H�[�J����C�ł��������A�\���O���C�e�B���O���t�����g�}����Mark�@Eitzel�����Ɏ����Ă����B
�@�@�܂��AAMC���U��ADanny�iAMC�����Dan���`�j�̑�����Mark�@Eitzel�̃\���A���o���Ɋ���o���������ŁA��ؕ\�w�ɕ�����ł��Ȃ������B����Ȃ���ȂŁA����Clodhopper�̃L���b�`�E�R�s�[�́u��AMC�̃x�[�V�X�g�v�Ƃ���搂�����ɂ��ŏ��͑S�R�s���Ɨ����ɁA���������Ă�AMC�̃A���o������������o����Dan�̖��O���m�F��������ł���B
�@�@�ǂ����AAMC���U��ADan��AMC�ł͂��܂�ǂ����߂��Ȃ��������[�c�~���[�W�b�N��g���b�h���y�������邱�Ƃ��n�߁A�n���ɃT���t�����V�X�R���ӂ̃N���u��o�[�Œe����������Ă����悤�ł���B�Z�b�V�����E�~���[�W�V�����Ƃ��Ċ�����������A����̂�肽�����y�����Ƃ��`�ɂ������āA�o���h�̃����o�[��T���̃h�T���ł������悤�ł���B
�@�@��������1995�N�����1�N���������āA���R�[�f�B���O�����o�[���W�߂邱�Ƃɐ����B1997�N�ɐ����̃Q�X�g��Clodhopper���`�Ř^���A1998�N�ɃC���f�B�����[�X���ꂽ�A���o�����{��ł���B
�@�@���ł����I�t�B�V�����T�C�g�ɂ��ƁAClodhopper�Ƃ����o���h�̓x�[�V�X�g�ł���o���W���[���e�����Ȃ��A���[�h���H�[�J���S����
�@�@Danny�@Pearson
�@�@�ƃo���W���[�A�}���h�����A�����ăt�B�h���Ƃ��������[�c�n�̌��y����\���i�C�t�̂悤�Ɋ�p�Ɉ���
�@�@Tim�@Bierman�@�i���b�N�X�̓A�u�h���E�U�E�u�b�`���[�̂悤�ȑ̌^�ƊO�������ǁj
�@�@�Ƃ����d�͂̌��������K�v�ȏ�ɂł������ȃI���a�̃��j�b�g�`���Ƃ̂��Ƃ������悤�ł���B�i��₠��ӂ�Ȃ̂����E�E�E�E�j
�@�@���C���ł͌㐔�����o���h�����o�[��������Ă������E�E�E�E�E�B
�@�@���̃��R�[�f�B���O�ł͎�v�����o�[�Ƃ���AMC�̃h���}�[�ł�������������Tim�@Mooney�ƃv���f���[�X�̈ꕔ�ƃG���W�j�A���S�����Ă���M�^���X�g��Joe�@Goldring���N���W�b�g����o���h�Ƃ��Ă�4���̐��ƂȂ��Ă���B
�@�@�Q�X�g�Ƃ��ẮA��͂�AMC�̃����o�[�ł������y�_���E�X�e�B�[���e����Bruce�@Kaphan�ƃM�^���X�g��Vudi�������邵�A��Pearl�@Jam�i���O���������łނ�������ǁA���Ⴀ�Ȃ���ȁB��芸�������ˁj�̃x�[�V�X�gJeff�@Ament���B��̃��W���[�A�[�e�B�X�g�Ƃ��ĎQ�����Ă���B���ɂ̓s�A�m����M�^�[�A���H�[�J���܂ł��Ȃ��}���`�Z�b�V�����v���C���[�ł���J�DC�DHopkins��Diana�@Trimble�̖��O���N���W�b�g����Ă��邭�炢���B
�@�@�e�Ɋp�A�ӊO�Ƒ吨�̎����č쐬���ꂽ�A���o���̂悤�ł���B�^����Ԃ����ɑf���炵���d�オ��ƂȂ��Ă���B���͂�C���f�B��[�J�����[�x���Ƃ����r�n�C���h��90�N��̌㔼�ɂ����Ă͑S�������B
�@�@���āA�A���o���̓��e�ł��邪�A�͂����茾����Alt�DCountry�̌����̂悤�Ȏd�オ��ɂȂ��Ă���B���Ȃ�ꕾ�����������Ȍ������ł��邪�A����ȊO�ɂ͌�b�̖R�����M�҂ɂ͕\���̎d�l�������B�J���g���[�Ƃ����ɂ͂��܂�ɂ��g���b�h�̐F�������������A���b�N�Ƃ��Ẵ��C���̗͋���������߂��邽�߁i�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�O�̂��߁B�j�J���g���[�Ƃ͐����Ăт����Ȃ��B�Ƃ͂����J���g���[���b�N�ł��Ȃ��A���R����I���^�i�E�J���g���[�̃A���o���ł���Ɗ�����̂��B���AAlt�DCountry�̕K�{�ł���K���[�W�p���N�̉��͖w�ǒ������Ă��Ȃ��B
�@�@�Ƃ������A�V�������[�c�~���[�W�b�N�̌`�Ԃ̂悤�ȋC������̂����A�l�I�E�J���g���[�Ƃ������r���{�[�h�Ń`���[�g�C���������ȓ��X�J�X�J�J���g���[�ƍ����������Ȃ̂ŁA���̕\�����g�������Ȃ��B
�@�@�T�E���h�I�ɂ͐V�����A�v���[�`�͊F�ڂł���B�g���b�h�����b�N�����[���ɗ��߂����y�A�܂��́A���b�N�Ƀg���b�h�̊��������o�Ɖ��������������������y�B����A�N���X�I�[���@�[�Ƃ����g���Â��ꂽ�������K�Ȃ̂��낤���A�P�Ȃ�g���f�B�V���i���̃I�}�[�W���ɏI�n���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A���́uRed�fs�@Recovery�@Room�v�����I�ɖ��Ղ��鏊�Ȃł���B
�@�@�J���g���[�Ƃ��āA�܂��͓Ƒn����_���ăg���b�h�\���O������I�ɃA�����W�����ĕ]���A���o���A�Ƃ����悤�Ȉ��ՂŃ`�[�v�ȃA�v���[�`���S���������Ȃ��̂��B�g���b�h���b�N�Ƃ��������ɋ߂����A�W�����I���ꐫ�̖������@�ɂ��Ȃ��B���ɌÏL�����A���j�[�N�ł��������ɃR�}�[�V�����ȑn������Ă���Ƃ��낪�����̂��B
�@�@��͂�Alt�DCountry�̌���A���o���Ƃ��ČĂт����B�g���b�h�Ƃ����P����o���ƁA���b�N�Ƃ��Ă̐V�N�Ȋ��o������ꂻ���Ȃ̂ŁB
�@�@���ǂ��ǂƏq�ׂĂ��܂������A�v����Ƀg���b�h���ۂ����b�N�����b�N�ȃg���b�h�������y���߂�A���o���Ȃ̂��B�����W���Ȃ����ǁB
�@�@�U�X�h�g���b�h�h�Əq�ׂĂ������A���ۂɃg���f�B�V���i���\���O��12�Ȓ���3�Ȃ݂̂ł���B�������A����3�Ȃ����Ƀ��b�N�����[�����Ă��āA�I���W�i���̕����]���g���b�h�̍��肪���邱�Ƃ��A�ƂĂ������B
�@�@�g���f�B�V���i���E�X�R�A�����ɍăA�����W���ꂽ�̂��A#1�wDinah�x�A#10�w900�@Miles�x�A#11�wMoonshiner�x��3�Ȃł���B
�@�@�܂��A#1�́wDinah�x�ł��邪�A�g���f�B�V���i���ƒm�炸�ɒ����Ă��S����a�����Ȃ����낤�B�|�b�v�ȃ����f�B���C���ɂ�������Ƃ����]�T�̂���r�[�g�B�ƂĂ��q�b�g���̂���~�f�B�A���E���[�c�i���o�[�Ƃ��Ă̂������猆��̃`���[���Ƃ��ĕ������C���p�N�g��^���Ă����B���ۂɂ��̃A���o���������A���̋Ȃ����Ŗ��Ռ���ƂȂ����قǂł���B���C���̃��B���B�b�h�ȉ��t���f���炵���������A���̃A���o�����^�̃��@�[�W���������瑻�F�̖��������x�ƂȂ��Ă���B�S�҂Ƀt���[�`���[���ꂽ�}���h�����ƃo���W���[�̊����Ă��Ă���ł��ăW�����ƐS�ɟ��݂Ă���悤�Ȏ������B�T���߂ł��邪�A���J�ȃM�^�[���[�N�B���X�łƂĂ��m�X�^���W�b�N�ɋ����u���[�X�n�[�v�B�X�l�A�ƃV���o���́A�����f�B�̍C�������ɔ���Ⴗ��悤�ȃN���A���B���t�͊������B�����āADanny�̂��n�C�g�[���ŃV���K�ꂽ�ƂĂ��Z�N�V�[�i�j�ȃ��H�[�J���������ł������B���̂悤�ȃ��H�[�J���X�g��AMC�����2�Ԏ�ɋ������Ă����͔̂[���������Ȃ��BPoco��Rusty�@Young�Ɠ��l�A������Ă�����ʂ̃��H�[�J���X�g���B���ɖܑ̖����B
�@�@�g���b�h2�Ȃ͏��ɏЉ��Ƃ��āA�܂��͋ȏ��ʂ�#2�wWalking�@Tune�x����B���E�E���E�E�y�_�����낤���A�ƂĂ������������Ђ˂�o�����t�ɁA�}���h������o���W���[���Ǐ]����C���邢�W�J�̂��̋Ȃ����A�g���f�B�V���i���E�\���O�Ɛ�������Ă��S����a���������B�A���o���̃W���P�b�g�̕��͋C�ɂƂĂ��t�B�b�g�����A�����̈������ꖖ�̖�̂ЂƃR�}���f���ė���悤�Ȃ̂�ׂ���Ƃ����X���[�i���o�[�ł���B���A�����̃����f�B���ƂĂ��L���b�`�[�Ȃ��߂ɁA�ƂĂ������₷���i���o�[�ƂȂ��Ă���B���̂ǂ��ƂȂ������������A�q���̍��[���Ɋ������u����������I���邪������Ȃ��B�v�Ƃ������S���������悤�ȍ����͔��ɓ���������B
�@�@�����āA�X�ɖ��w�I�ȕ��߂����ƁA�����͂��ƂȂ����킵�Ȃ������������悤��#3�w1000�@Days�@Of�@Shame�x�́A�I���^�i�f�B�����̉A�T�����������邱�Ƃ��ł���B�Ƃ͂����A�I���^�i�~���[�W�b�N���L�̕��ȑދ����͖����A�}���h�����ƃo���W���[�����e�������^�C�g�ȃA�b�v�r�[�g�ɂ́A�v�킸���L���Ĉ�������閣�͂�����B���̕ӂ̃g���b�h�Ƃ��������B�I�Ȉ��D�ƃ��b�N�r�[�g�̗Z���́A����������̂�����A���ۂɒ����Ă��炤�̂���Ԏ����葁���B
�@�@#4�wCafe�@Joli�x�͂��̃A���o��������e���W�I�V���O���ƂȂ�A�J���t�H���j�A�k���Ń��[�J�[���q�b�g�����i�Ƃ������T���t�����V�X�R�̃I���J���n���W�I�v���O�����ł����j�Ȃł���B
�@�@�u�l�����̓J�E�E�p���N�o���h�ł͂Ȃ����A���J�r���[�����Ȃ��B�����Ƃ����ƃo���[�h�ɋ߂�������肵�����y�����t�������̂��B�����āA�l���Ƃ������̂������ɖ`���Ƃ͉��������̂����̂��Ă������B�v
�@�@�Ƃ���Pearson�̃R�����g�ɂ��邪�A�m���ɃX�J���Ƃ���悤�ȃ��b�N�̎������𖡂킦��悤�ȃi���o�[�ł͂Ȃ��B�~�f�B�A���r�[�g�̖��邢����∤�ɂ̓����̂��郁���f�B�����ɐS�n�悢�|�b�v�\���O�ł���B�{�g���l�b�N�M�^�[�̓c�ɏL�����F���A�}�V���̗l�ɐ��m�ȃs�b�N�����ރ}���h�����Ɛ▭�ɗn�������Ă���B�R�[���X����͂萼�C�݂̃o���h�Ƃ����ʖږ��@�ɑu�₩�ł���B���[�J���q�b�g�������Ȃ������̂́A���̃_�T���ł͎d���Ȃ���������Ȃ����A�ƂĂ��ǂ����[�c�E�|�b�v�\���O�Ȃ̂ŁA����̓i�V���i�����C�h�Ńq�b�g���ė~���������B
�@�@����#5�wGoodnight�@Nobody�x�̃X���[�Ŕ������o���[�h�łق��ƈꑧ�����Ă����̂����A���̎₵���̎��͂��Ȃ�V���p�V�B���o���Ă��܂��B���̂ƂĂ��Y�킾���Â����͂���܂�Pearson��
�@�@�u�{���̓y�����y�Ƃ����͕̂��ʂ̐l�X���̂������̂Ȃ̂��B����ŁA�W���[�N�������āA�j���W�̂��ꂱ��������Ђ�����Ɍ��߂����̂Ȃ�B�v�Ƃ����C���^�����[����̉������悤�Ɏv����̂��B
�@�@�����Ă��̃A���o���̃^�C�g���Ȃɂ��ăn�C���C�g�V���O����#6�wRed�fs�@Recovery�@Room�x�����������ēo�ꂷ��̂��B�Ƃ͂����A�������L���b�`�[�ł��A�X�s�[�f�B�ł��Ȃ����A�|�b�v�X�̊�{�̔@���Ƃ������A�R�}�[�V�����Y���Ƃ͉��������ȂȂ̂��B�o���W���[�ƃ}���h�����A�y�_���X�e�B�[���Ƃ������[�c�y�킪�����Ђ����畨�������A���{�̖��w�ɂ����������f�B��t�ł�B�����A�P�Ɂu���v�̂���Ȃł���B����ł��āA�X���[�łȂ��̂��B�r�[�g�͌���Ȃ��A�b�v�e���|�ł���B���̐��������������Y���Ƒ嗤�I�ȂƂ��������̍��I�ȓ`�������f�B�̈��D�̃~�X�}�b�`���A���̂��ƂĂ��n�}���Ă���A�����Β����x�Ƀ��s�[�g�����o�Ă���̂��B���R�Ɛg�̂������Ă��܂��̂́A���{�̖~�x��Ƃ������Ղ�̂����q�ɒʂ���悤�Ȗ������ʂ̗v�f��{�\�������邩�炾�낤���B�E�E�E����قǂ���w�Ȃ��̂łȂ��ɂ���A�m���ɂ��̋Ȃ͖������y�̏Ă������Ƃ������x�����r�V���Ɠ\�ꂻ�����B���ɉ̂��ŐȂ����ߕs�������\���ł���Pearson�̉̂����ƃ��H�C�X�͂��̃A���o����Ԃ̏o���ł���B��{�I�ɃL���b�`�[���ȕM�҂������܂œ��ꍞ�ނƂ͉�Ȃ��璿�����B���̋Ȃ����W�I�V���O���Ƃ��ă��[�J���q�b�g���Ă���B��͂肱�́A�W���P�b�g�ʐ^�̋Ȗ�̐��E�����ۉ������悤�ȉ����E�Ɏ䂩�ꂽ���X�i�[�����������̂��Ǝv���Ɗ�������̂�����B
�@�@#7�wChrystalline�x�͋v�X�ɓd�C�M�^�[�����Ȏ咣���郍�b�N�`���[���ƂȂ��Ă���B�}���h�����ƃM�^�[�̃n�[���i�C�Y�͂ǂ��ƂȂ�Hooters��A�z����Ă����B���̃��b�N�e�C�X�g�ւ̒Njy�́A�ދ��ɂȂ肩�˂Ȃ��A���o���̗�����������߂Ă���铭��������B�܂��A�ƂĂ��L���b�`�[�ȋȂł��邽�߁A�V���O���ƂȂ��Ă��\���Ƀq�b�g�����Ǝv���B��ʓI��Alt�DCountry�Ƃ����Ȃ炱�̂悤�ȃI�[�\�h�b�N�X�ȃ��[�c���b�N�E�`���[�����w���̂��낤���A����ɂ��Ă��o���W���[�̓��������铱��������A�t�b�N�̂��郁���f�B�������A�q�b�g���Ƃ����Ȃ�A���̋Ȃ��A���o���ň�Ԃł��邾�낤�B�S�̂ɂ���قǑ����Ȃ͖����̂ɁA�X���[�����C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ƃ���́A��͂�e�Ȃ̎���͂����݂��A�y���Ƃ͖��������炾�낤�B
�@�@���̂��Ƃ̓X���[�ȃi���o�[#8�wCecil�x�����A#9�wThomas�@Hart�@Benton�x�ł����Ă͂܂�B���̃t�B�h�����v�������茳�C��ȁA��ԃJ���g���[�I�Ȗ��邳��L�����i���o�[�ł��A�X�J�X�J�Ȍ��炵���E�͂����y�����������Ȃ��Ƃ���ŁAClodhopper�̑n�肾�������E���A�ƂĂ������q�̂������肵����i�ł��邱�Ƃ��F���ł���B�����Ȃ�A���̃A�b�v�E�`���[���̓J���g���[�����Ղ�\���O�Ȃ̂ł��邪�A�y�����������[�c���y�Ƃ��Ă̊y�����Ɨ����������f����̂��B������悤�ȃ`���[���ł����Ă����B���̂�����̖��͂͂܂��Ƀ}�W�b�N�Ƃ��������Ȃ��悤�Ɏv����B
�@�@���āA����Ɩ`���ŐG�ꂽ�g���f�B�V���i���E�\���O���Љ�ł���B#10�w900�@Miles�x�͂��Ȃ�m�C�W�[�ȃM�^�[�ƃI���^�i�e�B���~���[�W�b�N�̑�\�ł���d���J�T�ȃ����f�B�ʼn��t�����B���낤���ă}���h�����ƃo���W���[���h���[�c�h�̎咣���s���Ă��邪�A�c�M�^�[�̃`���[�N�����Ƃ���ǂ������A�t�B�h���ƃ��j�]������Ƃ���Ȃǂ̓~�N�X�`���[�I�Ȑߑ��̂Ȃ���ɂ����\�H�ꗍ���I�ȃo���h���v�킹�Ă��܂��B���A���̋Ȃ��g���b�h�Ƃ��čŏ�����F�����Ē����A���Ȃ�`���I�ȃA�v���[�`���s���Ă���Ɗ����邱�Ƃ��ł��邵�A�ނ�̃��b�N�����[���ւ̐��_���_�Ԍ��邱�Ƃ��\�Ȃ̂ŁA���e�͈͂�1�ȂƂ�����B���j�[�N�ȃA�����W���������̂��B
�@�@�ΏƓI��#11�wMoonshiner�x�̓A�E�J�E�y���Œʂ��ĉ̂���2�����X�̍�i�ł���B���X���Ԃ��ĕ\�������APearson�̉̏����@�ɂ������|����邾���ł���B�������͂�Ńl�C�e�B���A�����J�������̌��Ɍ������Ď�������Ă���悤�ȕ��i�������Ԃ͍̂�҂������낤���B���̃A�E�J�E�y���\���O�͂ƂĂ��C���p�N�g������B�F�X�ȈӖ��ɂ����āB
�@�@�Ō�̋Ȃ͂��Ȃ肵���Ƃ�Ǝn�܂邪�A�R�[���X�����ŃO���Ɛ���オ��������Ă���郍�b�N�E�o���[�h�̖��ȂƌĂׂ�wLittele�@Match�@Girl�x���B��₮���������Ƃ������@�ɂ܂�悤�ȉ̂��������Ă���Pearson�̃��H�[�J���������I���B���̋Ȃ��������A��ɂ͘e���ɉ���Ă���G���L�M�^�[���S�ʂɏo���i���o�[�ƂȂ��Ă���̂ŁA�o���[�h�Ƃ��Ă͂��Ȃ�p���`�͂�����B���̋Ȃ��Ō�Ɏ����Ă���ƁA�S�̂Ƃ��ă��b�N�A���o���ł������悤�Ȉ�ۂ�������̂ŕs�v�c�ł���B
�@�@����ɂ��Ă��A���̑f���炵���A���o�����ǂꂾ���̐��A���{�ɗ��Ă���̂��낤�B�������҂������Ă���ꖇ������������Ȃ��B�i�����ɂȂ��Ƃ����|���B�j�S�����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邵�A���[�x�������ł��Ă��܂����炵���̂ŁA����͍��������Ȃ����A���Ã}�[�P�b�g�ł͏o����Ă���悤�����A���B�ł͂܂������Ă���悤�ł�����B
�@�@�g���b�h�����b�N�Ő\������x�ɏ������悤�ȃA���o���Ƃ͑S�R�Ⴄ�A�[�����킢������s�[�X�ł���B���[�c���b�N���D���ȃ��X�i�[�ɂ͐�ɕK�{�ȃA���o���ł���B�������Ȃ��Ƃ��낪�Ȃ����A����ł��āA�ƂĂ��Ƒn�I�ȃA�v���[�`���{���A���ʉ��Ƃ��Ă���̂��B
�@�@�W�����E���b�N�̋l�܂�Ȃ��|�ŋ߂�Dave�@Matthews�@Band�̂悤�ȁ|�ɖO���O�����Ă���t�@���́A���̃s���A�ȃg���b�h�ƃI���^�i�J���g���[�ƃ��b�N�̃t���[�W�������ĐS������ė~�������̂ł���B�@�@�i2001�D10�D7�D�j
 �@�@�@Tug�@Of�@War�@/�@Paul�@McCartney�@�i1982�j
�@�@�@Tug�@Of�@War�@/�@Paul�@McCartney�@�i1982�j
�@�@�@�@Adult�DContemporary�@����������
�@�@�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�@Acustic�@�@�@�@����
�@�@��u���̐��͂Ȃׂčj�������B�v�E�E�E�E�E�E�E�E���Ɉ�ۓI�ȃt�@�[�X�g�E�t���[�Y���B
�@�@�u�E�H�`�`�V�A���`�`�`�`�`�B�E�E�E�E�E�\���C�P�A�\���C�P�A�\���C�P�E�E�E�E�E�E�H�`�`�`�`�`�`�`�V�E�E�E�v
�@�@�Ăȋ�ɂ��̃A���o���̖`����SE�͂ǂ����̓��{�̍��l�łނ������ؓ��_���}���j���������Ă���Ƃ����^�������Ƃ����v���Ȃ����炢�A���{����ۂ��B�p��̕�����肪����Ȃ�ɂł���悤�ɂȂ��Ă��牽���Ă��A��͂�u����s���A����s���E�E�E�E�E�v�Ƃ����������Ȃ��̂͋C�̂������낤���B
�@�@���Ȃ݂�LP����́A�^�������F����ς����@�\�t���̃v���C���[�������Ă������߁A���̊|����SE�����剹�ʂɘ^�����Ē����Ă����B�i�j���Ȃ�ςĂ��Ȏv�����ꂪ���邪�A���́u���`�`�`�`�`�`�`�`�V�v��SE�͕֏��œ������������̂ɍœK�ȃC���p�N�g�̋���Ȍ��ʉ��ł���B�i�j
�@�@�ŁAPV���j���������҂��Ă������A���܂�債�����̂ł͂Ȃ������B��uIn�@Another�@World�v�̉̎��ɃV���N�������Ė����I�ȃ��P�b�g���ǂ��̑ł��グ�V�[�����o��ق��́A�A�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�������Paul�ƌ��ɗ�����Linda���w���ȃX���[�ȐU��t����������Ƃ����ʔ����Ȃ��f����i�������̂ŁA�����������肵�����Ƃ��v���o���B
�@�@�������A#1�wTag�@Of�@War�x����ƂĂ��s��ł��|�b�v�ȋȂ����Ă����͈̂����ł���B
�@�@�ȑO�ǂ����̃������[�Łh�wEvony�@And�@Ivory�x�̂悤�ȋȂ̓������A���o����n�����̂������AMcCartney�͂������b�N�����[���[�ł̓_���ŃA�K�����q�g�Ǝv�����B�h�Ƃ������͂�ǂ��E�E�E
�@�u���O���A�K����A�{�P�I�I�v
�@�@�Ǝv�����B���̂悤�Ƀ|�b�v�ŗD�������Ղ�n���l�Ԃ�߂܂��āA���b�J�[���i�Ƃ́I�I
�@�u���O�Ȃ��������Đl�ԐC��ɂȂ��Ă�I�I�v
�@�@�Ƃ��v�����B
�@�@�Ƃ����悤�ȋ�Łi�ǂ�Ȃ��j�A����Paul��Wings���܂߂�12���ڂ̍�i�ɂ͔��Ɏv�����ꂪ����B���炭�ނ̃A���o���ł́uGive�@My�@Regards�@To�@Broad�@Street�v�Ƌ��Ɉ�Ԓ������A���o���ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�@��u�����āA�����āA�����āA�����āv
�@�@�Ɗ��炩�ȗ]�C���c���āA�X�g�����O�X���t�F�C�h�A�E�g����ƁA���h���[����#2�wTake�@It�@Away�x�������B
�@�@PV�ł�Ringo�@Starr��Steve�@Gadd�ƃV���o�����V�F�A����v���C���A�ڂ�ڂ�̃A�p�[�g�̂悤�Ȉꎺ�Ŕ�I���Ă���f���������B���t�I�ɂ͂����債���v���C�łȂ����A���t�ł�Paul�̒e�������������x�[�X���C���̕�����ۓI�����A�v�X��Beatles�̃����o�[���Q������Paul�̃\����i�Ƃ��Ă̓t�@���Ȃ�D���ɂȂ炸�ɂ����Ȃ��Ȃ��낤�B�[���A���̋Ȃ��_���������_�����ˁB�v�X��Paul�̍�i���|Abby�@Road�ȗ����|�v���f���[�X���Ă���George�@Martin�̃��[�Y�s�A�m��Paul�̃A�N�[�X�e�B�b�N�s�A�m�̃_�u���̌��Չ��F�͂ƂĂ��S�n�悢�B
�@�@�N���W�b�g�ɂ͉��̂��L�ڂ��Ȃ����A�f���C�g�t���ȃz�[���Z�N�V�����̓�����Ƃ����A��10cc��Eric�@Stwart�����C���ɐ�����Beachboys���̃o�b�N�R�[���X�Ƃ����A�T�^�I��BeatlePop�ƌ����邾�낤�B
�@�@���X�g���@�[�X�́�uFaded�@Flowers�@Wait�@In�@The�@Jar�@�C�@Till�@The�@Evening�@Is�@Complete�v�̈Ӗ��[�ȉ̎��͂���܂�PV�ł��̎��ɉ����悤�ɉԂ��f���Ă������ƂƃI�[���@�[���b�v���āA�ƂĂ��S�Ɏc���߂��B
�@�@����ɂ��Ă��A���N�̃p�[�g�i�[�Ƃ������B��c����Wings�̃����o�[�ł���Danny�@Laine���E�ނ��āA���Ȃ�Paul�ɑ��Ĕᔻ�I�ȃR�����g����T���Ă�������̔����ł��������Ƃ���ې[���B
�@�@�uPaul�͂ƂĂ��P�`�ȂB�_��ɒ�߂������Ȃ�đS�R�Ⴆ�Ȃ������B�v
�@�@�u�ނƃ����_�͔_��ł̎��f�ȕ�炵�ɖ������Ă����悤�����ǁA����͂炩�����B�����l�̐����ƌ����邩�^�₾�ˁB����ł̓o���h�̃����o�[�͌��C���w���Ă�߂�̂��d���Ȃ��ˁB�v
�@�@�܂��A�M�ғI�ɂ̓A�[�e�B�X�g���P�`���낤���A���i�������낤���A�����S���C�h�̔�p�ꌗ���Ƃ�n���ɂ��Ă��悤���A���y�����ǂ���ǂ��ł��ǂ������肷��B�u�~�E���v�݂���������̂͊��ق��ė~�������B
�@�@����Denny�̉��t�����̃A���o���ł͐����ɃN���W�b�g����Ă���B�E�ޑO�Ƀe�C�N����Ă����g���b�N��George�@Martin���ϋɓI�ɍ̗p��������ł��邪�B
�@�@#3�wSomebody�@Who�@Cares�x�ł�Denny�̓M�^�[�E�V���Z��e���Ă���B���̃A�N�[�X�e�B�b�N�ȃi���o�[��90�N��̂��Ȃ�e���V�����_�E������Paul�������R�[�f�B���O������A�����Ƒ債�Ĉ�ۂɎc��Ȃ���������Ȃ����A���̂�⍨�����������f�B�́A1980�N�ɑ��E����John�@Lennon�ւ̒Ǔ��Ȃł���#5�wHere�@Today�x�Ɠ������AJohn�ɕ������Ȃ̗l�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@�@����#5�̉̎��ɂ͐����X���ė~�����BPaul�@McCartney��John�@Lennon�Ƃ����s�o���̃\���O���C�^�[�R���r�̕Њ��ꂪ�A�S�̓���f���ɕ\���Ă���B
�@�@��uI�@Am�@Holding�@Back�@The�@Tears�@No�@More�@�C�@�h�@Love�@You�v
�@�@��uFor�@You�@Were�@In�@My�@Song�v
�@�@���̂悤�Ȍ���̒[�X�Ɂu�����ĖY��Ȃ���B�v�u�ł��A�l�͑O�ɐi�ނ�B�v�ƁA���ȕ\���ŋ��k�����AJohn�̑r�������Ƃ��C�����I�ɐ���������Paul�̐S��`����Ă��Ă�邹�Ȃ��C������B
�@�@Elton�@John�́uEmpty�@Garden�iHey�@Hey�@Johnny�j�ƕ���ŁA�Y����Ȃ��Ǔ����̂ƂȂ��Ă���B
�@
�@�@Stevie�@Wonder�Ƃ̋�����#12�wEvony�@And�@Ivory�x������������炢��є����Ĉ�ۓI�����A#4�́wWhat�fs�@That�@You�fre�@Doing�x�������čD���ȃ^�C�v�̋Ȃł͂Ȃ��̂����A��͂�ƂĂ��C���p�N�g�������B���ߗ��s�ł������e�N�m�E�r�[�g���̃f�B�X�R�e�B�b�N�E�T�E���h�ɏ悹�āA�t�@���L�[�Ƀf���G�b�g����Paul��Stevie�̃��H�[�J���́A�V���O�����ӎ����Ă��Ȃ����߂��A���Ȃ胍�A�Ń����b�N�X���Ă����ۂ���B�B�ꂽ�Ǎ�Ƃ����������낤���B
�@�@�����Ƃ��A�����܂ŃA���o���������ΉB�ꂽ�������Ȃ�����ǂ��B�i�j
�@�@���Ղł͎��I�ɑ�D���Ȗ��Ȃ�2�ȓ���B��̎��쎩���̑ʍ�f��T�E���h�g���b�N�uGive�@My�@Regards�@To�@Broad�@Street�v�ɂ����e�C�N���ꂽ#6�wBallroom�@Dancing�x��#8�wWanderlast�x�ł���B�����Ƃ��V���O��������Ă��Ȃ����A��Ɏ��IPaul�x�X�g10�ɓ��錆��ł���B
�@�@#6�̖`���̊������A�ӎ��I�ɌÏL���@���������Ă���s�A�m�\�����炵�ăL���b�`�[�Ōy���Ȃ��̋Ȃ̃|�b�v���b�N�Ȋy������\�������Ă����B�h�����Ƀx�[�X�ɃG���L�E�M�^�[�Ɩw�ǂ�Paul�����Ȃ��ADenny�@Laine�̃M�^�[���C���ȊO�̃��b�N�E�C���X�g�D�������g�͑S��Paul�̃v���C�ł���B�����Ńp���p���Ɠ���z�[���A�����W���������̂����邵�A���Ղ̃C���^�[�v���C�Ńe�[�v��ϑ���]�������悤�ȃ��H�[�J����A�z������N�����l�b�g�����Ƀ��j�[�N�ȕ��͋C�������o���Ă���B���������܂Ŗ��邢�Ȃ�������Ƃ́A���̃A���o������Ɏ��܂őz�����Ȃ������B#1�A#2�Ƃ��ɖ��邳�����������邪�A�����܂Ő����ꂽ�C���[�W�͓`����Ă��Ȃ��������炾�B
�@�@���́wBallroom�@Dancing�x���ď��߂āA�u�����APaul��Paul�ɂȂ������Ȃ��B�v�Ɨǂ��킩��Ƃ���������������̂��B
�@�@�����Ĕނ̃o���[�h�ł́wMy�@Love�x���D���ŁA�wNo�@More�@Lonley�@Night�x��wOnce�@Upon�@A�@Long�@Ago�x�Ǝ��I�ɑo����#8�wWanderlast�x�BPaul���u���̋Ȃ���Ԃ��̃A���o���ōD�����ȁB�l�͂��C�ɓ���̋ȂƃA�����W���C�ɓ���Ȃ��Ȃ̓��e�C�N�����肷�邯�ǂˁB���̋Ȃ͂ǂ����ȁB�v�Ɠ����q�ׂĂ�������ǁA����4�N��Ƀ��e�C�N���Ă���̂͂�قǂ��C�ɓ���̋ȂȂ̂��낤�B�X�g�����O�X��z�[���Z�N�V�������}������A21���I�̃V�[���ł̓I�[���@�[�v���f���[�X�ƌ��w���h���ꂻ���ł��邪�A���R�[�f�B���O���Â����߁A�A�i���O�����Ƃ��Ă̕s���Ă�����߂��Ȃ���ۂ�^����̂Ɉ���Ă�悤�ɂ��v����B
�@�@���̋Ȃ�Paul�̃o���[�h���C�J�[�Ƃ��Ă̍˔\���⊶�Ȃ����������喼�Ȃ��B���ɃR�[���X�p�[�g��Paul���g�̃n�[���j�[���H�[�J���̃I�[���@�[�_�r���O�̃p�[�g�������I�ɑf���炵���B�ނ̃��H�[�J�����t�F�C�h�E�C���ƃA�E�g���J��Ԃ��Ȃ��烉�X�g�Ɍ������p�[�g�͂��������������A���s�����[���B�����A�s��Ȏ��R�|�傫�����������ʂ̗[�Ă��Ƃ������悤�ȁ|�������Ƃ��̐S�̊g�U��������̂��B
�@�@���������Ă���̂��A�Ǎ�Ȃ̂ɂ���2�Ȃ̊Ԃɖ�����Ă��܂��Ă���#7�wThe�@Pound�@Is�@Sinking�x���낤�B�����I�ȉ��������Ɏc��V���Z�T�C�U�[�A�����W�������ꂽ�AUK�Z���X�̌���i���o�[�Ȃ̂����A��͂��ۂ������̂��B
�@�@�����āA���S�ɂ��V�тƂ������u��肽�����Ƃ���Ƃ�Ł`�I�v�Ɛ錾���Ă��邩�̂悤��#9�wGet�@It�x�BPaul�̏��N����̃A�C�h���ł��������J�r���[�̑�䏊Carl�@Perkins�ƃW�����I�ȃZ�b�V�������̏���i���B�I�[���f�B�Y�����Ƃ��������A�W���Y���H�[�J���̃A�E�g�e�C�N�Ƃ��������t�ȋȂƂȂ��Ă���B
�@�@�e�Ɋp�A�����f�B���̂����A�Ō�ő�����Ă���Carl�̏����ƂĂ�����ɋL���Ɏc��Ȃ��B
�@�@�������A���̃A���o���ł͌��C�ɉ̂��Ă���Carl��1998�N�ɐɂ��ނ炭�����E���Ă���B���������h���݁h�̎�����ڂ݂�ƁA���́uTug�@Of�@War�v����20�N�߂��o�߂��Ă��܂������Ƃ����X�Ȃ���Ɋ�����̂��B
�@�@�u���b�W�I��#10���o�āA#11�wDress�@Me�@Up�@As�@A�@Robber�x�̂��Ȃ�N�T�C�i����j������э���ł���B�̎��͑�Âł��邪�A�����f�B�͉s���z�[���Z�N�V�������Ⴆ��A�V���v����R��B���b�N���BPaul���t�@���Z�b�g�C���ɗ}���ĉ̂��Ă���̂��ŏ��̂����͋C���������������A����������Ă��邤���ɁA���t�����������ނ悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă��鎩���ɋC���t���́B�s�v�c�Ȗ��͂̂���ِF�̃`���[���ł���B
�@�@�ŁA�I�[���X���A80�N��ɗm�y���Ă����l�Ȃ�m��Ȃ������Ȃ��ł��낤�A��q�b�g�ȁwEvony�@And�@Ivory�x�B
�@�@PV���������Y�ꂽ���炢���B
�@�@�����Ȃ葋�ӂ̃s�A�m�̌������ɂ��鑋���J����I�[�v�j���O����APaul��Stevie�̕ϑ������i�j��Q��������y���e�����Ȃ��V�[���i���ۂ�2�l�őS�Ẳ��t�����Ă���B�j�ƁA�s�A�m�̏���ђ��˂�2�l�B����PV���������Ƃ̂Ȃ����y�t�@���͑��݂��Ȃ����낤�B�i�f���j
�@�@�Ƃ��Ƃ�Ƃ��|�b�v�����R�}�[�V������`�̑�قƂ��ă_���A�Ƃ������Ǎ���W�Ԃ��郊�X�i�[�ȊO�Ȃ�A�����ꏭ�Ȃ��ꂱ�̋Ȃ͖��ȂƎv�����낤�B�s�A�m�̌��Ղɋ[�������b�Z�[�W���ɂ��Ă͍��X�t�������邱�Ƃ��Ȃ�����ǁA���ɐS���܂�B
�@�@���A���F�̏ے��ł���u���߁v�|Amber���ł���Γ���ė~���������Ȃ��A�Ƃ��Ȃ��ɂȂ��ċȂ�Ȃ�ɉp��𑀂��悤�ɂȂ��Ă���v�����肵�����̂��B
�@�@�ȏ�A�v�����܂܂Ɋe�Ȃ������Ă݂��B
�@�@����ɂ��Ă�80�N�㏉�߂̃A���o���uMcCartney�@�U�v���l�I�Ɏ����C�����̂悤�ȃA���o���ł��������߁A����12���ڂ͂ƂĂ��Y�V���Ɗ����ɂ����B
�@�@1990�N��ɂ͂͂����茾���đS���_���ɂȂ��Ă��܂���������Paul�ł���B1997�N�́uFlamming�@Pie�v���ǂ��E�ǂ��ƕ]������Ă��邪�A1970�N���Paul�Ɣ�r������A�c��ΓI�Ȏc�O�A���o���ł���Ǝv���B�s���R�ɃA�N�[�X�e�B�b�N�H����_���������́B
�@�@�l�I��Paul�ŕ]���ł���̂�1989�N�́uFlowers�@In�@The�@Dirt�v�ŏI�����Ă���B���A�ނقǂ̍ˋC����V�˂Ȃ炫���Ƃ܂��܂��B����������ɈႢ�Ȃ��ƐM���Ă���B
�@�@�uLiverpool�@Oratorio�v�ŃN���b�V�b�N�Ȃ���Ă�ꍇ��Ȃ��Ł`�A�Ǝv���̂����B
�@�@��͂茻���̃A�[�e�B�X�g���̂̃A���o�������ǂ������Ȃ��A�Ɖ�ڂ����͓̂��l�����Ă��Ȃ���h�����̂�����B������ԗ~�����BHere�@Today���v���̂��B�@�@�i2001�D10�D12�j
 �@�@�@Little�@Big�@Man�@/�@Jono�@Manson�@�i1998�j
�@�@�@Little�@Big�@Man�@/�@Jono�@Manson�@�i1998�j
�@�@�@�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@Blue-eyed�@Soul�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here
�@�@John�@Hiatt��Johnny�@Thunders�AElvis�@Costello�Ƃ������O�͒m���Ă��Ă��AJono�@Manson�Ƃ������O��m��Ȃ����y�t�@���͈��|�I�ɑ������낤�B
�@�@�܂��A���N�ɂȂ��đQ���Җ]��7th�A���o����4�N�Ԃ�Ƀ����[�X����Blues�@Traveler�͑�D���ł����Ă��A���̃o���h�ɊW�̐[��Jono�@Manson�Ƃ̌q�����S���m���Ƃ��Ď����Ă��Ȃ����X�i�[���w�ǂł���Ǝv���B
�@�@�܂��A���{�Ղ��S�������[�X����Ȃ��̂ŁA�d���Ȃ���������Ȃ����A�ނ̂悤�ȍ˔\���郔�H�[�J���X�g���Љ�Ȃ����{�̃��f�B�A�̊�̓r�[�ʈȉ��̍ގ��ł���̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�i���������j�����A�A���Ր��X�ł��X���ł͑S�������������Ƃ��Ȃ��B�܂��A�ő��Ƀ��R�[�h�X�֑����^�Ȃ��M�҂̂��ƂȂ̂ŁA�u���R���������v�ڌ�������|�[�g���đՂ���K���ł��邪�B�i��̐��������I�j
�@�@���O���琄�@�ł��邩������Ȃ����A���̃I���a�͈ږ��n�̃o�b�N�O���E���h�����B�ɑ������̌��c�Ɏ��j���[���[�J�[�ł���B
�@�@�����͖{���́u���[�m�v�܂��́u���m�v�E�}���\���ł��邪�A�A�����J�̏�Ń����_�����W�����_���ƁA��A�t���J�̃��n�l�X�u���O���W���n�l�X�u���O�Ɣ�������l�������悤�ɁA�W���m�E�}���\���ƌĂԐl�������B�p�ꔭ���Ƃ��Ă͐����������B�I�������[���ɂ̂��Ƃ�Ζ��炩�ȊԈႢ�ł��邯�ǁB
�@�@�܂��A�M�҂̓��[�m�E�}���\���ƌĂ�ł���BF1�h���C�o�[�ł���C�^���A���̃����m�E�g�D���[�������[�m�ƌĂԂ݂����Ȃ��̂ł���B
�@�@�ނ̉��y���̓��b�N�����[������{�ɂ��āABar�@Rock�AR&B�A�\�E���A�u���[�A�C�h�E�\�E���A�u���[�X�Ƃ������l�X�ȃ��[�c���b�N�̈��q�������������ɂ������̂ł���B
�@�@���������Ɛߑ����Ȃ����y����w�������~���[�W�V�����̂悤�Ȍ�����邩������Ȃ����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͌����ĂȂ��B�ŏ��ɋ�����John�@Hiatt�̂悤�ȃT�U�����b�N�̃��t���AJohnny�@Thunders�̖\���V�ȃ��b�N�X�s���b�g�AElvis�@Costello��R&B�������ꂽ�|�b�v�Z���X�A�����S�Ă������Ă���̂��B
�@�@�܂�A���W���[�ł��\���ʗp�����^���H�[�J���X�g�̃A���o���̗l�ɕ��ՓI�ȃ|�b�v���b�N�̃c�{�|���̍۔�����ɑ������Ƒ����U����Ă����Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�|�����������Ȃ������l�Ȃ̂ł���B
�@�@�A���AMTV�ŌJ��Ԃ��I���G�A�����悤�ȃL���L�������h�肳��`�����`���������y�����Ƃ͖����̃I���a�ł���B�܂��A�������������m�������Ă����瑽�������܂ō��ꍞ�ނ��Ƃ͂Ȃ������낤���B
�@�@�����A��߂��Ȃ��AMichael�@Bolton����I�[���@�[�v���f���[�X�ȕ������킬�Ƃ��āA���[�c�ȃt���C���@�[�����������T�E���h��z�����Ă��炦�悢���낤�B���H�[�J����Michael�قǂɂ̓\�E���t���ł͂Ȃ����A���Ȃ�M���̏������Ă����l�ł���B
�@�@����CD����ł̃v���P�[�X�ɂɓY�t���ꂽ�V�[���̃L���b�`�R�s�[��Ă݂悤�B
�@�@�u�����AJono�@Manson�����̐��ɂ��Ȃ�������ABlues�@Traveler�ASpin�@Doctors�AJohn�@Osborne�Ƃ������j���[���[�N��Jam�@Band�V�[���͔����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���̔삦���o�[�̒��O���K�c���ƈꔭ�Ԃ��̂߂��āA�ނ̔M��ȐM�҂ւƕς�������Manson�̑S�Ă������ɂ���B�v
�@�@���X��U���ȃR�s�[�ł��邪�A���̃A���o�����A���X�̃o�[�o���h��b�N�o���h���߂��ĖO���O�����A���X�̃T�E���h�ł͎��ڂ��X���Ȃ��Ȃ����j���[���[�J�[�̋C���邢�������܂��悤�ȋȂ��l�܂��Ă��邱�Ƃ��ǂ������邾�낤�B
�@�@�e�Ɋp�A�p���[�ƒj�L�������_�́A�����ȃ��b�N�A���o���ƂȂ��Ă���B
�@�@�v���f���[�T�[��Yayhoos��Eric�hRoscoe�hEmbel�A�������������Joe�@Flood�̃v���f���[�T�[�ł�����BEric��Joe�@Flood�Ƃ̕t������������Jono�̃L�����A�f���Ă��A�~���[�W�V������Joe�@Flood��2���ڂ̃A���o���̊�Ԃ�ɋ߂������o�[���W�߂��Ă���B
�@�@Jono�@Manson�@�iL�DVocal�CGuitars�j�@�C�@Joe�@Flood�@�iGuitars�Cfiddle�CMandolin�CVocals�j
�@�@Steve�@Lindsay�@�iBass�j�@�C�@Will�@Rigby�@�iDrums�j�@�C�@Joe�@Terry�@�iPiano�COrgan�CKeyboards�j
�@�@Eric�@Ambel�@�iGuitars�CVocals�j
�@�@���̃����o�[��Joe�@Flood�̃������[�ł����y���Ă���̂ŁA��������Q�Ƃ��đՂ���悢�Ǝv���B����ɂ��Ă������ɂ�Eric�@Ambel�֘A�̃~���[�W�V�������W�߂����C�݃��[�c�V�[���̍ՓT�̂悤�ȃ����o�[�ł���B
�@�@���̃��C���i�b�v�łȂ���Ƃ������t���Ȃ���锤���Ȃ��AJono�̃\�E���t���ȃ��H�[�J���Ƒ��܂��āA���t�Ń��[�c���A�ȉ��t���W�J����A�����͂����Ղ�Ƃ��Ă���B
�@�@Joe�@Flood�����������ɏo�����A���N�f���炵�����[�c���b�N�A���o���uCrippin�fCrutch�v�������[�X�����ނ����A�Ƃ����₷���|�b�v���ƃ��H�[�J���X�g�Ƃ��Ă̗͗ʂŁA�����Jono�@Manson������s���Ă���Ǝv���B
�@�@�ȑn��ɂ�Joe�@Flood�Ƃ̋����14�Ȓ�6�ȂƂ��Ȃ�̃E�G�C�g���߂Ă���AJoe�̃R���|�[�Y�̃Z���X�͂��̃A���o���ł��f����B�܂��\���O���C�e�B���O�Ɋւ��ẮA���̃A���o���̃����[�X�̑O�N1997�N�ɋ}������Jono�̃\���O���C�e�B���O�p�[�g�i�[�ł�����Jeffrey�@Barr�ɕ������Ă���BJeffrey�Ɍh�ӂ����߂Ă��A�A���o���̃g��2�Ȃ͔ނƂ̍�i�����ׂ��Ă���B
�@�@���͊O�����C�^�[�̋Ȃ�3�ȁi1�Ȃ�Jono�Ƃ̋���j��Jono�P�Ƃ̋Ȃ�4�ȂƂȂ��Ă���BJoe�@Flood�����|�b�v�Ɏd�オ���Ă���͎̂����̃��C�e�B���O�����łȂ��A�O�ւƃh�A���J���đ��̃��C�^�[���}������Ă��邩�炩���m��Ȃ��B
�@�@���āA���́uLittle�@Big�@Man�v�̓X���[�ȋȂ��A�b�v�e���|�ȋȂ��A�ϓ��ɋؓ����̗͂��U���Ă��āA���̗L��]��G�l���M�[�����o���Ă���悤�ȃr�[�g��������Ƃ��Ƃ��ł���B������Eric�@Ambel�̎�|�����i�ɂقڋ��ʂȃ��[�Y���Ƃ������ْ����������������悤�Ȋ��o���Y���B
�@�@�K���K���Ƀ��b�N�����t���Ă��Ă��A�ǂ����������ŗ͂��Ē����鉹�y�ł���B�����I�ɕ]������Ă���X���[�~���[�W�b�N�n��̖����n�Ƃ͑S������قɂ��Ă��邪�A�킴�Ƃ炵���X���[�A�N�[�X�e�B�b�N��T�b�h�R�A�n�̑ދ�����@�ɂ������Ȃ����b�N�����[���Ƃ��Ă̊�т����݂���̂ł���B
�@�@�A���o���͑����i���o�[�ƃ~�f�B�A���`���[���A�X���[�\���O�����悭�ϓ��ɎU��߂��Ă��邪�A�I�[�v�j���O�̓~�f�B�A�����b�N�`���[������n�܂�B
�@�@����̗ǂ�Jono��Joe�@Flood�̃c�C���E�M�^�[���D�L���Ƃ����������C�݃��b�N�̃X�}�[�g��������������#1�wI�@Wish�@I�@Could�@Here�@From�@You�x��Jono�̃\�E���t���ȃ��H�[�J����Eric��Joe�̔Z���ڂ̃n�[���j�[���H�[�J�����킳�邪�A�y���Ń\�t�g�ȃ����f�B���T�N�T�N�ƍ��܂�邽�߁A���ꂵ���������邱�Ƃ͂Ȃ��B�I�[�v�j���O�Ƃ��ă}�C���h�ȕ��͋C���o���Ă���Ƃ����Michael�@Bolton�̖��Ղ̃I�[�v�j���O�ł���^�C�g���Ȃł�wSoul�@Provider�x�ɋߎ������Ƃ����������B
�@�@�����āuRascoe�߁v�Ƃł��ĂԂׂ��AEric���D��Ńv���f���[�X�����\�̂悤�ȃ��b�N�i���o�[#2�wDon�ft�@Mind�@If�@I�@Do�x�B�R�[���X����#1�Ɠ������AJoe�@Flood��Jono�A������Eric�@Ambel��3�l�B�C���^�[�v���C��Joe���t�B�h�������C�ǂ���点�A�X�g�����O�X���g�������b�N�`���[���̑���ւ̃A���`�e�[�[�̂悤�ȃ��[�c���b�N�`���[���Ƃ��Ďd�グ�Ă���B����ɂ��Ă��h���}�[��Will�͂����Ȃ��猘���ȃh���~���O�����Ă����B
�@�@Joe�@Terry�̃I���K�����t���[�`���[����ăp���t���Ƀ\�E���t���ɂ��˂��Ă���R��B�I���G���e�B�b�h��Jono�̊�������������ɂ��ꂽ�A#3�wAlways�@Will�@Always�@Mean�@You�x�͋���Ă��܂����̃X�g���[�g�ȃ����E�\���O���B�G���[�V���i���Ń����n���̌�����Jono�̃��H�[�J�����X���[�o���[�h�ɂ��ǂ��f����Ƃ����ؖ��������悤�ȃi���o�[�ł���B
�@�@����#4�wFinest�@Hour�x���X���[�o���[�h���A������B�y�_���E�X�e�B�[�����J���g���[�E���b�N�I�ȕ��͋C�������o���Ă��邪�A��͂胔�H�[�J���E���b�N��Adult�@Contemporary�ȃg���b�N�Ƃ��Ē������Ă��܂��̂́AJono�̃��H�[�J�����ƂĂ��G��ł��邩�炾�낤�BJoe�@Cocker���̃��H�[�J���X�g��r���Ă�������Ƃ��낪�Ȃ��B���t����Ȃ̓��W���[�����łȂ��C�����Ȃ����̂ł��邯��ǂ��B
�@�@R��B�̃��Y�����o�Ƃ������r�[�g���o������C�Ȃ����t�ȃr�[�g�ɏ��������#5�wSure�@Looks�@Good�@To�@Me�x�͂Ƃ�����`�[�v��R��B�̃r�[�g�����C�g�E�O���[���ȃ��Y���Ŗ��邢�u�M�[���Ɏd�グ�Ă��āA���̂�����̃��[�c�o�b�N�Z���X��Eric�̎�r�ɂ��Ƃ��낪�傫���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@#6�wGone�CGone�CGone�x�́A�E�F�X�^�����̃n�[�h�h���C���E�J���g���[�i���o�[�ł����ɂ��ꑧ���悤�ȈӖ������ő}�����ꂽ�悤�ȍ�i�B�����A���܂肱�̃A���o���̃J���[�ɂ͍����Ă��Ȃ��Ƃ͎v�����B
�@�@Joe�@Flood�̃}���`�v���C���[�Ԃ�������茘���}���h�����̒��ׂ�#4�ɑ����y�_���E�X�e�B�[����e��Tom�@Brumley�̉��F���������Ƃ������E���\�z����#7�wNo�@Strings�x��Bruce�@Donnola�Ƃ������H�[�J���X�g�̏������n���ȃo���[�h���B�����Ȃ��ȂȂ̂����A���̃}���h�������S�ʂɏo���ꂽ�AJono�̃V���E�g�Ŏn�܂�~�f�B�A���`���[���̂��߂Ɉ�ۂ������B
�@�@#8�wLittle�@Baby�x�͏I�n�}���h���������������F�����˂点��A�T�U���E�\�E�����̃|�b�v�`���[���ŁAThe�@Band�𖾂邭���A�z���L�B�Ȋ��o���v���X�����悤�ȓ��Ȃ��̃��b�N�Ƃ����悤�Ȃ��Ղ�`���[�����B�I�n�X�D�C���O����}���h������Jono���J�b�e�B���O����M�^�[�̌㔼�ł̊|�������̓A�E�h���u�̋ɒv�̂悤�ȋC�����Ďv�킸�g�̂����Y�����Ƃ��Ă��܂��B���Ոȍ~�͂��X���[�e���|���嗬�ɂȂ邱�̃A���o���ł��邪�A��͂�A�N�[�X�e�B�b�N�ȃX���[�i���o�[#9���o�߂���#10�́wUnder�@The�@Gun�x���x���͂Ȃ����A����قǍ����ȃ��b�N�ł��Ȃ��B�u�M�E�M����50�N����v�킹��`���[���ŁAJono��Joe�̃c�C���d�C�M�^�[���D�L���u�M�[�����C�����o��t�ɉ��t����p�[�g�͒������̂ł���B
�@�@#11�wMadman�fs�@Sky�x���O�Ȃ̂悤�Ȃ�⍕���ۂ��S���͂̂���Â��X���[�`���[���ł���B����2�Ȃ̂悤�ȃ\�E���⍕�l���y�ւ̕肪����Ə������蒮���Ă��Ċy�����Ȃ��̂����AJono�̃o���g���Ƃ܂ł͂����Ȃ������ʂ̖L���ȍ��l���H�[�J���Ƃł��ʗp���鐺���ɂ͂ƂĂ��}�b�`�����Ȃł���B�ނ͉̂��郌���W���ƂĂ��L�����Ƃ����߂ėǂ�������B
�@�@#12�wLittle�@Bird�@Told�@Me�x�ŋv�X�ɖ��邢�Ȓ��̃~�f�B�A�����b�N���͋����W�J����B�����ł�Eric���G���L�M�^�[�������A3�l���M�^�[���[�N�����Ă����B��͂肱�̂悤�ȃ��b�N���̃i���o�[�ŁA���̖��͂�����l�ł��邱�Ƃ͋^���l�̂Ȃ��������B
�@�@���̂��Ƃ́A�㔼�̎R�ł���X�g���[�g�ȃ��b�N�i���o�[#13�wSomebody�@I�@Will�@Take�@My�@Rest�x�ōX�ɐ����͂����Ɏ���B�I�[���h�X�^�C���̃}�V���K���̗l�ɘA�ł����s�A�m����т��Ē��ˉ��B�M�^�[�����[�Y�ɑ~���炳��A�n�[���i�C�Y�E���H�[�J���Ƃ��ď������H�[�J�����t���[�`���[�����A�X��3�l�̃o�b�N���H�[�J�����������A�������Ґ��Ɏx����ꂽ���H�[�J���p�[�g�͑f���炵���̈ꌾ�B
�@�@���ɂ͐[���A�����Ă܂����ɂ̓V���E�g���ďc�����s�Ɋ���Jono�̃��H�[�J���̓t�B�[���[���̃T�|�[�g�ɂ悭�������Ă���B�܂��A�}�C�i�[�R�[�h���Ƀt�F�C�h�A�E�g����G���f�B���O�����ɃN���V�J���ȃ��b�N�����[���Ƃ�����ۂł���A�y�������_�ȃ`���[���ƂȂ��Ă���B
�@�@�����āA#14�wHolding�@You�@Near�@To�@Me�x�ł͍ēx�y�_���X�e�B�[����������Ă��邪�A���Ƃ������������F��a���ł���Ă���B���[�c�i���o�[�Ƃ���������ړI�Ȗ��o���[�h�Ƃ��Ē����������ƂĂ�����̂����A�Z���B3���ɖ����Ȃ�����i�ł���̂��c�O�ł���B
�@�@���āAJono�@Manson�Ƃ����l�ɂ��Ă����A�N�����Ă����B2001�N11���ɁA2000�N�ɁuLive�@Your�@Life�v�������[�X��������Ȃ̂Ɋ���5��ڂ̃\��������Ƃ����̂��B�^�C�g���́uUnder�@The�@Stone�v�ŃW���P�b�g���������Ă���B�T���v�����c�O�Ȃ���܂������Ȃ����A�n�Y���͂Ȃ����낤�B
�@�@�Ƃ������ƂŁA�ڂ����p�[�\�i���f�[�^�ɂ��Ă͂��̐V�����܂��́uLive�@Your�@Life�v�ŏq�ׂ邱�Ƃɂ��悤�ƌv�悵�Ă���B����Ă����ł͊ȒP�ɐG��Ă������Ƃɗ��߂悤�B
�@�@Jono�@Manson��80�N�㏉�߂���A�j���[���[�N�̃o�[���b�J�[�Ƃ��Ċ��������Ă���20�N�ȏ�̃L�����A�̂���~���[�W�V�����ł���B
�@�@���W���[�f�����[�����̂�1995�N�ɑ�背�[�x����A��M����ł���BJono�@Manson�@Band�Ƃ����o���h���Ń����[�X���ꂽ�A���o����Blues�@Traveler��Bob�@Seenham��Chan�@Kinchla���o���h�����̍��ԂɎn�߂��v���W�F�N�gHigh�@Plains�@Drifter�Ƃ������j�b�g�̃��H�[�J���X�g��Jono���������Ƃ��납��n�܂�B
�@�@Jono��Blues�@Traveler�̍ő�q�b�g�A���o���ł���1994�N�́uFour�v�Ƀo�b�N���H�[�J���Ƃ��Ă��Q���B
�@�@High�@Plains�@Drifter�Ƃ��Ă����s���Ċ����𑱂��邤���ɁAA��M�̊��m�āAJono�@Manson�@Band�Ƃ��ĕϖ���Blues�@Traveler�̃����o�[�������ă��R�[�f�B���O������B���́uAlmost�@Home�v�ɂ�John�@Hopper���n�[���j�J�ŎQ�����Ă���B
�@�@���A�Z�[���X�͑厸�s�ł������B���Ȃ�n�[�h�ȃ\�E�����u���[�W�[�ȃA���o���ł��������߁A��ʎ���������悤���B�����Ă܂����C���f�B��������Jono�̓C�^���A�݂̂ŁuOne�@Horse�@Town�v��1997�N�ɔ����B�A�����J�ɂ��t�A������ꕔ�ōD�]�������߁A����uLittle�@Big�@Man�v�̔������ĂуA�����J�Ō_��ł����ƌ�����ł���B
�@�@���̃A���o�����Z�[���X�I�ɂ͑S���ڗ��������Ƃ͂Ȃ��AJono�͐l�C�̂���C�^���A�≢�B���S�Ń��C���������s���悤�ɂȂ�A�A�����J�ł͂܂��������Ă���High�@Plains�@Drifter�̃��H�[�J���X�g�Ƃ��ăX�e�[�W�ɗ����Ƃ��w�ǂɂȂ�B
�@�@2000�N�ɂ͂�͂�C�^���A�̃��[�x������uLive�@Your�@Life�v�������[�X�B����܂��L�����A�ō�����ł���̂�����ǂ��A�A�����J�����͐����ɂ���Ă��Ȃ��E�E�E�E�E�B
�@�@�����A�Ηz�̊����������A�ȒP�ɔނ̌o�����L���Ă݂��B
�@�@�������A���̂悤�Ȑ����h���[�c�Ƃ������A�����J�����b�N�E���H�[�J�����S���ʗp���Ȃ��A�����J�̃��W���[�V�[���͂����M�҂Ƃ��Ă͂���ł���B
�@�@�ŋ߃��[�c�n��I���^�i�J���g���[�̃o���h�̉��B�ւ̓����Ƃ������������_�̃`�F���W�������ł���B��͂蔄��Ȃ��s��ɂ��Ă��d���Ȃ��Ƃ͗����ł���̂����A���Ẵn�[�h���b�N�Ɠ����悤�ȓ���H���Ă���̂��ƂĂ��s���ł���B���A���{�ł�HR�����E�ŗL���Ɏ��Ě�����Ă���̂ɑ��A���[�c���̈����͂���������ł���B
�@�@������]���Ȃ��I�����ɂȂ肻�����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�B
�@�@���A�̊i�I�ɂ͑啿�Ƃ͂����Ȃ����A�����ł��Ȃ��AJono�@Manson���u�����ȋ��l�v�Ƃ��ăV�[���ɓ����Ă���Ă������͔ނ̉��y�����Ƃ��ł���̂�����A�܂��K���Ȃ̂��낤�B
�@�@�^�C�g���̗l�ɂ��̃A���o���uLittle�@Big�@Man�v�́A����␢���̕]�������u�����v���������A���e�́u�傫���v�ꖇ�ł���B���̋@��ɖ{�M�ł͖����̔ނ̖��O��m���ĖႦ��Ύ���̊�тł���B�@�@�i2001�D10�D22�D�j
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
