 Selfish Propensities / Nana (1998)
Selfish Propensities / Nana (1998)Roots ★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★★
Southern ★
You Can Listen From Here
 Selfish Propensities / Nana (1998)
Selfish Propensities / Nana (1998)
Roots ★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★★
Southern ★
You Can Listen From Here
どうせレヴューは長くなるに決まっているので、取り敢えず言いたいことだけフォントを大きくしてぶち上げておく。
The Dirty Truckersが当たりやったら四の五の言わず
に買うとけ!
現在商流に乗ってへんので普通には買えへんけど、
Tom Bakerさんにメールして送金してでも買え!!
とまあ、この2つだけは言っておかないと、長いレヴューが読みたくない方には筆者のメッセージが伝わらない可能性があるので、取り敢えず叫んでおいた。
仮の話であるが、もし欲しい方が10人集まれば、管理人がTomさんと交渉しても良いです。掲示板にメッセージを残してください。
The Dirty Truckersを奇特にも筆者経由で購入してくれた方やMiles Of Musicで独自に買われた方には説明の必要もないかもしれないが、このNanaという、日本人の名前にも使われるし、西洋の女性名にも使用される些か可愛らしい名前のバンドは、ボストンの最高に素晴らしいThe Dirty Truckersのリーダー、Tom Baker氏が2001年に
「Bush League Romance」をThe Dirty Truckers名義でリリースする以前のプロジェクトである。
このTomがリーダーとなるセカンド・プロジェクトの前に、同じく2000年録音のこれまたボストン・ベースのバンドであるScrimshandersというルーツロックバンドにもギタリスト兼バックヴォーカリスト、そして1曲リードヴォーカルとして正式メンバーとしてクレジットされている。
The Dirty Truckersよりはかなり大人しいScrimshandersのデヴューアルバム「Longneck」は、Tomが曲創りには自身がリードを取る1曲しか関わっていないためか、キャッチーさやロックンロールの醍醐味としては相当に地味でポップさは今一歩であるが、良質なオルタナカントリー系のアルバムであるから購入して損をすることは絶対にない。
そしてTomの作品で、彼のヴォーカルが聴ける#5『Dealer’s Choice』はかなりコマーシャルでワイルドなポップロックチューンなので、必聴である。が、このバンドもTomが牽引役となれば、もっと吹っ切れたルーツロックアルバムになったのは間違いないだろうから、その点は残念である。
と、あくまでも今回の主役はTom Bakerでありその1stプロジェクトであるNanaであるから、そちらに焦点を当て直すことにしよう。
名前は結構女性的でコケティッシュな感じもするが、サウンド性は最高にアグレッシヴなロックンロールである。女性的というか中性的なナヨナヨした不甲斐なさは、微塵もない剛球一直線なロックサウンド。
走り出したらアクセル全開、熱暴走したエンジン、ロケットの打ち上げ、砂埃を上げて疾走する4輪駆動車、水煙を上げて突き進むジェットスキー、というような爆走一直線な、タテノリでタテノリでタテノリな性的快感を覚えそうなメガキャッチーなロックンロール。
が、適度な感覚で散りばめられた、少々のじっくりと耳を傾けられるスローナンバーも存在し、単なる底の浅いバンドでないことは言及する必要もないだろう。
単なるノンストップなインディパンクロックバンドやガレージロックバンドのような、お下劣さや粗野さを売り物にしてガキンチョの関心と尊敬を故意に集めようとしている、似非破壊・反抗願望を代弁するようなボケタレ楽団共とは次元が違うのだ。
ハードなロックンロールのようなイメージを上の文章で持たれるかもしれない。が、断じてハードロックではない。ハードでオーヴァーに詰め込み過ぎなギタープレイを看板にしたり、ヘヴィなリフを売り物にするハードロックの悪い点は爪の先程も存在しない。
また、ハードロックのこれは時には良い点でもあるが、胃もたれするようなヘヴィでノイジーなアレンジもされていないし、キャッチーさを削るようなこともしていない。
これは、Bar Band、Southern Rock、Roots Rockといったアメリカンロックの「動」な要素を全て程よく取り入れている。ここにPunk RockやGarage Rockの1990年型のサウンドの新しさもしっかりと加味されている。だからして、この「Selfish Propensities」はロックンロールなアルバムである。Pop&Rockなアルバムなのである。
言い換えれば、どんなに流行が変化し、オルタナティヴやラップ入り擬似メタルバンドといった歌心の核を忘れた音楽がメジャーシーンを席巻しようが、断固として存在するKing Of Rock And Rollな音楽性。
ロックチャンネルのラジオから流れてきた瞬簡に、皆が耳を無意識のうちに傾け、つま先でビートをなぞるようなサウンドなのだ。
鉱物や宝石の無機物に例えるなら、差し詰めNanaは玄武岩の鏃のような質感があるだろうか。鋭く、タフで、へこたれない強さを持つ。鈍色の原始的な武器というソリッドな映像が音を耳にしていると浮かんでくるのだ。
また、ジャケットに人体模型の如くな、あるいはマネキンのようなノッペラ坊的な写真を使っている。これは正直センスが良いとはお世辞にも思えない。が、それ以上に問題であると考えている・危惧しているのは、このジャケットが冷たく、アーティフシャルな音を主体にしたバンドではないかと第一印象やジャケットからの連想されるヴィジョンで誤解されないか、ということである。
ヘヴィでハードでノイジーなプレイが聴かれるというのはイコール、音楽に冷たく、押し付けがましく、ゴリゴリでガンガンとヒットするようなサウンドであるのに、人工的で血の通っていないオルタナティヴの唾棄すべき最悪な冷血サウンドにも共通する点であると思う。
そう、どれほどスピード感に溢れるロックンロールを好きでいるというか、中毒患者である筆者が、グランジ以降のアメリカンロックである(個人的にはロックと認めない人工雑音であるけども、便宜的にそう呼ぶ。)、ファンクもヘヴィもハードもスピードも無機質でポップさを申し訳しか足さない聴くに堪えないサウンドで表現している、オルタナティヴを家庭内害虫と同等に毛嫌いするのは、まさにこの瑕疵の所以である。
どれほどポップでデコレーションしようが、コマーシャリズムで塗り固めようが、Alternative Heavyという音には暖かい血肉の通った包容力を全く知覚することが不可能であるのだ。
極論であるが、高度に発達したロボットがプログラミングで楽器を弾き、歌を創っても殆ど遜色のない音楽が量産できると思う。楽器という無機物から、人間の感情という有機体の中でも、一番オーがニックな部分を震わせるエレメントを創造するのが音楽という存在意義であると思う。
コンクリートとアスファルトとガラスを衝突させてその騒音をメロディにしたような冷たい、冷え切った音がオルタナティヴの代名詞である。無機質なビートやリズムも稀に親しむのは悪くないとは思うが、心の入っていない、小手先だけのヘヴィネス、ロックという擬態−生命体はすべからく生命を守るための擬態を有するが、この故意にロックンロールという大衆文化の至宝の上っ面だけをなぞるような、外惑星の様に冷え切った音は醜悪以外の何ものでもない。
ロックンロールには静・動を問わずに秘められたパワーを感じるものであるが、ただヘヴィさをハードさを、憂鬱や怒りといったネガティヴな感情の表現方法とするというスケープゴートを掲げることで正当化したサウンドに、力・パワー・馬力という要素を真性に感知することは不可能である。少なくとも筆者の感性に於いては。
前置きというかどす黒い怒りを垂れ流してしまったが、このNanaには人工的な嫌らしさも、心の全く入っていない抜け殻だけの単純なヘヴィ&ハードさに充満している空虚さはまるで存在しない。
NanaのTom Bakerの音楽性が、ハードドライヴィンで、ヘヴィで、力任せであっても、その根底にはしっかりとどことなく懐かしい雰囲気がある。恐らくは人類発祥から同時進行してきた原始宗教の儀式では必ず叩かれたパーカッシヴなリズムや弦楽器の音色。こういった記憶の底に滓の様に沈殿している魂の始原の核に触れる、プリミティヴな熱い魂が篭っているのだろう。
まあ、小難しい表現を弄さなくても、聴き手のことを考え、自らの方向性をしっかりと抱え、良い曲を創り演奏すれば必ず魂が宿るだろうということだ。西洋風に言い換えればスピリッツだろうか。
であるからして、Nanaのタテノリ直球なロックサウンドに圧倒されている時も、無機質な金属がこすれ合うように不快な音は全く聴こえてこない。熱いスープを厳冬の屋外で飲んだ時に、胃の腑で感じる、織炎のようなじんわりとした暖かい核が心のど真ん中に浸透してくるように感じるのだ。
無論、ヘヴィ=熱い等という、頭の悪い分類は全く考慮する必要はない。きっとこの「Selfish Propensities」が、スローナンバーが大半なアルバムであっても、熱いロックの鼓動はきっと伝わってくる筈だ。
荒くてハードでタフネスさグイグイな音なのにハートウォーミング。これはヒューマン・ロックンロールと呼びたい。
このNanaやThe Dirty Truckersだけでなく、Human Rock’n Rollは全米のインディ・シーンには沢山あるのに、全く顧みられることがないのは、アメリカの市場が歪みの極致に達しているからであり、本邦に至ってはもうとっくの昔に匙を投げているので、大勢の同意や理解を求める必要も認めていない。
もう、分かるヤツが分かればエエねん、と悟りを開いた心境である。
さて、否定的な文章の割合と、未整理な論理を大半に垂れ流してしまったように思えるので、この辺でしっかりとこのアルバムの良さを具体的に語っておこう。
全体の流れは前述の簡潔な繰り返しになるけども、キャッチーでポップなメロディを基本としてハードでドライヴィン・フィーリンなロックンロールである。
ポップさの度合いはThe Dirty Truckersと殆ど肩を並べるくらいである。つまり最高なキャッチーなメロディを堪能できるということである。
が、ルーツっぽさ、というか土臭さはThe Dirty Truckersより相当薄い。「Bush League Romance」で顕著であった乾燥帯を吹き抜けるような一陣の風、という表現が似合いそうなアーシーさは少ない。
とはいえ、ガレージロックやパンクサウンドが突出しているというと、そこそこには耳に感じることが出来ても、それらが主体ではない。やはりアーシーさは存在するが、それ以上に幅を利かせているのが、英国で言うPub Rockの重量感である。アメリカで言うBar Band程にはカントリーやグラスソング系譜の埃っぽさを匂わせない。がブリティッシュロックと縦割りするのもやや不足な範疇付けである。
Georgia Satellitesの1stアルバムで顕著であった、ハードロック系のアメリカンロックの肌触りに一番近いようにも思える。FacesやQuireboysといった英国バンドのガッチリと足を鍛えた安定性と、Pretty Boy FloydやCinderellaの後期型のサウンドのアメリカンなあけすけな明るいメロディを融合させたロックというべきだろう。
完全に筆者のツボである。まあ、オルタナティヴやガレージの影響も宿唖の如く潜んでいるけれども、ロックの大将的な魅力を妨害するには力量不足で、むしろロックの強度を補強する手伝いとしてプラスに作用している。これはもう魔法の一種だろう。
しかしながら、未完成な点がまだまだ見えたThe Dirty Truckersの音楽性より更に若さを感じる、緻密さに欠ける荒さはもっと多い。が、そこがまたとっても吸引力があるのだ。この若さに任せて暴走系統の音楽は、歌心さえしっかりと織り込まれていれば、単なる姦しく、耳障りな音にならずに、ワイルドで硬派なロックンロールとして芯を通すことができるという模範解答のようなバンドである。
さて、Tom Baker氏はこの「Selfish Propensities」をEPと認識しているような発言を数回しているが、10曲入りのアルバムであれば、何の異論もなくフルレングスアルバムである。
まず、#1『Annoy』から狂奔するロックサウンドが全開の剛速球なポップ&ロックナンバーが襲撃してくる。まず、ルーツロックやロックンロールが好きなリスナーならこのナンバーでコロリと落ちるだろう。“衝撃のファーストタイム”的なナンバーとしてはThe Dirty Truckersの同じく1曲目『Settle Down』に匹敵する曲であるのは疑いようがない。但し、『Settle Down』よりもアーバン的な色合いがやや強く、Quireboysの更にやんちゃな感じのロックチューンと思えばよいだろう。Izzy Stradlin & The Ju Ju Houndsのデヴューアルバムにも通じるハード・ポップな傑作である。
が、この次も一息つくことを許してくれない凄いロック・ポップナンバーな#2『Percy』が追撃を敢行してくる。#1も最高に疾風怒涛なロックナンバーであったが、この#2も遜色のない1曲だ。リフ以降の前半部分ではビートのペースを落としながらキャッチーな展開を見せ、コーラス部分でまたポップにドライヴを続けるナンバーだ。中間部で突然演奏を止め、空白を瞬間に拵えてから、即座に再びロックンロールに戻る演出もニクイ。
2曲続いたストレートなロックナンバーから、ブレーキを緩やかに掛けていくようにゆったりと、しかしFacesのように質量の重さを感じられる#3『The Run Around』はやや抑えのあるポップさがジワジワと沁みてくる前半の地味な展開から、3分を過ぎた頃からハードなギターワークがうねるSouthern Rockのバラード風なギターチューンへと変化していく。かなりスケールの大きいナンバーである。
#4『On My Way Down』は前曲#3のヘヴィなスローさを振り切るかのように畳み掛けるノイジーなギターの咆哮でスタートし、キャッチーな本パートへと雪崩込んで行く、ミディアム・ファストなラウドなロックナンバーである。Tomのヴォーカルは2作目よりもよりラフで上手で巧みとは言い難いが、このコブシの入り方は胃袋から脳天まで突き通すような魅力がある。適度な煮込みが終わり味の染みたビーフストロガノフみたいなものだろうか。
そして冒頭の2連発のロックンロールと双璧な疾走感が終始かっ飛ばす#5『Foxholl Friend』が前半の最後に登場する。シンプルでハードでキャッチーで明るいロックンロールナンバーが生命を謳歌し、狂喜乱舞しているような元気印のロックナンバーである。この崩し方、荒っぽさ、う〜ん、男臭いぞ。ちまちまと纏まらずに豪気な豪腕を振るう最強剣士の剣舞を見ているかのように錯覚するほどのパワー・ロックである。やや#1や#2と比べると曲の凹凸が乏しい気はするけど、その分更にストレートになっている。
#6『Fake Me Out』は#3に続いてスローなブギーロックの要素も聴こえてくるヘヴィなスローナンバである。こういった曲ごとに強弱をつけてくれるとロックナンバーはより一層ロックとして、スローナンバーはより一層感動的に映えるのだが、見事にそのメリハリの付けを演じてくれるアルバムチューンである。
#7『Trap』はダークでヘヴィなギターがゴンゴンと攻勢をかけてくるロックナンバーであるけれども、ここには都会的なソリッドさやスマートさを感じることは可能だが、オルタナ的なキンキンとした耳に痛い音の押し付けは感じることは皆無である。どことなく人間味のあるサウンドが流れているし、何と言っても明るいのだ。
明るさで言えば、#8『Dirty Bit』も陽性なリズムとメロディを抱えた、ハードロック&ポップなチューンである。ややガレージやオルタナティヴロックの硬質な音出しも感じさせるアルバムであるが、やはりポップさと楽しげに演奏をするバンドの雰囲気がルーツハードとしての魅力を全面に立ててくれるので、全く鼻につくような悪い点はないのである。
2連発のロックンロールナンバーのあとで、初めてアクースティックなリフが耳に飛び込んでくる#9『Permanent』ではB3ハモンドの音が珍しくクリアにも聴こえる。アーシーでアクースティックな冒頭パートから泥臭いエレキギターが絡んで、南部ロックのロッカバラードの味わいも深い。このナンバーでも静と動のそれぞれの魅力をくっきりと付けてくれる補助をすると共に、じっくりと聴ける作品としても評価できるのだ。
最後のトラック#10『Fake Out Again』、#6の『Fake Me Out』の2作目のような内容を持ったこのロックナンバーはバタバタ鳴るドラムからボキョボキョと暴れるベースが被さり、Tomのシャウト気味のヴォーカルに乗せて、このアルバムでは一番埃っぽいメロディが元気良くドライヴしていく、まさにThe Georgia Satellitesが何処かのライヴ会場でレパートリーに挙げていそうなラフなロックである。
ややタイトなロックンロールナンバーで打ち上げられ、泥臭いルーツロックチューンで着陸するこのNanaロケットのアルバムは、まさにブースターを点火して、カタパルトから宇宙へとすっ飛んで行ってしまうかのようなパワーがどこにでも溢れている。
まあ、ルーツのカラーが少々弱くなったラフさの2割増なThe Dirty Truckersと考えて貰えれば万事理解される人は理解できるだろう。(何のこっちゃ)
多くを語ったが、敢えて多くを語らなくても「It’s Only Rock n’Roll.That’s All」で全て集約できるだろう。
まあ、買わないとロックンロール好きなら大損だ!
これだけだ。言いたいことは全て述べてたので、非常に気分爽快である。まるでこのアルバムを聴いている時や聴いた後の様に。 (2001.11.19.)
 American Town / Five For Fighting (2000)
American Town / Five For Fighting (2000)
Alternative ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★
Adult.Contemporary ★★★☆
You Can Listen From Here
ひょっとしたら大ブレイクするアルバムかもしれない。と、筆者が思ったアルバムはどっかのスパコンが計算間違いするくらいの確率でしか大ブレイクしない。(つまりコンマ以下凄いゼロが続くということやね。)
ここ近年ではMatchbox 20の「Someone Or Yourself Like You」とThe Wallflowersの「Bringing Down The Horse」、そしてHootie And The Blowfishの「Cracked Rear View」といったところだろうか。
どれも最初は全く売れずに、1年近くジワジワとチャートを上昇し、最後にはブレイクした。(尤も、Wallflowersのアルバムだけセールス枚数では相当ビハインドがあるけれど。)
考えてみればどれも5年以上前のリリースのアルバムばかりである。つまり、オリンピヤード以上、筆者が売れるべきと考えたアルバムが全く売れていないと言う結論に達する。
まあ、現在の音楽とは思えん音が氾濫するチャートの不満を綴りだすと、単に容量の無駄使いになってしまうので止めて置こう。
早速本題に入るが、昨年2000年の9月にリリースされた本作「American Town」がビルボードTop200アルバムにチャート・インしたのが、2001年の7月のこと。発売から10ヶ月以上経ってからのメジャーチャート入りである。
ちなみに今年は一度もチャート見てなかったので、泡を喰ってデータを漁ることになってしまったのはヒミツである。(笑)
で、10月の初めにピークポジションであった60位を記録して、またズルズルと落ち始めたところへ#3『Superman
(It’s Not Easy)』が今週である11月第2週についにシングルTop100の40位以内に飛び込んだ。当然キャリア初のTop40ヒットである。(現在第31位。この調子ならもっと上まで昇るだろう。)
つられるようにしてアルバムも息を吹き返し、最高位の54位を記録している。
このようにヒットチャートについて語るのは随分久方振りであり、どうも尻の座りが悪いが、それだけ作者の嗜好がインディ中心になってしまっている証左なのだろう。(何を今更、ではある。)
このようなジワジワ型、しかも筆者のブレイクの予感がするアルバムは本当に久方振りだ。真面目な話、大化けするアルバムである可能性はあると思う。現在のシーンでも好意的に受け入れられそうな音でもあることだし。
正直、筆者も昨年秋にこのアルバムをオークションの新古品でかなり安めに買い叩いてから、数回聴いた後は殆ど聴いていなかった。実際に2000年の私的ベスト20にも入っていない程の印象の薄さであった。
これはやはり1997年に何故かメジャーのEMIからリリースされたFive For Fightingのデヴューアルバム
「...Message For Albert」が大して凄いアルバムでなかったのも目を曇らせた原因であったと考えている。
大したヒットも記録せずに終わってしまったこの「...Message For Albert」を一言で述べるなら、「Ben Folds Fiveを一層サイケディリックにしてオルタナティヴ的陰鬱で鈍いメロディで仕上げたアルバム」(長いわい。)である。
決してクオリティが低いわけではなく、例えばBen Folds Fiveの世間的には評価が高いが筆者的には大外れである2ndアルバム「Whatever And Ever Amen」よりは良い出来であると思うし、数曲はかなり「おっ」と思わせるものがあった。が、決してリピートするアルバムではなく、この2ndのジャケットを見るまで存在を正直失念していたくらいである。
この2ndアルバム「American Town」が徐々にヘヴィ・ローテーションになるにつれて、比較の意味で結構な回数を聴き直してみたはものの、やはりそこそこのアルバムと言う評価に変わりは無かった。
繰り返すが、当初はこの「American Town」も1stと同様な評価に終わろうとしていた。購入してから約3ヶ月、2000年が明けるまで殆ど印象に残らなかったのだから。
実のところ、何がきっかけでこのアルバムを引っ張り出して聴き出したか、よく覚えていない。私的事情で恐縮であるけれど、当時は失業して間もない頃であり色々と葛藤があり、その時にふと#1『Easy Tonight』が聴きたくなったのが、そしてどことなく不思議で幻想的なジャケット(インレイを開いて全ての写真を見ると良く分かると思うが。)がふと懐かしくなって、CDをさり気なく聴き返し始めたのが、このアルバムが箱の下層で無聊をかこつ1枚にならなかった原因かもしれない、と推察している。
が、当初は#1をリピートで聴くだけであった。何となく、他の曲は大したこと無かった、という頼りない記憶が枷となっていたようである。従って、#1『Easy Tonight』だけ引っ張って私的ベストに入れれば良いアルバム、このような評価で終わる筈だったのだ、この「American Town」は。
で、何故このアルバムが1年をかけて私的殿堂入りをしたかというと、理由は極散文的なものである。というか益体無いものと呆れて貰っても構わないくらい詰まらないことなのだ。
筆者の所有するCDプレイヤーが(展示品処分を更に値切って購入した、4桁台の料金に値するボロ。)調子が一時期非常に悪くなり、リピート機能が上手く働かなくなってしまったのだ。よって、同じ曲をエンドレスで聴くことは不可能でないが、逐一1曲が終わるごとに金盤の回転を止めてまた掛け直し、といった手間を一部の趣味的行動を除き面倒なことは息をするのも嫌という程の億劫大将な筆者がしよう筈もない。(笑)
結局、何回も最後まで通しで聴くうちにこのアルバムの良さが、鯣<するめ>を噛むようにジワジワと内に浸透してきて、今年2001年の秋口には相当な愛聴盤と変質してしまった訳である。
実の話、その頃から漸くにして「American Town」がメジャーチャートの下方からゆっくりと上昇を開始し始めたことは全く知らなかったのだが。(汗)
何処が良いと言うとまず筆者の依怙贔屓の対象である、アクースティックピアノが全編でその音色を奏でていることである。しかも主役である、演奏の。
鍵盤、殊にピアノ至上主義の筆者には、余程相性が合わない限り、ピアノを取り入れたロックサウンドは無条件で数段階上の評価をし、好きになり易いという悪癖がある。
無論、1stもふんだんにメインの楽器としてピアノが取り入れられているが、肝心のメロディがいまいちなため、そこまでの評価は出来ないだけである。
当然ながら、評価すると言うからにはメロディが良いことが必要条件であり、この点に関しては1stとは比べ物にならないくらいポップでそして美しいメロディが増えている。難解でオルタナ的な濃さを引き摺り、どんよりとしたUK的なメロディが目立っていた1stよりも、アメリカンロック的なキャッチーさがかなり増加している。
それでいて、ロックの動的な側面はエモーショナルな演奏とコード進行、そしてヴォーカルで、こちらも随分と素直な方向に歩んでいる。
更にはヴォーカリストのJohn Ondrasik(オンドラシクと発音するのだろうか?アングロ=サクソン系のファミリー・ネームではないだろう、間違いなく。)のファルセットの効いた不思議に滑らかなヴォイスである。1stの暗ぼったい雰囲気では余計に鬱を増す助長をしていたような彼の声であるけれど、このポップで強弱のはっきりとついたメロディでは非常に活きている。
Ben Folds Fiveの1stのようなロックとポップの要素をしっかり併せ持った音創りを落ち着いて演っている印象が強い。ピアノロックという点では、Billy JoelというよりはElton John的なブリット・ポップに全く染まっていない普遍的なポップセンスが見えてくるようだ。アメリカンなあけすけさよりも少々抑えの効いた、然れどもコマーシャルな曲が多いのは喜ばしい。
まだ、オルタナティヴを引き摺ったような曲が少々あるのは球に疵という感が強いが、まあ許容範囲であるとは考えているし、それらの瑕疵を補って有り余る美しいピアノとラインが兎に角素晴らしいのである。
1stの消化不良であったアルバムと比べると、別バンドくらいのくっきりしたアメリカンな音に仕上がっていて、成長の度合いには正直驚かされる。このようなアルバムを数ヶ月放って置いたのは、ひたすら筆者の頑迷と偏見のなせる所業の報いだろう。
Ben Foldsが1stを除いてはヘタレなバンドであるのに、あそこまで持て囃される日本なら、きっと売れいているのだと思いきや−著者は日本のアルバムリリース状況やヒット状況に殆ど盲目状態である−ヒットを記録し始めているのに日本盤もリリースされていない始末である。
まあ、これは日本に限らないことらしく、ヒットチャートに飛び込み、#3『Superman(It’s Not Easy)』がヒットを記録してからプレスを決定したカナダのような国もあることだし。全般に売れていない間は評価もセールスもいまいちだったバンドであるのだ。
近頃のチャートには全く信頼も関心も敬意も寄せていないが、やはり売れてくれれば素直に嬉しくはある。それだけ世間の評価が高いわけであるし。
さて、まずはこのFive For Fighting(以下、FFF)というユニットについて説明しておこう。
Five For Fightingという意味は、アイスホッケー(観戦が)大好き人間な筆者にとっては非常に馴染みのある単語である。ホッケーゲームでペナルティを喰らった選手は待機ピットの中で所定時間を送らなければならず、その間総プレイヤー数が相手チームよりも、反則を受けて待機を命じられた人数分少ない中でプレイしなくてはならない。
これをPower Playというのだが、その反則のうち退場の次に重大な5分間の戦線離脱の罰則を”Five For Fighting”と言うのである。
この名前に込められら暗喩を考えると、「反則・叱責・罰則・闘い」というような結構硬い印象を与える語彙が出てくるようであるが、実際はどうなのだろう。このアルバムのソフトな音楽性からは、そのような感じを受けることは皆無であるけれども。
で、このFFFというバンドであるが、実際はピアニストであり、リードヴォーカリストであり、ソングライターであり、更にギタリストであるJohn Ondrasikという人のワンマン・プロジェクトであり、海外プレスでは「Johnのニックネーム」としてFFFを紹介していることが多い。
無論、彼はベースも弾き、ドラムも叩くワンマンレコーディング・プレイヤーではなく、セッションミュージシャン複数と共同でレコーディングを行っている。
が、やはりFFFはJohnのプロジェクトであり、バンド形式を取っているが、バンド名ではないようだ。FFFとしてはラインナップで紹介されること無く、各曲について参加ミュージシャンのクレジットが記載されている。1stアルバムでも同様の形式であったが、今回は誰一人として同一メンバーが2ndアルバムの録音にはかかわっていない事実を踏まえるとやはり、FFFはJohnの別名活動と捉えるのが妥当であろう。
それにしてもピアノをメインとするロック・ユニットがBen Folds FiveやFive For FightingのようにFiveの名前を冠しているのは奇妙な符丁であることだ。
そして、この”Five”の男、John Ondrasikという人について簡単に述べておこう。Johnはロス・アンジェルス近郊のサン・フェルナント・ヴァリーという街で生まれた。
彼が楽器を触りだしたのは何と2歳の時である。彼の母親がピアノの教師と言うそこそこ恵まれた音楽環境下にあったJohnは幼少時から母の手ほどきでピアノに親しむ。(というより半ば強制的に習わされていたらしい。)
彼が中学生の頃、妹がギターをプレゼントされた。そのギターを彼が独占し、独学で弾き始めた頃、ピアノの技術がある程度身についたらしく、母からのレッスンが強制で無くなった。今までピアノを習わされていた反動か、彼はピアノをパッタリと止めて、初めて書いたオリジナルの歌をギターで創ったそうである。
「僕は安物のアンプとエレキギターを買ってPeter Framptonの”Frampton Comes Alive”のカヴァーをやった。2年くらいギターを引き続けたけど、決して物凄いプレイヤーになれなかった。けれどもギターで作曲するには問題ないくらいの腕前にはなった。」
とJohnは述慨する。
また、近年あまり大型のヴォーカリストが出ないアメリカのモダンロックシーンにおいて、独特の裏声系の声を聴かせるJohnのヴォーカルも、やはりオペラを通じて正規にレッスンを受けたものであるそうだ。しかし、彼のオペラの手ほどきを受けながら愛したアーティストはElton John、The Beatles、Journey、Stevie Wonder、Earth,Wind
& Fireといった産業ロックからポップス、ブラック系という範囲は雑多だが、それぞれとても実力のあるヴォーカルを堪能させてくれる人達ばかりである。
ここにJohn Ondrasikのヴォーカルへの力の入れ方が分かろうというものだ。
「ロックンロールとオペラの間にあるものを目指している。」という彼の目標は中々にして崇高だが、確かに久々のロックアーティストとしては魅力的なヴォイスの持ち主であることは間違いない。
最後にこの「American Town」をColumbiaと契約してリリースするまで、色々とレーベル間でゴタゴタがあったらしくて、かなり嫌な経験をしたようである。
「音楽を演奏していることよりも、レコードと言う形のあるもので僕の音楽が存在していることを、より嬉しく思っているよ。Five For Fightingという名前は以前よりも恐らく明確なメッセージ性があると思う。だって文字通り”闘い”を継続しているんだからね。」
さて、このアルバムは第一弾ラジオシングルとなった#1『Easy Tonight』からスタートする。ピアノとアクースティックギター、それにエアブラシのトリミングでキャッチーなメロディを伴い始まるこの曲は、次第にB3やエレキギターを加えて、コーラス部分でドラマティックに日本人好みな甘く切ないメロディを紡ぎあげる。また、ファルセット・ヴォイスを滑らかに、しかし感情的に歌うJohnのヴォーカルは非常に説得力に富んでいる。前作の1stトラックがポルカ風のリズム・ポップでチープさが拭えなかったのとは大きく異なっている。これは名曲であると思う。ヒットはしなかったが、ブレイクが始まったため、再シングルにするのも面白いかも。
「この歌は現代風俗の無関心さをシンボル化したものだよ。」というJohnのコメントとは裏腹に、かなり熱いラヴ・ソングのようにしか思えない#2『Bloody Mary(A Note On Apathy』はマイナーコードから始まり複雑な変調を繰り返す曲だ。♪「On And On」というコーラス部分のリフレインで叙情的なメジャーコードにコロっと転調するのと、その部分での熱いJohnの熱唱が印象的である。後半のエレキギターのプレイは80年代産業ロックを髣髴とさせるアレンジとなっていてとても良い。
そして、現在Top40入りしているシングル#3『Superman (It’s Not Easy)』も#1のような美しいメロディラインを持ったバラードタイプのミディアムスローナンバーである。流麗なピアノにファルセット・ヴォイス。現在のアメリカのメジャーチャートではとんと聴かれなくなったようなどことなく懐かしいバラードである。スーパーマンというヒーローが自分は完璧でなく、普通の人間と同じ苦悩があるし、普通の人間になりたい、というような独白を歌いつつもメタファーとして普通の人間の理想と現実の鬩ぎ合いを直視したような歌であると思う。「超人であることは、簡単ではない」というタイトルからして何とも意味深ではないか。
初めてエレキギターが主役を演じる軽快なミディアム・ロックチューンが、タイトル曲#4『American Town』である。この直球的なメロディも1stアルバムではあまり見られなかったものだ。やや搾り出すようにして力を込めて歌うJohnのヴォーカルも、B3のバックトラックもとてもフックがあって良い。
このように前半がアクースティックでしっとりと流れ、後半コーラスでグンと盛り上げていくミディアムテンポの曲は、ウィルツァー・ピアノの音色が印象的な#12『Alright』やが存在する。#12の特に後半で心地良くシャッフルされる8ビートリズムは中々に心弾むものがある。このリズム感覚はElton Johnの有する英米を超えた普遍的なコンポーズのセンスを思わせるところがあり、#10『Love Song』も後半でストリングスを交えてエモーショナルに展開する曲であるけれどやや淡白なテイストがある。これを現代的というのだろうか。クールと言うよりもウエット感覚のジワっとしたアレンジと曲調が独創的だ。
#5『Something About You』や少しクールなポップセンス、英国的な雰囲気を感じさせるというか初期のDave Matthews Bandに通じるクロスオーヴァー的なアメリカンロックのメロディを感じさせるようなジャリジャリとギターが鳴るナンバーである。
タイトルで注目されるのは間違いない#7『Michael Jordan』は1st作品で結構聴くことができたナード感のあるアーバンオルタナ的なくぐもったナンバーである。最もギターが怪奇にうねるというかオルタナティヴのアンメロディアスを代表するようなチューンで、歌としては最低なアレンジと曲である。タイトルのスポーツ界の英雄が歌中には全く出てこずに、偶像崇拝的なシニカルな比喩として使われているアイディアは面白いが。
後半はやや評価の低い曲が多く、この#7から後の#8『Out Of Love』はジャムバンド的な無国籍なメロディとリズムを持った曲であるし、#11『Boat Parade』もマイナー調のメロディがハードに展開するノイジーな曲で、これも#7とならんで全体の美しさを阻害している曲だ。
だが、対になるように美しいバラードもちゃんとトラックインされている。前半最後の#6『Jainy』はノンギターでストリングスを伴って最初からファルセット歌唱が全開のアダルトコンテンポラリーなバラードであるし、現代社会の荒廃と腐敗をシニカルに表した#9『The Last Great American』も珍しくアクースティックピアノがフューチャーされてはいないのだが、B3とストリングスが活躍するメロウなバラードである。
メディアにはBen Folds FiveやElton John、Billy Joel等のピアノ・ロッカーを引き合いに出されて評価されるJohn Ondrasikであるが、Ben Foldsのような英国的なセンスやパンキッシュな羽目の外し方はしない。もっとオーソドックスなスタイルのシンガーである。
EltonやBillyのようにポップな曲を書ける人であるのは間違いないが、やはり90年代の必須テイストのようなオルタナティヴの呪縛からは悪い意味で逃れられていないようにも思える。確かに、完全にアダルト・ロックのポップシンガーとなってしまっては、退屈になることは確実であるけれど、もう少しジャムロックやオルタナティヴを排斥した方がより正統派な(売れないかもしれないが)シンガーになると思う。
即効性よりも後からジワジワとリピート性が出てくるアルバムであるので、取っ付き易くはあってもそれ程印象に残らないかもしれない。当初のうちだが。
筆者にしては珍しく長いスパンを経て、殿堂入りしたアルバムである。ヒットの仕方も結構ロングセラーになりそうな地味だけど・・・・云々、というストリームの渦中にあるので、これからヒットチャートにおけるFFFの位置を追いかけそうな予感はする。どこまで検討するか見ものである。 (2001.11.8.)
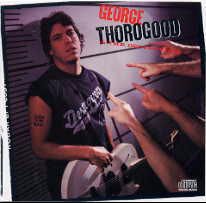 Born To Be Bad
Born To Be Bad
/ George Thorogood & The Destroyers (1988)
Roots ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★★
Blues ★★★
やはり、Unplugged Liveをやったり、頻繁にチャリティイヴェントとかに出演したり、日本盤のCDがどんどん出ないと日本では知名度が上がらないのだろうか。(かなり嫌味だが、我ながら。)
このレコードデヴューから24年目を迎える(活動開始は1970年であるから、ミュージシャンとしては30年選手である。2000年には活動30年を記念して2枚組アンソロジーもリリースされた。無論日本未発売。)ヴェテランオヤヂのCDはただの1枚も日本盤化されていないという“ていたらく”である。
まあメジャーチャートでのシングルヒット曲は1985年の全米第63位の『Willie And The Hand Jive』ただ1曲しかないので、ヒット曲至上の1980年代日本では知名度が上がらなかったのは仕方ないかもしれない。セールス的にもメガヒットには程遠いが、一番売れていたのはこのシングル曲が入ったアルバム「Marverick」前後だろう。
が、本国でそれなりに知名度が上がっていたこの頃でも、日本では不当に低い評価をされているように感じるのは気のせいではないだろう。
彼の音楽は、評論家を唸らせるような芸術性とか緻密さとかとは対極の、とことん荒っぽいロックンロールである。が、しかしB級と断言することもまたできない。
所謂B級バンドとか、とって付けたようにヒネリを入れたり、故意にチープにしたり、録音やアレンジを安っぽくして満足している似非真似B級バンドとは全く音楽に対する姿勢が異なるからだ。
Not Lame系とか、日本で何故か発売される「パワー・ポップ」とメディアが呼ぶバンドの群れは非常にこのような作り物のB級さが腹に据えかねることばかりである。必要ないところでナード感覚やチープな音作りをして、俗に言う“売れ線”から一段上の音楽を作ったかのように錯覚してるような薄焼き煎餅より薄く、縁日のクレープ並みに薄いトコロテン細工のような音楽とは比べようもない。
ただ、ロックをブルースロックを演奏したいからする。曲を書く。歌う。インストを弾きまくる。ツアーに出る、というアーティストの初心というかデヴュー当時の純粋な精神を何時までも持ち続けている人であると思うのだ。
別に「何某の神様」と賞賛されることを狙って、技巧的な複雑なギターの速弾きを入れることもないし、時流に乗ったようなUnplugged Liveをやって、ヴェテランの味を売り込むこともしない。売れ筋の音や楽器を取り入れたりもせずに常に自分のペースで曲を歌い続ける。
こう書くと「孤高のロッカー」とかいう陳腐なレッテルを貼られそうだが、別に気取るとか世間の流行に対してアンチテーゼ的なアレンジや方向性のアルバムを創って、我が高潔さを示そうとするような自己顕示欲もみられない。まあ、単なるロック好きの不良中年なだけである。
ロックンロール好きなカルトな人たちとの会話でも「スゲエ」とか「天才」とかと賞賛されることは殆どないけど「イイね」とか「好きだよ」と肩に力を入れずに語ることができるアーティストと表現すれば、彼の位置付けが何となくではあるがお分かり頂けるのではないかと想像する。
つまりはそういうロッカーである。
まずは、大抵の人が知らないであろうGeorge Thorogoodという男について経歴やディスコグラフィーから述べてみたいと思う。
活動が長い割には個人的な生活等には殆ど言及しない人である。
好きなものは、音楽・酒・野球・女性、だそうである。実に分かり易い。(笑)
生まれは1950年である。ついに21世紀に入り50歳を超えてしまったのであるが、昔から外見はあまり変わらないように見えるのは気のせいだろうか。少なくとも演奏する音楽には、今のところ最新のスタジオ録音アルバムである1999年の「Half A Boy,Half A Man」をプレイヤーに落として流れてくる音を聴く限り、衰えとか老いは全く感じられない。ややアダルトな整然さが出始めたようにも僅かに感じるけれど、やはり基本は全く不変である。
Evergreen Boyとか永遠青年とかいうような爽やかで清々しいイメージのある単語の当てはまるようなオヤヂではないけれども、不気味というと聞こえが悪いが、怪しいパワーを放っている。
出身は東海岸の非常に小さい独立13州の一つ、デラウェア州。
音楽に目覚めたのは、ロックシンガーとしては高齢に属しそうな20歳の時で、1970年にシカゴ・ブルース系のシンガーであるJohn Paul Hammondのショウを見て感激してから自身も音楽を始める。
演奏を始めたのは遅かったが、それからの特急振りは異様に早く、3年後の1973年にデラウェア州でThe Destroyersを結成している。
後に述べたいが、Thorogoodはブルース・マンとファンやメディアから称されることが多いが、やはりキャリアのスタートはブルースであったシカゴブルースの当時でさえ大ヴェテランのHound Dog Taylorの前座としてバンドの活動を始めている。またTaylorスタイルにかなり影響を受けたことをGeorgeも自認している。
その他に前座を務めたり、影響を多大に受けたアーティストの筆頭としてコテコテのブルースマンであるJohn Lee
Hockerを挙げており、他にはElmore James、Chuck Berry、Muddy Waters等のロックンローラやブルースシンガーにはインスパイアされたところが大であったと述懐しているが、元祖ロックアーティストのChuck Berryの名前がベタベタなブルースマンの中に混じっているのがやはりThorogoodたる所以であると思うのだ。
筆者は確かにGeorge Thorogoodはブルースも歌うが、やはりロックシンガーであると思うし、稀なシンプル・ロックンローラーの1人であると考えている。アルバムによっては90年代で言えば1991年の「Boogie People」や1997年の
「Rockin’My Life Away」のようにブルース色の強いアルバムも出しているが、1993年の「Hair Cut」や1999年の前述した
「Half A Boy,Half A Man」のようにブルージーさも勿論歌い込まれているが、ロックサウンドを基調にしたアルバムも作成しているのだ。
1980年代の作品については現在手元にCDが置いてないため明確な記憶はないが、「Marvelick」や「Bad To The Bone」はやはりロックンロールが聴けるアルバムであるし、当レヴューの「Bone To Be Bad」は80年代では恐らく最も直球的なロックサウンドに傾倒したアルバムであると思う。
まあ、各人によってThorogoodがブルースマンであるかロックシンガーであるか、ロッキンブルースであるかは、音楽に耳を傾けて判断すれば良いのだが、著者的には彼はロック&ロッキンブルースシンガーな位置付けにある。
濃いブルースや黒人ブルースが苦手というかToo Muchな筆者がここまで聴けるのだから、やはりGeorge
Thorogoodはロックの歌い手であると信じている。
話題が脱線したので話を戻そう。結成当時、バンド名はThe Delaware Destroyersを冠していた。メンバーはこの活動当初時代からちょこちょこと交代を繰り返していたようだが、結成当初から2001年現在まで全てに渡り在籍しているドラマーのJeff Simonは立ち上げ時からのメンバーである。このThe Delaware Destroyersは1974年に初のデモ音源を録音するが、当初はリリースする目処が立たずにオクラ入りすることとなる。
この音源は後にMCAから1977年に「Beter Than The Rest」として日の目を見ることになるのだが。
つまりどのレコード会社もGeorge Thorogood & The Delaware Destroyersのサウンドに興味を持ってくれなかった訳である。契約のままならない彼らは小さなブルース系のクラブでのギグを繰り返す。
事実上のデヴューアルバムである「George Thorogood & The Destroyers」を録音したのは1975年のことである。エンジニアであったJohn Forwardが彼らの才能に惚れ込み、インディレーベルのRounderに仲介を取ったからである。が、実際にアルバムがリリースされたのは1977年と2年後である。
この遅れに関しては諸説あり、George Thorogood & The Destroyers(以下GT&D)のサウンドが元来フォーク音楽レーベルであったRounderのカラーに合わなかったので、レーベルが発売を渋り、サウンドを大人しくするように求め、意見の調整が合わなかったため、とか、ジャケット写真がレーベルのフォーキィな色に合わなかったため、Rounderが改変を求め、意見の調整に時間がかかったとか諸説ある。
が、重要なことはこのレコーディング中に現在までベーシストを通しで勤めるBill Bloughが加わったことであろう。
この2年待たされて発売されたアルバムはそこそこの評判を得て、Rounderからの2作目「Move It On Over」が翌年の1978年に早くもリリースされ、100万枚以上のセールスを記録する。
1980年にサックスフォニスト兼キーボードプレイヤーのHank Carterを加えて3枚目のRounderからのアルバムであるブルースセッション的な「More George Thorogood & The Destroyers」を最後に、彼らはメジャーのEMIと契約を交わすことに成功する。
1981年にThe Rolling Stonesの前座を務めることとなったGT&Dの名前はブルースシンガーではなく、ロックシンガーとしてファンに浸透し、1982年の「Bad To The Bone」で初めてヘヴィなブルース寄りでない熱くロックするアルバムをリリースする。このChuck Berryへの敬意を隠さず出したアルバムは大ヒットというほどのチャートポジションを得たわけでないが、100万枚以上をまたも売る。Thorogoodはこのアルバムで初めて自作曲を披露している。
そしてTop40アルバムでメジャーシングルも出した1985年の「Marverick」、1986年の「Live」とロックアルバムにライヴアルバムと2枚のアルバムをリリースした後にリリースされたのが本作「Bone To Be Bad」である。
キャリア上、一番市場的に受け入れられていた時期のためもあろうが、非常にロックンロールなアルバムになっている。恐らく80年代では一番ブルースではなくロックンロールのカラーが強いアルバムではなかろうか。
このアルバムの反動を意味するかのごとく、次作、1991年の「Boogie People」はヘヴィなブルースアルバムであったことを踏まえると、一種のロックンロールの頂点を極めたとGT&Dが満足したアルバムという位置付けも可能になるような気がするのだが。
さて、この1988年のアルバムであるが、オリジナルの曲は2曲のみである。元々オリジナルにはそれ程拘らずに、ロックンロールやブルースのクラッシックを何の気取りもなく平気でどんどんカヴァーするバンドであるので、全くカヴァー曲のオンパレードに違和感はなく、むしろ全てGT&Dのオリジナルの曲のように聴こえてしまうので不可思議である。
その3曲のうち1曲は#2『You Talk To Much』である。Hank Carterのもはやお馴染みになったテナーサックスをダイナミックにフューチャーしたこのナンバーはハードドライヴィンであるがキャッチーでもある最高にブギーなロックナンバーである。いかにもGT&Dの音楽性を代表するようなブルースの匂いもするが、やはりロックンロールだ、と縦1本割りできそうな曲である。
もう1曲が、アルバム中では最もポップで疾走感覚に満ちたヒット性抜群のタイトルナンバー#4『Bone To Be Bad』である。メジャーチャートでは惜しくもヒットしなかったがアダルトロックチャートでは3位を記録するラジオヒットとなっている。この曲はアルバムの中だけでなく、GT&Dの歴代シングルの中でも彼らの売りでもあるゴリゴリの粘っこさや暑苦しさが最も少ない軽快なポップ・ロックチューンであるようにも思える。
そしてビッグバンド的なブギウギロックの80年代解釈版とでも言うべき豪快な#8『I Really Like Girls』に至ってはもうただ気持ち良くメロディに乗って身体がスゥイングするだけである。サックスとスライドギターのベタベタな掛け合いといい、Georgeの「あの娘が好きや、好きや、全部ホンマに好きや〜。」というお馬鹿な歌をガンガンにマシンガントークライクなヴォーカルといい、単に楽しむナンバーだけであろう。
これら3曲は全部George Thorogoodの単独作品である。これだけの曲がサラリと書けるのだから、彼らが単なる回顧的なロック&ブルースのカヴァーバンドでないということは、この点だけでも明白だろう。
残り7曲は殆どが60年代のロックナンバーかブルースチューンのカヴァーであるが、曲が書けないのでカヴァーを演っているのでなく、好きな曲だからスポットを当てて、自らの解釈を施して紹介したいという愛着が凄く見えてくるのだが、オリジナルが少ないという経歴が評論家筋やメディアから一段低いカヴァー・アーティストという色眼鏡で見られていることも確かである。
まあ、そのようなことを考慮しない人であるから一流の称号も求めないのだろうし、何時になっても好きな曲をカヴァーし続けるのだろうけど。もう少しオリジナルを入れても良いのでは、と思うことも率直に述べれば、結構あるのだ。
そのカヴァー曲からアルバムはスタートする。シカゴブルースの御大であるElmore Jamesの十八番であるブギーでスゥインギングな#1『Shake Your Money Maker』でいきなりロックンロール満載である。原曲のソウルフルなメリハリの付き方はそのままに、ハードでタフな色合いを増したチューンとして再紹介している。始まりにブルース系の曲でなくハードにジャンプするクラシカルなロックナンバーを持ってきていることから、このアルバムのロックンロールへの系統が伺えるというものである。
#3『Highway 49』もブラックシンガーであるシカゴブルースマンのHowlin Wolfの熱唱で有名なオールディズナンバーである。この曲もブラックシンガーに付きもののクド過ぎさをホワイトロックで薄めたことで、やや聴きやすいロックンソウルナンバーとして仕上がっている。
これまたクラシックなChuck Berryの#5『You Can’t Catch Me』をGeorgeは、原曲よりも垢抜けない、とても80年代のロックとは思えないくらい古臭いアレンジで泥臭く歌っている。間奏のスライドギターの黒っぽさはChuck Berryが持っていた黒いブルースと白いロックンロールの両方の融合を彼らも常に念頭に置いていることが分かるような安定感がある。
ビッグバンド風のライト・ファンクの色合いたっぷりなFats Dominoの50年代ソングのカヴァーである#6『I’m Ready』はもうただゴキゲン・極楽というオールディズなロックナンバーというしかない。このようなR&Bベースのロックナンバーを全く全体の流れから浮いた感じもなく取り入れられるロックシンガーは数少ないだろう。
次もオールディズ・ヒットナンバーであるRoy Head & The Traitsの1965年のブギーなロックチューン#7『Treat Her Right』を臆面もなく持ってきているのには図々しさというよりも、ただただロックシンガーとしての自信が見えるだけである。
スローでネバネバのブルースのクラッシック#9『Smokestack Lightning』で一息ロックの大攻勢に一息ついて、最後のこれまたパンクロックの元祖のような曲#10『I’m Moving On』は70年代後半にロック・パンクグループPagansが
披露していたナンバーであろうか。これまたやや肩に力を抜いて、軽快なリズムロックとしてこのロックアルバムのトリのナンバーとしてはあっさり風味であるようにも思える。が、この力の抜かし方というか透かし方は絶妙だ。終始リラックスして聴けるアルバムのラストナンバーとしては上手い具合な脱力感を持たせ、「そう難しく考えるなよ。単なるロックなんだから。」と語りかけているようにも思えるのだ。
以上、10曲。決してロックの名盤とかと銘打たれその手の雑誌のランクや評価に記載されるような「名作」風のアルバムではないけれども、シンプルなロックやロッキンブルースを何時までも歌ってくれるこのバンドはとても貴重である。
ちょっと元気が欲しい時や気分が乗らないときに何時の間にかプレイヤーに乗せているアルバムであってくれれば良いのだろうと思っている。つまりは個人的には愛聴盤であり、名盤になるのだ。そういって聴きつづけることのできるアルバムは。
少し古臭くても飾らない熱血ロックが好きな人ならまず聴いておいて損のないアルバムである。
(2001.11.18)
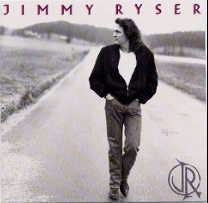 Jimmy Ryser / Jimmy Ryser (1990)
Jimmy Ryser / Jimmy Ryser (1990)
Roots ★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★
Adult.Contemporary ★★★★
You Can Listen From Here
Reviewed By Kyotaさん
「当時、俺はあのデイヴィッド・レナ−ド(ジョン・ク−ガ−・メレンキャンプを始めとして、数多くの有名ミュ−ジシャンの作品でミックスを手がけた)と一緒に、自宅で「Jimmy
Ryser」のミックス作業をしていたんだけど、途中で俺達はジョン・メレンキャンプのスタジオまで出向いて、スタジオ内に"侵入"したんだ。そう、デイヴィッドは実際にスタジオの鍵を持っていたんだな。それで、ミックスに必要な機材を"借り"て、後で戻しておいたというわけ。あの頃は楽しかったなあ!!」(ジミ−本人のメ−ルより)
そのジョン・メレンキャンプの親友として知られ、彼の「Dance Naked」('94)
「Mr.Happy Go Lucky」('95) 「John Mellencamp」('98)の3枚のアルバムにゲスト参加、近年ではヘンリ−・リ−・サマ−のオ−プニングを務める等、精力的な活動を続けているジミ−(現ジム)・ライサ−は1965年、オハイオ州の出身。ただ、生まれ育ったのはインディアナ州であるようだ。
彼のアメリカ中西部地域でのパフォ−マンスが話題を呼び、アリスタ・レコ−ズと契約したのが'88年のこと。'90年にディヴィッド・カ−シェンバウムのプロデュ−スによるこの「Jimmy Ryser」でデビュ−を果たしたのである。
まず、このアルバムからシングル・カットされ、ビルボ−ド誌のシングルTop100で78位まで上昇した#2"Same
Old Look"を聴いてみよう。 しなやか、かつ力強いジミ−のヴォ−カルによって歌われる美麗を極めたメロディ・ラインに、一度聴いたら忘れられないキャッチ−なサビ。名手ジム・ヴァランスによる的確なディレクションと(この曲と#4"Wishing
And Waiting"がジムのプロデュ−ス) 、これだけで既に"スタンダ−ド"になるだけのクオリティを有しているのだが、そこに更に5才から習い始めたというジミ−のヴァイオリンが見事に彩りを添え、この曲に単なる名曲以上の輝きを与えることに成功しているのである。
そう、"Same Old Look"の瑞々しいイントロを聴くまでもなく、彼の体の一部となって楽曲のなかで呼吸し、アルバム全体に躍動感を与えているバイオリンは、ジミ−・ライサ−のアイデンティティの重要な一端を担っているといえる。 ジミ−の音楽の基本にあるのはジョン・メレンキャンプと同じ、アメリカン・ロックの王道を行くスタイルだが、そこに彼の優れたポップ・センスと甘い歌声、キ−ボ−ド、ヴァイオリンを巧みに配した卓越したアレンジ(この"洗練され過ぎない"独特の感覚は、ジミ−の全てのアルバムに共通する要素だ)が加わって、個性的でありながらも、十分な普遍性を備えたメロディアス・ロックのアルバムとして完成されているのだ。
#1・4・7・8・9といったガッツィ−なロック・チュ−ンから、切なすぎるまでの叙情性を発散する#5・10・12といった静かな曲まで、歌心に満ちた名曲、佳曲でいっぱいの「Jimmy
Ryser」は、まさに'90年代アメリカン・ロックの隠れた名盤といってよいだろう。
MOTOさんのレビュ−にもあるように、いろいろな要素が相俟って、ジミ−のメジャ−・レ−ベルでの生活は、この「Jimmy
Ryser」1枚のみで終ってしまいます。
もし彼があと3年早くデビュ−していたら…。もしこのデビュ−・アルバムがもっと売れていたら…。そしてもし彼の持病が悪化していなければ…。
…うん、「たら」「れば」の話しは後ろ向きなのでもうやめよう。ジミ−は今でも素晴らしいアルバムを作り続けて、元気にライヴも行なっている。それで十分じゃないか。
何時からだろう・・・・・・・・。適度にアーシーで、相反するようにアーバンなサウンドも兼ね備え、中庸な中部アメリカのロックの典型の如きサウンドがメジャーシーンから次第に見られなくなったのは。
1980年代までは、メジャー・チャートに必ず見ることができた、こういったロックンロールは現在ではもうインディ・シーンにしか探すことができなくなっている。80年代当時はAdult Rockチャート、1990年代にはAdult Contemporaryチャートの代表な音楽と相成った名前の変化が、如実にこのようなサウンドがメジャーの“ロックンロール”としては歓迎されなくなったことを示しているようだ。
ロックとしてのチャートはアダルトなサウンドよりも、Main Rock StreamとModern Rock Tracksの2極化が進み、オルタナティヴ・ロックサウンドとしての、メロディよりもただ「ロック」らしく見せるための小手先だけのヘヴィさや派手が優先された1990年代冒頭には、特にこのようなアダルトで、しかもルーツというアメリカ伝統のテイストもある音楽は、とことん冷遇された。
不運なのは丁度、1990年くらいからの、アメリカのロックサウンドの変革期にデヴューをしたり、才能がピークを迎えていたアーティスト達だろう。彼らはその音楽性の良さに反比例してセールス的にほぼ大失敗し、次々と契約を切られてはインディに沈んでいった。
まだ、1990年という90年代初めの年は、アメリカンロックがそれでも寸でのところでメロディアスな伝統メインストリームな音楽性を受け皿として場所を空けていてくれた時代ではあったようだ。Firehouseがグラミー賞を受賞した事実にあるように、まさにグランジ&オルタナの侵略の開戦前夜の年であったように感じる。
否、侵略は既に始まっていたのだろう。当時、何とか叩き潰しておけば1990年代と21世紀はもっと幸せを感じれる年代になったというのは筆者の偏見まみれのIF予想であるが、あながち間違いでないとは自認している。
このJimmy Ryser(現在はJim Ryserと名前をよりシンプルにしている)もレコードデヴューが丁度、過渡期にぶつかってしまった非常に不運なミュージシャンである。このアルバム「Jimmy Ryser」が大手メジャーのArista Recordsからリリースされたのは1990年であった。現在ではこのようなサウンド性を有するアーティストが、Aristaのようなメジャーからデヴューすることなど、可能性はゼロに等しいとはいかないまでも、極小であることは疑いの余地がないだろう。
果たして、メジャーからのデヴューの結果は如何程であっただろうか。先に結論から述べてしまうと、ファーストシングルとなった#2『Same Old Look』がメジャー・ポップチャートでTop40に食い込む健闘を見せた(全米第26位まで上昇)ものの、アルバムは際立った成績を残せずに終わっている。最終的には10万枚以上のセールスを上げたらしいが、インディ・アーティストなら兎も角、メジャーのAristaが売り出した新人にしては、Jimmy本人もレコードレーベルも完全に満足のいく結果ではなかったに違いない。
とはいえ、一応ヒットシングルも排出したアルバムで、次回にも首は繋がったようである。Jimmy本人もAristaサイドも2枚目のリリースを契約とまではいかないにしても、暗黙の了解を得ていたようだ。
が、しかしここで不運がこのオハイオ州生まれの音楽家を襲う。先天的に疾患があり、幼少時から入退院を繰り返していたJimmyであるが、その難病がミュージックビジネスの最前線に立ったための緊張かプレッシャーか疲労かかは定かではないが、悪化してしまい、とてもレコード会社の求めるリリースペースやツアーを行えなくなったのだ。
無論、病の床で彼は曲を書き続ける努力をしたそうだが、ゴールド・ディスクも獲得できなかった新人に、メジャーのレーベルでは比較的我慢強くブレイクしなくても器用を続けるAristaも匙を投げたようで、契約を切られてしまう。
やはり、1991年には彼のようなアダルトオリエンティッドのロックが市民権を失いつつあったことも、契約破棄の後押しをしたことは間違いないだろう。
簡単に、この1990年発売のセルフタイトル盤のリリース前後について記してみた。
さて、まずは日本の余程のチャートマニアしか記憶していないだろう、Jimmy Ryserという名前を持つミュージシャンの経歴について書き綴ってみようと思う。
Jimmy Ryserはオハイオ州コロンバスに1965年に生まれている。今年2001年で丁度36歳になる。まだまだ若いミュージシャンである。が、闘病生活の苦労のためか、最近はかなり実年齢よりも老けて見える。このジャケットやインナーに見られるような若さは既に見ることができないのはちと悲しいものもある。
彼が音楽を正式に習いだしたのは5歳の時だという。職業演奏家であった祖父を持つ家系に連なる彼は、これまた音楽好きの父親にヴァイオリンの手解きを受けたのがそのキャリアの始まりであった。もっとも、ヴァイオリンのレッスンは当時から先天性の疾患のため、幼少時から病気の痛みと、単調な入院と退院の生活の退屈に耐えねばならなかったJimmy少年には格好の気晴らしであったようである。
しかし、気晴らしが単なる気休めに終わらなかったのは、彼の家庭環境だろう。
「僕のオフクロは完璧にマスターすることが何でも最高の喜びであり、目標にしなければならないと教えてくれたんだ。」
と、単なる趣味に終わらなかったのは母親の教育と指導の賜物らしい。結局、彼は4年ほどヴァイオリンを弾き続け、更にピアノも5年のレッスンを受ける。
このようにして音楽的下地を拵えたJimmyは病状の安定も手伝い、中学2年生の時自らバンドを組むことを志し、ギターを手に取る。が、14歳までJimmyは全くギターに触れた経験がなかったそうで
「初めてギターを弾いた時まで、この楽器がここまで素晴らしいものと知らなかったよ。」
と述懐している。
そして、15歳になると初めてのバンドTraitorを結成し、スクール内で演奏を開始する。これが本来のロックミュージシャンとしての活動開始となるのだろう。
高校へ進学しても、彼は音楽を更に続ける。彼の率いるバンドTraitorはオハイオ州のインディ・シーンではかなりの人気を博するようになる。
「女の子にアピールするのにギターピックを持っているのがとっても簡単だと分かったからさ。」
とJimmyは冗談めかして語る。が、彼にはこの時、他の選択肢もあったのだ。インディアナ大学の音楽治療研究の活動の一環として、高校生の頃から活動に参加していたJimmyはミュージック・ヒーリングとしての才能を見出され、特別奨学金を条件に進学を大学から薦められていたという。
結局、彼はヒーリング・ミュージックの研究の徒となるよりも、ロックミュージシャンとして活動することを選択した訳である。
当時、Jimmyの率いていたバンドTraitorは1980年代にはまだまだメジャーで受け入れられていたプログレッシヴ・ミュージックバンドだったようで、比較対象とされるのはYes、Pink Floyd、Rush、Kansasというアメリカンな音とはかなりかけ離れた音楽性だったようである。殊に、Rushの音楽をコピーすることも盛んに行っていたようで、完全なRushのフォロワーだったという。
こういった音楽を続けていれば、彼はきっと異なったジャンルのアーティストとしてこの場でも紹介されただろう。けれども、名前が売れるにつれて彼らの音楽に注目した当時のRushのマネージャーに、この音楽ではオリジナリティを発揮できないから、路線を独自に変更するようプッシュを受けたのだ。
Jimmyは苦悩の末、音楽スタイルをRushのフォロワーから変更することを決意する。明らかにメロディよりも演奏の完成度や音の重なり具合を重視する超絶技巧派集団のRushの追いかけバンドから、アメリカ中西部の音を主体としたポップロックに移り帰ることは相当抵抗があったようで、Traitorのメンバーはそれを不満としてJimmyと袂を分かってしまう。つまりはバンドの仲間から弾き出されたのだ。
「これは僕がこれまでに下した最も辛い決断だった。けれども最善の決意だったことも確かだと思うよ。」
このようにして、Jimmyはよりアメリカンな音へと、平たく言うとオハイオの正統派ミュージシャンが喜んで使用する
『Midwest Root And Rock』という単語に代表される音楽性に近い方向へと傾倒していくのだ。
1987年までにはこのアルバムでのバンドメンバーが顔を揃える。
Jimmy Ryser (L.&B.Vocal,Acoustic&Electric Guitars,Mandline,Violine)を筆頭に
Greg Fincke (Drums) , Jeff Hedback (Bass) ,Jeff Pederson(Piano,Organ,Keyboard)
Keith Skooglund (Guitars,B.Vocal)
という5名体制のバンドが完成する。そして1987年の秋に、Jimmyの作成したデモテープが人づてから人づてにという複雑な経緯を経て、Arista Recordsの社長へと渡る。殆ど即決で契約の指示が出たそうである。
が、実際にレコーディングに入ったのは1989年の夏である。発売は更に翌年の1990年となるし、レコーディングに入るのにも、その後にリリースされるにも相当の時間がかかっている。これは冒頭のJimmyの母親の主義であった「物事は完璧が一番」という教えがJimmyの性癖にとなっていたためのようである。
所謂完璧主義者のことであろう。Jimmy自身も、その悪癖(笑)を認めるコメントを発している。
「この完璧に拘るのは子供の頃レッスンを受けたヴァイオリンの影響だろうね。古典的な楽器を好きなように扱うにはある程度以上の完璧さが必要なのさ。」
と。彼にはテイクの取り直しやNGは全く苦痛にならないという美点があるのだ。まあ、こういうタイプは得てして寡作なアーティストになりやすいものだが。JimmyもJim Ryserと変名するまでは相当な寡作であったことは、色々な理由がるにせよ事実であったことだし。
兎に角、レコーディングの準備とレコーディング期間を合わせると1年では到底きかないタームで創り上げられたこのセルフタイトルアルバムはかなり完成度が高く、とても当時20代半ばであったアーティストの初作品とは思えないくらい緻密な丁寧な完成度を誇っている。
プロデューサーは、当時当確を現していた黒人フォーク系の女性シンガー、Tracy Chapmanを手がけたDavid
Kershenbaumが殆どの曲を担当している。またシングルヒットした#2他1曲を、Brian Adamsの才能を影でフォローしていたのは間違いない隠れた名手Jim Vallanceがプロデュースし、彼はキーボードやパーカッションでもゲスト参加している。また、The Outfieldのエンジニアやミキサーを経験して、90年代後半には広く活躍しているDavid Leonardも2曲に手を貸している。
またゲストミュージシャンでは、後に親交を深め、レコーディングにも参加するJohn MellencampバンドのドラマーであるKenny Aronoffがパーカッションでかなりのトラックに参加しているのが一番の話題性だろうか。
CDとカセットにはボーナスとして#11『Show Us The Way』と#13『I Am』が余分に収録されている。2001年の段階ではこういったデジタル・メディアのみのボーナストラックという特典は陳腐化というか形骸化して久しいが、1990年はまだ北米でのCDプレイヤーの普及率は30%を超えていなかったことを思い出せば、納得がいく。この辺りにも10年の年月の流れを感じたりもする、余談になるが。
曲の名義はJimmyと実姉のDiane Ryserの共作名義となっているが、実質は#9『Soul Break Free』をDianeが単独で書き、残りをJimmyが単独で書き上げる形になっているとのこと。曲創りの始めのアイディアを出し合う段階では協力をするらしいが。より正確に述べると、姉のDianeは作詞専門で、Jimmyは作詞も作曲もこなすとのことだが。
さて、デヴュー当時のキャッチコピーは『Heartland Rock And Roll Travels A New Path...』−アメリカ中部ロックンロールの新しい境地へようこそ−と、このようにプロモーションされていた。
Heartland Rock=同郷のMichael Stanley Bandもそうであるように、適度にルーツィでアダルトロックな落ち着きがあり、都会的なセンスも伺え、ベタベタな土臭い音楽までは踏み込まない上品さのある、という感じの典型的なロックアルバムであることは間違いない。
が、Heartland Rockと呼ばれるJohn MellencampやMichael Stanley、デトロイトまで東に足を伸ばしてBob Seger等まで括ってHeartland Rockを分類すると、このJimmy Ryserは相当ロックテイストをアーバンサウンドとアダルトロックに傾けた部類に入りそうだ。
音符やコードの進行の行間にアメリカンルーツの香りは漂わせるが、相当押さえを利かして、さっぱりしたポップロック風に昇華させている。
また、とことんまでキャッチーなアプローチを、例えばREO Speedwagon程まではストレートなメジャーな曲調には突っ込まずに、AORミュージック調なやや冷静なポップレヴェルにコマーシャルさを留めているようである。英国風に無理矢理コードを変調させるのではなく、自然にアレンジをクールに極めているという感じだろうか。
故に、迸る野生馬の暴走というようなダイナミックなロックサウンドよりも、コンテンポラリーなヴォーカル・アルバムとしての雰囲気のほうが前面に出ているように思えるのだ。
これは、やはりJimmyがヴァイオリンというストリングス楽器を自在に弾き熟すという、クラシック音楽のバックグラウンドが多少なりとも影響しているのでは、と想像している。また、元々プログレッシヴ音楽の熱心な追求者であった経歴も泥臭い湿地や埃まみれのフリーウェイまで暴走しない域に留まっていられる効果を補助しているとも考えている。
とはいえ、アメリカンロックの良質なサウンドの範疇には十分に入るという素晴らしさに何ら影響を与えるものではない。いかなアーバンコンテンポラリーの影響を匂わせようとも、オハイオ州のロックというのは何故か中部伝統音楽のアーシーさを宿命のように引き摺っているからであろうか、兎にも角にも、アメリカン・ハートランドな落ち着いたロック作品として完成しているこのアルバムは相当の出来であることに間違いはないのだ。
もしくはBilly Joelのようなロックヴォーカルとしてカテゴライズしてしまっても良いかもしれない。敢えて誤解を招きそうな区分の仕方であるけれども、それだけ、メロディとヴォーカルのバランスが良いという証拠を示したいという意図を汲んで頂ければと考えている。
先に述べたように収録曲はCDで13曲である。当時としても結構なヴォリュームだと思う。
やはりプレイヤーに乗せて一番に身体が乗り出すのはヒットシングルの#2『Same Old Look』である。Jimmyの奏でるヴァイオリンのやや哀愁を帯びた音色のリフに、Jim Vallanceが打ち込んだシンセストリングスが上品にオーヴァーダブされて、アダルトな雰囲気で始まるこのトラックにはJimmyの透明感のあるハイトーン・ヴォイスが非常に良く似合っている。また、ファーストヴァースをゆるりとしたテンポで流しながら、コーラス部から8ビートロックに変調するというアクセントの付け方は、些か古典的とはいえ、ヒット曲としての要素は過不足なく満たし、実際にTop30入りをしていることからもこの曲のクオリティの高さが分かるというものだ。
いきなりルーツィなB3ハモンドが聴こえて来る#3『Slow Down』も派手さはないが、さっぱりとしたドラミングがキャッチーなラインを強調する、リズムの醍醐味がたまらないポップロックナンバーである。間奏でのギターソロはまさに1980年代のアメリカンロックの基本のように耳に訴えかけてくる。Journeyのギタリスト、Neal Schonの紡ぐ音色のように綺麗なギターが聴けて思わず頬が緩んでしまう。
適度に泥臭いギターがアーバンなAOR的なメロディと同居したロックナンバー#4『Slow Down』もREO SpeedwagonやBrian Adams等が演奏しても全く違和感のないような地味であるけれども、印象が強いロックナンバーである。このルーツテイストと都会的な洗練されたサウンドの融合が、Jimmy Ryserの魅力の大きな部分であると筆者は考えている。#1『Climbing Out』や#8『Prophesize』そして#9『Soul Breaks Free』も同様にアーバンとルーラルの鬩ぎ合いが聴き取れるナンバーであり、「Corner Stone」以降のStyx辺りが好んで取り上げそうな都会的なポップさと適度なラフさが、アダルトロックという媒体でブレンドされている、今では懐かしく聴くことしかできないナンバーである。
中盤のアクースティック且つ、美しいスローナンバーも間違いなくこのアルバムのハイライトであるだろう。
#5『Benny』のアクースティックピアノ、ヴァイオリン、アクースティックギターと殆ど3本の楽器だけをメインに、ストリングスサンプリングをさりげなく配して切々と歌い上げる叙情性は素直に感動できるだけである。
また、#5よりも分厚いサウンドアレンジを施したアダルトバラードのスタンダード、というよりもパワーバラードに近い感情の篭った#6『Rain Came』はJimmyもお気に入りのナンバーだそうである。どこまでも、決して大仰ではないが哀愁を漂わせた美しいラインは彼の代表曲の面目躍如というところであろうか。それにしても、Jimmyの女性的というか中性的な澄んだヴォーカルはどのようなナンバーでもヴィヴィッドに富んでおり、まさに聴かせる声を持った人だとつくづく思うのだ。近年のインディ・シーンでの唯一の不満がハスキー系のシャガレ声・ヴァリトン・ヴォイスのヴォーカリストが氾濫しているという趨勢なのだが、彼くらいの美声を持ったヴォーカリストは早々出現しないのだろうかと思わず考えてしまうのだ。
またスローナンバー2曲の後にはキャッチーで奥行きのあるまったりとしたアレンジが産業ロックさえ髣髴とさせる美しいロックチューン#7『Through My Eyes』が置かれていて、このあたりのポップな流れは一番好きなパートでもあるのだ。この直球的なアメリカンなサウンドは、殆ど同じ時にデヴューして、時代に受け入れられず苦戦した、これまた素晴らしいロックシンガーのMichael McDermottが得意とするやや厚めのアレンジを施したロックチューンとシンクロする部分が大であると思う。
なお、#5、#6、#8はインディアナ州やオハイオ州でローカルヒットを記録しているらしい。
#10『Come Home』もしっとりとしたエモーショナルなバラードである。Jimmyの歌う♪「Come Home」での徹底的なハイキーを駆使した裏声には鳥肌が立つような心のざわめきを覚えてしまう。このようなバラードでヒットチャートを賑わすことはもう多分ないだろうと思うと、更にこの曲の失恋の心情を歌った機微が心に染み込んでくるように思えるのだ。また、しっかりとインタープレイでヴァイオリンをフューチャーしているところがJimmy Ryserらしくて良い。
ボーナストラックである#11『Show Us The Way』はそれなりに聴けるアダルトロックなナンバーであるが、
#13『I Am』は1分弱のNew Age風のピアノソロ・ブリッジから始まる北欧メタルのような寂寥感が支配する佳曲である。ボーナスにしては良質なトラックである。
が、しかし、#12『Truth Among The Lies』があまりにも個人的にツボを突き過ぎる、大評価な曲なため、やや余分な2曲である印象を感じてしまうのだ。とことんアクースティックで、基本のメロディは明るいけれども、そこはかとなく黄昏た寂しさが漂うナンバーである。これぞ中西部アメリカのグラスソングというかアーシーさが控え目なフォーキィ・メロディをポップで表現しなおしたような傑作である。「真実は嘘の中にしか見出せない。」というかなりリリカルな現実を透明感の溢れた美声で転がしながらも、どこかに希望を見出すように頑張れ、と訴えかけるような前向きなメッセージが聴こえてくるような歌詞も二重丸である。最後の最後でこの曲を持って来られてはもう白旗である。
このアクースティックで何ら突出したところのないアレンジでは、より一層Jimmyのヴォーカルが躍動しているように感じるのは決して気のせいではないだろう。
以上、水準以上のデヴューアルバムをリリースしながらも、現在はインディに活躍の場を探しているJimmy Ryserのデヴューアルバムについて思いを綴ってみた。
彼は難病とどうやら折り合いをつけたようで、1994年にセルフリリースに近い形で2枚目のフルレングスアルバム「Manana Mentality」をリリース。このアルバムも良い出来である。
また、同年のJohn Mellencampのアルバム「Dance Naked」にギタリストとしてかなりの曲で参加する。更にJohnの次作「Mr.Happy Go Lucky」では1曲目の『Overture』から彼のヴァイオリンが聴ける。
そして漸く3rdアルバム「Let It Go」を4年の間隔を空けて1998年にリリース。セルフリメイクも含んだこのアルバムは彼の最高傑作かもしれない。
更に2000年にはアクースティック・ライヴアルバム「Alive For The First Time」をリリース。そして2001年秋のリリース予定で4枚目のアルバムをレコーディング中であるとのことであったが、かなりリリースは伸びて来年5月くらいになるとJimから連絡が届いた。既に3曲ほどはレコーディングが終了しているそうだが、待ち遠しいことである。
それにしても近年の活動の活性化には、ただ嬉しい気持ちで一杯である。
時代はインディでも十分なアルバムを創ることの出来る風潮へとシフトしてきているし、彼のようなアーティストがじっくりと良い作品を制作するにはうってつけの時代かもしれない。
が、やはりもっと評価されて然るべき人であるし、この本国での過小評価は返す返すも残念である。
是非、3枚のスタジオ録音盤は聴いて欲しい人だ。・・・筆者はライヴアルバムだけは未聴なのだが。
(2001.12.15.)
 Change Of Season
Change Of Season
/ Daryl Hall & John Oates (1990)
Adult.Contemporary ★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★
Blue-Eyed Soul&Acoustic ★★★
洋楽を、洋楽のアルバムをレンタルやラジオからのエアーチェック(死語、完璧なる死語)でなく、自力である程度買えるようになった80年代後半には、Hall&Oatesのチャートにおける全盛期はピークを過ぎていたように思える。
これまでのところ最後のNo.1ヒットシングルとなった『Out Of Touch』のトラックインされたアルバム、「Big Bang
Bomb」の発売から4年もの間隔を空けてリリースされた1988年の「Ooh Yeah!」は勿論トップ40アルバムになり、プラチナ・ディスクを獲得したし、トップ3ヒットとなったシングル『Everything You Heart Desire』を生んだが、嘗ての1980年代前半のようなトップ10ヒットのオンパレードのような勢いは無くなっていたように感じる。
とはいえ、チャートアクションも含めて、Daryl Hall And John Oatesのデュオは、その全米でも屈指のトップアーティストの地位は未だ揺ぎ無いように見えたし、次なるディケイドの1990年代も順調にヒットアルバムを重ねていくように思われた。
ちなみに1980年代のファースト・クオーター(4分の1、約2年半)のチャート及びセールス総合一位はこのデュオ、Hall&Oatesであるらしい。2位はAir Supplyということ。これまた懐かしい。(笑)
というデータからも判別できるように、彼らは所謂一時代を築いたミュージシャンであり、1970年代後半から1980年代の前半は、これはHall&Oates“風”の楽曲と分類できそうな曲が日米を問わずに氾濫したこともあったように記憶している。折からのAORムーヴメントと相通じる、アーバン・コンテンポラリーな、そしてブラックコンテンポラリーにも連なるソウルテイストを兼ね備えていたことが、彼らの音楽のヒットを後押ししたこともあるだろうが、売れるアーティストというのは、そう時代の潮流とも言うべき、大きな流れの後押しを受けて上昇することが多いように、このブルー・アイド・ソウルベースの東海岸出身のデュオにも時代の風が味方したのだろう。
正直、後から聴いてみると、「何故、ここまでヒットシングルになったのか?」と疑問に思う曲もない訳ではないが、概ね良質な音楽を彼らは提供してくれていたし、良いものが売れていた健全な1980年代を懐かしむ一つの指標となるアーティストと考えて良いだろう。
少なくとも2001年最高のゴミ屑アルバムであるBlack Crowesの「Lions」が売れないだけの分別はアメリカのメジャーシーンには最後の一線として存在するようだけれども、やはり1990年代の後半の年間チャート等を眺めると、殆どくだらない曲しかヒットしていないメジャー・チャートは如実にその凋落振りを示している。
初心者にとってはメジャーのヒット曲というのは、かなりの曲を探す導(しるべ)となるのだが、このようなボケ茄子なヒットシーンを聴いて10代を送っていかなくてはならないこれからの世代には涙を禁じえない。嗚呼、還らぬのはヒット曲がアメリカンロックでありえた80年代後半まで、ということを痛感。
と、またも定番の不満の咆哮で無駄なカロリーを消費してしまったので、Hall&Oatesに話を戻すとしよう。
Hall&Oatesといえば『Kiss On My List』、『Maneater』、『I Can’t Go For That』、『Private Eyes』と枚挙に暇がないくらいだが、1980年代前後の大ヒットシングルに代表されるように、彼らの言う「Rock‘n’Soul」なロックのビートとブラックミュージックのリズムを都会的な洒落たセンスと、名状し難い類の尖角的な狂気じみたグルーヴ感を兼ね備えた“白い”ブラックロックンロールが持ち味という印象が強いのではないだろうか。
ナチュラルな手を加えないシンプルなロックという感じはこの頃のアルバム群からは殆ど感じることはできない。最新鋭の電子音楽機器の生み出す非オーガニックなビートに、熱く技量の高い演奏が合流していくような「熱」と「冷」が交じり合ったような音楽、それが大半の80年代からのリスナーの受ける彼らの全体像と推察している。
かくいう筆者も当然1980年前後からDaryl Hall And John Oatesに入ったリスナーであるため、数々のPVと共に記憶にあるのが、Daryl Hallが歌い、John Oatesは後ろでその他のメンバー(これが実は凄い面子ということは当時は判別が付かなかったねんけどね)とギター抱えて踊っている、というような映像である。
よって1980年代半ばを過ぎて彼らのアーリー・ワークスといも言うべき音源を聴くまで、このデュオがデヴュー当初はDarylとJohnの創る曲もリードヴォーカルもほぼ半々に分け合っていたことも知らなかったし、特にAtlanticで製作した3枚のアルバムのうち最初の2枚、「Whole Oates」と「Abandoned Luncheonette」がフォーキィーでマンドリンやアクースティックギターを中心に据えた、アーバン・フォークやアーバン・トラッドとも言うべきナチュラルサウンドを演奏していたとは想像の埒外であった。
Atlanticに残した3枚目のTodd Rundgrenがプロデュースした「War Babies」はフォーク色よりもRundgrenの手腕が発揮されたフワフワしたポップグルーヴと奇妙な前衛的なロックリズムが漂うアルバムであったけれども、それ以降のモダンなリズムロックというよりはやはり都会的なフォークテイストをまだ感じられるアルバムである。
更に余談になるのだが、このデュオのアルバムを1972年の1stアルバムから順に聴いていくと、次第にJohn Oatesのストレートなロックな味わいからDaryl Hallのブラックミュージックを背景にした垢抜けたリズムポップロックへと重心が移動していく過程が如実に刻まれていて面白い。資金と時間がある方は(持ってなければ手に入れなはれ)是非とも試して欲しい“通し聴き”である。
それは兎も角として、初期のアルバムに見られる音楽性は実にフォーキィで繊細である。薄い土臭さもあるけれども、レッドプレインズのど真ん中で水牛を見ながらフォークギターをかっ食らうというようなカントリータッチの田舎フォークではなく、ブリテュッシュ・フォークにより近似した都会の街角でギターを聴かせているような、素朴な都市生活者の心情を綴ったようなきめ細かさの存在する味わいがある。
この都市的なスマートなポップセンスは後のアルバムにも継承されていくのだが、このポップミュージックとしての肌触りの良さに、黒い音楽性や、正確なクロックワークのようなリズムマシーン類の影響があまり見られない初期のアルバムは即座にHall&Oatesの私的ベスト作品となった。
同時に何故にこのようなアクースティックなデリケートさを切り離してしまったのだろうと、「Ooh Yeah!」や「H2O」を聴きつつ不可思議に感じたものである。Steve Winwoodの英国的な作風に通じる気脈を持つ、このような打ち込み楽器を駆使したレコードも悪くはないとは考えつつである。
そのような折、1980年代後半から異様に盛り上がりを見せたUnplugged MTV LiveにHall&Oatesが出演して新曲を披露したというニュースを耳にした。この頃のUnpluggedブームはまさに猫も杓子もという潮流の最中にあり、中には素晴らしい作品も生み出したが、どこが良いのかさっぱり分からんマライア・キャリーの何処が良いのだか分からないようなアルバムまでも(著者はマラ嫌と呼びたい。)諸手を挙げて歓迎されているのには閉口していた。
故に正直「嗚呼、Hall&Oatesよ、お前もか。」と即座にげっそりしたものである。
時流に迎合するのは悪いことでは決してない。が、自分のサウンド性の方向を捻じ曲げても、無理矢理に時代に媚びるのはどうかと思った訳である。1980年代を通してアクースティックやシンプルという概念はHall&Oatesのレコードからは、すっかり脱色されていたから。
よってUnpluggedな曲はボーナストラックとでもとしてアルバムの最後に収録され、アルバムとしては1986年、4年前の「Ooh Yeah!」の路線を踏襲した方向性のアルバムになるだろうと漠然と予想していた。
が、この「Change Of Season」をレンタルして京洛のおんぼろ下宿屋で聴き始めた時、
第一聴・・・・・「随分とメロディアスな部分が強調されたな。これは買いだわな。」
第二聴・・・・・「かなりアクースティックな音を使い始めてるなあ。」
第三聴・・・・・「角が取れたというか、無理なファンク・ブラックのテイストがなくなった気がする。」
とどんどんとハマってしまった。当然即座に購入に走ったことは言うまでもない。
私的には現在でもHall&Oatesの数あるヒットアルバム・名盤の中でもベスト盤がこのアルバムである。
初期のアルバム程には「フォークロック」と声を大にして叫べるようなアクースティックさが際立ったアルバムではないけれども、レコードデヴューから18年を経過して、ミュージシャンとしての年輪を刻んできた厚みが十分に歌い込まれた名盤であると思う。
「Whole Oates」で1972年にAtlanticと契約し、フィラデルフィアでデュオユニットとして活動を始めた時、Daryl Hallは26歳、John Oatesは23歳。Darylは1966年に同郷のバンド、Temptonsのリードシンガーとしての活動歴があるけれども、本来のレコードデヴューはこのユニットが両者ともに初めてといってよい。
その青臭さというか若さ故のナイーヴな感性が行間に見え隠れする初期作群と比較すると、フォーク&トラッドとは厳密には呼べないかもしれないが、ギラギラとした輝きを放出しまくっていた1980年代のレコードたちと比べると、相当にナチュラルでアクースティックさを取り入れたアルバムに仕上がっていると思う。
シンプルさという点でも「Abandoned Luncheonette」等と対照してみても、色々なポップミュージックに挑戦してきた航跡がくっきりと反映されて、より深みのあるサウンドとして完成しているのではないだろうか。
これはこのアルバムに、ブラック・ミュージックがモータウン・ソウル等のディスコやマシンビートに毒される前の純粋なポピュラー音楽であった頃のテイストが沢山詰まっていることも、その音楽性の奥行に一層の影響を与えていると思う。もっとも、打ち込み系のソリッドなブラックを背景とした音楽が広まったのは1980年代のHall&Oatesの功績でもあり、罪でもあるという二律背信性もあるのだが。(苦笑)
ちなみにDarylがリード・ヴォーカルを担当していたHall&Oatesのアーリー・ワークというかテストヘッドのようなバンド、Temptonsは1996年に発表した曲の殆どを集めた編集盤が独逸で発売され、大手のネットショップなら手に入るので、興味のある方は購入してみては。まあ、Hall&Oatesのファンなら今更の情報であるけれども。
さてさて、この彼らの栄光の10年であった1980年代から新しいディケイドの始まりの1990年に発表された「Change Of Season」で彼らの目指したものは何なのだろうか。
Unplugged Liveに出演したことからも分かるように、アクースティックなサウンドに興味というか、立ち返るという意図が大なり小なりあったことは想像に難くない。インナーの裏スリーブにカットインされたアクースティックギターの写真が、このアルバムで目指したHall&Oatesの心情を代表しているように思えるのだ。
1980年代にはアクースティックギターとHall&Oatesという組み合わせにベストマッチなどと考えるリスナーはそうそうは存在しなかったと思う。デヴュー当時から聴き続けているリスナーさえ、1970年代の後半からのソウルミュージックを基本にしたスマートなリズムロックに慣れ親しんでしまった人が多いのではないか。それくらい、彼らのヒット曲はアクースティックという自然なシンプルなサウンドからはかけ離れていたのだ。
が、このアルバムのようなアクースティックギターを多用した音創りをした背景にはやはり、初期のフォークでアクースティックな方向性と、ビートで誤魔化そうとしない本来のブラックミュージックへの回帰を求めていたと思う。
しかし、単純なGet Back To Rootsではないとも思う。
本来、20代の若さでデュオを結成し、フィラデルフィアのコーヒー・ハウスや小さなハコでギターを抱えた活動を行っていた頃に持っていたフォーキィでトラッドな彼らのルーツでキャンバスをベタ塗りにするようなことはせずに、1980年代に自己で完成させたテクノロジーを駆使したロックン・ソウルのテイストと組み合わせて新しい色を創った。
そのような彼らのルーツと現在持ち合わせている武器を合体させて新色を捻り出したようなアルバムであると思うのだ。
ここには新しい10年に対して、これまでの築き上げられた自分達の固定観念やイメージから脱却して、新しい地平を目指すというような意気込みが見て取れるのだが・・・・・・。
MTVのUnpluggedプログラムで当初録画されたのは#1『So Close』と#2『Starting All Over Again』の2曲であり、それ以降幾曲かアンプラグド・ヴァージョンを披露しているが、録画したビデオが紛失してしまったので、セットリストについては明確な記憶がない。『She’s Gone』や『Out Of Touch』のヒット曲、そして#8『Don’t Hold Back Your Love』等を見た覚えはあるのだが。
本音を語れば、このアクースティックとシンプルではあるがロック楽器を併用したアルバムもかなり良いのだが、いっそのことUnpluggedでアルバムを作成して欲しかった。Bryan Adamsのフニャチンヘロヘロな詰まらないUnpluggedアルバムなんぞとは比較にならないくらい素晴らしいアルバムになったに違いない。
それはこのアルバムにボーナス的に収録されている#12『So Close/Unplugged』を聴けば明白である。このアルバムでは一番素晴らしい、シンプルでしかも適度に厚みのあるナンバーとして仕上がっていて、このアルバムからのファースト・シングルになり唯一のトップ40ヒットとなった#1『So Close』(全米11位くらいだったか?)も悪くないナンバーであるけれど、味わいを噛み締めれば、滲み出てくる深みは#12とは比較にならないくらい少ない。参考までにだが#1のPVヴァージョンは♪「So Close,Yet So Far Away」のア・カペラ・コーラスから始まり、こっちの方が感動的で良かったりもした。
#2『Starting All Over Again』の同日に収録されたUnpluggedヴァージョンも是非収録して欲しかったが。このヴァージョンは当時日本では発売されなかったシングルのB面というか2曲目で聴けるのみと記憶している。シンセサイザーやB3オルガンをバックに、かなりレイドバック風なソウルバラードして歌われる曲であるけれど、アンプラグドのヴァージョンは更に素朴で好感度が上である。オリジナル・ヴァージョンも女性バックコーラスを挿入してゴスペル的な雰囲気も出している。
#1『So Close』の、如何にもJohn Bon JoviとDanny Korchmarが手がけたのが丸分かりなドラマティックな産業ロックライクなシングルカット向けの曲とは好対照である。とはいえチャート・インしてないとはいえシングルにもなっているのだが。
シングル曲といえば、#12のようなイレギュラー・ヴァージョンを除けば筆者がHall&Oatesでは一番好きなナンバーが2ndシングルになった#8『Don’t Hold Back Your Love』である。80年代の大ヒット曲よりも全然好きである。アクースティックギターから始まるリフといい、控えめであるけれども美しく奏でられるピアノラインといい、Darylの円熟味のある伸びやかなヴォーカルといい、次第に後半にかけて盛り上がっていく、お約束であるけれどもロック・バラードとしてのチャーム・ポイントを完璧にクリアしたメロディといい、どれを取っても最高の1曲だ。70年代後半に東海岸出身の西海岸バンドとメディアに呼ばれたことを思い出させるようなコーラスワーク。何故、この傑作曲がトップ40にも入らずにスマッシュ・ヒットで終わってしまったのかが疑問でならない。この頃からクソ馬鹿オルタナ&グランジがのさばって来たとはいえ、忸怩たる思いが強い。やはりオルタナは死滅して欲しい、可及的速やかに。
アメリカでは最後のシングルとなった#6『Everywhere I Look』も自然な音響と、こってりした人口音響が程よくミックスされた、キャッチーなジャンプナンバーであり彼らの大ヒット曲に何ら劣るところがないのにヒットを記録せずに終わっている。思わず踊りだしたくなるようなリズム感抜群の曲なのだが。
更に、日本や欧州ではかなり切ないバラード#5『I Ain’t Gonna Take It This Time』も独自にヒットを飛ばし、シングルカットはされていないが、PVはそこそこのオンエアを見ている。このバラードは黒っぽさというよりもアーバン・ポップなバラードである。この悲しげなメロディはヒット街道驀進時のHall&Oatesのアルバムでは殆ど聴くことが出来なかったタイプの正統派バラードである。
他の曲も非常に良作が多い。
#3『Sometime A Mind Changes』は#2よりも更にアクースティックなスローナンバーである。フィラデルフィアの優しいソウル・ミュージックが彼らのルーツにあることを連想してしまいそうなナンバーである。
#8『Give It Up(Old Habit)』も#6のようにポップでモダンなセンスを持つメンフィス・ソウルを匂わせるナンバーであり、取り入れられているコーラスを聴くと、サザン・ソウル的な印象も受けてしまう。この曲はどちらかというと前作「Ooh Yeah!」までのソウルフィーリングを色濃く残しつつ、分かりやすいコードでコマーシャルに纏めたような曲であると思う。同様な感覚で作られているのは、大胆に打ち込み機器を使った彼ららしい#9『Halfway There』やリラックスした中にもロックンロールのパワーを見せる#11『Heavy Rain』であり、後半はアクースティックなカラーというよりも、ポップに仕上げたロック&ソウルという雰囲気が強い。
そしてタイトル曲の#4『Change Of Season』であるが、これまた久々にJohn OatesがリードヴォーカルとしてDarylとの掛け合いを見せてくれることが嬉しい。確かにDaryl Hallのヴォーカルはとても才能ある独特の艶があるのだが、John Oatesのヴォーカルとてそれ程悪くないし、歌はとても上手い人なのでもう少しリードを取っても良いとは常に思っていたので、これは傾聴に値する本来の意味でのデュオ・ナンバーであると思う。かなり素朴なソウル風なミディアム・ナンバーであるけれども、2人の織り成すヴォーカル・パフォーマンスは素晴らしい。
相変わらず殆どの曲はDarylが中心になって書いていて、Johnの手掛けた曲はこれまたJohnがリードヴォーカルを担当する#10『Only Love』だけなのであるが、この曲はJohnのシンプルなロックへの追求が相変わらずであることが伺えてほっとする。
日本盤のみ7曲目にボーナストラックが入っていたが、大した曲でなく、このアルバムのカラーには全くあってないギラギラした80年代前半風の曲だったので、安価な輸入盤を購入したことを最後に付け加えておこう。
しかし、この90年代のスタート台となるべき、ルーツ回帰を取り入れたアルバムはチャート的に大失敗し、1973年の「War Babies」以来、初めてトップ40入りを逃したアルバムになってしまった。またライヴアルバムやベスト盤も含めてプラチナアルバムを4作目から続けていたHall&Oatesには17年ぶりのゴールド認定のアルバムになってしまい、セールス的には彼らの基準から見ると間違いなく失敗に終わっている。
この失敗が響いたのか定かではないが、次のアルバム「Marigold Sky」を世に出すまで7年の歳月を費やしているし、肝心の内容もこのアルバムで見せてくれたアクースティックでライヴ感覚のある音は全く失せていた。
これは実に残念であった。丁度「Marigold Sky」ツアーをLAのHouse Of Bluesで見る機会に恵まれたが、最新アルバムからの演奏はたった2曲のみで、聴衆の受けも非常に悪かったことを覚えている。
一度失敗したからといって、折角ナチュラルな色合いを出してきたのに引っ込めてしまったのは、かなり宜しくないと思う。筆者的に相当減点対象だ。
また、2001年にまたもやHall&Oatesのいかにもレコード会社の企画盤というようなベスト盤が出されたが、そういったアルバムにこの「Change Of Season」にトラッキングされたキャッチーな佳曲が殆どセレクトされないのも実に納得がいかない。(せいぜい、『So Close』くらいか)
ややどぎつ過ぎる1980年代のアルバムよりも落ち着いて良心的なポップセンスを持った曲の多い傑作なのだけれども、一般の特に90年代からHall&Oatesに入門しようとするリスナーにはスルーされることが絶対に多いアルバムになっていると思う。
良い音楽が売れなかった90年代が終わり、2000年代に突入した今年2002年、Daryl Hall And John Oatesは5年ぶりにアルバムをリリースするらしい。が、このようなアクースティックなリラックスしたアルバムを届けてくれる可能性はあまりなさそうである。
一応は期待して待っているけれども。 (2002.1.5.)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
