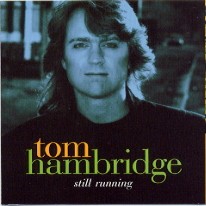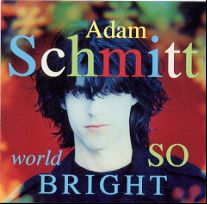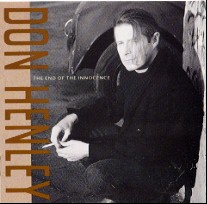 The End Of The Innocence / Don Henley (1989)
The End Of The Innocence / Don Henley (1989)
Roots ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Adult-Contemporary ★★★★
You Can Listen From Here
2000年の話だが、1994年に「Hell Freezes Over」というThe Eagles名義としては14年ぶりのアルバムをリリースしてから、思い出したようにライヴだけはちょこちょこと行ってきたEaglesが,前作より11年ぶりの発売となる「Inside Job」にDon Henleyが集中したいためにライヴ活動を停止したと聞いた時は、Eaglesの活動停止に落胆し、Don Henleyの待たされ過ぎたアルバムへの期待が少し以上という心持ちだった。
が、世紀のクソッタレ作である「Inside Job」を聴いた瞬間、Don Henleyの評価は地獄に落ちた!!
元来、Eaglesの後期の流れであるDon Henleyが中心となって他のメンバーを蔑ろにしがちな傾向が、「Hell Freezes Over」にまで引き継がれていたのは、Eaglesの再結成という興奮が薄れるにつれて、どうにも腹立たしいことのように思えた。
しかも、自分のボケ茄子なソロ作のために、Eaglesを休止するとは相変わらずのワンマンぶりであるとも感じ、どうにも良い印象を持ち得なくなった。
更に、何時までもアルバムを出す表明はしても、全くリリースの気配がしないEaglesへの不満も手伝って、Don Henleyはかなり嫌いなアーティストになっている、現在もだ。
兎に角、「Inside Job」は最低だ。
2001年、再びDon Henleyが全くのニューマテリアルで固めたEaglesとしてのアルバムを出すことを表明したが、その矢先にDon Felderがバンドを解雇され、Don FelderはHenleyとGlenn Freyを相手に不当解雇とEaglesの収益への版権の配分を主張して2億ドル(約240億円)の訴訟を起こしている。
この解雇劇への経緯は、あまりにも生臭いので敢えて説明しないが、(もうこの段階で十分生臭いが・・・・。)何をやっておるのやら、と呆れるしかなかった。
そうこうしているうちに、2001年の暮れには、「現在Eaglesはスタジオ入りしてアルバムを作成中」という情報も飛び込んできて、状況は混沌としてきた。
そして現在2002年の7月、Eaglesは数年ぶりの北米ツアーの真っ最中の筈だ。Don Henley曰く、「5ヶ月以上スタジオ入りしていたため、レコーディングに疲れ、アイディアが煮詰まってしまったため。ニューアルバムへのモチヴェーションを取り戻すため。」のツアーだそうであるから、Eaglesのスタジオ録音としては1979年の「Long Run」以来の新作は近年の内にリリースされる可能性も出てきている。
まあ、新作を出すにせよ、自分をあんまし中心にせんといて!そして何より「Inside Job」のようなクソをEaglesに持ち込んだらアカンで〜!!
くらいは言っておきたい。
しかし、この1980年代の終焉を象徴するようにリリースされた「The End Of The Innocence」まではソロアーティストとしては悪くない作品を残していたのだが。
「始め良ければ終わり良し」、という言葉もあるけれど、このDon Henleyがソロ活動を始めてから18年でたった4枚のオリジナルアルバムのうちの3枚目「The End Of The Innocence」はこの慣用表現とは少し異なる言葉が似合いそうなアルバムだ。
「始め良くて終わりも良い。」、と言えれば申し分ないのだが、実際は
「始めと、終わりは最高に素晴らしい。」という方がしっくりくるだろう。
オープニング・トラックの#1『The End Of The Innocence』。
クロージング・トラックの#10『The Heart Of The Matter』。
この歌詞の内容がそれぞれを相互に導き合い、暗喩し、対比し、そして補完し、対になるように幕開けと幕引きの場所に置かれた2曲のバラードは、その歌世界とメロディによって1980年代のアメリカン・ポップロック界の大名曲である。
だが、『始め』と『終わり』は最高に凄いということは、等分にアルバムを通して全てが素晴らしいとは言えないのである、残念ながら。
より正確に述べると、この「The End Of The Innocence」は
最初の曲と最後の曲が凄いが、結構後はしょうむないナンバーが偏在する凸凹のアルバム
であり、同義でファースト&ラストナンバーの出来の凄さの故に、名盤足り得る錯覚を惹起させる作品でもある。実際の完成度は始まりと締めの曲感から2割以上割引いた方が無難だろう。
些か、手厳しい評価であるとは思うが、事実である。
前作の「Building The Perfect Beast」(1984年)に比較すると、電子音やデジタルテクノロジーを使用した前衛的な構築を目指した作風は影を潜めてはいるが、やはり捨て曲とピックアップできるヒット性の高い曲の落差は激しいところは不変となっている。
Eaglesを解散させてから、Don Henleyという不出生のヴォーカリストでドラマーなシンガーは、EaglesでのCountryやWest Coast Rockのイメージを求めて払拭するよう努めて来たことが如実に感じられる。
1982年の「I Can’t Stand Still」が一番ルーツというかEagles的な空気をアルバムに纏わりつかせていたが、Don Henleyの最大のヒットである『Dirty Laundry』(全米第3位)は完全にテクノビートを使用したアーバン・ハード的な異色の曲−Eagles時代と比較した場合−であるし、他のスマッシュ・ヒットの『Johnny Can’t Read』と『I Can’t Stand Still』にしてもシンセサイザーを多用したシティ・ロック風のシングルだった。
この、無理矢理を感じさせる程の傾向は、2ndアルバム「Building The Perfect Beast」になると更に加速し、当時の流行であったTOTOライクなデジタル・プログレッシヴなサウンドをばら撒いた音楽になってしまった。
ここでもグラミーシングル『Boys Of The Summer』を始め、『All She Want To Do Is Dance』他のヒットシングル3曲はルーツロックとは皆目そぐわないアーバン・ポップスやリズム・サウンドになってしまっていた。
但し、ヴォーカリストとして焼けた砂漠からの熱い疾風を感じるようなDonのハスキー・ヴォイスにより、全てそれなりに聴けるナンバーとなっていたのが凄い。
兎に角、ヴェテラン・プロデューサーのDanny Kortchmarとソロデヴュー時から一貫して組んで目指したのは、Eaglesという偉大過ぎるバンドのフロントマンであった自分のカラーを塗り替えるようにした音楽であった。
この点、“芸術性”という観点からは全くDon Henley程には評価されない、元同僚でソングライターの相方であるGlenn FreyがEaglesの持ち味であったポップセンスを敢えて変換せずに、彼の原点であるというメンフィス・ソウルを基本にしたポップロックでアルバムを作成していったのとはかなりアプローチの仕方が異なっている。
どちらも80年型のアリーナ的人工サウンドを積極的に取り入れているというスタイルは共通しているとはいえ、Glennの方が素直な作風を誇っているといって構わないだろう。
しかしながら、EaglesとなるとGlennよりもDonがリーダー・シップを取るため、いまいち日陰者になってしまっている感が拭えない。「Hotel California」以降のEaglesサウンドの中心がDon Henleyという流れが、20年以上経た21世紀では変わってくれることを祈るだけである。
やや話が逸脱してしまった。Don Henleyの音楽性についてだが、このソロ3作目ではこれまでに必ず実行していた実験的なナンバーは姿を消したといえよう。というかここまでの2作である程度突き詰めてしまったのだろうが、Donのレヴェルでの斬新さは。(この予想は、「Inside Job」でまだ甘かったことを11年後に思い知らされるが、嫌な形で。)
しかし、架空の都市であるシャングリ・ラを歌ったソーシャル・ソングである#6『Shangri-la』では、やはりマシンビートとエフェクターを多用したアバンギャルドな難解さが見えるし、#6でもそうなのだが、全体的に社会批判的なナンバーはどれもヘヴィでダークな曲が多い。
Axl Roseがバックヴォーカルで参加している#3『I Will Not Go Quietly』も前の2曲と比べるとその落差が酷いし、暗い#8『Gimme What You Got』、そして我が愛しのJ.D.Southerが曲創りに参加した#9『If Dirt Were Dollars』の3ナンバーを合わせたこの4曲は、正直捨て曲なメロディだ。
歌詞的には、ラヴ・ソング主体であったDon Henleyからは珍しく痛烈な社会への皮肉や風刺が込められているので聴いていると興味深いが、如何せんメロディが宜しくない。このあたりはDanny Kortchmarの責任でもあるかもしれないが、
良い詩を書くんやったら、もちっとマシな曲を付けろ!!カバタレ
と思う。
と、このままではたいしたアルバムにはならないのだが、それはそこ、シングルカットされたナンバーは、意味の通りにシングル向けな優良ナンバーが揃っている。
トップ40入りした#4『The Last Worthless Evening』を筆頭に、チャートマニアではないので正確な順位は記憶していないが、トップ40近辺までは上昇した#2『How Bad Do You Want It』に#5『New York Minute』。
この3曲にプラスして頭と尻尾の2曲も勿論ヒットしている。タイトルナンバーは2枚目の最高位第3位に、#10は私的にはNo.1ヒットになっても良い筈なのだが、トップ40入りで留まってしまっているのが納得いかないけれど。
またJ.D.Southerがライティングに協力し、このキャッチーさはDonではなくJ.D.のペンに寄るものと勝手に未だ信じている#7『Little Tin God』もシンセサイザーと打ち込みプログラムがピロピロ鳴るナンバーであるが、軽快でリズミカルな佳曲である。これ以外のノン・シングル曲は駄目ということがあからさまで、分かりは易い。
まずは、クレジットではDonのドラムス以外は全てDannyのサンプリングとなっているのが信じられない#2『How Bad Do You Want It』。このぶん回されるホーンがシンセ・ホーンとはどう聴いても思えず、やはり生サックスフォンに聴こえてしまう。ダイナミックなドラムとノイジーなシンセラインと、そしてフルスイングに伸びるサックス。歌詞は俗なラヴ・ソングだがノリは最高に快調なナンバーだ。40位前後というヒットポジションも妥当だろう。
アクースティックなギターとしめやかな鍵盤が、都会の夜のアンヴィギュアスさを映し出すようなバラードの#4『The Last Worthless Evening』はトップ10にはキツイ曲だが、ヒットして当然な良作だ。一方的な恋心を唄ったナンバーであるけれども、かなり詩的なラヴ・ソングに思える。
#5『New York Minute』は筆者の大好きな鍵盤プレイヤーであるTOTOのDavid Paichが前作から続いて顔を見せ、ピアノとストリングスアレンジを担当。更に、黒人ア・カ・ペラ・グループのTake6がコーラスをなぞるという豪華なキャスティング。切ない、哀しいバラードで、都会の切なさと冷たさ、コンクリートの谷間で生きる孤独をしみじみと喉から搾り出す名曲なのだが、1994年のリユニオンアルバムでDon Henleyが唄い、あまつさえ、アルバムに入れていたのには呆れた。
しかも同日にテイクされた大名曲#10は映像作品のみにしか収録されていないのも更にムカツク。
そして、1989年という時代性を感じさせる、#1のタイトル曲。当時日本はバブル経済が膨れ上がっていたが、アメリカは社会問題を様々に抱え、空前の不況に喘いでいた。そういった中でのアメリカンドリームの崩壊、日本人をエコノミック動物と呼んでいたアメリカ人が拝金主義に鞍替えし、世界の正義を守っていたと(実際は大国の権力でブイブイいわしてただけやけど)信じていたアメリカの世界の警察という根幹の揺らぎ。
こういった現実を見つめ、「無邪気に時を過ごす時は終わりを告げた。」と唄う。Don HenleyとあのピアニストでヴォーカリストのBruce Hornsbyの共作だが、作風もアレンジも全くHornsbyのものだろう。Donが創ったらもっとゴテゴテなシンセサイザーやプログラミングを入れて台無しにした可能性が強いと思う。
グラミー賞を獲得できたのもBruce Hornsbyのおかげであろうし、曲にメロウで繊細な味付けをするWayne Shoterのソプラノサックスの助けも見落としてはいけないだろう。
そして、筆者がDon Henleyの最高の名曲と広言して止まない、#10『The Heart Of The Matter』。が、これも共作者でありバックヴォーカルでも加わっているJ.D.Southerの作風に近い気がする。Donだけでは完璧を見なかったバラードだろう。
HeartbreakersのMike Campbellがキーボードとギターを担当し、現在はCampbellの元同僚になってしまったドラマーのStan Lynchもパーカッションで参加している。
兎に角、大気に甘く溶け出しそうなアルペジオ風ギターの秋空をバックに揺れるコスモスの花のような清涼感。
Don Henleyのハスキーヴォイス炸裂なメロディ。
西海岸風の久しぶりなコーラス。
そして、混沌とした時代を見据えながら、「Forgiveness」−許す、許容することを覚える、という歌詞。
♪「Forgiveness・・・・・・Even If You Don’t Love Me Anymore」
このフレーズに込められた意味を#1の「The End Of The Innocence」と掛け合わせて考えると、どういった解釈が出来るか。言葉にして記述すると非才な筆者の言葉では陳腐化するので、敢えてここでは述べないことにしたいと思う。
♪「I’ve Been Trying To Get Down To The Heart Of The Matter」
これは何時の時代にも、誰にも存在する心理だと思う・・・・・・。
正直、この1曲で名盤になっているようなもんでもある。ミもフタもないけれど・・・。
このForgivenessのコーラスブリッジを聴いていると、どうしようもなく青かった学生時代を想い出して感無量になったりもする。当時よりも、この歌が染みるのは歳を食ったせいだろうか・・・・・・・。
それにしても、Eaglesの再結成や環境保護運動への参加等があったにせよ1990年代をソロアーティストとして沈黙したのに、結果があの駄作では救われない、待ちに待ったリスナーが。
まあ1995年のベスト盤「Actual Miles」での2曲の新曲=最低の駄作で、物凄く嫌な予感をDon Henleyの将来作に感じたことが正しかったのは、まだまだ筆者の耳も確かな証拠と自負する材料にするくらいしかない。
さて、Eaglesの新作が届くことを祈ることにしようか。それくらいしか、Don Henleyには期待できない。
ソロアーティストしてではなく、彼のヴォイスと共作者との協力で生まれるに違いない名曲に思いを馳せて。
(2002.7.5.)
 General Admission / Pat McGee Band (1999)
General Admission / Pat McGee Band (1999)
Roots ★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Acoustic ★★★★☆
You Can Listen From Here
“General Admission”という単語は、日本では殆ど馴染みのない表現だろうと思う。多分・・・・。
横文字好きの日本でも最近は使われているかもしれないが、ここ数年は全くライヴを見ていないので事情には疎くなり過ぎているから実際は不明確なのだが。
まあ、直訳すれば、「一般的な入場許可」ということになるだろうか。
転じて、「均一な入場資格」→「区別のない入場券」→「座席指定のない入場券」となるのだろうか。
仮に海外旅行でも出かけて、ライヴハウスのチケットを買う時、General Admissionと印刷されていれば、座席番号が印刷されていても、座席指定はない所謂自由な立ち見のスタイルを採ったライヴのことであるから、留意しておくと便利かもしれない。(どうだか・・・・。)
和製英語で表現すれば「スタンディング/立ち見」である。
まあ、日本ならフリーのドリンク券が付く場合が結構あるらしいが、米国では付随のバー等でドリンクを2本は買ってくれ、という指示が一緒に印刷されている場合が多い。そんなことはどうでも良いのだが。(苦笑)
どうでも良いついでに、当時地獄の安月給であった筆者は、バーでライヴを見てもビールは一本も買わなかった。年間300本近いショウを見ていたにも拘らず、だ。ここまで来るとセコさも一芸になるかもしれない。(ならんわ)
こういったことから推察できるとは思うけれども、General Admission扱いのライヴは小さなハコでが前提条件であり、しかもライヴに足を運ぶ観客がボールルームやバーで落とす金の方に、アーティストのチケット収益よりも期待がなされていると読んでも穿ち過ぎではないだろう。
つまり、新人バンドやインディバンドのギグに多いスタイルということだ。無論、メジャーのアーティストがGeneral Admissionで演奏することはあるけれども、相対的な比率をここでは述べている。
メジャーの大物アーティストの場合、意図して小さな会場を選択しない限り、General Admissionなフリーのライヴ形式は不可能に近い。
こういった「立ち見のライヴ」という意味を示唆するタイトルをPat McGee Bandは3枚目にして初のライヴ録音盤の題名として使用している。
当然、この「General Admission」は自主レーベルからインディ・リリースされたアルバムである。大物売れっ子が意図して小さなライヴ会場を選択したのではない。
1997年にPat McGee Bandとしての名義の初作品である「Revel」がビルボードトップ200アルバムの190位近くに数週ランク・インはして、インディ・アーティストとしては期待以上の成功を収めているとはいえ、この段階ではメジャーなアーティストと呼ばれるには不足である。
10万枚単位まで売上は届いていない。自主作品としては、完全に成功とは言える1万枚以上のセールスを記録してはいるのだが。
よって、自らをローカル・インディペンダントのマイナーバンドとして再認識させるようなタイトリングを、Pat McGeeは行っているのだ。
バンドが「Revel」とこの「General Admission」での好評を得て、Warner Brothers Recordsの傘下レーベルであるGiant Recordsと契約を交わして初のメジャーリリースへの取っ掛かりを掴むのが1999年末のことであるからして、 メジャーへ昇格したアーティストが、無名時代を懐かしがって、「初心に還る」という御題目により昔のスタイルで演奏をした、というような原点回帰の作品ではない。
参考までに、筆者はライヴ会場でこのアルバムを1998年に入手しているが、商流に乗ったのが1999年始めであるそうだ。よって、リリース年度は1999年と改めておいた。ご了承願いたい。
自らのステータスをひけらかすのでもなく、ことさら誇りとして主張するのでもない。
皮肉に無名であることを自己で諧謔している? メジャーでのアリーナ級ライヴへの批判めいた意見?
いや、そういったネガティヴな批評を込めてこのアルバムを、このタイトルで作成したとは到底思えない。
あくまで現在の立場で演奏することを、気負わずに、自然体で表現しているだけだと思えるのだ。このどこまでもナチュラルで優しい音を聴いていると。
実際に1997年くらいから、バンドはWallflowers、Blues Traveler、Counting Crowsといったバンドが東海岸でツアーする際にフロントアクターとして起用され、大観衆の前でパフォーマンスを披露する経験をしているのだ。
こういったショウに対して、Pat McGeeは素晴らしい経験であったとは述べているが、席が後ろになるとステージで演奏する人影が点のようにしか見えなくなるクラスのライヴ形式に対しての批判は述べていない。
やはり、現在の自分達のグループが行っているライヴをJust The Way We Are=素顔のままで、(を)伝えたいという意欲で作成されたライヴアルバムだと思う。
というのは、この10曲入りのアルバムに収められているのは、どのナンバーも、これぞPat McGee Bandというべきサウンドであるからだ。大抵の人がこのバンドのライヴを見たことがないだろうけれど、このライヴ盤の後に発売された「Shine」(2000年)を含めて3枚のスタジオアルバムを気に入っているなら、十二分にPat McGee Bandの魅力が伝わってくる作品である。
元来、ライヴアルバムは余程のことがない限り買わない筆者が、即座に購入してしまったくらいだから、筆者の中でも評価がとても高いアルバムということを推察して貰えれば幸いである。
このライヴは1995年にPat McGeeの名前で「From The Wood」をリリースしてから、足掛け3年で817のステージに立って、観客と演奏を楽しんできたというPat McGee Bandの活動を集大成としてファンのために残したというコメントがなされている。
年間にして平均270回以上のショウを行ってきた計算になる。1年365日だからして、3ヶ月以外はオン・ザ・ロードの生活をしていたということになる。これはライヴバンドが高く評価され、ハードなツアーを行うアーティストが増えてきたとはいえ、相当なスケジュールだと思う。
しかも、そのような苛烈なサーカス・ライクな活動を思わせないくらい、このアルバムはスタジオ録音盤と同様に、否、それ以上にふんわりとした、暖かく、優しいサウンドが展開されている。
ライヴ主体のバンドが創るライヴ盤によくあるように、「鬼気迫る」とか「必要以上に熱い」とか、「迸る熱狂」という単語はこのアルバムには全く似合わない。
また、辛く緊張を強いられるロードにより、ドラッグやアルコールに依存するミュージシャンは古今東西数限りなく、そういった態度が退廃的や暴力的な雰囲気となって、殊にライヴ盤では、音となって出てくる傾向にあるが、このアルバムで耳を欹てる限り、そういったやけっぱち気味な感情や破滅的な生活とはこのバンドは無縁なように感じる。 そのくらい、良質で、表面を撫でても手が切れるような鋭角的な凹凸や土壌の荒廃を感じさせないサウンドなのである。
とはいえ、演奏が手抜きとか気が入ってない、とかいうフニャフニャなアルバムとは縁遠い作品である。ハードロックではあるまいし、無意味にギターソロや楽器バトルを何十分も入れる必要はこの手のアーティストにはないし、自らがスタジオ録音盤で培ってきた既存のスタイルを破壊するような演奏をすることも無意味なのだ。
きっちりと、バンドが目指して表現している音楽性をライヴステージでも忠実に表現することに成功しているバンドであり、アルバムなのである。ここまで忠実にPat McGee Bandのソングをライヴらしく、そして自分らしく表現しているのは絶賛に値すると信じている。
単純に、レコードと同じパフォーマンスを忠実に再現しているという意味ではない。勿論、スタジオで録音した歌をステージで再現できないバンドは著者としては非常に評価が低くなる。
「ライヴで出来ないことはスタジオでやるな。スタジオで出来ることはライヴで出来るようになれ。」
というのがライヴバンドを標榜する限り、これがそのアーティストとしての最低のレーゾン・テートルであると考えている。
よって、スタジオ盤での音楽性をしっかりとライヴで再生出来ているこの「General Admission」は条件をクリアしているし、更にプラスアルファの要素、ライヴ・パフォーマンスならではの魅力も追加されているところに、名盤としてピックアップした理由があるのだ。
この理由については曲目の個々の感想の項で述べていきたい。
このライヴは2箇所で録音されたステージの編集盤である。これまたBilly Joelの「Songs In The Attic」までは美味しいところだけを貼り合わせた編集盤ではないにしろ、単なる1ステージを漫然と録音して売り出すというスタイルよりも好感が持てる形式だ。
ライヴアルバムというのはベストアルバムという性格も帯びていると筆者は考えているので、どうもワン・ナイトのステージを録音しただけの代物は程度の良いブートレグと同じに思えるからだ。
最低限、良いパフォーマンスと録音状態の音源をセレクトして欲しいと思うのは、購入層としては当然の欲求であると思う。
こうなると2箇所での録音というのはやや物足りないが、質的には十分なものがあるので、結果として満足度は高いので、良いだろう。
録音会場となったのは、バンドの活動拠点であるヴァージニア州のアレクサンドリアにあるThe Birchmereというクラブと、ワシントンD.C.のThe Bayouである。
The Birchmereは筆者も一度仕事のついでに出かけた際、ライヴを見たことがあるが、ティーンズよりも20代半ば以上の比較的客層の良いパーティ&ミュージック・ホールであり500人くらいを収容できるキャパシティがある。
The Bayouは訪れたことがないが、これもモッシュなどは起きない中程度の大きさのクラブであり、客層も良いという話である。どちらも物凄く小さなハコではないけれどもこじんまりとした会場で、モッシュの乱痴気騒ぎでなく音楽を本当に楽しみたい観客向けの場所だろう。実にPat McGee Band向けのステージだろう。
まあ、ケツの青い、ラップメタルや流行オルタナティヴだけ聞いているようなティーンズにはPat McGee Bandの良さは分かるまいが。
さて、収録曲は10曲であり、新曲・未発表曲・カヴァー曲という類は全く無し。全て、1st「From The Wood」と2nd「Revel」からのチョイスとなっている。
「From The Wood」からは
#1『The Story』、#2『Nobody Knows』、#3『Who Stole Her From Heaven』
#5『Could Have Been A Song』、#6『Pride』、#8『Haven’t Seen For A While』の6曲。
「Revel」から
#4『Flooding Both Of Us』、#7『Can’t Miss What You Never Had』
#9『Straight Curve』の3曲。
そして両方のアルバムにも収録され、#8『Haven’t Seen For A While』と共にメジャー作の3rdスタジオ盤である「Shine」にもヴァージョン4がリテイクされた#10『Rebecca』が大トリの曲となっている。
どのナンバーもオリジナルのアクースティックさとジェントルさ、そして「Shine」収録の曲のようにウルトラ・スーパー・ポップにはなっていないけれども、スーパー・ポップな点は余さず継承している。
加えて、原曲よりもライヴ向きなコーティングというか、ライヴ用にチューンアップされたようにアップテンポなナンバーはより速く、ミドルナンバーは、一層エッジを立てて歯切れ良く、そしてバラードはライヴの雰囲気を尊ぶが如く、よりドラマティックになっている。
何より、Pat McGeeのヴォーカルの成長が著しい。
ハードなライヴの連続で、何度も声を嗄らして、潰しかけて熟成した深みというか渋みがそのメロウでハートウォーミングな声に加わっている。
先にも述べたが、演奏テクニック自体は、鬼気迫るものでも圧倒されるものでもない。自らの技術を開示して自慢しようというでしゃばりは各パートで全く見えてこない。
全ての楽器がアンサンブルを、丁寧に組み立て、歌という川の流れに合わせてスムーズに進ませていくように気を配っているのが伝わってくる。
地味だが、堅実な演奏は、観客を楽しませるソロパートを幾度か披露しているが、自分の演奏に酔ってのめり込んでいってしまてっいる独り善がりなところは見えない。
インストゥルメンタル・バトルというような楽器の凌ぎあいがハードロックでは頻繁に聴くことが出来るが、そういった一部の演奏マニアが喜びそうなディープさよりも、一般のポップロック好きなリスナーに楽しんで聴いて貰いたいと主張しているような、ナチュラルにたゆたっていく演奏が、とても好感が持てる。
素晴らしい、アクースティック・ロックのライヴアルバムだ。
アクースティックと本邦でメディアや洋楽リスナーが命題する、
ただ線の細いだけとか、大人し目のアレンジだけとか、ただ生のアクースティックギターを鳴らすだけとかいう、厚さも複合的な装甲もない、旧帝国陸軍の九七式中戦車みたいな似非アクースティック作品とは大違いだ。
巷では、その代表格であるJohn Mayerなる凡才が俄かファンも巻き込んで評価されているが、Pat McGeeと比べたら月と泥亀である!(断言)
ちゃんと、自分の耳で判断しようや!良い音楽はもっと存在するんやし。
しかも、キャッチーなロック作品として評価できるところが凄い。特別にアンプラグドなスタイルをライヴ故に選択しているのではなく、最初からアクースティックでありつつもロックンロールを作成できるアーティストというPat McGeeの才能がここでも開花している。
何と言っても、圧巻は#10『Rebbeca』の13分近くに及ぶ熱演だろう。全てのアルバムに別テイクを収録するほど、Pat McGeeのお気に入りであり、バンドの代表ナンバーである『Rebbeca』をファンも心得たもので、ファースト・ヴァースでPatがマイクを向けると、合唱を行い、ステージと観客が一体となり楽しんでいる様が目に浮かぶようである。
アレンジとしては素晴らしいポップソングとして完成された「Shine」の2曲目のVer.4に近いロックアレンジなビートが楽しめる。メインのヴォーカル・パートが終った後、7分近いインプロヴィゼイションが展開されるが、これがまた実にバランスの取れたソロが続く。
どのパートでも極めてポップでグルーヴィな演奏が楽しく、楽しくジャムられる。アクースティックギターソロからベースへ、エレキギターとキーボードのアンサンブルへ、そしてまた全体のロックジャム、更にアクースティックギターへ、というようにジャズのステージを見るように目まぐるしく変わるソロパートの流れはもうライヴを見に行きたくて堪らなくさせる蠱惑的な引力がある。
同じく、代表曲の#8『Haven’t Seen For A While』もライヴならでわのサクサクとしたアクースティックギターがスタジオ録音盤以上に似合っているバラードとなっている。時折、観客と一緒になって唄うという箇所が嫌が応にも雰囲気を盛り上げていく。淡々と進む曲の筈だが、コーラス部分でのアンサンブルをオリジナルよりも強調し、アクセントをリマーカブルに付けているのも臨場感をアップさせている。
筆者のお気に入りは、ポップロックとして完成度の高い#1『The Story』や#5『Could Have Been A Song』、そして#9『Straight Curve』である。オリジナルから滑らかなポップロックであったけれども、ライヴにより微妙にアップビートなり、水切りのよいさっぱりとしたアレンジが実に似合っている。ややウェットであったスタジオ盤よりも湿気が抜けたようで、更にポップスとしてのスコアのチューニングが的確になっているため耳に溶け込んでくるキャッチーさの流れはより流暢になっている。
また、明らかにライヴのノリで数段楽しくなっているのが#3『Who Stole Her From Heaven』や#6『Pride』というJam Rockなルーズさをもったフォークロック・チューンだろう。原版には取り入れられていなかったドリーミングなキーボードを弾ませ、相乗効果で曲自体のリズムまでジャンピーにさせている。
特に#6『Pride』は観客のシャウトと音頭を取って交互にザクザクと曲を浮上させていくところが、もうライヴでしか聴けないのが残念で堪らない程である。
#4『Flooding Both Of Us』、#7『Can’t Miss What You Never Had』という「Revel」からのナンバーは、最初から曲としての完成度が高いためか、かなり長いソロパートでスタジオ盤と差別化を図ろうとしているようだ。どちらも地味なナンバーであるが、たっぷりとした良心的なインプロヴィゼイションが堪能できるから、これまた外すことの出来なライヴトラックとなっている。
メジャー昇格前のアルバムも簡単に入手できるアーティストに現在はなっているが、この1枚で過去の2枚のアルバムを補完できる充実性があるので、「Shine」から聴き始めて気に入った方はこのライヴアルバムから過去をトレースするのも良いかもしれない。
現在、Pat McGee Bandは新曲を既にライヴでも5曲以上セットリストに加えているそうで、4枚目のスタジオアルバム、通算5枚目のアルバムにぼちぼちと曲を書き溜めている状況である。
恐らく、新譜の到着は2003年と予想されるが、今から楽しみである。それまではこの「General Admission」を含めた4枚のアルバムを聴いて我慢するしかない。
ちなみに筆者は「Shine」に次いで、この3枚目の作品を2番目に聴き込んでいる。録音もまあ悪くないし、過去の2枚のスタジオ盤よりも出来が良いためである。
雰囲気としては「Shine」と「From The Wood」の中間的なアレンジであるアクースティックだが華やかさの出てきたサウンドが楽しめるアルバムだからだ。まあ、筆者の推す数少ないライヴ盤だからして、お薦め度はかなり高い。
(2002.7.7.)
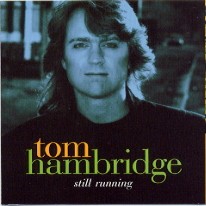 Still Running / Tom Hambridge (1996)
Still Running / Tom Hambridge (1996)
Roots ★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★☆
Adult-Contemporary ★★★★
You Can Listen From Here
Bryan Adams、Rod Stweart、Eddie Moneyといったシンガーの歌と名前を知らないという人は、少々熱心に洋楽というジャンルを聴いている人には少ないだろうと思う。いわんや、1980年代のメジャー・シーンに慣れ親しんできたリスナーをや、というところだ。
が、ロック・ヴォーカルとかアダルト・ロック、所謂正統派ロックシンガーとして、Michael McDermott、Tom Cochrane、Jim Ryserといった面々、そして今回の主役であるTom Hambridgeの名前はあまりにも日陰者扱いをされている。というよりも、その存在自体知らない音楽人口が大多数だと思うのだ、この極東の島国では。
米国ではリリースさえされなくなった、元ハードロックバンド・ヴォーカリストのソロ作品なんぞは熱心にトレースするくせに、こういったアメリカン・ルーツに経緯を払いつつもカントリー・シンガーではない普通のロックンロールを普通に表現するアーティストは「地味」、「特徴無し」という単語で切り捨てられてしまっている。
Adult Contemporary(日本ではAORと混同されてしまっているが)系で幅を利かせているのは、本国の市場でも女性ヴォーカルとボーイズ・グループ、そして黒人音楽とクロスオーヴァーしているが、ブラック・コンテンポラリーのみである。
増してやメジャー崇拝主義の強い日本の風土では、Adult、American Trad、Rootsといったオーソドックスな音楽性を大切に暖めているアーティストは顧みられることもなく、それ以前に紹介すらされないというのが現状である。
勿論、上で挙げた数名のシンガーの間でも音楽性にはかなりの差異がある。例を挙げれば、アメリカン・ルーツを叩き台にしたヴェテランシンガーでも、Tom PettyとBob Segerでもその創り出すサウンドには違いがあるのと同様のことだ。
カナディアン特有の中庸的なポップロックを主体にしているTom CochraneやBryan Adams、アーバンポップス寄りなAOR的音楽性を含んだロックシンガーのJimmy Ryser、そしてシカゴエリアの都会と田舎の狭間のサウンドを演奏するMichael McDermott。ルーツロックであるが全くカントリー的な要素を排出してロックに仕上げているArthur Dodge。
と、少し特徴を挙げても、これだけのヴァライエティが存在する。
Tom Hambridgeはどういったタイプの、どのような音楽を提示するアーティストであるだろうか。
真っ先に一つだけ述べておくと、Tom Hambridgeはシンガーとしてはその数が絶対的に少ない、ドラマー兼任のアーティストである。スタジオミュージシャンとしても活躍しているが、寧ろツアーミュージシャンとしてかなりの大物のステージでもスティックを握ることが多い。詳しい経歴に付いては後述することにしよう。
Tom Hambridgeは42歳という年齢の割には、現在までにたった2枚しかアルバムを発表していない。ソロシンガーとしてのデヴューが遅かったのが原因であるが、その2枚のアルバムでも方向性にギャップがあるのだ。
まずは、2枚目の比較的大手レーベルであるArtemis Recordsと契約を交わしてリリースされた「Balderdash」(2000年)に言及しつつHambridgeのシンガーとしての区分をしてみることにしよう。
参考までだが、Artemis Recordsはマンモス・レーベルではないが、かなり有名どころを抱えたレーベルである。
2000年にあのTom Scholzが率いるBostonとも契約をしている。・・・・・何時アルバムを発表してくれるのかは分からず、また全く期待していないが。
Tomは現在は唯一のバンドメンバーであるヴォーカリストのBrad Delpと「オルタナティヴの影響を受けた初期のBostonの音をプロデュースしたい。」というコメントを残してまた地下に潜っているようだが、どうにもかなり不安である・・・・。オルタナティヴとBostonの音は絶対に水と油と思うのだが。
Boston以外にも、Steve Earleの「Transcendental Blues」(2000年)からの所属先であり、Rickie Lee Jones、Peter Wolf、The Reverend Horton Heat、Warren Zevonといった巨大レーベルからヒット作を放ったアーティストを多数抱えている。また2002年7月に新譜を出す予定のMarahも同レーベル所属である。
さて、その「Balderdash」であるが、Tom Hambridge Bandという自らのバンドを結成して(名義はTom Hambridgeである)録音したアルバムだ。バンドの仲間ジャズのキーボーディストとして名の通ったTom Westを筆頭とする、テキサス州はナッシュヴィルのジャズ・ブルース系のミュージシャンを中心に集めたバックバンドであり、その音を反映してか、サウンド自体もかなりハードでブルースのフィーリングが漂う腹に響くようなロックンロールとなっている。
その分、全体としてはかなりポップさがクールダウンしているという感が否めないところがあり、重厚なロッキン・ブルースとしての性格を帯びたルーツロック作品となっている感触が強い。
その2ndアルバムに対して、Tom Hambridgeが35歳の時に作成した「Still Running」はルーツロックを基本としているというスタンスには違いが無いが、かなり毛色の異なったアルバムとなっている。
このジャケットの顔写真を見る限りは、とても1960年生まれの30代の男性には見えないのだが。もっとも長髪という髪型もこの当時のHambridgeを実年齢よりも若く見せているのかもしれないが。2枚目の「Balderdash」ではかなり老けたというか、本当の年齢に近い渋いスナップでジャケットを飾っているが、実際に見るとこのようにふっくらとした顔立ちの優しい好青年(?)という印象を受けるけれども。
本作、「Still Running」(1995年プレス。商流販売1996年。)は、きっちりとハードなブルースロックに纏まってきた2nd作程には一本ではない。2つの音楽性が2本の柱として立ち、同心円状の波形を放射しつつ、その伸びていく円形の縁が交わっているアルバムなのだ。
中心の一つは、日本でAORロックと間違えて輸入され、何時の間にかそのまま定着してしまった、Adult Contemporaryという概念がぴったりのソフトでコマーシャルなポップロック・チューン。
もう一つの柱石が、スライドギターを大幅に主張したナンバーが中心のアーシーでハードなSouthern Roots Rock風のロックトラックスである。
両者共に、ゴリゴリのSouthern Hardでもなければ、ベタベタに浪漫珠色一杯の「恋人たちのナントカ」とコンピレーションアルバムにチョイスされるコンテンポラリー・ソングでもないのが特徴だろう。
程好いルーツテイストというベースの上に乗っている故に、共にルーツテイストの強弱はあるにせよ、極端に一方向に走ったサウンドとはなっていない。
SouthernまたはBoogie Rock風のナンバーも、Adult Rock風味のナンバーも、互いにクロスオーヴァーする部分が多いか少ないかは別として、2つの音楽的中心から湧き出るように拡がる波紋が相互に共鳴し合っている。このようなバランス感覚に富んだナンバーで構成されたアルバムなのだ。
つまりはストレートに大道を行くアメリカン・ロックであり、激烈に良心的なアメリカン・ポップロックなのである。
まずは、流麗でスマートなアダルト・コンテンポラリーな作風を代表するようなオープニングから「Still Running」は幕を開ける。Tom自身がセットを叩く歯切れの良いドラムビートに、リード&リズムギター、ベース、そしてエレキ・ピアノライクなデジタル音をそのまま演出したキーボード。
この#1『Don’t Make Me Wait』は比較的ルーツ色が薄目のサーフ・ナンバーとでも表現できるミディアム・ポップロックであるが、非常に安定感があり、アーシーさが殆ど主張されていなくともルーツロック的な雰囲気を感じてしまうところが注目点だろう。
アクースティックとエレクトリックを均等に配分したギターのバランスも絶妙だが、やはり一番に耳にこびりつくのはパワフルかつ堅実なTom Hambridgeのドラミングだろう。コーラス部分での冷えた素麺のようなシャッキリとしたシンバルの連打は全盛期のBryan Adamsを思わせる。
また、時にハイ・トーンなヴォーカルを、時にはソウルフルな声を自在に変化させて使い分けるHambridgeのヴォイスもその幅広い強さを見せ付けてくれている。
続く#2『Homeless』もAdult Rockに属するタイプのナンバーであると思う。ドラマーが創った曲の良い部分が浮き出た証明のような、実にテンポの切れ味が良いミドルテンポのロックナンバーである。2本絡められたギターが乾いたサウンドを表現していて、当時の活動拠点であったボストン・エリアを代表とするような薄目の土臭さを纏ったルーツナンバーとも言えるし、やや土着的傾向のあるアダルトロックともいえるだろう。カラリとしていて大空へ拡散していくようなドライさはJourneyのような産業ロックの趣も感じさせる。
#4『Downpower』も#1と同じく、かなりアダルトなポップス味の強いナンバーである。James Taylorの妹で自らもフォーク・アルバムを数枚リリースしているKate Taylorをデュエット/ハーモニー・ヴォーカルとしてゲストに迎え、エコーを効かせたピアノ・サンプリングを冒頭から朗々と流したバラードである。やや、後半のブリッジ部分がサイケディリックに展開し、単なる甘々なバラードとは終らせずに、酸味を加えているのも面白い。
バラードなら#7『Drifting』がもっとオーソドックスなスタイルの曲かもしれない。まさにAORというべき、抑揚の少ないアーバンポップスライクなデジタル・サウンド的なリフから淡々と進行させ、コーラスの手前で一気にメジャーコードを叩きつけて打ち上げ。という極めて芸のない堅実なサウンドクリエイションで成り立つロックバラードだが、良いものはやはり良い、という感慨をのみ抱かせてくれる良曲である。ここで鍵盤をB3やアクースティック・ピアノとしてフューチャーすればルーツィな落ち着きを持つ傑作にもなりえるナンバーなのだが。
#9『Eyes』は売れっ子の第一線にいた頃のRichard Marxに唄わせるとかなりヒットしたかもしれないような、ヴォーカル・ポップナンバーである。あっさりとした高原の朝の空気のように清涼なナンバーであり、泥臭さや野暮ったさとは対極に位置するリズミカルな曲でもある。これまたTomの背骨が伸びる効果を持つクリアなドラムと、テレキャスターの陽性な音色が印象的である。
最後のアクースティックギターとTomのヴォーカルだけで密やかに綴られる、#12『Crybaby』はこのAdult Contemporary組ではなく、Roots Southern組としても良いのだが、これまたアーバン・フォークのように整然とした静かさを流す曲であり、一切カントリー的な田舎サウンドが組み入れられていないため、こちらの側に属するナンバーだと思う。これは小作品であり、アウトロ的な性格の強いラストナンバーだ。
さて、以上のアダルトロック色の強いナンバーとは違い、ブルージーでクラッシック・ブギーな泥臭くハードなカラーの浮き出たナンバーが対照的に散りばめられているのがこの「Still Running」の特色だ。
いきなり2曲続いたスマートなポップロックの後に出現するのが、ゴリゴリでノリノリなスライドギターを掻き鳴らしたロックチューンの#3『Cadillac』である。兎に角、ギュンギュンとドライヴしていくスライドギターに乗っかって、ドラムやベースが低音を響かせてパンチをかませるのが、このロックナンバーである。1960年代あたりのBoogie Rockの宴会的楽しさを1990年代のサウンドで再構築したかのようなロック。シンプル・ロックである。このラフでジョイフルな未整理さが堪らなく格好良いのだ。
#1〜2と続いた流暢なポップロックナンバーからいきなりな展開に驚くリスナーも多いのではないだろうか。
#5『Mad About You』も#3と同じく、大胆にスライドギターを全面に押し出したロックナンバーであるが、ブルースロック的な黒っぽさとうねっとした捻りが振り回されるナンバーである。#3もダサいナンバーだが、パーティ・コーラスを取り入れたこのトラックも負けず劣らずにダサさが満点となっている。ロッキン・ブルースというべきかもしれない。が、#3のポップ・フィーリングに比肩するようにキャッチーであるため、ブルース特有の暗さと粘っこさが鼻につかないナンバーとして完成している。
#6『Million Miles Away』という、とてもよく見られるタイトルを冠されたナンバーは、アクースティックで間の抜けたスライドの音色がトラッド/カントリーの埃っぽさを思いっきり演出したブルージーなトラッド・ソングである。スライドのダートなカントリー式サウンドよりも、曲の持つメロディのポップさが非常に良好なルーツポップナンバーとしてこの曲を見せてくれている。このアクースティック・スライドギターの使い方は、Jon Bon Joviが作成した「Blaze Of Glory」(1990年)で展開したルーツサウンドの音創りに似たものを感じる。片やバリバリのハードロックシンガーなJonとTomでは音楽の懐の広さでは比較すべくもないだろうけど。
#8『Paradise』、#10『Trashman』、#11『Rain』の3曲は完全にブルース・ロック、ブルース・ソングである。どのナンバーも複数のギターをハードにチューンして重ねている。#11は完全にスロー・ブギー的なナンバーでかなり重苦しい雰囲気がのしかかっている。
ダークなハードロックのソリッドさがヘヴィにリズムを刻むのが#8である。が、完全にアンキャッチーな暗いハードナンバーではなく、それなりにポップさがあるため聴き難いことはない。Southern Hard Rockの一形態であるとは思う。Lynyrd Skynyrd風な要素をも感じる。
#10になると、更にハードロック一直線で、Southern Hard Rockそのまんまである。が、エッジが立ったナンバーだけれども、ロックチューンとしてはなかなかにメジャーなメロディでコマーシャルさがかなり増量されている。ために、かなりノリ良く聴けるストレートなロックナンバーとなっていて、やや力不足な後半を牽引する曲ともなっている。
以上、12曲。1995年という正統派ロックシンガーにとっては決して追い風ではない時代に、しかも35歳という年齢でソロデヴューを飾ったTom Hambridgeのデヴューアルバムについて解説してみた。
本名をThomas Jay Hambridgeといい1960年にニューヨーク州で生まれている。家族の仕事の都合で、ニューイングランド州やカナダにも住んだ経験があるけれども、殆どをバッファーローとNYCで過ごしている。
物心つく前からフライパンやポットを叩いて遊んでいた4人兄弟の末っ子Thomasに、両親は5歳の時におもちゃのドラムキットをプレゼントした。それ以来、Tomはドラムを自分の楽器として育っていく。
多才なシンガーの類に漏れず、Hambridgeはギターとピアノもレコーディングでは担当することもあるけれども、基本はあくまでもドラマーである。
彼の姉が持っていたRolling StonesとBeatlesのレコードを片っ端から聴きまくり、Ringo Starrのドラムを模倣して叩き方を覚えていったそうで、Tomの最も影響を受けたミュージシャンと音楽はBeatlesだということ。
Tomはアメリカンフットボールも大好きで、大学に進学する時点で音楽の道を目指すか、スポーツを目当てに進学するかで結構悩んだが、結局ドラムを叩くことを選択し、ボストンにあるバークリー音楽学院に進み、無事卒業。一時期定職に就くことも考えたそうだが、結局Roy Buchananのバンドのドラマーとして雇われ、プロの音楽家に進むことになる。
1980年代から1990年代半ばまでの大半を、Tomはたくさんのミュージシャンのセッションやライヴでのサポートミュージシャンとして活動することになる。
Chuck BerryやBo Diddleyといった黒人ロックシンガーの長老格を始めとして、Patty Larkin、Jonathan Brooke、Catie Curtis、Tracy Nelson、The Drifters、The
Coasters、Orleans、 Sherman Robertson、Sha-Na-Na、Brook Benton、Del Shannonといった大物やヴェテランアーティストのツアーバンドのドラム叩きとしてスティックを振るい、バスドラムを踏んできた。
また、Pete DrogeやTodd Thibaudのようなインディのルーツ系ミュージシャンのステージにもサポートメンバーとしてギグを行っている。
Tom Hambridgeは自らも曲を書き、バンドを率いてボストン・エリアを中心にしてローカルな人気を得ることができていたが、何処のレーベルも契約に足を運んでも首を縦に振ってくれなかった。
結局、1996年にTomはこの「Still Running」を自主制作する。後年になって、自らのレーベルからエンハンストCD仕様となって再発もされることになるが、当時はどのレーベルも配給すら合意してくれない状況だった。
Tomは& The Wreckageを結成し、ボストン近辺でインディ活動を続けるしかなかった。
「僕は何度もメジャーのレーベルへ契約の交渉へ行った。だけど、結局一度もサインを貰えなかった。タイミングが悪いと思いたかったけど、毎回毎回じゃあね・・・・。何年もだし。僕は契約をメジャーが渋った理由の一つは僕のバンドが自主セールスでそれなりの成果を挙げ、人気を得ていたことだと思う。僕の前座でステージを共にしたバンドはかなりメジャーに上がったけど、一年後はまたインディ落ちしていたけどね。メジャーは新しい若いバンドを売り出すのがすきなんじゃないかな。」
結局、東海岸では目立った成功もレコードの契約も結べず、1998年にTomは家族と一緒にナッシュヴィルに移住する。ここで転機が訪れる。
女性ブルースシンガーであるSusan Tedeschiのデヴューアルバム「Just Won’t Burn」をHambridgeはドラマーとして、ソングライターとして、そしてプロデューサーとして製作に全面的に関わるのだが、このアルバムがメジャーでもヒットを記録し、グラミー賞を獲得するのだ。しかも、2曲のヒットシングル『Rock Me Right』、『It Hurt So Bad』はHambridgeのペンに拠るものだったのだ。
他人の作品で漸く注目を集めたTomがArtemis Recordsと契約を交わすことに成功したのは前述した。
そして、2000年には2枚目の「Balderdash」を同レーベルからリリースする。このアルバムは結構評論家筋では好反応を得ているのだが、売れ行きは全くだったようだ、残念ながら。
纏まりとしては「Balderdash」がやや上かもしれないが、多彩さとソフトなロックの味わいを求めるなら断然こちらの「Still Running」がお薦めである。
冒頭に挙げたカントリーやルーツの色合いがあまり露骨でないシンガーが好みなら、Tom Hambridgeは絶対にツボに嵌まるアーティストだと思う。全く無名の遅くデヴューしたドラマーなシンガー。
かなり通好みなプロフィールだが、演奏する音楽は実に一般的なロックンロールである。こういう人がもう少し紹介されて知れ渡れば、もっと日本のマーケットも面白くなると思うのだが。 (2002.7.11.)
 Discovery / Electric Light Orchestra (1979)
Discovery / Electric Light Orchestra (1979)
Adult-Contemporary ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Progressive ★☆
You Can Listen From Here
元来ボックス・セットというものを殆ど買うことのない筆者が、Electric Light Orchestraの「Afterglow」(1990年発売。3枚組47曲入り。当時、Jeff Lynneキャリア初のソロ作「Armchair Theater」の発売、そしてPart Twoのバンドの結成が報告されるというバンド関連の動きが活発になっていたことに触発してリリースされたようだ。)は何故かしっかりと持っていたりする。
それだけ、Electric Light Orchestra(以下ELO)というバンドに対する思い入れが当時はあったことは間違いない。既にバンドとしては活動の終焉を迎えて時が経っていたし、同年にはJeff Lynne抜きでElectric Light Orchestra Part 2のデヴューアルバムも出される等、本来のELOの時代は幕を閉じていたのだが。
ELO Part 2に関しては、Jeff LynneはELOの名前の使用を不当として、名前の変更を求める訴訟を起こしていたが、結局はELO Part 2の名前でアルバムは2枚リリースされることになる。オリジナルメンバーのBev Bevanが在籍していることがプラスに働いたのだろう。
当然、学生時代に一気にCDで再発されたELOを買い漁りリヴァイヴァル的にハマリまくっていた1980年代後半だけでなく、現在に至っても「A New World Record」(1976年。邦題何故か「オーロラの救世主」)から「Balance Of Power」(1986年)までの5枚のアルバムは、個人的にはどれも素晴らしいポップロックの名作となっている。1983年の「Secret Message」だけはどうしても好きになれないヒネリ過ぎの駄作のため、ELO私的名盤からは除外しているが。
Roy WoodとJeff LynneのツートップでスタートしたELOの当初のサウンドは、かなり実験的なプログレッシヴで前衛的なサウンドだったが、1974年にアメリカでの成功の礎を築いたコンセプトアルバム「Eldorado」から次第にプログレ・ロック的な側面を残しつつも、真性のトップ40ヒットナンバーを中心にアルバムを編み込むストリングス・ポップサウンドへと変革していく。
芸術性とかアート性を無駄に標榜することよりも、ポップでコンパクトなラジオ・プレイ向きのポップソングを作っていく方向へと移っていくのだ。
アルバムを重ねる度に、ポップミュージックとしての磨きに拍車がかかっているのも年代順にアルバムを聴いて行くとはっきりと分かるだろう。
そのELO−Electric Light Orchestraのうち、Orchestraという単語が意味するストリングスを主眼にした時代のサウンドの頂点が1979年に発売された「Discovery」であると思うのだ。
無論、この意見には諸説があると思う。純粋にストリングス・アルバムと定義つけるなら、この「Discovery」は生ストリングス楽器を全く使用せずにキーボードテクノロジーとシンセサイザーのみでシンフォニックを表現したナンバーも存在し、ELO最大のヒットとなった#9『Don’t Bring Me Down』に至ってはエレクトロニックか本物の楽器かに関わらず、初のノン・ストリングスサウンドで編曲されている。これ以降のELOの音楽性を示唆しているようなナンバーでもある。
つまりストリングスELOと「Time」からのエレクトロニックなシンセサイザーを中心としたサウンドの橋渡し的な位置にある1枚ともいえるのだ。
「Discovery」というアルバム・タイトルは色々な新しいことを発見したいというJeff Lynneの欲求を代表する形で付けられているが、
『ストリングス以外の音の可能性を“発見したかった”。』
という意味合いも込められている。このことから、「世界最小のオーケストラバンド」と呼ばれたこれまでのELOから変革を求めていたというLynneの意向も伝わってくる。
メンバーにしても、前作ではしっかりとバンドの結成当時からのアイデンティティでもあるストリングスを担当していたオーケストラ部隊のMik Kaminski、Hugh McDowell、Melvyn Galeという弦楽器の面々は全て解雇されてしまっている。(レコーディングには一部参加して弦を弾いているらしいのだが。)
Jeff Lynneが完全を求めるあまり、ツアーに出ることよりもスタジオに籠もってサウンドを重ねることを中心に置くようになり、レコーディングとツアーでしかギャラが稼げなかったオーケストラ隊はELOに居場所が無くなってしまったのが、そもそもの原因である。ベーシックトラックだけをさっさと録音して、後はダビングとミックスを長期間行うというスタイルは特にストリングス・セッションには金銭的負担が大きかったのだ。
これはSteely DanのDonald FagenとWalter Beckerが完璧な演奏を求めてスタジオに入り浸りになり、セッション・ミュージシャンを起用しだしたためJeff Baxtor等が生活苦に陥り、The Doobie Brothersに移籍した経緯と似ている。
兎も角、以上の点を踏まえると、ストリングス・ポップとしてのストリング=オーケストラという面からは「Discovery」よりもストリングスにより重点を置いた「A New World Record」の方がELOらしいという見方も出来るし、何より2枚組みの大作で、「Discovery」へと移行するプレ・ステップでもあるかのように、これでもかというくらいにストリングスを暴れさせた「Out Of The Blue」(1977年)もポップなプログレ・ストリングスの作品としてはELOの集大成と云えないこともない。
ストリングス・オーケストレーション有終の美を飾ったアルバムが「Out Of The Blue」という解釈には同意できる余地はかなりあると思っている。
しかし、ELOの最大の魅力は結成初期は兎も角として、ラジオ・フレンドリーな超の付くポップソングの供給者という点にあると筆者は考えている。無論、弦楽器とポップロックサウンドの融合はそのギターとは違う類のエッジが大変にグルーヴィなのだが、如何に弦楽器が頑張ろうがメロディがタコスケであったならそれは単なる難解なプログレッシヴを鼻に掛ける音でしかないのだから。
そのポップという面では、間違いなくこの「Discovery」はELO最高峰である。1981年以降の「Time」、「Balance Of Power」というこれまた激烈コマーシャルなシンセサイザーサウンド主体のELO作品と比べても、全体としては「Discovery」のポップさに軍配が上がるだろう。
「Face The Music」以来、研鑚され、熟成されてきたポップセンスの集大成。1970年代のELOサウンドを最高の形で大衆向けポップソング化したアルバムが本作である。
ストリングスも目立ったソロプレイは全く消滅している。「Out Of The Blue」でのポップ・ミュージックとの兼ね合いを取りつつもうねり回っていた弦楽器の音色にはダイナミズムが感じられたが、「Discovery」ではあくまで他のエレクトリック楽器に梃子を要れ、メロディの切れを向上させるために使用されている感じが強い。
このことも、ポップスとして楽曲をアレンジする際には、本来の“顔”であったストリングス・オーケストレーションを退行させることも親しみ易いポップナンバーを創作するためには厭わない、的な意図の表明のように思えるのだ。
確かに、サイケディリックさも兼ね備えたダイナミックなストリングス・セクションが聴けないことには一抹の寂しさも感じないことは無い。が、耳触りとしては「Discovery」のように要所を締める形でストリングスが曲を彩ってくれていた方が、格段に受け入れ易いことは間違いないだろう。
ストリングスの減少というか、後退と対照的に増量されているのが、シンセサイザーを始めとするキーボード・サンプリングだろう。初期の貧弱なサンプリング音しか出せなかったシンセサイザーも、1970年代後半にはかなりの発展を見せ、かなりのシンフォニックでオーケストレーション・アレンジのサウンドを創り出すことが出来るようになってきた時代でもある。無論21世紀の技術とは比較するだけナンセンスではあるが。
兎も角、こういった鍵盤で出せる音が拡大したことも、弦楽器担当を全て解雇『可能』にせしめた理由の一つだろう。
これまでのアルバムでも積極的にアクースティックピアノ以外のシンセサイザーやキーボードを取り入れてきているが、SEやヴォイス・サンプル共々、かなりカラフルなシンセサイザーがこれまでに増して加わっている。
ひとつ間違うと、C級のエレポップやテクノポップというトラッシュ・ミュージックに下落してしまう危険性をこういったエレクトロ・キーボードを多用したアルバムは孕んでいるものだが、ELOに関しては全くそういった懸念を抱いたことも無い。
シンセサウンドどころか、エフェクトと変調とアレンジをてんこ盛りにしたヴォーカルとコーラスまでぎっしりなのは相変わらずなのだが、これが全く嫌味のないポップメロディと違和感無く収まっているのだ。コテコテな手を加えまくった人工庭園のようなサウンドプロダクションを行っているのに、しつこさやクドさが浮き出てこないのである。
ひとえに、Jeff Lynneのソングライター、アレンジャー、コンポーザー、そしてプロデューサーの才能の賜物だろう。
このサウンドに人工的な装飾を使うというのは非常に匙加減が微妙で、やり過ぎると単なる中途半端なAORとPower Popの間にあるどっちつかずの凡作、聴いていて疲労を感じるだけのHR産業ロック、といった取るに足らない音楽の澱に沈んでしまう危険性が大きいのだ。
ELOはそのような没個性的で印象の薄いロックンロールにはならずに、ポップ、プログレッシヴな色合いを有した完全無欠のポップロックバンドとして独自の世界を構築しているところに、長くリスナーから愛され、どのアルバムからも複数のトップ40ヒットを量産するという黄金時代を築けた要因があると思う。
同時代のポップ・オリエンティッドなバンドには、10cc、Supertramp、Utopia、そしてやや初期の作品はプログレッシヴなカラーの強いところもELOに類似したThe Alan Persons Project等が挙げられるけれど、大半のバンドが大英帝国出身のグループであり、何処かしらブリティッシュなポップ感覚を引きずっている。
翻って、米国のバンドであっても、やはり英国的なBeatles的なポップソングの影響を多大に受けていることが明白な音作りをしていることが多い。
その点、ELOはBeatlesからの継承された雰囲気は感じるものの、完全に自らのアメリカン・ポップスとして独特の色塗りを練り上げてしまっているところに、特筆すべき箇所があると思う。
それはストリングスだけでも、ファルセットで甲高いコーラスだけでもなく、エレクトリック・サウンドを大胆に取り入れただけでもない。
全ての音が重なって、“これぞELO”と聴いた瞬間に判別できる世界を構築しているのだ。
聴く人によって、「これこそElectric Light Orchestra」だ、と知覚する要素には差異があるだろう。蓋し、そんなものはないと思う人がいても不思議ではないけれども。
筆者にとって、これぞELOと思うのは、
西独逸(当時)のスタジオで作られたあのバタバタドラムの音と、曲によって全然違う処理をされている、エフェクターを通されまくった、誰が歌っても桶(ヲイ)に思えたりするヴォーカルである。
・・・・・なんかあんまり誉めてない気もする・・・・・・・。
しかし、Jeff Lynneのヴォーカルは機械処理されまくっているのに、一聴しただけで、ELOのJeffと解る。これはある意味凄いことだと思う。ファルセットで曲によっては全く地声を出していないし、そもそもJeffの地声がどのようなものか未だに良く掴めてない気もするけれど。
でも、Jeff Lynneのヴォーカルということは即座に判別できる。これはやはり大したものだ。
さて、この「Discovery」の時点でメンバーは4名にまで減っている。ここ数作は共同プロデュースでアルバムを作成していたが、今作はJeff Lynneの単独プロデュースである。
他はファンにはお馴染みのBev Bevan、Richard Tandy、Kelly Groucuttの3名のELOロックパート。
ストリングスアレンジメントと指揮には何時ものLouis Clarkが手を貸し、TandyとLynneもストリングスとコーラスアレンジを担当しているという黄金パターンである。
Jeffはギターと鍵盤類を殆ど担当し、マルチプレイヤー振りを遺憾なく発揮している。このアルバムからJeffのワンマン化は更に促進したと考えてよいだろう。
前述したように、全9曲はどのナンバーもこれ以上ないくらいにキャッチーで一般受けするポップソングである。
今更であるが、米国でトップ40入りした4曲、そしてオマケに英国ではもう1曲がトップ10ヒットとなっているが、シングル曲以外もどれも秀逸である。
2枚組み大作である「Out Of The Blue」の後にリリースされた、セールスポイントでもあった弦楽器をそれ程押し立ててないポップアルバムだから、細かく纏まり過ぎてしまう印象を与えかねないが、どうして完璧な存在感を後光のように放っているアルバムだ。やはり捨て曲が皆無という点は大きいだろう。
その中でも、これぞELOという曲はやはりヒットシングルの2曲。トップ10入りした#1『Shine A Little Love』と#9『Don’t Bring Me Down』だ。
このオープニングとエンディング・トラックは「Discovery」のELO史における位置を雄弁に物語っているトラックであるとも思う。
バタバタドラムと、些か1970年代後半でさえクラシカルな低音を利かせたマシンガン・ピアノにリードされる、ロックンロールな#9。一切ストリングス系の音は使わずに、それでいて、ELOとしての音を最大限に表現しきっている。ファルセットでハイトーンなハーモニー。隠し味的に振り撒かれているシンセサイザーの音色。
弦楽器の音色がなくてもELOだ、というイメージを植え付け、更に大ヒットとなってしまったことから、ストリングスELO至上なファンからはバンドを脱線させた鬼子シングルとして色々と糾弾されることも多い曲だが、筆者はやはりこのナンバーが最高に好きなELOソングの1つである。
また、冒頭の宇宙船や宇宙空間を表わす未来的な(?)SEや、数々のシンセ・サンプリングといった新要素はあるものの、ストリングスと一貫してハーモニーで唄われるヴォーカル・パート、そしてバタバタなドラミングというこれまでのELOの美味しいところを合わせたフュージョンソングの極致である#1。#9とは違う意味で、これまたこれぞELOポップロックの代表作だ。また、当時興隆して全盛期を迎えたディスコ・サウンドへの挑戦もそのダンサブルな弾みに見れる。
ディスコ・ナンバーといえば、やはり一番それらしいのはヒット曲の#5『Last Train To London』(邦題:ロンドン行き最終列車)だろう。現在のディスコサウンドとは比べるべくもないが、Bee Geesのヒットソングに通じる独特のグルーヴ感を持ったムーディ・ナンバーである。
同じく、ディスコティックな匂いのする曲は、エレクトリックな冒険を盛り込んだ#2『Confusion』も該当するように思える。サンプリング・ヴォイスとエレクトリック鍵盤を重ねて仕上げたアーティフィシャル・ナンバーの局限なのに、冷たい感じもしなければ、濃過ぎる嫌味もない。ストリングス・シンセサイザーっぽい弦の音も的確なアクセントとなっている。ヒットしたのも頷ける。
英国のみのヒットとなった、#4『The Diary Of Horace Wimp』は某国のテュリャ・テュリャな(笑)民謡を思い出させるような内容。New Waveの雛型ポップナンバーと名付けたい。ストリングスのバッキングがこのアルバムでは一番痛快にフォローされていて、細切れなリズムと相まって独特のプログレ・ポップとなっている。このナンバーも相当な好みである。
後のエレポップと呼ばれるようなタイプのルーツとでも言うべき#7『On The Run』は、華麗なシンセプログラミングと明るいハーモニー・リードヴォーカルがとても絶妙にシャッフルされていて、「Time」あたりに収録されていても違和感のないナンバーだろう。ストリングスは本当に隠し味的にしか取り込まれていないが、やはり曲の深みを増すのに良い手助けとなっている。
こういったポップロックのチューンに挟まるように、しっとりとしたバラードが点在しているが、どれも甘く、メロウで、夜の優しい側面を際立たせてくれるようなアダルトなナンバーばかりである。
#3『Need Her Love』、#6『Midnight Blue』はシングルになっても絶対にヒットしただろう、クオリティの高いストリングスとエレクトリックサウンドが同居したナンバーだ。ムーグシンセが浮遊感を出す#8『Wishing』も勿論ヒット性は確実に内包するバラードだ。
まあ、卑俗な言い方ならどれをカットしてもシングルになるアルバムなのだ。仮定の話だが、この当時のトップ40量産体制であったなら、全曲カットしても全てヒットチャートに名を連ねたに違いない。
何処ぞの砂漠にある泉の名前の英国バンドのように、無理矢理全てをシングルにするという姑息な手段を取らなくても、自然に全曲カットが出来ただろう。
2001年には米国でELOのアルバムが殆どリマスターされ、シングルのB面や未発表デモを数曲付け加えて再発売された。こちらは聴いていないが、どのくらいのサウンドにリマスタリングされているのだろうか。
その再発以上に、2001年には15年ぶりのELO作となる「Zoom」がリリースされた。悪くないアルバムだが、内実はJeff Lynneのソロ・ロックアルバムであり、筆者はこれをELOと認定するのには今でも抵抗がある。
やはり、Jeff Lynneのソロの体臭が強烈であり、ELOとしての輝くメロディが欠けているように思えてならなかったのだ。これはJeffがアーティストのピークを過ぎたせいではなく、他のメンバーが参加しなかったJeff Lynneのソロ作をELO名義で出したための蹉跌に違いないと思いたい。
「Zoom」に肩透かし的な失望を感じたのは、「Discovery」のようなアルバムをもう一度、と期待し過ぎたためでもあることは自覚している。
全く、名盤というのは過大な期待を促すという作用において罪な存在であることだ。この「Discovery」はそのような罪作りのアルバムだ。
アメリカン・ポップスの良心に触れたければ、取り敢えず棺桶に入る前には聴いておくように。 (2002.7.16.)
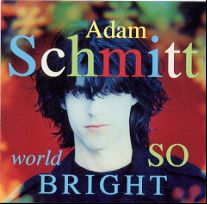 World So Bright / Adam Schmitt (1991)
World So Bright / Adam Schmitt (1991)
Adult-Contemporary ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★☆
Arena&Adult-Alternative ★☆
8年の沈黙を破り、2001年に3枚目に当たるデモトラック集「Demolition」を1993年の2nd「Illiterature」以来に発表した際のインタヴューで、Adam Schmittはこの1stアルバムのジャケットについて語っています。
「Warnerはどうやって僕をプロモーションするか良く分かっていなかったんだろう。(中略)
1stアルバムに関してはたくさんのすれ違いや食い違いがあったよ。例えば、ジャケットの写真だ。僕は「World So Bright」の絵柄はもっとティーンエイジ向けに焦点を当てたピンナップにしようと考えていた。その頃、僕はJellyfishの最初のアルバム「Bellybutton」を手にする機会を得た。
それを聴いた時、まさに僕がやりたかったのはこの「Bellybutton」だったんだ、って思った。実際の「World So Bright」の写真の感じやデザインは、僕のイメージをあやふやなものにしていた。そしてアルバムを完成させるのに、万能マルチミュージシャンという売り文句は全く意味をなしていなかった。実際に僕がひとりで作成したアルバムではないからね。というのは「World So Bright」では僕が全ての楽器を演奏していなかったんだしね。
ここにとても皮肉的なことがある。「Demolition」では「World So Bright」よりも遥かに大部分の楽器を僕が演奏しているというね。」
以上のように、メジャーレーベルであるWarner/Reprise Recordsでの不自由をAdamは語ってくれています。
しかし、
はっきり言って、それ以前にこのジャケットを採用したことで「海月」(クラゲ=Jellyfish。ああ親切な注釈)を比較に云々論じれる段階を下回っています。つーか終っとるやん(笑)
まあ、レーベルの意向が強かったのかもしれませんが、それはそれとして!
このどっから見てもオ●マにしか見えない(ヲ)ジャケットから良質なロックアルバムを想像できるリスナーは余程野性のカンが鋭いのか、倒錯した趣味の持ち主でしょう。(をいおい)
と書き殴りつつ、当時しっかり買ってたりしてるのがこの文の書き手ですけど。(自爆)
ファンの間で良く論じられることですが、あまりにも安っぽいジャケットや地味なアートワークでリスナーの興味を惹くことにビハインドがあったり、趣味の悪過ぎるデザインや絵柄で購入を敬遠されているアーティストの良作や傑作を惜しいなあ、と残念がること。
こういった議論自体が、内容の良さに比較して売れなかったアルバムを弁護するための免罪符的な役割を担っているところが大だと思います。
しかし、この「World So Bright」はそのサイケとも言える色彩から地味とは表現し難いですし、趣味が悪いという項目には当て嵌まりますが、ヲ下劣とか下品とかシモネタ関連の嫌悪は感じません。
とはいえ、素直にこのアルバムを手に取ることを躊躇する人はかなりの数ではないでしょうか。筆者も1991年当時にMTVでファーストシングルの#3『Can’t Get You On My Mind』を偶然に見なかったら、このアルバムを“文化倶楽部”モドキ(を)な腐れUKポップかビート系のダンスアルバムと勘違いしたままだった可能性は非常に高いです。
兎に角、Andrew W.K.の鼻血ジャケットのように趣味がズンドコに悪いという訳でもないのですが、ヲ耽美やナルシーが入っているようなイメージが感じられ、結構引く人が多いと勝手に想像しています。
アルバムのレヴェルは非常に高く、世間の注目を殆ど浴びなかったのは不遇としかいいようがありませんが、
仮に、仮定の話で、
この作品が馬鹿売れし、レコ屋の壁という壁や街頭にこのジャケットがベタベタと貼られている事を想像したら・・・・
かなり嫌です。つーか嫌過ぎ。
ということで、めでたくも(ヲイ)このAdam Schmittという1968年生まれのイリノイ州はシカゴ郊外シャンペーン出身のアーティストが幸運にもメジャー契約で処女作のリリースとなったアルバムは、商業的にはあまり華々しい成果を残すことができませんでした。
しかし、当時勃興を始めていたオルタナティヴやヘヴィロックに安易に染まらず、どちらかというと1980年代のPop/Rockのシンガーの作風を継承した王道なシティ感覚溢れる方向性はメディアやプレスに高い評価を得ます。
簡単にPower PopとかCollege Rockという単気筒な割り方をするにはあまりにも勿体無い掴みのバッチリある音楽性は、同年の1991年に「Girlfriend」を発表して地道にながら確実にファン層を拡大していたMatthew Sweetの新しいライヴァルとも目されていたのですが、日本では残念ながらこの1995年の「100% Fun」以降加速度的に才能が枯渇しているジャパニメーション・ヲタクのMatthew程には注目されませんでしたし、現在も全く同じです。
産業ロック程にはしつこ過ぎず、濃過ぎず。また極端にハードなポップサウンドに走らないところはCheap Trickのハード・ポップな音楽性にも擬えられたこともありますが、ポップセンスでは少なくともこの「World So Bright」においてはCheap Trickの遥かに上を飛行しています。
Power Popの草分けと言われるMarshall CrenshawやMatthew Sweet等と比較すると、遥かに骨太で聴き飽きしない奥行のあるサウンド創りをしている人です。
しかし、#1『Dead End』=行き止まり、ドンツキ、出口なし、行き止まり、とあたかもオープニングトラックのタイトルが暗示するように、このキャリア最高−といっても未だフルアルバムは3枚なのですが−作を発表した段階でAdam Schmittの行く先は全く希望の見えないものになっていたのです。というよりも、アルバムを1991年という時代にリリースした瞬間から『Dead End』への道を歩むしかなかったのでしょう。
この#1のようにウエル・クラフテッドという表現が似合う、適度に装飾した厚目なギターリフをキャッチーに配置したポップロックソングはメジャーシーンでは全くドル箱にならない時代が到来したからです。
1991年、シアトルを拠点に勃発したオルタナヘヴィネス/グランジ音楽の大波は瞬く間にシーンを席巻し、アンチ・メロディを標榜するかのような鬱や怒りという表現をラウドに、ノイジーにメロディを無視してただ撒き散らす見苦しいその雑音は1980年代のポップロックサウンドを駆逐してしまいます。
確かにAdamがメジャーレーベルの制約の中で四苦八苦して「World So Bright」を出した時は、まだ時代は彼にとって文字通り#2『World So Bright』だったでしょう。前途洋々としたメジャーでの船出。
そういった希望に満ちた感情を表すように、ストリングス・シンセサイザーを始めとする弦楽器サンプリングを軽いサイケディリック調子なラインに絡ませた#2は、ややマイナー調のバラードながら、明るいAdamの将来への展望を表すかのようなナンバーとなっています。
けれども、時代の端境期にデヴューしてしまい、レーベルのプロモーションも満足に受けれなかったAdamはこの殆どがシングルカットできそうなアルバムから僅か#3『Can’t Get You On My Mind』をシングルにしただけでした。このJay Bennetもギターで参加したナンバーは最高のアメリカ都市型ポップロックという称号が相応しい完璧な曲となっています。アリーナ的なコッテリ感を有しつつ、それだけでない切れ味の鋭さがドリーミーなシンセサイザーを多用したアレンジの中にあります。絶対に心に残ってしかるべき傑作なのですが、大多数のリスナーの記憶にも残れないハズレシングルとなり、図らずも『Can’t Get You On My Mind』な不遇なトラックとなってしまったのでした。
この「World So Bright」は評価は高かったものの、商業的な成功を殆ど収めることができませんでした。しかし、Warnerは2枚目のアルバムの作成をAdamと続行のサインをします。
それだけ、この1stアルバムが評価されていた証拠でしょう。
しかし、2年後の
2枚目「Illiterature」は必要以上にダークでヘヴィな、オルタナ的売れ筋に媚びた駄作になってしまひました。(怒)
そのメジャリティへの擦り寄りという、Adamらしくない方向性を取ったのはレーベルの意見かもしれませんし、彼
なりの1stで売れなかった反動かもしれません。が、彼は#4『Black River』という黒い流れに足を踏み入れ、苦い水を飲んでしまいました。
#4はその2枚目のダークでヘヴィな鬱屈に満ちたヘヴィロック作風を予感させるようなハードロック的な曲ですが、2ndに収録されている各曲ほどにはやり過ぎていないです。ちゃんとハード・ポップなツボを抑えた曲となっています。
その結果、1stを賞賛したメディアの殆どが「Illiterature」を酷評しました。
「Nirvanaを安易に模倣した駄作。」 「ヘヴィでノイジーさを取り入れ、生来の良さを台無しにした。」 「Adam Schmittもヒット曲が欲しかったのか。」
等々。
全然同意します。↑折角のAdamのポップセンスを自爆させてますね。
当然の結果として、1st以上にセールスは失敗。彼はRepriseとの契約を#5『Lost』=失います。3枚目の作製をWarnerが拒絶してしまったのです。
この#5のようにピアノを配置した賛美歌のようなコーラスを配した美麗なバラードが歌えるシンガーなのに暗いオルタナ・ヘヴィ風のアルバムを作った報いでしょう。
自分で自分の首を締めてしまったというか将来性を閉ざしてしまったのは、幾らメジャーレーベルとの擦り合わせが上手くいかなかったからとはいえ、Adamにも責任はあるでしょう。#7『My Killer』、自分の前途を滅殺してしまったのは、#7のタイトルのようにAdam Schmittだったのです。
#7のようにエッジの効いたドライヴィング・ポップを創れるアーティストなのに、実に勿体無いことです。特に、#7のようなギターが産業ロックのように咆哮するポップナンバーは#3とならんで、Adamの必殺技なんですが。それが殆ど2作目には活かされていません。
これ以降、Adamは自宅のスタジオを1作目でもレコーディングの場所として使用していましたが、更に手を加えて完全に録音の全ての作業が出来るように改良し、数年間曲を書き溜める傍ら、Titanic Love AffairやTommy Keene、Robynn Ragland、Suede Chain、Honcho Overload、Angie Heaton、Great Crusades、Boot Campといったインディ・ポップやロックのミュージシャンのアルバムにエンジニ、ミキサー、プロデューサー、キーボードやベース、ギター、ヴォーカルでも参加。というようにマルチプレイヤーとしての才能を裏方で費やすことになります。
この8年の間は、メジャーのソロ活動はAdamの記憶には#8『Remembered Sun』というように、懐かしい輝かしい時代としては映らなかったのかもしれません。反対に全くのセールスの失敗だけに終るという屈辱の『Never Remembered Sun』という斜陽の時代だったのでしょうか。
#8のようにややアクースティックなサクサクとした手触りとナード感のある半A級とB級の境のようなポップロックも良いアルバムトラックなのですが。
Adam Schmittはシャンペーンのインディ・レーベルであるParasol Recordsにメジャー落ち後に早々と移籍していますが、自分のアルバムが数枚作製出来るマテリアルをストックしながら、全くアルバムを出すという意欲が掛けていたようですから、あながち間違いでもない推測かもしれません。
心境的には#9『Everything Turned Blue』−全てが憂鬱になってしまっていたのかもしれませんし、実際にデモ集の「Demolition」の発売に際してもAdamは「自信がない」と再三インタヴューでも零していますし。
しかし、曲のタイトルとは正反対に底抜けにアップテンポで明るい、#9はその爽やかなギターワークやコーラスも相乗効果をもたらし、非常にシングル向きなナンバーとなっています。#3がヒットすれば、次はこの#9がシングルとして切られたのではないかというIFの想像を、ついついしてしまいます。
長い間、古い映画のリヴァイヴァルを見るように、黄昏た夕焼けでオレンジに染まった街角−#11『Scarlet Street』という閉鎖空間に彼は填まり込んでいたのかも知れません。
ただ、好きなレコーディングだけをして、デモを量産するに留まるという。
元来、積極的にライヴを行うよりも、スタジオに篭もってコツコツとマスタリングやオーヴァーダブを捏ね繰り回すのが好きなタイプのインドア派アーティストですから。
このジャケットからも如何にも不健康そうなインドア人間という匂いがプンプンしますし。(オイ)
しかし、#11にしても埋もれさせるには勿体無い、Matthew SweetやVelvet Crushも真っ青な激烈ポップなアップビート・チューンですし。
曲調で8年の空白を占うなら、#6『Garden Of Love』のややクールなインダストリアル・ポップナンバーがその不安で長い沈黙をした心情にマッチしているように感じます。が、意味合いとしては「順調な恋愛」と解釈するのが英文法的には妥当です。#9とはメロディと意味合いが正反対ですね。(タイトルにおいてですが。)
そうなると、プロデューサーやエンジニアとして音楽業外に関わる方が、Adamとしては蜜月な時代であったのかもしれませんが・・・・。
兎に角、Adam Schmittは2001年にシーンへの復帰を果たしています。スタジオでシコシコする時期は終わりを告げたようです。#12『At Season’s End』−雌伏の時は21世紀に終焉したと思いたいです。
これからもParasolからライヴ音源をリリースするという計画もあるとかですので、レーベルリーダーとして多くのご近所ミュージシャンを牽引していって欲しいですね。
最後に、このアルバムでは一番のバラード#10『Elizabeth Einstein』だけが、無理矢理こじ付け・曲解のレヴューのラインナップに入らなかったことだけが残念です。(笑)
しかし、Adamの素直なヴォーカルが甘く、甘く、スゥイートなメロディをストリングスとユニゾンして歌い上げるこのバラード。こういった曲を又聴かせて欲しいものです。
だって、人名はどうヒネッても、言葉遊びに組み込むことができなかったので。(苦笑) (2002.8.4.)

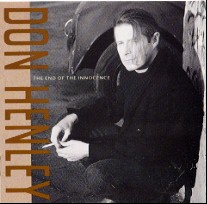 The End Of The Innocence / Don Henley (1989)
The End Of The Innocence / Don Henley (1989)