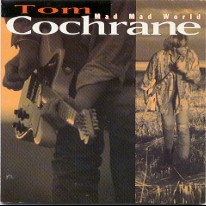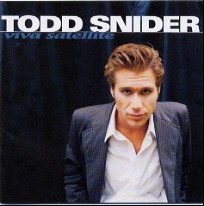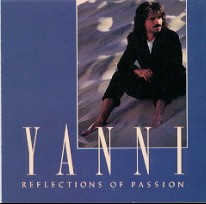Chris Alcaraz / Chris Alcaraz (1999)
Chris Alcaraz / Chris Alcaraz (1999)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Southern ★☆
You Can Listen From Here
Chris Alcarazがこのデヴューアルバムを録音したのは、実は生まれ故郷のアメリカ合衆国ではない。
英国ラジオチャートを筆頭に、阿蘭陀、瑞典、独逸といった欧州諸国で、このデヴューアルバムからシングルとなった#1『So Much』を筆頭に、前半の4曲全て、#2『Anne』、#3『Gotta Say Now』、#4『To Your Heart』が相次いでヒットを2000年に記録している。
後述するが、この4曲は全て、タイプは違えども、良質なルーツ・ポップ/ロックであり、このアルバム前半4曲で彼の才能は集約されていると見て良いだろう。適宜な時代を向かえていれば、ヒットを間違いなく本国でも連発したに違いないだろう。実に勿体無いことである。
が、実際は米国では殆ど無名のインディ・アーティストであるのが現状なのだ。この本国である合衆国での知名度を考えれば、欧州でのブレイクは少々想像がし難い歓迎振りであるだろう。
つまり、この「Chris Alcaraz」というセルフタイトルのアルバムは、彼の人気が非常に高い欧州にてレコーディング作業が行われ、米国よりも随分と先行で発売されている。いうまでもないが、現在は米国でも入手は可能になっている。
近年珍しくない、メインストリームの売れ筋から外れてしまった良質なミュージシャンの、合衆国から欧亜州大陸西端部への「移住」組にChris Alcarazもその名を連ねてしまっているのだ。
が、これは、本国で全くアルバムをプレスする機会も無いまま、活動を停止したりするミュージシャンの悲劇と比較すれば、まだ活躍の場が与えられているだけ恵まれているだろう。それに、欧州諸国で国境線を跨いで各国でヒットを記録しているという点でも、かなりの日の当たる場所に立っているアーティストであるとは思う。
この「Chris Alcaraz」は米国で発売されたヴァージョンのようであるが、バックカードには「Printed In U.K.」とあるし、インレイ・ジャケットには「Printed In U.S.A.」とあり、恐らくはバックの文字がオリジナルのコピーから変更し忘れたために、以上の混同が起きているのだろう。
更に、欧州を中心としているが、アメリカでも活動をしているので、完全に出稼ぎから異国に根を下してしまった訳ではないのだ。まだまだ、これからのミュージシャンである。何せ、かなりの若さである。正確な年齢は何処にも記述が無いので正確なことは不明であるが、間違いなく1990年代に入ってから本格的な音楽活動を開始した世代であることはその経歴から察するに、間違いないだろう。写真もかなり若い青年ミュージシャンに見えることだし。(特にインナーでは。)
アメリカのロックという大衆音楽が、オルタナティヴというレッテルの貼られた新式音楽で占領されて久しい。一時期よりも音楽に気を配ったバンドが出てくるようになった、と批評筋やライナー・ノーツで語るレヴュアーは多いけれども、筆者に言わせれば、その殆どは大同小異、十羽一絡げである。是非、集団で種の個体数を調整するために入水自殺するレミングのように、大西洋にも沈んでほしいものである。
所詮は、Alternativeという枠組みから逸脱できない、現在の若者の嗜好に媚びを売った作風だ。
しかしながら、音楽を演奏する供給側にしても、その曲を購入して聴く層のどちらにも、その聴き始めに流れていた流行や趨勢というのは非常に大切であると思う。
この理論が絶対的に全ての人間に当て嵌まるとまでは極論しないが、1990年代以降に音楽活動を始めた若手ミュージシャンには殆どこういったオルタナティヴの影響を感じてしまう。
ラジオが未だに重要なヒット曲の震源地となっている米国では、殊更ラジオから流れてくる歌に影響を受けやすいのだから。
無論、これまでにこのスペースで紹介してきたアーティストやグループの殆どが、その悪しき流行に染まらずに、独自の音楽を表現してきている。であるからして、オルタナティヴの呪縛から逃れることは不可能ではない、という結論は全ての場合には適用できないが、実例とはなっているのだ。
が、Chris Alcarazのように、20代そこそこの若手ミュージシャンであり、しかもソロシンガーの形態で歌うミュージシャンで、ここまでオルタナティヴを排斥し、しかもAlt-CountryやCountry Rockという別の薬味で音楽を調整することでオルタナティヴを薄めてしまうという技巧を必要としないシンガーに出会ったのは久々であった。
Tom PettyやVan Morrison、そしてBryan Adamsといった広範な意味においてルーツ系のロックミュージシャンというよりもPop/Rockを主眼に置いた畑のメジャー・シンガーを引き合いに出して論評に挙がることが多いということから、漠然とChrisの音楽性を想像できるとは、思える。
そう、完全無比にオルタナティヴを感じることの無いピュアでクラッシックで古臭くて、暖かくて、ダサくて、野暮ったくって、アダルトで、そしてルーツなシンガー・ソング・ライター。
Chris Alcarazという人の音楽から感じられる多様な印象を並べると、こうなる。支離滅裂になってしまってはいるのだけれども。
実際に、Chrisには近頃めっきりと姿を消してしまった「大型新人ロック・ヴォーカリスト」の臭い、しかも物凄い成長をしそうな体臭をムンムンと感じてしまうのだ。尤も、大型新人=大々的に売れる、という公式は全く当て嵌めるつもりはないのだが、現在の米国マーケットの趨勢を鑑みるにつけ。
それは兎に角として、Chrisには天賦の才能と、それに奢らずにしっかりと研鑚をしてきた努力が感じられる。
Chrisの音楽性については各曲のインプレッションで詳細を語るつもりでいるが、Chris Alcarazの経歴を述べることで彼の音楽性の説明の補足としていきたい。
Chris Alcarazは米国は南西部の殆どが岩石砂漠の大地、アリゾナ州はフェニックス近郊での生まれである。
Alcaraz少年の音楽史は、彼が4歳の時にそのページが開かれることになる。ドラマーとしてセッションミュージシャンであった彼の父が、4歳からクラッシック・ヴァイオリンを習わせたのだ。
その3年後、7歳になったChrisは、父親がBeatlesの歌をギターで弾いているのを聴き、コードを教えてくれと請う。父親がコードをなぞる見本を見せ、Chrisにギターを与えたところ即座に曲のコードを押さえてしまったそうだ。
それを見た父親は、Chrisにギターを習わせる。同時にジャズ・ベースのレッスンも受けさせる。
この影響もあり、Chrisはクラッシック音楽を練習する手段として続けていたヴァイオリンから、ウッドベースに楽器を持ち替えることになる。
Chrisはベーシストとしてアマチュアバンドに在籍し出し、Better Than Ezraの現ドラマーであるTravis Aaron McNabbが結成していたポップバンドのメンバーとして、初めてギャラが支払われるライヴに出演したのが14歳の時。
Chrisの10代はポップロックのバンドのベーシストとして終始しそうに思いきや、Chrisはロックバンドのメンバーであることよりも、より音楽を本格的に勉強したいという望みを実現するため、アリゾナ州立大学に入学する。
専攻はジャズ音楽であり、奨学金生徒であったというから演奏の技巧はかなり高いレヴェルにあったのだろう、当時から。キャンパスにてChrisは大学のオーケストラの一員として、ウッドベースを担当する。
このオーケストラのメンバーだった間に、ジャズ/フュージョンバンドのThe Rippingtonsのプロデュースを担当したりと、主にブルースやジャズの仕事しているプロデューサーのMike Broeningを始め、プロのセッションミュージシャンと交流を持ったりもしている。
そして、ブルースロッカーの重鎮であるBo DiddleyやJoe Houstonのライヴステージでウッドベースを弾くという機会にも巡り合っている。余程、演奏の技巧が評価されていたのだろう。
ここまでの経歴を振り返ると、Chrisはクラッシック、ジャズ、ブルースというロックンロール以前の根源音楽の正式な教育を受けていることが分かる。1980年代くらいまではメジャーなシンガーは多かれ少なかれ、こういったプロフェッショナルな教育を経験を経てレコードデヴューしていたものだが、最近はストリートや学生バンドからミュージシャンにシフトする例が増えている。
まあ、街角のバンドからメジャーという仮定を否定するわけではない。筆者の大好きなCounting Crowsもメンバーの殆どはストリート音楽出身なのだから。肝要なのは、最終的に良い音楽を届けてくれるかどうかだけなのだから。
しかし、やはり「齧った」だけでなく、正式に大学のジャズ音楽学士過程を無事卒業し、しかもクラッシックもブルースにも精通しているというバックボーンは、持っていて邪魔になることは無いだろう。
また、間違った音楽性に走ることが無いのなら−つまり正統派なポップ/ロックを指向すること−プラスとして働くべき後天的資質であると思う。
この点では、Chrisは先天的な才能だけでなく、これらの身に付けた要素を腐らせることだけはしていない。それだけは断言しておこう。
アリゾナ大学を無事卒業後、Chrisはテキサス州のオースティンに移り住み、セッションミュージシャンとして主にアメリカン・ルーツが濃厚なバンドのステージに参加するようになる。
クラッシック、ジャズと続いた彼の音楽的な探究心は、学生時代にセッションとして参加したブルースを契機にアメリカン・ルーツミュージックに向いたのである。
ここで、1970年代から活動しているブルース/ロックバンドのThe Fabulous Thunderbird’s(Danny Kortchmarも在籍していたことがある。)のメンバーであるMike Buckや、ラテン/テックスメックスバンドであるTexas Tornado’sのドラマーErnie Durawa等に目を掛けられ、ライヴへの参加が増える。
ライヴへ参加しているうちに、ゲスト的にソロで唄うことをしばしば行うようになり、たまたま彼と一緒にバックバンドに参加していたピアニストのWiley Cousinsという人が、Chrisのソロパフォーマンスにいたく感動し、Wileyが発掘した新人バンドであるThe Well Hungariansのプロデュースを共同でやらないかと持ち掛ける。
これを契機に、ChrisはThe Well Hungariansのアルバムをプロデュースし、同時にソロアーティストとしてThe Well Hungariansのツアーにも同行することになる。本格的にソロ活動を開始した切っ掛けが、他バンドのプロデュースからというのもあまり例がないユニークな事例のように思える。
Well Hungariansはかなりカントリーのカラーが強いが、ロックンロールのグルーヴが気持ち良いバンドなので、これまたお薦め。「Framed」は上のリンクから試聴できるので、興味のある方はどうぞ。
Well Hungariansとのツアーはアメリカだけでなく、欧州まで行われ、当地でChrisはかなりの人気を獲得する。ここで瑞典のレコードレーベルから、是非こちらでアルバムを作成してみないかというオファーまで持ち込まれることになったのだ。
ここに至って、Chrisは欧州でアルバムを録音することを決定。Wiley Cousinsも勿論ピアノ、オルガン、サックスと多岐に渡り協力している。他のミュージシャンは名前の語感からしてスカンジナヴィア系のミュージシャンのようだがデータが不足しているため良くは分からない。
それよりも、Chrisのマルチプレイヤー振りが見物である。インナーでもウッドベースを抱えた色男のショットが印刷されているが、実際に、アップライトベース、ベース、ギター、バリトンギター、キーボード、パーカッションそしてリードとバックヴォーカルを当然担当し、アレンジ、プロデュースまでこなしている。
こう書くと、宅録が好きな引き篭もりタイプのシンガー・ソング・ライターにこういったタイプが多いため、Chrisもそういった繊細といえば聞こえの良い線の細い内省的なシンガーという印象を与えてしまうかもしれない。
しかし、この「Chris Alcaraz」で展開されている音楽は、シンガー・ソング・ライターの作風というよりも非常にヴァライェティに富んだバンドサウンドである。マルチミュージシャンの閉じた世界を表現したようなちまちました感じを受けることは全く無い。
パワフルで技巧がガッチリとした手ごたえとして感じられる演奏といい、歌によって相当歌唱法やキーを変化自在に使い分けているところといい、とても新人が出したデヴューアルバムとは思えない。
さて、肝心の音楽性だが、直前に記したようにかなりあれこれと異なった音楽を追求している点が見受けられることは間違いない。が、軽薄な上っ面だけを追いかけているという、尻の軽さは全く感じられない。というのは、基本は良質なAmerican Roots Pop/Rockになっているからだ。
特に、オープニングナンバーであり、欧州でのヒットシングル第一弾でもある#1『So Much』は歯切れの良いギターの音色とリズムにベースやドラム、そしてオルガンが程好くブレンドされた良質なミディアム・アップビートなルーツロックチューンである。ルーツロック一辺倒であった時代のWilco名作「A.M.」に収録されていそうなポップでアーシーな名曲だ。しかも、ChrisのヴォーカルはWilcoのJeffの柳腰ヴォーカルとは違い、艶っぽいし暖かみのあるシンガーとしての才能を感じるところが更に高得点。
また、Beatlesを思わせるようなコーラスワークは、古き良き時代のブリティッシュ・ポップスを連想させる。
#2『Anne』では、#1とは違い、メロウでレイドバックしたバラードである。このトラックではベースはウッドベースだろうか、かなり腹に響くようなベースプレイが聴ける。これまた懐かしのウエスト・コースト風の優しく、ノスタルジックなコーラスが印象的に配置され、Chrisの鼻から抜けるような押さえたヴォーカルと絶妙のブレンドを見せている。
#10『Giving My Love To You』も実に手堅い創りのロックナンバーである。アクースティックな弾き語りのリフからハートウォーミングなメロディを紡いでいき、次第にSouthern Rockの雄大さを控え目に肉付けしていく手法は斬新ではないにしても、実に巧みでありポップでもある。
良質なアメリカン・ロックを下地にしているが、Chris Alcarazの音楽にはかなりオールディズやクラッシック・ロックへの敬意が込められていると思う。
アメリカ南部の豪快な音楽性をそのまま素で投げずに、ポップでグルーヴィなオブラートで包み、ゴスペル的な奥の深さも足したナンバーが、筆者がこのアルバムの中で#1と共に大好きな#3『Gotta Say Now』である。ブンブン唸るギターの音色とやや控え目に転がるアクースティックピアノ、ここに多人数の複雑なコーラスが絡まる。このヴォーカルのアレンジは1960年代から70年代のモータウン・ソウルに通じる手触りの良い黒っぽさが感じられてとてもノスタルジックな感覚を揺らしてくれる。
歌詞も、暖かいメッセージソングである。♪「Gotta Say Now.Everything’s Gonna Be Alright」と繰り返されるコーラスにChrisの人生観、「何とかなるさ。希望を持って頑張ろうや。」という楽観的な面を伺うことができるように思えるのだ。
#6『(After All)It’s Only Love』はモロにBeatlesのフォロワーであることを示しているビートル・ポップなナンバーである。コーラスの使い方といい、ギターのチューンといい、英国風のポップなスコアといいヴォーカルを変えれば、殆どLennon-McCartneyの作で通じそうだ。しかも、しっかりとダブル・ハーモニーでヴォーカルを処理しており、ここでもBeatlesしているところはもう感心してしまうくらいだ。
古典的な要素としては、R&BとR&Bロックそしてブルースの要素もかなり持ち込まれている。
#4『To Your Heart』はやや気だるいモダンロックのテイストもあるが、R&Bのアーバン色が強いリズムナンバーである。ファルセット気味にダルく歌われるChrisのヴォーカルもこののったりとしたR&Bによくマッチしている。ストリングスシンセとローズピアノを使うという選択も適切だろう。
#7『No Mo’Me & You』ではファンクロック風のトーキング・ヴォーカルをかなりの低音で唄い、1960年代のR&Bロックを思わせるようなスゥイング感をベタベタに出している。このユルリとした余裕というか落ち着きはとても20代の新人が出したアルバムとは思えない。
#8『The Way I Need You』では更にファンク/ブラックの色合いが強く出たR&Bロックナンバーとなっている。というか白人の歌うR&Bと表現するべきだろう。バリトンギターの崩れた音出しといい、ピロピロと流れるオルガンといいもうヴォーカルがもっと太かったら完全に黒人シンガーと勘違いしてしまいそうだ。後半ではTower Of Powerのようなテナーサックスがブンブンと振り回されている。しかし、これでかなりポップにアレンジされているので、筆者の苦手な黒い要素が多くても聴けるのだ。
ブルースな南部ロックが豪快に泥を跳ね飛ばしてのたうつのが#5『Do It Again』である。クラシカルなBoogie Rockのユルさとグルーヴ感をかなりライトに表現したRolling Stonesの初期に近い手触りのブルースロックなナンバーであり、アルバムの中でも屈指の骨太ソングである。これまたファンキーでベッタリとしたスライドギターがソロで暴れまくるが、クレジットに拠ればChrisはスライドギターは弾いていないようである。
これだけでなく、更に古典的で直截的なナンバーも存在する。
#11『Try Some Understanding』はファンクであり、シカゴ・ビッグバンド的なジャジーな臭いがバリバリと発散されたサックスメインのロックナンバーである。特に、サックスのソロなどはアーバン・ジャズの古典盤を聴いているようなスゥイングを見せるし、アシッドでくぐもった処理をしたヴォーカルはまんまなビッグバンドとファンクロックである。
この辺りに大学でジャズ・ベースを専攻した影響が現れているようである。間違いなくこのナンバーではダブルベースを抱えているのだろう。
パロディナンバーとして笑いが出そうな#9『Strange』では、完全に1950年代のホンキィ・トンクでR&Bなオールディズナンバーが飛び込んでくる。マシンガン・ピアノに勝手にコードを引き回すギター、低音で突っ走るベース、全てがフリースタイルでロック草創期を再現したようなナンバーである。オマケにChrisのヴォーカルはChuck Berryのようにフィルターを掛けて全く違ったアナログ風のヴォーカルとして撮られている。
ともすれば、単なるオールディズの焼き直しとしか受け止められないようなナンバーを入れてきたのは、Chrisのクラッシックへの敬意か、それとも遊び心か。どちらにせよ、イロモノとして弾かれないような自信を持っていたに違いないだろう。実際に、パロディ的なヴォーカルは兎も角、演奏はかなりタイトで楽しく聴き所はあるナンバーだ。
最後の最後で、シンガー・ソングライターの繊細な面を見せる、#12『Call On Me』が静かに淡々と歌われている。かなり奔放に暴れて見せた#11とのギャップに驚くが、こういったブルージーで切ないバラードも唄えることを最後にしっかりと主張している。肝っ玉の据わった新人である。
全体として、かなり懐古趣味が目立つが、それだけに終始しないルーツロックとオールドタイム・ロックンロールを独自に融合させているアルバムである。1990年代の影響をあまり感じさせずに、古臭さだけに留まらない作風を練り上げているのは傾聴に値するだろう。
Chrisは米国と英国でそれぞれ、本アルバム「Chris Alcaraz」のプロモーションを行い、両国でインディ発売することに成功している。現在は次回作のデモを撮りつつ、欧州を中心にツアーしているようだ。
できれば2枚目は最初から本国でリリースしたい意向のようだが、さてどうなることやら。
この1stから3年が経過してしまった。そろそろ2枚目に関する具体的な情報が欲しいところである。恐らく期待を裏切るような新作にはならないだろう。
久々に彼にレヴューの完成報告もかねてコンタクトしてみるとしようか。 (2002.8.31.)
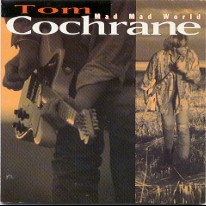 Mad Mad World / Tom Cochrane (1991)
Mad Mad World / Tom Cochrane (1991)
Roots ★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Arena&Adult-Contemporary ★★☆
You Can Listen From Here
「加奈陀(カナダ)のArena RockまたはPop/Rock、Adult ContemporaryにRoots Rock・・・・etc...と何でも良いので、加奈陀人のシンガーやロックンローラーとして誰を挙げるか?」
という質問に対して、貴方は何と答えるだろう。
1990年代のアフター・グランジ/オルタナ世代ならOur Lady Peaceでも挙げるだろうか。まあそういうリスナーは完全に経験値が不足しているから、城の周りでスライムでも倒しまくって経験値を稼いでから再度挑戦して戴くことを強くお薦めしよう。(謎)
こういった答えは1970年代、80年代、90年代、と何れかの時代の北米のヒットシーンを聴いて育ってきたか−つまり世代の差で答えはかなり変わってくるだろう。
が、1970年代以降のリスナーなら、筆頭に挙がるの恐らくBrian Adamsではないかと予想している。完全な主観だけれども。
事実1980年代のメジャー市場では最も顕著な成功を収めたカナディアン・ロッカーが彼であることは疑いようが無いからだ。
または、やや時代を戻してGuess WhoやBuchman Tuner Overdriveのフロントマンだった、Randy Buchmanを挙げるリスナーも確実に存在するに違いない。
更に、ヴェテラン陣に目を向けて、Neil YoungやThe Band、ひいてはRobbie RobertsonやJoni Mitchell、Leonard CohenにJeff Healey Bandといったフォーク/ルーツロックからキャリアを歩み始めた大御所に票を投じる人もいるかもしれない。意外に、これらの大物がカナダ出身であることは知られていないのだが。
他にも、RushやChilliwack、Loverboyと全米チャートでも一時期お馴染みとなったバンドを印象に刻んでいる人だって相当数とまではいかなくても、そこそこいても違和感は感じない。
しかし、加奈陀人のロッカーとしてTom Cochraneを即座に持ち出せる人は少ないだろう。仮にTom Cochraneという名前を知っていても、カナディアンであることを失念・忘却、或いは最初から知識に無い音楽ファンも多いのではないかと推定される。
1stレコードのリリースは1974年であり、それ以来21世紀まで殆どのアルバムをアメリカ印ではないとはいえ、メジャーレーベルから(加奈陀の)出し続けているシンガー・ソングライターであるのだが、日本の知名度はお世辞にも高いとはいえない。同様に米国での認知も低く、ことによると日本以下であるかもしれない。
もっとも、初めてプレスしたレコードであるCochraneという名義での(リイシュー時にTom Cochraneのアルバムとして改題ならぬ、改アーティスト名されているのだが。)「Hang On Your Resistance」が1974年に発売されてから、Red Riderというグループ名で「Don’t Fight It」を発表するのが1980年だから、1970年代の活動はアルバム1枚となってしまうし、1980年代もその半分をRed Riderのリードシンガーとして過ごしてきたので、純粋なソロ名義の活動としては厳密には1980年代後半のTom Cochrane And Red Riderを含めても20年には満たない。
そうであるけど、実際のキャリアとしては長いことには変わりないが。
だが、このレヴューで取り上げているとはいえ筆者も、Tom Cochraneが物凄いインパクトのある、加奈陀のロック界を背負っている看板アーティストだ、とはどうにも断言できるところまでは至っていない。
実に安定したクオリティのロックアルバムを常に届けてくれる人なのだが、良い意味で自分の形に填まり過ぎているし、悪い意味では過大な期待ができそうもないミュージシャン。
このような評価である。
大傑作というアルバムは殆どないのだが、出すアルバムに駄作無し、全て及第点以上。・・・・これはこれで凄いことであるとは思う・・・・・けれども。
何故、大傑作となるアルバムを持つアーティストとしてTom Cochraneを捉えられないのか、とかTom音楽性に対する意見は後述することにして、彼は加奈陀を代表するロックシンガーの“ひとり”として数えられるには十分値する才能があるとは思っている。
この見方には、ある意味、完全に米国で成功し、殆ど加奈陀で活動しなくなってしまったヴェテランやスター化したアーティストにはTom Cochraneが含まれていない。つまりそこまで米国化するほどにはロックスター化しなかったことを暗喩する面もあるのだが・・・・。
その長いキャリアで、Tom Cochraneは殆どのアルバムをCapitol RecordsかEMI Records Canadaから発売しており、現在に至るまでインディ落ちしたことは無い。(他のメジャーとしては、RCAで1枚、1988年に「Victory Day」を発表している。)
しかし、少々直前でも触れているように、アメリカでは殆どヒットをかっ飛ばしたことはない。
最初のバンド活動であるRed Riderでのベストアルバムを含む5枚、そしてTom Cochrane And Red Riderとして活動したその後に出された3枚のアルバムで、一度たりともトップ40ヒットを全米チャートに送り込むことはなかった。
よって、「加奈陀では成功したが、米国では全く売れないシンガー。」というレッテルを貼られていた。
この辺りは、Brian Adamsが「Cuts Like A Knife」を全米でヒットさせる前の状況に似ていなくも無い。Brianは僅か3作目で『From The Heart』をトップ10シングルに送り込み、デヴューから3年で全米での知名度をさっさと拡大してしまっているが。
勿論、Tom Cochraneが日本では全く無名のアーティストであったのは間違いない。少なくとも、1980年代に彼のアルバムが邦盤化されていた記憶は、筆者には無い。(実際はどうか知らないが。)
救いとしては、加奈陀では着実な人気を得ており、シングルヒットも毎アルバムから排出し、10万枚単位でのセールスは確実に挙げることのできるステイタスを築いていたことだろう。
このために、Canada EMIやCanada Capitolという巨大レーベルの契約を続行することが出来ていた(現在進行形であもるが。)のだから。
今回紹介する、「Mad Mad World」は、結論から言えば、加奈陀国内アーティストであったTom Cochraneの名前を世界中に拡げた出世作である。随分と活動開始からは遅れてやってきたのだが。
要するに米国をメインにそれなりの注目を集めるヒットを記録したのである。
そして、計らずも
「結局、アメリカでブレイクしなけりゃ、カナディアン・ミュージシャンなんて、所詮メジャーでも米国インディと変わらないローカルな歌い手並みなのね。」
という悲観的な事実を確認させてくれた作品でもあるように思える。
まあ、ネガティヴな物の見方はどっかに置いて、1991年末に本国でリリースされ、アメリカでも翌年2月に初のプレスとなった本作「Mad Mad World」に至るまでのTom Cochraneの足跡を、厳密な意味合いでのソロ1作目まで追って簡単に言及することにしよう。
Tom Cochraneは1953年に平原3州の1つであるマニトバ州で生まれている。4歳の時に、東部の州で加奈陀の心臓であるオンタリオ州に移住。11歳の時からギターを習い始める。
1970年代初期、高校を卒業後、フォークスタイルの弾き語りとして、珈琲ハウスやクラブを廻り始め、20歳になった1973年にはインディ・レーベルと契約を交わし、「Hang On Your Resistance」をリリースするも全く世間の注目を集めることは無かった。
その後、TomはカリフォルニアのLAに渡り、映画やテレビ番組用の曲を書いたりしたが、生活のため、タクシードライバーになったりカリブ海のクルージングのスタッフとして就職したり、宅配便の配達や皿洗いといった仕事をしなくてはならなかった。
結局、1977年に、Tomは米国からトロントに戻ることになる。ここでTomはヴォーカリストを探していたバンドと出会い、メンバーに加わる。バンド名をRed Riderと銘打ったミュージシャンたちは早速活動を開始し、デモ・テープを完成させる。
Tomは昔の伝手を頼り、作成したデモ・テープを当時RushのマネージャーであったRay Danielsの紹介でPrismのマネージャ担当であり、Red RiderもマネージメントすることになるBruce Allenに人脈を通じる。そしてBruceを通し、Capitol Recordsの上層部に届けることに成功する。
幸運にもCapitol Canadaと契約を交わしたRed Riderは1980年にデヴューアルバムの「Don’t Fight It」を発表。このアルバムは加奈陀国内で10万枚を超える売上を記録し、まずまずのスタートとなった。
これ以降、1984年までに合計4枚のアルバムを作成。
Red Riderはプログレ・ハードとも呼ばれる、所謂1980年型のAdult Rockなバンドであった。AOR的な要素もNew Waveなメロディも、ハードロックという側面も有したPop/Rockのバンドで、全くカナディアン・ロックらしいメロディのバンドなのだが、筆者はいまいちのめりこめなかった。やはり北米ルーツ的なエッセンスが薄過ぎるからだろう。
Red Riderはそれでも、カナディアン・ポップチャートでは少なくないヒットシングルを記録した。だが、アメリカでは遂にブレイクすることなく終っている。Rushの前座として全米ツアーに同行したにも拘らず、人気が沸騰することは無かった。
このためか、次第にメンバーが脱退していき、代替メンバーを加入させ急場を凌ぐのだが、バンドは次第に険悪になっていった。そして4枚目のアルバム「Breaking Curfew」を発売した後、Tomがツアーマネージャーと衝突し、Red Riderを脱退。ここでRed Riderは解散する。
しかし、Tom CochraneはRed RiderのギタリストであったKen Greerを引き連れて、Tom Cochrane & Red Riderとしてバンドを再編。Capitol Canadaとも契約を続行し、3枚のアルバムを残す。
そして、1990年にKen Greerがバンドを去ったことにより、初めてソロ名Tom Cochraneとしてのリーダー作「Mad Mad World」を吹き込むことになる。しかし、& Red RiderのメンバーであったベーシストのKen Spider SinnaeveやピアニストのJohn Websterもメインの演奏メンバーとして参加しているので、実質はTom Cochrane & Red Riderと変化した点は少ない。
目を引くのは、Brian Adams BandやHall & Oates Bandのドラマーを歴任してきたMickey Curryが全トラックでドラムを叩いていることだろう。
このアルバムは母国だけで100万枚以上、世界的には200万枚を超えるセールスを収めるのだが、唐突に全米トップ10ヒットとなった#1『Life Is Highway』が切っ掛けであることは明白だ。
著者としては、それ程エポックメイキングな曲ではないと思うし、当時既に完全にシーンを侵食していたグランジ/オルタナティヴとも全く共通するヒット性がない。(つまりはヒット性が常識的にはあるナンバーということだが。)
何故にこれほどブレイクしたかは理解の埒外だが、そもそもヒット曲とはそのようなものかもしれない。
それはそれとして、#1の大ヒットに牽引されるようにしてアルバム自体もアメリカにおいて、初めて好調なセールスを記録。
#1のカットに次いで、シングル化されスマッシュヒットした#5『Washed Away』、#4『Sinking Like A Sunset』だけでなく、当時加奈陀に住んでいた筆者は#2『Mad Mad World』と#3『No Regret』までも独自に国内シングルとして切られ頻繁にオン・エアされていたことを記憶している。
後で知ったことだが、1992年には日本でも日本盤がリリースされ、次作の「Ragged Ass Road」(1995年)までもが邦盤として発売されている。こちらは店頭で目撃したので間違いない。
しかし、話題が逸れてしまうが、Tom Cochraneを「トム・コクラン」と発音して記載してしまうのは如何なものかと。
この通りに彼の名前を呼んでも北米では全く通じないこと請け合いである。まあ、Billy Joelを「ビリー・ジョエル」と発音しても理解されないのと同じだろうから、今更どうでも良いことかもしれないけど。まあ、愚痴として。
これ以降、Tom Cochraneはアクースティックアレンジと新曲を加えた「Songs From A Circling Spirit」を含めて3枚のアルバムをカナディアン・メジャーからリリースしているが、全米でヒットシングルになったのは1995年のカット『I Wish You Will』のみである。アルバムも際立ったセールスを米国では残していない。
これらを鑑みると、「Mad Mad World」が突然売れただけという事実だけが残る。
確かに、数あるTom Cochrane関連のアルバム中で、この作品はトップクラスの出来と言えるが、その他のアルバムと比して特段飛び抜けて優れている訳でもないと正直なところ思う。
当然、ハードロック色の強かったRed RiderよりもHeartland Rock風のルーツィなテイストが増えたTom Cochraneの名前がクレジットに入った& Red Rider以降についての分析であり、Red Rider時代は外した上での考察である。
さて、Tom Cochraneとはどのようなサウンドを創る人物だろうか。
Tom Cochraneというシンガーは、同国のBrian Adamsと非常に近い音楽性を持っている人だ。John MellencampやTom Pettyというアメリカン・ルーツ系の大物とも比較されることもあるが、彼等の音楽より遥かにルーツロックが占める割合は少ない。
Jude ColeやCurtis Stigers、そして全盛期のHuey Lewis的なアーバン・ポップ/ロックの垢抜けたセンスを持ち、Michael Stanley Band、REO SpeedwagonといったArena Roots Rockとも言うべき良質なコマーシャルさとアメリカン・ルーツの感覚を同居させた音楽性。
それがTom Cochraneのサウンドだ。
が、惜しむらくは、そのヴォーカルがそれ程耳を引くような独自性が少ないことだろう。Brian Adamsのようにハスキーさと力技で圧倒するようなプライオリティは、Cochraneには無い。
かといって、甘さやソウルフルなヴァリトン・ヴォイスでリスナーを魅惑するという特徴も無い。
実に平凡なヴォーカルなのだ。この点が、アメリカで伸び悩んだ原因の1つだろう。
更に、これはTom Cochraneのアルバム殆どに当て嵌まるのだが、良い曲と俗に言う捨て曲タイプのいまいち以下なナンバーの落差が激しいことだ。
全くシングル向きで、シングル用に創られたとしか思えない曲は、素晴らしくキャッチーでアレンジも緻密で、とても完成度が高い。それなのに、変にハードロックやプログレ・ロックのような粗雑なナンバーや、脱力したようなスローバラードにアーバンポップスの出来損ないといった曲が必ず良曲の間に挟まっている。
こういったクオリティの低い曲がアルバム全体の包括した完成度を引っ張り下げ、どうにも段を落とした作品に見せてしまうのだ。
中途で疑問の提起をしているのだが、Tom Cochraneのアルバムに最高傑作とスタンプを叩き捺せるピースが少ないのはこの落差の激しい曲の混在にあるのだろうと、筆者個人は考えている。
それでもこの「Mad Mad World」は出来の良いナンバーが多いため、全体の良好な流れを駄曲が汚してボロボロにしてしまうには至っていない。だからこそ、この場で取り上げているのだ。
が、それでも個人的には捨て曲と思えるナンバーはしっかりとトラッキングされている。
まずはBon Joviが腐敗した、というか全盛期を過ぎたBon Joviそのものな必要以上にハードロックした重い#2『Mad Mad World』。母国では結構エア・プレイされていたが、どうにもこのアンキャッチーでハードな曲は嗜好に合致しないのだ。
同様にプログレハード的なマイナーで暗い#8『Brave And Crazy』。これは産業ロックからメロディアスな部分だけ取り去ったようなナンバーで、如何にハードロックというものが音楽の本質をスポイルするかという見本のようなナンバーでもある。
そして一番の問題が、#11『Get Back Up』、#12『Emotional Truth』、の2連発である。全て、当節大嵐を吹かせていたオルタナティヴ的な暗く、内に篭もった重苦しいダークな雰囲気を冗長に垂れ流す曲だ。ある意味、ハードなロックなら堪能できる#2、#8よりも始末が悪い。
しかし、反対にシングルとなった曲を中心に、良いナンバーは非常に良い出来だ。
#3『No Regret』のHeartland Rock的な雄大さと産業ロックの華やかさがミックスした断面の綺麗なロックビートから#6『Everthing Comes Around』の最高にキャッチーなロックAORとも言うべきナンバーへ流れていく4曲の部分は完璧なPop/Rockとして輝いている。
#4『Sinking Like A Sunset』の美しいサンプリングピアノやストリングシンセサイザーが活躍するミディアム・ポップ曲ChicagoやBrian Adamsのシングル曲に通じるヒット性が満載。
#5『Washed Away』のエモーショナルなヴォーカルワークはTom Cochraneの誠実さをロアに感じることが出来、Glen Freyがソロワークで取り上げそうなソウル・ポップの味わいがある。
穏やかな平原的伝統音楽をしっとりと表現する#7『The Secret Is To Know When To Stop』は地味ながら心に残るしんなりとした暖かさがある。
アクースティックさとアーシーさをTomが弾くスライドギターによってさり気なく醸し出している#9『Bigger Man』。オルガンの絡め方もルーツロックしている。
#10『Friendly Advice』は#5のようにリズムが都会的な流暢さを表わしているけれども、何処となく土の香りが漂ってくるような落ち着いたポップナンバー。このような地味なナンバーでも良好なポップさが注入されている。
そして、#13『All The King’s Men』は唯一Tomのセルフ・プロデュース作であり、スケールの大きい、然れども静かなバラード。ラストの幕引きには丁度良い類の曲であると思う。
このアルバムを10年ぶりに聴いてみて、非常に引っ掛かったのが、長らく売れなかったTom Cochraneが、その得意とする音楽性がセールスのベクトルとしては急速に沈没していた1992年という時代において、趨勢に逆行するようにブレイクしたという事象である。
Tom本来のスタイルは、Tom Cochraneをバンド名に掲げた過去5年以上に渡って変化していないのに、何故、この時代に売れたのだろうか。これには興味をそそられる。
想像するに、やはり既存のチャートの大勢を占めてきたアメリカン・ポップロックの市場そのものが、曲のメロディやコマーシャル性を全く考慮しないグランジ/オルタナティヴに対して抵抗する、超自然的−言い換えれば見えざる手か何かが、働いたのかもしれない。
そう簡単に伝統を破壊されるものかという、時代の良心・流れ・浄化作用、何でも良いが兎に角作用反作用となる力場が起こったのかもしれない。
いきなり胡散臭くなってしまったが、急激な変化に対して−ここでは新しい音楽の伝統への破城槌たるオルタナティヴ−はゆり戻しやぶり返しが来ることは何かにつけて多い。経済でも自然災害でも流行でも。
Tom Cochraneの予想もしなかったヒットというのは時代の仇花的抵抗だったように思えてならない。
結局、抵抗はレジスタンス活動の域を出ない結果となり、1990年代の北米メジャー・シーンは最低の迷走に突入していったのだ・・・・・。
しかし、Tom Cochraneは現在も自分のスタンスで堅実な活動をしている。現在の状況ではシーンが彼を求めることは、可能性としては非常に低いだろう。
だが、グランジ・ヘヴィロックの侵略に、意図せずにとはいえ、対抗した勢力の一角を担った彼には心からの拍手を送りたい。
(2002.8.18.)
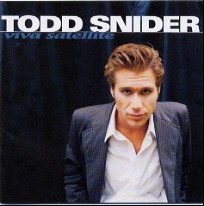 Viva Satellite / Todd Snider (1998)
Viva Satellite / Todd Snider (1998)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Alt-Country ★★
You Can Listen From Here
どうにもこうにも世間的には、Todd Sniderの傑作は1st作「Songs For The Daily Planet」か、それ以上に賞賛を受けているのが2ndアルバム「Step Right Up」の様子です。
確かに、この2枚はルーツ/カントリーロック系のシンガー・ソングライターの作としては良好な完成度を誇るアルバムであるとは思います。特に、全体の完成度の高さでは「Songs For The Daily Planet」がToddの2002年までに発売した5枚のアルバムの中では最高傑作と認めるのにやぶさかではありません。
が、しかし、だけれども、ところが(ヤメレ)、どうにもこの初期2枚は物足りないものを感じていました。
それは、殊に最高傑作と名高い「Step Right Up」について顕著です。
そう、ロックンロールとしての一発吹っ切れたパワーがあってしかるべきシンガーなのに、どうにもカントリーロック畑でジャガイモを収穫するかの如く、枯れていく−シリカゲルと一緒になった湿け煎餅のように−乾燥して行くような方向性を予感してしまう部分が、Todd Sniderには伺えたのです。
残念ながら、この予想はこの3枚目のアルバムで一度は覆ったものの、またぞろ正解であったことになってしまうのですが。まあ、それはどっかに棚を作って上げて置きましょう。
しかし、1998年春、忘れもしない4月・・・・・4月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4月某日(忘れとるやん!)、
北米中西部の大都市、シカゴの郊外のタワー・レコードでこのTodd Sniderの3枚目のアルバムが試聴機に入っているのを見た時、何かピピピッ、と来るものを感じました。
断っておきますが、電波や宇宙からの意志を受信した訳ではありません。それは常日頃なことですので特別ではないのれす。(ヲイ)
デヴューアルバムから、殆どを鬱陶しい長髪で過ごしていたTodd Sniderが突如短く髪を切り揃え、額にミミズのような猿ジワを浮き立たせて藪睨みしているという、この「かかってきなさい」とも語り掛けているジャケット写真。
ここは当然、「よっしゃ、挑戦受けたろやないか!」と白いマットのジャングルではなく、レジに即アルバムを運ぶのが真の男なんでしょう。けれど、安月給の故チキン野郎であることを強要されている身としては、しっかりと試聴機のヘッドホンを耳に当てるしかありませんでした。(涙)
で、1曲目。
冒頭のリフと最初のヴォーカルを合計10秒間聴いただけで、即、レジに持っていきました。(早ッ!)
もう、この「Viva Satellite」はこの1曲目が全てです。この1曲だけで全て桶です。
そう、
#1『噴進式紡錘型飛翔体燃料』(何つ〜ベタな)
(英題(違)『Rocket Fuel』)はTodd Sniderの最高傑作なのです!!!
このナンバーを聴いた時、真剣に
Sniderはん、アンタしかDan Bairdの後継者はいてへんわ。何せ、タイトルにも「衛星」入っとるし。(関係ありません。)
と勝手に芋判を掘って太鼓判を捺してしまいました。食べ物は大切にしなくてはなりませんね。
が、奇しくも同年の1998年に、こちらはMCAという大手の傘下に所属していたTodd程にはメジャーのプレスではないのですが、「Rock & Roll Band」というタイトルで、カントリー/パンクの堅実レーベルBloodshot RecordsからデヴューしたTim Carrollにも同じ予感を節操なく抱いたりしていたことは秘密にしておきましょう。
ちなみにこの「Rock & Roll Band」は1999年にSireから、2000年には「Not For Sale」と改題されてどうみてもCD-Rとして再発されています。
更に余分な感慨を述べれば、Todd SniderもTim Carrollもこれ以降のアルバムを出すごとに、開いた口が塞がらなくなり、終いには顎が地面まで落っこちるような尻すぼみなアルバムリリースを重ねていくところまで似ていたりします。
まあ、Timは2002年に発売された「Always Tomorrow」で殆どの曲がカントリーの軽さに失望させる中、僅かながらタフなロック魂を見せてたりはしてくれますが、とてもDan Bairdの後継者には及ばないです。
結論からすると、
結局は、Toddのキャリアの中で、突然変異的に出現したロックンロールなアルバムが「Viva Satellite」という感じです。が、かなりいい加減さが爆発している作品でもあるので、全体の完成度ではデヴュー盤の「Songs For The Daily Planet」には及ばないでしょう。
然れども、兎に角ロックです。ロックです。#1だけでもロックンロールのマスターピースです。
先に結論が出てしまっているので、これ以上は全て蛇足になりますが(腐)、まあ続けます。お付き合いして戴けるなら続けてお読みください。
上記のように、元来酔いどれロッカーの気質がデヴューからそれなりに見えていた人ですが、この3枚目にして現在までのところ最後のメジャーアルバムでは、その酔っ払いぶりが炸裂しています。
#1『噴進式紡錘型飛翔体燃料』(しつこい)での泥々でデロデロなスライドギターのリフ。当然、ギターはWill Kimbroughがリードを弾いています。面白いのはこのインテリ(死語)メガネの兄ちゃん、自分のソロ作では驚くほど大人しいギタープレイに徹していることです。というか、Kimbroughがここまで崩れたギタープレイを見せているのはおよそ本作だけのようにも思えます。
きっと、Will KimbroughもTodd Sniderの酔っ払い電波に感染していたのかもしれません。(合掌。チーン)
そして、投げ遣りでヤケクソ気味な♪「Rocket Fuel,Rocket Fuel,Buddy I’m Running On Rocket Fuel」♪のダミ声ヴォーカルとコーラス。まさにアルコールの代わりにロケット燃料のケロシンでも飲んであっちの世界にトリップしてしまったような唄が流れてきます。(注:ケロシン飲んだら腹痛では済みません。真似しては駄目。)
ファースト・ヴァースが終わると、ガスが抜けたような「2,3,4,5・・・・・」のカウントアップ。オラオラ状態とグデングデンな泥酔状態が合わさったような気合で次パートへとダイヴしていくところも最高に良いですね。
しかも、この歌、脱穀機にF1マシンの発動機を載せて田舎道を暴走しているような迫力満点です。当然、ドが付くキャッチ−さを誇ってます。まさに、Southern Rockの激烈ラジオ向けナンバー。これを聴いてポジティヴな反応しないロックファンは、かなりロックンロールの解釈に於いて一般とはかけ離れた趣味がありそうです。(を)
続く、#2『Yesterdays And Used To Be’s』も#1ほど棍棒で殴られるような衝撃はありませんが、これまた重戦車が砲塔をゆっくりと旋回させ、射撃準備に入るようなどっしりした安定感を持ったルーツロックナンバーです。#1の激烈ロックチューンの後にこれまでの作風のカントリーロックを即持ってこられたらその落差にガックリきたかもしれませんが、#1で予感させたロックアルバムの期待を裏切ることはありません。#1のヤケクソなヴァリトン・ヴォイスではなく、ここでのToddのヴォーカルは何処か抜けたヘロヘロ感を燻ぶしてます。酔いどれですねえ。
1966年、アメリカ北西部のオレゴン州で生まれたToddは1998年当時で32歳。20歳の頃に、自分が楽しいので歌を書き始めたというSniderもオーヴァ・ザ・ヒルしてしまった訳です。詰まる所、30歳を超えて初めて発表した作品でもあるのです。2ndは29歳の時にリリースされてますので。(ちと苦しい。)
30歳超えたら恥じも外聞もオヤヂ化の名のもとに何でも桶、になってしまったような暴れぶりです。前作の「Step Right Up」で非常にカントリーライクな作風で枯れてしまっていたことが嘘のようです。
#9『Positively Negative』というアンヴィバランツな題名のロックナンバーでも、ドン暗くウニョウニョとコブシが裏返る前半から唐突にハードな展開に持ち込むハード・サザンな赤土ロックを絶叫。きっとかなりの鬱屈があったに違いありません。(違)
#4『I Am Too』でのR&BとAlternative RockとSouthern Rockをアシッドに混ぜこぜにしたヘヴィさは、これまでの路線からは想像できないミクスチャーを覚えます。しかもエキセントリックな女性ヴォーカルまで起用。
#6『Out All Night』は活動拠点であるオースティンの埃にまみれた空気が押し寄せてくるようなヘヴィなサザンロックで、Alt-Countryとすれば、Altの頭の角が突っ張った曲ですね。
ことキャッチーさに掛けては1stアルバムで展開した太い南部ルーツロックベースの世界にはかなり見劣りするアルバムなのです。
が、更にネジが外れたというか迷走するナンバーが#5『I Am Two』や#7『Guaranteed』でしょう。#5は色々なSEとノイズをごった煮にしたプログレッシヴ・サウンド的なインストゥルメンタル曲。#7はワールドミュージック的な音節がそこかしこに感じられるエスニックでミステリアスなナンバーです。
このあたりを聴くと、Toddの脳味噌のシワが額にお引越ししてしまったので、トチ狂ってるかもしれない(をい)と心配になったりもしました。(いや、まぢで。)
しかし、正統派南部ロッカーとしての面目を見せるナンバーもあります。
#3『The Joker』はチャートファンならピンと来るSteve Miller Bandの1973年の全米No.1ヒットのカヴァーです。Rick Steffのハモンドオルガンとクラヴィアントを思いっきり効果的に使い、ローファイラップ気味な歌唱法で、何処となくアナーキーなSteve Millerを上手くカヴァーしてます。
#11『Godsend』ではカントリーロックを意識したボトルネック系のギター弦と敏腕ベーシスト兼ギタリストであるJoe Mariencheckのファズギターがグラスに転がるトラッド風のポップロックチューンが、優しく奏でられます。
続く#12『Comin’Down』でも酔っぱらいの怪気炎を具現化したようなパワーに載せて、程好い重量感のあるルーツロックがリズミカルに走ってくれます。#1さえなければ、もっと輝いた傑作ルーツドライヴ曲なのですが。
こういったオヤヂになったら栄養ドリンク片手じゃあ!!(謎)というロックチューンに正対するような、日本酒に例えると吟醸のような味わい深いナンバーも揃ってます。
#8『Can’t Complain』では出し過ぎて(ナニヲ?)カサカサになってしまったくらいに、枯れたフォーキィさをアーシーにじっくりと炙ってくれます。苦いタレで焼肉を食べる気分ですね。
#10『Once He Finds』では、突如正気に戻ったというか詩人に立ち返ったかのように、センチメンタルでポップでしかも激烈に渋シブなアクースティックでルーツィなバラードを押し殺した声で語ってくれます。Willのボトルネックギターとスライドギターの音色には男の背中が煤けて見えるような哀愁があります。某麻雀漫画の主人公は関係ありませんよ、全然。(マイナー過ぎ)
#13『Never Let Me Down』では、BoogieでSouthernなたっぷりとした余裕のあるロッカ・ブルースがのたくってます。女性コーラスはゴスペルの香りを強くしていますが、こういった南部式のナンバー(拳銃ではありません)でとぐろを巻かせると、かなりの蟒(うわばみ)になれる人ですね。
#14『Doublewide Blues』では、アイオワ出身のピアノシンガー、David Zolloがピアノで参加しています。そのDavidのブルージーでダンプな持ち味を魂ごと吸い取ったような枯れ枯れてススキ野原しか残らなくなった荒地のようなシンプルなバラードが打ち込まれています。切々と語られるToddのトーキングは酔っ払いの愚痴に聞こえるのは、間違いではないかもしれません。(笑)
最後のシークレットトラックでは思いっきり、パンキッシュにロックンロールを蹴飛ばしてます。この壊れっぷりが実に気持ち良く最後を締めくくってくれます。
「オレゴンには何の楽しみも無くて、俺はさっさと逃げ出した。」
と回顧するTodd Sniderは高校卒業後、テキサスへと流れていきます。しかし、ロクな仕事はなく赤貧に喘ぐ毎日を繰り返します。1980年代中期のテキサスではMTV全盛のメジャーシーンとは全く違ったルーツ/カントリーロックの世界が構築されていました。
Toddは、まずカントリーシンガーのJerry Jeff Walkerにドップリ填まってしまいます。それは音楽だけでなくて、生き方にも強い影響を与えました。
「俺は完全にJerry Jeffの追っかけをやっていた。Jerryだけでなくテキサスのアーティストの、Joe Ely、Kris KristoffersonそしてGuy Clarkもそうだったんだけど、彼等には物凄い共感を覚えた。確かにSam And Daveも好きで聴いたけど、ただ1ファンとして知ってて、聴くだけの音楽だったね。(註:黒人ソウルのデュオ)でも。俺が最初にJerry Jeffを観た時、『これこそ俺だ。俺と同じだ。』って思った。
俺はジプシーのように放浪生活をして、完全に壊れたヤツだったし、ギターを持っていた。Jerryのようなテキサスのミュージシャンはヒッチハイクしながらプレイしているようなもので、俺もヒッチハイカーだった。彼等は全ての感動を即興的に3コードで表現でき、それで世界は全てってな感じだった。
俺は今でも彼等のように上手にはギターを弾けないけど、Jerryにくっついてあちこち回るうちに、これこそ自分の天職だって確信したんだ。」
と20歳を越えた放浪青年はミュージシャンを志すことになりました。人生踏み誤ったのかどうか。(を)
まず、大きな血肉になったのが、テキサスからメンフィスに移った1980年終わりから前座として同じステージに立ったJohn Prineだったそうです。ツアーを終った後も、この爺さんはToddにソングライティングを教えてくれたのです。
「John Prineみたいなミュージシャンになるために努力することは不可能だけど、彼から学ぶことはできた。Johnは詩人になるために頑張ってはいけない、もっと単純に歌を書けばいい、ということを教えてくれたんだ。」
・・・・単純さを増すのにJohn Prineは背中を押してあげたようですね。
兎も角も、次第に実績を積んだToddがカントリー系のポップロックアーティストの大御所であるJimmy Buffetのバンドメンバーであり、シンガー・ソングライターでもあるKeith Sykesの目に留まり、Sykesの後押しでインディレーベルのMargaritaville Recordsと契約したのが1993年です。
そして、あのアルバムではヒドゥントラックとなっているあまりにも有名なシングル、『Talking Seattle Grunge-Rock Blues』のマイナーヒットにより次第に知名度が上昇し、それに目をつけたMCAが「Songs For The Daily Planet」を1994年に配給。『Talking Seattle Grunge-Rock Blues』は各国でそのグランジ世代へのアイロニカルな視点とフォークロックへの愛惜を歌った内容で多くのメディアにも注目されます。
ここからTodd Sniderのメジャー・アーティスト人生が始まりました。
何でも、日本盤も出てるとか?
が、この3枚目は前作に次いで芳しいセールスを残すことが出来ずに、Toddはインディ落ちします。
そして、2000年。
オナゴのように髪を伸ばして微笑んだ顔が移った4作目「Happy To Be Here」のジャケを見た瞬間、毛虫が背中を走りました・・・・・。
実に牧歌的でアクースティックだけの抜け殻青年に成り果てた作風に激しく失望。
2002年の「New Connection」もカントリー的なアプローチが強過ぎて、全然ロックを楽しめません。
もう、完全にあがってしまったのでしょうか?この「Viva Satellite」以降、急速にしょうむないシンガーに急降下しています。しかもアクセルの加速付きで。このままですと、引き起こしに失敗して、大地に激突。華と散りそうな予感までしてきやがります。
まだまだ萎むには若過ぎます。才能は枯渇したとは思えません。
頼むから、もう一度だけ#1『噴進式紡錘型飛翔体燃料』のようなロックをやってくで〜〜〜!!
と、これだけが望みなのです。ロックンローラーとしての気概を回復して貰いたい祈りを込めて、今回はTodd Sniderの最後のロックアルバムについて語ってみました。 (2002.8.22.)
 Elton John / Elton John (1970)
Elton John / Elton John (1970)
Adult-Contemporary ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Singer-Songwriter ★★★★
You Can Listen From Here
久々に、Elton Johnの2002年までの最新スタジオアルバム「Songs From The West Coast」を聴いてみた。
この「Big Picture」から4年を経て発売された最新アルバムを改めて聴きかえした時、まず感じたことは、
人間は誰しも老いる、という普遍的な真理だった。
「The One」を最後に、ロックアルバムとお世辞にも呼べるような作品を最終的に10年リリースしなかった1990年代のEltonは、その大半が40代であったことに驚くくらいに大人しくなってしまっていた。1990年代に3度観たライヴではまだまだ全然元気なステージを見せてくれていたものの、どうにもこのままバラードシンガーになってしまうのではないかと、半ば諦観の眼でこの英蘭人を眺めていたものだ。
しかし、発売前から、
「1970年代の頃の傑作を思わせるようなアルバム。」という噂と先行レヴューが飛び交っていた「Songs From The West Coast」には久方ぶりにロックしてくれるピアノ・マンという期待を抱いていたため、早速飛びついた。
これまでにそこかしこで言及されているが、確かにシングル・チャートでウケを狙った主に1970年代半ば以降から続いて行く作品群とはやや趣を異にした、アルバム・オリエンティッドな1枚であることを認めるほかはない。
シングルを1曲も出さなかったりと、様々な意味で異色に位置する名アルバム「Tumbleweed Connection」(1971年)や、ストリングス・セクションが大嵐のように曲を装飾する「Madman Across The Water」(1971年)に近いという意見も尤もと頷ける。
だが、やはりいくら原点に回帰しようとしても、
Eltonは失った若さを取り戻すことができない。
それを可能に見せるヴァイタリティを持つミュージシャンは存在しているけど、彼には無理だったようだ。
何処か痛々しい頑張りを感じる。
とこのような感慨が浮かんだアルバムだった。
2001年、Elton Johnは長年のドラッグとアルコール中毒を克服して久しかったが、心臓に疾患を持ち、それを圧してツアーを続けていたという情報もあり、英タブロイド紙の中には心臓発作で入院等のデマを報じたシロモノまで現れた始末であった。
結局、Elton Johnはもうポップ・スター、ロック・スター、ロックンローラーと名称はどうでも良いが、ロックの歌い手としてシーンに君臨するのは無理なのかもしれない、という危惧を抱かせてくれた作品なのである、「Songs From The West Coast」は。
全体としては、バック・トゥ・セルフ・ルーツを狙ったことがありありと伺えるアルバムであり、近年のバラード一辺倒な作風と比較すると、確かにパワーは感じる。
しかし、どうにも力み過ぎに終始した斬新さへの追求を覚えるのだ。齢50を超えようが60に手が届こうが、過激に絶倫振りを発揮するジジイロッカーは結構存在する。
が、Elton Johnはどうやら、もうゆっくりとピアノを愛でて生活していく方が良いのかもしれない。
クラッシックアルバムをリリースした、偉大なるピアノマンたる双璧の片割れ、Billy Joelのように。
でなければ、あまりにも痛々しい。
と、こんなことを考えさせられてしまった。
原点回帰をするをする必要など、微塵もない尽きることの無い才能とセンスを持ったコンポーザーのEltonが、1970年代の自分のカラーを敢えて取り戻す必要に駆られている様子は、ただ胸が痛かった。
このため、昨年はどうしても「Songs From The West Coast」について筆を進めることが出来ず、レヴューは断念に至っている。久々の来日ライヴも何故かチケットを予約までしておいて、結局券は取らなかった。・・・・今考えるとアホな行為をしたものだが。(涙)
こうして、暫くElton Johnのレコードから筆者は無意識に距離を置いてしまった。2001年秋から2002年の初夏にかけて、殆ど彼のアルバムを聴くことすらなかった。
原因はやはり良く把握できない。
どうにもパワーダウンしてきたのが哀しかったのは、「The One」以降のアルバムを聴くごとに常に脳裏にへばり付いていたことだし、単純にEltonは全盛期を終えてしまったと失望した訳でもない−実際にまだEltonはこれからのアーティストであるという希望と確信はあるし。
温故知新を図ったために、2001年現在のElton Johnと1971年頃の彼の差が歴然としたことにショックを受ける程には悪いアルバムではないと思っていることだし。
やはり、衰えを初めて現実問題として予感したのが、「Songs From The West Coast」だったのかもしれない。完成度がなまじ近作の中では高かっただけに、昔の傑作と同列に引き上げ比べてしまったのだろう。
結果として、ここまでやってみて、このくらいなのか。
無論、繰り返しになるが、良い出来のアルバムなのだ。しかし、Eltonには過去を再構築せずに、21世紀の彼を実現して欲しかった。それがなされなかったことに対しての失望が強かった。
己のことを他人事のように書いているが、まあこのような心理作用になっていたようだ。
それを変えたのが、大学時代の先輩の家に招かれて出かけて行った時に、昔を懐かしがってBGMにしてくれた『The Great Discovery』や『The Border Song』が、再びEltonへと回帰する切っ掛けとなったのだ。
この1980年代中盤からのEltonしか知らなかった先輩に1970年代の彼の作品をカセットテープにせっせとダビングして洗脳したのが、なにを隠そう筆者だったりするので(何という懐古趣味な10後半から20代前半だったろうか)、結局は廻り回って、張本人が再洗脳されたようなものである。
またぞろ脱線する。
筆者と同年代の80年代MTV経験世代では、特に日本では世間的に全くElton Johnが評価されておらず、MTVという映像にも色々な意味でフィットしないアーティストであったこともあり、更に1980年代はトップ10ヒットが1970年代程には排出されなかった。
ために、Elton Johnの1970年代の作品は1987年の「Live In Australia」からシングル化され全米第6位のヒットとなった『Candle In The Wind』を聴いてライヴヴァージョンから入った人が相当回りに存在していたような記憶が鮮明である。
「Live In Australia」では声帯ポリープの手術直前だったEltonの声が相当に擦れていて、それが渋い要素を加えているのは福音なのだが、これ以降Eltonの声はかなり太くなってしまったのは少々残念だ。
特に、こういった初期のアルバムを拝聴すると、その声の違いが明白であることよ。
閑話休題。
久しぶりにEltonの作品に触れたことが呼び水となったのだろう、この後から、たまたま手元にあった「Elton John」を良く聴くようになった。
当面は、Eltonの知名度を爆発的に広げ、これ以降の快進撃という呼び方も陳腐に響くくらいの、黄金時代の基礎を固めた、このセルフタイトル盤のみを繰り返し流すだけだったが、次第に帝都に持ってきていたElton Johnのお気に入りのアルバムを次々と無意識のうちに流しっぱなしにしている自分に気が付いた。
「The Fox」、「The One」、「REG Strikes Back」、「Ice On Fire」、「Breaking Hearts」、「Here And There」、「Blue Moves」、「Single Man」、「Too Low For Zero」、「Jump Up
!」。
振り返ってみると、帝都には殆どセールス的にも世間の評価も絶頂期だった1970年代前半から中盤以降にかけてのアルバムは殆ど持ってきていないのに気が付いた。
「The One」以降の完全にピアノ演歌オヤヂに落ち着いてしまった非ロックアルバム群を持ってこないのは狭いスペースを圧迫しないための生活の知恵であるが。(を)
あれほど聴いた「Goodbye Yellow Brick Road」や「Honky Chateu」、「Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player」、「Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy」、「Madman Across The Water」その他の名盤がポッカリと抜けていた。
やはりリアルタイムで聴いた作品に対する愛着と思い入れの差だろう。現在でも一般的な評価は低いがElton Johnは1980年代の作品の方が華やかで好きである。
しかし、この「Elton John」を聴いていると、無性に1970年代のアルバムがまた聴きたくなってしまうのだ。
何故かというと、やはり初期のアルバムで最初に手にしたのがこのレコード(文字通りアナログ盤)だったということもあるのだろうけど、シンガー・ソング・ライターとして最も繊細な面が浮き出たのがこの作であり、「ロック界の吟遊詩人」というネーミングが最高に似合うのがこのアルバムだからだろう。
Eltonにしては異色の、カントリー/アメリカン・ルーツの風潮が濃い3作目「Tumbleweed Connection」でのダスティでほろ酔いな雰囲気。
「Madman Across The Water」でのオーヴァー・プロデュース気味な数十人の弦楽器隊のストリングスに支えられたドラスティックな緊張感。
こうしたクロース・トゥ・ジ・エッヂな音楽性ではなく、よりモデレイトされた青年シンガーらしい蒼さときめの細かさを丁寧に綴れ折るアルバムが「Elton John」である。
デヴュー作で、1969年に発売されていた「Empty Sky」で見せていたR&Bやサイケディリック・ポップの辛味と酸味を全く切り捨てて、英国でのみヒットした『Skyline Pigeon』での浪漫漂う美麗さを、より一層広義に拡大して一般性を確立したアルバムでもあるだろう。
後に、奇抜な衣装でピアノロックンローラとしての街道を驀進していくEltonだが、その繊細さからポップロックへのモデレイトの展開期に出された「Honky Chateu」に於ける、ストリングスを極力抑えPop/Rockとしての柔らかさを求め出したマイルドさとは質の違う柔らかさがある。
思うに、この2枚目のレコードにはこれ以降のEltonが成長していく可能性と将来性が全て掲載されているのではないだろうか。
例えば、#4『No Shoe Strings On Louise』では完全に他のナンバーと毛色の違う、レイドバックしたルーツロックと表現できる、カントリー・ブルースロックがソウルフルに唄われている。どちらかというと、ソフトでデリケートなナンバーが多いこの10曲の中では異彩を放っているのだが、これは翌年に出される「Tumbleweed Connection」でより明確なカントリー風のアルバムとなって再表現されている。
#6『Sixty Years On』での冒頭のプログレッシヴ・サイケディリックと、どうとも取れそうなストリングの尖がったオドロオドロしさと、それから急転してメインヴァースが哀愁たっぷりにスパニッシュギターとストリングスで紡がれる。
こういったメリハリのあるストリングス・ソングは、「Madman Across The Water」にてより大仰さを増量して成果を見せてくれる。
しかし、Elton Johnも遂に「60歳の時」(#6の邦題)が現実に迫る年齢になってきている。この曲を聴くたびに、60歳になったEltonはちゃんと活動してくれるのだろうか、という予想を10年20年前は漠然と考えていただけが、いざ時期が足音を聞かせる時を生きていると、ふと我が身を経過した年月を思い、しんみりしてしまったりもするのだ。
数年後に『Crocodile Rock』を初の全米No.1ヒットにして、突如“吟遊詩人”ソングライターからポップスターへと変貌していくElton Johnだが、その予兆は#3『Take Me To The Pilot』で既に噴出していると見ることが出来る。現在でもライヴでの重要なアンコール曲となっているこの#3。
シンガー・ソング・ライターが念入りに積み上げたこのセルフタイトルでは一番ライヴを意識して書かれた歌であることは間違いないだろう。オリジナルアレンジでは勿論、現在でも第一線で活躍する名コンダクターにしてストリングスアレンジャーであるPaul Buckmasterが弦をダイナミックにロックビートに載せている。
その古典的とも言うストリングス・ロックにかなり奔放な♪「Na,Na,Na・・・・・」♪のコーラスがバトルを仕掛けるフェイドアウト前のブリッジはかなり聴き所あり。
このファンにもエヴァーグリーンとなった#3とは異なり、地味で日陰者となった感のある#9『The Cage』も強力なロックビートと泥臭いうねりのあるメロディに支えられた隠れた名曲だろう。ホーンやストリングス、当時は最先端の電子楽器であったムーグ・シンセサイザーのソロが1970年という過去を偲ばせる。
#3程にはコマーシャルでなく、やや複雑な曲の構成故にライヴで披露されることが少なく、自然に埋もれてしまったのかもしれない。
まあ、シングルヒット曲となった2曲、特に#1『Your Song』については今更クドクドと語る必要もないだろう。が、一応言いたいことは書いておくことにする。
#1は現在ほどElton Johnの名前が浸透していなかった時代にもCM曲等で結構耳にしている人は多かったであろう曲だ。Eltonの記念すべき最初の全米トップ40ヒットであり、これ以降30年間に渡り、Eltonは毎年全米トップ40シングルをチャートインさせるという記録を打ち立てることになる。この金字塔はもう破られることはあるまい。
刹那的にトップ10ヒットをバンバンと量産するアーティストがかなり存在したが、どれも10年のディケイドを待たずにシーンから消えていってしまった。こういった事実を鑑みると、如何にEltonが偉大か再確認できる。無論、チャートが実力の指標ではないし、実力がヒットチャートに反映されない1990年代を眺めれば、こういったヒットポジションをとやかく言うのはナンセンスであることは百も承知だ。
さて、#1であるが、その背中が痒くなるような甘く、そして文学的な歌詞はもう青年の主張というか青い夢というかオヤヂにはこそばゆい限りだが、あからさまな「Love」という単語を使わずにここまでラヴ・ソングを書き綴れるのは流石に詩人、Bernie Taupinだ。この時代は後年のようにBernieが詩専門、Eltonは作曲専任という明確な色分けがされていなかったそうだが、やはりBernieの詩の特徴があると思う。
詩については、シェイクスピアの物語から引用した形を取る、アカデミズムを感じる#10『The King Must Die』が、政治的な風刺をしているように思えて、かなり当時の世界情勢と照らし合わせると面白いかもしれない。
この場ではかなり脱線するので割愛するが。
#7『The Border Song』は小ヒットであったが、実はこのアルバムで筆者が最も好きな曲の1つである。歌詞については完全に宗教曲なので−これまた初期の特徴でもある、宗教観があからさまに出ていて興味は深いが−無視するとして、聖歌隊のようなコーラスを入れたピアノ&ストリングスバラードのお手本であるような堅実で美しいバラードである。Eltonのシャウトするヴォーカルも若々しくて微笑ましい。
が、やはりこのアルバムでのベスト・トラックは#8『The Greatest Discovery』だろう。シングルとしてカットされてもいないし、「Live In Australia」に収録されたのが数少ない他のアルバム音源というマイナーな(多分)ナンバーだがそのオープニングでの優しいチェロ・エンディングでのドリーミーなハープとEltonのハミングであっさりと虜になってしまうリスナーは実は相当存在するのではないか。
その歌い込まれている世界も、もうガラス細工のように綺麗。
少年の日の良い記憶のようにセピアカラーにソフトフォーカスまで掛けた色彩が耳にたゆたってくる。
ある少年の視点で弟が生まれた次の朝を、少年らしい驚きと思考に立って書かれた歌詞は、Elton Johnの数え切れない名曲の中でもトップクラスに入ると信じている。しかも、相当風景描写を入れたデリケートな歌詞であり、現在のアメリカでは絶対に理解できる人口が少ないこと請け合いの語学センスが光っている。
哀愁と繊細さなら#2『I Need You Turn To』や#5『First Episode At Hienton』でも過不足無く表現されているが、そのフワリとした暖かさと、ほんのり心を掴む包容力では断然、#8が上。
甘い、現在では喉から出すことが出来ないハイキーを駆使したEltonのヴォーカルもフニャフニャに溶けてしまいそうな光線を発してくれる。
筆者は#3〜#4の流れも好きだが、#6〜#9の2曲のお気に入りを挟んだ流れが一番の好みである。
このアルバムには数年後、Elton John Bandとなるメンバーは誰一人参加していないのも面白い。「Empty Sky」で既にドラマーのNigel Olssonはクレジットに名前が載っているのに。
1992年に他界したベーシストのDee Murryと、現在もEltonとNigelとバンドを組むギタリストのDeavy Johnstonが顔を揃えるのは1年後の「Madman Across The Water」からになる。
このようなアメリカン・ルーツロック中心のサイトを運営しているが、神様はElton JohnとSteve Winwood、そしてPaul McCartenyという、全部英国人というのも自分のことながらどうにも矛盾している気がしなくもない。(笑)
元来、英国というのは良質なポップスの発信地であった筈なのに、ブリット・ポップが流行してからはさっさと北海に沈んでしまった方がマシな音楽しか出てこないのは何故なのか。(涙)
正直、Eltonに関しては、嘗てのワクワクさせるような傑作は1992年の「The One」以来打ち止め状態だった。
で、久々に痛さのみが聴くことを辛くさせた「Songs From The West Coast」を聴き直した。
冒頭に書いたように、年齢・老いを感じてしまうのだ、やはり。
が、嘗ての痛みは消えてなくなっていた。
何となく、次こそは21世紀に残る傑作がEltonから届きそうな予感が非常に漠然としてだがしてきた。あくまで予感でしかないのだが。・・・身もフタもない・・・・。
この「Elton John」から32年経過した。次の傑作リストに入るアルバムは何時届くのだろう。
Elton Johnが歳をとれば、筆者も加齢する。お互いがまだ固まって干上がらないうちにもう少し傑作の数を増やしてくれることを、この植毛手術が大成功した御大に祈ることにしよう。 (2002.8.24.)
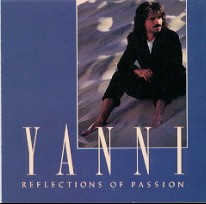 Reflection Of Passion / Yanni (1990)
Reflection Of Passion / Yanni (1990)
New Age ★★★★
Progressive ★★
Adult-Contemporary ★★★★
You Can Listen From Here
ルーツロック系という、所謂電子鍵盤とは共存・競演することはあっても、完全に融合することは厳密には不可能に近い音楽を扱うサイトを管理してて、また節操のなさを暴露してしまうことになるけれども(今更ではあるが)、こういったシンセサイザーやサンプリング音源を駆使して構築された音楽は相当好きである。
とはいえ、無作為に何でも雑食するという訳ではない。電子鍵盤メインとはいえ、シークエンサーにリズムボックスやスクラッチまでノイズ的に活用した人工音を吐き出すリズム音楽には全く興味はないし、可能なら消えうせて欲しいとも願っている。
いくらキーボードが好きという趣味があるにしても、筆者はメロディとサウンド・プロデュースが全然音楽としての形態を取らない音の積み上げであるなら、それを傾聴に値する存在とは見なさないからだ。
非ヴォーカルアルバムにポップさだけを求めるという、無謀な評価基準を押し付けるつもりは更々ないとはいえ、コンポーザーやアレンジャー、そして何よりも才能が伺える曲創りをしていない音の工作人をアーティストと呼ぶことはどうしても許容できないからだ。
実際に、鍵盤を使いインストゥルメンタルのノン・ヴォーカルアルバムを作製するミュージシャンは、Pop/Rock音楽シーンほど目立つことはないにしても相当な数が存在する。
ノン・ヴォーカルで総合的な楽器をコンダクトして作製するという概念に当て嵌めれば、映画音楽のサウンド・トラック、ダンスミュージックにワールド・ミュージック、そしてインストモノのロックやポップ、当然フュージョンやジャズもこの枠に円で囲まれていることになるからだ。
今回紹介するYanniというアーティストは基本的にノン・ヴォーカルのインストゥルメンタル作品を手掛けるサウンド・クリエイターであるが、分類としては広汎な意味でのイージー・リスニングとまで解釈しても良いアルバムを発表してきた人である。イージーリスニングと表現すると、流行歌のBGMアレンジとか、ショッピングモールで流れているクラッシックモドキのアルバムという印象を与えてしまうかもしれない。
厳密にはBillboardのチャートを参考にすれば、YanniのサウンドはNew Ageと分類されるだろう。もっともヒットアルバムをリリースし一時期はTop100の常連となったので、Kenny G等と同列にポップ・ポピュラーミュージックと考えられていた時もあるようだが。
まあ、New Ageとするのが一番無難なカテゴライズだろう。日本では全般的にBGMやイージー・リスニングという系類に分けられているようだ。が、どっちにしてもアメリカン・ルーツミュージックとは全く模索する次元の異なる音楽であることは間違いないだろう。
New Ageというカテゴライズには、シンセサイザーだけでなくギターやベースという弦楽器においても電子楽器を使用せずに自然な音楽を表現するという音楽も存在する。
例えば、あの辛口のRollingStone誌に「1980年代で最大の成功を収めた新レーベル」と絶賛されたWindam Hill Recordsや、その成功を追うようにして設立され二番煎じに留まらない地位を確立したNarada RecordsそしてLandscape Recordsが日本ではまだ知名度がが高いNew Age系列だが、これらのレーベルの初期ラインナップは殆どがアクースティック・ピアノやギターを中心としたナチュラル・ミュージックで固められている。
しかし、レーベルから出したアルバムが好調なセールスを記録し、次第に巨大レーベルになるに従い、シンセサイザーを中心としたキーボード音楽が次第にラインナップに登場するようになり、1980年代末にはアクースティック系列の音楽と共に、テクノロージーを駆使した鍵盤系の音楽はNew Ageを支える柱となっていく。
当初はNew Age=アクースティック系のヒーリングアルバム、と捉えられていた節が強いが、次第により自由な音楽表現を含めた範囲まで広がっていったのだ。
が、別にシンセサイザーを使ったインストゥルメンタル作がNew Ageという比較的新しいジャンルに分けられる音楽の専売品ではないのだ。
1960年代から1970年代に掛けて全盛期を構築したプログレッシヴ・ロックの派生形として、プログレッシヴ・ロックバンドのキーボーディスト達がアルバムをかなりの数リリースしている。中でも大ヒットを記録したMike OldfieldやYesの鍵盤弾きであるRick Wakemanの1970年代のアルバムは著名である。
また、EL&PのKeith Emarson、AsiaのGeof Downsも定期的にソロ作を送り出しているし、1980年代になるとハードロックのキーボディストが独自にインストゥルメンタルのアルバムを−目立ったセールスを記録したものは少ないが−リリースしている。当節流行したテクノポップというジャンルのBGMアルバムも方向性は違うけれども固定のファンを掴む市場を形成している。
これらの作品に多く見られるのは、所謂コンセプトアルバムというスタイルである。プログレッシヴ・ロック全盛期より興隆した大作主義の終末点ともいうべき、1枚のアルバムで世界観を統一し各曲をリンクさせるという試みは、歌詞が付いてないというハンディキャップは存在したにせよ、ヴォイス無しという特性故に曲のそのものの繋がりを強調できるという利点があったのだろう。1970年代のヒット作インストアルバムにはコンセプト作が結構多い。
またコンセプトというよりも最初から世界観が限定されている映画音楽のフィールドからも、その制約から離れて独自の曲を発表するコンポーザーも順当に輩出されている。同じく、Pop/Rockのプロデューサーが自分のリーダー作としてインスト作品を創ることもそれ程頻繁という訳ではないが、然程珍しくはなくなってきているだろう。
こういった鍵盤インストゥルメンタルの歴史を簡単に振り返ってみると、Yanniという人もそれ程珍しい出発点からインストゥルメンタル音楽を始めた訳ではない。彼も1970年代後半から80年代半ばまでロックバンドの鍵盤弾きであったのだから。
Yanniと同じギリシャの出身で、『Chariots Of Fire』を数少ないインスト曲の全米No.1ヒットに押し上げたVangelisがYanniの先輩格のように扱われることがあるけれど、Vangelisは映画音楽でもソロ活動と同時にそれなりの実績を積んでいた人だし、YesのヴォーカリストであるJohn Andersonと親交が強く、John & Vangeris名義でヴォーカルアルバムも数枚出している。
どちらかというとYanniよりもヴォーカルポップ等を含め、マルチメディア展開しているように思えるコンポーザーという印象が強い。このことはYanniがVangelisに劣っているとか多彩な音楽を提供する能力が欠如しているという意味を示さないことだけはお断りしておくが。
音楽性にしても、かなりプログレッシヴとしてのエキセントリックで前衛的な作品も多いVangelisとYanniは似ているところもあるが、実は似て非なるアーティストであると筆者は考えているのだ。
Yanniの経歴は日本盤も数多くリリースされていることだし、詳細には書き下さないことにするが、一応概略は紹介しておくことにしよう。
Yanniは3人兄弟姉妹の真ん中として1954年にギリシャで生まれている。
音楽好きの家庭に育ち、6歳から家に置いてあったピアノを弾き始める。が、正式なレッスンは受けることなく、釣りや水泳をすることが、ピアノを弾くことと同じくらい大好きな少年だった。
1969年には50メートル自由形の国内記録を破り、レコードフォルダーになる程の才能あるスイマーだった。このまま水泳の道を辿ればひょっとすると五輪で記憶に残る選手になったかもしれないが、Yanniは水泳をこれ以上必死になって追求することはしなかった。漠然とではあるが、音楽をやりたいという気持ちがあったのだ。
1972年に、彼は米国のミネソタ大学へ留学することを決意する。専攻は心理学。これは勉学と同時に音楽の本場の国で音楽を演奏してみたかったからという動機もあったそうだ。
言語的なギャップがあるが、Yanniは見事に4年で大学を卒業。学士となる。同時に学生時代は地元のローカルロックバンドで鍵盤を弾いていたが、卒業後は本格的にキーボーディストとしてロックミュージック界に飛び込む。
彼の在籍していたバンドはChameleonというプログレ・産業ロックバンドであり2枚のインディアルバムを発表している。Yanni自身のアルバム「Chameleon Days」(1988年)は、このロックバンド時代への想い出をタイトリングしたようである。
Chameleonの活動と並行して、自らの音楽を表現するため曲を書いていたYanniは1980年に「Optimystique」をレコーディングする。が、インディ発売されたのは4年後の1984年のことである。
彼の転機はここで訪れる。1960年代からプログレッシヴアートロックを長々と続けているTangerine Dreamのフロントマン、Peter BaumannがPrivate Musicを1984年に設立。New Age系のアーティストをレーベルメイトとして探していたところに、Yanniの「Optimystique」を聴いたPeterがYanniの才能に惚れ込み、彼をPrivate Musicに加入させたのである。
1986年に「Keys To Imagination」をPeter BaumannのプロデュースでPrivate Musicからリリース。その後、1989年までに「Optimystique」の再発を含め、「Out Of Silence」(1987年)、「Chameleon Days」(1988年)、「Niki Nana」(1989年)と5枚のアルバムを毎年毎に発売。
日本でもビクターから「Out Of Silence」を皮切りに彼のアルバムが発売されるようになるが、セールス的にはNew Ageファンは別としてそう注目されるような跡を残すことも無かった。まあ、インスト系のアルバムが大々的に売れるというのは相当稀なことなので、これは致し方ないだろう。
寧ろ、日本で紹介されていたことに拍手を送りたい。そうでなければ、当時ラップとLAメタルの氾濫に嫌気が差してNew Ageに逃避していた筆者の耳に止まることはリアルタイムではなかったかもしれないからだ。
さて、1990年以降−「Reflection Of Passion」の発売以降−のYanniについては最後に簡潔に述べることにして早々に「Reflection Of Passion」について触れておこう。
まず、最初にお断りしておくが、このアルバムは純然たるベストアルバムである。
3曲の新曲はトラッキングされてはいるものの、特別にアレンジされたアルバムでも新録として取り直した曲のアナザー・ベストでもない。これまでに当HPで取り上げてきた2枚のベストアルバムは変則だったのだが、これはそのままのベスト盤である。
まあ、New Age系とか特殊ジャンルの作品にはこれからは拘らずにベストアルバムをお薦めとして紹介することにしようという気概の表れと受け取って戴けると幸いだが、それ以前にこの「Reflection Of Passion」がこの音源の収録元の5枚のアルバムより、ぶっちゃけた話、良いのだ。
ミモフタも無い言い方だが、これ1枚で1980年代のYanniは全てカヴァーできる。5枚のオリジナル作を購入して聴く必要は殆ど感じられない。まさに究極のベストアルバムと断言したい。
更にミモフタも無いのだが、筆者はNew Age系のアルバムはベスト盤だけ聴けば満足ということが多く、その性癖もこのベスト盤を取り上げたことと無関係ではない。実際に、オール・インストのアルバムはどうにも差別化というか同じアーティストのバックナンバーを数枚揃えても聴いて区別することがなかなかに難しい。
これは単に筆者の貧相な感性の仕業なのだが、それを別としてもこの「Reflection Of Passion」は完璧なベスト盤であると言える。1990年に中古購入してから(ヲイ)10年以上傍から離していない数少ないベスト盤でもある。
ということで、これからはNew AgeやFusionのアルバムはベスト盤の紹介も機会あればしていきたいと思う。このHPに未来があるかはまた別の話であるが・・・・・・・・。
ということで、Yanniの1980年代の5枚の作品を総括した形のベストアルバム「Reflection Of Passion」について少々語るとしよう。
まず、驚くべきことにこれまで全くTop200チャートには無縁であったYanniなのだが、本ベスト盤はTop100に登場するとジワジワとチャートを上昇し、何とTop40アルバムになった。しかも、Top40に30週以上−半年以上も居座り続ける安定したロングセラーのアルバムとなり、200万枚以上を売り上げたのだ。
全く派手さも話題性もアイドル性もない、こういった良心的な作品が1990年という年代はまだ自然にしていても売れる時代であったことをしみじみと懐古する次第である。未だAlternativeというバイキンが蔓延する寸前の時代だったのでリスナーにも良識が存在したのだろうか。
まあ、売れたのは不思議であるとことであるが、売れたという事実は全く意外ではないだろう。5枚のアルバムから代表曲・良曲を集めた美しく、丁寧で、ロマンティックで、ドリーミーで、荘厳で、ハートウォーミングで、繊細で、悲しさと透明感がある素晴らしいキーボードインストゥルメンタルなのだから。
全15トラックのうち、
新曲が3曲、「Optimystique」から1曲、「Keys To Imagination」から1曲、「Out Of Silence」から4曲、「Chameleon Days」から4曲、「Niki Nana」から2曲。
以上の構成で「Out Of Silence」と「Chameleon Days」からの選曲が最も多い。この2枚は筆者がもっとも好きなアルバムで全体の完成度も高いので、このチョイスの比重は納得行くものである。
このアルバムの特徴は即ち1980年代のYanniの特長にもなるのだが、実にサンプリングとシンセサイザーを巧みに使用しているという箇所が最も目立つ方向性である。
筆者はこの時代のYanniが最も好きなので、このアルバムが大好きなのだが。
というのは、この「Reflection Of Passion」の成功に触発されたのか、それとも10年というディケイドの節目に集大成のベストをリリースしたからなのかは不明なのだが、1990年代のYanniは生の音に傾倒しだし、ヴァイオリンを始めとする弦楽器やアクースティックなギター弦等を次第に取り入れ始め、どうにも顔を向けいている方角がぼやけたアーティストになってしまった気がする。
また、1993年のチャートインしたヒットアルバム「Yanni Live At The Acropolis」でフルオーケストレーションをバックにライヴを行ったり、殆どピアノソロオンリーの同年のスタジオ録音盤「In My Time」とやや暗中模索というか、色々と手を広げているという感じが強烈であった。
最近作の「Tribute」(1999年)、「If I Could Tell You」(2000年)では大胆な生ストリングやヴォイスの挿入等があったりして、初期の面影は完全に消えうせている。
どうにもこういうアクースティックやワールド音楽に走りすぎるYanniは気持ちが良くない。
やはり、電子鍵盤を駆使して音を練り上げていた、この初期作が最も優れた音の構築と構成を行っていたと考えている。
その15曲の中でもお気に入りを挙げてみれば、まずやはり#1『After The Sunrise』である。というかこれこそYanniの最高傑作であると信じて止まない。
恐らくはライヴオーケストラではなく、フェアライト・プログラムとストリングスシンセサイザーを目一杯のスペックまで活用しきった荘厳で雄大なオーケストレーションに、奥行のあるサンプリングピアノが美しいタブローを描く。
まさに、「夜明けの後」というタイトルに相応しい。良く徹夜明けにこの曲を流して登ってくる夏や秋の朝日を貧乏下宿から眺めたものである。雄大な大自然の息吹を感じ取れる曲で、一日がワクワクするような感動に満ちていると錯覚することができる(笑)ナンバーでもある。
同じく「Out Of Silence」からの選曲である#7『Acroyali』。未だ訪れたことは無いが、メディタリニアン・ブルーに輝く地中海が瞼に浮かんでくるような、どうにも南欧らしいエスニックさを醸し出す電子鍵盤。まるでハープのようなチューニングをされているところが非常にグリークを臭わせる。前半の美しいソロから、ややゆったりとたゆたう春の海のように流れる後半の哀愁を含んだシンセアンサンブルも素晴らしい。
アップビートに展開する#9『Swept Away』は明るいポップナンバーであり、リズムマシンのビートとサンプリング・ピアノのややフェードを掛けた音色、そしてストリングスシンセが腕を組んでワルツを踊る。こういったナンバーを聴くとYanniというアーティストがメロディを最も大切にしている鍵盤奏者ということが良く分かる。
新曲の#10『True Nature』も実に明るく、そして繊細な良曲である。ハーモニカのような音色のストリングス・シンセがとてもノスタルジックであり、何処となく透明感の漂う欧州トラッドなラインも伺えて興味深い。非常にこじんまりとした小さなオーケストラとピアノの合奏という演奏風景画が浮かんできそうだ。
#11『Secret Vows』はかなりプログレッシヴで広い空間を演出するような雄大なシンセサイザ−が実に印象的な映画BGM的要素を持ったナンバーである。ここまで遠くまで広がる深遠や海原を視覚化できるサウンドを簡単に創り上げてしまうのだからYanniという人の才能は凄いと聴くたびに思う。
#13『A Word In Private』も映画のロマンティックなシーン、感動的なシーンでバックグラウンドに流れていそうな優しく美しいピアノバラード。当然シンセサイザーのストリングスが雰囲気を盛り上げる。Yanniが得意としている地中海的な透き通ったサウンドというよりも、もっと大地の懐を感じさせる暖かさに満ちたナンバーである。好きな映画の感動的な再会や別れのシーンを思い浮かべて聴くと感動が倍増する曲でもある。
どうアルバムの後半に好きなナンバーが集まってしまっているが、#14『First Touch』もシンプルで素朴。多分この曲ではアクースティックピアノが使われていると思うが、必要以上にダイナミックなキーボードアンサンブルを絡めずにピアノ一本で溢れるリリカリズムを表現しているところにまた別種の好感を覚えるのだ。
そして最後のタイトル曲であり、Yanniの代表曲とファンの間でも人気のある#15『Reflection Of Passion』。青く降り注ぐ月光に濡れた情景が浮かんでくるようなしめやかで玲瓏なソロパート。
抑えたストリングスをバックにコロコロと変調し表情を変えるピアノソロ。
そして、大きな腕に抱かれてゆっくり揺すられているような感覚を投げてくる広大なストリングス。
高いキーで精一杯歌うピアノに、甘く載っていく吹奏楽器のサンプリング。ハーモニカのような音色。
それらが、次第にフェイドアウトして静かな炎が消えていくように曲が終る。
取り立てて派手さの無い、#1等に比較すれば地味なのだが、とても心の琴線を打つナンバーである。
ここで紹介しなかった曲もどれも素晴らしい傑作ばかりである。どの曲もレヴェルが相当高い次元で纏まっているのはベストアルバムの面目としては最高の部類だろう。
普段ロックンロールばかり聴いているとアクースティックサウンドだけではなく、こういった巧みに創り上げられた精巧な鍵盤アルバムが無性に聴きたくなることがある。そういう時は、まずYanniのこのアルバムを聴いてリフレッシュするのは筆者の習慣にもなっている。
やたらなハードなロックや尖ったオルタナティヴに疲れを感じたら、美味しいお茶をすると思ってこういったインストゥルメンタル作品をゆっくりと聴くのも良いだろう。
その中でお薦めの筆頭の何枚かに位置するのがこの「情熱の回想」である。
アクースティック系でないのにかなり心を和ませ、落ち着かせてくれる筆者にとっての癒しアルバムでもある。
確かに、この15曲にはYanniの情熱が静かに熾火のように燃えている。 (2002.9.16.)

 Chris Alcaraz / Chris Alcaraz (1999)
Chris Alcaraz / Chris Alcaraz (1999)