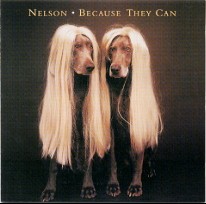 �@�@Because�@They�@Can�@/�@Nelson�@�i1995�j
�@�@Because�@They�@Can�@/�@Nelson�@�i1995�j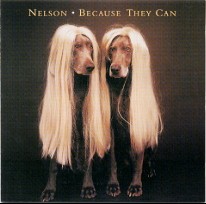 �@�@Because�@They�@Can�@/�@Nelson�@�i1995�j
�@�@Because�@They�@Can�@/�@Nelson�@�i1995�j
�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@WestCoast&Acoustic�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here
�@�@�n�[�h���b�N���玟��ɋ�����u���l�ɂȂ����̂́A�O�����W/�I���^�i�w���B�l�X������ɂ��̐��͂����߁A�k�A�����J�嗤�ɏ㗤���A����n�߂�1990�N��O���̍��������Ǝv���B���������̑��C���͖����M�ђ�C���ɂ��X�P�[���_�E�����邱�ƂȂ�����Ă���B���ɟT�������B
�@�@1980�N��̃|�b�v�ŃR�b�e���������W���[�q�b�g�`���[��������ɔ×����Ă��鎞�ɂ́A�h���ȃn�[�h���b�N���ǂ������o�܂��I�Ȍ��͂����Ă����̂ł������������Ă����B
�@�@�܂��A�����Ĉӎ����ăn�[�h���b�N��I�Ȃ��Ă�Hair�@Metal��Pop�@Metal�A������Light�@Metal�Ƃ������P��ɑ�\���ꂽLA���^����1980�N��㔼����S�������}���Ă������炾�B
�@�@�����A�O�����W��I���^�i�e�B���̒P�ɈÂ��A�l�K�e�B���Ŗ\�͓I�Ƀm�C�W�[�ȃT�E���h������ɂ��̗̈���g�債�Ă��������ɁA�n�[�h���b�N�͑S���K�v�̖������y�ɕω����Ă������B���̖{���̓n�[�h���b�N�ƃI���^�i�w���B�l�X�ł͈Ⴂ�͂��邾�낤���A�m�C�W�[�ŕK�v�ȏ�Ƀn�[�h�ȃM�^�[���g�p����Ƃ����_�͒��x�̂������ꎗ���Ƃ���������Ă���ƕM�҂͍l���Ă���B�܂��A�٘_�͑������낤���B���ۂɃn�[�h���b�N�o���h��Guns�@N�fRoses�͂��̌�̃w���B���b�N�̗����ɐ}�炸�Ƃ�����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���������邱�Ƃ����B
�@
�@�@�b��߂����A�k�ł����|�b�v�ŃL���b�`�[�ȃ����f�B���܂ǎ��ȃA�����J�����b�N�����̍s��������A�m�C�W�[�Ń_�[�N�Ńw���B�ȉ������o���n�߂�1990�N��́A�����ăn�[�h���b�N�����߂�K�v��g�̂������Ȃ��Ȃ����̂��낤�B�{�M�ł̓����f�B�A�X�E�n�[�h�ƏЉ���n�[�h���b�N�̃o���h�����܂�ɂ��`�[�����āA�S�R�����f�B���ǂ��Ȃ��������̂��w�ǂŃn�Y���̃A���o������������Ƃ����o�����l�K�e�B���Ȍ����̌㉟�������Ă��邯��ǂ��B
�@�@����Ȃ���Ȃ�90�N����܂�Ԃ����}����1995�N�ɂ́A�܂��w�ǃn�[�h���b�N�͕��u�v���C�ł������B���ɋ��߂čw������悤�Ȃ��Ƃ͋H�ɂȂ��Ă����̂��B
�@�@�ł��邩�炵�āA1990�N�ɁuAfter�@The�@Rain�v�Ƃ����n�[�h���b�N�n�A���炭�͎Y�ƃn�[�h���b�N�Ƃ����\�����ł���������Ƃ���앗�̃A���o���������[�X����Nelson��5�N�Ƃ��������̒��ق�j����2���ڂ\�����ƒm�������A���͐��������u�v���C�������肷��B�i���ۂ̓I�N������ƂȂ����uImaginator�v�����̃A���o���̑O�Ƀ��R�[�f�B���O����Ă��邪�A����͏��X�ڂ����t�@���ɂ͔n�̎��ɉ��Ƃ�炾�낤�B�j
�@�@���ǁA������������wAfter�@The�@Rain�x��w�iCan�ft�@Live�@Without�@Your�jLove�@And�@Affection�x�̂悤�ȃV���O���������邩������Ȃ��ƍl�������A���������Ɉ����ȗA���Ղ��w�������B
�@3������A2�Ȃ̃{�[�i�X�g���b�N�g���b�N�ړ��Ăœ��{�Ղ������Ă��܂��B�i�����j
�@�@���ہA1990�N��Ő�ɊO�Ղ��w��������A�M�Ղ̃{�[�i�X�ړ��Ăōw�������A���o���͐�����������Ȃ��B�܂����e�����́uBecause�@They�@Can�v�B������R�̃v���X���Ɏ䂩��čw������Hootie�@And�@The�@Blowfish�́uCracked�@Rear�@View�v�A���ꂩ��č�����A����Ƀ{�[�i�X�g���b�N�wTired�x���ʖڋȂƒm��i�č��̃��C���ʼn��x���������̂Łj���ÂŎ�ɓ���Ă��܂���Matchbox20�́uSomeone�@Or�@Yourself�@Like�@You�v�B���̂��炢�ł���B
�@�@��O��Ƃ��ă��W���[�Ŕ����A���o�����N���o�邲�ƂɌ������Ă��邵�A�̂�������A���Ղ��w�����邱�Ƃ��ȂɂȂ��Ă���̂ŕ��ꂪ���Ȃ��Ƃ͂����A2�������̋��s�����s�����������Ȃ��A���o���Ȃ̂��B
�@�@�܂��A�{�[�i�X�g���b�N���{�P�֎q�g���b�N�Ƃ����������啔���K�p�����X���������`���i?�j�ɋt����āA���́uBecause�@They�@Can�v���^��2�Ȃ͗�O���̗�O�I�ɑf���炵���lj��Ȃ����^����Ă����̂ŁA����͗\�����ʊ�тɂȂ����B
�@�@���ɁA#14�wAfter�@The�@Rain�e95�x�͍ō����B�I���W�i���̑S�ăg�b�v10�q�b�g�ɂȂ����wAfter�@The�@Rain�x���g�b�v40���b�N�V���O���i�n�[�h���b�N�ł͒f���āA�Ȃ��B�j�̌����̂悤�Ɋ��S�����̃|�b�v���b�N�������̂ő�D�����B
�@�@�������A���̃}���h�������n�߂Ƃ���A�N�[�X�e�B�b�N�y������C���ɂ��������A�N�[�X�e�B�b�N/�A���v���O�h�E���@�[�W�����ł́A�Y�ƃ��b�N�̌��h��R�[�e�B���O���ꂽ�����f�B�����X�R�A���g�̎��{���̗̉̂ǂ�����������Ă���Ǝv���B
�@�@�e���|���r�[�g���ꕔ�ύX�͂���Ă��邪�A��{�͌��Ȃ��X���[�_�E�����������̃i���o�[�ł���B�s�A�m�A�����o���W���[�A�����ăm���h�����Ƃ����^���̃A�N�[�X�e�B�b�N�`���[�������A���C���B��ł͂Ȃ��A�X�^�W�I�Œ��J�ɉ����I�[���@�[�_�u���Ă���̂�������B
�@�@���̃m�X�^���W�b�N�Ȑ��C�ݕ��R�[���X�ɐZ���Ă���ƁA�܂��ɏt�H�Ƃ����G�߂̒�����[���̉J�オ��A�}�C�i�X�C�I������C�ɖ������S�n�悢��C�̗��ꂪ�`����Ă���B���ꂱ���u�J�オ��v�Ƃ����ȑ�ɓK�����A�����W���낤�B
�@�@�܂��A�Z���t�E�J���@�[�ɂ͉��̃N�I���e�B���オ���������Ƃ����p�^�[�����������ŁA�����ɑS���V�����C���v���b�V������^���邱�Ƃ̂ł���V�ȂƂ��čĐ������Ă���B�W���^�̒P�ɃG���N�g���b�N���A�N�[�X�e�B�b�N�ɂ��������Ƃ����A���v���O�h�E���C���X�^�C���̘^���ł͂Ȃ��̂��B
�@�@�����Ă���1�Ȃ̃{�[�i�X�A#15�wNothing�fs�@Good�@Enough�@For�@You�@�iDemo�@Version�j�x�̓f���Ɩ��ł��Ă��邪�A���̌�̍�i�ŏЉ�͖����Ȃ���Ă��Ȃ��B�������A�f���Ƃ������Ƃ�Y�p���Ă��܂������Ɋ����x�͍����B����͌�q���邪�A���Ƀ\�t�g�œ�炩���A�����W�œZ�߂Ă������̃��W���[2��ڂ̒��ł́A���Ȃ�n�[�h�G�b�W�ȕ��ނɑ�����g���b�N�ƂȂ��Ă���B�i���x�̖��ł��邩��A����܂��n�[�h���b�N�ł͂Ȃ����낤�B�j
�@�@���J�ɗ���ꂽ�X���̋����A���o�����^�Ȃ������t�Ŕn�͂�����A�{�҂ɃI�t�B�V�����i���o�[�Ƃ��Ď��^������#11�wBe�@Still�x�ƕ���ŗǂ��A�N�Z���g�荞�ރ��b�N�g���b�N�ɂȂ������낤�B�f���ɗ��܂�A�ĔՂɎ��^����Ă��Ȃ��ܑ͖̖̂����B�܂��A�p�[�e�B�E���b�N�I�ȓc�Ƀ_���X���̖��t�������Ă���i���o�[�ł���A�x��ɂ͓K�������b�N�i���o�[��������Ȃ��B
�@�@�ƁA��Ƀ{�[�i�X�Ȃɕt���Č���Ă��܂������A���R�{�҂�13�Ȃ�����������ȏ�ɗǎ��ȃA�����J���E�|�b�v/���b�N�̃I���p���[�h�ł���B
�@�@�`���ɏq�ׂ��悤�ɁA1995�N�ɂ�HR/HM�͂�����ێ�̕K�v�������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA
�@�@�u�܂��A���ȃV���O�������̋Ȃ��y���߂�Ηǂ����B�v
�@�@�Ƃ������x�̊��҂Ńv���C���[�ɍڂ����̂����A
�@#1�w�iYou�@Got�@Me�jAll�@Shook�@Up�x�łԂ���сB#2�wThe�@Great�@Escape�x�ŏ���肵�i���^���n�łȂ����Ƃ��Z���ɂȂ����̂��j�A#3�wFive�@O�fClock�@Plane�x�ŗn�����B
�@�@�Ƃ����悤�ɁA�����Ƀm�b�N�A�E�g���ꂽ�B�����Ȍ����ł������B
�@�@�������A�������ŁA�N�����o���Ă���Ȃ����A�Ƃ����M�҂̊�]�����̂܂��̉������悤�ȃA���o�����������炾�B
�@�@���̃A���o��������́A�]�����������Ȃ߂�Ӑ}�͂Ȃ��̂����A
�@HR/HM��Nelson�͐����ă��V�I�I
�@�@�ƃA�b�T���]�сA�X��
�@�[���A���Ńf�����[���炱�����̕����ōs���Ȃ������̂��낤�H
�@�@�ƌ������^�₷�犴���Ă��܂����B�����A���̃A���o���̌��HR��A���ă����f�B�������i���o�[�𑽐��܂uSilence�@Is�@Broken�v�ƃI�N�����艹���uImaginator�v��2���́A�����ׂ��V���O���Ȃ͂���ɂ���A��������ł��܂���2���ɂȂ��Ă��܂����B���F��HR����̃A���o���ł����Ȃ��A�M�҂ɂƂ��ẮB
�@�@�uAfter�@The�@Rain�v�͎Y�ƃn�[�h���b�N�Ƃ��Ă͖��Ղɑ�����.�B�������܂��A���̂܂�HR�𑱂��Ă������ɁuNelson�����ă��V!!�v�ɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ����A1999�N�̍Ăѕ��������uBecause�@They�@Can�v���ɖ߂����uLife�v��2000�N�̃o���h����The�@Neslons�ɉ��������uBrother�@Harmony�v�̃J���g���[���b�N�ւ̌��_��A�ɂ��A�M�҂͍Ă�Nelson�ɒ��ڂ��Ă���B
�@�@��͂�AFirehouse�́uGood�@Acoustic�v�������[�ł����������Ƃ����A�����f�B�̗ǂ���j�Q���铭���͊ԈႢ�Ȃ��n�[�h���b�N/�w���B���^���ɂ͑��݂���B���́uBecause�@They�@Can�v�͂��̏؍���1���Ƃ��Ȃ��Ă��邾�낤�B
�@�@���āA���܂�̍앗�̈Ⴂ���甭�����~�ƂȂ�A�_��̃S�^�S�^�ƌ����ƂȂ���1993�N�����́uImaginator�v������ł��́uBecause�@They�@Can�v�Ɏ����������̂ɂ͂��Ȃ����]�Ȑ܂��o���悤�ł���B���̂��Ƃ́uImaginator�v�̓��{�Ճ��C�i�[�m�[�c�ɂ��ڂ����L����Ă���̂ł����ŃX�y�[�X���������Ƃ͂��Ȃ��B�������_�[�N�Ńw���B�ȋȂ̑����uImaginator�v�ɐ��쓖����Nelson�Z��̐S�������f����Ă��邾�낤�B
�@�@�������A1993�N�^���́uImaginator�v�ȍ~�ɂ��́uBecause�@They�@Can�v�̃i���o�[���S�ď����ꂽ���͐r���^��ł͂���B�Ƃ����̂̓f�����[��̃v���f���[�T�[�����ċ����\���O���C�^�[�Ƃ��Ă�Nelson�̃��R�[�h�쐻�ƃv�����[�V�����ɂ���v������Marc�@Tanner��Matthew��Gunnar�Z��Ƌ��삵�Ă���i���o�[��6�ȁB
�@�@�����āA1980�N��㔼���瓪�p��\�킵�A1990�N��ɂ����ă\���O���C�^�[�Ƃ���Peter�@Wolf�AY&T�AJohnny�@Van�@Zant�ACeline�@Dion�AAerosmith���ɋȂ���Ă���Taylor�@Rhodes��2�ȂɃy��������Ă���B
�@�@���̃\���O���C�^�[�w�̋��͂���ӂ݂āA���̃A���o���Ɏ��^����Ă���i���o�[�̑����́uAfter�@The�@Rain�v�̔����O��ɏ�����Ă������A�n�[�h���b�N�������ꂽ1st��̗���ɍ��v���Ȃ����ߓ��̖ڂ����邱�Ƃ��Ȃ������i���o�[�ł͂Ȃ��낤���Ɛ��@���Ă���̂����@�����낤?
�@�@�܂��A���������������͗ǂ��Ƃ��āA�܂��ɁuAfter�@The�@Rain�v�̃q�b�g�V���O���wAfter�@The�@Rain�x��w�iCan�ft�@Live�@Without�@Your�jLove�@And�@Affection�x�A�����āwMore�@Than�@Ever�x����K�v�ȏ�Ƀn�[�h���b�N�ł�����������������āA����ɃJ���g���[���b�N�A�A�����J���E�g���b�h�A�E�G�X�g�R�[�X�g�E���b�N�Ƃ�����n�̕��������ɂ����v�f���[�U�����i���o�[�������Ă���B
�@�@���R�̂��ƂȂ���A�����f�B�̃L���b�`�[���ƃN���e�B�J������1st�̃q�b�g�i���o�[���炻�̂܂܌p������Ă���̂ŃR�}�[�V�������Ɋւ��Č����A�����܂Ń|�b�v�ŗǂ��̂��A�Ǝv�킸�s���ɂ����邭�炢���S�����̃R�}�[�V���������ւ��Ă���B
�@�@���A�����b�Ȕ���ȃA�C�h���|�b�v�Ƃ��A�P�ɃM���M������������Power�@Pop�Ƃ��������̒Ⴂ�����F���ɗ��܂�Ȃ��E���g������|�b�v�ȃ��b�N�A���o�����B
�@�@�܂��A�A�[�V�[�Ȉ��芴�����邱�ƁB�܂��A���C�݃��b�N�̐�����������������Ă��邱�ƁB�����1970�N�ォ��r�ꂸ�ɑ����Ă���Westcoast�@Pop/Rock�̐����ȗ�����p���������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�����ĉ������A�P�Ȃ�|�b�v�łȂ����b�N�Ƃ��Ă̎����������݂��邱�Ƃ��B���̉ӏ���BB�@Mak�Ƃ��̃|�b�v�o���h�Ƃ̑傫�ȈႢ�ł���B�����ł̓n�[�h���b�N�Ɉꎞ��������Ă����e�����v���X�ɓ����Ă���Ǝv���B�������������Ƃ����ł͂Ȃ����̂ł���B
�@�@�⑫�����A���C�݃T�E���h�ƕM�҂͂��̃A���o���ނ��Ă���B���R�̂��ƂȂ���T�E���h�I�ɐ��C�݂̉e�����������炻���������̂����A�Q�����Ă���~���[�W�V�������܂����C�ݎ��ӂŊ������Ă��������Ȑl�B���������Ƃ�����Ɉ���Ă��邾�낤�B
�@�@�Ⴆ��Eagles��Timothy�@B�DSchmit�@�iB�DVocal�j��#1�A#2�A#3�A#9�B
�@�@2001�N��Eagles�����ق��ꂽDon�@Felder�@�iMandolin�j��#3�B
�@�@��Toto�̃L�[�{�[�f�B�X�gSteve�@Porcaro�iKeyboard�j��#3�D
�@�@Bread�̃I���W�i���h���}�[��Dan�@Fogelberg��Andrew�@Gold�Ƃ��������C�݃A�[�e�B�X�g�̃A���o���ɂ������Q�����Ă���Michael�@Botts�@�iDrums�j��#4�B
�@�@Doobie�@Brothers��Steely�@Dan�̃M�^���X�g�Ƃ��Đ����̕K�v���Ȃ�Jeff�gSkunk�hBaxter�@�iPedal�@Steel�j��#4�B
�@�@2000�N�ɃA���o���������[�X���Ă܂��܂������p������Andrew�@Gold���G���W�j�A�B
�@�@���C�݂ł͂Ȃ�����ǂ��ACars�̃M�^���X�g�ł�����Eliott�@Easton�@�iGuitar�j��#6�A#7�A#13�B
�@�@�ƁA���ɍ��ȃQ�X�g�w���Q�����Ă���B
�@�@�uAfter�@The�@Rain�v�Ńw���B���^���b�N�X��o�q�ƃL���Ă������̃o���h�����o�[�͂��ꂼ��ʂɋȂɎQ�����ANelson��5����6���̎Y�ƃn�[�h���b�N�o���h�Ƃ����X�^�C���͂��̃A���o���Ŋ��S�ɕ���A�{���̒��S�l���ł���Matthew��Gunnar�̑o�q�̃f���I�ɏW�����Ă���B
�@�@�������A�����܂Ŏ̂ċȂ��Ȃ��A�S�ȃq�b�g����A���o���͏��Ȃ��B�{�[�i�X�g���b�N���Ė{�҂����ōl���Ă��A#1�w�iYou�@Got�@Me�jAll�@Shook�@Up�x����#13�wNobody�@Wins�@In�@The�@End�x�܂ŃV���O���ɏo���Ȃ��̂�2�Ȃ̃C���X�g�D�������^���Ȃł���#6�wRemi�x��#9�wJoshua�@Is�@With�@Me�@Now�x���炢���낤�B
�@�@�������A�M�҂͂���2�Ȃ̏���i�͑�D���ł���A���ɃA�[�V�[�Ń_�[�g��#6�̓A���o���ł����H�[�J���Ȃ��܂ߕM���𑈂����炢�Ɉ������Ă���B���̃C���g��/�A�E�g���I�Ƀu���b�W�C���X�g�i���o�[�����ނ̂́uAfter�@The�@Rain�v�ł����l�̎�@������Ă����B���ł�#4-1�wTracy�fs�@Song�x�̃g���b�h�ȃm�����D���������M�҂ɂ͂��̓y�L���ƃg���f�B�V���i�����t�ȃA�����W�͊���Ȃ��B
�@�@�̎��ɂ��Ă��A���Ȃ萬����������Ǝv���B#10�wLove�@Me�@Today�x��#3�wFive�@O�fClock�@Plane�x�̂悤�ɒ��ړI�ȃ����E�\���O�����邯��ǁA�����E�\���O�ƐS�g�܂郁�b�Z�[�W�\���O�̒��ԓI�ȋȂ������B#2�wGreat�@Escape�x��#8�wOnly�@A�@Moment�@Away�x�̂悤�ȃi���o�[���������B
�@�@���C�g���^���E�̃A�C�h���I�Ȉ����Ńf�����[����Nelson�Z�킾���A���́uBecause�@They�@Can�v���特�y�I�ɂ��̎��I�ɂ��y���ȗ��s����E�p�����Ƃ������������B
�@�@�ǂ̃i���o�[���c�{��˂��܂���ŁA�u�ō��v�A�u���ɂ������ɖY��Ȃ��v�A�u���W�I���痬��Ă���̂����R���ɂ������Ƀ\�[�X��T���Ď�ɂ���ꂸ�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ����^����^����݂̂��B
�@�@���A���������e�Ȃ̂��C�ɓ���̕����ɐG��Ă��������B
�@�@�܂��A#1�w�iYou�@Got�@Me�jAll�@Shook�@Up�x�B��Ԃ̍D���ȃp�[�g�̓��X�g�̃M�^�[�\���ɑ����A�E�J�E�y���C���ɉ̂����uAnd�@Now�@I�fm�@All�@Shook�@Up�v�������Ŋ������p�[�J�b�V���ȃX�l�A�h�������}������鏊�B�ō��ɃO���[���ł���B
�@�@#2�wGreat�@Escape�x�̓R�[���X��������n�܂郍�b�N�����[���ȕ������R�[���X���삯���i�K�Ƃ���ȑO�̃A�N�[�X�e�B�b�N�ȑO�u�������̃M���b�v���ǂ��B
�@�@#3�wFive�@O�fClock�@Plane�x�̓I�[�v�j���O��Don�@Felder�̃}���h�����\���B�@�ׂŐ��X�����������}���h�����̌������ꗎ�������ȂƂ���B���ꂩ���uI�CI�CI�E�E�E�E�v��Ɂ�uWhy�CWhy�CWhy�v��̃R�[���X�̃��t���C���B�����͂��ꏏ�ɂȂ��ĉ̂��Ă��܂��B
�@�@#4�wCross�@My�@Broken�@Heart�x�͏��߂ďo������o���[�h�ł���B�܂��ASkunk���̃y�_���X�e�B�[���͕��喳���Ȃ͓̂��R�Ƃ��āAGunnar�@Nelson�̃n�C�g�[���E���H�C�X�������V�������炢���}���e�B�b�N���B�t�F�C�h�A�E�g�O�́�uUh�CUh�`�`�`�`�`�`�v��̃n�[���j�[�ł��o�Ȃ�����������o�����ƍA��m�炵�Ă��܂��B
�@�@#5�wPeace�@On�@Earth�x�͂���܂����C�ɓ���̕M���i�ɓ�����o���[�h�B���Ȃ�͋������A�N�[�X�e�B�b�N�̗��_�ƃJ���g���[�~���[�W�b�N�̓y�L�����Y�ƃ��b�N�̃o���[�h�ɗn�������悤�Ȑ[�݂Ƒ���������i���o�[���B�������̓��X�g�t���[�Y�ł�Matthew�̃V���E�g�B���ꂩ��u���b�W�����̃A�h�E���u�I�ȃ��H�[�J���ƃR�[���X�̃n�[���i�C�Y���R�����������čō��Ɋ�������B
�@�@#7�wWon�ft�@Walk�@Away�x�͑��e�V���O���Ƃ��ăJ�b�g���ꂽ���S���`���[�g�Ɍ��ʂ����f����Ȃ������B���̎��オ�����ł��}�g���Ȃ���Top40�ɂ͓��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��X�s�[�f�B�ȉ����q�b�g�H���̃��b�N�`���[�����ł���B���̃i���o�[���q�b�g���Ȃ��������A�{�i�I�ɕM�҂͕č����W���[�`���[�g�����������B
�@�@�e�Ɋp�A�u�₩�ȃR�[���X�A�n�[�h�|�b�v�Ƃ����\�����\�ȃI�[���@�[16�r�[�g�̃��b�N�i���o�[�ŁA�����ɖ�s�A�m��I���K���̉��F���D�����B�������v�������[�h�I��#6�Ƃ̃M���b�v���A�Â��瓮�ւ̒��W�����s�[�ł���̂��B
�@�@#8�wOnly�@A�@Moment�@Away�x�͍ł��D������������̎��ƃ����f�B�B�����ď�i�ɒe�����X���C�h�M�^�[���S�n�ǂ��A�ɏ�̃~�f�B�A���o���[�h�ŁA�S�����D���ł���B�吨�̍����R�[���X�Ő���オ��㔼����Ԃ̃n�C���C�g���B
�@�@#10�wLove�@Me�@Today�x�������E�ł������������Ȋ����ƃ��}���`�V�Y�������o��A�X�g�����O�X���g�p�����A�_���g�E���b�N�̌o�T�̂悤�ȋȁB�R�[���X�́�uI�fll�@Be�@On�@My�@Way�@Love�@Me�@Today�E�E�E�E�E�v��̊Â����H�[�J���p�t�H�[�}���X�͏�Ɉꏏ�ɉ̂��Ă��܂��B
�@�@#11�wBe�@Still�x�͑O�q�������A�Ƃ�����ΊÂ��f���P�[�g�ȋȂ̑����A���o���S�̂����b�N�����[���̃^�t���ň������߂���ʂ�����B�ґ�������A�����������������Ȃ��~�����������A�n�[�h���b�N���w�^�ɓ��������͑S�R�����ȕ����Ɍ������A���o���Ȃ̂ŁA����̊�]�͂���ȏ�q�ׂȂ����Ƃɂ��悤�B�U�N�U�N�Ƃ����X�e�B�[�����̎�G�肪�`����Ă���悤�ȃi���o�[���B
�@�@�����čł��D���ȃi���o�[#12�wRight�@Before�@Your�@Eyes�x�B�C���g���̃A���y�W�I�M�^�[�̔������B�Y��ȃo�b�L���O��悵�Ă����s�A�m�B��uI�@Hear�@You
!!�v����A�b�v�r�[�g�ɓ˂��i�މ����I�ȓW�J�BGunnar�̃\���E���H�[�J���p�[�g�̗��킳�B�����ȃA�N�[�X�e�B�b�N�ƃG���N�g���b�N�A�����ăE�G�X�g�R�[�X�Ƃ̃��j�]�����B
�@�@�Ō��#13�wNobody�@Wins�@In�@The�@End�x�̓n�C�L�[�ɑ������s�A�m���N���A�ɉ����o���Ă�����B�܂��Styx�̖��ȁwCome�@Sail�@Away�x�����A�N�[�X�e�B�b�N�Ɠy�L�����ۗ������čČ������悤�ȁA���̃A���o���̒��ł͍ł�1st�̎c��𗯂߂Ă���i���o�[���낤�B�㔼�̃X�g�����O�X�ƃM�^�[�̃o�g���͏��X�g�D�E�}�b�`��������Ȃ����A�Ō������ɂ̓_�C�i�~�Y���Ɉ��ėǂ��i���o�[���낤�B
�@�@���̌��W���P�b�g�����܂����Ƃ������A�V�ѐS������Ƃ������A����Ƃ��A�C�h���I�ȑ����������{�i�I�Ƀ\���O�I���G���e�B�b�h�ȃ~���[�W�V������ڎw�����Ƃ����C�T�̕\�ꂩ�B
�@�@�����܂Ń|�b�v�߂���Ȃ����ԂƁA�ӊO�ɑ����O���Ă��܂����Ƃ������̂����A�Ȃ̏��Ȃ��A���o���Ȃ̂ɉ����܂ł����x�����Ă��O���Ȃ��B�܂��A���ꂪ�u�₩�߂���Ƃ������X�i�[�͑������鑶�݂��邾�낤���ǁA����Ȃ��Ƃɂ͑S���S�D���Ȃ��B���̃A���o���̗ǂ���������Ȃ��͎̂��ɋC�̓łƕΌ��Œ��߂邾��������B
�@�@�����ƒP���ɃR�}�[�V�����Y���ɑ��邾���łȂ��A�A�����J�����[�c�E�J���g���[�ւ̖͍������m�Ȍ`�ɂȂ��Ă��Ă��邩�炾�낤�B
�@�@Counting�@Crows�ɏo���Ȃ�������ԈႢ�Ȃ����̃A���o����1990�N��10�N�ԂŃx�X�g�������B���ł��������h���C������ۂɂ͌������Ȃ��A���o���ł���B
�@�@���Â��ANelson���EHR/HM���Ă���ėǂ������A�Ə����ȍK�������ݒ��߂A�����uBecause�@They�@Can�v���Ă���B�@�@�i2002�D9�D21�D�j
 �@�@19�@/�@Chicago�@�i1988�j
�@�@19�@/�@Chicago�@�i1988�j
�@�@Adult-Contemporary�@�@�@��������
�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@Arena�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here
�@�@��������Chicago�t�@�������łȂ����y�t�@���̊Ԃł��U�X�c�_����A�����ς���J�r�������Ă��邱�ƂȂ̂ŁA1980�N��ȍ~��Chicago�̘H���ύX�A�{�M��AOR���ƕ\������鉹�y���̕ύX�ɂ��Ă̐���ɂ��ẮA���X�����̕��ʂ���Ƃ��������Ȃ��B
�@�@�Ƃ͂����A���́u19�v������ŁA��͂�1982�N��i�u16�v����̕������̓]���ɂ��āA�M�҂Ȃ�̌������q�ׂĂ��������Ǝv���B
�@�@���ԓI�ɂ́A�v���f���[�T�[�߂��瓪�p��\�킵�Ă���David�@Foster�ɕύX�����u16�v����Chicago�̕ϐ߂͎n�܂����Ƃ����ӌ��������悤�����A���ۂ́u�[�i8�j�v��u�]�i10�j�v�i�@��ˑ������̂��߁A�ꉞ�i���o�����O�����Ă������Ƃɂ���B�j�������Adult�@Contemporary���͑����i�s���Ă����悤�Ɏv����B
�@�@�ɏ����̃W���W�[�ł���A�r�b�O�o���h���ŁA�u���X���b�N/�z�[�����b�N�̗��s�ɍڂ����W���Y�E���b�N�Ƃ������y��W�J���Ă����f�����[�삩�琔����4���̍��Ƃ́A���ɑ����\�t�g���b�N�����Ă���̂�������ׂ�Ɨǂ�������B�m���ɊO�����C�^�[��Q�X�g�~���[�W�V�����𑽂��ق�����A�z�[���Z�N�V�������S���}������Ȃ��Ȃ������������Ƃ́u16�v�ȍ~�̑傫�ȕύX�_�ł���ɂ���A�u16�v���炢���Ȃ�Chicago���A�_���g���A�A�_���g���b�N�̌����ɉ�������ł͂Ȃ��ƍl���Ă���B
�@�@�m���ɁA�u�]�i10�j�v�̍���Chicago�Ɣ�ׂ�ƁA�u16�v����u18�v�܂ł�Chicago�͂���w�\�t�g���b�N�����i�s���Ă���̂͒��������낤�B
�@�@�܂��ADavid�@Foster�̏\���ԂƂ������ׂ��I�[�P�X�g���[�V���������Ȃ��Ƀt���[�`���[�����悤�ɂȂ��Ă���B���_�A����܂ł̃A���o���ł����ʓI�ɃX�g�����O�X��������Ă����o���h�ł͂���B�Ⴆ�A�wOld�@Days�x�̂���C�Ȃ��nj��y��̎g�p����A�wIf�@You�@Leave�@Me�@Now�x��A�X�Ɋnj��Ƀ��C���̃��C�����ʂ点���wBaby�CWhat�@A�@Big�@Surprise�x�ƁA�����ăX�g�����O�X�ɏ��ɓI�Ȏp�����������o���h�ł͂Ȃ������B
�@�@�����āA����͎���ƂƂ��ɓd�q���Ղ��i���������Ƃ��w�i�ɂ��邾�낤���A���h��̃L�[�{�[�h�T�E���h�����ɑ������Ă���B���Ɂu17�v��u18�v�ł̓X�g�����O�X�E�V���Z�T�C�U�[���܂߁A�����ȃp�[�g���L�[�{�[�h�Ō`����Ă���̂�������B
�@�@���̎����́A�O�҂ɂ��Ă͏��Ă̓X�g�����O�X�Ƌ��Ƀz�[���Z�N�V���������s���Ďg���邱�Ƃ����������̂ɁA�u16�v�ȍ~����3���̃u���X���̏o�Ԃ��������Ƃ����_�B
�@�@��҂ɂ����Ă̓s�A�m�ƃI���K���ɖw�ǂ̌��Ղ��ˑ����Ă����o���h���K�v�ȏ�ɓd�q���Ղ������ꂽ�Ƃ����_�A����������Chicago�̘H���ύX��Q����������̃t�@���͑����B
�@�@���Ƀu���X�Z�N�V�����̃E�G�C�g�����������Ƃ́A�܂���Chicago�̊�ł������z�[���T�E���h��ސF���������Ƃ��Č������ӌ���@���t����t�@���͑������݂���悤���B�ȑO�A�W���Y���b�N������Â��\�t�g���b�N�ւƕϊv�����}���������A���l�ɘH���̕ύX�ɑ��Ă̔ᔻ�������r�ꂽ�炵���̂ŁA�܂��A�����̂�����x�ł܂������[���̏ォ��E�����ĐV�������H�ɏ������o���h�ɂ͏h���I�ɂ��܂Ƃ��ᔻ�Ȃ̂��낤�B
�@�@�ł��邩�炵�āA��͂�Chicago�̃T�E���h���u16�v�����ɂ��ċ}���ɕϖe�����Ƃ͍l���ɂ����B�g�b�v10�A���o�������߂ē������Ƃ͂����A�q�b�g���L�^����12���ڂ̍�i�uHot�@Street�v�����Ȃ�̋C�͂�������Ŏ�Ԃ��}�����ӗ~��ł��邱�ƂƁA���̌�́u13�v��u�]�W�i14�j�v��Chicago�Ƃ��Ă͍ň��̃Z�[���X�I�s�k���i���Ă��܂��ڗ����Ȃ������̂ŁA�Ăя��ƓI�ɕ����яオ�����_�@�ƂȂ����u16�v���^�[�j���O�|�C���g�Ƃ��Ĉ�ۂ�����ɗ^���Ă���̂��낤�B
�@�@Robert�@Lamm�Ɍ��킹��Ɓu���鐡�O�v�܂ōs���Ă����u13�v��u�]�W�i14�j�v�̎���Ɣ�r����A�m���Ƀ��X�i�[�ɗ^����C���p�N�g�͑S���Ⴄ�B���������M�҂��A���o����Chicago����������ƒ����n�߂��̂́u16�v����Ȃ̂ŁA����Chicago�Ƃ����A�u16�v����Ƃ����C���[�W������B�u13�v�A�u�]�W�i14�j�v�����A�i���O�ՂŒ����Ă͂����̂����A�ǂ��ɂ��ς��Ƃ��Ȃ��A���o���ł��������Ƃ����o���ĂȂ��B
�@�@������A�u�]�i10�j�v���炢����Chicago���V���O�����S�ł������Ƃ͂����A���������Ă���M�҂ɂƂ��ẮA1980�N��̍D���ȃZ�[���X��Top40�q�b�g�̗ʎY�͊������������AChicago���Â��Ȃ����Ƃ����ᔻ�ɂ��Ă��������������̃u���X���b�N���オ��ǂ��Ȃ��߁A�ʂɈ�a����������Ă����B
�@�@�J��A�ŏ��ɁuChicago�@Transit�@Authority�v���n�߂Ƃ��鏉����i�������͂��̂��܂�̉��y���̈Ⴂ�Ɍ˘f�����o�������炢���B
�@�@�܂�A�M�҂́u16�v�ȍ~�̔ᔻ�h���q�ׂ�Ƃ���́u�V���O�������̋Ȃ��O�����C�^�[�ɏ�������v�A�u�q�b�g�_���̃A���o�����v�A�u�{���̎��������̂Ĕ�����_���ɑ������v�Ƃ����ᔻ�ɑ��ẮA
�@���y�������Ƃ������b�N�Ȃ��甄��ĉ�����������{�P�֎q�I�I
�@�@�ƍl���Ă���A�����uChicago�A�_���g���m��h�v�ł���B
�@�@�k�Ɉ����ȗ��s�����̂܂����ꂸ�ɁA���Ȃ��Ƃ��gChicago�̃A���o���h����ʂł���L���b�`�[�ȃA�����J���T�E���h��n���Ă������A������_���̉����������̂��A�ƕM�҂͍l���Ă��邩�炾�B
�@�@���ɁA1980�N��́u16�v����u19�v�͏��������̂悤�ȓƑn���̋����u���X�T�E���h������Ȏ��Ȏ咣������i���o�[�͖w�ǖ�������ǁA�����܂ł��������o���[�h�𑽐��r�o��������Ƒ����Ă���B
�@�@�ł��V���O���q�b�g�𑽂����̂͂���4���A���Ɂu17�v�Ɓu19�v�ł��邪�A�����Ƀ`���[�g�E�|�W�V��������v�Z����ƍō��̃q�b�g�V���O���̃v���b�g�z�[���ƂȂ����̂͂��́u19�v�ł���B�u19�v�̔����̗��N��3���ڂ̃x�X�g�ՂƂ��ă����[�X���ꂽ�uGreatest�@Hits�@1982�|1989�v���烊�~�b�N�X���ăV���O��������A�S�đ�5�ʂ܂ŏ㏸�����wWhat�@Kind�@Of�@Man�@Would�@I�@Be�x�܂Ő�����ƁATop10�V���O����4�Ȃ�����Ă���̂��B
�@�@���A���̂��A���o����Top40�ɂ�����Ȃ��Ƃ����s�v�c�Ȍ��ʂƂȂ��Ă���B�u�]�W�i14�j�v�ȗ��̃I���W�i����Ƃ��Ă�Top40������i�ƂȂ��Ă���B�ł��V���O���I�ɂ͔��ꂽ�̂ɁB
�@�@�����������`���[�g�A�N�V�����͂��̎�̃}�j�A�ɘ_���邱�Ƃ�C����Ηǂ����낤�B�����ł́u19�v�ɂ��Č���Ă����ׂ����B
�@�@�u���X���b�N�F����w����A�A�_���g�E�R���e���|�����[�����i�s�����Ɣ��f�����1980�N���Chicago�̍�i�̒��ł��A���́u19�v�͍ł����قȏꏊ�Ɉʒu����o���h�ł���ƕM�҂͍l���Ă���B��{�I��Adult�@Contemporary�Ƃ����������̍����ɂ͕ω��͖����̂����A����ł��u16�v����u18�v��3����Top40�A���o���ƕ��ׂĂ݂�ƁA��͂�u19�v�ِ͈F�Ƃ͂����Ȃ�����ǂ��A���قȂ�F�����̌�����1���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�@����́u16�v����18�v�܂ł���|����David�@Foster���u19�v�ł̓v���f���[�T�[�Ƃ��đS���A���o������Ɋւ���Ă��Ȃ����Ƃ��傫���B
�@�@���̃A���o������|�����̂́AHeart���n�߁AUFO�AOzzy�@Osbourne�AMichael�@Schenker�@Group�ADamn�@Yankees�ABad�@Company�AThe�@Babys�AEurope�Ƃ�����Ƀn�[�h���b�N/�A���[�i���b�N���̃v���f���[�T�[���C���ASurvivor�AEddie�@Money�AJefferson�@Starship�AKiss�AJoe�@Cocker�Ƃ������H�[�J���n�̎Y�ƃ��b�N�̃A���o������|���Ă���ARon�@Nevison���q�b�g�V���O���S�Ă�4�ȁB
�@�@�����ăV���O���J�b�g����Ȃ������i�j6�Ȃ�Chas�@Sandford�Ƃ����l���S�����Ă���BChas�͂ǂ��炩�Ƃ�����1980�N��̓Z�b�V�����~���[�W�V�����Ƃ��ĎY�ƃ��b�N�n�̃A���o���ɎQ�����Ă���ꍇ���������A�����Y�ƃ��b�N�����t���Ă���Jimmy�@Barnes�̃v���f���[�T�[�����o�����Ă���B
�@�@David�@Foster�̃v�����[�g���鉹�y�ɍ����̃}���l�����������̂��O�����̂��A���̕ӂ̓����o�[�̃R�����g����͐��m�Ȃ��Ƃ͗ʂ肩�˂�B
�@�@�����A�A���o��������A���Ɏ��̃I���W�i���A���o���ł���uTwenty 1�v�̍��̃C���^�����[�ł́A�ł������o�[���A���o���쐻�ɃR�~�b�g�ł��Ȃ������Ƃ����s�������o���Ă���B����͉��t�ʂɂ����Ă��Ȃ̍쎌��Ȃɂ����Ă��A�S�Ăɓn���Ă̂��Ƃ炵���B
�@�@�����������Z�[���X�T�C�h�y�у}�l�[�W�����g�T�C�h�ɗp�ӂ��ꂽ�}�e���A����Chicago�̖��O�ʼn��t���������A�Ƃ�����������A���́u19�v���Y�ƃ��b�N�̌����ƌĂ�Ŗь�������t�@���������ƕ����B
�@�@�m���ɁARon�@Nevison��Chas�@Sandford�Ƃ����Y�ƃ��b�N/�A���[�i���b�N�Ŋ�������v���f���[�T�[���R�[�f�B�l�C�g�������������āA�����ɃT�E���h�I�ȈӖ������ł����̃A���o���́A�A���[�i���b�N�F������ł���B�A���o���̊����Ɏ���ѐF�܂ŎY�ƃ��b�N��F�ɐ����Ă��܂����Ƃ���������Ɗ�Ɉ�v����Ƃ���͖ʔ������R���낤�B
�@�@�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�Â��A�A�_���g�|�b�v�ȃT�E���h�ӂƂ���David�@Foster�̎�@�Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�ʂ����݂���B
�@�@�����Œf���Ă��������̂́A�M�҂͐���̉ߒ����ǂ��ł��낤�ƁA���́u19�v�͔��Ƀ����F���̍������b�N�A���o���Ƃ��ēZ�܂��Ă���Ǝv���A1980�N���Chicago�̍�i�ł͈�ԕ]�����Ă���B
�@�@�u�\���O���C�^�[���ߔ����ȏ�O������̎Q���v�Ƃ��A�uChicago���n�����A���o���ł͂Ȃ��A�̂킳�ꂽ�A���o�����v�Ƃ�����@�ɂ��Ă͐����ǂ��ł��ǂ��B�T�E���h�����C�ɓ���Ζ��Ȃ����炾�B�ǂ��炩�Ƃ��Ɖ��ʂ̌������u16�v��Z�܂�Ɍ�����u18�v���������x�͗y���ɍ������낤�B
�@�@�ȉ��A�e�ȂɐG��A�u19�v�����̓��{�Ō����gAOR�V�J�S�h�Ƒ���_���q�ׁA�����Ɏv���Ƃ����f���o���Ă������Ƃɂ���B
�@�@�܂��A��ɏq�ׂ��悤�ɁA�Y�ƃ��b�N�Ƃ��Ă��Ȃ�T�E���h�������̂��郍�b�N�����[���ɔ�d��u�����A���o���ƂȂ��Ă���̂��傫�ȓ������낤�B
�@�@1980�N���Chicago�́uChicago��Ballade�v�ƃ��f�B�A����^�y�ѝ������ꂽ�悤�ɁA�o���[�h���ڗ���Adult�@Contemporary�o���h�Ƃ��Ă̐��i��1970�N��㔼�ȏ�ɑS�ʂɉ����o���Ă����B�A�b�v�e���|�̃q�b�g�Ȃ͖w�Ǒ��݂��Ȃ����߁A���̖ʂ�����A�_���g�����ă��b�N���痣�ꂽ�Ƃ����ᔻ�����X�������B
�@�@�m���ɁA�u16�v�ȍ~�̃A���o���ł̓A�b�v�e���|�ȃ��b�N�i���o�[�͔��ɏ��Ȃ��A�~�f�B�A���E�i���o�[���x���Ȃ��唼���߂Ă���B���̓_�ł͂��́u19�v�����̃A���o���Ɩw�Ǖς��Ȃ��B�w�ǂ��~�f�B�A���e���|������Ńo���[�h�ɌX�����i���o�[�ł���B
�@�@�������A�T�E���h�v���_�N�V�����̈Ⴂ���낤�A���́u19�v�ɂ̓��b�N�����[��������������Ȃ������B
�@�@#1�wHeart�@In�@Pieces�x�A#3�wI�@Stand�@Up�x�A#8�wRunaround�x�Ƃ����i���o�[�͌y���ł���A�ɒ[�ȃA�b�v�r�[�g�ȃi���o�[�ł͂Ȃ��̂ɁA���b�N�����[���Ƃ��Ă̑��b�̌������\���ɔ������i���o�[���B
�@�@���ɁA#1�wHeart�@In�@Pieces�x��Danny�@Seraphine�̐▭�ȃh�����E���t�����Ƀ��Y�~�J���ł���AJason�@Scheff�̎�X�������H�[�J�����V�N���B�O��u18�v�Ŗ��ȁw25�@Or�@6�@To�@4�x�ɓD��h��悤�ȃn�[�h���^���E�A�����W���̂킳�ꂽ���̓A�b�v�e���|�ȃ`���[���𖢂���I���Ă��Ȃ������V���H�[�J���̖��͂������Ŋy���߂�B
�@�@#3�w�h�@Stand�@Up�x���p���t���ȃu���X���b�N�E�`���[���ł���A1980�N��͊��S�ɗ����ɉ��V���O���Ȃ�1�Ȃ��̂킹�ĖႦ�Ȃ�����Robert�@Lamm���������݂ł��邱�Ƃ������悤�Ƀt�b�N�̌������W�����s�[����グ��Ȃł���B
�@�@#8�wRunaround�x�͂��̃A���o���ŗB�ꃁ���o�[�����őn��グ���i���o�[�ł���B���C�^�[��Jason��Bill�@Champlin�ł���B���ɃL���b�`�[�ŃV���O�������Ă��ǂ������~�f�B�A���|�b�v�i���o�[�BJason�̃n�C�g�[���ȃ��H�[�J����Peter�@Cetera�Ƃ͎����Ⴄ���������Ɉ��Ă��ėǂ��B�o���[�h�����łȂ��A�����������i���o�[���̂��邱�Ƃ����͂ŏؖ����Ă���B
�@�@�������A�ł��d�����b�N�i���o�[#5�wCome�@In�@From�@The�@Night�x�͊m���ɉs���t�@���N���o���ڂ̃A�[�o�����b�N�E�`���[���Ȃ̂����A����̓o���[�h�ɕ�Ƃ�����ۂ�����邽�߂ɂ킴�Ǝ_���̌������Ȃ���ꂽ�Ƃ����킴�Ƃ炵�����@�ɂ��̂ŏo���͈����Ȃ�����ǂ��D���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�u16�v�́wBad�@Advice�x�ƋȒ����g���b�L���O���ꂽ���R�����Ă���悤�Ɏv����͍̂l���߂����낤���B�������A���[�h���H�[�J����Bill�@Champlin�Ƌ��ʓ_�܂ł������肷��̂����B
�@�@�܂��A#8�ŐG�ꂽ�̂ł����ŋ����Ă��܂����A�O�����C�^�[�̓������ł������̂��u19�v�̓����ł�����B�O��u18�v�ɂ��Ă�����܂ł̃��C�����C�^�[�ł�����Peter�@Cetera���E�ނ������߂���܂ňȏ�ɑ��̃��C�^�[�Ƃ̋��삪�ڗ��������{��͂���ȏ�B
�@�@����܂��uTwenty 1�v�̔�����Ƀ����o�[���F�X�Əq�ׂĂ��邪�A�����o�[�̃��C�e�B���O������������21���ڂ̃A���o���͂��Ȃ�s���D�Ȗ}��ɗ��������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA��͂肱���܂ŊO���ɗ��邱�Ƃ͖�肩������Ȃ����A�o���h�O�̃\���O���C�^�[�ƃy�������邱�Ƃ͌ł܂����o���h�ɐV�����ʕ��E���J����Ӌ`�͂������ƍl���Ă���B
�@�@�Q�l�܂łɊO�����C�^�[�����ŏ����ꂽ�Ȃ�
�@�@#1�@Tim�@Feehan�@/�@Bryan�@MacLead
�@�@#2�@Diane�@Warren�@/�@Albert�@Hammond
�@�@#6�@Diane�@Warren
�@�@#9�@Jim�@Scott
�@�@#10�@Mark�@Jordan�@/�@John�@Capek
�@�@�Ɖߔ������߂�B�c��̃i���o�[�������o�[���ւ���Ă��邾���Ƃ�������������#7�wWhat�@Kind�@Of�@Man�@Would�@I�@Be�x�ł�Jason�ȊO�ɂ�Chas�@Sandford�Ɠ��{�ł͐l�C�̍���AOR�V���K�[Bobby�@Coldwell����҂ƂȂ��Ă��邵�A#5�ł�Bruce�@Gaitsch���A#4�ł͉f��Top�@Gun�̃T�E���h�g���b�N����|�����v���f���[�T�[��John�@Dexter���N���W�b�g����Ă���B
�@�@Diane�@Warren��Albert�@Hammond�ɂ��Ă͍��X����͕K�v�Ȃ����낤�B
�@�@�����l����Ɗm���ɑS��No�D1�q�b�g�ƂȂ�N�ԃg�b�v�̃V���O���ƂȂ���#6�wLook�@Away�x��S�đ�3�ʂƂȂ�A�u���E�s�v�c�����v�̃G���f�B���O�e�[�}�ɂ��g�p���ꂽ#2�wI�@Don�ft�@Wanna�@Live�@Without�@Your�@Love�x�Ƃ�������q�b�g�ȁA�����ăg�b�v10�q�b�g��#9�wYou�fre�@Not�@Alone�x�܂ł������l�̃i���o�[�ł���B
�@�@Chicago�̃A���o���ł͂Ȃ��A�Ƃ�������������C�͂���ǂ��A��͂肵�傤�ނȂ��i���o�[���I���W�i���ŕ��ׂ�����O�����C�^�[�Ƃ́g������Ɓh�𑝂₷���Ƃ͗ǂ����Ƃ��ƍl���Ă���B�{���������A�q�b�g�����ǎ��ȃV���O�����y���߂�Ζ��Ȃ��Ǝv���B
�@�@���A�����o�[�����ɂ����p�����̂��ACD����v���X�ɂ̓\���O���C�^�[�̃N���W�b�g�����݂��Ȃ��B����܂ł͂ǂ̃A���o���ɂ������ƃ\���O���C�^�[���L�ڂ��Ă���Chicago�������̂ɁB�����Ƃ��A�i���O�Ղ͂ǂ��Ȃ��Ă������͒m��Ȃ��̂ʼn��Ƃ���������B
�@�@���ɁA�Y�ƃ��b�N�Əd�Ȃ�v�f�ł��邪�A���̃A���o���ł͓d�q���Ղ̐�߂銄�������ɑ����B����܂ł̓A�_���g�������V���Z�T�C�U�[���s�A�m�܂��̓s�A�m�T���v�����O��\�ɉ����o�����A�����W�����������|���Ƀo���[�h�ɂ����ā|Chicago�����A�18�v���瑝���̌X���ɂ������L�[�{�[�h���傫���̈�𑝂��Ă���B
�@�@#6�wLook�@Away�x�A#2�wI�@Don�ft�@Wanna�@Live�@Without�@Your�@Love�x�A#9�wYou�fre�@Not�@Alone�x�A#10�wVictorious�x�ł̓s�A�m�T���v�����O�̋[��������w�ǒ������Ȃ��B����܂ŁwHard�@To�@Say�@�h�fm�@Sorry�x��wHard�@Habit�@To�@Break�x�A�wYou�fre�@My�@Inspiration�x���ł̓A�N�[�X�e�B�b�N�s�A�m��s�A�m�T���v�����O�����C���ɐ����Ė���o���[�h�����������Ă����������Ƃ͂��Ȃ�قȂ�B
�@�@#4�wWe�@Can�@Last�@Forever�x��#7�wWhat�@Kind�@Of�@Man�@Would�@I�@Be�x�ł̓s�A�m�T���v�����O���g�p����Ă���Ƃ͂����A���S�ɓd�q���Ղƕ�����T�E���h�v���_�N�V�����ł���A�����ăA�N�[�X�e�B�b�N�s�A�m�̑@�ׂ����o�����Ƃ���w�͕͂�������Ă���͗l�ł���B
�@�@�u16�v�ȍ~���V���Z�T�C�U�[�𑽐��g�p���Ȃ�����ǂ��ƂȂ��I�[�K�j�b�N�ȗD�������ڗ�����Chicago�̉����A���́u19�v�ł̓A���[�i���̃R�b�e���ƌ��ڂ̃T�E���h�Ƃ��Ă�������G���N�g���j�Y���ɑg�ݓ�����Ă��܂��Ă���B
�@�@�������A���̂��߂ɔ��Ƀ^�C�g�ŏd���Ȏd�オ��ɂȂ�A���ʂƂ��ă��b�N�����[���̗͂������Ă��邽�߁A�꒷��Z�ł��낤�B
�@�@�������AChicago�̊ŔƂ�������u���X�Z�N�V�������A���Ȃ�f�W�^��������Ă���悤�Ɋ�����B
�@�@�u16�v���炱�����A���Ȃ�e�������ƂȂ��Ă��܂���3���̃u���X�o���h�ł��邪�A1980�N��̃A���o���ł͂��́u19�v����ԏo�Ԃ������Ǝv���B������ӊO�Ɋ�����������邾�낤���A�u16�v��u17�v�ł͑S���z�[��������Ȃ��i���o�[�����Ȃ葶�݂��A���̖ƍߕ��̔@���s���R�Ƀz�[�����ۗ������i���o�[�������Ă����Ƃ��������A���o���̍\�����l����Ƒ����C������B�Ⴆ�wHard�@To�@Say�@�h�fm�@Sorry�x�ɑ���wGet�@Away�x�̂悤�ɁB
�@�@���A�u19�v�ł̓z�[�����X�̋Ȃ�#9�wYou�fre�@Not�@Alone�x�����ł���B���̃i���o�[�ł͑����ꏭ�Ȃ���z�[�����g�ݍ��܂�Ă���B#10�̂悤�Ɉ�u�����g�p����Ȃ��Ȃ����邪�B
�@�@#1�A#3�A#5�A#8�̂悤�Ƀ��b�N�^�C�v�̃i���o�[�ł͂��Ȃ�z�[�����t���[�`���[����Ă��邵�A�o���[�h��#7�ł͈�ۓI�ȃI�[�P�X�g���[�V�����E�A���T���u����������B�������A���~�b�N�X���ꂽ�V���O���E���@�[�W�����ł͉���Ȃ��\���̃T�b�N�X�Ƀ��e�C�N����Ă��܂��A����͍��ł��������������E�E�E�E�B
�@�@�o���[�h�ł�#2�̂悤�Ɍ㔼�����Ƃ��A#4�̂悤�ɃR�[���X���������A�����#6�̂悤�ɖw�ǖڗ������A�V���Z�T�C�U�[�̉��ɉB��Ă��܂��ȂǁA��͂�e���ł͂��邯�ǂ���B
�@�@�Ƃ��낪���́A���̂悤�Ƀz�[���͂���Ȃ�Ɋ��Ă���̂ɁA�w�ǖڗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B
�@�@�����ɎY�ƃ��b�N�������u19�v�̃}�C�i�X�ʂ�����B
�@�@����́A�z�[���̃A�����W���V���Z�T�C�U�[�ɂ��[���z�[����L�[�{�[�h�ɂ��X�g�����O�X�V���Z�̉��Ƃ��܂荷�ʉ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃ��B�܂�u���X�p�[�g���L���郔�B���B�b�h�ȃA�i���O���o���f�W�^����������Ă��܂��Ă��邽�߁A���NJy��̊��������Ƃ���������������Ă��܂��Ă���̂��B
�@�@�ɒ[�Ȍ�����������A���̃v���_�N�V�����Ȃ�V���Z�z�[�������ŃA���o�����쐻�\�Ƃ������ƁB���u���X���͕K�v�������܂芴�����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��B
�@�@�܂��A�����������Ȃ�C�ɂȂ����̂́ABill�@Champlin���啝�Ƀ��[�h���H�[�J���X�g�Ƃ��Đ��͂��g�債�Ă��邱�Ƃ������BPeter�@Cetera�ݐȎ��́ARobert�Ɠ��������S��2�Ԏ胔�H�[�J��������Bill�B�u18�v�ł��V�����̈���ȏ�N��̈ႤJason�@Scheff���Љ��K�v���������̂��낤���A�ł��o�Ԃ̑����������H�[�J���X�g��Jason�ł������B
�@�@���A�g�b�v10�V���O��3�Ȃ͑S��Bill�̃��H�[�J���BJason�͓��R�J�b�g�����Ɨ\�z���Ă������̃A���o���ł͈�ԏo���̗ǂ��o���[�h#7�ł͂Ȃ��A�����#4�ŃV���O���Ȃ��ꂽ�����������B�i�q�b�g���g�b�v40�����B�j
�@�@�����A�M�҂̑�D����#2��#6��Bill����Jason���̂��ׂ��i���o�[�ł���Ǝv�����A����܂ł�Chicago�Ȃ�ԈႢ�Ȃ��n�C�g�[���E���H�C�X�̃��H�[�J���ŏ�����q���邾�낤�B�����炵�āA���̂�Bill�@Champlin�������܂ň������Ă�ꂽ���͕s�����B�V���O��4�Ȃ̒��ŁA�A���o���E���@�[�W�����Ƃ��Ȃ�A�����W�̈قȂ�#9�wYou�fre�@Not�@Alone�x��Bill�����ł���Ǝv�����B
�@�@�������A���̃A���o���ł̊���ɂ��ABill�@Champlin���\���Ńo���[�h�����������̂���Ƃ��ĔF�����ꂽ�Ƃ����_�ł͌��т͂���ƍl���Ă��邪�B
�@�@�������A#5��#10�ȊO�͑S�ăV���O���ɂł���|�e���V�������������̂ɁA�A���o���̃Z�[���X�����܂����Ȃ��߂��A�J�b�g��4�Ȏ~�܂�ƂȂ��Ă��܂����B�i��Ƀx�X�g�Ղ���#7�����~�b�N�X����ăq�b�g����̂͋L�q�����ʂ�B�j
�@�@�Y�ƃ��b�N�Ƃ��ĕK�v�ȏ�Ɍ����AChicago�Ƃ��Ă͂��َ��̃��b�N�A���o���Ɋ������Ă��܂����̂ŁA��������̃t�@�����h�������̂��낤���B
�@�@�A�����W�̕��������ς���������ŁA���Ԃ�1980�N���Adult�@Contemporary��Chicago�̊����_�ɒB�����A���o�����Ǝv���̂����B
�@�@�J��Ԃ����A���b�N��i�Ƃ��Ắu13�v�ȍ~��Chicago�ł͍ō�����ł���Ǝv���BChicago�炵���Ƃ����̂���̃o���h���������Ă������y������͈�Ԉ�E������i�ł�����Ǝv�����B
�@�@����ɂ��Ă��A���̃A���o���ȍ~�A�I���W�i�����1991�N�́uTwenty 1�v�݂̂ł���B1990�N��͔��X�̃x�X�g�Ղ𖼑O�ς��A�Ȗڂ�ς��̃����[�X�ɏI�n�����o���h������ɂ��A�ǂ��ɂ���邹�Ȃ��C�����ɂȂ�B
�@�@�x�X�g�Ղ�����Chicago�̃J�^���O�i���o�[�������Ă����̂�����̂ɑς����Ȃ��t�@���͑������낤�B
�@�@����A�ߓ������\�肩�玞�Ԃ��~�܂��Ă��܂����悤�ȁu27�v�ł́A���́u19�v�̂悤�Ɋ����̃C���[�W��j��|�b�v�Ń��b�N�ŐV����Chicago�������ė~�����ƐS����肤�B�@�@�i2002�D9�D26�D�j
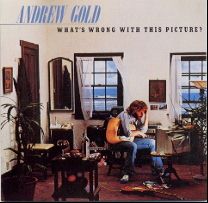 �@�@What�fs�@Wrong�@With�@This�@Picture�@?
�@�@What�fs�@Wrong�@With�@This�@Picture�@?
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@Andrew�@Gold�@�i1977�j
�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@WestCoast�@�@��������
�@�@����A�Ƃ���R���r�j�G���X�X�g�A�[�ŁA�T���G���𗧂��ǂ݂��Ă����i�����I�I�j��A�X����BGM�p�X�s�[�J�[���班���h���C�Ōy�߂Ș^���̃s�A�m���y���ɒ@�����A���z�I��Pop/Rock�̃C���g��������ė��܂����B
�@�@�p�[�J�b�V�������s�A�m�Ƀ��Y�������킹�A�x�[�X�A�����ăM�^�[����Œn���ɃT�|�[�g�����邱�̋Ȃ́AAndrew�@Gold�̎��I��Ԃ̖��ȁwLonely�@Boy�x���Ⴀ�A���`��܂���J�i���Ή��j�A�Ǝv���A�v�킸�������𗧂ĂĂ��܂������̂ł��B���̃i���o�[��1970�N��̐��X�̖��ȁE�q�b�g�Ȃ̔��M���ƂȂ������C�݂̃E�G�X�g�R�[�X�g�\���O���ŋ��w�̃|�b�v���b�N�ł���Ǝv���Ă��邩��Ȃ̂ł����B
�@�@�����A�������A���҂ɋ���c��܂��A���H�[�J��������̂�҂��Ă�����A���̏u�ԓޗ��ɗ��Ƃ���邱�Ƃɑ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���܂��B�Ƃ����̂�
�@�̂��Ă����̂��A���{�l�̎�I�I
�@�@�܂��A����Ńw�{�w�{�ȉp�ꔭ���ʼn̂�����A���{��Ō����̂�������Ȃ�ڂ��}�V�ł��邩������܂��A���F�͂ǂ������N�\�Ƃ����̂ɂ͕ς�肠��܂���B�i�����j�ڕ��@�����Ȃ��Ƃ������c�ł��傤�B�i��j
�@�@�X�ɁA
�@�I���i�̃��H�[�J���I�I
�@�@�������A�@���l�܂����悤�Ȏ���������Ƃ͂����肹����
�@�����̂��Ă���̂��T�b�p��������܂���I�I
�@�@�S�_�o���W�����ĉ̎�����낤�Ƃ������A�ʖځB�g�쁜�i�⎛�������Ȃ݂̃{�\�{�\���B�i����&�Â��j
�@�@�g�h����
�@�R�[���X����uOh�CWhat�@A�@Lonely�@Girl�v��I�I�x�^�߂��I�I�[���Z���X�F���B
�@�@���Ȃ͉̎������ɏG��ȁu���v�A�u����v�ƌĂׂ邭�炢�ȉ̂Ȃ̂ł��B�w�lj̎����������Ȃ������̂𗧂��ǂ݂��~�߂āA���Ƃ����͂悤�Ȋ����ł͂����Ȃ����Ȃ��̂ł����i���j�A�I���W�i���̃A�C���j�J���Ɠ����ɃA�h���b�T���X�ȉ̎������S�ɔj�������Ă���悤�ł����B���Ȃ��Ƃ����Ȃɒ����ȉ̂ł͂���܂���ˁB�ǂ���烉���E�\���O�������\���O���ۂ��ł��B
�@�@�J��Ԃ�����ǁA��ϒ������ɂ��������̂Ő��m�ȃR�����g�͎c���܂��B
�@�@�[���A
�@���ŁA�p��̉̂̕����A�ꍑ��̉̎���蕪����Ղ��Ⴂ�I�H
�@�@���̉̎��������\���O���C�^�[�ƁA���Ȃ��w�i�`���R�ȃ��H�[�J���ʼn̂������̎��
�@���͂Ƃ�����A���@���@�ā@���@�V�@�I
�@�@��́A�wLonley�@Boy�x�̑ւ��̂ŁA�^�C�g���͒m��Ȃ�����uLonely�@Girl�v�Ɖ̂킹�邱�Ɓ|�ǂ����^�C�g�����w���^�̃������[�E�K�[���x�Ɍ��܂��Ă���ł��傤���ǁ|�Ŋ��ɏI����Ă��܂��B���Ȃɒ����ɕ킦�Ƃ܂ł͌����܂���B���A�ǂ����Ȃ犮�S�ɕʂ̉̂ɂ��Ă��܂��ΒP�Ȃ郁���f�B�̎ؗp�ŏI����āA�A�z��Ȃ��A�Ə��ďI����̂ɁB
�@�@���ꂱ���A���r���[�̃��N�f�i�V�Ƃ����T�^�ł��傤�B
�@�@�Ƃ��������A�̎��̖{���܂ŕς��Ă��܂�����A���ɃJ���@�[�E�\���O�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�ւ��̂ɂ����߂����A�C�����m�ɋ������ނ���܂��A�M�҂̒��ł́B
�@�@���{�ɂ͐�����Ȃ����炢�����^��ł��Ă��Ȃ�̓��{�ʂł���Andrew�@Gold�ɎӍ߂���I�I�I
�@�@�܂��A����JPOP��Œ����Ă��鐢�オAndrew�@Gold�́wLonely�@Boy�x��m���Ă邩�Ƃ����A���������̓l�K�e�B���ł��傤�B�܂�A�p�N���Ƃ������e���v���̈߂�����Ă��āA���g�̋�̓X�J�X�J�ȑ��݂��A�u�����A�ǂ��̂�Ȃ��B�v�ƒ����Ă���̂ł��ȁB�܂��A���m�͍ō��̍K���Ƃ����܂����A�x����Ă��邱�ƂɋC�����Ȃ��̂͒[���猩��ƂĂ��C�̓łŗ܂����傿���܂��B
�@�@�������AAndrew�@Gold�͖��i�g�̃v���f���[�T�[��1980�N�㔼�����肩��1990�N�㏉�߂��炢�܂őS�ĒS�����Ă���̂łЂ���Ƃ����炱�̃w�i�`���R�\���O�Ɋւ���Ă�\�����Ȃ��ɂ������炸�����B
�@�@�����������o�҂�����{�ōs�����̂́A�������ł��ˁB���{���ŃA���o���������[�X�ł��Ȃ��Ȃ�Ɖ��B�ւƓ����s������~���[�W�V�������������̂ł��B���AAndrew�̏ꍇ�A�\�����`�̃A���o����1980�N��͊m����1�������ł����A10cc��Graham�@Gouldman�ƃ`�[����g��ŁACommon�@Knowledge�Ƃ������j�b�g���������A�A���o���������[�X�B���Wax�Ƃ����f���I�ɕϖ����A3���̃A���o�������W���[��RCA���烊���[�X���Ă��܂��B
�@�@1990�N��̓v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̊����������܂����A1991�N�ɓ��{��CM�p�ɏ����ĉ̂���CM�\���O�W�uHome�@Is�@Where�@The�@Heart�@Is�v�������[�X�������1995�N��Bryndle�̕����A���o���܂Ń��R�[�h�����[�X�͂Ȃ��Ȃ邯�ǂ��A����ȍ~�̓\����3���A�V�ȓ���ҏW�Ղ�x�X�g�Ղł�2���A���̑��̃T�C�h�v���W�F�N�g�ł������̃A���o���\����Ƃ�����ɐ��͓I�Ȋ��������Č��݂Ɏ����Ă��܂��B
�@�@�ł��邩�炵�āA���ʃA���o�����o���Ȃ��قǁi���Ԃ̑啝�Ȏ���Ԑ������邩�͕ʖ��Ƃ��āj�������Ă��Ȃ��̂ɓ��{��ɂ��Ċ����������Ƃ́A��͂�e���I�ȂƂ��낪�������̂��A����Ƃ��P�ɃM�������ǂ������̂��ڂ������Ƃ͉Ǖ��ɂ��Ēm��܂���B�܂��A��������gLA�^���h�Ƃ������̂����̃X�e�[�^�X�Ƃ��Ď��Ě������X���͋��������̂ŁAAndrew���킴�킴���{�܂ő����m��n��K�v�͂Ȃ������̂͊m���ł���A�ǂ������Ƃ����Ƒ����m���z���ĉ��������Ă������{�l���y���̑�������Ă���邭�炢Andrew�@Gold���D���������̂�������܂���B
�@�@�܂��AAndrew�@Gold�̌o���ɂ��ẮA�ނ͈ӊO�ɓ��{�ň�����Ă���̂ŁA������ڍׂɏ����K�v���Ȃ����낤����A�܂��̓A���o���ɕt���ďq�ׂ邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�@�@�uHome�@Is�@Where�@The�@Heart�@Is�v�i1991�N�j�A�uWarm�@Breezes�v�i1999�N�j�Ƃ������{�ŃI���E�G�A���ꂽCM�\���O���S�̓Ǝ��ҏW�Ղ��o�Ă��邭�炢�ł�����B
�@�@���̃A���o����1977�N�Ƀ\���f�����[��ł���uAndrew�@Gold�v�Ɏ�����Elektra/Asylum����̃��W���[�����[�X��2�e�ł���A2��ڂ̃\���A���o���ł��B
�@�@�uWhat�fs�@Wrong�@With�@This�@Picture�v���u���̎ʐ^�ɉ������ԈႢ������܂��B�����A�������ȁB�v�Ƃ����^�C�g���ł���A���ۂɃW���P�b�g�̒��ɊԈႢ������Ƃ����V�ѐS�̂���A����̃M�X�M�X�����I���^�i�e�B���̃o���h�ɂ͏o���Ȃ��悤�Ȃ����������A�[�g���[�N�ɂ����o���Ă��܂��B�m����CD�T�C�Y�ł͂Ȃ��ALP�T�C�Y�ł��邩�炱���\�������V�т�������܂��B
�@�@�A���A���̃A���o�������߂Ē�����1980�N��O�������20�N�o�߂������ł��A�M�҂͉������ԈႢ�Ȃ̂��S�������ł��Ă��Ȃ��̂ł��B�N���m���Ă��狳���Ă��������B�i���j
�@�@�A���o����11�Ȏ��^�ƁA1970�N��Ƃ��Ă͂��Ȃ萔�̑������R�[�h�ł���Ǝv���܂��B�����A�J���@�[���̑��l�̍�i��3�Ȃ��߂܂��B
�@�@1�Ȃ�#3�wDo�@Wah�@Diddy�x�B�I�[���f�B�Y�t�@���Ȃ炸�Ƃ����ɂ������Ƃ̂���l�͂��Ȃ�̐��ɂȂ�ł��傤�B�p���̃��b�N�o���h�ł�����Manfred�@Mann��1964�N�ɑS��No�D1�V���O���ɂ��Ĉ���L���ɂ̂��グ�����b�N�N���b�V�b�N���AAndrew�@Gold�͂܂���1960�N��̍���Y���m�X�^���W�b�N����U��T���ABryndle�̗��F�ł�����Kenny�@Edwards��v���f���[�T�[��Peter�@Asher���̃R�[���X�������ăS�L�Q����R&B���b�N�ɂ��Ă��܂��B�M�^�[�ł�Danny�@Korthmar���Q���B1980�N�ォ�玟��Ƀv���f���[�T�[�Ƃ��Ă̒n�����ł߂Ă���Danny�����̓����̓\����������~���[�W�V�������������Ƃ��v���o����܂��B
�@�@�����Ă���1�Ȃ́A���J�r���[/���b�N�����[���̔ߌ��̃X�^�[������Buddy�@Holly�̑�q�b�g�o���[�h#4�wLearning�@The�@Game�x�ł��B�X�e�B�[���M�^�[��Danny�@Kortchmar���S������}���h�����A������Andrew�̓s�A�m��@���A���[�c�F�̒��D���g�߂�ꂽ�o���[�h�Ɏd�グ�Ă���BAndrew�@Gold�̗D�����Ⴓ���c��Â����H�[�J�������ɂ��̖��Ȃƃ}�b�`���O���Ă��܂��B�������A�������n�����O�ɔ�s�@���̂ŎႭ���Ă��̐����������~���[�W�V�����̘b�������Ƃ͂��܂�ǂ��C���ł͂Ȃ��ł��B�i2002�N10��20���B�M�҂͓n������\������z���Ă���������Ă܂��B�j
�@�@�����čŌオ#9�wStay�x�ł��BR&B���b�J�[��Mauraice�@Williams��1953�N�ɏ������h�D�E���b�v��R&B�\���O�ł��B�����Ƃ��A�Ȃ�������������Do�|Wop�Ƃ������t�͑��݂��Ȃ������炵���ł����B���́wStay�x�I���W�i����1960�N�ɔ��\����A�S��No�D1�q�b�g�ƂȂ��Ă��܂��BAndrew�̓R���K���̃n���h�E�p�[�J�b�V������������A���Q�G���h�D�E���b�v�Ƀ��g���\���O���Č����Ă��܂��B�����������J���@�[���o���Ȃ��A�z�ȓ��{�l�̎�͌��ł��@���Ė��܂��Ă��炢�������̂ł��Ȃ��B
�@�@�c��8�Ȃ͖w��Andrew�@Gold�P�Ƃ̃y���ɂ����́B�����쐬�ƂȂ��Ă���̂�#1�wHope�@You�@Feel�@Good�x�݂̂ł��ˁB����#1�ł����A�n�[�h�ȋȂɂȂ邩�ȁA�Ƃ��������̃I�[�v�j���O�̃M�^�[���v�킹�܂����A�w���B�Ȃ�Ă��Ƃɂ͂Ȃ�܂���B���ۂ͌y��R&B�ȃ|�b�v�𐼊C�ݕ��̃A�[�V�[�ȃX�p�C�X���u�߂��悤�ȃO���[���B�ȕ��͋C�̂���ȂɎd�グ�Ă��܂��B
�@�@���K�̉��K���O���悤�ȁA�R��ǂ��g�[�L���O�X�^�C���̃��H�[�J���ł͂Ȃ�Andrew�@Gold���L�̐��������\�Ɋ��Ă���i���o�[�ł�����܂��ˁB
�@�@#2�wPassing�@Time�x��J�DD�DSouther��James�@Taylor�Ƃ������E�G�X�g�R�[�X�g�o�g�̃~���[�W�V���������ʂ��ď������Ă��郍�}���e�B�b�N�ŃW�F���g���B�Ȋ������A�A�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�ł͂Ȃ��A�s�A�m�𒆐S�ʼn̂��グ��o���[�h�B
�@�@�����Ƀ}���`�~���[�W�V�����ł���Andrew�@Gold�̓������������Ă��܂��B�������ڔ��܂Ŗ؊NJy��̃\���Ɏg���Ă���̂ɂ͋�������܂��B���̍�������{�����ɑ��铲�ۂ◝�������������̂ł��傤�B��N�̓��{��ɂ��Ă̊����̌��_������悤�Ȏv�������܂��B
�@�@���H�[�J�����v�����č��ڂɐݒ肵�A�X�D�C�[�g��Andrew�@Gold�̐����ۗ������Ă��܂��ˁB
�@�@#5�wAngel�@Woman�x�͍X�ɓ������̂��鏖��Y���i���o�[�ɂȂ��Ă��܂��B�I�[�P�X�g���[�V�������o�b�N��Andrew�@Gold���s�A�m1�{�����ł��̃o���[�h���̂��グ��̂ł����A����1�����Ƃ����Z�����������i���o�[�Ŋ�����̂�1960�N��Ɋ���Leon�@Russell��Procol�@Harum�̃��}���`�V�Y�����o���Ă��܂��͕̂M�҂����ł͂Ȃ��ł��傤�A�����āB
�@�@#6�wMust�@Be�@Crazy�x��Andrew�炵���������A�����W�������X�E�G�b�g�ȗD������������i���o�[�ł��ˁB�q�b�g���Ƃ��Ă͒���ɒ�������ލő�̃q�b�g�ȁA#7�wLonely�@Boy�x�ɗ��ʂ��̂�����Ǝv���܂��B�y���ɓ]����Andrew�̃s�A�m�ɃI���K���A���ɃI���K�������̃i���o�[�̎��x�𑝂��A�K�x�ɐG��₷���\�ʂ��`�����Ă���Ƃ�����ł��傤�B�����Ĕh��ɂȂ�߂��Ȃ��X�g�����O�X�A�����W�����g�ɁA�m���m���ɐU����T�b�N�X�t�H���B1960�N��̌Â��ǂ����b�N�����[���̎����Ă����]�T�����R���e���|�����[�Ȋ��o��Pop/Rock�ɓZ�ߏグ���i���o�[�Ƃ�����̂ł́B�X�D�C���O���ł�#7�������R�x�������i���o�[�Ƃ�������ł��傤�B
�@�@�����āA���̃A���o���ő�̃n�C���C�g�́A��͂�Andrew�@Gold�̗B��̃g�b�v10�q�b�g�ł���#7�wLonely�@Boy�x�ł��ˁBAndrew�@Gold�����܂ꂽ1951�N�A���̔N����uHe�@Was�@Born�@On�@A�@Summer�@Day�@1951�v�Ɖ̎��̖`���ň��p����Ƃ���ŁAAndrew���g�̌o���k�A�����`�I�ȐF������тт�ƌ����Ă��܂��B���A���l�ɉ�ژ^�̑�\�Ƃ��Č��Ȃ���Ă���Gilbert�@O�fSullivan�̑�q�b�g�i���o�[�wAlone�@Again�x���A����Gilbert�̑n��ł��镔�����w�ǂł���Ƃ������������܂��̂ŁA���̕ӂ�͂͂����肵�܂���B
�@�@���A�m���Ȃ��Ƃ͂��̃i���o�[���̎��A�����f�B�A�A�����W�A�S�Ăɓn���ĉi���ɂ����͂��ƂȂ�������������ݏo�����鐼�C�݃��b�N�̖��Ȃł���Ƃ������Ƃł��B�o�b�N���H�[�J���ɂ͔ނƕt�������̒��������̉̕PLinda�@Ronstadt��������Ă��܂����A�J�E�x���܂Ŏg�������̐[���͗Ⴆ�悤�̂Ȃ�������^���Ă���܂��B
�@�@#8�wFirefly�x�͑S�Ă̊y��|�h�����A�x�[�X�A�M�^�[�A�V���Z�T�C�U�[�A�p�[�J�b�V�����|��Andrew�������A�}���`�~���[�W�V�����Ƃ��Ă̍˔\���\�S�ɔ������Ă���Ȃł��B���C�݂̃J���g���[���b�N���ȃ_�X�e�B���𐏏��Ɍ����Ȃ�����A���Beatles�̉e�����B�����Ɋ������邱�̗D�����o���[�h�ł̓R�[���X����Andrew�ЂƂ�̃I�[���@�[�E�_�r���O�ƂȂ��Ă���̂������ł��B�{���͂����ƃp���`�͂̂���̂������ł���V���K�[�Ȃ̂ɁA�����������X���[�i���o�[�ł̗}������l�̉̂������ł���Ƃ���͒E�X�Ƃ��������܂���B
�@�@#10�wGo�@Back�@Home�@Again�x�́A�A�[�V�[�ȃA�����J�����b�N�ƒP���Ɋ����ɂ́A���X�ܑ̖����i���o�[�B�����50�N��R&B��60�N��̃u���e�B�b�V���E�C�m���F�[�V�����������f�B�ɓ���Ă���z���L�B�Ń_�C�i�~�b�N�ȃI�[���h���b�N�����[���B����Ƀh���C�Ȑ��C�݂̓V���������������悤�ȑS�̂̊��G���t�������̂́A��͂�Andrew�����C�݂̃A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̊�{���ǂ̃i���o�[�ɂ�����ƂȂ��ł�����ł��邩��ł��傤�B�������A�u�ƂA�낤�v�Ƃ������D��U���ɂ͂����Ă��̃i���o�[�ł���܂��B�y�����i���o�[�ł����A���ƂȂ��uThe�@Party�fs�@Over�v�Ƃ������̌�I�ȕ��͋C������܂��B
�@�@���̃A���o���̓�����1�ɁA�X�g�����O�X�����ɂ������Ȃ�Ȃ����x�ɏ��Ƀt���[�`���[����Ă���Ƃ����_������̂ł����A#11�wOne�@Of�@Them�@Is�@Me�x�����̗�ɘR��܂���B21���I�ɓ������ŋ߂͖w�ǒ������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă����G���N�g���b�N�E�s�A�m�̃f�B���C�̊|���������o���́A���̎���Ȃ�ł͂̃T���v�����O�ł͂Ȃ��A���Ȃ�����ȉ��F�������邱�Ƃ��ł���B���ꂾ���ł��̎₵�����D�����o���[�h�͈ꋉ�i�ƂȂ鎑�i������܂��B�X�ɃX�e�B�[���M�^�[�̓y�L���͂��̃i���o�[�Ɉ��S����^���Ă���Ă��܂��B
�@�@���́A�M�҂Ƃ��Ă�1978�N�����ł��郁�W���[�A���o��3���ڂ́uAll�@This�@And�@Heaven�@Too�v�i�M��F�u�K����j�v�E�E�E�E���ł�˂�E�E�E�B�j��Andrew�@Gold�̍�i�̒��ł͍ł��D���������肵�܂��B�i�����j���A����Փ��I�ɂ��̃A���o���ɍ����ւ����̂́A��͂肠�܂�ɂ����{��́u�ւ��́v�������o������������ł��ˁB
�@�@���̂ɂ͌��x���������A�����Ƃ͍l���ă����f�B���g���܂킹�ƁA�̎��S���ƃw�{�̎�ɉ��߂ē{��������C���ł��ˁB���ꂭ�炢�Ռ�������܂����B�܂��������d�g�\���O�������S�y���߂�]�n������܂��ȁB���Ȃ��I�}�[�W���ɂ���̂͗ǂ��ł��傤���A���ȉ����ƙ��ނ͊��ق��ĖႢ�������̂ł��B
�@�@���āA�Ō��Andrew�@Gold�ɂ��ďq�ׂĂ������Ƃɂ��܂��傤���B���{�ł̒m���x�͂���������͂Ȃ��̂ɁA�x���w�͂�������Ƒ��݂��邵�A���X��CM�ɂ��ނ̉̂��N�p����Ă��܂��̂ŁA������x�̔N��̐l�͔ގ��g��m��Ȃ��Ă�Andrew�@Gold�̉̂͒��������Ƃ�����Ƃ͎v���܂��B
�@�@���܂��1951�N�ŃJ���t�H���j�A�B�o�g�B���e�͍�ȉƂł���A�f�批�y�ŃA�J�f�~�[�܂���܂���Ernest�@Gold�Ƃ����l�B��e�́u�E�G�X�g�T�C�h����v��u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v�̉f�撆�ŏ��D�̉̂̐����ւ������V���K�[��Marni�@Nixon�A�Ƃ����悤�ɉ��y��Ƃɐ��܂�Ă��܂��B
�@�@���R�c�������炠����y��̃��b�X�����A�S�Ă̊y����ꗬ�Ɏg�����Ȃ��鉺�n���`�����邱�ƂɌb�܂ꂽ�����������Ă��܂��B16�ɂ͉p��Polydor����V���O�������Ă��܂����A�S�����ڂ𗁂т邱�ƂȂ��A�����̋��_�͌̋��̐��C�݂ɗ����������ƂɂȂ�܂��B1973�N��LA�ɂ�Kenny�@Edwards�AWendy�@Waldman�AKarla�@Bonoff�ƃ��H�[�J���o���h��Bryndle���������܂����A�V���O����1���쐬�������_�ŁAAndrew��Kenny�@Edwards��Rinda�@Ronstadt�̃o�b�N�o���h�ɉ���������߁ABryndle�͉��U�B1995�N�̍Č����Ə��A���o���̃����[�X�܂�22�N��҂��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�܂�Bryndle��2���ڂ̃A���o���uHouse�@Of�@Silence�v��2002�N�ɔ��\���Ă��܂��B
�@�@Rinda�́uHeart�@Like�@A�@Wheel�v����ɁA1980�N��܂ł̔ޏ��̃A���o���w�ǑS�ĂɃ}���`�~���[�W�V�����Ƃ��Ċւ��A�\����������s�����܂��B
�@�@����Љ���uWhat�fs�@Wrong�@With�@This�@Picture�v�Ɋւ��ẮA
�@�@�u���̃A���o����Rinda�́wHasten�@Down�@The�@Wind�x�Ɠ��������ɘ^�����A�������ꂽ�B�ޏ��̃o���h�Ɩl�̃o���h�͑S�������~���[�W�V�����Ő��藧���Ă����B�V���K�[���l��Rinda���̈Ⴂ�����A���ꂩ��Rinda���l�̃A���o���ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��������Ƃ��Ⴂ���ˁB�v���f���[�T�[��Peter�@Asher��G���W�j�A�A�����Ę^�������X�^�W�I�܂ňꏏ�������B
�@�@�l��Rinda�̃c�A�[�̑O���������Ă�������A�܂������̃o���h�ʼn��t������A���̂܂�Rinda�̃X�e�[�W�Ńv���C�������̂���B�v
�@�@�Ɖ�z���Ă��܂��B
�@�@�������A4���ڂ̃��W���[��A�uWhirlwind�v���s���ɏI�������Ƃ���Elektra����_�����Ă��܂����AAndrew�͐�ɏq�ׂ��悤��10cc��Graham�@Gouldman�Ƒg��ŁACommon�@Knowledge����Wax�Ƃ����ł����n�̃|�b�v�A���o����4���쐬�B
�@�@���s���ăv���f���[�T�[�Ƃ��Ă�����BRita�@Coolidge�AMoon�@Martin�ANicolette�@Larson�AArt�@Garfunkel�AStephen�@Bishop�̃A���o����V���O�����v���f���[�X�B
�@�@1996�N�ɂ̓I���W�i���A���o���Ƃ��Ă�15�N�Ԃ�́uSince�@1951�v�\�B1996�N����͂��Ȃ��]���オ�肾�����̂��A���N�ɂ͂������̉̂��W�߂��q���̂��߂̃A���o���ł���And�@Friends���`�́uHalloween�@Howls�v���A1997�N�ɂ̓T�C�h�v���W�F�N�g�I�ȃA���o���uBell�@Bottoms�v�Ƃ���1960�N��̃J���@�[�o���h�\������AGreg�@Prestopino�Ƃ����\���O���C�^�[�̃A���o�����쐬�BRhino���珉�̃x�X�g�A���o���uThank�@You�@For�@Being�@A�@Friend�v�������[�X�B
�@�@������1998�N�ɂ̓��A�g���b�N�W�́uLeftovers�v�A2000�N�ɂ�5�N�Ԃ�̃I���W�i���\���uThe�@Spence�@Manor�@Suit�v���p���̃C���f�B���[�x����Dome����B
�@�@�X�ɋߔN�ɂȂ��Z���X�p���ō��N�̔ӉĂɁA�ŐV��uIntermission�v�\�B���̃A���o���͂܂��茳�ɓ͂��Ă��Ȃ��̂ŏڂ����R�����g�͂ł��Ȃ��̂��c�O�ł���B�����������胋�[�c�ȍ������b�N�ł܂��܂��̃A���o���̂悤�Ɋ����Ă���̂Ŋy���݂ł͂���܂��B
�@�@����1970�N��̃E�G�X�g�R�[�X�g���ʂ��Ă����~���[�W�V�����B�̑����͋ߔN�w�ǕN�ǂ����悤�ɊJ�X�x�Ə�Ԃ𑱂��Ă��邪�A���̂悤�ɒn���ł͂��邪�A�����Ɋ撣���Ă��郔�F�e�����͐���Ƃ��������Ă��������ł��ˁB
�@�@�܂����҂𗠐�Ȃ������̍�i���o�Ă���̂��܂��͈��S�ł���̂ł����A���̃f�����[�����̃��W���[�A���o���ɕC�G�����i��1991�N�́uHome�@Is�@Where�@The�@Heart�@Is�v�ȍ~�o�Ă��Ȃ��̂ŁA�����ɓ͂����낤�ŐV��ł͈ꔭ�ԉ�ł��グ�Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���������܂��A�����ɁB�i�j�@�@�i2002�D10�D18�D�j
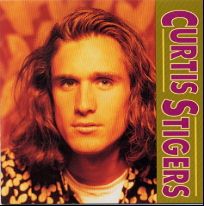 �@�@Curtis�@Stigers�@/�@Curtis�@Stigers�@�i1991�j
�@�@Curtis�@Stigers�@/�@Curtis�@Stigers�@�i1991�j
�@�@Blue-Eyed�@Soul�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@Adult-Contemporary�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here
�@�@�@�@1998�N�~�A�V�J�S��House�@Of�@Blues��Eddie�@Money�̃��C���������B����قǏ����ȃn�R��Eddie�������Ƃ�1980�N��̒i�K�ł͑z�������ɂł��Ȃ������B����ȏ�ɋq�̓��肪8���ڈȉ��̏�����Eddie�@Money���R���T�[�g���s��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��č��̉��y�������������������B
�@�@�ƁA�{��͑S���W�Ȃ��B�b��i�߁AEddie�@Money�̃��C���ɖ߂�B
�@�@���C�����ŁAEddie�@Money���A���g�E�T�b�N�X�t�H�������Ɏ�ɂƂ��Đ����Ă��ꂽ���́A�u�����A�v���Ԃ�v�Ɗ����������̂����A���̎��ӂƕ������Ƃ́A
�@�@�u���������AEddie�̂悤�ɃT�b�N�X�𐁂��郍�b�N�V���K�[���́i���j�����Ȃ��B�v
�@�@�Ƃ��������̊��S�����C�����������B����Ɠ�����1992�N�ɂ��̃V���K�[�̃��C�����J�i�_�Ō������Ƃ܂ŃI�[���@�[���b�v���Ă��܂����B
�@�@���̃V���K�[�Ƃ����̂�����Љ��Curtis�@Stiger�ł���B1991�N��Arista�@Records�����Ȃ�̊��҂������āg�{�i�h���b�N�V���K�[�h�̃R�s�[�Ƌ��ɔ���o�����A�[�e�B�X�g�ł���B
�@�@�������A�l���Ă݂�ƁA�������N�̃X�p���ł͂Ȃ������f�B�P�C�h�|10�N�߂��ɓn���āA�g���b�N�o���h�h�ł͂Ȃ��g���b�N���H�[�J���X�g�h�Ƃ��ă��W���[�V�[���Ŋm�ł���n�ʂ�z�����V�l��S�����Ă��Ȃ��悤�ȋC������E�E�E�E�E�E�E�E�C������ł͂��A���ۂɃ��b�N���H�[�J���X�g�Ƃ��Ĕ��ꂽ�V�l�A�[�e�B�X�g�͑��݂��Ȃ����낤�B
�@�@���Ȃ݂ɂ����ł͏����|�b�v���H�[�J���͑S���l�����Ă��Ȃ��B�������H�[�J���͂ǂ̂悤�ȃ^�C�v�ɂ��Ă��S��Out�@Of�@�ᒆ�Ȃ̂ŁB�i�����j
�@�@�ƒf�����ꂽ�Ƃ���ŁA���b�N���H�[�J���ɘb��߂��Ƃ��悤�B
�@�@1970�N�ォ��80�N��Ɋ|���āA�K�����݂������f�B�A�����`����Ƃ���́g��^�V�l���H�[�J���X�g�h�B
�@�@���̂����A�ǂꂾ�����{���ɑ�^�̖��ɒp���Ȃ��劈��Ǝ��͂����Ă������͂܂��ʂ̘_�c�ł���Ǝv���̂ł����ł͏q�ׂȂ��B�������A���R�[�h��Ђ�}�̂���`����V�l�A�[�e�B�X�g�̒��ɂ̓��b�N�o���h�ł͂Ȃ��A�V���K�[�Ƃ��ă��b�N�����[����\���ł���l�������������Ƃ����ƌꕾ�����邪�A�K�����݂����B
�@�@1980�N��㔼�Ɍ����Ă�Richard�@Marx�A�����ăf�����[�͂����Ƒ����������n�[�h���b�N�Ƃ��Ăł͂Ȃ����b�N�V���K�[�Ƃ��đ䓪���Ă���Michael�@Bolton�B�����܂Ŕ���Ȃ��Ă�Judd�@Cole��Michael�@Damian��Robbie�@Nevil�Ƃ������V���K�[�����������̃q�b�g���L�^���Ă���B
�@�@���A1990�N��ɓ���A�O�����W/�I���^�i�e�B�����V�[���ߐs�����Ă��܂�����A�j���̃��b�N�V���K�[�Ƃ����͖̂ő��ɏo�����Ȃ��Ȃ����B���W���[��������������H�[�J����u���b�N�A�����ăA�C�h�����H�[�J���o���h�Ɉڂ������ƂɋC���t���͓̂����ŁA���b�N�V���K�[�̌㉟�������邱�Ƃ�������ƌ����Ă��܂����B
�@�@���R�AMichael�@Mcdermott���n�߂Ƃ��āA�ǎ��ȃA�����J�����b�N���̂���A�[�e�B�X�g���o�������̂����A�ǂ���Z�[���X�s�U�̂��߁A�C���f�B�ɗ������芈����~��]�V�Ȃ�����Ă���B
�@�@�ߔN�AJohn�@Mayer�̂悤�ȃW�������b�N�̎c��J�X�̂悤�ȃt�k�P�V���K�[���r���𗁂тĂ��邪�A�{���̈Ӗ��ŃK�b�`���Ƃ����艞���������邱�Ƃ��\�Ȗ{�i�h�͐�ŏ�Ԃɋ߂��B�ܘ_�A���W���[�f�����[�ƃZ�[���X�Ƃ������ƓI�Ȗʂɂ����Ă����B���R�A�C���f�B�V�[���ɂ͖{�i�I�ȃA�����J�����b�N���̂���A�[�e�B�X�g��21���I�ɂȂ��Ă����݂��Ă���B
�@�@���āA����Curtis�@Stiger�����A�ނ��{�i�I�ȃ��b�N�V���K�[�Ƃ��ă��W���[�V�[���Ɏ����̑��ŗ��Ă�͗ʂ��������l�ł���A���ʂɎs�ꐫ�������Ȃ�A���̃f�����[�N��1991�N����10�N�ȏ���o��2002�N���݂ł����b�N�����[����͂��Ă���锤�̉̂��肾�����B
�@�@�������E�E�E�E�E�����A�ߋ��`�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B���A�ʂɂ��B��ɂȂ����Ƃ����b�ł͂Ȃ��B�i���������j
�@�@�S���Ⴄ�����ցA��Curtis�@Stigers���i��ł��܂��Ă���̂��B
�@�@1999�N�ɐ�����3��ځuBrighter�@Days�v�̏��ƓI���s��Curtis�@Stigers�͂��Ƀ��W���[�̌_����������ƂɂȂ��Ă��܂����B���̃A���o���ł̓��b�N�V���K�[�Ƃ��������A�V���K�[�E�\���O���C�^�[�̑��ʂ�傫�������L�����Ǎ�ł������Ǝv���Ă���̂����A�M�҂Ƃ��ẮB
�@�@�������A2�N���2001�N�ACurtis�͉��ƃW���Y���[�x�����瑊���ɃW���Y�E���H�[�J���ɑ������A���o���uBaby�@Plays�@Around�v�\�B
�@�@����ɂ͂��Ȃ���������A�܂�1������̎����I�ȃg���C�A���ƍl���Ă����B���A���̗\�z�͐Ƃ����O���B
�@�@���N2002�N�ɂ͓����[�x����Concord�@Jazz�@Records����A��w�W���Y�ɓ��������uSecret�@Heart�v���B���̃A���o���Ŋ��S�ȃW���Y�E���H�[�J���X�g�Ƃ��Ă̓]�i���ʂ����Ă��܂����悤�Ɏv����B
�@�@Curtis�H���A
�@�@�u�|�b�v���b�N�E�̃X�^�[�I�Ȋ��������Ă������͏�Ɉ�a���������Ă����B�l�̃��[�c�̓W���Y��\�E���Ƃ��������l���y�A���ɃW���Y�ɂ���̂�����B����Ƀ|�b�v�����̃t�B�[���h�ɂ����ݕt�������Ȃ������B�v
�@�@�v��Έȏ�̂悤�ȃR�����g���Ă���B
�@�@�m����Curtis�̃\�E���t���Ŕn�͂̂��鍕�l�畉���̃o���g���E���H�C�X�͎��ɃW���Y�E���H�[�J���̋ȂɓK���������������Ă���Ƃ�����B
�@�@���A���̂悤�ȃ��b�N�����[�����̂��̂ɂ��K�������H�[�J���X�g�����b�N�r�[�g���痣��Ă��܂������Ƃɂ͑����̎₵���������Ă��܂��B
�@�@�{�Z���t�^�C�g���A���o���ł�150������č��Ŕ���A�܂��܂��̐��������߂�Curtis�����A����2���̃A���o���͑S�����ƓI�Ɍ���ׂ����ʂ��c���Ă��Ȃ��B���ɏ�����3���ڂ܂ł̃��b�N�E�|�b�v�̍�i���l�C�Ă�����A���ݔނ��W���Y���̂��Ă��邩�͐r���^��ɂ͎v���̂����A�܂��F���Ȃ����Ƃł���B�����Ƃ��āA�M�����ł��郍�b�N�V���K�[���ЂƂ�e���ւƕ���i�߂��Ƃ������ƂȂ̂�����B
�@�@�Ƃ������ƂŁA�uCurtis�@Stigers�v��Curtis���ʎZ5���̃A���o���̒��ōł����b�N�����[���[�Ƃ��ẴJ���[��ł��o���Ă��邠��Ӗ��M�d�ȍ�i�Ɖ��������������B�ߍ�2���̓W���Y�B3���ڂ̓V���K�[�\���O���C�^�[���B2���ځuTime�@Was�v�̓v���f���[�T�[��David�@Foster���Q�����Ă��邱�Ƃ��琄�����\���ƍl���Ă��邪�A1st�A���o�������X��Adult�@Contemporary�����i�s�����A�_���g���b�N�̃s�[�X�ƂȂ��Ă���B
�@�@���̏�Ŗ��O���o���̂�2nd�A���o���́uTime�@Was�v�ɂ��Ă����X�����q�ׂĂ������Ƃɂ��悤�B�{��ł��v���f���[�X��S�����Ă���Glen�@Ballard��Danny�@Kortchmar��M����David�@Foster�Ɩ{�l���܂߁A7���̃v���f���[�T�[���N�p���č쐻�����A���o�����B
�@�@���̂��߂��A�S�̂�ʂ��ƕ��͋C�ƍ앗�������ɂ����͂��Ȋ������ۂ߂Ȃ��B�ꉞ�A�_���g�E���b�N�Ƃ��Ă̓���͂Ȃ���Ă���̂����A�������ɊԈႢ�������x���G�̂悤�ɂ��܂����J�b�`���Ƃ������ꂪ�������Ȃ��̂��B
�@�@�܂��ACurtis�̃g���[�h�}�[�N�ł��鑾���Ď��ʂ̂���o���g���E���H�[�J�����P�Ȃ�Y�ƃ��b�N���o���[�h�ɂ��k�ɏ����Ă��܂��Ă���B���̓_���ł��d��Ȗ�肾�Ǝv���B
�@�@�m���ɂ����������^�C�v�̊���̎�����f�Œ@���t���Ă��郔�H�[�J���́A���{�l�D�݂̃G���[�V���i���ȃo���[�h�Ƃ̑������ƂĂ��ǍD���B���ۂɐ����ׂ����H�[�J���X�g����������Ȃ����b�N�o���h�̕��ʂȃ��H�[�J���X�g���̂������A�M���A������o����郔�H�[�J���͔��ɐ����͂����邾�낤�B
�@�@�������A�o���[�h�n���吨���߂Ă��܂��Ă���A���o���́A��͂胍�b�N�A���o���Ƃ��Ă͐H������Ȃ��v�������Ă��܂����Ƃ������A�uTime�@Was�v���S�������Q�ɓU�܂��Ă��܂�����i�ƍl���Ă���B
�@�@�v����Ɉ����Ȃ��A�_���g�E���H�[�J���̃A���o���ɂȂ��Ă���̂����ACurtis�@Stigers�̃��b�N��u���[�A�C�h�E�\�E���̉̂���Ƃ��Ă̓��������S�Ɋ��p����Ă��Ȃ����̂ɂȂ��Ă���̂ł���B
�@�@�M�҂Ƃ��Ă̊��z�́A���̔M���\�E���n���b�N�A���o���Ńf�����[�����V���K�[��2���ڂɏo���A���o���ƍl����ƁA��������������H���������̍�ł���B10�N���炢�L�����A��ς�ł��������点�A�ƃ����[�X����o���[�h�n�R���e���|�����[��i�������瑊���[�����s�����Ɨ\�z���Ă���B
�@�@�J��Ԃ��ɂȂ邯�ǁA�����A���o���ł͂Ȃ��B�����҂��Ă����p���[�̕s���͔@���Ɋ����Ă��܂����B�n�C�I�N�^�����̃K�\�����⋋�����҂��Ă����烌�M�����[�K�X���`���[�W���ꂽ�Ƃ����Ƃ��낾�낤���B
�@�@���āA�f�����[�ȍ~��Curtis�@Stigers�Ɋւ��ĕM�҂��v���Ƃ���͈ȏ�ł���B
�@�@�{�l�̏��ɕt���ẮA�f�����[�����͂��Ȃ�G���ɂ����グ���i�C�O�́j�A���{�Ղ������[�X����Ă����l�q�Ȃ̂Ńo�C�I�֘A��m��ɂ͓��{�Ղ�����Ηǂ����낤���A���݂͔p�Ղ炵���B�M�҂̃A���o���͕ĔՂł���B
�@�@�ł���̂ŁA�ȒP��Curtis�@Stigers�ɏq�ׂĂ������Ƃɂ��悤�B
�@�@�o�g�̓A�C�_�z�B�B���܂��1966�N�ł���A�c��������N���b�V�b�N���y���w�ѐ�U�̓N�����l�b�g�������B
�@�@�炿�͐��C�݂̃V�A�g�����ӁB�P�ȑ�w�ݐВ��ɁA�N���b�V�b�N����W���X��u���[�X�ւƋ������ڂ�A���̍�����T�b�N�X���v���C����悤�ɂȂ����炵���B
�@�@�ł��邩��A�ŋ߂̃W���Y�A���o���͊m���Ɍ����ȈӖ��ł͌��_��A�Ƃ����ׂ���������Ȃ��̂����A���b�N�V���K�[�Ƃ��ď����I�Ɋy���݂Ȑl�������̂ł�͂�]�i�͎c�O���B
�@�@Curtis�͑�w�𑲋Ƃ���1987�N�Ƀj���[���[�N�ւƉ��y���v���̃L�����A�ɂ��邽�߂Ɉڂ�Z�ށB�����Ńu���[�X�n�̃��b�N�o�[�o���h�𗦂��ĉ̂��A�T�b�N�X�𐁂��n�߂�B3�N�قǂ̊������ԂŁACurtis�@Stigers�̓Z���g�����E�p�[�N������Ő����Ɉʒu����n��̃A�b�p�[�E�E�G�X�g�E�T�C�h�̃N���u�V���K�[�Ƃ��Ă��Ȃ�̐l�C����悤�ɂȂ�B
�@�@���̕]����Arista�@Records�̖ڂɗ��܂�A1991�N�n�߂�Curtis�@Stigers�͓����[�x���ƌ_������킷���Ƃɐ�������B
�@�@������Glen�@Ballard��Danny�@Kortchmar�Ƃ������啨�v���f���[�T�[�̎�ɂ���ăf�����[�E�A���o����^���B1991�N�㔼�ɁuCurtis�@Stigers�v������B
�@�@�����A�M�҂̓J�i�_�̓g�����g�ɂ����̂����A�A���o�����g�b�v100�Ƀ����N�C�����A�S�đ�9�ʁi�����j�܂ŏ㏸����#2�wI�@Wonder�@Why�x���܂�2�Ȃ̃g�b�v100�V���O���ނƂ����悤�ɐV�l�Ƃ��Ă͂܂��܂��̐��ʂ��c�����悤�Ɏv�����B
�@�@�c�A�[��Eric�@Clapton�ARod�@Stewart�ABonnie�@Raitt������Elton�@John�̑O���ɔ��F���S�Ă����B���Ȃ݂ɕM�҂�Elton�@John�́uThe�@One�v�c�A�[�̑O���Ŕނ̃X�e�[�W������@��Ɍb�܂�Ă���B
�@�@���̗��N�ɂ́AWhitney�@Houston�̎剉�f��uThe�@Bodyguard�v�̃T�E���h�g���b�N�ɂ�Nick�@Lowe�̃J���@�[�Ȃł���#10�w�iWhat�fs�@So�@Funny�@�eBout�jPeace�CLove&Understanding�x�����������ĎQ���BJoe�@Cocker��Kenny�@G���Q���������̑�q�b�g�A���o���ɔ��F���ꂽ�Ƃ����͓̂����̕]���Ɛl�C�̍����𑪂镨�����ƂȂ邾�낤�B
�@�@���A�听���Ƃ͂����Ȃ����̂̂܂��܂��̐��ʂ��c�����f�����[����A2nd�A���o���uTime�@Was�v�܂�4�N���₵�����߁A���̊ԂɋN�������O�����W�E�I���^�i�e�B���̕ϊv���ɍ��킹�Ďs�ꐫ���ω����Ă��܂������߂ƁA���炭�w�ǖY�ꋎ�ꂽ���݂ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��傫���̂��낤���A���ꂩ���2���̃A���o���͑S�����ꂸ�ɁA�C���f�B�����B
�@�@21���I�ɓ˓����Ă���̓W���X�E�V���K�[�ƂȂ茻�݊����p�����|�ȏオ�ȒP�ȗ����ł���B
�@�@���āA�A���o���̓��e�ɂ��Ă����A���Ƀ\�E���~���[�W�b�N�̉e���������|������������l���y�̉e�����Z���ȃu���[�E�A�C�h�E�\�E���A�\�E���ȃ��b�N�A���o���ɂȂ��Ă���B
�@�@���������͑S�Ẵ��f�B�A�ɁgMichael�@Boston�@Meets�@Huey�@Lewis�h�ƌĂꂽ���̂ł���B����2���̑啨���b�N�E���H�[�J���ɂ��Ă͍��X��������K�v���Ȃ����A�ǂ����R&B��\�E�����y����{�ɂ��đ�O�ɃA�s�[���ł��鉤���I��Pop/Rock�̍�i�����������ɏo���Ă����A�[�e�B�X�g�ł���A�M���ʼn�������\�E���t���ȃ��H�[�J���X�g�ł�����B
�@�@Curtis�@Stigers�͋^���Ȃ��AMichael�@Bolton�^�C�v�̃V���K�[�ł���B���l�Ɛ�������Ă�������Ȃ���Ε�����Ȃ����炢�̑������H�[�J���ƃT�b�N�X�������ꂽ�u���[�W�[�Ń��[�f�B�ȃ\�E�����y�B���̍����ۂ����b�N�T�E���h�ɃA�_���g�E�R���e���|�����[�̃R�}�[�V�����ȃZ���X��������Ă���B
�@�@�܂��|�b�v�Ƃ������ڂɂ����Ă�Huey�@Lewis�������Ȃ����e���݈Ղ��i���o�[�������Ǝv���B���̃\���O���C�e�B���O�ɂ����ẮA�P�Ƃŏ������Ȃ̓[�������A�S11�Ȓ�9�Ȃ𑼂̃��C�^�[�Ƌ����ŏ����グ�Ă���B
�@�@�w�ǂ̃p�[�g�i�[���v���f���[�T�[�ł���Wayne�@Cohen�ł��邪�A#6�ł͂���Barry�@Mann�Ƌ�������Ă���̂ɋ������ꂽ�肷��B
�@�@�Ƃ�����A1980�N��㔼����J���⡂̂悤�ɗ����������b�v/�q�b�v�z�b�v�ɖ��ߐs�����ꂽ���l�`���[�g��ł����݂ɑ���߂����u���b�N�E�R���e���|�����[�n�̃V���K�[�̃A���o���Ƃ͔�r�ɂ��Ȃ�Ȃ����炢�\�E���t���Ő����h�̃u���b�N�E���[�c���b�N��������1���ł���B
�@�@�܂��A1991�N�����l�C�̍Ő����ɏ�����Ă���Michael�@Bolton�ɒʂ���Arena�@Rock�̕������T�E���h����������Ă���ACurtis�̐[�����H�[�J���Ɣ��Ƀ}�b�`���Ă���B�u���[�E�A�C�h�E�\�E���̌���Ζ{���̃\�E���~���[�W�b�N���猩��ΖT�n�̃~���[�W�V�������f���Ƀ\�E����Nj��������߁A�{�Ƃ𗽂������h�̃A���o����n���Ă��܂��Ă���̂��B
�@�@�܂��A����͉����̉��y�W�������ɂ������錻�ۂł͂��邪�B�Ȃ܂������Ƀ\�E���⍕�l���y��Nj������̂ŁA�����ȑł����݂̗��s�ɏ�炸�ɂ��̂��낤�B
�@�@�v���f���[�T�[�͑O�q�̂悤��Danny�@Kortchmar��Glen�@Ballard�ł��邪�ADanny��4�ȁA�c���Glen����|���Ă���B���A���ҋ���Curtis�̎����������Ɉ����o���Ă���A�o���o���Ȋ����͊F���ł���B
�@�@�܂���Danny�̊ւ����4�Ȃł��邪�A���̈�Ԏ�ł���I�[�v�j���O��#1�wSleeping�@With�@The�@Lights�@On�x���烍�b�N�����[���̔M���ƁA�\�E���̔M���q�[�g�A�b�v���Ă���B�h�����ɍ��͖S��Jeff�@Porcaro�A���Ȃ�I�[���@�[�E�_�u���ꂽ�L�[�{�[�h��David�@Paich�Ƃ���Toto�̃��F�e�����E�~���[�W�V�������}���A���t�͊����BDanny�̎������i���o�[�ɂ͑S�Ă���Toto�̒����ł���Z�b�V�����~���[�W�V�������Q�����Ă邵�ADanny���w�ǂ̃i���o�[�ŃM�^�[��e���Ă���B�_�C�i�~�b�N�Ȗ��������郍�b�N�r�[�g��Curtis���U��e�i�[�T�b�N�X���O�C�O�C�Ɨ���ł����p�[�g�͍ō��ɋC�����ǂ����b�N�r�[�g�̃O���[�������\�ł���B
�@�@��3�i�V���O���ƂȂ����̂����A�c�O�Ȃ���`���[�g�E�C���͊m�����Ă��Ȃ������B
�@�@#4�wThe�@Man�@You�fre�@Gonna�@Fall�@In�@Love�x�̓j���[���[�N�̃o�[�o���h�Ŋ������Ă���Curtis�̃L�����A���v�킹��w���B�ʼns�p�I�ȃu���[�X���b�N�ł���B���Ȃ�R&B�ȃt�@���N���o�������o���Ȃ���A�����R�[���X�ɂ��A�_���g���A������Curtis�̃e�i�[�T�b�N�X�ɂ���F�̉��F����ۓI���B�M�^�[�ɂ�Michael�@Landau���Q�����Ă���B
�@�@#9�wI�@Keep�@Telling�@Myself�x��#5�wPeople�@Like�@Us�x�Ɠ��l�A�L���b�`�[�Ńu���b�N�J���[�������l�Ƃ��Ẵ|�b�v�X���o���S�ʂɏo���ꂽ�ǎ��ȃ~�f�B�A���E�|�b�v�ł���B1980�N�㕗�̃L�[�{�[�h�v���O���~���O�𑽗p�����ł����݉��y�̉��n�ɗ����Ă���i���o�[�����A�S�X�y���������R�[���X�ɃA���g�T�b�N�X�̏_�炩�����F���Ɠ��̒��q��^���Ă���B
�@�@�Ō�̃i���o�[#11�wThe�@Last�@Time�@I�@Said�@Goodbye�x�ł́A���C�ݕ��̓�������L�������[�f�B�Ńg�����Ƃ����x�C�E�G���A���̒��q����A�X�g�����O�X��V���Z�T�C�U�[���������o���[�h�ɕς���Ă����A���ɗ������������H�[�J���i���o�[�ł���AOtis�@Redding����f�i�Ƃ�����B
�@�@Glenn�@Ballard����r��U������c��7�Ȃ̃g�b�v���ACurtis�ő�̃q�b�g�ȂƂȂ���#2�wI�@Wonder�@Why�x�ł���B
�@�@Curtis���t�ł��ۓI�ȃA���g�T�b�N�X�̃��t���炽���Ղ�Ƃ������ʂ̂��郔�H�[�J�����L���b�`�[�ȃ����f�B�ɏ悹�ăh���}�e�B�b�N�ɗ���Ă����B�\�E���o���[�h�Ƃ��������\�E���t���ȃ��b�N�V���K�[�̃o���[�h���낤�B
�@�@�I���K���ɂ�Little�@Feet��Bill�@Payne�A�h�����ɂ�John�@Robinson�Ƃ��������C�݃~���[�W�V�����̍��Q�X�g�w��Danny�̑��ɕ����Ȃ����炢�ɑ����Ă���B
�@�@��͂�o�F��Curtis�̎��T�b�N�X���낤�B��������H�[�J���X�g�{�l���K�b�`�������Đ����Ă���Ƃ���������m�邱�ƂōX�ɔM���`����Ă���悤�ŁA���͂������B
�@�@��2�i�V���O���ɂȂ�A�X�}�b�V���q�b�g���L�^�����̂�����#3�wYou�fre�@All�@That�@Matter�@To�@Me�x�ł���B�X�g�����O�X�Z�N�V�����ƁA�z�[���Z�N�V������z���A���̃i���o�[�ł�Curtis�����NJy������t���Ă��Ȃ��̂��������B
�@�@�����R�[���X���g�������͋C�������炷�A�z�[���ƌ��y��ɍʂ�ꂽ�암���S�X�y���̂�Ƃ肪�`����Ă���I�[�Z���e�B�b�N�ł��ďd�߂��Ȃ��o���[�h�ƂȂ��Ă���B���Ȃ�N���V�J���ȕ��͋C��Y�킹�鉽�������������i���o�[�ł�����B�g�b�v40���肵�Ă��s�v�c�͖��������̂����B
�@�@#5�wPeople�@Like�@Us�x�ɂ�Bill�@Payne���I���K���ŎQ�����Ă��邪�A���̃i���o�[���ł����l���b�N�Ƃ��Ă̑��ʂ��������낤�B����������A�y���ŃN�Z�̏��Ȃ��f���ȃ`���[���ł���Ƃ������Ƃ��B���R�V���O���ɂȂ�ƍl���Ă������A2nd�V���O����#3�������̂ɓ����͋������L��������BMichael�@Landau�̃M�^�[�\�����ނ炵����������Y��ɏo�����C�����̗ǂ��`���[�j���O�ł���B�M�҂����̃A���o����#1�Ƌ��ɑ�D���ȃi���o�[�ł���B
�@�@�܂��A�o���[�h�Ƃ��Ă�#2�����C�ɓ����Ă���A�s�A�m�Ƀ��[�h������ꂽ���F��a���o��#6�wNever�@Saw�@A�@Miracle�x����D���ȃi���o�[�ł���B���̃i���o�[�����l�|�b�v���b�N�̃V���K�[���D��Ŏ��グ�����ȉ����o���[�h�ł���B��|����ȃo�b�N�R�[���X���ƃX�g�����O�X�V���Z�T�C�U�[�������h�肱�߂��i���o�[�ł��邯��ǂ��A�������͑S�������Ȃ��B���̃i���o�[�ł�Billy�@Joel��Elton�@John�Ƃ������s�A�m�E�}���̍ō���ɒʂ���˔\���������Ă��܂��̂��B
�@�@���C�g��R&B���b�N�̊��o�����X�����A#7�wI�@Guess�@�h���@Wasn�ft�@Mine�x���A�[�o���ŃX�}�[�g�ȃZ���X��������Ȃł���Ǝv���B���̃i���o�[�ɂ����l�F�͊ł���A�S�̓I��Glenn�@Ballard���S�������i���o�[�̓���������Ă���ƍl���Ă���B����͏����R�[���X���D��Ŋ��p���_�炩���S�X�y��������t�������邱�ƂƁACurtis�̐����e�i�[�T�b�N�X���u���[�W�[�Ƃ��������A�_���g���b�N�̋����Ɏg�p����Ƃ����_���B
�@�@#8�wNobody�@Loves�@You�@Like�@I�@Do�x�̓����t�B�X�E�\�E���AAl�@Green���v�킹��n�[�g�E�H�[�~���O�Ń��C�g�ȃ\�E���o���[�h�B�����A���ꂽ�v���C�𑱂���s�A�m�ɂ̓W���Y�̓��������邵�A���Y���I�ɂ̓��b�N�ƃ\�E���̒��Ԃ����\�E���ɂ�������l�D�݂̃r�[�g��������B�������A���̕\���̖͂L���ȃ��H�[�J���E�p�t�H�[�}���X�͂ƂĂ��V�l�Ƃ͎v���Ȃ��B
�@�@#10�wCount�@My�@Blessings�x�̓N���b�V�b�N�\�E���̃��R�[�h���悤�Ȋ��S��^���Ă���邪�A�M�ғI�ɂ͂����܂Ń\�E���~���[�W�b�N�̓����������Ȃ�ƁA���b�N���痣��Ă��܂����߁A���̃i���o�[�͂ǂ��ɂ��D���ɂȂ�Ȃ��B�A���o���̒��ł͍ł��n�Y���̃i���o�[���B�Ƃ͂������R�����i���o�[�ł��Ȃ��̂����B
�@�@���̓��������Ƀ��C�h���̃T���O���X�Ƃ����t�@�b�V����������Curtis��2nd�A���o���ł̓o�b�T���ƎU�����ĒZ���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B���̃W���P�b�g�̒���������ɂ��A��͂胁�W���[�Ŋ�������ɂ̓t�@�b�V�����ɂ��Ë����K�v�Ȃ̂��Ȃ��A�Ɗ����Ă��܂��̂��B
�@�@Curtis���g�������͂���قǍD���łȂ������炵���B�ǂ����������}�[�P�b�g�ɍ��킹��K�v���������ɂ͑��݂���̂��낤�B���A���y�I�ɂ͎���ɓ��p��\�킵�Ă����I���^�i�e�B���Ƃ͑S�����e��Ȃ����̂��B�ƂȂ�ƁA��͂�f�����[���������������ł��邱�Ƃ������ƂȂ�B
�@�@1991�N�ȍ~�͔ނ̂悤�ȃ��b�N���H�[�J����ɂ����V���K�[�����R�[�h��Ђ��v�b�V�����邱�Ƃ��������Ă����X�������邾���ł����炩�ł��낤�B
�@�@�����l����ƁACurtis�@Stigers�͒[�����Ƃ͂����A�܂������h�̃��b�N���H�[�J�����}�[�P�b�g�Ŕ����]�n�̂��鎞��Ƀf�����[�ł��A�q�b�g���L�^���������K���ł���̂�������Ȃ��B
�@�@������x�AMichael�@Bolton��Curtis�@Stigers������悤�Ȏs�ꐫ���K��Ȃ����̂��ƁA���̃A���o�����v�X�Ɉ�������o���Ē����Ȃ���v���Ă���B�@�@�i2002�D10�D3�D�j
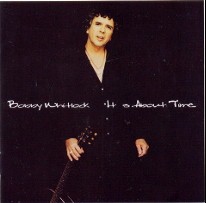 �@�@It�fs�@About�@Time�@/�@Bobby�@Whitlock�@�i1999�j
�@�@It�fs�@About�@Time�@/�@Bobby�@Whitlock�@�i1999�j
�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@Blues&Southern�@��������
�@�@�@�@�u����A�wIt�fAbout�@Time�x�|���낻�낻�̎����A��2���3��ł͂Ȃ��A4��͎����X���ė~�����ˁB���낻��l�͉�����n�삷�ׂ������������A���낻�됶���Ă������߂̂��ǂ����E��z�����߉�����ς��鎞���Ǝv���Ă���B�������������Ƃ��̂ɍ��߂Ă���B
�@�@�̂��ĖႦ��A���̂悤�ȉ��߂͕s�v���ˁA�̂�����Ă���邩��B���ꂪ�S�Ă��B
�@�@�̂��āA���̉̎������ɕt���ď�����Ă��邩�𗝉����ĖႢ�����A�{���ɁB���̂Ȃ�A�S�Ă��u���v�ɂ��Ă����炾�B�����Ėl�͍̉̂��̐��I���玟�̐��I�ɂƒN���Ƀ��R�[�f�B���O����Ă������낤����B���ꂱ�������̍\�}�������Ă��邾�낤�B
�@�@���͂��́wIt�fs�@About�@Time�x��p�ݎ��ς̒��x�O���A�����ЌR���T�_���E�t�Z�C���ɑ��Đ�[���J�����O�̓��ɏ������B��������?
�@�@��u�����āA�q���B�͊X�p�ŋ����Ă���B
�@�@�@�@��̑����ɑ��q�►�̎��[���]�����Ă���B
�@�@�@�@�����A���낻�뎞������|����������鎞�オ�B
�@�@�@�@�����A���낻�뎞������|��X�̏h������B
�@�@�@�@�₪�āA��X�͒��r�܂����������邱�Ƃ��o���邾�낤�B
�@�@�@�@�₪�āA���a�̉̂��S�����Ƃ��o���邾�낤�B
�@�@�@�@�߂����l�������邱�Ƃ���n�߂悤�B
�@�@�@�@�N�̖ڂ��܂��Ă��Ȃ�����A��Ǝ��D������荇�����B�v��
�@�@�@�i��Ғ��F�wIt�fs�@About�@Time�x�̉̎�����̂������łȂ������_����Bobby�����C�������グ�Ă���B�j
�@�@
�@�@�@�@���낻�뎄�����͂��̉̂̂悤�Ɏ����ς��Ă����ׂ����B������A�͕̂K�v�ȂB�v
�@�@�A���o���̃^�C�g���A�����ă^�C�g���Ȃɑ������z���ɂ��āA�uIt�fs�@About�@Time�v�̔������ɁABobby�@Whitlock�͈ȏ�̂悤�Ɍ���Ă���B
�@�@�����Bobby�̃C���^�����[�̈ꕔ��ق��Ȃ���ɂ��`���Ɏ����Ă����B�����Ŋ���50���邨�������̌����咣�ɂ��Ă͏��X�L���C�͂��邪�A���̃A���o���ɍ���U�߂����Ƃ͊�炩�`����Ă����K���ƍl���A�������������Ă݂��B
�@�@Bobby�@Whitlock�̖��O�́A���ړI�ɂ͂��܂�L���ł͂Ȃ���������Ȃ��B
�@�@Eric�@Clapton�͒m���Ă��Ă��ABobby�@Whitlock�̖��O�͒m��Ȃ��Ƃ�����ʉ��y�t�@���͑��������ɓo�邾�낤�Ƒz�����Ă���B���Ȃ����A���̑z���͓I�O��ł͂Ȃ��Ǝv���B
�@�@�ܘ_�A�M�S��Clapton�̃t���[�N��t�@���ɂƂ��Ă�Bobby�@Whitlock�Ƃ����s�A�j�X�g���M�^���X�g�̖��O�͂�����݂ł��邾�낤���ǁB
�@�@���̃������[��ǂ�ł����悤�ȕ��ɂ́A�߉ނɐ��@�ł��邱�Ƃ�����邪�A�ꉞBobby�@Whitlock�ɂ��ĊȒP�ɐ������邱�Ƃ��獡��͎n�߂悤�B��Ԏ����葁���̂́A1�N�x��œ��{�Չ����ꂽ���́uIt�fs�@About�@Time�v�i�M�Ճ^�C�g���́u�x���E�{�g���E�u���[�X�ƂȂ��Ă����B�X���Ō����������ɂ́B�j�̃��C�i�[�E�m�[�c�ɉ�����t������Ă��邻���Ȃ̂ŁA��������w�����Č��邱�Ƃ��ǂ���������Ȃ��B
�@�@�Ƃ������A���{�Չ����ꂽ���Ǝ��̂������ȋ����ł���BBobby�@Whitlock�̊C�O�ł̕]���͂���Ȃ�ɍ������A�X�e�C�^�X�I�Ȗʂł͑����ȑ�䏊�̒n�ʂɂ���ƌ����Ă��邱�Ƃ���������ǁA���{�ł͒m���x�͑O�q�����悤�ɍ����͖����B���̃����[�X�ɂ͔ނ��ݐЂ��Ă����r�b�O�E�l�[���ȃo���h�q����|�܂�Clapton�q���肪�����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�@Bobby�@Whitlock��1948�N�A�e�l�V�[�B�̓����t�B�X�ɐ��܂�āA�A�[�J���B�ŗc�����̑唼���߂����Ă���B
�@�@10��㔼���烁���t�B�X�ʼn��y�Ɍg���n�߁ABucker�@T�DJones&The�@MG�fs��Ɛe����[�߂Ă����B�����č��l�u���[�X��R&B�̃��[�x���ł�����Stax�@Records�ɔ��l�Ȃ���_���������AMG�fs�ƃc�A�[��60�N��㔼�ɍs���悤�ɂȂ��Ă����B
�@�@1969�N�ɁA�����t�B�X�ɘ^���ɂ���Ă���Delaney�@&�@Bonnie��Whitlock���͂���R&B�ȉ̏��ƃs�A�m�̉��t�X�^�C����]������ADelaney�@&�@Bonnie�̃L�[�{�[�f�B�X�g�ɗU��ꂻ�̂܂܃o���h�ɉ����B1971�N�́uMotal�@Shot�v�܂ŁA���̗L���ȁuDelaney�@&�@Bonnie�@&�@Friends�@On�@Tour�@With�@Eric�@Clapton�v���܂�5���̃A���o���Ƀo���h�����o�[�Ƃ��ĎQ�����Ă���B�i1���N���W�b�g����Ă��Ȃ����A���ۂɂ͔ނ̃v���C���^������Ă���̂��uFrom�@Delaney�@To�@Bonnie�v�ł���B�j
�@�@���̍��Ԃ́A1970�N�Ɋ��ɑO�N�ADelaney�@&�@Bonnie�̃c�A�[�̃��C���A�N�g�ł�����Blind�@Faith����E�ނ��Ă���Eric�@Clapton��Derek�@And�@The�@Dominos�������B�u���[�X���b�N�̖��ՂƂ����]������Ԃ́uLayla�@&�@Other�@Assorted�@Love�@Songs�v���쐬�B
�@�@���̃A���o���̃��[�h�E���H�[�J����Clapton���������AWhitlock�̃o�b�N���H�[�J���ł̃w���v�͈꒮�̉��l�͂��邾�낤�B
�@�@�������A2���ڂ̃A���o�����쐬����Derek�@And�@The�@Dominos�͉��U���Ă��܂��B���̌�A2���̃��C���A���o�������\����Ă��邪�A���̉�����1970�N�̂��̂ł���B���̎��オ�ł�Bobby�����͓I�Ɋ����������Ԃł�����AGeorge�@Harrison�́uAll�@Thing�@Must�@Pass�v��The�@Rolling�@Stones�́uExile�@On�@Main�@Street�v�i������̓A���o���ɂ̓N���W�b�g�͂���Ă��Ȃ����B�j�Ƃ��������b�N�j�Ɏc��N���b�V�b�N�A���o���Ɍ��Ղƃo�b�N���H�[�J���ő��Ղ��c���Ă��邵�ADuane�@Allman�̃��R�[�f�B���O�ɂ��X�^�W�I�~���[�W�V�����Ƃ��ĎQ������������Ă���B
�@�@���̌�ABobby�@Whitlock�̓\���������Ɏn�߁A1970�N���4���̃A���o�����쐬�B1972�N�́uBobby�@Whitlock�v����1976�N�́uRock�@Your�@Sox�@Off�v���c���Ă���B���A1st��͂��Ȃ�̕]��������Ă��邪�A�c��3���̃\����͂����������ς̃A���o���������悤�ł���B
�@�@����4���̃\����͖���CD������Ă��炸�A�M�҂�1��ڂ��e�[�v�Œ��������Ƃ�����݂̂����A�m���Ƀx�b�^���ȃ\�E����R&B�ȃX�����v���b�N�ł������L��������B����Ƃ��f�W�^�������Ƃ��čĔ����Ă��炢�������̂��B
�@�@�������A���̌�A1980�N���1990�N���20�N�ȏ��Bobby�͖w�ǃV�[���ɏo�邱�ƂȂ��߂����Ă���B
�@�@Eric�@Clapton�AJohn�@Prine�AColin�@James������The�@Jeff�@Healey�@Band���̃A���o���ɃL�[�{�[�f�B�X�g�����ăo�b�N���H�[�J���ŋH�ɖ��O������ꂽ���炢�ł���B
�@�@1990�N��ɂ͊���̓암�̃\�E����u���[�X���b�N�̃��C���ɂ͏o�����Ă����悤�ŁA���{�ł��ނ̃\�����C�������f���ꂽ���Ƃ�����B�A���o��1�������炢�̕��ʂ��������A�wLayla�x���J���@�[���Ă����悤�ȋL��������B�S������Ɉ�������ł�����ł͂Ȃ����������A�̂�т�ƍD���Ȏ��ɍD���Ȃ����̂��ăs�A�m��n�����h�I���K����e���A�M�^�[������Ă����悤���B
�@�@���ɁA1990�N��͉B���̎���ɂȂ��Ă��܂��Ă����Ɗ����āA�ނ̖��O��Y�ꂽ���ɓˑR�̐V��̔��\�ɂ͑������������Ƃ��v���o���B
�@�@���̃A���o����1976�N��4��ڂ��琔����ƁA23�N�U��ƂȂ�A�������ˑR�̃A���o���������B�������_���͉p���̃C���f�B�E���[�x���ł���Gravebine�Ƃ������R�[�h��Ђł���A���{��č��ɃA���o�������Ԃ܂�1�N���̎��Ԃ��|���邱�Ƃɂ��Ȃ��Ă���B
�@�@���̋�4�����I�ɂ��āABobby�̒��ړI�ȃR�����g�͂Ȃ����A�`���ɏq�ׂ��悤�ɁA51�ɂȂ���1999�N��Bobby�@Whitlock�́A�ނ�n��ɋ�藧�Ă鎞��̗���⒪����ނ͊����Ă����̂�������Ȃ��B
�@�@
�@�@���㐫�Ƃ������Ƃɂ���Bobby�͍X�Ɍ��B
�@�@�u���������Ȏq���̍�����A��������s�����Ƃ����d�v���ɂ��Ă͂����ƋC���t���Ă����B�哝�̂��@�c������Ђ̎В��ɂȂ��đS�Ă��R���g���[�����悤�Ȃ�Ė�]�͕��������Ƃ͂Ȃ�����ǂˁB���́A�ω��Ƃ������̂ɏ�ɕq���ŁA���N���Ă���ω��A�����ċN�����Ă��܂����ω���m��A�l���ɉe�����y�ڂ�����m�邱�Ƃӎ��Ɏ��s���Ă������������ǂˁB�v
�@�@�����āA����𑼐l�ɔ}�����@��Bobby�̏ꍇ���y�������Ƃ�����ł���B
�@�@�u���͂���Ȃ�̒n�ʂ������Ă���Ǝv���A�����𑼐l�ɓ`���邱�Ƃ̏o����B�������A��x����Ƃ����������������Ƃ͂Ȃ���B���̍��͖S���Ȃ����f���̓}���h�����ƃt���b�g�E�g�b�v�̃M�^�[���v���C���Ă����B�f���͂����������B�w��肽�����Ƃ����A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��肽��������B���ꂪ�^�����B�x
�@�@���̊T�O�͐������p������Ă���Ǝv���B�i�����j���������ׂ����Ƃ�����̂Ȃ�A����́wI�@Love�@You�x�A���ꂾ�����ˁB���͂�������̋Ȃ������A��������Ƃ��̂��Ă������ǁA���̃��b�Z�[�W�͂��������ȂB�v
�@�@Bobby�͖q�t�����e���������Ƃ�����A���y�I�ɃS�X�y���E�~���[�W�b�N�̉e�������Ȃ�Ă��邱�Ƃ������邯��ǂ��A�@���I�Ȕ������_�����l�Ɍp�������悤���B���̂������Ɂu���v�Ƃ������ƂX�Əq�ׂ���I���a�͂��Ȃ菃���Ƃ������M�d�ȑ��݂ł��邩������Ȃ��B
�@�@���āABobby�@Whitlock���u���낻��A���o�����o�������v�Ǝv�������ċv�X�ɔ��������A���o���́A�ߋ��̃A���o�������ׂĔp�ՂȂ��߁A�ߋ��̃\����i�Ƃ̔�r�͕s�\�ɋ߂����A�ȒP�Ɏ�ɓ���uLayla�@&�@Other�@Assorted�@Love�@Songs�v�i�M��F���Ƃ��̃��C���j���Ɣ�r����ƁA��͂�30�N�߂��Ό����o���V���ƁA���y�ɂ����܂�邱�ƂɂȂ邾�낤�N�ւ̂悤�ȏa�݂ł���B
�@�@Bobby�̃X�^�C����LA�X�����v��Delaney�@&�@Bonnie�̃����o�[����������ADerek�@And�@The�@Dominos��Clapton�Ɖ��t���Ă������Ɗ�{�͑S���ς��Ȃ��B
�@�@�S�X�y���A�\�E���AR&B�A�u���[�X�Ƃ������암�̍��l���y�ɍ��������R�b�e���Ƃ������b�N�����t���Ă���B�܂������̍������y�ɃJ���g���[���̃|�b�v�Z���X����������������Ă���A�P�Ȃ�u���[�E�A�C�h�E�\�E���̃V���K�[�ł͂Ȃ��A���l�I�A�����J���E���[�c�����܂��p�����Ă���l�ł��邱�Ƃ��ނ̓����ł��낤�B
�@�@�Q���~���[�W�V�����ɂ�Delaney�@&�@Bonnie����̃o���h���Ԃł���T�b�N�X�t�H�j�X�g��Jim�@Horn���n�߁A�M�^�[�ɂ�Steve�@Cooper�A�����Ă���Buddy�@Miller�B����Buddy�@Miller�͔ނ̐l�������āA�x�[�V�X�g��h���}�[��Bobby�̃A���o���ɎQ�������Ă���B
�@�@�����đS�̂��i��̂��ABobby�̃v���C����s�A�m��B3�n�����h�I���K���ł��邱�ƁA�����Ă��̑��ڂő�炩�ȁA�܂�Ń��F�����F�g�̃I�u���[�g�ŕ�܂ꂽ�悤�ȃ��H�[�J���ł���B�\���A���o���������Ƀ����[�X���Ă���������20�N�ȏ�̃u�����N������̂����A�����S�����������Ȃ����炢�ɑf���炵���A���̓������������Ă����B
�@�@�����Ɩ��N�����̍D���Ȋ��Ԃ����̂������̂��āA�A�̃����e�i���X�͑ӂ邱�Ƃ��Ȃ������̂��Ə���ȑz�������点�Ă��܂����炢�ɁA�N��ƕs�݂����������Ȃ��̂����Ղ肾�B
�@�@�܂��A�ڂɕt���̂�#2�wWhy�@Does�@Love�@Got�@To�@Be�@So�@Sad�x�i�M��F���͔߂������́j��#10�wBell�@Bottom�@Blues�x��Derek�@And�@The�@Dominos����̃����C�N��i���낤�B
�@�@�ȑO�̃N���W�b�g�ł�#10��Clapton�̒P�ƍ�ƃN���W�b�g����Ă������A����Bobby�@Whitlock���ȑn��Ɏ��݂��Ă��������ŁA�����ł͉��߂ďC�����s���Ă���B
�@�@�܂��A#2�͑O���4���ځuRock�@Your�@Sox�@Off�v��1�ȖڂƂ��Ă����^����Ă����̂ŁA���@�[�W������3�ڂƂ������ƂɂȂ�B
�@�@#2�Ɋւ��ẮA���ς�炸�̃t�@���L�[�ŔS�����̍���Bobby���L�̃I���K���v���C���ADerek�@And�@The�@Dominos���ォ�琊����ǂ��납�A�������𑝂��Ă���Ƃ���Ɋ��������o���Ă��܂��B����R&B�Ńt�@���N�ȃ��Y���ɃS�X�y���I�ȉ��̐[�����~�b�N�X���Ă���̂��A�암���o���o�b�N�{�[���Ɏ���Bobby�̎��������낤�B���̃A���o���ł̓M�^�[��Whitlock���e���āA���Ȃ�̃u�M�E�M�����o���Ă���B�o�b�N�R�[���X�ɂ͑��q��Beau�@Whitlock���Q�����Ă���B
�@�@#10�ɂ��Ă͌�ɐG���Ƃ��āA#2�ʼnߕs���Ȃ��\�����Ă����R&B�ƃ��b�N�����[���̃_�C�i�~�Y����ʂ̌`�ŕ\�����Ă����i���o�[�͑��ɂ����삪�����B
�@�@#5�wSold�@Me�@Down�@The�@River�x�ł̓T�U�����b�N�����Ղ�ȃX���C�h�M�^�[�������A�X�Ƀ��b�L���E�u���[�X��Njy�����R�e�R�e�̓D�L�����b�N���i���o�[���\��܂��B���̃X���C�h��e���܂���̂�Bobby�ł���B�X�ɁA���Ɍ��̂���s�A�m���I���K���ƈꏏ�ɒ@�����Ƃ���́A�L�[�{�[�f�B�X�g�̃A���o���̗Ǔ_����������ƕ\������Ă���Ƃ���ł���B�M�^�[�����ł͊������߂���앗���A�����Ƀs�A�m��n�����h�I���K���Ŏ���C��t���Ă���B
�@�@�|�b�v���b�N�i���o�[�ł��A�N�[�X�e�B�b�N�Ń}���h�������������A�z���C�g�E�T�U�����b�N�̉����I�ȃA�v���[�`��W�J���Ă������邭�|�b�v��#12�wI�@Love�@You�x�ł͂�����u���b�N��\�E���̉e����Y�킹�Ă��Ȃ��̂��ΏƓI�Ŗʔ����v�f�ł���B�X�����v�I�ȃ��[�Y���ƃX�P�[���̑傫���A�_���g�E���b�N�̗v�f���암���Ƃ���������_�ɏ�肭驂������Ă���̂��B
�@�@�܂��A�`���Ƃ��Ă̓��b�J�E�o���[�h�P���Ă���^�C�g���i���o�[��#3�wIt�fs�@About�@Time�x��#6�wIt�fs�@Only�@Midnight�x�ł��p���`�͂Əd�ʋ��̍H��@�B�����U���Ă���N�h�C�܂ł̈��芴���K�b�V���Ƒł����܂�Ă���B���̒��ɂ������B�ꂷ��J���g���[�I�ȓy�L�����A#6�ɂ͐▭�ȃo�����X�Ő��荞�܂�Ă���B�ꌩ�A�X�}�[�g�ȃA�[�o�����b�N�̃p���[�o���[�h���ȃA�����W�������A��Œ͂߂�悤�ȓ암�̑�n�̍��̎�G��ƔM�����`����Ă���悤�ȏ����i���o�[�ł���B
�@�@�ӊO�Ȗ��O���\���O���C�^�[�Ƃ��Č������肷��̂��V�N�ł���B
�@�@#11�wGhost�@Driver�x�ł͋���҂ɉ��ƁAJohn�@Parr���N���W�b�g����Ă���B1980�N��㔼�ɑS��No�D1�q�b�g�ł���wSt�DElmo�fs�@Fire�x��David�@Foster�Ƃ̕M�Ńq�b�g���������b�N�V���K�[�ł��邪�A�܂���Bobby�@Whitlock�ƌq���肪�������Ƃ͎v�������Ȃ������B
�@�@�������A���Ȃ�Z���ڂȃt�@���N/R&B�̉s�����ڗ���#11�̃n�[�h�E�\�E���ȃi���o�[����|���Ă���Ƃ́B�܂��A�\�E���ȃ��H�[�J���ƃn�[�h�ȃ��b�N������ł�������John�@Parr�̏����̍앗�ɒʂ��Ȃ����Ȃ����B
�@�@���l�Ƀx�^�x�^�ȃu�M�[���̃��[�Y�E�u���[�X�i���o�[���A�Ȃ̑薼�̒ʂ��#8�wBorn�@To�@Sing�@The�@Blues�x�B���̋Ȃ��Ă���ƁA�������萺�̌y�߂ȍ��l�V���K�[�ƍ��o���Ă��܂������ɍ����B
�@�@�o���[�h���f���炵���̂����̃A���o���̓��������A#4�wA�@Wing�@&�@A�@Prayer�x�͍��l��̂̔w�i�A�S�X�y���E���[�c���͂�����ƕ\�ʂɏo���Ă���o���[�h���B
�@�@�X�ɂ��C�y�Ȋ����Ń��C���E�t�B�[�����O���_���X���Ă���T�b�N�X�Ƀ��[�h�����#9�wHigh�@On�@You�x�ł͐��C�݂̃A�_���g�E�R���e���|�����[�\���O�I�AAOR�̂悤�Ȋɂ������X���[�ȃ��[�f�B�\���O�Ƃ��ĉ̂��Ă���B�����ł̓t�@���Z�b�g�C����Bobby�̃��H�[�J�������C�g�E�u�M�[�ȉ����̘A�Ȃ�ɏ���Ċ����ł��镗�i�������Ă���悤���B
�@�@�����āA�V���K�[�E�\���O���C�^�[�Ƃ��ĊÂ��A�Ȃ����͋C���o�����Ă���o���[�h���A�I�[�v�j���O��#1�wThere�@She�@Goes�x�ł���A#7�wStanding�@In�@The�@Rain�x�ł���B
�@�@���Ȃ�#10�wBell�@Bottom�@Blues�x���܂߂Ă̂���3�Ȃ́A�O���珇�ɊÂ��A���C�h�o�b�N�������D�A�S�̋Ր���݂͂܂���������Ƃ���3�_�ŋ��ʂ��Ă���B
�@�@�g���`���Ƃ����n����`�[�Y��ɓ��Ă������̂悤�ȃl�b�g�����o�Ń��X�i�[����i����͂̂���#1�ł́ABobby�̐��B
�@�@�}���h������A�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�A������12���M�^�[�Ƃ��������y��݂̂ł���h�������X��#7�̑@�ׂȃ����f�B�Ƃ�����������ȁA������������Ղ��Whitlock�̏����A�B�ׂ��A�����@����鏬���ȃs�A�m�̉��F�B�㔼�ł̃n�C�g�[����Bobby�̃n�~���O�B
�@�@�t�@���Z�b�g���������Ƃ���A�I�[���@�[�E�u�[�X�ƋC���ɑS�J�ɂ���A�����f�B�I�Ɋ����ȃo���[�h��#10�͍Ę^�g���b�N�Ƃ͂����A��͂肱�̃A���o���̊炾�낤�B�����e�[�}�ɃA���o����n����Bobby�ɂ͂��s�{�ӂ�������Ȃ����A���̖��Ȃ̑��݊��͑��̃i���o�[�����|���Ă���BEric�@Clapton�ɂ��I���W�i�������ɓ����ł��邽�߂����邾�낤���ǁA���̈�ۂ̋����́B
�@�@�������A���H�[�J���X�g�Ƃ��Ă�Clapton�����y���Ƀ\�E���t���Ŗ��킢�[��Bobby�@Whitlock�����[�h�������āA���߂Ă��̃o���[�h�͖{�̂������Ǝv���͕̂M�҂����ł͂Ȃ����낤�B���ɃV���K���A���ɗ��Ԃ��āA�T�b�N�X�̊��炩�ȉ��F�ƃu���b�W���q���ł����t�F�C�h�A�E�g�O�̏�̓��ꍞ�ݕ��͔��[�ł͂Ȃ��B
�@�@�܂��A�I���K����͋Z�Œe���Ƃ����������̃X�^�C������A�����}�������F���o���悤�ȃA�����W�����Ă���\���p�[�g�̃��[�c�B�ȃp�[�g���ׂ����Ȃ��璮�����Ƃ��ĊO���Ȃ��B
�@�@�A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ẵf�����[�͏������������������A�����N��ł���A�����悤�ɔ��l�u���[�X�E�}���Ƃ��Ċ������n�߂�Eric�@Clapton�����W���[�X������O��邱�ƂȂ������̍�i���o���A�_�l�Ə̂���Ă��闠�ŁABobby�@Whitlock�͒n���ɕ��݂�i�߂Ă������������B
�@�@�A�����J�암�̍L��Ȕ�����ōk���悤�ȁA�������Ƃ����m���ȑO�i�����s���Ă������Ƃ�������点�Ă����A���o���ł���B
�@�@���̓�����ꏊ�ɏ�ɑ��݂��邱�Ƃ���肩��`���t����ꂽ�悤�ȁu�M�^�[�̐_�l�v�ƁA�����łЂ�����Ǝ����o�Ă����u���Ղ̐E�l�v�B����2���̓�����̃\�������ׂ����Ȃ�1���ł�����B
�@�@�ǂ����Ă�Clapton���A�u���[�X�炵���u���[�X�����҂���A�X�Ƀ��b�N�V���K�[�ł��邱�Ƃ����肳��Ă������߂��앗�Ɏ��R�x���Ƃ肪���Ȃ��v���Ă��܂����������ABobby�̂��́uIt�fs�@About�@Time�v�������ŁB
�@�@�v�X��Eric�@Clapton�ł���������o���Ē����Ă݂悤���ȁA�Ƃ������@����藧�������i�ł�����B
�@�@�i2002�D11�D12�D�j�@�@�@�@
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
