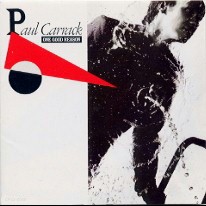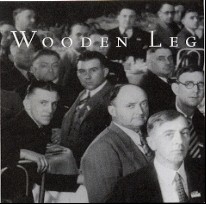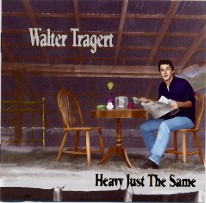Give My Regards To Broadstreet
Give My Regards To Broadstreet
/ Paul McCartney (1984)
Adult-Contemporary ★★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Soft Rock ★★★★☆ You Can Listen From Here
2002年11月14日、東京ドームでPaul McCartneyのライヴを久しぶりに観た。
正直、1989年の「Flowers In The Dirt」を最後に、それ以降のオリジナルのアルバムはPaulの大ファンである筆者でも首を捻らざるを得ない駄作「Off The Ground」。
世間的な評価は高いが、どうみてもピークを過ぎたアーティストの残りカスとしか思えない力の抜け加減をアクースティックという包装紙で欺瞞した「Flaming Pie」と続いたため、もう駄目かな、と密かにPaulは過去のアーティストになりつつあった。
「Run Devil Run」という鬼の霍乱的なロックカヴァーの好盤は突然変異として出現したが、あくまでもカヴァーのアルバムであり、オリジナル作ではなかった。
しかし、このステージを観たことにより、「Run Devil Run」で「まだ、ロックをやれるんじゃああ!!!!」と主張していたようなPaulが、確かにロックンローラーとして死んでいないことをまざまざと見せつけらた。
オリジナル曲が70年代や80年代のWings時代よりも劣るのは仕方ないかもしれないが、それを補って余るライヴ・パフォーマーとしての輝きを持つ人ということをガツンと突きつけられた感じでもある。
最新作のスタジオ盤「Driving Rain」も未だ未購入である体たらくなのだが、さて購入してみようかという気力を持ち上げさせてくれる素晴らしいショウをPaulは見せてくれたのだ。(実際に買ってしまった。やはり『Driving Rain』以外の知らない曲は全て新譜からだった。)
2時間30分、30曲を超える圧倒的なショウの熱狂に身を委ねながら思ったことは
「ああ、もっとPaul McCartneyのソロ作を聴きたいなあ。」
という著しくマニアックな感慨が1つ。これはリアルタイムで追いかけたのが彼のソロ活動時代からだったから思い入れの違いもあるだろうが、Paul McCartneyとして活動するなら、過去の遺産であるBeatlesの曲よりもソロとして自らの足のみ出歩き始めた曲で客を魅了すべきじゃなかろうか、という勝手な思い込みもこの欲求を助長しているのだろう。
とはいえ、PaulにBeatlesの名曲を演奏されると、もうヘロヘロの骨抜きになってしまうのだが。(苦笑)
そして、もう1つ。
Paulが歌うBeatlesの曲を聴いて連想したのが、今回のアルバム「Give My Regards To Broadstreet」なのだ。まあ、これくらいメジャーな作品になると、殆どの人が知っているとは思うが、一応解説。
批評家の間では物凄い評価の低いアルバムだが、筆者的にはPaulのソロ作でも1・2を争う程好きなアルバムだ。
というのはこのアルバムにはPaulがリメイクしたBeatlesのナンバーが6曲もスタジオ録音盤として収録されているからに他ならない。
ライヴの形ではPaulはかなりBeatles時代の曲を自分流にアレンジしたヴァージョンを幾つも吹き込んでいるが、スタジオ盤の形で発表しているアルバムはこの映画サウンドトラックのみである。
であるからして、Paulの歌うBeatles=このアルバム、という些か短絡的な連想に至った次第で、更に何か書きたくなってしまったという段階にある。
まず、Paulのライヴについて感想を述べつつ、このアルバムにシンクロする部分も語っていこう。ちなみにライヴ感想は青字にしてある。レポートではなくあくまでもインプレッションと言うことをお断りしておく。
まず、Prologue的なミュージカルらしきものが20分くらい行われる。
前衛オペラ? アヴァンギャルドなミュージカル? 中華、東南アジア、アフリカ、欧州各国の民族衣装を模した俳優たちが音楽に合わせて踊るステージからショウは始まる。
正直、邪魔。(を)早くPaulが観たいのだが。これを“じらし”として使っているなら相当の策士だが、まあそんなことはないだろう。
そして19時30分頃、音楽に合わせて踊っていた俳優たちが袖に消え、照明が消える。
そして「One,Two,Three,Four」のカウント・アップと共に
「You say yes,I say no〜♪」で場内大歓声。
もうこれでヤラレタ。まさか、『Hello,Goodbye』をアタマに持ってくるとは。この曲のリードはJohnだったからセットリストに入っていることは知っていたが、本当かどうかいまいち信じられなかったのだ。
黒いレザーのジャケットに真っ赤なTシャツという服装で歌うPaul。ややバックの楽器の演奏がラウド過ぎると感じるのは小会場の音響に慣れ過ぎたせいだろうか。
しかし、オープニングにJohn主導作であり、最もJohnの曲ではキャッチーなナンバーを出すという演出は、やはり度肝を抜かれた。既に大声で歌っている自分に驚き。スタートからギアが入ってしまった。
ラストの「Hela heba helloa CHA CHA,hela...」のブリッジの観客を巻き込んだ合唱の余韻も消えない内に、次が待望のソロ作『Jet』。まあ、ファンなら知らないナンバーではないだろうが、やや盛り上がり率が低く感じる。Paul=Beatles的な人が多いのかなあ、と頭の隅で思う。非常にライヴ向きのナンバーなのだが。
しかし、インターミッションのシャウトなア・ド・リヴもコロコロピアノのソロも忠実に再現してくれているのは感涙モノである。当然、♪「Jet」のところは片手を突き上げシャウト。
この曲が終った段階で、「Hello,Tokyo」の挨拶。予想通り日本語も喋り、そこで観客を笑わせる。これは少し寂しいかもしれない。英語圏なら詰まらないジョークでも挟んで、その下らなさで笑わせるのだろうが。
次の『All My Loving』ではバックのスクリーンにBeatles時代のモノクロ映像が多数フラッシュバック的に流され、否応にも4人のBeatlesを思い出される。このショウではバックの大スクリーンに映されるフィルムや光のモザイク、風景等が曲ごとに細かく演出を変えて、目を飽きさせない。この点は凄い。確かに高いチケット代を取るだけのことはある。
そして『Getting Better』。もう感動モノである。この曲は何回聴いたか分からない。Paulはレスポールでこの曲を弾いていたが、ここまでライヴ映えするナンバーだとは思わなかった。過去のツアーでは全くセットリストに入っていない曲なので、この選択は嬉しい。
これまた定番の『Coming Up』で再びロックに盛り上がる。アレンジ的には両面扱いで、結局No.1に認定されたライヴ版の『Coming Up (Live At Glasgow)』に近いストレートでソリッドなロック・ヴァージョン。1989年の「Flowers In The Dirt」ツアーの時は、かなりシンセを加えたNew Waveなアレンジ。1993年次は、スタジオ録音に近いややゆったりとしたアレンジだったけど、今回のロックアレンジが最も良い。
そしてWingsナンバーの『Let It Roll It』が来る。このナンバーは好きだし悪くないのだが、ライヴでここまで取り上げる程のナンバーではないような気がする。「Wings Over America」に収録されていたBoogieでSouthern Rockを感じられるブルージーでマッディなアレンジなら好みなのだが、日本ではウケないだろうなあ。
ところで、大スクリーンにはPaulのトーキングを同時通訳したキャプションが表示される。Paulによると6人のタイピストが一生懸命にステージ裏で打ち込んでいるそうだ。が、やはり追いつかないし、間違いも多かったのが笑えた。
試しにPaulが「僕の犬はバナナを食べる。」と言って訳させたのは笑えたし、それすら間違って打ち込まれていたりしたのにも・・・・。
このバラードを入れるなら「Give My Regards To Broadstreet」から第一弾シングルとなってトップ10ヒットに名を連ねた#1『No More Lonely Nights(ballad)』をリストに入れて欲しかった。数あるPaulのバラードの中でもヒットしているため“隠れた名曲”とは残念ながら呼べないけど、Dave Gilmoreが弾いているようなラストのギターソロをライヴで引っ張ったら相当エモーショナルな曲としてウケると思うのだが。
この後3曲は2001年のアルバム「Driving Rain」から。タイトルトラック『Driving Rain』では、
「この曲をLAでレコーディングしている最中に、オフを取って皆でドライヴに出かけた。PCH(パシフィック・コースト・ハイウェイ)を走っている時に雨に降られた。その時の思いを綴った歌だよ。」
というトークや歌詞の中に懐かしのPCHを聞けてそれが最も感慨深かったりする。やはり聴いていないアルバムからの曲では感動が低い。観客全体の反応もそれ程宜しくなかったようだ。
どうせなら、まあこれでは「Driving JAPAN」というツアーの意義がないのだが、どうせ誰も知らないだろうから、「Give My Regards To Broadstreet」に収録された新曲の#8『Not Such A Bad Boy』や#10『No Values』のロックナンバーを演ってくれたら多分感動で心臓麻痺になったかもしれないが、最高だったのだが。
新曲はバラード有り、ロックナンバー有りで良さそうなナンバーばかりだったけれども。寧ろ、Beatles時代の作風を強く意識して書かれた#8や#10を入れたほうが面白かったとは思う。
ここでPaulはギターをアクースティックに持ち替え、「60年代に人権問題を闘った人を歌った曲」と解説して『Blackbird』を歌いだす。日本語で「ジンケンモンダイ」とPaulがたどたどしく述べていたが、そこで笑ってはイケンだろうさ、日本の皆さん・・・・・。
ここからアクースティック・セットに様変わりするのだが、次のソロ作1970年作の『Every Night』はまたしても反応はいまいち。まあ、大声で合唱するナンバーでもないのだけども少し寂しい。
対照的に『We Can Work It Out』では観客も大喜び。当然♪「We Can Work It Out」や♪「Life Is Very Short」ではそこそこの合唱になっていたような。しかし、このナンバーを弾き語りするのには驚いたが、これがまた良い。
『You Never Give Me Your Money 〜 Carry That Weight』をピアノを弾きつつ、熱唱してくれているが、やはりキーボードプレイヤーとしてもPaulは凄いと思わせてくれる。
それよりも、キーボードのミキシングとチューニングは凄く上質である。コンバインド・キーボードを使っているのだが、ピアノからオルガン、エレキピアノ、ホーン、そしてバグパイプまでもコントロールしてしまっている。インディのステージではこうはいかないので、同時に出演している他のバンドの鍵盤弾きを借り受けたり、オルガンを共同で使いまわしたりするのが一杯いっぱいなのに・・・・・。
しかし、『You Never Give Me Your Money〜』のようなバラードやってくれるなら、そっちよりも#5『Wanderlast』を聴きたい。Paulのバラードでは最も浪漫珠溢れる最高にエモーショナルなナンバーである。比較的リリースが近い「Tag Of War」に収録されていたのに関わらず、更にリテイクされている。こちらの新ヴァージョンは更にアクースティックに纏められ、生ホーンも取り入れられ一層ドラマティックにしかもしっとりとしたアレンジになっている。今回のライヴでも演奏されたBeatlesの佳作#4『Here,There And Everywhere』からメドレー的に切れ目無しで続く展開は悶絶しそうに良いのだ。
そして、遂にキタ、キタ、喜田、北!!!!!!(錯乱中)
サイケディリックカラーの極彩色に塗装されたシンセサイザーが人力で持ち運ばれる。Paulは「ステロイド系でドーピングはしていないよ。」という冗談を軽く挟んでいた。
少々おどろおどろしいミステリアスなシンセのソロの後に、悲しげなピアノサンプリングが・・・・・。
そう、筆者が最も好きな『The Fool On The Hill』を12年ぶりに聴けるのだ。この曲は1988年頃、深夜テレビでPaulがピアノ一本で弾き語っている映像を見た時に忘れられなくなってしまった、後から好きになったベスト・ナンバーである。ケルティックなインタープレイといい、♪「Ooh Round Round Round Round」の調子の外れたようなサイケディリックさも最高だ。
で、更に「人が亡くなった時はとても悲しい。『これを言っておくべきだった』と後悔することも多い。僕の最高の友人だったJohnが死んだ時にこの曲を書いた。皆、Johnに拍手を。」
というPaulのコメントに凄い拍手が。この時点で『Here Today』をかなりのPaulマニアは予想しただろう。John Lennonへの追悼歌としてはElton Johnの『Empty Garden(Hey Hey Johnny)』がヒットして有名だが、この2分ほどのアクースティックナンバーは隠れた名曲だ。「Tag Of War」にひっそりと収録されていたこの曲がまさか聴けるとは思わなかった。
ついでに同じ「Tag Of War」収録の隠れた名曲で、リメイクされている#6『Ballroom Dancing』は滅茶苦茶ライヴ受けするオールド・パーティロックンロールなので、演奏してくれないかなと淡く期待したが、やはり駄目だった。非常に悲しい・・・・・・。
米国では『C Moon』なんぞもセットリストに入っていたので、これまた#14『No More Lonely Nights(playout version)』のレゲエでダンサブルな曲も息抜き的にやってくれないかと儚い期待を抱いていたがこれまた駄目。このプレイアウト編のPVは結構面白かったのだが。
John追悼の次はGeorge。「Georgeはウクレレの名手でね。彼の家には物凄いウクレレのコレクションがあった。で彼のディナーに招かれるとデザート代わりに『さあ、ウクレレどうぞ』って勧められたものだよ。」
と笑って冗談にしていたPaul。しかし、笑えるまでには時間が掛かったと思う・・・・・。
何と、Paulはウクレレソロで『Something』をプレイ。これまた吃驚仰天。が、「Georgeにも拍手を」というPaulのお願いに反応した音量はJohnの時のハンドクラップの5分の1位か?・・・・・・嗚呼、Harrisonよ・・・・・・。(涙)
これから『Eleanor Rigby』、『Here,There And Everywhere』、『Michele』といった懐かしのナンバーが矢継ぎ早に飛び出す。いまいちライヴとしてのノリには合わない曲かもしれないが、個人的に好きなナンバーなので問題なし。
「Give My Regards To Broadstreet」にも#12『Eleanor Rigby』、#4『Here,There And Everywhere』、#2『Good Day Sunshine/Corridor Music』、#11『For No One』そして#3『Yesterday』、#13『The Long And Winding Road』と6曲が再録されている。
#12『Eleanor Rigby』にはメドレーとして続く新曲、クラッシックオペラの『Eleanors’Dream』が続いている。後年の「Liverpool Oratorio」の原石を感じる。
そしてアクースティックセットが再び終了し、クライマックスへとステージは雪崩れ込んでいく。
まず、先陣を切るのが『Band On The Run』。この変調を繰り返す雄大なNo.1ヒットはライヴとしては盛り上げに最適だろう。時にゆっくりと、ポップに。時にオーケストレーション・シンセを含めて大仰過ぎるくらいに。このメリハリは部屋で聴くとかったるいこともあるが、ライヴでのノリは抜群だ。次の『Back In The USSR』のひたすらソリッドなロックチューンのタテノリには敵わないかもしれないが、聴いていて下っ腹に力が入るのは『Band On The Run』。
『Back In The USSR』ではイショフ・スターリンを始め、ソビエトの重鎮や軍隊が映されていた。20年前だったら社会問題になったなあ、と考えると時代の流れに気が付く。
思えば、「バンドは走ってきた」から今ここでPaul McCartneyのステージをシェア出来るのだから。
またまた、あまりセットに入らない『Let’em In』が来た時は息が止まりそうになった。「チャイム」のイントロで周りを無視してひとりで盛り上がってしまった。
この曲も知らない人が多いのか、いまいち反応が鈍い。パレードドラムやバグパイプといった英国トラッドの風味を効かした最高のワルツ・ポップなのに。当然全米No.1ヒット。やはりソロ時代のPaulは「イエスタディ」で十分満足している一般ファンには遠いのだろうか。
これが#7『Silly Love Song』だったらもっと反応が顕著だったろうか。「ラヴ・ソングしか書けないライター。」という批判に「それの何処が悪いんじゃ。」と堂々と反論したPaulのスタイルは大好きだ。今回のセットリストに漏れたのは非常に残念。こちらの新録ヴァージョンは、ややルーズでヴォーカルを抑えた歌。少々チープなアレンジを狙ったのだろうか。パーカッシヴなドラムと、これだけはオリジナルより強調されたホーンがドタバタな感じを出している。しかもリプライズのオマケ付き。
この名曲をPaulがどのように演奏するか、以前のヴァージョンと比べたかったのだが。予想ではかなりロックに仕上げてきただろう、今回のロックなアレンジを眺めてみれば。
まあ、『Let’em In』が仮に#9『So Bad』だったら、全く盛り下がったかもしれないが。(笑)このヴェルヴェットな雰囲気の柔らかいバラードは好きだけれど、ライヴにはあまり向かないかも。
『My Love』は定番。良かったが、やはり『Tag Of War』か、ヒット曲のよしみで『Once Upon A Long Ago』にマニア受けを狙って欲しかった。
続く、『Can’t Buy Me Love』で観客を静から動へと誘う引っ張り方は凄い。そして『Band On The Run』以上にダイナミックな007映画主題歌の『Live And Let Die』ではマグネシウムの反応を使った爆発が案の定使われた。スクリーンはやはり007映画のショットが数珠繋ぎ。このナンバーは歌のパートよりもストリングスが暴れまわる間奏の方が長いように思える。レコードのヴァージョンではToo Muchで聴く気分によってはスキップする曲だが、ライヴでの爆走には最適なナンバーだろう。
『死ぬのは奴らだ』からピアノに座ったPaulは続けて『Let It Be』。そして再びサイケカラーリングのキーボードに座り直してオーラスが『Hey Jude』。このコンボは反則だろう。『Let It Be』で『Hey Jude』だ。最も有名なヒット曲の筆頭を2曲並べられてはもうコメント無し。
『Hey Jude』では「最後は皆で歌ってくれよ。」という宣言通り、コーラス部分では観客だけに歌わせる。
「オトコダケ。」「ツギハWomen、オンナダケ。」「イッショニ、All」と♪「Na,Na,Na.....」の役割を割り振り、鍵盤から立ち上がりステージの際まで身を乗り出し、オーディエンスを乗せていくが、そうするまでもなく、全員が歌っている。まあ、最初から歌ってくれと海外では何時も言うのだが、流石日本のことを良く分かっている。コーラスだけ歌ってくれと言うのは。(苦笑)
本編終了後のアンコールは2部構成で、5曲。
まず、『The Long And Winding Road』。Paulが常々批判してる「Let It Be」のスペクターアレンジを蹴り飛ばすようなシンプルなアレンジ。スクリーンではひたすら道を走る車から撮影された、道路の映像が映される。単純だが効果的な演出だ。
次いで、ホンキートンクなピアノが懐かしい、『Lady Madonna』。ここで一段バラードからロックに持ち上げておいて・・・・。やっぱり出てきた『I Saw Her Standing There』。場内恐らく総立ちだ。来るとは分かっていても、お約束でも熱いロックナンバー。Paulは琵琶ベースを持ち、Beatles時代に、10代に戻ったよう。「Run Devil Run」で弾けていた絶倫ロック魂を叩き付けてくれる。しかし今年2002年で60歳になったとはとても思えないのだが。50代で老成して隠遁するシンガーも多いのにこのパワーはなんだろう。
第2部が『Yesterday』。これは今まで散々一緒に歌っていたのだが、ただ、耳を傾けるだけ・・・・・。
「Give My Regards To Broadstreet」に収録されている#3『Yesterday』もアクースティックギター1本のアレンジで、ライヴでPaulが好んで演奏するスタイルに近い。#2の『Good Day Sunshine/Corridor Music』からメドレー的に続く流れも良い。ライヴ・ヴァージョンが気に入ったら、このアルバム買えばスタジオ録音で同じ『Yesterday』が堪能できること請け合いだ。
対して、#13『The Long And Winding Road』はサックスを絡めた、ややムーディなアレンジにしている。オーケストラも控え目に取り入れているが、オリジナルのようにドラムやベースが殆ど聴こえないという欠点はない。よりアダルトなヴァージョンと考えるべきだろう。
そして最後の最後は何と、ロックメドレー。『Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band 〜 The End』。『ペッパー軍曹』はリプライズの方だ。これまた物凄いハードドライヴィンなロックに仕立てている。できればアルバムのオープニングであったオリジナルのブルージーでファンキーな方を聴きたかったのだが。そして『The End』。これまたかなり変則的なアレンジ。ドラムのソロの後、ギターリスト3人がお互いに物凄い自己主張する。
「色々な人に感謝します。バンドのメンバー。ステージを作り、サウンドを補助してくれたクルー。そして何より、今日観に来てくれた君たちへ!」
の挨拶で終るライヴは何と2時間半のぶっ続け演奏。物凄いパワーだった。
今回はこれが最後と思い、ライヴに足を運んだが、これならまだまだワールドツアーをやりそうである。実際に若手のアーティストのライヴとエネルギー的には遜色ない。実に濃厚なギグを楽しめた。久々にシアワセを感じた・・・・。
さて、最後に本題の筈だった(汗)「Give My Regards To Broadstreet」についてもう少しだけ触れておくか。
映画のサウンドトラックである本作は「ビートルズがやってくる、ヤア!ヤア!ヤア!」に近い作品だろう。
映画の中でもPaulはロックスターであり、彼の新アルバムのマスターテープが盗まれるところから始まるミュージカルと物語をごっちゃにしたような作品。
が、正直映画はクソだ。(をい)見る必要なし。80年代はレンタルビデオ屋の大きい所なら1本くらい置いてあったが、最近は見ない。し、見ないほうが幸せと思うこと。(おい)
映画の不出来も手伝って、「今更Beatlesの再録を入れて話題性かい。」と批判を受けたが、内容的には良いと、少なくとも筆者は思う。ライヴ録音以外で6曲もBeatles新ヴァージョンが聴けるし、新曲や他のリテイクも素晴らしい。
未聴の人は発売されたばかりのPaulのライヴ盤よりこっち聴いて見るべし。
なお、青で書かれたライヴのインプレッションの曲順・曲名は完全に記憶に頼っているので不正確。ということでその点だけ了承を。
筆者はセットリストをメモしながら見るライヴなら家でDVD買えば良いと考えているからだ。ライヴならライヴの空気に身を任せヒートアップし、記憶に残ったナンバーだけ書き残せば良いのだ。・・・・・言い訳がましいなあ・・・・。
(2002.11.16.)
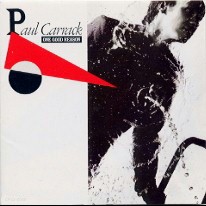 One Good Reason / Paul Carrack (1988)
One Good Reason / Paul Carrack (1988)
Adult-Contemporary ★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Blue-Eyed Soul ★★☆
Steve Winwood、Felix Cavaliere、Michael McDonald、Daryl Hall & John Oates、Boz Scaggs、Van Morrison......etc....。
筆者が愛して止まないヴォーカリストは自身の浮気性な性質なため数多いが、上で列挙したヴォーカリストは多かれ少なかれ、ブルー・アイド・ソウルという「青い瞳の白人が歌う黒人音楽」の影響を音楽に取り込んでいるシンガーである。
コテコテなアフリカン・アメリカンのR&Bは全く苦手で聴く必要を感じないけれども、微妙に黒っぽいこういった音楽は嫌いではない。黒くなり過ぎるとサヨウナラになるけれども。
しかし、ブルー・アイド・ソウルのヴェテランシンガーを愛して止まない理由は、特にそのヴォーカルそのものに魅力があるからだ。最近のヘヴィロック勢の頭悪そうなヴォーカリストは宇宙の果てで乾燥していって貰えれば全然良いのだが、ルーツロックのインディバンドヴォーカリストも「普通に聴ける」「悪くない」という程度の及第点なヴォーカルが溢れている現状を鑑みると、声に魅力のあるヴォーカリストと言うのはそれだけで宝石並に貴重な存在だ。
それだけ、ブルー・アイド・ソウルをロックやポップのポピュラリティに混合させるには、ヴォーカリストの喉がある水準に達していることが必須条件なのだろう。
また、こういうアーティストが希に(一部は頻繁にだが)作製する、Blue-Eyed Soul色よりもPop/Rockの面積が広く塗りこまれたアルバムが更にこういうヴォーカリストを好みにさせている要因でもある。どこかに小粋で渋いソウルやR&Bのグルーヴなリズムを刻みながら、ポップの即効性やロックの元気さを同時に並立させている。こういうアルバムこそロックの名盤になり得る可能性が高いし、実際に私的名盤になっているのは、ブルー・アイド・ソウル系のアーティストが作ったポップ・フィールドに翼を展開した作品が、ベッタリR&BやBlack Contemporaryという青い瞳が黒く濁るくらいに深みにはまり込んだアルバムより圧倒的に多い。あくまで私的嗜好の問題だが。
Paul Carrackもそういった名ヴォーカリスト、ブルー・アイド・ソウルを基盤にしたロック/ポップ・ヴォーカリストという基準を満たしている男である。当然、筆者の愛すべき男達のリストには随時名を連ねているシンガーでもある。
特にスター的な地位を得たSteve Winwood、Hall & Oates、Boz Scaggs、Michael McDonald等冒頭で列挙したシンガー達と比較すると非常に地味と言うか、裏街道を進んできた人でもある。
ヒット曲を全く持っていないということはないし、著名なグループに在籍したり、大物アーティストのバックバンドやパートーナーとして堅実に活動しているし、全米No.1ヒットシングルも彼名義ではないにしろ持ち歌にしているのだが、どうにも目立たないのだ。
これはソロシンガーとしては大ブレイクしたことがないのも要因かもしれないが、ヴォーカリストというバンドの看板でありながら、ここまで知名度や世間の評価が長くメジャー・シーンで活動しているにも関わらず不当に低い名ヴォーカリストも少ない。
「ポップ・ミュージックの職人」、「ロック界の渡り鳥」というような表現を洋の東西を問わずに与えられていることに、Paul Carrackのステータスを窺い知ることができるだろう。こういった別名は普通、完全に裏方に徹しているセッションミュージシャンに与えられることが大多数だろう。
勿論、Paul Carrackはキーボーディスとしての腕も確かであり、Eric Clapton、Elton John、Roger Waters、John Hiatt、Aztec Camara(懐かしい・・・)、BB King、Phil Manzaneraといったアーティストのメジャーアルバムで多彩な鍵盤を多様にプレイしている。これ以外にもソングライターとして、またバックヴォーカリストとしても多数の参加アルバムがある。
例えば、Eaglesの復活アルバム「Hell Freezes Over」に14年ぶりの新曲としてThimosy B.Schimtがリードを取った『Love Will Keep Us Alive』のソングライターのひとりがCarrackであるということは意外に知られていない。(1996年のPaulのソロ作「Blue Views」で後追いセルフ・カヴァーしているからファンにはお馴染みだろうけど。)
しかし、やはりPaul Carrackの魅力はセッション・ミュージシャンやソングライター以上にヴォーカリストと言うこの一点に尽きると考えている。
甘くもあり、苦くもあり。粘り気があり、然れども柔らかいフレキサブルさもあり。ソウルフルであり、パワフル。高音域を実に巧みに使いこなし、ハスキーにならない程度な絶妙なコブシの振り回しは一級品だろう。
声自体はハイトーンに特化していないけれども高目の音域は得意。バスやテナーのヴォーカルでもないが、コッテリとした味わいのある深みがある声質。
Steve WinwoodとPhil Collinsを足して、Paul Young(先年無くなった元バンドの同僚ではなく、『Every Time You Go Away』のカヴァーヒットを持つシンガーの若い方。)の滑らかさと黒っぽさを隠し味にしたような得も言わぬ魅力のあるヴォイスだ。
ソウル風のバラードから産業ロックにプログレシッヴナンバー、ポップチューン、ニュー・ウェーヴ、勿論R&Bやロックナンバーまでオールマイティに歌いこなす十徳ナイフのような器用さ。まさに職人と言うステイタスが相応しいヴォーカリストである。
この何でも歌えてしまう器用さが、逆に器用貧乏として印象を薄くしているのかもしれないが、幾つものバンドやプロジェクトでリードヴォーカルに起用される実績を踏まえても、その実力は折り紙付き。
筆者としてはPaul Carrackの音楽自体が全て凄いとは思っていない。それは後にもう少し長く書くことになるが、特にR&Bに走り過ぎている場合が結構多いからである。勿論、Carrackをブルー・アイド・ソウルのシンガーとして尊敬はしているけれども、彼にはPop/Rockのヴォーカリストであって欲しいのだ。
とはいえ、そうやってコマーシャリズムから適度に距離を置いているからこそ、Paul Carrackが評価できるという点も確かにあるので、このあたりは非常に微妙である。
Steve WinwoodにしてもBoz Scaggsにしても、Felix Cavaliereにしろ、幾分かポップで売れ筋に踏み込んだアルバムを作成してヒットを飛ばしているからこそ、好きである面が存在するのはPaul Carrackと同じであるし。
振り子みたいな現象、というよりも柱時計の振り子が揺れるように、時にはコマーシャリズムに迎合と言うと響きは悪いけれど、売れ筋の境界線を越えることがあるからこそ、Paul Carrackを始めとするブルー・アイド・ソウル系列のロックシンガーが好きなのだから。
今回筆を執ったPaul Carrackの3枚目のソロアルバム−メジャー・リリースでは2枚目−の「One Good Reason」は恐らくPaulのキャリアの中でもかなりポップサイドへ、メインストリームのポピュラリティに針が触れている作品であると思う。
Felix Cavaliereで言えば1995年の「Dream In Motion」、Michael McDonaldなら1982年の「If That’s What It Takes」という具合のブルー・アイド・ソウルやR&BよりもポップやAORの指向性が多目なヴォーカルアルバムのクラスに当て嵌まるだろう。
21世紀のアメリカン・ポップチャートは崩壊していて粗大ゴミ処理場所のような体たらくに堕落しているが、1980年代の「それなり」にヒットチャートが信頼できた時代に、このアルバムは2曲のトップ40ヒットを排出している。Paul Carrackは合計4曲しかソロ名義のトップ40ヒットを持っていないのだが、その内2曲はこの「One Good Reason」に収められているのだ。
このアルバムで商業主義に媚びてはいないが歩み寄りをし過ぎたのを恥じたのか、2年後の1989年に発表した4作目の「Groove Approved」ではかなりレコード会社の売れ筋路線から外れた玄人指向の強い−どこかしらSteely Danを連想させる−ブルー・アイド・ソウル路線に戻っている。
が、その当時Paulは「ボチボチ、僕がソロで売れても良いんじゃないかな。Mike
+ The MechanicsやSqueezeの一部としてではなく、僕本人を見て貰いたい。」という趣旨の発言をしているので、時代感覚そのものがズレていたのか時代を読み誤ったものか・・・・・。
とはいっても、比較の問題でポップ指向が強いアルバムということである。前後作と比べた場合、最もキャッチーでメジャー感覚が豊富なだけであり、やはり自分の持ち味であるブルー・アイド・ソウルへの拘りは随所に見られる。
まずは、半数を占める他のライターが書いたマテリアルのうちの#3『Button Off My Shirt』。このナンバーは英国ポップデュオとして1970年代に活躍しSimon And Garfunkelの英国版とまで呼ばれたGallagher & Lyleの片割れ、Graham Lyleが元バックバンドの鍵盤担当であるBilly Livseyと書いたリズミカルなポップナンバーである。モータウン・ソウルを思わせる女性コーラスを効果的に駆使したグルーヴィなポップチューンであり、シンセサイザーの多用とパーカッションが使われ過ぎにも思えるが、ポップ感覚とソウル感覚が上手くミックスしている。
そして当時ヒットシングルを量産し、トップバンドの地位を固めていたHeuy Lewisが提供したナンバー、『Here I am』。こちらはまさに書き手のHeuy Lewisが得意の、黒っぽいノリを持ったダンスリズムな、それでいてロックしている曲だ。R&Bの酸味ではなくマッタリとした包容力を備えているナンバーでもあり、これはHeuyが歌ったほうがしっくりくるかもしれない等とは考えなかった。Hueyが歌うともっと荒削りになりそうだし、それはそれで魅力はあるけど、この柔らかさは出ないだろう。
しかし、ブルー・アイド・ソウルへの傾倒は基本として、この「One Good Reason」を特徴付けているのは、このアルバム直前に参加した、GenesisのギタリストMichael Rutherfordが一時プロジェクトとして結成したMike
+ The Mechanicsへ参加した影響だろう。
このプロジェクトからは2曲の全米トップ10ヒットを含む3曲のシングルヒットが生まれ、アルバム自体もトップ40入りするというヒットを記録し、Paulもヴォーカル専任として雇われ、3曲を歌っている。しかも第一弾シングルとしてカットされ全米第6位まで上昇した『Silent Running (On Dangerous Ground)』はPaulがリードヴォーカルである。
このヒットにより、1989年には2枚目のアルバム「Living Years」が生まれ、そこからPaul担当のナンバー『Living Years』が全米No.1ヒットとなるのだが、それはまた後のお話。
兎に角、このプログレッシヴ・ポップロックのバンドへ参加し、久々にメジャー級のヒットをかっ飛ばしたことと、その人脈は「Mike
+ The Mechanics」のヒット直後に発表されたPaulの3作目に鮮度を保ったまま持ち込まれていることが明確である。
まずは、第二弾シングルとなって小ヒットとなった#1『One Good Reason』。ファンキーなR&Bの味わいのあるロックナンバーだけれども、「Mike
+ The Mechanics」のプロデュースも担当していたChristopher Neilの手腕が発揮されたのか、プログレッシヴで産業ロック的な装甲を鎧った厚めのホーンシンセサイザーが鋭いナンバーとなっている。
また、1980年代の前半を殆どパートナーとして過ごした英国パブロック界の重鎮Nick LoweとPaulが共作した#5『Double It Up』は、ニュー・ウェーヴの香りに満ちたギターロックとシンセホーンがハードにうねるナンバーで、これはブリティッシュ・ルーツを感じると共に、モロにMike
+ The Mechanicsのプログレ・ハードな展開を得意とする方向性を持ち込んでいるのが分かる。
この要素は#7『Fire With Fire』にも共通である。Christopher Neilは「Mike
+ The Mechanics」でも殆どのナンバーをMike Rutherfordと書き上げているが、コーラスの付け方や生サックスフォンのアレンジで固めのロックナンバーに緩衝材的な役割を持たせるところは、実に「Mike
+ The Mechanics」似せた作りとなっている。
更にエレクトリックで浮遊感のあるナンバーに仕上げているのが、同じくChristopher Neilと書いた#9『Collrane』である。このNeilとの共同作業の成果は、それなりにドライヴするギターの音色とオルガンサンプリングを含む多彩なキーボードを駆使した、如何にも80年代英国エレクトリック・ロックというナンバーだが、幾つかの瞬間に英国ルーツロックの元祖的なパブロックな側面が見えているのが、Paulの原点を窺わせて興味深い。
バラードも、Paul Carrackのヴォーカリストとしての実力を素で示すことを主眼に置いたに違いない、地味だが、じっくりと味わえるものが揃っている。
唯一のCarrackの単独作である#4『Give Me A Chance』では少しだけディレイを掛けたシンセサイザーとストリングスシンセをメインに置いた鍵盤をメインにして極力ギターやリズムセクションを押さえ、Paulがエモーショナルに綴るバラード。ハーモニカのようなチューンを施したキーボードが実に甘い郷愁を惹起させる。
#10『(Do I Figure)In Your Life』はJoe Cockerのデヴュー盤「With A Little Help From My Friends」でのソウルバラードが有名であるけれども、Paulはキーボードを幾つか重ねて、よりブルー・アイド・ソウルをモデレイトしたポップバラードに仕上げている。この歌にはRod Stweartに通じる男の浪漫を感じたりもするのだ。
残り2曲のシングルとして切られたナンバーはどれもアルバムのハイライトだろう。
まず、Paulのソロとしては最大のヒットになっている#6『Don’t Shed A Tear』(邦題『涙に別れを』)。トップ10圏内に飛び込んだ1987年の大ヒットナンバーである。これはカナダの産業ロッカーでありシンガーソングライターで、自らも小ヒットナンバーを記録している一発屋Eddie Schwartのナンバーをカヴァーしたものだ。Eddieのオリジナルはもっと大人しいアレンジである。
その地味ナンバーを、弦楽器系のサンプリングかギターで出しているのか非常に微妙な音色だが、不可思議に耳に残ってしまう電子弦楽器リフを中心にポップロックとして手直ししている。このエレクトリック・チェロやコントラバスで重ねたようなシンセストリングスの繰り返しが奇妙に古臭くて、しかし新しいというアンビヴァランツを醸し出し、一度聴いたら忘れられられないという印象度を生み出している。物凄いヒット性のあるナンバーではないのだが、何故かヒットしたのも頷けるという面白いナンバーだ。
最後が3枚目のシングルとして切られたが、英国でしかヒットしなかった#2『When You Walk In The Room』。
英国のヴォーカルグループ、The Searchersが1964年にヒットさせている超弩級にキャッチーな曲がオリジナル。これをJackie Raneという女性バックヴォーカリストとデュエットの形でPaulは再生している。前作から生まれたトップ40ヒットで後にLinda Ronstadtがカヴァーもしている『I Need You』と並んで、Paulが歌ったナンバーでは最もキャッチーな曲となると思っている。
筆者も最も好きなナンバーであるのだが、ヒットしなかったのは残念だ。このアルバムでは最もバランスのよいPop/Rockであると思う。
このアルバムが結局、Paulのソロ作では4作目の「Groove Approved」と共にセールスとしては最も善戦した。しかしながら、結局中ヒット程度のアルバムで終ってしまっている。寧ろ、1980年代の後半から1990年代初めに掛けてのPaulはMike
+ The Mechanicsの2枚の看板ヴォーカルとしての片割れというイメージの方が強い。グループに所属していることが多いので、ソロ作のリリースには空白が長い期間もあるけれど、他のバンドのヴォーカルとしてリリースされたアルバムを加えると、2年か3年毎に何らかの作品を発表しているシンガーである。
全体的にブルー・アイド・ソウル系の名シンガーは寡作な人が多い中で、90年代にはMike Rutherfordとの活動を含めると6枚のアルバムをソロ作を含めリリースしているのは実に精力的と言える。その点でもこのシンガーは評価できると思っている。あまりにアルバムを出さない人がWinwoodやCavaliereを代表として多過ぎるのだ。
Paulの経歴については、かなり簡単に手に入るだろうから、サラリと流すだけにしておく。
1951年に生まれ、パブロックバンドのWarm Dustからプロのキャリアをスタートさせ、欧州を中心に活動。
その後Aceのヴォーカルとして『How Long』の全米トップ3ヒットを残す。
Ace解散後はカントリーロックに傾倒していた時代のFlankie Millerのアルバムに参加。バックバンドにも加入。
1970年代後半には、Bryan FerryのRoxy Musicへキーボーディストとして参加。副メンバー扱いとして2枚のアルバムのレコーディングに加わる。それと並行してSqueezeも掛け持ち。「East Side Story」でリードナンバーとなった『Tempted』がヒットする。
1980年代はNick Loweとコンビを組んで活動。Nick Lowe & His Cowboy Outfitの中核メンバーとなる。この頃からソロアルバムのリリースを開始。2枚目の『Suburban Voodoo』からメジャー契約となる。』
そして1985年にはMike RutherfordのプロジェクトThe Mechanicsにヴォーカルとして参入。次第にPaulのウェイトは増加し、キーボードに作曲とアルバムが後に行くほどPaulのクレジットは増える。
このバンドの活動と共に、ソロアルバム、セッションミュージシャンとして活躍。
最新作は2001年のカヴァー中心に纏めたアルバム「Groovin’」となっている。簡単過ぎるが、彼の経歴は簡単にキャプチャー可能なので、このくらいで良いだろう。
まさに職人という経歴である。万能の鍵盤プレイヤーであり、ヴォーカリストである。
これからも決して大ブレイクはしないが、堅実に活動していくことは全く疑いないシンガーでもある。それはそれで安心と共に残念さも覚えるのだが。
ちなみに初期のアルバムは殆ど廃盤になってしまっているが、日本の中古屋には結構高確率で転がっている。もし見かけたら聴いて損はしないので、是非救出して欲しい。
また彼のアルバムはほぼ日本盤化されているので、新しいアルバムなら比較的簡単に入手可能なのも嬉しい。
折角日本盤をリリースするならもう少しプロモーションもして欲しいのだけれども。 (2002.11.23.)
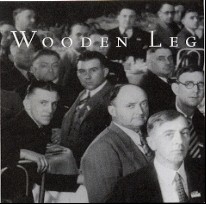 Wooden Leg / Wooden Leg (1996)
Wooden Leg / Wooden Leg (1996)
Roots&Traditional ★★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Alt-Country ★★★★
名盤というものは得てして、オープニングの1曲目から最高に素晴らしいナンバーが飛び出ることが多い。だからこそ、アルバムへの好感度が増し、更にアルバムの評価を高めるという循環になるのだが。
それとは別に、「最初の曲だけは良いのに・・・・・。」とネガティヴに評価されるアルバムもこれまた数多存在する。
1曲目に気合入れ過ぎたのか、後に行く程尻すぼみという作品の傾向は珍しくない。というかこれまた多いし、1曲聴いて買って後に後悔というパターンを量産する困った存在でもある。
で、本題。この「Wooden Leg」は確かに好きなアルバムだけれども、物凄いストライクなゾーンに鎮座しているアルバムでもないのだ、正直な話。勿論、良いアルバムなのだけれども。だがしかし、オープニングの2曲は最高。この流れを聴くだけでも、このアルバムを手にする価値は絶対にある。
#1『Champaign』からメドレーで続く#2『Sweet Lies』への流れは90年代では最も好きなアルバムの幕開け!!
なのである。これは後に各曲のインプレッションで再度取り上げるが、この2曲のコンボに勝るオープニングにはここ10年ほど出会っていない。勿論、個別の曲ではこの#1『Champaign』〜#2『Sweet Lies』よりも完成度もメロディもアレンジも高い曲はゴマンと存在するのだが、個人的な嗜好ではこれが現在も私的ランクのトップとなっている。
裏を返すと、このアルバムに対する高得点はこの2曲のツボ填まりに引っ張られている箇所もないとはいえないかもしれない・・・・。どっちや!!
Terry Andersonを始め、Eric Ambel、Bottle Rockets、Yayhoosといったルーツロックのロックが濃厚なアーティストを多数抱えていた、East Side Degitalというレーベルが1990年頭に発足している。かなり面白いレーベルだったのだが、丁度この「Wooden Leg」のリリース後、1996年後半あたりから非常に方向性が分からないレーベルに変わってしまった。
現在はルーツ系のアーティストを抱えてはいるけれども、1970年代や80年代に活躍したあまりメジャーでないバンドを抱え、プログレッシヴやニュー・ウェーヴのバンドまで混在する面白いレーベルではなくなってしまっている。寧ろ提携レーベルである北欧のルーツロックを扱い始めているレーベルの方がこれからを期待できそうである。
・・・というかもう潰れていると思っていたりしたら、しっかりと存続していたので驚いた・・・・。(汗)
そのESD=East Side Digitalには1990年代の前半にThe Blood Orangesというバンドが所属していた。
このBlood OrangesというバンドはAlt-Countryという単語が造成される前から活動していたという点では、一般にAlt-Countryの発火点となったのはUncle Tupeloが1990年に発表したデヴューアルバムである「No Depression」であるとされており、プレAlt-Countryバンドのひとつであると言うことは間違いなかろう。
しかし、Uncle TupeloがAlt-Countryの草分けとか、第壱号のアーティストとかとまで混同してしまっている見解が多く見られるののまでは看過することは出来ない。確かに、Alt-Countryの代名詞となる「No Depression」というアルバムを発表したUncle Tupelo(以下UT)の功績は大きいが、UT以前や同時期にも今で言うAlt-Countryという音楽を演奏していたバンドは存在するのである。
それが、Blood Orangesである。アルバムのデヴューもUTと同じく1990年。寄り道になるが、このデヴュー盤の「Corn River」は非常にプレス数が少なく、そのため後追いのファンによる検索熱から火が付いて現在でも物凄いプレミア価格になっている。
そのBlood Orangesは解散する1995年までの間に2枚のフルレングスアルバムと1枚のミニアルバムを世に出しているけれど、どれもカントリーというジャンルでは少々選り分けに難のある作品であった。つまりAlt-Countryと呼ぶべきアルバムなのだが、UTらが世間に新しい音楽として認知させた(または再評価させた)Alt-Countryというシロモノとは少々趣を異にするサウンドであると思う。
UTがガレージロックやパンクロックをトラディショナルな音楽と融合させていたのに対し−これとてJason And The Scorchersを始めとするカウ・パンクのバンドが既に1980年代に実践はしているのだが−Blood Orangesはもっと草の根的な伝統音楽であるグラスルーツ/ブルーグラスの田舎臭い音楽性をより多く含んでいた。
まあ、要するにカントリー的なポップさよりも、米国中部から南部に掛けてのブルーグラスなノリをロックサウンドと共存させようと意図していたバンドだった訳である。結果としてかなりヒネこびて翳りのあるサウンドが印象的なロックバンドになっていったのだが。
さて、それなりのスペースを使ってThe Blood Orangesについて書いたのにはそれなりの理由がある。
それはこのWooden Legというバンドが、Blood Oranges解散後にバンドの主要メンバーによって再編成されたグループだからである。しかも、Blood Orangesよりも面白い音を出すバンドである。ポップさでもロックの度合いでもBlood Orangesを上回っていると思うし、トラディショナルなベントさというかアクの強さも実にユニークに引き継いでいるのだ。
Blood Orangesではアクの強さが陰鬱なサウンドやダーティな点がポップミュージックの一般性をスポイルしていることが結構起こっていた−それこそルーツバンドだという意見はもっともだけれど、筆者にはあまりポップさと掛け離れるとどうも駄目なのだ。ルーツ愛好家としては異端たる所以だ−けれども、Wooden Legではトラディショナルの土と伝統に澱んだようなクセの強さを独特のPop/Rockとして表現することにより長けている。
このTraditonalと巧みに折り合いをつけているという点では、既に紹介済みのClodhopperと似ているバンドでもあるだろう。が、Clodhopperよりもロックするところはロックするバンドである。よりアクの強さも強烈であるという箇所も同時に引き摺っているけれども。
それから、バンドのメンバーのうち4人がBlood Orangesに在籍経験を持つミュージシャンなのだが、最大のポイントは
Blood Orangesでメッチャ鬱陶しかった女性ヴォーカルがいないこと!!!
である。Blood Orangesにはベース兼ヴォーカリストのCheri Nightという女性がいたのだが、これがたまにリードヴォーカルを担当していたのが実にウザかったのだ、女性ヴォーカルに殆ど価値を感じない筆者においては。バックヴォーカルとしてもそれ程良いコラボレーションを歌に与えていないヴォーカルなのに、あまつさえ、リードも担当するとはけしからんと常々苦々しく思っていたところに、まるで筆者の願いが届いたような女性ヴォーカルを外しての再編成である。
これで買わずにいられるだろうか、いや、ない。(反語)
そして、更に購入の動機を後押ししたのはCDに貼られたステッカーの
「Wooden Leg Consists Former Blood Oranges Menbers」という紹介コピーのみならず、
このオヤヂてんこ盛りのジャケットだ!!(をい)
オヤヂマニアな変態的嗜好を特にジャケットに対して有する筆者のずれた嗜好にクリティカルヒットした。グラマーな女性なんぞを使うジャケットは信用ならないという歪んだ筆者の眼にはこの売る気の全くないキャッチーさの欠如したジャケットは、それだけで信用できるという盲信を与えるものだったのだ・・・・・。(腐)
この枯れ過ぎたオヤヂ大集合の表ジャケットと比べて、反対側の裏面にはやはりモノクロームで小学生のクラスで撮影された記念写真と思える子供たちの写真が貼られており、卒業何十年か後の嘗ての少年少女(とはいえ、表ジャケットはおっさんオンリーだが)の時間の経過を示唆することをジャケットの構図を介して行っていると予想している。
クレジットに拠れば、プロデューサー兼メンバーであり、更にジャケットのデザインも手掛けているギタリストのMark Spencerの家族の写真を借用しているとのことだが。
インナーのジャケットにもメンバーの家族写真があちこちにモノクロームに印刷され、嫌が応にもレトロアクティヴな雰囲気を演出している。
唯一のカラー写真はバックインレイのマンドリンを演奏しているリードヴォーカリストのJim Ryanと歌詞カードの裏面に書かれた前衛的な落書きのみという、デザイン的には白黒色が非常に多く使われている。しかし、暗色に染まったジャケットに相反して、Wooden Legのサウンドは、Blood Orangesにしばしば見られた薄っすら掛かった雲のように翳った空気はそれ程目立たない。
トラッド的なものよりも、民族的、エスニック的、ワールドミュージック的な無国籍風味が際立ったオルタナティヴ的なトラッドサウンドが目に付くのだ。が、Wooden Legの基本音楽性にはあまり暗さやダートさは感じられない。
寧ろ、カラカラに乾ききった大地に座り込んで民謡を歌う褐色の肌をしたアメリカン・ネイティヴの姿が瞼に浮かぶようだ。
乾き、乾燥し、赤茶色と褐色と黄土色の岩石砂漠の暑い空気に触れるようなドライな寂寥感がダート感覚を押しのけて存在している。
Jim RyanはBlood Orangesの次に立ち上げて一時期掛け持ちもしていたBacon Hill Billiesというロックな方向性も持っていたブルーグラスバンドでも一貫してマンドリンを弾いていた筋金入りのマンドリン・マンである。1990年代のインディアーティストのそれなりのアルバムでマンドリンで参加することが多く、ヴォーカリストとしての力量もある人なのだが、どうやらマンドリン担当として高い評価を受けている模様だ。
マンドリンだけでなく、スライドを始めとしたルーツギター各種もWooden Legの音楽をユニークな存在へと押し上げる後押しをしている。雰囲気としては完全にトラッドやブルーグラスの境界を跨いで超えてしまっている歌にも、ロックギターとして骨子を支え、安易にトラディショナルのみのバンドに陥らない防波堤の役目をしてもいるのだ。
もっとも、基本としてポップなナンバーが多い。だから、トラディショナルの磨れ切って草臥れた土に塗れる土着音楽との融合をポップさが果たし、アクが強いだけでなく一風変わった様相で完成することに寄与している。
つまり基本としての楽曲が良いバンドは何を指向してもPop/Rockとして成り立つということを実証しているのだが。
まず、何処かの民族音楽を取り入れたような怪しくもエスニックな打楽器とマンドリンだけで鬱々と綴られる#1『Champaign』。ポップでもキャッチーでもない。
♪「Sleepin’all day.Watchin’the sun.Thinking of you.Layin’in the ground」♪
・・・・日がな一日寝て暮らす。太陽を眺めながら、君のことを思いつつ大地に寝転がっている・・・・・
というフレーズを延々と繰り返すだけの、エコー処理が軽くされたコーラス。このスコアがエンドレスで延々と4分以上続くのだ。実に不可思議な魅力のあるナンバーである。ワールドミュージック的なボーダレスな空気をマンドリンの固い弦が煽りまくっている。
で、ここからが最も聴き場所なのだが、マンドリンとパーカッションが夏の暑い午睡を表現したように気怠るくフェイドアウトするや否や、スライドギターが唸り一発をチョーキングし、
♪「Sweet sweet lies I can almost believe.Sweet sweet lies when you tell those sweet lies to me.」♪というコーラスが野暮ったく、しかし元気に歌われ、間髪を入れず潰れたスライドギターとマンドリンが泥々に土に汚れた音色を捏ねくり廻す。#1のアン・コマーシャルさと対極にあるようなドポップなロックナンバーであり、Jim Ryanのエレクトリックマンドリンは常にメインを張る。またインタープレイでのMark Spencerのバリバリのスライドギター・ソロに続き鬼のようなマンドリンソロ。
Pop/RockなマンドリンソロはHootersに敵う者は無し、と思ってきたが、この速弾きマンドリンはまさに鬼神のロック・インプロヴィゼイションだ。
そしてこの2曲の怒涛の幕開けが終ると、ガクンとトーンダウンするエスニックなダートさ満載の#3『To The Bone』との落差がまた乙だ。ひたすら中南部ロックの粘着感を唸らせるスライドギターに、サイケディリックなマンドリン弦が溶けていく。そして更にダウン・トゥ・アースな曇り空のようなメロディを土を全身に塗りたくりながら進める。
#4『Tuesday’s Paper』はこれまたキャッチーにロックする、#3のベントしまくる民族グラスソングとはトーンが違い過ぎるロックナンバー、のように見えるが実はこれまた相当グラスルーツのアーシーさを取り憑かせている。アクースティックギターにマンドリン、そしてスライドのアンサンブルはエスニックであるがロックしていて良い。
#5『Out Of My Yard』はこれまた無国籍式なリズムとブルーグラスの必要以上のリラックスさが混在した不思議なナンバーである。古いマイクを通じて発生しているような変声処理は電話を通じて歌わせたゲストヴォーカルのMark Sandmanという人のもの。大半をこのゲストに歌わせ、Jimはほんの一部しかリードを入れていない。ドラム缶やゴミ捨て場の空き缶を叩いているようなチープさで刻まれるパーカッションもミステリアスさを盛り上げている。
#6『Hard Luck』は#4よりも更にグラスルーツの色が入ったロックナンバー。マンドリンの緊張感の欠如した速弾がスカスカな16ビートのリズムとお間抜けなアンサンブルを繰り返す。このナンバーはアクースティックなロックナンバーと分類出来ようが爽やかさよりも、寧ろ重苦しい鋤で大地を耕すような根っ子の音楽を感じる。
プログレッシヴ・グラスロックとでも呼ぶべきか、かなりハードに吹っ飛んでいく民族意匠たっぷりに彩られた#7『Pretty Polly』でのザクザクとしたマンドリンとスライドをはじめとするギターの汚れ具合は物凄く高い。まさにエスニックというナンバーである。アメリカンなルーツ以上に暗黒大陸でのリズムを思わせるところがある。
#8『Nothing But Time』は軽快なアクースティックな弦を多用したロックナンバー。エレキギターとマンドリン、そして幾つかのネイティヴアメリカンの弦楽器が使われているようだが、Counting Crowsの名曲『Rain King』を連想させるようなキャッチーさと即効性が十分だ。
#9『I Got A Wife』はゆったりとしたサニーな南部バラード風にスローに進むと思いきや、カントリー風のアクースティック弦の掻き鳴らしがジャカジャカと挿入され、急遽変調する、しかも16ビートを超えてアクースティックマンドリンが弾き潰されるまで止まらないような変化を取り入れたユニークなナンバーだ。女性のバックコーラスの入れ方にはゴスペルの要素も取り入れているように思える。
その速さを最初からアクセル全開で、しかも先鋭グラスロックとして振り回しているのが、最後のナンバー#10『Feel Like A Rock』である。殆どアクースティックマンドリンのみでビデオを速送りしたような前のめりスピードで突進していくアクースティックというよりもブルーグラスバンドで酔っ払った勢いを嵩にロックを演ったようなものだろうか。
Jim Ryanの歌い方を是非ライヴで見たくなるような早口と速弾きのナンバーである。
クセとエスニックと怪しさとポップさとロックンロールと南部と中部の伝統音楽が混ぜこぜになったアルバムだ。実にアメリカンルーツの面からは正統だが、奇抜さも同時に覚える作品である。トラッドをそのまんまに直球で放り込みながら、スコア的にはロック作品として仕上がってきているという点も上手いというか危ういというか。
米国中南部のちっぽけな街に張り付き、毎晩酒場で弾いて語って飲んでいるようなブルーグラスバンドがロックとポップを独自にモルトして熟成させたような音楽がここにあるようにも思える。
しかし、このWooden Legだが、この1枚だけでどうやら終ってしまったようだ。
中心人物の片割れであるMark Spencerはメジャーな女性シンガーLisa Loeb And Nine Stonesのギタリストとして正式に活動しつつこのバンドに参加していたが、結局それ以降もLisa Loebのアルバムには殆ど参加。
Son Voltを開店休業にしてソロ活動を始めたJay Farrarのアクースティックツアーを始め、やや脱ルーツしたソロ作をリリースした後のツアーにもほぼ全面的に協力。
他にもFreddy Johnston、Amy Allison、Kelly Willisといったシンガーのアルバムにもクレジットされ、Will RegbyやNeal Clearyといった良質なルーツバンドやシンガーにも協力している。完全にWooden Legの一員でなく、敏腕ギタリスト兼エンジニア兼プロデューサーとして定着してしまったようだ。
ヴォーカルとマンドリンでWooden Legを引っ張っていたJim Ryanもボチボチとインディ系のミュージシャンのアルバムでマンドリンを弾いているのみで、バンド活動に意欲的には見受けラれないのが非常に残念。
是非、Blood Orangesから続いた原点的Alt-Countryを独自の手法で展開していたミュージシャンたちにもう一度玄人な仕事をして貰いたいのだが。
なお、このアルバムはかなり入手が困難になってきているので、興味ある人は早目に手を打っておいた方が無難であると思われる。廃盤になって久しいので。
まずは頭の2曲でルーツロック好きとしてぶっ飛んで欲しいものであるが。 (2003.11.25.)
 Flying High On A Dream / Scott M. Katz (1999)
Flying High On A Dream / Scott M. Katz (1999)
Roots ★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Adult-Contemporary ★★★★
You Can Listen From Here
これぞ、ロック・ヴォーカルアルバムの真髄、と声を大にして呼びたい。
カントリーやブルース、フォークといった、差別化が容易く土臭い要素をもって語られる場合のアメリカン・ルーツの音楽性は非常に希薄である。厳密にはRoots Rockの範疇には当て嵌まらないかもしれない。しかし、バリバリのAdult Rock/Contemporaryだけに染まったサウンドだというと、そうでもない。
1970年代から80年代にかけて、総合チャートでヒット曲を連発していたシンガーに共通して存在したアメリカンロックの良い面がまんべんなく織り込まれているサウンドを、このScott M.Katzというアーティストは20世紀の終わりである1999年12月に録音し、翌2000年に発売している。
要するに、どこまでもアメリカンロックなポップ・ヴォーカルなのだ。日本ではAORと呼ばれてしまう可能性すら存在するだろう、誤解を承知で書いておくことにする。
本邦に於けるAORの謝った訳と解釈については散々述べてきたので、もうこれ以上は言及しないが、Andrew Goldの「All This And Heaven」を“AOR名盤”という命名のシリーズの中で堂々とリリースするくらいだからその程度が伺えよう。
しかし、Andrew Goldの名前を引用したついで、といっては何なのだが、Scott KatzのサウンドはAndrew Goldに通じるラインが存在する。こういったロック・ヴォーカリストの作品を思い浮かべてもらえば、ある程度彼の音楽は想像が可能だと思う。試聴リンクから飛んでもらうのがベストなのだが。
Andrew Goldのようなアメリカンルーツを叩き台にしたPop/Rockを歌うシンガーとすると、Don Henley、Glenn Freyといったウエストコーストのシンガーの名前が即座に思い浮かぶが、Eaglesのヴォーカリストのソロ作のように、適度にアメリカンルーツとスマートなポップの折り合いが付いている作風という点では遠からず近からずか。
また、音楽性のもう1つのポイントとして、Scott Katzがピアニストであるという点が挙げられる。
そう、Scott Katzはピアノを弾きつつ歌うピアノ・マンなのである。故にピアノロック好きな筆者が取り上げているというのは丸分かりだろう。(苦笑)
Scott Katzのピアノはルーツィさを助長するDavid ZoloやIan McLaganといったルーツ系のキーボーディストが叩く酔っ払いでスゥインギングな音色ではなく、Billy JoelやElton Johnを連想させる美しく、コンテンポラリーなピアノプレイを主に紡ぎ出している。
#9『I’m Not Ready』のハードなギターサウンドのエッジに沿って、重たく鍵盤を転がすような場面もたまさかには見られるが、そこにはブルースやジャズというルーツ系のカテゴリーを補助するようにリズムと音を併せるというような意図は見られない。メロディがルーツロックに近いため、それに併せてルーツスタイルのキーボードを弾いているに過ぎないだろう。
ピアノにしてもピアノサンプル/シンセサイザーにしても、極端にルーツロックへ傾いたアレンジの鍵盤を弾くことはないプレイヤーでもある。その一端が尻尾を出しているのは、ルーツミュージック鍵盤としてはアクースティックピアノと同等かそれ以上に相性の良いハモンドオルガンを積極的に使用していないところだ。
何曲かでレコーディングをしているプレイヤーか又はScott自身がオルガンを演奏しているが、ルーツィな割合が増すことを目的としたアレンジでないことは明らかである。
あくまでも、Pop/Rockのヴォーカリストとして鍵盤に指を乗せているのであり、Scott Katzにはルーツロックを追求する狙いは希薄−もしかするとないのかもしれない。
基本として良いロックヴォーカルの音楽を追求したアルバムを拵えた結果が、アメリカン・ルーツを感じさせる作品となって現れただけという気がする。
別にペダルスティールやスライド、マンドリンにバンジョーや生ギターが入っていなくても良質なアメリカンロックのアルバムはゴマンと存在するし、アメリカン・ルーツを感じさせるアルバム全てがアーシーである必要はないだろう。
アメリカン・ロック=アメリカン・ルーツ、と公式化する必要はないし、アメリカンロックの魅力はルーツサウンドにあるだけではないのだから。
Scott Katzの音楽性は、非常にアダルトなロックである。しかし、アクースティックに際立っている訳ではないし、かといってアーバンな打ち込みサウンドに溢れているのでもない。
キーボード、リードギター、リズムギター、ベース、ドラム、オルガン少々、時々ストリングスという4から6ピースのスタッフで小ぢんまりと録音をしているだけだ。
ここには極端にバンドをシンプルにしてソリッドに纏めようとか、ありったけのゲストミュージシャンを起用して豪華な演奏を演出しようという気構えは見ることは出来ない。固定のミュージシャンと協力して丁寧にレコーディングしたシンガー・ソングライターのアルバムという印象は間違っていないと思う。
実に基本であり奇を衒わない演奏の編成である。同様に音楽的にも斬新さはあまりない。シンセサイザーを使用しているからといって打ち込みやシンセノイズ、ドラムループ、何某かのSEというような昨今の潮流に乗った小癪な技を取り入れずに、ロックインストゥルメントを忠実に重ねているだけ。
全く誠実で真っ正直なサウンドの組み立てをしている。ピアノを始めとする鍵盤は印象的だが、それだけを押し立てたピアノ弾き語り的なポピュラーアルバムにはせずに、他の楽器とのロックアンサンブルを上手くブレンドしたものとなっている。
Scott Katzがキーボーディストであることを考慮すると、Michael McDonaldやPaul Carrackという鍵盤シンガーを連想してしまうが、彼等ほどにはBlue-Eyed Soulに染まった音楽ではない。
ポップなヴォーカルということなら、Christopher CrossやHerb Alpert、またちょっと異なってしまうがBarry ManilowやAir Supplyという1980年代のヒットシンガーのPop/Rockなセンスを引き合いに出す方が適しているかもしれない。
無論、ここまでソフトロック化してしまってはいない。非常に近いところまで踏み込んではいるが。
ルーツサウンドを期待して聴くと、かなり違和感を覚えるというのは筆者が保証する。Elton JohnやSteve Winwoodが洋楽のインプリンティングになった趣味だから、この「Flying High On A Dream」に非常に当たりが出たのは間違いないのだから。
美しい鍵盤の音色と透明感の溢れるサウンドアレンジ、ハイトーンまでは到達していないが良く通るScott Katzのヴォーカル。これらのAdult Rockの背後に植え付けられたアメリカン・ルーツの安定感。時にはプログレッシヴなシンセサイザーの使い方も現れる。
これら全てを包括するヴォーカル・アルバムと捉えて、その透き通った綺麗なメロディを楽しむことがこのアルバムを聴けば良いと思う。
紛らわしいのは、他にもScott Katzというシンガーが存在することである。しかも殆ど同時期の1999年にアルバムを作成し、フォークポップ系のレーベルであるYellow Tail Recordsから「Wrong」というアルバムを発売している。しかも、筆者がまだ聴いていないこちらのアルバムの方がどうやら名が知られている様子なのだ。大手のオンラインショップなら大抵の場所で入手できる。
こちらのScott Katzはマンドリン、アコーディオン等を使用したルーツ系のアルバムらしい。John Prineと比較される位だからそれなりにルーツでアーシーなのだろう。一度は聴いてみたいのだが、肝心の試聴サイトのリンクが死んでいるため、いまいち購入に踏み切れないで今日を迎えてしまっている。
と、同姓同名のシンガーの話はこのくらいにしておく。今回ピックしたScott Katzは完全な自主制作でアルバムを作成したシンガーで、こちらのScott Katz氏とは全くの別人である。
写真を見比べると、こちらのScott氏の表面積は違うKatz氏の倍位はありそうだが。(苦笑)
で、こちらの更にマイナーなKatzは自らのアイデンティファイのためだろうか、ミドルネームのM.を所々に加えている。ところが、アルバムの表ジャケットではM.を記入しているのに背表紙ではScott Katzのまま、インナーでも一部でM.を加えているが大半はScott Katzのまま、という具合にどうにも統一性がないのだ。
ネット上ではScott Katzのままでオフィシャルホームページをアップしているし、試聴できるmp3.comでもミドルネームは加えていないところを見ると、間違われる心配をしていないようにも見受けられる。・・・・まあミモフタもないけれど、どっちでもいいのだ。どの道メジャーへの距離は似たようなものだろうから、両者ともに。(失礼)
Scott M.Katzのデータは殆ど存在しない。以前本人にバイオグラフィーをメールで質問したことはあるけれど、回答を戴けなかったので、乏しい資料しか手元にない。
出身と活動拠点はフロリダ州。10代の頃からミュージシャンを目指して積極的に活動していたのではなく、家庭を築き、勤め人を続けながらかなりの間アフター5で音楽活動に関わってきたキーボディストだ。幾つかのアマチュアのバンドやローカルバンドの鍵盤をテンポラリで担当したり、バーでの弾き語りを副業的に若い頃から続けていた。何と4児の父親だそうな。
年齢もはっきりしないが、このアルバムを作成した時点で30代は完全に超えている容姿である。先程引き合いに出したChristopher Crossよりも恰幅の良い体形をしたおっさんである。子供が4人ということから40歳は超えてしまっている可能性が高い。
ある程度生活に目処が立ったので、予てからの望みであったミュージシャンとして本格的にソロシンガーとして活動を始め、地元での活動が予想外に好評だったため、ローカルのセッション・ミュージシャンを雇い、マイアミの音楽スタジオでこのアルバムを録音。マイアミのアダルトロック系のラジオでは2000年にそこそこの反応を得た模様である。
が、その後全く積極的に活動しているかは定かでない。ライヴ情報とか全く入ってこないため、未だに勤め人としてのステータスを維持したままミュージシャンを2足の草鞋で行っている可能性もある。
このアルバムを発売した当時は、
「ここまで来るのに随分回り道をした。音楽家として独り立ちする以前に、僕は父親であり夫であり、そしてビジネスマンだったのだから。」
と短いが、これからはミュージシャンに専念していくぞ、的な決意表明を匂わせるインタヴューが存在したのだけれども。ともあれ、才能あるシンガーであり良いメロディを書ける人なのだから、この1枚で終わって欲しくない。何時になるかは全く判然としないが、2枚目のアルバムが届く日をここ数年待っている。
・・・・が、活動しているのかも分からない状態が続いているのであまり楽観はしていないのだが・・・・。
アルバムは全部で11曲。構成としてはかなり極端な形が取られている。
アルバムの前半、というよりも#9までは殆どがテンポの速遅は程度としてあるが、ピアノを中心としたバラードとなっている。#5『I Believe Dreams Come True』の軽快なミドル・テンポのナンバーはあるにしても、殆どがスローで綺麗なヴォーカルナンバーである。
が、#9『I’m Not Ready』から最後に至る3曲はかなりハードなロックナンバーとなっている。この落差というか格差はかなり激しい。ハードロック呼んだ方が適切なナンバーが尻上りに現れるというのは、後半に入るまで全く予想が出来ないに違いない。
また、上がり3曲の完成度だが、大半を占めるゆったりとした雄大なポップナンバーと比較すると手放しで賞賛可能な出来ではないと思う。しかし、このロックンロールな展開があるからこそ、このアルバムがロックアルバムとして成り立っているのは確か。
曲順としてはもう少しロックンロールが尖ったナンバーは均等に散らした方がバランス配分の面からは良かったのでは、とも感じるが、最後にロックナンバーが集中配備されているため、「Flying High On A Dream」がそのスロー曲の多さの割にはロックアルバムと錯覚させる働きをしているとも云える。
よって、全くマイナスな効果だけを発揮しているのではないだろう。
#1『My Own Way』の頭でストリングシンセサイザーとキーボードの透明感のあるリフが、あ、これでは駄目だと感じたら人なら、このアルバムを聴くことはお薦めしない。
エコーを少々掛けたヴォーカルとコーラスの処理といい、野暮ったさのない流暢なギターといい、ここに土臭さとルーツさは皆無・・・・・・のように思える。
がしかし、この澄み切ったコッテリ目のバラードには、良心的なPop/Rockの流れがしっかりと織り込まれている。AORサウンドとして割り切るにはロックが強いし、ドラムにしてもギターにしてもオーヴァー・プロデュースにまでは至っていない。
アーシーさを感じれなくても安定度を感じられる歌。これがScott Katzなりのアメリカン・ルーツへの敬意の表し方だと考えている。
#2『True Love』はアクースティックピアノとオルガンが加わった#1、このように見なして構わないバラードである。
所々でヒョロヒョロとクネらせるオルガンの音色はElton John的なバラードに近いモノを覚える。ハイエナジーなギターはまるでTotoのSteve Lukatherの全盛期の音色のようだ。
タイトルナンバーである#3『Flying High On A Dream』まで、オープニングからストリングスがサンプリング(多分)でアレンジメントされ、冒頭からここまでバラードが連続する。しかも、どの曲もかなり美しく、大袈裟な盛り上げはしないのにかなりのエモーショナルな熱さを感じる。
このナンバーではコーラスの入れ方とか、シンセサイザーとピアノの重ね方等はかなりの割合で産業ロックを感じてしまう。JourneyのキーボーディストであるJohnathan Cainのソロアルバム「Back To The Innocence」のようなピアノバラードである。
#4『Younger Days』も毛色は全く同じ。日本人好みの哀愁がありしかも甘いメロディ、そしてエコーを多用したコーラス処理。ドラムの音響にも行き過ぎなくらいのエコーを掛けて処理している。
確かに、筆者はピアノは好きだし、Scott Katzのような透き通るまではいかない普段着な声で歌を自在に唄えるヴォーカルは相当に好物だが、ここまでバラードばかり続くと少し飽きてくる。何よりもバラードオンリーであり、ロックナンバーが出だしから皆無というのは不満になるのだ。
そこで登場するのがScottがピアノ、B3、サンプリングと独りで鍵盤を多種弾いている軽快なビートが気持ち良い#5『I Believe Dreams Come True』の登場になる。はじめての弾んだビートを持つナンバーであり、B3が効果的に使われ、仄かなルーツナンバーの落ち着きをスロー・テンポとは違う手法で表現してくれるトラックでもある。
こういったタイプの曲をもう少し増やした方がアルバムとして面白くなったと愚考しているのだが、あながち的外れな願望ではないと思ったりする。
#6『Only Love Is Real』も#5に近いミディアムなビートが優しく歌われるポップナンバーである。かなり音を絞ってバックに紛れてしまっているピアノの音色が、隠し味として効いていて、全面に押し出されたオルガンが目立つが忘れてはならない働きをしているように感じる。
#7『Anything For You』から、またしてもアダルト路線のバラードに戻るのだが、このナンバーではギターがアクースティックな弦を弾いているし、やや淡々と進むメロディのため、他の美しいバラードよりもしっとりとした曲になっていると感じる。
Linda Ronstadtの『Cry Like A Rainstorm』を思い出すようなコーラスと、後半のドライヴな盛り上がりが綺麗なコントラストを成しているバラード#8『Where Do I Go From Loving You』は最早お定まりになりつつあるバラードなのだが、崩れたピアノプレイや、かなり自己主張のあるギターソロが後半で飛び出し、スケールとしては最も壮大なナンバーとなっている。Scott KatzのAdult Contemporaryなアスペクトを際立たせた曲だ。
そして#9『I’m Not Ready』のギターが引っ張るロックナンバーが突然出現する。やや暗めなスコアも顔を見せるが、基本はキャッチーなロックナンバーであり、乾いたギターのソロは爽快感すら演出してくれる。時折思い出したように襲来するオルガンの音、叩きまくられるピアノの鍵盤、とこれまでのマッタリ展開を吹き飛ばすような一撃。
次の#10『All I Need You』は更にギターが暴れるハードロックを匂わせるナンバーである。陰鬱な曇り空を想像させる如きロックリフが支配するナンバーである。が、この思いっきりの良さはこれまでの優等生振りからすると悪くないとは思うが。
最後のナンバー#11『Right Or Wrong』になると、プログレ・ハード的に大仰なシンセサイザーがブンブンと圧力を上げ、これまた完全なハードロックギターが引っ張る展開になり、曲としてもかなりの緩急のついた大袈裟な流れをバリバリと叩き出す。
一体、前半のバラード一筋はどうなってしまったのか、と唖然としてしまうくらいの変貌ぶりで、このアルバムは唐突に幕を引く。
自主制作とは思えないくらい丁寧なミックスとアレンジを施されたアルバムで、1980年代ならトップ40ヒットに顔を出したであろうナンバーが何曲も並んでいる。
ルーツロックとして厳しく見れば邪道であるが、オルタナティヴに汚染されていない良質なアメリカン・ロックと考えておけば、その精緻な音世界に浸れると思っている。
ルーツファン向けというよりも、もっと都会的な音を出すシンガーソングライターが好きで、ロックの厚いアンサンブルが無くては物足りないリスナーにはかなりヒットするのではないだろうか。 (2002.12.16.)
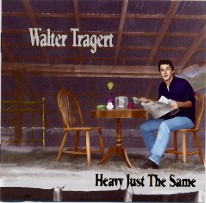 Heavy Just The Same / Walter Tragert (1995)
Heavy Just The Same / Walter Tragert (1995)
Roots ★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Southern&Americana ★★★★
You Can Listen From Here
Walter Tragertとの出会いは常に偶然がつき纏っている。
とはいえ、悪い意味での「憑き」ではないけれども、当然ながら。
Walterの音楽に初めて触れたのは1992年。アメリカ合衆国はバッファーローへ、カナダから国境を越えて買い物に出かけた際のこと。インディ音楽を扱う店で、新品と中古の入り混じった特価カセットテープが乱雑に積みあげらているコーナーで、ジャケットも何も付いていない裸のテープが1ドルで売られていた。
マジックインキで書いた手書きのレーベルに普通の安物テープ。恐らくは不法コピー版だろうか。それとも、オリジナルのジャケットレーベルが紛失していたかどちらと思われる。
このテープをWalter Tragertという、何となくだがオルタナティヴでもハードロックでもなさそうな響きの名前に惹かれるようにして購入。
これが、Walterが自主レーベルで作成したデビュー作「Scrapple From The Roadapple」だった。なかなか良質なPop/Rockだったと記憶している。当時はルーツロックという呼び名はまだされていなかったので、単にアメリカン・ロック・ヴォーカルとしてまずまずと感じたものだ。
その時に一緒に購入したのはBruce Hornsbyの「The Way It Is」の中古テープとJoe Cockerの「Unchain My Heart」のこれまた中古テープ。
これらのロック名盤に挟まれても、Walter Tragertの音楽は遜色の無い出来であったと感じている。
で、Walter TragertのCDが欲しくなって、カナダに戻った際、大手のレコード屋に足を運び問い合わせたが、「そのようなアルバムは扱っていない。」と店員に肩を竦められた結果に終った。
「Scrapple From The Roadapple」というタイトルに間違いはない。レコード屋で問い合わせるためにメモを書いたので何故か良く記憶しているのだ。いらんことは必要以上に人間覚えているものだ。
当時は知る由もなかったが、1993年には2枚目の作品をデビュー作同様にセルフレーベルから発表しているようだ。タイトルは「Victory At Sea」というそうな。こちらもお持ちの方や情報を知っている方がいたら(絶対にいないだろうが)是非御連絡をお願いしたい。御礼は惜しみませんので。
で、幾つかのアングラ系やローカル系のCDやレコードを扱う店をトロントで探したが、これまたWalterのCDは全然見つからなかった。ネタを明かせば、最初からCDは存在しなかったらしいが・・・・・、直後述。
当時は今日のようにマイナーな作品をネットで流通させたり、何よりルーツロック系のアルバムを扱っているところは殆どなかったのだ。まあ、現在でも状況は改善されたとは言い難いが。
で、学生であったことも理由で、さっさと諦めてしまったのだ。
残念ながら、このテープは翌年の帰国の際に荷物を減らして輸送料金を浮かすため−船便で日本に送ったけど、それすら厳しい財政状態だったりした。まさに赤貧に喘いでいたのを思い出す−CDを優先して詰め込んだため、他のテープ全てと一緒に処分してしまった。
ところが、後になってだが、この初期の2枚の音源は現在完全に幻になってしまっていることを聞いた。何しろ、CDにプレスすらされていない。これはこのレヴューを書くに当たり確認した。
カセットテープオンリーの発売だったのだ。どうりで見つからない筈だ、と後になって苦笑したことを思い出す。
最近はインディ作をオーダーすると3分の1の確率でCD-Rが混じり、相当ウンザリしているのだが、1990年代初頭はCDをプレスすること自体がローカルの無名シンガーには難しかったのだろうと思う。
以上のような出会いがまず在った。
で、次の出会いが、これまた偶然に起こっている。それが今回紹介する「Heavy Just The Same」である。このアルバムは、2002年現在までにWalterが残している唯一のソロ作品でもある。
1996年の米国はL.A.。とある量販レコード店の「欧州と英国からの輸入レーコード」のコーナーを何気なく漁っていたら、ばったりと目に付いたのが、Walter Tragertのこのアルバムだったのだ。これにはかなり驚かされた。今まで遠い外国の出来事を書物で読むような存在だった−まあ、この時点で外国にいたりするのだけれど−人物が唐突に眼の前に出現した感じというところだ。
その時まで顔すら知らなかったので、同姓同名のアーティストかもしれないとさえ考えたものだ。というのは、このCDは伊太利亜産−伊太利亜拠りの輸入というシールが貼ってあったからだ。
そう、Walterの初のCDにして、これまで唯一のCDは生まれ故郷のアメリカ合衆国ではなく、伊太利亜のレーベルとの契約でプレスされたものなのである。
試聴リンクから、そのレーベルにもジャンプできるので興味のある人はアクセスしてみると良いだろう。
当時、新譜のメジャー関連CDが7ドルから12ドルであった相場で18ドルというのは関税を考慮しても安くない値段だったと思ったし、あのテープだけの出会いであったWalter Tragertかどうかも怪しかったため、少し躊躇したが、そのくらい飯を2食位質素にすればどうにかなる、と思い立ち税金込みで20ドルを投資し、「Heavy Just The Same」を手に入れた次第。
その決断が全く正解であったのは筆者にしては結構珍しいかもしれないが。(笑)
それは兎も角として、常にこの人との出会いは偶発的に訪れるものだと当時思ったものだ。
まずは、この殆ど名前の知られていない良質なルーツ・シンガーについてその足取りを述べることから始めるとしようか。
Walter Tragertはオハイオ州、クリーヴランドの生まれ。育ちはワシントンDCの郊外。まだ5歳にもならないうちから音楽に対して興味を持ち始め、David BowieやLou Reedに多大な影響を受けて育っている。6歳の時にはBowieやReedの歌を元に自分で作詞をしていたとのこと。
10代にはギターを始め、キーボード、サックス、トランペットと様々な楽器を習い、幾つかのローカルバンドに参加する傍ら、自分でも作曲をするためにペンを執るようになる。
曲を書くに当たって影響を受けたミュージシャンは、Ray Charles、Neil Young、Bob Marleyや初期のSteve
Winwood、更に子供用の童話ミュージックやインドやアフリカのワールドミュージックと、様々な音楽から薫陶を受けたということだ。
が、最終的に最も感銘を与えられたのはパブロックやニューウェーヴの代表格とされている幾人かのアーティストの中でも著名なElvis CostelloとGraham Parker。彼らの英国的なルーツロックの解釈と、何処か都会的なセンスを有しつつもアーシーなスタイルをアメリカンロックの音楽性を加えて独自に消化した結果がWalter Tragertのサウンドと評価されているし、その点に関しては筆者も全然同意する。
ローカルミュージシャンとして活動を開始して暫くの後、3年程米国各地を歌を書きつつ、ローカルバンドに雇われミュージシャンとして加わりつつ放浪したWalterは、テキサス州のライヴ・ミュージシャンのメッカであるオースティンに流れ着く。
Walterの言によると、
「オースティンだけは行ったことがなかったので、行ってみようと思い立ったんだ。そうしたら、そこは自由にやりたい音楽の羽根を伸ばせる場所だったんだよ。」
ということ。
オースティンでWalterは前述のように「Scrapple From The Roadapple」(1992年)、「Victory At Sea」(1993年)を連続でカセットテープのみで少数リリースする。
このテープはオースティン界隈ではそこそこの評判を得たようである。1990年代後半ならCDとしてプレスが可能だったかもしれないし、この「Heavy Just The Same」よりは完成度は1作目に限ってでは低いが、是非ともCDでリイシューして貰いたいものだ。
だが、Walter Tragertはソロミュージシャンよりもバックヴォーカリストやギタリストとして、オースティン周辺の草の根活動をするヴェテランミュージシャンに評価されていく。
特に、Loose DiamondsやHighwaymenという、テキサス式カントリー/ブルース/ロックバンドの珠玉という底辺活動を1980年代から続けている“Scrappy” Jud Newcombにその才能を見出されたことは大きい。
Jud Newcomb自体は「自分で看板の表に立ちたくない」という心情が強い人で最近はLoose Diamondsも開店休業状態だが、オースティンあたりのサウンドを追いかけている人ならかなりお馴染みの名前だろう。
Beaver Nelsonの全てのアルバムでプロデューサーを引き受け、ギターや鍵盤をプレイしているのが最も最近での目に付く活動だろう。
他にも、女性ブルース/カントリー・シンガーのToni Priceのバンドでもギタリストを務め、Jon Dee Grahamのアルバムにも登場。2002年になかなかの渋いルーツアルバム「Lucky Too」を発表したテキサスのシンガーであるMichael Hallの殆どのアルバムを手掛けていたりもする。更にGurf Morlixのプロジェクト、
Imperial Golden Crown Harmonizersにもギターとヴォーカルで参加という具合に、地味だがその手のテキサスルーツのファンには垂涎の的である作品の多くに関わっているのが、Jud Newcombである。
Jud繋がりで、Beaver Nelsonの3枚目のアルバム「Undisturbed」(2001年)ではバックヴォーカルでクレジットされて、久々にレコードのクレジットにも顔を出している。
話が前後してしまうが、Jud NewcombやFacesのピアニストIan McLaganにも評価を受ける。このピアノ爺さんもWalterの3作目には1曲参加している。
こうして、それなりのシンガー・ソングライターとして活動を開始したWalterだが、アルバムを作る契約先が何処にも見つからなかった。セルフリリースのテープというメディア使用にはいい加減欲求不満になっていたと述懐するWalterに声が掛かったのが、大西洋を挟んだ長靴型の地形を有する半島国家、伊太利亜であった。
1990年代初めからアメリカンルーツのアーティストと契約を交わし、伊太利亜で人気のあるアメリカンサウンドを地道に売り始めていたClub De MusiqueがWalterにCD製作を持ちかけたのである。
本国で契約先が見つからないという事実は如何ともし難いが、取り敢えずWalterは伊太利亜のレーベルから、オースティン録音でデビューのCDを発表する。(通算では3枚目となるが。)
しかし、このアルバムも合衆国では全く話題にならず、少数が逆輸入され、オースティン界隈や一部のインディショップのカントリーロックのコーナーやインポートCDの隅に並べられただけで終ってしまっている。
Jud Newcombがギターで全面参加し、Ian爺もオルガンで参加、更に、George Reiffがベース、Don Harveyがドラム、Kirk Carpenterがキーボードとコアのメンバーだけでもかなりの腕利きを揃えている、演奏だけでも非常にクオリティの高いアルバムなのだが。
この後、アルバムを作成するというオファーは無いようである。Walterはテキサス州で思い出したようにライヴを継続はしている。Walter Tragert And His Bandという名義になったり、Walter Tragertの名前を時々によって使い分けている様子だが、詳細は不明。
こちらの日本では非常にレアで貴重なSXSW(South By Southwest)のレポートにも少しWalterが登場するが、南部地帯ではそれなりに活動している模様。2002年のSXSWにも出演していたらしい。
アルバムで見られるのは、少し前に触れたBeaver Nelsonの3作目のヴォーカルくらいである。
是非、セルフリリースでも良いので2枚目のCDに取り掛かって欲しいものだが。
さて、最後にアルバムの内容について語っておくことにする。
かなりルーツの香りが濃厚なのだが、カントリーやカントリーロックとは全く無縁のサウンドをWalter Tragertは届けてくれる。Southern Rockではあるのだが、それだけでない一般性が彼のサウンドには存在する。
率直に言うと、オースティンで典型の泥臭いロックバンドの音とは全く違ったタイプのルーツロックであり、ヴォーカルアルバムであるということ。
カントリーやブルースにはそれ程踏み込んでいないPop/Rockということは、Americanaと表現するしかないかもしれないし、やはり英国パブロックやニューウェーヴの世代を通過してきた人故の、コテコテのアメリカンサウンドに徹し切れない要素があるため、余計にテキサス臭さを感じないのかもしれない。
ブリティッシュ・イノヴェーションを通過儀礼として体験してきてそれを咀嚼し尽くしたミュージシャンが表現可能なレヴェルに到達していると考えている。Elvis CostelloやGraham Parkerという英国ポップスのメインストリームを米国的に表現できるアーティストの丁度裏ヴァージョン−米国の南部ロックに英国的なルーツやポップセンスを持ち込んで消化が十分になされているシンガーと捉えればベストではなかろうか。
然れども、繰り返すが、ルーツのフィーリングは気温差が大きい地方に頻繁に出現する霧のように厚い。だが、口当たりは英国ロックのバックボーンがあるためか、ルーラルというよりもサバーブに近い感じがする面白いロックヴォーカルの作品となっている。
#1『Sweet Nothing』以外は全てWalterの単独作。#1は“Scrrapy”Jud NewcombとGeorge Reiffの2人がWalterに手を貸している。
その#1は南部ルーツサウンドの優しげな顔と、幾許かのスマートなシティ・ポップスのエッセンスが結婚して出来上がったようなタイトルとは正反対のスゥイートなナンバーとなっている。
オルガンに複数のキーボードを配し、ナチュラルなギターをブレンドしたジワジワと暖まるカレーうどんのような(笑)雰囲気を持ったナンバーである。女性のバックコーラスの引っ張り方もかなり上手で、このあたりのアダルトな感覚はやはり英国ポップスの大御所であるSteve WinwoodやElton Johnが若い頃に持っていた気配が漂っているようだ。 基本は素直なポップに見えて、かなり半音を多用した複雑なメロディをサラリと届けているところも技を感じたりするのだ。歌詞はかなり社会的な批判を内省的に歌った面白い内容なので、じっくり聴いて貰いたい。
#2『Hyattsville』は完全にSouthern Roots Rockの典型と名付けるしかないようなドキャッチーで素直なロックナンバーである。#1のマッタリ感が余韻を引く後に飛び出すロックチューンなため、かなりインパクトが大きい。
これといって特徴のない素のままの声が親しみ易いWalterのヴォーカルだが、こういったダンダンと弾むビートのナンバーを懸命に歌う態度には好感が持てる。何と言っても鍵盤好きな筆者には、ドラムの堅実なプレイもさることながら、縦横無尽に駆け回るハモンドオルガンの元気の良さが印象的で、盤のポムポムと空砲を鳴らすようなペダル・プレイは圧巻である。
このアルバムの最大の山場の前半は#1から#3『Skelton Jones』までだろう。暖かく、そしてリズミカルなアクースティック・ピアノを骨組みの中心に据えて、オルガンや出しゃばり過ぎないギターとリズムセクションが極上のミドルテンポなロックアンサンブルを生み出す#3はアメリカナイズされたパブロックナンバーの体を様している。というよりも、少しノスタルジックで甘いPop/Rockと表わした方が妥当だろうか。
実に陽性で歯切れのよいポップチューンであり、筆者が最も好むタイプのピアノ・ジャンピーな曲でもある。
#4『Don’t Rule Me Out』はフィドルとマンドリンにB3、そしてゴスペルロック風の女性コーラス隊がThe Bandの如く、ダウン・トゥ・アースにホンワカとそしてザラザラとメリハリを付けて流れていく南部ソング。しかし、ギターのチョッパーやキーボードの使い方、フィドルのひねり出し方等にCostelloやTodd Rundgren的な先鋭さを覚えてしまうのだ。トラッドにドップリ漬かったナンバーなのに何故か垢抜けている気がしてならない。
対して#5『Beating A Dying Horse』はとても分かり易い直截的なブルースロックンロールとして耳に飛び込んでくる。FacesやRolling Stonesといったブリティッシュなハードパブサウンドを彷彿とさせる南部の酔いどれバーボンの匂いをプンプンと発散しているナンバーだ。ブルースハープのR&B的な演奏に、ホンキィなピアノの連打、そしてファンキーなギターと、こちらはハンマーを振り回すように力任せのWalterが見れる。
後半に突入すると、アメリカンルーツの勢いが強かった前半と比較してだが#6『Over The Line』や、#9『Ton Of Feathers』、#10『Purple Heart』を筆頭に、Nick LoweやVan Morrison、そしてElvis Costello等に通じる英国的ソウルやニューウェーヴの音楽性がかなり身近に感じられるようになってくる。
#6はかなりキーボードを多用した木目の粗いポップナンバーである。ギターはルーツィというかアーシーなエッジを含んでいるけれど、リズムマシンのようなドラムを際立たせて進むリズムはCostelloやPaul McCartneyのスマートなポップ感覚を連想してしまう。
#7『Straight』はB3を始めとする複数のキーボードをIan McLaganが弾きまくっているが、ゴスペルの大らかさを大量にロックの行間に詰め込んだ懐の広いナンバーである。これまたインタープレイではかなりロックンロールな演奏が展開される。Van Morrisonに通じる素養が実に色濃いナンバーだと思っていたが、WalterはSXSWや他のロックフェスティヴァルでVan Morrisonのカヴァーをかなりレパートリーに入れているとのこと。
続く#8『Sleepless Nights』も#7程には南部ゴスペルタッチではないにせよ、ほのやかなアーシーさとキャッチーなポップチューンのまろやかさが同居した佳曲である。その中にあってJud Newcombのザクザクと地面を掘り返すようなパワフルなギターの音色は抜きん出ている。これまたアメリカン南部ロックなのだが、やはりCostello的な下地を思い浮かべてしまうのだが、それはかなりカラフルに彩られた鍵盤の音色のせいかもしれない。
Blue-Eyed SoulとR&Bの淡白でありつつもルーツィな意匠をしっかりと纏った#9でも女性コーラスとオルガンが大活躍してくれる。この心を暖めてくれるVan Morrisonも感心しそうなゴスペルフィーリーがあるがために、Walter Tragretの音楽は単なるブリティッシュ・イノベーションのオマージュに終始しない。少なくともその要因の一つにはなっていると思う。
ベントなギターとアクースティックでは歩けれど、フワフワとしたプログレッシヴな味わいのあるスローナンバーの#10は、もっとも英国シンガーソングライターの影響を表に出したナンバーである。Traffic時代のSteve WinwoodやJoe Cocker、そしてNick Loweといったしみじみと歌を演らせると聴かせずにはいられない名ヴォーカリストのメロディを肌で感じることができるナンバーだ。
残念ながら、ヴォーカリストとしてはまだその域には達していないとは思うが。良くも悪くも、普通で聴き易い声がWalterの武器だと思うから。
しかし、このアルバムのリリースから7年も全くアルバムを作っていないのが納得できないくらい素晴らしい出来になっている1枚だ。加えて、このアメリカンロックやブリティッシュロックの垣根を越えたルーツロックとしての良作が、伊太利亜という非英語圏のレーベルでしか契約の対象とならなかったというのも頭の痛い事実である。
何としても、逆境を乗り越えて、Walterにはアルバムを創って貰いたいところである。のんびりオースティンの周りでライヴやるのも人生としては悪くなさそう、というか見ていて羨ましいが、音楽ファンとしてはぼちぼち次のステップをアルバムに刻む形で見せて貰いたいのだ。
現在、このアルバム「Heavy Just The Same」は北欧や独逸でも手に入るので、是非聴い欲しい。
きっと欧州のレーベルの質の高さに驚くだろうから。 (2002.12.25.)

 Give My Regards To Broadstreet
Give My Regards To Broadstreet