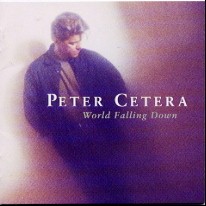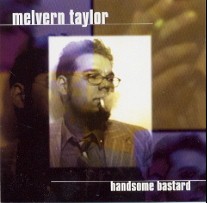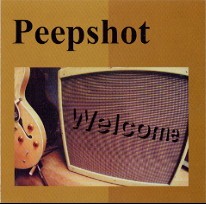 Welcome / Peepshot (1999)
Welcome / Peepshot (1999)
Roots ★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★☆
Americana&Adult-Alternative ★★
You Can Listen From Here
2003年1月、遂にPeepshotの公式ホームページが消滅した。この消滅までには幾つかの緩衝材が用意されていたとはいえ、実際に結論がバンドの決定的な終焉という形で出されてしまうと寂しいものである。
なお、PeepshotのCD販売や試聴については、インディ系アーティスト支援サイトのIUMAが引き継いでいる。上の試聴リンクからジャンプ可能なので興味があれば覗いて見ることをお薦めする。
また、mp3.comでも試聴が可能である。
Peepshotというバンドがどうやら危ないことは2002年早々に伝わってきていた。
「僕はこれ以上、サイトの更新をすることを止めた。これが全てだよ。」
というコメントがバンドのリーダーで、同時にリードヴォーカリストとギタリストでもありソングライターでもあるBrian SummersによってHPのニュース欄に掲載された。
それまでに、「2001年には必ず2枚目のフルレングスアルバムを発表することを約束するよ。」とステイトしていたにも拘わらず、一向にアルバム発表の気配がないため、漠然としたPeepshotの将来に関する不安は存在していた。
しかし、サイトの更新を停止=バンドの活動停止とまでは短絡的に繋がらないにしても、何らかのトラブルによって演奏活動が暗礁に乗り上げてしまっていることは容易に予想できた。
そして、同年年末の2002年には以下のコメントが掲載され、PeepshotのHPは消滅する。
「僕は今が休暇の時なのかそれとも別の時なのか何とも言えないけど、Peepshotのメンバーは全員バラバラになってしまった。バンドは終わってしまったよ。でも僕は未発表音源やライヴ音源をMP3に変換する作業を終えたところ。僕はPeepshot時代から僕の作った歌を気に掛けてくれている人たちへこういったマテリアルを届けてあげたいんだ。これからも曲をアップロードしていくからチェックを頼むね。」
と、ソングライターであったBrian Summers自身が音楽活動に積極的であるのが救いであるが、Peepshotは休止状態を経て遂に解散。
だが、Brian Summersの音源はここで聴ける。Brianは現在ギター教室でギターの講師をして生計を立てつつバンドのメンバーを探しているそうだ・・・・・。
残りのメンバーは皆音楽業界からは距離を置いた生活を送っているとのこと。
ベース兼ヴォーカリストのBenjamin HinchはPeepshotの活動エリアであった南部カリフォルニアから北部へと引越し、念願だった小説を書くことを始めている。
Brianの兄弟であるDave Summersはバンド解散後に海外放浪の旅に出かけてしまっているということ。
ドラマーのHale Savardはドラムを叩くことを止め、ミュージシャンとしての生活から足を洗ったらしい。
本音を言えば、Brian SummersよりもBenjamin Hinchに第一線で活躍して貰いたいのだが。PeepshotはBen(Benjamin)とBrianがそれぞれ単独で書き上げた曲をメインのリードヴォーカルをBenが、Brianは主にハーモニー・ヴォーカルを担当するスタイルで分け合う形を選択していた。
が、2枚のアルバムを聴き返すと、親しみ易いルーツロックやカントリーフレイヴァーの多くを含んだトラックはどちらかというとBenのペンから生まれている方が多いのだ。
Brianの書くナンバーは、アメリカンルーツを感じるエレメントも含まれて入るのだが、それと同等かそれ以上にオルタナティヴやモダン・ヘヴィネスという1990年代型のメインストリーム・ロックサウンドの影響が現れていると思う。言うまでも無いけれど、アルバムに収録されていない曲ではBrianもかなり西海岸カントリーを耳にして育ったという環境を反映するソングライティングを行っているが、Peepshotのルーツ以外を受け持っていたのは主としてBrian Summersであることはバンドの過去作を追えばはっきりとする。
だからこそ、BrianとBenがコンビを組んで新世代のアメリカンルーツロックやロックンロールを模索していたPeepshotというカリフォルニアのロックユニットに意義がありえたのだけれども。
以上の様に、完全に解散してしまい、バンドのソングライターがその後のソロ活動を行うことにも腐心しているという状況でPeepshotのレヴューを書くのは少し心苦しいものがあるが、今書かないとこのまま過去のバンドとして忘れていきそうなので、今回スポットを当ててみた次第である。
しかし、1997年にオレンジカウンティで彼らのライヴを見た時(メインではなく前座であったが)は、かなり荒削りではあったが、新時代のルーツロック−ただオルタナティヴに盲従するだけでないアメリカンな土臭いテイストを抱えた−を確かな感触として掴むことができたので、この良質な初のフルレングス作が届いた時はこれからの活動にかなり期待するところがあったのだが。
死児の年齢を数えるとまで極論はしないが、この先の活動がとうとう無くなってしまったバンドを書くことはあまり好ましくないようにも感じている。多くの実績を残した訳でもなく、無名のまま終焉を迎えたローカルバンドを実際に知る人は本邦では殆ど存在しないだろうし。
ただ、レヴューの順番が解散公式発表直後に廻ってきたことは全くの偶然である。先年末に、来年はPeepshotでも取り上げようか、と考えていた途上で解散を知ったのだ。
さて、このPeepshotというバンドであるが、西海岸はカリフォルニア州の大都市LAに連結するようにして発展したロング・ビーチのバンドである。
バンドの母体が始動したのは、1989年。当時まだ10代の高校生であったBrianと弟のDaveのSummers兄弟が友人達とバンドを組んだのがその始まりだ。
単科大学に通いつつ、Brianがギターとリードヴォーカル、Daveがギターとヴォーカルというギターデュオを中心に沢山のメンバーが入れ替わり立ち代りしていった。
最終的にリードヴォーカルにしてベーシストのBenjamin HinchとドラマーのHale Savardがメンバーとして固定した時に彼らはPeepshotを名乗ってデビューした。これが1996年のことで、LA周辺のライヴハウスを他のローカルアーティストとジョイントで廻ることを続けつつ、演奏スタイルを固定していった。
バンドのメンバーが影響を受けたのはNeil Young And The Crazy Horse、Elvis CostelloとPresley、活動初期のハードパンクなスタイルだったLou Reed、そしてWillie Nelson。以上のような古典アーティストから、WilcoやThe Jayhawksというオルタナカントリーブレイク以降のバンド、それにSonic YouthやPearl Jamというモダンヘヴィロックまでも挙げている。
この点がPeepshotの特徴なのだ。西海岸カントリーロックを何処かに感じさせながらもあからさまなAlt-Countryやカントリーへのアプローチは見せない。とはいえ、ルーツロックという範疇に括る以外には何処にも行けないという音楽性を有してはいる。
同時に、現代ロックの主流であるオルタナティヴのヘヴィさと鬱な感情を込めたナンバーも包括しているバンドなのである。前述したように、Brian SummersがPeepshotとして提供したナンバーにはこの手のマッチョでダークなオルタナティヴ味付けを塗した曲が多い。無論、Benもオルタナティヴロックを書いているし、Brianが逆を行うことも然り。
このアルバムをリリース後のインタヴューでドラマーのHaleは以下のように自分達の音楽を分析している。
「僕達の歌は一層焦点が絞れ、円熟味を増してきたと思うよ。最終的には僕達はこの方向性を当面維持していくつもりなんだ。僕達はCrazy Horseと同じくらい長く一緒にやれると思うし、バンドの音楽性は丁度良い位置に落ち着いたね、そうPearl JamとTom Pettyの中間的なロックサウンドにね。」
まあ、Crazy Horseのように何十年もバンドを組むことは適わなかったにしても、Tom PettyとPearl Jamを併せたようなロックンロールを演奏しているという自己分析は的を得ている。
つまり1970年代から継承されてきたアーシーでパワフルなアメリカンロックの基本に1990年代典型のヘヴィでノイジーなロックパワーが乗っかったサウンドということだ。安直にオルタナティヴがルーツロックと合体し融合したサウンドとは言いたくは無い、然れども。
この2者は水と油とまで反発はしないけれども、そう簡単にはエマルジョン化しない疎水的な相性のある音楽ジャンルだと思う。
Peepshotの音楽を分析すれば、大人しいAdult-Alternative Rockと極端にCountry Rockに突っ込んでいないRoots Rockの曲が共存しているものと捉えれば一番適切。
トラックごとにその割り方を適用してみると、Adult-Alternative的な色合いの強い曲は、まず頭から行けば#3『Already Lost One』。バンドの説明によると、「メロウでレイドバックしたロックトラック。」となっているが、メロウというよりもドゥーミィなオルタナティヴ・ソングだろう。これはBenの書いたナンバーであり、このアルバムでは唯一オルタナ臭いBenの曲である。
そして、次が#6『The Big One』。こちらもかなり重い空気が漂うステロタイプなオルタナティヴ・トラックである。但し、それなりに土臭いアレンジに纏め、頭ごなしの剛球一直線で押し出すという空虚なオルタナ的アレンジをしていないために、聞き苦しい箇所はそれ程ないナンバーである。
メディアにはJohnny CashとSonic Youthを同時に再現するバンド、という筆者としては肯定的な雰囲気では捉えかねる表現をされているが、まさにCashのダークなフィーリングとSonic YouthのアンダーグラウンドB級感をフュージョンさせているナンバーであるだろう。Pearl Jamから低脳な強引さを差っ引くとこういった重めのロックが抽出できるかもしれない。
この2曲ほどではないが、ルーツサウンドに現代ロック的な怜悧さと無機質感覚を混ぜ込んだのが#2『Any Other Way』だ。これもBrianの手による作詞作曲となっている。メロディ的には一部ポップに走るのだが、かなり固めのアレンジが頭角を表わし始めると、ギターが硬く走るラインにポップさは隠されてしまい、オルタナティヴの悪臭が微妙を超えて浮き上がってくる中途半端なオルタナ・ルーツソングに集束していく。
正直、#2、#3、#6は全く必要ない。邪魔なナンバーだ。このアルバムがもっと良くなった可能性をドブに流してしまっているので、非常に残念。やっぱりオルタナ氏ね!!!(結論はこれ)
マッチョでヒネリの無いというオルタナ・ヘヴィネス的な要素を持ちながらも、ロックンロールの速さと痛快さで暗鬱さを吹き飛ばしてしまっている#8『Rock N Roll Show』くらいの直球勝負をこれらのオルタナティヴ・インフルエンスド・トラックでしてくれれば、「Welcome」はまさに諸手を挙げて名前の通りに「歓迎」可能なアルバムになったと返す返すも残念である。
反面、単なるカントリーロックのバンドに終始していないのは、モダンサウンドをある程度咀嚼して表現することに成功しているからでもあるから、現代ロックの全てがA級戦犯と断言するつもりはないのだが。
しかしながら、この暗礁地域のような3曲を脳内から洗浄してしまうと、ハードなロックンロールの#8を含めた5曲はとても良質なPop/Rockである。
オープニングナンバーの#1『Rhymes With End』からBenとBrianの決して流麗とはいえない不器用なダブル・ヴォーカルに乗って歯切れの良い西海岸的な清涼感のあるロックチューンが出現するのは嬉しい。キャッチー且つ、シャープな演奏がアメリカンロックの中庸とはかくやと語ってくれるかのようである。
#4『Who Makes You Laugh』はメロディのみを追えば、#1よりも更にマイルドでありしぇイキングなリズムが映える好チューンである。ギターロックの快感ともいうべき軽快なギターの音色がシンバルの目立つドラムと堅実なベースラインに彩られて元気にタップしてくれる。
こういった決して派手さは無いのにどこか晴れやかな印象を曲に有するのは流石に西海岸の土壌から生まれてきたバンドというところだろう。やはり西海岸ロックの血を受け継いでいるバンドなのだ。
#5『I Heart Las Vegas』は記号のハートマーク(機種依存文字なため書かないが。)によりアルバムではHeartがマークと置き換わっている。最初はてっきり『I Love Las Vegas』と思ってしまった。歌を聴く前の段階であるけれど。このナンバーは#4の流れている空気を更に暖めて包容力を付けたというところだ。
メロディ的には#4よりもダンシングなロックリズムが強烈である。バラードとまではスローダウンしていないけれどもコッテリとした調子が聴く耳を安心させてくれるナンバーだ。
#7『Matter Of Choice』まで、ここでピックしたお気に入りは全てBenjamin Hinchの作品というのは完全に筆者にとってはBrianの評価が低いことを意味している。本当に良い曲を書くライターなのだ。
この#7は最もカントリー的な土臭さと開放感が振り掛けられている曲でもある。言い換えれば、西海岸サウンドを確実に表現している筆頭のナンバーでもある。かなりメロウであり、しかも曲の後半は延々とウエストコースト青空風ギターソロが続くというインストゥルメンタルが大半を占めるトラックでもある。
何と12分以上にも及ぶ大作になっている。ギターソロもハードロックやサイケディリック、そしてクラシカルなパンク風味と頻繁にその顔を変えていくのも興味深い。このナンバーはPeepshotがライヴバンドであることを主張するためにトラッキングされたとしか思えない。少し10分近いギター中心のソロパートは蛇足というか8曲入りのこじんまりとしたフルアルバムには流れに乗りかねている面はあるが、曲自体は西海岸カントリーをベースにしたダイナミズムのあるメークマークでもあり、悪くは無い。
Peepshotは筆者がLA在住の折、1997年にミニアルバムである「B.I.G.F.I.N.」をまずリリースしているが、こちらの5曲入り作品の方が、開き直ったカントリー的な背景を打ち出している。
「Welcome」はよりモダンロックとオルタナティヴの音が増してルーツとの二極化が進んだ作品ともいえるだろう。その分、ヴォーカルが決して強くないPeepshotが演奏するには少し向いていないと考えていたフォーキーでロー・ファイなウエストコーストの一要素が引っ込んだため、ロックアルバムとしては「Welcome」の方が手応えが重く、強い。
Peepshotとは日本語に訳すと「盗撮」という意味になる。また、「いかがわしい見世物」というようなニュアンスでも使われたりもする。
こういった名前を堂々と名乗る連中だから芸術性とか繊細さを気にするようなアルバムでは食い足りない箇所があったので、「Welcome」はオルタナティヴの影響を打ち出したとはいえ、ロックンロール好きとしては満足の出来る1枚だったのだ。
寧ろ、当時は2001年にプレス予定の2作目フルレングスで、どのようなルーツロックとオルタナティヴの調理方法を晒してくれるか楽しみに待てることを齎してくれるアルバムだったので、重ね重ね解散は残念である。
Brianは非常に音楽活動をしたくて堪らないことを事あるごとに述べているのだが、問題はBenjaminである。この曲を書かせるとBrianよりも一般向きなポップなルーツロックを生み出す才能が北カリフォルニアで小説書きのために浪費されているのは勿体無い。
Brianとのジョイントはバンドの内紛と解散を想像するにつけ難しいだろうが、是非また一線で活躍して欲しいと祈っている。 (2003.1.18.)
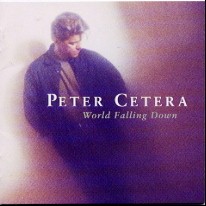 World Falling Down / Peter Cetera (1992)
World Falling Down / Peter Cetera (1992)
Adult-Contemporary ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★★★
Soft Rock ★★★★★
You Can Listen From Here
何時か、何時の日かPeter Ceteraが古巣のChicagoに戻ってリードヴォーカルを歌ってくれないものか。
このような願望をまだ何処かに抱いているポップ・ロックのファンは少なくない数に登るだろうと推測している。かく言う筆者も、Bill ChamplinやJason Scheff主導のChicagoよりもPeter Ceteraがバラードやロックナンバーで牽引するChicagoがやはりChicagoと考えているひとりである。
これには1990年代にたった1枚のオリジナル音源しか出さなかったCetera脱退後のChicagoというバンドの印象が最近頓に薄いということも梃入れをしていることは確かだ。
とはいえ、やはりJasonが歌う『Hard To Say I’m Sorry』や『You’re The Inspiration』はそれで凄く良いのだが何処か違和感が残る。「18」以降の歌ならまだしも、Peter在籍時の歌はPeterに歌って貰いたいというのは多くのファンが持つ願望だと考えているのだが・・・・。
Peter Ceteraといえば、やはり1970年代から80年代を通過してきた層には、ソロシンガーというよりChicagoというアダルト・コンテンポラリーまたはブラスロックバンドの看板シンガーという印象が強いだろう。
1970年代後半から1980年代初頭の一時の低迷期を除いて、Chicagoは間違いなくチャートのハード・ヒッターであったし、『If You Leave Me Know』をヒットさせてからのシングル曲は殆どがPeter Ceteraのヴォーカルだった。
英語表現ですらDavid FosterNIZEと造語される「16」以降のバラードバンドへの変遷に対して賛否両論はあるにせよ、その牽引役となっていたのはRobert Lammでもなければ、Bill Champlinでもなく、Peter Ceteraだった。
そのCeteraが抜けた後のバンドは「19」までは順調なヒットアルバムを記録したものの、それ以降はツアーにかまけるばかりのベスト盤を手代え品代え出すという集団に堕落してしまった感は否めない。
そもそものCeteraの脱退理由は
「僕はアルバムをレコーディングしたかった。でもバンドの連中は何かというとツアー、ツアーとしきりにライヴツアーに出たがった。これがそもそもの衝突理由なんだ。僕はアルバムを創りたいんだから。」
というツアーバンドになることをPeterが厭うたからであり、その後のChicagoのリリース状況を鑑みると、Ceteraの弁が一面正しかったと思える。
そうしてバンドと袂を分かったPeterだけれども、くっついてまたぞろ離れるのは日常茶飯事な音楽界。いずれはきっとChicagoと和解してくれるだろうという期待はある時点までかなり楽観的に抱いていたのだが、その願望はかなり非現実的だと思い知らされたのが、1997年のA&M Recordsが消滅寸前にリリースしたベスト盤「Collection:You’re The Inspiration」の裏話を知った時である。
当時A&M傘下にあったRiver North RecordsにてPeterが企画したのは、過去のデュエットした曲全てが半分、更に新曲を半分フューチャーしたベストワークス的アルバムだった。
しかし、レコーディングが進む内に、PeterはChicago時代も加えたコンプリートなアンソロジーを作りたいという意向を示すようになる。
そこでCeteraはChicagoのマネージメントサイドにPeterが歌ったナンバーの使用許可を求めたのだが、Chicagoのメンバーがこれを拒否。かなり問題が拗れたらしい。
版権は確かにChicagoサイドにあるのだが、ここまで感情的にPeterのソロアルバムにバンド時代の音源を加えることを拒むとは思わなかった。確かに1990年代のChicagoの収入源はカタログナンバーとは名ばかりの少し曲目を変更しては発売されるベスト版が主だったので、Peterにヒット曲を持っていかれるとバンドの看板ソングが消失してしまうという危惧はあっただろう。
だが、ここでChicagoとPeter Ceteraの関係が手切れ後10年以上を経過してもしっくり行っていないことは明らかになってしまった。
結局、『If You Leave Me Now』、『Baby,What A Big Surprise』、『You’re The Inspiration』の3曲を新たにリメイクすることでCeteraのソロとしては初のベストは完成に漕ぎ着ける運びになったのだが、これでChicagoと和解することは永遠になくなってしまったということもはっきりした。
結果としては、アンプラグド的なアクースティックサウンドを押し出したこのリメイク3曲の方が、オリジナルよりも良い出来になっていると思うので、それはそれで良かったとは思うのだが、これからもPeterのソロベストにはChicago時代のオリジナルが入ることは無いし、ChicagoのメンバーとCeteraが同一のステージに上がることも無い。
これは非常に残念であると思う。
さて、そういった事件が起きる前、1992年に発売された「World Falling Down」について今回は書いてみたい。
このアルバムはソロ作としては通算4枚目となる。1stソロの「Peter Cetera」(邦題:何故か、「夢のライムライト」)はバンド在籍時に録音されているので、独り立ちしてからは3枚目となる。
このアルバムを発表した時点で、年齢は48歳である。2003年には59歳に達し、60歳に手が届いている人であるが、今現在でもとても1944年生まれとは思えない。永遠青年の見本のような人である。
増してや、1992年の段階では、エアブラシを掛けたようなジャケットフォトとモノクロームな写真ではやや判別し難いが更に若く見える。というか流石に物凄く若くは見えないが、年齢相応にはとても見えない若さがある。決して童顔という訳ではないのだが、兎に角若い。
筆者が最後にPeter Ceteraを生で見たのは1996年のことだが、とても50歳を超えた人には見えなかったことは記憶に焼き付いている。1995年に初めてメジャーレーベルからインディ発売に切り替えた「One Clear Voice」のリリースツアーのことだった。
「One Clear Voice」は実際のところPolygram系列のレーベルであったため、諸外国ではメジャー発売となっているところが多いし、後にPolygramからのリリースもされているけれど。
1995年夏にオートバイで事故を起こし、顔面を大きく傷付けてしまい大手術をしたために、アルバムのツアーが半年近く遅れてしまったと聞いていたが、事故の影響は全くないステージを見せてくれたので、ひとまず安心を覚えたものである。
しかし、容姿もさることながら、やはり永遠青年たる所以はその声にあるだろう。流石に『Questions 67 And 68』や『25 Or 6 To 4』の1970年代初頭の青臭さは抜けているけれど、『If You Leave Me Now』や『Hard To Say I’m Sorry』の頃と比べても声が太くなったり、粗くなっているということが全くないのは驚きだ。
恐らく何時か引退するまでこの美声を維持していくシンガーであると思う。2001年の最新作にして初の純粋なインディアルバムである「Another Perfect World」(日本ではビクターからの配給)でもそのハイトーンな甘いヴォイスは遺憾なく発揮されている。
典型的バラード用ヴォーカルと事ある毎に揶揄され、バラードしか歌えないと口さがないメディアの批判を受けてきたPeterだが、確かに大ヒットナンバーは9割どころか10割バラードである。しかもメジャーコードで売れ筋アダルド路線にカッチリと便乗したような。
ソロデビューした後直ぐに2曲の全米No.1ヒット『Glory Of Love』、『The Next Time I Fall』は共にこれでもかという具合のトップ40ヒット狙いのバラードだったし、Cherとのデュエットでトップ5まで上った『After All』も混合デュオの得意技であるバラード。
これではバラードだけで生きるシンガーというレッテルを貼られてしまうのは仕方ない面もあるのだが、それに真っ向から歯向かったのが、3枚目のソロ作品、「One More Story」である。Patrick Leonardをプロデューサーに据え、これまでのメロウでナチュラルな路線を全く無視したマシンビートとダンスリズムを中心にしたミステリアスなアルバムを自らへの挑戦状として叩き付けた感じのする迷作だったと捉えている。
Peter本人も後のインタヴューで、「このアルバムはひと言で述べれば『コンピューター・アルバム』だね。アップビートを追求しようとしたけど、リズミックなアルバムになってしまった。」
のようなコメントを漏らしている。
従来のテクノビートから離れたポップロックの名曲『One Good Woman』は全米第4位まで上昇するヒットになったのだが、ファーストシングルである『Best Of Times』はチャートの下位に留まり、3枚目のシングル『Body Language』はチャートにすら飛び込まなかった。
ところが、筆者がPeterの歌の中で最も好きなのは、この異色作「One More Story」のオープニング曲であるミステリアス且つNew Waveポップな『Best Of Times』だったりする。何処が良いのか我ながら理解できないのだが、知らず知らずのうちに何回も聴いてしまい耳に残って離れなくなってしまっている。全く特筆するところはなく、ベストアルバムにも選出されないナンバーなのだが。
しかし、ソロ1作目から「World Falling Down」を眺めてみると、Peter Ceteraはオープニングにキャッチ−とはいい兼ねるタイプのマイナーで不思議なメロディを持つナンバーを持ってくる傾向があるように思える。
1作目の『Livin’In The Limelight』、2作目の『Big Mistake』、3作目の『Best Of Times』、そして今回紹介する4作目の#1『Restless Heart』。どれもシングル曲としてカットされているが、お世辞にもトップ40で回転しそうなメインストリームなメジャーコードな歌とは言い難い。
2作目から4作目では、寧ろ2番目の曲の方が遥かにヒット性を高確率で内包している点でも共通部分がある。
「World Falling Down」も、これまでの流れを継承しているかのように、それ程リマーカブルでない曲から幕を開ける。
何故か第1弾シングルとして切られた#1『Restless Hearts』だが、2003年現在までPeter Cetera個人としては最後のトップ40シングルでもある。
デビュー盤のオープニングを除けば、それ程恣意的にテクノロジーが使われている手法は取られていない。『Big Mistake』や『Best Of Times』と比較しても、ミステリアス度は低く、ナチュラルな音出しに配慮しているプロダクションが感じられる。
これは、前作である「One More Story」があまりにもテクノビートやダンスリズム、そしてメカニカルビートを多用して仕上がったことへの反作用なのだろう。この反動は「World Falling Down」全体に影響を及ぼしている。
前作や最大のヒットとなった前々作「Solitude/Solitiare」でふんだんに使用されていたコンピュータープログラミングは最小限度に抑えられ、メロディックでオーセンティックなAdult Contemporaryの王道を選択した作風が貫かれている。
反面、ベースギターを一手に引き受けていたベーシストでもあるCeteraがこのアルバムからは1曲のみのベースプレイに変化し、ステージでは未だにベースを弾くが、レコーディングではベーシストはセッションミュージシャンに委任するようになるのも特徴である。ナチュラルなサウンドへ回帰するステップとなったアルバムでベースをストラップから外したというのはどうにも暗示的であると思えるのだ。キーボードベースやサンプリングに頼る頻度を減らしたのに、ベースは自分の手を離れてしまったという。
その脱テクノビートを推進しているアルバムの中でも最もテクノロジー・サウンドの使用頻度が高いのは#1であるのは、オープニングナンバーへのCetera自身の思い入れか何かかもしれない。もっとも、次作「One Clear Voice」では“1曲目にヘンなナンバー”が来るパターンは崩れてしまうのだが。
さて、#1であるが、遅過ぎず、とはいえロックビート未満であるというゆったりとしたナンバーである。物凄くキャッチーでもないし、ダークに特化した訳でもない地味なポップナンバーである。この曲がAdult Contemporary Chartで年間2位になったのは俄かには信じ難い。このシングル化にしても、やはり「バラードシンガーだけの存在とは見られたくない。」というPeterの意地が起因していると思う。
その地味な開幕の次に続くのが、3rdシングルとなり小ヒットを記録した#2『Even A Fool Can See』である。このキャッチ-でメロウなPop/Rockの教本の如きナンバーにPeterの甘いヴォーカルは非常にマッチしている。#1がプロデューサーである英国人のAndy Hillが全ての楽器をプログラミングし、プレイしていたのに対して、#2ではより生に近い演奏が耳に入ってくる。何といっても、名プレイヤーであるRobbie Buchananのシンセサイザーとピアノの音色が印象に残る。特に後半でのジェントリーなピアノソロは最高に素晴らしいインパクト−とはいえ強烈なものではなく、優しくまろやかな空気を演出する−を与えてくれる。また、ささやかでありつつ巧みなブラスセクションのフュチャーも上手い。
こちらを最初にカットしておけば、このアルバムもトップ200の尻ではなくトップ100までは善戦できたろうにと予想させるくらい良質なアダルト・ポップである。このナンバーと#8『The Last Place God Made』のみDavid FosterとPeter Ceteraのプロデュースとなっている。この完成度の高さは流石にDavid Fosterであると思う。
David Fosterが手掛けたもう1曲の#8は、David Fosterが殆どのキーボードを演奏している。ソングライターにはElton Johnの80年代のアルバムのパートーナーであったGary Osborneの名前が見て取れる。シンクラヴィアを駆使した厚目のオーケストレーションはやはりDavidの得意とするところだ。ダイナミックなパートでの大仰さも彼ならではのアレンジだろう。Chicagoの「16」や「17」でのコンビが復活した訳だ。
が、1991年には湾岸事変の救済チャリティソングとしてPeterはDavidと『Voices That Care』を録音し、トップ10ヒットにしているから、長期のブランクが空いていたということでもないのだが。
Elton John関連では#9『Dip Your Wing』のミディアムロックバラードでBernie Taupinが作詞を担当している。このナンバーは美しいピアノサンプリングで始まるスローナンバーのように見せかけて、意外にロックンロールしてくれる気持ちの良い爽やかさが目立っている。
そして、3番目はPeter Ceteraの十八番となったインスタント男女デュエットである。これまた5曲を越えるヒットの実績を持つPeter Ceteraのデュエットでは筆者が最も好きなナンバーである。
パートナーをChaka Khanに迎えるという一見かなりミスマッチのような組み合わせだが、どうしてどうして、#3『Feels Like Heaven』は感動的なパワー・バラードに仕上がっている。入りどころのツボをしっかりと抑えたアルトサックスのソロやオーケストレーションと最強のタッグを組んだロックアンサンブル。どれを取っても大ヒットという単語が連想されるのに、結果は70位前後のスマッシュ・ヒットに終わってしまっている。当時は首を捻りにヒネッたものだが、やはりオルタナティヴの台頭が市場性に与える影響が顕著に現れ始めた1992年から93年のマーケットでは美しいアダルトロックは苦戦を免れない運命にあったのだろう。
他の名デュエット・ソングスと並べても全く遜色の無い傑作曲なのにこの結果は実に残念だ。
#4『Wild Ways』、#5『World Falling Down』と2曲続けて、軽快なロックビートが耳に残るキャッチーなナンバーが連続する。#4はかなり分厚い産業ポップナンバー風の佳作なのだが、#3の感動的なピアノのフェイドアウトから続くオープニングリフが安っぽいシンセサイザーになってしまっているため、名曲#3の余韻をぶち壊すというマイナス効果を持っていて、そのために減点対象になるナンバーである。
#5のタイトルナンバーは#1と同じくPeter CeteraとAndy Hillのプロデューサーコンビが書いたナンバーであり、スマッシュヒットした#2に劣らず良質なメロディが光る曲だ。ピアノとB3ハモンドが、シンセサイザーに鍵盤パートを頼りがちなこのアルバムでは珍しく、プログラミングサウンドを押しのけて目立っている。こちらもシングルとしてカットするべきナンバーだったと今でも思っている。このアルバムの中でも好きな曲だ。
#6『Man In Me』は元Totoのリード・ヴォーカルであるJoseph Williamsが提供したリズミカルで複雑なコード進行を持つアーバンポップ風なコンテンポラリー・トラック。Josephもバックヴォーカルで参加している。筆者はToto最高の選任ヴォーカリストはJosephと信じているので、彼にももっと活躍して貰いたいと思っている。このアルバムでの参加のように。
#7『Where There No Tomorrow』もシャープなギターが映えるアップビート系のポップナンバー。このナンバーで唯一Ceteraがベースを弾いている。パワフルなコーラスワークと弾むロックリズムは、Peterの作品の中でこのアルバムが最もロックしているという評価を得るのにかなり貢献しているだろう。この曲もAndyとPeterの書いたものだが、この2人が書いたナンバーで一番出来のくすんだ#1がシングルになったのは重ね重ね納得が行かない。#5やこの#7をシングルにするべきだった、間違いなく。
そして、Peter Ceteraの中で筆者が一番好きなバラード(一番が多いな)である#10『Have You Ever Been In Love』でアルバムは終幕を向かえる。
殆どのパートをピアノとストリングシンセのみで節をつけ、バックコーラスの全くないPeterの甘く甘く甘いヴォーカルがしめやかに歌い上げる美麗なバラード。アダルトなバラードの理想はかく在れ、と声を大にして主張したくなるくらいのPeter Ceteraにうってつけのナンバーだと思っている。シングルとしてカットされるような派手さも決め手にもいまいち欠けている点は否定しない。
しかし、Tim Pierceのエモーショナルなギターソロをオーヴァープロデュース気味に曲後半で登場させることにより単調に成りかねないピアノバラードにインパクトを植えることに成功している。このプロデュースは2名のプロデューサーに完全にしてやられたというしかない。控え目なメロディだからこそ、何時までも飽きずに聴けるという要素もこのバラードがエヴァーグリーンである所以だとも考えている。
以上、際立ったヒットナンバーも無ければ、商業的にも成功しなかったが、全体のバランスと完成度ではPeter Ceteraの作品では最も高いレヴェルにあると筆者が見なしているアルバムについて述べてみた。
このアルバムでもどのアルバムでも思うのは、何十年もあの透き通る美声を維持できるこのヴォーカリストの魔力というか不可思議さである。これからもきっとこの声を幾度か聴きつつ歳月を重ねていくと思う。永遠に好きなヴォーカリストのひとりでもある。曲とアルバムにはやや出来不出来の波があるのが玉に瑕だろうか。 (2003.1.16.)
 Learning Curve / Michael Heaton (2000)
Learning Curve / Michael Heaton (2000)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★☆
Alt-Country ★★★★
You Can Listen From Here
Michael Heatonのショウを1998年にシカゴで観た。
当然のことながら、その際は本作「Learning Curve」は発売されていなかった。
当時、筆者の住居の合ったシャンバーグから自動車で30分程度南下した所に、Michael Heatonが定期的にライヴを行っている都市、ネイパーヴィルがある。Michaelはこの街をホームグラウンドにして現在も活動してる模様だ。
要するに、ネイパーヴィルもシャンバーグもミシガン湖畔のセントラル・シカゴから西へ自動車で1時間弱走った場所に分布する非常に治安と環境の良い衛星都市の一部である。
そのライヴ会場にて、カセットテープのみの販売となっていた「Rest In Pieces」を入手して、ライヴの余韻を引き摺りつつ帰宅して80ドルで購入した安物のCDラジカセに放り込んだ時の衝撃は、今なお忘れることが出来ない。
この衝撃というのは、決してネガティヴなものではない。
容量の小さいスピーカーから流れてきたサウンドが、ライヴで披露していた音楽とはかなり異なるフィールドに属する代物だった故に、単純にかなり驚いたのだ。
また、Michael Heatonのライヴパフォーマンスから漠然と予想していたサウンドと、カセットテープの録音はかなり食い違いが合ったにも関わらず、双方共に音楽としてはかなり良質であった。このことは、ライヴ演奏とレコード上の音楽性の差という、通常はあまり歓迎できない状況に当て嵌まりやすい事象なのだが、その予測の斜め上を行ったというレアなケースのため、驚きの印象が強いのだ。
異なるというよりも、ジャンルが全く違うと言い切っても問題なかった。一瞬、別のミュージシャンのカセットテープを間違って購入してしまったのではないかと、テープのレーベル面にあるクレジットを慌てて調べるハメになった。
確かに、このカセットテープの歌い主はMichael Heatonではなく、Cutというバンドであったのだが、購入の際、売り子に
「このCutってバンドはMichael Heatonのグループかいな?」と尋ねたら、「クロネ●ヤマト(=うん、そうや。)・・・・・(南極ギャグ)。」って返事が返ってきたし、クレジット上でも曲を書き、ヴォーカルを担当しているのは紛れも無くMichael Heatonであったので、全く別の存在ということはありえなかった。
と、いい加減前置きがクドくなってしまったので、そろそろ本題を述べるとしよう。
まず、Michael Heatonのライヴ演奏から筆者が受けた彼の音楽性は以下の通り。
Alt-Countryであり、アクースティックなFolk Rockの感覚を同時に有しつつ、非常にポップなサウンド。
何はともあれ、アクースティックギターを手にして歌うMichael Heatonのライヴ・アクトはかなり気分爽快なものであった。
しかし、Cutのカセットテープである「Rest In Pieces」に流れている音楽は、モダン風味のあるエレクトリックギターを大幅に強調した、所謂Power Popであったのだ。
殊に、アクースティック感覚が満載だったMichaelのライヴを観た後では、このSwagにも通じそうなドリーム・ポップサウンドが異様にスマートに見えてしまった。
また、かなりCountry Rockの野暮ったいフィーリングをメロディに取り入れていた−あからさまにカントリー風のナンバーもレパートリーに入れていた−ライヴ演奏と比較すると、Cutの音には全くといって良い位カントリー臭さは存在しなかったのだ。
所謂Power PopやModern Popの創り手が、ルーツ回帰ということでAlt-Country、Country Rockという作風が濃厚なPop/Rockアルバムを作成することは、John P.Strohamを筆頭にそこそこ起こり得るのだが、Michael Heatonの場合、ナチュラルな音をキープしたPower Popのバンドを率いていたとはいえ、ここまでアクースティックなライヴを観せるまでに転身してしまったのはかなり稀なケースではないか、と当時は驚いたものだ。
実際に、筆者の所有しているMichael Heaton関連の音源は、本CDである「Learning Curve」とカセットテープで販売していた「Rest In Pieces」の2枚だけなので、それ以前の録音については、他の文献やレヴューに頼るしかないことをお断りして、ここでMichael Heatonの経歴について簡単に触れておこう。
Michael Heatonは1980年代後半から、シカゴ郊外のアンダーグラウンド・シーンでライヴ活動を始めている。
生まれと育ちはオクラホマ州のタルサという街ということだ。彼は、この地域性が自分自身の音楽性にかなりの影響を与えたと語っている。
「多分だけど、僕がタルサで生まれて育ったから、今の僕があると思っている。ラジオから流れてくる音楽はカントリーと一直線なロックンロールだけだった。正確にはどれが、ということはハッキリしないけど、そういった音楽から受けた影響は大きい。」
というバックグラウンドを持ったMichaelは、1991年にリーダーとなって、バンドを結成。The X−Trasという名を得たバンドは、同年にカセットテープのみの12曲入りアルバム「Kamboo!」をインディペンダントのレーベルから発表し、デビューを果たす。
この音源は残念ながら筆者も聴いたことが無い。が、ディスクリプションにはGeorgia Satellites Meets The Ramonesという記述があり、パンキッシュでポップで、ルーツフィーリングを有したロックなピースであった模様だ。非常に興味があるのだが、再発は全く望めないとのこと。Michael Heaton氏本人から、
「残念だけど、リイシューの予定はないんだ。CutもCD化の予定は無い。」
というコメントを戴いている。
また、バンドとしてアルバムを発表した同年には、新しいバンドを立ち上げている。これが、前述のPower PopなバンドのCutであり、1993年には7曲入りのセルフタイトル「Cut」をインディ・レーベルから発売。
2年後の1995年には、5曲入りのカセットテープ「Rest In Pieces」を自主制作して発表している。
しかし、このカセットテープを出した後、ソングライターであり、シンガーでもあった自らの3ピースバンドであるCutを解散し、ソロ活動を始めるようになる。
まず、ソロ活動開始後は、シカゴエリアのケルティック/アクースティックバンドのThe Droversのサポートメンバーとしてツアーに同行し、時にはフロントライナーとしてソロシンガーとなってステージに立つ生活を暫し続けていた様子である。
このアクースティックでアイリッシュ・トラッドバンドとの関連で、Michael Heatonが自らの原点回帰を思い立ったのかは不明だけれども、完全に勢いで押すPower Popバンドのリーダーだった面影は1990年代後半では殆ど消えうせていたように感じる。
次第にアクースティックやカントリーといったアメリカンルーツに傾倒を始め−未聴だが、The X−Trasの頃に立ち返ったのかもしれない−次第にシカゴ郊外のミュージシャンをバックバンドに従えて、ソロ活動を中心に行うように変遷していく。
これが1998年くらいから。
この頃にステージを共にしたバンドには、残念ながら消滅してしまった筆者の大好きなMount Pilotや、Robbie Fulks、そしてフロリダのルーツロックバンドであるHang-Town等があるそうだ。
更に、ブルースバンドやジャムポップのローカルバンドともジョイントツアーを行うように、完全にナチュラル嗜好のサウンドへと方向転換をしていっている。
そして、2000年にイリノイ州のインディ・レーベルから、初のソロ名義作「Learning Curve」をリリースし、現在もシカゴ郊外のネイパーヴィルを中心に3日と空けないスケジュールでクラブサーキットを行っている。
バックバンドはかなりの人数が入れ替わったとのことで、このアルバムのレコーディングに参加しているミュージシャンで現在もMichaelのバンドに残っているのは、リードギタリストのStan Dembowskiだけ。
Stanを始めとして、現在のバンドメイトはMichael以外、モダンロックバンドであるNude Buddhaというグループとの掛け持ちであるというから面白い。
先に述べたように、現在のMichael HeatonのスタイルはAlt-Countryであり、アクースティックなPop/Rockであるのだけれど、バックバンドの本職はモダンロックのインディバンドであるのだ。
しかし、バックの演奏には、装飾過多のモダンサウンドは全く伺えない。完全にMichael Heatonのカラーで染め上げられた音世界を堅実にサポートしている様子が音に刻まれているのが分かる。
さて、このアルバムだが、実はMichael Heatonの名前で筆者は発見したのではなく、元Wilcoの主要メンバーであり、シカゴ周辺のPower Pop系のアーティストと繋がりが何かと深いJay Bennetが参加したアルバムという話を仕入れて発見した次第である。
まあ、この頃は「まだ」Wilcoに対して期待する要素があったのだなあ、と2002年のアレを聴いた後でしみじみと述懐したりもしているのだ・・・・・。
2000年に、このアルバムに出会うまで、シカゴの酒場で観たMichael Heatonというシンガーの名前は全く記憶の底に沈んでいたことを告白しておく。
が、このアルバムを一度聴いてしまえば、Michael Heatonの名前は二度と忘れられなくなるし、事実筆者はHeatonの名前を記憶に刻み付けることが出来た。1998年当時よりも確実に成長し、熟成したシンガー・ソングライターであり、彼の持つ複数のバックボーンと音楽経験を堅実に反映したアルバムになっている。
そのJay Bennetは僅か1曲でリードギターを担当しているだけだが、そのナンバーはアルバムの冒頭、オープニング曲である#1『If It’s So Easy』だ。
この曲は、元Power PoperとしてのMichael Heatonのポップな感覚が十全に活かされ、しかもルーツやトラッドといった土臭い雰囲気も巧みに織り込まれている。
Michaelの魅力は、
ポップであること。
アップビートな曲でも五月蝿過ぎない落ち着きがあること。
アクースティックであること。
極端にカントリーしないけれども、Alt-Countryと名指しするには何ら問題の無いトラディショナル・ミュージックの
雰囲気が存在すること。
それでいてモダンロックのスマートな感覚もそこはかとなく残っているスマートさがあること。
等、数多いが、そのうちのかなりの部分がこのナンバーで表現されている。Jay Bennetのアーシーに捻くり廻すエレキギターのプレイは、派手さは無いが、Jayの芸達者を明白に表現している。
また、アクースティックギターのリフに即座にマンドリンのポロポロした弦が合流するアレンジには、気持ちの良い大地賛称の匂いが含まれている。
#2『Honest』は全13曲のうち、唯一鍵盤であるオルガンが使用されているナンバー。
Cutで全開だった、都会的なパワーサウンドに一番近い位置にあるナンバーのように思える。しかもアルバムでも有数の手応えのあるロックアンサンブルが楽しめるチューンでもある。アクースティックが身上なのは理解できるが、このような効果的なオルガンプレイをアレンジ可能なら、もっとピアノやオルガンの使用に積極的になっても良かったと思ったりする。
#3『Smells Like Gasoline』はシャカシャカとビートを刻む弦楽器に、シェイカーやトランペットが乗っかる、メキシカンやカリビアン・ミュージックをベースにした古臭い南国風ナンバーだ。このあたりは、南部のオクラホマ州出身であるMichaelがテックスメックスやザディコ(それ自体は仏語の歌だけど)の洗礼も受けていることを予想させる。
少し意外な曲調な#3の後は、実にオーソドックスなアクースティックロックナンバーが続く。#4『So,Here We Are』は、これでもか、というくらいに堅実に書き上げ、確実に演奏し、きっちりと歌った結果は間違いないことを実証している如き曲。Heatonの伸びやかなヴォーカルもこの爽やかなロックチューンを補助している。
後半のエレキギターソロは、西海岸サウンドを思わせるくらいに清涼感のある音色を紡ぎ出している。
と、西海岸風のポップセンスが出てきたと思ったら、#5『Silver Lining』ではバンジョーやペダルスティールがスカスカな脱力感を演出する、完全無欠のカントリーロック曲が展開される。
ここまで、Alt-Country“っぽい”ナンバーが殆どだったが、ここまであからさまにCountryさを突きつけられると、何となく力が抜ける。これは西海岸というよりも、カントリー・ミュージックそのものだ。アレンジとしては少しばかり、コテコテさを避けようとしてフォーク・ミュージックを意図したところは見れるが、これは少しやり過ぎなカントリーナンバーではないかと思う。Cutの頃のMichaelなら絶対に書かなかった曲だろう。
寧ろ、Michael Heatonらしいのは、そこはかとなくCountry Rockのテイストがたゆたう#6『Caroline』のようなタイプのアクースティックでアーシーなナンバーだろう。殊更バンジョーやボトルネックギターを使用せずに、田舎臭いギターを鳴らすこういったナンバーの方がシンガー・ソングライターであるHeatonにはお似合いだと考えているのだが。
この形は、次の#7『In The End』にも当て嵌まる。この中間に位置するスローナンバーは、ペダルスティールがかなり目立つアクースティックナンバーであるけれども、軽過ぎず、振り回し過ぎずと、極力カントリー風の定型アレンジを避け、サザンロックに顕著なレイドバック感覚を濃くしようとしたCountry Rockのバラードだ。
また、いかにもCountry Rock式なアクースティックギターのリフでリードされる#8『Big Life』でも、ザクザクと梃入れされるリズミカルなビートのため、かなり濃密にカントリーさを含んでいるけれども、それ以上にポップでジャンプビートな快感が勝るようなアレンジにすれば、スマートなルーツナンバーとして光ることが出来るのだ。
このザックリした音の創りは、1970年代には頻繁に聴くことが出来たのだが、最近はめっきりとメジャーシーンではお目にかかれなくなった種類のサウンドでもある。
と、カントリーをバックグラウンドにしつつも、ウエル・シェイピングなアレンジでPop/Rockさに軌道を載せ変えようとしているかに思えてくると、またもベタなカントリーナンバー、ブルーグラスナンバーが現れる。
フィドルとマンドリンがダンスする#9『Straight To Hell』はフィドルをこう弾くと、やっぱり曲はカントリーに見えてしまうという典型を実践した曲と見なしている。
やはり、こういった伝統曲は、幼少期のカントリーを聴いた経験が影響を与えているのだろうが、CutであそこまでドリーミーなPower Popを広げれたのだから、ここまでグラスに染まることもないと思ったりする。
#10『We’re Not Sleeping』は少しヘヴィな調子と重めな空気を纏った、Michaelの明るい音世界からは異色に感じるライト・ブルースで、レッド・ダートを彷彿とさせる曲。
この後の#11『Saving Grace』も、1990年代のアクースティックロックを引っ掻き回して詰まらない定型を量産した原因となったJam Rockの影響を相当直接投影したナンバーである。
クールに曲調を抑えるのが悪いとはいえないが、どうもこのジャムっぽい暗さと気抜け感覚は好かない。Michaelの才能かポップ好きの故か、かなりキャッチーに仕上げられてはいるのだが、どうにも消化不良なアクースティック・ナンバーであり、退屈という印象を拭えない。
この#9から#11の3曲が、この名盤と呼びたい作品で最も中弛み、気合が抜けている、他と違うことを行って多彩さを出そうとしてあまり上手く運ばなかったパートだと思っている。この3曲は抜いてしまっても問題なかったと、やや辛辣だが思うことはしばしばある。「Learning Curve」を聴く度に。
#12『The World Is An Ocean』は、Folk Rock、弾き語り、メランコリック・アクースティックと何でもいいから、兎に角ギター1本で歌われるシンプルなナンバーであり、しみじみとした叙情感が心に響いてくるという感の質感を有した曲。アクースティック・シンガーであり、このアルバムでも常にアクースティックギターだけを担当しているMichaelの素の表情が聴き取れるトラック。歌い方にも、最も情感を込めているのがこの曲を聴けば一撃で判別可能だ。
そして、最後はトラッドなマッタリ感覚がたまらなく日向臭い、インストゥルメンタル曲の#13『Irene’s Waltz』。
確かにタイトル通り、カントリー・ワルツである。アコーディオンとマンドリンの素朴な演奏がゆったりと流れていくのに耳を傾けると、あくせくした日常を暫し忘れることが出来るように思えてくる。
このトラディショナルなノン・ヴォーカル曲でアルバムを締めるという手法には意表を付かれたが、なかなかにして技巧を披露する多芸さにニヤリとしてしまったり。
全体としては、トラッドやカントリー、ブルーグラスとPop/Rockの分量をアクースティックという重心で均等に支えている良作である。
が、もう少しパワーのあるアクースティックでドライヴするロックナンバーを期待していた面があり、数曲のコテコテカントリー風のナンバーやジャムサウンドをなぞったトラックが画竜点睛を欠くというところがある。
しかし、それすらもこの「Learning Curve」をスポイルし切れないくらい、良い仕上がりなのだ。
このアルバムは2000枚以上、ネット口コミとライヴ会場で売れたそうだが、ゼロが1桁増えて当然の内容だ。
これまでのバンド活動と、ソロ初作で「学んだ」要素で、次回作は売上の「曲線」をもっと伸ばして貰いたい。
そう願っている。現在も順当にライヴ活動をしているようなので、2ndソロ作もボチボチ届けられるかもしれない。
(2003.2.14.)
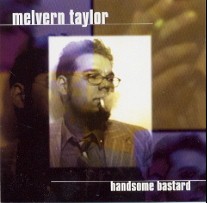 Handsome Bastard / Melvern Taylor (1999)
Handsome Bastard / Melvern Taylor (1999)
Roots ★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Acoustic ★★★★★ You Can Listen From Here
仮に、このレヴューを読み、試聴リンクからサウンドサンプルを聴いた後にMelvern Taylorへ興味を持った人(殆ど皆無だろうが)は、急いで購入した方が賢明だ。
というのも、発売元レーベルの実務とディストリビューションを行っていたRockbottom CDsが2002年の半ばに廃業してしまっているからだ。現在のところ、「2003年の始めのうちまでオーダーがあれば発送は行う。」という発表がなされているが、それも何時まで継続するかについては全くコメントがないのだ。
第一次配給元であるBroken White Recordsが健在なら何らかの手段を講ずるとは予想されるが、ここ2年近くBroken White Recordsから新しいレコードが出たことはない。他レーベルから出たアルバムの発売を代行はしているのだが。
ということで、このMelvern Taylorの2枚のアルバムを販売していたレーベルも先行き不透明だし、そのディストリビューターに至っては店仕舞いを済ませてしまっている。正直未来に楽観的な展望を持つことは困難にしか見えない状況である。
だからこそ、Melvernにはこれからも頑張って貰いたいし、何処でも活躍できる実力のあるシンガーだとも思う。
Melvern Taylorの音楽を一言で表現するなら、Power Folk Rockにするべきか、それともAcoustic Rockの方が適当か少々迷う。
近年、アクースティックギターを積極的にエレクトリックアンサンブルの中心に据えたり、アクースティック楽器のみでロックをパフォーミングする音楽を、Power Folkと言い習わすことが増えてきている。
呼び方としてはどちらでも構わないのかもしれないが、このアクースティックなロックンロールが何処から興隆してきたのかを考えると、それなりに興味深いものがある。
何時の時代にも、例えば1970年代のパンクやニュー・ウェーヴのファッション全盛期や、1980年代後半に暴風雨となったメタルサウンドのブームの頃、そして1990年代に時を移してのグランジ/ヘヴィロックの台頭期にすら、アクースティックなナチュラルサウンドを求めるミュージシャン人口は確実に、細々とではあるが存在していた。
であるから、今更アクースティックなロックンロールが改めて発生したのではなく、こういった系譜の末、現在に至る音楽の一形態がPower FolkやAcoustic Rock、そしてこれらのメジャー版であり大流行な亜流であるJam Rock/Jam Bandだと解釈することが正しい。
筆者はJam Rockは流行に迎合した多くの「音楽屋」がイミテーションしているのが殆どのジャンルと考えているので、敢えて亜流という表現を用いている。無論、中にはオリジナリティを持ちミーニングフルなアクースティックとジャズやトラッドを融合させた、本当のJam Rockを演奏する人々は現実に存在しているし、そういったリアル・ミュージックには「亜流」という否定的な語感は似合わない。
が、多数が少数を駆逐するという、経済理論にも似た音楽マーケットの流行を鑑みれば、基本的にJam Rockはアクースティック・サウンドの継子扱いして然るべきリジェクトであると考えるのが極主観的だが妥当だ。
今回紹介の場を設けた、Melvern TaylorはJam Rockとは完全にジャンル違いの、然れどもアクースティックサウンドを基本にしているミュージシャンである。
また、カントリーやルーツロックへの傾倒度合いも物凄い高いとは云い難い。アメリカン・トラッド音楽の野暮ったく土臭いポイントは押さえているサウンドを演奏する人ではあるのだが、コテコテなカントリー音楽をベースにしてアクースティックなルーツサウンドを展開してはいない。
されども、ジャムバンド特有の半端なブルースやジャズテイストを塗して薄っぺらいデコレーションを施しただけの尻軽な流行音楽とも趣を異にする。
勿論、カントリー、ブルース、R&Bという根源音楽の影響が無いかというと、そうでもない。曲によってはカントリーのバックボーンを、R&Bの影響を、ブルースの感覚を匂わせているからだ。
しかし、そのうちのどれにも特段漬かることの無い、アクースティックなロックサウンド特有のシャカシャカしたギターを聴かせてくれる音楽をMelvern Taylorは創り上げている。そこにフュージョンする、濃厚ではないけれども自己主張ははっきりと行っているルーツなアレンジ。
海外レヴューでは、ある場所ではカントリーと一緒くたにされていたり、フォークサウンドと評されていたり、アクースティックなジャムバンドに伍されていたりと、捉え方もまちまちの様子である。
となると、Melvernの音楽は、やはりAcoustic Rockと呼ぶのが適当だと思う。
軸が極端にブレずに、中道というか癖の無いアクースティックなサウンドを貫通している音楽を、Acoustic Alternativeと近年は云うことが増えてきているが、そのAlternativeな部分−即ち陰鬱でダークで抑揚に乏しい退屈なサウンド−がTaylorの音楽には根本的に欠如しているため、世間に溢れている、「擬似」アクースティックとも違う。
この「擬似」とはやはりJam Rockの異様な氾濫によって、申し訳程度にアクースティックなギターを加えたり、エレキギターを抜いた曲を取って付けたようにトラッキングするオルタナティヴ系のバンドのことを揶揄しているものだ。当然ながら、Melvernには当て嵌まらない表現。
そして、Folk RockやFolk Popというカテゴリーに属するシンガーとも違って、ただアクースティックなギターでシンプルな自然サウンドや繊細なポップ世界をデリケート組み上げようとする、所謂大人しいアクースティックなシンガーとしては、少し動的に過ぎる。言い換えれば、ドタバタしているのだ、アクースティックの静的な面でアレンジと雰囲気を出そうとする層と比べると。
事実アクースティック系の、特にFolk Pop/Rockと定義されるジャンルに属するシンガーの伝家の宝刀とも云うべきバラードを、Melvernは殆どアルバムに持ち込んでいない。
レイドバック感覚は、しっかりと持ち込まれているので、その雄大なダウン・トゥ・アースさが曲を緩く、スロウに見せかける働きをしているところはある。
同時に、アクースティックだけでエンジンを全開にしたロックンロールをドライヴさせるのではなく、ルーツロックの馬力で線の細くなりがちなアクースティックなポップサウンドを支えて加速させていると考えるべきかもしれない。
バラードの話に戻るが、はっきりとバラードと仕分けることが可能なのは、恐らく#4『Wool Over My Eyes』と#12『My Darling Marle』だけに感じる。
所謂スロー・ナンバーに属する曲はそこそこの割合を占めているが、バラードの美しさと叙情性に訴えているのはこの密やかな#12だけだろう。
アクースティックギターよりもMelvernのハイトーンを極端に強調したヴォーカルとハーモニウムサンプリングをした鍵盤のしっとりした音が印象に残る。
#4はアクースティック弾き語りという、いかにもなパターンを踏襲しているが、パワーのあるアクースティックギターのスライドが跳ねる箇所が幾つか有り、このシンガーのロックスピリットがバラードに噴出した形態を示している。
スロー・タイプの曲の場合、Melvernのアルバムに限れば、レイドバックした薄目のカントリーやブルーグラスなフレイヴァーが殆どの場合スローリズムを補助している。
#2『Graceland』という、どっかの賞を獲得したビッグネームのアフリカンアルバムを思い出させるナンバーはグラスルーツの影響をそこはかとなく感じさせる。マンドリンの零れ落ちる音色がそういった雰囲気を後押ししているのだろうが、ここまで牧歌的にアレンジをしておいて、ブルーグラスやカントリーの軽薄さよりも暖かいレイドバックな味わいが強く出せているのはかなり巧い。
Melvernのハーモニカ、マンドリン、といった演奏が聴け、彼のマルチプレイヤー振りが発揮された曲でもある。
#7『Mary Magdeline』はアクースティックギターで殆どが語られる大人しい曲だが、バラードでもスローでもないフォーキィだが、それなりにロックリズムのあるナンバー。
後半にはボックス・オルガン(クレジットではオモチャのオルガンとなっている。)やマンドリン、そしてエレキ・ピアノまで加わるが、全体の感覚はとてもシンプルな弾き語りスタイルに見える。こういった繊細な曲でmTaylorのヴォーカルがシンクロする率はかなり高レートだ。
トラッドに根ざしたナンバーもそこそこ。これまたアクースティックなポップソングとのバランスを上手く調節して、単なるトレディショナルに陥らないようにしている。ここに美声シンガーとしてだけでなく、アレンジャーやコンポーザーとしてのMelvern Taylorの才気を感じる。
ケイジャンの雰囲気を感じる、アコーディオンを模したサンプリングがフューチャーされた#5『Jonatha』ではバンジョーが活躍し、かなり南部風味が聴ける。また、エフェクトを掛けてレコードの針飛びのようなノイズで歌われるバックコーラスの使い方は、後のカッ飛んで極楽なウエスタン・ナンバー『The End』への布石にもなっている。
アクースティックブルースとモダンブルースの中間に位置する曲が、#6『The Sad And Ugly Truth』か。かなりクラシカルな展開を見せるナンバーだが、ロックとしてのパワーは持っている。
同様にブルース−ロッキンブルースとR&Bの境界線を跨いでいるのが#8『Older Than You Think』。後半の哀愁あるメロディはアクースティックで表現しているからこそ、クドくならないのだろう。
以上のナンバーは良好なのだが、やはりMelvern Taylorサウンドの本命はパワフルなシャッキリとしたアクースティックなロックンロール。
#1『Jullet』のシェイキングの大きい、ゆったりとしたコーラスにタップリとしたメロディのローリング。懐の深さとナチュラルな弦の醍醐味がここにある。特にコーラスの大合唱は爽快に尽きる。バックで鳴っているキーボードサンプリングはかなりチープなのだが、それを感じさせない。
#3『Third Verse』はエレキギターがしっかりと投入されている、かなりロックンロールのテイストが強いナンバー。歯切れの良いギターの音色とキャッチーなメロディが元気にパンピングする。アルバムでは最もエレクトリックなアンサンブルが取り入れられた曲の1つ。
#9『Nothing At All』はアクースティックな切れ味は#3以上だし、メロディの綺麗さは#3の上を行く。こちらはエレキ楽器に依存せずに、アクースティックのパワーだけでロックの厚味を出そうとして、しっかりと成功している。別なタイプのアクースティックロックだ。
#10『Your Ugly Sister』と、あまり妹のいる友人の前で口にしたくないタイトルのトラックは、スピーディさではアルバム随一。同時にカントリーな明るさの影響をかなり表わしている。軽快さではGypsy Kingsに引けを取らないが、こちらはエレクトリックな楽器が積極的に使われている。
しかし、カントリーとなると、パーカッションを使用して馬の蹄の効果音まで演出しているお気楽ソングの#11『The End』には敵わない。この曲で突き抜けているのは、ファルセットな音域までギアを入れて歌うMelvernの気合の入ったヴォーカル。そしてハーモニカをバックに崩れて壊れて、大騒ぎして口笛吹いて、音割れし、笑いも入るアホなコーラス隊をオールディズの如く取り入れていることだ。
こういった崩壊スレスレの危険な馬鹿さ加減を持ったナンバーは大好き。格好良さでは#1や#3、そして#9には遠く及ばないけど、得体の知れない魅力がある。
このユニークなアクースティックでルーツィなアルバムを作成したMelvern Talyorというシンガーは、ジャケットで見せる垢抜けない容貌とは似ても似つかない甘いハイトーンなヴォイスの持ち主。
彼は1960年代前半にボストン郊外で生まれている。生年月日に関しては、はっきりしたデータは無いが、Melvern TaylorがBeach BoysやBee Geesを聴いて幼年時代を過ごし、Eaglesの「Greatest Hits」に人生が変わるほどの影響を受けたと述べているので、恐らくはその年代の生まれだと想像している。
Melvernは兄からギターを教えて貰い、ヒットソングをエアプレイするラジオを聴くのが楽しみな一桁の年代を送ったそうである。中学に入学するまでには独学でギターを不足無く弾くようになった。
「Eaglesのスコアからインスピレーションがやって来た。ああ、あとはStyxだね。」
Melvernが少年だった頃はヒット曲がしっかりとしたヒット曲な時代だったのだ。
「80年代の『メタル時代』については多くを語るつもりは無いけど、僕の親父にそれらの音楽を尋ねれば、蹴飛ばすような勢いで貶してくれると思うよ。」
と1980年代後半のメジャー・ヒットソングには楽しまなかった模様だが、1990年代掛けてマサーチューセッツ大学で学んでいた時に、多くのインディミュージシャンと既知を得、影響を受け、レコーディングのチャンスを獲得する。
この「Handsome Bastard」を1999年にローカルレーベルから発表するまで、Melvernはマサーチューセッツやテキサスで細々とソロアクースティックを行ったり、あちこちの無名バンドを渡り歩いていた模様だ。
契約に漕ぎ着けた時も、レーベルを開設し自らのレコードを発売しようとしていた友人が酔っ払っている時に、自らのレコードを売り込んで、有耶無耶の内に承諾をさせて言質を取って発売を認めさせたという詐欺紛いの強硬手段で発売まで持っていったと語っている。本当かは定かではないが。
この「Handsome Bastard」はマサーチューセッツ州を中心にジワジワと評判を呼び、これがニューハンプシャーのインディレーベルであるBroken White Recordsの注目するところとなる。
そして2000年には改めてレコード契約を締結し、「The Spider And The Barfly」のレコーディングを始める。同時にデビュー盤の配給もBroken White Recordsが実施するようになる。
2001年に「The Spider And The Barfly」を発売して、活動は順当に見えたが、親レーベルが沈没しかかっている現状ではどのように巻き返しを図ってくれるか期待するくらいしかない。
ライヴは地元でそれなりに順調に行っているらしく、レコードレーベルを代えても、または自主レーベルにスケールダウンしてしまったとしても、次のアルバムでも良い仕事を見せてくれることは十二分に期待できる。
が、これまでのリリース間隔なら3枚目が出ても良い頃なのに、動きが鈍いのが少し気に掛かる。
アクースティックシンガーとしては天賦である、綺麗でソウルの入ったヴォーカルを持っている人なので、シンガーとしての活躍を特に期待したい。彼の音楽はもとより、声に筆者は惚れ込んでいるのだ。 (2003.4.5.)
 Hallucination / Shaw Blades (1995)
Hallucination / Shaw Blades (1995)
Roots ★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Country&Adult-Contemporary ★★★
「僕とTommyはこれまでに20枚近いアルバムの作成にコミットしてきて、2500万枚以上の売上を上げてきた。そして漸く心からやりたかった1つのとある音楽に辿り着くことができた。そして、それは幻想=Hallucinationではなかったんだ。」 Jack Blades
“Hallucination”とは「幻覚」、「幻聴」、「錯覚」というような意味を持つ単語である。
何とも示唆的なタイトルだと、このアルバムを聴くたびに思う。
というのも、このアルバムがこれまでShaw/Blades、即ちTommy ShawとJack Bladesが手掛け、追い求めてきた音楽性から考えると、まさに幻聴に聴こえそうな意外な方向性を選択した作風になっているからだ。
Tommy ShawそしてJack Bladesという名前を耳にして即座に連想するのは、ハードロック、産業ロック、プログレッシヴ・ロック、アリーナ・ロック、ヘヴィ・メタル、という音楽ジャンルに違いない。それ程異論は出ないと思う。
今更述べるまでも無いが、Tommy Shawは1970年代から80年代にかけてヒット街道を驀進したプログレッシヴロックバンド且つポップな産業ロックバンドのStyxのヴォーカリスト兼ソングライターとして1980年代前半までシーンの最前線で活躍している。
また、Jack Bladesは日本で特に人気が爆発したポップメタル/ハードロックバンド−最強のツインリード・ギターを持つバンドと呼ばれたNight Rangerのリード・ヴォーカル兼ベーシスト、そしてソングライターとして1980年代にヒットシングルを多数放っている。
この1980年代の流行に深くコミットしていた2人のヴォーカリストとソングライターが、あのTed Nugentを加えてDamn Yankeesを結成したのが1989年。
丁度グランジ/オルタナ・ヘヴィロックの大侵略の前夜1990年に発売された「Damn Yankees」から突如、『High Enough』が何のプロモーションもしていないのに全米ポップチャートで3位まで上昇するヒットを記録したのが、1991年のこと。
この頃にはニルヴァーナを始めとするシアトル発、重いだけ憂鬱雑音なグランジサウンドが全米の若者の間で爆発的に受け入れられ始めていたが、そのファッションの間隙を縫うようにしてアルバム自体もトップ20入りした。
まあ、正直このアルバム自体は産業ロックバラードの『High Enough』以外はしょうむない曲、ハードロックだけだったのだが、やはりヒットシングルの牽引力は凄まじいものがあるなあと思ったものだ。当時北米のMTVでも『High Enough』のプロモーション・ビデオは頻繁にオン・エアされていた。
ついでにアルバムのトップバッター・ナンバーである『Come Again』も全米50位くらいの中ヒットになったが、これはご祝儀ヒットと言うべきものだろう。
「Damn Yankees」のヒットの熱量が冷め切らないうちの1992年には、バンドは2枚目のアルバムである「Don’t Tread」をリリース。このアルバムも時代は完全にグランジやヘヴィロックに流れ出していたにも拘らず、全米トップ30ヒット入りし、『Where You Going Now』がシングルとして全米第20位まで上昇。
Damn Yankeesはこの後1993年まで活動を続け、ジャン・クロード・ヴァン・ダム主演のマイナー映画である「Nowhere To Run」のサウンドトラックに『Silence Is Broken』というナンバーを提供し、スマッシュヒットさせたところがこれまでの表舞台の最後の活動となっている。
1994年の1年はバンドを休止させて新しい音楽の可能性を模索していたというが、実際はバンドは解散状態にあった模様だ。
このアルバムには数曲のみ、Damn YankeesのドラマーであるMichael Cartelloneが参加しているが、Ted Nugentの名前は何処にも見ることが出来ない。どちらかというと新生Damn Yankeesの別ヴァージョンとして捉える方が適切かもしれない。
「バンドに所属しているとね、特定の連中と24時間顔を合わせないといけないんだ。この状態が続いて暫くすると、お互いに上手くやれるか、それとも互いの首に紐を掛けて締め上げているような状態かのどっちかに落ち着くことになるんだな。
その点、僕はTommyと実に上手くやっている。僕達は常に創作活動を楽しんで共同作業しているからね。何のフラストレーションも無い。」
というJack Bladesの当時のコメントに、Damn Yankees内部での、特にTed NugentとShaw/Bladesコンビの間で何かしらのトラブルがあったという可能性は高い。
オフィシャルとしては、Tommy ShawとJack Bladesが新しい境地を切り開くため、Damn Yankeesを開店休業して取り組んだユニット名がShaw Bladesとなっているのだが。
「僕達はこれまでに全く手をつけなかった新しい形の音楽を創りたかった。スタジオに入り浸って、時間とかスケジュールという拘束を気に掛けずに自由に曲を書いてレコーディングをしたよ。」
という成果がこの「Hallucination」に当たる訳だ。
で、以上のJack Bladesのコメントを忠実に裏付けるように、Styx、Night Ranger、Damn Yankeesといったこれまでのキャリアのジャンルからは少し予想の斜め上(ファンにとっては下か。)を行くサウンドを創り上げてきた。
この「Hallucination」では、ハードロックやヘヴィ・メタルを連想させる曲は皆無。
強いて言えば、最もハードなエッジが装填された、#1『My Hallucination』がハードロック“っぽい”チューンかもしれないがこれとて、コテコテなハードサウンドとは程遠い。少しハードなロックナンバーという方が相応しい位だ。
ハードなギターサウンドと同時にアクースティックでアーシーなギターがオーヴァーダブされている。
そう、この「Hallucination」はハードロックやプログレッシヴロックの旗手だった男達が、アクースティックな弦音と土臭いカントリーサウンド、そしてアダルトなPop/Rockを主眼に置いて作成した番外編的アルバム。多少ネガティヴな表現を利用するなら鬼子的なレコードである。
Firehouseがアクースティックに特化したアンプラグド風再レコーディングベスト盤たる「Good Acoustic」を1996年に発表しているが、肌合いとしてはこういうタイプに近いか。
まあ、完全にアンプラグド作品ではないし、曲もこのライターデュオのオリジナルを収録したもので、過去のバンドからのトラックをアレンジしなおして収録という再燃は行っていないし。
それよりも、やはりアメリカンルーツたるカントリーロックにより色濃い影響を感じてしまう。
サザンロック、ハートランドロック、西海岸ロックという、メインストリーム街道まっしぐらの産業ロックやポップメタルとは対極の地域性を反映した音楽にのめり込んでいる印象が強い。
使われている楽器もルーツ楽器が多く、Tommy Shawはスライドギター、ペダルスティール、マンドリン、ドブロギターと、エレキとアクースティックギターを筆頭にしつつもかなり数の多い土臭い音を出す弦楽器を演奏している。
この楽器を見るだけで、ハードロックとは縁遠いアルバムということが分かるとは思う。
「僕達はBeatlesの大マニアなんだ。多くのビートルズナンバーでは、1本か2本のギターに後はタンバリンとシェイカーとボンゴだけってパターンが見られる。だからこう思ったのさ、Beatlesに十分なアレンジだったら、どうして僕達がそれで十分ではないなんてことがあるだろうかって。
実のところ、このアルバムの11曲の殆どがLennon=McCartneyのアレンジからインスピレーションを得たことで編曲されているよ。」
とJackはBeatlesの影響を特にアレンジ面で強調しているが、このアルバムを聴くと、Bob DylanやTom Petty、そしてByrdsの影を感じずにはいられない。
少なくともメロディメイキングでは英国ポップスよりもアメリカンなカントリーロックや南部ロックをベースにしていると思うのだ。
また、演奏のシンプルさという点に於いても、ギター1本とパーカッションだけというような完全アンプラグドスタイルの曲は皆目。しっかりと時代性を反映した形の各種のギターを始めとする楽器のアンサンブルが丁寧に織り込まれたサウンド・コラージュが完成している。
そう、確かにアメリカンなルーツロックの一種ではあるけれども、それはそれとして、メインストリームの第一線に長くあったソングライターが手掛け、R.E.M.やJohn Mellenchamp、Hootie And The Blowfishといったアルバムのプロデューサーを歴任してきたDon Gehmanが共同プロデュースを行っているためか、悪い意味でも良い意味でもインディらしいラフで未完成さの残る荒っぽさは無い。
かといって、ハードロックの硬く激しいエッジから離れたとはいえ、妙にフ抜けたサウンドに萎んでしまっているのでもないのだ。
要するに、非常にメジャーなPop/Rock指向の強い、丁寧に創られたアクースティックでアーシーなヴォーカルロックのアルバムなのである。この時点、1995年でもミュージシャンとしての活動歴はかなり長いヴェテラン・コンビの円熟味がサウンドにも反映していると言ってよい。
「真実、金を掛けないアルバムだったね。Don Gehmanが『Tommy、オルガンをここで弾いてくれ。』って指示してくるんだけど、僕は遅かれ早かれオルガニストを雇えばイイや、って思ってオルガンを弾かなかった。結局、オルガン弾きは加わらず、僕がキーボードを入れたんだけど。
普遍的な時代性を感じさせない音を出すために、ヴィンテージな楽器も使った。ベースは1952年のもの。レス・ポールは70年代製を使ったよ。アクースティックギターにはギブソンという具合。
最後には2インチのテープマシンを引っ張り出してきて録音に使用した。古い機材で古い音楽をって感じかな。」
Shaw/Bladesはこのようには述べているけれど、しっかりとメジャー感覚は息づいている。録音レヴェルに関しては確かに1995年という時代を考えるとやや音のレートが低く感じられるが、アナログ録音とは程遠いクリアな音質が出ているし。
やはり、Shaw/Bladesの基本はメジャーな音創りにあると知れる。
そのメジャーなハードドライヴ感覚がスライドギターでバリバリに走るのが#1『My Hallucination』。元Journeyのライオン・ドラマーなSteve Smithの芸術的ともいえる堅実の極限まで磨き上げたドラミングに乗っかって、Tommy ShawとJack Bladesのダブル・ヴォーカルが飛び込んでくれば、もう説明の必要は無いだろう。
ハモンドB3のサンプリング鍵盤まで取り入れられてかなり厚目のロックナンバーになっているけれど、スライドギターの泥臭い音色とアクースティックさがこの曲に絶妙なエレクトリックとアクースティックのバランスを付与している。
「レノンは死んだ。」「のっぽのサリー」というBeatlesフリークの2人の趣味が露出した歌詞もエキセントリックだったりする。
アルバムからの唯一の、そしてファーストシングルとなったのが#2『I’ll Always Be With You』だ。このナンバーはTom PettyやJohn Mellencampを思わず連想させるくらい、アクースティックでアダルトなPop/Rockになっている。
ファーストヴァースをJack Blades、セカンドヴァースにTommy Shawの鼻に詰まったようなハイトーン・ヴォイスを入れる構成も面白い。
このナンバーではTommyがドブロギターやマンドリンを弾いて、思いっきり土臭いサザン・ポップ風の味わいを出しているのが、Styx時代の名曲『Boat On The River』を想い起こさせたりする。筆者のこのアルバムでのお気に入りナンバーの1つでもある。
#3『Come To Be My Friends』はこれまたスライドギターが活躍するブルージーなオープニングリフから始まり、ハードなブギーロックに流れ込んでいくというLynard Skynardのような南部サウンドを確固として掌に掴んでいる曲。多少ダークでスローなブギー調子はこのデュオが演奏するとはかなり意外だったりした。
しかし、Tommyがリードを引っ張る#6『Blue Continental』では完全なスローブルースを見せてくれる。Tommyはこの曲を「霊歌のように歌った」と述べているが、確かにゴスペル・サウンドの影響を匂わせるバラードでもある。
#4『Don’t Talk To Me Anymore』はシンセサイザーとパーカッシヴなドラムをフューチャーしたビートナンバーが基本だけれども、そこはかとなくエスニックというかワールドミュージックのミステリアスさが漂うバラードになっている。
Adult Contemporaryなバラードに最終的には仕上げているけれども、無国籍差を感じさせるリズムが耳に残って離れない。
#5『I Scumble In』は非常にオーソドックスで、このアルバムでは最も快活なロックナンバーだろう。スライドギターを始めとして何本かのギターが重ねられているようだが、分厚いというよりもこれは安定感のあるルーツロックナンバーと評するべきだ。ポップなフックとスライドな重さがブレンドされたヒット性の高いナンバーでもあるので、#2がヒットしたならもしかしたらシングルになった可能性もありそうだ。
同じロックナンバーでも#8『How You Gonna Get Used To This』はメロディで考えればハードロックバンドの無機質さを残した曲だ。#1よりももしかするとハードで重いかもしれないが、如何せんやや印象が弱い。アクースティックや土臭いアレンジが欠如しているためだと思っているが。
よりカントリーロックやフォークロックを直接に表わしたのが以下の2曲だ。
#7『Down That Highway』ではペダルスティールがいきなり流れてくる、完全にウエスタン・カントリー調子の曲。ここではTommy Shawの弾くアクースティックスライドギターのソロが聴ける。
しかし、ここまでベタなカントリーメロディを演奏しているが、TommyとJackのリッチなヴォーカルのためか、奇妙にカントリー臭さが出ないナンバーでもあるのだ。ここでバスやテノールの男性ヴォーカルが歌ってしまうと単なるカントリーに下落してしまうのだが、優しいハーモニーが活きた、ザクザクした気持ちの良いトーンが楽しめる。
対して#10『The Night Goes On』はTommy曰く「ほぼ100%アクースティック楽器で演奏した唯一のナンバー」からも推し量れるようにBob Dylanのフォークロックにインスパイアされただろう曲。マンドリンやドブロギターがここでも繊細に使用されている。
後半2曲は綺麗なバラードが揃っている。
#10『I Can’t Live Without You』ではくぐもったキーボードがじわじわと侵食していく朝焼けの光のようにメロディを盛り上げている。Rod Stweart等を引き合いに出して解説したくなりそうなさりげない土の香りが漂うマイルドなロックバラードとなっている。前半はルーツィなロック調子、後半は産業ロックバラードにジャンプアップという構成になっている。
最後はシンセサイザーを加えたアクースティックな小曲の#11『This Is The End』。2分足らずのアウトロ的なナンバーだが、ここではTommyだけでなくJackもアクースティックギターを持ってデュエットしている。もう少し長く聴きたくなるしっとりとしたナンバーだ。
この尻2曲でのノスタルジックでクラッシックなキーボードの使い方はなかなかツボを得ていて巧みと評価せざるを得ない。自らはあまり鍵盤を弾くことは無かったが、流石にパーマネント鍵盤プレイヤーが在籍するバンドに長年所属していたミュージシャンの経験が活用されている、というところだろうか。
結局、このアルバムは全く売れなかったし、この後もShaw/BladesはAerosmith等に曲を提供するに留まり、次のアルバムを出すことは現在までには至っていない。
折りしも1990年代後半にはお互いが古巣のNight RangerとStyxの再結成に関わったためか、自然とこのデュオも動きが鈍ってしまった様子でもある。新生Styxのダメダメアルバムである「Brave The New World」(1999年)ではJackがTommyと共作しているところが見られたりしたが、Journeyの「Arrival」(2001年)ではJack BladesがTommyとではなく、Journeyのメンバーと曲を書いているという事実も明るみに出ている。
2000年頃にDamn Yankeesとして再出発して3枚目のアルバムをレコーディングしたのだが、契約先が見つからずにアルバムはお蔵入り、プロジェクトも再び分解してしまったという情報も流れたりした。
と、ハードロックの住人にはあまり芳しくない音楽業界の情勢が続いているためか、ShawとBladesの動きも不活発だ。こういう時こそ、このようなバック・トゥ・ザ・ルーツ的なアルバムが求められているように感じる。
是非、この作風でもう一度アルバムを作成して貰いたいと、「Hallucination」を聴くたびに思うのだ。
ハードロックファンにはいまいち受けの悪かった本作だけれども、ルーツロックやPop/Rock、スライドギター好きにはかなりストライクになることは請け合い。
Joey TempestのEurope時代とソロの「A Place To Call Home」の音楽性ほどの差が、Shaw/ Bladesと彼等の元バンドにあると言い換えれば、理解しやすいと考えている。
EuropeよりもJoeyのソロが良いというリスナーは是非探して聴いてみて欲しい。 (2003.3.9.)

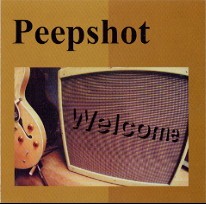 Welcome / Peepshot (1999)
Welcome / Peepshot (1999)