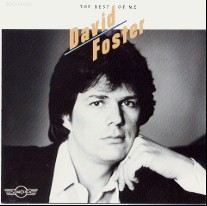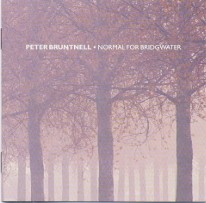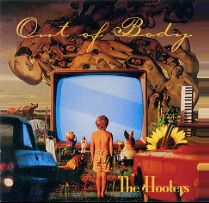 Out Of Body / The Hooters (1993)
Out Of Body / The Hooters (1993)
Roots ★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Arena ☆
◆1993年、発売当初一番好きだった曲は
Hootersのメジャー作3枚目としてColumbia Recordsから発売された、前作の「Zig Zag」。それから4年を経て、本作「Out Of Body」は発表されている。
発売当時、筆者はカナダに居住中だったのだが、一撃でトップバッターである1曲目の『Twenty-Five Hours A Day』にノックアウトされてしまった。
まず、何を置いてもHooters、というバンドの“顔”の1枚であるマンドリンの楽しげなリフが弾け飛ぶオープニング。
即座にフォローに迸る、これまたEric Bazilianが弾きまくるエレクトリックギターと、Rob Hymanのハモンド・オルガン。
Hootersの歴代の曲では最もキャッチーでハードドライヴなロックナンバーだ。ポップさではこれまでの3枚のアルバムのOPナンバーも縦一直線には並んでいるが、この#1『Out Of Body』程斬新な展開を見せている曲は無い。
これまでのHootersとは違う、The Hootersの意気込みが伝わってくる曲になっている。
まず、このアルバムからメンバーとなった女性ヴァイオリニストであるMindy Jostynの女性バックコーラスが、コーラスの尻で、間奏の前で些か調子の外れたソロシャウトを何度も叫び、独特の色合いを曲に加えている。それ以前に、Hootersの特徴である多重バックコーラスに加わり、これまで男性のみで構築されていたハーモニーコーラス部分に新しい息吹を叩き込んでいる。
そして何よりも特異なラインを著しているのは、インタープレイのモロにケルティックな演奏だ。
Mindyのヴァイオリンに、Robのアコーディオン、そしてEricのアイリッシュ・リコーダー(プロモーションビデオではオカリナのようなゲール系の笛を吹いている。)の欧州フェスティバル曲を、それもトラディショナル全開な空気でお気楽に振り回してくれる。
このケルティックな明るさに心弾まないリスナーは少ないだろう。
やや低音域を強調して歌うRob Hymanのこれまでとは一風変わったヴォーカルも、この曲では全体に調和しているので、違和感よりも太くなった頑丈さが目立つ。
そして、これまたHooters以外の何物でもない、David Uosikkinenの決して派手さは見せないが、超絶に技巧派なドラミングと、Fran Smith Jr.のベースの堅実さが曲を支えている。
ハモンドオルガンを更に周囲から際立たせる効果を発揮しているシンセサイザーのノイズも決して曲を必要以上に厚化粧せず、適度な重みを載せるのみだ。
まさに、伊達にこれまでのリリース間隔の倍、4年間を空けたのではない、という自信が見れる最高に吸引力のあるナンバーだ。当然真っ先に好きになり、今でも好きである。
その次に続く、#2『Boys Will Be Boys』。
これまた、1回聴けば忘れられなくなるアンフォゲッタブル・ナンバーであり、これまでの3枚のHootersとは異なったイメージを与えるトラックでもある。
♪「And We'll All Go Together
To Pull Wild Mountain Thyme
All Around The Blooming Heather
Will You Go , Lassie , Go?」
と日本ではあまり知名度が高くないが、Roger McGuinnやThe Byrdsのカヴァーを筆頭に数多くのアーティストが歌っている、スコットランド民謡のラヴ・ソング、『Wild Mountain Time』のコーラス部分といえば、分かる人には分かるし、別名である『Will You Go Lassie Go』の方が海外では通りが良い。
歌詞自体も取り上げるシンガーによって、細かい変更が加えられており、このHootersレコーディングヴァージョンもオリジナルの詩とは少々異なっている。
1957年にバグパイプ奏者のFrancis McPeakeがテレビシリーズのBGMとしてレコーディングしたのが切っ掛けとなり広まったトラッドソングだ。
と薀蓄はこの位にして、この歌のコーラス部分を些か小さ過ぎるヴォーカルSEとしてイントロに入れている#2『Boys Will Be Boys』。
これまでのHootersとはこれまた一味違うが、反面Hootersらしさもしっかりと包括しているナンバーである。
#1に続き、またも英国の要素を取り入れているのが特徴だし、常以上にラブな演奏が#1と共通してもいる。このあたりが一味違う。
また、新加入となったMindyのヴァイオリン(フィドルではない)を中心に何処と無く大陸的な広大さを終始ストリングスアレンジメントを窓口にして放出しているロックナンバーでもある。
が、それ以上に特筆すべきはCyndi Lauperがゲストヴォーカルとして、ダブルハーモニーだけでなく、ソロパートまで唄いまくっている事だろう。
Cyndiのデビュー盤にして最大のヒット作となっている「She's So Unusual」(1984年)にHootersのRobとEricがエンジニアとして、バックバンドとして、そしてソングライターとしてHootersの長年のパートナーだったRick Chertoffと共に参加していたのは有名だし、RobとCyndiの共同作である『Time After Time』が全米No.1ヒットとなったのも今更なお話だ。
そのCyndiが初めてHootersのアルバムに参加したのが#2なのだ。しかもソングライターとしてもお返しとばかりにRobアンドEricのコンビと一緒に曲も書いているのだ。
Cyndiの一度聴けば即分かってしまうヴォイスがハーモニーパートではMindyのヴォーカルと重なってしまうため、やや聴き取り辛いが、コーラス部分で自己主張をすると、すぐに個性が浮き彫りになるのも微笑ましい。
実にダイナミックなポップロックナンバーであり、『Satellite』のストレートさと『Karla With A K』のトラッド且つ大らかな面を同時に備えている曲だと思う。
これまた即効性抜群で、1回聴くと忘れられなくなる。こういったポップさはやはりHootersの看板に偽り無しだと認めさせてくれる。
このスタート2曲のインパクトは、アルバム冒頭の2連コンボがどれもハイ・レヴェルなHootersの各アルバムと並べても何ら遜色は無い。
やはりアルバムを最初に聴けば印象に残ってしまうのがこの2曲、というのが最も一般的な反応だと思う。
◆聴き込むに従って好きになった曲は
筆頭は、#5『Private Emotion』だ。この「Out Of Body」では唯一のメジャーコードなバラード、と言い切って良いと思う。
当初は『Beat Up Guitar』や『Where Do The Children Go』といったHootersの代表的なバラードと比較すると、少々線が細くてパンチが弱いバラードだと思っていた。が、筆者自身が加齢するに従って(苦笑)、その曲の持つセンチメンタルでリリカルな良さが理解できるようになったためか、マンドリンで切々と奏でられるメロディが胸に沁みる様になった。
同じく、スローナンバータイプの#3『Shadow Of Jesus』。
かなりHootersにしては珍しいサイケディリック且つマイナーコードな曲だ。微妙に音程を外したようなEricのヴォーカルが更にコードをウネウネと変調させる効果を発揮している。
ヴァイオリンだけでなく、サイケに尖がるストリングス弦の活用が独特でもある。オープニングリフでギターではなく弦楽器の重奏でドラマティカルなメジャーバラードに上昇するかな、と予想させておき、ブルースハープとギターのオドロオドロしいソロプレイでバラバラなアンマッチ感を早くも出す。
このマイナー感覚は、ファースト作から最初にシングルカットされ、ある意味Hootersに対する誤った認識を一般リスナーに広く植え付けた『All You Zombies』のシンセサイザーを過剰アレンジしたプログレッシヴな空気が漂う所にソックリでもある。
が、80年代シンセサイザー曲のナード側代表とも云うべき『All You Zombies』と比較するとアレンジは多彩で、分厚い。産業ロックの残り香を漂わせたナンバーとも云えるのでは。
何よりも、鍵盤ハーモニカであるフーターを使用せずに、単なるハーモニカでベント感を演出する手法は、このメジャーコードとマイナーラインが複雑怪奇に絡まったメロディよりも意外に思える。
が、何故か聴けば聴く程に麻薬のように耳に残るナンバーなのだ。こういったエキセントリックなタイプの曲は取っ掛かりで一定レヴェルのキャッチーさが存在すると、不思議と肌身離せなくなる事が起こるが、これはまさにそれである。
他にも好きになってきた曲を挙げると殆ど全部になってしまう。が、即効性よりもジワジワと筆者の感性を侵食してきた曲が、購入から10年を経て出現している。それが・・・
◆2003年現在のベストナンバー
#1や#2のような即効性にはやや欠け、#3のような毒とアクの強さも無し。#5のように美しさで勝負するタイプの曲でもない。元来Pop/Rockなナンバーなので良質ではあるけれど、目立たない曲。
筆者としては、この条件を満たすのが
#4『Great Big American Car』
#6『Driftin' Away』 の2トラックである。
まず、#4『Great Big American Car』は、前作の最もルーツ色が強かったアルバム「Zig Zag」の印象を吹き飛ばすようなシンセサイザーのインダストリアルな鍵盤リフから始まる。
しかもキーボードのリフに続いて、ハモンドオルガンのバッキング、そしてシンセオルガンのひと撫で演奏が続き、メインヴァースではピアノの正確なリズムが刻まれるという、かなりコッテリした鍵盤ロックナンバーを予感させる出発だ。
マンドリンやギターも主役に昇格しようと頑張るが、やはりメインの鍵を握るのはRobの弾くハモンドオルガンのリードラインと、リズムプレイにドラムのように徹するピアノ、そして裏方に廻りつつも曲に華を添えるシンセサイザー類だ。
ルーツさやアクースティックの度合いは「Zig Zag」には及ぶべくも無いが、ハモンドオルガンの引っ張りとマンドリンが土臭さを補ってくれている。
分厚いコーラスと豪快な演奏を支えるのは、常に無い多種多様な楽器のクロスオーヴァーだろう。オルガンやシンセサイザーのノイズが微妙なアリーナ風の浮遊感を付与しているが、アメリカンロックとしては良質。
目立たない、アルバムトラックなのだけれど、ここ数年で何故か最も好きになったナンバーだ。EricとRobのダブルリードヴォーカルも馬力がある。
次の#6『Driftin' Away』も、同様のアルバム用バランストラックの性格を帯びたミディアムで地味なナンバーだ。
こちらは冒頭からEricのマンドリンが炸裂、という程強烈ではないけれど、まさにこれぞメジャーシーンのマンドリンバンドたるHootersの看板と叫びたくなるマンドリンがポロポロとギターラインを彩っている。
隠し味的なアクースティックギターとメロトロンのフニャっとした音色がルーツ感を増量させてもいる。
そしてかなり低音に押さえたEricのヴォーカルに少々、今作特有のヴォーカルアレンジに対する共通項となる違和感を覚えてくる矢先に、しっかりHootersコーラスが女性ヴォーカルたるMindyを加えて登場する。
また、Robのウィルツァーピアノが相当メカニカルな音を出しているのに、ギターとマンドリンの活躍でかなり土臭い曲になっているのが特徴。
そして全体を締めているのが、Davidの素晴らしいスティック捌きであることが、フェイドアウト前のパーカッシヴなドラミングで理解できるだろう。Mindyのア・ド・リブなソロシャウトと恬淡としたスティックの叩きによるデュエットがえも云わぬ余韻を残してくれる。
Ericがヴォーカルに手を加え過ぎ、というか弄り過ぎな傾向が所々見受けられるが、それを補って余るアクセントのあるメロディと展開。
産業ロックとルーツロックが不恰好だがユニークに同居した、アメリカンロックの旨みを堪能できるナンバーだと考えている。
これまた何故か、コーラスを口ずさんでいるうちに一番好きになってしまったのだ。
◆荒っぽく未整理なんだけど、そこから奥行きが少ない
これまでで、幾度か軽く触れてきたが、このメジャー4作目に当たる「Out Of Body」。Hootersらしさはそれなり以上に自己主張しているのだが、それ以上に新しい試みが目に付く。
今までの3枚のアルバムでも、それぞれ異なったカラーを出してきたHootersだが、キャッチーで親しみ易い曲創り、マンドリンやメロディカといったルーツ楽器を活用したトラッド音楽への敬意、特別に優れた声質ではないけど等身大に感情移入できるEricとRobの2枚ヴォーカリストの歌。
丁寧にスタジオでアレンジされたプロデュース。
とこれらは大小の振れはあるとはいえ、共通していた。
そのベースを踏まえて、1枚目の「Nervous Night」は当節流行のポップな産業ロックへ歩み寄りを見せ、2作目の「One Way Home」ではよりアメリカントラッドとソリッドなロックを目指す。3作目の「Zig Zag」ではアクースティックとルーツロックへの憧憬を余さず表現していた。
そしてこの4枚目なのだが、筆者が見るに、欧州トラッドへの傾倒が見える。が、これは巧みに本来のHootersのカラーに融合して何ら違和感を見せない。
それよりも演奏自体のアレンジがかなり荒っぽく、未整理な点が際立っている。
例えば、#7『Dancing On The Edge』や#8『All Around The Place』は相当ルーズなパフォーマンスがライヴ録音をしたのではと勘ぐらせる位、ラフに暴れている。
#7は恐らくHootersでは最もハードドライヴなロックナンバーだろう。これはこれで悪くないのだが、丁寧さを故意に排出したかのようなアレンジには若干の違和感を覚えたりするのだ。
#8はハードながらルーツィでメロディ的には好みなのだが、駄目な点がある。(後述)
が、ハードで荒っぽいからとはいえ、シンプルなアレンジメントで纏まっているかというと、そうでもないのだ。
キーボードを中心として相当数のサンプリングが曲に絡められ、ヴァイオリン弾きが加わったため、更に弦楽器が厚くなっているのだ。恐らく使用楽器としては最大の分量になっているだろう。
このため、「Zig Zag」での優しくダウン・トゥ・アースなルーツ色は薄くなり、初期のアリーナサウンドの重ね着的な多層さを持った太い演奏でどの曲も仕上げられている。
これはこれで良いと思う。少し繊細で手をかけ過ぎな面が、ライヴバンドな割にはスタジオワークが好きなリーダー2人に率いられたHootersの面白い顔だったので、その枠を敢えて外したとも考えられる。
が、これだけ楽器を新規につぎ込むなら、一見ラフだが、丁寧なサウンドのコラージュを行った方がアルバムとして完成度が格段に上昇したのではないかと愚考している。
事実ソリッドなロックサウンドと産業ロック的な先進性、そしてトラッドカラーを同居させた「One Way Home」では外見ラフだが実は織り込み方が緻密なアレンジを成功させているのだ。
「One Way Home」よりも骨太で大仰な展開が多い「Out Of Body」では、奔馬の如く走る疾走感覚よりも、隙間の多い未完成さが鼻につく場面があるのだ。
やはり、これはプロデューサーという立場を超えて、長年"6人目のHooters"といった地位にあったプロデューサーのRickとの決別が響いているのだろう。
ZZ TopやSteve Earle、Tom Corchrane等のプロデューサーを歴任したJoe HardyとRob&Ericの共同プロデュースは選択として誤りではなかったが、Hootersらしさを完全に引き出すことができなかったと云わざるを得ない。
それでも標準以上のアルバムになってしまうところがこのバンドの才能なのだが・・・・。
◆ヴォーカルアレンジが致命的 勿体無さ過ぎ
特に後半の#8『All Around The Place』と#10『Nobody But You』でのヴォーカルのアレンジが正直気色悪い。
#8は前述したが、酔っ払いのマンドリンに、Davidの馬力満タンなドラム、Robのアコーディオン、そしてファンキーなラインと、筆者のお気に入りな要素は全て備えている。しかもゴージャスなメンフィス・ホーン付きとなれば垂涎モノなのだ。
が、このRobのラップっぽい作ったようなバスヴォーカルがかなり気色悪いこと夥しい。これさえなければ、物凄いお気に入りのナンバーになるのだが、よって普通以上の曲という評価しか与えられない。
#10もホーンセクションが活躍し、マンドリンとギターがアーシーにポップに転がる良好なロックチューンなのだ。がしかし、これまた今度はEricのヴォーカルが気持ち良くない。気持ちの悪さでは#8のRobを上回る酷さ。これがHootersとは思えない位でもあったりする。
この2曲は実に勿体無い。これさえマトモなヴォーカルで締めていてくれたら、このアルバムの平均点は20点上がるだろう。Hootersの4作中でクセはあるが不思議な吸引力のある名盤にのし上がっていた可能性が大だ。
この2曲のアクの強い雰囲気にサンドイッチされたため、切ないメロディを持ったアップビートな#9『One Too Many Night』がすっかり霞んでしまっているのも残念。
「Out Of Body」ではたった2曲しかフーターが使用されていないのもマイナスになりかねない特徴だが、この#9ではしっかり鍵盤ハーモニカが使われている。しかもハモンドオルガンのソロは、ルーツィで最高に破壊力があるのだ。
◆結局、惜しいアルバム
良作ではあるのだが、一部のヴォーカル処理によって、どうも凸凹したアルバムになってしまった残念作。
これが全ての印象だ。
前作「Zig Zag」が良過ぎたルーツ作だったという事もあるが、この4枚目もルーツロックをしっかりと感じられる1枚という事には偽り無しだ。
寧ろ1st作よりも即効性で劣る分、ジワジワと噛み締めるタイプの曲が多いため、長く聴けるアルバムだと思う。
が、まさかこの1枚でHootersのスタジオ盤が停止するとは当時思いをだにしなった。
この後リリースされた「Live In Germany」にて2曲の物凄いアーシーで素朴なカヴァー曲を聴かせてくれた時は、
「すわ、次の5枚目は最高のルーツロックアルバムになるかも」と胸を膨らませたものだ、期待で。
しかし、2003年夏、Hootersは独逸で久方ぶりのライヴツアーを敢行。
EricとRobもニューアルバムに対してポジティヴなコメントを表明している。
10年を置いた新作が出るのか出ないのか、それ以前にこのツアーは短期結成なのか、とHooters関連の話題が久々に盛り上がり出している。暫し、座して静観してみるつもりだ。
なお、日本盤にのみ#11『Strange Strange World』というボーナストラックが収録されている。
まあ、ボーナストラックの“常”を上回れないナンバーといっておこう。
このアルバムは廃盤なため、もし見つけたら手に入れておくことをお薦めだ。1000円以下で見ることも結構ある。
これまた喜んで良いのか、悲しんで良いのか・・・・。 (2003.7.1.)
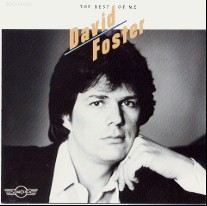 The Best Of Me / David Foster (1985)
The Best Of Me / David Foster (1985)
Adult-Contemporary ★★★★★
Pop ★★★★★
Rock ★
New Age ★★★★★
◆Airplay、Skylark、Attitudesを聴きながら
David Fosterのソロ2作目、「The Best Of Me」のレヴューを書くにあたり、このソロアルバムを出す前の、Davidの音に興味を持ってしまった。
ここでは個別の彼が関係したプロジェクトやバンドの感想には触れない事にしておく。いずれ、別の機会に書くこともあるだろうから。
で、まずは手持ちのAirplayの「Airplay」をかなり聴いてみた。
次に、2曲のボーナストラック入りで再発されたSkylarkの「Skylark」を聴いてみた。タイトルは「Wildflower A Golden Classics」で日本盤も出ているらしいが、良く知らない。
それから、学生時代にAORマニアからダビングして貰った、Attitudesのシングル『Sweet Slimmer Music』をテープの廃品置場から掘り起こして聴いてみた。が、テープが延びてしまい音程が完全に狂っていたのは残念。
更に、AirplayでのパートナーであるJay Graydonと一緒に作成したバンドプロジェクトであるPegasusuの同名アルバムと、The Bottom Lineの「Crazy Dancin’」が日本盤のみで再発されていると知って、驚き。
海外でLPを少し聴かせて貰ったことがあるけれど、基本的にインストゥルメンタル系のフュージョンやプログレッシヴ風のアルバムであり、まずCD化なんぞされないと思っていたからだ。
流石にAOR(Album Rock)の再発王国。世界中のAORマニアが涎を垂らして羨ましがるメッカの日本だけの事はあるとしみじみ思い知った。
この調子なら、Danny KorchmerやJim Keltnerと結成した隠れたスーパーバンドであるAttitudesの2枚のアルバムも直にデジタル音源化されそうな予感までしてくる。
◆今更、AORの定義
それにしても、筆者が言うのもなんだが、AORの真性フォロワー諸氏のマニアックさ、ディープさにはとても敵わないものを感じてしまう。
ルーツロックやアメリカーナ等と異なり、長い年月を経て形成されたファン層のネットワークと熱意と組織力は空恐ろしいものを覚えるのだ。とても、個人サイトの管理人が追従できるレヴェルではないことを痛感した。
筆者も“AOR”ブームのピークより少し後の年齢層に属するとはいえ、かなりAORは好きである。ここでいうAORとは日本でのAORの解釈に基づいた音楽であり、Pop/Rockから産業ロックやハートランドロック、アダルトロックを広く網羅する米国でのAlbum Rockとは少々ズレのあるジャンルになっている。
嗚呼、ややこしい。
欧州ではメロディアス・ハードロックやハードロックにAORという名称が頻繁に使用されるし、そもそもAdult Oriented Rockという単語は、Album Oriented Rockが何時の間にか変化したものらしい。
米国ではAdult Contemporary Musicという大きな枠に全て括られてしまっている。
筆者の解釈としては、日本で言うAORは、よりソフトな西海岸系のポップスやジャズロック、フュージョンロック、アクースティックサウンドに偏らないシンガーソングライターのアルバムといったサウンドを中心に、ロックに寄りかかり過ぎていないAdult ContemporaryなジャンルをAORと区別している様子だ。
◆日本発売のみの「The Best Of Me」とそれ以前の音源
話がかなり脱線したが、筆者が実行した事其の壱は、David Fosterの1985年に発売されたこの「The Best Of Me」以前の音をおさらいした事である。
これ以前には、David Fosterのソロ名義のフルアルバムは1枚も無い。
1982年に「Songwriters For The Stars」という5曲入りのミニアルバムを発表しているが、このアルバムはBozz ScaggsやE,W&Fire等に提供したヒットナンバーを集めて再レコーディングした焼き直し盤。
オリジナルの曲を寄せ集めたベスト盤ではなく、スウェーデンのレーベルによって、Fosterのピアノと北欧の無名シンガーによってライヴレコーディングされた5曲入りのアルバムだ。
また、発売は本作の後、1988年になってしまったのだが、録音自体は1981年に行われている「The Symphony Sessions」も存在する。(邦題が確か「ピアノ・コンツェルト」だったような気がする。)
そして、本作「The Best Of Me」は日本のレコーディング会社で作成された、日本限定盤だったりする。が配給先はPolydor Recordsなので、欧州では発売されている様子だが。母国であるカナダでも輸入され、1985年に発売されたらしい
彼のオフィシャルサイトでは発売が1985年となっているのもそのためだろう。日本では1984年にCDとしてリリースされている。邦題は「君にすべてを」。
だからして、米国ではDavid Fosterのデビューアルバムは1986年の「David Foster」になる。
よって、アルバム順から見ればイレギュラーな1枚かもしれないが、反面貴重な1作でもあると思う。というのは、実質スタジオレコーディングのソロ作としては、この「The Best Of Me」がFosterの処女作となるからだ。
これ以前のリーダー的アルバム−Jay GraydonやDanny Korchmerとの共同作−が体裁としてはアダルトロックだったのに比べ、この「The Best Of Me」は1980年代前半にDavidが深くコミットしていたグループやアーティストの音楽性を反映したものになっている。
つまり、美しさを表面に押し出した、New Age系のインストゥルメンタル・アルバムになっているのだ。
◆特に連想してしまうのは、やはりChicago
一時期、セールス的に大低迷に陥り、Robert Lammに言わせれば「腐る寸前」だったChicagoを再びヒットチャートの常連に持ち上げる手助けをしたのが、David Fosterである事は1980年代ポップロックのファンなら今更説明するまでもないと思う。
“商業主義”、”売れ筋追及”といった批判も存在するけれど、迷走していたChicagoのサウンドをアダルト・コンテンポラリーのバラード主体なソフトな音に修正し、ソングライターとしても積極的に参加し、結果として第2の黄金時代を築いた功績は大きいだろう。
例えば、Chicagoの「16」でのヒットシングル、『Hard To Say I’m Sorry』、『Love Me Tomorrow』、『Waiting For You To Decide』には全てFosterがライターとして登録されている。
アルバムとしても大ヒットとなった「17」では『Stay The Night』、『You’re The Inspiration』をPeter Ceteraと共作している。
チャート的にはやや低迷した「18」でも大ヒットの“Fosterバラード”である『Will You Still Love Me』を提供。
まさに、ソフトロック/アダルト・コンテンポラリーの顔となっていたChicagoの好調を支えていたのが、「The Best Of Me」を発表した頃のDavidだったのだ。
また、直接のクレジットはされていないが、80年代前半のトップAORバンドの1つであったTotoのアルバムにも、メンバー達との交流を踏まえてかなりコミットしている。
当時のTotoの正規メンバーだったSteve Porcaroがシンセサイザー・プログラミングで参加もしている。
他には、フェンダーロウズでTom Keane。知る人ぞ知る、アダルトコンテンポラリーやAORのプロデューサー兼ミュージシャンである。
そしてJay Graydon。彼については説明は必要ないだろう。Steely Danの演奏メンバーとして選ばれた事で、一躍評価を得たエピソードは有名だ。
更に、数年後にソロアーティストとして大ヒットをかっ飛ばす、Richard Marxと、Mr.MisterのRichard Pageが2曲のヴォーカルナンバーでバックヴォーカルに顔を見せている。MarxはChicagoの「17」にバックヴォーカルとしてクレジットされているので、そちらの繋がりか、Davidが参加していたLionel Richieのアルバムにバックヴォーカルとして長期レコーディングスタッフだった関連からの縁だろうか。
Richard PageについてはPages時代からのL.A.ポップスシーンでの人脈だろうか。
以上のように、実に豪華−一般にはあまり知名度が高くないかもしれないが−なバックメンバーによって演奏をサポートして貰っている。無論メインのピアノやシンセサイザー類はDavid Fosterが殆ど担当しているが。
◆ヴォーカル曲としてヒットしたナンバーのインストゥルメンタル
このアルバムには、Fosterがライターとして提供した大ヒット曲のインストヴァージョンが何曲か見られる。
例えば、#1『Whatever We Imagine』はJames Ingrahmが1983年にFosterのキーボードをバックに唄っている。
#7『Mornin’』も同じく1983年にAl Jarreauが、これまたFosterの演奏とアレンジで唄っている。
そして#8『Love,Look What You’ve Done To Me』はBozz Scaggsが1980年にヒットさせている。
これら3曲はオリジナルのヴォーカルヴァージョンから、声をオフトラックした言わばカラオケ・ヴァージョンであるが、単独のインストナンバーとしても十分に鑑賞に耐えれる美しさがある。
特に、フェンダーロウズ特有のディレイ気味な音響が印象的な#1は、軽快なピアノのリズムが心地良く、とてもブラックコンテンポラリーのシンガーに提供された曲とは思えない。
Jay Graydonのギターがスムースジャズ的に滑る#7は、Airplay時代のセンスを感じることが出来る。シンセホーンの使い方やプログラミングの手法も80年代独特の流行が残っていて、今聴くと懐かしいが、決して古臭い感じはしないのが凄い所か。
流石に、#8はBozzの彼しか出せないヴォイスでリードされているインパクトが強過ぎるので、バック楽器のみにしてしまうと、やや弱い。が、ヒット曲らしい落ち着いたバラードの叙情さは十分に堪能できるだろう。
更に例外として#3『Chaka』は『Through The Fire』と改題され、Chaka Karnを始め幾人ものアーティストによってカヴァーされている。
歌詞を付ける際に手を貸したためか、Tom KeaneとCynthia Weilがライターとしてクレジットされているが、こちらのオリジナルヴァージョンではFoster単独の作曲となっている。
◆意外にヴォーカリストとしても上手
常に思うのだが、Fosterはヴォーカリストとしても悪いミュージシャンではないと思う。
このアルバムには1986年にOlivia Newton-Johnとのデュエットヴァージョンとして再レコーディングされ、ヒットを記録する#6『The Best Of Me』。
このソフトなバラードをFosterは独りで歌っているが、決して適当なヴォーカルではない。これ単独でも十分にヒット性がある甘い声だと思う。
また、Vicki Mossとの男女混合デュエットをしている#9『Love At Second Sight』に於いても、Vickiのソウルフルな声に負けず、そして競合しないヴォーカルパフォーマンスを見せてくれる。
FosterのヴォーカルはAirplayやAttitudesでも決してバックヴォーカルに甘んじないレヴェルである事は証明されているのだが、これだけバラード向きの喉をしているのだから、もっと歌っても良いように常日頃から考えているのだが。
この他には1988年に映画“Stealing Home”(邦題:君といた夏)のオリジナルサウンドトラックで、主題歌『And When She Dance』をMarilyn Martinとデュエットしている。筆者はこのナンバーが彼のヴォーカル作品では一番好きである。
また松田聖子と『Every Little Hurt』をデュエットもしていたりする。
どの曲でも女性とのインスタント・デュオが良く填まっているのが凄い。
◆完全オリジナルの4曲はどれもFosterらしい美麗なナンバー
やはり、このアルバムの聴き所は完全にオリジナルのインスト曲4トラックだろう。
#2『Our Romance』、#4『Heart Strings』、#5『The Dancer』、#10『Night Music』。
哀愁漂うピアノ主体の#10。シンセサイザーとピアノによってジワジワと盛り上がりそうで盛り上げない絶妙な力加減で進むが山場はしっかり創る#5。といった具合に派手過ぎない、嫌味にならない程度にストリングスシンセサイザーを使用した傑作が揃っている。
Chicagoとのコラボレーション時は、シンセストリングスや弦楽器を使い過ぎと、その過剰アレンジに嫌味が出たものだが、この程度に抑えてくれると実に聴き易い。疲れないので。
ギターやドラム、そしてベースはあくまで補助的なリズムを演出するに留め、主役はアクースティックピアノとシンセサイザー類。
筆者のお気に入りは、まず#2『Our Romance』。映画音楽を思わせる、音響の拡がりを覚えるナンバーだ。透明感漂う雰囲気からストリングスやギターを交えたクライマックスへと上昇していく過程が宜しい。
優しく、センチメンタルなメロディが終始優しくたゆたう#4も、大作映画のサウンドトラックに入れられて違和感無しなナンバーだ。決して派手さは無いが、無機質ながら美しい都会の朝焼け風景とスカイラインを視覚的に浮かべてしまいそうな雰囲気がある。
◆1990年代後半にリニューアルされたが・・・
このアルバムは、再び1997年頃に再発されている。ジャケットもFosterの顔からピアノのイラストをあしらったものに差し替えられている。
その差し替え自体はどうということはないが、この新ヴァージョンでは『Hard To Say I’m Sorry』がピアノインスト曲として1曲目に加えられた結果、ヴォーカル曲の『Love At Second Sight』が削られている。
ここに、Foster=コンポーザー/アレンジャーとしての見方が強い傾向を感じてしまうのだ。
最近は全くソロの新譜を出さなくなってしまった。1990年代前半までは順当にソロ作をリリースしていたのだが、ベスト盤やコンピレーションの発売に1990年代の大半は終始している。
超の付く売れっ子プロデューサーであり、忙しいのだろうけど、ぼちぼち新譜が欲しい所である。
Airplayのようなヴォーカルロックも歓迎だし、本作のような美しいキーボードアルバムももっと歓迎だ。
ゲストヴォーカルに歌を歌わせるだけのアルバムは正直あまり聴きたくない。David Fosterのオリジナリティが薄れるためだ。
しかし、数曲のゲストヴォーカルナンバーにインスト曲多数という「David Foster」や「The Best Of Me」の形なアルバムならもろ手を挙げて迎え入れたい。
是非新譜を、と叫んで、レヴューを終る。 (2003.7.9.)
 California / Scott Thomas Band (1998)
California / Scott Thomas Band (1998)
Roots ★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Acoustic&Alt-Country ★★★ You Can Listen From Here
◆1990年代の"California"アルバム
殆ど期待せずに、Scott Thomasの2作目「California」を聴いた時、思い浮かんだのがEaglesの「Hotel California」だった。
Eaglesが「Hotel California」で西海岸のみならず世界中を席巻したのが1978年。Scott ThomasがHotelという単語が付かない単なる「California」を発表したのが丁度20年後の1998年。
#1『California』を初めて聴いた時点は、ああ、何て地味な曲なんだろう。オープニングには向かないんじゃなかろうか、と考えた事が懐かしい。
特別キャッチーでも無し、耳に速攻ダイヴしてくるようなロックビートでもない。
アクースティックギターとペダルスティールやドブロギターを中心に固めた、淡い哀愁と陰鬱さを漂わせるこのタイトルトラックは、大した印象にはならなかったのだ。
しかし、何故か何回も聴きたくなる曲だった。この地味でマイナーな土臭いアクースティックナンバーの後が、実に親しみ易いビーチロック風の#2『Black Valentine』であり、その2曲の落差が気持ち良く感じたからかもしれない。
静から動へのポップアップは、筆者がとても好みな曲の配列だからして、聴き込んだ為に耳に居着いて離れなくなった事もあるが。
が、よくよく聴いてみると、何本も重ねられたギター。西海岸カントリーというよりもダークなルーツサウンドの雰囲気を塗したアレンジ。そしてコーラスワークの妙。
メロディ自体のインパクトは及ぶべくも無いのだが、マイナー版『Hotel California』という趣が、このオープニングナンバーに存在するように思えるのだ。マイナーというのは、メロディにしてもアレンジにしてもマイナーであり、全体的な曲調も地味、という複数の意味で使用している。
Eaglesは『Hotel California』で1970年代のアメリカ合衆国が抱える様々な問題をアイロニカルに伝えている。対して、Scott Thomasは"カリフォルニア"を象徴的なシンボルとして掲げつつ、個人の内面が抱える葛藤に付いて歌っている。
"ホテル"という仮想舞台に仮託した手法に、その皮肉なメッセージ性を持ちつつも何処と無く退廃的なゆとりさえ感じるEaglesに比較して、Scott Thomasは現代社会への絶望、夢の崩壊と現実、それによって傷つく内面を描き、より閉じた輪の中での人間を表現していると思う。
オルタナティヴ世代の鬱さを込めている所に、『California』が90年代の西海岸ナンバーであることを納得する。
この2曲の“カリフォルニア”の詩に対するスタンスの差が、1970年代と90年代両方の時代性の相違なのかもしれない。より直接的で自傷的な歌詞を読むとそう感じたりもする。
とはいえ丁度、"カリフォルニア"を含んだ大名盤から20年を経て「California」というタイトルのアルバムが発売されたのは偶然に過ぎないし、たまたまタイトルが共通する物だったので比較対象に出しただけでもあったりして。
如何に、Scott Thomas Bandの親レーベルがEaglesの所属レコード会社だったAsylum Recordsの後身であるAsylum/Electraと同じだったり、タイトル曲が1曲目になっている構成も共通とか、Scott Thomas Bandもメジャーでのデビューが一番の発売てなことを書いてみても、それは蓋然性の羅列に過ぎない。
が、Scott ThomasがBand名義で出した2作目が、まさかここまでルーツやカントリーといったトラディショナル・アメリカンの音楽を視野に入れたまさに西海岸ルーツロック作になるとは思わなかったし、音楽性としてはEaglesを幾許かは連想させるアルバムになったのは、やはり"California"という言葉の魔法かもしれないと、柄にも無く考えてみたりもするのだ。
◆メジャー2作目での変身−これぞ西海岸のバンド!!
あまり知られていないのだが、Scott Thomas Bandはこのアルバムがデビュー作ではない。加えて、インディ盤が先行して発売されているから、数えでデビュー盤でもないのだ。という解説を垂れている訳でもない。
ちゃんと2年前の1996年にMercury Recordsから「Scott Thomas」というセルフタイトルアルバムを発売しているのだ。つまりメジャーで計算しても2枚目に当たる訳だ。(「Wonderful」というタイトルでインディプレスされたCDをメジャーで再発したもの。ベイエリアではかなりの評判を得ていたのでメジャーに刈り取られたらしい。)
名義は1st作がScott Thomasとなっているが、実際にはバンドのギタリストでもあり、プロデューサーでもあるAndrew WilliamsやペダルスティールプレイヤーのGreg Leisz、そしてStephen Stillsの息子であるヴォーカリストのChris Stillsが本作と同じく参加していたりして、かなりのレコーディングスタッフが「California」に横滑りしている観が強い。
実際にこのアルバムが発売される以前から、L.A.ではScott Thomas Bandの名義で活動していたのを筆者が実際にライヴに足を運んで知っているのだから、単に名前にBandを追加しただけだろう。
レーベルを移籍する際に、正式な名前をScott Thomas Bandに刷新の為に改めておいたという考えもできる。
しかし、結局のところ名前は然程重要ではない。問題なのは、全くの見るべきところがなかった平凡なアクースティックロックアルバムだった「Scott Thomas」とは比較にならない位の完成度を、この「California」が成している事だ。
全くサンフランシスコ郊外生まれ、L.A.育ちという背景が音楽性に見えなかったデビューアルバムとは異なり、非常にウエスト・コーストの、1970年代近辺の良質な西海岸カントリーロック風味が漂うアルバムになっているのだ。
ポップな曲はポップに、ロックな曲はロックに、レイドバックした曲はルーツィに、と押さえるべきポイントはキチンと押さえた曲創りをしている。
別のバンド?、と疑念を抱かせるくらいの大躍進だ。
前作が特別悪かったアルバムではないが、メジャーがピックアップした事には少々疑問を覚える出来だった。Scott Thomas氏には申し訳ないが、誉めれる箇所は無し。インディ発売時のタイトルトラック『Wonderful』は中々のザクザクしたロックナンバーだけれども、全体的に単なるジャムロックの域を出ない退屈なアルバム。
Jam Rockだからこそウケが取れ、Mercuryの傘下からの発売になった可能性が高いか。
が、2作目こそ、メジャーに相応しい出来となった事は喜ばしい。というか、オルタナティヴ/グランジの基本色で染まってしまったメジャーシーンで、このような良質な非オルタナ系のアルバムが出たという事自体、珍しい。
毎年数回くらいの確率で起こる珍事と言い切ってしまっても差し支えないだろう。そのくらい市場性には合致しない−珍しく1995年から98年あたりまでオルタナティヴ一色ではないアルバムが売れてはいたが−ため、売れ行きに付いて思わず心配してしまった程である。
実際に論評筋の評価は高かったけれど、売れ行きとしては目立った結果を何一つ残せず終ってしまっている。
予想通りだが非常に寂しいものがある。
◆前作からのロケット・ローンチを著す尺度としての#3『Sad Girl』
デビュー盤から持ち越され、再録音された曲が#3『Sad Girl』のみだ。
このEaglesの『Wasted Time』を連想させるような哀愁を含んだバラードの王道曲のオリジナルは、「Scott Thomas」の8曲目に収録されていた。
目立ったキラー・ナンバーが殆ど存在しない1st作の中では数少ない良曲だった、と1枚目を聴いていた頃は思っていたものだが、「California」の新録ヴァージョンを聴いた後ではどうにもジャムサウンド的隙間の多過ぎるアクースティックナンバーとしか思えないのだ。
オリジナル曲はアクースティックギターとピアノを中心に、エレキギターとリズムセクションがサポートするアレンジがされていた。ちなみに殆どの楽器をプロデューサーのEthan Johnsが弾いている。
これに対して、2年後の新ヴァージョン#3は、ストリングスをバックに流し、ラップスティールとペダルスティールギターを加えている。ピアノが外されたのがアレンジ上の大きな特徴だ。
普通ならピアノ至上主義の筆者として、文句をつけたくなる変更なのだが、この新しいアレンジがとても素晴らしいので、不満の付け所が無いのだ。
まず、メロディラインの基本は全く変わらないのだが、より緩急を付けたと表現すれば適当なのだろうか、兎に角、演奏に“溜め”が効くようになっているのだ。言葉にすると難しいのだが、スコア1つ1つの繋がりに情熱が見えてくる説得力が加わっている。
また、淡々とし過ぎていたジャム風の1本道だったアクセントが、コーラス部分でグッと盛り上げ、メインヴァースでは切々と沈み、陰影のはっきりしたバラードになっているのが特徴でもある。
何よりも、オリジナルでは呟くように良く聞き取れない声で歌っていたScott Thomasが、実にセックスアピールの強い男臭い声で歌っている点が大きく異なっている。
バックコーラスの厚味もファースト・ヴァージョンと比較して凄くタップリとなり、ScottのJackson Browneに何処となく似た素朴な声を盛り立てている。
この1曲で、アーバンタイプの何処にでも転がっているようなアクースティックジャムシンガーから、本格的西海岸シンガーに成長した跡がはっきりと見える。
#6『Days Of Hours』にしても、以前のScottなら単なるアクースティックにサラリと流すナンバーとして終らせてしまっていただろうが、アクースティックラインをベースにして、強弱を少々加えたナンバーにしている。
Rami JaffeeのB3オルガンとコーラスワークによって、曲に山と谷をちゃんと拵えているので、退屈なアクースティックナンバーにはなっていない。
◆ロックナンバーがとても秀逸
デビュー盤では1曲しかなったアップテンポの曲が増えているのも、「California」の特徴だ。
特に前半の2曲はインパクトが強い。
まず、しんしんと夜間行進を続けてきた#1から、夜明けを迎えたような光明を覚える、#2『Black Valentine』。
#1のしめやかな曲調から、コロっと転調する落差が、#2の楽しさと速さを強く見せる働きをしている。
PocoやDoobie Brothers、BeachboysやBeatlesまで網羅できそうな、甘いコーラスから始まる激烈にキャッチーでビートの効いたロックナンバーだ。
何本も重ねられたエレキギターとアクースティックギターが、上品な土臭さ−これぞウエスト・コーストという空気を噴出している。3分と掛からずに終ってしまうのが唯一の不満点な曲。
そしてこれまた海岸サウンドの魅力をタップリ詰め込んだ、サーフ・ロックの#4『Happy』。
ベイ・エリアのルーツロックと云えば、こういったタイプのナンバーが真っ先に浮かびそうな好感触のポップチューンになっている。Heuy Lewisの初期のロックナンバーからR&B色を抜いて、アーシーなギターを加えたような曲と考えれば雰囲気が掴めるのではないだろうか。
Tom Petty & The HearbreakersのBenmont Tenchがピアノを軽快にぶっ叩き、少々カントリーロックの匂いのするラップスティールギターラインがまた爽やかだ。
続く、少しハードで泥臭いルーツフィーリングが新鮮な#5『Never Coming Home』ではL.A.のアルバムでは本当に頻繁に顔を出すRami Jaffeeがハモンドオルガンをウネウネと引き回している。低音域を駆使したピアノまで加わり、少し崩れたヴォーカルと演奏は昔のサイケディリックロックのムーブメントを思い出させる。ピアノはドラマーのSandy Chilaが弾き、ウィルツァーピアノをこれまたAndrew Williamsが弾いている、最も鍵盤の多いナンバーでもある。
また、ロックンロールというには少々重苦しくスロウな#9『Run Baby Run』でもハードでベッタリしたアレンジが展開されている。Eaglesの『Victim Of Love』のようなハードさを感じるが、ここにやはりオルタナティヴの匂いが少し入っている所が、Scott Thomas Bandの現代性を思わせる。
◆そしてアルバム後半2曲の西海岸ルーツコンビへ
アルバムとして最も流れがスムーズに進むのが#1から#4なのは確かだが、後半に突出して輝いている西海岸ルーツロックナンバーの#7『Full Moon Painter』、そして最もAlt-Countryの顔が浮き出ている#8『Believe』の爽快な土地柄を思わせるコンボも最高だ。
アルバムの中で最も骨太で、しかもキャッチーなロックナンバーという条件を同時に満たしているのは、#7だ。(#5や#9はポップさという点で後落する。)
元気一杯のエレキギターが痛快にキックを入れるリフからして絶好調な#7。Rami Jaffeeのハモンドオルガンが加わり、更にサウンドの迫力を増してくれる。
それよりも、やはり西海岸バンドのお家芸であるコーラスワークが最高である。リフレインして、リードヴォーカルと掛け合いをするバンドのメンバー全員でのハーモニー。
このスピーディーさが、曲のアップビートさと相乗効果を発揮し、ルーツロックでありながら泥臭さよりも清涼なドライヴ感を引き出すことに成功している。
♪「I Am A Full Moon Painter」♪の追いかけるコーラスがこのアルバムで一番印象に残るヴォーカルパートになっている。
#8『Believe』ではドブロギターを中心に、西海岸カントリーサウンドのお気楽さが遠慮なく出されている。が、コテコテのカントリーにならずに、少しスマートでクールなラインが同時に込められている所が、西海岸サウンドの真骨頂だと思ったりする。
間奏部分で休憩的合間を取り、Rami JaffeeのB3を加えて、曲のアレンジに少しの重みを加える。こういった手法によって、極楽カントリーとは異なった、西海岸カントリーロックの特質を演出出来ているのだろう。
◆思わぬ良作はララバイによって終息していく
振るように沸いて出た(失礼)、西海岸ロックのメジャーレーベルからのプレスとしては久々に本格的な“アメリカン・ロック”−オルタナティヴではない−を感じさせる「California」がリリースされたのは1998年。
#1『California』というアメリカン・ドリームの象徴の1つを題に掲げて始まるこのアルバムは、#10『Goodnight Baby』という子守唄=ララバイで静に終息していく。
メロディも完全にLullaby調になっている、アクースティックな静歌である。
『Hotel California』で現代の腐敗を揶揄し、『The Last Resort』で歴史の暗部を批判しつつ、理想郷など最早無いと夢の終焉を歌って幕を引いたEagles。
Scott Thomasは、『California』をEaglesと同じく社会のある象徴と捉え、苦悩する個人の思いからアルバムを始めている。丁度、大不況から立ち直り、好景気が始まっていた米国を社会背景にしたにしては、内省的過ぎる歌詞な気もするが、ある種の空洞な達観をこのオープニングナンバーに感じるのだ。
そして、最後は、「お前の親父はおかしくなっている。でも何にも心配することは無い。今夜は大丈夫。」というかなり辛辣な子守唄でアルバムを締めている。
現代の育児問題に対する警鐘を読もうとするなら可能だろう、が、寧ろ漠然とした次世代への不安を描いている詩と解釈できそうだ。
「今夜は大丈夫」。という刹那的な安心感で子供を寝かしつける。
個人的な内面というフィルターを通して社会を見ている詩人。そんな感じがScott Thomasにはするのだ。
このアルバムで子守唄を届けた後、Scott Thomasは4年ほど沈黙する。
その間の情報は全く伝わってこなかったが、突如2003年に新作の「Lovers And Thieves」という3作目を引っ提げてカムバックを果たす。
名義は再びソロとなったが、バンドのメンバーは全員レコーディングに参加しているので、内実は全く不変と見て良いだろう。
この5年近く、歌を書いては考え、書いては書き直しをしていたらしい。
しかし、初のインディレーベルからのプレスとなった3rdアルバムは、今のところだが、あまり聴き込めていない。
裏返せば、聴き込めるほどの魅力に乏しいと云えるのかも知れない。
これから聴いて行くつもりだが、やはりこの「California」には遠く及ばないアルバムという評価は覆せそうにない。何しろ、またデビュー時に近いアクースティック中心だが非ルーツのサウンドに戻ってしまった印象が強いので。
しかし、Scott Thomasがオルタナティヴサウンドにまみれた1990年代のメジャーシーンで、貴重な西海岸正統派サウンドを発表したという功績は、少なくとも筆者の心には永遠に残るだろう。
ライヴも良かったのだから、3枚目にはとても期待していたのだが・・・・・。 (2003.7.4.)
 Great Big Universe / Satellite Soul (1999)
Great Big Universe / Satellite Soul (1999)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Adult-Contemporary ★★★★ You Can Listen From Here
◆マイナーだが、メジャーのCCMより凄いバンド
現在、米国のポピュラー・チャートにてCCM(Christian Contemporary Music)のバンドが好調な売れ行きを示すことは珍しくなくなってきている。
南部ロックをベースにしてオルタナティヴ。ヘヴィロックバンドとしてデビューしたThird Dayが、最新アルバム「Offerings 2 A Worship Album」で初のトップ40ヒットを記録したのは今年の初夏であるし、トップ10アルバムを生み出し、人気ポップバンドとして広く認識されているJars Of Clayも紛れもない宗教バンドである。
また、Jars Of Clay程のビッグセールスは記録していないが、Sixpence None The Richerもメジャーで成功を収めているロックバンドだ。
これらの一部の例を見れば、白人宗教ポップロック自体が宗教音楽という枠から外れて、その音楽そのものに注目されている事が分かると思う。最も、Michael W.SmithやAmy Grandといったヒットメイカーは80年代から存在するし、ゴスペルチャート出身のメジャーシンガーは1970年代から存在していたので、今に始まった事ではないのだが。
さて、数あるCCMの中でも、実にポップでレイドバックな音楽を基本とする宗教バンドが1995年にアメリカ中部のカンサス州で産声を上げている。
全般に宗教系のミュージシャンやバンドはキャッチーな曲創りを心掛ける傾向が1990年代までの潮流だった。
ハードロックやヘヴィメタルの宗教バンドも基本はポップな音楽という線を尊守していたものである。
しかし、Alternative CCMという1990年代特有のオルタナティヴ・ミュージックとCCMの融合が90年代に入って進捗していくと、流行のノイジーでヘヴィなメロディに宗教的な歌詞を載せただけのオルタナ宗教バンドが増えてしまい、CCM=分かり易いポップメロディという公式は、部分的に崩壊を始めて久しい。
が、その中にあって、頑ななまでにポップさとトラッドミュージックのレイドバック感覚を大切に守っているバンドが存在していた。
それが今回紹介するSatellite Soulなのである。
◆Satellite Soulよ、現在は何処へ・・・・?
前段の最後に、「いた」と過去形で強調しているが、それには理由がある。
この通算4作目である「Great Big Universe」を発表後、既に3名体制になっていたバンドから、ベース担当のTyler Simpsonが脱退。
デビュー時から3枚目の「Satellite Soul」まで在籍していたギタリスト兼バックヴォーカリストのRustin Smithは既にこの4作目ではクレジットされておらず、ジワジワとメンバーが抜ける傾向にあったようだ。
Satellite Soulの発足は1995年。
17歳の時からソロ活動を続けていたTim Suttleがカンサス州立大学でバンドメンバーを募った事からバンドはスタートしている。
Timは1969年生まれで、当時の他のメンバーが1970年代中盤生まれと、少々年齢差のあるカップリングなところが特徴かもしれない。
地元教会に所属し、ライヴを続けつつ、1995年に「Homegrown」、1996年には「White Album」と次々に自主制作アルバムをフルレングスで発表。
カンサスを中心に周辺諸州でかなりの人気を博すチャーチバンドとなった1997年に、宗教ロック専門のレーベルArdent Recordsと契約を交わし、契約盤1作目の「Satellite Soul」をリリース。
このアルバムの3分の1の曲は「White Album」の再レコーディングである。
「Satellite Soul」の発売に合わせて、全米ツアーを敢行。この時にレーベルメイトに当たるBig Tent Revivalや同郷の女性チャーチシンガーであるJennifer Knappをサポートするためにツアーメイトにしている。
後年、Jenniferはメジャーチャートでも安定したセールスを記録し、Big Tent Revivalはクリスチャン・チャートのヒット常連となり、現在Ardentでは唯一のルーツ系CCMバンドとなっている。
ちなみに、Satellite Soulよりも土臭さは若干劣るが、非常にポップで優しいルーツ系のバンドとして、Big Tent Revivalは強力にお薦めしておく。Satellite Soulが好きなら問題なく受け入れられるだろう。
そして、1999年にArdentからの2作目、「Great Big Universe」を発売し、順当に活動を継続している。
翌年2000年には、所属先のArdent Recordsのレーベルを上げての企画として、ライヴアルバムを発表しているが、その時にはメンバーにJared AndersonとKevin lgartaを加えてライヴを行っている。
この「Ardent Worship Live」は、コーヒーハウスで複数のレーベル所属バンドがマラソンライヴを行った模様を、バンド毎に「Ardent Worship Live」と名付けて発売した代物だ。
他の「Ardent Worship Live」にはアダルト・コンテンポラリーとオルタナティヴの中間的なAll Together Separeteと、インダストリアル・ロックバンドのSkilletのリーダーアルバムが存在する。
というように、Ardent Records自体からSatellite Soulのアクースティックでレイドバックした音楽は浮き気味であった事も災いしたのか、翌年にはレーベルを脱退。(契約を切られてしまった可能性が高いが、詳細は不明。)
ここで、正式にベーシストのKevinをバンドのメンバーに加え、Satellite Soulは再びドラマーのRyan Greenと、リーダーでシンガーのTim Suttleを核とした3ピースに戻る。
しかし、サポートメンバーを加え、ライヴ活動は順調に行い続ける。ライヴを続けながら、2002年晩秋には完全自主制作で新作、総合6枚目に当たる「More To Love You」をプレス。
久々のセルフリリースとなった「More To Love You」だが、ジャケット無しの裸CD、そしてCD-Rということを知ったので、正規プレスになるまで買いを控えようと思い、注文はしなかった。
これが間違いの元になると分かるのが、翌年の2003年になる・・・・・。
2002年後半から、オフィシャルサイトの更新が全く行われなくなる。それまでは頻繁にアップロードを行っていたのに、急激な変化が訪れたのだ。
また、オフィシャル通販オンリーだった、裸CD(しかもCDのレーベルはセルフ1作目「Homegrown」の使い回し)の送金システムも、「入金受付の都合により、使用禁止」になってしまっている。
更に、掲示板やチャットルームCGIまでエラーを起こして掲示板にも入れない。
心配だったので、Tim Suttle氏にメールを、バンドのマネージメントにもメールを何度か送ってみたが何の返事もこれまでに無い。
考えたくは無いが、Satellite Soulは少なくとも活動を休止、最悪の場合はサイトを放置している理由が解散の憂き目を見ているため、かもしれない。
というか、殆どの確率でSatellite Soulは活動停止してしまっていると思う。ネット送金システム(CC Now)に使用停止処分を喰らうというのは余程の放置か何かをしないとそうはならない筈だし。
筆者としては是非とも6枚目の新譜を聴きたいので、あちこちと市場に流れた「More To Love You」を探しているのだが、未だに見つからない体たらくである。
嗚呼、Satellite Soulよ、いまはいずこへと・・・・・。
◆カントリーロック的なアルバムから、ルーツロック・フォークポップ風のアルバムへ
CCMにしてはかなり本格的なAlt-Country風味の強いルーツロック作品だった、契約1作目「Satellite Soul」。
が、「White Album」からの横滑りが3分の1以上あり、新曲とのバランスもまずまずだった好盤だが、Lost Dogsの最近作に似たカントリーロックの色合いが少々強過ぎる点が目立つアルバムでもあった。
特に、「White Album」からの再録ナンバーは、ポップでブルーグラスの匂いが感じれるものが多いと思う。それはそれでスピーディでありポップで良いと思うけど。
が、この契約2枚目に当たる「Great Big Universe」は、トラッドカラーとルーツ色は前作以上に割合が強くなっているように思えるが、その反面、カントリー、Alt-Country Rock的な側面はかなり減少していると感じられるのだ。
アーシーでトラッドな暖かさはそのままに、軽薄なカントリーの混入を極力排除出来ている。
これは、ルーツな土臭い曲はより、土臭いパワフルさを追求。
フォーキィなポップナンバーでは、カントリー・ポップではなく、よりスマートなアダルトコンテンポラリーなキャッチーさを追求。
これらの2タイプの曲を混在させ、柱を中西部根源音楽のブルーグラスにせず、トラッド的なPop/Rockに据えているため、ルーツ度合いが減退せずに、グラスルーツ的なカントリーテイストを抑えられているのだろう。
その反作用か、アップテンポな側に分類されるロックナンバーや軽快なポップチューンが減少している。カントリー的な明るさを切り詰めたのだから、ライトなアップビートナンバーが割合を少なくするのは仕方ない所だ。
全体としては、落ち着いたルーツロック・ポップのアルバムとしてどっしりとした風格を備えはじめた作品。
このように思える。「Satellite Soul」とはそれぞれ一長一短であり、どちらも甲乙は付け難いが、筆者としてはこちらの安定感のある雰囲気の方が好ましい。
◆マルチプレイヤー、Tim Suttleの本領、今回も発揮
元来、ヴォーカリスト兼ソングライターのワンマンバンドの性格が強いSatellite Soulだが、ギタリストが抜け、トリオ編成に縮小したことで、更にその傾向が強まっている。
今アルバムの全11曲は全て、Tim Suttleの手による作詞、作曲。
そして、ベースとドラムス、それからストリングス以外の全ての楽器とバックヴォーカルをTimが担っている。
挙げてみると、
アクースティックギター、エレキギター、ピアノ、ハモンドオルガン、各種キーボード、ハンマー・ダルシマー、ラップ・ダルシマー、ハーモニカ。
以上のマルチタスクである。やはり特徴はマンドリンとバンジョーの中間音を出せるダルシマーだろうか。
#2『Revive Me』、#4『I’m Not Leaving Now』等で透明感のある弦をタップリと表現している。
◆パワフルなルーツロックナンバーの#1
前作のOPトラック『Either Way』は‘のっけ’からBlues Travelersばりのブルースハープが這い回るルーツィなミディアムナンバーだった。
その次の「Great Big Universe」でもTimのブルースハープが最初から活躍する。しかし、より低音域を活用したハープは重みを遥かに増したギターアンサンブルの添え物として挿入されているに過ぎない。前作の#1程には自由奔放に走らず、リズムにフュージョンしたアレンジを遂行している。
ザックリとしたロックアンサンブル−ギター、ハモンドB3、ドラム、ベースが、バランス良く纏まって、重量感のあるミディアムな速度を引いて行く。
全てのパートが、前作よりも熟成を覚えさせる。特に、Tim Suttleのヴォーカルの優しさだけでなく、男としての膂力をも備えてきたヴォーカルは素晴らしく、厚い演奏にマッチしている。
このオープニングナンバーが、今回のSatellite Soulの在り方を雄弁に物語っている。
率直な所、この#1以外には重厚なルーツロックナンバーは皆無だ。コマーシャルなポップロックナンバーは他にも見受けれるし、#3『Always The Same』のように重苦しいジックリとしたマイナー調のヘヴィナンバーや#9『These Field』のようにダークでアクースティックオルタナティヴな雰囲気のあるナンバーは別口なタイプに当て嵌まるだろうし。
大分類ではバラード的な大作になるけれど、#7『Broken Again』はスタートからストリングス弦がギターと奥行のある壮大なアンサンブルを聴かせるナンバーで、ロックの派手さは表現できている曲だとは思う。
厚さという点では、#1に伍することが出来るミディアムポップなチューンである。ダルシマーとアクースティックギターがメインとなるメインヴァースとストリングスとエレキギターが存分に延びるコーラスパートがドラマティックに展開する。
この2曲くらいしかアルバムにはロックトラックが無いため、ロックとしての割合は少なそうに見えるかもしれない。
然れども、全体として落ち着きのある重みが出ているアルバムになっているのだ。
無論、#1の尻の座り具合が良過ぎるので、全体が締まったルーツアルバムに見えてしまう効果もあるだろう。
が、やはりトラッド・ロックの雰囲気が宜しいナンバーが増えていることが、速いナンバーは少ないのに、全体像を落ち着かせる効果をもたらしていると考えている。
◆ダルシマーとストリングスが引き出す、トラッドとアダルトロックのフュージョン形態
ダルシマーの明るい音色のリフで始まる、#2『Revive Me』。ストリングスの雄大な音色が、広大な空間の拡がりを瞼に浮かべさせる効果を発揮すると同時に、アクースティックなラップダルシマーの音色がトラッドサウンドのドライな気持ちよさを表現している。実に耳触りの良いポップなアダルト・ルーツナンバーだ。
アップビートな#2よりも、少しトーンダウンしたダルシマーのゆったりしたリフとドラムスのユニゾンから始まるミディアムナンバーの#4『I’m Not Leaving Now』。
ここでもダルシマーの活躍は続く。このナンバーでもストリングス、そしてTimの多重録音されたヴォーカルがタップリとした懐の深さを曲に加味しているが、マンドリンの音色と全く区別が付かないダルシマーの音色がHootersを思わせる位決まっている。アクースティックピアノとの合奏も優しさが滲み出ていて思わず微笑んでしまったりする。
見せ場はコーラスの輪唱だろう。次々に追いかけていくコーラスのリフレインで、曲は最大の山場を迎える。
トラッドとアダルトロックが実に巧みに融合している。
ストリングス及びシンセサイザーとピアノが、アクースティックなギターと絡まり絶妙のハートウォーミングなフレーズを生み出しているのが、#5『Heaven Waits』だ。
このナンバーのみ、過去作からの録り直しになっている。デビュー盤の「Homegrown」にもっとアクースティックでシンプルなアレンジで収録されていたが、こちらでは宗教バンドの暖かい音色を代表するような暖かいアレンジに包まれたミディアポップにリアレンジされている。
#10『Mercy Maker』はハンマーダルシマーとアクースティックギターの弦がトラッド色を補佐し、かなりフォークロックに特化した顔を見ることが出来るナンバー。コーラス部分ではエレキギターとストリングスが暴れ、静と動のコントラストを際立たせている。目立たないが良質なミディアムバラードだ。
◆バラードが成長したのが一番のメークマークかも
#6『Single Moment』の終始アクースティックで平板に進むフォーキィなナンバーが例外になるくらい、バラードタイプの曲はアーシーさとアダルトロックさが絡まったメジャーな構成の良曲が多い。
#8『Poor Reflection』はピアノのサニーで余裕のある音色にリードされ、Timのハイトーンヴォイスが一杯に拡がり、ピアノのセンチメンタルな感覚とストリングスの柔らかさが同居している。
アダルトコンテンポラリーの一面を代表するバラードだ。
対して、#11『Love Is All We Own』は美しいメロディとポップなラインという面では#8と同様だが、よりアーシーな感覚が前面に出ているトラッドなバラードに天秤が傾いているナンバーだ。
包容力のある暖かさと優しさでは他のバラードと全く遜色無い、Satellite Soulの成長を見せつけるラストナンバーである。
◆このまま消えて欲しくないバンド
ここまで良質なルーツとアダルトロックの融合という、宗教ロックのある種の理想形を具現化したバンドが、ジャケット無しのCD-Rを最後に消えていくのは実に惜しい。
Satellite Soulというバンドがある種の行き詰まりに当たってしまい、解散同然になっているのは仕方ないと割り切るべきかもしれない。
まだ、リーダーのTim Suttleの創作意欲が尽きていないと思うからだ。バンドを結成するまで10年近くソロ活動をインディシーンで行ってきた人である。年齢的にも30代前半と、萎むには早過ぎる事だし。
好きなレコードはAmy Grant、Rich Mullinsというゴスペルチャートの常連というのはさもありなんだが、あまりCCMは聴かずに、John Denverの「Rocky Mountain High」からJourneyの「Escape」、そしてThe Samplesの「Transmission From The Sea Of Tranquility」といったカントリーから産業ロックやパワーポップまでバックグラウンドが広いミュージシャンである。
きっと普遍的なPop/Rockのアルバムを引っ提げて何時の日か復活してくれると信じている。
その前に、「More To Love You」どっかで売ってください。今度はジャケ無し、CD-Rでも買うので。
(2003.7.13.)
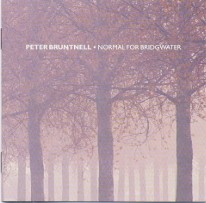 Normal For Bridgewater / Peter Bruntnell (1999)
Normal For Bridgewater / Peter Bruntnell (1999)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★
Alt-Country ★★★☆ You Can Listen From Here
◆Peter Bruntnellの変質・変身?
「このアルバムに収録する曲は、前のレコードの発展形だよ。最初の2枚のアルバムでは僕自身に迷いがあった。何をメインにするかというね。でも「Normal For Bridgewater」では、僕は自分のやりたい事をそのまま形にした。このレコードを聴き手が好きになってくれるととても嬉しい。」 Peter Bruntnell
Peter Bruntnell(tは無音となるから、ピーター・ブルンネルと読むべし。ブランネルよりも発音の表記としてはブルンネルの方がより近いだろう。)は、特に本作で彼を知ったリスナーからは新大陸の人間と誤解される事が多いらしい。
この3rdアルバムのリリースの前に、Peterは米国のインディレーベルから2枚のCDを発表している。
●「Cannibal」 (1995年)
●「Camelot In Smithereens」 (1996年)
現在この2枚は廃盤となっており、特に2nd作の「Camelot In Smithereens」はかなり入手が困難な状況にある。海外中古サイトやオークションでプレミア価格付きで取引されていたりもする。なお、発売はそれぞれ翌年にずれ込んでいるため、リリース年を1年遅れで記しているサイトも多い。
が、筆者の米国ルーツ好きな嗜好を通すと、この初期2作はそれ程凄いアルバムという気はしない。
確かにこの2枚ともそれなりのアメリカン・カントリーへの傾倒は見れる。特に2作目ではかなりカントリーに嵌り込んだ曲が増えている。
しかし、この「Normal For Bridgewater」を聴くまでは、筆者はPeterをかなりブリティッシュ・フォーク並びに英国系シンガー・ソングライターに連なる人と見なしていた。
つまり、ルーツ系のミュージシャンというよりも、アクースティック系・フォークソング系のシンガー・ソングライターとしての性格が強い人だった訳である。
アメリカンな音楽性は、その繊細さで初期のJayhawks等に通じる箇所はあるものの、やはり際立っていたのはブリティッシュ・サウンド特有のマイナー・コード。否、Peterの場合は捩れたポップセンスと呼ぶ方が相応しいだろう。
Peterの聴いた音楽については後述するが、音楽の道を選択するに至った切っ掛けとなったNeil Youngの「After The Gold Rash」、そしてその後に多大な影響を受けたというNick Drakeのオリジナル3部作を非常に身近に感じるサウンド・メイキングを行っている。
知っての通り、Neil Youngはカナダ人、Nick Drakeはたった3枚のオリジナルアルバムを残しただけで26歳の時に頓死したブリティッシュ・フォークの旗手的ミュージシャンである。両名ともポップな音を創るかと思えば、如何にも英国連邦文化のバックグラウンドを背負った素直ではない音を出す先達だ。
そういった英国的なサウンドの特徴が、アメリカ風な部分に混ざる。もとい、英国センスのメロディにアメリカン・カントリーが混在した作品をPeterは出していた。
筆者としてはサウンドのプロダクションは別として、Paul CarrackやNick Loweといった英国の地味な部分を背負って活動しているシンガーに近い感覚をPeterに感じている。
SqueezeやXTCが時折見せる、アクースティック・トラックやブリティッシュ・パブロック的な曲をよりシンガー・ソングライター的な姿勢で追及するとPeterの初期作みたいなアルバムが出来るのではなかろうか。
要するに、英国に時折出現するアメリカン・カントリーを追及するタイプのシンガーに属する人だったが、どうしようもなく英国的な部分を引き摺っているミュージシャン。
これが筆者のBruntnell観だったのだ。
しかし、レーベルを変え、2年以上の空白を置いて世に出された3作目を聴いて、その印象を全く改める必要に駆られてしまった。
このアルバムを聴いて、Peterが英国を拠点に活動している英国連邦出身のシンガーと判別出来るリスナーは殆ど存在しないと思う。
それくらい、良い意味でアメリカ的な色に染まったアルバムなのだ。
筆者としては、前作から続きモノの発展形というよりも、全くアプローチを変えた成果がBruntnellを変身させたという感が強いのだ。
◆英的カントリー音楽のアプローチが良い意味で働いた稀な例
英国ではカントリーロックやAlt=Countryといったジャンルの音楽はなかなか市民権を得ることが出来ない。
懐かしの時代に流行したパブ・ロックというジャンルも米国のルーツ音楽やカントリーロックの温床であるバー・ロック程にカントリーにのめり込まないルーツサウンド。
以上の意味合いを込めてパブ・ロックと命名されたくらいであるから、カントリーロックがあまり重視されていない事が理解できるだろう。
その代わりといっては何だが、フォークサウンド、アクースティックサウンドは非常に人気があり、ブリット・ポップが音楽的な伝統を汚染し破壊し尽くした21世紀に於いても、それなりに需要と供給が成り立っているジャンルとなっている。
初期のRod Stewartがかなりアメリカンルーツ的なレコードを量産し、一時期は英国のチャートを席巻したが、じきに“Atlantic Crossing”して米国に拠点を移したように、英国でのカントリーやルーツ的なベッタリ音楽は息が長く続かない様子である。(Rodの場合、文字通りのアルバム「Atlantic Crossing」以降になると脱ルーツに転向してしまうのは皮肉な事実だが・・・・。)
そんな状況のため、英国バンドや英国系シンガーの創作するアメリカン・ルーツ的なアルバムは、カントリー色が薄く、反対にブルース、R&B、そしてシンガーソングライターの繊細な側面を強調したものが数多い。
これが近隣の欧州諸国になると、本場のカントリー顔負けのベタベタなアメリカン・カントリーを惜しげもなくコピーするバンドが溢れている、という事情とはかなり対照的でもある。
それはそれとして、カントリー×2したサウンドがかなり苦手な筆者としては、英国系のルーツバンドが創造するカントリー・レス或いはロックとポップの要素が強いアルバムが大好きだ・・・・・。
・・・・と言いたいのだが、実際には英国系のルーツバンドには当たりが少ない。というのも、カントリー的な音楽が少ない代わりとして英国連邦民族特有のマイナーでヒネクレていて、素直で無い難解なメロディ・ラインが幅を利かせる場合が殆どだからである。
英国的な先進性のあるエクスペリメンタルでスノビッシュな音が好きな日本人と日本のマーケットには、こういった音が出回るのは大変結構なのだろう。が、筆者は英国的な親しみ難い一筋縄で捕らえられないサウンドはある意味ベタなカントリーよりも苦手なのだ。当然例外もあるが。
であるからして、英国系のミュージシャンの作成するアメリカンルーツ/アメリカーナ風のアルバムは非常に評価がバラける傾向がある。欧州諸国のシンガー程オリジナルに忠実にならない分、ベッタリなカントリー風味は少量だが、その分、こんがらがって素直ではない英国的メロディが多いと、ストレートではない変化球的なポップ・ロックアルバムになってしまうからだ。
実際にカントリー的な軽薄さをモデレイトさせ、尚且つ英国メロディのビターでベントで、フォーク路線に極端に踏み込みロックンロールで無くなってしまう欠点を解消。
以上の2点をクリアしているアルバムやその作り手のミュージシャンはそう多くは無い。
しかし、Peter Bruntnellは過去の2作ではこのポイントを的確に実践していたのに、突如3作目で英国的な部分をバッサリと叩き切り落とし、アメリカーナとして良質なアルバムを発表したのである。
かなりカントリーの影響が増しているが、しつこさややり過ぎを感じることは少なく、上手にアメリカンルーツであるカントリーを本来のPop/Rockと融和させる事に成功している。
まさに英国的な“嫌カントリー”性がポジティヴに働いた稀な例だと思う。
付け足しておくと、Peter自身は英国人的なカントリーと距離を置くという姿勢は採っていない。寧ろ積極的にアメリカン伝統音楽のカントリーを取り込もうとしている。
が、三つ子の魂何とやらで、いい具合にバリアが本能的に張られている為、カントリーが濃厚になり過ぎる事を防いでいるのだ。
だが、このバリアもこのアルバム限りで決壊した模様。この3作目から約4年弱の沈黙を経て2002年に発売された4作目の「End Of The Earth」は完全なAlt-CountryとCountry Rockのアルバムになってしまっている。
つまり、英国フォーク的な2作目とアメリカンカントリーロックにベッタリ吸着してしまった4作目の過渡期にあたる、中庸的なアルバムと云う解釈も成り立つのだ。
事実、絶妙にバランスが取れたAlt-Country Rockの良作だと思っている。
◆特にミディアムからロックチューンに於いて代表曲になる名曲が
このアルバムの特徴として、ロックチューン或いはミディアムテンポの曲に名曲が多い事だ。
前2作では、ロックチューンでそれ程ルーツカラーを出して来なかったPeterだが、この3枚目では骨太でアーシーなロックナンバーを中心に、ルーツトラックでかなり良い仕事をしている。
全体的にアクースティックの色合いが支配的だった初期2作ではロックチューンではより現代的なロック−ブリット・ポップとは違うが−パワー・フォーク的なナンバーが彼の持ち駒だったように感じている。
それが見事にルーツカラーを帯びて素晴らしいルーツロックとしてロールアウトされているのだ。
全体としてアルバム前半がアメリカーナ・ロック。
後半がカントリーとアクースティックチューンという区分けになっているようだ。厳密ではないが、ロックサイドが#1〜#5あたりまで。#6〜#12がスローサイド。このような2部構成になっている。
やはり、ミディアムテンポでは#1『Handful Of Stars』(というかこれしか無い気がする。)が出色。
ペダル・スティールの音響を上手に使って、寂しげなレイドバック感を出している。ハモンドオルガンやバンジョー、マンドリンを隠し味的に使用して、Peterの甘くて少し擦り切れたヴォーカルのバックアップを巧みに行っている。
この「Normal For Bridgewater」は米国のメディアにJayhawksやSon VoltそしてUncle Tupeloと比較されているケースが多いが、のっけからこのような最高級のAlt-Countryのメロウさを付き付けられては、このような著名バンドを引き合いに出さざるを得ないだろう。
しかし、彼の最高傑作はこの#1の後の曲、#2『You Won’t Find Me』それと後半で唯一のロックチューンである#8『Lay Down This Curse』だと思っている。
「う〜ん、僕は自分自身に向かい合って曲を書いているからね。ひいては自分の為に曲を創っているから、曲がコマーシャルかどうか意識したことは無いよ。結果的にコマーシャルな曲のレコードとなっても僕が意図した訳じゃない。」
とPeterは述べているが、どうしてどうして、非常にキャッチーな曲ばかりだ。
特に、Peterの切な気なヴォーカルとドブロギターのユニゾンでゆっくりと幕を開ける#2。
イントロからメインヴァースに入るポイントでスローナンバーからロックビートにシフトするメロディの変化が最高に胸に迫るモノがある。ピアノ、ドブロ、ペダルスティール、ハモンドオルガンという楽器を使い尽くしてミディアムとアップビートの境界線を走るルーツィなラインは最高にコマーシャル且つアーシーで、これの何処がコマーシャルでないかPeterに問い詰めたくなる。(笑)
ロックチューンにはへヴィでダウン・トゥ・アースな感覚が嘗ての英国ハードパブロックを思わせる#4『Forgiven』や、キャッチーな度合いでは#2と対等でアルバム最高峰の#5『By The Time My Head Gets To Phoenix』がある。
特にハモンドオルガンが滑かに流れ、ヴォーカルオンリーのソロを交えた静と動のコントラストが素敵な#5もPeterの歴代傑作5位までに入る完成度の高さだ。
しかし、ロックチューンで−ルーツ系のナンバーに限れば、#5は第2位にしかなりそうもない。
それは、英国ルーツロック・ポップのバイブルになりそうな#8『Lay Down This Curse』が後に控えているからだ。
適度に重く存在感のあるエレキギターに、少し英国風味を含んだビター・スゥイートなライン。
これはJayhawksやSon Voltを引き合いに出すよりもFacesや初期のRod Stewartと並列な位置に持ち上げて語るべき名曲だと思う。
キャッチーさでは「Songs From Northern Briten」の最も良かった頃のTeenage Fan clubに匹敵する。
#1、#2、#5、#8の4曲だけを聴くために、このアルバムを購入する価値は絶対に、ある。
◆音楽的なルーツへの敬意とブリティッシュ・フォーク
「子供の頃はサッカーばかりやっていて、音楽はそれ程重要じゃなかった。中学生の頃にGram Personsを聴いてカントリーロックやオルカンに目覚めたって事は僕は無かった。最初に買ったレコードはグラムロックバンドのSladeだったし、次にハマったのがT-Rexだった。
Neil Youngを聴いて音楽にのめり込んだのは20歳前後だったね。」
「僕が小学校4年生の頃に英国アナーキズムの表現であるパンクロックが流行った。けれど、正直なところ僕にはパンクの良さが理解できなった。それよりもプログレロックのYesやGenesisを聴いていたね。パンクの一部は好きだし、今ではもっと聴ける様になったけど、その野蛮さはやはり苦手だね。ハードロックのほうが全然良い。Thin Lizzyは僕の好きなHRバンドだよ。」
「僕が本格的にミュージシャンに憧れ行動を開始したのは、やはりNeil Youngを聴いた後だった。彼の音楽はこれまでに僕が聴いていたどのレコードよりもアクースティックギターで語れるものだったし、全ての要素が彼のアルバムには揃っていたからね。」
というように、普通にメジャーチャートでオンエアされる音楽を聴いてサッカーに打ち込んでいた青年が、サッカーの次に趣味としていたギターへと転向する契機はNeil Youngだった。
Peterは20歳になる前から地元のパブで少量のギャラを稼ぐためにアマチュアバンドとしてステージに立っていたそうだが、Neil Youngを切っ掛けにして彼のカヴァーバンドを始め、次第にNick DrakeやJohn Martynといったブリティッシュ・フォークの代表アーティストのカヴァーにも手を染めていく。
当時、パブではNeilやNickのカヴァーをやっているバンドが存在しなかったため、ある意味で重宝されたとPeterは回顧している。
そのNeil Young的な影響が見れる−彼が人生を変える切っ掛けとなったのが「After The Gold Rash」だが−のは主にカントリーロック風のトラックだ。
ペダルスティールをのんびりとくゆらせるスローカントリーロックな#3『N.F.B.』、CSN&Yを連想させるアクースティックなトラッドポップの#7『Cosmea』。この曲ではフィドルがマンドリン等と一緒に使用されているが、このメロディはアメリカントラッドよりも欧州的なトラッド色が見える気もする。
そしてあくースティックとブルース、カントリーが同居したへヴィなリフと、メインヴァースの繊細さのコントラストが印象的な#9『Shot From A Spring』では唄い方にもNeilを意識している跡が見えている。
英国的なフォークロックでは、最もNick Drakeのオマージュに当たるのが#6『Played Out』。とことん線が細く、そして優しい弦を切々と唄うPeterのヴォーカルの上質さが光るトラックである。ドブロギター等を活用しているが、アメリカンカントリー的な性格は希薄だ。
これぞ英連邦音楽と言うアクースティックナンバーである。
バンジョーを主軸に据えた#11『Flow You Are』や、米国トラッドと英国フォークの融合形態ともいうべき#10『Jurassic Parking Lot』(まあ、名前からしてハリウッドしているが。)は#6程の潔さが無いが、やはり何処かに英国らしいクールな感情がある気がする。
アーシーに特化するのは歓迎だが、あまり露骨にアメリカンカントリーを出すよりは#6のように新西蘭生まれ、英国育ちというPeterらしさを出したフォークナンバーとして纏めた方が良いと思っているので、もっと英国的な微妙さを出しても良かったかもしれない。
が、そうなると1stや2ndアルバムでのブリティッシュフォーク主体の作風との差別化がやり難くはなるだろうけれど。
しかし、かなりドの付くカントリータイプな、米国南部のララバイやディキシィを思わせる#12『Outlaw(May The Sun Always Shine)』は奇妙な事にカントリーの軽さや嫌らしさがあまり匂って来ない。
これは#7のように微妙に欧州トラッド色が含まれている故なのかもしれないが、こちらはJohn Martynが唄っても可笑しくないアメリカンカントリーへの英国的な回答に思える。
◆Normal For Bridgewaterの意味
「僕の友人が労働者階級向けのパブをBridgewaterで経営しているんだ。Bridewaterというのは英国西部の小さな街の名前なんだ。そのパブのママさんがある日、僕にこんな話をしてくれた。
Bridgewaterのある医者はNFB(Normal For Bridgewater)という略語を良く使うそうだ。診察の結果が少々患者にとって宜しくない場合にね。その配慮は実にユニークだと思った。
これがこのアルバムのタイトルの由来だよ。」
◆ローファイな英国フォークアルバムから、Alt-Country Rockへ、そして・・・
前述したように、この次のアルバムは相当にカントリーロックになってしまい、Peterの持ち味が活かし切れない、やや平凡な作品に終わってしまっている。
少し手厳しい言い方になるが、普通のポップなカントリーロックなら米国のインディシーンを探せば沢山発見出来るのだから、もっと英国的なバックボーンを活用したルーツアルバムを創るべきだったと思っている。
アルバムの出来としてはかなり良好なのだが、ちょっとカントリーロックになり過ぎているのが残念だった。
ブリティッシュフォークの新世代ミュージシャンからアメリカーナを唄う英国人(実際は新西蘭人)として評価されたBruntnellは、昨年はメディアには歓迎されている。とてもピュアなカントリーロックの歌い手として。
さて、この次は彼は何処に向かうのだろう。よりカントリー路線を強化するのか、それともNick Drakeを追従するサウンドに戻るのか、はたまたPop/Rockの快作である本作の方向に走るのか。
何れにせよ、次のアルバムはもう少し早く届いて貰いたいとは思う。4作目は随分待たされたから。 (2003.8.21.)

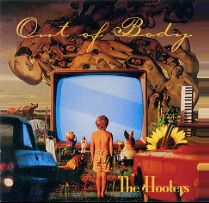 Out Of Body / The Hooters (1993)
Out Of Body / The Hooters (1993)