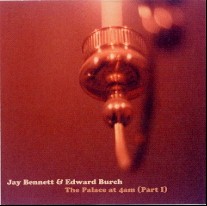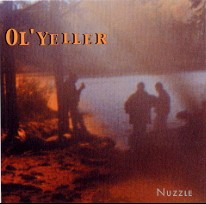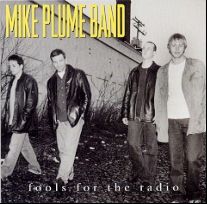 Fools For The Radio / Mike Plume Band (2001)
Fools For The Radio / Mike Plume Band (2001)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★★
Southern&Alt-Country ★☆
You Can Listen From Here
最近、骨太でありつつも、ハードにゴリ押しするだけでないパワフルなサウンド、付け加えてアーシーでポップな音が全然無い、と贅沢な不満にお嘆きの貴方。(酒の宣伝かい!!)
そういった玉虫色の願望を、現実の希望にしてくれるバンドが、アメリカではなく隣国のカナダにちゃんと存在することを忘れてはならない。・・・・というか最初から殆どの人がその存在を知らない可能性が物凄く大きい可能性が殆どではあるけれど。(苦笑)
カナダの中央部は、森と山と湖以外何もない(を)広大な州、アルバータはエドモントンを故郷とするMike Plume Bandが、それらの諸条件を満たす稀有なバンドである。(ついでに地下資源は豊富である。)
そう、Mike Plume Bandはカナダのバンドである。カナディアン・ロックには只でさえ目がない筆者は、それが単なるパンク・ポップの単純なだけと分かっているSimple Planのような底の浅くて溺れることもないようなペラペラな単純パワーポップアルバムも敢えて買ってしまうという、採点の甘さを有している。(後で、殆ど聴かなくなり金の無駄使いに涙するのだが。)何せ、この国に住まなかったらここまでインディ系のバンドに開眼することもなかったからだ。
そういった個人的な感情論はひとまず隅に寄せておいても、Mike Plume Bandはかなりの評価が出来るグループである。
1993年のレコードデヴュー以来、ミニアルバム1枚を加えてMike Plumeが作製してきたアルバムはこれまでに5枚を数え、最新作「Fools For The Redio」で6枚目となる。
一応、これまでの作品を列挙しておこう。
#1 「Songs From A Northern Town」(1993)
#2 「Jump Back Kerouac」(1996)
#3 「Simplify」(1997)
#4 「Song & Dance Man」(1997 / 1999 Remasterd By Buddy Miller)
#5 「Steel Belted Radio」(2000)
#6 「Fools On The Radio」(2001)
となっている。なお、1stアルバムの名義は、Mike Plume。2ndの「Jump Back Kerouac」ではMike Plume And His Bandと某オールディズ−ロック時代初の全米No.1ヒットを連想させるような古典的な名前に変わる。
そして3枚目の「Simplify」から、Mike Plume Bandという名前に固定となり現在に至っている。以下の詳しいバイオについては後程述べるとしよう。
このアルバムで唯一の不満は、このあまりにも安っぽく投げ遣りにデザインしたとしか思えないジャケットである。しかも故意にそうしたのか、単に適当に取り上げたのかも不明確なソフト・フォーカスが懸かった如くのピンボケな写真である。Web上にアップした写真では判断がつき難いかもしれないけれども、どうみてもチープさ炸裂だ。
折角、「Song & Dance Man」で初めて、アーティスティックなフロントジャケットを作成したので、厳密な意味での久方ぶりの本格的なリリースとなる今回もかなり期待していたのだが。
それ以外の5枚は、アートワークとしては見るべき箇所は残念ながら皆無だ。が、ジャケットと音楽性が比例することの方が稀である事実を鑑みると、こういった省コストジャケットの方が名盤であることが多いのかもしれない。
実際に、このMike Plumeが作成した6枚目のアルバムは、間違いなくこれまでの名盤の中でも群を抜いている。元々、それ程カントリーロックに足を突っ込んでしまい抜けなくなっているようなバンドではなく、どのアルバムにもカントリー・ロック風のナンバーがトラッキングされているにせよ、その数は少なかった。
が、予想以上に深いルーツのテイストを配し、アクースティックでフォーキーな−どちらかというとブリティッシュ・フォークの流れを組むナンバーが目立ち、やはり大英帝国連邦の一員たるカナダのバンドであることを感じさせた4thアルバム「Song & Dance Man」。殆ど同時にレコーディングされた、アンプラグド方式のアクースティックな第3作「Simlify」、加えてミニアルバムでアウトテイクを中心にリミックスされた5枚目の「Steel Belted Radio」、と1〜2枚目のワイルドなロックテイストから落ち着き始めたことを予感させるようなアルバムが続いていた。
が、久々にガッチリとしたローギアで荒地を噛んで走るようなロックアルバムが届いたのは嬉しい。
この「Fools For The Redio」で展開されているのは、フォークやカントリーの味わいを確かに残すが、如何にもカナダの中立性を示すような、単なるルーツロックである。つまり、一本筋を通しているのはトラッド系の音楽ではなくてロックンロールなのである。当然、重たいだけで爽快感の欠片も無いオルタナティヴとは全く違った次元のハードでマッシヴなサウンドである。
どうにも名状し難い、普通のコマーシャルで癖の少ない直線的なロックンロール。これがいわばMike Plume Bandの全てなのだが、細微を眺めると、Southern Rockに存在する野性の鋭さもあり、中部アメリカの牧歌的なルーツの影響あり、そしてブリティッシュ・クラッシックロックの崩れたようなルーズさもあり、とまさに色々な要素を混ぜ合わせてカナダの雄大な大自然で中和させたような“大きさ”を感じる。
National DustやMike McDonald Bandといった、カナダの平原3州を中心に活動するミュージシャンに顕著な、ポップさと純粋なルーツ音楽への敬意というプライオリティを、このMike Plume Bandもまた保持しているのだろう。
但し、カナダのルーツロック・バンドの中ではかなりヘヴィで筋肉質なロックンロールを演奏する(筆者の乏しい知識の中では。)バンドだ。が、その直球勝負な剛直さの中にもカナディアン・ポップ&ロックの多くのバンドが不思議に持っているバランス感覚をちゃんと携えている。
バランスとは、あまり極端な方向性に濃く、深く、ベッタリと嵌らないということだ。1980年代のメジャーであった、アーシーなアメリカンロックにとても近い音楽性を21世紀になってもちゃんと再現してくれているバンドでもあるのだ。
さて、「Fools For The Radio」と、解釈に拠っては(つーか、拠らなくても)かなり現代のヒットシーンに対する痛烈な批判と取れるタイトルを冠していると思うのだ。
『ラジオのために流行曲を書く考え無しなアホ』
と筆者は受け取っているのだが、皆さんは如何考えるのだろう。または自分達の反語的に揶揄して
『ラジオに乗るような曲を演っていると勘違いしている愚か者』
とも曲解できる(笑)かもしれない。とまれ、内容を辿ってみよう。
オープニングから、気持ち良い切れ味のあるロックナンバーが炸裂する。Mike Plumeのシャガレ声がアクースティックとエレクトリックのギターのカッティングにテンポ良く乗っかっていく#1『When In Rome』から
「僕達は小細工をしないロックンロールバンドだと思っている。」
というMike Plumeの考え方を代表したようなナンバーである。が、単純にシンプルなだけでなく、プロデューサーのMarek Forysinskyが重ねる複数のキーボードが格好良く絡まり、英国的なロックテイストをも醸し出している。
過去、Mike Plumeは「Simplify」を除く全ての作品のオープニング・トラックで説得力ある躍動感を持ったロックナンバーを揃えて来ているが、このナンバーは1stアルバムの1曲目に匹敵するナンバーである。何と言ってもMikeの枯れたヴォーカルがシャウトし、テナーを唄い縦横無尽な活躍を見せることでリスナーを惹き込む効果を発揮している。
が、ロックナンバーの真髄は次のナンバー、#2『Sensitive Guy』で炸裂する。テンポ的には#1よりもややユルリとしているのだが、リフから堀りたての山芋のように泥臭いヘヴィなスライドがラインを叩き付ける。サザン・スウィングの豪快なうねりに合わせて、ハモンドオルガンがビュンビュンと唸る。完全に英国ロックの琥珀色を懐古したナンバーであり、Facesを南部ロックの雄大さで包んだ如くのヘヴィ・ドライヴチューンだ。
#3『Dreamer』はポップビートがオルガンとアクースティックギターに溶けて、ルーツとして再凝結したキャッチーなルーツロック曲。兎に角、軽快であり、ダンダンと刻まれるドラムのリズムがひたすら痛快である。しかも全体として適度に土臭い郷愁が感じられ、暖かい気持ちにさせるナチュラルさが存在する。
#4『She’s Still Everything To Me』はハーモニカが甘酸っぱくメロディを彩る、これまた最高にキャッチーなクラッシック・ダンスなタテノリソングである。カントリーの土臭さというよりも、ロカビリーやパーティ・ロックのホンキィな弾力が波打つ快感の方が一つ群を抜いている。この古臭いのに、キレの良いメロディは普遍的なポップスタンダードと呼びたくなる魅力がある。ギターソロでの胸がすっきりとする躍動感は、もう陽気で明るいとしか表現できない。
#4までの激烈にコマーシャルな流れから少々スローダウンするのが、#5『Walkin’By』だ。かなり粘つくブルージーなAメロから、トーンが一気に上昇するコーラス部分のハーモニーの入れ方、そして作曲の工夫はなかなかに素晴らしいものがある。ギターソロの汚れを跳ね飛ばして進むようなダートさに男臭さを覚えるのは筆者だけでないように思えてならない。
ファンク・ロックの苦味と重さを、野暮ったく引き伸ばしている#6『Fl y
In The Ointment』では、オルガンだけでなくギターもヴォーカルもファンキーなスタイルを敢えて取っているように思える。このややダークであるけれども、キャッチーさもしっかりと有したヘヴィ・グルーヴが特徴なナンバーでは、何と云ってもギターの力の入り方が特徴的である。力任せのドロドロとしたギターの重さに、オルガン・サンプリングを始めとするキーボード・サンプリングがムーグのようなアレンジでハーモナイズされ、ユニークなラインを演出している。
と、前半はすべからくロックナンバーで固められている。この流れが転じるのは、Mike Plumeが大好きで始終聴いていたという
Simon And Garfunkelの影響を覚えずにはいられない、切々と紡がれるアクースティック・バラードの#7『Dimaccio』だ。Marilyn MonroeとJoe DiMaggioの実話を唄い込んだというPlumeのコメントにもあるが、大人の恋愛を歌ったようなラヴ・ソングである。
が、しっとりとしたナンバーは1曲で終わり、再び、ヘヴィでシャープなロックナンバーが2曲連続する。
#8『Climbing The Walls』はこのアルバムの中でも最もハードで崩れたノイジーさが咆哮するナンバー。曲全体の気持ち良いリズム感は#2に負けているが、オルタナティヴ・ヘヴィな現代性も確実に感じさせる程のルーツ・ハードロックをガツンガツンと叩き付けて来る。ディストーションの効いたギターはライヴ演奏で本領を発揮しそうである。
ロック攻勢は続くが、同じロックナンバーでも、#9『Bird’s Eye View』はヘヴィさよりもその炭酸飲料のような爽快なスピード感が強烈なインパクトになっている。このアルバムでは一番シングルに向いてそうなドライヴィングなエッジが激ポップなメロディラインを牽引していく。また胸を締め付けるような甘いハーモニカもこのナンバーに即効性の高い柔らかさを振り撒いている。
Mike Plumeは常にかなりのナンバーをアルバムに収録する傾向のあるミュージシャンだが、このアルバムは14曲も入っている。ミニアルバム「Steel Belted Radio」を除けば、最低でも「Song & Dance Man」の11曲という高レート(?)だが、今回の6作目が一番多くのナンバーを収録している。
2桁台の#10『Promise Me You’ll Never Tell』は、ペダルスティールとアクースティックギターがパタパタと煽られるドラミングに乗っかって軽快にシャッフルするカントリー・ロックタッチの柔らかい雰囲気を持つポップナンバーだ。が、バックでラップスティールの音色のようなブワブワとしたスライドギターが控え目に鳴っていて、アクースティックなだけのナンバーにしていない。
#11『Radiate』はEverclearのポップナンバーを思わせるようなモダンなリズムで導入され、ミディアムな調子で進んでいくと思いきや、元気一杯なギターが2本でバトルを始める。全体としてハードなギターがコマーシャルなロックを引っ張るパート、ギターソロが甘めなメロディを引き摺るパート、そしてドラムとリズムギターが淡々とモダン・ポップをリフレインさせる3つの曲が組み合わさった複雑だが分かり易いポップ・ロックである。
#12『We Both Knew』でやっと久々におっとりとしたバラードがじっくりと歌われる。エコーを効かせたギター、控え目なデジタル型のキーボード、そして抑え目のMike Plumeのヴォーカルがジワジワとバリトン・ヴォイスを聴かせるという、かなりウェットな感覚のバラードであり、どちらかというとカラリとした豪快さが目立つMike Plume Band(以下MPB)には珍しいバラードかもしれない。
#13『You’re The Only One』はルーツィなオルガンをフューチャーし、ディストーションのかかったギターが音色をうねらせる、かなりアーシーでダートなナンバーだが、一方古典的なスクールロックの踊り出すような楽しさをスコアに注ぎ込んでいるナンバーだ。ブルースやR&Bの影響を思わせる。
最後の#14『Eggshells(New Day)』はノイジーなギターソロから、雄大なうねりを盛り上げていくミッド・テンポのバラードである。物凄くポップなナンバーではないけれども、ラストを飾るのに相応しいダイナミックな展開を繰り広げてくれる1曲である。このナンバーで初めてピアノ・サンプリングがくっきりと使用されているが、これまでピアノが効果的に使用されていないにも拘らず、演奏が分厚く強靭なものという印象が濃いのは、シンプルな楽器を巧みに重ねて効果的なアレンジを施しているからだろう。
ロックアルバムとしては1997年の「Song & Dance Man」以来のアルバムとなった第6作目に付いて長々と述べてみた。この4枚目(3作目の「Simplify」と殆ど同時リリースなのだが。)が、1999年にBuddy Millerのリマスターによって初めてアメリカで発売されたのは、とても納得がいかない。
米国ではこのアルバムと本作「Fools For The Redio」しか発売されていないのも間違っている。また、本作が正式に米国でリリースされたのはつい先日、2002年5月のことである。ま、中古盤を待って2001年を越してしまった筆者がとやかく言えることではなかったりするが。(苦笑)・・・・米国で売り出した途端に中古マーケットの値段が暴落したのも腹立たしい、と愚痴はこのあたりで止めて、Mike Plume Bandについて説明しておこう。
バンドの編成が固定したのはAnd His Bandの名義になった2作目「Jump Back Kerouac」から。が、このタイトルから連想されるものとは正反対に、Mikeはそれ程Jack Kerouacからソングライティングの影響を受けてはいないと語っている。
「彼の著作は読んで、映像作品も見たけれど、ソングライティングに限っていえば、最も大切なのは自由に創作をすることだよ。その点ではKerouacは凄い人だけれどね。」
Mike Plume (Vocal,Rhythm Guitars,Harmonica) ,David Klym (Lead Guitar,Vocal)
Ernie Basiliadis (Drums) , Meck Meyers (Bass,Vocal)
このメンバーは1996年以来不動であり、各レコーディングにはこの4ピースにゲストが参加する形だ。プロデューサーは恒例のMarekが担当し、彼の担当するキーボードの割合が増えたのが大きなアルバムの変化でもある。(4作目では2曲でサポートしたのみ。)
幾度か触れたが、Mike Plumeはカナダ生まれのカナダ育ち。アルバータ州のエドモントンを拠点に活動をしているロックンローラーである。
彼はBeachboys、 Simon And GarfunkelそしてBob Dylanを聴いて育った。が、子供の頃の夢はプロのアイスホッケーの選手になるという、如何にもカナディアン・キッズらしいものだった。が、高校生になり、彼の才能ではプロとしてはやっていけないことを痛感し、17歳でギターを始める。スポーツ選手が駄目なら、ミュージシャンという、三文小説の登場人物のような話だが、実際にアーティストになっているところが凄い。(笑)
この頃、ドラマーのErine Basilaadisと出会い友人となり一緒に演奏を始めるようになるが、1990年代に入るとMike Plumeはテキサスはナッシュヴィルに単身渡り、スタジオミュージシャンのサポートでソロ名義の1stアルバム「Songs From A Northern Town」を作成する。とはいえ、アルバムはカナダ限定でリリースされることになる。レヴェルが違い過ぎるが、日本のアホ芸能人がちょっと売れるとロス録音とかをしたがるような、願望があったのだろう。
事実、Mike Plumeはカナダが好きだけれども、ナッシュヴィルに活動拠点を持ちたいと、現在でも思っているそうである。
「僕は、人生の半分以上カナダに住んでるし、音楽活動は全てアルバータを拠点としている。が、是非ナッシュヴィルに住んでみたい。この前バンドで滞在した時、ホテルの一室を借りるのに3000ドルも取られた。もっと安ければ絶対にあっちに住むさ。だって、Bruce SpringsteenもJohn MellencampもJohn Hiatt、John Prine、Mark Knopfler、それにSting。皆ナッシュヴィルに家やスタジオを持ってるんだ。あの街はソングライターの街だよ。」
が、これ以外のアルバムは全てカナダで録音され、2枚以外はカナダのみでしかプレスされていない。現在も演奏活動の中心はカナダである。もっとアメリカで脚光を浴びるべき存在なのだが。とても素晴らしい曲を書けるシンガー・ソング・ライターであるのだから。
Mike Plumeは自分をソングライターであり「歌うたい」と捉えているそうだ。よってリズムギターに専念している。
「僕は17歳でギターを始めたけれど、2年後には絶対に凄いギタリストになれないって分かった。落ち込んだね。けれども、その時Springsteenの記事を読んだんだ。彼は常に格好良いギター引きではなく、歌を唄い、そこに織り込まれた物語を伝えたいと考えている、というね。僕はまさにそれがこれからの僕の在り方だと思った。」
確かに、リードギタリストのDavidの熱意溢れるプレイには、Mikeのリズムギターは押されて目立たなくなっているが、それを補って余るソングライティングの才能と、男臭いシャガレ声を持っている人だ。演奏を眺めてみても、バンドとしてガッチリと纏まったマッシヴで剛毅なスタイルを貫いている潔さが素晴らしいと感じるだけである。
Mikeは1980年代のアメリカンロックの大御所が大好きで、彼らから影響をかなり受けていると述べているが、実際に90年代に失速してしまった王道的なアメリカン・ロックの色合いを、濃く音楽性に反映しているアーティストだ。
グランジ・オルタナの暴風雨は隣国カナダにも相当の影響を与えたのだが、きっちりと流行に左右されないで演奏活動をしているのは瞠目に値すると思う。
「このアルバムは自然な要素と、是非とも聴かずにはいられないサウンドを結びつけたものだよ。」
とMike Plumeも今作が今までで会心の出来であることを誇っている。
「Fleetwood Macの『噂』をどれだけか感じる歌だけど、Eaglesの『ホテル・カリフォルニア』のように聴こえるようにしたいね・・・・。僕は歌に形を与えるんじゃなくて、歌がどのように演奏してくるかを語ってくれる、このようにして曲を創っている。」
確かに、「Rumours」のポップで基本に忠実なメロディが存在する。そして「Hotel California」のヘヴィであるが、得体の知れない吸引力を伴った魅力がある、この「Fools For The Redio」には。より現代的で硬派なルーツロックという表現形式を取ってはいるが。
このような曲が一日中ラジオから流れてくれる地域や国に住めるのなら、「ラジオの前に張り付く愚か者」になっても一向に構わないと思うのだ。
このアルバムは筆者の2002年のベストに入れなくてはならないだろう。米国での発売は2002年ということだし。
(2002.5.24.)
 Come Together / Third Day (2001)
Come Together / Third Day (2001)
Roots&Alternative ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Southern&Modern ★★★
You Can Listen From Here
邪道ページと笑わば、笑え!!
まず、Roots Rockという音楽を扱うホームページでは顧みられることが殆ど無いバンドである。が、このHPはあくまでもポップ・ロックを紹介するサイトである。ベッタリな“ルーツ音楽”を、非ロックなトラッドをレヴューする場所ではないのだから良いのである。とはいえ、ハードロックとかヘヴィ・メタルも全然取り上げる気は無いので、どうにも異端なジャンルになってしまうのだが・・・・。
さて、邪道と書いたが、この「Come Together」はRoots Rockと呼んでも何ら差し支えの無い作品となっている。寧ろ、Southern Rock、Southern RockベースのModern&Roots Rockという表現が似つかわしいかもしれない。
しかしながら、このバンドのデヴュー作を聴いた時は、筆者は速攻で投げ捨ててしまった過去を持っている。というか、無駄使いをしたことを悔いて泣きたくなった記憶さえある。それくらい、この5枚目(セルフリリースを加えれば7枚目)の「Come Together」まで至る途上で、Third Dayというバンドの音楽性は変遷を見せているのである。
唯一聴いたことの無い、自主制作の極少数リリース盤「Long Time Forgotten」(カセットのみ)と「Contagious」(後にセルフタイトルとして曲目をかなり変更して再レコーディング。)の音楽性は不明なため、ここでは言を持たないけれども、実質のレコード・デヴューである1995年の「Third Day」を聴いた時、その基本となる音は、紛れも無くAlternative Heavy Rockであった。
確かに、ポップなメロディラインを多少なりとも含んでいたにせよ、眼を瞠らせるほどのコマーシャルさは皆無。マシンノイズや人工ドラムループを多用しつつも、硬く歯が立たないような重過ぎるギターがズコンズコンと殴りつけてくるだけの音楽。
当時、彼らの出身地が米国南部のジョージア州だったこともあり、Lynyrd Skynyrd ミーツ Pearl Jam等と呼び名を冠されていたことを挙げれば、どうにもこうにも筆者の苦手な音楽だったことはお分かりになると思う。ちなみに筆者はまだ音楽に慣れていない頃、どうとってもコマーシャル・ポップから程遠いLynyrd Skynyrdを聴き、その良さが全く理解できなかった経験を持つ。それがトラウマになって、未だにLynyrdは苦手である。
が、まだ「Third Day」は硬派なロックアルバム、と云えない訳ではなかったし、その当時はそこそこオルタナ・アルバムも聴いていたので地面に叩きつけて割る程の相性の悪さはなかった。
問題は、2枚目のアルバム「Conspiracy No.5」だ。このアルバムはThird Dayキャリアの汚点である、と断言して憚らない。ヘヴィなギター・チューンは1stから更に癖の悪さを増加し、そこへ絡むスクラッチとヒップホップのアシッドな雑音。所謂、ヒップ&ラップ・メタルというこの世で最も最悪の部類に入る、10代の餓鬼共のファッションのためだけに作られたゴミ芥。聴けるナンバーも幾許かはあったけれども。
1回通しで聴くことが相当の苦痛であったアルバムである。在米中の1997年に聴き、完全に萎えてしまった。
Third Dayは無宗教の著者が到底理解し得ない「信仰」を唄う、クリスチャン・バンドであるのだが、
「おめ〜ら、神様の罰が当たるんとちゃうか!そないな低俗な音を作って。取り敢えず、死んで来い!!」と暴れたことを想い出す。
このため、次作の「Time」(1999年)は当然無視。当時の風評も、
“宗教ロック界のCreed” “Three Door Downのクリスチャン・ロック版”
といった代物であった。・・・後程バンドが方向性を転換したことを聴き知った後で購入したら、まあそこまで腐ったサウンドではなく、AlternativeとRoots Rockが混在したそこそこの作品だった。何よりもマシンドラムとシンセ・プログラミングが大幅に減少していたのは評価の対象だ。
しかしながら、まだまだAlternative Mixed Southern Rockというやや中途半端な音楽性ではあるが・・・。
まあ、単にヘヴィで重くて、ヘヴィなだけの音を出して、チャートに媚びている上記の2バンドと比較される段階で、永遠にサヨウナラであるからして、筆者の脳のキャッシュ・サーバーからは殆ど完全にThird Dayの名前はSome Dayという程度のランキングに下落してしまった訳である。(当然、Long Good-Byeが頭に接続される。)
こういった最低の評価が、あっさりと覆ったのが、2000年に偶然繋いだネットラジオでエア・プレイされていた1曲のナンバーだった。
アクースティックなアレンジをメインにして、大地に楔を打ち込んだような安定感。且つそれ程埃っぽくないという、まさにアメリカンロックのナチュラルさを具現化したようなバラード。その『King Of Glory』がまさか、最低の烙印を押していたThird Dayとは想像をだにしていなかった。
慌てて、そのアルバム「Offerings:A Worship Album」を試聴してみた。ま、タイトルからして宗教バンドという事実が丸分かりなのは何であるのだが。(苦笑)どうにも宗教ロックには歌詞の面からメロディ以外の共感を得ることが著者としては困難極まる。
Christian Rockの歴史と変遷については、以前にLost Dogsの2001年作「Real Men Cry」で薀蓄を述べているので、参考にして貰えば幸いである。
で、その2000年の4thアルバム「Offerings:A Worship Album」は新曲が2曲入っただけのライヴアルバムだったのだが、その2曲のスタジオ録音ナンバーはかなりのツボをついたアーシーな正統アメリカンロックであり、更にライヴ収録された未発表曲を含むナンバーも、アクースティックでハートフルなアレンジで演奏されていた。
頭ごなしにがなりつけるヘヴィネス・サウンドの影は全く霧散していた。これに驚き、1999年の3枚目である「Time」を中古で入手。前述のように、このアルバムもまずまずの南部系オルタナ風ロックアルバムであったので、5枚目には期待していた次第なのだ。
で、2001年11月に、ここ2作は続けてリリースという物凄いピッチを崩さずに、本作「Come Together」が届いたという訳なのである。
しかし、Third Dayには過去に筆者の感性をドン底に叩き落して踏みつけたという前科があるために、即時購入を躊躇わせるものがあったのだ。AlternativeとModern Rockのベースからは完全に逃れられないだろうという予感はあったし、また初期のヘヴィ・ミクスチャー路線が強烈にならないとも限らなかったからだ。
で、取り敢えず中古盤を待ちつつ、試聴をしてみた。30秒サンプルを数曲流した感じでは、悪くないアルバムという掴みだった。結局、入手は2002年の早春までずれ込んだのだが、結論としてはもっと早く入手しておくべきだった、ということになった。
確かに、まだまだ完全にオルタナティヴが拭い去られた訳ではないし、この現代クリスチャン・ロックユニットがゴスペルやカントリーといった古典的な宗教ポップに完全に転ぶとはハナから考えるほど楽観的でもない。
が、ヘッドロックを噛まして鼻っ柱を殴りつけるようなヘヴィサウンドは完全に近い形で消滅している。とはいえ、まだまだ、ドラム・ループやスクラッチ、そしてシンセプログラムを取り込んでいるナンバーや、オルタナティヴ的な鬱陶しい重さが支配している曲も存在する。
ギターの音色にしても、自然に弦から零れ落ちる自然さを不必要に捻じ曲げた、知能指数の低そうな弄繰り回した無機質な音が大手を振るって闊歩している曲も、ある。
そういった、筆者が音楽とは考えていないジャンルの残滓と残り火を纏わりつかせつつも、全体としてはルーツ・サウンドと呼べる土臭さの割合が上昇している。
あからさまに、濃いストレートなRoots Rockとは定義できないにはしても、Roots Rockな雰囲気を湛えたアルバムという評価をするにはやぶさかではない1枚。いわば、90年代以降のメインストリームなAmerican Rock−ここが肝要である。AlternativeとかGrungeではない−に踏み込んだ作品といえる。
現代ロックに特有な、頭を抑えられたために不完全燃焼なポップさ、という要素があるにしても、十分に楽しめるキャッチーさを誇れるメロディ・メイキングをしている。
特筆すべきは、出身エリアの伝統的なサウンドである、Southern Rockのタフさと豪快さ、そしてハードさを現代のロックサウンドと上手く折り合いをつけて同居させていることだろう。Southern Heavy Metalまでノイジーに咆哮するでもなく、適度にハードで重量感のある筋力を殆どのメロディに感じることができる。
また、アクースティックな感覚も以前よりもグンと前面に押し立てている。このことが、ヘヴィ一辺倒な単調さを緩和するのに貢献しているのだ。
南部サウンドの泥臭い雰囲気はモダンサウンドの都会的なアレンジのために薄められているけれども、メロディラインを安定させることが可能なレヴェルなら問題なくクリアしている。適度なアーシーさはBruce Springsteenや後期の38 Special、そしてLittle Feetの音楽を垣間見させるのだ。所謂、Southern Arena Rockという80年代の主流を占めた分厚いロックサウンドを思い起こさせる、フックの存在するサザン・ロックの一形態に成長している。
筆者はそれ程好きではないが、やはりLynyrd Skynyrdのサザン・ハードなサウンドの現代版、と捉えるのが一番適当なのかもしれない。
様々な音楽要素が絡まってサウンドを形成しているのだが、ロックンロールとしての凝集に成功している音を聴くことができる。即ち、ロックンロール・アルバムということだ。
全体としてはかなりヘヴィでパンチの効いたギターが強烈だが、疾走するレーシングカーに例えるような甘いポップ・ロックチューンは皆目存在しない。
それこそ南部ロックンロールという感じの、強靭でややユルリとしたリズムのロック・チューンが大半だ。このあたりの境界線が微妙で、あまりにも重くて人工的な音を作ると、単なるモダン・ヘヴィネスとなってしまう。
ヴォーカリストのMac Powellは「Third Dayが好きなら、Southern Rockバンドをお薦めだね。」と述べるが、ここまでは良い。が、ところが、「Pearl JamやCreedを聴くといいよ。」
ってのに納得できるかああああ!!
と思うのだが、それこそ、Third Dayがボーダーラインに位置するバンドという証明になるのではなかろうか。
ま、兎に角、
Pearl JamもCreedも一回氏ね!!
とこのようなポップをヘヴィと勘違いしたアホバンドは絶対にSouthern Rockではないと思う。Mac、アンタ間違ってんで、ホンマに。(涙)
そこまでやり過ぎずに、ハードドライヴィンだが、メロディアスでがっちりとした大地の息吹を注ぎ込んだ、玄武岩のようなタフなロックンロールの域に、Third Dayは現在立っていると思う。
そのタフネス振りは1曲目から攻勢をかけてくる。タイトル曲の#1『Come Together』はいきなりキーボード・シークエンスの電子音から始まり、「しまった」と思わせるが、即座に豪快なギターがぶん回されるロックチューンに突入し、ルーツィなハモンドB3までがヒョロヒョロと絡んでくる。これでかなり安心した。サザン・ルーツ・ロックと呼べるに値する曲だったからだ。また宗教バンドに特有の鼻声ハイトーン・コーラスが良い味を出している。
#2『40 Days』はサンプリングサウンドやオルタナティヴ風の重苦しいギターが唸りをあげるヘヴィなナンバーだがメロディがそこそこポップなので聴けないことも無い。
これがドラム・ループを使ったモダン・ヘヴィ調の#4『Get On』やスクラッチにリズムボックスまで持ち込んだ#8『I Got You』になると、やはりかなり不満の残るナンバーになってしまう。#4は女性コーラスを入れたファンクでハードなミクスチャーを直に感じる曲。#8はヒップ・モダンというべき重苦しいナンバー。これは苦手だ。
このようにオルタナ/ミクスチャーの側面を持つところはマイナスだが、それを補って余るのが、アクースティックまたはエレクトリック、そしてスゥイートなバラードの数々である。
#3『Show Me Your Glory』はメジャーな展開になると思わせて、意外にマイナー調子に転変したりと、聴き飽きることをさせないバラード。くぐもった電子鍵盤の使い方にはやや不満があるけれど、情感が溢れそうな哀歌である。
ややくすんだピアノを中心に紡がれていく#6『It’Alright』は、やや平坦でおとなしいアクースティックなスローナンバーであるけれども透明感のあるコーラスワークが光る佳曲だ。Macのソウルフルなヴァリトン・ヴォイスもバラード向けであることが良く分かる。
最も王道派のバラードとなると、#9『I Don’t Know』だろうか。アクースティックなリリカルさとストリングスまで加えたエレクトリックなダイナミズムがスムーズな流れで移ろい行くアダルト・オリエンティッドなバラードである。産業ロックの雄大さを、80年代の売れ筋南部バンドのコマーシャルなアレンジをそのまま写したような感動的−少々やり過ぎな面もあるけれども−大作である。
その#9に比べて、もっと優しく、そしてデリケートなナンバーが続く#10『When The Rain Comes』だ。このナンバーにもオーケストラが配置されているが、大仰なメロディでなく、アクースティックでしっとりとした雰囲気を切々と語るバラードで、こちらの方が好感を持てる。エコー処理を施した♪「la,la,la〜」という激甘なコーラスまでジンワリと取り入れられているため、オルタナ・ヘヴィナンバーとの差があり過ぎ、本当に同じアルバムに入っている曲かと耳を疑いたくなる。
また、ラストナンバーの#12『Nothing Compares』も#9と同様にドラマティックでハードなフックを投げつけてくる感動的なバラードである。ピアノ、オルガン、ストリングス、ハーモニーコーラスに、浮遊感のあるギター。これらを並べると、やはりアリーナ・バンドがシングルヒットさせていた、またはLAメタルバンドがシングル曲にしていたパワー・バラードを想い出す。Bon Joviあたりが演奏していても違和感がなさそうなところが凄いのかToo Muchなのか・・・。
他のナンバーもキャッチーでユニークなラインナップである。
#5『My Heart』はモダンロック風のシャリシャリしたドラム・バッキングに合わせて多彩なキーボードがノイズを入れつつ淡々と進行する、アーティフィシャルなナンバーだ。と思いきや、唐突に暑苦しいほどのロックビートを突き付けるミディアム・バラードである。このコーラス部分のサザンロック風の豪快さと、人口ビートの対比が面白い。
#7『Still Listening』は冒頭からダートでアーシーなスライドギターが炸裂する、サザン・ロックナンバーである。力強いドラムのビートがジャンピーなリズムを刻み、それにフリースタイルのピアノが加わり、周りを顧みない爆走ロックから一皮剥けた、ゆとりを見せるホンキィ・トンクな調子を転がす。ホーンとホールで録音したような音響を残す多人数のコーラスまで取り入れたパーティ・ロックである。このアルバムでは一番ルーツ・ロックとして楽しめる。
カリビアンなドラムからBeachboysのようなサーファー・ロック風のコーラスと明るさを見せてくれるのが、#11『Sing Praises』だ。必要以上にヘヴィなギターを使用せずに、ヴォーカルとコーラスで勝負しようとする気概はなかなか見上げたものである。このナンバーには海岸ロックだけでなく、サザン・トラッドのリズムまで感じてしまう。これまた面白いモダン・トラッドな曲だ。
以上、デヴュー時から紆余曲折を経て、ガッチリとしたルーツロック系のアルバムを完成に至った、初のスタジオ録音盤「Come Together」についてその曲目を解説してみた。
さて、Third Dayというバンドはアメリカ南東部のジョージア州出身のバンドだ。バンドの名前の由来は聖書の一節にある「On the third day Christ will rise again」=「主は三日目に甦り・・・」というジーザス・クライストの奇跡のエピソードから引用されたものである。まあ、クリスチャン・バンドなのだから当然かもしれない。
メンバーは最年長でも1971年、最年少になると1976年、平均的には1973年前後の生まれという、かなり若手に属するメンバーである。
バンドの始まりは、高校の同級生である1972年生まれの、リードヴォーカルのMac PowellとリードギタリストのMark Leeがピアニストを1名加えてアマチュア・バンド活動を開始したことからだ。この80年代の後半を嚆矢とするバンドはNuclear Hoedownというアクースティックのトリオだったそうだ。
高校を卒業後、このデュオにドラマーのDavid Carrが加わり、Davidの所属する教会を中心にクリスチャン・バンドとして演奏を継続していく。
Davidはレコーディング設備を所有しており、デモの録音を始める。この頃、臨時の雇われベーシストとしてTai Andersonがバンドに参加。彼を他の3人は正式メンバーとするつもりはなかったそうだが、最年長のTaiはバンドが気に入りズルズルと在籍し何時の間にか正式メンバーとなったらしい。
が、Taiはマネージメントや金銭感覚に秀でており、現在もバンドの財布を管理しており、思わぬ拾いものだったとMacは回顧している。(笑)
この4名を中心にThird Dayは結成され、1992年にカセットオンリーの「Long Time Forgotten」を、翌年に「Contagious」を発表。そして3枚目となる「Third Day」で漸くインディ・レーベルと契約し、最後のメンバーである2人目のギタリスト、Brad Averyがバンドに参加し、現在の5人編成となるのだ。
この1995年にリリースされた「Third Day」は宗教チャートで好評を博し、大手レーベルのAristaの眼鏡にかなったため、翌年の1996年に傘下の宗教レーベルであるReunion Recordsから新曲2曲とリミックスを施され、再リリースされることとなる。
ここから彼らの躍進が始まるのだ。2002年4月には、1999年の「Time」と2000年プレスの「Offerings:A Worship Album」の2枚がRIAAから50万枚を売り上げたという正式の認定を受け、ゴールドディスクを獲得する。メジャーのトップ200ではなく、ゴスペル・チャートでの売上だから、大したものだ。
またこの2枚のアルバムは「ベスト・ゴスペル」のアーティストとグループとして2年連続、計3回のグラミー賞にノミネートされるのだ。まあ、こんな腐ったアワードは眼中にはないけれど、人気の尺度を計るという側面ではThird Dayのステイタスの指標となるだろう。
特に、この2枚からメロディックなルーツ&モダンロックへと変化し始めたので、世間の評価もあながち捨てたものでは無いようでもある。そして、今作の「Come Together」が現在も順調に宗教マーケットでは売上を記録しているとのことである。
このアルバムのタイトルは、
「人間は絶対に仲良くやらなくてはいけない。人は独りでは生きてはいけない。」
という趣旨から「Come Together」と躊躇無く銘打った、とベーシストのTaiは語る。他にも信仰や神について述べているが、その辺はバッサリと割愛させて頂く。どうにもWorshipという概念は、研究するには面白いが、実践の信心となると筆者は否定的で引いてしまうのだ。
作詞は殆どがヴォーカルのMacが担当し、作曲は全てThird Day全員の名義という、共同でコンポーズを貫いている珍しいバンドでもある。
「曲を創り上げるのはとても難しい。僕等は多かれ少なかれ、日々の生活で起こっていることからインスピレーションを得ている。耳に入ってくることを興味深い話に書き綴ること。僕達はお互いに意思疎通をし理解し合いたい。心に浮かぶことを話し合えるように務めることで、僕達は曲を創っている。」
これ以下にも、沢山のコメントやインタヴューがあるけれども、殆どが「神様」が関連しているのでパス。(をい)
歌詞については言を持たないが、歌詞の意味を聴き取らなくても、そのハード・ドライヴィングなロックンロールの豪快さと、ポップなメロディで十分に音楽を堪能できるバンドである。
このファッショナブルとは程遠いメンバーのスナップを配したジャケットも、彼らの暖かい人柄と、雄大な南部の大地に木霊するような音楽を連想させて、かなり爽快である。
オルタナ・ヘヴィネスから始まり、次第にルーツロック/アメリカンロックという流行に左右されない音楽に回帰を始めているこのThird Day。
物凄い濃厚なSouthern RockやRoots Rockは苦手で、現代のロックバンド(と言われている)の音の方が良いというリスナーにも、ルーツなロックンロールが大好きな聴き手の、両者に対応が可能な微妙なバランスを有した、これから正常進化をするなら、かなり期待できるグループである。
入手は容易なので、ロックが好きでサザンロックも好きな人、カントリー系は駄目な人は是非手に取って貰いたい作品である。筆者が聴けるモダン・オルタナ風のロックが入った数少ないバンドでもある。
このペースでドンドンとリリースをし、バンバンとオルタナ・ヘヴィネスから遠ざかって欲しい。 (2002.5.25.)
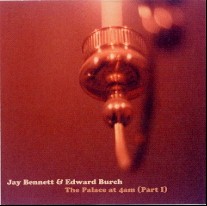 The Palace At 4 am (Part 1)
The Palace At 4 am (Part 1)
/ Jay Bennet & Edward Burch (2002)
Roots ★★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Alt-Country&Modern ★★★
You Can Listen From Here
まあ、Wilcoは逝って良し!!
今回の何とかHotelいうアルバムはボケ茄子そのまんまでんな。
筆者はどんなに凄い作品をこれまでにリリースしてきて、好きなアーティストでも、ファンを不安以上(寒)の奈落の底に蹴り落とすようなアルバムを出したら、因果地平の彼方へと飛ばされようと、貶してこき下ろして、トドメを刺します。
2002年、Wilcoは頭の螺子が外れて、その外れた部分が駆動部へと飛び込み全てをグズグズに破壊してしまったような最低の雑音を出しやがりました。最早、これはアメリカン・ポップ&ロックという名称は烏滸しい不燃物処理場直行ディスクですね。
前衛音楽とかエレポップとか、全く違う嗜好のリスナーに乗り換えたとしか思われない、裏切りの1枚。まあ、次からWilcoは買わないですね。
きっと何もしなくとも、自然に自己の骨格を支えきれず、このボケバンドは沈没・自壊するに違いないだろうから、生暖かい三白眼で見守ってあげませう。
謚(オクリナ)的BGMは、これしかありません。
♪「戦艦大和が沈むとき〜、山本五●六長官は〜蟹に・・ ゲフン、 ゲッフン!!(以下ヲ下劣につき自粛)
尚、軍艦●ーチで唄うこと。これ基本です。(何故に)
その、沈没を始めたWilcoからエスケイプを決め込んだのが、ここに紹介するJay Bennett & Edward Burchという何の捻りも無い名前を付けたデュオの片割れであるJay Bennetです。
が、彼は件のWilcoの4thアルバムに収録されたしょうむない曲の大半である8曲をJeff Tweedayと共作しているので、まあA級戦犯扱いしても良いですが、ここは
おまい、ちっとは反省しとかんかい、
故羅(コラ)!!
くらいに留めておきましょう。ま、Jay Bennetはこないなアホボケカス(以下好きなだけ罵詈雑言)バンドと縁を切り、このプロジェクトに乗り換えたこと、更にEdward Burchとのデュオが良い作品となっている、この2点で評価できる故に許してあげましょう。
加えて、確かに11曲中8曲に関わり、演奏とエンジニアも担当しているけれど、Jayは「このアルバムにはそれ程手を貸していない。」と主張しています。
ちなみに、Jay BennetはWilcoの脱退については、こうコメントしています。
「僕の脱退劇は、脱退という事件が可能な限り平和なものだったよ。勿論、全てが完璧ではない、ということは心に留めておいて欲しいけどね。例えば、仕事を辞める、彼女と別れる、遊び仲間から抜ける、そういった場合は常にこう疑問に思わないかい?『どうして、僕がやって欲しいことを皆やってくれないのか?』『どうして彼らにはこうして欲しいと思うのに、そう行動してくれないのか』ってね。
何事にも辞める・抜けるという場合は、怒り、傷つき、不安を持ち、後悔する−こういったことが常に伴うよね。でも僕の脱退の際は、こうしたネガティヴな感情は、僕がまだWilcoのメンツを好きで、彼らは彼らで上手くやって欲しい、という気持ちによってあまり浮かんでこないんだ。
僕は、僕のやりたいことができるんで、とても幸せだよ。」
つまり、脱退に際しては多かれ少なかれ衝突があったにせよ、口角を飛ばして喧嘩別れする程ではなかったということでしょう。
実際に、Jay Bennetは演奏にも参加し、曲の大半を共作し、そしてレコーディングエンジニアまで担当しているのですから、「顔も見たくない」という状態で録音をしていたのではないでしょう。
2001年の8月に、JayはWilcoを辞めています。レコーディングは終了していたのですが、レーベルから待ったが懸かったのが、丁度彼のバンドから去る時期と一致するのも面白いですね。
それはそれとして、Wilcoの4thアルバムを、契約先のRepriseがコマーシャルでない、と駄目出しをしたのは、
大変、賢明でした!!
タイトルまで決定していたアルバムですが、WilcoのフロントマンであるJeffは「そやったら、アンタらとは組まんわ。マスター返してよし。」と、よせば良いのにメジャーの契約を反故にしてしまいました。
それから、レーベルを捜す傍ら、新曲入りのツアーを始めましたが、その時点でJay Bennetは当然ツアーには参加していません。
彼はこうも述べています。
「『この前のツアーに君がいなかったけど、それじゃあWilcoとしては駄目だよ。』って言われるね。僕を評価してくれるのに申し訳ないけど、彼等は友人だし、僕の友人を貶したくない。僕は自分の元バンドを悪し様に言う知り合いが沢山いる。それでもう充分だよ。(笑)」
と、このようにWilcoに対して含むところを持っていないというJayですが、彼の脱退の動機は何だったのでせう?彼のコメントから引用してみましょう。
「約めて言えば、Jeffが話した内容はこうさ。『僕は僕のバンドを取り戻したい。』Jeffはこう言ってくれて良かったのに、思うに、彼はもっと婉曲的な表現をしたね。
『僕は円という存在は中心は1つだけだと思うよ。』」
こうもって廻った表現をされたら、
普通、暴れます。 (そうけ?)
流石に、JayもJeffが自分を中心にバンドを再編成しようと意図していることを気がついたようで、柔らかな追放に抵抗しなかったようです。これ以前にも、JayはJeff等によってやや蚊帳の外に置かれていたようです。
「レコーディングの時、僕は何故か疎外感を受けていたから、何か重大なことを言われそうなことに対して心構えができていたね。どうにも奇妙な雰囲気だった。」
まあ、本人が知らないうちに学校で村八分にされた(いぢめ、格好悪い)ってとこでせう。少なくとも気の弱い筆者は、こんなセリフを言われたら、泣いて先生に言いつけます。(卑怯モノ)
さて、どうみてもJeffに疎まれて邪魔者扱いされ、Wilcoを蹴りだされた(でも、本人は円満と主張)Jay Bennetですが、これまでの多彩なスタジオミュージシャンやプロデューサーとして活躍していた人脈がここで活かされます。
1991年に、Jayは出身地のシカゴで2つのプロジェクトに参加します。1つがパワー・ポップ&ロックのユニットであるTitanic Love Affair、もう一つがAlt-Countryのバンド、Steve Prideです。この時期にJayは同郷のミュージシャンであるEdward Burchと出会い、音楽的な趣味が似通っているという点で意気投合し、御互いの音楽活動を縫いながら曲を共作し始めます。
Edward Burchは、Jay Bennetのようなメジャーで著名なアーティストとは殆ど活動していません。アメリカン・ゴシックバンドのThe Handsome Family関連にクレジットが見えるくらいでしょう。
Jayはプレイヤーやプロデューサーとして、Sheryl Crow、Jellyfish、Titanic Love Affair、Tim Easton、Billy Joe Shaver、Tommy
Keene、Adam SchmittJeff Blackといったルーツ系からアダルト・オルタナティヴのアーティストと幅広く活動しているので、知名度では比較にならないですね。
が、JayとEdwardは一緒に曲を創り始めてから9年目になるそうで、Jayは非常に高くEdwardの才能を買っていることを常に広言しています。
このコンビは前述のSteve PrideのバンドSteve Pride And His Blood Kinの「Pride On Pride」(1999年)や、Wilcoの脱ルーツ化に伴いバンドを解雇されたペダルスティールプレイヤーのBob Eganのソロ作「Bob Egan」でコンビとして客演しています。
また、Edwardはこのデュオを立ち上げつつも、The Kennett BrothersというAlt-Countryグループや、ジャズバンドのThe Viper & His Famous Orchestraといったバンドにもメンバーとして参加するという多様にわたる活動を続けています。
このデュオはこれまでに仕上がった曲だけで50曲以上、創りかけのナンバーで20曲、アイディアでは数え切れないくらいの曲を寝かしているそうです。まあ、9年間のソングライティング活動は伊達ではないということですな。
Jay BennetのWilco脱退に合わせたようにレコーディングを始めたデュオは、シカゴのルーツロック、アクースティックポップを扱う良心的なレーベルであるUndertow Recordsからデヴューアルバム「The Palace At 4
am (Part 1)」をリリース。レーベルメイトにはNadine、Marc Chellickといった当HPでもレヴューしたアーティストがいます。
アヤシゲなポップモドキを扱うNonesuchレーベルしか契約してくれなかったWilcoとは選択の時点で差がついていると思います。
が、このデヴューアルバムは、ベッタリのルーツロックやAlt-Countryのアルバムではありません。ルーツやアクースティックの雰囲気は所々に漂わせていますが、どちらかというとModern Popであり、Jungle Popという表現がまさにピッタリのライトなポップ・ロックでしょう。
Wilcoの脱ルーツした「Summerteeth」に完全なルーツアルバムであった「A.M.」の味を加えて、クラッシック・ポップスで割ったようなアルバムです。
兎に角、これでもかというくらいの多種多様な楽器−特に鍵盤類・シンセサイザーは物凄いレパートリーに及んでいる−を殆ど2名が演奏し、ホーン、ストリングス、ドラムをゲストが参加で録音しているというスタイルです。
90年代のパワー・サウンドとも呼ぶべき、ドライヴィングでシンプルなギター・ロックという代名詞で語られる傾向にあるPower Popの趨勢からタイムスリップしたように、1960年代から70年代にかけての英国ポップやサイケディリック・ポップを彷彿とさせる味わいがあります。
このあたりはとても微妙で、メロディを重視しなくなると、単に変態的なWilcoの4枚目のような箸にも棒にもつかないようなアルバムになるのですが、JayとEdwardの音楽はメロディとして聴けるポップさがちゃんとあります。
必要以上にマイナー・キーを使ったり、陰鬱にしている作曲のヒネクレを感じることは、しかし非常に多いです。
実際にBennetもこのアルバムがDarkであることを認めています。
「うん。ダークだね。でも気を滅入らせるような暗さじゃあないだろう。むしろリリカルでエモーショナルな陰鬱さがあると思っている。反面キャッチーなメロディだしね。」
確かに、ポップであることは間違いないですが、スパンと切れ味の良いポップロックではなく、つかみ所の無いヘナヘナした流れが全体を支配しているように感じます。そのヘニャっとした感覚は、JayとEdwardの両者のリード・ヴォーカルにもそのまま当て嵌まります。というかこのフニャフニャなヴォーカルが全体の骨を抜いたような頼りなさをヒートしているようでもあります。
しかも、ヴォーカルにはパンチ力が皆無で、Jay Bennetが8曲、Edward Burchが5曲、2人のハーモニーヴォーカルが2曲ということですが
どっちがリード・ヴォーカルなのか
サッパリ区別がつかんですね。(笑)
まあ、この妖しげで頼りない声が、フワリとしたアレンジに乗っかって微妙な危うさと浮遊感を演出しており、それが魅力と印象に一役買っているのは確かなので、ヨシとしておきましょう。
また、50曲以上のストックから選んで15曲も収録していますが、
正直、もっと絞り込んで10曲く
らいにした方が良かったでせう。
70分近くも、このヘナチョコなヴォーカルと空中遊泳をしているアレンジの曲を聴き続けていると、かなりタレます。反面、良いナンバーも多いのですが。
例えば、#1『Puzzle Heart』はアクースティックでポップ、しかもアレンジが彼らの曲では相当シンプルなため、気持ち良く楽しめます。サラリと取り入れられたホーンも牧歌的で良いです。
ピアノとバンジョーといったアクースティック楽器に加えて、ベルやメロトロンという暖かい音色を発するインストゥルメンタルが共存している、Alt-Country風のナンバー、#2『Talk To Me』では雑多なアレンジをしつつもきっちりとしたポップ・ロックソングを創造してしまう2人の才能に舌を巻く思いがします。
オルガンと低音部で纏めたコーラスが、アーシーで明るいメロディに綺麗に溶け込んでいる#3『Whispers On Scream』もルーツ・ポップのアレンジにシンセサイザーを鳴らしてしまっているところがユニークです。
「Discovery」の頃のELOを即座に連想させるプログレ・古典ディスコ的なナンバー、#4『Shakin’ Sugar』は70年代サウンドのゴージャスさを感じます。
メロトロンの調子外れなラインがハードでダークなギターのリフとアンマッチなのが何故か印象に残る、ファンキーなサイケチューン#6『Drinking On Your Dime』。
Wilcoの「Summerteeth」にWilco作という名義で収録されていた、#7『My Darlin’』が実はBennet/Burchの提供であったと分かったのが、このアルバムのクレジットを見てからです。シンセサイザーを使いまくっている点ではWilcoヴァージョンと似通っていますが、よりナチュラルな仕上げをしているのでロアな手触りを持っていて、Wilcoよりも好感が持てます。
メロウなフュリューゲル・ホーンがバックで静かに鳴り渡る#10『Forgiven』は、フュージョン・ロック的な要素も匂わせます。
アクースティックで牧歌的な#14『Little White Cottage』やエレクトリック・フォーク風の#15『It Hurts』といったバラードはかなり捻りがありますが、ムーディで悪くないです。
が、全体的に後半が弱いアルバムですね。この捻りさや英国的な脱力感はElvis CostelloやNick Loweに通じるところがあると思われます。事実、Jayはヒントを得たミュージシャンにCostelloの名を挙げています。
と、少々大人しく、スノビッシュで一筋縄では行かないメロディ・メイキング、そして雑多過ぎる楽器とアレンジを詰め込んだアルバムですが、全体としてはアクースティックをベースに、モダン・ルーツ・フォーク・ポップのガラクタ箱といった感が強く、何が出てくるのか予想できない面白さがあります。
が、このあまりルーツテイストが強くない本作や、昨年未だWilcoに留まるJohn StirratのプロジェクトThe Autumn Defenseの「The Green Hour」のモダン・ポップな作風を耳にするにつけ、
誰がWilcoを脱ルーツさせたか?
と考えると、
おめ〜ら、全員共犯かい!?
という結論も出そうです。よってWilcoをクソ味噌に貶すのはお門違いかもしれませんが、このWilco関連の3枚の中では一番下の下が「Yankee Hotel Foxtrot」なのは絶対ですから、やっぱし貶めます。(を)
さて、「 The Palace At 4 am (Part 1)」というタイトルですが、Alberto Giacomettiという彫刻家の作品から引用したそうですが、Part
1という副題が付いています。
驚く無かれ、Jay BennetとEdward Burchは後3枚連作で「The Palace」シリーズを作成する予定だそうです。
まずは、この「At 4 am」のアンプラグ・ヴァージョン−ステージで演奏するバンド編成でのアレンジでのレコーディングをする「Palace 1919」が次のリリースということです。
・・・何だか、これ出すよりもその「1919」版アクースティック・アルバムだけで良くて、後3枚も要らないなあ、
ということは、心で思うだけにしておきませう。(ヲイ)(2002.5.28.)
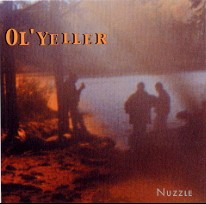 Nuzzle / Ol’Yeller (2002)
Nuzzle / Ol’Yeller (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Alt-Country&Garage ★★★★
You Can Listen From Here
#1『Out There』を聴いた瞬間、かなり驚いた。
Ol’Yellerのデヴューアルバムである、「Ol’Yeller」では殆ど聴くことが出来なかったキャッチーでアップテンポなロックナンバーが飛び出してきたからだ。
アクースティック・パンク/フォーク・ロカビリーという独特のスタイルで、1年の大半をツアーで費やすというHamell On Trialのリーダー、Ed Hamellへの敬意を表したナンバーである。Edの歌であるが、曲はガッチリとしたソリッドでスピーディなロックナンバーだ。
#2『Under The Tree』は泥臭くがなりたてるギターがハードなカントリー風に縦揺れするナンバーだ。このライヴ感覚一杯の切り落とした自然木の切り口のようにギザ付いた感触はメジャーなファッション・ロックでは出せないだろう。更にハードにストレート・バーボンな酔いどれギターが炸裂する#9『Making Enemies』は更にエッヂが尖っていて荒々し過ぎるナンバーだが、どちらもロックのロアな野太さを直に伝えてくれる。
#3『Burn』は、雄大なアメリカ中央部の平原を連想させる。適度にポップであり、ノラクラしたテンポはサザンロックの大らかさを兼ね備えているようでもある。が、もう少しコマーシャルなコードを組み立てた方がよりフッキーなミディアム・ロックになると思う。
#4『Expecting To Die』はバンジョーのゲスト演奏を加えた、カントリー・ロック。Richのファルセット・ヴォーカルが聴けるナンバーでもある。歯切れの良いリズムが刻まれるが、これまた未整理な曲の組み立てがやや残念なナンバーでもある。少しメロディの組み合わせに統一性がないので散漫に感じる。まあ、そのラフで即興的な部分が魅力でもあるのだけれども。
その未整理なメロディが面白く展開するのが、#6『Sulpher』だ。スローなブルースロックから、即効性のあるAlt-Countryなロック部分が交互に出現する野暮ったいロックチューンだ。パワフルなギターに引っ張られるAメロからトラッドなスローコーラスへと雪崩れ込む落差が強烈な印象を与える。
ローズ・ピアノが気怠げに音階を連ねていく#5『Passed Ambition』はメランコリーなガレージロックの静なる部分を引き伸ばして広げているようなスロー作。
軽快なテンポのポップロックなのだが、どこか抑えられた淡々としたメロディの進み具合が淡白なロックナンバーとしてしまって、やや惜しいナンバー#7『Summer Of Madness』の次がパワー・ポップ風の甘いコーラスを全体にハーモナイズさせ、フックの効いたメロディと潰れたギターのコラボレーションが胸を弾ませる#8『I Can’t Hang』。この爽快感あるチューンの連荘は絶妙な並びになっている。
ハーモニカとアクースティックギターが、そしてハーモニー・コーラスがアーシーなバラードを優しく演出する#10『We All Gotta Go』のさりげない叙情性は、このバンドがノイジーでタフなナンバーだけを泥まみれにして叩き付けるだけでないことを教えてくれる。最もほっとして聴ける曲でもある。
#11『Tag Along』は完全にReplacementsのフォロワー的な意図を曝け出したガレージでノイジーなパンクナンバーそのもの。もうこのあたりは卒業しても良いのでは。
続く#12『You Never Know』のリフも崩壊したようなガレージロック的ギターが震えるので、最後の2連はガレージ回帰ナンバーと思いきや、意外にゆったりとしたレイドバック感覚を刻むミディアムナンバーなので、安心した。が、かなりチョークを引っ張る潰れたギニョギニョなギターソロを入れているのが、このバンドらしいか。パンクというよりもサイケディリックなブロークン・メロディを思わせる最後のソロは正直しつこ過ぎる。まるでJohn Lennonの手によるナンバーのように曲が崩壊していく様は、ロックとはいえ、やや引いてしまう。ラストはもう少し丁寧な曲を置いて欲しかったけれど、これが彼らのロックバンドたる主張なのだろう。
何時までも若いつもりなバンドで、思わず苦笑してしまったりする。
2001年にその素朴なジャケットから発散されてくる、“これは田舎の純朴なルーツロックだよ〜ん”という臭いを感じて、バンド名をタイトルにした「Ol’Yeller」を買い求めた。
一言で評価すれば、「うん、ルーツロックでオルタナ・カントリーのアルバムだなあ。」であり、
二言で述べるなら、「悪くないけれど、あまり好みではないなあ。」であった。
何故ならば、「だって、あんまりポップでロックではないから。」、だ。
バンドの核であるRich Mattsonがミュージシャンになる際に目標としていたThe Replacementsのガレージ・パンク時代−初期のサウンドに通じる苦めのポップに陰鬱でハードなサウンドを叩き台にして、ルーツロックへの傾倒をより深めたような音楽性。
確かにOl’Yellerとしてのデヴュー作「Ol’Yeller」では、ガレージロックからルーツサウンドへの移行が顕著に感じられた。これは、Ol’Yellerを立ち上げる前に12年間もアンダー・グラウンドで続けていたユニットである、The Glenrustlesがルーツ的な音楽性をReplacementsのように有していたが、これまたReplacementsと同じくルーツの領域にドップリと漬かっていない音楽という方向性からの変革である。
Glenrustlesについてはこれから解説していくつもりであるが、ガレージロック的なルーツ、またはルーツロック的なガレージサウンド、とどちらとも表現がオルタネイト出来るバンドであった。
ここで話をOl’Yellerに戻すとしよう。彼等の1作目では、ガレージロックの暗く重い雰囲気がメロディの過半数を飲み込んでいたため、ポップ&ロックの側面としてよりも、ややアンダー・グラウンドな音楽性がRoots Rockの特性を主張しているようなアルバムだった。
いわば、ポップのコマーシャル性やロックの簡易なビートよりも、難解で鄙びた本来の意味でのトラッド音楽を求める。そういった意味におけるルーツ・ミュージックファンに歓迎されそうな、ルーツとしての“売り”を掲げていた1枚である。
基本的な目的が陽気で、ルーラル・ダンス音楽としての開放性を持つカントリー・ミュージックに連なる土着サウンドではなく、より内省的に、じっくりと土を踏み込むように唄われるカントリー特有のローファィな草の根サウンド。これがOl’Yellerに感じたルーツロックとしての希求対象の差異であった。
言い換えれば、カラリとした乾燥帯の埃っぽさを能天気に唄うか、それとも、汗臭く湿度を伴った大地でもがくべとついた重苦しさを拳を握り締めて唄うか、という違いだろうか。
無論、ポップ性が皆無であった訳ではなく、Glenrustlesから引き継いできたコマーシャルなコード進行はそこそこ残ってはいたので、完全にアンチ・ポップなカウンター・ファッション的位置付けにあるアルバムではない。程度の問題であり、ポップ度合いがダートでローファイな大地サウンドに印象を薄められているだけだ。
リスナーによっては、これでも過不足なくポップなアルバムだと感じる人もかなり存在するのでは、と推定すら可能だ。
兎に角、ガレージからルーツへと音楽の比重が変わったことにより、ロック的な要素が引っ込んだのだが、同時にコマーシャル性まで頭が下がり、ルーツと結託したダークで地味なセンスが強調された作品であったのだ。褒めれば、硬派で渋い。欠点を挙げるなら、ポップでないし、陰気な雰囲気が大勢を占めている、となるだろう。
しかし、各ナンバーのインプレッションで述べたようにこの「Nuzzle」は、Alt-CountryのAltの原点であるガレージ的なロックのノイズを再び取り戻し、加えて、Countryのキャッチーなラインを大幅に増量した2枚目となった。
終始一貫でポップな直線軌道を引いて行くような薄っぺらいパンク・ポップやエモ・ポップではなく、所々に電流を流せば抵抗値が物凄く高そうな、凸凹した赤土にウェザリングされた如くのルーツナンバーを配しているので、単調でないが重さが不愉快にならない重厚なAlt-Country Rockと呼ぶに相応しい。
このバンドはミネソタ州のTwin Cityという異名を持つ、ミネアポリスで活動している。ミネアポリスにはScott Laurent、Lee Rude、The Cultivators、嘗てのThe Jayhawks、Bellwether、Mason Jenningsというような、ポップとロックとアーシーの釣り合いが良好なルーツ&アクースティックなアーティストの宝庫である。
このOl’YellerもGlenrustlesからデヴューして14年目にして、漸くこういった筆者の私的名盤を生んだバンドに肩を並べるレヴェルのロック・アルバムを作成したと考えている。
ガレージに寄り掛かり過ぎたノイジー中心のアルバムでもなく、ルーツに足を踏み込み過ぎてしまいポップさが貧血気味のアルバムでもない。まさに、Minneapolis Well Balanced Rock n Rollの端に名を連ね得る1枚を届けてくれたのだ。
この域に到達するまでの道程は決して安楽なものではなかったようである。
最初に200本のカセットテープを作成してから、数々のメジャー・レコードレーベルにアプローチを繰り返したが、現在までに全く契約に成功していない。未だ、自主レーベルからの発表をしているのだ。
さて、このOl’Yellerが2枚目の「Nuzzle」をリリースするまでの14年を追ってみよう。バンドのソングライターであり、リードヴォーカリストであり、現在はリードギターも担当しているRich Mattsonが20歳でミネソタの北部にある、アイアン・レンジという如何にも工業都市っぽい街から、ミネアポリス出身で数々のアーティストに影響を与えたとされるReplacementsに憧れ上京(?)してきたことからスタートする。
1968年生まれのRichは、故郷で5年程、Importsという彼自身に言わせると「安っぽいカヴァーを演奏するつまらない」バンドを組んで活動していた。何とかReplacementsのようにロックスターとして成功したかったImportsのメンバーの意を汲んで、リーダーのRichが先行威力偵察として(謎)先に州都へと出てきたのである。
彼に続くようにバンドのメンバーが次々と合流し、彼等はベース、キーボード、ドラム、ギターのカルテット編成で“華の音楽の街”で活動を開始する。
が、Importsのメンバーは活動を開始後間も無くバラバラになり、Richはこの時からメンバーの流動を繰り返すバンドの中心になることを運命付けられたようでもある。
Importsとしての活動には何の未練も無かったRichは清々したとばかりにソロでアクースティックの弾き語りを開始することになる。が、彼のソロ演奏を聴きにクラブへと足を運んだメンバーと演奏をするうちにRichは再度バンドを結成することを思い立つ。元ImportsのベーシストRussell Burgamと、Richの弟であるGlen Mattsonがドラムを始めることでバンドが出来上がる。
この2人の名前、Glen−Russellをもじって、Glenrustlesが誕生する。1988年のことである。最終的に4ピースでスタートしたバンドは同年にRichの地下室に作ったスタジオで4トラックマシンを使い、1夜のレコーディングで、初めてのデヴュー盤を録音する。
当時、メンバー全員が、ミネアポリスの著名ロックバンド(Soul Asylum、Al Anderson、Mekons等)を数多く抱えていたメジャーレーベルであるTWIN/TONEと契約をしたくてデモ・テープを同レーベルへと持ち込んだが、全く歯牙にもかけてもらえなかった。が、この9曲入りのカセットは200本ダビングされ、ライヴ会場で配布され、地元情報誌に掲載されるという具合に知名度を上げる助けには貢献した。
バンドはローカル・サーキットを行いつつも、カセットのみの音源を発表していく。1991年には、バンド名の由来となった片割れのRussellが脱退し、3ピースになっていた。
ここから、Glenrustlesはミネアポリスから出て、アメリカ中をツアーすることを開始する。クラブサーキットといえば聞こえは良いけれども、実際はドサ廻りという表現の方が似つかわしい内容だったらしい。
最初のうちは、全くの無料でライヴを「やらせて貰った」ことが殆どだった。中ではたった25人しか観客がおらず、その半数がクラブの従業員だった、ということもしばしば。この時代のツアーをRichは“無益な繰り返し”と呼んでいる。
どのレーベルも興味を持ってくれず、ラジオでもオン・エアされることもなく、ギャラも貰えずにひたすらツアーを続ける。公園で野宿したり、真冬に移動用のバンの車中で寝る。こういったことを繰り返しつつ、最後の方では曲がりなりにも出演料を貰える位には状況が改善したそうであるが。
「俺達は若くて、馬鹿野郎で、アル中だったからね。何はともあれ、ライヴを続けた。頼れるのはロックンロールのスピリットと各地にいる友人だけだった。」
Richはこの1年をこう総括している。
1992年から数枚の7インチシングルをリリースし、演奏活動を続けていたGlenrustlesであるが、1994年にはGlen Mattsonが電波を受信したらしく、かなり奇矯な行動をとり始め、バンドは彼を外す。ここに至り、Glenrustlesの名前に関連するメンバーは存在しなくなる。もっとも、Glenは後に更生し復帰するが。
代わりのドラマーを加え、Richは約1年を費やして、初のフルレングスCD「Brood」を1995年にリリース。ここでも沢山のレーベルにデモテープを送ったが、何一つ反応がなく、自主レーベルのSMA Recordsからの発売となっている。
が、地元紙では評価の高いレヴューを掲載され、CDの作成費用は2ヶ月で完済できたということだ。これに勇気付けられて、バンドは1996年に「In Stone」を発表。が、ここでもマネージャ不在、何もかもバンドで全て行うという状況が続く。が、このアルバムはミネアポリスの年間ベストロックアルバムにノミネートされる等、少しずつ状況は売れない地方バンドから好転していくようだったが。
が、97年冬にに発表した「Fire At Night」は地元紙や地方紙のレヴューでもたいした評判を得ることなく終わっている。Richはこの3枚目のCDがかなり気に入っているとのことだが。
初めて2年を置いてリリースされた1999年の「Honey Grease And Neptune」は鍵盤やパーカッションをかなり積極的に導入した意欲作であったが、世間の反応は相変わらずだった。
この当時、Richは何時までも芽の出ないバンドの将来に付いて暗いヴィジョンを抱いていたようで、かなりテンションが下がっていたらしい。
「地方へ行けば行くほど、プレイするにつれて、観客が減っていく。俺はローカルミュージックのシーンで活動することに疲れてきていたよ。このままローカルなバンドとして演奏を続け、レコードと出していくか。それとも諦めてミネアポリスから出て行って新しい生活を始めるか・・・・・。」
バンドの他のメンバーも次第にハードなツアーを疎むようになってくる。
全体として4枚のアルバムを残しているThe Glenrustlesであるが、サウンド的にはルーツ色の強いReplacements、或いはSoul Asylumの「Soul Asylum And The Horse They Can Ride On」の頃のガレージ風ロックやポップのルーツ版という感じであり、確かに時代性からして大ブレイクするのは難しそうな音楽性だった。
インディ・シーンで確実に売れるので、メジャーへと上がり、ハードなツアーで広い範囲を廻りたくない、とインディに留まるバンドが増えている時勢に、「ロックスターになりたい。もっと売りたい。」とあからさまに広言するその上昇志向は賞賛すべきだ。また、安易にオルタナやモダンロックに転ばないでいる点も讃えたい。
が、やはりReplacementsにしても活動時代はそれ程ブレイクした訳でもないし、Soul Asylumも『Runnaway Train』がなかったらあそこまでメジャーで輝いたかは疑問だ。確かに、この2つのバンドは少なくともメジャー・レーベルを注目させ、契約を結びレコードをメジャーから出した、という点でGlenrustlesよりも上を行くだろう。オリジナリティを、独自のカラーを出せなかったGlenrustlesは良いロックバンドであったが、そこまでが限界のバンドだったかもしれない。
無論、メジャーにはGlenrustlesよりも全くレヴェルの低い音楽をやっている連中は数多く転がっているのだが。
煮詰まってしまったRich Mattsonは1999年の東海岸への小ツアー中に頭を切り替え、新しいプロジェクトを興そうと考えることで停滞した気分のリフレッシュを図る。
ここで、Ol’Yellerが漸く登場する。この名前は1996年にバンドのドラマーが脱退した時に思い浮かんだそうである。
「ああ、俺は27歳を超えてしまった。」と思ったことがOld → Ol’
ライヴの最後で常に叫んでいる自分を「叫ぶヤツ」Yell → Yeller
この2つを組み合わせて造語したのが、Rich Mattsonの新バンドである。
1999年にOl’Yellerを立ち上げたRichは、当初はGlenrustlesの2名のギタリストもメンバーに加えて、3本のギターでライヴ活動をしていたが、過密なツアーを行いたいRichの意向に反して、Glenrustlesのメンバーはツアーを忌避したため、結局Richは両方のバンドを掛け持ちすることにしている。
同じ会場で、Ol’YellerとGlenrustlesのショウを一度に行うことを年数回実施しているそうだ。RichはGlenrustlesの歌はGlenrustlesでしか唄わず、Ol’YellerのギグではOl’Yellerの持ち歌だけを披露する、と述べている。
現実的には活動中心は既にOl’Yellerに移っているようであるが、ツアーを続けている以上、当然の帰結となるだろう。
筆者としても、よりルーツロックに目を向けているOl’Yellerを歓迎したい。Glenrustlesで何曲か存在した、パンキッシュなポップロックも捨てがたいが、この「Nuzzle」のように分かり易いポップなルーツサウンドになるなら何ら未練はない。
2001年冬に、デヴューアルバム「Ol’Yeller」をリリースしてローカル誌レヴューを中心に好評を得たバンドは、その年の殆どをツアーに費やす。当初はカルテット編成であったバンドであるが、翌年の2002年の本作では3ピースになっている。
今までの2つのバンドによる5枚のCD中では、ルーツロックのアルバムとして捉えれても、ロックンロールのピースとして考えても最高の傑作である。
飾り気のない、荒削りなロックンロールは、1980年代のTom PettyやSoul Asylumの「Grave Dancers Union」より以降のルーツテイストが増加した作品を何処かに感じさせる。が、よりピュアで、未整理で、売れ筋から外れ、ロアなライヴ感覚を......というように、そういったメジャーなアーティストよりも良い所、劣る点を合わせてもなお、タフでタイトなルーツロックアルバムとして心にガッチリと杭を打ち込まれるような衝撃がある。
メジャーでの成功となると、しかし、このサウンドでは可能性が殆ど零に近い。しかし、めげずにチープなオルタナやミクスチャーに転向することなく、この方向性で突っ走って欲しいものだ。
きっと、いつか報われると信じたい。是非、応援していきたい。 (2002.5.31.)
 Just Now Finding Out / Fojimoto (2002)
Just Now Finding Out / Fojimoto (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Alt-Country&Modern ★★★★
You Can Listen From Here
正直、最初バンド名を見た時はFUJIMOTOと思った。フジモト、藤本?。(苦笑)(どっかの失脚した大統領に似てるような・・・)
であるからして、日本のバンドかもしれないし、最低日系のミュージシャンが在籍しているバンド、もしくは日本の文化に異様に興味を持つ親日家のバンドか、と勝手に想像しややイロモノ扱いで興味を抱いたのが、このFojimoto−フォジモトとの出会いだった。
非常に発音の語感が日本語に近くはあるが、このバンドの名前はFujimotoではなく
Fojimotoというのである。紛らわしいというか、偶然のなせる業というか・・・・・。
海外のポップロックの販売サイトに日本人の作品が並ぶ可能性は、皆無ということでもない。2000年に米国のポップシーンでは高い評価を得た、Yuji Onikiの例も存在することだし。そのため、漠然と日系のバンドと予想していたら、全く違っていた。まあ、違っていた方が良かったのだが。(笑)
名前の由来は、メンバーのひとり、ドラマーのJohn Fojitikにmoto−素晴らしい名前やね〜(アホ)−を付け加えたのだと推察している。いずれ、名の由来には彼等に確認をしてみたいのだが。
さて、些か日本語に類似した名前のこのバンドであるが、結成は2000年の夏。3名の20代後半のミュージシャンがバンドを結成した時に遡る。
Marwan Kanafani (Vocal,Guitar,Piano,Keyboard) , Ryan Waggoner (Bass,Guiatr,Vocal,Trumpet)
John Fojitik (Drums,Percussion,Vocal)
この3人がFojimotoを結成してから、1年半の期間を置いて漸くデヴューアルバムが発表された。
それにしても、リード・シンガーでありソングライターでもあるMarwanの苗字は、また妙に日本風である。KanafuneならぬKanafaniとなっているが、南太平洋の移民系のファミリー・ネームなのだろうか?また、他のメンバーもかなり変わった姓を持っている。Waggonerは独逸系の苗字としても、Fojitikとなると、ミクロネシアかアフリカ系の苗字のように聞こえる。Kanafaniもまた然りである。が、このバンドは純粋な白人種とは違い、間違いなく移民系の顔立ちをしているが、モンゴロイドの血は入っているようには見えない。東洋系のミュージシャンがインディバンドではそれ程珍しくなくなってきているが、このバンドはオリエンタル・カルチャーへの憧憬も歌詞には見えないので、単に偶発的なものだろう。
まあ、姓名のユニークさは音楽性の前には些細なことなので、これ以降は言及しないことにする。
この3人のうち、RyanとJohnはミシガン州の牧畜さかんな田舎街出身で、中学1年生からJohnの父親が組んでいたウェディング・バンド入りし、バンドマンとしてのキャリアをスタートさせている。それから12年間、リズム隊としてペアを組んで活動してきたが、25歳の時新天地を求めて西海岸はカリフォルニア州に活動拠点を移す。
サンフランシスコ近郊のバークレイという街で彼等は個々に演奏活動を開始する。無論、JohnとRyanの間には親交があったのだが。その時にJohnは友人であるDavid Simonというベーシストを介して、Marwan Kanafaniという5歳年下のミュージシャンと知り合いになる。
この3人で、Marwanの担当するハモンドB3とフェンダー・ローズピアノを中心としたポップバンド、Solarcaneを結成し、1999年に「Book Of Alibi」という15曲入りのフルレングスを発表する。このアルバムはロックンロールやルーツロックのゴツい踏ん張りはあまり感じられないが、優しくふんわりとした音創りを中心とした数十年の時を戻して録音したような、1960年代ポップスの香りが漂う佳作である。
ルーツロックというよりも、クラッシック的な英国風ポップのダラリとしたルーズさが漂う感じなので、興味のある方は手にとっても良いと思う。断っておくと、他にもSolarcaneというオルタナティヴ系のバンドが幾つか存在するようだが、このカリフォルニアで編成されたバンドは、かなりユニークな音を出すという点で、かなりの独自性があったことは確か。
そのSolarcaneは2000年終わり頃にオフィシャルサイトが消滅し、解散したのだろうと漠然と予想していたのだが、まさかメンバーが新しく結成したユニットがFojimotoとは思わなかった。筆者はFojimotoがSolarcaneの次代バンドとは知らずに、「西海岸に良いルーツロックのバンドがいる。」という情報と彼等のHPにアップロードされた数曲のサンプルのみで、フルレングスアルバムを待っていたのだ。
どうやら2000年にSolarcaneが解散。元メンバーであったMarwanとRyanが、Ryanの友人であったJohnと親交を深めるうちに自然発生的に発足したのが、このFojimotoらしい。2000年の結成から、このトリオはサンフランシスコ周辺の所謂ベイ・エリアのクラブシーンでギグを繰り返しながら、Splintered Tree、Luster、John O’Brien And Priscilla Ederleというベイ・エリアの先輩ローカルバンドに評価され、ジョイントライヴ等を行うようになる。
その一方、2001年にはレコーディングに取り掛かる。
「僕たちは、顔も知らない何処かのリスナーに『ギターのチューンが歪んでいるし、ヴォーカル・パートを撮り直すべきだね』とか言われたくなかった。だから、時間50ドルのスタジオを3日間だけ借りて10曲を録音し、何の手直しもせずに発売するという選択はしなかった。」
とメンバーの意見が述べられているように、Marwan達は貯えをはたいてホーム・スタジオを建てる。
「自己満足の極限だけど。」とやや自嘲気味な感想を洩らしているものの、録音機材とスタジオを買い揃えた彼等は試行錯誤を重ねつつ、録音技術やミックスダウンを独学で、また親交のあるバンドからアドヴァイスを受け、習得していったそうである。
ポータブルの録音機器とミキシングボードを購入したので、敢えてスタジオでの録音に拘らなくて良くなったためか、ドラムパートは友人宅で音響効果を考慮して録音され、それ以外の楽器とヴォーカルをスタジオでオーヴァー・ダブしているとのこと。
かなり、インディバンドとしてはサウンドのミキシングとプロダクションに留意して少しでも良い音質を届けたいと考えている、結構希なバンドであると思う。インディのバンドには4トラックで殆ど手を加えずにライヴ形式で録音した音をそのままCDに載せる連中が大勢を占めているだろう。
それは、特別否定すべきことではないが、やはり装飾過多まで行っては困るが、ある程度綺麗なエンジニアリングとミキシングを施してくれた方が良いに決まっている。音質に付いては、率直なところメジャーに及ぶべくもないけれど、確かに丁寧に録音され、構築されていることを即座に感じ取れるアルバムにはなっている。
この点はその誠実さを素直に評価したいと思う。
また、東京で仕事をしている友人達に、このアルバムのジャケットを依頼して、この趣味の良いサンフランシスコの地図を複写したようなジャケットを作ったようだが、モチーフとなったのは筆者の心の父、アーネスト・ヘミングウェイの名作『老人と海』だそうである。
『老人と海』の舞台はカリヴ海であるが、確かにこのややクラシカルで色褪せたような配色は、『老人と海』での南国の海の世界を連想させるようなところがある。
Fojimotoは自らの音楽性を
「悲しく、メランコリーで、意気揚揚としていいて、暗く、そして嬉しげという全てを同時に含んでいる」
と極彩色のように、オールマイティ性満載のように、と自己分析しており、このジャケット絵はそれら全てを暗示してくれている、と賞賛をしている。
確かに、メランコリックな印象と地味な色彩のため枯れた音楽性は漠然と想像できる範囲にあるけれども、“海”と“地図”というモチーフに対しての様々な感慨の内、全部をこのアートワークに感じるというのは少々過大な想像力を必要とするのではないかと考えている。
が、この地図画のタッチからは、最低、ゆったりとした落ち着きと、優しげな凪の海の広大さ、的な要素を感じることができると思う。
はたまた、プラクティカルな俯瞰図に暗示されるような冷静さを絵だけ見れば覚えることはあるかもしれない。
では、実際に収録されている10曲はどのような感触なのだろうか。以下、順を追って見ていきたい。
原色を全く私用していないフロント・ジャケットに見られるように、暗さや陰鬱というものは、筆者的にはあまり感じることはできなかった。哀しさとある種の淡々としたクールさはなきにしもあらずだが。
それよりも面白いのはこの収録されている曲が綺麗な塊に分割されていることだと思う。
筆者的には、このアルバムは3つのパートに分かれて成り立っている、と分析をしている。以下、勝手に切り分けた部分を箇条書きしてみる。
■第一部
#1『Lonely Daughter』 〜 #3『Nostalgia』・・・レイドバック・ミュージックと多彩な楽器のフューチャリン
グが楽しめる。
■第二部
#4『Summer Day Parade』 〜 #7『Map』・・・ロックンロール・ミュージック。軽快なベイエリアサウンドと
ハードなオルタナ&モダンの影響があるナンバーが続く。
■第三部
#8『Dry』 〜 #10『Upside Down』・・・西海岸サウンドの展示場。カントリーロックからバラード等、爽や
かでアダルト・ロック的な要素が強い。
やや、無理に分割してしまったと思わないでもないが、概ね上手く3部に分けることが可能だ。つまり、アルバムを聴く場所によってかなり受け取れる感覚と音楽性が違って耳に入ってくる。
別な表現を用いれば、多彩な曲を同系統で3つの集合にしたとも云えるか。普通同じタイプの曲を纏めて続けるということは単純な曲しか作れないバンドには多いだろうが、Fojimotoのように実力があるグループは現実問題としてかなり多彩な曲を届けてくれるバンドなのであるからして、このアプローチは面白い。
意図して3部作的な分類をしたか、と問われれば多分違うだろうけど。(苦笑)
まず、第一部のレイドバック=オルタナ・カントリー/ルーツポップのパートだが、ここでかなりのアレンジの冴えと楽器を使いこなすFojimotoの力量が見て取れる。
#1『Lonely Daughter』ではペダル・スティールのような浮遊感のあるギターの弦がホワホワとした暖かい感じを出しているが、この音はひょっとしたら、まるでBostonの『Amanda』で聴くことができるシンセベルのようにくぐもらせたアレンジのローズピアノかもしれない。全体的にややウエットなポップメロディに西海岸のバンドが得意とするハイトーンのコーラスが絡まる、カントリー風のナンバーでこの「Just Now Finding Out」は大人しく始まる。
#2『Easy To Lose』もアーシーなアクースティックギターとピアノの綺麗なユニゾンのリフからスタートする、優しい雰囲気を湛えたポップナンバーである。やや、弱いとも思えるくらい繊細なMarwanのヴォーカルとメンバーのコーラスが自然な厚味で流れていくところは、これまた西海岸カントリー・ロックを思わせる。まるで、Buffalo Springfieldを思わせるようなポップ・バラードであり、かなりの数のギターとヴォーカルが重ね撮りされているのが良く分かる。Fojimotoがスタジオ録音に拘った成果が出ているナンバーでもある。
が、ここまで手の込んだアレンジをしてしまったら、3ピースではライヴ再現ができないのでは、と思うくらいにオーヴァー・ダブが結構凄い。
#3『Nostalgia』はタイトルが示すように、かなり哀しげにたゆたうバラードである。切ないトランペットをバックにフューチャーして哀歌的に暗めのカントリー・バラードを予想させる始まりを見せるが、広大な音響を空間に満たすような盛り上がり方をしていく。が、終始マイナーな調子のバラードのため、明るさを殆ど感じさせずに切々とした哀愁が漂う大作となっている。パーカッションもかなりユニークなアレンジをされていて、面白い素材が使われているようにも思える。
この前半のしっとりとした展開から急変を迎えるのが、#4『Summer Day Parade』以降である。如何にもサンフランシスコのベイ・エリアのバンドという、パンチの効いた爽快なポップ&ロック・チューンの#4が、突然アルバムを支配していたレイドバックでデリケートな流れを引っ繰り返してしまう。
#4は「夏の日のパレード」の題名に相応しい、元気印なパワー・ロックであり、ルーツらしさよりも普遍的なアメリカン・ポップの名前が相応しいドライヴィング・ミュージックである。軽快に青い海を滑るクルーザーのように吹っ切れたロックである。
続く#5『Sleepwalking』は唐突にヘヴィなオルタナ風ギターが押し寄せてきて吃驚するが、メロディ的にはそこそこ正道なナンバーであるため、聴き苦しいところはそれ程無い。結構チョーキングで引っ張り、ベントなギターワークを見せる部分がオルタナティヴ風でもあるけれど、ヴォーカルとファルセットなコーラスがポップなラインを歌ってくれるため、それほどディストーションが目立つことなく、ヘヴィロックというよりも骨太なナンバーという印象を濃くしている。
#6『Zig Zag Kid』も重いギターリフからスタートするナンバーであるが、即座にアダルト・コンテンポラリー風のキャッチーで分厚い演奏とコーラスが入るので、重いというより手応えの存在するパワフルなロックナンバーと表現した方が良いだろう。#4と同じくらいにポップなナンバーであり、斬新さは無くともラジオ向きの聴き易い曲である。
この#6もルーツさはそれ程自己主張が強烈ではない。アリーナロック的な側面も垣間見せる隙の無いアレンジがたっぷりとしたナンバーで、ルーツロックと産業ロック的な要素が同居しているミディアムなロックチューンだろう。
やや、調子を外したヴォーカルと、歪んだギターが崩壊気味に混ざり合っていく#7『Map』はかなり現代的なロックの影響を受けた世代性を思わせる。アナログ的に鳴らされるシンセサイザーにしても、ヘヴィにのた打ち回るギターの音色といい、これまでの展開からはかなり外れて浮いていると思わせるナンバーでもある。ヴォーカルのMarwanの声も通常のトラックより鼻に懸かったようであり、消化不良な滞りを匂わせている。
そして、ロックでヘヴィに上昇した中盤から、またもアクースティックなウエストコースト・ロックに回帰していく後半になる。
#8『Dry』はペダル・スティールをゲストに迎え、ピアノやアクースティックギターを淡々と配置して、静かに歌われる海岸ナンバーである。レイドバックというよりも、西海岸ミュージックの線の細さが目立つナンバーである。まったく動の部分が無い静のみで構築された曲であり、#7からの落差によってそれなりに浮き上がるナンバーだが、繋ぎのトラックという印象は拭えない。
というのは、エモーショナルでノスタルジックな甘さのある、これぞWest Coastという#9『Elizabeth』が素晴らしいバラードだからだ。オルガンを効果的に鳴らしつつ、メジャーなコードを惜しげも無く使うバラードである。美しいコーラスとアクースティックなアレンジ、そして手で掴めば掌に残りそうな存在感を大気中に放出しているハモンドを中心にして曲を魅せてくれる。特にエレキギターの泣きや大仰なアンサンブルを使わずに、ここまで玲瓏としたバラードを聴かせるとは、もう恐れ入るだけである。
#10『Upside Down』はとてもバランスの良いルーラルとアーバンロックの中間点を、そしてエレクトリックとアクースティックの分岐点上を、フックの効いたメロディで爽やかに流してくれるロックナンバーである。特別名曲という訳でもないが、かなり存在感のあるナンバーとして耳に馴染むのは不思議である。曲の始まりと終わりに多彩なパーカッションをややルーズに取り入れているのは何故か分からないが、まあ特徴的ではある。
以上、10曲。前半のカントリーロック的な展開から、モダンロックやベイ・エリアサウンドまでを網羅して、アクースティックとエレクトリックの折り合いを微妙に釣り合わせているグループの好盤について述べてみた。
全体として、中庸的な故に、目立たずに終りそうな作品であるが、じっくり聴くととても丁寧に創り込まれていることがじんじんと心に伝わってくる。
こういった良心的なポップロックがもう一段階レヴェルアップすると大名盤になる可能性があると思う。で、Fojimotoという名前のバンドはその大化けする才能は十分に秘めているし、このデヴュー作でもその片鱗を見せているのは確かだ。
その、アレンジとサウンド・クリエイションへの関心の深さは、将来的にメジャーになったとしたら間違いなく財産となる筈だ。もっとも、現在の腐敗したメジャーシーンでスポイルされるくらいなら、地元の人気バンドであって欲しいとも願ったりするのだが。 (2002.6.8.)

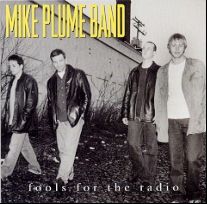 Fools For The Radio / Mike Plume Band (2001)
Fools For The Radio / Mike Plume Band (2001)