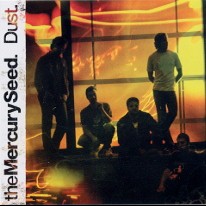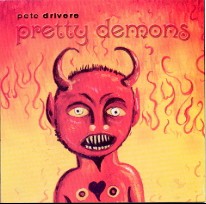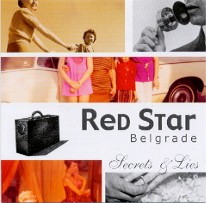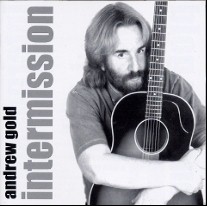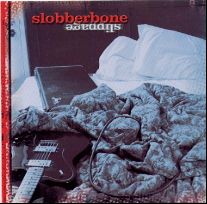 Slippage / Slobberbone (2002)
Slippage / Slobberbone (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Southern ★★★
You Can Listen From Here
Slobberboneというネーミングは、かなりネガティヴというか汚れ物というか、綺麗ではない。
Slobberという単語は名詞かつ動詞であり、「涎、涎でベトベトする。」とか「感傷的なことを言う。」更に「猫可愛がりして駄目にする。」という意味を持つ。
で、SlobberなBone=「骨」となると、「涎まみれの骨」という直訳になるのだが。実際に命名の意味も直訳に似たり寄ったりだったりするのだ。
SlobberboneのリーダーにしてソングライターのBrent Bestは、バンドの命名に付いて以下のように説明している。
「僕等がバンドの名前を決めた時のことを思い出すと、笑ってしまうよ。その時、僕は以前バンドに在籍したベーシストのLeeと一緒に裏庭の芝生で駄弁っていた。で、そこではしょっちゅう犬がでっかく古ぼけた骨を噛んで遊んでいたんだけど、僕等はその様子を“Slobberbone”−ヨダレだらけの骨、って子供がお気に入りのシーンに勝手な名前を付けるようにして呼んでいたんだ。
で、僕はある日こう言った。『これはきちゃなくて、しょうがねえスロバーボーンだなあ。』
するとLeeが叫んだ。『それだ!』ってね。こうしてバンドの名前はSlobberboneになったんだ。その時はSlobberboneは別に毒にも薬にもならない人畜無害な名前と思っていたんだけど・・・・・。得てして、普通に決めたことは、人々がそれに対して注目するようになると、色々な意味を暗示するようになるものだね。」
確かに、“涎だらけの骨”というセンスはお世辞にも良くない。しかし、Brent Bestは改名することは考えていない模様である。
「僕は最初から言い続けているんだが、もしこのマイナスイメージを捺されているバンド名を乗り越えることができるとしたら、それは真実音楽的に素晴らしいものを成し遂げた時のことなんだ。」
まあ、命名の過程と動機はどうであれ、Slobberboneという看板が良いバンドの代名詞として認識されるなら、それが良い音楽の創り手を意味することになるのだから、名前はその程度のものだ、位にBrentは見なしているようだ。
つまり、自分もリスナーも満足できる作品を創り続け、提供し続けることを目標にしていると受け取れる。
こう率直に述べる代わりに、些か麗しいとは云えないネーミングをネタにし、且つ創作姿勢を前向きに保ち続けるためのモチヴェーションとしていると推測される。
これはこれで、非常に立派な心掛けであるとは思う。
が、肝心の音楽の質はどうなのだろうか・・・・・・・・。
正直、これまでの3枚のフルレングス作を含めて、Slobberboneのアルバムはどれもバンド名の下品さを打ち負かすくらいの素晴らしいロックアルバムだ。
と断言できれば問題ないし、そうしたいのだが、これまでの3作全てを通して、ロックの名盤と呼ぶにはやはり抵抗がある。このアルバムが本作「Slippage」を聴くまでは、筆者的にSlobberboneとしてはベスト作だという判定があったデビュー作の「Crow Pot Pie」を聴き直してみても、ロックの誉れ高い名盤とは口が裂けても云えない。
というよりも、Slobberboneはロック名盤と評される類の音を作成できるバンドではないとさえ考えていた。
以下、各アルバムの簡単な印象と評価を思いつくままに挙げてみよう。
●「Crow Pot Pie」(1996年リテイク盤)
率直に述べれば、ゴリゴリのカントリー&カントリー・パンクアルバム。
シンプルというよりも暴力的なくらいにルーズ。小技を一切使用せず、ただ濃厚でグチャグチャしたハード
メタルの要素も入れたルーツ作。ロックンロールというよりもハードパンク時々カントリー。
まあ、田舎臭い粗野な兄ちゃんが作業用トラックをチューン・アップしてダートを走り回っているような音楽。
カウパンクというカテゴリーに入れた方がしっくり来るだろうか。Wild Wild Southという感じ。ひたすら濃い。
<評価>
突っ走り過ぎ、やり過ぎ。必要以上に単調なハードパンクなカントリーアルバム。不器用さが突出し過ぎて
いるが、ここまでやりたい放題にやってくれるとそれが痛快でもある。しかし名盤には程遠いし、それを意図
もしていないだろう。
●「Barrel Chested」(1997年)
前作の暴れん坊でスマートさのカケラも無い粗暴なカントリーパンクの割合が相当減り、変わりに濃さでは
全く同等のレイドバックなスローソングや、サザン・カントリー風のナンバーを絡めて強弱を付けたアルバム。
これまたレイドバックを狙っているのだが、Brent Bestのガラガラ声とノイジーで特濃トンカツソースよりも
味のしつこい演奏のため、煮詰めた出し汁に醤油と砂糖と味醂を加えて更に煮こごりにしたようなベタベタ
感山ほど。しつこいくらいに粘つく南部カントリーロックのアルバムに落ち着いている。
<評価>
デビュー作でトラクターに乗ってダートを転げ回っていた兄ちゃんが、少しは緩急を付ける事を学んだ感じ。
急激に渋さを狙って背伸びしたが、その渋さを際立たせる以前に自らの個性が強過ぎて、渋さよりもクドさが
突出してしまった。田舎モノがローギアの使い方を覚えて田舎道を走るにはダートにしても道路にしても不自
由しなくなった程度のテクニックは得た、というアルバム。これまた濃過ぎて口に合わないリスナーは多いだ
ろうと予測。
●「Everything You Thought Was Right Was Wrong Today」(2000年)
唐突にこれまでのゴリゴリな音楽性から脱却を図ったようなアルバム。1枚目は殆ど3ピース演奏。2枚目で
ドブロギターやフィドルを加えてルーツというテーマに取り組んでいた姿勢は測れたが、そこから更に普遍
的なロック音楽に昇ろうとしたアルバム。ホーンやキーボードを加え、アルバム前半ではPop/Rockへの憧憬
を隠そうとしていない。それとは対照的に後半はじっくりと乾いたテキサスルーツを搾り出すようなアクーステ
ィック音楽を模索。突如スマート化を目指したアルバムだ。
<評価>
これまで業務用のトラックや作業車しか運転してなかったアンちゃんが、いきなりスポーツカーを買って格好
を付けようとした背伸びというか無理が見える。ロックンロールとルーツの二極化は前作を継承して変化を加
える努力はみれる。が、所詮地下足袋に作業着でフェラーリを運転するのが似合わないように、ここまで優
等生を装っても、全然決まってない。寧ろ外している。
トラッカーは粗野さと勢いをガソリンにしてオラオラとトラック転がしている方が向いているなあ、という印象を
受けた作品。世間的な評価は高いが、理解不能。力押しのゴリ技が薄れてしまったのはマイナス。
一言、「似合わないからやめれ!」
となっている。特に3枚目の長いタイトル「Everything You Thought Was Right Was Wrong Today」はロックバンドとしてやりたいんだけど、やっぱり硬派なカントリー路線がないと駄目かなあ、という迷いが見れた。筆者には少なくともそう思えた。バンドの底力があるため、それなりに纏まっているがやはり中途半端なルーツロックモドキとカントリーロックモドキが混濁した名盤ならぬ迷盤。
何時までもパンクやメタルルーツでブイブイ言わせていても、所詮パターンに変化が付けられなくなる時はやってくるだろうから、何とかカウパンクやカントリーロックの既存スタイルから脱却を図ろうとしているのは理解できた。
しかし、方向性の定まりがいまいち不明瞭で、手放しでは誉められなかった。極端に濃かった2枚目までの作風の方が極端な分アクは強いけどそれが個性として光っていることは確かだった。だのに、妙にソフィスティケイトを狙ったため、アクの強さが不完全に残っていて、どうにもSlobberboneらしいやんちゃぶりが薄れたように感じたものだ。
であるからして、この4枚目も物凄い期待を抱いてはいなかったのだ。期待でなければ幻想か。
しかし、このアルバムは予想を覆したRoots Rockとしてかなりの王道さを有したものになっていたのだ。
結局、作業着に演歌、煙草と酒のつまみが友達であるトラックの運ちゃんがフェラーリに乗ることは浮いていると理解し、四輪駆動の無骨だが信頼性の置けるオフロード車を購入した、という結末だろうか。
要するに、自らの分をわきまえた上で、最良のパフォーマンスを発揮できる路線を走り始めた、こういうことだ。
これまでガリガリと氷の塊を噛み砕くの如きゴリゴリのハードロックにカントリーの影響がかなり混ざっていたのだが、この「Slippage」からは、相当数のカントリー臭さが抜けている。
更に、Bottle Rocketsよりも濃密だったパンクカラーもそのスピードの変換先をロックンロールに進めている。パンクをパンクで表現、という単純変換ではなく、パンクをロックンロールとして表わすことに成功している。それはこの4枚目のアルバムがCountry Rockではなく、Alt-Country、それ以上にSouthern Roots Rockとして成長を遂げたことを意味するものでもあるのだ。
しかし、ロックアルバムとしてレヴェルが上昇したことが即ち3枚目で見せたようなアプローチに繋がるかというと、決してそうではない。高級車を運転しているが、パッチに腹巻きといういでたちのおっさんではサマにならないという例を音楽にシフトしたようなソフト化を図った3枚目のような小手先の小細工は選択されていない。
生のままのロックンロールはそのままに持ち込んでいる。元来Slobberboneが武器として使用してきた暑苦しさ満載のパワーとワイルドさをよりストレートなロックンロールとして投げつけてくるのだ。
方向性としては1stと2ndから濃過ぎる野暮ったさを蒸発させた後にロックンロールを触媒に融合させた。このような音楽性となっている。
まだまだ、少々やり過ぎなハードでパンキッシュな演奏も見られるけど、決してToo Muchな境界線を大幅に越えないようにコントロールすることを学んだように思える。やり過ぎでお腹一杯なCountry/Punk Rockではなく、ハードでパンチ力のあるSouthern Rockとして容認できる程度まではバランス感覚が出ている模様である。
何よりも、ポップ感覚がこれまでで最も良質に配分されている。渋さを狙いに走った余り、折角のキャッチーさが活かされなかったり、ハードでメタリックな曲のためにポップさが喰われてしまっていたことが過去のアルバムには幾つも存在したが、今作ではまんべんなくポップで即効性のあるメロディが確かな手応えとして感じられるのだ。
ポップさはレーベルメイトであり、頻繁に比較対象とされるBottle Rocketsが「Brand New Year」でオルタナティヴなハードバンドに沈没したこともあるのとは対照的に、ハードでゴンゴンな音楽を踏み鳴らしながらも、しっかりとキープしていたバンドではあるが、今回は何と言ってもカントリーやパンク、メタルサウンドへの極端な傾倒が減ったことが大きく影響を与え、よりキャッチーでメジャー感覚のあるメロディを浮き上がらせているのだろう。
しかし、スマートな音楽を追求することに代わり、少々難解な構成を主眼にした音楽性への追求が特にアルバムの後半で見られるので、まだまだひと波乱ありそうなバンドであるようにも漠然としたものを覚えるところはある。これは各曲の感想の段で述べよう。
楽器を色々と使い過ぎてしまっていた3作目と比べて、「Slippage」ではピアノ、オルガン、アコーディオン、その他の鍵盤をプレイするサポートミュージシャンがバンドの4ピースに加わっているだけがメインの演奏となっているのも、小細工が似合わないSlobberboneにはプラスに効能していると思う。
1曲でドブロ、もう1曲でUkalyという名前の楽器−これは寡聞にしてどのような楽器か分からないが、パーカッションだろうか−を担当するゲストが参加しているだけである。
殊にBrent Bestのガラガラガラなシャウト以外は向かない金剛ヴォーカルにはなまじカラフルな要素を持ち込む音は不整合を起こし易いので、この4ピース・プラス1という演奏隊の編成はベストだろう。
加えて、プロデューサーはRolling StonesやTom Petty And The Heartbrakers、Bruce Hornsbyのエンジニアを担当したり、John HiattやRoy Orbinson、Stevie NicksやEvery Brothers、オルタナティヴ音楽のCrackerという多くのヒットミュージシャンのプロデュースを手掛けているDon Smithがクレジットされている。
この癖の強いバンドをモデレイトしてバランスを取らせたのはDon Smithのメインストリーム音楽をスルーしてきた経験も一役買っているのは間違いないだろう。しかしながら、少々バランスを逸して実験的に幅広い音楽を選択させている点も見える。これはDon SmithがSlobberboneの将来性を考えて、新しいモノへの挑戦を薦めたのだろうか。
オープニングナンバーの#1『Springfield,IL.』から、これまでに見せたことの無かったRock’n’Rollとして形が整ったメジャー感覚がしっかりと植え付けられている。Brent Bestのヴォーカルは相変わらず骨から削りだした武器のようにプリミティヴだし、バンドの演奏もハードで尖った暴走感はあるものの、パンクでもカウパンクでもなく、ロックナンバーとしてキャッチーに、またスピーディに仕上がっている。
#2『Stupid Words』のハードでノイジーなロックチューン、#3『Write Me Off』の南部風Power Popと呼びたくなるようなタイトでコマーシャルなスピード・サウンド、と序盤は圧倒されるようなパンキッシュでサザンなナンバーが続く。
#2でしっかりとルーツ感覚の尻の座り具合を表現していることも、#3の暴れ具合も以前のような荒削りだけで押し捲るだけでなくなり、しっかりとメロディを殺さずに走っているところ等にバンドの成長を感じる。Soul Asylumの中期を少し整理した風のナンバーだろうか。
#4『Sister Beams』で漸く、ロックのスタンピードに歯止めが掛かる。ウィルツアー・ピアノとピアノを出過ぎず、引き過ぎずに配したこのバラードは、Brentの酒焼けヴォイスのためメロディの割には重く、美しさも何割か減少してしまっているが、これまでに表現できなかったウェットな感覚を打ち出せたナンバーだと思う。
#5『Buchers』も#1に負けないポップさを持ったロックナンバーであり、乾いたドラムと泥臭いギターの音がそれぞれ印象的な曲だ。このナンバーでは機械処理として抑えられてしまっている濃い目のヴォーカルが、良質なメロディに負けているくらいである。
#6『Sweetness,That’s Your Cue』は如何にもSouthern Rockを代表するような土臭さとハードなドライヴ感覚が主役を張っている。Brentのハーモニカがアーシーな色合いを加えるのに良い働きをしている。
#7『To Love Somebody』は言わずと知れたBee GeesのNo.1ソングのカヴァーである。原曲のアダルト・コンテンポラリーなアレンジは全く遠くに追いやられ、テキサスのロックバンドという出自が丸分かりな重量感の溢れるロッカバラードとして表現されている。が、ここにピアノを入れているのが、SlobberboneとしてPop/Rockの普遍性を意識してきた証拠だろう。単にラフな南部インディサウンドに落ち着かない可能性を感じる。
Neil Youngのややエキセントリックなルーツ感覚を匂わせる#8『Find The Out』はかなり暗めでありながら、プログレッシヴなピアノがポンポンとリズムを刻む、Slobberboneとしては初の境地を開いただろう新しいタイプのナンバーである。
よりハードで土臭い、しかも間歇的に取り入れられるキーボードの音がブリティッシュロックを連想させる#9『Down Town Again』もやや複雑なナンバーである。この2曲は3rdアルバムとは異なる崩れた演奏方法を選択しつつラフな中に前衛さを表わそうとしているBrent Bestのソングライターとしての冒険を感知してしまう。少々小難しい方向性を模索しているように見受けられるのが幾許かの不安を漂わせる。
#10『Live On It The Dark』にしてもギターの音の出し方が浮遊感をイメージ出来てしまう箇所があり、表面上は大人しいサザン・バラードなのに何処か違和感を感じてしまうのだ。
#11『Back』のようにドブロギターを加えた、ローファイなアクースティックバラードをしんみりと聴かせてくれるようなシンプルさがこのバンドには相応しいと思うから。#7を境にして、ロックンロール・サイドとエクスペリメンタルな要素を含んだスロー・サイドと二分化が結構はっきりとなされているアルバムでもある。これは前作の後半がアクースティックナンバー中心であった構成と似ていないことも無い。
Slobberboneはテキサス州のデントンという街出身の若者、Brent Bestが同郷のミュージシャン達とライヴバンドを結成した1994年に始動している。
マイナーバンドのお定まりのコースだが、酒場や喫茶店でライヴを繰り返しつつ、バンドを結成した年に僅か400ドルの経費しか掛けなかった、2トラック機材で録音したフルレングスのアルバムを作成している。
これがSlobberboneとしてのデヴューとなる「Crow Pot Pie」である。翌年の1995年から、プレスを開始し、ライヴ会場のみで売られたこのCDは地域的にはかなりの評判になり、テキサス州のカントリーやカウパンク、そしてルーツロックのファンに注目されるようになっていく。この当時から同郷のバンドCentro-Maticとの親交は続き、かなり頻繁にジョイントライヴを行っていたらしい。
Centro-Maticは、Slobberboneよりもダークでサイケディリックな南部バンド、言ってみればオルタナ臭いところもあるロックバンドだが中々の作品も多いので、興味のある方は調べてみると面白いかも。なお、レコードデビューは1996年だからSlobberboneの後塵を拝していることにはなる・・・・。
この活動がオースティンのインディ・レーベルであり今は消滅してしまったDoolittle Recordsという帝都を航空母艦から発艦した双発爆撃機で初空襲しそうな名前のレコード会社に注目され、1996年に契約を交わす。
Doolittle契約下での最初の仕事は「Crow Pot Pie」のリメイクだった。レコードレーベルの契約の元で、全てのトラックを再度録音し直して、1996年に「Crow Pot Pie」は発売されることになった。ついでに、ジャケットの印刷や紙質も上等なものになり、レイアウトも若干の変更を見ている。
筆者は米国の友人宅で自主制作盤の「Crow Pot Pie」を聞かせてもらった事があるが、曲目と曲順はオリジナルも再録盤も差は無かったように記憶している。しかし、オリジナル盤の音質は酷く、宅録かライヴ一発撮りというのが丸分かりなサウンドクオリティだったのは鮮明に覚えている。
これで中堅以下の規模とはいえ、テキサスのルーツロック系レーベルとしては優良であったDoolittle Recordsの着目を浴びるくらいに評判になって売れたのは矢張り音楽が良かったからだ。
このDoolittleで翌年1997年には早くも2枚目の「Barrel Chested」を発表。この頃から更にローカルライヴを加速し始め、年間250ステージという最盛期のDoobie BrothersやREO Speedwagon並みなスケジュールで南部を中心に演奏活動を開始。Jason And The Scorchers、Old
97’s、Drivin’N’Cryin’の前座を務めたりもしている。
1999年には所属先のDoolittle RecordsがNorth West Recordsに吸収され、New West Recordsと新しいレーベルに変わってしまったが、その変更に左右されずに契約を続行。「Everything You Thought Was Right Was Wrong Today」は同レーベルの第壱号リリースともなっている。
そして、2002年に届いたのが4thアルバム「Slippage」となる訳だ。
バンドの名前が、依然“涎まみれの骨”に加えて、この「Slippage」という単語の意味は「事が上手く運ばない様子」や「価値の低下」、「滑ること」という類のネガティヴな響きを持つ。
だが、この傑作ロックアルバムのリリースで間違いなくSlobberboneの株は上昇するに違いない。バンドの知名度も徐々にであるが本邦でも知れ渡ってきているようだし、状況は上向きであると思う。
Brent Bestも自分の4作目には自信があるという発言をしているところを鑑みると、「価値の低下」という意味合いのタイトルは、「これまでに築いた音楽性を“滑り落として”新しいロックンロールを目指した。」という気概の表れなのかもしれない。
が、アルバム後半で前衛的なオルタナティヴに近いテイストを模索している様子があるため、あんまり違った場所へは滑って行っては欲しくないのだが。次回に来る筈の5枚目が評価のポイントとなりそうだ。 (2002.12.18.)
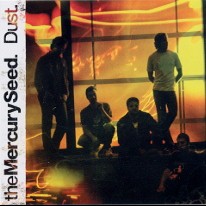 Dust. / The Mercury Seed. (2002)
Dust. / The Mercury Seed. (2002)
Roots ★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★
Adult-Alternative ★
You Can Listen From Here
コネティカット出身で、主にNYCを中心にライヴ活動を展開しているロックバンド、The Mercury Seed.の2枚目のアルバムが2年ぶりに届いた。
特徴というべきか非常に判断に迷うところだが、Seedの後にピリオドが付いているのが、このバンドの名前のユニークなところだろう。バンドはこの句読点を以下のように説明している。
「“The Mercury Seed”ではなくて、僕達の名前は“THE” Mercury Seed. “ピリオド”なんだ。これは別にタイプミスでピリオドが竃(へっつい)ているんじゃないよ。Theと.(ピリオド)を冠することで、このMercury Seedが唯一の存在だってことを示しているのさ。
唯一のバンド、つまりクラッシックロックのハードでプリミティヴな音楽を、新世代の音楽に引き継いでいるたったひとつのバンドということを言いたいのさ。」
Rolling Stones、Faces、そしてHumble Pieというロックの古典に大きく影響を受け、そういったサウンドを現代に演奏するということを標榜しているこのバンドの趣旨にも合致するコメントである。
デビュー作がNYCのインディ音楽雑誌で紹介された時は、
「Black Crowesが好きで、StonesやAllman Brothers Bandといった伝統的なアメリカーナを感じることの出来る音がお気に入りなら、まずThe Mercury Seed.を聴いてみて損はない。」
というコピーが付随していた。
筆者の見解が海外のレヴュー筋やバンドの自己分析と完全無欠に一致するということはないけれども、確かに1960年代から80年代のメジャーなロックンロール−オルタナティヴとかエモとかルーツロックというジャンル分けが細かく成されていない時代のアメリカン・サウンド−を懐かしくさせる要素を持っているグループであることは同意しておこう。
しかし、バリバリのルーツロックか、と尋ねられると少々答えに詰まりそうなサウンドであることも間違いない。
ルーツロックと非ルーツロックの境界線は越えているが、カントリーロックやオルタナ・カントリーロックとは全く質の違う音楽性を持っていると思ってもらえばその解釈が最も適当だと思う。勿論サザンロック、スワンプロック、ジャズにブルースというアメリカン・ルーツの諸音楽に深く傾いているのでもない。
例を挙げれば、Bryan AdamsやEddie Money、Tom Corchrane、そしてDon Henleyといった土臭く田舎臭い音楽でアメリカンロックを表現するよりも、よりアーバンでストレートなロックンロールをオーソドックスに演じるアーティストにより近いサウンドといえば良い。
Bob SegerやTom Petty、John MellencampよりもPeter FramptonやRon Wood、Freeといったハードロックやアリーナサウンドのより濃厚なロックンロールを思い出させる音楽。
かといって、古典そのままな音楽ではない。
1990年代初頭のグランジ/オルタナティヴの洗礼を通過してきた世代のミュージシャンが意識してそれを遠ざけない限り、どうしても影響を音楽性に反映してしまう要素が、The Mercury Seed.の中には確固として存在していると感じている。
酷く偏ったり強烈なアピールはしていないが、ハードロックやアリーナロックと呼ぶよりも、モダンロック、オルタナティヴ・ロック的な傾斜が目に見えて付いているサウンドだ。
言ってみれば、以下のようなものだろう。
Highway 9、Legend Of Rodeo、Jaded SalingersというようなAdult-Alternative と命名するしか他がないような現代性もクラッシックロック一色でなく、何処かに有するサウンドである。
とはいえ、今年メジャーから売り出されたHighway 9やLegend Of Rodeoと比較すれば、絶対的にオルタナティヴの含有率は低い。これが、巨大レーベルから売り出されたバンドとインディレーベルからの発売の条件故の格差となっていることは想像に難くない。
どうしても大レーベルからの発売の場合、その時代の流行を、殊に新人である際は取り入れなくてはならないからである。
が、インディであるからこそ、The Mercury Seed.にはもっと突き詰めたルーツロックを演奏して欲しかったと思うところも確かにあるのだが。先に述べたように、ルーツを感じさせるサウンドではあるが、同時にオルタナティヴやアーバンなロックサウンドも同居している。
ルーツとオルタナティヴ、どちらの方が濃厚かというと、The Mercury Seed.(以下MS)の音楽性の骨子を成しているエレメントに左右されている面もあるかもしれないが、このバンドの基本としている姿勢がクラッシックロック=アメリカンロックのオーソドックスなベースであり、エモやパンクポップ、ヘヴィロックという90年代以降のスタイルでないため、やはりアメリカン・ルーツの割合が遥かに多分に含まれる音の構成とはなっている。
便宜上、Adult-Alternativeという分類にしてあるが、Adult RockやAdult Contemporaryに置換可能な程度のオルタナ・ロックのカラーが存在すると思えば適当な判別になると考えられる。
現代性−21世紀に音楽を作り、歌い、演奏し、それがリスナーの耳に訴え掛ける何かを有する最低条件はやはりそのアーティストの独自性だと思う。
その独自性のベースが徹底的な懐古主義だろうと、現代的な音楽を取り入れていようと、アメリカン・サウンドを正統に継承している限り、やはり「古き善き時代の残滓」等と批判を受けようが、不変の良さを持ったアメリカ音楽になると思う。
このMSというバンドの場合は、カントリーやブルースといったフォーク系の音楽ではなく、都会で培われたソリッドな古典音楽という根っ子からアメリカン・ルーツを引き出しているのだ。つまり、普遍的なPop/Rockをそのメインフレームに据えて、サウンドを組み立てているのである。
であるから、Alternativeという分類はあくまで便宜上の存在であり、現代性を色濃く有したロックンロールを語る場合の単語と受け止めるのが、MSのような音楽を仕分ける際の方便だろう。このバンドはあからさまなオルタナのカラーは非常に希薄である。その分、アーシーで合衆国の大地を直接的に感知させる音構成も高いとはいえない。
いってみれば、
オルタナティヴの興隆以降、激減した“普通のロックバンド”なのである。
Heartland Rock,Arena Rock,Hard Rock,Pop/RockプラスのModern/Alternative Rock こういう総合的なロックンロールと思えば良いだろう。
普通という意味には、オーソドックスで極端に何かに特化することのないサウンドを意味するが、更にどの時代にもオルタネイトに対応できる無難な音楽という意味も含んでいる。
勿論、1970年型の普通や1980年型の普通と全く同じではなく、1990年代からの米国ロックミュージックの変遷を経験してきた世代の感覚を含んだ普通なロックサウンドである。
ハードロックや産業ロックとオルタナティヴ・ロックの両方を匂わせたり、ルーツロックっぽさとオルタナティヴの人工サウンドっぽさ、このように中々融合し難い要素が複雑に絡み合っているので表現がまことし辛いことこのうえない。
例えば、Humble Pieに対する敬意を持っているというのが如実に表わされている#1『Learning To Crawl』では、確かにForeignerにも通じるハードで固めのギターサウンドが繰り延べられている。
しかしながら、ハードであるけれど、テクニックをひけらかすようなハードさではないし、ギターの音色を聴かせるような所謂ハードロック的な手法よりも、硬くラウドさを求めるオルタナティヴ的手法の方が目立っているように思える。
ルーツロックというナチュラライズされたサウンド・プロダクションではなく、もっとメカナイズされた都会的なロックノイズを搾り出しているナンバーである。
最も近いのはオルタナティヴと産業ロックを融合させたNeveの『Digital On』のようなシングルだろうか。
#2『Come Undone』はテープの逆回転ノイズをオープニングのSEに取り入れたりした#1よりもメロディアスでHeartland Rockに近いアプローチをしているナンバーである。こういうナンバーがモダン・ヘヴィネスの影響をジンジンと感じるオープニングナンバーの後にもって来るバンドであるがため、非常にMSという創作集団のカテゴライズが難しくなるのだが。
アダルトで且つハードなサウンドの厚味が頼もしいロックナンバーであるが、何処となく土臭さが微量に漂う曲。例えるなら都会のビルの谷間に小さく身を縮めて佇む公園で嗅げる土の匂い。このくらいの自然回帰度は存在するナンバーであると思う。
しかし、ここにもモダンロックやオルタナティヴの硬さが存在するのは確実。ハードロックとは少々質の違う、Pop/Rock程にはソフト化されていないモノがある。
これらのナンバーとは全く違う、ハーモニカやピアノを取り入れた、アメリカンルーツの暖かさを含んだバラードが#3『Last Trace』である。このスマートなルーツ要素の歌い込みはWallflowersやMatchbox 20の一番メロディが素直だった頃の音楽に近い手触りを感じる。
適度にエモーショナルなギター。ノイジー過ぎなく、とはいえ線が細くならず。ヴォーカリストのVolkerの声はとてもオルタナティヴやヘヴィロックを歌うのに向いていそうな一本槍な声の持ち主だが、#3のようなエモーショナルなバラードを歌わせるとハードロックバンドのシングル曲に使われるパワー・バラードの歌い手としても適材な声質を持っていることがわかってくる。
#4『Waiting』ではそこそこにポップでアクースティックさも感じさせる、Adult-Alternative系のバンドに多い、八方美人的な曲を提供している。ルーツロック、モダンロック、オルタナティヴ、クラッシックロック、とどの範疇にも対応できるような中間的な音とメロディで曲を作っているのだが、それ故に消化不良な感が否めない。
王道的なPop/Rockをロックの古典から発展させると、得てして全ての音楽に面を向けることの出来る万能タイプなナンバーが多くなってしまうものだが、同時に個性というか特徴の掴み難いサウンドになってしまうことがある。
これでもっと大仰になったり、更にポップの柔らかさを押し出してこないのが、やはりオルタナティヴを経験した世代だろうか。十分に耳通しの良いロックナンバーなのだが、何故かロックビートもスコアも単調であり、もう一歩踏み込んで欲しいと感じてしまう。まあ、この淡白さがオルタナティヴが若者受けしているところかもしれないが。
ハードロックというかロックバラードのメインストリームをサラリと歌い上げているのが、2曲目のバラードである#5『Misery Loves Co.』。アーバンロックのアダルトさを何のヒネリもなく素直に打ち出すとこのようなナンバーに成るという見本のような曲になっている。ストリングス・シンセサイザーとピアノをお約束通りに取り入れてきて、美しいバラードに仕上げている。
ここには頭ごなしにラウドさを求めるだけのエモ・サウンドやヘヴィネス音楽の悪癖は持ち込まれていない。どちらかというと産業ハードポップのバンドが得意とした、現在の米国からは失われつつあるタイプの曲であろう。オーヴァー・プロデュースにせずに、少しばかり淡々と結んでいるところはやはり現代型のバンドだとは思う。アリーナ時代のバンドならもっと日本人に受けそうな感情を剥き出しにした悲哀をメロディに載せるだろうから。
#6『Coming Down Again』は古典ハードロックをモダンロックの解釈で甦らせたようなナンバー。Backcherryのようなハードパンクの現代バンドとは違い、組み立てとインプロヴィゼイションを大切にしたハードアンサンブルのプロダクションに拘ったギターナンバーだ。
バンドにギタリストが2名という編成を活用したギターのユニゾンが重く漂うところは、ツインリードのギターが一世を風靡した1980年代を思い起こさせる。このカチンカチンな音出しは、ブリティッシュのハードロックムーヴメントの時代に遡ったかの如くである。しかし、ここにもオルタナティヴの必要以上な硬さを含んでいるため、純然たるハードロックよりも雑然とした印象は拭えない音がややハナにつく。
最もルーツの感覚が濃くなるのは#7『Two Step(From The Move)』から以降。
「やられた〜」と脱帽するくらいにポップに走らないのはこのバンドの特徴だが、それなりに口当たりの良好なポップなリズムを歯切れ良くピアノと一緒に転がして、ブギーでグルーヴなロックビートが伸び伸びと動いているのが#7。
ギターのやり過ぎなきらいのあるソロも産業ロック風の娯楽音楽を思わせ、不快にはならない。土臭いアメリカンロックを身近に感じさせる、軽めなダンスリズムが踊る曲。こういうパーティサウンドがもう少しお手軽な気分でできるようになるとバンドとしての将来が更に楽しみになると考えている。
現在のMSは、緊張感が張り詰め過ぎた展開が結構多くて、そのためにロックの鋭さを演出は出来ているのだが、硬質過ぎて触ると痛みを覚える不快さも並存していると感じる箇所もある。
#8『Dust』はタイトルではピリオドが付いているが、シングルでは外されている。このナンバーもアクースティック一辺倒ではないけれど、懐の深い大地の広がりを視覚化させるスケールの大きい音楽が内包されている。
アクースティックの静なるところから、エレクトリックアンサンブルの動なるメロディへと流れるように続いて盛り上がる展開は、斬新なものではなくまさにMSの標榜する古典的なロックサウンド構築の典型ではあるだろうけど、それをきっりと表現すれば、良曲になるという例を実例で示してくれている。
オルガンの使い方が、WallflowersやFive Easy Peicesを匂わせるアメリカン・ルーツの正常な音への回帰を表現している。こういったミディアムなロックとバラードの中間のナンバーが上手いバンドは概して良好なアルバムを作れる才能がある。The Mercury Seed.に関してはその才気はまだ未知数の部分が多いとはいえ、将来を期待できる証拠として挙げれる1曲にはなっている。
#9『Sky Is Falling』は、英国的なハードロック、しかもパブロックやハードパブの時代のロアなサウンドを色濃く感じることのできるエッジが強い。FacesやRolling Stonesに影響を受けたということが確かに理解できるルーツのハードさを有しているだろう。
東海岸のアーバン・ミュージックと融合したルーツロック、または南部のハードさから土臭さを極力減らしたロックンロールというサウンドの形だろうか。Lynard Skynardあたりが演奏しても違和感はそれ程に噴出しないかもしれない。
#10『Times Of Trouble』に関しては、古典的なことは確実だが、サイケディリックなクラッシックと呼ぶのが相応しい。またはプログレッシヴロックの初期に見られた、エクスペリメンタルなギターのベントが掛かった音だろうか。かなりフニャリとしたディレイの入ったギターが延々とうねっていくナンバーであり、モダンロックにも結構見受けられる方法論にも思えるが、やはりサイケディリックで前衛的だった1960年代のロックへのオマージュ的な色彩を多目に含んでいるナンバーだろう。最後にコードが崩壊して突如カットアウトする展開は、アバンギャルドが持て囃された嘗ての時代性を反映していると考えられる。
こういう異色なナンバーにも手を広げるところは、いまひとつバンドに確固たる個性を与えられないかもしれない。もう少し焦点を絞った方がわざわざピリオドまで付けてバンドを「現代に溢れているロックバンドとは違う存在」と喧伝した意味が薄れてしまうのではないだろうか。
東海岸やNYCにはこのようなシティサウンドとルーツロックの中間を行くバンドがたまさか見かけることができるけれども、その中でもかなりタフで頑固にも古典を倣っているバンドがThe Mercury Seed.である。
メンバーはバンドのコアとなったヴォーカリストのVolkerとリードギタリストのDarren Salmeri。この2人が主にソングライティングを手掛けている模様。曲のクレジットではVolkerは本名を使用している様子でLammerという名義が現れている。
が、Darren以上に曲を書いているのが、デュオに加わった2人目のギタリストであるJohn Jacksonであり、7曲に手を入れている。(Darrenは5曲。)
1990年代の終わりにマンハッタンでVolkerとDarrenが結成したコンビに、ベーシストのGray D’Andreaが加わりバンドとして発足。そこにDarrenの友人であるJohnが合流。更にバンドとしてフルタイムのドラマーが必要なためRob Langerを雇ってThe Mercury Seed.が完成する。
2000年にセルフタイトルのアルバムを作成。今作よりもハードでブルージーなアルバムだった。同時にもっとオルタナティヴの湿度が高かったアルバムでもあったので、そこそこのアーバンロックのアルバムとしか記憶していなかった次第である。
だからこそ、次作が評価の分かれ目になりそうだ。
ポップでスマートな曲を創れるようになった2作目である「Dust.」はかなりの進歩を見せてくれているから、このままの勢いで進化して貰いたい。Mercury Seedという名前のバンドはマイナーシーンに幾つか存在しているが、このピリオドを打ったMercury Seed.が他のバンドと差別化できる存在になるか楽しみに待てるレヴェルには上昇していると考えているのだ。
しかし、オルタナティヴに転んでしまう可能性もなきにしもあらずというところもある・・・・・。 (2002.12.22.)
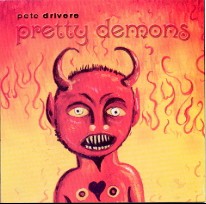 Pretty Demons / Pete Drivere (2002)
Pretty Demons / Pete Drivere (2002)
Roots ★★★
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Americana ★★☆
You Can Listen From Here
微細に違う点は多々あるけれど、米国版Joey Tempestと呼べそうな位置にある作品でしょうか?
オハイオ州はヤングスタウンという、一見若者の街にしか聞こえない響きを持ち、実のところ単なる1地方都市に過ぎない場所で現在Pete Drivereは活動しています。年齢的にはヤングスタウンという名称はやや危なくなってきている領域に差し掛かっているようですけど。
このヤングスタウンという都市は、フィラデルフィアとオハイオ州の州境に近く、更にクリーヴランドとピッツバーグを結ぶ中間点にあるという利便は悪くない場所で、総合大学も存在するためか、かなりインディバンドの活動が学生バンドや学生上がりのバンドを中心に活発な傾向もあります。
試聴リンクから飛べる、YoungstownSecen.comにはこの街のローカルバンドが数多く紹介されていますので、興味がありましたら、じっくりと試聴して掘り下げてみるのも面白いかもしれません。
さて、お話をInfidelsに戻しましょう。
何故にPete Drivereというアーティストを語るのに、Infidelsを持ち出すかというと、Pete Drivereというギタリストが所属していたバンドがInfidelsだったからなのです。
と、ここまではInfidelsに関しては過去形で記述してしまっていますが、これは2001年までは間違いなく正しい時制の使用法であったのです。
1982年に結成された激烈ローカルバンドであるInfidelsは1990年に2枚目のフルレングスアルバムを発表してから2002年に活動を再開するまで約10年以上の沈黙にいたのですから。というか、既に解散したと思われていたというのが正しい認識でしょう。
マイナーレーベルで2枚のフルアルバムと数枚の7インチシングルを出しただけで10年間Infidelsという名前が聞かれなくなってしまっていれば、普通は既に終ったバンドと見なしてしまいますね。
かく言う筆者もInfidelsは1枚のCDを所有していたのですが、このPete Drivereが初のソロ作「Pretty Demons」のクレジットを見るまで、Pete DrivereがInfidelsのメンバーであったことなど、完璧に忘却の彼方へ去っていましたし。
まず、Pete Drivereについて語るにはInfidelsの歴史を追うのが最も適切と思うので、Infidelsの活動に即して、Peteについても触れていきましょう。
Infidelsは1982年にペンシルヴァニア州のウエスト・ミドルセックスという英国にある都市と同名の街で結成されています。バンドの創始者はギタリストにしてヴォーカリストのPete DrivereとベーシストにしてヴォーカリストのJohn Hlumykです。この2名は双方共に1967年生まれ、2002年では35歳ですので、まあヤングスタウンに入れて貰えるのではないかとは思います。(笑)
このコンビにリードヴォーカリスト兼ギタリストのTony Mentzerとドラマーを雇い入れ、Infidelsは1982年に初めてステージに立ちます。
折りしも、大英帝国発/セックス・ピストルズ謹製のパンクロックが世界中を席巻した余波が未だ残っていた1980年初頭の潮流を反映してか、Infidelsはパンクバンドとしてカテゴライズされる集団でした。
但し、21世紀のパンクと呼ばれているエモ・ロックやパンク・ポップ系の音とはかなり異なる、よりプリミティヴなパンクロックを叩き出すバンドですね。上辺だけをパンク“っぽく”固めたスカスカ内容無しの最近のポップバンドとは全く音の重みが違います。
更に、大英帝国からアトランティック・クロッシングして米国に上陸したパンクロックが、アメリカナイズ/アメリカンロックと融合して独自のサウンドになっていった例−RamonesがAmerican PunkやNew York Punkと呼ばれたのと同様に、Infidelsのパンクサウンドも単なるダーティでノイジーなパンクサウンドではありませんでした。
ハードロックをベースにしたパンクロック、ルーツロックを感じさせるパンクロック、という風に解釈すれば良いでしょうか。前者はかなりハードロックに比重が置かれていると思います。パンキッシュなハードロックと理解する方が適切と思います。
自由奔放と裏返しのチープな感触は確かにパンク音楽を基礎にしていることを感じさせますが、それ以上にロックンロールの重みが節々に突っ込まれているのです。米国風ハードドライヴなロックンロール=アメリカン・パンクと捉えることも可能なら、Infidelsの音楽はハードロックでありパンクロックといえるでしょう。
また、特にこの傾向は初期Infidelsの最終期に近づけば増加していくのですが、アメリカンルーツロックへの傾倒が強く出ているバンドでもあるのです。
現在までは最新にして最終のアルバムとなっている「Wondrous Strange」(1990年)ではR&B古典ロックンロールの能天気なシンプルさやアーシーな雰囲気をもったナンバーが、ノイジーでハードな曲の間にしばしば姿を表わすようになってきます。
また、アクースティックな音で埃っぽさをそこはかとなく表現するようなナンバーも出てきているのです。
パンキッシュなナンバーにしてもゴリ押しするだけではない曲も少しですがトラッキングされていたりもします。
この面ではルーツ・ハードロック、ルーツパンクという側面も垣間見せているバンドとも言えるでしょう。とはいえ、全体としてはやはりパンクでハードな爆走ナンバーが大半を占め、どうしてもBクラスのローカルバンド、アンダーグラウンドの酒場バンド、という印象は払底できませんね。
決して、スターダムには上がれない、万年クラブサーキットで歌い続ける集団。
このようなパンク/ルーツをベースにしたアメリカン・ハードロックのバンド、これがInfidelsというバンドです。無論、後に吹き荒れるLAメタルや北欧メタルのような宇宙的なシンセサイザーをブンブンいわせる類のハードロックではなくて、Guns N’Rosesを代表とするハードで飾り気のないハードサウンドに属する音という意味合いでのハードロックということをお断りしておきましょう。
ということでInfidelsの音楽性を説明しましたので、バンドの経歴へと話を返します。1983年にレコーディングのために隣州のオハイオに渡った彼等は、ヤングスタウン出身で2枚のメジャーアルバムを1970年代に残しているBlue AshのメンバーであったFrank Secichの既知を得ます。
Frankは1970年代後半に出現し、90年代には多数のロックバンドにその歌をカヴァーされているDead Boysとも繋がりのあるミュージシャンであり、InfidelsはDead BoysとBlue Ashのマネージメントサイドのサポートを受けることに成功します。
ここでJohn Kouryがドラマーとして加入。4名体制が定着し、ウエスト・ミドルセックス周辺でプレイを続けます。
1985年には初のシングル「Mad About That Girl」を発表。この後すぐにヴォーカリストのTony Mentzerを解雇して、1964年生まれのリードヴォーカリストDavid Liskoを加入させます。
Davidは「Mad About That Girl」の作成にはタッチしていませんでしたが、このシングルのリリースパーティからバンドのヴォーカリストとして活動を始めます。
この1985年頃から、Infidelsは活動拠点をヤングスタウンに移すようになります。マネージメントのサイドがオハイオ州にあったことを考えれば当然かもしれません。
1986年には「Infidels Times Four」という4曲入りのEPを、1988年にはシングルを1枚発売。地元ではそれなりのオン・エアとセールスを記録したようです。
1988年にはライヴ盤ですが、はじめてのフルアルバム「9:25 And Seven Seconds」を発表。これは完全なパンクロックとハードロック色の強いアルバムです。
そして、Dead Boysのオハイオツアーに同行したりしつつ、欧州や豪州にアルバムが輸出されるようになり始めた1990年にはスタジオ録音盤一発目の「Wondrous Strange」をリリース。
「60年代のメロディアスさと70年代のパンクロックを兼ね備えたバンド」という評価を得る等、活動は順調に思われていたのですが。ちなみに筆者がInfidelsを知ったのもこのあたり、1992年のことです。
しかし、1992年にはバンドは既に崩壊に突き進んでいました。2枚目のアルバムを発売後、リードヴォーカルのDavidとドラマーのJohnが相次いでバンドを脱退。代えのドラマーと幾人ものギタリストを加入させ、リードヴォーカルはPete Drivereが穴を埋めていました。が、1992年には創始メンバーのJohn Hlumykまでがバンドを離脱してしまい、残ったのはPete Drivereだけになってしまいました。
1995年まで、然れどもInfidelsは存続していました。ドラマーのDennis Kocholek、ベース兼キーボードのMike Polombi、ギタリストのLarry Kennedyというメンバーを引き連れて。が、ローカルのレコーディングにぼつぼつと参加するくらいで、精彩を著しく欠く活動内容だったようですが。
それでも1996年にPete DrivereがMike Polombi、Dennis KocholekとSac’sというバンドを結成すると、Infidelsは遂に消滅してしまいます。このSac’sは1枚のアルバムを残しているようですが、こちらは未聴です。
ここで完全にInfidelsは消え去ってしまったように見えましたが、2000年にDavid LiskoがPete Drivereにレコーディングの誘いを掛けたことが切っ掛けで、再びInfidelsを始動しようとする意欲が持ち上がります。
「ローカルレーベルが、Infidelsのような音を録音しないかというオファーがあった時に、Peteに出会って話を持ちかけたら、とんとんと話が進んで、過去のアルバムもリイシューするということになった。」
とDavid Liskoは語っています。
2枚のInfidelsのアルバムはそれぞれボーナストラックを数曲加え、Pete Drivereが所有している機材でリマスターされて2002年に再発売されました。次いで、Infidelsも2002年からライヴ活動を再開。
これと並行して、Pete Drivereはソロの活動も活性化させています。1996年以降殆ど休眠状態にあったSac’sのメンバーを軸に、自分のバンドを立ち上げ、現在はPete Drivere And Pretty Demonsというバンド名を名乗り、Infidelsの前座を務めたりすることも多い様子です。つまり、Pete Drivereとしてソロステージを行った後、Infidelsのギタリストとして再び演奏するというハードなパフォーマンスをこなしています。
やはり、Infidelsの再開が起爆剤となってPete曰く「休眠状態のようだった10年間」から決別できたのでしょう。
本作、キャリアのデヴューから20年後に初めて作成されたアルバム「Pretty Demons」は発売の時点ではソロ名義のPete Drivereとなっていますが、現在ではPete Drivere And Pretty Demons扱いとなっています。
Pete本人からのメールでは
「このアルバムを作成した時は、バンドとして活動するとは思わなかったので、Pete Drivereとしたんだけどね。バックバンドをPretty Demonsと呼ぶ予定は正直なかった。Infidels後期のメンバーを集めてセッションした結果のアルバムだったんだ。だから、バンドとして活動しようと思い立った時、アルバムの名前の由来となった“可愛い鬼さん”のイラストが頭に浮かんだので、Pretty Demonsというところに落ち着いたんだ。」
ということですが、このジャケット・・・・・
この鬼が可愛いとか、ぷりちー、という見方にはかな〜〜り抵抗があるのは筆者だけでしょうか?(笑)
しかし、ジャケットだけ見ると中に詰まっている音楽性には激しく不安を覚えそうですが、ところがどっこい。
この小学生の図画の時間に書かれたようなイラストからは比較できないくらい、
物凄い正統派のルーツロック、アメリカンロックが収められています。
元(というか再結成してますが)ハードロック系のヴォーカリストが作成した正統派ロックアルバム、という関連性を元にJoey Tempestを冒頭に持ち出してみましたが、確かにバンド時代の方向性とはかなり違う音楽を目指しているという点では類似点があり、それがルーツを感じさせるPop/Rockであるという箇所も近似しているでしょう。
しかし、産業北欧メタルのEuropeからPop/Rockのヴォーカリストへ転身したJoey Tempest程には極端な変革を遂げたとは厳密にはいえないかもしれません。
というのは、Infidelsが元々ルーツの流れを控え目に取り入れているバンドであったこととが1点。Infidelsがバリバリのインダストリアルなハードバンドではなかったので、Peteのソロ作と比較対象の共通点が存在するのです。
またJoeyが完全に元グループの音楽性を切り離しているのに対して、Peteはパンキッシュでハードなロックンロールを−Infidelsをリヴァイヴァルさせたようなナンバーをトラック・インさせているというのが2点目です。
これは#7『There’s Been A Change』、そして#10『Swine』の2曲と全体から眺めれば僅かに2割弱なのですが、ルーツサウンドレイドバックしたPop/Rockで固められた「Pretty Demons」の曲群の中では異彩を確かに放っているナンバーですね。
やや今風のAlternative Rockなギターリフが鋭角なハードロックナンバーの#7といい、目一杯崩したシャウト・ラップからスタートするハードコア・パンクの#10は、Pete Drivereの出身フィールドを明確に示唆しているナンバーであると思います。
とはいえ、この2曲もガチャガチャとしたノイジーさがあるのですが、全体のロックンロール度合いを引き上げる痛烈なアクセントの役割も果たしており、一概に駄目な捨てトラックとは言い難いところはあります。オルタナティヴを聴くほどには脳味噌を金属で引っ掻き廻されるような不快感はありません。
これは人工サウンドを安易に取り入れず、従来どおりの古き善きアメリカンサウンドをアレンジしようとしているからでしょう。
まあ、全部のトラックがこの#7や#10であったなら完全にクソアルバム扱いになるでしょうけどね。(苦笑)この2曲を補完して、更に流れに取り入れてロックのマスターピースにしてしまえるくらい、残りのナンバーは良質なアメリカンルーツなのです。
基本的にカントリーやブルースというコッテリ濃い目のルーツエレメントはPete Drivereのサウンドスタイルではありません。このあたりもJoey Tempestの王道的なPop/Rockに近いでしょう。
言い換えれば、現在の活動拠点であるオハイオ州のルーツサウンドに顕著に見られるHearland Rockをややルーツに傾かせたものというところです。
それとこのアルバムの特徴ですが、ギタリスト上がりのシンガーにありがちなギター中心のシンプルな3ピースサウンドに落ち着かせず、ハモンドB3を筆頭にキーボードを上手く活用している点に尽きます。
#1『Can’t Sit Still』はアクースティックなギターのレイドバックした音色が印象的な素晴らしいPop/Rockチューンですが、ハモンドのディレイを振り回して取り入れるというアレンジにはもう脱帽してしまいます。2分足らずという演奏時間はやはりパンクロックバンド出身を痛烈に感じさせますが、このナンバーは4分程度の長さにしてもっとインプロヴィゼイションを聴かせて欲しかったですね。
#2『She’s With Me』は同州のルーツロックデュオであるHenslySturgisの「Cavin Fever」を思わず連想してしまいそうになるハードにドライヴするルーツロックンロールですが、ここでも弾きまくりのギターに混じって嫌味にならない程度に力の入ったオルガンが暴れてくれます。
アルバムタイトルの元になっているだろう#3『All The Pretty Demons』は緩急の付いた極上のミディアム・ポップナンバーです。アクースティックな自然の感触を大切にしつつ、しっかりとエレクトロニックサウンドのアーシーなサウンド・プロダクションも自己主張をしています。ベースラインもかなり際立ったところがありますね。
この曲だけではないのですが、少々Pete Drivereがギターを弾き過ぎる傾向がどのナンバーにもあるのですが、これが筆者には丁度良いドライヴ・フィーリングを与えてくれます。これでは五月蝿過ぎるというリスナーも物足りないというリスナーも双方存在するでしょうけど。
#4『Just Do It』はやはり少々ギターソロがそのダルなメロディに沿うには強過ぎると思いますが、後半のブリッジで盛り上げるという展開は悪くありません。ザクザクとしたアクースティックギターやギコギコと鳴るパーカッションを配して淡々と進める前半はやや退屈ですが。
#5『Michael』のアメリカの大地を具現化したようなゆったりとしたバラードは、少々Peteのヴォーカルでは表現を過不足無く行うには辛い箇所がありますが、オーヴァーダブされたPeteのヴォーカルコーラスとハモンドB3の暖かさを感じさせる音色と、アーシーな手触りを間近に知覚させるメロディのおかげで深みのあるナンバーになっています。
#6『Stuck In A Hole』はかなりAORやフュージョンを匂わせるタンディなピアノが印象的な異色ナンバーです。何処かにSteely Danを思わせるR&BやLittle Feetを感じさせる前衛的な要素があります。
#8『Take A Look At Yourself』は英国ポップ、ずばりBeatlesを直接に意図したところが明白なサイケディリックな面と、粘っこいリズムが絡み合う複雑な展開が聴き所です。半音外したコーラスが入ったり、擬似ホーンがぶつかり合いながら崩壊して行くラストはJohn Lennonのソングライティングを想い起こさずにはいられません。
#9『Your Love Killing Me』はザラザラした土の粗さをモダンロック風のリズムで消化したという感じのナンバーですね。モダンポップとルーツロックの角先が衝突しあって、干渉しあって出来上がったようなナンバーです。メロディ的にはアーバンなところも含んでいますが、暖色系のオルガンが全体色をルーツに纏めてくれています。
#11『Blue Highway』は最後に的役なアクースティックな感覚とそれをフォローする電気楽器のフュージョンが絶妙になされている好トラックです。Heartland Rockの特徴である空間の広がりを十分に引き出しているオルガンとギターのユニゾンに、飾り気のないPeteのヴォーカルはかなりマッチしていると思います。
しかし、安直なアクースティックバラードにせずに、結局ギターをかなり被せてロックリズムを際立たせてしまうのがどうにもPete Drivereのギタリストたる所以でしょうか。
以上11曲、これまでに専任でヴォーカルということはあまりアルバム上では行っていないミュージシャンが作成したアルバムです。
ギタリストらしく、ヴォーカルよりもギター、次に鍵盤に比重が置かれているところはあるのですが、決してヴォーカルワークを蔑ろにしてはいません。丁寧というと語弊があるかもしれませんが、ロックのハメはきっちりと外しつつ、基本のアメリカンサウンドからは逸脱することの無い手堅さを覚えます。
しかし、問題はこの悪趣味なジャケット。確かにこのDemon=鬼は怖くは無いですが、これを10倍に拡大して部屋の壁に貼って、夜独りで見ているのは気分の良いものではないでしょう。(それはそうや)
このジャケットでイロモノとして見られないか、これだけは心配です。どうにもチープさ120%という光線を発散する絵柄ですので。
先にも述べていますが、音楽は驚くほどに正統を走っています。可愛い鬼さんというよりも、優しく、あるときは厳しいロックの業師、というどちらかというと鬼退治に出てくるようなタフさと性根の良さをヒロイック的に感じれる良盤ですので、是非聴いてもらいたいです。ここで買えますし、買うと本人からメッセージがきますよ。
しかし、元ハードロック&パンク系のバンドのギタリストがここまで良質なルーツアルバムを出すとは。Joey Tempestはヴォーカルとして評価していたので、その路線変更には驚きましたが、Peteの場合はここまでのソングライティングが出来た人であることと、ヴォーカリストとしても結構良いものを持っている人ということを改めて知ったことが大きな収穫ですね。 (2002.12.30.)
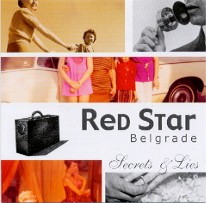 Secret And Lies / Red Star Belgrade (2002)
Secret And Lies / Red Star Belgrade (2002)
Roots ★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★★☆
Adult-Alternative ★★☆
You Can Listen From Here
Red Star Belgrade。日本語発音にすると、「レッド・スター・ベオグラード」となる。
この名前でピンとくる人は、十中八九サッカーのファンだろう。そう、欧州の名門サッカークラブ、ユーゴスラビアはベオグラードをホームとするチームがRed Starである。(英語発音でね)
特に1990年代前半まで、ユーゴが分裂独立の内乱に陥る前までは欧州でも十指に入るといわれた強豪チームだった。けれども、1995年まで継続したユーゴ紛争の煽りを受け、資金確保のため若手の成長株を国外のクラブに移籍させることで生き残りを画策した結果、最近はトヨタカップで優勝した当時の勢いは失速しているのだが。
というフットボール雑談はこっちに置いておこう。が、全く関係ないこともないのだ。
というのは、今回4枚目のフルレングスを発表したRed Star Belgradeというバンドはユーゴスラビアのサッカーチームである「レッド・スター」から名前を取ったものであることを公式に述べているからである。まあ、Belgradeという名前を付けた「赤星」という段階でサッカー好きには丸分かりなのだが。
しかし、これは米国のバンドにしては少し面白い趣向の命名方法かもしれない。
元来米国は国内リーグの決定戦に「ワールド・シリーズ」という呼び名を与えるように独自のスポーツ嗜好を有し、その道を驀進している文化の国である。パクス・アメリカーナの一面の顕現だろうが。
例を挙げれば、四輪モータースポーツの最高峰が世界的にはフォーミュラ・ワンとして認知されているのに、米国ではそれがCARTのインディシリーズだったり(2003年でIRLに統合となってしまったが)するのだ。
同じく、フットボールも世界的なレヴェルでは最も人気のあるスポーツであろうけれど、北米に於いてはまったくマイナーな競技としてしか認知されていない。ワールドカップにしても出場国の常連なのだが、国民の大半は熱狂はおろか、関心さえ払おうとしないし、あまつさえ自国が開催国でも全く盛り上がりを見せない。
と、冷遇の極みにある競技の、しかも自国ではなく欧州のクラブチームから名前を戴いたバンドが、今レヴュー対象となるRed Star Belgradeである。上記のように米国では即座に「これだ!」と名前の起源を連想されないようなカテゴリーからの引用をしているところが、Red Star Belgradeのポリシーと言うか主張が見てとれそうだ。
敢えて、自分の国土ではマイナーなスポーツの、しかもマニア以外は知名度がなさそうな外国のサッカークラブの名前を借用すること。
これは、進んでメインストリームから外れて、支流を進むぞと宣言しているようだ。更に何処かしらメジャーな流行に逆らうまでは至らなくともナナメに見ているようなアナーキズムのメタメッセージも少々穿った見方かもしれないが込められているように思える。あくまでRed Star Belgradeというサッカーチームの名前の米国知名度に於いての話であるけれど。(世界的にはそれ程マイナーな名前ではないだろうし。)
さて、実際のRed Star Belgradeの音楽は如何様に表現できるのか。
米国に於けるサッカーの如く、米国の音楽としてのポピュラリティからは離れたサウンドなのだろうか。
それとも米国のサッカー熱の冷めっぷりとは逆に、流行に即したサウンドなのだろうか。
結論から述べれば、20世紀後半から21世紀に跨る10年の米国でヒットした音楽を振り返って、これをメインストリームの売れ筋と定義するならば、Red Star Belgradeの音楽性は、米国におけるサッカーの人気と同程度の位置にあるものであると思われる。
まあ、ぶっちゃけた話、売れ筋まんまの音楽とは完全には離れ切ってはいないけれども(ここがポイントでもある。後述。)、1990年代型の主流なロックミュージックからは距離を置いた代物であるということだ。
つまり猫も杓子も追いかけているメインストリーム系のラジオ局やMTVで飽和状態の音楽ではなく、マイナーなリスニング人口を擁する類のロックミュージックなのだ。
イコール、ルーツ系のロックンロールと呼んでも差し支えはないと思う。
が、確かにルーツロックなのだけれど、その純度はハイオクタン価とは一概に言い切れないものがあるのだ。
このRed Star Belgradeが結成された理由に付いて、バンドリーダのBill Curryは以下のように述べている。Billは1990年代以前からソングライターとして地元のノース・キャロライナ州のミュージシャンを中心にマイナー・メジャーを問わずに曲を提供する仕事をしていた。所謂、フリーランスのソングライターと言うデビュー前のシンガーによく見られる仕事で音楽業界に従事していたのだが、
「メジャーに氾濫している流行バンドのために、盲目的に曲を提供することに幻滅した。これ以上他のバンドのために曲を書くことは人生と時間の浪費だと思ったので、自分のやりたい、自分で創った曲を自分で演奏することにしたんだ。」
というソングライターにしてリードヴォーカリストにしてマルチプレイヤーであるBill Curryの、流行シーンへの彼なりの抵抗或いは挑戦という形で始まっている。
であるのだから、間違ってもロックバンドに感染しまくって、完全にロックの主流をアメリカンロックから乗っ取ってしまったオルタナティヴではないジャンル。
これにRed Star Belgradeは属すると予想するのは当然の流れだろうと思うのだ。
しかし、Bill Curryが「1990年代半ばのロックシーンは酷いものだった。そんなシーンに迎合しているバンドや歌い手に曲を書くのは非常に精神に良くなかった。」
と述べている割には、
Red Star Belgradeの音楽性にはAlternative的な要素が少なからず含まれているのだな、これが!!!
当然、コテコテのオルタナティヴに迎合したサウンドを抱えているグループではなく、基本とする方向はルーツ系の音だということは間違いない。
Alternative Country Rockという表現でもRed Star Belgradeを全面的にではないにしろ、大幅な部分を語ることは可能だろう。殊に、2000年の3作目である「Telescope」では前2作より大幅にカントリー的なテイストを増やしたサウンドが展開されている。
だが、Red Star Belgradeの基本たるサウンドはかなりダートでダークな現代的オルタナティヴサウンドに似通ったハードで重いロックサウンドに帰結する傾向が強いのだ。
このあたりの分類は、最終的には個人の耳に頼るしかないのだが、筆者的にはこのバンドの音は「Telescope」も含めてだが、
ハードなルーツロックのサウンドとオルタナティヴ・ロックの現代的なノイジーさが8:2、時には7:3で共存している指向性のあるバンド。
以上のように考えている。
90年代のミュージックシーンに失望し、我が道を歩むために結成したグループ。
と謳っている割には、そこかしこにオルタナティヴの影響が明らかに感じられるナンバーが聴き取れる。元来からロックの骨太さと重さを振り回すことを主眼とした方向性にあったので、重さと暗さを纏わり着かせながらも、よりアーシーなロックサウンドへ−Alt-Countryへと特化した「Telescope」を発表した時は、次作に期待するものが結構あったのだ。
けれども、アーシーで普遍的なルーツサウンドへの歩み寄りは2年後に発表された本作「Secrets And Lies」では2歩後退したという感じである。どちらかというと、処女作や2作目でウエイトを大きめに占めていたハードでノイジーなルーツロックへ回帰した音創りを実行していると思う。
それは、3作目で稀釈されたオルタナティヴのダーク・サイドが捲土重来とまで大仰なものではないが、再び帰還してきたことをも意味するものだ。というか、どっか逝って帰ってきて欲しくなかったのだが。(怒)
とはいえ、1作目「Where The Sun Doesn’t Shine」や2作目「Fractured Hymnal」程には極端なオルタナティヴが突出したトラックは減っている。アメリカンルーツの音楽とオルタナティヴ的なメインストリーム性を天秤に掛ければ、間違いなくルーツ的な懐の深さは量を増していると感じる。
また、Red Star Belgrade(以下、RSB)のサウンドをオルタナティヴっぽく響かせている原因の大きなものは、メロディやサウンドアレンジよりもBill Curryの実にオルタナティヴした、オルタナティヴを歌うための、オルタナティヴのバンドに非常に多く見られる野太い声である。
叩き割れば、Billの声質は質実剛健過ぎるきらいがある。粗野と言い換えても些かネガティヴだが、それで通ると考えている。鼻を摘んで目一杯力んで歌っているバス・ヴォーカル、という感じである。
あまりにゴッツい存在感のため、ソウルフルを通り越してしまっている。全般に、ソウルフルな声というのは大地の恵みを音声に変換したと捉えることの可能な暖かみや深みを天性で所持することが多いが、Bill Curryのヴォーカルはハードロックやメタルバンドのヴォーカルに顕著なように、声質が太過ぎてガチガチな金属のカタマリのような重さを表現することに向いているのだ。
土の塊を掬い上げて握り締めた時に感じる柔らかさは皆無。金属の塊を握り潰したは良いが、己の掌まで傷つけてしまうようなヒーリング効果の皆無な剛毅な声なのである。
パワーはあるのだが、その受け流しが出来ない不器用なヴォーカルといえる。Matchbox 20のRob Thomasが更に不器用になったような感じ。Creedや3 Door Downのヴォーカリストと共通するのは、ノイジーさで誤魔化しは効く程度のヴォーカルということか。どちらにせよ、あまり歌い手としては評価は出来ない。
繰り返しになるが、この声がもっとハートフルさを兼ね備えていれば、ここまでオルタナティヴのギスギスした箇所が浮かび上がることは無いと思うからである。
そのオルタナティヴ的な音楽性は、オープニングトラックの#1『Browing』から炸裂している。土嚢を被せられ、その厚さ越しに強烈なパンチを食らっているかの如く、非常にヘヴィでダークなロックナンバーである。こういったナンバーにオルタナティヴ・ヘヴィネス風のBillのヴォーカルが被されば、ハイ、Alternative Rockが一丁揚がりとなる。
ポップさが申し訳程度以上には振り撒かれているし、キンキンと耳障りなだけな雑音ギター一色のアレンジにはなっていないため、#1にしても、#1と共にオルタナティヴ側な風味満載の曲筆頭格である#9『Atomized』にしてもそれなりに聴けるものである。オルタナティヴのコンクリートとアスファルトの冷たさを表わすアレンジの中に、土臭い、というよりもサザンロックのハードドライヴさを匂わせる重さが混在しているからだ。
しかし、この#1と#9をルーツロックか、それともオルタナサウンドかと択一を迫られたなら、筆者は迷わずこの2トラックはオルタナティヴの烙印を捺してやるつもりだ。
ハードでダークなのはRSBの生来の傾向だから特別嫌悪することは無いが、まだオルタナ風味が消臭されていないのは少々残念。
更に、この2曲ほどのオルタナ含有度はないにせよ、特にアルバムの前半にはオルタナティヴを感じさせるハードにのたくるナンバーが集中している。
このアルバムのタイトルトラックであり、同じタイトルの歌がPart.3まで存在する#2『Secrets And Lies』はこれまたノイジーでハードで豪快なナンバーである。ブリッジ部分でユニゾンしているヴァイオリンを押しのけるように狂気さえ孕んでブリブリと振り回される複数のギターを聴いていると、テクニックや心ではなく、大音量で圧倒して短期決戦で誤魔化しを図るオルタナティヴのバンドを見ているように錯覚してしまう。
オープニングのリフはAerosmithのヒット曲『Livin’On The Edge』にも似たアーシーさとサイケディリックさを含み、ハードロックとトラッドのフュージョンソング的な資質を有したナンバーでもありそうだ。このナンバーもギターの重さは問答無用なのだが、メロディがキャッチーに傾いていることと、そこはかとない南部的アーシーさが激しいアンサンブルの中に見えるので、ルーツ的なオルタナティヴサウンド、またはルーツハードなナンバーとして認知している。
#3『Insecure Pop Star』はこれまた重いロックチューン。RSBを立ち上げ時にBillの恋人であり、後に結婚した妻のGraham Curryの女性コーラスが初めてクッキリとコーラスに加えられた曲でもある。この場合の女性ヴォーカルは曲をモデレイトする働きがあると思うので、評価すべき点は普通の女性ヴォーカルよりは多いと考えている。
#3に関しては確かにヘヴィであるが、それ以上にサザンハードのバンドやロッキンブルースのグループに見られるようなマッディな土臭さが感じ取れるので、それなりにルーツとアーバンサウンドが折り合いをつけた音に仕上がっているのが面白い。
#4『Artifical Highs』はアレンジとヘヴィさで括るなら、#1や#9と同じ枠に嵌められて追放したくなりそうな激烈にモダンロックとオルタナティヴのテイストが漂うナンバーだ。まるでEverclearやNickelbackのサウンドを連想させるようなオルタナティフサウンドが走っている曲である。が、Everclearが時折見せてくれるポップなメロディがヘヴィ一辺倒な音と共存しているため、それなりにロックナンバーとして耳を傾けられる仕上がりにはなっている。
ルーツロック的な音がしっかりと聴けるのはアルバム中盤以降に多い。
アクースティックさとこれまでギコギコしていたハードサウンドの緩衝材になりそうなくらい「静」のテンポで綴られる#5『The Stalker Talks To The Jury』は本来もっとルーツに聴こえても良い筈なのだが、ゴリゴリに硬いBillのヴォーカルのために柔らかさが減少してしまっている。とはいえ、それなりに一息つけるアクースティックなトラック。
このバンドがAlt-Countryのグループであることを表明しているのは主に次の3曲だろう。
ペダルスティールを全面に押し出して、ハートウォーミングな田舎音楽の暖かさを聴かせてくれるのが、#6『Twinkle』。BillとGrahamの夫婦男女コーラスも和める音を出してくれている。この#6が前作で余すことなく追求していたAlt-Countryへの憧憬を色濃く受け継いでいる。
同様にカントリー的なカラーが強くインプットされているのが、#11『Hong Kong Farewell(The Sun Sets A Little Sooner On The British Empire)』とカッコ以下のタイトルが滅茶苦茶長く、しかもタイトルから容易に内容が想像できるように、大英帝国から中華人民共和国に返還された香港の歴史的事件を、男女の仲や人々の別れという題材も仮託して歌っている。
何しろ、「斜陽の帝国」というタイトルは歴史好きな筆者の嗜好を擽るし、パーカッシヴでありバンジョーやヴァイオリンまでフューチャーされたカントリーロック風のマイルドなナンバーでほっとできることろは嬉しい。
そして#11のタイトルのアンサーソング的なタイトルを貰っている#12『The Sun Will Shine』。ブックレットでは『Sunshine』とタイトリングされているがどちらかが誤植なのだろう。
銅鑼やエスニックさ漂うパーカッション各種、これにピアノを含めた多様なキーボードを絡めて、ワールドミュージック的な無国籍さとアメリカン・トラッドのサウンドが混じって出来上がった雑種のような曲になっている。この不思議に脱力してフワフワしたメロディはマッタリと心に響いてくれ、アルバムの最後を飾る余韻を持たせてくれるので、前半のオルタナティヴ系のハードロック攻勢を薄めてルーツロックぽい作品である印象を与えてくれる効果もある。
#7と#8はそれぞれ『Secrets And Lies』の2と3となっている。#7は(Inerlude)の副題が付けられているようにインストゥルメンタル曲である。各種のキーボードとパーカッションで淡々と語られる哀愁を含んだ小作品。
対して#8には(Organ Blues)という題名が後続している。この#8『Secrets And Lies 3(Organ Blues)』は読んで字の如しな曲だ。物凄くアシッドでオルガンが粘着した音をギターの泥臭い音と一緒になって捏ねくり廻すブルースである。しかも思いっきり南部のレッド・ダートな風景が浮かんできそうなブルース。
よくもまあ、ヒネリのないオルガン・ブルース等という副題を冠したものだと感心すらしてしまいそうだ。
#10『We Tried』にもオルガンは使用されているが、こちらはしつこさが少ないアッサリ目のスローナンバーになっている。この曲ではGraham Curryのヴォーカルがハーモニー・ヴォーカルとして最も目立っている曲でもある。初期のアルバムでは最近とは比較にならないくらいにメインラインのヴォーカルに声を合わせていたGrahamであるが、最近は出番が減っていたように思える。
彼女は決してソロでは歌わないし、夫であるBillのキツ過ぎる野太さを薄める働きをしてくれる、女性ヴォーカルがやってしかるべき仕事をしてくれるため、好感を持てる。
以上、ノースキャロライナ発の夫婦デュオを中心としたバンドの4枚目のアルバムに付いて少々辛口ながら書いてみた。冒頭で欧州で最も盛んなスポーツであるサッカーから引用された名前と記したが、リリース状況までも3枚目にして似たような方向に進んでしまっている。
デビュー当初の1994年から処女作リリースまでは南部エリアで活動していたが、あまり評判が取れなくて、1998年にはシカゴ周辺を活動の拠点に切り替え、2枚目フルレングス作はまず英国レーベルからのリリースを経て、米国はシカゴのレーベルにて発売という、米国でのサッカー人気のように苦戦模様であったRed Star Belgradeだが、この4枚目にして遂に最初のリリースは欧州のみ。数ヶ月遅れて大英帝国で発売。米国でのリリースは未定というていたらくに堕ちてしまっているのだ。
確かにオルタナティヴとルーツハードの曖昧な境目を有したバンドであるが、硬派(硬過ぎるきらいはあるにせよ)なロックバンドであるからもっと評価されても良いとは思うのだが。
然れども、米国でサッカーが永遠にメジャー化しないだろうことを思うと、Red Star Belgradeの米国でのブレイクはその名前が如何にも示唆的とはいえ、可能性は薄いと思わざるを得ない。
寒い時代である、こういったバンドには。 (2003.1.9.)
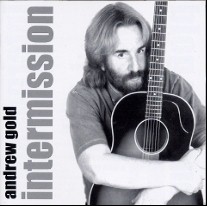 Intermission / Andrew Gold (2002)
Intermission / Andrew Gold (2002)
Roots ★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★☆
Adult-Contemporary ★★☆
You Can Listen From Here
1980年代から90年代の20年を通して、僅か3枚のオリジナルアルバムしか発表しなかったAndrew Gold−しかも1枚は未発表レアトラック集の「Leftovers」。
その4半世紀近くを眠って過ごしていたのではなく、プロデューサーやミュージシャンとしてそれなりに音楽業界には関わってはきているのだが。
Andrewについては、以前に書いたレヴューでそれなりに述べているので、そちらを参考にして戴きたい。
ベスト盤1枚、日本編集の独自盤2枚、それから& Friendsの名義でリリースされたオバケの歌集お子様アルバム「Halloween Hawls」やソロデビュー前に結成していたBryndle名義での活動、Waxでのデュオ活動、とアルバム自体のリリースは物凄く間遠になったという程でもない、数だけ追えば。
但し、ソロ名義ではたったの2枚である。厳密にいえば、オリジナルは1995年の「...Since 1951」だけと考えた方が無難だろう。お子様向けに『Ghostbusters』のカヴァーをしているアルバムを厳密にオリジナルとは考えたくないし、Waxを含めたキャリア全般を網羅するレアトラック集もオリジナルではあるにしても、裏技みたいなものであるから。
BryndleやThe Bellbottomsといったサイドプロジェクトはそれなりに評価できるが、ファンとしてはやはりAndrew Goldはソロシンガーという先入観もどきがあるため、Andrewがソロを全く発表しなかった1990年代は寂しいものであった。
そのAndrew Goldが2000年に久々のオリジナル作「The Spence Manor Suite」をリリースした時は、そのリリースしたという事実だけでかなり舞い上がってしまい、冷静に内容を評価することができていなかったかもしれないように思うのだ。
現在、改めて聴き返してみると、懐かしの西海岸サウンド−ウエストコースト・カントリーロックとAndrew Goldのシンガーソングライター的な側面が浮き出た長いブランクを感じさせない良作に属するアルバムだと思う。
Wax的なエレクトリックなポップソングが結構見られた1995年の前作と比べると相当に原点を見つめ直した作品であると思う。
その久々のソロ作から、僅か2年で今作「Intermission」が届けられた。前作に続いて、Andrewとしては2枚目のインディ・レーベルからの発表となる。
「Intermission」という単語の意味は、「休憩」とか「中断」、「中休み」果ては「中止」という動きが完全に止まったという範囲まで示唆する。
当然のことながら、Andrew Goldがこのアルバムで活動を長期「中断」するとか、「止めて」しまうという事実はないので、そういった意味合いはまず含んでいないとは思う。
しかし、アルバムのタイトル「Intermission」がサウンドと全く無関係かと考えると、おさおさそのようなことはない。
と、思う。
元10ccのGraham Gouldmanと緻密なアーティフィシャルなポップバンドであるWaxを結成し、アルバムを作成できるくらいの職人芸、それにシンガー・ソングライターとしての繊細な面をあからさまには見せ付けないが、ラフそうで実は精密なポップソングをクラフトできる才能の持ち主がAndrew Goldであると筆者は考えている。
実際に、「The Spence Manor Suite」は全盛期のデビュー当時からの3枚のソロと比べれば見劣りは少々するものの、Andrewが抱える玄人な演奏及びアレンジ、そしてメロディメイキングのテクニックが彼本来のフィールドである西海岸カントリーロックと上手く融合している技を見せてくれた作品だった。
しかし、この「Intermission」は文字通り、「中休み」、「休憩」という単語が良く似合いそうな雰囲気が一杯に引き伸ばされているのだ。
ゲストミュージシャンが参加しているの14曲中たったの2曲のみ。
それ以外の12曲はドラムやシンセサイザーのプログラミングを始め、全ての楽器をAndrewがマルチプレイヤーの本領を発揮して演奏。
プロデュース、ミキシング、エンジニアリングと大半のレコーディング作業もAndrew自身が担当。
自宅録音という程にパーソナルで(=ショボイ音質)はなく、しっかりとスタジオを使用して音を高品質に仕上げているところはレコーディングエンジニアとしての経験と手腕を感じるけれども、アルバム作成のアプローチは寧ろ宅録に近いかなり規模の小さいところがあると思う。
最低限の参加ミュージシャン、打ち込みを中心としたビート楽器。
そしてなによりも、かなり押さえ気味のポップライン。1980年にこれまでの西海岸音楽路線を脱却して当時流行していたパンクミュージックへの挑戦の如くシンプルに演奏されたアルバム「Whirlwind」に近いシンプルであっさりしたメロディが目立つ作品であると思う、この21世紀初のAndrew Goldのアルバムは。
しかし、よりしっとりしているというか、良い見方をすれば「Whirlwind」では表現されていなかった熟年の落ち着きを感じるし、悪い意味で言えば、それ以降のエレクトリック・ポップ界の色に染まってしまった方向性がそこかしこに現れて、シンプルに余計な贅肉を付けてしまっているともいえるアルバムなのだ。
元来派手さという単語には無縁の良心的なシンガーであるけれど、その派手さの無さに輪をかけてあっさりしたソリッドなアルバムになっている。しかも、かなりラフで生音に近いアレンジが多い。
ライヴ感覚を活かしてその方向性に統一してくれれば、それはそれで面白かったのだが、Andrew Goldらしい拘りなのだろう、テクニカルな音も少なからずアレンジされていて、どうにもどっちつかずのアルバムに終始してしまった感じは否めないのだ。
無論、全体としてはロックンロールのロアな側面をなるべく生のままにはじき出そうとしている姿勢は見て取れるけれども。
しかし、キャッチーなAndrew Goldらしいソングライティングまで、このアルバムのモノクロームのジャケットみたいにくすんでしまっているのは少々期待ハズレ。
メロディだけを引っ張り出して分析するとAORらしいやや平板で淡白な進行が目に付く音の流れになってしまっているようでもある。
全体としてはロックンロールの割合とアクースティックな割合が多目な作風である。
#1『Ain’t It Just』は打ち込みドラム−大半のトラックが打ち込みドラムなのだが−が余り気にならないくらいの粘りとパワーのあるギターロックとリズムロックが組み合わさったナンバー。かなりAndrewにしてはラフで粗めの創りをしており、このアルバムのカラーを表わしているような佳曲でもある。
このナンバーで、ある程度本作の行く道が予想できそうだ。ドラムプログラミング、Andrewのヴォーカルの重ね撮りによるコーラス、泥臭いギター、と。
#2『Big Fat Daddy』はブギ・ウギ調子のクラシカルなバス・コーラスと捻じ曲がりながらビッグバンド的に展開する崩れたメロディがファンキーにバタバタと暴れるナンバー。オールディズというかR&Bの焼き直しのようなナンバーであり、The Bellbottomsで見せたクラッシックなブギーを再編成したような小作。シンセホーンまで入れているのはさすがにAndrewの芸の細かさを思わずにはいられない。
#3『The Night Show』はこれまた重めのエフェクトを掛けたギターが泥臭い音色を出し、そのバックにかなりのシンセノイズを加えた、アバンギャルドな風味のある曲。WaxでGraham Gouldmanと展開したミステリアスなポップワールドを懐かしむような手触りがある。
ここまでの3曲はとてもLA録音とは思えないような泥臭い南部風のギターが目立ち、しかもあまり素直なメジャーコード的なポップセンスが伺えないという、Andrewにしては異色な展開をまず突き付けてくれる。
#4『Crawl Into The Light(9/11)』は副題の「9月11日」にあるように、今年非常に多くのシンガーが取り上げたアノ話題を歌ったもの。これに関しては今更言うことは余り無い。このトラックはBryndleのメンバーが全面的に参加している。Kenny Edwards、Wendy Waldman、Karla Bonoff、Scott BabcockとまさにバンドがAndrewのソロ作に横滑りしただけである。
最初にKennyのマンドリンが流れてきた時は、をを、と思ったが、かなりアンビエントなシティ・フォーク調子の曲であり、Bryndleのコーラス以外はあまり聴き所がないナンバーでもある。もっとも、曲の内容が内容だからそれはそれで適切な気はするが。
#5『Highwire』も似たようなモダン・フォークナンバーである。このあたりの繊細さはAOR時代を通過してきたシンガー・ソングライターの持つ特徴であるのだろうが、どうにも少し物足りない。次の#6『Driven To Extremes』はロックのビートが#5よりも際立っているが、似たようなAndrewのヴォーカルを多彩にオーヴァーダビングしたコーラスは#5と同じだし、何処となく鬱な雰囲気の漂うメロディも似通っている。決して暗くは無いのだが、あけすけに明るい訳でもないというポイントが今作の特徴かもしれない。
一言で述べれば、内省的。パーソナル・ワーク的な位置を持つアルバムか。
内省的なのはピアノの弾き語りナンバーである、哀しいバラード#7『Hannah』が代表格かもしれないが。
#8『I Think I Love You』ではラップやスクラッチまで飛び出すというWax時代など問題ならないハメの外し方をしているのは、内省的という概念には程遠いかもしれないけど。このナンバーを入れてきたのは少々理解に苦しむところがあるのだが、やはりリズムナンバーやヒップホップに対するAndrewの興味の現われなのだろうか。それは非常に困った事態なのだが。
後半になると、かなり良いナンバーが増えてくるのも特徴である。
#9『Sure Got Quiet In Here』はやっと出現したAndrewらしい親しみのあるメロディに軽快でドライヴィングなすピードロックが映える良曲。ピアノの連打に、ラフなギターが豪快に絡んでいくルーツロックナンバーである。このナンバーは1980年のロック作品「Whirlwind」をストレートに連想させる。
アクースティックで西海岸的柔らかさを持った#10『Don’t Talk About Forever』はAndrewのヴォーカルを活かすことができるメロディを持ったナンバーで、#5や#6のアクースティックさとは少々趣を異にしている。ペダルスティールのような弦をシンセサイザーで表現しているところが、このアルバムが殆どワンマン録音である所以であるのだが、こういう曲ならミュージシャンを募って録音して欲しかった。Andrewの人脈には西海岸を中心に広いものがあるのだからそれを活用しないのは勿体無い。
これは、やはり「Intermission」的な狭間にあるアルバムだからなのだろうか。
#11『Good Luck』は何処となくユーラシア大陸的なエスニックな雰囲気を持つナンバーである。シタールのような音色まで聴こえてくる。ミステリアスというかプログレッシヴなシンセサイザーやエコー、ヴォーカル処理を随所に取り入れている。
#12『Drama Queen』も同じようなプログレッシヴなリズムナンバーである。この2曲はWaxに先祖返りしたようなアレンジを大量に含んでいる。特に#12は女性が電話で話しているトーキングまで入れて、完全に前衛リズムポップに染まっている異色ナンバーである。
この2曲に正対するようなナンバーが、#13『It Happened To Me』である。西海岸の懐かしさを一杯放出しているハートウォーミングな曲だ。この曲は#4に続いて数少ない非ワンマンレコーディングなトラックでもある。暖かいコーラスにペダルスティールがゆったりとしたオーセンティックな曲を支え、しっかりと強弱を付け曲をロックンロールに盛り上げる流れはウエストコーストの王道路線。
#7に次いでピアノの弾き語りで進むのが最終トラック#14『A Little Mercy』である。こちらにはドラムマシンやギターもフューチャーされるが、骨組みはピアノバラードという点は変わらない。然れども、暗さが目立っていた#7と比べてしまうのも何だが、#14はよりメロディアスでジンワリとした核の存在するバラードである。
この最後の2曲はかなり良い連続となっている。#9から#10への展開と似ている。
このような一言でいえば、手を余り掛けていない(ように聴こえる)シンプルなメロディと地味な歌が大半を占めるという、こじんまりしたアルバムは、やはりAndrew Goldにとっては息抜きというか、少々リラックスして拵えた「Intermission」=「休憩」という位置に属するのではないかと思うのだ。
これから来るべき21世紀に向けて、これまでやってきた音楽で遣り残したことを、一通りこっそりと再構築してみたという様相を覚える小作品である。とはいえ14曲とヴォリュームは盛り沢山だが。
Andrew Goldのシンガーとしての魅力は全く損なわれていないし、Waxや「...Since 1951」のようなエレクトロニカルなポップロックに抵抗が無いのなら聴いて決して損はしないだろう。
筆者としては、集大成の取り零し的なエレクトロニカやテクノナンバーは切り捨てて、シンプル/アクースティックなザックリしたロックアルバムに纏めて欲しかったのだが。
しかし、この中休み−Intermissionで休憩したAndrewは一体これからどういった活動をしていくのだろうか。
この番外編的なアルバムで20年の活動を吐き出してしまってくれれば良いのだが。
できればデヴュー当時のような瑞々しい西海岸サウンドを聴かせて貰いたいと思うのはファンの儚い願望かもしれないが、まだ才能的には枯れ果てた人ではないから、今後には十分に期待できるアーティストであると思うし、「Intermission」でも次に繋がる手応えを感じることはできた。これは収穫であったと考えている。 (2003.1.12.)

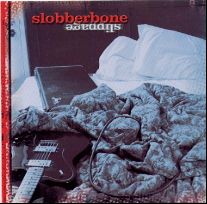 Slippage / Slobberbone (2002)
Slippage / Slobberbone (2002)