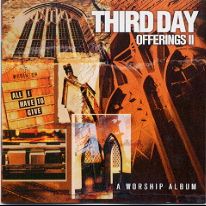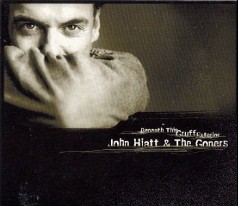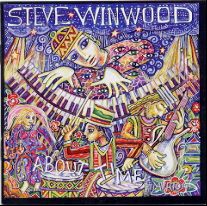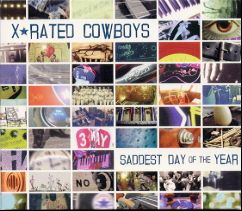 Saddest Day Of The Year
Saddest Day Of The Year
/ X-Rated Cowboys (2003)
Roots ★★★☆
Pop ★★★★★
Rock ★★★★
Southern&Alt-Country ★★☆ You Can Listen From Here
◆Dan Baird、アンタは偉い!!
↑ネタが古いので若い人には分からないかもしれない。(苦笑)
個人的には、Dan Baird関連のアルバムでは、Mount Pilotの2ndアルバム「Mount Pilot」以来の大当たりとなったアルバムである。
Yayhoosの「Fear Not The Obvious」、Fred Harringの「This Grand Parade」、Chris Knightの「A Pretty Good Guy」、そしてDan Baird And The Sofa Kingsのライヴアルバム「Redneck Survant」と比較的大人しいAlt-Country RockからRoots Rockまで参加するアルバムは必ず一定量の良さを刻んでいる人だが、このX-Rated Cowboysの2作目「Saddest Day Of The Year」のようにポップとロックとルーツとカントリーのバランスが取れまくっているアルバムは久々と感じる。
というよりも、Mount Pilotのように1作目が平均以上のアルバムではあったが、物凄い特色がなかったのと似ていたX-Rated Cowboysが、Dan Bairdがプロデュースしたことで一気に2作目レヴェルアップを果たした事が、類似しているので、余計にそう感じるのかもしれない。
とはいえ、Mount Pilotは1stは大凡作だったし、既に活動停止してしまったので、筆者が寄せる期待はX-Rated Cowboysの方が遥かに大きい。
そして個人的2002年のベストに唯一2001年からのチョイスとして彼等のデビュー盤「Honor Among Thieves」を筆者が選んでいるように、1stアルバムはレヴューが書き難い平均的なアルバムであった事は確かなのだが、良いアルバムだったことは間違いない。
◆2枚のアルバムトラック#1から#4までの前半戦で分かる、バンドの成長と方向性の違い
対比として1枚目・2枚目のアルバムの4曲目までを書き出しておく。
「Honor Among Thieves」 V.S. 「Saddest Day Of The Year」
#1『Trans Am』 #1『Just Can’t Wait』
#2『Rear View Mirror』 #2『Whoever You Are』
#3『End Of The World』 #3『Only Everyday』
#4『Devotion』 #4『Evicted』
「Saddest Day Of The Year」のファーストナンバーである#1『Just Can’t Wait』は、そのゆったりした曲速や落ち着きの感じれる雰囲気が、デビューアルバムの1番手だった『Trans Am』に似ている。
実際に、#1を初めて聴いた時は、「おお、1作目に似ているかもしれない、このアルバム。」とある程度の安心感を抱いたものだ。
同時に、「この調子ならポップさに関しては不安無しだな。」と「またカントリーを感じる曲が多いのかな?」という期待と不安が入り混じった思いが脳内を走ったことも確かだ。
しかし、それ程注意しなくても#1『Just Can’t Wait』はアレンジ面でかなり前作の頭出しの『Trans Am』とは異なっていることが判別できるようになった。
『Trans Am』で土臭い空気の放出口となっていた、ラップスティール、バンジョー、そして幽かなピアノといった楽器が新譜の#1『Just Can’t Wait』では全く使用されていない。特にボトルネックギターが全廃された事は寂しげなアクースティックとグラスルーツの雰囲気を減量させてしまっているが、代わりにロックンロールとしてのズッシリした手応えが格段に増している。
そのロックリズムの増量に力を貸しているのが、ハモンドB3とバタバタと鳴るバスドラムにスネアだろう。直接的に感性へ接触するアーシーな音は減っているが、大地に根を下ろした如くの安定感は些かの揺るぎもない。
そして、何とDan Bairdがリードギターを弾いているのだ。そのヴェテランの経験が自然な重みとなって滲み出るような音色は、ギターの音色で訴え掛けてくるものが多量に含まれていると思ったりする。一言で述べれば、感無量。
1st作の2曲目『Rear View Mirror』はそのタイトルがHootie And The Blowfishの90年代最高にセールスを記録した“ロック”のアルバムを連想させ、タイトルからして好きなのだが、それ以上に1つの曲としてデビューアルバムでは最も好きなナンバーだ。
B3オルガンとバンジョー、マンドリンがメジャーでポップなラインを押さえて行く、ミディアム・ルーツロックナンバーでは最高級の出来を誇る#2は、X-Rated Cowboysのルーツを土台としたメロディメイカーの才能と、BeatlesやBeachboysばりのコーラスワークを自在に扱う技量を如実に示してくれた傑作だった。
が、#2『Whoever You Are』はYayhoosやGeorgia SatellitesがDanを介してX-Rated Cowboysに乗り移ったと錯覚を覚えるくらい、トワンギィでサザンフィーリング満載のロックンロールだ。
恐らくこの暴走エレキギターのアンサンブルには、バンドのリードギタリストであるAndy HarrisonだけでなくDan Bairdも参加しているに違いない。そう確信させるくらいフックを打ち付けるドライヴ・ロックだ。
この2作目の#2と対比するには、デビュー盤の#3『End Of The World』の方が相応しい。
ロカビリーとカントリー・パンクをB3オルガンで混合させたような『End Of The World』はモロにカントリーロックやトラッドフェスティヴァルナンバーの野暮ったい面を表現している。
が、同じようにスピーディな#2『Whoever You Are』では、ロックの速さは共通に覚え得るが、ロカビリー的な軽薄さは皆目感じないのだ。
同じように、Alt-Countryの節回しが顕著な軽快チューン#4『Devotion』では、スライドなラフさが全編を流れていくが、やはりカントリー音楽の影響が濃い。
2ndアルバムの#4『Evicted』もラフで粗い演奏が特色のルーツロックナンバーだ。少々ビターでザクザクした曲であることも前作の4番目のトラックと類似項に当たるだろう。
が、#4『Evicted』はロックナンバーとして一層タイトであり、泥臭さくもある。つづめて云えば、カントリーロックらしさは殆ど知覚出来ない。
順番が前後するが、「Saddest Day Of The Year」の3曲目、#3『Only Everyday』はWorry StonesやCounting Crowsの手触りに近いキーボードルーツソングになっており、かなりアメリカントラッドへのアプローチを感じる。
が、引き合いに挙げた2つのバンドと同じく、ルーツィであるけれど、カントリー・ミュージックのエッセンスは希薄という曲なのだ。
ウィルツァー・ピアノのホワンとした音色にシャカシャカと忙しいタムにシンバル、そして暖かいコーラス。この曲はAmerican Trad Rockではあるが、前作の3曲目や4曲目のようなカントリー風味のナンバーでは断じて、無い。
ここまで書くと、X-Rated Cowboysの2枚の差が明確に浮き出てくると思う。
◆18禁扱いのカウボーイ隊 ?
X-Rated Cowboyを日本風に訳すと、副題のようなモノになる。又は、18歳未満は入隊禁止のカウボーイズ、てな感じでも良いかな。
とはいえ、歌詞に淫語をバンバン混ぜるとか、セックスとかドラッグとか退廃とか排泄物について歌いまくるアングラなバンドでもない。
2002年の始めにデビューアルバム「Honor Among Thieves」をオーダーした時に、そういった“お下劣”、“愚連隊”(完全に死語)的な斜に構えた所があるかもしれないと思っていたのは秘密だ。(笑)
筆者の淡い期待(ヲイ)は裏切られたわけだが、Cowboysという単語の入ったバンド名を関したこのグループは、名は体を表わすではないけれど、まさに気持ちの良いカウボーイズのロック、即ちカントリーロックやルーツポップをたくさん聴かせてくれた。この点に於いては、X-Rated Cowboysは期待通りの音楽を聴かせてくれたと云えない事もない。
と持って回った謂い回しになっているのは、カウボーイ的な音楽もあるのだけれど、それ以上に普遍的なルーツィでポップなトラックが多数入っていたからだ。
確かに、モロCowboysの名前に合致したイメージの曲もかなりあるのだけれど、Cow Punkやウエスタン、そしてグラスルーツ系のサウンドだけでは断じてなかった。ここでは寧ろ良い意味で予想を裏切ってくれた。
しかし、X-Ratedと修飾されているけれど、このCowboysは大人専科では絶対にない。反面、お子様向けのグディ・グディなカントリーバンドでもない。
つまるところ、極端な属性は存在せず、老若男女−どの年齢でもカントリーやポップス、ルーツロックを好むリスナーなら、問題なく受け入れられるバンドだと思っている次第だ。
Elvis Costelloや「Lost Together」、「Five Days In July」の頃のBlue Rodeoを重ねられるアダルトロックとルーツやカントリーの要素が芳醇なバンドだ。
殊更アダルトな雰囲気も無いのに、18禁扱い(国によっては21未満禁。米国だから寧ろ21歳未満禁止の方が正しいのかもしれない。ど〜でも良いけど。)されるように危険なロックバンドではありえない。
恐らく、X-Rated Cowboys特有のジョークがバンド名にも反映しているのだろう。
彼等の悪ノリというかお馬鹿加減は、オフィシャルサイトの殆どマトモなことを書いていないバイオグラフィを斜め読むだけで理解できるだろうから、一度目を通してはどうだろう。
何故、未成年禁止のカウボーイズという名前が付いたのか、予想が何となくだが可能になると思われる。
◆カウボーイズのポップから本格ロックバンドへ
2001年末に発売された、X-Rated Cowboysのデビュー盤は基本的に緩めのルーツロック・ポップとロカビリー系の中西部カントリーナンバーが殆どだ。
当初、1st作を聴いていた時には、そのポップセンスの清冽さに目が行ってしまいがちで、あまりカントリーやロックンロールといった要素を顧みることは無かったように思える。
これが、2枚目では本格的なロックバンドへと変貌を遂げたのだ!!!!!
◆と前半を聴いた時点では書きたくなるのだけれど・・・・
懐の深い、アーシーな南部風バラード、#5『Fallen』ではラップスティールが、ボトルネックギターが、そしてオルガンが思いっきりサザン・カントリーの調味料を一面に散逸させてくれるのだ。
当然、ベタなカントリーナンバーではなく、キーボードやアクースティックギターが、整ったポップバラードとしての足掛かりをアンサンブルへと添加もしてくれている。
しかし、バンドの出身地オハイオを象徴するようなグラスルーツさの大気は消し去れない曲でもある。
更に、まんまなウエスタン・ポップ、キャッチーなロカビリー風ポップスの#7『High & Lonesome』でも、そのストレートなポップラインに紛れ込んでしまいそうになるのは1stアルバムの曲群と同じとはいえ、かなりのブルーグラスをベースとしたお気楽な雰囲気があるロックナンバーが聴ける。
が、単なるお祭りグラスポップに成らないのは、オルガンと切れ味の良いロックリズムの賜物だと考えて良い。これも1stアルバムで評価できた点と重なるが。
そして、後半の息抜き的な#10『Drinkin’ For Two』では、ラップスティールの泣き、ゲストヴォイスによるローファイラップに加えてバンドのキーボーディストBob Hiteがオルガンだけでなくアコーディオンの蛇腹を波打たせている。
もう完全なブルーグラス風のバラードになってしまっているのだ。
以上から、まだ完璧なカントリーロックからの脱却は行われていないことは即、判断可能だ。
が、これがマイナスに働いているというと、そうでもないのだ。
◆怒涛のロックンロール攻勢 / やっぱり鍵盤メンバーがいるバンドは良いなあと思ったり
まるで、Dan Bairdの魂が離脱して乗り移ったとしか思えないような、アメリカ中西部のルーツィなロックナンバーが目立つようになったのが、2枚目のフルレングスの最も輝く特徴である。
#6『Behind』では、南部地区バンド顔負けの土を掘り返すという比喩が一番似つかわしい、ハードでキャッチーなアメリカンロックが、まさにアルバムの真ん中にパイルドライヴァーをブチ噛ます。
スライドギターが大暴れしてくれるが、中盤では少し弱虫君に泣いてくれる強弱の付け方も微笑ましい。
ここでもピアノからシンセサイザー、そしてアコーディオンは元より、トランペットやサックスまで吹きこなすBob Hiteがオルガンを滑らせている。
が、このドラスティックなロックシアターでサックスを吹くのは、ユニークなバイブロックと呼ばれるO.A.R.のサキスフォンニストであるJerry Depizzoなのだが。
続くカントリーっぽいが歯切れの良い#7を経由し、#8『Saddest Day Of The Year』が満を持して登場。
タイトル曲に恥じない、ガッツの入ったハード・パブロックとでも呼びたい、暴走ロックナンバーだ。乱れ弾きされるアクースティックピアノ、弾けまくるリズム隊、そしてDan BairdとAndy Harrisonのギターのバトル。
実に野放図なロックトラックだ。
1枚目のアルバムでは少し鼻に掛かった青臭さが残っていたリードヴォーカリスト、Quinn Fallonの声も、タフさとパワーをかなり成長させている。Dan Bairdがバックコーラスに加わったため、全体的にコーラスは綺麗だった印象の強い1stアルバムよりも荒っぽくなっているが、それはそれでロックが加速している雰囲気にバッチリ合致している。
古典的なブリティッシュ・ルーツロックの、FacesやRolling Stonesの1970年代を活き活きと映し出したと顕わせるナンバーだ。カントリー的なアプローチよりもパーティ・ロックンロールのジョイフルな浮かれ雰囲気をビシビシと叩き付ける箇所が、パブロック的な面ではなかろうか。
更に、ロックンロールの重連、3重連の機関車は驀進する。
ピアノの音色がクリアに響く、少しスピードが緩んだ#9『Stupid』。ガチャガチャした図太さでは#2や#8には及ばないが、その分メロディラインの綺麗さと流暢さを楽しむ余裕がある。サクサクと進んでいくアンサンブルは気持ち良さを聴き進むに従って増やしてくれる。
Pop/Rockのフックと即効性では、アルバムのどのロックトラックよりも上位に登ってくるファーストクラスのロックチューンであると思っている。
そして、ラストイグジットになる#11『Nowhere Is My Home』。
#6からロケットスタートする怒涛の“後半攻勢”、を何ら盛り下げることなく、雄大な気分でフェイドアウトさせることを可能とする効能があるナンバーだ。
余裕タップリなミディアム・ファストなテンポを、壮大な広がりのある雰囲気で拡散させていく、ロックンロールの存在感をじっくりと内面に向けて問い掛けてきてくれるような曲なのだ。
X-Rated Cowboysを生み出した土壌と成った、広大で平原の多いオハイオ州の田園風景を瞼の裏に俯瞰できそうな、広大なイメージを伴っている。
後半部分でメロウに、そしてアーバンライクに挿入されるサックスの音色が、ピロピロとバッキングされるキーボードや高音を叩くピアノ、そして乾いたドラムと重なり、草原を吹く風のようなブリッジを形成。
そしてフェイドアウトしていく。最後に残る曲感の後味が実に宜しいのだ。このタイプの曲は1枚目にはまるで無かった事を鑑みると、やはりプロデューサーのDan Bairdが良い仕事をしたとしか思えないのだ。
大ファンの贔屓目を控除したとしても、成長の急上昇するカーヴは傍目にも明らかだから。
それにしても、鍵盤担当がバンドメンバーとして加わっているグループは、心にその特色を刻み付ける深みのある演奏が出来るのは、少々不思議でもある。
キーボードパートにゲストを参加させて、演奏を完成させるバンドよりも総じて音がまろやかでありつつも鋭角的なキレがあるサウンドを形作れることが多い。何事にも例外はあるし、例外が大勢を占めることも多々あるが、X-Rated Cowboysは例外にはならない好例だ。
◆X-Rated Cowboys
はロックンロールの中心地であり、筆者の大好きなHensley Sturgisも活躍しているコロンバスで活動する5人組のルーツバンドである。
リーダーはQuinn Fallonという人で、全ての曲を書いている。1stアルバムではマンドリンやバンジョーを弾いていたのだが、今回はアクースティックギターのみになっている。
このことも2枚目での変遷の象徴となると思う。
他のメンバーは前作もプロデュースを手掛けているリードギタリストにしてバックヴォーカルやボトルネックギター担当のAndy Harrison。今回はDan Bairdと共同プロデュースを行っている。また、シンセサイザーも弾けるマルチプレイヤーでもあったりする。
リズム隊は、ドラムスにC.Douglas Wells。かなりバタバタな音が出せる、筆者好みなドラマーだ。
そしてベースにBen Lamo。あまり目立たない気がするが、それはベーシストの宿命みたいなものだ。(同情)
で、このバンドを特徴付ける、パーマネントメンバーとしてのキーボーディストBob Hite。
2000年頃には地元ではかなりの人気が出るバンドになっていたそうで、このアルバムからも#3『Whoever You Are』がローカルラジオでヒットを記録していることの事。更に#8『Saddest Day Of The Year』と題にそぐわない元気印なタイトルトラックもヒットの兆候を見せているそうで、順調の模様なのは何よりだ。
2001年年末に発売された1stアルバムは、インターネットを中心として評判を地道に稼ぎ、大手のオンラインショップなら何処でも手に入るくらい好評を得るようになった。
そしてほぼ1年数ヶ月で2作目「Saddest Day Of The Year」のリリースが順調になされた。これもまた嬉しい。
◆米国中部のルーツロックバンド、プラスアルファ
再三記述しているが、カントリーロックの優良ポップな面と、ブルースやロカビリー、ハートランドロックといった要素が混在していたAlt-Countryが柱となっていたデビュー盤から、かなりRoots Rockがメインになる音楽性に移行しつつある傾向が見れる。
が、時折挿入されるカントリーな土着音楽に根を発したサウンドが、何とも言えない優しさとリラックスできる空気を付加してくれている。このトラッドに接点を持とうとする姿勢が、X-Rated Cowboysの独自性として良い方面を向いて開花しているのが現状だろう。
これからよりパワーロック的な南部サウンドに移行するのか、それとも再びAlt-Country中心の組み立てになるのかは、現状では何とも云い様がない。が、どちらへと転がるにしてもキャッチーでハートウォーミングなソングライティングは忘れないバンドである事には確信を抱いている。
2枚連続のポップさには、完全に白旗だから。まあ、個人的な嗜好では、もっとロックンロールを太くして欲しいとは思うが、そうなるとHensley Sturgis等と区別が付かなくなる可能性もあるので、微妙な気持ちでもあったりするが・・・。
何はともあれ、Dan Bairdの眼鏡に留まる才能は持っていたのだろうが、それを引き出したDanの眼力には素直に敬服したい。繰り返すが、やっぱりこのオッサン凄い。 (2003.6.20.)
 TCG / The Color Green (2002)
TCG / The Color Green (2002)
Roots ★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★★
Adult Alternative ★★★ You Can Listen From Here
◆ジャケット無しのバンドThe Color Green
The Color Greenは、リーダーのJon Kahnのソロ作以外は、ジャケットを持たないアルバムが3枚続いている。
正確に言うと、mp3.comからmp3フォーマットのCDをリリースしているため、味気ないmp3.comデフォルトのジャケットが使用されているのだが。
このmp3CD-ROMのジャケットは以前は白と明るめの青を基調にした角張ったデザイン一辺倒の散文的なものだったが、最近のものになると暗青色のバックに幾何学模様とアーティストとアルバムのタイトルが記されただけの、更に無味乾燥な代物に昇格(?)している。
よって、The Color Greenのmp3.comの試聴ページから画像を拝借して、今回のレヴューにおけるジャケット代わりとさせて貰っている。(Jon Kahn氏了承済み)
が、取り込み画像がデフォルトで画素数が少ないために、このサイズまで拡張すると相当画質が劣化してしまう。実際はこの日の丸ジャケットではないことを念頭に入れて頂ければ問題ないだろう。
ちなみにColor Greenの音源の殆どはmp3.comとオフィシャルサイトでストリーミングが可能であり、ダウンロード出来る曲もそれなりにあるので、上に貼ったリンクから是非試聴に行って貰いたい。
しかし、mp3の音質の劣化何ぞは余り気にしないが、やはりオリジナルなアートワークは欲しいところだ。クレジットも全く無く、単にCDの曲目を書いた紙1枚のmp3ジャケットは味気ないことこの上ない。場合によってはバイオグラフィー等が一緒に焼き込まれている場合もあるが、この「TCG」に限れば全くエクストラなデータは同梱されていない。
これまた少々残念な点だ。何処ぞのメジャーのCDと同様、プロモーションビデオやライヴ映像を同梱されるよりは筆者的にシンプルな音楽のみのCDの方に好感を覚えるけれど。
次こそは、mp3.com系のデータCD発売ではなく、普通のジャケットをあしらったバンドオリジナルの4作目が待たれるところである。
◆プロデューサーはRami Jaffee、そしてエグゼクティヴ・プロデューサーがJeff Hanson
というかなり有名な2名のミュージシャンがこのアルバムのプロデュースを手掛けている。Ramiは2001年発売の前作「It’ll Be Allright」でもプロデュースと鍵盤で全面的にColor Greenと関わっている。
今更だが、Rami Jaffeeは1996年の「Bringing Down The Horse」という、アメリカンロック史に燦然と輝く名盤を頂点にした後、凋落をフリーフォールのように続けているWallflowersのキーボーディストだ。
もうひとりのプロデューサー、Jeff Hansonについてはその声質の方で際立った存在感を放っている人という方が通りがよいと思う。このJeff Hansonはどう聴いても女性の声としか思えないくらい、オナゴ声のシンガーだ。というか、性別を偽っているとしか思えない。(をひ)
このアルバムを試聴すれば、筆者の気持ちは分かると思う。インディバンドであるm.I.J.でヴォーカルを歌っていた頃から、メディアにまで女性と誤解されていたある意味稀有な存在でもある。だがしかし、彼の(彼だぞ。念のため。)名前自体は、女声シンガーよりも、プロデューサーや補助役として有名なのだ。
Creedのアルバムの全てをプロデュース、SR-71のマネージメントといったメジャー系のオルタナティヴバンドを補佐する役割が多い人だ。自分の音楽とはかなり方向性が違うタイプを手助けしているのがユニークと云える。とはいえ、彼の声には敵わないだろうけど。
だが、実は前作からエクゼクティヴ・プロデューサーとしてThe Color Greenに関与している、かなり一般には名の知れたミュージシャンがいるのだ。
何と、メジャーの堕落と退廃ぶりのかなりの割合を背負って君臨している如くな、オルタナヘヴィネスバンドの西前頭筆頭(をい)CreedのヴォーカリストであるScott Stappが統括プロデュースを2枚連続で行っているのだ。
そもそもCreedの前座をL.A.のライヴで務めたことが、一般のロックファンに知名度を広める良い切っ掛けになったということだ。
しかし、CreedとThe Color Greenのリスナーはそれ程共通はしないと思うし、第一Creedの単純馬鹿なアニキ&サブの世界並みにマッチョで汗臭さに頭痛がする程のヘヴィネスさはThe Color Greenには全く存在しない。
やはりメインのプロデューサーは、総括担当ではない、プロデューサーのRami Jaffeeだろう。
◆「Bringing Down The Horse」が聴きたくなるアルバム、「TCG」
このThe Color Greenの音楽性は、かなり野暮ったいルーツロックの色合いが強かったWallflowersの1st作「The Wallflowers」ではなく、2枚目の最高にして最後の傑作「Bringing Down The Horse」の頃に短期間確立されていたメインストリームなモダンサウンドと王道ルーツロックが程好くブレンドされたロックサウンドに通じる箇所が多い。
流石にアクースティックさとルーツィな度合いはこのWallflowersの名作と比較すると、及ばない。
モダンなサウンドを水面下に沈めつつ、アメリカントラッド音楽とロックンロールを絶妙に混ぜ合わせたのが「Bringing Down The Horse」であると筆者は考えている。
であるからして、次作の「Breach」における、中途半端なモダンロックとオルタナティヴミュージックの導入には脳の血管が切れたかと錯覚するほどの怒りを覚え、CDを床に叩きつけたし、4thアルバム「Red Letter Day」での趣味の悪い打ち込みサウンドを聴いた時の失望は赤色巨星並みにでかかったのだが・・・・。
と、最近の2枚には全く失望していたため、必然的に縁遠くなっていたWallflowersの「Bringing Down The Horse」だが、再びこの名盤をプレイヤーに落としてみたくなる。そんな気持ちを与えてくれるのが「TCG」なのだ。
矢張り、キーボードをRami Jaffeeが弾いている点が類似性を大きく接近させている要因の一つだろう。アクースティックピアノは筆者の耳には全く聴こえてこない。完全にハモンドオルガンを中心としたキーボードサンプリングがメインとなっている。
ここも1stアルバムのピアノ中心のアレンジから大幅にオルガンへとスイッチした「Bringing Down The Horse」と繋がる点ではないかと思う。
そして最近のWallflowersが失ってしまった素直な良いメロディ。いかにも西海岸のポップロックバンドといった素直で安心してリスニング可能な曲がたくさん詰まったアルバムが、The Color Greenの特徴だ。
そして、リードヴォーカルのJon Kahnのハスキーでありつつ繊細さを特徴とするヴォーカルは、かなりJacob Dylanの声と似ている部分がある。
男臭い芯の強さを有しながらも、酒場のシンガー・ソングライター的な翳りを同時に反映した声はJacobがメジャーシーンで大売れした起爆剤の1つだと考えているのだが、Jonのヴォイスもポテンシャルとしてはかなり期待の出来るレヴェルにあると思う。
少なくとも、現在のオルタナティヴロックバンドで流行りとなっているPearl Jam風エディ・ウエーダー亜流の低音ダミグラ声の下品系ヴォーカルとは近い面を持ちつつも遠い、本格ヴォーカルだ。
例えば、冒頭のナンバーである#1『You Make The Sun Go Down』や#2『The Fotunate Ones』の親しみ易さは、それぞれWallflowersのヒット曲『One Headlight』、『The Difference』に匹敵する素晴らしさがある。
そこはかとなくルーツィでありつつ、スマートでコマーシャルな曲の連続は、善き時期のWallflowersを彷彿とさせてくれるのだ。
◆が、初期のWallflowers程にはルーツ寄りではない
#1のスタートステップとなるメロトロンサンプリング、そして全編で地道なバックアップを見せるB3オルガンとキーボード。ひき続き#2では、Rami JaffeeがWallflowersそのまんまのハモンドオルガンプレイ。
このようにルーツィな鍵盤類だけなら、多少のモダンさを増しているとはいえ、Wallflowersに匹敵するルーツロックの空気を曲に注ぎ込んでいる。
が、スライドギターやアクースティックギターの使い方は、Creedのヴォーカリストがエグゼクティヴ・プロデューサーを行っているが故なのか、より浮遊感があり、スマートでオルタナティヴ寄りだ。
#1のギター音はかなりAdult Alternative的な性格を帯びている。がそれ以上にBostonの『More Than Feeling』アクースティックリフを現代に甦らせた如くの爽やかウエストコースト風味も兼ね備えている。
必要以上にオルタナではないのが、良い。
#2はハードさを抑え、もっとポップになった『Laughing Out Loud』という感じで、ギターもかなりルーツィになっているのが特徴。ハードドライヴィンでキャッチーという素晴らしいナンバーだ。ここでもハイトーンに弾かれるギター弦が必要以上にルーツロックさを持ち上げない。
メロディの良さ、ルーツロックな側面が#2のように切れているのが、#7『Turn Myself In』だ。Holland Mcrea、そしてJohn Thomasという2名の専任ギタリストを要するThe Color Greenのアンサンブルを代表するくらい、重ねられたギターが心地良い。
初期WallflowersやCounting Crows程にはトラッドロックに極化していないけれど、アメリカンルーツロックの根っ子は固めたサウンド。これがThe Color Greenの音楽の肝だ。
◆モダンでポップな面とルーツロックの融合・同居
#3『If I』になるとスライドなギターとドブロギターを使い、アーシーさを演出しつつ、打ち込みドラムやシンセサイザーサンプリングを使いスペイシーなサウンドを同梱させたトラックになっている。モダンロックとトラディショナルサウンドの奇妙なユニゾンを見れる。
よりエモーショナルなスローナンバー、というよりもパワーバラードの#8『Don’t Look Down』でもアーシーなアレンジが見られる。
がこの曲での最大の見せ場は、感情を切々と歌い纏めて行くJon Kahnのヴォーカルだろう。ハモンドB3やスライドギターの濃厚なバックアップを裏切らない仕事が出来ている。
#5『Do You Come Clean』もシンセサイザーの浮遊感と泥臭いギターが混然としたルーツでモダンな曲だが、よりパワフルなロックチューンだ。こちらはCollective Soulがルーツへのアプローチを忘れなかった頃の雰囲気に似ている性格を帯びている。
Ramiのオルガンプレイが最高潮に達するのが、#9『Everyone』だ。少し寂しげなメロディが意識の片隅に引っ掛かるという感のある、地味な演奏で幕を開けるバラードだが、縦横無尽に弾きまくられるB3がムードをグングン盛り上げてくれる。
更に、ドラムのウエットなスネアとパーカッションのパッキングも次第にエモーショナルに上昇していく曲調をサポートしている。シャウト・シャウトのJonのヴォーカルの瑞々しさは語るに及ばずだ。
◆Adult AlternativeやAlternative寄りなナンバーもある
#4『Under The Bed』は微量な土臭さとアダルト・オルタナティヴの狭間にあるAAA(Adult Alternative Album)と呼ばれるナンバーだ。とはいえ、AAAが恐らくAdult Alternative Americanaと解釈できるくらいルーツ寄りだと思うし、キャッチーさという面ではこれまた際立っている。
AAAというよりも、Collective Soulがセルフタイトル2ndアルバムで突如表現したヘヴィさを持ち込んだナンバーが、#6『Wasted』だ。最もノイジーでアーティフィシャルなトラックで、このバンドの現代的、90年代的な時代性を映している曲だ。このナンバーだけはいまいち。
◆前作「I’ll Be Allright」と比べるとルーツギターとアクースティックな曲は激減
全体としてWallflowersのようなアクースティックギターの音は希薄なアルバムに仕上がっている。前作「I’ll Be Allright」の方が、アコーディオン、マンドリン、ラップスティール、アクースティックギターを積極的に活用し、少なくともギターの面では生な音出しに心を配っていると云える。
このアルバムでは、最後の#10『You’re No Mistake』になって、やっとストリングスシンセサイザーをバックにアクースティックギターやラップスティールが淡々と弦を紡ぐ。この曲でJon Kahnのソロ作で既にその手腕が実証済みのアクースティックナンバーが漸く姿を表わす。
2000年のアルバム「Acoustic」で、既にジャムバンドとは異なった、本物のアクースティックさを見せていたThe Color Greenの異なった一面での本領発揮である。
本作「TCG」では、キーボード類はルーツ度自体を底上げしているが、音質の問題としてのギター類ではよりアダルト・オルタナティヴの血を取り入れたものに移行しつつあると思う。
同時にメロディとアレンジは力強く、ロックンロールの躍動感を感じられるものにレヴェルアップしているが。
前作はルーツィであると同時にアングラポップやジャム的な土壌が見られた面も多かったので、ルーツロックとして包括すれば、割合はイーブン。Pop/Rockとしてはジャンプアップしていると考えるべきだ。
よりメロディアスに、ストレートになったことは歓迎するが、これ以上AAA系列にシフトして貰いたくはないので、痛し痒しな気持ちもある、が正直な感想でもある。
◆mp3.comのデータCDから一般プレス「Rust」へ
1990年代後半から、ソングライターのJon Kahnを核にしてL.A.のインディシーンで活動を開始したThe Color Greenだが、地元の著名クラブやライヴハウスで定期的にライヴを行うまでに成長している。
映画「Girl」のサウンドトラックに7曲を提供したり、MTVの挿入歌としても曲が使用される等、評判を上げている。
何よりも、メジャーバンドの大手Creedの後押しがあるのは大きい。音楽性はかなり異なるのだが・・・・。
また、このアルバムからは、案の定ベストトラックと目星をつけていた#1『You Make The Sun Go Down』と#2『The Fotunate Ones』が地元のロック系ラジオでヒットを記録している。
そして、2002年末には「TCG」をmp3ではなく通常のレートでトラッキングしたプレスCD版である「Rust」を自主発売開始の運びとなっている。
が、このCDも裸販売でオリジナルジャケットは無いらしい。とことんジャケットには拘らないバンドなのだろうか。
また、2003年の春から、OHPやmp3.comにて既に新曲が5曲程DL可能になっている。
Jon Kahn氏に伺ったところ、新譜のための曲で、現在ミックスダウン中とのこと。昨年の「TCG」に次いで、早くも4枚目のフルレングスが今年中にお目見えする可能性も高い。実に貪欲な創作意欲を見せてくれている。
が、出来るなら、新作はmp3フォーマットではなく、The Color Greenらしい顔を示せるジャケット付きのプレスCDになって貰いたい。mp3.comの素っ気無いジャケットではアップロードすることが楽しくないし、この期待のバンドの顔がいまいち見えてこないからだ。
それから、もう1つを望むなら、Rami Jaffeeをプロデューサーとして迎えるのは大いに結構だが、これだけ鍵盤類を駆使するならパーマネント・キーボーディストをバンドに加えて貰いたいということだ。
折角5名体制になったのに、Jonも含めて3人のギタリストがバンドに存在するという構成は、多少行き過ぎな傾向だと鍵盤マニアとして思ったりしている。・・・かなり手前味噌な意見だが・・・・。 (2003.6.15.)
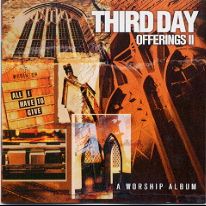 Offerings 2 All I Have To Give / Third Day (2003)
Offerings 2 All I Have To Give / Third Day (2003)
Roots ★★☆
Pop ★★★★☆
Rock ★★★★
Southern ★★ You Can Listen From Here
◆2枚目の「A Worship Album」、続編「2」と考えて良い??
「Offering」とは宗教関連の団体への「捧げ物」、「献金」、「奉仕」という意味で使用される。
また「A Worship Album」という副題が今回も付随しているので、このThird Dayが宗教バンドであることは簡単に見て取れる。
また、もう1つの副題として「All I Have To Give」−「全てを捧げます。」的な意味合いがタイトルに加えられているが、このタイトルはCCMアルバムではかなり見られる歌のタイトルであり、アルバムの題でもある。
クリスチャンロックバンドとしてのThird Dayに関する情報は、前作に当たるスタジオ録音盤「Come Together」にて拙文ながら紹介しているので、そちらを参考にして戴きたい。
今更ながら、Third DayがCCM(Christian Contemporary Music)バンドということを再確認のため、アルバムタイトルに言及するついでに述べておいた。
さて、本作は「Offering A Worship Album」の続編という位置に該当する。
そのまんま「Offering 2 All I Have To Give A Worship Album」となっているので、これは一目瞭然。
スタイルもまた全く同じで、半分近くがスタジオ録音の新曲。そして半分がライヴ録音となっている。形としては、ライヴ盤に新曲がトラッキングされたもので、厳密に述べれば新譜かライヴ盤に新曲を入れただけのレコードかは微妙かもしれない。
しかし、「Offerings 2」では丁度半分の6曲がライヴステージからの録音をマスタリングしているのだけれど、そのうち既存のスタジオトラックを再演しているのが、3曲だけ。メドレーとして既出のナンバーを取り込んでいる歌も1曲あるのだが、そちらも1曲として考えると殆ど新曲として解釈できる。
ということで、3曲しかアルバムでこれまでに聴けたトラックは入っていない。これはライヴでしかお披露目されていない曲をピックした新譜と考えるべきだ。
「Offerings」では11曲中6曲がライヴトラック。その内、5曲が過去の3枚のアルバムからの選曲だったことを考慮すれば、「2」における新曲率は非常に高くなっている。4分の1が既出、残りは新しく発表されたナンバーだからだ。(必ずしもオリジナルではないのだが。)
だから、ライヴ音源入りの新譜として見ても良いし、レアトラックスと新譜が混在したイレギュラーな新譜と考えても問題ないだろう。筆者は前者と見なしているが。
更に云えば、ライヴ盤は殆ど購入しないが、Third Dayの「Offerings」“シリーズ”(これからも続くかは不明だが。)に限れば、全く買うことに躊躇を感じない。純粋にアメリカンロックを楽しめるし、これまでのどのスタジオ録音盤よりもオルタナティヴ度が低いのは「Offerings」で実証されているから。
ここでThird Dayのアルバムに寄せられたメッセージを紹介したい。つい直前に「Offering」がこれからも続くかどうかと疑問を述べているが、その回答も予想できる、かもしれない。
「『何故、また「Offerings」のレコードを作るのか?本当にもう1枚Worshipアルバムが必要なのか?』という質問が結構寄せられた。そして僕達自身もレコード作成を決定する前に真剣に同じ事を自問した。
そして、僕達の回答が、今聴こうとして手にとっているレコードになる。
主とThird Dayと信仰心は切り離して考えることは出来ない。主はいかなる人々と信仰心から切り離して考えることは出来ない。僕達は主に与える事の出来るものは、須らく捧げなければならない。
ミュージシャンとして、僕達は音楽を捧げることを選んできた。信仰が音楽だけを意味するものではないけれど。僕達は主を僕達の持っている特技で敬っている。この世で与えられた縁で敬っている。人生そのものを賭して敬っているんだ。
僕達はこのレコードが、全てを与え給うた主に君の持つ全てを捧げる手助けになればと考えている。」
・・・・正直、この信仰心は理解不能・・・・。まあ、ざっと総括すれば、神様を称えるための手段として音楽を演奏できるから、目一杯活用して神様を尊敬しよう。それにはレコードを作ることが一番良いんだ、てなところだろう。
毎度の事ながら、CCM系の音楽は意識的に歌詞を排除して純粋に音楽だけを楽しむことにしている。これが筆者流の宗教音楽との付き合い方。
◆アクースティックでロックな「Offerings 2」
2枚前の第一弾「A Worship Album」の特徴は、かなりアクースティックなアレンジが目立った事だ。2000年までヘヴィなエレキギターが目立ったThird Dayが革新を始めた一歩となったアルバムだ。
また、Bob Dylanの『Saved』をカヴァーした実績から見られるように、自らの音楽ルーツの根本を掘り下げようとする姿勢が感じられたことも特徴だ。
翻って、第二弾である「Offering 2」はどのようなアルバムになっているだろうか。
全体としては、アクースティックギターの活躍もかなり見られるし、同時にロックンロールのダイナミズムも成し遂げている。この点に於いては、「Offerings」を正統に継承する「2」という呼称は適切以外の何物でもない。
が、本格的な南部サウンドへのアプローチを始めて純粋に開始している前作のスタジオ録音盤「Come Together」でそれなりに含まれていた、流行ではない本格派ロックンロールのパワーが目立つ曲が多いと体感出来る。
更に、最も重要な点が、アメリカンルーツを感じさせる音−決して南部サウンドの泥臭さに依存し切ったのではなく、ナチュラルにアーシーで安定感のあるサウンド−をデビュー時とは比較にならない程出せるようになったことだ。
今作ではDylanの『Saved』程の古き善きオールドロックンロールを直接に印象付ける曲はないのだが、何処となく懐かしさを感じさせる下地を持った曲が殆ど。
1980年代のアルバムオリエンテッドなPop/Rock、Adult Contemporary、そしてSouthern Arena Rockと呼び習わされたキャッチーでポップ化したSouthern Rock、最終的には産業ロックやアリーナロックまで加えても差し支えなかろう。しかもちゃんとアメリカントラッドを叩き台にしたREO SpeedwagonやMark Stanley Bandのヒット性をトレースしたサウンドが記憶の底から浮かんできそうなアレンジとメロディがとても印象的だ。
厚目のロックアンサンブルに、南部特有の固い芯が通ったサウンド、そして宗教バンドならでわのチャーチミュージックのセンチメンタリズムと包容力が加わり、大仰でありつつ美しい音楽を広げるアルバムになっているのだ。
アクースティックな音色で表現される美しさとは少々趣が違い、ほんのり土臭い中で躍動するロックギターとリズムセクション。たっぷりと質量を覚える、1980年代までメインストリームの一角を占めていたTop40ロックンロールの味わいがあるアルバムだ。
◆ゆったり系(?)が多い、スタジオ収録の新曲
スタジオ録音の新曲は6曲。メジャー系3枚目のCD「Time」から常にThird Dayのアルバムのピアノ類を弾き、プロデュースを担っているMonroe Jonesが手掛けている。
収録位置は、#1、#2、#4、#7、#9、#10となっている。頭2曲がスタジオ録音曲という構成は「Offerings」と全く同じである。
全体を俯瞰するため、ライヴトラックを排除して、この6曲だけを選曲して何度か聴くと、バラードタイプの曲が過半数を占めることが分かる。
#4『Offering』、#9『May Your Wonders Never Cease』、#10『The Everlasting』の3曲は哀歌以外の他に名の付けようがない完全無欠のスローバラード。
#4『Offering』は寂しげなメロディをピアノがトレースする、ややマイナー調のバラードから、グンとメジャーコードに転調し、またマイナーへ戻ることを繰り返す、産業ロックタイプのバラード。ロックコーラスの部分でのB3オルガンとピアノの美しいプレイと1970年代のStyxを思わせるメロディックなギターが宜しい。
#9『May Your Wonders Never Cease』もシンセサイザーとエレクトリックパーカッションで淡々と進むメイン・ヴァースから急上昇するコーラス部分のロックの格差が著しいバラード。こちらはハードロックのバンドがシングル用としてトラッキングするマイナー風パワーバラードの体を見て取れる歌だ。
#10『The Everlasting』はローズピアノサンプリングの覚束ない鍵盤の音色からスタートし、アクースティックギターがしずしずと歌を編み上げていく、アクースティックなバラードだ。必要以上に流れに凹凸を付けずに、しっとりと纏める所は大仰なバラードが続いた後には良いインターミッションになっている。
しかし、コーラス隊をここでも投入し、チャーチミュージックの一端に連なる空間の広さを見せているところは、矢張り宗教バンドだ。
が、やはり最高級の新曲はミディアムテンポ以上のナンバーだ。
ヴォーカルのコーラスで幕を開ける、#1『Sing A Song』。決してガリガリのスピードロックではないのだが、南部サウンドに必須などっしりとした土臭い安定感抜群な曲だ。ザクザクと食い込むギター。オルタナティヴ程下世話ではないけれど、1990年代の音を表現している少しスマートなギターアレンジ。
間奏で飛び出す男女ゴスペルコーラスとヴォーカルのMac Powellとの掛け合い。
南部でも都市部を思わせるロックサウンドにゴスペルの暖かさが融合した感覚のフュージョン形態なナンバーと云って良いかも知れない。
#2『You Are So Good To Me』はロックの馬力は#1には及ばないが、これまた奥の深さを有したミディアムチューンである。ストリングスをスタートから巧みに使い、そこへコーラス隊とバンドのエレキサウンドを載せている。
特にコーラス部分でのゴスペル隊とストリングスのユニゾンは、大宇宙の広がりを視覚化してしまえる位に、開放感が伴った優しさを運んできてくれる。
このマイルドでマッタリした雰囲気はこれまでのThird Dayに欠けていた物だと思う故、かなり貴重な曲だ。
また、最もアクースティックで土臭いナンバー、#7『Anything』は、真性のルーツロックトラックと見なしたい。数本のアクースティックギターにアクースティックスライド、そしてエレクトリックスライドギターが軽快でキャッチーなメロディを重ねていく。適度に弾むラインもまた心地良い。
このサザン・トラッドをオープニングリフから直裁的に臭わせるルーツィなアレンジは、Third Dayとしての初の試みだと思える。更に、ブリッジ部分の「ハレルヤ」のコーラスでは女性コーラス隊とスライドギターが頑張って、更に曲の締めを感動的にしてくれている。
一見派手さ、#1や#2のコマーシャル性が少ないように見えるけれども、実は最も出来の良いナンバーかも。
◆U2の『With Or Without You』も独自アレンジしたライヴ曲
ライヴナンバーのうち、2曲が前作の「Come Together」からのチョイスとなっている。
該当アルバムのレヴューでも筆者がそこそこ誉めているバラード#5『Show Me Your Glory』。そして続く#6『Nothing Compares』だ。
#5はオリジナルよりもドライ且つヴィヴィッドに富んだバラードになって、より美しさを増している。ライヴトラックのバラードの中では最もフッキーなコマーシャル性のある曲だと思う。
#6もアリーナーバラード的な雰囲気を感じさせるドラマティックな調子が、原曲に劣らず健在だが、少し大人し目なバラードに落ち着いている感じもある。泣きのギターが古い時代のギターヒーローを連想させる。
ラストトラックの#12『Take My Life』のみ、1996年の契約デビュー盤「Third Day」からの選曲と、やや古い。が、デビュー時はそれ程強くなかったミクスチャー色を実証するかのような、アクースティックなアレンジで叙情的なバラード。
この当時は宗教界のHootie And The BlowfishがLynard Skynardと出逢った音楽、と表されていたが、確かにサザンバンドの優しい面を覗かせる曲でもある。原曲と聴き比べると、Mac Powellのヴォーカルに説得力が格段に増していることが見て取れる。
そして8分近いメドレー形式のライヴトラックが、#11だ。
が、本当に曲を取っ替えひっ変えするのではなく、基本は「Time」のラストナンバーの『Give』。このザックリしたアーシーなミディアムバラードに他3曲分の歌詞を付け、Giveの変則アレンジとして歌い繋いでいるもの。
『Give / Turn Your Eyes Upon Jesus / With Or Without You / Your Love Oh Lord』のリレーなっている。
メドレーの3番目『With Or Without You』は云うまでもなくU2の全米トップ1シングル。しかし、歌詞の後半を取り入れているだけで、メロディとしては登場しないのも面白い。
最後になるが、物凄いヘヴィなギターの唸りで始まる#3『Creed』は他のライターのカヴァーとなっている。
これは1980年代後半から1997年に自動車事故で急逝するまで、宗教音楽界のコンテンポラリーソング部門で絶大な人気を誇ったピアニスト兼シンガーであるRich Mullinsが1993年に発表のナンバー。
かなりダートでハードなディストーションで始まるこのナンバーだが、本編はRichらしいポップで軽快なビートが転がるアダルトなロックンロールナンバーとなっている。
Rich MullinsにはThird Dayがかなりの影響を受けたことを、Macがこのアルバムのブックレットでも書いている。少しスローナンバーの比率が多いアルバムとなっているので、こういったパワーロックは全体の流れを締めるにも丁度良い仕事をしている。
◆脱オルタナティヴ/ミクスチャー/ヘヴィロック バンド!!
正直、驚いている。
まさか、Third Dayがここまで優良なアメリカンロックアルバムを出してくるとは予想をだにしていなかったからだ。
こう書くと、Third Dayには失礼かもしれない。しかし、率直な感想であるのだ。
#3のギターのノイズを初めて聴いた時は、そらきた、と思ったものだが。
確かにここ数作、「Offerings:A Worship Album」(2000年)、「Come Together」(2001年)と連続で、デビュー当時からの特徴だったオルタナティヴやミクスチャー系の耳障りなノイズが相当減衰していた。
しかし、Southern Rockと呼ぶよりも、Alternative Southern Rockと銘打った方が適切という、ルーツロック以前に正統派アメリカンロックと分類するにはかなり微妙な音楽性の境界線をフラリフラリとしていたことも、また事実だ。
元々がSouthern Rockをベースとしたヘヴィでクロスオーヴァーな音楽的特長のあるバンドだったので、ロックンロールの馬力には事欠かなかった彼等だ。
但し、アメリカンルーツやサザンルーツ、そしてなによりもThird Dayが宗教バンドであることの前提ともいえるゴスペル/クリスチャン・サウンド、といった要素。これらよりも、重たく、必要以上にノイジーで、人工的で、反自然的なヘヴィロックやモダン・ヘヴィネスの力が勝っていることが大半だったのだ。
よって、ロックバンドとしての五月蝿さと腕力は兼ね備えながらも、それが形になっていない−言わば、体力は有り余っているのに技が全く身に付かない格闘家みたいな存在だったのだ。
2000年の「Offerings」以降、メジャー宗教系レーベル3作目「Time」までと比較して、相当オルタナティヴ・ヘヴィロックを脳内に焼き付ける如くな剛球ナンバーは数を減らしつつあったけれど、前作スタジオアルバム「Come Together」のレヴューでも言及しているように、どうしてもAlternative−控え目に表現してもAdult Alternative的なサウンドの角がチクチクと肌を突付く箇所があった。
しかし、2枚目のライヴ盤とスタジオ録音トラックの混在盤となる「Offering 2:All I Have To Give」に至り、筆者はレヴュー冒頭の区分わけからオルタナティヴの単語を取り除かなければならないという思いを新にしたのである。
つまり、この「Offerings 2」はオルタナティヴという要素をもって、耳をネガティヴに刺激する機会が激減している。こういうことだ。ここまで述べてきた曲ごとのインプレッションでそれは理解して貰えるだろうが。
カントリーやオルタナカントリーとは全く質を異にする音楽性だが、これもアメリカントラディショナルな土臭く、分かり易いスコアを看板としたアメリカン・ルーツロックと認知するべきだ。
◆次のスタジオアルバムに大期待
と、第壱号の「Offerings」をかなり上回るポップでアーシーで美しいロックアルバムを、一般に名作の後では作ることが難しい「2」でサラリと成し遂げてしまうバンドが、Third Dayなのだ。
「Offerings」を聴いた時、次のスタジオ盤には相当期待をもってみたが、結果としてそれなりな南部サウンドとルーツサウンドを封入した「Come Together」が出ていることで終っている。
「Come Together」ももう少しオルタナティヴ色を排除すれば、満足から大満足なアルバムになったと今でも少し無念に思っていたりする。
しかし、今回の「Worship Album」は前作を超えたものになった。
だからこそ、次の5番目のスタジオアルバムも、きっと「Come Together」よりも素晴らしいロックアルバムになると、どうしても期待せずにはいられない。
リリースのペースは決して遅くないバンドなので、2年後の2005年辺りまでには期待への結論が出ているだろう。
さて、どう転ぶのか・・・・。 (2003.6.18.)
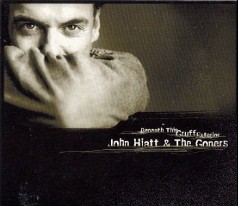 Beneath This Gruff Exterior
Beneath This Gruff Exterior
/ John Hiatt & The Goners (2003)
Roots ★★★★☆
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
Swamp&Southern ★★★☆ You Can Listen From Here
◆Beneath This Gruff Exteriorを訳すと
アルバムの趣旨と合致するかは別として、普段こういった表現が会話で使用される際には、
「無愛想な外見だけど、本当は・・・云々」とか
「顔は強面だけど、実際は・・・・云々」という、比較的肯定的な意味として会話文に登場する。
が、Gruffを“シャガレ声”とか“ガラガラ声”と解釈すると、些かその文意が異なったモノになりそうでもある。
「このガラガラ声が一杯に溢れ出ている」とか「このシャガレ声が耳を支配している中で」
てな意訳も出来そうな気がする。確かにJohn Hiattの声は、美声とは口が裂けても言えないオヤヂ声だ。だから、この解釈も出来なくも無い。
だが、やはり筆者としては最初の語感がより適していると考えている。
「外見は無骨なオッサン顔が写ってるアルバムだけど、実際は凄いんだぜ。」
「ぱっと見は、飾り気のないゴッツイアルバムだけど、中身は味わいがあるんだぜ。」
といった、聴いて貰えれば全て分かってもらえるさ、的な自信が湧き出ているタイトルに思える。
逆にいうと、ヴィジュアルでアピールする自信が無いといえなくもないこともないかもしれない可能性もあるかもしれないが。(どっちや)
余談だが、外見面ではおやっさんのハゲはあまり後退していないので、外見的には退化していないとは思うのだったりする。(笑)
◆18枚目のアルバムが出来るまで
前作のスタジオ録音盤「The Tiki Bar Is Open」が発売されたのが2001年。その更に前作である初のマイナーレーベル配給の「Crossing Muddy Waters」が2000年。
このように、近年のHiattはかなりハイペースで創作活動を行っている。本作「Beneath This Gruff Exterior」も2年弱で発表された。
50歳を超えたおやっさんの活動としてはかなり過加速気味ともいえるくらい、凄い。
今作はHiattのオフィシャルでのカウントでは18枚目(筆者はベスト盤等を除くと17枚目と思っていたのだが)に当たるそうだが、このアルバムの曲を書き始めたのが2001年秋との事だ。
「時間はドンドン流れていく。私達は若返ることは絶対に出来ない。だから、しなければならない事がある。
そう、“carpe diem”をね。」
このcarpe diem−カルペディエムとはラテン語で、原意は「バラは摘める時に摘め。」となり、つまり「今を楽しめ。人生を謳歌しよう。」的な意味の諺だ。
ロビン・ウィリアムス主演の映画、「Dead Poet Society」(邦題:いまを生きる)にて、決めセリフとして使われていたのが懐かしい。映画中では英語訳に当たる「seize the day」も併用されていたが。
閑話休題。
つまり、「自分はおっさんから更に老けに向かって急降下しているから、出来るうちに出来る事をやっとくべえ。」とJohnは言っている訳だ。
で、前作にて1988年の「Slow Turning」以来再びジョイントしたThe Gonersとの感触が非常に良いため、次のアルバムはGonersの音に打てば響くようなサウンドプロダクションを中心にしたいと思い立ったそうだ。
「このアルバムは、4人の不良中年が多少なり活力を取り戻せるように、って考えが元になっている。そして行き当たりばったりに、リフレッシュ出来た所なら何処でも−例えば床屋に行った経験とかからもアイディアを追加した。でも、このアルバムで私達はやりたい事をそのまま形に出来たし、このカルテットの基本に沿うことも出来たと思う。もしライヴを聴くことが出来るなら、それで全て理解して貰えると確信しているよ。」
Hiattが本アルバム用の曲を書き出したのが、2001年のB.B.KingとBuddy Guyとのジョイントツアー中。アリゾナ州のとあるコーヒーハウスだったそうである。丁度Gonersとのコラボレーションをキープしたまま「The Tiki Bar Is Open」の全米ツアーを敢行していた時になる。
「何時ものように、ロードが長いなあ、ってボヤキが出始めたので、気分転換を兼ねて私は全く新しいノートを買い込んだ。で、コーヒーカップを傍らに置いて、『さあ、ノートを詩と歌で最後まで埋めるぞ』と自分に宣言したんだ。一番最初に優しさと泣き虫さを混ぜた『Window On The World』を書いた。これがアルバムがスタートする切っ掛けだったんだ。」
「Beneath This Gruff Exterior」のために書き下ろした曲はかなり早く仕上がったそうだが、Hiattは色々と曲に加える要素を考えるため、相当の期間をレコーディングまで置いたそうである。
「私はギターとヴォーカルのデモを撮る小さな部屋に座り込んで曲創りを終えたよ。このテープに記録されたパフォーマンスを完璧にしたい事は自覚していた。けれども、しっかり準備をしないと万事は進まない物という事も分かっていたからね。だから私は本当に曲について理解するように務めた。おかげでレコーディングに際しては全く頭を捻ることは無かったよ。ちゃんと自分の頭の中にガイドラインが出来上がっていたんだ。」
と、レコーディングまではかなりの時間を掛けて曲を練り込んだおやっさんだけれども、レコーディング自体は異常に速い期間で終了させている。
レコーディングは完全なライヴ録音形式で実施され、僅か8日で完了しているのだ。
「仮に私がヴォーカルの撮り直しをしたいと思っても、やりようがなかっただろうさ。」
◆比較対象は前作よりも「Slow Turning」になる
「The Tiki Bar Is Open」でもSonny Landrethのスライドギターは良いサポートをしていたし、曲によっては完全に主役を張っていた。
が、全体としては17thアルバムでのSonnyの役割はエレキギターとスライドギターの両方でPop/Rockのアンサンブルに多大な貢献をした、という位置にあったと思っている。
しかしながら、今作「Beneath This Gruff Exterior」では初のAnd The Goners名義が採用されている。これまでの2枚の名義はあくまでJohn Hiattであり、インナースリーブにThe GonersとしてSonny Landreth、Dave Ranson、Kenneth Blevinsが記載されていたに留まっていたのに、である。
これまでのHiattのアルバムでは、And The Giluty Dogsが「John Hiatt Comes Alive At The Budokan」にて使われているのみ。
このクレジットにおける扱いから予想可能とは思うが、今回のアルバムではSonnyのスライドギターが完全にHiattのエレキギターやアクースティックギター、そしてLandreth自身も弾いているエレキギターを脇役に追い遣ってしまっているのだ。
ここまでスライドギターが大きく目立ったアルバムは、矢張りGonersがバックバンドとして演奏に関わった1988年の名作「Slow Turning」以来だ。
が、シンプルなスライドギターロックと評判の高い「Slow Turning」でさえ、John Hiattがエレキピアノやウィルツァー・ピアノを、そして元EaglesのBernie Leadonがマンドリンやバンジョーでアンサンブルに華を添えていたのに、今作では1曲のみサックスでBobby Keyが参加している他は、完全な鍵盤レス、他の楽器もミュージシャンも参加していない形になっている。
常ならば、Honer Gonersの名義でゲストプレイヤーがそれなりの数クレジットされてきたのが、これまでの形式だったのだが、今回はBobby Keyのみがひっそりとブックレットに名前を載せているに過ぎない。
この手のスワンピーなスライドギターアルバムの必須の友である筈のハモンドオルガンすら聴こえないという潔さといって良いのか不明瞭だが、兎に角ソリッドな演奏で括られている。
ギターがドブロ、アクースティック、それにスライドとエレキの他はベースとドラムスのみの3ピースに近い編成だ。
このシンプルさはドラムレスだったインディレーベル処女作の「Crossing Muddy Waters」に通じる点があるかもしれない。あちらはおやっさんのシンガーソングライターの顔を強調した完全アクースティック作品だが。
また、アクースティックスライドや12弦や6弦のアクースティックギターが大活躍していた「Slow Turning」の隙間の多いサウンド創りに比して、最新作の18枚目は遥かにロックンロールしている。エレキギターの含有率は取り立てて高いということもないのだが。
だから、アクースティックなルーズさに掛けては、「Slow Turning」の方が粗さが目立っている。
が、タイトさとロックンロールの引き締まり具合では、遥かに「Beneath This Gruff Exterior」に軍配が上がる。アクースティックサウンドのサクサクした音色よりも、スライドギターのスワンピーな音が全体を司っている作品だと思って差し支えない。
従って、ラフで荒っぽい未整理さは、両方のアルバムに共通しているが、その馬力とパワーではやはり2003年発表のレコードが上位に来るだろう。これはアルバムの優劣という面での話ではなく、特質に限った話と考えた方が良い。
だが、「Slow Turning」の『Drive South』や『Tennessee Plates』、『Icy Blue Heart』といった曲とシンクロするナンバーは見られるアルバムなので、全くタイプを異にするのでもなかったりはするが。
Hiattの名曲としてピックアップが頻繁にされるカヴァー曲の『Feels Like Rain』に匹敵するバラードは収録されていないのが別の違いであるだろうけど。
◆アレンジはSonny Landreth、曲はJohn Hiatt。でもブルース曲もある
大まかな感じとして、Sonny Landrethのレコードからブルースらしさを相当差っ引いた、ルイジアナ周辺のスワンピーなアレンジで纏められたPop/Rockのアルバムだろうか。
演奏の中心は、前にも書いているが「Slow Turning」と同様にThe Gonersである。というかSonnyのアルバムでヴォーカルをHiattに差し替え、そして曲をよりポップ寄りにすればこの「Beneath This Gruff Exterior」が出来上がるだろう。
結果として、これまでのJohn Hiattの作品の中では最も南部色の強烈なアルバムとなっている。サザンロックのブギーでラフな感覚をGonersというバックバンドを主体にして活用することで最大限に演出しているのだ。
これまで殆どベースにしていた、出身地インディアナ州周辺の音楽である中庸的なルーツロックのサウンドとはかなり毛色が異なっている。これまた「Slow Turning」と同じだ。
勿論、ブルージーな曲は皆無という事は無い。
#6『Almost Fed Up With The Blues』では粘っこくハードにブギーする、タイトルの通り過剰供給気味のブルースロックが展開される。おやっさんの熱いシャウトも聴ける、如何にもSonnyが好む曲をHiattが書いたという感じがする。
しかし、アップビートでブルージーなナンバーの割にポップなソングライティングなラインが、ベタなサザンルーツ系の音と並行している所は、やはりHiattのカラーが見える。
Bobby Keyのサックスが唯一聴けるのもこのトラックだけだ。
更にハードなサザンブルースになっているのが#11『The Last Time』である。こちらはキャッチーであるよりも、ファンキーでブギーな粘っこいロッキンブルースの本格派だ。こういった曲は中々メジャーレーベルではトラッキングし難いだろう。著名なブルースマン以外は。
これらの2曲とは少々性格が違うが、ロック+ブルースという印象があるのが、#2『How Bad’s The Coffee』だ。出だしのスライドギターのリフは、コテコテのルイジアナ風エレクトリック・ブルースだし、所々で唸りを挙げるLandrethのスライドギターを聴いていると、スライドギターロックのサザン・フィーリングが掌から溢れるようだ。
しかし、ブルース調子を時折混ぜながら、実にポップにロックンロールするガッツなナンバーである。ライトなロッキンブルースと考えた方が良いかな。
◆Hiattらしいロックナンバーも健在
オープニングナンバー#1『Uncommon Connection』は、今年50歳を超えたHiattの心情が歌詞に現れているナンバーだが、ある種の開き直りすら感じさせる、軽快でテンポの良いロックチューンだ。
Kennethのバタバタしたドラムのリズムがグルーヴィだが、矢張りSonnyのエレキギターを裏から支えるようなザラザラした音色が特徴的だ。後半でのHiattのエレキギターとのバトルもエネルギッシュだ。
#3『The Nagging Dark』はこのアルバムの中で、最も最後に書きあがった曲で、レコーディングを始める数週間前に完成したそうだが、この曲ではスライドギターは裏方的サポートに徹し、Hiattらしいパンチの効いている飾り気のないロックチューンが素直に楽しめる。
#7『Circle Back』のロードハウスロック風なラフでリズミカルなロックナンバーを聴くと、おやっさんの50歳過ぎという年齢を思い浮かべれなくなってしまう。絶倫オヤヂ復活は、既に前作の「The Tiki Bar Is Open」にてある程度果たされていると思う。
が、こういったChuck Berry的な古いポップR&Bを何処かに連想させる曲を大暴れで演奏されると、おやっさん悪ノリといった単語が浮かんで来ざるを得ない。
ロカビリーソングをスライドギターで爆走させている、#10『Fly Back Home』が、ロックビートとしては最もライトでノリが良好なナンバーだろう。良い意味でロックの重厚さを保持したロックナンバーやブルースナンバーが多いこのアルバムでは、やや異色に写る位、レスポンスが軽いナンバーだ。アクースティックギターとドブロが相当頑張っているが、ちゃんとスライドギターの爆音も、必要以上にカントリーに天秤を傾かせない働きをしている。
◆ブギー、スワンピー、Boogie-Woogie
スライドギターの音色が目一杯裏返るリフが印象的な、#4『My Baby Blue』はブギウギで、ダンシングなパーティロックナンバーだ。
このバタバタしつつもリズミカルでポップな調子、特にコーラスの部分はつい一緒に歌いたくなってしまう親しみ易さが満載だ。Gonersのコーラスワークで最も出来が良いのがこの曲ではないかと思ったりする。
スライドギターのソロパートではHiattの鼻声ハイトーンな声が聴ける。
アルバムで一番最初に書かれた#8『Window On The World』は、Hiattの本来の持ち味の1つであるHearland Rockの暖かさが滲み出ている中庸的なナンバー。が、Sonnyの弾くスライドギターによって、スワンピーな脱力感も同時に思わせてくれる。
ミディアムでアーシーな曲感は、30年も継続して活動し、コンスタントにアルバムを出し続けているおやっさんの懐の深さと、大らかさを如実に感じさせる。
ハーモニカと12弦ギター、アクースティックにスライドギター、そしてドブロといった土臭いルーツギターが勢揃いでフォーキーなアレンジが特徴的な#9『Missing Pieces』は前曲#8に続いてスロータイプな曲だけれども、「The Tiki Bar Is Open」の後半パートで鼻についた息切れやロックの失速を匂わせない。
ゆったりとしたブギーな曲感と、ザクザクと進む堅実な演奏が、ロックンロールではなくても、ルーツナンバーとしての質感を逃がしていないからだろう。
この後半2曲のジェントリーなコンボはタイトな前半のロック攻勢よりも、筆者的には好きと思えるパートだ。
Hiattのアルバムでは最もバランスの取れた「Walk On」(1995年)をプロデュースしているDon Smithが再びこのアルバムでも共同プロデューサーとして参加しているが、Donの方向性がこれらのナンバーに垣間見える。Gonersが前面に出たとはいえ、完全にHiattのカラーが2番手に沈んだわけではないのだと、改めて思わせてくれる。
『Feels Like Rain』や『Have A Little Faith In Me』といった名曲には及ばないが、しっとりとしたスライドギターメインのバラード、#5『My Dog And Me』もスワンプのルーズさと覚束なさが出ていてじっくり聴けるナンバーだ。
ドブロギターとスライドが頭出しからアーシーに振り回される#12『The Most Unoriginal Sin』のみ、このアルバム用に書き下ろされていない。1993年にHiattがWillie Nelsonへ提供したナンバーなのだ。
如何にもカントリーの大御所Nelsonが取り上げそうな、サザン・カントリー風のじっくりとしたスローナンバーだ。
2002年にWillieのライヴにゲスト出演したHiattに、Willieがデュエットを求めたのがこの曲だった。
「ウィリーが、彼のステージに私を上げて、一緒にこの歌を歌わせてくれたんだけど、殆ど自分の書いた曲ながら忘れていたね。(笑)で、コンサートが終ったあと、私は彼に『悪くない曲だね、これ。』と言ったものさ。
その時、新作のレコードにの最後の曲が見つからなかったんだけど、これだと感じた。」
◆デビュー30周年
Hiattのレコードデビューは1974年。今年2003年は30周年に当たる。
正直、以前の分裂劇もあったので、The Gonersが2枚続けてHiattのアルバムに出演するとは思っていなかったし、ここまでGonersの色が演奏に出るアルバムになるとも思っていなかった。
「ミュージシャンとしてキャリアを始めた頃は、何を求めていたのか自分でも分かっていなかった。投げ遣りで、自分の事も理解せずに、多くの事に飢えていた。それは愛情であり、評判であり、知名度だったりした。今でも過剰ではないけれ、それらを欲しているとは思う。けれども、今現在私は自分自身と自分のいるべき場所をもっと理解している。
それだけが私の全てではないけれど、曲を創造する情熱は依然として私の中に在る。この事を発見した時、音楽が自分へとフィードバックする物があると分かった。
兎に角、今より良い形で出来る事にトライすることだね。僕の場合、他の50歳を超えた人達と考えていることはそう変わらなだろう。時間は貴重で有限だから、馬鹿をやって浪費しないこと。
明日を読むことは出来ないけれど、今日得れるものは、確実に手に入るんだからね。」
と、50歳を超えたから隠遁生活に入る、みたいな事態にはこのおやっさんは陥らないだろう。そのくらい精力的に活動することを伺わせる発言を繰り返している。
これからも良いアルバムを届けてくれるだろう。この人の特徴である大外れがない、というのはキャリアを考えれば凄い実績だと思う。 (2003.6.25.)
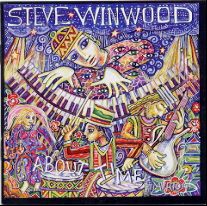 About Time / Steve Winwood (2003)
About Time / Steve Winwood (2003)
Blue-Eyed Soul ★☆
Pop ★★★
Rock ★★★
Latin&Jazz ★★★☆ You Can Listen From Here
◆Winwoodのインタヴューに見られる今
<質問>貴方は衰えのない創造力を持っていると評価されてきていますね。
何が貴方の多岐にわたるクリエイティヴな魂を駆り立てるのですか?そして貴方の音楽経験と
人生経験が、どのようにミュージシャンとしての成長を促すのですか?
<SW>僕のキャリアを振り返ってみると、音楽をもっともっと取り入れたい欲求に絶えず駆り立てられているね。
この希求心は単に違ったスタイルの音楽を取り入れる事だけではなく、異なった楽器を学ぶという事
も含まれている。幸い、僕は積み上げてきた経験に新しく学んだプレイスタイルや作詞を併せて取り入
れることができている。学びたいという欲求が僕を新しい地平へと誘って来てくれている。有り難い事
に、僕の渇望は枯れた事がない。ので、僕はミュージシャンとして前進し続ける事が出来ているんだ。
創作姿勢に衰えの無い人物である事は良く理解できる。が、この寡作過ぎる傾向は何とかして貰いたいが。
多作であれば良しというものでもないが、やはりここ13年でたった3枚のソロ作に1枚のグループ作というのはどうかと思う。
芸術家タイプのミュージシャンの割にはヒットの程度により相当気分を左右される人で、前作「Junction 7」が全くチャート的に失敗したことが、6年以上の空白に繋がっている事は想像に難くない。
◆Trafficの「Far From Home」やWinwood名義の「Refugees Of The Heart」
最近のWinwood関連のアルバムなら、この2枚が最新作「About Time」に“一応”最も近いだろうか。
最近とはいえ、「Refugees Of The Heart」は1990年。
「Far From Home」は1994年の作品だが。
Steve Winwoodの最も最新のアルバムが1997年の「Junction 7」という経歴を振り返ると、この2枚は最近とは言い難いかもしれない。が、そもそもソロ作としては「Junction 7」が前作よりも7年の歳月を経ているのだから、強ち間違いでもないだろうが。
Steve Winwoodの作品としては6年以上の期間を置いて登場した「About Time」は、マーケットが彼を持て囃し、スターダムに乗せた1980年代のアルバムとは相当異なった異色作となっている。
これを第一に述べておこう。
少なくとも筆者としての見地からは、素直なPop/Rockのアルバムとはどうしても云えない。
Winwoodのファンには今更馬の耳に何とやらだが、「Refugees Of The Heart」の『You’ll Keep On Searching』や『In The Light Of Day』。
そして「Far From Home」のインストナンバーである『Mozambique』。
こういった“華麗でスマート”の代名詞で殆どが表現できてしまう、Winwoodの1980年代のヒットソングとは些か毛色の異なった曲が懐かしいリスナーなら、この「About Time」はかなりの好物になりそうな予感がする。
参考までに『Mozambique』はアフリカの地名である。
その由来を反映するようなアフロ・アメリカン調子のパーカッシヴな民族音楽風のインストゥルメンタルソングだ。
『You’ll Keep On Searching』は華やかなR&Bポップアルバムとなった前作「Roll With It」から一転して、シックでエキセントリックさの増した作風を代表する第一弾ナンバーだ。
『In The Light Of Day』はサイケディリックなリズムが異彩を放つ曲。1990年ソロ作の幕を引くナンバーで、ジャズとサイケとプログレッシヴが交じり合った不可思議なエレクトリックナンバーだった。
・・・こういったソロ作における、どちらかというとTrafficに近い独自性と実験的な性格が入り混じった無国籍さが特色なナンバーを念頭に入れると、本作「About Time」の方向性に置いてきぼりを喰らう事は無いだろう。
とはいえ、このソロ作はTraffic−Steve、Jim、Chris、Daveの個性が凌ぎを削って生まれた芸術的な先進音楽−とはその根本を異にしている。これは断言できる。
やはり、外側やコラボレイトしたミュージシャンからの影響を大なり小なり受けているとはいえ、このアルバムはSteve Winwoodのソロ作なのだ。
作風として既存のソロ作よりTrafficに少しだけ傾いていると云いたかったのだ。
◆今度のアルバムは、ハモンドオルガンのみプレイ
これまで多種多彩な鍵盤−ピアノ、ミニムーグ、シンセサイザー、オルガン、フェンダー・ロウズ、ウィルツァー、ハープシーコード、メロトロン、etc...−を1枚のアルバムの中で叩いてきたWinwoodだけれども、最新作「About Time」では何と、ハモンドB3オンリーのプレイになっている。
これまでにSteveが単独の楽器だけをオンリープレイしたアルバムは全く無い。これまた初めての試みだ。更にサンプリングサウンドやプログラミングすら活用していない。
以下のWinwoodが受けたインタヴューにコメントがある。
<質問>ハモンドB3に対する貴方の興味を語ってもらえませんか。また何処からその興味が生じたのかも。
それから、ワールドミュージックとロックサウンドにハネッ返りの強いB3を組み入れたことによる最も
大きな挑戦は何でしょうか。
<SW>私のハモンドB3への興味のルーツはトラフィック時代まで遡る。クリス・ウッドやジム・キャパルディ
とトリオを組んでいた頃だね。私は当時からハモンドの音が大好きだったよ。
ハモンドを使用した事での挑戦は、ベースラインをB3で弾いた事だね。これまでB3は常にメジャ
ーラインをなぞっていたからね。そしてベースラインをよりシンコペーションを活用してリズミカルに
近づけた事かな。
私はこの方法が、様々に活用されているジャズのメロディラインとの結合よりも、ロック音楽との結合
には効果的ではないかと思うんだ。
<質問>「About Time」のサウンドの中心はハモンドB3ですね。どのようにしてこの手法を選ぶに至った
のでしょうか。
<SW>私はTrafficに居た極初期にベースパートをオルガンで弾いていた。それ以来だね。だって、足で
オルガンペダルを踏みながら歌を唄うのは相当の重労働だったんでね。
でも数年前に、今度のアルバムはベーシスト無しで創ろうと決心したんだ。その決心がアルバムの
形を作ってくれたと言っていいね。ベース無しというアイディアによって速やかに曲とアルバムの形
が定まったよ。
次に曲を書いて、それを私が活用したい多種多様の演奏スタイルに合わせるという問題が出てきた。
私は熱心に黎明期のオルガニストのスタイルを取り入れたよ。Jimmy Smith、Jack McDuffそれから
Groove Holmesといった具合にね。彼等は“Kicking The B”と呼ばれるスタイルの素晴らしき代表
格として知られているね。そしてワールド・ミュージックの要素をロックに結び付けている。(中略)
ジミー・スミスは1950年代半ばにオルガニストへ影響を与えるスタイルを確立していたね。彼のプレイ
スタイル自体はそれ以前から演奏されてきたモノだと思うけどね。だけれど、ジミーは既存スタイルを
彼自身のジャズスタイルとして纏めたからね。Bebopスタイル−よりロックンロールに親和性の高い音
楽としてだ。(小略)
以上のコメントにもあるように、今回のアルバムはノン・ベースである。Steve Winwoodがオルガンペダルを踏んでベースパートを演奏しているのだ。オルガンジャズ等でたまに見かける手法だが、最近はとんと見なくなってしまった。
基本的にブラジル人のギタリスト、jose Neto、キューバからの移民であるドラマーのWalfredo Reyers Jr.、そしてWinwoodのヴォーカルにハモンドオルガン。というトリオ編成となっている。
しかも人種的なルーツを見ると中南米のリズムをネイティヴで獲得しているミュージシャンとの共演となっている。
彼等を加えたことによる多民族的なリズムがアルバムに与えた影響についてもSteveはコメントしている。後に彼のインタヴューから引用するとしよう。
他に4曲でサックスフォンとフルート、6曲でコンガとティムバルのパーカッションが参加してるというシンプルさ。
流石に1980年代初頭のワンマンレコーディング時代と比較すると参加メンバーは多い。が、1980年代中期以降に積極的な外部ミュージシャンを起用した流れとは正反対の向きになっているのが興味深い。
◆というアルバム−ブラジリアン・ロック、カリビアン・リズム、ジャズ・・・・
Steve Winwoodが再三述べているように、「About Time」はワールドミュージック、そしてジャズをロックンロールと融合させたもの。
本来の意味でのフュージョン・ロックアルバムとしての性格が強い。1970年代にSteely DanがジャズとアルバムロックやR&Bを融合したサウンドから本邦でフュージョンロックの名称が流行したが、感覚としてはそれに近いだろう。
ドラムスとパーカッションのリズムはかなり非西洋系であり、有体に言えば、カリビアンであったり、ラテンリズムであったりする。
ギターにしてもモロにラテン系。ブラジリアン・ロックやスパニッシュ・ミュージックを聴いているような錯覚さえ感じることがある。
無論、ベッタリのエスニック・ミュージックではない。
骨子となっているのは、Steve Winwoodの持つアーティスティックな英国ロックの感覚だし、ブルーアイド・ソウル、R&Bの肌触りも薄いとはいえ曲の裏側で触れることが出来ると思う。
1980年代に彼が確立し、チャートやアワードを席巻したアダルト・コンテンポラリーなポップさは殆ど見られなくなっている。また、前作で積極的に黒人音楽関連のミュージシャンやエンジニアを採用し、擬似ブラックR&Bの打ち込みアルバムを作成した跡は影も形も無い。
やはり、この冒険的な手法、かなり尖ったアートロック的アルバム構築を見ると、Traffic的な要素を強く感じる作品になっていると思う。
が、Trafficがアメリカンルーツ的な要素と英国ルーツ的な要素、それに加えた黒人音楽を加え、複数のリーダーによってミクスチャされたエキセントリックで複合的な要素を有するバンドであるのに対して、今作はJoseを始め幾人かのライターが曲を共同で書いているとはいえ、カラーはSteveで単一に統一されている。
最も近いのは、2名だけのTraffic−SteveとJim Capaldi−で録音となった1994年作品、「Far From Home」に近似していると考えている。筆者はこのTraffic最新作をSteveのソロワークとTrafficの伝統を融合させた妥協点と見なしているが、「About Time」も基本姿勢は同じだと思う。
要するに、創作的なロックリズム=ソロでの仕事 と 実験的新型サウンドの導入によるアートロック=Traffic
という手前勝手な公式に当て嵌まるのではないか、と。
◆レコーディングとバンドミュージシャン
<SW>私は「About Time」が特定の“レシピ”に従って創られたものではない、と表明しておく必要がある
と考えている。その理由は、ブラジリアンロックの影響をJoseから、キューバロックの影響をWallyから
受け、それらが私の作風と並列しているからね。私達は新しい創作料理を作ってしまったのかもしれ
ないね。沢山の風味があり、幾らかのスパイスが効き、幸運にも多数の舌に訴えることの出来る味わい
のある。
という様に、Winwood自身がカリビアンリズムやラテンアメリカのサウンドを積極的に取り入れた事を認めている。
実際、ギタリストのJose Noteは#2、#5、#11と3曲でSteveと曲を書いている。
レコーディングは英国はイングランドで行われており、ミックスダウンはロンドンにて敢行されている。
バンドのメンバーとの馴れ初めとレコーディングに付いてWinwoodは次のように語っている。
<SW>私とドラマーのWalfredoを10年来の既知だ。1994年のTrafficツアーに彼は参加していたからね。
Joseに出会ったのは1980年代だ。Joseは当時Fourth World With Airto MoreiraとかFlora
Purimというグループでプレイしていた。
と、このトリオは初顔合わせではないのだ。WallyはツアーメンバーとしてWinwoodと仕事を経験済みでもある。でなければ、幾らヴェテランミュージシャンとはいえ、この完成度の高い演奏は一朝一夕には出来ないだろう。
<SW>JoseとWallyがレコーディングのためイングランドに到着してから、私達は全員で交互に演奏を繰り
返したけど、一緒に演奏はしなかった。とても面白い状況だったよ。
レコーディングの最初の数日で録られた数曲で私達は一緒のスタジオでプレイした事はあるけど。
今までとは違うタイプのレコーディングだったよ。スタッフをスタジオに配置して、ただマイクロフォン
をセットするだけという。
本当はこれがレコーディングのあるべき姿だから、こう述べるのは馬鹿馬鹿しいかもしれないね。
でも最近はこういったレコーディングは実際に行われていないんだな。
今回はコンピューターもループも全く使用しなかったよ。(中略)
以上のように、3人だけで演奏している4曲以外は、それぞれのメンバーがスタジオに入り、各パートを演奏。それをオーヴァーダビングしたらしい。
しかも、あれだけサンプリングやドラムマシンの使用に何の躊躇いも見せなかったWinwoodが、今回は全く擬似サウンドを使用していないのだ。
ライヴ録音を行ったのではないが、スタジオライヴに近い演奏を繋ぎ合わせて完成させたアルバムと見ていい。
ライヴを意識しているのに、メンバーが一緒にプレイしないのは、やはりサウンドと演奏の完璧を求める、録音オタクでありスタジオ引き篭もりが得意のWinwood的な特有の性格のためか。
◆For Popというメッセージがブックレットにあるけれど
全体として、Pop/Rockのメジャーコードで完成されたアルバムではない。元来、英国人らしいヒネリやネジレのあるメロディを不思議にポップに表現するのが得意の、ロックンローラーでありR&Bシンガーであるのだが、今回はポップ職人ではなく、拘りとアーティスティックな側面を煮詰める側のWinwoodの顔が前面に貼り付いている。
ポップミュージックの基本路線からは逸脱はしていないが、華やかな英国風ポップロックを振り撒いていた1980年代のポップへの追求とは全く異なった次元のスタンスを見て取れる。
ファーストシングルとなった#1『Different Light』からして、それなりにポップでリズミカルであるのだが、カリビアン系のリズムを感じられるナンバーだ。ハモンドオルガンのアレンジもムーグシンセサイザー風の無機的な音響を強調して音を出しているように感じる。
何と、この曲だけがWinwoodの単独作である。アルバム中では最もキャッチーだとは思う。
Karl Densonのテナーサックスの入れ方は、やはり『You’ll Keep On Searching』を連想させる。
#2『Chicago(For The Gypsies)』、#5『Domingo Morning』、#11『Silvia(Who Is She?)』
の3曲がJose Noteとの共作曲。#2はシカゴ・ジャズを思わず頭に浮かべるくらい、ジャジーなポップナンバー。インタープレイでのJoseのギターはスムーズ・ジャズ系統のライヴ感覚で一杯だ。
#5はファンクロックを表現するオルガンと、ラテンサンバ的な情熱的なリズムを持つギターがぶつかり合う曲。『One And Only Man』からギラギラした輝きと打ち込みドラムを除くとこのようなナンバーになりそうだ。
#11は11分以上に及ぶ、久々の大作。Traffic時代の『The Low Spark High Heeled Boy』を引き合いに出したくなるようなロング・ナンバーだ。延々と繰り広げられるオルガンとエレキギターのバトルはプログレッシヴに広がり、時にハードに時に静に沈む。
全くシングル的要素を排したサイケディリックでプログレッシヴな作風は最もTrafficに近いといえる。
Neil YoungやWinwoodの「Refugees Of The Heart」に参加していたギタリストである、Anthony Crawfordが今回はライターとして2曲をSteveと書いている。
暗の#3『Take It To The Final Hour』、そして明の#10『Walking On』という曲調が対照的な2曲だ。
気怠るいR&Bナンバーで最もワールドミュージック色が希薄な英国的ナンバー#3は最もダークで粘っこいR&B。
インタープレイでのオルガンワークの滑りは流石に御大だけのことはある凄まじさを見れるが。
対して#10はカリブ海の明るいノリをスパニッシュなギターで絡めたビーチサイドナンバーの性格を持ち、腰をシェイクさせるような南洋のリズムが楽しいナンバーだ。最も明るいかもしれない。フルートが陽気さを更に増している。
カヴァーも1曲。1973年にブラコンチャートで大ヒットを記録した#4『Why Can’t We Live Together』がそれだ。
ファンクロックとディスコ的なマシンビートでオリジナルは仕上がっているが、Winwoodはクラシカルなファンク風味をそのまま残し、パーカッションにアフリカン的な色合いを付けて再構築している。
ために、かなり無国籍な曲になっている。
残りは#8以外、全て妻のEugenia Winwoodと作成したナンバーだ。
#8『Phoenix Rising』はThe BlessingのリーダーであるWilliam Toplayとの共同成果である。
英国人ながらアメリカン・カントリーとブルースへの愛着をくどい位に求めるTopleyの影響を感じる、ブルージーでファンキーなナンバーである。しかし、Topleyがアメリカ的なポップナンバーを好むのに対して、やはりWinwoodの手に掛かると、R&Bなアシッドさが上に来る。
バックでジャムるフルートを聴いていると、やはりTrafficのソウル的なアプローチを連想してしまう。
夫婦で書いた3曲、#6『Now That You’re Alive』、#7『Bully』、#9『Horizon』の評価が最も難しい。
#6は『In The Light Of Day』のサイケディリックでプログレッシヴなノリと『One And Only Man』のファンキーなビートを混ぜた感じのディープなソウルトラック。
「Shoot Out At The Fantasy Factory」の頃の鋭角的南部黒人音楽への追及が垣間見える気がする。
オルガンとサックスのインプロヴィゼイションはかなり熱い。
#7はワールドミュージック的な難解さと、R&B的なリズムが複雑に絡んだようなエキセントリックなナンバー。かなりジャズ的な自由な発想をベースにしている感じはする。ヘヴィなギターとオルガンのベースラインがズンズンと腹に突っ込んでくる。
#9は唯一なスローでメランコリックなバラードタイプ。が、綺麗さとか美しさとは無縁で、ドライな哀愁、欧州トラッド的な物悲しさに、ラテンアメリカ風味を加味したタイプの曲。
これら3曲はWinwoodらしいのだが、いまいち地味か。
◆初の自主レーベルからの発売、で売れるかな?
Virgin Recordsとの契約が切れたため、Steve Winwoodは自前のレーベル、Wincraft Musicを設立したのが数年前の事。
このアルバムは初のインディ・レーベル作品となっている。(配給先は異なったディストリビューション・レーベル)
全世界では各メジャーの海外法人からメジャー盤としてリリースされている様子なので、流石に著名な英国を代表とするシンガーの面目は保てているようだ。
久々に、Winwoodの創作意欲のみを押し立てた、シャープで芸術家の感性をフルに活かしたアルバムであるとは思うのだが、果たしてこれが市場性があるかとなると、かなり疑問である。
評論家や批評家筋のウケは悪くないと思う。
かなり極端に走り、やりたい事をヴェテランが敢行すると、直ぐにグラミー賞が取れる時勢になっているので。
しかし、エスニックでユニークなロックアルバムとしては、筆者としても評価したい。
が、似たようなスタンス−ソロとグループでの作風の融合−を行った「Far From Home」がセールス的には伸び悩んだ事実を思い出すと、かなり不安を覚えるのだ。
Santanaがプライドをかなぐり捨てて、売れっ子の若手オルタナティヴシンガーと組んだ結果、彼のとっつき難いラテンロックが馬鹿売れした実績とはかなり内実が異なる。
より硬派でストイックな曲とメンバーを選んだのがWinwoodらしい不器用さといえばそれまでだが。
筆者の予測としてはまず売れないと思う。(外れるに越した事は無いが。)
が、それは仕方ないとしても、またぞろセールス不振で落ち込み何年も逼塞するのだけは勘弁だ。
年齢的にもイイ歳になっているのだから。次のアルバムはせめて五輪の間隔以内でお目に掛かりたい事だし。
(2003.7.6.)

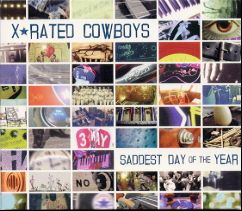 Saddest Day Of The Year
Saddest Day Of The Year