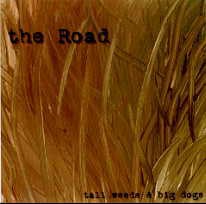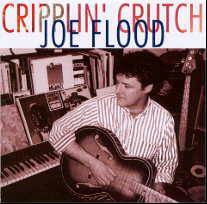Fear Not The Obvious / The Yayhoos (2001)
Fear Not The Obvious / The Yayhoos (2001)
Roots ★★★★★
Pop ★★★★
Rock ★★★★☆
Southern ★★★★
You Can Listen From Here
一言、SatellitesファンとDan Bairdのファンは何も考えずに買え!!!!!!
更にTerry AndersonとEric Ambelのファンも買うべし。
人間、稀には待つことで報われることがある。このThe Yayhoosのスタジオ録音盤がまさか聴けるとは昨年までは期待もしていなかった。ちなみにYah★osではなくYayhoosであるので、どっかのネットバンクから成り上がって株価が暴落した某IT関連の(って丸分かりやんか)企業と間違えないように。(笑)
無論、熱心なDan BairdとGeorgia Satellitesのファンなら1996年発売の「Buffalo Nickel」の日本盤ボーナストラックとしてYayhoosのライヴトラックが収められていたのを覚えているだろう。この曲が日本では、当時店頭で入手可能な唯一無二のYayhoos音源であった。もう5年以上前の話になる。
Yayhoosが結成されたのは、Danが2ndアルバムをリリースする約1年以上前のことである。
一応メンバーを紹介しておくと、元Georgia Satellitesのリーダー、
Dan Baird (L&B.Vocal,Guitar,Bass)
この当時はデブだったが数年前に30キロ近く減量してガリガリになり、近年リバウンドでまた太り出した
Terry Anderson(L&B.Vocal,Drums,Guitar)
80年代のルーツハードロックバンドのDel Lordsオリジナルメンバーで、Blue Mountain、Bottle Rockets、 Backsliders、The Blood Oranges他多数のルーツアルバムのプロデューサーとして敏腕を振るってきた
Eric ”Roscoe”Ambel (L&B.Vocal&Guitar)
そしてBilly Joe Shaverのバンドでの活動が一番著名で、自身でも地道なソロ活動を続けてきたヴォーカリストの
Keith Christopher (L&B.Vocal&Bass&Drums)
この4人がバンドを結成、「The Yay−Hoos」を名乗ったのが1995年のことであった。ちなみに結成当時はハイフンが付いていた。直ぐにとれてYayhoosとなったが。
全ての仲間がサザン&ルーツロッカーとしてキャリアの長い域に達しようとしてる頃合に組まれたこのバンドは、1995年に「Wrapped In Sky」というかなりアクースティックとカントリー色が強い意欲作を発表したDrivin’N Cryin’の前座として、1ヶ月ほど南部をツアーする。
その後、Dan Bairdの2枚目のソロ作「Buffalo Nickel」のレコーディングに残りのメンバーも参加する。特にTerryは曲もDanと競作している。そして当然のことながら、Danのツアーに同行することになり、この頃のYay−HoosはDan Bairdのライヴバンドという色合いが強かった。ツアーも全米と欧州を廻るものであったが、Dan Baird And The Yayhoosと紹介されていたそうだ。
冒頭に述べたように、「Buffalo Nickel」のボーナストラックとして聴ける音源以外には1996年に数曲の録音をThe Yayhoosとして行っている。当時、Terry Anderson等の所属していたEast Side Digitalのコンピレーションアルバムである「East Side Story Vol.1」で大トリの18曲目で『California』という曲を披露している。もっともこのレーベルアーティスト紹介サンプラーには、Eric AmbelやTerry Andersonの曲も入っているのだが。
更に、同年の1996年に「Rig Rock Deluxe:A Musical Salute to the American Truck Drivers」というアメリカを「コンボ〜イ」(懐かしい〜)のように走るトラック・ドライヴァーのための伝統ソングや新曲を集めたユニークなトリビュートアルバムにSteve EarleやShaver、Son VoltにDon Walserといった顔ぶれと共に参加し、2001年にDanのプロデュースで2ndアルバムをリリースしたChris Knightの書いた「Highway Junkie」という曲を演奏している。
更に、「Beer Run」という曲を始め数曲を何らかの形でリリースしているらしいが、こちらは未聴である。残念なことであるけれども。
このように1995年から96年にかけて、そこそこの活動をライヴ中心に行い、スタジオ録音も単独アルバムでなく、オムニバスに参加という形式でこなしていたため、セルフレコードの発表は近いうちかと思われた。
が、しかし、その後「Buffalo Nickel」のツアーが終了するあたりからパッタリと情報が入らなくなる。Terry Andersonはそれまで順調にソロ作を出していたのが、地下に潜るように姿を消し、Keith ChristopherもShaverのベーシストに戻ってしまったようであった。Eric Ambelは精力的に新人ルーツバンドのプロデュースを手掛けていた。
肝心のDan Bairdはプロデューサーとバックミュージシャンとして再びシーンで目立つ出すのが1999年頃なため、これまた殆ど音信不通になってしまったようであった。
1998年頃であったと記憶するが、Danのインタヴュー記事を雑誌で読んだ。
「Yayhoosは基本的に終わってしまったよ。僕たちは物凄い自信がこのバンドにあったのに、どのメジャーレーベルも相手にしてくれなかった。『ヴォーカリストが3人もいるバンドは今は売れない』ってさ。僕たちは皆、自分のやりたいことを持ってるし、それがYayhoosで活かせないんじゃ、もうこれまでだね。」
というような概略であった。Danの発言の裏には、これだけ良い音楽を創作できる音楽仲間が集まっても、もはやラップを取り入れた重いだけの音楽をやる連中ほどにも評価されないことへの苛立ちというか絶望があったようだ。事実、1999年までDanは殆どやる気のなかったことを証明するように、音楽活動が鈍っている。
以上のような事情で、既にYayhoosは終わってしまったライヴ・バンドであった、との認識しかなかったのだが、突如彼らのスタジオ録音盤に出会うことになったのが2000年、活動が停滞してから4年後のことだった。
シカゴのレコードレーベルで現在はカントリー&カントリーパンク系のルーツロックのメジャーなレーベルとなりつつあるBloodshot Recordsの設立5周年記念のオムニバスアルバム「Down To The Promised Land」という2枚組アルバムのトップバッターとして、Yayhoos名義の『Oh!Chicago』(本作にも#7として収録されている。)がトラッキングされていたのである。内容はもうシンプルなロックンロールナンバーである。Dan Bairdの男らしさ爆裂、的なルーツナンバーであった。
この時点ではYayhoosとしての活動は全く表面に出てこず、ひょっとしたら過去の音源を引っ張ってきただけかという危惧があった。何しろ、当時Danはソロの形態をとってツアーを行っていたし、後にそれがThe Sofa Kingsとのジョイントであることも判明したため、Danのライヴバンドであった位置付けの強烈なYayhoosの影すら水面下から浮かんでこなかったのである。
が、2001年に入り、初夏の頃「Yayhoosとして6月くらいにアルバムを出す準備をしている」という怪情報が、海外のファンの間に流れ始め、その6月にBloodshotから正式にリリースが決定したと発表があった時は喜ぶよりも、正直なところ驚いた。結成以来5年が経過し、しかもこのようなソロミュージシャンのジョイント・プロジェクトは長続きした例がないため、絶対にもう駄目であると結論を打ち出していたからだ。
そんなこんなで、アルバムが出るだけで嬉しい限りなのであるが、肝心の内容が嘗てDan Bairdが加わったレコードの中では一番ルーツ・ロアで粘着力の高い、粗っぽいアルバムになっている。詰まるところ、もっとも南部ロックに傾倒した創りになっているということ。もう一歩踏み込んで考えると、結成当時画策していたメジャーへの売込みを考慮しないで作成されたアルバムであると言えるだろう。兎に角、とことんシンプルさを追求したロックアルバムである。
ピアノやオルガンは残念なことに全く使用されていない。ゲストミュージシャンも参加は皆無。ギターのチャンネルの左右をDanとEricが分担し、後はドラムスにベースのみという簡潔さを突き詰めた楽器の使用をしている。
直感的な感想では、殆ど一発セッションに近い録音で叩き込まれたアルバムのようだ。
何と言っても最大のセールスポイントはヴォーカリストが4人、全てのメンバーがリードヴォーカルを取れるという点であろう。但し、ヴォーカルの質はどちらかというと暑苦しい系列の、ソウルフルな声質なシャガレ声に集中しているため、幅広いヴォーカルを聴けるというアルバムではない。が、しかしどのシンガーもヴォーカリストとしては、少なくともサザンロックを歌う分には非常にハマリな声であるので、アクセントを付けれて良い、という利点はある。
告白すれば、Dan BairdとTerry Andersonだけ歌ってくれれば良かったのだが、・・・・・ヴォーカリストとしてはあまり期待していないEric Ambelについてはまんま予想通りの可も無しだった。が、Keith Christopherのヴォーカルは予想以上に悪くなかった。
この4人のヴォーカル比率というか受け持ちは全12曲のうち、Danが#1、2、5、7、8、11、12の半分以上の7曲。
Terryが#4と10。Ericが#3、9、そしてKeithは#6の1曲のみリードを担当。但し、ハーモニー・ヴォーカルとバックヴォーカルは殆ど全員でつけられている。特にTerryとEricはDan Bairdのリード曲ではほぼ100%ハーモニーを付け、裏ヴォーカルとして同じラインを歌っている。
このため、演奏的には実に単純かつソリッドであるのだが、曲全体では結構厚みのあるヴォーカルを聴けるアルバムになっている。まあ、ここまで似通ったタイプとはいえ個性的なヴォーカリストが顔を揃えると、ヴォーカル・パートが際立つのは当然と言えば当然なのであるけれど。
今回は、海外のレヴューも多数掲載されていることから、やはり待っていたファンが多いのだと考えると、頬が緩んでくるのだけども、更に嬉しいことには、あるアーティストの批判に対して筆者と同じ意見のレヴュアーが存在することである。
海外のレヴューで引き合いに出されてこき下ろされているのがBlack Crowesであるのには非常にシンクロにシティを感じて我ながらネガティヴであるけど、誠に喜ばしい限りである。このような飾り気の無い真のロックアルバムを聴いてる人々は、あのクソ以下の駄作を作って「芸術的やろ、オイ。」とリスナー舐めきっているアホなRobinson兄弟に対して国籍と言語を超えて非難してくれるのはまったくもって痛快である。
「変に流行に媚びない振りして実際コビコビなアルバムはサックスだ。」
「芸術性を出して、評論家や音楽雑誌受けするアルバム創ったBlack Crowesはこのロックスピリットを見習え。」
「ルーツロックはハードなだけでは成り立たない。もはやサックス以下のCrowesの存在意義はこのアルバムが
出たからにはない。」
「耳障りとハードドライヴィンな音は違うのだ。Black Crowesも膝を正して聴け。」
少なくとも片手以上のレヴューページで以上のような批判が読める。筆者以外にもあのアルバムをこき下ろしているレヴュアーが複数存在するのには驚いた。
真新しいことに挑戦という名目でメジャーに媚びた、しかも聴くに堪えない雑音を出したグループと、このYayhoosは全く余裕の度合いが異なる。装飾を施した都会的なサウンドが芯に存在するアメリカンロックは最高に大好物であるが、このような必要以外の要素を切り落として、力技勝負を掛けるストレートなロックンロールアルバムも同じくらい愛聴している筆者には、最高の1枚である。
まさにBar Bandの真骨頂の如くな酔っ払いロケンロールが全編を通して爆走している。必要以上にハードドライヴィンなハードロックな展開に持ち込まなくても、十二分に埃っぽく、重量感覚一杯なのだ。
男臭く、タフでワイルドでラフ。しかしながら、そういった南部のルーツ音楽のテイストを損なうことなく、ポップミュージックとロックンロールの基本はちゃんと踏襲している音を創ってくれているのが、さすがにヴェテランオヤヂ集団である。「中年軍団、鬼の霍乱・狂い咲き」とスパーンと叩き割って売り出したいくらいの勢いがある。
但し、久々のセッションということもあり、作詞作曲に関しては殆どが各自で創った曲をそのまま担当して歌うという形式が大半である。純然たる共作曲はDanの歌う2曲だけである。1曲はカヴァーであるし、Terry Andersonが歌う#4『I Can Give You Everything』はメンバーでないAl ”Big” Andersonとの作品であるからだ。
このことを踏まえると、このアルバムタイトル「Fear Not The Obvious」ー得体の知れない不安・惧れ−が圧し掛かってくるような気になる。一時的な集合のアルバム作成で終わってほしくないし、がっちりとチームで活動して欲しいグループであるからだ。各自が忙しいミュージシャンなので、四六時中一緒に活動という訳にはいかないのだろうけれど、是非次回(絶対に!)はメンバーで共作した曲のオンパレードを聴きたいと思う。
さて、各ヴォーカリスト別に曲感を述べていこう。
Keith Christopherはたった1曲#6『For Cryin’ Out Loud』のみでリードヴォーカルを担当している。前述の様に自作曲である。このアルバムの中では#12のABBAの『Dancing Queen』カヴァー以外では、最もすっきりしたアレンジのオーソドックスなルーツロックチューンである。南部サウンドというより中部のHeartland Rockに類似した中庸性を有した、しかしながら泥臭いギターリフが、やはりサザンロックの職人集団を再確認させるナンバーだ。以前から才能あると評価されているシンガーであるが、ソロ作以上の出来である。
Eric Ambelは#3『Monkey With A Gun』と#9『Baby I Love You』の2曲。彼独特の鼻の詰まったようなヴォーカルは相変わらずである。#3はスワンプロック的な適度に崩れたメロディと演奏がリラックスした雰囲気を醸し出してくれる。少々投げやりというかやる気の無さが感じられるところがEricらしい。バックヴォーカルのお間抜けな合いの手とコーラスがとても面白く、60年代のクラッシックなロックを連想させてくれる。
全体的にEricの曲が一番ノスタルジックというか、古臭いパターンを踏襲しているようだ。良い意味においてであるけれども。#9もやや気だるいリズムと脱力したようなコーラスとヴォーカルが何とも言えず、のんべんたらりんとした、これまたスワンプ的なルーズさを聴かせてくれる。全体のタイトな流れの中で、Ericの曲が表現するユルイ感覚は、緩急をつけるという点で効果的な仕事をしていると思う。
やはり長髪・ヒゲ・デブが似合うTerry Andersonの提供する曲は、彼のポップセンスを遺憾なく発揮している。#4『I Can Give You Everything』と#10『Hunt You Down』の2曲はスピード感とコマーシャルさ、それに躍動感という要素を全て過不足無く満たし、しかもタフでルーツィな粘っこさが軟弱なポップスとは一線を引く曲にしている。この2曲は#10の方がハードで泥臭い。#4は力任せなロックナンバーであるが、キャッチーなメロディラインがシンプルでワイルドなアレンジと絶妙に合致して時代が15年位前なら絶対にメジャーでもヒットしそうな、ロックナンバーである。テキサス的な田舎臭さの感じられる#10も、ルーツドライヴナンバーとしては一級品である。
オープニングの#1も彼がペンを取っているけれども、ことメロディメーカーとしてはTerryの方がDanよりポップでロックとして楽しい曲を書いてくれるのではないかと思う。実に才能のあるドラマーである。
TerryとEricの作品である#1『What Are We Waiting For』で、Georgia Satellitesのアルバムと錯覚を覚えそうな気さえする。Danのヴォーカルを久々にスタジオ録音で聴けたが、やはり鳥肌が立つくらい素晴らしい。Terry節の発揮されたロックのビートとキャッチーなメロディが、もう文句無しのナンバーだ。しかもDanのヴォーカルというだけで無条件に白旗。(笑)アレンジは以外に丁寧である。が、演奏はシンプルかつダイナミック。
続く2曲目『Get Right With Jesus』は、Danの得意な泥っとしたブルージーでバー・ロック的なサザン・ナンバーである。かなり濃いうねりを持つ曲である。この暑さは、熱の入れようはやはりロックンロール以外の何者でもない。このハードとダサダサなリズムが鼻につかないかで、このアルバムを聴けるか聴けないかの踏絵がなされそうだ。これは#8のロッキン・ブルース的な『Wicked World』にも同じことが言えるだろう。80年代のDan Bairdでは創らなかった、又は曲目に加えなかったであろう、ダークで弾け方の少ない地味なチューンであるが、この曲にDanの今を感じれるような気がする。
#7『Oh!Chicago』は2000年からもう何回聴いたか判らないので、今更改めて言うことはそれ程無い。が、このラフでストレートなロックナンバーを聴けたことで、Yayhoosが再び筆者的にアップデートなバンドとなりえる可能性を示唆してくれたことは印象に深過ぎる。この曲だけ聴いた回数が先行発表の関係で図抜けているため、やはり耳に触りが良い。このようなシンプルでポップなロックを演奏してくれるミュージシャンは後にも先にも希少であると思う。
#5『Bottle And Bible』はアクースティックなスローナンバーである。この、落ち着いて暢気なメロディは、やはりDanの加齢を思わずにはいられないが、心和む南部ルーツナンバーである。
ラスト2曲は、先に発売されたライヴアルバム「Redneck Savant」にも収められていたABBAのクラッシックヒットである『Dancing Queen』のルーツアレンジしたナンバーと#11『Hankerin’』のホンキィ・トンク調でオールドタイム・ロックの元気印が炸裂の2連コンボである。この2曲のラフさとポップさと暴れ具合を聴いていると、やはり永遠少年のオヤヂ頑張る、というキャッチコピーが浮かんでくるのだ。#11はシングルカットは出来そうも無いくらい荒っぽいが、聴き応えは最高。続くエヴァーグリーン・ソングの#12へと場を盛り上げる効果は絶大である。
#12の底抜けに明るいアレンジと、かなりルーツィであるが、爽やかなリフが冴える演奏は、もう単純に楽しい。それ以外には言いようが無い。以前どっかのオルタナバンドの同じ曲のカヴァーを聴いたが完成度は比較にもならないというか比較したくないので、きれいさっぱりそちらのヴァージョンは脳内から洗い流した。
それにしても最近のDan Bairdは元気が良い。モチヴェーションが戻ってきた証拠と考えると、今後が期待できない方が不思議である。何せ、年に2枚もアルバムをリリースしたのだから。2001年はWill Hogeのバンドのギタリストから始まって、Danが活発に動きを再開した年として後年、記憶できるようになればなあ、と思う。Terry Andersonも5年ぶりにニューアルバムを出したし、風は順風のようだ。
こうなるとやはり後欲しいのは、Georgia Satellitesである。求む、再結成!! (2001.9.21.)
 Plan B / Huey Lewis And The News (2001)
Plan B / Huey Lewis And The News (2001)
Roots ★★★★★
Pop ★★★
Rock ★★★☆
R&B,Southern ★★★★☆
You Can Listen From Here
このアルバムをすんなりと聴けるようになった理由は、「Small World」から顕著になった、R&Bやジャズ、黒人音楽への傾倒に慣れてしまったからだと思う。
これまではやはりデヴューアルバムのごとくなベイエリアサウンド、そして「Four!」のような艶やかさを詰め込んだロックアルバムの残滓をHuey Lewis & The Newsに求めていたため、期待を外されたという落胆の方が強くて、90年代の彼らのサウンドに失望していたのだろう。
しかし、「Picture This」までは兎も角、現在改めて聴き返すと「Sports」でのブラック・ミュージックへの追及が良く分かるのだ。ダイナミックなロックサウンドが際立っているため、また『Heart Of Rockn’Roll』や『If This Is It』のような黒い音楽性を内包しながらもアメリカン・ヒットチャートオリエンティッドなメロディラインがそのクドさを押し込めてしまっている名曲の印象がより強烈なため、私的に苦手なブラックミュージックの要素が鼻につかないのだろう。
ずばり、ロックンロールの良さは黒人音楽の汗まみれの肌着のようなベタつきを駆逐する力量を有した最高の音楽だ。・・・とはいえロックンロールのルーツの1つは黒人ブルースなんだから、単に依怙贔屓が入っているだけなのだが。(汗)
結局、Huey Lewisが自ら求めるルーツ音楽への表現をどこまで出すか、またレコード会社の求めるヒット性の高い音をどの程度織り込んでいくか、というその妥協点でアルバムを製作してきたのだろうと思う。
が、サンフランシスコ・ベイエリアのタテノリ3コードもHuey Lewisの原点の1つであることは間違いない。次第にこちらのポップで元気の良い音楽性が後退して行ったのは、この良質なアルバムを聴いて評価している現在でも、残念に思うのだが。
彼らのNo.1シングルである『Jacob’s Ladder』を提供したBruce Hornsbyのインタヴューコメントを思い出す。
「僕とJohn(Bruceの弟でソングライティングの相方)が創った原曲はとてもスローでアクースティックで垢抜けないものだったんだ。それをここまでヒット性の高い曲に仕上げるとはさすがだね。」
これは決して売れ筋路線への皮肉ではない。実際Hornsbyは2ndアルバム「Scenes From The Southside」でこの聖書において天使が天上に架けると言われている梯子の歌を、当初のアレンジよりアップテンポでスマートに変えてかなりのポップロックナンバーとして披露している。まあHuey Lewisのヴァージョンと比較すればナチュラルではあるけれども。
このように、売れ線の狙いのキャッチーで艶やかなポップとオーヴァープロデュース気味な方向性を思い切って切り捨てまではしなかったが、より自らのルーツを出そうとし出したのが、1988年の「Small World」からである。が、この転換がセールス的にも音楽性としても成功したとはどうしても言い難い。
ジャズ・R&B・ブラックミュージック・ソウルといった、テイストを押し出そうとしているのに、何故かロックのダイナミズムを無理矢理持ち込もうとしたためか、ハード過ぎることと黒っぽい音楽の重さが二重に競合してとても聴き易いとはいえない、クド過ぎるサウンドが目立ってしまった。
ここには、やはり「ロック」アルバムとして市場性を中途半端に追及した故の、失敗が感じられてならない。「Small World」から「Hard At Play」のアルバムは殆ど失望しかもたらしてくれなかったし、カヴァーアルバムである「Four Chord And Several Years」に至っては、何故このようなテンションの低いカヴァーアルバムを出す必要があるのか、と疑問に思わざるを得ない作りであった。
以上のような経緯から、全くもうHuey Lewis And The News(以下HL&TNとする。長いのでしんどくなってきたんで。)には期待していなかった。が、ところが、今作、21世紀に入って届けられたオフィシャルでの9作目は80年代後半からのヘタレぶりを払拭する出来であったのだ。何故か?
もはやHuey Lewisはチャートアクションを念頭に置くことを断念したに違いない。現実問題として、例え「Fore!」のようなアメリカンロックアルバムを作成したとしても、売れる可能性はゼロに等しいだろうし。現在の市場性では。
というような流れで、今作「Plan B」において、筆者も漸くにして、80年代のHuey Lewisの残した名作の影を踏み続ける螺旋から抜け出すことが出来、R&Bベースのルーツロックとして彼らを評価することができるようになった。
このことも評価を上げていることに寄与しているだろう。
であるからして、1st、2ndのベイエリアサウンドの底抜けに明るいロックさや、3〜4枚目の華やかな売れ線ロックを未だ求めているリスナーにはこのアルバムはお薦めできない。
とはいえ「Hard At Play」や「Small World」の重たいジャジーなロックが好きな方にも手放しでは推薦できない。理由は、以下に述べる。
セールスとして全盛期であった頃を比較対象とすれば、勿論、最近作の傾向である、R&B、ブルース、ソウルといった音楽への歩みよりは明白に打ち出されている。が、どこかしら開き直った開放感が全体から感じられるのだ。チャートで売ることと自らのルーツへのせめぎ合いの故か、重苦しい雰囲気がのしかかっていた前作までの迷走ぶりは全く伺うことが出来なくなっている。ともすれば耳に障っていた、必要以上にハードでヤケクソ的なロックンロールへの無駄なエネルギーの使い方は感じられない。
底抜けに明るい雰囲気は、デヴューアルバムに相通じる箇所があるけれども、若さ(とはいえデヴューは遅かったけれど。)に任せて突っ走っていた熱さの裏返しの明るさよりも、吹っ切れた年長者のゆとりから来る肩肘の張らないスラップ・スティックス的なノリを感じるのだ。
ホーンセクションをこれまでの殆どのアルバムで取り入れてきたHL&TNではあるが、今回はマルチプレイヤーで、PVでは常に煙草を吸っていた細い顔のサックス吹きJohnny Collaだけでなく、3人のブラス隊を正式メンバーに加えて9人編成と大き過ぎる程の所帯となっている。
ツアーやレコーディングにはTower Of Powerを始めとして著名なホーンバンドとジョイントしてきたバンドであるが、このように正式なメンバーとしてブラスセクションを加えるとは予想をだにしなかった。
このホーン・パートが強化された結果として、全曲に思いっきりスゥイングするブラスがフューチャーされ、この「Plan B」を特徴付ける一要素となっている。もはやBig Band的なノリも随所に聴かれ、黒人のソウルアルバムと、予備知識のないリスナーが聴いたら間違えそうなサウンドになっている。
またはBig Band風のシカゴ・ホワイトブルースという様に捉えられそうでもある。
ここまでの居直りというか、大幅な改変を断行したのは、やはり鬱屈した何かから脱却できたのではないか、と想像している。常に売れなければならなかったプレッシャーか、はたまたやりたいことが完全にままならなかったレーベルへの不満か・・・・・。兎に角、サウンドからも完全に悩みがなくなったようなネアカな気概を聴き取れるのは間違いないのである。
さて、メンバーであるが、デヴュー以来鉄壁のコンビネーションであった6人のうち、1名だけ交代がなされている。常に不動であったメンバーであったが、ベーシストのMario Cipollinaがメンバーから外れており、代わりに1970年代の半ばにそこそこの成功を収め1980年の半ばに解散した、西海岸ロックグループのPablo Cruiseのベース弾きであったJohn Pierceが加入している。Marioに何があったのかは情報が無いために全く分からないでいる。情報をお持ちの方は一報を戴けると幸いである。
このメンバーチェンジ以外は全ていつもの顔ぶれである。
Huey Lewis (L.Vocal&Harmonica) , Johnny Colla (Sax,Guitar,Piano&Vocals)
Chris Hayes (Guitar&Vocals) , Sean Hopper (Keyboards&Vocals) , Bill Gibson (Drums&Vocals)
このロックンロール・ユニットに3名のブラスセクション
Marvin McFadden (Trumpet) , Ron Stallings (Tenor Sax) , Rob Sudduth (Tenor&Baritone Sax)
以上が正式なバンドメンバーとしてクレジットされている。3人ともに多数のソウル・ブラックコンテンポラリー系のアーティストのアルバムでホーンを担当しているヴェテランである。特にRob Sudduthは嘗て何回もHL&TNのツアーに正式なサポートホーンバンドのリーダーとして同行している人である。
全11曲のうち#4『When I Write The Book』がNick Loweのカヴァー曲である。また嘗ての殆どのアルバムにバックヴォーカリストして参加しているMike Dukeの作品である#9『Let Her Go Start Over』以外はメンバーとHueyの共同作品という従来のスタイルと変化は無い。
しかし、タイトルの「Plan B」である。これは何を意味しているのだろうか。タイトル曲として#7『Plan B』を聴いてみると、ファンキーでムーディジャズのような黒っぽいうねりを持つこの曲はかなり意味深な詩であると思う。アルバムの中でも特にファンクテイストとブラックミュージックの傾きが深いこの曲を聴くと、各ヴァースの最後にメンバー全員で♪「Plan B」とシャウトされるが、3つのパートの最後の歌詞が
♪「Well It’s time for me to wake up to reality」
♪「There’s only one option that’s left for me」
といった何らかの転換・変革を決意したような歌である。切羽詰ったというような意味合いに受け取れなくも無いけれども、ここまで気持ち良くジャジーにスゥイングをかましてくれると、やはり開き直って悟りを開いた、というすっきりとした何かへの決別に聴こえる。
やはり彼らの原点であるBar Rockへの回帰を、中途半端でなく決意したという意味の「オプション」であり「計画」であるのではないだろうか。Bへと移行=インディへと移る=とことんやりたい事を突き詰めてみよう、こういった証がタイトルなのだと想像している。
実際にホーンセクションをオフィシャルにメンバーに迎え入れたことで、サウンドは分厚くならずに、ルーツロックへの色合いを濃くした効果のほうが高い。ホーンセクション=派手な分厚いサウンドという一般的なアレンジ手法へ背を向けているようなアルバムを作成したことで、「Bクラスへ落ちてももう気にせえへんど。どや。」というような明るい決意を思わせる。
中途半端な方向性の決定ではないようだが、悲壮感は微塵も感じられない。むしろ水を得た魚の様に、得意のフィールドへ戻ってきたぞ、カンバック・サーモン!!(謎)のような清々しさが存在している。
シングルとしては#9『Let Her Go Start Over』がファースト・カットされている。嘗てのトップ10ヒットである『If
This Is It』や『Doing It All for My Baby』を懐かしく思い出させるような、ソウル・バラードであるが、この大ヒット曲よりも2ndアルバムからのトップ30ヒットになった『Hope You Love Me Like You Say You Do』に通じるBar Bandのまったりとしてそれでいて豪快なルーツテイストが如実に感じれる曲である。オープニングリフやインタープレイで切なげに吹きまくられるHueyのブルースハープといい、ゲストのJim Pughがオルガンを掻き鳴らし、重いピアノがしっかりとラインをなぞるところは、感動モノである。そういえば、『Hope You Love Me Like You Say You Do』もDukeの単独作品であった。しかし、殆ど唯一新ホーンセクションが活躍していない曲がこの#9なのである。それを1stシングルに持って来るところは太っ腹というか、考え無しというか。(笑)それにしてもオルガンの多重な演奏は一聴の価値があるトラックだ。
このアルバムの特徴は、アナログ盤でのA-sideにあたる#1〜#5までがかなりキャッチーなポップ・ソウルナンバーが多く、反してB−sideの#6〜#11がより一層黒人音楽へ踏み込んだR&Bでブルージーなナンバーで固められていることである。
そのA面で、ヒット性が高いトラックは目白押しである。#3『I Ain’t Perfect』のが前半ではややジャジーなラインとR&Bのウネウネとした流れが強めではあるが、特にとっつきにくい曲という訳ではない。
1曲目の、まるでパーティの会場で騒ぐ人々の嬌声のようなSEがオープニングから終始バックトラックとして流しつつも、ジャンプするピアノと、ブンブンと振り回されるホーンセクションに乗せて、あのHuey Lewisのソウルフルなヴォーカルが炸裂する『We’re Not Here For A Long Time(We Are Here For Good Time)』は新生のHL&TNの元気の良さが出たナンバー。うねりながら力強く躍動するオルガンの音色は、『Hip To Be Square』のゴリゴリなアップテンポに比類するくらい気持ち良く抜けている。
続く『My Other Woman』も実にリラックスしまくった極楽なスゥイング感覚満載のホンキィなミドルチューン。ベースとシンバルの音がとても爽快なリズムを刻み、ホーンの3人(+Johnnyで4人か)の息もピッタリと合って、アンサンブルの極意をこの段階で見せ付けれくれる。しかし、この場末の煙草の煙が漂うようなナイトクラブで演奏されるようなジャンプナンバーを何の気負いも無く演奏しているところに、現在のHL&TNのスタンスが現れていると思う。
そして#4のNick Loweのカヴァー曲『When I Write The Book』もオリジナルよりも更に明るく、弾むビートを取り込んだ、ポップロックとブラスロックの両方を堪能できる好アレンジとして蘇らせている。メンバーのコーラスとHueyの後半でのヴォーカルの掛け合いは、ルーツへの傾倒が強まろうが、彼らが昔からのコーラスワークにおいては健在であることを教えてくれる。この軽快に仕上がった名曲はシングルとなっても良いのではと思う。
#5『I’m Not In Love Yet』では女性ヴォーカルWynonnaとのインスタント・デュエットを披露している。このWynonnaはカントリーシンガーのWynonna Juddのことだろうか。彼女については名前しか知らないため、同一人物かは良く分からない。(汗)このデュエットはややアクースティックなギターと、控えめなオルガンとブラスがさり気なく演奏される、かなりソウル・ミディアムバラードの雰囲気を持った曲である。やや大人し目のナンバーではあるけれども、悪くない出来上がりになっている。
そしてB面に当たる#6から#11までは、黒っぽさとR&Bが色濃く反映されたナンバーが殆どである。#5と同じようなスローなグルーヴ感の漂う『Thank You #19』から始まり#9以外はややキャッチーさが目立たなくなっている渋めな曲が多いのはかなり残念である。もっと明るく楽しいナンバーがあっても良かったのに。
ドラムループというかいかにもR&Bソングのカシャカシャいうドラムから始まる#8『The Rhythm Ranch』はラップのようなバックコーラスまで飛び出す、もうアーバン系のブラックミュージシャンが普通にアルバムトラックとして録音しそうなリズムナンバーで、まさにタイトルの如しである。この曲は些か苦手である。どうしてもR&B特有なこのチープなリズムとドラムマシンの音には耐性が付かない。
#10『I Never Think About You』もややアーバンソウルという感じのするブルージーさがのっぺりと流れるナンバーである。少々元気の良さが感じられないし、中途半端にポップであるので、これまたあまり好きでない。どうも後半の曲にあまりにも黒さをロックテイストを抜かし過ぎて追及した曲が固まっているようだ。
このようにやや胃に重い曲が続くため、ラストの#11『So Little Kindness』がファンクなリズムを躍動感を込めて聴かせてくるとほっとする。このようなブラックオリエンティッドなブラス・ファンクチューンを最後の曲にするとは、やや予想が外れた気がする。恐らくはソウルバラード的な曲が来ると予想していたのだが。それにしても、もう少し羽目を外した暴れ方をしても良いR&Bの豪快さがありそうなのだが、やや小さく纏めているのが残念。
全般としては、後半に息切れと、ブラックの憧れを強く出し過ぎて、前半の明るさとミスマッチなところを何とか上手に処理できなかったものか、とも思うのだ。
しかしながら、全体を通しては、お気楽な南部系のブラック&ブルースルーツを必要以上にハードにしないで表現した良質なルーツロック&ソウルアルバムであると思う。
ついにこのアルバムにしてメジャーとの契約を打ち切り、中規模の,ロックミュージックよりもソウルやR&Bシンガー系列のZomba Records傘下からのリリースに踏み切った彼らは、独自の道を進もうとしているようである。
嘗てのロックなサウンドを振り切ったのは賞賛はしているとはいえ、本音を言えばかなり寂しい。それ故にこのアルバムの前半では、キャッチーな楽しさをまだまだ持っていることを再確認できて幸いであった。
が、後半の様にR&B、ジャズ、ブルースにあまりにもベッタリと密着しすぎると、90年代のような濃いけれど、濃さが鼻につくバンドになりかねない。吹っ切れた明るさを、是非とももっと音楽性に活かしてもらいたい。
そうすれば、まだまだリリースが楽しみなバンドでありつ続けてくれる筈だ。Huey Lewisは2001年で50歳を超えるが、元々老け顔で年齢を感じさせない絶倫さと得体の知れないパワーがある人だから、安易にスローな黒人音楽だけに陥ることは勘弁して欲しい。
兎に角、久々にちゃんと聴けたアルバムを出してくれたことは嬉しい限りだ。もうダメになったアーティストと思い始めていたことだし、近年は。良い意味で予想が外れた。 (2001.9.23.)
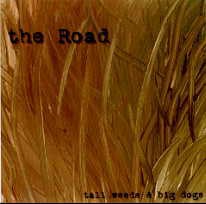 Tall Weeds & Big Dogs / The Road (2000)
Tall Weeds & Big Dogs / The Road (2000)
Roots ★★★★★
Pop ★★★
Rock ★★★☆
Southern&Blues ★★★★
You Can Listen From Here
このジャケットで即ジャケ買いをしてしまった。まあ例えジャケットが滅茶苦茶趣味が悪かったとしても、
例えばこんなの→2000年度・マイ・ワースト・ジャケット であったとしても以下の理由から即買いは必然であったのだが。
バンドの名前−「The Road」・・・・何か良さそう。きっとオン・ザ・ロードの乾いた風が感じられるだろう。
タイトル−「Tall Weeds & Big Dogs」・・・・何か良さそう。いかにも田舎な鄙びた味わいがあるだろう。
ジャケット−もうこのワビ・サビた枯れ具合は古今集が大好きな(全く関係ないぞ。)人間には麻薬のような吸引力 がある。このジャケット見て欲しくならない人間はもう一度中学から古文の勉強をし直した方が良かろう。
・・・・・・え、普通はこのジャケットで衝動買いはしない、って?・・・・・・・・・否定できないところが弱い。(笑)
更に、常に筆者の求めているアルバムの一つであるピアノやオルガンの目一杯聴けるルーツロックアルバムというのは、最終的なトドメとなっている。
ついこの間というか一つ上でHuey Lewis And The Newsのレヴューを挙げているが、このアルバムはHL&TNよりも全然全然黒人音楽への傾倒は弱い。身も蓋もない表現をすれば、それだけインディ風なアルバムなのだ。
おいそれと比較は出来ないにせよ、ここでニ連に挙げているのアルバムはブルースという音楽への憧憬というか敬意を持って、音楽を創作しているのはしっかりと伝わってくるものがある。
しかし、重ねて引き合いに出してしまって些か単調だが、HL&TNのアルバムよりこちらの「Tall Weeds & Big Dogs」の方がやはり若さというか、1990年代の音を感じさせてくれるし、白人ルーツロックとして捉えると、こちらのアルバムが全然ロックンロールしてくれている。
ちなみにこのアルバムも、筆者が恒例の日本で確認されている初の購入者となっている。また処女峰を登頂してしまった。(笑)
さて、このThe Roadであるが、2000年の発売当初と比べて、かなりの内部構造の変化を経験している。2001年8月現在で名称がソングライターでヴォーカリストでギタリストのShawn Davisの名前を冠した”Shawn Davis & The Road”と変更されている。恐らくこの変更は、バンドのメンバーの大幅なチェンジを理由にバンドを刷新するためのものであろうと推察している。
本作はバンドが活動しているL.A.で演奏・録音がされているが、何と所用日数がたったの10日であるそうだ。しかしながら、アレンジもミキシングも全く音源的には高い水準にあり、インディ録音が酷かったのはもはや過去の話であったことを再認識させてくれる。
California出身のルーツロックバンドというのは意外に少ない気がする。恐らく今年は数枚くらいしか入手していない、と今更ながら気が付いた。土壌的には60〜70年代の西海岸ロックというカントリーロックをベースにした音楽の発祥の地なのだから、種が育つ余地はあると思うのだが、やはりこの州もオルタナ&モダン軍団に席巻されているのかと思うと、相当に悲しいものがある。やはり、現地で暮らさないと旬なマイナーバンドを発掘するのは困難であると改めて思う次第である。
話を戻すが、このアルバムは2000年の10月に自主制作され、未だもってどこのレーベルとも契約をしていない、CD番号のない完全セルフリリース盤である。
が、彼らは100%近くCaliforniaというよりもL.A.周辺のほぼ決まったバーやライヴハウスでしか演奏をしていないのに、ライヴ会場とネット販売で既に1万枚を超える売上を上げているのだ。事実、メジャーで発売されても何ら問題のない完成度であると思うが、現在の市場性では何をか言わんをや、である。
そのレコーディングは5人のバンドメンバーと数人のゲストを迎えて行われているが、2001年秋現在で、バンドに残っているのは、フロントマンのShawn Davisとプロデューサーも担当している鍵盤プレイヤーのGregg Buchwalter だけである。厳密に言うとドラムのMike Pettedがバンドに出たり入ったりを繰り返していて、腰が定まっていないようで、一時期はどうやらBrian PlaineというNew Yorkから西海岸へと移ってきたドラマーが正式メンバーになったらしいが、また元の鞘に戻り、Mikeがドラムを叩いているようである。少々この辺が不透明である。クリアになり次第訂正するつもりである。
その他のレコーディングスタッフは全てバンドから離れている。現在は6人編成となったばかりのようだ。
以下、
Shawn Davis (L&B.Vocal,L&R.Guitar) , Gregg Buchwalter (Piano,Hammond Organ,Synth)
Andrew Bush (L&R.Guitar) , Kevin Heath (Bass,B.Vocal) , Mike Petted (Drums)
に加えて、女性バックヴォーカリストのSidという人が正式にバンドのメンバーとして加わったそうである。リードヴォーカルも担当するのか、それともハーモニー程度で控えるのかは未だ新曲が聴けていないために分かっていない。
またギターのAndrew Bushはゲストプレイヤーとして当初はクレジットされていた人で、本作のミキシングとエンジニアを担当している。レコーディングに立ち会って、Shawnの音楽性に共感を覚え活動を共にするようになった結果の正規メンバーへの登録らしい。
フロントマンのShawn Davisは10年以上もL.A.周辺のインディバンドでギタリストやソングライター、シンガーとして活動を地道に続けてきたミュージシャンだそうで、自身のバンドを作ってやりたい事をやろうと思い立ったのが、1999年のこと。曲を書き上げ、ミュージシャンを集めてレコーディングをし、CDをプレスするまで1年以上かかった訳である。にしては10日でレコーディングというのは、バンドとしての活動を軌道に乗せることに比べて、物凄い速度であるけど。
「現在のラジオで流れているような流行に迎合することを全く考えずに、ただ自分の気持ちを正直にぶつけ、心をこめた歌を届けたい。」
というShawnの目標に沿って創られた10曲は、基本的にはシンプルかつ重厚なルーツロックである。ブルースを根幹に置いてロックンロールを演じるところはThe Rolling Stonesの音楽性と非常に近似しているところがある。また時折垣間見せる、コーラスのハーモニーワークや、ピアノの流麗なライン、そして泥臭く重いメロディを奏でながらも端々で聴こえてくる抜けるようなギター・ワークには、The Byrdsの如き彼らの出自であるウエスト・コーストの音楽性を感じることもできるように思えるのだ。
まず、アルバムはかなりモダンロックというより、モダン・ヘヴィネス=オルタナティヴの香りがプンプンするハードロックナンバー#1『My World』で幕を開ける。リフのメカニカルなSEといい、ヘヴィでアーティフィシャルなギターサウンドがスピーカーから聴こえてきた時は、「あら、こらハズレやったかな。」と思ったものだが、重苦しいリフからコーラスに懸けて唐突にスピーディになるスコアといい、Shawnのやや熱過ぎるバリトンヴォイスといい、リピートして聴くと、そうそう悪くないモダン・ブルース&ヘヴィネスな曲として受け入れることができている。必要以上に力の入ったヘヴィロックにしていないから何とかなったのだろう。一歩間違えば、この曲で放り投げたかもしれない。
一転して、ホンキィトンク・ピアノのリフで明るく突っ走る、#2『Better Than He Can』は、ピアノのソロに冒頭からB3が被さるというアレンジで、既にお気に入り決定である。歌詞はかなりストレートかつ単純ななラヴ・ソングである。が、デフ・レパードのコーラス隊であるBankrapt Brothersまんまの奥行きのあるバックコーラスと、ガツンガツンな頭立て振りなロックンロールが縦横無尽に駆け回り、素直に豪快なロックの楽しさを受け入れられるナンバーである。このくらい痛快なピアノはFreewheelersのツイン・キーボードを懐かしく連想させるものがある。
続いて#3『Misunderstood』。これまたFreewheelersが演奏しても違和感のないようなロックとブルースがせめぎ合いを演じているパワフルなロックチューンである。が、ややブルースの色合いが強く、Rolling Stonesの黒っぽさを少々現代的にアレンジしたような曲と言えるだろう。この#2〜#3までの暴れん坊将軍振りはアルバムのハイライトの一つであると思う。
一転してメロウというよりも気だるいサックスの演奏から、ダークで物悲しいメロディが淡々と流れる#4『Fallin’』で全力疾走であった冒頭の展開が一時、スローダウンする。ブルースロックの静的音楽性である、哀愁・哀歌・憂鬱と何でも良いだろうが、このローファイでダークな曲はメジャーアルバムではとてもトラック・インできないだろう。重苦しく叩かれるピアノが、曲感を更に鬱な方向へと誘っている。
同じくスローナンバーで、これまたコテコテなブルース・バラードである#5『Let It Rain』は#4との類似点はスローなコード進行だけである。終始バックで弾かれるマンドリンのもの悲しいアクースティックサウンドに、叙情性が零れ落ちそうな力強いピアノの音とB3の音が絡み、キャッチーなメロディにソウルフルなShawnのヴォーカルが非常にマッチした傑作である。このダイナミックでエモーショナルなバラードはソウル・バラードと言い換えても良いだろう、否、やはりロック・バラードの感動的な要素をルーツ音楽で表現しきったナンバーである。
中盤はスローな曲が続くが、#6『Lover’s Moon』もゆったりとしたレイドバック・ナンバーである。ここまでのタイトな演奏とはち切れんばかりのパワーに溢れた曲群から、初めてリラックスして歌い、演奏している印象を受ける曲である。この明るさというかやる気が一時的に欠如したような間の抜け方は、ほっと一息入れるのに丁度良い。このようなバリトン系ヴォーカルのブルースロックアルバムは、結構聴いていてクドイところと疲労するところがあるのだが、その緩和にうってつけの曲だ。
#7『Sanctuary』はかなり人工的な音出しをしている奇怪なギター音と、ネバネバしたヴォーカルと、憂鬱なメロディがアメリカン・ゴシック風な複雑怪奇さを醸し出している、これまたかなりヘヴィなブルースの影響を感じるナンバーである。この曲は正直いらないと思う。この1曲で全体の評価が10点は下がってしまっている。勿体無い。何もここまで気味悪い曲を入れる必要はなかったと思うのだが。
#8『Time & Money』は、哀愁と寂寥の漂う、ややオルタナティヴ的なメロディと同じくブルースの哀愁が複雑に交じり合った評価のし難い1曲である。西海岸のバンドであることを証明するように、適度に弾んだリズムが美しいピアノのラインに乗っているし、メロディもさりげなくポップである。アルバムトラックとして良作になるのだろうが、少々抑えが効き過ぎているように感じている。
ニューエイジ・ピアノアルバムの様に美しい小インスト曲#9『Fly Away』からラストの#10『Took Your Love Away』の感情のこもったバラードに至る流れが、最後のハイライトとしてとても印象的であり、かつ素晴らしい。初めてアクースティックな曲が登場するが、Shawnのコブシの効いたヴォーカルと、キーボード類の巧演奏で、静から動へ、動から静へと何度も変転するこの曲は、アルバムのラストは大作、といった70〜80年代の風潮を想い起こさせてくれるようだ。このような素晴らしいメジャーコードのバラードが創れるなら、敢えてブルース的な愛惜にどっぷり漬からなくても良いのでは?と思えるくらいのバラードとして好曲である。
以上10曲、さすがに1万枚売っただけの力量を感じるアルバムである。が、まだまだ全てを出し切っていないように思えるし、足りないところも正直ある。このアルバムからブルースにより傾いていくのか、前半で展開しているゴリゴリなロックを求めていくのか、非常に興味深い。
しかし、このような潜在力を持ったバンドがあちこちに埋まっているアメリカの懐の深さを改めて感じる。最近西海岸からあまり注目に値するルーツ系のバンドが出ていないので、是非、Shawn Davis & The Roadには頑張ってもらいたいと願うところが大である。 (2001.9.25.)
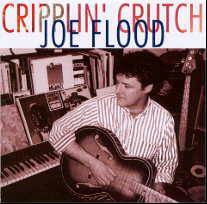 Crippin’Crutch / Joe Flood (2001)
Crippin’Crutch / Joe Flood (2001)
Roots ★★★★★
Pop ★★★☆
Rock ★★★☆
Alt.Country ★★★
You Can Listen From Here
Special Thanks To Mr.Motofusa Hattori With Conq Records
ジャケットのバックに置いてあるアップライトピアノの上に黒人のレコード−黒人音楽については全く興味がないため恐らく名盤であるだろうが、誰のレコードかは分からない−と、こちらは直ぐに分かるJohnny Cashのアナログ盤が見られる。
また、戦前のオーケストラジャズの重鎮、Hoagy Chemicalの名の入ったレコードも置かれている。更に乱雑に書籍やレコードが積み上げられ、Joe Floodが抱えているのはアクースティックギターだろう。ギターについては素人なので詳しいことは分からないが、何気なく抱えている格好はその辺の青年という風にしか見えない。
このジャケットから即座に感じるのは、とても音楽や文学が好きな普通の兄ちゃんの部屋、という印象、それ以外には何もない。よく見ると、ピアノの鍵盤は手垢が付くくらい古ぼけている。彼の後ろに積み上げられた乱雑なケース類はPA機器の類だろう。
直にジャケットを見ても、かなり見難いので、これ以上この解像度とサイズのジャケット写真に言及してもあまり効果がなさそうなので、このくらいにしておこう。
一番思うことは、この乱雑さと整頓のなさは非常に個人的にシンパシィを覚えるのだ。ふと見渡すと、筆者の部屋は寝るスペースを除いては、CDと書籍の山が複雑な稜線をなしているので。(笑)ズボラ=ラフでルーズな音楽好き、と短絡するつもりは毛頭ないけれど、整然とした書斎の写真を持ってこられるよりもこのようなカオス的にとっちらかった音楽の匂いのこびりついたような部屋の方が居心地がよさげである、ただそれだけのことだ。
少々、極個人的な生活状況とクロスオーヴァーしてしまったせいか、かなりこのアーティストJoe Floodとは距離が近い気がする。実際、非常に自然体で製作されたアルバムであると思う。ニューヨークはブルックリンのレーベルであるDiesel Only Recordsからのリリースとなっているが、自主制作の完全インディ盤として手元に到着しても何ら違和感はない。
さて、このJoe Floodというシンガー・ソング・ライターについて述べるのは今回は後回しにして、まずこの11曲入りのアルバムについて語ってみたい。
冒頭でも触れているが、彼のレコードコレクションである、カントリー、ジャズ、黒人音楽という、アメリカン・ルーツの要素のうち、どのパートが突出しているかと考えると、どれもそれ程強烈に自己主張をしていない。とはいえ、中途半端な方向性の見えないアルバムだ、というのでは決してない。
そういったアメリカのクラッシックな音楽性を全て土壌に染み込ませて良い肥料とした上で、1990年代以降のオルタナ・カントリー・ムーヴメントに端を発するロックンロールを果実として実らせている。
最近の新人バンドに非常に良く見られるのだが、ルーツロックではない”ルーツに寄りかかったルーツ音楽の改善版(または単なる改悪版)”という、あまりにもルーツテイストを追求した故の「ロックンロール」のビートとリズムの欠如した安易な回帰音楽となっていない。
とはいえ、ゴリゴリに濃いロックをぐいぐいと押し付けるようなロックアルバムでもない。適度に伝統音楽、特にブルーグラス風の中部アメリカ伝統音楽に向けたあこがれが見られる。
豪快なサザンロックやアクースティックな繊細なブルーグラスのどちらにも属さない、あらゆるルーツ的要素が伺えるアルバムなのだ。こういったアルバムは得てして散漫で、耳触りが良い割にはあまり印象に残らなく、リピート性が希薄なアルバムに陥る可能性が高く、実際及第点だけどもどの曲もそれなりでしかないというアルバムが多い。
が、この「Crippin’ Crutch」はそういった散漫さや無節操さとは全く縁のないアルバムである。
全体的に滅茶苦茶骨太で、ルーズで、体育会系の男臭さがプンプンしているという竜骨のような一本棒がズンと通っているからだ。
通常、ハードロック系以外の重目のアルバムというのは、黒人系のブルースとかヘヴィロック系の憂鬱でノイジーな暗さや陰鬱さが目立つが、このアルバムの場合、ヘヴィではないのに、質感がたっぷりあるという、まさにルーツロックの浮ついたチープさのない音楽性という成功例を具現化した如くのピースである。
また、ブルース&南部系黒人ルーツへの寄りかかりも聴き取れるけれども、ブルースの愛惜というような哀しさは殆どメロディラインに乗っかっていない。ブルージーな重厚さは感じることができるけれども、必要以上にどんよりとしたゲル状のような粘つきが癇に障ることがないのだ。
基本は東海岸ロックの明るい部分というよりも、むしろ中西部アメリカのカントリー系譜に連なる大陸的な伝統音楽から継承された乾いた明るさを内包しているサウンドが基本の様に思えるのだ。
イーストコースト特有の都会的ポップセンスというか、ダサダサになる一歩手前で少々アーバン風味の流麗さを見せるというような、ルーツミュージックとシティ・モダンポップのブレンドというようなことは、しかしながら、Joe Floodの場合は皆目ない。どこまでも田舎臭い、飾り気のない泥臭いアレンジを追及した、Bar Rockの原点のような音楽である。
ここまで男臭いアレンジとサウンドに仕上げているのに、力任せな印象よりも、ややリラックスしたルーズさと余裕が流れているアルバムは結構珍しい気がする。ちなみに筆者は力に乗っかって爆走するダサダザロックンロールは恐らく一番好きではあるが、このようなやや気合の入りかけというか、根性と演奏を楽しむような面が同居している、喜び第一的なアルバムも大好きである。
タイトル曲である#1『Crippin’Crutch』からRolling Stonesのようなシンプルでストレートなロックが炸裂する。クラッシックブギー調というべきか、それともロッキン・ブルースというべきか、兎に角、適度にキャッチーなメロディを持ちながらも泥々なギターとベタベタなハモンドの音色にマンドリンやリズムセクションがバックをサポート。初っ端からかなり密度の濃いロックナンバーを聴かせてくれる。サザンロックのあけすけな爆走感を思わせるが、どこかしら脱力した一本抜けたところが存在し、そのいい加減さがたまらない荒っぽさとなっている。このダイナミックなうねりは、Black Crowsが一番まともであった1stアルバムの頃の素直な正面からの勝負というサウンド性を思い起こさせてくれる。
一転してThe Bandのフォロワーの如きアクースティックで明るいマンドリンラインをフューチャーした、#2『A Little Bird Told Me』で、#1で盛り上がったグングンと迫るタイトさを一気にぶち壊すのも非常にヴァラエティに富んでいて宜しい。ドラムの爽快なシャッフル音と、これまた暢気に歌うオルガンの音色。Hootersの名曲『Always A Place』を連想させるような日なたの匂いのするようなマンドリンのライン。どの音楽性をとっても心から和める1曲となっている
続く#3『Niagara』もサニーサイド・ミュージックという表現が似合いそうなマンドリンと12弦アクースティックギターから始まるため、あれれ、2曲続けてレイドバック・アクースティックナンバーのゴリ押しかな、と思わせておいて、いきなり一撫でされるピアノのクラッシュプレイから、活きの良いロックンロールに展開していくところは、Facesを髣髴とさせるリラックスロックンロールの風格さえある。弾むピアノにマンドリンに、アクースティックギター。時折暴れるドラムとピアノの酔いどれっぽいラフさ。#2と非常に似通ったサザン・レイドバックなリズムを基本としながらも、ラフでディライトフルなロックナンバーとして仕上がっている。このアルバムでも1・2を争うハイライト曲であるのは間違いないところだ。この力の篭ったパンチ力と、どこかしらゆったりした感覚が漂うメロディの妙が彼の一番の持ち味かもしれない。
#4『All The Same To You』も3分以内の短いロックナンバーであるが、曲感的には#3と同様にどことなく懐かしい甘いメロディとコーラスを基本としながらも、タフでラフなフックを有した傑作曲である。#3と異なり、エレキギターが地味ながら掻き鳴らされ、ピアノやマンドリンの音色はやや後ろに回っている。代わりにJoe Floodのバリトンヴォイスとバックヴォーカルの仕事が一層堪能できるようなアレンジを意図したのだろう。リズムセクションはかなりタイトに演奏をこなしているが、Joeのヴォーカルとマンドリンやピアノが、やはりイナタ臭いアップビートな間延びしたブギー感を醸し出している。この#2〜4の一連の流れはレイドバック・ロックとしては相当の密度の濃厚な出来になっている。
更にThe Bandファンにはたまらないスロー曲が#5『Deep Sleep Blue』で現れるに至って、前半は#1を除いてみると、古典的レイドバックロックを目指したアクースティックアルバムのオマージュ的な色合いが濃いように思えてくるのだ。かなり抑えた歌唱法をここではJoeが披露している。単なる酒焼けヴォイスでないという彼のヴォーカルの奥深さが確認できるトラックでもある。ラップ・スティール、マンドリン、ピアノという、ここまで聴いてくるとお馴染みとなった楽器類が優しくさりげないメロディをサポートするところは、もう堪らなく心が休まる、ただそれだけである。
ゆったりまったりな中にも力強い芯の通った前半から、アナログ盤ならB面にターンするところで、個人的にまたもアルバムのハイライト曲が登場する。バタバタなドラムソロのリフから、歪んだ電気ギターの音色が被さり、更にアクースティックピアノにエフェクトをかけ、壊れたエレキピアノのようなブカブカした音にアレンジしたパッキングが重なってラフでノイジーに展開する曲。#6『Big Daddy Blues』はかなりシンプルで、バスドラのズンズンという音色が腹の底でリズムを刻むようなロックチューンである。タイトルの如く、ブルージーでジャジーなうねりを持っているが、この奇妙なリズムと微妙にキャッチーなコーラス。そしてかなりシニカルな社会批判とユニークでウィットの効いたフレーズ
♪「A B C D E F G H I’ve Got The Pain Reduced Only 1 2 3 4 5 6 7 I’ve Got Far Big Daddy Blues」
という印象的なラストヴァース。もっとも歌詞は筆者の聴き取りなため、あまり自身で信用はないが。兎に角、即効性はないのであるが、ひたすら印象に残るアグレッシヴなロックチューンである。
#7『Automatic Monkey』ではブルースハープが吹きまくられ、泥臭いギターと黒っぽいメロディが炸裂するブルースロックチューンが披露されて、後半2曲はかなりハードドライヴィンで、Joe Floodのヴァリトンヴォーカルが縦横にそのタフネスさを使いまくるナンバーが続く。むしろ今までハーモニカが取り入れられなかったのが不思議なくらいの音楽性なのだが、なる程、ハマリ過ぎるくらいこのやや間の抜けたブルースハープの音色はこの整然としていない荒削りなサウンドに非常に似合っている。
前半の流れとは正反対に#8『I Don’t Want To Tell You Again』も#1を更にシンプルでロアに焼き直したような重心の低いロックチューンと、3曲もラフでタイトなナンバーが連続する。この辺の流れはひたすら明るい陽気さの存在した前半と比較して極端に鬱な感じがする。特にこの#8からブルースの哀愁と暗さを具体化したような『Shades Of Gray』の#9で顕著である。あまりにも黒っぽい曲が続き過ぎるところは唯一全体の流れを見ると不満な点であるのだ。単体で聴くと#9はかなり感情の篭ったスローブルーなーナンバーであり、味わいが深いのだが、こうも連続するとやや食傷気味になる。この構成はマイナス。
やっと後半でも弾んだ陽性なロックナンバーが登場するのが#10『High-Maintenance Woman』である。残念ながらかなり豪快なジャンプナンバーでもっと聴いていたいのだが、2分半程度の短さである。ヤケクソなコーラスにブギーなリズム、連打されるピアノやドラムといった楽器。どこを切ってもオーソドックスなクラッシック・オールド・スクールロックという曲であるが、こういうチューンをさり気なくトラックインしてくれるところが嬉しい。
そして、最後の締めはスローバラードであるが、ノン・ブルーステイストである、個人的に大歓迎な#11『So The Story Goes』。タイトルも筆者が大好きな言い回しであるし、詩としてもストーリー・テラーとしてのJoe Floodの才能が伺える佳曲であると思う。このアクースティックなナンバーでもJoeの歌い方やキーを微妙に変化させ、メリハリをつけるという彼のヴォーカルの才気がよく分かる。こういったすっきりしたアクースティックナンバーで初めて東海岸出身の彼のバックグラウンドが感じ取れるのは、興味深いことである。最後の最後でだ。
さて、Joe Floodというルーツロッカーについて、殆どの方は馴染みがないだろうから簡単に説明しておこう。
1980年代からニューヨークのバーやクラブで地道な活動をしてきた人である。メジャーシーンで名前が出たのは1993年のThe Bandの再結成アルバム「Jericho」の『Move To Japan』でソングライターの一人としてクレジットされた時であろう。また、Jono Mansonの最後のメジャーアルバムである「Little Big Man」でもライター陣として参加し、殆どのギターパートのクレジットに名前が見られる。
プレイヤーとしてはマンドリンやヴァイオリン、フィドルをギターと同様にこなせる人で、東海岸のインディバンドのアルバムでは1990年代に入ってから少々名前が見られることもある。1994年のRon Sunshineのアルバム「Pick It Up」でかなりのトラックでギターを弾きバックヴォーカルを担当している。
今作のプロデューサーであるEric Ambelとの繋がりは、Ericの手掛けたBottle Rocketsの1997年のアルバム『24 Hours A Day』や同じく1998年の『Leftover』で曲を提供し、フィドルやマンドリンで参加した時からの親交であるそうだ。また、EricがプロデュースしたMojo Nixonのアルバム「Whereabouts Unknown」でもマルチプレイヤーとして多彩な楽器を担当している。
自身ではThe Munbo Gumboというグループの創設期のフロントマンであるが、フルアルバムを作成する以前に脱退している。このグループはメンバーを変えて現在も活動中だが、あまり特筆するようなバンドではないと思う。どうも個性が弱くて。
Joe Floodのソロ活動としては1997年にセルフリリースした「Hotel Albert」という作品がデヴューアルバムとなる。が、かなりジャジーで黒人音楽に傾倒したルーツアルバムであったため、筆者的にはあまり印象に残っていないのが正直なところである。ライヴも見ているはずなのだが、あまり記憶に残っていない。まあ、当時は週に6回くらい見ていたので、余程良いものがないとセットリストも浮かんでこないのだが。
よってこのアルバムでかなりレイドバックした中にも、静かに沸騰する鉄瓶のようなパワーを秘めた骨太ロックを聴かせてくれた時は、かなりびっくりした。相当1stよりレヴェルアップしている。
やはりこれはプロデューサのYayhoosギタリスト兼ヴォーカリストであるEric”Rascoe”Ambelの力量が大きなウェイトを絞めていると思う。この硬派でいて、しかもポップな創りはEricのお約束でもあるのだが、非常に安心して聴ける。
これ以上メジャーなアーティストになるともっとすっきりしたアレンジで纏めてきそうである。それはそれで聴いてみたい気はするが、Joe Floodの場合はこの適度なラフで粗いアレンジがとてもマッチしていると思う。しかし、Yayhoos関連の人脈は2001年は活発に動いているようで、何とも嬉しい限りである。
最近、妙にカントリーに傾倒した新人しか出ない、とかブルースに偏り過ぎるアーティストに食傷気味のリスナーは是非ともこのアルバムを聴くべきだろう。どちらの要素も必要以上には有していないロックアルバムである。
日本でもコンクレコードさんで買えるのだ。男のルーツロックに浸りたい人にお薦めである。 (2001.9.30.)
 Future Perfect / Yuma House (2001)
Future Perfect / Yuma House (2001)
Alternative ★
Pop ★★★★
Rock ★★★☆
You Can Listen From Here
新作・良作コーナーでは本当に久々の非ルーツアルバムのレヴューのような気がする。(気のせいではないわな)よく、「こんな音も聴くんですね。」と驚かれたり意外に思われたりするのだが、日がな一日ルーツロックだけ聴いてる訳ではないのだ。・・・・・年々ルーツロックを聴く割合はズンドコに増加してはいるけれど。(汗)
筆が乗らないというか、ルーツ以外の音楽は最近、どうしてもオルタナティヴの無機質さが大なり小なりつきまとうので、その人工的なモノトニアスさがポップというコーティングで隠れるというか控え目になる度合いが多くない限り、リピートしないし、書く意欲が湧いてこないのだ。
ということで、このレヴューは近来稀に見る最短レヴューになる可能性が強い。というかまともな分量かもしれないけれども。
このYuma Houseはざっかけない言い方をすると、Power Popというジャンルに分類されるだろう。現代音楽の常なのか宿唖なのだろうか、どうしてもオルタナティヴ的単一色なメロディが楽譜の間に存在しているのは仕方がないことだろうが、やはり少々不満が残る。
再三にわたり、あちこちで述べているけれども、Power Popというジャンル分けはとてもアンビギュアスである。まず、Popという概念から人様々である。”パワーポップ”とわざわざPopを銘打つからには、概念からしてポップでなければ存在自体がたちゆかなくなる筈なのに、世間一般で−特に日本のメディアで−もてはやされているポップという単語は、正直「どこがポップなんじゃあ、ボケ、カス!!!」と言いたいような(言ってる)全然ポップでない作品ばかりである。
どうも、UK的なヒネリネジクレポップや、中身のないスカスカ軽々なポップが”Pop”という認識を受けているようである。挙句の果てには、ヘヴィでノイジーなリフに申し訳程度のキャッチーさを加えた音楽をPower Popと呼んでいるような始末である。
まあ、大勢に唾を吐いてもマイノリティな叫びにしかならないけれども、本物のアメリカンロックの分かりやすさを、濃縮したようなコマーシャルさにロックの躍動感とエネルギーを加えたものを、筆者的にはPower Popと分類したい。というか、ポップであれば、Power Popで良いと思う。Powerを負荷する意味は、ポピュラー系のアダルトコンテンポラリーな音楽と−ブラック系のポップアルバムを含むべきだろう−線引きをするために足された概念と考えているからである。
かなり前置きが長くというか、クドくなってしまったが、要するにこのYuma Houseは十分にPopであり、ややロックとしてのスピード感に欠けるきらいはあるけれども、作者的にはPower Popと呼称するに足るグループであるということなのだ。
このアルバムとしては2作目にあたる「Future Perfect」はデヴューアルバムであるセルフリリース盤が11曲入りであったのに対して、僅か7曲しかトラッキングされていない。1970年代や80年代のアナログ盤時代なら兎も角、現在ではミニアルバム扱いされる曲数でしかない。EPでも(CD−Singleと言うべきか)4〜5曲収録されることが珍しくない時勢である。が、筆者としては曲数よりも内容が問題なのであって、6曲以上あればフルレングス扱いとして見る事に最近はしている。
さて、この「Future Perfect」というタイトルとジャケットに描かれた、宇宙飛行士(みたいなもの)・無重力状態で宇宙を見ている(ような状況の)人・ロケット(だろう)・宇宙船(シリカ号・・・・っていつの生まれやあ!!)というように、ジャケットからして全然ルーツロックぽくない。事実ルーツのテイストのテの字もない。
いかにも近未来やSFライクな内容のコンセプトアルバムのような印象があるが、歌われている歌詞を聴き取ってみると全くそのようなことはない。
タイトルの「Future Perfect」というフレーズは#1の『(Write Off)Summer』で
♪「When You Write In The Past Tense About The Cream In Your Coffee
A Future Perfect Is Evident In The Leaves In Your Green Tea
I’m Thinking About The Time When You Wrote Down A Cryptic Line On A Card」
というヴァースからの引用らしい。(筆者の聞き取りによるもので信憑性は皆無だ。あしからず。)
このかなりアイロニカルというかウィットに富んだヒネクレ失恋ソングからこのアルバムは幕を開ける。少々弱い感じもしなくない優しいヴォーカルが、ハード過ぎないギターリフに載って、ポップなメロディと共に流れていく。適度にロックでアップテンポ。日本では個性がないとか、目立たないとか、地味だとかで一般受けしそうもないスコアとアレンジで曲は進んでいく。この#1がアルバム全曲に共通する基本である。ポップで適度にロックな展開。但し、近年のインディ・ロックバンドに殆ど見られるオルタナディヴ風味の極端に盛り上げないで、単調なコード進行という姿勢が見られるのはかなり残念。もっとも、ポップさが十分にそののっぺりとしたメロディを支えて、聴き易いものにしてくれているのだが。
#2『Red Car』はハードで元気の良いギターリフからブレイクして、流暢なコーラスが被さっていく、気持ちの良いロックチューンである。が、中盤でやや冗長的なっているのが惜しまれる。ここを改善すれば、インディ・ポップの名曲になった可能性もあったのだが。後半のややラフに跳ね回るギターソロは聴きモノである。
#3『Girl You Know』は単純なコードを軸に淡々と流れるミディアムテンポのアルバムトラックである。ヴォーカルとコーラスはとても温かみがあるし、所々挿入される女性コーラスも良い雰囲気を出しているのだが、ミディアムバラードとしては後半の山場以外は単調過ぎる感が強くて、いまいちのめり込みに欠けるところがある。丁寧に作られた良い曲であるのだが。
#4『All By Design』もカラッとしたギターが印象的なミディアムチューンである。ポップさは十分にあるのだが、ややオルタナ的な単調さが普通の曲という印象以外を与えてくれない。
#5『Ezmiralda』も#4に良く似た構成の曲であるが、ポップさと展開の豊かさで、随分とより良いチューンとして耳に入ってくる。全体に言えることなのだが、とてもポップのセンスはあるバンドなのに、メリハリの付け方に成功していないために冗長的な曲という感想を与えてしまっている場合が多い。アレンジを分厚くしろとか、もっと弾けた方が良いのではというような意味ではなく、ここまでポップさを出すなら、中途半端にせずにもっとアレンジとコンポーズにおいて工夫の仕様があるのではないか、ということだ。(あ、同じかな?)
#6『Sick In Bed』も#3や#4の残念な部分を引き摺っているチューンだ。及第点なのだがそれ以上ではない。
#7『Smile』はこのアルバムの中では大作というか、変調を多く取り入れた、ダイナミックなナンバーだ。気持ち良くハード・ドライヴィンするギターとコーラスワークの妙、次第に盛り上がる曲調と、ロックンロールな速さよりも、壮大な曲を創り上げるところに主眼を置いたようなナンバーであり、これはなかなか聴き応えがあって、楽しめる1曲になっている。
とかなり辛口な批評になってしまっている。American Hi−Fiの時といい、どうも非ルーツアルバムに対しては採点がキツくなっている傾向にあるが、この辛いところをクリアして良作としてレヴューしているところを評価として考えて貰えれば、と考えている。
基本的にオルタナティヴに必要以上には媚びていないし、オーヴァーアレンジとも無縁のバンドであるため、基本的にはかなり良いものをもっているのだから。が、デヴュー作ではもっと元気に(というか必要以上にハードにしていたわざとらしさもあったが)冒険をしていたのが、今作では無難に纏めすぎたという印象が強いことも確かである。
兎に角、今後には十分に期待できるインディ・ポップバンドであると思う。ロックに勢いがなくなっているアメリカにあって是非とも健闘して欲しいバンドの一つである。
最後にこのYuma Houseというバンドについて触れておこう。出身及び活動拠点は首都ワシントンD.C.という東海岸のバンドである。1995年に結成されている。
影響を受けたサウンドはThe Replacements、SuperchunkそしてBuffalo Tomといったオルタナティヴ・ポップロックバンドというのは彼らの音楽を聴くと即座に頷けるものがある。キャッチーさにおいては「超デブ」以上に光るものがあるが。
地元ワシントンでのカレッジチャートでじわじわと人気を上げながら、1998年に11曲入りの自主制作アルバムをリリースする。1999年から2000年にかけて、mp3.Comやインターネット販売をボーナストラック入りで始め、そこそこの成果を得る。
この評価が、ガレージロックからオルタナティヴ、ラップやヒップホップまで手掛ける、大手のインディレーベルであるGarageband Recordsの目にとまり、2001年に契約を交わすことにこぎつけ、初の大手レーベルリリースとなったのが本作である。
大手と書いたが、このGarageband.Comは新世代のレーベルである。インターネット販売オンリーのレーベルで現在販売を委託しているインディバンドが世界53カ国で35,000以上だそうである。ここで1,000枚売れるとバンドには2万ドル(240万円程)が支払われるというような仕組みで、インディ販売ながらレコードレーベルとしてはかなりの規模になっている。
と、脱線してしまった。Yuma Houseに戻るとしよう。
本作のプロデューサーはインディ落ちする前のMother May Iの1stアルバムやこれまたAdult AlternativeのメジャーバンドEmmet Swimmingを手掛けたMark Harveyが担当している。エモコアとか呼ばれるメロディックなオルタナ風サウンドには定評がある人である。筆者的にはダメなアルバムが多いジャンルではあるが・・・・。
メンバーは4ピースで
Don Brasek (L.Vocal&Guitar) , Eric Chang (Bass&Vocal)
Danny Espinoza (Guitar,Keyboard&Vocals) , Lee Huber (Drums)
というラインナップである。ベーシストのChangは明らかに東洋系である。最近漸くモンゴロイドの移民系が白人バンドに出てくるようになったのは時代の流れだろう。
「僕たちはオタクじゃないけど、コンピューターをかなり使用するんだ。僕たちはインターネットに常に注意を向けているしGarageband Comでの販売がかなりのウエイトを占めているからね。」
とEric。
インターネット通販をメインに考えるバンドが出現して、しかも人気を博そうとしているのはやはり新時代の潮流かもしれない。
願わくば彼らの将来がよりよい形の音楽とセールスに帰結して欲しい。「Future Perfect」と宣言できるくらいに。
ああ、やはり短いレヴューになってしまった、が世間の常識から考えるとまだ長いわな。(笑)
(2001.10.8.)

 Fear Not The Obvious / The Yayhoos (2001)
Fear Not The Obvious / The Yayhoos (2001)